2024年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講解説 ●9●9 鉱物化傾向と鉱物治療9.人間は自らの内に鉱物化しようとする傾向を有している。その点に関して、鉱物治療の視点が重要になるが、それは鉱物をそのまま取り入れるというのではなく、ホメオパシー原理が重要になる*ホメオパシー原理:ホメオパシー療法は、「似たものが似たものを治すという基本原理(ホメオパシー原理)から成り立ちます。つまり、健康な人に与えてある症状を出す物質は、同じような病気の症状を治すことができるとされています。ホメオパシーは、ドイツ人医師サミュエル・ハーネマンによって確立された治療法で、同じような症状を引き起こす物質を希釈して患者に与え、自己治癒力を強力に刺激することによって治療する高度に体系化された治療法です。参照画像:homeopathy 人間の「下部」へとより深く下降していく場合、腸内植物相から腸内動物相へと下降していくわけですが、逆に「上部」へと昇っていく場合は、人間内部の植物相が克服される領域から、鉱物化、つまり人間の硬化が克服されなければならない領域へと上昇していくことになります。人間は、上へ向かえば向かうほど、鉱物的になる傾向が強くなるのです。それは、頭部が著しく骨化しているということに典型的に表われています。人間は、自らの内に鉱物化しようとする傾向を持っているのですが、この鉱物化の傾向が克服されなければならないというわけです。この鉱物化に対抗する働きかけのためには、外的な鉱物界の活動性に対置されるような力が、鉱物界から取り出されなければなりません。それが、鉱物化療法の基本的な原理としてのホメオパシーです。腸内植物相に対抗するには、植物療法、腸内動物相に対抗するには、血清療法が有効なように、鉱物化傾向には、ホメオパシーを行なわれなければなりません。このホメオパシーについては、第2講でも言及されていました。ホメオパシーは、同種(*類似)療法で、健康体に与えるとその病気に似た症状を起こす物質を、ごく低濃度に希釈し、それを薬品としてその病気にかかった患者に投与して治療する方法です。アロパシー(Allopathie/逆症療法)はちょうどこれとは逆のやりかたですが、これについては、次の5講で述べられていますので、ここではふれません。シュタイナーは、第2講で、上部と下部の二元性をホメオパシーで説明していました。物質の特性は、一律にどこまでも分割可能なものではなくて、ある限界を超えると反対のものに転化する可能性すらもっていて、自然にはそうしたリズミカルな過程があるというのです。生体の上部組織と下部組織の間にもこうした内的なリズムがあって、上部組織はホメオパシー的なもので、下部組織は特性がある時点で逆転したものであるといえますから、その特性を利用して、希釈を行うことで、下部組織に関係した諸特性を上部組織に関係した諸特性に導くことができるわけです。このように、この「精神科学と医学」という講義は、他の講の内容と照らし合わせていくことで、理解の進む部分もありますので、今後もできるだけそうした説明を折りにふれて、付け加えるようにしていければと思っています。けれども、私たちが一面においては、植物化の出現に対抗する戦いを循環プロセスのなかに見出すことによって、人間内部の、つまり腸内の動物相及び植物相の克服へと進んで行かなければならないように、皆さんはここから出発して本来の神経ー感覚人間へと進んで行くわけです。この神経ー感覚人間は、人間の生活全体にとって、通常考えられているよりもずっと重要なのです。科学というものがこのような抽象に高められたために、次のようなことを適切な方法で考慮する可能性はまったく失われてしまいました。つまり、この神経ー感覚人間を通じてたとえば光と光に結びついた熱とがそもそも入り込んでくるわけですが、この神経ー感覚人間は内的な生活と密接に関係しています。なぜなら光とともに入り込んでくる計測できないものは、諸器官において変容させられねばならず、そしてこの計測できないものは、計測できる領域に存在しているものと同様、器官を形成するものだからですが、こういうことを考慮する可能性は失われてしまったのです。神経ー感覚人間が人間の組織化にとって特別な意味を持っていることは、まったく考慮に入れられておりません。しかし、私たちが下部人間のなかにより深く下降していく場合は、腸内植物相を形成する力から、腸内動物相を形成する力へと下降していくのですが、他方、人間の上部へと昇っていく場合は、私たちは内部の植物相が克服される領域から、人間の絶えざる鉱物化、いわば人間の硬化が克服されねばならない領域へと上昇するのです。皆さんはここで、いわば外的に、頭部の骨化が他の部分より顕著であるということから見ても、人間は上へ向かって進化するほど、その器官を通じてまさに鉱物的になる傾向が強まるということを研究することができます。この鉱物的になるということ、これは人間の生体組織全体にとって大きな意味をもっています。と申しますのも、よろしいでしょうか、これは繰り返し留意されねばならないことなのですが、人間を三つの部分、すなわち、頭人間、胴体人間、四肢人間という三つの部分に分けるとき、これらの三つの部分が並列的にあって、外的空間的な境界を有していると考えていただいては困るのです。質的に区分するとすれば、人間というものは当然まったくもって頭人間です。頭であるものは人間全体に拡がっていて、その主要な部分が頭にあるというだけです。他の部分、つまり循環と、四肢及び新陳代謝についても同じで、これらも常に人間全体に拡がっています。このため、当然のことながら、頭ないし頭部人間にとって存在しなければならないものが、素質としては人間全体のなかに存在しているのですが、この人間全体における鉱物的になっていく素質は克服されねばならないのです。今日の人間が、まだ遺伝的な霊視能力から導き出されていた古代の著作をひもといても、もはや何も理解できない分野というのは、まさしくここにあるのです。なぜなら結局のところ、パラケルススの言う塩プロセスについて読んでも(☆3)、今日ほんのわずかの人しか何かまっとうなことを読みとることはできないからです。ところでこの塩プロセスというのは、私がちょうど今特徴をお話ししている領域にあたり、硫黄プロセスというのが、その前にお話しした領域にあたります。さて重要なことは、人間は自らのうちに、鉱物化しようとする傾向を有しているということです。ちょうど、動物相・植物相プロセスの基礎を成しているものがいわば独立的になり得るのと同様に、人間全体にとってこの鉱物化の傾向も独立性を持つ可能性があるのです。この鉱物化の傾向に対して、どのように対抗して働きかけねばならないのでしょうか。これに対抗する働きかけは、この鉱物化傾向を粉砕し、いわばそのなかに絶えずくさびを打ち込む以外にはありません。そしてこの領域こそ、皆さんが血清療法から植物療法を経て鉱物療法へと移行して踏み込んでいくところなのです。何しろ鉱物療法なしでやっていくわけにはいきません。なぜなら、皆さんが、鉱物化していく傾向、普遍的に硬化していく傾向に対する人間の戦いにおいて、支えられねばならないものすべてを支えるための拠り所を得られるのは、鉱物と、人間のなかで自ら鉱物になろうとするものとの関係においてのみだからです。その際皆さんは、鉱物を単にその外的な状態のままで人間の生体組織に取り入れる方法でやっていくことはできません。ここで、何らかの形でのホメオパシー原理を示すもの、つまり、外的な鉱物界の活動性に対置されるような力が、ほかならぬ鉱物界から探り出されねばならないことを示すもの、そういうものが登場してくるのです。これはよく指摘されてきたことで、実際正しいのですが、治癒作用のある泉のわずかなミネラル成分に注目しさえすれば、この泉ではめざましいホメオパシープロセスが起こっているのがわかります。このプロセスは、私たちが通常見ている外的な諸力から鉱物の連関を解放する瞬間に、まったく別の諸力、つまりまさしくホメオパシーを行うことによってしか特別に解き放たれない別の諸力が本当に現れてくることを示しています。けれどのこのことは、申しましたように、別の章で述べようと思います。 ((第四講解説●9 了)哲学・思想ランキング
2024年08月31日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講解説 ●7 マクロコスモスへの視点の重要性7.顕微鏡での観察は、真のプロセスから目をそらせるマクロコスモスへの視点が重要である記:通常、最近を顕微鏡を使って観察することによって、生命を把握しようとすることが行なわれているのですが、むしろ、私たちに関わる真のプロセスは、マクロ的な視点で研究されなければならないことをここで、シュタイナーは強く示唆しています。 ここで、世界全般を観察できる人にとって奇妙なことが起こってきます。そういう人には些(いささ)か外交的でない言い方となることをお許しください。私がお話することは一見反駁される可能性もあるにもかかわらとなること、これはそもそも共感も反感も無いという意味でまったく客観的なことなのです。顕微鏡で観察することすべてに対して、微小な世界の観察全般に対して、一種の激しい怒りをおぼえるのです。なぜなら、顕微鏡での観察はそもそも、生命と生命を妨げるものとを健全に把握する可能性に導くやいなや、むしろそこから逸脱させるものだからです。と申しますのも、健康であるにせよ病気であるにせよ人間において私たちに関わってくる真のプロセスはすべて、顕微鏡的なものにおけるよりも、巨視的なもののにおいてはるかによりよく研究できるからです。私たちはマクロコスモスのなかにこそ、こういう事柄を研究する機会を探さなければならないのです。第四講解説 ●8 鳥は、人間の生体組織のマクロコスモスにおける写像である8.鳥は、人間のより精妙な生体組織のマクロコスモスにおける写像である。人間は鳥よりも下降した存在であるといえるが、光を変容に導く活動において、つまり膀胱と大腸に関わるエーテル体に関しては、人間は鳥と同じ位置にある。 鳥類の体内には、腸菌群落がなく、それに対抗する必要がありません。膀胱と大腸の発達が未発達で、食べたものを体内に蓄積しないのです。ある意味で、私たち人間は、鳥よりも下降した存在であるといえます。しかし、エーテル的なものを変容させる活動、光を変容させる活動に関しては、私たちは鳥と同じ位置に立っているのだといえます。大腸や膀胱に関わるエーテル体に関して、私たちは鳥なのです。鳥は、人間の「より精妙な生体組織のマクロコスモスにおける写像」だといえます。ですから、人間をそういう視点で研究しようとすれば、マクロコスモス的に鳥を研究しなければなりません。このように、人間の外部にある植物相と動物相に起こっていることと、人間の生体組織のなかの腸内の動物相と植物相で起こっていて、克服されねばならないこととの対応を調べていくことが重要になります。そして薬と器官との関係を明らかにするためには、こうした一般的特徴や原理から、個別的なものを見ていく必要があります。この講義の最初で、単に経験的-統計的な方法からではなく、病理学から治療法を取り出す理性[Ratio]の重要性ということが言われていましたが、経験的-統計的な方法が帰納法的なのに対して、病理学から治療法を取り出す理性[Ratio]というのは、演繹的な方法です。マウス実験などを繰り返したりしてそこから治療法を見つけだすのではなく、病気という現象の根底にある原理そのものから、個々の治療法を取り出してくるということであり、さまざまに応用の可能性が開かれているということだと思います。ですから、この章で述べられているような病気に関する原理を認識することで、個別の治療法へと進んでいくことができるようになります。皆さんに注意していただきたいことは、鳥類は、膀胱と大腸の発達が不十分であるために、摂取と排泄との間に絶えず持続的な平衡状態を保っていることです。鳥は飛翔しながら排泄することができます。鳥は食べたものの残りを体内にとどめて蓄積するということはありません。鳥にはそうする機会がないのです。もし鳥が食べたものの残りを体内に蓄積したとしたら、それは即座に病気であり、鳥の体をだめにしてしまうでしょう。私たちが人間である限り、物質的な人間である限り、私たちは、いわば、今日的な見解に沿って言うならば鳥よりも進化したわけですが、もっと正確な言いかたができるとすれば、鳥よりも下に降りてきたと言えるのです。鳥は実際のところ、腸菌群落に対して激しい戦いを展開する必要はありません。高等動物や人間には必要なこの腸菌群落が鳥の体内には全く無いのですから。けれども私たちの、より高位に置かれた活動と申しますか、例えば先ほどお話しましたエーテル的なものを変化させる活動、光を変化させて変容に導く活動、こういう活動に関しましては、私たちは鳥と同じ位置に立っているのです。私たちは物質的な膀胱と物質的な大腸を有していますが、これらの器官に関わる私たちのエーテル体に関しては、私たちは鳥なのです。実際こういう器官は宇宙において動的に存在してはいないのです。そこでは私たちも光を受け取って直接これを加工し、排泄物としてまた排出するということに頼っているのです。ここに支障が起こると、この支障に対応する器官がないために、私たちは健康を損なうことなしに難なくこの支障に耐えるということはでません。ですから、この小さな脳を備えた鳥というものを観察する際に明確にしておかなければならないことは、鳥は、私たちのより精妙な生体組織のマクロコスモスにおける写像であるということです。したがって人間というものを、鳥よりも下に降った粗雑な組織に写し取られた、より精妙な組織ということに関連して研究しようとすれば、皆さんはまさにマクロコスモス的に鳥の世界の出来事を研究しなければならないのです。ただここで申し上げておきたいことは、これは括弧付きで述べるのが望ましいことかましれませんが、人間が物質的組織において鳥類に比較して有している特性を、そのエーテル的組織においても持っているとしたら、実際人間の生活は悲しむべきものになるでしょう。なぜならエーテル的組織は物質的組織のようには外界から遮断されることができないからです。そうなると変容させた光を貯蔵する時には、それを感じとる臭覚器官がもし存在するなら、人間の共同生活はかなり悲惨な状態になるでしょう。もっとも先ほど申しましたとおり、これは括弧付きで述べるべきことです。私たちが羊を死後解剖して、その内部の匂いをかいだときに経験するのと同じことが起こってくるわけです。一方、エーテル体的なものに関しては、実際のところ私たちが人間としてお互い向き合っているやりかたは、たとえば腐肉を食する鳥でさえそれを解剖する際に不快な匂いを発散しませんが、この全く不快でない匂いに比較されます。もちろんすべては比較的、相対的にそう言えるだけですが。この不快ではないというのは、私たちがとりわけ反芻動物、ようやく反芻動物への素質を持ち始めた、たとえば馬のような動物でも、馬は正確には反芻動物ではありませんが、その組織において反芻動物への素質が見られるのです。これを解剖する時に発散される匂いに比較してそう言えるのです。つまり重要なことは、外部の植物相と動物相に起こっていることと、人間の生体組織のなかの腸内の動物相と植物相において起こっていて克服されねばならないこととの対応を調べていくことなのです。そして何らかの薬と器官との関係を確定しようとすると、私たちは、きょう展開してまいりました一般的な特徴付けから、明日以降の講演での個別的な特徴付けへと進んでいかなければなりません。参考画像:Phoenix (第四講解説●7・8 了)哲学・思想ランキング
2024年08月30日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講解説 ●6●6 人間は自らの中で光を変容させている6.人間は自らの中で光を変容させていで、太陽光とそれを内的に変容させることとの均衡が崩れることで人間は結核菌に適した土壌となる 私たちは、光に囲まれて在りますが、その光を取り入れるにあたってそれを変容させています。植物化プロセスが人間のなかで阻止されるように、光も人間のなかで変化させられているのです。病原菌、結核菌は、太陽光の下ではすぐに殺されてしまうのですが、人間の体内にいるときは、よく生存するというのもその証明になっています。しかし、その菌が人間の内部で増えすぎるときには、そこになんらかの異常があるのだといえます。菌は常に存在しているのですが、なんらかの状態において、増殖していくわけです。けれどもここでも、事実を正しく評価し始めた人にとっては、このことは非常に大きな意味を持っています。なぜなら、このことは私たちに、結核の動物相ないし植物相に属するもの、つまり病原菌は太陽光のもとでは自らを維持できない、ということを示しているからです。病原菌は太陽光のもとでは自らを維持できません。太陽光は病原菌には都合が悪いのです。病原菌が自らを維持できるのはどういうときでしょうか。人間の体内にいるときです。それではなぜ、人間の体内でなら自らを維持できるのでしょうか。病原菌を本来的に害をなすものであるかのように見るのではなく、体内で活動しているもの、これこそが探究されねばならないものなのです。けれどもこのとき注意を払われていないものがあるのです。私たちは絶えず光に囲まれています。この光はおそらく皆さんが自然科学から記憶しておられるように人間の外部の生物の発育にとってきわめて大きな意味を持っています。とりわけ人間の外部の植物相全体の発育にとってきわめて大きな意味を持っています。私たちはこの光に囲まれているのです。しかし、私たちと外界との境目において、この光に、つまり純粋にエーテル的なものに、非常に重要なことが起こっています。つまり光が変化させられているのです。光は変化させられねばならないのです。よろしいでしょうか、ちょうど植物化プロセスが人間によって阻止されるように、この植物化プロセスがいわば中断され、炭酸の発生というプロセスによって植物化に抗する働きかけがなされるように、ちょうどそのように、光生命のなかにあるものも、人間によって中断されるのです。したがって私たちが人間のなかの光を探究すると、それはなにか別のもの、つまり光が変容したものであるにちがいありません。私たちが人間の境界を内に向かって越える瞬間に、光の変容が見出せます。すなわち、人間は自らのなかで、単に通常の外的な計測しうる自然現象を変化させているのみならず、計測できないもの、つまり光をも変化させているのです。人間は光を別のものに変えるのです。太陽光のもとではすぐに死んでしまう結核菌が、人間の内部ではよく生存するということは、次のような事実を、それが正しく評価されればですが、端的に証明するものです。その事実とは、人間の内部に生じてくるこの光の変容の産物、すでにこのなかに結核菌の生命元素があるということ、すなわち、結核菌が内部で増えすぎるときは、この変化した光の状態になんらかの異常があるにちがいないということです。さらに皆さんはそこから出発して、結核の原因のなかには、人間のなかで、この変化させられた光、この光の変容に関して、本来起こるべきでない何かが起こっているということもあるにちがいない、何と言っても結核菌はいつも存在しているけれども、人間は通常、結核菌をたくさん取り込みすぎることはないのだから、という事実を理解されるでしょう。実際結核菌はいつもいるのです。ただ通常は十分な数ではないというだけで、人間が結核に屈服するとおびただしく増えるのです。この変容させられた太陽光の発達に関連した何らかの異常がない限り、ふつう結核菌がどこにでも見つかるというわけではないのです。人間は、変容させた光を自らの内に蓄えています。しかし、人間が太陽光を十分に取り入れることができないか、取り入れる太陽光と太陽光を変容させることとの均衡が崩れるかすると、その蓄えられた光を引き出さざるをえなくなります。そのようにして、人間が結核菌に適した土壌になるとき、菌は増殖していきます。変容させられた光が肉体から奪われていくことで、「上部」が病気になるか、「上部」にとって必要なものを「下部」から引き出し、「下部」が病気になるかするのです。記:最近また結核が流行っているということですが、今回の結核はこれまでに効いたといわれている薬が効かないのだそうです。シュタイナーのこうした考え方に照らせば、変容された光が肉体から奪われ、人間が結核菌に適した土壌になってきているということなのかもしれません。 さて、またもや、この分野の学位論文や私講師論文の大多数から次のようなことを引き出すのは、私がここで観点としてしか与えることのできないもののための経験的な素材は、このようなやりかたでのみ皆さんのところに集まってくるでしょう。つまり、人間が結核菌に適した土壌となる場合に起こってくることというのは、人間が太陽光を十分取り入れることができないか、あるいはその人の生活習慣のために十分太陽光を得ていないために、その人のなかに入ってきた太陽光と、太陽光を変容させて加工することとの間の均衡がくずれ、その人はずっと自分のなかに備蓄していた変容させた光から、貯えを引き出さざるを得ないということです皆さんにぜひとも考慮に入れておいていただきたいことは、人間はまさに人間であることによって、変容させた光を絶えず自らのうちに貯えて持っているということです。これは人間の生体組織にとって必要なのです。人間と外界の太陽光との間の相互プロセスが正しく実現されないと、このような影響下にあっては、ちょうど痩せていく場合に自分のために必要な脂肪が肉体から取り去られるように、変容された光が肉体から奪われるのです。そしてこういう場合人間は、上部を病ませるか、あるいは上部にとって必要なものを下部から引き出す、すなわち変容させた光を下部から取り出して下部を病ませるかというジレンマの前に立たされているわけです。このように、人間は、太陽光とそれを取り入れ変容させたものを必要としていますが、こうしたことから、治療の可能性を導き出すことができます。太陽光との相互プロセスを秩序あるものにするために太陽光にさらすことや変容させられた光が取り出されるプロセスを薬の作用によって弱めるといったことです。このことからおわかりだと思いますが、人間はとりもなおさずその生体組織のために、外部から入ってきて変化させられた計量可能な実質を必要としているだけではなく、人間を正しく観察すれば指摘できることですが、人間のなかには、変容したかたちではあっても、計量できない実質、エーテル的な実質も存在しているのです。しかしこのことから看取していただきたいのは、このような原理を通じて、太陽光の治癒的な作用のための正しい見解を打ち立てる可能性をいかに生み出していくかということです。たとえば、一面においては、周囲の太陽光との相互プロセスが秩序を失っているのを再び秩序づけるために直接その人を太陽光にさらすことによって、あるいは他面においては、変容させられた光が奪われる際に不規則になったものを調整するような実質に、その人を内的にさらすことによって、治療を行うことができます。薬の作用によって、変容させられた光が奪われる状況をなくしていかなければならないのです。ここで皆さんは人間の生体組織をのぞきこむことができます。参考図:rosarium-philosophorum (第四講解説●6 了)哲学・思想ランキング
2024年08月29日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講●解説 ■5 腺から引き出した形成力としての魂生活●5 腺から引き出した形成力としての魂生活5.人間の魂的霊的生活における体験は、我々が腺から引き出した形成力である。*ここでシュタイナーは、以下とても興味深いことを述べています。 唾液の分泌、腸内の粘液分泌、母乳の分泌、尿の分泌、精子関連の分泌など、なんらかの「腺」の分泌が起こる場合、私たちはその「腺」から力を取り出し、魂生活のための諸力としているというのです。つまり、自らの「下部」における腸菌群落、植物化プロセスから形成力を引き出し、私たちはそれによって思考しているというわけです。そうした「下部」における腸菌群落、植物化プロセスにおける形成力は、外的な自然の植物相に潜在している諸力でもあります。しかし、私たちの「下部」における腸菌群落は、外部の植物相とは異なっています。外部の植物相においては、思考は植物の内部に潜在したままなのですが、私たちは腸菌群落からその形成力を奪って思考の力に変えています。もし腸菌群落の形成力を奪わなければ、思考ができないのです。こうした洞察によって、人間と植物薬との関係を見ていく必要があります。更にこれに加えてもうひとつ注意していただきたいことがあります。おそらく皆さんも日常経験から、こういう事実があるのを御存知と思いますが、この事実がまたしても十分に評価されていない事実であり、健全な科学においてはこういう事実の正しい評価こそ重要なことなのです。つまりこの事実というのは、皆さんがある特定の器官について考える瞬間、もっと良い言い方をすれば、その特定の器官に関連する考えを抱く瞬間に、この器官にある種の活動が起こるということです。人間においてわき起こってくるある種の考えと、唾液分泌、腸内の粘液分泌、母乳の分泌、尿の分泌、精子関連の分泌などとの関連を、ここにもまた未来の学位請求論文のための豊かな領域があるのですが一度研究してみてください。これらの生体組織の現象と並行して現れるある種の考えがどのようにして起こってくるのか、研究してみてください。ここで目にしているのはどのような性質の事実なのでしょうか。皆さんの魂生活に特定の考えが生じると、それと並行して生体組織の現象が起こってくるのではないでしょうか。これはどういうことなのでしょうか。皆さんの思考のなかに生じてくるものは、まるごと器官のなかにあるのです。つまり皆さんがある考えを抱いてそれと並行して何らかの腺分泌が起こる場合、その考えの基礎を成している、そう考える基礎となる活動を、皆さんは腺から取り出しているのです。皆さんがその活動を腺から分離させて実行し、腺をそれ自身の運命にゆだねると、腺は自身の活動に没頭して分泌をおこなうわけです。この分泌が妨げられているということはつまり、そうでなければ腺から排除されるものが、思考がそれを結びつけたことによって腺と結びついたままになっているということです。ここで、形成活動が器官から思考のなかに入り込んで現れてくるということを、いわば明白にご理解いただけると思います。私がそのように考えなかったとしたら、私の腺は分泌しなかっただろう、と言うことは可能なのです。すなわち、私は腺から力を奪い、これを、この力を私の魂生活に移行させる、だからこそ、腺は分泌をおこなう、ということです。ここで皆さんは人間の生体組織そのもののなかに、私が今までの考察で申しあげてきたことの証明を見出せるのです。つまり、私たちが霊的・魂的生活において体験していることは、私たちの目の前にある他の自然秩序のために分泌された形成力に他ならないということの証明です。外的な植物相として外的自然のなかで私たちの腸菌群落(*腸内植物相)に並行して発達するものを通じて、外部の他の自然のなかで起こっていることのなかに、まさにこの内部にこそ、私たちが自らの腸菌群落から引き出した形成力が潜んでいるのです。皆さんが戸外で山の植物相を、草原の植物相を眺めるとき、本来は次のように言わなくてはなりません、このなかには、表象のなかに生き、感情のなかに生きているときに、皆さんが思考のなかに発達させる諸力が潜んでいるのだと。したがって、皆さんの腸菌群落は外部の植物相とは異なっています。外部の植物相からは思考が取り去られる必要はないからです。外部の植物相において思考は、茎、葉、花と同様に植物の内部に潜んだままなのです。ここで皆さんは、花や葉のなかで支配しているものと、皆さんが腸菌群落を発達させるときに皆さん自身のなかで起こっていることとの親近性について理解を得られるでしょう。このとき皆さんは腸菌群落に形成力をゆだねず、腸菌群落から形成力を奪い去るのです。これを奪い取らないとしたら、皆さんは思考する人間ではあり得ないでしょう。皆さんは、外部の植物相が持っているものを、自らの腸菌群落から取り去ったのです。上記に述べられたようなことを、動物相においても洞察することが必要です。人間と植物薬との関係を見ていくだけではなく、動物に関係した治療をも見ていかなければなりません。人間は、その外部の動物界において「形態を与える諸力」を、自らの内部における「腸内動物相」から取り去っています。そのこを認識することで、治療用血清について正しく理解することができるのです。動物相の場合においても事情は変わりません。こういうことを洞察することなくしては人間と植物薬との関係に行き着くことが出来ないのと同様、外部の動物界において形態を与える諸力を、人間は自分の内部の腸内動物相からは取り去ったのだということについて意識しなければ、治療用血清の使用に関して正しい理解に至ることはできないのです。このように、治療薬についての正しい理解のためには、人間とその環境との関係を真に洞察しなければなりません。そうでなければ、意味のないことが、治療において大真面目に行なわれてしまうことになります。このことからおわかりだと思いますが、このように人間とその環境との関係を本当に見据えないことには、理性、つまりこうした事柄の体系学は不可能なのです。さらに私はもうひとつ、非常に重要なことを皆さんに指摘したいと思います。少し前に滑稽にも至る所で唾を吐くことが禁止されたとき、はなはだひどい状態になりましたが、あれを共に体験された方がここに多数おられるかどうかは存じません。ご存じのように人々はこの唾吐き禁止によって結核を撲滅しようとしたのです。さて、この唾吐き禁止が滑稽なのは、これは誰もが知っておくべきことでしょうが、病原菌、結核菌は、ごくありきたりの分散した太陽光によりきわめて短時間で殺されてしまうので、しばらくしてから痰を調べてみると、少ししか時間がたっていなくても、痰のなかにはもう結核菌はいなくなっているからです。太陽光は即座にこの病原菌を殺すのです。ですから、通常の医学上の前提が正しい場合でも、こういう唾吐き禁止はなおもきわめて滑稽なことと言えるでしょう。このような禁止行為はせいぜいのところ、ごく一般的な衛生という面では意味もあるでしょうが、最も広義の予防医学にとっては意味のないことなのです。参考画:人間の植物化 (第四講解説●5・了)人気ブログランキングへ
2024年08月28日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講●解説 ■2 植物化に対抗するプロセス ■3 植物化の止揚 ■4 植物化プロセスの下部における活性化●2 植物化に対抗するプロセス2.炭素に酸素を対抗させ、炭酸に加工することで、植物化に対抗するプロセスを形成する必要性 シュタイナーは人間を三分節化した存在としてとらえています。 1は神経・感覚存在としての人間、2は循環存在・律動的存在としての人間、3は新陳代謝存在としての人間です。そして、そうした三分節化した人間が、人間の外部の自然で起こっていることの陰画(ネガ)として関係づけれらているというのです。そのネガ・ポジ関係を認識することで、人間と人間外部の自然との関係性を理解する必要があるわけです。人間の外部にある自然のなかの植物界は、「炭素の集積に基づいた本質を持つ有機体、形成物」であり、人間も「下部の人間」において、その植物化のプロセスの端緒を持っているのですが、それが「上部」において、「酸素」によって、その植物化プロセスに対抗し、「炭酸」に加工しなければならないと述べられています。この上部と下部というのは、第2講で述べられていたように、生体組織の上部の活動である呼吸プロセスと生体組織の下部の活動である栄養分の摂取、消化のプロセスのことで、この両者は互いに働きかけ合っているのですが、それが「滞留器官」としての心臓において、互いの働きかけを妨げあうということでした。上部では、いわば酸素プロセスがあり、それが下部のいわば炭酸プロセスに対抗し、炭素を止揚しなければならないというのです。きょうは誰もがよく知っている事実から始めようと思います。この事実は自然科学的、医学的思考との関連ではまったく正当に評価されておりませんが、人間の人間外部の自然に対する関係を判断するための基礎を提供してくれるものなのです。これは、三つの部分から成る存在としての人間、すなわち、神経・感覚存在としての、循環存在、つまり律動的存在としての、そして新陳代謝存在としての人間は、新陳代謝存在であることによって、外部の自然、植物界において起こっていることに対する陰画(ネガ)として関係づけられているという事実です。次のような事実を魂の前に描き出していただきたいのです。つまり外部の自然において、さしあたりこの自然のうちの植物界だけを観察すると、植物相においては、いわば炭素を集積し、この炭素を全植物相の基盤とする傾向が認められます。私たちは植物に囲まれていることによって、炭素の集積に基づいた本質を持つ有機体、形成物に囲まれているわけです。忘れないでいただきたいのは、この形成の基礎を成しているものは人間の生体組織にも現れているのですが、人間の生体組織はその本質において、形成の過程でいわば発生期状態(Status nascendi)が進行していくうちに、この形成を止揚し、破壊して、代わりにその反対の形成を取り入れねばならないということです。このプロセスの端緒は、私たちの内部の、私が先日来下部の人間と呼んできたもののなかに見出されます。私たちは炭素を沈殿させて、いわば私たち自身の力から植物化のプロセスを始め、その後私たちの上部の組織に誘導されて、この植物化に抵抗しなければなりません。私たちは炭素に酸素を対抗させることで炭素を止揚し、炭素を炭酸に加工し、それによって私たちのなかに植物化に対抗するプロセスを形成していかなければならないのです。●3 植物化の止揚3.人間は植物化を止揚することで生きているが、その認識が生体組織と植物薬との関係を探求するためには必要である。 人間は「下部」において植物化でもある炭酸プロセスを持っているのですが、それが「上部」における酸素プロセスによって止揚されなければならないということでした。それは外的な自然のプロセスに対抗するプロセスであって、そうすることで、人間は生きているわけです。そして、そのことを認識することが、病気にかかっている生体組織に対して、「植物薬」がどういう働きをするのかということを理解するためには必要になります。この外的自然を止揚するという視点はとても重要な観点で、人間は自然存在であると同時に、それに対抗する存在でもあるのだということを認識しておかないと、「自然にしていればそれでいいのだ」というような自然礼讃のような安易な視点に陥ってしまうことになるわけです。いたるところでこの外的な自然とは反対のプロセスに注意していただきたいのです。と申しますのも、このことに注意していただければ、皆さんは真実の人間をますます根本的に理解されるようになるからです。人間の重さを計っても、物理学的な研究方法にのっとった他の研究に対しては象徴的にこういう言いかたができます。人間の「一」そのものを理解することはできないのですが、次のようなことを考慮すれば、人間のメカニズムについてすぐさま何らかのことは理解できるのです。つまり、脳の重量は良く知られているように平均千三百グラムあるけれども、この重量で頭蓋の下半分の面が圧迫されることはない、なぜなら脳の自前の重量で圧迫されたなら、繊細な血管が拡がっている部分はすべて押しつぶされてしまうからといったことです。脳が自らの土台を圧迫している重さはせいぜい二十グラムです。これは、脳が脳水のなかに浮かんでいるという事実のために、良く知られたアルキメデスの水圧の原理に従って浮力を得ており、その結果脳の重量の大部分は作用せず、浮力によって止揚されているからです。ここにおいて重さが克服され、私たちが自らの生体組織の重量のなかではなく、重量の破棄のなかに、物理的な重量とは反対の力のなかに生きているということは、人間のその他のプロセスの場合も同様なのです。実際のところ私たちは自然現象(Physis)が私たちとともに作り出すものではなく、自然現象から止揚されたもののなかで生きているのです。さらに私たちは実際のところ、外的自然のなかにも存在していて、植物界においてその最終部分を体験するプロセスとして知覚されるようなプロセスのなかで生きているのでもなく、私たちは植物化を止揚することによって生きているのです。このことは、私たちが病気にかかっている人間の生体組織と植物薬との間に橋を架けようとすれば、当然本質的に問題となってくることです。●4 植物化プロセスの下部における活性化4.人間の上部と下部の相互関係において、上部の下部に対する反作用が少なすぎるため、植物化プロセスが下部において活性化する可能性 羊を解剖すると、その腸内には、「腸菌群落」のためひどい腐敗臭がするのですが、鳥類の場合には、そうした腐敗臭はありません。その差異に注目することが重要な視点を示唆してくれます。鳥類の場合、膀胱と大腸がきわめて未発達であって、排泄物を蓄積したり、生体内にとどめたりしておいてから排泄するとかいうことはなされません。摂取と排泄との間に常に平衡状態が保たれているのです。こういうことは、いわばちょっとした短編小説風に叙述できるかもしれません。世界のすばらしい植物相(Flora)として私たちを取り囲んでいるものすべてに眼差しを向けると、私たちは当然のことながら歓びを、とても大きな歓びを感じると言えるのではないでしょうか。けれども、羊を解剖して、その解剖の直後に別の植物相(Flora)を目にするときはそうではありません。この(羊の体内の)別の植物相は、その発生原因という点でも、外部の植物相の発生原因と決定的に類似しているのですが、羊を死後に解剖して、この羊の内部のまったき腐敗臭がこちらに漂ってくるのを感じるとき、この腸内の植物相、すなわち腸菌群落(Darmflora)に対して私たちは歓びを感じるどころではありません。けれども、このことにこそ特に注目する必要があるのです。なぜならば、人間の外部の自然においては植物相を軌道にのせる原因であっても、それは人間においては克服されねばならず、腸内の腸菌群落が発生させられてはならないことは明白だからです。ここにはきわめて広範な研究領域が拡がっており、比較的お若い、勉学中の医学生の皆さんにお勧めしたいのですが、学位請求論文のためにこの領域から多くを役立てられるとよいのではないかと思います。とりわけさまざまな動物の形態、哺乳動物を経て人間にいたる形態における、腸形成の比較研究という領域からは得るところが多いと思います。この領域においては、きわめて重要なことがまだ数多く研究されないままなので、非常に実り豊かな分野が成立するでしょう。とりわけ、羊を解剖すると、その腸菌群落のためにひどい腐敗臭が発散されるのに、鳥類の場合は腐肉を食する鳥の場合でも腐敗臭はなく、解剖しても比較的心地よいとさえ言える匂いを発するのはなぜなのか、一度その隠れた事情を探究してみていただきたいのです。こういう事柄においては、まだ非常に多くのことが今日まで十分学問的に研究されておりません。この領域における腸の形態の研究についてはなおさらです。ちょっと考えてみて下さい。鳥類全体が、哺乳類との、そして人類との本質的な差異を示しているのです。鳥類の場合、例えばパリの医師メチュニコフ(☆2)のような唯物論的な医師たちは、まさにこういう事柄について最大の思い違いをしてきたわけですが、膀胱と大腸は、きわめて未発達なのです。鳥類が走禽類となるところでようやく、大腸の形態、および膀胱の形態におけるある種の膨隆(Ausbuchtungen)が見い出されます。こうして私たちに重要な事実が示されるのです。つまり、鳥においては、排泄物を蓄積したり、一定期間生体組織内にとどめたりしてからその排泄物を随意に排出するなどということはなく、摂取と排泄との間に持続的な平衡状態が成立しているということです。原注2 Elias Metschnikoff/1845-1905 オデッサ大学で動物学教授、後にパリのパスツール研究所副所長。 病気になるのは、「菌」によってであるということがいわれますが、それはあくまでも「ひとつの指標」にすぎないのだということを認識する必要があります。そうではなくて、「菌」の土壌になっているあり方の観察こそが、病気の原因を究明するのは不可欠なことなのです。人間身体の上部と下部を構成する腸内、そして人間の生体組織全般に現れてくる植物相、さらには私たちがこれから見ていくように動物相のなかに、病気であることの原因のようなものを見るとしたら、それは表面的な見方でしょう。実際これはもう恐るべきことなのですが、今日病理学の文献を調べてみると各章ごとに新たに、この病気にはこの菌が、あの病気にはあの菌が発見された云々にぶつかるのです。これらはすべて、人間の生体組織の腸内植物学、腸内動物学にとっては非常に興味深い事実なのですが、病気にとっては、せいぜいひとつの指標という以上の意味を持ってはおりません。つまり何らかの病気の型が根底にあると、人間の生体組織においては、何らかの興味深い微小な動物あるいは微小な植物の形状がこの基盤のうえに発達する機会が提供されるけれども、そうでない場合はそれ以上のことは何もないと言える限りにおいての、指標にすぎないのです。この微小な動物相および植物相の発達が実際の病気に関与している程度は非常に低く、せいぜい間接的に関わっているだけです。と申しますのも、おわかりでしょうか。この今日の医学の内部で展開されている論理は、きわめて奇妙なものだからです。考えてもみて下さい、皆さんが、良く飼育されて見事な雌牛がたくさんいる土地を発見するとします。皆さんはそのとき、これらの雌牛がどうにかして飛び込んできたから、この土地が雌牛に感染されたから、私がここに見ているものはすべて見ての通りなのだ、などとおっしゃるでしょうか。たぶんそのようなことはほとんどお考えにならないでしょう。そうではなくて、この土地に勤勉な人たちがいるのはなぜか、何らかの動物の飼育に適した土壌がそこにあるのはなぜかを探究せざるをえないでしょう。要するに、皆さんはおそらく、良く飼育された雌牛がそこにいるということの原因となりうるすべてのことを、思考の拠り所とされることでしょう。けれども、ここで起こっていることは、この土地が、良く飼育された雌牛がやってくることによって感染されたからそうなったのだ、と言おうなどとはまさかお考えにならないでしょう。しかし、今日の医学が微生物その他に関して展開している論理はそうではないのです。この興味深い生きものが実在しているということから見て取れるのは、そこに肥沃な土壌があるという以上のことではなく、この土壌の観察こそ当然留意されてしかるべきものなのです。ただ、たとえば、この地方には良く飼育された雌牛がいる、これを何頭か譲ってやろう、そうしたらもっと勤勉になろうと奮起するひともいるだろうと言うとき、間接的にあれこれのことが起こる可能性はあります。これはむろん付随して起こりうることです。準備の行き届いた土壌が菌によって刺激され、土壌自体も何らかの病気のプロセスに陥ってしまうということは当然起こりうるのです。けれども実際のところ、この菌という生物の観察は、本来の病気というものの観察とはほとんど関係がないのです。健全な論理の養成ということに留意されているならば、このように他ならぬ公認された科学から発して健全な思考の荒廃を招くようなことはそもそも起こり得ないはずなのですが。人間の「上部」の反作用が少なすぎるために、「下部」における植物化プロセスが止揚されず、それが「下部」にいて活性化する可能性に目を向けなければなりません。「腸菌群落(*腸内植物相)」が活性化してしまうということです。考慮すべきことは、先日来その特徴をお話ししてきました人間における上部と下部のある種の関係が誘因となって、上部と下部との正しい相互関係が成立しない可能性もある、ということです。その結果、上部の人間の反作用が少なすぎることにより、植物化していく傾向を阻止されるべき植物プロセスと申しますか、そういう植物化プロセスを阻止することのできない力が、下部の人間において活性化する可能性があるのです。そうすると腸菌群落(腸内植物相)がおびただしくはびこる機会も与えられ、そしてこの腸菌群落は、まさに人間の下半身がしかるべきやりかたで働いていないということを示すものとなります。「下部」におけるプロセスが正常に起こることができない場合、そのプロセスは、「上部」へと押し戻されてしまうことになります。つまり、「上半身で起こりうることの多くは、下半身から押し戻されたプロセスに他ならない」というのです。現代の医学では、ある臓器での疾患に対しては、その臓器そのものを治療するという視点が基本なのではないでしょうか。肺の疾患はその担当の科があり、泌尿器や胃腸の疾患にはその担当の科があるように。*ここでシュタイナーが提示している視点では、病気の「原因」へのアプローチによって、人間の臓器などを機械のようにとらえて、それぞれの故障を直すような視点が問題にされなければならないことを示唆しています。 この講の最初に、現代医学が個々の症状への治療ということが一見して有効なようにみえても、それは病気の本質を明らかにすることなのではないということが述べられていましたが、そうしたあり方は機械としての臓器の故障を修理するような発想でしかないということです。もちろん、とりあえずは、現在故障している臓器を修理することは有効かもしれないのですが、それは今なぜそういう病気になっているのかを明らかにし、それを治療するという視点でないのは確かです。人間においては、下部の水準に従って起こるべき活動が下部で起こることができない場合は、せき止められて押し戻されるという特殊な事態が起こります。つまり、下半身において、この下半身に組織されている特定のプロセスが起こることができない場合、これらのプロセスは、押し戻されるのです。こういう言い方は素人臭いと思われるかたもおられるかもしれませんが、これは今日通用している病理学に少なからず見出される表現よりは科学的なのです。人間の下部において規定通りに起こるべきこれらのプロセスが上部へと押し戻されるわけですが、肺における排出や、肋膜その他のように上へ向かって置かれた部分における排出についても、その原因は、それが人間の下半身の正常あるいは異常な排泄プロセスといかに関連しているかを調べることによって追求されねばなりません。生体のこういうプロセスが下半身を通じて上半身に向かって押し戻されることを正確に見ていくことがきわめて重要です。上半身で起こりうることの多くは、下半身から押し戻されたプロセスに他ならないのです。上部人間と下部人間との間に正しい関係が成り立たないと、これらのプロセスは押し戻されるのです。参照画像:alchemy 第四講●解説 ■2・3・4 了哲学・思想ランキング
2024年08月27日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講●解説■●テーマ概観■●1/病理学から治療法を取り出す理性[Ratio]■●2/植物化に対抗するプロセス■●3/植物化の止揚■●4/植物化プロセスの下部における活性化■●5/腺から引き出した形成力としての魂生活■●6/人間は自らの中で光を変容させている■●7/マクロコスモスへの視点の重要性■●8/鳥は、人間の生体組織のマクロコスモスにおける写像である■●9/鉱物化傾向と鉱物治療■●10/人間の二元性■●11/松果腺と脳下垂体の真の緊張関係■テーマ概観・■1 病理学から治療法を取り出す理性(Ratio)●テーマ概観 この第四講では、次のようなテーマが扱われています。1.単に経験的・統計的な方法からではなく、病理学から治療法を取り出す理性[Ratio]の重要性。2.炭素に酸素を対抗させ、炭酸に加工することで、植物化に対抗するプロセスを形成する必要性。3.人間は植物化を止揚することで生きているが、その認識が生体組織と植物薬との関係を探求するためには必要である。4.人間の上部と下部の相互関係において、上部の下部に対する反作用が少なすぎるため、植物化プロセスが下部において活性化する可能性。5.人間の魂的霊的生活における体験は、我々が腺から引き出した形成力である。6.人間は自らの中で光を変容させている太陽光とそれを内的に変容させることとの均衡が崩れることで人間は結核菌に適した土壌となる。7.顕微鏡での観察は、真のプロセスから目をそらせる。マクロコスモスへの視点が重要である。8.鳥は、人間のより精妙な生体組織のマクロコスモスにおける写像である。人間は鳥よりも下降した存在であるといえるが光を変容に導く活動において、つまり膀胱と大腸に関わるエーテル体に関して、鳥と同じ位置にある。9.人間は自らの内に鉱物化しようとする傾向を有している。その点に関して、鉱物治療の視点が重要になるが、それは鉱物をそのまま取り入れるというのではなく、ホメオパシー原理が重要になる。10.人間は上部と下部という人間性として自らを開示し、下部において形成されているものは、常に上部で形成されているものの平行器官である。人間の霊的・魂的活動は、脳形成と同時に腸形成とも結びついている。11.上部と下部は、常に緊張関係にあり、それを制御することが治療においては重要になる。松果腺には、上部の力であるすべての力が現われており下部の力である粘液腺、脳下垂体の力との真の緊張関係という観点がさらなる治療プロセスのための基本原理となる。●1 病理学から治療法を取り出す理性(Ratio)1.単に経験的-統計的な方法からではなく、病理学から治療法を取り出す理性の重要性注:この講の最初には、治療に関する基本的なシュタイナーの考え方が示されています。 治療、治療薬と器官、症状との関連は非常に複雑なものなので、それを見出すためには、「基礎的問題」を扱う必要があります。薬(*自己再生・回生能力を持つオートファジーは夢想さえされない医科学時代です。)人間の外部から人間に投与されるわけですが、それによってそうした人間と人間外のものとの関係の認識の有効範囲についての洞察が可能となります。昨日の午後の議論はなるほど極めて興味深いものではありましたが、私が今しがた目にいたしました質問との関連で、既にもう行ったことではありますが、やはりもう一度、次のようなことを強調しておく必要があります。すなわち、個々の治療薬と個々の症状との関連を見出すために十分な方法は、ここでの考察のなかで前もってある種の基礎的問題を処理してしまってからでないと得られないだろうということです。これらの基礎的問題によってようやく私たちは、人間と人間の外部のもの、この人間の外部にあるものから薬が取り出されるのですが、この人間と人間外のものとの関連についての認識の有効範囲を推し量ることができるようになるのです。とりわけ、個々の治療薬と個々の器官との関係について語ることは、これらの基礎的問題を処理することなしには不可能なのです。その理由は明白で、この薬と器官との関係というのは全く単純なものではなく、いささか複雑なものであって、私たちがきょう、あるいはもしかすると一部は明日にも処理していくべき基礎的問題を処理してからでないと、この本来の意味を推し量ることはできないからです。それに続いて、この治療薬とりわけ治療処置と、個々の器官疾病との具体的な関係を実際に議論する可能性がでてくるでしょう。けれども、きょうさっそく前置きとして申し上げておきたい今一つのことも、とりあえずは皆さんに取り入れていただきたいのです。そのことからある種の光が当てられることもあるでしょうから。と申しますのは、こういう事柄は当然のことながら最初はショックを与えるものですので、これらはいささかショッキングな事柄なのだということを先に強調しておかなければなりません。昨日の午後ここで検討されたこととの関連で申し上げたいのは、皆さんが物事の別の側面に留意してくださるようお願いしたいということです(*ここで、シュタイナーは、治療ということに関して、思いきった、けれども極めて原則的な意味での、問題提起を行なっています。それは、現代の唯物論的な医学に対する一種のアンチテーゼです)。一見、効果的な治療が行なわれているように見えるそうした医学ですが、それは個々の「病人」を治療するという視点のみが重要視され、病気の本質への探求ということがなされているとはいえないのです。それは一面的なアプローチであるといえます。個々人の治療ということと同時に、「人類の治癒ということを全体として見る」という視点が重要だというのです。現代の医学は、まるで新興宗教の御利益のように、特定の症状に「効く」ということばかりが重要視され、その「効く」ということがいったい病気の本質とどう関係しているのかといったことに対する視点が希薄です。従って、ある症状が起こるとそれを専門別に「~科」ということで分類し、その症状別にそれに対処するということになってしまい、その病気を全体としてとらえるということさえなされないのが現状です。肝臓が悪ければその担当の先生がいて、目が悪ければその担当の先生がいるという感じで、それらの症状の連関やそれらがどういう原因から生じているのかということを見ようとせず、クロスワードパズルのように部分のピースだけを扱うのが医者であるというようになってしまっているわけです。だから、それでどうにもならなくなると、急に御利益を求めて新興宗教に走ることどもがあり得るわけです。そんな馬鹿げた状態から脱するためにも、病気の本質へのアプローチが重要になってくるのです。昨日ここでまったく特定の治療について非常に啓発される事例が数多く紹介されたことは、私たちにとってきわめて満足のいくことでした。さて、私はこういう治療をおそらくは稀少なものにしていくごく単純な手段を皆さんに示すことができます。けれども私は皆さんがこの手段を用いないようにするためにこそ、これを用いることは当然考えられることですが、この手段をご紹介したいのです。この手段については、むろん人智学的な素養のある方々のもとでしかお話しすることはできません。この手段というのは、皆さんがリッターの治療法(☆1)を普遍的なものにしようとあらゆる策を講じるという点にあると言えるでしょう。皆さんは治療の成功に関しては、自分は個人的としてひとりの医師であるということを尊重するわけにはいきません。なるほど、個人としては次のようなことを意識しておられる方もいらっしゃるかもしれません。つまり、自分はひとりの医師として、大きな医師集団というものに対して戦わなければならない、けれどもリッターの治療法を大学の要件にしたとたんにそれに染まってしまうだろう。もはや反対の立場には立たず、非常に多くの、すべてのとは決して申しませんが、病気が癒されるので、自分の治療の成果は著しく減少するという経験をするだろう、このように意識しておられる方ももしかするといらっしゃるかもしれません。現実の生活においてはこういうこともあり得ます。つまり、ものごとは普通考えられているのとは異なっていることが多いのです。医師個人としてはひとりひとりの人間を治療することが最大の関心事であるのは当然のことですが、現代の唯物論的な医学は、それどころか、ひとりひとりの人間を治療することに単に挑みかかるしかないということの一種の法的根拠と申しますか、そういうものをこの方法で探し求めてきたわけです。原注1 リッターの治療法:「M・リッターの光力学的治療の実践的応用のための手引き」(ミュンヘン、1913) 及び「神経・力学的治療法ーー蛍光素材及び発光(ルミネセンス)素材の細胞領域と神経死に対する作用に関する研究と経験との関連で」(ライプツィヒ、1905)参照。 実際、この法的根拠は、そもそも病気などというものは存在しない、存在しているのは病人だけだと言われているところにあるのです。当然のことながら、人間が病気に関しても、今日外面的に見えているとおり切り離されているのだとしたら、このような根拠も真の根拠となるでしょう。しかし実際に起こっていることは、人間はこのようなことが大きな意味を持つほどには実際に切り離されてはおらず、ちょうど昨日E.博士が言及されたように、ある種の病気のスパンは、かなり広範囲にわたっており、皆さんがある人を治したとしても、別の場合にはまた別の人たちに病気を押しつけたこともあるかも知れない、といったことは決して確定できないのです。個々の病例をプロセス全体のなかに置いてみないと、こういう事柄は個別的にははなはだ驚愕させられるものです。けれども、人類の治癒ということを全体として見ようとする人は、やはり別の角度からも語らなくてはならないのです。記:シュタイナーは、「単なる経験的ー統計的な」在り方に、病理学から治療を引き出してくるという一種の理性[Ratio]をもたらさねばならないと言います。 理性[Ratio]というとわかりにくいかもしれませんが、これは、「経験的ー統計的な」いわば帰納法的な在り方に対して、演繹的な在り方だといってもいいと思います。病気という現象の根底にある原理そのものから、個々の治療法を取り出してくるということです。病気はなぜ生じるのか、その病気である状態をどのようにすれば治療の可能性が生じるのか、そういった「なぜ」の部分を重要視しているのだといえるでしょう。このことから、一面的に単に臨床的な方向付けをするだけではなく、完全に病理学をもとにして治療というものを引き出してくることがぜひとも必要となってくるのです。私たちがここで試みようとしていることはまさしく、通常は単なる経験的ー統計的な思考であるものに一種の理性(Ratio)をもたらすことなのです。参照図:医療や医学の分野 第四講●解説 テーマ概観・1病理学から治療法を取り出す理性(Ratio)了哲学・思想ランキング
2024年08月26日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講本講:本文1-2 腸内、そして人間の生体組織全般に現れてくる植物相、さらには私たちがこれから見ていくように動物相のなかに、病気であることの原因のようなものを見るとしたら、それは表面的な見方でしょう。実際これはもう恐るべきことなのですが、今日病理学の文献を調べてみると各章ごとに新たに、この病気にはこの菌が、あの病気にはあの菌が発見された云々にぶつかるのです。これらはすべて、人間の生体組織の腸内植物学、腸内動物学にとっては非常に興味深い事実なのですが、病気にとっては、せいぜいがひとつの指標という以上の意味を持ってはおりません。つまり何らかの病気の型が根底にあると、人間の生体組織においては、何らかの興味深い微小な動物あるいは微小な植物の形状がこの基盤のうえに発達する機会が提供されるけれども、そうでない場合はそれ以上のことは何もないと言える限りにおいての指標にすぎないのです。この微小な動物相および植物相の発達が実際の病気に関与している程度は非常に低く、間接的に関わっているだけです。と申しますのも、おわかりでしょうか、この今日の医学の内部で展開されている論理は、きわめて奇妙なものだからです。考えてもみて下さい、皆さんが、良く飼育されて見事な雌牛がたくさんいる土地を発見するとします。皆さんはそのとき、これらの雌牛がどうにかして飛び込んできたから、この土地が雌牛に感染されたから、私がここに見ているものはすべて見ての通りなのだなどとおっしゃるでしょうか。たぶんそのようなことはほとんどお考えにならないでしょう。そうではなくて、この土地に勤勉な人たちがいるのはなぜか、何らかの動物の飼育に適した土壌がそこにあるのはなぜかを探究せざるをえないでしょう。要するに、皆さんはおそらく、良く飼育された雌牛がそこにいるということの原因となりうるすべてのことを、思考の拠り所とされることでしょう。けれども、ここで起こっていることは、この土地が、良く飼育された雌牛がやってくることによって感染されたからそうなったのだと言おうなどとはまさかお考えにならないでしょう。しかし、今日の医学が微生物その他に関して展開している論理はそうではないのです。この興味深い生きものが実在しているということから見て取れるのは、そこに肥沃な土壌があるという以上のことではなく、この土壌の観察こそ当然留意されてしかるべきものなのです。ただ、たとえば、この地方には良く飼育された雌牛がいる、これを何頭か譲ってやろう、そうしたらもっと勤勉になろうと奮起するひともいるだろうと言うとき、間接的にあれこれのことが起こる可能性はあります。これはむろん付随して起こりうることです。準備の行き届いた土壌が菌によって刺激され、土壌自体も何らかの病気のプロセスに陥ってしまうということは当然起こりうるのです。けれども実際のところ、この菌という生物の観察は、本来の病気というものの観察とはほとんど関係がないのです。健全な論理の養成ということに留意されているならば、このように他ならぬ公認された科学から発して健全な思考の荒廃を招くようなことはそもそも起こり得ないはずなのですが。考慮すべきことは、先日来その特徴をお話ししてきました人間における上部と下部のある種の関係が誘因となって、上部と下部との正しい相互関係が成立しない可能性もあるということです。その結果、上部の人間の反作用が少なすぎることにより、植物化していく傾向を阻止されるべき植物プロセスと申しますか、そういう植物化プロセスを阻止することのできない力が、下部の人間において活性化する可能性があるのです。そうすると腸菌群落(腸内植物相)がおびただしくはびこる機会も与えられ、そしてこの腸菌群落は、まさに人間の下腹部がしかるべきやりかたで働いていないということを示すものとなります。人間においては、下部の水準に従って起こるべき活動が下部で起こることができない場合は、せき止められて押し戻されるという特殊な事態が起こります。つまり、下腹部において、この下腹部に組織されている特定のプロセスが起こることができない場合、これらのプロセスは、押し戻されるのです。こういう言い方は素人臭いと思われるかたもおられるかもしれませんが、これは今日通用している病理学に少なからず見出される表現よりは科学的なのです。人間の下部において規定通りに起こるべきこれらのプロセスが上部へと押し戻されるわけですが、肺における排出や、肋膜その他のように上へ向かって置かれた部分における排出についても、その原因は、それが人間の下腹部の正常あるいは異常な排泄プロセスといかに関連しているかを調べることによって追求されねばなりません。生体のこういうプロセスが下腹部を通じて上半身に向かって押し戻されることを正確に見ていくことがきわめて重要です。上半身で起こりうることの多くは、下腹部から押し戻されたプロセスに他ならないのです。上部人間と下部人間との間に正しい関係が成り立たないと、これらのプロセスは押し戻されるのです。さてこれに加えてもうひとつ注意していただきたいことがあります。おそらく皆さんも日常経験から、こういう事実があるのを御存知と思いますが、この事実がまたしても十分に評価されていない事実であり、健全な科学においてはこういう事実の正しい評価こそ重要なことなのです。つまりこの事実というのは、皆さんがある特定の器官について考える瞬間、もっと良い言い方をすれば、その特定の器官に関連する考えを抱く瞬間に、この器官にある種の活動が起こるということです。人間においてわき起こってくるある種の考えと、唾液分泌、腸内の粘液分泌、母乳の分泌、尿の分泌、精子を、ここにもまた未来の学位請求論文のための豊かな領域があるのですが、それを一度研究してみてください。これらの生体組織の現象と並行して現れるある種の考えがどのようにして起こってくるのかを研究してみてください。ここで目にしているのはどのような性質の事実なのでしょうか。皆さんの魂生活に特定の考えが生じると、それと並行して生体組織の現象が起こってくるのではないでしょうか。これはどういうことなのでしょうか。皆さんの思考のなかに生じてくるものは、まるごと器官のなかにあるのです。つまり皆さんがある考えを抱いてそれと並行して何らかの腺分泌が起こる場合、その考えの基礎を成している、そう考える基礎となる活動を、皆さんは腺から取り出しているのです。皆さんがその活動を腺から分離させて実行し、腺をそれ自身の運命にゆだねると、腺は自身の活動に没頭して分泌をおこなうわけです。この分泌が妨げられているということはつまり、そうでなければ腺から排除されるものが、思考がそれを結びつけたことによって腺と結びついたままになっているということです。ここで、形成活動が器官から思考のなかに入り込んで現れてくるということを、いわば明白にご理解いただけると思います。私がそのように考えなかったとしたら、私の腺は分泌しなかっただろうと言うことは可能なのです。すなわち、私は腺から力を奪い、これを、この力を私の魂生活に移行させる、だからこそ、腺は分泌をおこなうということです。ここで皆さんは人間の生体組織そのもののなかに、私が今までの考察で申しあげてきたことの証明を見出せるのです。つまり、私たちが霊的ー魂的生活において体験していることは、私たちの目の前にある他の自然秩序のために分泌された形成力に他ならないということの証明です。外的な植物相として外的自然のなかで私たちの腸菌群落(腸内植物相)に並行して発達するものを通じて、外部の他の自然のなかで起こっていることのなかに、まさにこの内部にこそ、私たちが自らの腸菌群落から引き出した形成力が潜んでいるのです。皆さんが戸外で山の植物相を、草原の植物相を眺めるとき、本来は次のように言わなくてはなりません、このなかには、表象のなかに生き、感情のなかに生きているときに、皆さんが思考のなかに発達させる諸力が潜んでいるのだと。したがって、皆さんの腸菌群落は外部の植物相とは異なっています。外部の植物相からは思考が取り去られる必要はないからです。外部の植物相において思考は、茎、葉、花と同様に植物の内部に潜んだままなのです。ここで皆さんは、花や葉のなかで支配しているものと皆さんが腸菌群落を発達させるときに皆さん自身のなかで起こっていることとの親近性について理解を得られるでしょう。このとき皆さんは腸菌群落に形成力をゆだねず、腸菌群落から形成力を奪い去るのです。これを奪い取らないとしたら、皆さんは思考する人間ではあり得ないでしょう。皆さんは、外部の植物相が持っているものを、自らの腸菌群落から取り去ったのです。動物相の場合においても事情は変わりません。こういうことを洞察することなくしては人間と植物薬との関係に行き着くことが出来ないのと同様、外部の動物界において形態を与える諸力を、人間は自分の内部の腸内動物相からは取り去ったのだということについて意識しなければ、治療用血清の使用に関して正しい理解に至ることはできないのです。このことからおわかりだと思いますが、このように人間とその環境との関係を本当に見据えないことには、理性、つまりこうした事柄の体系学は不可能なのです。さらに私はもうひとつ、非常に重要なことを皆さんに指摘したいと思います。少し前に滑稽にも至る所で唾を吐くことが禁止されたとき、はなはだひどい状態になりましたが、あれを共に体験された方がここに多数おられるかどうかは存じません。ご存じのように人々はこの唾吐き禁止によって結核を撲滅しようとしたのです。さて、この唾吐き禁止が滑稽なのは、これは誰もが知っておくべきことでしょうが、病原菌、結核菌は、ごくありきたりの分散した太陽光によりきわめて短時間で殺されてしまうので、しばらくしてから痰を調べてみると、少ししか時間がたっていなくても、痰のなかにはもう結核菌はいなくなっているからです。太陽光は即座にこの病原菌を殺すのです。ですから、通常の医学上の前提が正しい場合でも、こういう唾吐き禁止はなおもきわめて滑稽なことと言えるでしょう。このような禁止行為はせいぜいのところ、ごく一般的な衛生という面では意味もあるでしょうが、最も広義の予防医学にとっては意味のないことなのです。けれどもここでも、事実を正しく評価し始めた人にとっては、このことは非常に大きな意味を持っています。なぜなら、このことは私たちに、結核の動物相ないし植物相に属するもの、つまり病原菌は太陽光のもとでは自らを維持できないということを示しているからです。病原菌は太陽光のもとでは自らを維持できません。太陽光は病原菌には都合が悪いのです。病原菌が自らを維持できるのはどういうときでしょうか。人間の体内にいるときです。それではなぜ、人間の体内でなら自らを維持できるのでしょうか。病原菌を本来的に害をなすものであるかのように見るのではなく、体内で活動しているもの。これこそが探究されねばならないものなのです。けれどもこのとき注意を払われていないものがあるのです。私たちは絶えず光に囲まれています。この光は、おそらく皆さんが自然科学から記憶しておられるように、人間の外部の生物の発育にとってきわめて大きな意味を持っています。とりわけ、人間の外部の植物相全体の発育にとってきわめて大きな意味を持っています。私たちはこの光に囲まれているのです。しかし、私たちと外界との境目において、この光に、つまり純粋にエーテル的なものに、非常に重要なことが起こっています。つまり光が変化させられているのです。光は変化させられねばならないのです。よろしいでしょうか、ちょうど植物化プロセスが人間によって阻止されるように、この植物化プロセスがいわば中断され、炭酸の発生というプロセスによって植物化に抗する働きかけがなされるように、ちょうどそのように、光生命のなかにあるものも、人間によって中断されるのです。したがって私たちが人間のなかの光を探究すると、それはなにか別のもの、つまり光が変容したものであるにちがいありません。私たちが人間の境界を内に向かって越える瞬間に、光の変容が見い出せます。すなわち、人間は自らのなかで、単に通常の外的な計測しうる自然現象を変化させているのみならず、計測できないもの、つまり光をも変化させているのです。人間は光を別のものに変えるのです。太陽光のもとではすぐに死んでしまう結核菌が、人間の内部ではよく生存するということは、次のような事実を、それが正しく評価されればですが、端的に証明するものです。その事実とは、人間の内部に生じてくるこの光の変容の産物、すでにこのなかに結核菌の生命元素があるということ、すなわち、結核菌が内部で増えすぎるときは、この変化した光の状態になんらかの異常があるにちがいない、ということです。さらに皆さんはそこから出発して、結核の原因のなかには、人間のなかで、この変化させられた光、この光の変容に関して、本来起こるべきでない何かが起こっている、ということもあるにちがいない、何と言っても結核菌はいつも存在しているけれども、人間は通常、結核菌をたくさん取り込みすぎることはないのだから、という事実を理解されるでしょう。実際結核菌はいつもいるのです。ただ通常は十分な数ではないというだけで、人間が結核に屈服するとおびただしく増えるのです。この変容させられた太陽光の発達に関連した何らかの異常がない限り、ふつう結核菌がどこにでも見つかるというわけではないのです。さてまたもや、この分野の学位論文や私講師論文の大多数から次のようなことを引き出すのは、私がここで観点としてしか与えることのできないもののための経験的な素材は、このようなやりかたでのみ皆さんのところに集まってくるでしょうし、困難ではないでしょう。つまり、人間が結核菌に適した土壌となる場合に起こってくることというのは、人間が太陽光を十分取り入れることができないか、あるいはその人の生活習慣のために十分太陽光を得ていないために、その人のなかに入ってきた太陽光と、太陽光を変容させて加工することとの間の均衡がくずれ、その人はずっと自分のなかに備蓄していた変容させた光から、貯えを引き出さざるを得ないということです。皆さんにぜひとも考慮に入れておいていただきたいことは、人間はまさに人間であることによって、変容させた光を絶えず自らのうちに貯えて持っているということです。これは人間の生体組織にとって必要なのです。人間と外界の太陽光との間の相互プロセスが正しく実現されないと、このような影響下にあっては、ちょうど痩せていく場合に自分のために必要な脂肪が肉体から取り去られるように、変容された光が肉体から奪われるのです。そしてこういう場合人間は、上部を病ませるか、あるいは上部にとって必要なものを下部から引き出す、すなわち変容させた光を下部から取り出して下部を病ませるかというジレンマの前に立たされているわけです。このことからおわかりだと思いますが、人間はとりもなおさずその生体組織のために、外部から入ってきて変化させられた計量可能な実質を必要としているだけではなく、人間を正しく観察すれば指摘できることですが、人間のなかには、変容したかたちではあっても、計量できない実質、エーテル的な実質も存在しているのです。しかしこのことから看取していただきたいのは、このような原理を通じて、太陽光の治癒的な作用のための正しい見解を打ち立てる可能性をいかに生み出していくか、ということです。たとえば、一面においては、周囲の太陽光との相互プロセスが秩序を失っているのを再び秩序づけるために直接その人を太陽光にさらすことによって、あるいは他面においては、変容させられた光を取り出す時に不規則になっているものを調整するような実質に、その人を内的にさらすことによって、治療を行うことができます。このように変容させられた光を取り出すことは、薬から作用しうるものによって弱体化させられねばならないのです。ここで皆さんは人間の生体組織をのぞきこむことができます。ここで、世界全般を観察できる人にとって奇妙なことが起こってきます。そういう人はーーいささか外交的でない言い方をお許しください。しばらくすると私がお話することは一見反駁される可能性もあるにもかかわらず、これはそもそも共感も反感も無いという意味でまったく客観的なことなのです。顕微鏡で観察することすべてに対して、微小な世界の観察全般に対して、一種の激しい怒りをおぼえるのです。なぜなら、顕微鏡での観察はそもそも、生命と生命を妨げるものとを健全に把握する可能性に導くやいなや、むしろそこから逸脱させるものだからです。と申しますのも、健康であるにせよ病気であるにせよ人間において私たちに関わってくる真のプロセスはすべて、顕微鏡的なものにおけるよりも、巨視的なもののにおいてはるかによりよく研究できるからです。私たちはマクロコスモスのなかにこそ、こういう事柄を研究する機会を探さなければならないのです。皆さんに注意していただきたいことは、鳥類は、膀胱と大腸の発達が不十分であるために、摂取と排泄との間に絶えず持続的な平衡状態を保っていることです。鳥は飛翔しながら排泄することができます。鳥は食べたものの残りを体内にとどめて蓄積するということはありません。鳥にはそうする機会がないのです。もし鳥が食べたものの残りを体内に蓄積したとしたら、それは即座に病気であり、鳥の体をだめにしてしまうでしょう。私たちが人間である限り、物質的な人間である限り、私たちは、いわば今日的な見解に沿って言うならば鳥よりも進化したわけですが、もっと正確な言いかたができるとすれば、鳥よりも下に降りてきたと言えるのです。鳥は実際のところ、腸菌群落に対して激しい戦いを展開する必要はありません。高等動物や人間には必要なこの腸菌群落が鳥の体内には全く無いのですから。けれども私たちの、より高位に置かれた活動と申しますか、例えば先ほどお話しましたエーテル的なものを変化させる活動、光を変化させて変容に導く活動、こういう活動に関しましては、私たちは鳥と同じ位置に立っているのです。私たちは物質的な膀胱と物質的な大腸を有していますが、これらの器官に関わる私たちのエーテル体に関しては、私たちは鳥なのです。実際こういう器官は宇宙において動的に存在してはいないのです。そこでは私たちも光を受け取って直接これを加工し、排泄物としてまた排出するということに頼っているのです。ここに支障が起こると、この支障に対応する器官がないために、私たちは健康を損なうことなしに難なくこの支障に耐えるということはでません。ですから、この小さな脳を備えた鳥というものを観察する際に明確にしておかなければならないことは、鳥は、私たちのより精妙な生体組織のマクロコスモスにおける写像であるということです。したがって人間というものを、鳥よりも下に降った粗雑な組織に写し取られた、より精妙な組織ということに関連して研究しようとすれば、皆さんはまさにマクロコスモス的に鳥の世界の出来事を研究しなければならないのです。ただここで申し上げておきたいことは、これは括弧付きで述べるのが望ましいことかましれませんが、人間が物質的組織において鳥類に比較して有している特性を、そのエーテル的組織においても持っているとしたら、実際人間の生活は悲しむべきものになるでしょう。なぜならエーテル的組織は物質的組織のようには外界から遮断されることができないからです。そうなると変容させた光を貯蔵する時には、それを感じとる臭覚器官がもし存在するなら、人間の共同生活はかなり悲惨な状態になるでしょう。もっとも先ほど申しましたとおり、これは括弧付きで述べるべきことです。私たちが羊を死後解剖して、その内部の匂いをかいだときに経験するのと同じことが起こってくるわけです。一方、エーテル体的なものに関しては、実際のところ私たちが人間としてお互い向き合っているやりかたは、たとえば腐肉を食する鳥でさえそれを解剖する際に不快な匂いを発散しませんが、この全く不快でない匂い、もちろんすべては比較的、相対的にそう言えるだけですがそれにに比較されます。この不快ではないというのは、私たちがとりわけ反芻動物、ようやく反芻動物への素質を持ち始めた、たとえば馬のような動物でも、馬は正確には反芻動物ではありませんが、その組織において反芻動物への素質が見られるのですから同様にして、これを解剖する時に発散される匂いに比較してそう言えるのですが、この不快ではない匂いに比較されるのです。つまり重要なことは、外部の植物相と動物相に起こっていることと、人間の生体組織のなかの腸内の動物相と植物相において起こっていて克服されねばならないこととの対応を調べていくことなのです。そして何らかの薬と器官との関係を確定しようとすると、私たちは、きょう展開してまいりました一般的な特徴付けから、明日以降の講演での個別的な特徴付けへと進んでいかなければなりません。けれども、私たちが一面においては、植物化の出現に対抗する戦いを循環プロセスのなかに見出すことによって、人間内部の、つまり腸内の動物相及び植物相の克服へと進んで行かなければならないように、皆さんはここから出発して本来の神経・感覚人間へと進んで行くわけです。この神経・感覚人間は、人間の生活全体にとって、通常考えられているよりもずっと重要なのです。科学というものがこのような抽象に高められたために、次のようなことを適切な方法で考慮する可能性はまったく失われてしまいました。つまり、この神経・感覚人間を通じてたとえば光と光に結びついた熱とがそもそも入り込んでくるわけですが、この神経・感覚人間は内的な生活と密接に関係しています。なぜなら光とともに入り込んでくる計測できないものは、諸器官において変容させられねばならず、そしてこの計測できないものは、計測できる領域に存在しているものと同様、器官を形成するものだからですが、こういうことを考慮する可能性は失われてしまったのです。神経・感覚人間が人間の組織化にとって特別な意味を持っていることは、まったく考慮に入れられておりません。しかし、私たちが下部人間のなかにより深く下降していく場合は、腸内植物相を形成する力から、腸内動物相を形成する力へと下降していくのですが、他方、人間の上部へと昇っていく場合は、私たちは内部の植物相が克服される領域から、人間の絶えざる鉱物化、いわば人間の硬化が克服されねばならない領域へと上昇するのです。皆さんはここで、いわば外的に、頭部の骨化が他の部分より顕著であるということから見ても、人間は上へ向かって進化するほど、その器官を通じてまさに鉱物的になる傾向が強まるということを研究することができます。この鉱物的になるということ、これは人間の生体組織全体にとって大きな意味をもっています。と申しますのも、よろしいでしょうか、これは繰り返し留意されねばならないことなのですが、私は公開講演においても指摘してきたのですが、人間を三つの部分、すなわち、頭、胴体、四肢という三つの部分に分けるとき、これらの三つの部分が並列的にあって、外的空間的な境界を有していると考えていただいては困るのです。質的に区分するとすれば、人間というものは当然まったくもって頭人間です。頭であるものは人間全体に拡がっていて、その主要な部分が頭にあるというだけです。他の部分、つまり循環と、四肢及び新陳代謝についても同じで、これらも常に人間全体に拡がっています。このため、当然のことながら、頭ないし頭部人間にとって存在しなければならないものが、素質としては人間全体のなかに存在しているのですが、この人間全体における鉱物的になっていく素質は克服されねばならないのです。今日の人間が、まだ遺伝的な霊視能力から導き出されていた古代の著作をひもといても、もはや何も理解できない分野というのは、まさしくここにあるのです。なぜなら結局のところ、パラケルススの言う塩プロセスについて読んでも(☆3)、今日ほんのわずかの人しか何かまっとうなことを読みとることはできないからです。ところでこの塩プロセスというのは、私がちょうど今特徴をお話ししている領域にあたり、硫黄プロセスというのがその前にお話しした領域にあたります。原注3 パラケルスス「オープス パラミールム」記:「オープス・パラミールム」(Opus Paramirum)は、16世紀のスイス出身の錬金術師であり医師でもあったパラケルスス(本名:テオフラストゥス・フォン・ホーエンハイム)の著作の一つです。この作品は、彼の医学や錬金術に関する理論をまとめたもので、特に病気の原因や治療法についての新しい視点を提供しています。パラケルススは、従来の四体液説に反対し、病気の原因を化学的な不均衡に求めました。彼は、硫黄、水銀、塩の三原質が人体の健康に重要であると考え、これらのバランスが崩れることで病気が発生すると主張、今じゃ非常に危うい説となります。よく話題にされるナポレオン・ボナパルトの脳内発見された水銀から推察された水銀他殺説やヒ素中毒説も、真相は養生訓の実践だったのかもしれません。参考画像;Napoléon Bonaparte Died さて重要なことは、人間は自らのうちに、鉱物化しようとする傾向を有しているということです。ちょうど、動物相・植物相プロセスの基礎を成しているものがいわば独立的になり得るのと同様に、人間全体にとってこの鉱物化の傾向も独立性を持つ可能性があるのです。この鉱物化の傾向に対して、どのように対抗して働きかけねばならないのでしょうか。これに対抗する働きかけは、この鉱物化傾向を粉砕し、いわばそのなかに絶えずくさびを打ち込む以外にはありません。そしてこの領域こそ、皆さんが血清療法から植物療法を経て鉱物療法へと移行して踏み込んでいくところなのです。何しろ鉱物療法なしでやっていくわけにはいきません。なぜなら、皆さんが、鉱物化していく傾向、普遍的に硬化していく傾向に対する人間の戦いにおいて、支えられねばならないものすべてを支えるための拠り所を得られるのは、鉱物と、人間のなかで自ら鉱物になろうとするものとの関係においてのみだからです。その際皆さんは、鉱物を単にその外的な状態のままで人間の生体組織に取り入れる方法でやっていくことはできません。ここで、何らかの形でのホメオパシー原理を示すもの、つまり、外的な鉱物界の活動性に対置されるような力が、ほかならぬ鉱物界から探り出されねばならないことを示すもの、そういうものが登場してくるのです。これはよく指摘されてきたことで、実際正しいのですが、治癒作用のある泉のわずかなミネラル成分に注目しさえすれば、この泉ではめざましいホメオパシープロセスが起こっているのがわかります。このプロセスは、私たちが通常見ている外的な諸力から鉱物の連関を解放する瞬間に、まったく別の諸力、つまりまさしくホメオパシーを行うことによってしか特別に解き放たれない別の諸力が本当に現れてくることを示しています。けれどのこのことは、申しましたように、別の章で述べようと思います。それでもなお、きょう皆さんがたにお話ししておきたいことは、次のようなことなのです。皆さんが実際に、特に比較的若いかたがたに私は切にお勧めしたいのですが、腸組織全体の形態変化、言うなれば、一面においては魚類から両生類、爬虫類を経て鳥類に至る変化、とりわけ両生類、爬虫類と腸組織との関係はきわめて興味深いも。他面においては、哺乳類そして人間にまで至る変化について、比較研究されてみれば、次のようなことに気づかれるでしょう、つまり、器官の特殊な形態変化が起こり、たとえば盲腸ができてくるのです。すなわち人間の場合には後に盲腸となるものが現れ、下等な哺乳動物の場合や、鳥類の組織から何かが落ちて盲腸の原基が現れてくる場合には、魚には全く存在していない大腸から、魚の場合大腸については語ることし得ずですが、いわゆるより完全な秩序による上昇を通じて大腸が、さらには複数の盲腸、人間の場合はひとつの盲腸であるものがあらわれてくるのです。他の動物のなかには複数の盲腸を持つ種類もいるのです。こういう発生のしかた全体のなかに皆さんは独特の相互関係を見出されることでしょう。本来こういう相互関係こそ比較研究が非常に厳密に指摘せねばならないことなのです。皆さんは単に外面的に、ご存じの通り実際しょっちゅうこう問われるのですが、いったい何のために、人間の盲腸のようなこういう外に向かって閉じたものが存在しているのかと問うことができます。こういう事柄について問われることはしばしばあるのです。このような問いを投げかけるとき、通常は次のようなことに注目されることはありません。つまり、実際のところ人間は二元性(Dualitaet)として自己を開示しているということ、したがって、一方つまり下部において形成されているものは、常に上部で形成されているものの平行器官(das Parallelorgan)であり、この平行器官、いわば対極が、下部において発達することができないとしたら、上部において何らかの器官が発生できないということ、こういうことに注目されてはいないのです。そして、動物の系列において前脳が形態を取れば取るほど、人間の場合これを後に発達させるのですが、それだけいっそう腸は、まさに食べたものの残りを蓄積する方向へと形成されるのです。腸形成と脳形成の間には密接な関係があり、動物の進化系列において大腸、盲腸が現れてこなかったら、結局は物質的本性として思考する人間というものも発生できないでしょう、なぜなら、人間が脳すなわち思考器官を持つのは、腸器官の負担、まったくもって腸器官のおかげだからです。腸器官は脳器官の忠実な裏面なのです。皆さんが一方において思考のために物質的活動を免除されるためには、他方において皆さんの器官に、形成された大腸と形成された膀胱による負担のきっかけとなっているものを担わせなければならないのです。このように、人間の物質的世界に現れているまさに最高の霊的ー魂的活動は、脳の完全な形成と結びついているのと同時に、その一部である腸の形成とも結びついているのです。これはきわめて重要な関係であり、自然の創造全体に途方もなく多大な光を投げかけるものです。さて、ここで皆さんは、たとえいくぶん逆説的に聞こえるにしても、人間にはなぜ盲腸があるのかと問いかけ、人間が相応なしかたで思考することができるためにあるのだと答えることができるのです。なぜなら、盲腸において形成されているものは、人間の脳のなかに、それに対置されるものを持つからです。一方にあるものはすべて、他方にあるものに対応しているのです。これは新しい種類の認識方法で再び獲得されねばならないことです。むろん私たちは、いまだ遺伝的な霊視力に立脚していた古代の医師たちを、今日そのまま模倣することはできません。それでは得るところはほとんどないからです。それでもこういう事柄を再び獲得しなくてはならないのです。こういう事柄の獲得にとってまさに最初の障壁になっているのが、このような関連をそもそも探究しない純粋に唯物論的な医学教育です。今日の自然科学と医学にとって、脳はまったくもってひとつの内蔵であり、下腹部にあるものもひとつの内蔵です。ここでは、陽電気と陰電気はまったく同じもので、両方とも電気だと言う場合と同じ誤謬が犯されているということに、人々はまったく気づいておりません。陽電気と陰電気の間には、互いに均衡を求める緊張が生じているのとまったく同じように、人間においても上部と下部の間に絶えず緊張が存在しているからこそ、この誤謬に気づくことは、いっそう重要なのです。医学の分野において優先的に探究されるべきことは、本来、この緊張の制御という点にあるのです。この緊張は、きょうはこのことを暗示しておきまして、以後の考察でさらに詳しく述べていきますが、二つの器官に集中する力のなかに、つまり、松果腺といわゆる粘液腺のなかに現れています。松果腺においては、上部の力であるすべての力が現れており、下部の力である粘液腺の力、脳下垂体(Hypophysis cerebri)の力に対して緊張関係を成しているのです。ここには真の緊張関係が成立しています。この緊張関係に関して人間の状態全体から見解を打ち立てるならば、さらなる治療プロセスのための非常に良い基本原理が得られるのですが。これについては明日もう少しお話ししようと思います。皆さんのご質問にはすべて入っていくつもりです。けれどもすでに申しましたように、そのための基礎を作り上げなければならないのです。 (第四講本講:1-2了 本文 了)
2024年08月25日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第四講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 本講:本文・解説第四講本講:本文1-1 昨日の午後の議論はなるほど極めて興味深いものではありましたが、私が今しがた目にいたしました質問との関連で、既にもう行ったことではありますが、やはりもう一度、次のようなことを強調しておく必要があります。すなわち、個々の治療薬と個々の症状との関連を見い出すために十分な方法は、ここでの考察のなかで前もってある種の基礎的問題を処理してしまってからでないと得られないだろうということです。これらの基礎的問題によってようやく私たちは、人間と人間の外部のもの、この人間の外部にあるものから薬が取り出されるのですが、この人間と人間外のものとの関連についての認識の有効範囲を推し量ることができるようになるのです。とりわけ、個々の治療薬と個々の器官との関係について語ることは、これらの基礎的問題を処理することなしには不可能でなのです。その理由は明白で、この薬と器官との関係というのは全く単純なものではなく、いささか複雑なものであって、私たちがきょう、あるいはもしかすると一部は明日にも処理していくべき基礎的問題を処理してからでないと、この本来の意味を推し量ることはできないからです。それに続いて、この治療薬とりわけ治療処置と、個々の器官疾病との具体的な関係を実際に議論する可能性がでてくるでしょう。けれども、きょうさっそく前置きとして申し上げておきたい今一つのことも、とりあえずは皆さんに取り入れていただきたいのです。そのことからある種の光が当てられることもあるでしょうから。と申しますのは、こういう事柄は当然のことながら最初はショックを与えるものですので、これらはいささかショッキングな事柄なのだということを先に強調しておかなければなりません。昨日の午後ここで検討されたこととの関連で申し上げたいのは、皆さんが物事の別の側面に留意してくださるようお願いしたいということです。昨日ここでまったく特定の治療について非常に啓発される事例が数多く紹介されたことは、私たちにとってきわめて満足のいくことでした。さて、私はこういう治療をおそらくどんどん稀少なものにしていくごく単純な手段を皆さんに示すことができます。けれども私は皆さんがこの手段を用いないようにするためにこそ、これを用いることは当然考えられることですから、この手段をご紹介したいのです。この手段については、むろん人智学的な素養のある方々のもとでしかお話しすることはできません。この手段というのは、皆さんがリッターの治療法(☆1)を普遍的なものにしようとあらゆる策を講じるという点にあると言えるでしょう。皆さんは治療の成功に関しては、自分は個人的としてひとりの医師であるということを尊重するわけにはいきません。なるほど、個人としては次のようなことを意識しておられる方もいらっしゃるかもしれません。つまり、自分はひとりの医師として、大きな医師集団というものに対して戦わなければならない、けれどもリッターの治療法を大学の要件にしたとたんにそれに染まってしまうだろう。もはや反対の立場には立たず、非常に多くの、すべてのとは決して申しませんが、病気が癒されるので、自分の治療の成果は著しく減少するという経験をするだろう。このように意識しておられる方もいらっしゃるかもしれません。現実の生活においてはこういうことがあるのです。つまり、ものごとは普通考えられているのとは異なっていることが多いのです。医師個人としてはひとりひとりの人間を治療することが最大の関心事であるのは当然のことですが、現代の唯物論的な医学は、それどころか、ひとりひとりの人間を治療することに単に挑みかかるしかないということの一種の法的根拠と申しますか、そういうものをこの方法で探し求めてきたわけです。原注1 リッターの治療法:「M・リッターの光力学的治療の実践的応用のための手引き」(ミュンヘン、1913)及び「神経ー力学的治療法ーー蛍光素材及び発光(ルミネセンス)素材の細胞領域と神経死に対する作用に関する研究と経験との関連で」(ライプツィヒ、1905)参照。 実際、この法的根拠は、そもそも病気などというものは存在しない、存在しているのは病人だけだと言われているところにあるのです。当然のことながら、人間が病気に関しても、今日外面的に見えているとおり切り離されているのだとしたら、このような根拠も真の根拠となるでしょう。しかし実際に起こっていることは、人間はこのようなことが大きな意味を持つほどには実際に切り離されてはおらず、ちょうど昨日にE.博士が言及されたように、ある種の病気のスパンは、かなり広範囲にわたっており、皆さんがある人を治したとしても、別の場合にはまた別の人たちに病気を押しつけたこともあるかも知れないといったことは決して確定できないのです。個々の病例をプロセス全体のなかに置いてみないと、こういう事柄は個別的にははなはだ驚愕させられるものです。けれども、人類の治癒ということを全体として見ようとする人は、やはり別の角度からも語らなくてはならないのです。このことから、一面的に単に臨床的な方向付けをするだけではなく、完全に病理学をもとにして治療というものを引き出してくることがぜひとも必要となってくるのです。私たちがここで試みようとしていることはまさしく、通常は単なる経験的ー統計的な思考であるものに一種の理性(Ratio)をもたらすことなのです。さて、きょうは誰もがよく知っている事実から始めようと思います。この事実は自然科学的、医学的思考との関連ではまったく正当に評価されておりませんが、人間の人間外部の自然に対する関係を判断するための基礎を提供してくれるものなのです。これは、三つの部分から成る存在としての人間、すなわち、神経・感覚存在としての、循環存在、つまり律動的存在としての、そして新陳代謝存在としての人間は、新陳代謝存在であることによって、外部の自然、植物界において起こっていることに対する陰画(ネガ)として関係づけられているという事実です。次のような事実を魂の前に描き出していただきたいのです。つまり外部の自然において、さしあたりこの自然のうちの植物界だけを観察すると、植物相においては、いわば炭素を集積し、この炭素を全植物相の基盤とする傾向が認められます。私たちは植物に囲まれていることによって、炭素の集積に基づいた本質を持つ有機体、形成物に囲まれているわけです。忘れないでいただきたいのは、この形成の基礎を成しているものは人間の生体組織にも現れているのですが、人間の生体組織はその本質において、形成の過程でいわば発生期状態[Status nascendi]が進行していくうちに、この形成を止揚し破壊して、代わりにその反対の形成を取り入れねばならないということです。このプロセスの端緒は、私たちの内部の、私が先日来下部の人間と呼んできたもののなかに見出されます。私たちは炭素を沈殿させて、いわば私たち自身の力から植物化のプロセスを始め、その後私たちの上部の組織に誘導されて、この植物化に抵抗しなければなりません。私たちは炭素に酸素を対抗させることで炭素を止揚し、炭素を炭酸に加工し、それによって私たちのなかに植物化に対抗するプロセスを形成していかなければならないのです。いたるところでこの外的な自然とは反対のプロセスに注意していただきたいのです。と申しますのも、このことに注意していただければ、皆さんは真実の人間をますます根本的に理解されるようになるからです。人間の重さを計っても、物理学的な研究方法にのっとった他の研究に対しては象徴的にこういう言いかたができますし、人間そのものを理解することはできないのですが、次のようなことを考慮すれば、人間のメカニズムについてすぐさま何らかのことは理解できるのです。つまり、脳の重量は良く知られているように平均千三百グラムあるけれども、この重量で頭蓋の下半分の面が圧迫されることはない、なぜなら脳の自前の重量で圧迫されたなら、繊細な血管が拡がっている部分はすべて押しつぶされてしまうからといったことです。脳が自らの土台を圧迫している重さはせいぜい二十グラムです。これは、脳が脳水のなかに浮かんでいるという事実のために、良く知られたアルキメデスの水圧の原理に従って浮力を得ており、その結果脳の重量の大部分は作用せず、浮力によって止揚されているからです。ここにおいて重さが克服され、私たちが自らの生体組織の重量のなかではなく、重量の破棄のなかに、物理的な重量とは反対の力のなかに生きているということは、人間のその他のプロセスの場合も同様なのです。実際のところ私たちは自然現象(Physis)が私たちとともに作り出すものではなく、自然現象から止揚されたもののなかで生きているのです。さらに私たちは実際のところ、外的自然のなかにも存在していて、植物界においてその最終部分を体験するプロセスとして知覚されるようなプロセスのなかで生きているのでもなく、私たちは植物化を止揚することによって生きているのです。このことは、私たちが病気にかかっている人間の生体組織と植物薬との間に橋を架けようとすれば、当然本質的に問題となってくることです。さて、こういうことは、いわばちょっとした短編小説風に叙述できるかもしれません。世界のすばらしい植物相(Flora)として私たちを取り囲んでいるものすべてに眼差しを向けると、私たちは当然のことながら歓びを、とても大きな歓びを感じると言えるのではないでしょうか。けれども、羊を解剖して、その解剖の直後に別の植物相を目にするときはそうではありません。この羊の体内の別の植物相は、その発生原因という点でも、外部の植物相の発生原因と決定的に類似しているのですが、羊を死後に解剖して、この羊の内部のまったき腐敗臭がこちらに漂ってくるのを感じるとき、この腸内の植物相、すなわち腸菌群落(Darmflora)に対して私たちは歓びを感じるどころではありません。けれども、このことにこそ特に注目する必要があるのです。なぜならば、人間の外部の自然においては植物相を軌道にのせる原因であっても、それは人間においては克服されねばならず、腸内の腸菌群落が発生させられてはならないことは明白だからです。ここにはきわめて広範な研究領域が拡がっており、比較的お若い、勉学中の医学生の皆さんにお勧めしたいのですが、学位請求論文のためにこの領域から多くを役立てられるとよいのではないかと思います。とりわけさまざまな動物の形態、哺乳動物を経て人間にいたる形態における、腸形成の比較研究という領域からは得るところが多いと思います。この領域においては、きわめて重要なことがまだ数多く研究されないままなので、非常に実り豊かな分野が成立するでしょう。とりわけ、羊を解剖すると、その腸菌群落のためにひどい腐敗臭が発散されるのに、鳥類の場合は腐肉を食する鳥の場合でも腐敗臭はなく、解剖しても比較的心地よいとさえ言える匂いを発するのはなぜなのか、一度その隠れた事情を探究してみていただきたいのです。こういう事柄においては、まだ非常に多くのことが今日まで十分学問的に研究されておりません。この領域における腸の形態の研究についてはなおさらです。ちょっと考えてみて下さい。鳥類全体が、哺乳類との、そして人類との本質的な差異を示しているのです。鳥類の場合、例えばパリの医師メチュニコフ(☆2)のような唯物論的な医師たちは、まさにこういう事柄について最大の思い違いをしてきたわけですが、膀胱と大腸は、きわめて未発達なのです。鳥類が走禽類となるところでようやく、大腸の形態、および膀胱の形態におけるある種の膨隆(Ausbuchtungen)が見い出されます。こうして私たちに重要な事実が示されるのです。つまり、鳥においては、排泄物を蓄積したり、一定期間生体組織内にとどめたりしてからその排泄物を随意に排出するなどということはなく、摂取と排泄との間に持続的な平衡状態が成立しているということです。原注2 Elias Metschnikoff/1845-1905はオデッサ大学で動物学教授で後にはパリのパスツール研究所副所長を務める。参考画像:Elias Metschnikoff (第四講本講:1-1了)哲学・思想ランキング
2024年08月24日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」第三講●解説 概要・解説 1-3 治療手段と人間の関係。植物における成長の変容。適応力と再生。人間の形成力と霊的・魂的機能。現実に適応した心理学の基礎。上昇する進化と下降する進化。血液形成プロセスと乳汁形成プロセス。●解説1-3 人間の外部から薬というものを取り入れるわけですから、人間と人間の外部とがどのように関係しているのかを正しく認識する必要があります。人間の外部からの人間の生体組織に対する影響は3種類あります。感覚による知覚、呼吸と循環、新陳代謝による影響の3つです。このうち、外界と人間の間の相互作用が最も顕著に現れているのが、感覚による知覚、つまり神経組織への影響です。とはいえ、つぎのような疑問を提出せざるを得ないでしょう。つまり、感覚による知覚(Sinneswahrnehmung)とそれに類するすべてのものは、人間の生体組織に対して薬剤から発せられている筈の、いわば少々異なった種類の影響のための手がかりを私たちに与えてくれるのかという疑問です。さて、正常な状態において、人間の生体組織に対する三種類の影響があると言えるのではないでしょうか。第一に感覚による知覚を通しての影響で、これは神経組織のなかでさらに継続されます。第二に、律動組織、すなわち呼吸と循環による影響、第三に新陳代謝による影響、以上の三つです。これら三つの正常な関係は、何らかの方法で外的自然から取ってこなければならない薬剤と、人間の生体組織の間に私たちが作り上げる異常な関係のなかに、何らかの相似物を有しているはずです。しかしながら、外界と人間の生体組織との間に起こっていることがもっとも顕著に現れるのは、神経組織への影響においてなのです。従って私たちは次のように問わなければなりません。人間自身と、人間の外部にある自然であるもの、つまり、その経過としてであれ、実質的に薬剤としてであれ、人間の治療のために私たちが利用しようとする外的自然、この両者の間に、私たちはどうやって合理的な関係を考えることができるのかと。私たちは、人間と、私たちがそこから薬剤を取ってくる人間の外部の自然との相互関係がどのようなものであるかについて、ひとつの見解を獲得せねばなりません。と申しますのも、水治療法を適用するときでさえ、私たちは何か人間の外部にあるものを用いているからです。適用されるものはすべて、人間の外部にあるものから人間のプロセスへと適用されているのであり、私たちは、人間と人間の外部のプロセスとの間の関係がどういうものなのかについて、合理的な見解を手に入れなければならないのです。現代の医学教育にあっては、人間外部の自然と人間との関係について十分に追求されているとはいえません。ともかくここで、現在慣例となっている医学という学問の組織的関係に代わって純粋な集合体としてまとまりのあるテーマにたどり着きます。医学生は通常まず準備段階として自然科学の講義を聴きます。それからこれを基礎にして、一般病理学および個別病理学的なもの、一般治療学的なもの等が構成されるのですが、いざ本来の医学の講義が始まると、この本来の医学講義で語られているプロセス、つまり治療処置というものが、外的自然の経過といかなる関係にあるのかについては、もはや聞くべきことはあまりないということになります。私が思いますには、今日の医学教育を受けてきた医師達は、このことを、単に外的知性的に欠陥であると感じるだけでなく、実際に病気のプロセスに介入すべきときに沸き起こってくる感覚のなかで、ある感情として、何かを用いようとする際にある種の不確実さの感情として、自らの心のうちに強く刻みつけることでしょう。使用すべき薬剤と、人間のなかで生じている、実際に存在しているものとの関係が真に認識されることは何といってもまれなのです。ここでは、ことの本性そのものから医学という学問の改革の必要性を指摘することが重要です。人間の外部の自然と人間の生体組織との関係について認識するためには、まず人間外の自然のプロセスと人間の内部のプロセスとがどのように異なっているかを明確に知る必要があります。とりわけ植物や下等な動物にみられる成長の形態変化が人間の場合とはまったく異なっていることがニセアカシアの形態変化を例として説明されています。さて、今日は先ず、人間の外部の自然におけるある種のプロセスを手がかりに、これらのプロセスが、多くの点において人間の内部の自然のプロセスといかに異なっているかを明確にすることから始めたいと思います。私はまず、下等な動物や植物において観察できるプロセスから始めて、そこからさらに、人間の外部にあるもの一般つまり植物界、動物界、とりわけ鉱物界から取り出されるものによって引き起こされるプロセスへの道を見出したいと思います。けれども私たちが、純粋な鉱物実質のこういう特徴付けに接近することは、ごく基本的な自然科学的表象から出発して、さらに、例えば砒素や鉛といった薬品ではないものを人間の生体組織のなかに取り入れる際に起こることへと上昇していくときに、はじめて可能になるのです。ここでまず指摘せねばならないことは、人間以外の存在においては、成長における形態変化(Wachstums-metamorphosen)が、人間の内部の自然そのものの場合とはまったく異なっているということです。私たちは、人間のなかの本来の成長の原理、生きた成長の原理を何らかの方法で考えないわけにはいかないでしょうし、人間以外の存在の成長の原理も考えねばならないでしょう。けれども根本的な意味を持っているのは、そこで生じてくる差異なのです。例えば何か非常に身近なもの、通称ニセアカシア、ロビニア・プセウドアカシア(Robinia pseudakasia)を観察してみてください。このニセアカシアの葉を葉柄のところで切り取ると、興味深いことに、葉柄が形態変化によっていくらか変形され、さらにこの変形されてこぶ状になった葉柄が、葉の機能を受け継ぐということが起こります。ここでは、私たちがとりあえず仮説的にひとつの力と呼びたい何かが強く働いています。この力は植物全体のなかに潜んでいて、私たちが、その植物がその正常に形成された器官を特定の機能のために用いるのを妨げるときに発現してくる力なのです。単純に成長する植物において非常にはっきりと現れているものの名残りと申しましょうか、そういうものが存在している、ということは、人間の場合も、何らかの理由によって一方の腕あるいは手を何らかの機能のために用いるのを妨げられた人は、もう一方の腕あるいは手がより力強く形成され、物理的にも大きくなる、などといった事例によって証明されます。私たちはこういう事柄を互いに結びつけなければなりません。なぜなら、これが治療法の可能性を認識することに至る道なのですから。人間の外部にある自然においては、たとえば植物がその環境に適応しようとして葉を変形させるように、その内的な形成力が存在しているということがわかります。こうした形成力は、特にミミズのような下等動物において顕著に見られます。つまり、ミミズの一部を切り取っても、その切り取られた部分は元通りに形成されるのです。さて、人間の外部の自然においては事態は非常に広範囲にわたっています。例えば次のようなことが観察できるのです。山の斜面にある植物が生えていると考えて下さい。こういう植物は、葉を形成させないようなかたちで特定の葉柄を発達させる、ということが起こるのです。葉が生えてこないのです。これに対して葉柄は湾曲して、支持する器官になります。葉は萎縮し、葉柄は湾曲して支持器官となり、自らを支えます。これは変形した葉柄を備え、葉の萎縮した植物なのです。植物というものが、その環境に限定された生存様式に広範囲に適応することができるということは、植物において作用している内的な形成力の存在を示しています。さて、この内部で働いている諸力は、とりわけ下等生物においてきわめて興味深いかたちで現れてきます。たとえば、原腸胚段階まで進んだ胚を取りあげてみましょう。記:原腸胚とは嚢胚卵発生における胞胚の次の段階 原腸胚を切断し、真ん中で切り離すと、切り離されたおのおのの断片は再び丸くなり、それぞれ前腸、中腸、後腸の三つの部分を形成する能力を自らのうちに養成します。つまり私たちが原腸胚を切断すると、二つの断片はそれぞれ、切断されていない全体がしたであろうことと同じことをするのがわかります。ご存知のように、この試みは、下等動物、蚯蚓(ミミズ)にまで広げることができます。何らかの下等動物の一部を切り取ると、その部分は新たに補充されます。自らの内的な形成力から、切り取られたものと同じものが元通り得られるのです。こうした内的な形成力によって新たに成長してくるのは、その傷口のところにある緊張力によってだという考え方は事実に即したものではありません。もし仮にそれが事実だとすれば、新たに生じてくるものは、傷口のすぐとなりにある部分が機械的に複製されるはずであるにもかかわらず、実際にはそうではなく、失われた部分の全体が再生されます。ですから、緊張力ではなく、生体組織全体が関与しているというふうにとらえる必要があるのです。こういう形成力は、事実に即して指摘されねばなりません。何らかの生命力を想定することで仮説的に指摘するのではなく、事実に即してこういう形成力が指摘されねばならないのです。なぜならば、そのとき実際起こっていることをより正確に見て本当に追求するならば、次のようなことがわかるからです。たとえば、非常に初期の段階のカエルの生体組織のどこかを切り取ると、切り取られた組織、別の組織が新たに生じてきます。いくらか唯物論的な考えかたをする人は、次のように言うでしょう。傷口のところに緊張力(Spannkraefte)というものがあるではないか、この傷口の緊張力によって、ここに新たに成長してくるものが生えてくるのだと。けれどもそういうことはあり得ないのです。なぜなら、もし私がある組織をここで切断して(図)この傷口のところに、ここにある緊張力によって新しいものが生じてくるとするなら、ここに生じてくるのは、このすぐ近くの部分、すなわち完全な組織のなかで直接隣り合っている部分であるはずだからです。けれども実際にはそういうことはなく、カエルの幼生の一部を切り取ると、末端器官、つまり尾や頭部でも、他の動物の場合は触覚糸といったものでも実際に出現してきます。つまりそこに接しているものではなく、その組織にとってとりもなおさず必要なものがそこから生じてくるのです。ですから、ここに直接内在している緊張力によって、自らを形成するものがここに生じてくるということは不可能なのです。この再生に際しては、緊張力ではなく、生体組織全体がなんらかの方法で参加していると考える必要があります。人間の場合は、指や腕が切断されても、下等動物のように、それが再生させることはありません。下等動物にみられるような形成力が人間にはなぜ存在していないのかという問いはおそらくは多くの方が、少なからず問いかけた疑問ではないかと思われます。私にしても、「トカゲの尻尾が再生するのに人間はどうしてそうではないのか」とかいう類の疑問は小学生の頃から持っていましたが、それに対する何らかの答えはシュタイナーの示唆によって始めて得ることができました。このように、下等生物において起こっていることを実際に追求していくことができます。私は、今日まで文献に記載されたあらゆる経験までこのことを拡張していくときこれをどのように追求していくかという道を皆さんに提示したわけですが、この道を通ってしかこういう事柄についての見解にはたどりつけないのだということを、いたるところでご確認いただけると思います。皆さんは、人間の場合だったらこういうことはあり得ないのだ、という以外の思いはほとんど抱かれないのではないでしょうか。実際、指や腕が切断されてもそれを補充できるとしたら、とてもすばらしいでしょう。でもそれは不可能なのです。そこでこういう問いが生じます。この、かつての成長形成力であり、ここに非常に顕著に現れている力、こういう力は、いったい人間の生体組織においてはどうなっているのか。この力は人間においては失われてしまったのか、そもそも人間にはまったく存在していないのかという問いです。シュタイナーは、下等動物において存在している内的な形成力は、人間の場合、実質的な器官のなかには存在せず、魂的ー霊的なもののなかにのみ存在しているのだといいます。下等動物や植物界において造形的に働いている諸力を使って人間は、考えたり感じたり、意志したりできるというのです。つまり、内的な形成力がそうした魂的ー霊的な力に変容しているのだといえます。事実に即して自然を観察することを心得ているひとは、人間における精神的なものと物質的なものとの関連についての自然に即した見解に至ることができるためには、そもそもこの道を通って行くしかないということを知っています。つまり、私たちがここで造形的な、と申しますか、そういうものとして始めて出会う力、ここで実質から直接形態を創り出す力、こういう力は、人間の場合には諸器官からすっかり取り出され、人間の魂的ー霊的なもののなかにのみ存在しているのです。つまり、魂的・霊的なもののなかにあるわけです。この力が諸器官から取り出され、それがもう諸器官の形成力ではないことによって、人間はこの力を特別なかたちで所有しています。人間はそれを、自らの霊的ー魂的機能のなかに有しているのです。私が考えたり、感じたりするとき、私は、下等動物や植物界において造形的に働いている諸力と同じ力によって考えたり、感じたりしているのです。私が、物質素材から引き出した力を使って思考し、感じ、意志することを行わないとしたら、私は考えることなどできないでしょう。従って下等生物を眺めると、私はこう言わざるを得ません。この下等生物の内部にひそんでいるもの、造形的な力であるもの、これと同じものを私も自らのうちに有している。けれども私は、これを私の器官から取り出し、自分自身のために所有している、そして、外部の下等生物の世界では造形的に働いているこの同じ力を用いて、私は思考し、感じ、意志しているのだと。今日の心理学を構成しているような単なる言葉によってではなく、自らの心理学的組成における実質によって心理学者になろうとする人は、そもそも思考、感情、意志のプロセスを次のように追求しなくてはならないでしょう。つまり、下方では造形的な形態化のなかに現れている出来事を、ここではまさに霊的ー魂的にのみ経過しているものとして、思考、感情、意志のプロセスのなかに明確に示していかなければばならないのです。もはや生体組織においてはできないことを、私たちがいかに内部の魂的なプロセスにおいてはやってのけているか、ちょっと考えてみてください。私たちは、忘れてしまった一連の思考を他のものから補完できます。このときの私たちのやり方は、先ほど私が、(下等生物の再生について)直接隣り合ったものではなく、そこからずっと離れたものが現れる、説明したこととよく似ているではありませんか。以上、下等動物において存在しているような内的な形成力は、人間の場合、実質的な器官のなかには存在せず、魂的ー霊的な力に変容しているのだという事が述べられましたが、外的な自然現象における形成原理と内的な魂的ー霊的な力とは対応していて、人間においては、外的な形成原理はそのまま生体組織の物質的な基礎となっているのではありませんし、人間の魂的-霊的な力は、生体組織からさまざまな形で取り出してきたものです。私たちが内的・魂的に体験しているものと、外的世界において形成する自然の諸力、形成する自然の原理であるものとの間には、完全な平行現象が成立しています。そこには完全な平行現象が成立しているのです。この平行現象に注意を払わねばなりません。そして、人間にとって根本的に外界における形成原理としてあるものは、人間が魂的ー霊的生活として自身の生体組織から取り出したものであり、その結果それは自身の生体組織においてはもはや物質素材、実質の基礎とはなっていないということを示さなければなりません。とは言っても、私たちはそれを生体組織のすべての部分から同じ度合いで取り出したというわけではなく、取り出し方はそれぞれ異なっています。ただ今展開してまいりましたような予備知識をいわば身に備えている場合にのみ、人間の生体組織に、それに相応しい方法で近づくことができるのです。私たちの神経組織は、原始的な細胞形成の特徴を示していて、進化した細胞であるとはいえません。けれども、それは原始的とはいっても、分割不可能で増殖力を持ちません。初期の進化段階で、そうした増殖力が取り去られ、麻痺させられているのです。この神経細胞のなかで麻痺させられたものが、魂的ー霊的なものとして自らを分離し、通常人間において最高のものとされる精神活動に奉仕しているわけです。一番高等な精神活動に従事しているはずの頭部が、一番原始的な外骨格を有しているというのも、これと関連させて考えると非常に興味深いことではないでしょうか。と申しますのも、私たちの神経系を構成しているすべてのものを観察してごらんになれば、次のような特徴に気づかれるでしょう。つまり、通常神経細胞あるいは神経組織(Nervengewebe)などと呼ばれるものはまさに本来的な形成物であり、比較的初期の発達段階にとどまっていて、それほど進化した細胞形成物ではない、ということです。従って、こうしたいわゆる神経細胞は、初期の原始的な細胞形成の特徴を示していることを期待せざるを得ないと言わねばならないでしょう。けれども別の関連においてはまったくそうではありません。なぜなら、神経細胞はたとえば増殖力を持たないからです。神経細胞は、血液細胞と同じく、形成されると分割不可能で、増殖できないのです。つまり、人間以外のものの細胞に与えられた能力が、比較的初期の段階に神経細胞から奪われているのです。この能力は取り去られているわけです。神経細胞は初期の進化段階にとどまり、いわばこの進化段階で麻痺させられています。この神経細胞のなかで麻痺させられたものが、魂的ー霊的なものとして、自らを分離するのです。その結果私たちは実際に、自らの魂的ー霊的なプロセスによって、かつて器官的実質のなかで自らを形成していたものに立ち返るのですが、これに到達するのは、私たちが比較的初期の段階で殺した、少なくとも麻痺させた神経実質を自らのうちに有していることによってのみ可能なのです。このようにして神経実質の本質に近づくことができます。さらに、この神経細胞が、一面ではかなり原始的な形成に似ているように見え、さらにそれが発達した段階においてさえ原始的な形成に似ているように見えるにも関わらず、それが通常人間において最高のものとされる精神活動に奉仕しているという特性を備えているのはな何故かということがわかってきます。私が思いますに、これはちょっとした挿話で、考察の本筋ではないのですが、人間の頭部を表面的に観察するだけで、つまり人間は頭部のなかにさまざまな神経細胞を有していて、この細胞が固い装甲で覆われているわけですが、このことは、高度に進化した動物よりもむしろ下等な動物を思い起こさせます。私たちの頭部そのものが言うなれば有史以前の動物を想起させるのです。こういう動物をちょっと変形させただけのように思われます。私たちが下等動物について語るとき、通常私たちはこう言います、下等動物は外骨格を有し、他方高等動物と人間は内骨格を有すると。けれども、私たちの最も高度に発達している頭部、この頭部だけは外骨格を有しているのです。このことは、少なくともさきほど述べましたことの一種のライトモチーフとなりうると思います。外的な自然の中に存在している形成力を、植物などからとられた薬として再び生体組織に供給することによって、生体組織の助けにすることができるように、治療プロセスというのは、外部の自然の諸力を補い、生体組織に欠けているものを結びつけることだといえます。形成原理が霊的・魂的な力へと変化したわけですが、そのためになくしてしまった形成力をサポートするわけです。ここで提出される疑問は、霊的・魂的活動へと変容してしまった形成力や外部の自然における諸力とはどういう力なのかということです。そういう問いかけから、あらゆる治療法を導きだせるような一種の原理を見い出すことができます。さて、ちょっと考えてみてください、このように私たちの生体組織から奪われてしまったものを、私たちが病気と称する何かあるものを通じて、このことはさらに詳しくお話するでしょうが、生体組織に補給するよう働きかけるなら、つまり私たちが、この形成力、人間の外部の自然のなかには存在しているけれども、それを霊的ー魂的なもののために使うので私たちの生体組織からは奪われてしまっているこの形成力を、植物などのものを使うことによって薬として再び生体組織に補給するなら、私たちは生体組織と、この生体組織に欠けているものとを結びつけるわけです。私たちは、私たちが人間になることによって生体組織から取り去られたものを、生体組織に付与することによって、生体組織の助けにするのです。さしあたりここまでで、私たちが治療プロセスと呼びうるものの姿がほのかに見えてくることがおわかりになると思います。つまり、治療プロセスとは、私たち人間が通常の状態では有していない外部の自然の諸力を、助けとして利用することであり、私たちは何かを通常の状態よりも自身の内部で強めるためにそれを用いるのです。ここで、ちょっと具体的にお話しするために、とは言ってもただ例としてあげるだけですが、私たちの何らかの器官、例えば肺かなにかを取りあげてみましょう。こういう器官の場合も、私たちは霊的ー魂的なもののために形成原理をこの器官から取り除いた、ということが判明するでしょう。私たちが今度は植物界において、私たちが肺から取り除いたこの諸力にたどり着き、肺組織に何らかの障害がある人間にこの諸力を付与すると、この人の肺の働きに助けをもたらすことができます。そうすると、つぎのような問いが生じてくるでしょう。人間の諸器官の基礎を成しているけれども、霊的・魂的活動のために取り除かれてしまった諸力、人間の外部の自然においてこういう諸力に類似しているのはどのような力なのかという問いです。皆さんはここで、単なる試行錯誤的な治療から治療における一種の理性(Ratio)に至る道を見出すでしょう。現代では、唯物論的な観点から、単純なものから複雑なものへの進化、つまり、鉱物から植物、動物への進化といったことが考えられるようになっています。しかし、そうした進化と同様に、植物から鉱物への、いわば下降する進化も考えられなければなりません。この下降する進化は、上昇する進化と鏡像関係にあり、その上昇する進化に対して特別の関係にある諸力が現れうるのです。つまり、下等生物における形成力のように、鉱物において存在している特別の力が、結晶化のなかに現れてくるわけです。そして、下等動物に見られるような形成原理が霊的・魂的な力へと変化したためになくしてしまった形成力をサポートするために、植物界、動物界から取り出して人間の生体組織に供給するように、鉱物界のなかに存在する別の種類の力を人間の生体組織に供給するということが考えられるというのです。然し乍らここには、神経組織つまり人間内部に関して人々が陥っている誤謬とならんで、人間の外部の自然に関わるいささかならぬ誤謬が存在しているのです。きょうはこれを暗示するだけにとどめ、後日さらに詳しくご説明しようと思います。唯物論的な時代において、人々は次第次第に、いわゆる最も単純なものから最も複雑なものへと、外的な存在の一種の進化論を考えるようになりました。人々はまず最初に下等生物に観察範囲を広げた後で、最も複雑な生物まで形態の変化を研究し、さらに生物でないもの、例えば鉱物界にも注目しました。人々は鉱物界に注目して、鉱物界は植物界よりどう見ても単純である、と言ったのです。このことは結局、鉱物界からの生命の発生とか、単なる無機的な集合体から有機的な集合体へと物質が集合するためにかつて存在した条件といったことについての、あらゆる奇妙な問題を生み出すことになりました。いわゆる「自然発生/Generatio aequivoca(*)」は多くの議論を呼んだものです。*Generatio aequivoca:もとのラテン語の意味は「多義的な生殖、発生」で、一般には、神の創造行為によらない地球上の生命の発生に関する仮説。参考画:上昇する進化と下降する進化 けれども偏見なしに観察すれば、このような見解はまったく正しくないこが明らかになります。そして次のように言わなければならないでしょう。そもそも何らかの方法で、植物から動物を経て人間に至るひとつの進化が考えられるのとまったく同様に、今度は生物から生命が取り去られることによって、生物すなわち植物から鉱物に至るひとつの進化も考えられるのだと。先に申しましたように、きょうはこのことを暗示するだけにしておきます。後日の考察でもっと明らかになってくるでしょう。進化というものを、鉱物から始まって植物的なものを経て、さらに動物的なものを通って人間に至る、というふうに考えるのではなく、出発点を中間に取って、植物的なものから始まって動物的なものを経て人間に至るひとつの進化を考え、今度は逆に鉱物的なものへと下っていくもうひとつ別の進化を考えると、つまり出発点を鉱物に置かず、自然の真ん中に置いてみると、一方は上昇する進化を通じて、もう一方は下降する進化を通じて現れてきます。このことから次のようなことが洞察できるようになります。つまり、植物から鉱物へ、とりわけ私たちがこれから見ていくように、きわめて意味深い鉱物すなわち金属へと下降していくことによって、この下降する進化においては、その鏡像である上昇する進化に対してまったく特別の関係にある諸力が現れうるということです。要するに、鉱物においてはどのような特別の力が存在しているのかという問いが私たちの魂の前に提示されるのです。私たちがこの特別な力を研究できるのは、下等生物において研究してきた形成力を鉱物においても研究するときのみです。鉱物の場合、この力は結晶化のなかに現れてくるのが見られます。この結晶化が私たちに非常に明確に示しているものというのは、私たちが下降する進化を観察するときに現れてきて、上昇する進化を観察するときに形成力に現れてくるものと関係はしているけれども同じではないものなのです。したがって、鉱物のなかに力としてあるものを生体組織に供給すると、新たな問いが生じます。私たちはよく似た問いに次のように答えることができました。つまり、私たちが霊的・魂的なものによって私たちの生体組織から取り去った形成する諸力を、植物界、動物界から取り出して人間の生体組織に供給すると、生体組織を助けることができると。けれども今度は、下降する進化すなわち鉱物界のなかに存在する別の種類の力を人間の生体組織に供給すると、どんなことが起こるのでしょうか。きょうはこの問いを出しておいて、考察を進めつつ詳細にお答えしていこうと思います。しかしそれでもやはり、きょう考察の頂点で出された問い、つまり、私たちは自分で自然から治療プロセスをひそかに学びとることができるのかという問いに、正しい意味で何かを役立たせるというところまでまだ到達していないのです。こういう問いにおいて常に重要なのは、正しい洞察力をもって、私たちはこういう事柄に関して少なくとも概略的にはこのような洞察力が得られるよう試みてきたわけですが、その自然に近づくことです。そうしてはじめてある出来事の本質が顕現するのです。これが重要なのです。さて、人間の生体組織には、血液形成と乳汁形成という二つの対立的なプロセス存在しています。その本質的な差異は、血液形成が形成力を自らつくり出す能力を非常に多く有しているという点にあります。血液形成は、下等動物における形成力をまだ有しているといえるのです。増殖能力を持たないという点では、赤血球は神経細胞と共通しているのですが、神経細胞ほどには、血液には形成能力が取り去られてはいないのです。さて、よろしいでしょうか、人間の生体組織には二つのプロセスが存在していて、これは動物にも存在しているのですが、さしあたっては重要ではありませんので割愛しますが、私たちが今までに得た理念を備えて観察すると、これはある意味で対立するプロセスとして現れてきます。この両者は完全に対立しているわけではないのですが、この説明を誤解なさらぬよう注意してくださるよう強調しておきたいのですが、かなりな程度まで対極的なプロセスです。このプロセスとは、人間の生体組織に現れてきている、血液形成と乳汁形成のプロセスです。血液形成と乳汁形成、この両者はすでに外面的な点で本質的に異なっています。血液形成は、いわば人間の生体組織の隠された面へと強力に引き戻されています。乳汁形成は、最後にはむしろ表面の方へと向かう傾向を有するものです。けれども私たちが人間そのものを観察すると、血液形成と乳汁形成との間の本質的な差異というのはやはり、血液形成は、形成力を自らつくり出す能力を自身のなかに非常に多く有しているという点です。血液は実際、俗っぽい言い方をさせていただくなら、人間の生体組織の予算全体のなかで形成力を繰り入れねばならない部分なのです。つまり血液は、下等生物において認められる形成力をある意味でまだ有しています。この形成力を自らの内部に有しているのです。ところで近代科学が血液を観察するなら、ここで非常に重要なものに依拠することができるかもしれないのですが、結局真に合理的な意味において今日までそれはなされておりません。近代科学は、血液の主要成分は赤血球であり、赤血球は増殖能力を持たない、つまり増殖力が無いという特性を持つ、ということを拠り所とすることができるかもしれないのです。増殖力が無いという点は神経細胞と共通しています。けれどもこういう共通の特性を強調する際に重要なことは、共通である理由が、両者とも同じなのかどうか、ということです。理由は同じではありません。なぜなら、神経細胞から取り去ったほどには、私たちは血液から形成能力を取り去ってはいないからです。神経細胞の内的な形成能力は、外的な影響に適応する能力に対して後退していますが、血液は内的な形成能力を高度に保存しています。その形成能力は、母乳を乳児に与えるということからもわかるように、乳汁にもある程度は存在していますが、血液がその存続のために必要としている「鉄」を乳汁はほとんど持っていません。では、血液はなぜ鉄を必要とするのでしょうか。血液は、人間の生体組織において病んでいて、鉄によって常に癒されなければならない実質だというのです。実際表象生活の基礎を成す神経実質は、かなりな程度内的な形成能力を欠いています。人間の場合、生後しばらくの間は、神経実質はまだはるかに外的な印象に依存しつつ、それを模して形成されているのです。つまりここでは内的な形成能力は、外的な影響にもっぱら適応する能力に対して後退しているわけです。血液の場合は事情は異なっています。血液は内的な形成能力を高度に保存しています。この内的な形成能力は、生活上の事実からおわかりのように、ある意味では乳汁にも存在しています。なぜなら、乳汁に形成能力がなかったら、健康に良い食品として母乳を乳児に与えることなどできないでしょうから。乳児は母乳を必要としています。乳汁のなかには血液と似た形成能力があります。ですから、形成能力という点においては、血液と乳汁のあいだにはある種の類似があるのです。けれども少なからぬ違いもあります。乳汁は形成能力を有しています。けれども、血液がその存続のために最高に必要としているものを、乳汁は持っておらず、少なくとも少量、ほんのわずかしか持っておりません。それは鉄です。鉄は基本的に人間の生体組織内で唯一の金属であり、人間、つまり人間の生体組織との結びつきにおいて、自ら整然とした結晶化能力を示しています。従って乳汁がほかの金属を微量に有しているとしても、いずれにせよ、血液は自らの存続のためにまぎれもない金属である鉄を必要としているという点に違いがあるのです。乳汁も形成能力は有しているのですが、鉄を必要としていません。ここで、なぜ血液は鉄を必要とするのか、という問いが生じます。これは結局医学という学問全体の根本問題なのです。血液はとりわけ鉄を必要とします。私がきょう触れた事実のための判断材料はもうここにあるでしょう。私がまず確認しておきたいのは、血液は人間の生体組織において、それ自身の本性によりもっぱら病んでいて、鉄によって絶えず癒されなければならない実質であるということです。乳汁の場合にはこれは当てはまりません。乳汁が血液と同じ意味で病んでいるとしたら、それは人間自身のための、現在そうであるような類の形成手段、人間に外から与えられた形成手段であることは不可能だからです。鉄によって絶えず治療され続けていなかればならないというところに、血液プロセスの特殊性があります。しかし、それが異常なプロセスだというのではありません。正常なプロセスではあるけれども、自然自体が常に治療し続けなければならないプロセスだといえるのです。血液が、あくまで生体組織のなかにとどまろうとしながら、自然が人間の外部にある金属の力を人間に付与することで完了するプロセスであるのに対し、乳汁は、癒される必要はなく、生体組織から外へと向かうものであり、形成力をほかの生体組織へと健全に導くことができます。この両極性に目を向け、それを手がかりにすると、多くのことが研究可能になるというのです。血液を観察すると、人間において人間の構成のゆえに、その組織構造のゆえに、常にいくらか病んでいるものが観察されます。血液はもっぱらそれ自身の本性により病んでいて、鉄の付与によって絶えず治療され続けなければならないのです。すなわち、私たちは、血液のなかで起こっているプロセスにおいて、私たちの内部に絶え間ない治療プロセスを有しているわけです。医師が自然を通じて試行しようとするなら、自然のなかのすでに異常なプロセスを何よりもまず観察せねばならないというのではなく、正常なプロセスを観察せねばなりません。血液プロセスは確かに正常なプロセスではありますが、同時に、自然自体が絶えず治療し続けねばならないプロセス、自然が、付与された金属つまり鉄によって絶えず治療し続けねばならないようなプロセスなのです。そういうわけで、血液において起こっていることを図で示そうとすると、次のように言わなければなりません。血液が鉄なしで自身の構造によってのみ有しているものは、下に向かう曲線ないし直線で、これはとどのつまりは血液の完全な分解に至るでしょう。一方、血液中で鉄が働きかけているものは、常に上に向かい、絶えず癒しています。実際のところ私たちがここで有しているのは、正常なプロセスであって同時に、私たちがそもそも治療プロセスについて考えようとすれば、それを模して形成されねばならないようなプロセスなのです。ここで私たちは真に自然を通じて試行していくことができるのです。自然が、人間の外部にある金属の力を人間に付与することで、いかにプロセスを完了しているか、私たちはここで理解できるからです。そして同時に、あくまで生体組織のなかにとどまろうとするもの、すなわち血液が癒されねばならず、生体組織から外へと向かうもの、すなわち乳汁が癒される必要がないこと、乳汁は、形成力を有しているとき、形成力をほかの生体組織へと健全に導くことができることも理解できます。これは一種の両極性です。一種の、であって、血液と乳汁との完全な両極性とは申しませんが、この両極性に目を向けなければなりません。このことを手がかりに、非常に多くのことが研究できるからです。これを明日さらに継続していきましょう。 (第三講解説1-3・了 第三講解説 完了)哲学・思想ランキング
2024年08月23日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」第三講●解説 概要・解説 1-2暗示と催眠●解説 1-2 暗示と催眠 私たちは昨日、たとえば結核の場合に起こって、神経によって単に知覚されているものを、新陳代謝における出来事によって特徴づけました。こういうことにこそ留意せねばならなかったのに、そうするかわりに人々は、神経組織の振動可能性や振動のなかにのみ、ヒステリーを探究し、すべてを神経組織のなかに置き換えてしまったのです。魂的なものを神経組織だけで説明しようとしている強い傾向があります。それは事実とは矛盾するものですし、魂的なものを生体組織に近づける可能性も与えないものです。その矛盾をなんとか説明しようとして、架空の運動神経というものを考え出したりしているというのが、現代医学の現状なのです。たとえば、怒るとドキドキするとか、恥ずかしくて顔が赤くなる、感動して胸が熱くなる、とかいう現象は神経組織だけで説明するのはかなり無理があるということとも関係してくるのではないでしょうか。こうして、さらにまた別のものももたらされました。とは言え、ヒステリーの遠因のなかにはやはり心魂的な原因もあることは否定できません。心痛、失望感、実現可能なものも不可能なものも含めて何らかの内的な興奮、これらがヒステリーの徴候のなかに入り込んでいます。けれども、神経組織以外の生体組織全体をいわば魂生活から切り離し、神経組織だけをまさに直接魂生活に関係づけたことによって、すべてを神経組織に負わせることを余儀なくされている状況です。これにより生じてきた見解は、第一に、もはやわずかなりとも事実には裏付けされず、また第二に、魂的なものを人間の生体組織にさらに近づける手がかりを何ら与えないような見解です。魂的なものをもっぱら神経組織にのみ近づけ、人間の生体組織全体に近づけることはしないのです。せいぜい、存在してもいない運動神経というものを考え出して、運動神経の機能からさらに循環その他への影響を期待することによって、全体に近づけようとするぐらいですが、この循環その他への影響というのもまったく仮説の域を出ないものです。今回ご紹介する部分では、ヒステリーの男性の死の例が紹介されます。(*この内容については、本文をご覧ください。)この例に関して、暗示による死といった診断を下すのは早計で、それは原因と結果が混同がされているです。暗示が原因で死に至ったのではなく、自己暗示とみなされるような心理的な混乱を導く原因は、生体組織そのものの深部にあったのです。死の原因そのものは、生体組織のなんらかの異常であったのですが、この男性は、混乱したイメージによってではあっても、自らの死を正確に予見することができたわけです。つまり、死の原因は暗示といった心理的なものではないのです。人間の本質を洞察し、生体組織の深部で起こっていることを慎重な態度で見ていくことが重要です。自然における複雑な事象について適切な判断を得ようとするならば、あまりに単純なことから出発することはできません。それについては慎重であることが求められるのです。私が説明いたしましたことは、暗示と催眠といったようなことが現れてきたときに、きわめて思慮深い人たちを結局誤謬の道に導くことになってしまったことなのです。その際、少し以前のことにはなりますが、ヒステリーのご婦人がたが、きわめて思慮深い医師たちを誤謬に導き、欺くといったことが体験されました。こういう人たちが医師の前で披露してみせる、ありとあらゆることに気をとられて、本来生体組織のなかで起こっていることには入っていくことができなかったからです。けれどもこのことに関連して、この場合はヒステリーの婦人ではなく、ヒステリーは男性なのですが、もともとこういう事柄に関しては、非常に思慮深いのが常であるシュライヒ(☆3)のような医師が、いかなる誤謬に陥ったか、陥らざるを得なかったかををお話しするのも一興かもしれません。つまりこの時、医師であるシュライヒのもとに、インクのペンで指を刺してしまった男性がやってきて、明日の夜にはきっと死んでしまうだろう、血液が毒されてしまうから、腕を切断してもらわなければならないと言ったのです。当然のことながら、外科医であるシュライヒは切断を敢行することはできませんでした。彼にできたのは、この男性を落ち着かせ、傷口を消毒するなど必要な処置を施すことだけであって、明日の夜には血液が毒されてしまうからなどという申し立てに応じて、この男性の腕を切断することなどむろんできませんでした。するとこの患者は、また別の権威のところに行きましたが、当然ここでも彼の腕は切断してもらえませんでした。しかしシュライヒは事態にいささか不吉なものを感じました。朝になってすぐ問い合わせると、その患者はほんとうにその夜死んでいたのです。そこでシュライヒは、「暗示による死」と診断をくだしました。「暗示による死」と診断することは、はなはだ容易に推測できることです。しかしながら、人間の本質への洞察があれば、このやうなやりかたで暗示による死を考えるということはあり得ません。ここでは、暗示による死が診断されるやいなや、原因と結果との根本的な混同がされているのです。もちろん血液が毒されているということはなく、これは解剖により確認されましたが、当の患者は、医師たちには公表されない原因によって死亡したように見えますが、事態を洞察することのできる人にとっては、彼の死はまぎれもなく、生体組織の深部に根ざした原因によるものなのです。この生体組織の深部に根ざした原因が、その数日前からこの人物をぎごちなく不安定にさせていたので、彼はインクのペンで自分の指を突き刺すというような、通常はしないことをしてしまいました。これは彼がぎごちなくなった結果起こったことなのです。そしてこの人が外的・物質的な意味でぎごちなくなる一方で、内的な透視能力はいくらか高められ、病気の影響で、夜になってやってくる自らの死を預言的に見通していたのです。彼の死は、彼がインクのペンで指を突き刺したこととは全く関係なく、彼が自分のなかに有している死の原因によって感じたことの原因となったのが、この予見された死だったのです。起こったことはすべてが、死をもたらした本来の内的プロセスに、もっぱら外的に関連していることにほかなりません。ですからここで「暗示による死」が登場してくるのは全く問題外です。なぜならこの男性が信じていたことや彼の有していたすべてのものは、死を招いたこととは何の関係もなく、もっと深い原因があったからなのです。ともあれ彼は死を予見し、起こったことをすべて、この死の予見に引き込んで解釈したわけです。この例によって同時に、自然における複雑な事象について適切な判断を得ようとするといかに慎重でなければならないか、おわかりいただけたと思います。自然においてはきわめて単純なことから出発することはできないのですから。参照図:wound on fingertip哲学・思想ランキング
2024年08月22日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」第三講●解説 概要・解説●概要 1-1病理学と治療の診断による結びつき。三分化された人間。運動神経と感覚神経。1-2暗示と催眠。1-3治療手段と人間の関係。植物における成長の変容。適応力と再生。人間の形成力と霊的・魂的機能。現実に適応した心理学の基礎。上昇する進化と下降する進化。血液形成プロセスと乳汁形成プロセス。●解説 1-1病理学と治療の診断による結びつき。三分化された人間。運動神経と感覚神経。 今日の医学においては、治療と病理学との関係は明らかではなく、単なる経験的方法ばかりが優勢であるため、実践的なものに対して応用のきくような合理的なものを、治療において見い出すことはできません。(*ちなみに、ここでは、哲学的なイギリス「経験論」と大陸「合理論」の対比を踏まえて語られているようです。)。医療は対象を診断し病気を識別することで満足するのではなく、まず診断の段階で病気の本質から治療プロセスまでを見通すような仕方で病気の本質を認識することができなければならないのです。ここで治療における「理性/Ratio」の必要性ということが示唆されます。そもそも今日の医学研究はどのような性質のものなのか想定すると、少なくとも大筋において見い出せることは、治療は病理学と並んで現れているけれども、両者の間に、明確に見通せる関係は成立していないということではないでしょうか。とりわけ治療においては、今日現在(こんにちげんざい)でも往々にして、単なる経験的な方法の独壇場となっています。合理的なもの、つまり、それに基づいて実践的なことにおいて実際に原理を打ち立てることのできるような、そういう合理的なものは、とりわけ治療においてはほとんど見出すことができないのです。周知のとおり、19世紀におけるこの医学上の思考方法の欠陥は、医学上でのニヒリズム派にさえ通じてしまいました。このニヒリズム派は、すべて診断に基づき、病気が識別できれば満足し、治療における何らかの理性(Ratio)に対しては大体においてまさしく懐疑的な態度をとったのです。医療制度に対して、いわば純粋に理にかなった要求をするとしたらやはり、そもそも診断と関連したところですでに治療を暗示するものが存在していなければならないと言わねばならないでしょう。治療と病理学の間に単なる外的な関係が保たれているだけではいけないのです。私たちはいわば病気の本質を、この病気の本質から治療プロセスについての見解を形作ることができるようなしかたで認識することができなければならないのです。病気の本質から治療プロセスまでを見通すというあり方は、自然のプロセス全体において、治療法と治療プロセスがどの程度まで存在するのかという問いと関連したものだといえます。人間の病気と治療のプロセスに対応するようなものが、自然のなかに見い出されるのかどうかという問いが出てくるのです。然し乍ら今日の自然科学にもとづいた医学ではこうした問いかけはなされてはいません。唯物論的傾向にある医学では、神経組織を機能においてまったく誤解しているからです。このことは当然のことながら、そもそも自然のプロセス全体において、治療法と治療プロセスがどの程度まで存在し得るのかという問いと関連しています。パラケルススの大変興味深い箴言「医者は自然を通じて試行していかねばならない」は非常にしばしば引用されますが、最近のパラケルスス文献は、まさにこういう箴言からとりかかるということをじゅうぶん心得ているとは申せません。さもなければ、自然そのものから治療のプロセスをひそかに学びとることをどのみち目論まざるを得ないからです。なるほど、自然そのものがそれに対して策を講じてくれるような病気のプロセスがそこにあるときは、其のような試みもされるでしょう。けれども、真の自然観察は正常なプロセスを観察するものなのに、すでに損傷があって自然が自ら自衛策を講じる場合は、その治療処置に関して、やはり自然というものを特例として観察することが目指されているのです。すると、次のような疑問が起こってくるにちがいありません。つまり、治療処置について何らかの見解を得るための手がかりとして、正常なプロセス、いわば正常なプロセスと呼ばれているものを自然のなかに観察する可能性があるのかという疑問です。皆さんはすぐにお気づきになるでしょうが、このことはいくらか考慮を要する問題と関連しています。病気のプロセスが自然のなかに正常な在り方で存在しているときには、当然のことながら、自然のなかに正常なしかたで治療プロセスを観察することが可能です。すると、いったい自然そのもののなかに自然を通じて試行し、自然を通じて癒すことができるような、病気のプロセスがすでに存在しているのかという疑問が生じてきます。この疑問に対してはもちろん、この連続講演が進むにつれてはじめて完全に答えが与えられるでしょうが、きょうのところはせめて少しだけこの答えに近づくことを試みてみましょう。けれどもその際、即座に言えることは、ここに呈示しましたような道は、今日通用しているような「自然科学に基づいた医学」を注がれて覆われてしまっているということです。現在のような前提においては、このような道を歩むことは非常に困難です。と申しますのも、たいへん奇妙なことに、ほかならぬ19世紀における唯物論的傾向が、ここで私が骨組織、筋肉組織、心臓組織に続いて付け加えねばならない組織、すなわち神経組織をそもそもその機能において完全に誤解するという事態を招いてしまったからです。霊的・魂的なものを神経組織によるものであるとすることが一般的になってきていることに対して、シュタイナーは異論を提出しています。神経組織と関係しているのは、表象プロセスのみであって、感情プロセスは、律動組織(呼吸・循環系)と関係し、意志プロセスは新陳代謝組織と関係しているというのです。これが、シュタイナーのいう、いわゆる「生体組織の三分節」という概念の基本となっています。この考え方は、生物学上の事実によって証明できることですが、それに対して、神経系に関する従来の考え方、つまり魂生活を神経組織によるものだとする見解は証明できないのだといいます。いわば魂的なものをすべて神経組織に負わせ、人間において起こっているあらゆる霊的ー魂的なものを、その際、神経組織のなかに見出され得るはずの平行現象において解明するということが次第に一般的になってきました。ご存知のように私は、こういった類の自然観察に対して、「魂の謎について」という著書のなかで異議を申し立てざるを得ませんでした。この本において私がまず第一に示そうと試みたことは、この真実を実証するために経験の面から加えられることは、ほかならぬこの通常の観察法によってこそ数多く得られるのですが、神経組織と関係しているのは、本来の表象プロセスのみであって、感情のプロセスは、間接的にではなく直接的に、生体組織の律動的現象に関連しているということです。今日の自然科学者は通常、感情プロセスは律動組織とは直接関係はなく、この律動プロセスが神経組織に中継されることによってのみ関係している、つまり、感情生活も神経組織によって営まれるのだと考えます。さらに私は、意志生活全般もまったく同様に、間接的にではなく直接的に、新陳代謝組織と関係していることを示そうとしました。つまり、意志のプロセスに関しても、神経組織にとっては、この意志プロセス自体を知覚すること以外の何物も残されていないわけです。神経組織を通じて何らかの意志が実行されるのではなく、意志を通じて私たちのなかで起こっていることが知覚されるのです。私が主張いたしましたことはすべて、生物学上のそれに応じた事実によって完璧に証明されうることですが、他方、これと反対の、魂生活を神経組織だけに組み込む見解は、まったく証明することができないのです。感覚神経と運動神経が別のものであるとするとらえ方がありますが、運動神経といわれるものと感覚神経を切断するとしますと、その両者をつなぎ合わせることができ、そこから均一の神経が生じるという事実があるように、感覚神経と運動神経は別のものではありません。運動神経というものは存在せず、運動神経と呼ばれているものは、四肢の新陳代謝で生じていることを「知覚する感覚神経」のことなのです。シュタイナーは、第二講で、病気の本質を探究するためには、新陳代謝に関連した「下部」と感覚・神経活動を含む呼吸活動に関連した「上部」とが密接に関係しあっているという事実を見なければならないことについて語っていましたが、現代の医学の傾向としてあるのは、病気の諸症状について、感覚神経と運動神経の区別で済ませてしまったり、ヒステリーを神経組織だけで説明しようとしたりすることなのです。いわゆる運動神経を切断し、感覚神経を切断して、両者をつなぎ合わせることができ、そこからまた均一の神経が生じるという事実がありますが、感覚神経(sensitive Nerven)と運動神経(motorische Nerven)があるという見解とこの事実が、まったく健全な理性のもとではどうやって関係づけられるべきなのか、ちょっと見ていきたいと思います。感覚神経と運動神経といったものは実は存在せず、運動神経と呼ばれているものは、私たちの四肢の運動、すなわち、私たちが意志するときに、私たちの四肢の新陳代謝において起こっていることを知覚する感覚神経にほかならないのです。つまり、運動神経とは実際のところ、私たち自身の内部においてのみ知覚する感覚神経なのです。それに対して、「感覚神経と本来呼ばれているもの」は、外界を知覚しているのです。医学にとって非常に重要な意味を持っているけれども、事実そのものをきちんと見据えることによってはじめて正当に評価され得るものは、この方向にあるのです。なぜなら、昨日私が結核の例を得るために出発点とした病気の諸症状に対しても、感覚神経と運動神経の区別で済ませてしまうことは実際困難だからです。従って、賢明な自然観察者は、どの神経も単に周辺から内部へ、あるいはその逆へと伝わるだけでなく、周辺から中心へ、あるいは中心から周辺へも伝わるということをすでに受け容れてきたのです。同様に、どの運動神経にも二つの回路があるということになります。すなわち、神経組織から、何かを、たとえばヒステリーを説明しようとすると、互いに反対に流れている二つの回路を容認することが必要なのです。つまり、事実に立ち入るやいなや、神経組織についてのそもそもの仮定に完全に矛盾する、こうした神経の特性を容認することがどうしても必要になるのです。たとえばヒステリーの場合に起こっていることのように、生体組織のなかで通常神経組織に定められているものについて知るべきであったことが、神経組織についてのこういう通例の考えかたを習ったことですべて塞がれてしまったのです。参考画:sensitive Nerven - motorische Nerven哲学・思想ランキング
2024年08月21日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第三講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 1-5本講1-5 進化というものを、鉱物から始まって植物的なものを経て、さらに動物的なものを通って人間に至るというふうに考えるのではなく、出発点を中間に取って、植物的なものから始まって動物的なものを経て人間に至るひとつの進化を考え、今度は逆に鉱物的なものへと下っていくもうひとつ別の進化を考えると、つまり出発点を鉱物に置かず、自然の真ん中に置いてみると、一方は上昇する進化を通じて、もう一方は下降する進化を通じて現れてきます。このことから次のようなことが洞察できるようになります。つまり、植物から鉱物へ、とりわけ私たちがこれから見ていくように、きわめて意味深い鉱物すなわち金属へと下降していくことによって、この下降する進化においては、その鏡像である上昇する進化に対してまったく特別の関係にある諸力が現れるということです。要するに、鉱物においてはどのような特別の力が存在しているのかという問いが私たちの魂の前に提示されるのです。私たちがこの特別な力を研究できるのは、下等生物において研究してきた形成力を鉱物においても研究するときのみです。鉱物の場合、この力は結晶化のなかに現れてくるのが見られます。この結晶化が私たちに非常に明確に示しているものというのは、私たちが下降する進化を観察するときに現れてきて、上昇する進化を観察するときに形成力に現れてくるものと関係はしているけれども同じではないものなのです。したがって、鉱物のなかに力としてあるものを生体組織に供給すると、新たな問いが生じます。私たちはよく似た問いに次のように答えることができました。つまり、私たちが霊的・魂的なものによって私たちの生体組織から取り去った形成する諸力を、植物界、動物界から取り出して人間の生体組織に供給すると、生体組織を助けることができると。けれども今度は、下降する進化すなわち鉱物界のなかに存在する別の種類の力を人間の生体組織に供給すると、どんなことが起こるのでしょうか。きょうはこの問いを出しておいて、考察を進めつつ詳細にお答えしていこうと思います。しかしそれでもやはり、きょう考察の頂点で出された問い、つまり私たちは自分で自然から治療プロセスをひそかに学びとることができるのかという問われれば、未だ正しい意味で何かを役立たせるというところまでまだ到達していないのです。こういう問いにおいて常に重要なのは、正しい洞察力をもって、私たちはこういう事柄に関して少なくとも概略的にはこのような洞察力が得られるよう試みてきたわけですが、より自然に近づくこと、こうしてはじめてある出来事の本質が顕現する。これが重要なのです。さて、よろしいでしょうか、人間の生体組織には二つのプロセスが存在していて、これは動物にも存在しているのですが、さしあたっては重要ではありませんので割愛しますが、私たちが今までに得た理念を備えて観察すると、これはある意味で対立するプロセスとして現れてきます。この両者は完全に対立しているわけではないのですが、この説明を誤解なさらぬよう強調しておきたいと思います。かなりな程度までの対極的なプロセスが要因です。このプロセスとは、人間の生体組織に現れてきている、血液形成と乳汁形成のプロセスです。血液形成と乳汁形成、この両者はすでに外面的な点で本質的に異なっています。血液形成は、いわば人間の生体組織の隠された面へと強力に引き戻されています。乳汁形成は、最後にはむしろ表面の方へと向かう傾向を有するものです。けれども私たちが人間そのものを観察すると、血液形成と乳汁形成との間の本質的な差異というのはやはり、血液形成は、形成力を自らつくり出す能力を自身のなかに非常に多く有しているという点です。血液は実際、俗っぽい言い方をさせていただくなら、人間の生体組織の予算全体のなかで形成力を繰り込まねばならない部分なのです。つまり血液は、下等生物において認められる形成力をある意味でまだ有しています。この形成力を自らの内部に有しているのです。ところで近代科学が血液を観察するなら、ここで非常に重要なものに依拠することができるかもしれないのですが、結局のところ真に合理的な意味においては今日までそれはなされておりません。近代科学は、血液の主要成分は赤血球であり、赤血球は増殖能力を持たない、つまり増殖力が無いという特性を持つということを拠り所とすることができるでしょう。増殖力が無いという点は神経細胞と共通しています。けれどもこういう共通の特性を強調する際に重要なことは、共通である理由が、両者とも同じなのかどうかということです。理由は同じではありません。何故なら、神経細胞から取り去ったほどには、私たちは血液から形成能力を取り去ってはいないからです。実際表象生活の基礎を成す神経実質は、かなりな程度内的な形成能力を欠いています。人間の場合、生後しばらくの間は、神経実質はまだはるかに外的な印象に依存しつつ、それを模して形成されているのです。つまりここでは内的な形成能力は、外的な影響にもっぱら適応する能力に対して後退しているわけです。血液の場合は事情は異なっています。血液は内的な形成能力を高度に保存しています。この内的な形成能力は、生活上の事実からおわかりのように、ある意味では乳汁にも存在しています。なぜなら、乳汁に形成能力がなかったら、健康に良い食品として母乳を乳児に与えることなどできないでしょうから。乳児は母乳を必要としています。乳汁のなかには血液と似た形成能力があります。ですから、形成能力という点においては、血液と乳汁のあいだにはある種の類似があるのです。けれども少なからぬ違いもあります。乳汁は形成能力を有しています。けれども、血液がその存続のために最高に必要としているものを、乳汁は持っておらず、少なくとも少量、ほんのわずかしか持っておりません。それは鉄です。鉄は基本的に人間の生体組織内で唯一の金属であり、人間、つまり人間の生体組織との結びつきにおいて、自ら整然とした結晶化能力を示しています。従って乳汁がほかの金属を微量に有しているとしても、いずれにせよ、血液は自らの存続のためにまぎれもない金属である鉄を必要としているという点に違いがあるのです。乳汁も形成能力は有しているのですが、鉄を必要としていません。ここで、なぜ血液は鉄を必要とするのかという問いが生じます。これは結局医学という学問全体の根本問題なのです。血液はとりわけ鉄を必要とします。私がきょう触れた事実のための判断材料はもうここにあるでしょう。私がまず確認しておきたいのは、血液は人間の生体組織において、それ自身の本性によりもっぱら病んでいて、鉄によって絶えず癒されなければならない実質であるということです。乳汁の場合にはこれは当てはまりません。乳汁が血液と同じ意味で病んでいるとしたら、それは人間自身のための、現在そうであるような類の形成手段、人間に外から与えられた形成手段であることは不可能だからです。血液を観察すると、人間において人間の構成のゆえに、その組織構造のゆえに、常にいくらか病んでいるものが観察されます。血液はもっぱらそれ自身の本性により病んでいて、鉄の付与によって絶えず治療され続けなければならないのです。すなわち、私たちは、血液のなかで起こっているプロセスにおいて、私たちの内部に絶え間ない治療プロセスを有しているわけです。医師が自然を通じて試行しようとするなら、自然のなかのすでに異常なプロセスを何よりもまず観察せねばならないというのではなく、正常なプロセスを観察せねばなりません。血液プロセスは確かに正常なプロセスではありますが、同時に、自然自体が絶えず治療し続けねばならないプロセス、自然が、付与された金属つまり鉄によって絶えず治療し続けねばならないようなプロセスなのです。そういうわけで、血液において起こっていることを図で示そうとすると、次のように言わなければなりません。血液が鉄なしで自身の構造によってのみ有しているものは、下に向かう曲線ないし直線で、これはとどのつまりは血液の完全な分解に至るでしょう(図、赤い線)。一方、血液中で鉄が働きかけているものは、常に上に向かい、絶えず癒しています(黄色の線)。実際のところ私たちがここで有しているのは、正常なプロセスであって同時に、私たちがそもそも治療プロセスについて考えようとすれば、それを模して形成されねばならないようなプロセスなのです。ここで私たちは真に自然を通じて試行していくことができるのです。自然が、人間の外部にある金属の力を人間に付与することで、いかにプロセスを完了しているか、私たちはここで理解できるからです。そして同時に、あくまで生体組織のなかにとどまろうとするものすなわち血液が癒されねばならず、生体組織から外へと向かうものすなわち乳汁が癒される必要がないこと、乳汁は、形成力を有しているとき、形成力をほかの生体組織へと健全に導くことができることも理解できます。これは一種の両極性です。「一種の」であって、血液と乳汁との完全な両極性とは申しませんが、この両極性に目を向けなければなりません。このことを手がかりに、非常に多くのことが研究できるからです。これを明日さらに継続していきましょう。以上のことをすべて前もってお話しせねばならなかったのは、質問を見て、返答のための概念、基礎があれば、まったく違ったやりかたで質問に答えられることがわかったからです。記:母乳はママの血液から作られています。「プロラクチン」の刺激は、乳房の中の乳腺に指令を出し、乳房の中の血管から母乳を作り出します。このことから、「母乳はママの血液から作られる」と表現されることとなります。 母乳が白色なのは、血液中の栄養分や白血球などは取り込まれても、赤い赤血球は取り込まれないためですプロラクチンの主な刺激因子は、乳児が母乳を吸引することです。この刺激により、プロラクチンの分泌量が増加し、乳汁の産生が促進されます。また、プロラクチンはドパミンによって抑制されており、視床下部からの制御を受けています。参考画:generatio aequivoca□編註☆1 パラケルスス「オープス パラミールム」参照。☆2 「魂の謎」(1917)GA21☆3 カール・ルートヴィヒ・シュライヒ Carl Ludwig Schleich 1859ー1922 局所麻酔の考案者。「思考の切替装置について」(エッセイ、ベルリン、1916)260頁以下。その他の著作:「魂について」(エッセイ、1910);「意識と不死」(講演、1920);「幸福な過去」(回想録、1921)□訳註*generatio aequivoca(平行生成)は、ラテン語由来の用語で、一般には神の創造行為によらない地球上の生命の発生に関する仮説を指します。この概念は多義的な生殖や発生を含む意味合いを持ちます。 (第三講本講・了)哲学・思想ランキング
2024年08月20日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第三講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 1-4本講1-4 私が思いますに、これはちょっとした挿話(そうわ)で、考察の本筋ではないのですが、人間の頭部を表面的に観察するだけで、つまり人間は頭部のなかにさまざまな神経細胞を有していて、この細胞が固い装甲で覆われているわけですが、このことは、高度に進化した動物よりもむしろ下等な動物を思い起こさせます。私たちの頭部そのものが、言うなれば有史以前の動物を想起させるのです。こういう動物をちょっと変形させただけのように思われます。私たちが下等動物について語るとき、通常私たちは下等動物は外骨格を有し、高等動物と人間は内骨格を有するといいます。けれども、私たちの最も高度に発達している頭部、この頭部だけは外骨格を有しているのです。このことは、少なくともさきほど述べましたことの一種の「ライトモチーフ/Leitmotiv(主導動機・示導動機)」となりうると思います。さて、ちょっと考えてみてください、このように私たちの生体組織から奪われてしまったものを、私たちが病気と称する何かあるものを通じて、このことはさらに詳しくお話するでしょう。生体組織に補給するよう働きかけるなら、つまり私たちが、この形成力、人間の外部の自然のなかには存在しているけれども、それを霊的・魂的なもののために使うので私たちの生体組織からは奪われてしまっているこの形成力を、植物などのものを使うことによって薬として再び生体組織に補給するなら、私たちは生体組織と、この生体組織に欠けているものとを結びつけるわけです。私たちは、私たちが人間になることによって生体組織から取り去られたものを、生体組織に付与することによって、生体組織の助けにするのです。さしあたりここで、私たちが治療プロセスと呼びうるものの姿がほのかに見えてくることがおわかりになると思います。つまり、治療プロセスとは、私たち人間が通常の状態では有していない外部の自然の諸力を、助けとして利用することであり、私たちは何かを通常の状態よりも自身の内部で強めるためにそれを用いるのです。ここで、ちょっと具体的にお話しするために、とは言ってもただ例としてあげるだけですが、私たちの何らかの器官、例えば肺かなにかを取りあげてみましょう。こういう器官の場合も、私たちは霊的・魂的なもののために形成原理をこの器官から取り除いたということが判明するでしょう。私たちが今度は植物界において、私たちが肺から取り除いたこの諸力にたどり着き、肺組織に何らかの障害がある人間にこの諸力を付与すると、この人の肺の働きに助けをもたらすことができます。そうすると、つぎのような問いが生じてくるでしょう。人間の諸器官の基礎を成しているけれども、霊的・魂的活動のために取り除かれてしまった諸力、人間の外部の自然においてこういう諸力に類似しているのはどのような力なのかという問いです。皆さんはここで、単なる試行錯誤的な治療から、治療における一種の理性(ラツィオ/Ratio)に至る道を見出すでしょう。しかしながらここには、神経組織つまり人間内部に関して人々が陥っている誤謬とならんで、人間の外部の自然に関わるいささかならぬ誤謬が存在しているのです。きょうはこれを暗示するだけにとどめ、後日さらに詳しくご説明しようと思います。唯物論的な時代において、人々は次第次第に、いわゆる最も単純なものから最も複雑なものへと、外的な存在の一種の進化論を考えるようになりました。人々はまず最初に下等生物に観察範囲を広げた後で、最も複雑な生物まで形態の変化を研究し、さらに生物でないもの、例えば鉱物界にも注目しました。人々は鉱物界に注目して、鉱物界は植物界よりどう見ても単純であると言ったのです。このことは結局、鉱物界からの生命の発生とか、単なる無機的な集合体から有機的な集合体へと物質が集合するためにかつて存在した条件といったことについての、あらゆる奇妙な問題を生み出すことになりました。いわゆる「自然発生/Generatio aequivoca(*1)」は多くの議論を呼んだものです。けれども偏見なしに観察すれば、このような見解はまったく正しくないことが明らかになります。そして次のように言わなければならないでしょう。そもそも何らかの方法で、植物から動物を経て人間に至るひとつの進化が考えられるのとまったく同様に、今度は生物から生命が取り去られることによって、生物すなわち植物から鉱物に至るひとつの進化も考えられるのだと。先に申しましたように、きょうはこのことを暗示するだけにしておきます。後日の考察でもっと明らかになってくるでしょう。参考画:双方向進化論哲学・思想ランキング
2024年08月19日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第三講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 1-3本講1-3 さて、人間の外郭、外部の自然においては事態は非常に広範囲にわたっています。例えば次のようなことが観察できるのです。山の斜面にある植物が生えていると考えて下さい。こういう植物は、葉を形成させないようなかたちで特定の葉柄を発達させる、ということが起こるのです。葉が生えてこないのです。これに対して葉柄は湾曲して、支持する器官になります。葉は萎縮し(図)、葉柄は湾曲して支持器官となり、自らを支えます。これは変形した葉柄を備え、葉の萎縮した植物なのです。植物というものが、その環境に限定された生存様式に広範囲に適応することができるということは、植物において作用している内的な形成力の存在を示しています。さて、この内部で働いている諸力は、とりわけ下等生物においてきわめて興味深いかたちで現れてきます。たとえば、原腸胚段階まで進んだ胚を取りあげてみましょう。この原腸胚(Gastrula:原腸胚、嚢胚=卵発生における胞胚の次の段階)を切断し、真ん中で切り離すと、切り離されたおのおのの断片は再び丸くなり、それぞれ前腸、中腸、後腸の三つの部分を形成する能力を自らのうちに養成します。つまり私たちが原腸胚を切断すると、二つの断片はそれぞれ、切断されていない全体がしたであろうことと同じことをするのがわかります。ご存知のように、この試みは、下等動物、ミミズにまで広げることができます。何らかの下等動物の一部を切り取ると、その部分は新たに補充されます。自らの内的な形成力から、切り取られたものと同じものが元通り得られるのです。こういう形成力は、事実に即して指摘されねばなりません。何らかの生命力を想定することで仮説的に指摘するのではなく、事実に即してこういう形成力が指摘されねばならないのです。なぜならば、そのとき実際起こっていることをより正確に見て本当に追求するならば、次のようなことがわかるからです。たとえば、非常に初期の段階のカエルの生体組織のどこかを切り取ると、切り取られた組織の状況によって、新たな別の組織が生じてきます。いくらか唯物論的な考えかたをする人は、次のように言うでしょう。傷口のところに弾力(Spannkraefte)というものがあるではないか、この傷口の弾力によって、ここに新たに成長してくるものが生えてくるのだと。けれどもそういうことはあり得ないのです。なぜなら、もし私がある組織をここで切断して(図)この傷口のところに、ここにある弾力によって新しいものが生じてくるとするなら、ここに生じてくるのは、このすぐ近くの部分、すなわち完全な組織のなかで直接隣り合っている部分であるはずだからです。けれども実際にはそういうことはなく、カエルの幼生の一部を切り取ると、末端器官、つまり尾や頭部でも、他の動物の場合は触覚糸といったものでも実際に出現してきます。つまりそこに接しているものではなく、その組織にとってとりもなおさず必要なものがそこから生じてくるのです。ですから、ここに直接内在している弾力によって、自らを形成するものがここに生じてくるということは不可能なのです。この再生に際しては、弾力ではなく、生体組織全体がなんらかの方法で参加していると考える必要があります。このように、下等生物において起こっていることを実際に追求していくことができます。私は、今日まで文献に記載されたあらゆる経験までこのことを拡張していくときこれをどのように追求していくかという道を皆さんに提示したわけですが、この道を通ってしかこういう事柄についての見解には辿り着けないのだということを、いたるところでご確認いただけると思います。皆さんは、人間の場合だったらこういうことはあり得ないのだという以外の思いはほとんど抱かれないのではないでしょうか。実際、指や腕が切断されてもそれを補充できるとしたら、とても素晴らしいでしょう。でもそれは不可能なのです。そこでこういう問いが生じます。この、かつての成長形成力であり、ここに非常に顕著に現れている力、こういう力は、いったい人間の生体組織においてはどうなっているのか。この力は人間においては失われてしまったのか、そもそも人間にはまったく存在していないのかという問いです。記:「生体再生能力」は英語で (biological regenerative capacity または regenerative ability と表現します参考画:Ambystoma mexicanum 事実に即して自然を観察することを心得ているひとは、人間における精神的なものと物質的なものとの関連についての自然に即した見解に至ることができるためには、そもそもが、この道を通って行くしかないということを知っています。つまり、私たちがここで造形的な、と申しますか、そういうものとして始めて出会う力、ここで実質から直接形態を創り出す力、こういう力は、人間の場合には諸器官からすっかり取り出され、人間の魂的・霊的なもののなかにのみ存在しているのです。つまり、魂的・霊的なもののなかにあるわけです。この力が諸器官から取り出され、それがもう諸器官の形成力ではないことによって、人間はこの力を特別なかたちで所有しています。人間はそれを、自らの霊的・魂的機能のなかに有しているのです。私が考えたり、感じたりするとき、私は、下等動物や植物界において造形的に働いている諸力と同じ力によって考えたり、感じたりしているのです。私が、物質素材から引き出した力を使って思考し、感じ、意志することを行わないとしたら、私は考えることなどできないでしょう。従って下等生物を眺めると、私はこう言わざるを得ません。この下等生物の内部にひそんでいるもの、造形的な力であるもの、これと同じものを私も自らのうちに有している。けれども私は、これを私の器官から取り出し、自分自身のために所有している、そして、外部の下等生物の世界では造形的に働いているこの同じ力を用いて、私は思考し、感じ、意志していると。今日の心理学を構成しているような単なる言葉によってではなく、自らの心理学的組成における実質によって心理学者になろうとする人は、そもそも思考、感情、意志のプロセスを次のように追求しなくてはならないでしょう。つまり、下方では造形的な形態化のなかに現れている出来事を、ここではまさに霊的・魂的にのみ経過しているものとして、思考、感情、意志のプロセスのなかに明確に示していかなければばならないのです。もはや生体組織においてはできないことを、私たちがいかに内部の魂的なプロセスにおいてはやってのけているか、ちょっと考えてみてください。私たちは、忘れてしまった一連の思考を他のものから補完できます。このときの私たちのやり方は、先ほど私が、下等生物の再生について直接隣り合ったものではなく、そこからずっと離れたものが現れると説明したこととよく似ているではありませんか。私たちが内的・魂的に体験しているものと、外的世界において形成する自然の諸力、形成する自然の原理であるものとの間には、完全な平行現象が成立しています。そこには完全な平行現象が成立しているのです。この平行現象に注意を払わねばなりません。そして、人間にとって根本的に外界における形成原理としてあるものは、人間が魂的・霊的生活として自身の生体組織から取り出したものであり、その結果それは自身の生体組織においてはもはや物質素材、実質の基礎とはなっていないということを示さなければなりません。とは言っても、私たちはそれを生体組織のすべての部分から同じ度合いで取り出したというわけではなく、その取り出しかたはそれぞれ異なっています。ただ今展開してまいりましたような予備知識をいわば身に備えている場合にのみ、人間の生体組織に、それにふさわしい方法で近づくことができるのです。と申しますのも、私たちの神経系を構成しているすべてのものを観察してごらんになれば、次のような特徴に気づかれるでしょう。つまり、通常神経細胞あるいは神経組織(Nervengewebe)などと呼ばれるものはまさに本来的な形成物であり、比較的初期の発達段階にとどまっていて、それほど進化した細胞形成物ではないということです。従って、こうしたいわゆる神経細胞は、初期の原始的な細胞形成の特徴を示していることを期待せざるを得ない、と言わねばならないでしょう。けれども別の関連においてはまったくそうではありません。なぜなら、神経細胞はたとえば増殖力を持たないからです。神経細胞は、血液細胞と同じく、形成されると分割不可能で、増殖できないのです。つまり、人間以外のものの細胞に与えられた能力が、比較的初期の段階に神経細胞から奪われているのです。この能力は取り去られているわけです。神経細胞は初期の進化段階にとどまり、いわばこの進化段階で麻痺させられています。この神経細胞のなかで麻痺させられたものが、魂的・霊的なものとして、自らを分離するのです。その結果私たちは実際に、自らの魂的・霊的なプロセスによって、かつて器官的実質のなかで自らを形成していたものに立ち返るのですが、これに到達するのは、私たちが比較的初期の段階で殺した、少なくとも麻痺させた神経実質を自らのうちに有していることによってのみ可能なのです。このようにして神経実質の本質に近づくことができます。さらに、この神経細胞が、一面ではかなり原始的な形成に似ているように見え、さらにそれが発達した段階においてさえ原始的な形成に似ているように見えるのにもかかわらず、それが通常人間において最高のものとされる精神活動に奉仕するという特性を備えているのは何故かということがわかってきます。哲学・思想ランキング
2024年08月18日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第三講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 1-2本講1-2 19世紀における唯物論的傾向が、いわば魂的なものをすべて神経組織に負わせました。そこから人間において起こっているあらゆる霊的・魂的なものを、その際神経組織のなかに見出され得るはずの平行現象において解明するということが次第に一般化します。ご存知のように私は、こういった類の自然観察に対して、「魂の謎について」(☆2)という著書のなかで異議を申し立てざるを得ませんでした。この本において私がまず第一に示そうと試みたことは、この真実を実証するために経験の面から加えられることは、ほかならぬこの通常の観察法によってこそ数多く得られるのですが、神経組織と関係しているのは、本来の表象プロセスのみであって、感情のプロセスは、間接的にではなく直接的に、生体組織の律動的現象に関連しているということです。今日の自然科学者は通常、感情プロセスは律動組織とは直接関係はなく、この律動プロセスが神経組織に中継されることによってのみ関係している、つまり、感情生活も、神経組織によって営まれるのだと考えます。さらに私は、意志生活全般もまったく同様に、間接的にではなく直接的に、新陳代謝組織と関係していることを示そうとしました。つまり意志のプロセスに関しても、神経組織にとっては、この意志プロセス自体を知覚すること以外の何物も残されていないわけです。神経組織を通じて何らかの意志が実行されるのではなく、意志を通じて私たちのなかで起こっていることが知覚されるのです。私が主張いたしましたことはすべて、生物学上のそれに応じた事実によって完璧に証明されうることですが、他方、これと反対の、魂生活を神経組織だけに組み込む見解は、まったく証明することができないのです。いわゆる運動神経なるものを切断し、感覚神経なるものを切断して、両者をつなぎ合わせることができ、そこからまた均一の神経が生じるという事実がありますが、感覚神経(sensitive Nerven)と運動神経(motorische Nerven)があるという見解とこの事実が、まったく健全な理性をもってすればどうやって関係づけられるべきなのか、ちょっと見ていきたいと思います。感覚神経と運動神経といったものは実は存在せず、運動神経と呼ばれているものは、私たちの四肢の運動、すなわち、私たちが「意志する」ときに私たちの四肢の新陳代謝において起こっていることを知覚する感覚神経にほかならないのです。つまり、運動神経とは実際のところ、私たち自身の内部においてのみ知覚する感覚神経なのです。それに対して、感覚神経と本来呼ばれているものは、外界を知覚しているのです。医学にとって非常に重要な意味を持っているけれども、事実そのものをきちんと見据えることによってはじめて正当に評価され得るものは、この方向にあるのです。なぜなら、昨日私が結核の例を得るために出発点とした病気の諸症状に対しても、感覚神経と運動神経の区別で済ませてしまうことは実際困難だからです。従って、賢明な自然観察者は、どの神経も単に周辺から内部へ、あるいはその逆へと伝わるだけでなく、周辺から中心へ、あるいは中心から周辺へも伝わるということをすでに受け容れてきたのです。同様に、どの運動神経にも二つの回路があるということになります。すなわち、神経組織から、何かを、たとえばヒステリーを説明しようとすると、互いに反対に流れている二つの回路を容認することが必要なのです。つまり、事実に立ち入るやいなや、神経組織についてのそもそもの仮定に完全に矛盾する、こうした神経の特性を容認することがどうしても必要になるのです。たとえばヒステリーの場合に起こっていることのように、生体組織のなかで通常神経組織に定められているものについて知るべきであったことが、神経組織についてのこういう通例の考えかたを習ったことですべてふさがれてしまったのです。私たちは昨日、たとえば結核の場合に起こって、神経によって単に知覚されているものを、新陳代謝における出来事によって特徴づけました。こういうことにこそ留意せねばならなかったのに、そうするかわりに人々は、神経組織の振動可能性や振動のなかにのみ、ヒステリーを探究し、すべてを神経組織のなかに置き換えてしまったのです。こうして、さらにまた別のものももたらされました。とは言え、ヒステリーの遠因のなかにはやはり心魂的な原因もあることは否定できません。心痛、失望感、実現可能なものも不可能なものも含めて何らかの内的な興奮、これらがヒステリーの徴候のなかに入り込んでいます。けれども、神経組織以外の生体組織全体をいわば魂生活から切り離し、神経組織だけをまさに直接魂生活に関係づけたことによって、すべてを神経組織に負わせることを余儀なくされている状況です。これにより生じてきた見解は、第一に、もはやわずかなりとも事実には裏付けされず、また第二に、魂的なものを人間の生体組織にさらに近づける手がかりを何ら与えないような見解です。魂的なものをもっぱら神経組織にのみ近づけ、人間の生体組織全体に近づけることはしないのです。せいぜい、存在してもいない運動神経というものを考え出して、運動神経の機能からさらに循環その他への影響を期待することによって、全体に近づけようとするぐらいですが、この循環その他への影響というのもまったく仮説の域を出ないものです。私が説明いたしましたことは、暗示と催眠といったようなことが現れてきたときに、きわめて思慮深い人たちを結局誤謬の道に導くことになってしまったことなのです。その際ーー少し以前のことになりますがーー、ヒステリーのご婦人がたが、きわめて思慮深い医師たちを誤謬に導き、欺く、といったことが体験されました。こういう人たちが医師の前で披露してみせる、ありとあらゆることに気をとられて、本来生体組織のなかで起こっていることには入っていくことができなかったからです。けれどもこのことに関連してーーこの場合はヒステリーの婦人ではなく、ヒステリーの男性なのですが、もともとこういう事柄に関しては非常に思慮深いのが常であるシュライヒ(☆3)のような医師が、いかなる誤謬に陥ったか、陥らざるを得なかったかををお話しするのも、一興かもしれません。つまりこの時、医師であるシュライヒのもとに、インクのペンで指を刺してしまった男性がやってきて、明日の夜にはきっと死んでしまうだろう、血液が毒されてしまうから、腕を切断してもらわなければならないと言ったのです。当然のことながら、外科医であるシュライヒは切断を敢行することはできませんでした。彼にできたのは、この男性を落ち着かせ、傷口を消毒するなど必要な処置を施すことだけであって、明日の夜には血液が毒されてしまうからなどという申し立てに応じて、この男性の腕を切断することなどむろんできませんでした。するとこの患者は、また別の権威のところに行きましたが、当然ここでも彼の腕は切断してもらえませんでした。しかしシュライヒは事態にいささか不吉なものを感じました。朝になってすぐ問い合わせると、その患者はほんとうにその夜死んでいたのです。そこでシュライヒは、暗示による死と診断をくだしました。「暗示による死」と診断することは、容易に、はなはだ容易に推測できることです。しかしながら、人間の本質への洞察があれば、このやうなやりかたで暗示による死を考えるということはあり得ません。ここでは、暗示による死が診断されるやいなや、原因と結果との根本的な混同がされているのです。もちろん血液が毒されているということはなく、これは解剖により確認されましたが、当の患者は、医師たちには公表されない原因によって死亡したように見えますが、事態を洞察することのできる人にとっては、彼の死はまぎれもなく、生体組織の深部に根ざした原因によるものなのです。この生体組織の深部に根ざした原因が、その数日前からこの人物をぎごちなく不安定にさせていたので、彼はインクのペンで自分の指を突き刺すというような、通常はしないことをしてしまいました。これは彼がぎごちなくなった結果起こったことなのです。そしてこの人が外的ー物質的な意味でぎごちなくなる一方で、内的な透視能力はいくらか高められ、病気の影響で、夜になってやってくる自らの死を預言的に見通していたのです。彼の死は、彼がインクのペンで指を突き刺したこととは全く関係なく、彼が自分のなかに有している死の原因によって感じたことの原因となったのが、この予見された死だったのです。起こったことはすべて、死をもたらした本来の内的プロセスに、もっぱら外的に関連していることにほかなりません。ですからここで「暗示による死」が登場してくるのは全く問題外です。なぜならこの男性が信じていたことや彼の有していたすべてのものは、死を招いたこととは何の関係もなく、もっと深い原因があったからなのです。ともあれ彼は死を予見し、起こったことをすべて、この死の予見に引き込んで解釈したわけです。この例によって同時に、自然における複雑な事象について適切な判断を得ようとするといかに慎重でなければならないか、おわかりいただけたと思います。その際はきわめて単純なことから出発することはできないのです。とはいえ、つぎのような疑問を提出せざるを得ないでしょう。つまり、感覚による知覚(Sinneswahrnehmung)とそれに類するすべてのものは、人間の生体組織に対して薬剤から発せられているはずの、いわば少々異なった種類の影響のための手がかりを私たちに与えてくれるのかという疑問です。さて、正常な状態において人間の生体組織に対する三種類の影響がありますね。第一に感覚による知覚を通しての影響で、これは神経組織のなかでさらに継続されます。第二に、律動組織、すなわち呼吸と循環による影響、第三に新陳代謝による影響、以上の三つです。これら三つの正常な関係は、何らかの方法で外的自然から取ってこなければならない薬剤と、人間の生体組織の間に私たちが作り上げる異常な関係のなかに、何らかの相似物を有しているはずです。しかしながら、外界と人間の生体組織との間に起こっていることがもっとも顕著に現れるのは、神経組織への影響においてなのです。従って私たちは次のように問わなければなりません。人間自身と、人間の外部にある自然であるもの、つまり、その経過としてであれ、実質的に薬剤としてであれ、人間の治療のために私たちが利用しようとする外的自然、この両者の間に、私たちはどうやって合理的な関係を考えることができるのか、と。私たちは、人間と、私たちがそこから薬剤を取ってくる人間の外部の自然との相互関係がどのようなものであるかについて、ひとつの見解を獲得せねばなりません。と申しますのも、水治療法を適用するときでさえ、私たちは何か人間の外部にあるものを用いているからです。適用されるものはすべて、人間の外部にあるものから人間のプロセスへと適用されているのであり、私たちは、人間と人間の外部のプロセスとの間の関係がどういうものなのかについて、合理的な見解を手に入れなければならないのです。ともかくここで、現在通用している医学という学問の組織的関係に代わって純粋な集合体としてまとまりのあるテーマにたどり着きます。医学生は通常まず準備段階として自然科学の講義を聴きます。それからこれを基礎にして、一般病理学および個別病理学的なもの、一般治療学的なもの等が構成されるのですが、いざ本来の医学の講義が始まると、この本来の医学講義で語られているプロセス、つまり治療処置というものが、外的自然の経過といかなる関係にあるのかについては、もはや聞くべきことはあまりないということになります。私が思いますには、今日の医学教育を受けてきた医師達は、このことを、単に外的知性的に欠陥であると感じるだけでなく、実際に病気のプロセスに介入すべきときに沸き起こってくる感覚のなかで、ある感情として、何かを用いようとする際にある種の不確実さの感情として、自らの心のうちに強く刻みつけることでしょう。使用すべき薬剤と、人間のなかで生じている、実際に存在しているものとの関係が真に認識されることは何といってもまれなのです。ここでは、ことの本性そのものから医学という学問の改革の必要性を指摘することが重要です。さて、きょうはまず、人間の外部の自然におけるある種のプロセスを手がかりに、これらのプロセスが、多くの点において人間の(内部の)自然のプロセスといかに異なっているかを明確にすることから始めたいと思います。私はまず、下等な動物や植物において観察できるプロセスから始めて、そこからさらに、人間の外部にあるもの一般つまり植物界、動物界、とりわけ鉱物界から取り出されるものによって引き起こされるプロセスへの道を見出したいと思います。けれども私たちが、純粋な鉱物実質のこういう特徴付けに接近することは、ごく基本的な自然科学的表象から出発して、さらに、例えば砒素や鉛といった薬品ではないものを人間の生体組織のなかに取り入れる際に起こることへと上昇していくときに、はじめて可能になるのです。ここでまず指摘せねばならないことは、人間以外の存在においては、成長における形態変化(Wachstumsmetamorphosen)が、人間内部の自然そのものの場合とはまったく異なっているということです。私たちは、人間のなかの本来の成長の原理、生きた成長の原理を何らかの方法で考えないわけにはいかないでしょうし、人間以外の存在の成長の原理も考えねばならないでしょう。けれども根本的な意味を持っているのは、そこで生じてくる差異なのです。例えば何か非常に身近なもの、通称ニセアカシアと呼ばれるロビニア・プセウドアカシア(Robinia pseudakasia)を観察してみてください。このニセアカシアの葉を葉柄のところで切り取ると、興味深いことに、葉柄が形態変化によっていくらか変形され、さらにこの変形されてこぶ状になった葉柄が、葉の機能を受け継ぐということが起こります。ここでは、私たちがとりあえず仮説的にひとつの力と呼びたい何かが強く働いています。この力は、植物全体のなかに潜んでいて、私たちがその植物がその正常に形成された器官を特定の機能のために用いるのを妨げるときに発現してくる力なのです。単純に成長する植物において非常にはっきりと現れているものの名残りと申しましょうか、そういうものが存在している、ということは、人間の場合も、何らかの理由によって一方の腕あるいは手を何らかの機能のために用いるのを妨げられた人は、もう一方の腕あるいは手がより力強く形成され、物理的にも大きくなるなどといった事例によって証明されます。私たちはこういう事柄を互いに結びつけなければなりません。なぜなら、これが治療法の可能性を認識することに至る道なのですから。参考画:Robinia pseudakasia哲学・思想ランキング
2024年08月17日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第三講 1920年 3月23日 ドルナハ*1998.11.21.改訳 1-1本講1-1 私に提出していただいた皆さんのご希望はすべて、この連続講演を進めていくなかで自然に消化していきたいと思います。もちろんそのためには、重複することもあるでしょうから、少なくともある部分まで、全部の希望が集まっていることが必要です。その際、ここで質問されたり、示唆されたりすることを、ある種の基礎を作りあげる前に語るか、作りあげたあとに語るかはどうでもよいことではありません。従って本日は、皆さんのご希望を見て気づいたことを考慮に入れながら、でき得るかぎり、明日以降の講演のための基礎を作りあげる試みをしてみたいと思います。もうおわかりのように、私は、最初の考察のために骨・筋肉組織の形成とその内的効力を起点にしようとしました。そして、わたしたちは昨日、少なくとも取り敢えずは、病気のプロセスの具体的な観察と治療の必要性へと押し進み、ひとつの実例とそれに適した観察を結びつけるために、心臓組織における循環から出発しなければなりませんでした。さて、きょうは、治療全般の可能性とその本質についてのより深い人間観察から得られる見解について、原則的な前置きをさらに二乃至三述べておきたいと思います。個々のものについては、引き続き考察のなかで立ち入っていくつもりですが、まずこの原則的な説明を優先したいと思います。そもそもが、今日(こんにち)の医学研究はどのような性質のものなのか想定すると、少なくとも大筋において見出せることは、治療は病理学と並んで現れているけれども、両者の間に、明確に見通せる関係は成立していないということではないでしょうか。とりわけ治療においては、今日往々にして、単なる経験的な方法の独壇場となっています。合理的なもの(etwas Rationelles)、つまりそれに基づいて実践的なことにおいて実際に原理を打ち立てることのできるような、そういう合理的なものは、とりわけ治療においてはほとんど見出すことができないのです。周知のとおり、19世紀におけるこの医学上の思考方法の欠陥は、医学上のニヒリズム派にさえ通じてしまいました。このニヒリズム派は、すべて診断に基づき、病気が識別できれば満足し、治療における何らかの理性(ラツィオ/Ratio)に対しては全般的にまさしく懐疑的な態度をとったのです。さて、医療制度に対して、いわば純粋に理にかなった要求をするとしたらやはり、そもそも診断と関連したところですでに治療を暗示するものが存在していなければならないと言わねばならないでしょう。治療と病理学の間に単なる外的な関係が保たれているだけではいけないのです。私たちはいわば病気の本質を、この病気の本質から治療プロセスについての見解を形作ることができるようなしかたで認識することができなければなりません。このことは当然のことながら、治療法と治療プロセスは、そもそも自然のプロセス全体のなかにどの程度まで存在しうるのかという問いと関連しています。パラケルススの大変興味深い箴言「医者は自然を通じて試行していかねばならない(☆1)」は非常にしばしば引用されますが、最近のパラケルスス文献は、まさにこういう箴言(シンゲン)からとりかかるということを充分心得ているとは申せません、さもなければ、自然そのものから治療のプロセスをひそかに学びとることをどのみちもくろまざるを得ないからです。なるほど、自然が自らそれに対して策を講じるような病気のプロセスがそこにあるときは、そういう試みもされるでしょう。けれどもこれは、すでに損傷があって自然が自ら自衛策を講じる場合、その治療処置に関して、やはり自然というものを特例として観察することに通じます、真の自然観察というのはやはり正常なプロセスを観察するものなのにです。すると、次のような疑問が起こってくるにちがいありません。つまり、治療処置について何らかの見解を得るための手がかりとして、正常なプロセス、いわば正常なプロセスと呼ばれているものを自然のなかに観察する可能性があるのかという疑問です。皆さんはお気づきでしょうが、このことはいくらか考慮を要する問題と関連しています。病気のプロセスが自然のなかに正常なありかたで存在しているときには、当然のことながら、自然のなかに正常なしかたで治療プロセスを観察することが可能です。すると、いったい自然そのもののなかに、自然を通じて試行し、自然を通じて癒すことができるような、病気のプロセスがすでに存在しているのかという疑問が生じてきます。この疑問に対しては、もちろん、この連続講演が進むにつれてはじめて完全に答えが与えられるでしょうが、きょうのところはせめて少しだけこの答えに近づくことを試みてみましょう。けれどもその際即座に言えることは、ここに呈示しましたような道は、今日通用しているような自然科学に基づいた医学を注がれておおわれてしまっているということです。現在のような前提においては、このような道を歩むことは非常に困難です。と申しますのも、たいへん奇妙なことに、ほかならぬ19世紀における唯物論的傾向が、ここで私が骨組織、筋肉組織、心臓組織に続いて付け加えねばならない組織、すなわち神経組織をそもそもその機能において完全に誤解するという事態を招いてしまったからです。記:パラケルススの思想は新プラトン主義の系譜を引く自然神秘主義としての側面を持っており、自然を神によって生み出されたものとして捉えている。神においてある第一質料=大神秘から硫黄、水銀、塩の3つの元素の働きが展開することによって四大元素(地、水、火、空気)が生まれ、ここから万物が生み出されるとした。全宇宙を一つの生きた全体(有機体とも)と考え、水銀を宇宙の始原物質とした。神秘思想家としては、体と魂を結合する霊的な気体とされる「アルケウス(英語版)」の提唱で知られ、後に「ガス」という言葉の考案者でもあるフランドルの医師ヤン・ファン・ヘルモントに影響を与えた。この「アルケウス」は人体に内在しているとされ、例えば胃のアルケウスは食べた物の中から栄養分と栄養分でないものに分離し、栄養分を同化するとし、肺のアルケウスは空気を一種の栄養分として吸収していると考えた。パラケルススの思想にはマクロコスモスとミクロコスモス、大宇宙と小宇宙たる人間の照応という世界観が根底にある。マクロコスモスとしては地上世界、天上世界(星の世界)、霊的世界の3つを考え、それに対応するミクロコスモスである人間を身体、精気、魂に分けて考えている。地上界-身体と天上界-精気は目に見える世界であり、それを支配する霊的世界-魂は目に見えない世界であるとした。参考図:宇宙の始原物質/mercury哲学・思想ランキング
2024年08月16日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講解説・第8回 生体組織のプロセス全体を健康にしていくこうした医学的処置をするにあたって、最大の障害となるのは、社会的状況であり、また患者自身であるといえます。患者は、まず症状そのものを取り除くように求めるからです。しかし、そういう処置をしてしまうと、病状をもっと悪くしてしまうこともあるのです。言うまでもなく、こうして少しばかり特徴をお話しました処置にとって、最大の障壁はまず第一に状況、社会的な事情です。従って医学とはまったくもって社会的な問題でもあるのです。他面において、最も強力な障壁を築いているのは患者自身であるともいえます。患者は当然のことながら、何はさておき、何かを、彼らが言うように「取り除いて」ほしいと要求するからです。しかしながら、彼らが持っているものをそんなに直接取り除いてしまうと、すでにそうなっているよりももっと病気を悪くしてしまうという事態が容易に起こりうるのです。患者を今の状態よりももっと悪くしてしまうことも考慮しておかなくてはなりませんが、彼らを再び健康にすることができる状態になるまでは待たなくてはならないのです。けれども、大多数の皆さんにご同意いただけるでしょうが、その時にはたいてい患者さんは逃げ出してしまっているわけで、治療を正しく方向づけるためには、医師は病気の後のケアも完全にしなければならないのですが、症状を取り除いたことで満足してしまいがちです。障害は、医師にもあるのです。そもそも治療というもの全体に正しい価値を与えようとすれば、医師は後療法をも完全に掌握していなければならないのですが、これこそ、健康な人間及び病気の人間の正しい観察の結果帰着することなのです。こういうことこそ、まさに公然と目指されねばならないのです。現代のような権威信仰の時代にあっては、このような動きがが導入されさえすれば、その必要性を指摘することが困難であったりしてはならないはずです。然し乍ら、言うまでもなく皆さんの前でこのようなことを申しあげるのをお許しいただきたいのですが、病気をほんとうにその支脈の末端まで追求することを適切であるとみなさず、単に何かを取り除いたことで多かれ少なかれ満足しているのは、いつも患者や社会状況であるのみならず、医師のかたがたであることも屡々あるのです。治療にあたっては、上部と下部の二元性を正しく把握しなければなりません。それは唯物論的な見方に基づいた言葉によっては、非常に説明しにくいのですが、シュタイナーはそれを、アナロジーによって説明しようとしています。とはいえ、このように人間の生体組織のなかでの心臓の位置づけを正しく追求することが、私たちを病気の本質へと徐々に導いていくということはご理解いただけると思います。ただ、皆さんに注目していただかねばならないのは、下部の諸々の組織的活動は単に外的な化学的活動であるものをなるほどある意味で克服してはいるけれども、それと全く反対の上部の活動にやはり何らかのしかたで類似しているというとき、これら上下の間に成立している徹底的な差異なのです。この人間の生体組織における上下を指摘する二元性(Dualismus)に満足に足る定義を与えることは非常に困難です。私たちの言語は、物質的、器官的なものに対立するものを暗示すための手段をほとんど有していないからです。けれども、まず次のようなアナロジーによって、こういう事柄について語るべきことはもっとたくさんあるでしょうけれども、本来この下部プロセスと上部プロセスの間の二元性がどんなものなのかを明確にするなら、もしかすると良くご理解いただけるかもしれません。もしかすると皆さんのどなたかの何らかの先入見にぶつかる可能性が無きにしも非ずですが、私はあえてそういたします。シュタイナーは、上部と下部の二元性をホメオパシー(*同種療法)で説明しています。物質の特性は、一律にどこまでも分割可能なものではなくて、ある限界を超えると反対のものに転化する可能性すらもっています。自然にはそうしたリズミカルな過程があるのです。皆さんが何らかの物質の特性を考えるとき、つまりどういうかたちであれ私たちの前にある物質が効力を生じる際の特性を考えるとき、まず第一に、消化の際に起こっているように生体組織によって克服されて人間の下部の活動に取り入れられるものが考えられます。さて、こう言ってよろしければ、ここでホメオパシー(同種療法)(**)を行うことができます。その物質の集合性、連関性を止揚することができるのです。このことは、その物質を何らかのやりかたで希釈するとき、いわゆるホメオパシー的極小量を用いるときに生じます。よろしいでしょうか、このとき、現代の私たちの自然科学全般においてまともに観察されていないことが明らかになるのですが、人々はすべてを抽象的に観察することに慣れっこになってしまっています。ですから、ここにひとつの光源があるとすると、彼らは、光はあらゆる方面へ広がっていくと言い、これがあらゆる方面へ広がっていって無限のかなたで消滅すると考えるのです、彼らは太陽についてもそう考えます。けれどもこれは正しくありません。このような活動はいかなる無限のかなたでも消え去ることはなく、ある範囲の限界まで達するのみで、その後弾力性をもっているようにはね返ってきます。たとえその性質はしばしば往路の性質とは異なっているにしても、はね返ってくるのです(図)。自然のなかにはリズミカルな経過があるのみであって、無限のかなたに通じる経過は存在しないのです。リズミカルに再びそれ自身にはね返ってくるもののみが存在しているのです。これは単に量的な拡散にのみあてはまることではなく、質的な拡散にもあてはまることなのです。皆さんがある物質を分割し始めるとき、その物質は最初の出発点において特性を持っています。これらの特性は、無限に減っていくのではなく、ある点にいたると、はね返ってきて、それとは反対の特性になるのです。上部と下部の対立性もそういうふうにイメージすることが可能です。生体の上部組織と下部組織の間にもこうした内的なリズムがあります。上部組織はホメオパシー的なもので、下部組織は特性がある時点で逆転したものであるといえますから、その特性を利用して、薬剤師は希釈を行うことで、下部組織に関係した諸特性を上部組織に関係した諸特性に導くことができるのです。私たちの生体の上部組織と下部組織の間の対比もこの内的なリズムに基づいています。私たちの上部組織はホメオパシー的なものです。それはある意味で通常の消化プロセスの正反対のもので、その反対物、ネガを形成するものです。したがって、ホメオパシーの薬剤師は希釈をおこなうことで、普通は人間の下部の生体組織に関係していてこれと関係のある諸特性を、今度は人間の上部の組織に関係のある特性へと、実際に導いているのだと言うことができるでしょう。これはたいへん興味深い内的な連関です。この連関については明日以降さらにお話していきましょう。<訳注>*ホメオパシー[Homoeopathie] 同種(類似)療法。健康体に与えるとその病気に似た症状を起こす物質を、ごく低濃度に希釈し、それを薬品としてその病気にかかった患者に投与して治療する方法。アロパシー[Allopathie](逆症療法)はちょうどこれとは逆のやりかた。シュタイナーはホメオパシーとアロパシーをどう捉えるべきかさらに第五講で述べています。ホメオパシーは、19世紀初頭にドイツの医師ハーネマンによって始められた治療法で、稀釈したレメディー(治療薬)を使用し、同様の症状を引き起こす物質を使って病気を治そうとします。一方、アロパシーは一般的な現代医学で、主に薬物療法や手術を用いて病気を治療します。両者はアプローチが異なり、ホメオパシーは代替医療の一種として位置づけられています。*参考資料:「健康な人に投与して、ある症状を起こさせるものは、その症状を取り去るものになる。」ホメオパシーとは同種の法則を根本原理とする自然療法です。難解ではありますが、近いものが日本の民間療法にもあります。喉が痛いときショウガ湯を飲んだり、 熱が出ているときに布団をかぶって熱くしたりするのがそれです。ホメオパシーでは、熱には熱を生じさせるもの、不眠があれば不眠を起こすものという具合に、 同種でもって自然治癒力に働きかけ、病気の原因を自分で押し出し、体の芯から健康を取り戻すことを主眼においています。参考画:Homoeopathie and Allopathie 第2講解説・第8回 了 「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 終了哲学・思想ランキング
2024年08月15日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講解説・第7回 病気の諸症状の間には相互作用が生じています。痩せるという症状は、諸々の症状の間の相互作用のなかのひとつなのだといえます。ですから、そうした症状をひとつひとつをばらばらに見るのではなく、一連の連関のなかでそれを見ることが大切なのです。結核の場合にも、防御反応のひとつとして生体組織自体にそうした反応を引き起こす力がない場合には、それを助けて反応を起こすようにすることは、合理的なことなのです。「健全に病んでいる人間」の生体組織の成長と生成全体と関係しているあらゆる出来事を注意深く研究すれば、病気の諸症状の間にも相互作用が生じていると言えるところまで導かれることがおわかりになると思います。痩せることはまずもってひとつの症状です。記:健全に病んでいる人間とは、自分の状態を受け入れつつも、精神的な問題を楽しむ余裕を持つ人のことを指します。このような人は、自分自身との対話を楽しみながら、より健康的な方法で自分の感情や悩みと向き合います。 しかしながら、結核の素質との関係において、つまりいくらか活動し始めている結核との関係において、この痩せるということは、諸々の症状の間の相互作用の一部なのです。すなわち、ひとつの組織体、諸々の症状の観念上の組織体とでも言うべきものが成立しているのです。ひとつの症状はある意味でほかの症状に属しているのです。従って、生体組織の他の条件によって何か反応のようなものが起こるとき、結核の例にてとどまりますが、生体組織自体にこの反応を引き起こす力がない場合は、これを助けて反応を起こしてやること、まさにひとつの病気に別の病気が続くようにしてやることは、全く理にかなったことになるのです。古代の医師たちは、霊視力を持ってそうした諸連関を見ていたがゆえに、別の症状との正しい関係をもたらすために、ある症状をも引き起こすことができなければならないことを知っていました。病気を癒すことができると同時に病気を引き起こすこともできなければならないわけです。古代の医師たちはこのことを、医師のためのいわば意味深い教育法則として語ってきました。医師であることによって危険なのは、単に病気を取り除くことができねばならないというだけではなく、病気を引き起こすこともできなければならないということだと古代の医師たちは語りました。つまり、医師は病気を癒すことができるのと全く同じ程度に、病気を引き起こすことができるというわけです。隔世遺伝的な霊視力によってこういう関連についてもっと多くのことを知っていた古代人たちは、医師のなかに、彼が悪意を持てば、人々を健康にするばかりでなく、病気にすることもできる人物を同時に見ていたのです。けれどもこのことは、他の発病状態との正しい関係をもたらすために、何らかの発病状態を引き起こさなければならない必然性と関連しています。とはいえ、これらは病気の状態であることは確かです。咳、喉の痛み、胸の痛み、痩せる徴候、疲労の徴候、盗汗、これらはすべて、病気の症状には違いないのですから。これらの症状は引き起こされねばならないとはいえ、やはり病気の症状であることは間違いないのです。防御反応として起こしたことであっても、一度そういう症状を起こした場合には、適当な時期が訪れたときに、それを治療してその症状をなくさなければなりません。結核の場合、防御反応として咳のや喉の痛みが引き起こされた場合には、通常、下部においては便秘状態になっているのですが、それを改善するために、下痢の状態へと導かねばならないのです。このことから、半分治療した時すなわちこれらの症状を引き起こした時点で、病人をその運命に委ねてしまうことはできず、この時こそ治療プロセスの第二の部分が現れてこなければならないということがおのずと容易にご理解いただけると思います。その時は、単にこれらの反応、つまり病気を防ぐために引き起こしたものが存在するように配慮されねばならないだけではなく、今度はこの反応を癒し、生体組織全体を再び正しい道に導くものが生じてこなければならないのです。したがって例えば、結核の素質に対しての自然なあるいは場合によっては人為的に引き起こされた防御として、咳の刺激が引き起こされたとき、また喉の痛みが起こったりあるいは引き起こされたときには、その際常にいくぶん詰まった状態つまり便秘状態を呈しているであろう消化プロセスが秩序正しいものになるように配慮されねばなりません。何らかの方法で気づかれることでしょうが、ひとつの防御プロセス、一種の下痢に移行させられねばならないのです。常に、咳の徴候や喉の痛みその他に続いてこのような下痢が起こることが必要なのです。まさにこのことが、上部に現れていることをそれ自体として観察してはならず、たとえ物質的な媒介物はなく、対応関係があるだけだとしても、上部に現れていることの治療を、下部における経過を通じて探究せねばならないことが多々あるということを示唆しているのです。このことは何にもまして考慮されてしかるべきなのです。防御反応の症状は、適当な時期に、それを克服しなければなりません。新陳代謝が優勢であって、それが上部によって制御されないときには疲労の徴候が現れますが、その場合には、消化活動を活発にさせる必要があります。痩せるという症状に対しては、脂肪を形成させるような食餌療法が必要ですし、寝汗という症状も、汗を出させるための活動が必要になるのです。疲労の徴候、私はこれを単に主観的な疲労徴候と呼ばずに、本来常に新陳代謝の優勢に基づいている、全く組織的に引き起こされた疲労徴候と呼びたいのですが、新陳代謝が上部によって制御されない時に強く現れるような疲労徴候は、結核の場合これが実際に引き起こされねばならないので、その後必要な時点で克服されねばなりません。つまり、それに応じた食餌療法によって、こうした食餌療法の詳細についてはさらにお話すべきことがあるでしょうが、消化が優勢になるように、すなわちその人の通常の状態よりも消化活動が活発になるように、いわばもっと簡単に消費されてしまうものが、消化プロセスを通じて消費されるように配慮することで、こういう疲労徴候は克服されねばならないのです。痩せることも、今度は一種の脂肪形成,つまり器官や器官組織のなかへの蓄積を起こさせるような食餌療法によって、後から克服すべきでしょう。盗汗もまず最初に引き起こされた後に、きわめて知的な活動、つまり努めて熟考するなどして実際に汗を出すような活動を指示することを試みることによって、後から克服されねばなりません。そうして再び健康な発汗が促されるのです。病気の諸関連を見ていくならば、病状を強めたり弱めたりすることで病気の経過を必要な方向に導き、やがて生体組織のプロセス全体を健康にしていくことができるようになります。まず最初に心臓の活動を正しく把握することにより、人間において上部と下部がいかに対応しているかを理解するなら、さらに、神経衰弱やヒステリーのような、機能的なもの、エーテル的なもののなかに病気の最初の発生、いわばかすかな兆しが見られることを理解するなら、器官的なもの、物質的なものにそのとき刻印されているものを理解することへも進んで行けるのだということがおわかりになると思います。こうして相関しあっている病気の像の外観を研究することにより、最初に引き起こすものも含めて、いわば病気の経過を、場合によって病状を強めたり弱めたりさえしてある方向に導き、時期が到来すれば、プロセス全体を再び健康にすることができるでしょう。参照画像:cat-Tuberculosis 第2講解説・第7回 了哲学・思想ランキング
2024年08月14日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講解説・第6回 結核患者には、咳、喉や胸、四肢の痛み、疲労状態、特に寝汗などが徴候として現れてきますが、これらは上部と下部の不規則な相互作用の結果として生じているものです。しかし、これは同時に病気に対する生体組織の戦いでもあります。たとえば、咳の場合、下部組織が上部組織によって制御されないで起こるのですがこれは、侵入してくるものを防ぐための生体組織の健康な反応です。ですから、咳を止めてしまうということが害になることもあります。咳を止めることで、肉体が有害なものを受けいれてしまうからです。咳をするというのは、そうした有害なものに耐えられないがゆえに起こるのであって生体内に侵入してくるものを侵入させないために必要なことなのです。結核患者になりかかっている、つまり将来結核が顕れてくる兆しがある人にきわめてしばしば見られる徴候を取りあげてみましょう。おそらく彼が咳をするのに気づかれると思います。また、彼が喉や胸の痛み、あるいは四肢の痛みも感じていることに気づかれるでしょう。さらに、ある種の疲労状態、そしてとりわけ盗汗(寝汗)に気づかれるでしょう。これらは何なのでしょうか。これらの徴候を目の前にするとき、これらすべてはいったい何なのでしょうか。私が今挙げたものはすべて、何よりもまず、先ほどお話しました内部の不規則な相互作用の結果として生じているものなのです。けれどもこれは同時に、もっと深い根拠として存在しているものに対する、生体組織の戦いでもあります.おわかりでしょうか、咳を、ここでは、まずはこのような単純な事柄を観察し、それからもっと複雑な事柄に移っていきますが、咳を、いかなる場合でも常に克服することは、全く良くないことなのです。生体組織にとっては咳をわざと引き起こすことが必要な場合さえあるのです。人間の下部組織が上部組織によって制御され得ない場合に咳の刺激として現れるものは、さもなければ侵入してくるものを侵入させないための、人間の生体組織の健康な反応なのです。したがって、いかなる場合にも咳を直接止めてしまうことは、場合によっては害になることもあり得るのです。肉体が有害なものを受け入れてしまうからです。その人のその時点での素質ではこうした有害なものに耐えられず、それを取り除こうとするために、彼は咳をするのです。咳の刺激は、生体組織に何らかのものが欠けていて、そのために生体内に侵入してくる可能性のある侵入者を侵入させない必要性があるということを示すものにほかなりません。咳の場合と同じように、喉や四肢の痛みといったものも、下部が上部によって制御されないで起こるプロセスが起こらないように結核の素質があるために近づいてくる有害なものに対して、生体組織が戦っているのだといえます。ですから、結核の素質があるとわかったならば、適度に咳を引き起こすようにしたり、食餌療法によって病気の徴候を引き起こすことで、生体組織を支えることが有効な場合もあります。たとえば、痩せるということもひとつの防御手段です。ですから、ある人が痩せていくからといって、すぐに太らせるための食餌療法をとるのが有効だとは限りません。そうしたことについて、個別的に研究していくことが重要なのです。私たちが挙げた別の徴候もまた、結核の素質があると近づいてくるものに対する、生体組織の防御や戦いなのです。喉の痛み、四肢の痛みはまさしく、生体組織が、上部のプロセスに制御できないような下部のプロセスが起こらないようにしていることを示しているのです。例えば逆に、早めに結核の素質に気づいたら、適度に咳の刺激を引き起こしたり、とりわけ、どういうふうにこれをすることができるかは、明日以降の講演で見ていきますが、ある種の食餌療法によって疲労の徴候を引き起こすことさえして、生体組織を支えるのが良いこともあるのです。さらに、例えば痩せるということも、ひとつの防御手段にすぎないのです。なぜなら、痩せない場合におこってくるプロセスは、下部における、上部に制御され得ないものに他ならないかもしれず、その場合生体組織は、制御され得ないものが一時的に存在しないように、痩せることによって自らを守るからなのです。ですから、例えばある人が痩せていく場合、すぐさま太らせるための食餌療法をほどこすのではなく、こういう事柄を個別的に研究することが非常に重要です。痩せるということが、まさにその時点で生体組織に現れてきていることにとって、たいへん良い意味を持っている可能性もあるからです。また、結核に対する生体の防御反応としてとりわけ重要なのは盗汗(寝汗)です。そして、まだ結核患者ではないけれども、結核にかかる見込みのある人の場合、とりわけ有益なのは盗汗です。なぜなら、盗汗は、睡眠中に実行される生体組織の活動に他ならず、これは本来ならば目覚めている時に、完全な霊的・心的活動のもとに行われるはずのものであるからです。本来ならば昼間に完全に目覚めた状態で行われるべきことが行われず、夜になって現れてきているのです。これは結果の現象であると同時に防御手段でもあります。生体組織が霊的な活動から解放される一方で、生体組織は盗汗に表される活動を行うのです。発汗などのあらゆる分泌現象は、目覚めた意識的活動に対応するものであり、魂的、霊的活動に密接に関係しているのですが、それに対して、生命的な構築プロセスは無意識的なものです。肉体をもっとも活発に形成する必要のある乳児がほとんど眠っているというのはこのことと深く関係しているのだといえます。もっともこうした事実を完全に評価することができるためには、あらゆる分泌現象は、汗の形成も含めて、普通は魂的、霊的活動がその中に含んでいるものと密接に関係しているということについて、少しばかり知っておかなくてはなりません。構築するプロセス、本来の生命的な構築プロセスというものは、すなわち無意識的な基盤をなすものにすぎません。目覚めた、意識的な魂的・生体組織的活動に対応するもの、これはいたるところにおいて、分泌プロセスなのです。私たちの思考というものも、脳の構成的プロセスには対応しておらず、脳の分泌プロセス、分解プロセスに対応しています。盗汗という現象は、通常の生活において本来は霊的・魂的活動と平行して進行していなければならないはずの分泌プロセスなのです。上部と下部が正しい相関関係にないので、そういう分泌プロセスは、生体組織が霊的・魂的活動から解放される夜まで持ち越されることになるのです。記:寝汗は睡眠中の発汗のことですが、東洋医学では生理現象とは別の良くない汗のことを「盗汗(トウカン)」と呼びます。盗汗は、シーツまで濡れてしまうほどの寝汗のほか、上半身、特に頭から首筋に汗をかきやすいのも特徴です。また、サラサラとした運動後にかくような寝汗と違い、粘っこい汗が頭部や首から胸のまわり、腰から股の周囲に多く出る場合も盗汗と呼ぶ場合があります。記:東洋医学では生理現象とは別の良くない汗のことを「盗汗(トウカン)」と呼びます。シーツまで濡れてしまうほどの寝汗のほか、上半身、特に頭から首筋に汗をかきやすいのも盗汗に見られる傾向のひとつです。参考図:Night Sweats 第2講解説・第6回 了哲学・思想ランキング
2024年08月13日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講解説・第5回 結核になりやすい素質は、下部の活動の上部への反作用です。こうした生体組織の持つ原素質、つまり結核になりやすい素質に遡ることで、結核の本質を見い出すことができます。細菌に感染するのは、そうした結核になりやすい素質の結果生じます。もちろん、結核菌に感染することで結核になるのですが、細菌による伝染は必要条件のひとつであるということであって、それだけで結核という病気が真に理解されるのではありません。ちなみに、「恐るべき範囲に広がっている」といっているように、シュタイナーがこの講義をした当時は、結核に罹(かか)る方が多かったようです。結核菌の発見から、結核の流行、死亡率の現象までに関しては、訳注を参照してください。これは興味深い関係です。結核になりやすい素質は、皆さんにただいまお話した通り、下部の活動の上部への反作用なのです。このように完全に終わりきらないプロセスが上部に反作用することによって生じる、この全く独特な相互作用が結核への素質をもたらすのです。この人間の生体組織の原素質(Ur-Anlage)とも言うべきものにさかのぼらないと、合理的に結核を扱う方法を見出すことはできないでしょう。と申しますのも、寄生生物(訳注)が人間の生体組織にはびこるということは、たった今皆さんにお話しました原ー素質の結果生じる現象にすぎないからです。記:「Ur-Anlage」は、生物学に関連する用語で、特に遺伝や胚発生の初期段階を指すことがあります。具体的な文脈によって異なる可能性があるため、詳細については関連する文献や資料を参照することをお勧めします。(注:住宅関連用語と紛らわしい。) このことは、必要な条件がそろえば結核のような病気は伝染するという事実に矛盾するものではありません。もちろんそのために必要な条件が整わなければなりません。しかし、この下部の器官活動の優勢は、残念ながら今日の人類の極めて大多数に現れておりますので、結核になりやすい素質は、今日実際恐るべき範囲に広がっているのです。必要条件のひとつとはいえ、細菌に感染するという観点は有効なもので、結核に罹っている方はやはり、その周囲に作用を及ぼしていきます。そういう意味で、最初の原因である第一次発生と伝染という概念は、ともに特にこの結核においては正当なものです。しかし、伝染という現象に関しては、必ずしも細菌の存在を原因としなくても説明は可能であって、伝染という現象から結核の本質がわかるのではないのです。とはいえ、伝染というのはこの領域においてやはり有効な概念です。かなりな程度に結核を病んでいる人は、周囲の人々に作用を及ぼすからです。内部で結核患者が生活しているものに晒(さら)されていると、通常は単なる作用にすぎないものが、今度は原因になり得るということがまさしく起こってくるのです。私はいつも、ひとつのたとえ、アナロジーによって、この、病気の第一次発生と伝染との間の関係を明確に説明しようとしているのですが、たとえば次のように言えるのです。私が道で、ふだんそれほど親しくつきあっていない友人と出会ったと考えてください。彼は悲しそうにやってきます。彼の悲しみには理由があります。彼の友人が死んでしまったのです。私が彼に出会い、彼が自分の悲しみを私に告げることにより、私も彼と一緒に悲しくなります。彼は直接の原因によって、私は伝染によって悲しくなるわけです。この場合確かなことは、この伝染の条件は彼と私とのお互いの関係のみであるということです。従って、第一次発生と伝染、という概念はどちらもまったく正当であり、とりわけ結核においては極めて正当なものなのです。ただ、合理的な意味においてこれらを真に用いなければなりません。結核療養施設がほかならぬ人工結核孵化場となっていることは少なくありません。結核患者を結核療養施設に詰めこむと、この施設をできる限り何度も繰り返し取り壊して、別の施設に作り替えねばならないでしょう。一定期間ののちには、結核療養施設は結局さらに遠ざけられねばならないでしょう。なぜなら奇妙なことに、結核患者自身がきわめて感染させられやすい素質を有していて、彼らはもっと重い結核患者の近くにいると、そうでなければもっと良くなっているかもしれない病気がおそらくいっそう悪くなってしまうからです。こうした結核の本質に関する事例から、人間の生体組織のさまざまなプロセスについて理解できるようになります。つまり、人間の生体組織における、呼吸活動、感覚・神経活動に関連した「上部」と栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝に関連した「下部」とが密接な関連しあっているという事実から、病気の本質を探究することができるようになるのです。さて、まずはとりあえず、結核の本質を指摘しておくだけのつもりでした。私たちはこの結核を一つの例として、人間の生体組織におけるさまざまなプロセスが、いかにお互い密接に関連し合っていなければならないかを理解します。これらのプロセスは、皆さんにもご想像いただけると思いますが、お互いにポジの像とネガの像が相対しているように対応している、上部組織と下部組織があるのだという事実に常に影響を受けざるをえないのです。ご説明しましたような生体組織の構造が存在することによって結核が準備されるという、いわば極めて特異な現象を手がかりにして、その経過のなかでさらに、そもそも病気の本質をどのように見るべきかを研究することができるのです。<訳注>* 寄生生物:原文ではDie Parasiten(Der Parasit:寄生動物、寄生植物の総称)の複数形で、ここでは広い意味での「細菌」の意味あいも含まれていると思われます。ちなみに、ローベルト・コッホによる結核菌の発見は1882年で、同時に発表された論文により、この菌が結核の第一次的要因になるという説が認められました。20世紀になると、ストレプトマイシンの効果が1944年に発表され、同時期にパラアミノサリチル酸、その後イソニアジドの抗結核性も実証されるなど、新薬の発見が相次ぎました。なお、肺結核の死亡率は17世紀半ばに非常に高くなり、その後徐々に低下し、再びピークを迎えたのは、18世紀の終わりから19世紀前半ということで、この講演の時期(1920年)と一致しています。シュタイナーは1925年に亡くなっているので、ストレプトマイシンのことは知る由もないのですが。興味深いことに、イギリス、フランス、ドイツなどでは、すでにストレプトマイシンの投与が始まる以前から死亡率が下がり始めていたそうです。けれども、日本で肺結核による死亡率が激減した1950年代は、ちょうどストレプトマイシンと新しい肺外科の技術が導入された時期と一致しているそうです。(訳者) 参考画:Heinrich Hermann Robert Koch 第2講解説・第5回 了哲学・思想ランキング
2024年08月12日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講解説・第4回 人間の生体組織における、呼吸活動、感覚・神経活動に関連した「上部」と栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝に関連した「下部」の相互作用について、新陳代謝プロセスが独立的な傾向を強める在り方が「ヒステリー」であり、それとは逆に、上部のプロセスが、上部の組織を酷使しすぎ、そのプロセスが正常に経過しないということによって起こるのが「神経衰弱」ですがそうした実像から認識されるのは、最初は単に機能的、エーテル的に存在しているものがその力を凝集することで、物質的現象が刻印されるということです。たとえば、最初はヒステリーの徴候としてだけ存在しているものが、下半身の疾患という形で物質的に現れたり、神経衰弱の場合も、喉の病気、頭部の病気として現れたりしますが、そのようにひとつの組織で起こることは、組織全体にも作用を及ぼすことになります。そうしたことを研究することこそが、医学の未来のために重要になります。さて、この上部と下部の相互作用について満足のいく実像が得られたなら、そこから出発して徐々に次のようなことが認識されるでしょう。すなわち、最初は単に機能的に存在しているもの、つまり私たちが言うところのエーテル的なもののなかで起こっているものが、いわばその力を凝集することで、器官的・物質的なものをとらえていくこと、そして最初はヒステリーの徴候としてのみ存在しているものが、さまざまな下半身の疾患のなかにいわばその物質的な形態を取り得ること、他面において神経衰弱は、喉の病気、頭部の病気のなかに器質的な形態を取り得ることについて語ることができるのです。神経衰弱的なものとヒステリー的なものに、当初は機能的なものだったこれらの物質的現象が刻印されるということ、これを研究することこそ未来の医学にとってはなはだ重要なことでしょう。器質的となったヒステリーの結果として、消化過程全体、下半身のあらゆる経過に不規則が生ずるでしょう。けれども、このようにひとつの組織で起こることは、さらに組織全体にも作用を及ぼします。不規則として生じていることが、さらに組織全体にも作用を及ぼすということを見過ごしてはなりません。たとえばヒステリー現象が、機能的、エーテル的にはまったく現れず、エーテル体が即座に物質体に押しつける場合がありますが、この場合、下半身の器官には疾患として現れてはきません。つまり物質的な病気にまでは到らないのです。しかしそれは、器官の疾患としてはあらわれてはこないものの、内部には存在していて、生体組織全体に働きかけています。そういう状態は病気と健康の間を漂っている状態だといえますが、その場合、下部から上部へと作用し、上部に反作用を与え、上部のネガのなかに、それが現れてくるという特殊な現象が起こります。そうした現象が、結核の素質をもたらすのだといえます。ふつうは神経衰弱を引き起こす領域に、ヒステリーの最初の物質的な結果である状態が作用して、結核の素質が現れるというのです。さて、その初期に機能的のもののなかに観察できるとしたら端的なヒステリー現象であるようなものが、そもそも機能的には全く現れてこないという場合を考えてみてください。確かにこういうことが起こりうるのです。機能的に表面に現れてくることなく、エーテル体が即座にそれを物質体に押しつけるのです。それは下半身の器官においてどんなかたちであれ明らかな疾患としては現れてきませんが、内部には存在しています。つまり下半身の器官には、いわばヒステリーの刻印を押されたものがあるのです。これは物質的なものに自らを押しつけたことにより、ヒステリー現象として心的に前面に現れてくることはないのですが、かと言って、やっかいな病気、物質的な病気であるにはまだ十分強くないのです。けれどもこれは、生体組織全体に働きかけるには十分な強さを持っています。その時、病気と健康の間を漂っていると申しましょうか、そういうものが、下から上へと作用を及ぼし、上部に反作用し、上部にいわば伝染してそのネガのなかに現れる、こういう特殊な現象が起こります。そこが一面的になったり、不規則になったりするとふつうは神経衰弱を引き起こすもとになる領域に、ヒステリーのいわば最初の物質的な結果である状態が作用してそこに現れる、こういう現象が結核への素質をもたらすのです。記:人間の身体は、上部と下部で異なる機能を持っています。以下にそれぞれの主な働きを簡単に説明します。●上部の働き脳: 脳は思考、感情、記憶、運動の制御など、多くの重要な機能を担っています。脳の各部位には特定の役割があり、例えば前頭葉は意思決定や計画、頭頂葉は感覚情報の統合、側頭葉は聴覚と記憶、後頭葉は視覚を担当します1。心臓: 心臓は血液を全身に送り出すポンプの役割を果たします。酸素と栄養を含む血液を体中に循環させることで、各組織や臓器が正常に機能するのを助けます2。肺: 肺は呼吸を通じて酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出する役割を担っています。酸素は血液を通じて全身に供給されます。●下部の働き胃と腸: 胃は食物を消化し、腸は栄養素を吸収します。胃は食物を分解し、腸はその栄養素を血液に取り込みます3。腎臓: 腎臓は血液をろ過し、老廃物を尿として排出します。また、体内の水分や電解質のバランスを保つ役割もあります3。骨盤内臓器: 骨盤内には膀胱や生殖器があり、排尿や生殖に関わる重要な機能を持っています。参考図:人間身体2区分説 第2講解説・第4回 了
2024年08月11日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講解説・第3回「健康な生体組織」では、上部と下部に緊密な補完関係があり、特に、下部のプロセスに対する上部のプロセスの方向付けが重要なわけですが、そうした「健康な生体組織」から「病気の生体組織」へと至るにはさまざまな推移があります。ちなみに、上部は、「呼吸活動、感覚・神経活動」という関連し、下部は、「栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝」に関連しています。さて、病気の徴候を見ていく場合、機能的な在り方、つまりエーテル体(*パラケルススにおいてはアルケウス)において見ていくならば、その上部と下部の二元性について語ることができます。しかし、その二元性に関しては、必ずしも両者が対応関係にあるとは限らず、その関係が変則的になっているということに注目する必要があります。この上部が下部に対応して健全な作用をする生体組織から病気の生体組織まで至る推移が見い出せます。パラケルススがアルケウスと呼び、私たちがエーテル体と呼ぶものにおける病気のかすかな兆候を出発点とすると、或いは、皆さんが外部から、つまりこういう事柄については何も知ろうとしない人々に快く思われない、悪く思われないように取り繕うとすると、やはり皆さんは、機能的なもの、動的なもののなかの病気の徴候、いわば病気の最初のかすかな兆しについてまずは語ろうとするでしょう。記:神秘思想家としてのパラケルススにおいては、体と魂を結合する霊的な気体とされる「アルケウス」の提唱で知られ、新プラトン主義(ネオプラトニズム)に影響を受けて全宇宙を一つの生きた全体「有機体世界」と考え、水銀を宇宙の始原物質とした。参考画像:Paracelsus 私たちがこれらを出発点とし、まずエーテル体あるいは機能的なもののなかに最初に予告されるものについて語るなら、二元性についても語ることがでます。ただこの二元性はすでに自らのうちに、対応しないもの、変則的なものを有しているのです。これは次のようにして生じます。健康な生体組織では、食物において作用している力は、すべて上部によって克服されているのですが、下部を完全に制御する、エーテル化しつくすほどには、上部が強くないという場合も生じます。その場合、下部における栄養分の化学的、有機的な力が優勢になります。下部において、つまり栄養分摂取とより広い意味での消化機構において、摂取された栄養分の内的、化学的な、あるいは有機的な力が優勢であると考えてみてください。健康な生体組織においては、私たちが実験室で食物を分析して得られる、食物そのものの中で作用している力、食物に内在している力はすべて、上部によって克服されており、生体組織内部の効力にとっては全く問題にならず、外的な化学、外的な動力学その他のいかなるものも行われず、あらゆるものが完全に克服されています。けれども、下部を実際完全に掌握し、いわば完全に料理しつくし、こういう言い方が可能ならエーテル化しつくす、こう言えばいくらか厳密に語ったことになりますが、そのためには、対応する上部が十分強くないという事態も起こりうるのです。その場合、人間の生体組織においては、通常は外界で起こっていて人間の生体組織のなかでは起こるべくもない、本来人間の生体組織には属さない優勢な経過が現れます。物質的な身体はこうした変則的な在り方を完全にとらえることができないので、そのプロセスは、エーテル体若しくはアルケウスという機能的なもののなかにまずは現れてくることになります。そうした新陳代謝プロセスが独立的な傾向を強める在り方を「ヒステリー」と呼ぶことができます。本来のヒステリー現象というのは、そのような不規則な新陳代謝が頂点にまで達した状態なのです。そのヒステリーのプロセスにおいては、人間の生体組織のなかにあってはならない不規則な新陳代謝が生じているのだといえます。これが、一方の極です。物質的身体は、このような変則性に完全には捉えられないので、こういう経過は、まさに機能的なものと呼ばれうる、エーテル体若しくはアルケウスのなかにまず現れてくるのです。この変則性の特定の形式から取られたと思われる慣用表現を選択するとすれば、ヒステリーという表現を選ばなければなりません。新陳代謝プロセスが多大な独立性を持つようになることを表す用語として、ヒステリーを選択しようと思います。後ほどこの表現が悪くない選択であったことがおわかりになると思います。狭い意味での本来のヒステリー現象は、実際この不規則な新陳代謝が頂点にまで達した状態にほかならないのです。事実、性的な症候にまでいたるヒステリーのプロセスにおいて本質的に存在しているのは、の人間の生体組織なかにあるべきではない、その本質において外的なプロセスであるような不規則な新陳代謝にほかなりません。こういうプロセスに対して上部は、それを克服するにはあまりに弱すぎることがわかります。これが一方の極です。一方の極は「ヒステリー」ですが、もう一方の極は「神経衰弱」です。それは、先ほどとは逆に、上部のプロセスが、上部の組織を酷使しすぎ、そのプロセスが正常に経過しないということによって起こります。そのプロセスはあまりに霊的であり、器官的に知性的すぎるのだといえます。心臓により下部の組織に中継される前に終わってしまうのです。つまり、心臓での滞留を通じて、上部でのプロセスが下部に流れ込むことができなくなっている状態なのです。それは、先の「ヒステリー」の場合の反対、下部のプロセスのネガだといえます。ヒステリーの特徴とともにそのような現象が現れてくるときは、人間の生体組織の下位部分において、人間の外部にある活動が強くなりすぎた状態なのです。しかし、上部のプロセスが正しく経過しないこと、つまり上部のプロセスが上部の組織を酷使しすぎることによっても、同様の不規則な相互作用が起こります。それは反対のプロセス、いわば下部のプロセスのネガであって、上部のプロセスをあまりに激しく使いすぎるのです。このプロセスはいわば、心臓によって下部の組織に中継される前に終わってしまいます。つまりこのプロセスは、あまりに強く霊的であり、あまりにこう表現してよければ器官的に知性的すぎるのです。こうして変則性のもう一方の極、神経衰弱が現れてきます。このように、人間の生体構造の機能的なもの、エーテル体における「ヒステリー」「神経衰弱」という二つの変則性に注目する必要があります。それは、上部で表現され、下部で表現される欠陥であるといえるからです。病気によって欠陥が生じた器官そのものを実際に見て診断することは、単に結果としての現象に過ぎません。それよりも重要なのは、病気の全体像、形状に注目することです。つまり、病気の実像そのものをトータルに見るということなのです。参考までにいうと、こうしたことはシュタイナーがよく言う「ゲーテ的世界観」につながる観察法に結びつくものだといえます。こうした視点を拡大していく必要があるのです。まだ人間の生体構造の機能的なものに潜んでいるこれら二つの変則性に、何にも増して注目せねばならないと申し上げたいのです。それらはいわば上部で表現され、下部で表現される欠陥だからです。そして人間の生体構造におけるこの二元性が何らかの欠陥のもとになっているということが、次第に理解されるようにならなければなりません。つまり、神経衰弱は、上部があまりに激しく上部の器官を使って機能することであり、その結果、本来は上から心臓で中継されて下部で起こるべきことがすでに上部で起こり、上部で行われてしまうので、その活動が、心臓での滞留を通じて下部の流れに入り込むということがなくなってしまうのです。おわかりでしょうか、欠陥を生じた器官の実見よりもはるかに重要であると申し上げたいのは、病気の実像の外的形状(Physiognomie:骨相、人相、形状、外観、外面的特徴)を観察することです。なぜなら欠陥を生じた器官が示すものは単に結果としての現象にすぎないからです。重要なことは、病気の全体像、形状に注目することなのです。この病気の形状は常にある種の仕方で皆さんに、一方かあるいはもう一方への傾向を持つ、つまり神経衰弱的なものか、ヒステリー的なものへの傾向を持つ実像を提示してくれるでしょう。もちろん、こういう表現を通常の言語使用に向けて拡大しなければなりません。 第2講解説・第3回 了哲学・思想ランキング
2024年08月10日
コメント(0)
-
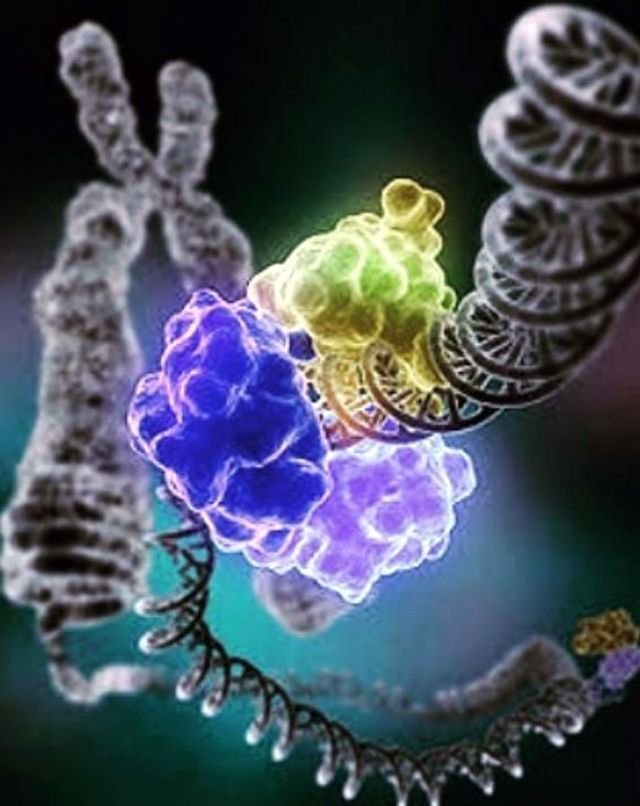
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講解説・第2回 人間における「二元性」を理解するためには、心臓は、人間の上部の活動が下部の活動を知覚、感受することを可能にするための感覚器官であり、下半身で起きていることを知覚しているというように、人間は上部から下部を知覚する二重構造である存在だということを知らなければなりません。しかし、さらにつけ加えなければならないのは、心臓は、上部と下部の均衡を表現している下意識的な知覚器官であり、人間の生体構造の二極間を中継しているということです。生体構造の一方の極は、呼吸活動、感覚・神経活動という関連している全てでありもう一方の極は、栄養分の摂取、栄養分の消化、新陳代謝に関連している全てです。この原理によって、初めて人間の生体構造を理解することが可能になります。解剖学、生理学、生物学をこの原理で探究していくことができるのです。心臓に中継されている上部と下部を区別しない限り、人間を真に理解することはできないといわなければなりません。人間における二元性そのものを理解できるのは、人間は本来、このように上部から下部を知覚する二重構造の存在であるということを知る時のみなのです。しかしここで次のようなことを付け加えておかねばなりません。より広い意味での栄養分の摂取、栄養分の消化を呼吸との同化に至るまで研究する時に、下位部分の活動、つまり人間の本性全体の一方の極が与えられました。呼吸との同化はその時律動的活動と共に行われます。私たちの律動的活動の意味についてはさらにお話すべきことがあるでしょう。しかし呼吸活動と組み合わさり、呼吸活動に所属していると見なければならないものは、感覚・神経活動、すなわち外的な知覚とこの知覚の継続に関わる全てのもの、神経活動による知覚の加工に関わる全てのものです。つまり皆さんが、一面において、呼吸活動、感覚・神経活動という関連している全てのものを思いうかべてくださるなら、いわば人間の生体構造の一方の極が得られるのです。他面において、栄養分の摂取、栄養分の消化、言葉の通常の意味での新陳代謝である全てのものを総合的に見れば、人間の生体構造におけるプロセスのもう一方の極が得られます。心臓は本質的に、その観察できる動きにおいてこの上部と下部の均衡を表現している器官であり、心意的あるいはもっと良い言い方をするなら下意識的な知覚器官であって、人間の生体構造の二極間を中継しているのです。解剖学、生理学、生物学が提供してくれる全てのものを、皆さんはこの原理に向かって研究することができます。そうすれば、この原理によって初めて人間の生体構造の中に光が差し込むことがおわかりになるでしょう。心臓によって中継されているこの上部と下部を区別しない限り、皆さんは人間を理解することはできないでしょう。なぜならこれは、人間の下部の生体活動において起こっている全てのものと、上部の生体活動において起こっているものとの間の根本的な差異だからです。「人間の下部の生体活動と上部の生体活動との差異を下部で起こっていることはすべて上部に反対の対応物としてのネガを持っている」ということによって表現できます。上部に関連するものはすべて、下部に対応物を見出すことはできるのです。「ネガとポジの関係」にあるということができます。ここで重要なのは、上部と下部は物質的に中継されているのではなく、「対応」しているということです。ですから、中継するものとしての物質的な仲介物、つまりコードや導線のような管がそこにあると考えてはなりません。たとえば、上部に関係しているものとして「咳」をとりあげてみるとすると、それに対応する下部のものは「下痢」のなかに見出すことができます。こうした対応関係を正しく見ていくことで、真の人間理解が可能になるのです。この差異を単純に表現しようとすれば、下部で起こっていることはすべて、上部にそのネガ、つまり反対の対応物を有していると言うことができるでしょう。上部に関連するものはすべて、常に下部においてその対応物を見出すことができるというわけです。中継されているわけではなく、対応しているということなのです。下部におけるあるものを、常に正しく上部における別のものと関連づけるということを理解しなくてはなりませんが、物質的な仲介物を見出すことを目指す必要はありません。単純な例として、私たちの咳、これは上部と関係しているという意味で上部に属しているわけですが、下部において咳に対応するものは下痢のなかに見出せます。上部に対応するするものが常に下部において見い出せるのです。こういう対応関係に正しく着目することによってのみ、同様のものは観察していくうちにしばしば登場してくるでしょうが、真の人間理解に到達できるのです。 しかし、このことを抽象的な対応関係としてとらえてはいけません。健康な生体組織では、上部と下部に緊密な補完関係があるのです。上部と活動と下部の活動は、常に相互に対応し、制御し、お互いを方向づけていくようなものでなければなりません。特に重要なのは、下部のプロセスに対する上部のプロセスの方向付けです。しかしながら単にこのような抽象的な対応関係があるだけではなく、健康な生体組織においては同時に上部と下部との緊密な補完関係が成立しているのです。健康な生体組織において成立している補完関係とは、上部のもの、つまり呼吸と関係する活動であれ、神経・感覚機構に関係する活動であれ、何らかの上部の活動は、下部のものに何らかのかたちで抑制せねばならず、下部と完全に調和しなければならないということです。何らかのかたちで下部が優勢になったり、支配的になったりすると、つまり下部がそれに対応する上部の活動にとって強くなりすぎると、あるいは逆に、上部がそれに対応する下部の活動に対して強くなりすぎると、すぐさま、これは後ほど病気のプロセスを正しく理解することにつながっていくでしょうが、生体組織に変則が生じます。上部の活動と下部の活動の関係は常に、両者が何らかのしかたで相互に対応し、互いに制御し、両者がいわばお互いに方向づけられながら経過していくようなものでなければなりません。ここに確固たる方向づけが存在します。この方向づけは人によって異なりますが、下部のプロセス全体に対する上部のプロセスの確固たる方向づけが存在するのです。記:ルドルフ・シュタイナーの哲学では、人間の存在を「上部」と「下部」の二重構造として捉えることが特徴的です。シュタイナーは、上部構造を精神的・霊的な領域、下部構造を物質的・身体的な領域と見なしました。この二重構造により、人間は物質世界と精神世界の両方を知覚し、相互に影響を与え合う存在として理解されます。この考え方は、マルクスの上部構造・下部構造の概念とも対比されることがあります。マルクスは、経済的基盤(下部構造)が法律や政治、文化(上部構造)を決定するとしましたが、シュタイナーはより精神的な視点から人間の存在を捉えています。このような視点は、現代の心理学や哲学にも影響を与えており、人間の多面的な存在を理解するための一つの枠組みとして興味深い課題となります。参考画:人間存在の二重螺旋構造 第2講解説・第2回 了哲学・思想ランキング
2024年08月09日
コメント(0)
-
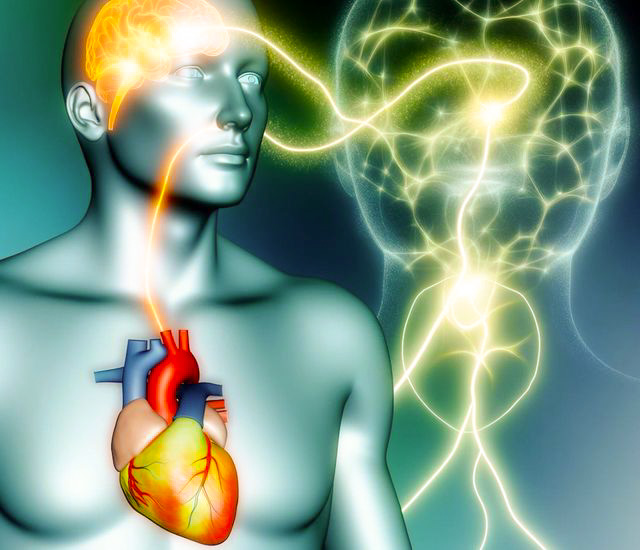
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ●第2講 解説第2講解説・全体概要 心臓論。上部と下部の均衡器官としての心臓。人間の生体組織の二元性。病気の形状。新陳代謝プロセス優勢の現れとしてのヒステリー。感覚プロセス優勢の現れとしての神経衰弱。結核:素質と感染。経過と治療の個々の徴候の意味。第2講・解説第1回 ここから第二講に入ることになります。第一講ではこの講義の前提となる姿勢と視点が語られていましたが、その全体からさらに進んで、まずは「人間の本質において支配的なある種の二元性」に着目しながら、人間の本質へとアプローチしていくことになります。第一講では、動物とは違って、人間では、負荷のかかっている力に、さらに垂直方向の力と結びついて平行四辺形の力が働いていて、それは骨組織だけではなく、筋肉組織についても、重要な視点が提供できるということが述べられていましたが、ここではその視点がさらに、心臓学へと向けられていきます。昨日選択しましたような出発点から先に進んで、「人間の本質において支配的なある種の二元性」に着目することにより、さらに人間の本質へと徐々に迫って行きたいと思います。すでに昨日気づかれたように、私たちは、動物においては未だ負荷のかかっている力を、ある種の垂直方向の力と結びつけて平行四辺形を成す必要があり、筋肉の反応においてもそれに相応した類似が見られます。この人間の骨組織と筋肉組織の研究における考えかたをさらに追究すると、その追究の際に今日経験がすでに与えることのできること全てを助けにすると、おそらくは骨学、筋肉学からすぐさま、医学にとって従来なされていたよりも意味のあることを為すことが可能でしょう。けれどもとりわけ困難なのは、人間の認識を、今日心臓学から出発する時に医学が必要としているものと結びつけることです。私が申し上げたいのは、骨学、筋肉学において初めてその構想を示すものは、心臓学に関して培われてきた見解において根本的に生じてきたということです。通常、心臓は血液を送り出すポンプであるととらえられています。そのポンプであるということを説明するために、その力学的構造が問題にされているのです。しかし、その観点を疑ってみることが必要です。心臓の活動というのは、「原因」ではなく、「結果」だといえるのです。つまり、心臓はポンプとして血液を送り出しているのではないのです。と言いますのも、そもそも一般に人間の心臓について、まずはこれに限定しようと思いますが、どのような見解が持たれているのでしょうか。心臓は血液をさまざまな器官に送り出す一種のポンプであるというふうに見られています。そしてこの「心臓」というポンプ機構を説明すべく、あらゆる興味深い力学的な構造が考案されているのです。さてこの力学的な構造は、胎生学に全く矛盾しているのですが、この力学的心臓論を実際に疑ってみること、少なくとも通常の科学においては制御しないにしても、この心臓論をもう一度制御することに留意されてはおりません。心臓観においてとりわけ考慮せねばならないことは、後日お話することは、最初に観点として示す必要があったことを、少しずつ裏書きしていくかたちになると思いますので、まずは概略を述べましょう。この心臓というものは全くもって、一種の活動している生体組織と呼ばれうるようなものではないということです。なぜなら、心臓の活動は原因ではなく、結果だからです。この、心臓はポンプではないということを理解するために、人間の生体組織での活動において生じる二元性に着目しなければなりません。二元性というのは、呼吸プロセスと消化プロセスとの間の対立であるといえます。栄養分の摂取、消化、血液中の移動ということを見ていくならば、栄養分を取り入れる血液の活動と空気を取り入れる呼吸の活動の間の相互作用にまで、栄養の消化ということを追求することができるのです。呼吸プロセスと消化プロセスの対立においては、何かが均衡しようとします。液体状になった栄養素と呼吸を通じて気体の形で生体組織に取り入れられたものとの間に生じる相互作用がありますが、この相互作用は、お互いに働きかけあう力のなかで生じ、その互いに働きかけ合うものが、心臓において、互いの働きかけを妨げあうのです。この原則が理解できるのは、皆さんが人間の生体組織におけるあらゆる活動の間に生ずる二元性に着目する時のみでしょう。すなわち、栄養分の摂取に関係する活動、さらに栄養分の消化に関わる活動と、直接かあるいは血管を通じての、栄養分の血液中への移動に関わる活動、これらの活動間に生じる二元性です。いわば生体組織内で下から上へと、栄養分を取り入れる血液と空気を取り入れる呼吸との間にまず生じる相互作用まで栄養分消化を追求できるからです。その際観察される経過を正確に見るなら、実際正確に見さえすればよいのですが、呼吸プロセスに中にある全てのものと、最大範囲の消化プロセスの中にあるものとの間に、ある種の対立があることがおわかりになるでしょう。ここでは何かが互いに均衡をとろうとします。謂わば、お互いに渇望し合うものが、相互に満たし合おうとするわけです。もちろんもっと他の表現を選ぶこともできるでしょうが、先に進むにつれて、もっと良く理解できると思います。液体状になった栄養素と、呼吸を通じて気体の形で生体組織に取り入れられたものとの間にまず生じる相互作用があります。この相互作用が厳密に研究されねばなりません。この相互作用は、お互いに働きかけ合う力の中に生じます。そしてこの互いに働きかけ合うもの、これがいわば、心臓においてその互いの働きかけを妨げ合うのです。心臓は、生体組織の下部の活動である栄養分の摂取、消化と生体組織の上部の活動である呼吸という、上下の活動の滞留器官として存在しているのです(*「滞留器官」というのは、原文ではStauorganとなっていて、Stauはせき止めるもの、澱み、渋滞、それを動詞化したstauenはせき止めるということorganは器官という意味です。)。心臓の活動は、液体養分と外部から取り入れられた空気との間の相互作用の「結果」だということなのです。血液をポンプのように送り出す「原因」ではなく、「結果」として考察していく必要があるわけです。ここで少しシュタイナーの論とは別に少し付け加えておきますが、東洋医学などでいわれる「心経・肝経」というのが「心臓」や「肝臓」などの臓器そのものを指しているのではないといわれるのと関連するのではないかと思われます。これについては、今後少し探りながら、その関係を見ていくつもりです。心臓はひとつの滞留器官(Stauorgan)、つまり、私がさらに生体組織の下部の活動と呼びたい栄養分の摂取、消化と、呼吸をその最下部の活動に組み入れたい生体組織の上部の活動、この上下の活動の滞留器官として存在しているのです。ひとつの滞留器官が組み込まれているわけで、その際本質的なことは、心臓の活動は、液体状になった栄養素、すなわち液体養分と、外部から取り入れられた空気との間の相互作用の結果であるということです。心臓に表現されている全て、心臓において観察されうる全ては、まずは力学的な意味で、ひとつの結果として考察されねばならないのです。この観点において、心臓の活動の力学的な基礎について、オーストリアの医師、カール・シュミット博士は1892年の「心臓の動悸と脈拍の曲線」という論文で、心臓をポンプ的なものであるとはとらえているものの、心臓の動きと心臓の動悸という経過全体を水流によって動かされるひとつの流れの結果としてとらえています。唯一有望な発端は、少なくともこの心臓の活動の力学的な基礎に注目することです。この口火を切ったのが、オーストリアの医師であるカール・シュミット博士でした。彼は北部のシュタイアマルクの医師で、”ウィーン医学週報”の1892年15号から17号に彼の「心臓の動悸と脈拍の曲線」が掲載されたのです。この論文にはまだそれほど多くのことが含まれてはいませんが、少なくともここにひとり、扱うべきは通常のポンプとしての心臓ではなく、ひとつの滞留装置としての心臓なのだと、自らの医療実践から気づいた人がいたことは言っておかなくてはなりません。シュミットは心臓の動きと心臓の動悸という経過全体を、水流によって動かされる水撃ポンプとして想定しています。カール・シュミット博士の論述に内在する真理はまさにこの点なのです。心臓の活動であるもの全てを、液体の流れと気体の流れ、ここでは象徴的にこれらを流れと呼びますが、これらの互いに入り込んでいく流れの結果として把握する時初めて、力学的なものに近づくのです。心臓はつまり、ひとつの感覚器官なのだといえます。心臓は、人間の上部の活動が下部の活動を知覚、感受することを可能にするための感覚器官なのです。眼は外界の色彩現象を知覚するように、心臓は、下半身で起きていることを知覚しているのだといえます。結局のところ、心臓とはいったい何なのでしょうか。つまるところ、心臓とはひとつの感覚器官なのです。たとえ私たちが心臓の感覚活動であるものを直接は意識しないとしても、つまり心臓で起きていることが、識閾下の感覚活動に属するものであるとしても、やはり心臓は、いわば人間の上部の活動が、人間の下部の活動を知覚し、感受することを可能にするために存在しているのです。ちょうど皆さんが眼によって外的な色彩現象を知覚するように、皆さんは、もちろん暗い下意識においてではありますが、皆さんの下半身で起きていることを心臓を通じて知覚しているのです。結局のところ心臓とは内的知覚のための感覚器官なのです。心臓はそういうものとみなされねばなりません。参考画像:Heart 第2講解説・第1回 了哲学・思想ランキング
2024年08月08日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」 第二講(本講・解説) 1920年 3月22日 ドルナハ第2講 本講 昨日選択しましたような出発点から先に進んで、人間の本質において支配的なある種の両極性(Polaritaet)に着目することにより、さらに人間の本質へと徐々に迫っていきたいと思います。記:ルドルフ・シュタイナーの思想における「両極性(Polarit?t)」は、人間の本質に関する重要な概念です。彼は、人間の存在が二つの極端な要素の間で成り立っていると考えました。具体的には、物質的な側面と精神的な側面の対立です。物質的な側面:これは、物理的な身体や感覚、物質世界に関連するものです。シュタイナーは、物質的な側面が人間の現実的な生活や経験に深く関わっていると考えました。精神的な側面:これは、魂や精神、超感覚的な認識に関連するものです。シュタイナーは、人間が物質的な世界を超えて、精神的な成長や霊的な発展を追求する能力を持っていると主張しました。この両極性のバランスを取ることが、人間の成長や発展にとって重要であるとシュタイナーは考えました。彼の教育や医療、農業などの実践も、この両極性の調和を目指しています。この考え方は、シュタイナー教育(ヴァルドルフ教育)やアントロポゾフィー医学など、彼の多くの活動に反映されています。 すでに昨日気づかれたように、私たちは、動物においては進化的に未だ負荷のかかっている力を、ある種の垂直方向の力と結びつけて平行四辺形を成す必要があり、筋肉の反応においてもそれに相応した類似が見られます。この人間の骨組織と筋肉組織の研究における考えかたをさらに追求すると、その追求の際に今日経験がすでに与えることのできること全てを助けにすると、おそらくは骨学、筋肉学からすぐさま、医学にとって従来なされていたよりも意味のあることを為すことが可能でしょう。けれどもとりわけ困難なのは、人間の認識を、今日心臓学から出発する時に医学が必要としているものと結びつけることです。私が申し上げたいのは、骨学・筋肉学において初めてその構想を示すものは、心臓学に関して培われてきた見解において根本的に生じてきたということです。と言いますのも、そもそも一般に人間の心臓について、まずはこれに限定しようと思いますが、どのような見解が持たれているのでしょうか。心臓は血液をさまざまな器官に送り出す一種のポンプであるというふうに見られています。そしてこの「心臓」というポンプ機構を説明すべく、あらゆる興味深い力学的な構造が考案されているのです。さてこの力学的な構造は、胎生学に全く矛盾しているのですが、この力学的心臓論を実際に疑ってみること、この心臓論をもう一度点検してみることに留意されてはおりません。少なくとも通常の科学においては点検されていないのです。心臓観においてとりわけ考慮せねばならないことのまずは概略を。後日お話することは、最初に観点として示す必要があったことを、少しずつ裏書きしていくかたちになると思いますので、この心臓というものは全くもって、一種の活動している生体組織と呼ばれうるようなものではないということです。なぜなら、心臓の活動は原因ではなく、結果だからです。この原則が理解できるのは、皆さんが人間の生体組織におけるあらゆる活動の間に生ずる両極性に着目する時のみでしょう。すなわち、栄養分の摂取に関係する活動、さらに栄養分の消化に関わる活動と、直接かあるいは血管を通じての、栄養分の血液中への移動に関わる活動、これらの活動間に生じる両極性です。いわば生体組織内で下から上へと、栄養分を取り入れる血液と空気を取り入れる呼吸との間にまず生じる相互作用まで栄養分消化を辿ることができるからです。その際観察される経過を正確に見るなら、実際正確に見さえすればよいのですが、呼吸プロセスに中にある全てのものと、最大範囲の消化プロセスの中にあるものとの間に、ある種の対立があることがおわかりになるでしょう。ここでは何かが互いに均衡を取ろうとします。いわば、お互いに渇望し合うものが、お互いに満たし合おうとするわけです。もちろんもっと他の表現を選ぶこともできるでしょうが、先に進むにつれて、もっと良く理解できると思います。液体状になった栄養素と、呼吸を通じて気体の形で生体組織に取り入れられたものとの間にまず生じる相互作用があります。この相互作用が厳密に研究されねばなりません。この相互作用は、お互いに働きかけ合う力の中に生じます。そしてこの互いに働きかけ合うもの、これが謂わば、心臓においてその互いの働きかけを妨げ合うのです。心臓はひとつの滞留器官(Stauorgan)、つまり、私がさらに生体組織の下部の活動と呼びたい栄養分の摂取、消化と、呼吸をその最下部の活動に組み入れたい生体組織の上部の活動、この上下の活動の滞留器官として存在しているのです。ひとつの滞留器官が組み込まれているわけで、その際本質的なことは、心臓の活動は、液体状になった栄養素、すなわち液体養分と、外部から取り入れられた空気との間の相互作用の結果であるということです。心臓に表現されている全て、心臓において観察されうる全ては、まずは力学的な意味で、ひとつの結果として考察されねばならないのです。唯一有望な発端は、少なくともこの心臓の活動の力学的な基礎に一度(ひとたび)は注目することです。この口火を切ったのは、オーストリアの医師、カール・シュミット博士(☆)でした。彼は北部のシュタイアマルクの医師で、「ウィーン医学週報」誌の1892年15号から17号に彼の「心臓の動悸と脈拍の曲線」が掲載されたのです。この論文にはまだそれほど多くのことが含まれてはいませんが、少なくともここにひとり、扱うべきは通常のポンプとしての心臓ではなく、ひとつの滞留装置としての心臓なのだと、自らの医療実践から気づいた人がいたことは言っておかなくてはなりません。シュミットは心臓の動きと心臓の動悸という経過全体を、水流によって動かされる水撃ポンプ(Der hydraulische Widder/水撃ポンプ、水圧ラム)として想定しています。カール・シュミット博士の論述に内在する真理はまさにこの点なのです。心臓の活動であるもの全てを、液体の流れと気体の流れ、ここでは象徴的にこれらを流れと呼ぶことができます。これらの互いに入り込んでいく流れの結果として把握する時初めて、力学的なものに近づくのです。結局心臓とはいったい何なのでしょうか。つまるところ、心臓とはひとつの感覚器官なのです。たとえ私たちが心臓の感覚活動であるものを直接は意識しないとしても、つまり心臓で起きていることが、識閾下の感覚活動に属するものであるとしても、やはり心臓は、いわば人間の上部の活動が、人間の下部の活動を知覚し、感受することを可能にするために存在しているのです。ちょうど皆さんが眼によって外的な色彩現象を知覚するように、皆さんは、もちろん暗い下意識においてではありますが、皆さんの下半身で起きていることを心臓を通じて知覚しているのです。結局のところ心臓とは、内的知覚のための感覚器官(Ein Sinnesorgan zum inneren Wahrnehmen)なのです。心臓はそういうものとみなされねばなりません。人間における両極性そのものを理解できるのは、人間は本来、上部から下部を知覚する二重構造の存在であるということを知る時のみなのです。しかしここで次のようなことを付け加えておかねばなりません。より広い意味での栄養分の摂取、栄養分の消化を呼吸との同化に至るまで研究する時に、下位部分の活動、つまり人間の本性全体の一方の極が与えられました。呼吸との同化はその時律動的活動と共に行われます。私たちの律動的活動の意味についてはさらにお話すべきことがあるでしょう。しかし呼吸活動と組み合わさり、呼吸活動に所属していると見なければならないものは、感覚・神経活動、すなわち外的な知覚とこの知覚の継続に関わる全てのもの、神経活動による知覚の加工に関わる全てのものです。つまり皆さんが、一面において、呼吸活動、感覚・神経活動という関連している全てのものを思いうかべてくださるなら、いわば人間の生体構造の一方の極が得られるのです。他面において、栄養分の摂取、栄養分の消化、言葉の通常の意味での新陳代謝である全てのものを総合的に見れば、人間の生体構造におけるプロセスのもう一方の極が得られます。心臓は本質的に、その観察できる動きにおいてこの上部と下部の均衡を表現している器官であり、心意的あるいはもっと良い言い方をするなら下意識的な知覚器官であって、人間の生体構造の二極間を中継しているのです。解剖学、生理学、生物学が提供してくれる全てのものを、皆さんはこの原理に向かって研究することができます。そうすれば、この原理によって初めて人間の生体構造の中に光が差し込むことがおわかりになるでしょう。心臓によって中継されているこの上部と下部を区別しない限り、皆さんは人間を理解することはできないでしょう。なぜならこれは、人間の下部の生体活動において起こっている全てのものと、上部の生体活動において起こっているものとの間の根本的な差異だからです。この差異を単純に表現しようとすれば、下部で起こっていることはすべて、上部にそのネガ、つまり反対の対応物を有していると言うことができるでしょう。上部に関連するものはすべて、常に下部においてその対応物を見出すことができるというわけです。けれども重要なことは、こうした上部と下部は本来物質的に中継されているわけではなく、対応しているということなのです。下部におけるあるものを、常に正しく上部における別のものと関連づけるということを理解しなくてはなりませんが、物質的な仲介物を見出すことを目指す必要はありません。単純な例として、私たちの咳、これは上部と関係しているという意味で上部に属しているわけですが、下部において咳に対応するものは下痢のなかに見出せます。上部に対応するするものが常に下部において見出せるのです。こういう対応関係に正しく着目することによってのみ、同様のものは観察していくうちにしばしば登場してくるでしょう、この対応関係に正しく着目することが真の人間理解に到達できるのです。しかしながら単にこのような抽象的な対応関係があるだけではなく、健康な生体組織においては同時に上部と下部との緊密な補完関係が成立しているのです。健康な生体組織において成立している補完関係とは、上部のもの、つまり呼吸と関係する活動であれ、神経ー感覚機構に関係する活動であれ、何らかの上部の活動は、下部のものを何らかのかたちで抑制せねばならず、下部と完全に調和しなければならない、ということです。何らかのかたちで下部が優勢になったり、支配的になったりすると、つまり下部がそれに対応する上部の活動にとって強くなりすぎると、あるいは逆に、上部がそれに対応する下部の活動に対して強くなりすぎると、すぐさま、これは後ほど病気のプロセスを正しく理解することにつながっていくのですが、生体組織に変則が生じます。上部の活動と下部の活動の関係は常に、両者が何らかのしかたで相互に対応し、互いに制御し、両者がいわばお互いに方向づけられながら経過していくようなものでなければなりません。ここに確固たる方向づけが存在します。この方向づけは人によって異なりますが、下部のプロセス全体に対する上部のプロセスの確固たる方向づけが存在するのです。さて、この上部が下部に対応して健全な作用をする生体組織から病気の生体組織まで至る推移が見出せます。パラケルススがアルケウスと呼び、私たちがエーテル体と呼ぶものにおける病気の前兆を出発点とすると、あるいは、皆さんが外部から、つまりこういう事柄については何も知ろうとしない人々から悪く思われないように取り繕うとしても、やはり皆さんは、機能的なもの、動的なもののなかの病気の前兆、いわば病気の最初のかすかな兆しについてまずは語ろうとするでしょう。私たちがこれらを出発点とし、まずエーテル体あるいは機能的なもののなかに最初に予告されるものについて語るなら、両極性についても語ることがでます。ただこの両極性はすでに自らのうちに、対応しないもの、変則的なものを有しているのです。これは次のようにして生じます。下部において、つまり栄養分摂取とより広い意味での消化機構において、摂取された栄養分の内的、化学的な、あるいは有機的な力が優勢であると考えてみてください。健康な生体組織においては、私たちが実験室で食物を分析して得られる、食物そのものの中で作用している力、食物に内在している力はすべて、上部によって克服されており、生体組織内部の効力にとっては全く問題にならず、外的な化学、外的な動力学その他のいかなるものも行われず、あらゆるものが完全に克服されています。けれども、下部を実際完全に掌握し、いわば完全に料理しつくし、こういう言い方が可能ならエーテル化しつくす。こう言えばいくらか厳密に語ったことになります。そのためには、それに対応する上部が十分強くないという事態も起こりうるのです。その場合、人間の生体組織においては、通常は外界で起こっていて人間の生体組織のなかでは起こるべくもない、本来人間の生体組織には属さない優勢な経過が現れます。物質的身体は、このような変則性に完全には捉えられないので、こういう経過は、まさに機能的なものと呼ばれうる、エーテル体、アルケウスのなかにまず現れてくるのです。この変則性の特定の形式から取られたと思われる慣用表現を選択するとすれば、ヒステリーという表現を選ばなければなりません。新陳代謝プロセスが多大な独立性を持つようになることを表す用語として、ヒステリーを選択しようと思います。後ほどこの表現が悪くない選択であったことがおわかりになると思います。狭い意味での本来のヒステリー現象は、実際この不規則な新陳代謝が頂点にまで達した状態にほかならないのです。事実、性的な症候にまでいたるヒステリーのプロセスにおいて本質的に存在しているのは、人間の生体組織のなかにあるべきではない、その本質において外的なプロセスであるような不規則な新陳代謝にほかなりません。こういうプロセスに対して上部は、それを克服するにはあまりに弱すぎることがわかります。これが一方の極です。ヒステリーの特徴とともにそのような現象が現れてくるときは、人間の生体組織の下位部分において、人間の外部にある活動が強くなりすぎた状態なのです。しかし、上部のプロセスが正しく経過しないこと、つまり上部のプロセスが上部の組織を酷使しすぎることによっても、同様の不規則な相互作用が起こります。それは反対のプロセス、いわば下部のプロセスのネガであって、上部のプロセスをあまりに激しく使いすぎるのです。このプロセスはいわば、心臓によって下部の組織に中継される前に終わってしまいます。つまりこのプロセスは、あまりに強く霊的であり、あまりに、こう表現してよければ、器官的に知性的すぎるのです。こうして変則性のもう一方の極、神経衰弱が現れてきます。まだ人間の生体構造の機能的なものに潜んでいるこれら二つの変則性に、何にも増して注目せねばならないと申し上げたいのです。それらはいわば上部で表現され、下部で表現される欠陥だからです。そして人間の生体構造におけるこの両極性が何らかの欠陥のもとになっているということが、次第に理解されるようにならなければなりません。つまり、神経衰弱は、上部があまりに激しく上部の器官を使って機能することであり、その結果、本来は上から心臓で中継されて下部で起こるべきことがすでに上部で起こり、上部で行われてしまうので、その活動が、心臓での滞留を通じて下部の流れに入り込むということがなくなってしまうのです。おわかりでしょうか、欠陥を生じた器官の実見よりもはるかに重要であると申し上げたいのは、病気の実像の外的形状(Physiognomie:骨相、人相、形状、外観、外面的特徴。また、これらを観察する学問。観相学、骨相学。)を観察することです。なぜなら欠陥を生じた器官が示すものは単に結果としての現象にすぎないからです。重要なことは、病気の全体像、形状に注目することなのです。この病気の観相学は常にある種の仕方で皆さんに、一方かあるいはもう一方への傾向を持つ、つまり神経衰弱的なものか、ヒステリー的なものへの傾向を持つ実像を提示してくれるでしょう。もちろん、こういう表現を通常の言語使用に向けて拡大しなければなりません。さて、この上部と下部の相互作用について満足のいく実像が得られたなら、そこから出発して徐々に次のようなことが認識されるでしょう。すなわち、最初は単に機能的に存在しているもの、つまり私たちが言うところのエーテル的なもののなかで起こっているものが、いわばその力を凝集することで、器官的ー物質的なものをとらえていくこと、そして最初はヒステリーの徴候としてのみ存在しているものが、さまざまな下腹部の疾患のなかにいわばその物質的な形態を取り得ること、また他面において神経衰弱は、喉の病気、頭部の病気のなかに器質的な形態を取り得ること、これらのことについて語ることができるのです。神経衰弱的なものとヒステリー的なものに、当初は機能的なものだったこれらの物質的現象が刻印されるということ、これを研究することこそ未来の医学にとってはなはだ重要なことでしょう。器質的となったヒステリーの結果として、消化過程全体、下腹部のあらゆる経過に不規則が生ずるでしょう。けれども、このようにひとつの組織で起こることは、さらに組織全体にも作用を及ぼします。不規則として生じていることが、さらに組織全体にも作用を及ぼすということを見過ごしてはなりません。さて、その初期に機能的のもののなかに観察できるとしたら端的なヒステリー現象であるようなものが、そもそも機能的には全く現れてこないという場合を考えてみてください。確かにこういうことが起こりうるのです。機能的に表面に現れてくることなく、エーテル体が即座にそれを物質体に押しつけるのです。それは下腹部の器官においてどんなかたちであれ明らかな疾患としては現れてきませんが、内部には存在しています。つまり下腹部の器官には、いわばヒステリーの刻印を押されたものがあるのです。これは物質的なものに自らを押しつけたことにより、ヒステリー現象として心的に前面に現れてくることはないのですが、かと言って、やっかいな病気、物質的な病気であるにはまだ十分強くないのです。けれどもこれは、生体組織全体に働きかけるには十分な強さを持っています。その時、病気と健康の間を漂っていると申しましょうか、そういうものが、下から上へと作用を及ぼし、上部に反作用し、上部にいわば伝染してそのネガのなかに現れる、こういう特殊な現象が起こります。そこが一面的になったり、不規則になったりするとふつうは神経衰弱を引き起こすもとになる領域に、ヒステリーのいわば最初の物質的な結果である状態が作用してそこに現れる、こういう現象が結核への素質をもたらすのです。これは興味深い関係です。結核になりやすい素質は、皆さんにただ今お話した、下部の活動の上部への反作用なのです。このように完全に終わりきらないプロセスが上部に反作用することによって生じる、この全く独特な相互作用が結核への素質をもたらすのです。この人間の生体組織の原ー素質(Ur-Anlage)とも言うべきものにさかのぼらないと、合理的に結核を扱うすべを見出すことはできないでしょう。と申しますのも、寄生生物(*1)が人間の生体組織にはびこるということは、たった今皆さんにお話しました原ー素質の結果生じる現象にすぎないからです。このことは、必要な条件がそろえば結核のような病気は伝染する、という事実に矛盾するものではありません。もちろんそのために必要な条件が整わなければなりません。しかし、この下部の器官活動の優勢は、残念ながら今日の人類の極めて大多数に現れておりますので、結核になりやすい素質は、今日実際恐るべき範囲に広がっているのです。とはいえ、伝染というのはこの領域においてやはり有効な概念です。かなりな程度に結核を病んでいる人は、周囲の人々に作用を及ぼすからです。内部で結核患者が生活しているものにさらされていると、通常は単なる作用にすぎないものが、今度は原因になりうるということがまさに起こってくるのです。私はいつも、ひとつのたとえ、アナロジーによって、この、病気の第一次発生と伝染との間の関係を明確に説明しようとしているのですが、たとえば次のように言えるのです。私が道で、ふだんそれほど親しくつきあっていない友人と出会ったと考えてください。彼は悲しそうにやってきます。彼の悲しみには理由があります。彼の友人が死んでしまったのです。私が彼に出会い、彼が自分の悲しみを私に告げることにより、私も彼と一緒に悲しくなります。彼は直接の原因によって、私は伝染によって悲しくなるわけです。この場合確かなことは、この伝染の条件は彼と私とのお互いの関係のみであるということです。従って、第一次発生と伝染、という概念はどちらもまったく正当であり、とりわけ結核においては極めて正当なものなのです。ただ、合理的な意味においてこれらの概念を真に用いなければなりません。結核療養施設がほかならぬ人工結核孵化場となっていることは少なくありません。結核患者を結核療養施設に詰めこむと、この施設をできる限り何度も繰り返し取り壊して、別の施設に作り替えねばならないでしょう。一定期間ののちには、結核療養施設は結局さらに遠ざけられねばならないでしょう。なぜなら奇妙なことに、結核患者自身がきわめて感染させられやすい素質を有していて、彼らはもっと重い結核患者の近くにいると、そうでなければもっと良くなっているかもしれない病気がおそらくいっそう悪くなってしまうからです。さて、まずはとりあえず、結核の本質を指摘しておくだけのつもりでした。私たちはこの結核を一つの例として、人間の生体組織におけるさまざまなプロセスが、いかにお互い密接に関連し合っていなければならないかを理解します。これらのプロセスは、皆さんにもご想像いただけると思いますが、お互いにポジの像とネガの像が相対しているように対応している、上部組織と下部組織があるのだという事実に常に影響を受けざるをえないのです。ご説明しましたような生体組織の構造が存在することによって結核が準備されるという、いわば極めて特異な現象を手がかりにして、その経過のなかでさらに、そもそも病気の本質をどのように見るべきかを研究することができるのです。結核患者になりかかっている、つまり将来結核が現れてくる兆しがある人にきわめてしばしば見られる徴候を取りあげてみましょう。おそらく彼が咳をするのに気づかれると思います。また、彼が喉や胸の痛み、あるいは四肢の痛みも感じていることに気づかれるでしょう。さらに、ある種の疲労状態、そしてとりわけ盗汗(寝汗)に気づかれるでしょう。これらは何なのでしょうか。これらの徴候を目の前にするとき、これらすべてはいったい何なのでしょうか。私が今挙げたものはすべて、何よりもまず、先ほどお話しました内部の不規則な相互作用の結果として生じているものなのです。けれどもこれは同時に、もっと深い根拠として存在しているものに対する、生体組織の戦いでもあります。おわかりでしょうか、咳をーーまずはこのような単純な事柄を観察し、それからもっと複雑な事柄に移っていきますーー咳を、いかなる場合でも常に克服することは、全く良くないことなのです。生体組織にとっては咳をわざと引き起こすことが必要な場合さえあるのです。人間の下部組織が上部組織によって制御され得ない場合に咳の刺激として現れるものは、さもなければ侵入してくるものを侵入させないための、人間の生体組織の健康な反応なのです。したがって、いかなる場合にも咳を直接止めてしまうことは、場合によっては害になることもあり得るのです。肉体が有害なものを受け入れてしまうからです。その人のその時点での素質ではこうした有害なものに耐えられず、それを取り除こうとするために、彼は咳をするのです。咳の刺激は、生体組織に何らかのものが欠けていて、そのために生体内に侵入してくる可能性のある侵入者を侵入させない必要性があるということを示すものにほかなりません。私たちが挙げた別の徴候もまた、結核の素質があると近づいてくるものに対する、生体組織の防御、戦いなのです。喉の痛み、四肢の痛みはまさしく、生体組織が、上部のプロセスに制御できないような下部のプロセスが起こらないようにしていることを示しているのです。例えば逆に、早めに結核の素質に気づいたら、適度に咳の刺激を引き起こしたり、とりわけ、どういうふうにこれをすることができるかは、明日以降の講演で見ていきます。ある種の食餌療法によって疲労の徴候を引き起こすことさえして、生体組織を支えるのが良いこともあるのです。さらに、例えば痩せるということも、ひとつの防御手段にすぎないのです。なぜなら、痩せない場合におこってくるプロセスは、下部における、上部に制御され得ないものに他ならないかもしれず、その場合生体組織は、制御され得ないものが一時的に存在しないように、痩せることによって自らを守るからなのです。ですから、例えばある人が痩せていく場合、すぐさま太らせるための食餌療法をほどこすのではなく、こういう事柄を個別的に研究することが非常に重要です。痩せるということが、まさにその時点で生体組織に現れてきていることにとって、たいへん良い意味を持っている可能性もあるからです。そして、まだ結核患者ではないけれども、結核にかかる見込みのある人の場合、とりわけ有益なのは盗汗です。なぜなら、盗汗は、睡眠中に実行される生体組織の活動に他ならず、これは本来ならば目覚めている時に、完全な霊的ー心的活動のもとに行われるはずのものであるからです。本来ならば昼間に完全に目覚めた状態で行われるべきことが行われず、夜になって現れてきているのです。これは結果の現象であると同時に防御手段でもあります。生体組織が霊的な活動から解放される一方で、生体組織は盗汗に表される活動を行うのです。もっともこうした事実を完全に評価することができるためには、あらゆる分泌現象は、汗の形成も含めて、普通は魂的、霊的活動がその中に含んでいるものと密接に関係しているということについて、少しばかり知っておかなくてはなりません。構築するプロセス、本来の生命的な構築プロセスというものは、すなわち無意識的な基盤をなすものにすぎません。目覚めた、意識的な魂的ー組織的活動に対応するもの、これはいたるところにおいて、分泌プロセスなのです。私たちの思考というものも、脳の構成的プロセスには対応しておらず、脳の分泌プロセス、分解プロセスに対応しています。盗汗という現象は、通常の生活において本来は霊的ー魂的活動と平行して進行していなければならないはずの分泌プロセスなのです。上部と下部が正しい相関関係にないので、そういう分泌プロセスは、生体組織が霊的ー魂的活動から解放される夜まで持ち越されることになるのです。健全に病んでいる人間の生体組織の成長と生成全体と関係している、あらゆる出来事を注意深く研究すれば、病気の諸症状の間にも相互作用が生じていると言えるところまで導かれることがおわかりになると思います。痩せることはまずもってひとつの症状です。しかしながら、結核の素質との関係において、つまりいくらか活動し始めている結核との関係において、この痩せるということは、諸々の症状の間の相互作用の一部なのです。すなわち、ひとつの組織体、諸々の症状の観念上の組織体とでも言うべきものが成立しているのです。ひとつの症状はある意味でほかの症状に属しているのです。従って、生体組織の他の条件によって何か反応のようなものが起こるとき、結核の例にとどまりますが、生体組織自体にこの反応を引き起こす力がない場合は、これを助けて反応を起こしてやること、まさにひとつの病気に別の病気が続くようにしてやることは、全く理にかなったことになるのです。古代の医師たちはこのことを、医師のためのいわば意味深い教育法則として語ってきました。医師であることによって危険なのは、単に病気を取り除くことができねばならないというだけではなく、病気を引き起こすこともできなければならないということだ、と古代の医師たちは語りました。つまり医師は病気を癒すことができるのと全く同じ程度に、病気を引き起こすことができる、というわけです。隔世遺伝的な霊視力によってこういう関連についてもっと多くのことを知っていた古代人たちは、医師のなかに、彼が悪意を持てば、人々を健康にするばかりでなく病気にすることもできる人物を同時に見ていたのです。けれどもこのことは、他の発病状態との正しい関係をもたらすために、何らかの発病状態を引き起こさなければならない必然性と関連しています。とはいえ、これらは病気の状態であることは確かです。咳、喉の痛み、胸の痛み、痩せる徴候、疲労の徴候、盗汗、これらはすべて、病気の症状には違いないのですから。これらの症状は引き起こされねばならないとはいえ、やはり病気の症状であることには間違いないのです。このことから、半分治療した時すなわちこれらの症状を引き起こした時点で、病人をその運命に委ねてしまうことはできず、この時こそ治療プロセスの第二の部分が現れてこなければならない、ということがおのずと容易にご理解いただけると思います。その時は、単にこれらの反応、つまり病気を防ぐために引き起こしたものが存在するように配慮されねばならないだけではなく、今度はこの反応を癒し、生体組織全体を再び正しい道に導くものが生じてこなければならないのです。したがって例えば、結核の素質に対しての自然なあるいは場合によっては人為的に引き起こされた防御として、咳の刺激が引き起こされたとき、また喉の痛みが起こったりあるいは引き起こされたときには、その際常にいくぶん詰まった状態つまり便秘状態を呈しているであろう消化プロセスが秩序正しいものになるように配慮されねばなりません。何らかの方法で気づかれることでしょうが、この消化プロセスが、ひとつの防御プロセス、一種の下痢に移行させられねばならないのです。常に、咳の徴候や喉の痛みその他に続いてこのような下痢が起こることが必要なのです。まさにこのことが、上部に現れていることをそれ自体として観察してはならず、たとえ物質的な媒介物はなく、対応関係があるだけだとしても、上部に現れていることの治療を、下部における経過を通じて探究せねばならないことが多々あるということを示唆しているのです。このことは何にもまして考慮されてしかるべきなのです。疲労の徴候、私はこれを単に主観的な疲労徴候と呼ばずに、本来常に新陳代謝の優勢に基づいている、全く組織的に引き起こされた疲労徴候と呼びたいのですが、新陳代謝が上部によって制御されない時に強く現れるような疲労徴候は、結核の場合これが実際に引き起こされねばならないので、その後必要な時点で克服されねばなりません。つまり、それに応じた食餌療法によって、こうした食餌療法の詳細についてはさらにお話すべきことがあるでしょうが、消化が優勢になるように、すなわちその人の通常の状態よりも消化活動が活発になるように、いわばもっと簡単に消費されてしまうものが、消化プロセスを通じて消費されるように配慮することで、こういう疲労徴候は克服されねばならないのです。痩せることも、今度は一種の脂肪形成,つまり器官や器官組織のなかへの蓄積を起こさせるような食餌療法によって、後から克服すべきでしょう。盗汗もまず最初に引き起こされた後に、きわめて知的な活動、つまり努めて熟考するなどして実際に汗を出すような活動を指示することを試みることによって、後から克服されねばなりません。そうして再び健康な発汗が促されるのです。まず最初に心臓の活動を正しく把握することにより、人間において上部と下部がいかに対応しているかを理解するなら、さらに、神経衰弱やヒステリーのような、機能的なもの、エーテル的なもののなかに病気の最初の発生、いわばかすかな兆しが見られることを理解するなら、器官的なもの、物質的なものにそのとき刻印されているものを理解することへも進んで行けるのだということがおわかりになると思います。こうして相関しあっている病気の像の外観を研究することにより、最初に引き起こすものも含めて、いわば病気の経過を、場合によって病状を強めたり弱めたりさえしてある方向に導き、時期が到来すれば、プロセス全体を再び健康にすることができるでしょう。言うまでもなく、こうして少しばかり特徴をお話しました処置にとって、最大の障壁はまず第一に状況、社会的な事情です。従って医学とはまったくもって社会的な問題でもあるのです。他面において、最も強力な障壁を築いているのは患者自身であるともいえます。患者は当然のことながら、何はさておき、何かを、彼らが言うように「取り除いて」ほしいと要求するからです。しかしながら、彼らが持っているものをそんなに直接取り除いてしまうと、すでにそうなっているよりももっと病気を悪くしてしまうという事態が容易に起こりうるのです。患者を今の状態よりももっと悪くしてしまうことも考慮しておかなくてはなりませんが、彼らを再び健康にすることができる状態になるまでは待たなくてはならないのです。けれども、大多数の皆さんにご同意いただけるでしょうが、その時にはたいてい患者さんは逃げ出してしまっているわけです。そもそも治療というもの全体に正しい価値を与えようとすれば、医師は後療法をも完全に掌握していなければならないのですが、これこそ、健康な人間及び病気の人間の正しい観察の結果帰着することなのです。こういうことこそ、まさに公然と目指されねばならないのです。現代のような権威信仰の時代にあっては、このような動きが導入されさえすれば、その必要性を指摘することが困難であったりしてはならないはずです。しかしながら、言うまでもなく、皆さんの前でこのようなことを申しあげるのをお許しいただきたいのですが、病気をほんとうにその支脈の末端まで追求することを適切であるとみなさず、単に何かを取り除いたことで多かれ少なかれ満足しているのは、いつも患者や社会状況であるのみならず、医師のかたがたであることもしばしばあるのです。とはいえ、このように人間の生体組織のなかでの心臓の位置づけを正しく追求することが、私たちを病気の本質へと徐々に導いていくということはご理解いただけると思います。ただ、皆さんに注目していただかねばならないのは、下部の諸々の組織的活動は単に外的な化学的活動であるものをなるほどある意味で克服してはいるけれども、それと全く反対の上部の活動にやはり何らかのしかたで類似しているというとき、これら(上・下)の間に成立している徹底的な差異なのです。人間の生体組織におけるこの二元性(Dualismus)に満足に足る定義を与えることは非常に困難です。私たちの言語は、物質的、器官的なものに対立するものを暗示すための手段をほとんど有していないからです。けれども、まず次のようなアナロジーによって、こういう事柄について語るべきことはもっとたくさんあるでしょうけれど、本来この下部プロセスと上部プロセスの間の二元性がどんなものなのかを明確にするなら、もしかすると良くご理解いただけるかもしれません。もしかすると皆さんのどなたかの何らかの先入見にぶつかるかもしれませんが、私はあえてそういたします。皆さんが何らかの物質の特性を考えるとき、つまりどういうかたちであれ私たちの前にある物質が効力を生じる際の特性を考えるとき、まず第一に、消化の際に起こっているように生体組織によって克服されて人間の下部の活動に取り入れられるものが考えられます。さて、こう言ってよろしければ、ここでホメオパシー(同種療法)(*2)を行うことができます。その物質の集合性、連関性を止揚することができるのです。このことは、その物質を何らかのやりかたで希釈するとき、いわゆるホメオパシー的極小量を用いるときに生じます。よろしいでしょうか、このとき、現代の私たちの自然科学全般においてまともに観察されていないことが明らかになるのですが、人々はすべてを抽象的に観察することに慣れっこになってしまっています。ですから、ここにひとつの光源があるとすると、彼らは、光はあらゆる方面へ広がっていくと言い、これがあらゆる方面へ広がっていって無限のかなたで消滅すると考えるのです。彼らは太陽についてもそう考えます。けれどもこれは正しくありません。このような活動はいかなる無限のかなたでも消え去ることはなく、ある範囲の限界まで達するのみで、その後弾力性をもっているようにはね返ってきます。たとえその性質はしばしば往路の性質とは異なっているにしても、はね返ってくるのです(図)。自然のなかにはリズミカルな経過があるのみであって、無限のかなたに通じる経過は存在しないのです。リズミカルに再びそれ自身にはね返ってくるもののみが存在しているのです。これは単に量的な拡散にのみあてはまることではなく、質的な拡散にもあてはまることなのです。皆さんがある物質を分割し始めるとき、その物質は最初の出発点において特性を持っています。これらの特性は、無限に減っていくのではなく、ある点にいたると、それははね返ってきて、以前のそれ自身の特性とは反対の特性になるのです。私たちの生体の上部組織と下部組織の間の対比もこの内的なリズムに基づいています。私たちの上部組織はホメオパシー的なものです。それはある意味で通常の消化プロセスの正反対のもので、その反対物、ネガを形成するものです。したがって、ホメオパシーの薬剤師は希釈(Verduennung)をおこなうことで、普通は人間の下部の生体組織に関係していてこれと関係のある諸特性を、今度は人間の上部の組織に関係のある特性へと、実際に導いているのだと言うことができるでしょう。これはたいへん興味深い内的な連関です。この連関については明日以降さらにお話していきましょう。□編註☆カール・シュミット[Dr.Karl Schmidt] 「心臓の動悸と脈拍の曲線について」1891年10月26日グラーツで開催されたシュタイアマルク医師協会の月例会における講演。「ウィーン医学週報」1892年15号から17号に掲載。□訳註*1 寄生生物:原文ではDie Parasiten(Der Parasit:寄生動物、寄生植物の総称)の複数形で、ここでは広い意味での「細菌」の意味あいも含まれていると思われます。 ちなみに、ロベルト・コッホ(Heinrich Hermann Robert Koch/1843年-1910年)による結核菌の発見は1882年で、同時に発表された論文により、この菌が結核の第一次的要因になるという説が認められました。20世紀になると、ストレプトマイシンの効果が1944年に発表され、同時期にパラアミノサリチル酸、その後イソニアジドの抗結核性も実証されるなど、新薬の発見が相次ぎました。なお、肺結核の死亡率は17世紀半ばに非常に高くなり、その後徐々に低下し、再びピークを迎えたのは、18世紀の終わりから19世紀前半ということで、この講演の時期(1920年)と一致しています。また、興味深いことに、イギリス、フランス、ドイツなどでは、すでにストレプトマイシンの投与が始まる以前から死亡率が下がり始めていたそうです。けれども、日本で肺結核による死亡率が激減した1950年代は、ちょうどストレプトマイシンと新しい肺外科の技術が導入された時期と一致するそうです。(訳者) 参考:山崎幹夫 「薬の話」中公新書□訳註*2 ホメオパシー[Homoeopathie] 同種(類似)療法。健康体に与えるとその病気に似た症状を起こす物質を、ごく低濃度に希釈し、それを薬品としてその病気にかかった患者に投与して治療する方法。ハーネマン(第1講 編註*12参照)によって創始された。アロパシー[Allopathie](逆症療法)はこれとは逆のやりかた。シュタイナーはホメオパシーとアロパシーについて、さらに第五講、第十一講で述べています。第十一講の訳註*2も参照。参考画:Samuel Hahneman 「精神科学と医学」第2講 本講 了哲学・思想ランキング
2024年08月07日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」(GA312) 第一講(本文・解説付) 8回第1講・第8回 骨組織から筋肉組織へと目を転じると、通常の化学的作用という点では、静止している筋肉の場合、アルカリ反応に「似た」反応を示し、それに対して活動している筋肉はわずかに酸性反応を示します。筋肉は新陳代謝によって人間の摂取したものからできているのですが、それは地上的な物質における諸力の成果だということができます。しかし、それが活動しはじめるとともに、そうした新陳代謝の支配下から脱して別の変化が現れるようになります。この変化は、人間の骨の形成に作用している力といえるものであって、それが地上的な力との合力を形成しているのだといえます。地上的な化学のなかに、地上的でない化学的作用が働いているのです。さて今ご説明したことと関連して今度は次のようなことをお話したいと思います。骨組織から筋肉組織に移ると、私たちは筋肉の本質におけるこの重要な差異を見出すわけですが、つまり、通常の化学的作用に留意するなら、静止している筋肉はアルカリ性の反応を示すということです。ただし、静止している筋肉の場合、アルカリ反応はその他の場合ほど絶対的に明確には現れないので、アルカリ性に似たと言えるだけなのですが。活動している筋肉の場合もやはりあまり明確でない酸性反応が働いています。さて考えてみてください、当然のことながら、筋肉はまずもって新陳代謝に応じて、人間が摂取したものから構成されています。つまり筋肉はいわば、地上的な物質の中に存在している諸力の成果なのです。けれども人間が活動し始めるとともに、筋肉が単に通常の新陳代謝の支配下にあることによって自らのうちに有しているものが、次第に明確に克服されます。筋肉に変化が現れるのです。この変化はつまるところ、通常の新陳代謝に応じた変化に対して、人間の骨の形成に作用している力と比較する以外にないものです。人間の場合こういう力が外から取り入れたものを越えていくように、またこういう力が地上的に貫かれて、それらと合一して合力を形成するように、筋肉のなかで新陳代謝における作用として現れるものとならんで、地上的な化学の中に化学的に作用するものにも目を向けなければならないのです。ここでは、もはや私たちが地上的なものの中には見い出せない何かが、地上的な力学、動力学の中へと作用を及ぼしていると言えるかもしれません。新陳代謝の場合、地上的な化学の中に、地上的でない化学であるもの、地上的な化学の影響下においてのみ出現可能な作用とは別の作用をもたらすものが作用を及ぼしているのです。人間の本質を見出そうとするならば、形態観察という側面と質的観察という側面の双方を出発点とする必要があります。私たちは、医学において、地上的な薬物のみを取り入れてきましたが、人間においては、地上的でないプロセスが作用しています。ですから、病んだ生体組織と物質的な地上環境との相互作用において、病気の状態から健康な状態へと導く相互作用をどうやって呼び起こすかという問いに対しては、地上的な薬物だけでは地上的でないプロセスに対して有効なものであるとはいえません。私たちが本来人間の本質にあるものを見出そうとするならば、このような、一面においては形態観察であり、他面においては質の観察であるような観察を出発点とせねばならないでしょう。ここで再び、失われてしまったものへの帰路が、病気の本質を単に形式的に定義することにとどまりたくなければ、是非とも必要なものへの帰路が開けてくることでしょう。実際形式的な定義のみでは実践においてあまり多くをてがけられないのです。なぜなら、考えてもみてください、そこには非常に重大な問題が発生するのです。私たちは根本的に、私たちの環境から、地上的な薬物のみを取り入れてきました。その薬で変化をきたした人間の生体組織に働きかけることができるのです。けれども人間においては、地上的でないプロセス、あるいは少なくともそのプロセスを地上的でないプロセスにする力が作用しています。従って次のような問いが出てくるのです。つまり、私たちが病んだ生体組織とその物質的な地球環境との間に相互関係として引き起こすもののなかに、いかにして、病気の状態から健康な状態へと導く相互作用を呼び起こすことができるのかという問いです。私たちが如何にしてこのような相互関係を引き起こすことができ得るのか、その結果、この相互関係を通じて実際に、人間の生体組織の中で活動している力に影響を及ぼすことができ得るのかということです。この力は、たとえそのプロセスが食餌療法のための指示などであったとしても、私たちがそこから薬物を選べるようなプロセスが現れているもののなかには現れてこない力なのです。 人間と動物の差に注目しなければなりません。人間には、地上的でない力が働いています。ですから、動物も植物も病気になるのだから、動物と人間を区別すべきでないという議論は取り除かれねばならないのです。動物実験から人間の治療のために何も得られないというのではないものの、人間と動物の違いに目をむけるならば、そこから得るものは少ないと言わざるをえません。その差異を明確に認識しなければなりません。医学の発達にとっての動物実験の意味も、そこで問い直されることになります。最終的に特定の治療へと導かれ得るものが、人間の本質を正しく把握することといかに密接に関わり合っているか、おわかりだと思います。そして私たちをこの問いの解決へと上昇させることができるはずの、まさに最初の要素を、私は人間と動物の差異から全く意識的に取って参りました。勿論、動物だって病気になる、場合によっては植物も病気になるではないか。最近は鉱物の病気についてすら議論されていますので、だから病気になることについては動物と人間を区別すべきではないという非難は非常に容易なのではありますが。この非難は後で取り除かれるでしょう。しかし人間の医学において前進する目的で動物の本性を単に調べることからは、長い間には医師たちは得るところが少ないということがわかってくると、この課題の差異が認められるでしょう。人間の治療のために動物実験から達成できることが若干あるのは全く確かなのですが、なぜそうなのかはいずれ判明するでしょうが、それはやはり、動物と人間の組織の間には極めて細部にいたるまでどんな根本的な差異があるかについて、徹底して明確に認識されている場合のみなのです。従って問題なのは、医学の発達にとっての動物実験の意味をそれに応じた方法でますます明確にしていくことです。 第1講・第8回了第1講・第9回 地上を越えた力に関することは、人間の人格が重要になります。医学を未来に向けて発展させていくためには、医学の本質に関して直観的な能力を磨いていくことが必要なのです。病気や健康に関する個々の生体組織の本質を観ていくためには、その形態観察から推論できるような直観が求められるということです。さらに引き続き皆さんに注意していただきたいのは、このような地上を越えた力を指摘せねばならない時は、いわゆる客観的法則、客観的自然法則を常に指摘できる時よりも遥かに、人間の人格が要求されることが多いということです。むろん重要となるのは、医学の本質をずっと直観的なものへと調整すること、何らかの関係で病気であったり、健康であったりする人間の生体組織、個々の生体組織の本質を、形態の現象から推論する才能によって、形態観察のための直観が鍛えられているということが、医学の発展においてまた未来に向けて、よりいっそう大きな役割を果たさねばならないということなのです。この第一講では、通常の化学や比較解剖学では得られないような精神科学的事実の観察によって到達できるものに目を向けることが目的です。けれど、現状の物質的な薬に霊的な薬を置き換えることが重要なのではなくて、物質的な薬による治療の可能性を霊的に認識し、精神科学的な在り方による治療の可能性を広げていくということなのです。こういう事柄は、先に申しましたように、一種の前置き、方向付けのための前置きとしてのみ役立てようと思います。と申しますのも、きょうはここで、化学や通常の比較解剖学によっては到達できないもの、精神科学的な事実の観察に移行する時にのみ到達できるものに、医学は再び目を向けなければならないということを示すことが問題だったからです。このことに関して今日人々はまだ多くの錯誤に身を委ねています。医学の霊化のために物質的な薬に霊的な薬を置き換えることが重要であるはずだと考える人もいます。けれども、特定の領域で正当なことは、全体としては正しくないのです。なぜなら、とりわけ重要なことは、物質的な薬剤にどのような治療価値を置き得るのかを霊的なやり方で認識すること、すなわち物質的な薬剤の評価に精神科学を適用することだからです。つまりこれが、私が先に挙げた、人間と他の世界との関係を認識することによる治療の可能性を探すことという部分の課題となるでしょう。ここで重要なのは、個々の病気に関して、しっかりした治療プロセスを基礎づけるために、どちらも自然のプロセスである正常なプロセスと異常なプロセスとの関連について明確な見解を得るということです。 私は、これから特殊な治療プロセスについて語るべきことができるだけ基礎のしっかりしたものであるように、また個別の病気において、これもひとつの自然のプロセスにちがいないいわゆる異常なプロセスと、これもまた自然のプロセスに他ならないいわゆる正常なプロセスとの関連についてひとつの見解が得られることを、できるだけ全てが目指すようにしたいと思います。病気のプロセスもやはり自然のプロセスであるということと、そもそもどうやって折り合っていくのかとう問い、この根本的な問いが生じてくる時は、いつでも、これはいわばちょっとした付け足しとして触れておきたいことなのですが、人はいつもできる限り早くこの問題から逃げ出そうとするのです。 19世紀の前半、トロクスラーは、病気の正常さということを指摘していました。つまり、別の世界では正当な法則が、私たちの世界では病気を引き起こすかもしれないということ、その別の世界を認知しなければならない方向へと向かわねばならないことです。彼は、不明確にせよ、その点において、医学という学問の健全化を目指そうとしたのです。例えば、トロクスラーはベルンで教鞭をとっていましたが、興味深いことにすでに19世紀の前半に非常に熱心に次のようなことを指摘していました。すなわち、いわば病気の正常さということが探究されねばならないこと、それによって、ある方向へ、つまり私たちの世界と結びついていて、正当でない穴を通ってくるように私たちの世界へすべり込んでくるある種の世界を、結局は認知することに行き着くような方向へと導かれること、そしてそのことによって病気の現象に関して何らかのものに到達しうることを指摘していたのです。考えてもみてください。ここではざっと図式的に説明するだけにしておきますが、何らかの世界、つまりその世界の法則からすれば全く正当な事柄が、私たちの世界では病気の現象を引き起こすようなそういう世界が背後に存在するとしたら、その世界が私たちの世界に入り込んでくるある種の穴を通じて、別の世界においては全く正当な法則が、私たちのところでは災いを引き起こすことも可能なのです。トロクスラーはこういうことを目指して努力していました。たとえ彼の述べたことが、少なからぬ点において曖昧で不明確であったにせよ、彼が医学において、まさに医学という学問の健全化を目指す道の途上にあったことは注目に値します。しかしながら、トロクスラーのそうした学問的意義はまったく注目されませんでした。事典にさえ、そのことが記載されていないのです。私はかつて、かのトロクスラーがベルンで教えていた頃、ある友人と、トロクスラーが同僚たちの中でどのように見られていたか、また彼の提案によって何がなされたかを調べてみたことがありました。しかし、大学の歴史について多くの事柄が記されている事典の中でトロクスラーに関して発見できたことはただ、彼は大学で何度も騒動を巻き起こしたということだけでした。記載されていたのはそのことだけで、彼の学問上の意義については何ら特別なことは発見できなかったのです。記:シュタイナーは、この第一講の最後に、あらためて、今回の講義を受けている医学者に対して、具体的な質問事項及び希望を提出するように言っているのですが、それは、この講義をより具体的で実りの多いものにしたいという願いであり、医学に精神科学的認識をより具体的な形で注ぎ込もうとする熱意だといえます。<註釈(原注より)> ・トロクスラー(Iganz Paul Troxler/1780-1866)、スイスの医師、政治家、哲学者である。著作「人間の本質へのまなざし」アアラウ、1812「人間の認識の自然科学または形而上学」アアラウ、1828「哲学に関する講義、人生に関する内容・教育の限界・目的及び応用に関する講義」ベルン、1835参考画:Iganz Paul Troxler (第1講・9回了) さて、先に述べましたように、きょうはこういうことだけを指摘しておくつべることができるように、どうか明日か明後日までに皆さん全員が希望を書いて提出してくださるようお願いいたします。そうして初めて、皆さんの希望から、この連続講演に必要な形式を与えることができるのです。それが最も良いやりかただと思います。どうか実り多いものにしてくださるようお願いいたします。 (第1講・終了)哲学・思想ランキング
2024年08月06日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」(GA312) 第一講(本文・解説付) 第7回第1講・第7回 この講演内容は、通常の書物などでは述べられていないものではあるけれども、其の前提とされているのは、その逆に通常見い出せるものであるということができます。人間の骨格とゴリラの骨格を比較してみると、ゴリラの下顎組織全体が特に大きく発達していて、その下顎組織は頭骨全体のなかで負荷をかけられ、その骨格全体が前に突き出しているということです。そうしたことから、人間に比べてゴリラは、そうした下顎の負荷に逆らっては直立し難い姿勢になっているということがわかります。参照図は、ゴリラの頭骨と人間の頭骨を横から見た形で比較したものです。ゴリラの場合は、下顎全体が前に迫り出しています。ご理解いただけるでしょうが、私はこのたびの回数のかぎられた講演において、主として皆さんが通常書物や講演では見出せないことをお話しております。けれども、その前提としておりますのはまさに通常見出せるものなのです。皆さんにも通常お馴染みであるような理論を私が並べ立てることはさして価値があるとも思えません。ですからここで、人間の骨格と、いわゆる高等なサルであるゴリラの骨格を思い浮かべていただいて見てとれることを単純に比較すれば明らかになることを参照していただきます。両者の骨格を純粋に外的に比較してみると、本質的なこととして、ゴリラの場合にはもっぱら下顎組織全体が特に大きく発達していることに気づかれるでしょう。この下顎組織はいわば頭骨全体の中で負荷としてあり、それでゴリラの頭部をその大きな下顎とともに見ると、この下顎組織は何らかの方法で負荷をかけられており、骨格全体が前に突き出ている、そしてゴリラは、言うなれば、とりわけ下顎で働いているこの負荷に逆らって、幾分苦労して直立していると感じられます。手の部分を伴う前膊部、つまり肩口から手口までの腕のうちの、肘から手口までの腕の部分の骨格に関しては、人間とゴリラは同じような負荷システムを持っいて、両者ともに重力的に作用しますが、ゴリラのそれは人間のそれに対してかさばっているということができます。このことは、足および下肢の骨格に関しても見出すことができます。ここにも、ある特定の方向に圧力をかける負荷的なものがあるといえます。ここにも「図」がありますが、これは少し説明しにくいものですが、簡単にご説明しますと、ゴリラの下顎が人間のそれに比べて、下向きのベクトルの働きを受けているというものです。人間の場合は、上向きの力と水平方向の力として働くものが、ゴリラの場合は、上向きの力と水平よりは下向きの力として働いているということです。つまり、ゴリラの場合、顎を突き出して前向きの姿勢で手を下にだらんと垂らし、足もまっすぐではなく、前傾姿勢になっているということです。手の部分を伴う前膊部の骨格に目を向けると、ゴリラと同じ負荷システムを人間の骨格にも見出すことができます。これらは重力的に作用しますが、ゴリラの場合はすべてがかさばっているのに対し、人間の場合はすべてが精密繊細に分化されています。人間の場合は量が目立たないのです。下顎組織と、指の組織をともなう前膊組織というまさにこの部分において、人間においては量的なものが目立たず、ゴリラの場合には量的なものが目立つのです。こういう関係に対して観察眼を鋭くした人は、足および下肢の骨格にも同様のものを追求できます。ここにも、ある特定の方向に圧力をかけるいわば負荷的なものがあるのです。これらの力、これらは下顎組織、腕の組織、脚および足の組織に見出せるのですが、これをこういう線によって図式的に描いてみたいと思います。ゴリラに比べて、人間の場合、下顎が後退していて、腕や指の骨格が精密に形成されているということは、「上昇しようとする力」を持っているということができます。ゴリラでは、負荷によって下降する力が優勢なのに対して、人間では、「上昇しようとする力」があるということなのです。ここで「一種の力の平行四辺形」ということが言われているのは、下降する力のベクトルに対して、上昇しようとする力のベクトルが合わさって、いわば「合力」として、平行四辺形で描かれる力となるということです。「図」に関していえば、その下降する力のベクトルと上昇しようとする力のベクトルが合力として平行四辺形を形成しているということが表現されています。ゴリラの骨格と人間の骨格を純粋に観察することから差異として現れてくること、すなわち、人間においては下顎は後退していてもはや負荷がかかっておらず、腕および指の骨格は精密に形成されていることに着目していただければ、人間の場合は至る所で上昇しようとする力がこれらの力に対抗していると言わざるをえないでしょう。人間においては一種の力の平行四辺形から形成されるものを設定しなければならないのです。これはこの上に向かう力から生じるもので、この力をゴリラは外的にのみ習得していて、それはゴリラが直立し、直立しようとする努力のなかに見出せます。こうして次のような線で描かれた平行四辺形が得られます。今日では、高等動物の骨や筋肉を比較するということはするものの、こうした形態の変化ということについては、あまり注意を払いません。しかし、まさに本質的なことというのは、そうした形態の変化なのです。ゴリラの場合のような形態の形成する力に逆らって、上昇する力として作用する力があるということに注目しなければならないということです。きわめて奇妙なことは、今日私たちは通常、高等動物の骨あるいは筋肉を人間のそれと比較することに限定していて、その際、これらの形態の変化には重点を置かないということです。本質的で重要なことは、こういう形態の変化を見るということの中に求められねばなりません。ごらんのように、ゴリラにおいてその形態を形成している力、この力に逆らって作用するような力が存在せねばならないからです。実際こういう力が存在せねばならず、こういう力が働いていなければならないのです。 こうした種類の力に注目することで、ヒポクラテス的な体系によって切り捨てられてきたものを再び見出すことが可能になります。力の平行四辺形ということに注目するならば、地球外的な力を起源とする力の合力に注目しなければならないのです。人間の直立二足歩行をもたらしたのは、そうした地球外的な力の作用であり、しかもそうした直立姿勢をもたらしただけではなく、その作用する力は同時に形成力でもあるのだといえます。私たちがこういう力を探すとすれば、古代の医学がヒポクラテス的な体系によって濾過された際に捨て去られたものを再び見出すことになるでしょう。さらに、こういう力は地上的自然の力の平行四辺形の中にあって、力の平行四辺形の中で地上的な力と合成され、その結果今や地上的な力を起源とせず、地上を越えた、地球外的な力を起源とする合力が成立することがわかるでしょう。こういう力を私たちは地上的なものの外に求めなければなりません。私たちは人間に直立姿勢をもたらした牽引力を求めなければなりませんが、この牽引力は単に、高等動物にも時おり見られるような直立姿勢をもたらすのみではなく、直立姿勢の中で作用している力が同時に形成力でもあるようなありかたで直立姿勢をもたらすものなのです。 サルの場合も直立歩行しないわけではありませんが、人間の場合は、下降する力に逆らって働く力が強く、地球外的な起源をもつ力の方向を強くもっているというところに、その相違点があるのです。人間の骨格構造におけるダイナミズムということを見ていくならば、そこには、そうした地球外的な力が働き、そこに、下降する力との間に、合力としての平行四辺形がでてくるということが重要です。サルは直立歩行しますが、量的にそれに逆らって働く力を有しているかどうか、あるいは人間はその骨組織の形成が地上的でない起源を持つ力の方向に作用しているかどうか、これが相違点なのです。人間の骨格の形を正しく見れば、個々の骨を記述して動物の骨と比較することに限定されることはありません。人間の骨格構造におけるダイナミズムを追求すれば、地球の他の領域にこれを見出すことはできない、私たちがここで出会う力は、他の力と合わせて力の平行四辺形を作らねばならないそういう力なのだ、と言うことができるのです。動物から人間へと向かうそうした飛躍を見ていくことで、病気の本質に関する考察が可能になります。この講義が進むうちに、そうしたことが数多く発見されていくことになります。私たちが単に人間の外部にある力に注目しているだけでは発見できない合力が成立しているのです。ですから動物から人間へのこの飛躍を一度きちんと追求してみることが重要となるでしょう。そうすれば単に人間のみならず動物の場合にも、病気の本質の起源を見出すことができるでしょう。私は皆さんにこういう要素を少しずつしか指摘できませんが、さらに進むうちに、これらから非常に多くのことを発見できるでしょう。記:人間とゴリラの主な違い 人間とゴリラの骨格にはいくつかの違いがあります。まず、人間は二足歩行をするために、直立した体形を持ち、脊椎はS字カーブを描いています。一方、ゴリラは四足歩行もできるため、骨格はよりがっしりしていて、肩や腕が発達しています。また、頭蓋骨の形状も異なり、人間は額が平らで脳が大きいのに対し、ゴリラは上顎が突出していて、顎が強い作りになっています。骨格以外に、人間とゴリラの重要な違いの1つは、人間は話すことができますが、ゴリラは話すことができないということです。 これは、喉頭またはボイスボックスの位置が高すぎて話せないためです。これにより、彼らの筋肉や声帯が単語を形成するために必要な可動域を持つことができなくなります。参考画:ゴリラの下顎 第1講・第7回了哲学・思想ランキング
2024年08月05日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」(GA312) 第一講(本文・解説付) 第6回第1講・第6回 今日医学に携わる者にとって、病気とはいったい如何なるプロセスかという疑問は必然的な疑問として提示されて然るべきであるにもかかわらず、病気とは、人間の生体組織のいわゆる正常な状態からネガティブに逸脱している状態であると指摘されるだけが現状なのです。そこには、人間の本質をしっかり認識しようとする姿勢が欠けています。そういう認識が欠けているこそそのものが、現代の医学的見解全体が病んでいるということを示しているのだといえそうです。さて、次のようなことに注意してくださるようお願いいたします。私は、今日医学に携わっている人は必然的に、そもそも病気とはいったいいかなるプロセスなのかという疑問を提示せざるをえないということに皆さんの注意を向けることから出発いたしました。病気は、人間の生体組織のいわゆる正常な状態からいったいどのように区別されるのでしょうか。と申しますのも、このような逸脱に関するポジティブな観念をもってのみ活動もできるというものなのに、公認の科学において通常見出され、与えられる表現は結局ネガティブなものでしかないからです。もっぱらこのような逸脱があると指摘されるだけなのです。それから、この逸脱をいかにして取り除けるかが試されます。けれども人間の本質に関する透徹した見解はそもそもそこにはないのです。人間の本性に関するこういう透徹した見解が欠けているということにおいて、根本的に、私たちの医学的見解全体が病んでいるのです。外的な自然のプロセスを正常と看做し、病気のプロセスを異常であると看做すのは、いったい何故なのでしょうか。その正常・異常というとらえ方について、それを絶対化することによって、病気のプロセスそのものが見えなくなってしまうということに注目する必要があります。そうした、正常・異常は、ある意味では言葉遊びに過ぎない部分があるのです。いったい病気のプロセスとは何なのでしょうか。やはり皆さんは、それは自然のプロセスであると言わざるをえないでしょう。外部で進行していてその結果を追求できる何らかの自然のプロセスと、病気のプロセスとの間に、すぐさま抽象的な区別を立てることはできないのですから。自然のプロセス、皆さんはこれを正常と称し、病気のプロセスを異常と称します。その際、人間の生体組織におけるこの病気のプロセスがなぜ異常なものなのかについては注意しておられません。少なくともこのプロセスがなぜ異常なのか説明できなくては、実際のところ実践に移ることはできないのです。説明できてはじめて、このプロセスをいかにして終結させることができるかを探究していけるのです。そうすることによってはじめて、このような病気のプロセスを取り除くことは、宇宙に存在するもののどの一隅から可能なのかという問題に行き着くことができるからです。つまるところ異常とみなすこと自体が妨げになるのです。いったいなぜ、人間における相当数のプロセスが異常とみなされねばならないのでしょうか。私が指を切ったとしても、それは人間にとって単に相対的に異常であるだけなのです。私が自分の指を切るのではなく、一片の木材を何らかの形に切るとしたら、これは正常なプロセスといえるからです。自分の指を切ると、これを異常なプロセスと呼ぶわけです。おわかりでしょうか、自分の指を切るのとは違うプロセスの方を追求するのに慣れているということによっては、実際何も語られはしないのです。単なる言葉遊びが世に広まっているにすぎません。なぜなら、私が自分の指を切る時に起こっていることは、ある側面からすれば、その経過においては他の何らかの自然のプロセスと全く同様に正常なものと言えるからです。ですから、病気のプロセスを異常だというふうにとらえるのではなく、プロセスとしては正常であるけれども、特定の原因によって生じたに違いないプロセスと、通常健康であるとしている日常的なプロセスとの差異を見ていく必要があるのだといえます。この決定的な差異を見出すことこそが重要課題です。この導入部としての第1章では、その差異を見出すための観察方法についての最初の基礎が示され、次章からそれが個別的に話されていくことになります。さて、次のようなことに行き着くのが課題です。つまり、私たちが病気のプロセスと呼んではいるけれども、根本においては全く正常なプロセスであり、ただ、特定の原因によって引き起こされたにちがいないプロセスと、私たちが通常健康なプロセスとみなしている日常的なプロセス、人間の生体組織におけるこの二つのプロセスの間にどのような差異があるのかということです。この決定的な差異が見出されねばなりません。この差異は、真に人間の本質へと導く観察方法に立ち入ることができなければ、見出すことはできないでしょう。この導入部において私は皆さんにそのための少なくとも最初の基礎を示しておきたいと思います。その後あらためて個別的に詳しくお話していくつもりです。参照画:指を切ると枝を切る 第1講・第6回了哲学・思想ランキング
2024年08月04日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」(GA312) 第一講(本文・解説付) 第5回第1講・第5回 1842年に出版されたロキタンスキーの「病理学的解剖学」以後の20年間が、世界を原子論的・唯物論的にとらえる医学の基礎となりました。然し乍ら、細胞説を樹立したシュヴァン(Theodor Schwann)においては、細胞形成の根底に形式化されてない液体形成があり、細胞的なものが発生するには液体的要素に依っているのだとしています。つまり、液体病理学的なところをまだ有しているということなのですが、それが同時に、人間の生体組織は細胞から構成されているというような今日の常識の基礎にもなっているということがいえるのは皮肉なものです。参考画:Matthias Jakob Schleiden - Theodor Schwann さて今度は、ロキタンスキーの「病理学的解剖学」出版後の20年間が、医学の本質の原子論的・唯物論的考察にとっての本来の基礎をなす期間となったことに注目してみたいと思います。古くからのものは、奇妙なことになおも19世紀前半に形成された表象の中に入りこんでいるのです。ですから、例えば、植物細胞の発見者と言えるシュヴァンはなお、細胞形成の根底には、ある種の形式化されてない液体形成、彼が胚胞とみなした液体形成があるという見解を持っていますが、彼のように、この液体形成から細胞核が硬化し、細胞原形質が周囲に分化するのを観察するのは興味深いことです。シュヴァンがなお、細分化していく方向に流れる特性を内在させている液体的要素に依拠していること、そしてこの細分化を通して細胞的なものが発生することを観察するのが興味深いのです。さらに興味をひくのは、人間の生体組織は細胞から構成されている、という言葉で総括し得る見解が、その後次第次第に形成されていくのを追求することです。細胞は一種の基本的有機体であり、人間の生体組織は細胞から構成されているという見解は、実際今日あたりまえになっているものでしょう。さて、シュヴァンがなおもその行間に、いやその行間以上に、と私は言いたいのですが、有していたこの見解は、つまるところ古代の医学の本質の最後の名残りなのです。なぜならこの見解は原子論的なものには向けられないからです。この見解は、原子論的に現れてくるもの、細胞質を、きちんと観察すれば決して原子論的には観察できないもの、つまり液体的な何かから生じてくるものとして観察します。この液体的なものが力を内在させていて、この力が自らのうちから原子論的なものを分化していくというのです。1858年に出版されたウィルヒョウの「細胞病理学」によって、より普遍的であった古代の医学の見解は終焉にむかいます。人間に現れてくるものがすべて細胞作用の変化からとらえられるようになり、器官組織の細胞の変化から病気が理解されるようになりました。こうした「原子論的観察」はきわめて分かり易いのですが、その分かり易さこそが、自然や宇宙の本質に覆いをかけてそれを見えなくさせてしまっているのです。19世紀の40年代と50年代のこの20年間に、より普遍的であった古代の見解は終焉に向かい、原子論的な医学的見解が黎明を迎えます。1858年にウィルヒョウの「細胞病理学」が出版されたのがまさしくその時でした。実際この二つの著作、つまり1842年のロキタンスキーによる「病理学的解剖学」と、1858年のウィルヒョウの「細胞病理学」の間に、近代の医学的思考における大きな飛躍的転回を見出さねばなりません。この細胞病理学により根本的に、人間に現れてくるものはすべて細胞作用の変化から推論されるようになります。公的な見解にしたがって、すべてを細胞の変化に基づいて構築することが理想とみなされます。ある器官組織の細胞の変化を研究し、この細胞の変化から病気を理解しようとすることにこそ理想が見出されるのです。こうした原子論的観察は実際容易なものです。つまるところそれは自明の理とでも言うべきものなのですから。すべてをこのように容易に理解できるように作りあげることができます。こうして、近代科学はあらゆる進歩をとげたとはえ、この科学はあいもかわらずすべてを容易に理解することを目指し、自然の本質と宇宙の本質はきわめて複雑なものなのだということを考えてもみないのです。これは簡単に実験で確かめられるでしょうが、例えばアメーバは水中でその形を変化させ、腕のような突起を伸ばしたり、また縮めたりします。それからアメーバが泳いでいる水を暖めたとします。すると、ある特定の温度になるまでは、突起を伸ばしたり縮めたりするのがだんだん活発になるのがわかります。その後、アメーバは収縮してしまい、もはや周囲の媒体で起こっている変化について行けなくなります。また、この液体のなかに流れを作り出すと、アメーバはその体を球状にし、流れをあまりに強くすると、最後には破裂してしまうのが観察されます。つまり個々の細胞が環境の影響によってどのように変化するかを研究し、そこから、いかに細胞の本質の変化により次第に病気の本質が構築されるかという理論を形作ることができるわけです。 19世紀の40年代と50年代のこの20年間に、世界を原子論的・唯物論的に理解しようとする傾向が形成されたとえいます。今日の医学の基礎がそこで形成されたといえるのです。20年間に起こった転換によって到来したもの、これらすべての本質とは何なのでしょうか。この時ひき起こされたものは、今日公認された医学のすべてを貫いているものの中に実際生き続けています。この時ひき起こされたものの中に生きているのは、まさしく唯物論的な時代に形成された、世界を原子論的に理解しようとする傾向に他なりません。<註釈>*小林鼎三「医学の歴史」(中公新書)を参考。■シュヴァン(Theodor Schwann/1810-1882)細胞説を樹立。シュヴァンは1839年に「動物と植物の構造と成長における一致について」という論文をだしたが、これは動物も植物と同じく細胞からできていることを初めて述べたものである。■ウィルヒョウ(Rudolf Ludwig Karl Virchow/1821-1902)ポメラニア生まれで、ベルリンの軍医学校に学んだ。病理解剖学をめざしてすすみ、これと臨床医学との提携を生涯の仕事として大きな成果をおさめた。1849年にヴュルツブルグの教授となり、7年後ベルリン大学に転じた。そして1858年に「細胞病理学」を著した。ガレヌスの液体病理学は遠く過去のものとなり、モルガーニは病気の座として器官を考え、ビシャーはそれを組織においた。ウィルヒョウはさらに生活体の単位である細胞にその座を置いたのである。彼は「すべての細胞は細胞より生ず」という生物学の鉄則をつくった人である。1863-68年には彼の「病的腫瘍論」がでた。ウィルヒョウは長い間病理学の法王ともいえる最高の地位にあった。人類学にも造詣が深かったし、政治的にも活躍して民間政党の首領であり、ビスマルクと渡りあったといわれる。参照画:ウィルヒョウ 第1講・第5回了哲学・思想ランキング
2024年08月03日
コメント(0)
-
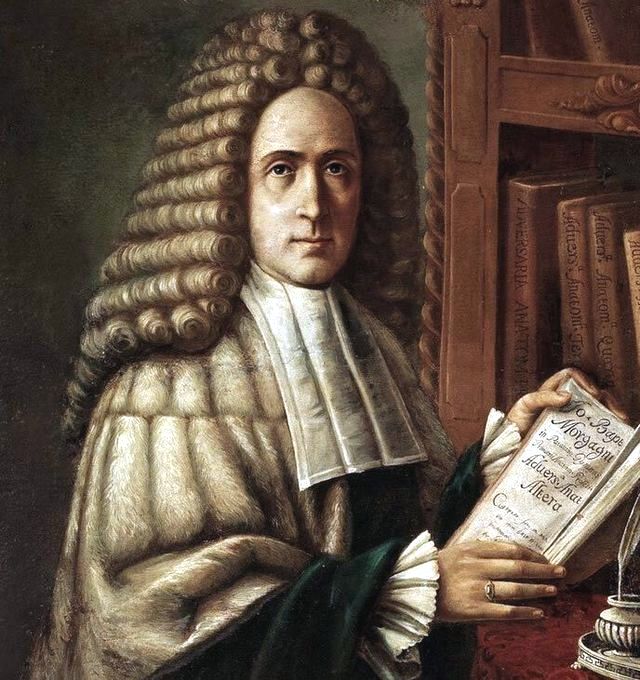
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」(GA312) 第一講(本文・解説付)解説 第4回第1講・第4回 スタール医学は、宇宙の作用についてまったく理解していないといえます。パラケルススとファン・ヘルモントにおいては、霊的魂的なものと物質的な生体組織との間のものについて意識的であったのですが、スタール医学においては、意識的・魂的なものが姿を変えて人間の生体組織に働きかけるというような、一種の仮説的な生気論になってしまっているのです。そういう方向性の反動としてでてきたのが、19世紀のヨハネス・ミュラー(Johannes Peter M?ller/1801年7月14日 - 1858年4月28日)です。。彼の指向したのは自然哲学からの脱却と、観察・実験であった。実験生理学よりも形態学研究に傾斜し、比較解剖学、動物分類学に興味を抱いた。また病理学とくに腫瘍(しゅよう)の研究に顕微鏡を応用した先駆者でした。さて、当時もともと意味されていたことが、どんどん理解されなくなっていったと言うことができます。とりわけこのことが明白になってくるのは、私たちが17-18世紀と進んで、スタール医学に出会う時です。ここにいたっては、この、宇宙の地球的なのものへの作用についてはもはやまったく理解されていません。スタール医学は純粋に空気中に漂っているあらゆる可能な概念、生命力、生命霊についての概念を利用します。パラケルススとファン・ヘルモントは、人間の本来の霊的・魂的なものと物質的な生体組織との間にあるものについて、まだある程度意識的に語っていましたが、一方、スタールとその信奉者たちは、あたかも意識的-魂的なものが別の形をとってのみ人間の身体の構造付与に働きかけるかのように語りました。このことによって彼らはむろん強い反動を呼び起こしました。なぜならこのような方法をとって、一種の仮説的な生気論(Vitalismus)を打ち立てると、結局は純粋に恣意的な提示になってしまうからです。このような提示にとりわけ其れに対抗したのは19世紀です。例えば、エルンスト・ヘッケルの師で1858年に亡くなったヨハネス・ミュラーのような偉大な精神のみが、人間の生体組織に関するこういう不明確な言い方に由来するあらゆる害悪を克服してそれを越えて行ったのだと言うことができます。この不明確な言い方というのは、人間の生体組織において作用しているという生命力について、それがどのように作用しているのかはっきりと考えることなしに、もっぱら魂的な力について語るように語ってしまったことなのです。対して、全く別の流れ、つまり唯物論的な流れが出てきます。18世紀のモルガーニの病理学的解剖学です。モルガーニは、死体解剖によって病気の原因を探ろうとし、生体組織の病んだ結果だけに目を向けました。さて、こうしたことすべてが起こっている間に、全く別の流れが現れてきました。私たちは今まで、謂わば、流れ去っていくものをその最後の余波まで追求してきたわけですが、近代とともに、とりわけ19世紀の医学上の概念形成にとって今度は別の仕方で決定的となったものが到来したのです。それは結局、18世紀の、法外に強力な決定的影響を与えた唯一の著作、パドゥアの医師モルガーニの著「解剖所見による病気の所在とその原因について」に遡(さかのぼ)ります。モルガーニとともに、根本において医学における唯物主義的な傾向を導いたものが到来したのです。こういうことは、共感、反感をまじえずにまったく客観的に特徴づけられねばなりません。と申しますのも、この著作とともに到来したものは、人間の生体組織が病んだ結果に目を向けさせるものだからです。決定的なものとなったのは、死体鑑定でした。死体鑑定が決定的なものとなったと言えるのは、実際この時代からなのです。人々は死体から、病名は何であれ、何らかの病気が作用すると、いずれかの器官が何らかの変化を蒙(こうむ)るにちがいないということを知りました。今や、何らかの変化を他ならぬ死体鑑定から研究するということが始まったのです。実際ここではじめて病理学的解剖学が始まります。他方、医学のなかに以前からあったものは、すべて、なおも作用し続けている古代の霊視的な要素に依拠していました。さて、20世紀において大きな転換が起こります。古代的な遺産が打ち捨て去られ、医学は原子論的・唯物論的になってゆきます。古代の体液病理学の最後の遺産は、1842年に出版されたロキタンスキーの「病理学的解剖学」でした。興味深いのは、大きな転換がそれから一挙に最終的に起こったことです。実際直接20世紀を示すことができ得るのです。興味深いことに、20世紀に大きな転換が成し遂げられ、それによって古くからの遺産としてまだ存在していたものがすべて捨て去られ、さらに現代の医学制度における原子論的・唯物論的な見解が基礎付けられたのです。ちょっと努力して、1842年に出版されたロキタンスキーの「病理学的解剖学」を調べてごらんになれば、ロキタンスキーにおいてはまだ、古代の体液病理学の名残(なご)り、つまり病気は体液の正常でない相互作用に基づくという見解の名残りが存在していることがおわかりになるでしょう。このような体液の混合に注目せねばならないとする見解、これができ得るのは、体液の地球外的な特性についての見解の遺産を有している時だけなのですが、この見解はロキタンスキーによって非常に機知に富んだやり方で器官の変化の観察と結びつけて処理されました。つまり、ロキタンスキーの書物はもともと常に器官の変化の死体鑑定による観察を根拠としているのですが、これが、このような特殊な器官変化は体液の異常な混合の影響によって生じてきたのだという指摘に結びついているのです。ですから、古代の体液病理学の遺産から現れた最後のものは1842年にあったと言いたいのです。この古代の体液病理学の没落の中に、例えばハーネマンの試みのような、包括的な病気の表象を考慮に入れるという未来指向的な試みがいかに投入されたか、これについては後日お話していこうとおもいます。これは単に前置きで取りあげるにはあまりに重要なことですから。まずは同様な試みとの関連において、それから個々の場合において議論されねばなりません。 <註釈>*小川鼎三「医学の歴史」を主に参考■スタール(Georg Ernst Stahl/1660-1734)ホフマン、ブールハーヴェとともに、医学界の三巨匠とされた。彼らは体系学者と呼ばれる。物理派と化学派を合わせながらその上に、ライプニッツの唯心論をのせて、生命や病気の解釈に体系をたてるのが得意。■ヨハネス・ミュラー(Johanes Mueler/1801-1858)ドイツ医学の哲学的要素を排し、科学的なものとする。ライン河畔のコブレンツに靴屋の子として生まれた。ボン大学で医学をおさめたが、そのときの解剖学への深い傾倒が、その後実物に即してのみ考える習慣をもつのに大いに役立ったという。ついでベルリンで生理学者のルドルフィに学び、またボンに帰り、1830年正教授になる。3年後にベルリン大学に転じて、解剖学、生理学、病理学を一人で兼ね教えた。生理学では神経系と感覚器に関する研究を多く行い、解剖学ではとくに生殖器の発生などについて業績をあげた。動物学、発生学、比較解剖学、生理学、化学、心理学、病理学など、あらゆる方面で活躍した。病理解剖学では顕微鏡を用いる方向に深く進んだ。その著書「人体生理学全書」は、この世紀の金字塔と言われる。 ■エルンスト・ヘッケル(Ernst Haeckel/1834-1919)■モルガーニ(Giovanni Battista Morgani/1682-1771)フォルリに生まれ、ボローニャで医学をおさめ、19歳のとき、解剖学者ヴァルサルヴァの助手になった。29歳の時パドアの解剖学教授となり、90歳の高齢で没するまでその職にあった。地味な学者だったようで、こつこつと多数の人体解剖を生前の病状と照らし合わせながら行い、それをまとめた大著「解剖所見による病気の所在と原因について」を、驚くべきはやっと1761年80歳のときに出して、一挙に病理解剖学を打ち立てた。■ハーネマン(Christian Friedrich Samuel Hahnemann/1755-1843)ホメオパシーの創始者。ドイツ生まれ、ライプチヒ大学で医学をおさめ、エルランゲンで学位を得た。キニーネの働きを調べて、これがマラリア類似の熱をひきおこするとなして、そこから考えが飛躍していった。そして、ある病気を治すにはその症状と似たものを健康な人におこすような薬を用いる必要があるととなえた。「似たものが似たものを治す」というのがその主張であった。参照画:モルガーニ(Giovanni Battista Morgani) 第1講・第4回了哲学・思想ランキング
2024年08月02日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神科学と医学」(GA312) 第一講(本文・解説付)解説 第3回第1講・第3回 今回からは、翻訳引用部分を読みやすく段落分けすることにしました。原文では、1ページほど段落分けのない場合がしばしばなので、そのまま訳すと読みにくいのを考慮して、適宜そうさせていただきます。そもそもこれは著作ではなく、講演集なので、理解しやすい形にするのが望ましいのではないかとも思ったからです。さて、ヒポクラテスのいう「血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁」を、「単に化学的反応によって確認できる特性」としてとらえるのが現代の科学的な観点での医学なのだといえるのですけど、そうではなく、そのなかで「黒胆汁」だけがその要素を持つのであって、それ以外のものは「地球の外部からやって来る諸力に浸透されている」というふうに考えられていたということを認識する必要があります。今日の人間が、できる限り科学的に準備してこのようなことに近づくなら、まずもって次のように考えるでしょう、つまり、血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁が混ざり合うというのは、これらに特性として内在しているもの、多かれ少なかれ、低次あるいは高次の化学により特性としての配列を確認できるものに従って混ざり合っているのだと。あたかもヒポクラテス派もこういう方法でのみ血液、粘液その他を見ていたかのような、こういう光のなかで、体液病理学が端を発したと本来思われているのです。しかし、そうではありません。そうではなく、ただ一つの要素、今日の観察者にとって実際最もヒポクラテス的だと思われる黒胆汁についてのみ、通常の化学的特性が他のものに作用すると考えられたのです。他の全てのもの、白胆汁や黄胆汁、粘液、血液に関しては、単に化学的反応によって確認できる特性のことが考えられていたわけではなく、人間の生体組織のこの液体的要素の場合、常に人間の生体組織に限定し、動物の生体組織についてはさし当たり考慮しませんが、これらの液体は、私たち地上的な存在の外部にある諸力の、それぞれの液体に内在する特性を有していると考えられたのです。つまるところ、水、空気、熱が地球外の宇宙の諸力に依存していると考えられたように、人間の生体組織のこれらの要素も地球の外部からやって来る諸力に浸透されていると考えられたのです。「地球の外部からやって来る諸力」という視点は、現代科学ではほとんど失われてしまっています。ですから、15世紀以前の医学的文献を理解することは困難になっているといえます。しかし、古代においては、生体組織内の液体的要素を通じて、宇宙に由来する諸力の作用がもたらされると考えられていたことをここでは理解していく必要があります。このような地球の外部からやって来る諸力への視点は、西洋の科学の発展にともなって全く失われてしまいました。ですから、今日の科学者が、水は単に化学的に検証できるものとして与えられた特性のみではなく、それが人間の生体組織のなかに働きかけることによって、地球外の宇宙に属するものとしての特性も持っているのだと考えることを要求されたなら、彼らにとって、それは全く奇妙なことと思われるでしょう。つまり、人間の生体組織の中にある液体要素を通じて、古代の人々の見解によれば、この生体組織の中へと、宇宙そのものに由来する諸力の作用がもたらされるのです。この、宇宙そのものに由来する諸力の作用こそ、次第にかえりみられなくなったものなのです。とは言え、15世紀までは、医学的思考はまだ、私たちがヒポクラテスにおいて出会う濾過された見解の、いわば残滓の部分に基づいていました。従って、今日の科学者にとって、そもそも15世紀以前の医学的古文献を理解することは困難なのです。なぜなら、当時それを書いた人々の大多数は、自分の書いたものを彼ら自身秩序立てて理解してなどいなかったと言わねばならないからです。「血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁」といった人間の生体組織の四つの基本要素などはヒポクラテス以降失われてしまった古代の智慧へと遡ることのできるもので、そういう智慧はまだ15世紀頃までは影響を及ぼしていたのです。彼らは、人間の生体組織の四つの基本要素について語りましたが、彼らがこれらの基本要素をあれこれの方法で特徴づけた理由は、本来ヒポクラテスとともに埋没してしまった智慧へと遡るものなのです。こうした智慧がのちに及ぼした作用、人間の生体組織を構成する液体の特性についてはなおも語られていました。従って、ガレノスによって成立し、その後15世紀に至るまで影響をおよぼしたものは、基本的に、次第次第に理解不能になっていった古代の遺産の組み合わせなのです。記:ガレノスは、ヒポクラテスの医学をはるばるルネサンスにまで伝えた。彼の On the Elements According to Hippocrates は、ヒポクラテスの四体液説を叙述している。四体液説は人体が血液、粘液、黒胆汁、黄胆汁から成るとする説で、それらは古代の四大元素によって定義付けられ、且つ四季とも対応関係を持つとされた。彼はこの原理を基にして理論を創出した。しかし、それらは純粋に独創的なものというよりも、ヒポクラテスの人体理論の上に構築されたものと見なしうるものである。。古代の医学を集大成し自らも多くの価値ある実験を行い、著作の量も膨大であり医学を系統だてた。彼は実験生理学の創始者ということができ、その学説は正否とも十数世紀にわたって欧州やアラビヤで金科玉条とされた。15世紀以降でも、すべてを化学的物理的に確認しうるものとするような体液病理学と闘った偉大な医学者がいました。パラケルスス(Philippus Aureolus Paracelsus Theophratus Bombastus von Hohenheim/1493-1541)とファン・ヘルモン(トJohann Baptist van Helmont/1577-1644)です。参考画:ヒポクラテスとガレノス しかしながら、まさしくそこに在るものから認識することのできた人々が常に少数存在していました。つまり彼らは、化学的に確認しうるものや物理的に確認しうるもの、すなわち純粋に地上的なものに汲み尽くされない何物かを指摘できることを知っていたのです。人間の生体組織においては、化学的に合成するのとは別な仕方でその中の液体的な実質を作用させる何物かが指摘されうるということを知っていた人々、つまり世に知られた体液病理学と闘った人々の中に、パラケルススとファン・ヘルモントその他の名前を挙げることもできる病理学者がいます。彼らはちょうど15、16世紀から17世紀への変わり目に、言うならば他の人々がもはや明確に表現しなくなったことを、まさしく明確に表現しようと試みることで、医学的思考の中に新たな動向をもたらしたのです。この表現のなかにはしかし、人々がいくらか霊視的であった時にのみ本来追求し得たものが含まれていました。実際のところパラケルススとファン・ヘルモントが霊視的であったことは明らかです。私たちはこうした事柄すべてを明確にしておかねばなりません。さもなければ、今日なお医学用語に定着してはいるけれども、その起源についてはもはや全く知られていないものについて、理解することはできないでしょう。こうしてパラケルススと後に彼の影響を受けた他の人々は、生体組織における作用の基盤としてアルケウス(Archaeus)というものを想定しました。私たちがおおよそ人間のエーテル体について語るように、彼はこのアルケウスを想定したのです。 記:パラケルスス(Paracelsus)は、ドイツの貴族の出でチューリッヒの近くで1493年に生まれ、長じてフェララで医学をおさめ、その後に欧州の諸地を遍歴して実地医学を身につけた。1527年、バーゼルの教授となり、市医を兼ねたが、ガレヌス、アヴィセンナなどの諸大家の学説に盲従することをはげしく攻撃して、自然の観察と実験にもとづく医学の在り方をとなえた。その言動があまりにも過激だったため大学を追われて諸国をめぐり、診療と著述をなして1541年、ザルツブルグで病没した。彼の医学思想はすこぶる独創にとみ、化学眼をもって生命現象をみて、新陳代謝を論じている。身体を構成するものとして、硫黄、水銀、塩の3つを挙げたが、硫黄は燃えて消え去るもの、水銀は熱により蒸発するもの、塩は火に滅びず灰となって残るものを意味した。人体に内在して生活現象をおこす力をアルケウスとよび、それはヒポクラテスの自然の力よりも、いっそう具体的なものである。たとえば胃のアルケウスは食物の中から有用なものを無用のものから分離して、有用なものを同化するのであり、肺のアルケウスは空気を一種の栄養物として吸収すると考えた。パラケルススは、医学の分野にかぎらず自然科学、神学、哲学などなどを縦横無尽に展開させた、いわばファウストのような人物だと云えますから、上記のような部分的な紹介では紹介しきれるものではありません。このパラケルススについては、ユングの「パラケルスス論」など邦訳でもたくさんの解説書がでています。 さて、パラケルススのいうアルケウスを、シュタイナーはエーテル体のようなものとしてとらえています。シュタイナーのいうエーテル体は、地上的なものではなく、宇宙的なものです。私たちの物質的な生体組織は地球の組織の一部であるということができますが、その根底には宇宙的なエーテル的組織があると考え、パラケルススはそれを「アルケウス」と名づけたわけです。しかし、それは個別的な形で暗示するにとどまり、さらにそれを研究することはありませんでした。パラケルススのようにアルケウスについて語るなら、私たちがエーテル体について語るようにアルケウスについて語るなら、存在してはいるけれどもその本来の起源については追求されていないものが統一されます。なぜなら、その本来の起源を追求するとなれば、次のような方法をとらざるをえないからです。人間は、地上的なものから作用する諸力から本質的に構成されている物質的な生体組織を有すると言わねばなりません。私たちの物質的な生体組織はいわば地球の組織全体の切り取られた一片です。そして私たちのエーテル体とパラケルススの言うアルケウスは地球には属さない、すなわち宇宙のあらゆる方向から地上的なものへと作用するものの一片です。つまるところパラケルススは、以前はもっぱら人間における宇宙的なものとみなされていてヒポクラテス医学とともに没落したものを、物質的な組織の根底にあるエーテル的組織という彼の見解において統合的に見たわけです。彼は、このアルケウスにおいて本来作用しているものがどのような地上を越えた諸力と関係しているのかに関してはそれ以上は研究しませんでした。なるほど個別的に暗示はしましたが、それ以上は研究しなかったのです。最後に、この「アルケウス」についての理解を深めるために、K.ゴルトアンマー著「パラケルスス」から、それについて書かれているところを引用紹介させていただきます。植物にも、生命の精気(Lebensgeist)は与えられており、「表徴者アルケウス(Archaeus Signator)」がすでに植物の外形に、その本性と治癒力との表徴を刻印している。たとえば、アザミは内蔵の刺痛に効くとされている。「アルケウス」は、世界の大いなる原理の一つなのだ。やはり、アルケウスも宇宙的な生命力であり且つ原動力なのである。それは、自然における秩序原理、もしくはエンテレヒーと解することができる。アルケウスは、「諸力を秩序だてる者」であり、「配置者(dispensator)」であり、アルケウス直属の「職工」が、水銀・硫黄・塩なのである。アルケウスを配置したのは神であり、それはパン職人やブドウ栽培者と同じ働きをする。その仕事は、アタナール(化学炉)内での錬金術的課程に模することができる。ついには大宇宙全体がアルケウスと同一視されることにもなる。とはいえ、アルケウスが一個の個体原理であることに変わりはない。記:ファン・ヘルモント(ohann Baptist van Helmont/1577-1644)に関することが分かりましたので、補足しておきたいと思います。ヴァン・ヘルモントとも表記され発見に難がありました。。ファン・ヘルモントは化学医学派の首領ともいわれている人で、パラケルススの流れをくむ人物です。ブラッセルに生まれて、まずルーヴァンで哲学を学び、ついで法律に転じてその後に医学をおさめた。二十二歳でドクトルとなり、五年間諸地をめぐって後に郷里で開業した。化学実験をたくさんなしたが、神秘的な考え方もしたので、その点もパラツェルズスと似ている。一六二四年異端の疑いをうけてその裁判が二十年も続き、投獄されたこともある。酵素作用の重要性を認めており、またガスという言葉はこの人の創始といわれている。第一講(本文・解説付) 解説第3回了哲学・思想ランキング
2024年08月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- ^-^◆【助言の光】支えられたことばの…
- (2024-11-16 01:00:11)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 筧利夫「踊る大捜査線」の名シーン“…
- (2024-11-16 03:47:04)
-








