2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
第二十一回 インドの自動車業界(その3)
2006年1月27日 インドの自動車業界(3) 今日のポイント1.金利上昇は自動車株にとってネガティブ 2.石油価格高騰はネガティブ 3.金利政策の変更回数が少ないので突然大きな調整を余儀なくされる場合がある 4.外国製品との競争が激化するリスクがある 5.原材料費の高騰のリスクがある 6.ストのリスクがある 7.雨季に十分な降雨が無いと需要が減退するリスクがある インドの自動車株に投資する際のリスク先ず最初に指摘すべきリスクは金利の上昇が自動車を購入するローンを組みにくくし、それが需要減退につながるリスクでしょう。インド準備銀行総裁は最近のコメントで現行の金利水準を維持していくつもりであることを示唆しています。しかし、インドのマクロ経済のファンダメンタルズは案外脆弱で、中央銀行の好むと好まざるにかかわらず金利が上昇してしまうリスクがあります。 石油価格についてその第一の理由は石油です。インドは石油輸入国(国内消費の約70%を輸入に頼っています)であり、しかも国内の石油製品の価格は消費者保護の為、世界の実勢水準より低く設定されてきました。つまり、政府が実質上の「補助金」を出している格好になっているわけです。従って、今のように国内の需要が急増し、しかも石油の国際価格が上昇している局面では国庫の負担は雪だるま式に大きくなります。 財政赤字と金利の関係もともとインドは財政赤字がGDPの4%を超えており、BRICs諸国の中では最も悪くなっています。また、インドの経済が中国のような「加工輸出型」でないことも貿易収支にとってハンデとなっていますから、国際資金フローが逆流すると慌てて金利を引き上げる必要が出ることが予測されます。石油高騰は一般にインフレを引き起こしますから、上に述べた不健全な財政の体質と併せて、ダブルで痛手を蒙ることも十分ありうるわけです。インドの場合、アメリカなどと違って、一年のうちに中央銀行が政策レートを変更する回数が少なく、小刻みな「ガス抜き」が出来にくい面があります。これまでのところ金利見通しが激変するような事態は起こっていませんが、それは今後の安定を保証するものではありません。 関税と外資からの競争次のリスクとして競争の激化を指摘したいと思います。前にも述べたようにインドの自動車業界はこれまで輸入関税によって保護されてきました。既にインド政府はこの関税を撤廃する方向で動き始めており、実際、完成品ならびに自動車部品に対する関税は今後WTOの規約に従って漸次下がってくることが予想されます。そのことは即ち国内メーカーが競争に晒されることを意味します。加えて、これまでは部品の殆どを国内から調達していた関係で、国内の下請けと特別親しい関係にある国内自動車メーカーは当然、その面で有利な立場にあったわけです。そういう非関税障壁が今後下がってくることが予想されます。 原材料費の変動次のリスクとしては、インドは人件費が安い分だけ、一台の自動車を製造するに当って、そのコストに占める原材料費が高いことがあげられます。2005年度の決算では原材料費がコストに81%を占めていました。その少なからぬ部分が鉄鋼価格ですから、鉄鋼価格が高騰するとインドの自動車会社のマージンは圧迫されることが予想されます。 ストのリスクタタ・モータースの場合、経営陣を除いた全ての従業員は労働組合に所属しています。同社の賃金契約は3年契約ですが、その一部は今年の夏から更新期に入ります。一般的にインドの労使交渉は他のBRICs諸国に比べて荒れやすいと言えるでしょう。これも頭の隅にいれておくべきファクターです。 モンスーン最後に毎年4~5月からインドは雨季を迎えますが、その時期の降雨の如何によっては農産物の作柄に大きく影響してきます。ここ数年はモンスーン期の降雨に問題が無かったので、投資家は良いニュースに慣れっこになっていますが、若し、雨がちゃんと雨を降ってくれないと農家の家計収入は大きく落ち込み、GDP成長に悪影響をあたえないとも限りません。その場合、自動車の購入は当然、手控えられるので自動車株も下落することが考えられます。
2006年01月27日
-
第二十回 インドの自動車業界(その2)
2006年1月20日 インドの自動車業界(2) 今日のポイント 1.外資の新規参入は乗用車市場に集中している 2.タタの乗用車市場での成功はマルチ・ウドヨグにとってネガティブ 3.乗用車の関税引き下げで外国製品からの競争が激化する 4.今年の成長率は鈍化が避けられない 5.新製品の投入に市場が敏感に反応する 市場開放と競争について インドの自動車市場が外資に開放されて以降、全ての外資の新規参入は乗用車市場を目指したものとなっています。この為、乗用車市場は競争が激しくなっています。必然的にこれまでマーケット・シェア・リーダーだったマルチ・ウドヨグの相対的な地位も低下傾向にあります。 海外からの参入に加えて国内勢で、これまでもっぱら商用車に特化してきたタタ・モータースが乗用車市場に参入してきたことに注目すべきだと思います。タタ・モータースが最初に乗用車市場参入を発表したときには懐疑的な見方をする業界関係者も少なくありませんでした。しかし、1998年に発表された『インディカ(インド初の純国産コンパクト・カー)』と、それに続くミッド・サイズの『インディゴ』が相次いで成功を収めたことでタタ・モータースもマルチ・ウドヨグにとって手ごわい競争相手であることが認識されつつあります マルチ・ウドヨグの問題点はこれまで保護関税やその他の規制で守られた市場でぬくぬくと育ってきた面があり、「他流試合」の機会が少なかった点でしょう。今後、輸入乗用車に対する関税(新車の場合、すべて込みで現行税率103.39%)がさらに引き下げられると一段の競争激化は必至です。 一方、商用車市場は今のところタタ・モータースが独走態勢ですし、外資の動きも活発ではありません。さらに商用車の輸入関税は既に比較的低い水準に設定されています(全て込みで現行税率は35.93%)。これらの面から今は商用車市場の方が不確実性が低いと言えると思います。 乗用車と商用車の成長率について さて、上では主に競争について議論しましたが、今年の需要成長について考えてみたいと思います。前回、ここ数年、インドの自動車市場は急激な拡大を見たことを紹介しました。しかし、市場規模が大きくなった分だけ、去年と同じ成長を維持してやろうとするとそれだけ多くの数量をこなしてやる必要があります。また、ここ数年はモンスーン・シーズンの降雨がおおむね良好で農業セクターが潤ったこと、さらにここ数年の金利低下で自動車購入のローンを組みやすくなったことなど好材料が重なったのでこの実績を超えるのは並大抵の努力ではありません。なお、銀行の小口貸付金利は今後上昇する可能性が高いです。これらのことから今年(06年3月〆の12ヶ月)の乗用車ならびに商用車の出荷台数の成長率は一桁台に留まると考えた方が無難でしょう。前回見たように、04年が29.3%、05年が18.0%成長しているわけですからこの成長鈍化はある時点で日柄ないしは値幅調整という形で株価に織り込まれる筈です。 さて、商用車の中での成長率を見てみると中・大型商用車の成長率はこのところ低迷しています。その一方で軽商用車(LCV)は健全な成長を見ました。これはタタ・モータースが『タタ・エース』という1トン以下の軽商用車を新発売した関係です。『タタ・エース』が発売されるまでは1トン以下というカテゴリーは存在しませんでした。このように新製品の発売や新しいカテゴリーの登場が需要に一定のインパクトを持つのもインドの自動車業界の特徴と言えます。これまで消費者の選択肢が狭かった事が新製品が需要を喚起しやすい環境を作っているのだと思います。
2006年01月20日
-
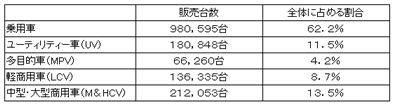
第十九回 インドの自動車業界(その1)
2006年1月13日 インドの自動車業界(1) 今日のポイント 1.インドの自動車市場は現在急成長中である 2.規制緩和とインフラ整備が需要爆発の主因 3.低金利、銀行サービスの伸長も自動車販売を支えている 4.乗用車のリーダーはマルチ・ウドヨグ、業務用ならタタ・モータース 概観 今日からインドの自動車業界について見ていきます。インドの自動車販売は2004年が+29.3%、2005年が+18.0%(いずれも3月〆、Society of Indian Automobile Manufacturers調べ)と強烈な成長を記録しました。インドの自動車市場がこのような急成長を遂げている背景には長年に渡って自動車購入に対する潜在需要が以下に述べるいろいろな要因によって抑制されてきたことが挙げられます。その反動が今、一気に需要の爆発となって現れていると言って良いでしょう。従って、上記のような成長率が今後も維持可能であると決めてかからない方が良さそうです。まあ、それは兎も角、インドの自動車業界の歴史についてちょっと振り返るところから始めましょう。 インドでは1984年以前は自動車産業は厳格な政府の規制の下に置かれていました。政府の許可なくしては自動車会社を創立することは実質的には不可能でした(インダストリー・ライセンス制度)。個人所有の乗用車は贅沢品だとみなされ、多重課税、価格統制の対象とされてきました。このため、インドの自動車産業は少量生産を強いられた上、コスト高で品質の安定しない国内部品メーカーからの部品調達に頼らねばなりませんでした。一方、輸入関税が高かったので外車の輸入も少なかったです。この結果、インドの国民は昔の共産圏の国がそうだったように、ごく限られた車種の、かわりばえのしない車を押し付けられる結果になったわけです。 最初の規制緩和は1984年に実施されました。このときは車種カテゴリーの規制の緩和が主な改革の内容でした。次に1991年にインダストリー・ライセンス制度が撤廃され、同時に輸入関税が引き下げられました。これらの措置によって初めて自由競争の素地が出来たと言えるでしょう。1980年代半ばにスズキがマルチ・ウドヨグとJVを組んだのが本格的な外資参入の皮切りでした。2001年には輸入に関する全ての数量規制が撤廃されています。また、外資系企業が100%所有の現地自動車会社を設立することもOKになっています。但し、輸入車(新車、中古車とも)に対する関税は現在も比較的高く、今後はWTOの規約に沿ってそれらに対する関税がさらに引き下げられることが予想されます。 さて、このような一連の規制緩和がインドの自動車販売にどのようなインパクトをもたらしたかについては次ぎの自動車販売台数の統計が全てを物語っていると思います: インド国内(輸出も含む)の全車種の年間販売台数(出典:SIAM) 1980年 10.6万台 1990年 35.5万台 2005年 157.6万台 ※SIAM:Society of Indian Automobile Manufacturers つまりインドの自動車消費市場はいわば「眠りの森の美女」のように魔法にかけられて時間が止まっていたようなものです。それが突然、規制緩和によって眠りから覚めたというわけですね。 需要を左右するファクター さて、規制緩和以外にも需要を喚起する原動力となったファクターが幾つか存在します。その第一は自動車ローンが組みやすくなったということでしょう。自動車ローンのブームが起こっている背景にはインドの市中金利が近年下がっていることが指摘できます。また、前回までインドの銀行セクターについて研究したわけですけど、そこで紹介した通り、今、インドの銀行各行はコンシュマー・ローンに大変力を入れています。これもインドのミドルクラスが自動車を買いやすくなった大きな要因として見逃せません。また、インドの経済そのものが近年好調であることも当然影響してきます。それからインドでは今年、ゴールデン・クウァドリラテラル(黄金の四辺形、略して「GQ」と呼ばれることが多い)という高速道路が開通しました。デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタの各主要都市を環状に結ぶ幹線道路です。これまでのインドの道路のイメージとしては乗用車が人力車などと同じ道路を使うため、交通が一番速度ののろい乗り物の速度に揃ってしまうケースが多かったです。新しい高速道路の開通で初めて「この高速道路を飛ばしてみたいなぁ」と思うような、消費者のイマジネーションをかき立てるインフラが整備されたと言っても過言ではないと思います。日本の例でたとえれば、最初に東名高速道路が開通した時のようなモータリゼーションに対するロマンチシズムをインドの人々が今感じているわけです。 どういうメーカーが存在するか? それでは次にどういう国内メーカーが存在するのかを見てみましょう。SIAMはインドの自動車市場を以下のカテゴリーに分類しています: 乗用車:6人乗りまで(運転者を含む) ユーティリティー車(UV):7~12人乗り(運転者を含まず) 多目的車(MPV):バン・タイプ 軽商用車(LCV):7.5トン以下 中型商用車(MCV):7.5~16.2トン 大型商用車(HCV):16.2トン以上 それぞれのカテゴリー別のマーケット・シェアの推移を見てみましょう(輸出分を含む。、主要企業のみの抜粋): なお、これらのメーカーのうちADRが米国に上場されていて我々が投資可能な銘柄はタタ・モータース(TTM)1社のみです。
2006年01月13日
-
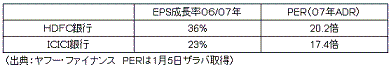
第十八回 インドの銀行業界(その3)
2006年1月6日 インドの銀行業界(3) 今日のポイント1.原油価格高騰は銀行株にネガティブ 2.FDIの低迷は銀行株にネガティブ 3.民営化の遅れは銀行株にネガティブ 4.モンスーン・シーズンに降雨が少ないと銀行株にネガティブ 5.景気の減速は銀行株にネガティブ EPSはどのくらい成長しているか? 前にも述べたようにインドではADRを出している銀行の方が現地株しか出していない銀行(その多くが政府系です)より遥かに積極的な経営をしています。ADRを出している銀行各々のEPS成長率は下の表の通りです。 なお、HDFC銀行の方が成長率が高いのは、規模そのものが小さく、成長余地が大きいのに加えて住宅ローンなど内需・消費への比重が高く、それらのマーケットが今ブームを経験していることによります。同行のPERが高いのはそういう急成長に加えて、焦げ付き比率が低いこと、自己資本比率が高いこと、預金比率が高く、貸出し利鞘が他行より大きいことなどから「当然の評価」と言えるかと思います。 リスク・ファクターの整理 インド経済が順調に成長するシナリオ下では、ただ単純に銀行株を買って、ずっと持ち続ければそれで良いのかも知れません。しかし、外部環境が変化した場合、今後銀行株が乱高下する可能性が無いとは言えません。そこで今後起こりうる変化の可能性を列挙するとともに、それらが銀行株に与えるインパクトを整理してみたいと思います。 1.原油価格が急騰した場合 前述の通り原油価格が急騰するとインド政府は石油製品に対する補助金の負担が増えます。また、インドの経常収支も石油の輸入代金の膨張で悪化するでしょう。また、インド政府のファンディング・ニーズも増えますから銀行と政府との間で「資金の奪い合い」がおこる可能性が強いのです。具体的には預金金利の上昇(それは銀行にとってコスト増、ひいては貸出し利鞘の縮小を意味します)プレッシャーが働くわけです。 さらに細かい議論になりますが、インドのそういう補助金政策を徐々に止める為に現在国際実勢価格よりかなり低く設定されている石油関連製品価格を段階的に引き上げるとインフレ圧力が強まります。このインフレを抑制するためにインドの準備銀行が金利(リザーブ・レポ・レート)を現行の5.25%からさらに引き上げる可能性があります。 2.FDI(海外直接投資)が低迷した場合 インドは中国に比べて海外企業の直接投資の額が小さいです。もしインドが海外企業の誘致に成功しなかった場合は政府自身がインフラの整備や雇用の創出などに乗り出さないといけません。これは政府のファンディング・ニーズの増加につながり、上で議論したのと同じ預金金利上昇プレッシャーを招来するでしょう。 3.民営化プログラムが頓挫した場合 先のFDIと関連してきますが、インド政府は「政府のバランスシート」が悪いですから、政府系企業の民営化を促進する必要があります。しかし、過去にインド政府はずっとポピュリスト的な政策スタンスをとってきたので、突然、「小さな政府」を標榜すると国内的な反発も大きいと思います。民営化プログラムの遅延は国際機関投資家のインドに対するコンフィデンスの低下を招き、銀行株も売られるでしょう。 4.農業部門の家計収入が落ち込んだ場合 インドはまだ農業部門のGDPに占める割合が大きいですからモンスーン・シーズンに降雨が少なく、作柄が悪ければこれは消費セクターにとってマイナス要因となります。この場合、融資需要や預金集めに悪影響が出ることが予想されます。 5.景気が減速した場合 インド経済は現在絶好調で、銀行各行も今、どんどん融資残高を増やしている最中です。貸出し金利も過去最低水準です。こういう局面では銀行はクレジット・リスクに鈍感になりやすいものです。しかも現在融資残高を構成しているローンの殆どはシーズニングされていない新規のローンです。こういう場合、それらの新規のローンの焦付き率を予想するのは大変むずかしいのです。インドの銀行業界の歴史に言及した際、昔は「箸の上げ下ろし」まで政府が厳しく規制していたことについて書きました。一般にそういう政府の従属機関のような時代が長いとクレジット・リスクに見合った金利を自ら判断し、それに合わせてローン金利を設定する(つまりプライシング・ノウハウ)などのスキルは育ちません。従って思慮に欠ける融資が今どんどん行われていると疑ってかかったほうが安全かも知れません。
2006年01月06日
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- つぶやき
- 楽天ブラックフライデーまず購入した…
- (2025-11-21 06:00:04)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- “首アイロン”で首元にも自分時間◎
- (2025-11-20 19:10:08)
-







