2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年01月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
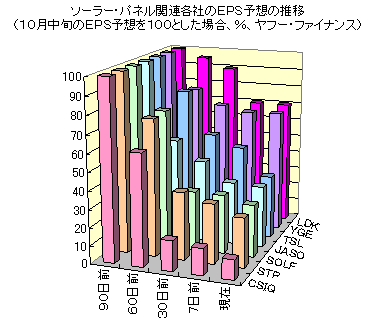
第155回 「中国の太陽光発電関連株の近況について」
今日のまとめ 1. 再生可能エネルギーへの予算の割当ては意外に少なかった 2. EPS予想はどんどん下がっている 3. 業界ぐるみの生産調整が必要になる ■オバマ大統領の就任 いよいよ1月20日にバラク・オバマが大統領に就任します。オバマはノーベル物理学賞の受賞者でローレンス・バークレー国立研究所の所長であるスティーブン・チューをエネルギー長官に任命しました。スティーブン・チューは熱心な再生可能エネルギーの支持者で、彼自身、ヘリオス・プロジェクト(太陽光利用燃料製造プロジェクト)の推進者のひとりです。 このため世界の投資家は再生可能エネルギーのストーリーに飛びついていますが、実際には投資家の期待が裏切られる危険性も高いです。事実、先日上院が承認した「経済復興プログラム」に予算計上された再生可能エネルギーへの減税・優遇項目へは200億ドルが割当てられただけで、これは市場関係者の期待を下回る金額でした。200億ドルというと相当まとまった金額のように思えるのですが、実は現在のソーラー・パネルの需要は州政府などが実施している再生可能エネルギー促進プログラムの補助金などに依存している場合が多く、州政府の予算が払底するとともに補助金が底を付くケースが続出しているのです。 またオバマ氏は「経済復興プログラム」の予算を実際に使ってゆく際も「長期に渡り給与水準の高い雇用機会を創出するやり方」で実際のプログラムを進めると公言しており、単にアジアで組まれたソーラー・パネルをそのまま買ってきて据え付けるということはやらないという意味の発言をしています。 ■業績予想は急激に悪化 そんな中で中国のソーラー・パネル・メーカーのリーダーであるサンテック・パワー(ティッカー:STP)には先日、大規模なレイオフの噂が飛び交い、会社側が慌てて事実を訂正する事態になりました。一部で4000人と伝えられた人員削減は「実際には800名程度だ」と会社側はコメントしました。しかしそのコメントをした際に現在のサンテック・パワーの設備稼働率が僅か50~60%に過ぎないという事実が公表され投資家の落胆を誘っています。下のグラフは過去3ヶ月の間に最近の主要ソーラー・パネル関連企業の2009年のEPS予想がどのように推移したかをグラフ化したものです。(去年の10月中旬の時点でのコンセンサスEPS予想を100としています。) このグラフからわかるように最悪のカナディアン・ソーラー(ティッカー:CSIQ)の場合、EPS予想は3ヶ月前の予想の10分の1に減っています。サンテック・パワーも去年の10月のコンセンサスの約28%に過ぎません。ソーラーファン(SOLF)、JAソーラー(JASO)、トリナ・ソーラー(TSL)の予想数字もずいぶん下がりました。唯一、インリー(YGE)とLDKソーラー(LDK)のみが比較的小幅な削減にとどまっています。 次に各社の去年と今年のEPS予想の比較を見ます。こちらもインリーとLDKソーラーを除く全部の企業が前年比でマイナス成長になると予想されています。 ■株価出直りのために必要なこといま太陽光発電セクターに求められていることは乱立するソーラー・パネル・メーカーの生産計画の調整です。それと同時に原材料となるポリシリコンの価格がもっと下がることが必要です。去年の第3四半期の時点では未だポリシリコン価格は高止まりしたままです。
2009年01月20日
-
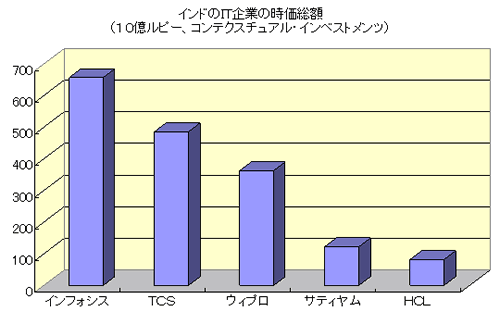
第153回 インドのITアウトソース業界に統合の嵐が来る?
今日のまとめ 1. サティヤムの経営陣の去就が問題になっている 2. ITアウトソーシング業界はM&Aが起こりやすい業界である 3. 厳しい経営環境下、M&Aが重要な企業戦略になる ■M&Aの渦中に放り込まれたサティヤム 前々回のレポートでインドのITアウトソーシング企業、サティヤム・コンピュータ(ティッカー:SAY)が企業統治の問題で急落した事件を紹介しました。その後、この事件に新しい展開がありました。同社は12月28日に予定されていた取締役会を1月10日に延期したのです。同社はそれと同時に株価テコ入れのために何ができるかを検討するためメリルリンチをアドバイザーに指名しました。通常、この手の発表は身売りの可能性を仄めかす意図があります。 今回の事件の後で同社の取締役に名を連ねていたインディアン・スクール・オブ・ビジネス(ISB)のM・ラモハン・ラオ学長はサティヤムの取締役を降りると発表しました。さらに他にも2名の取締役が辞任を発表しており1月10日の取締役会はかなり荒れそうです。 ところでサティヤムの創業会長、B・ラマリンガ・ラジュの一族は同社株の8.6%を所有していることになっているのですが、どうやらラジュはその持株を担保に借金していて、今回、サティヤムの株価が下がったので担保不足になったようです。このためお金を貸していた銀行が場で差し押さえた担保のサティヤム株を処分したのではないか?という報道があります。 ■買収検討に入る企業が後を絶たない 上記のような経緯からB・ラマリンガ・ラジュがサティヤムの経営者として居残る道は極めて険しく、ラジュ一族の持ち株が他の企業に売却される、若しくはサティヤム全体が他の企業の傘下に入る可能性が強まっています。既に多くの企業がサティヤムの値踏みをしていると伝えられていますが、その中には最近、EDSの買収を完了したばかりのヒューレット・パッカード(ティッカー:HPQ)などの大手も含まれて居ます。また海外の企業だけでなくインド国内のライバルであるウィプロ(WIT)なども食指を動かしていると伝えられています。下のグラフはインドのITアウトソーシング企業の時価総額を比較したものです。 サティヤムの株価は例の建設会社買収の発表を契機に大きく下落したのですが、実は業績見通しが悪いのは他のインドのITアウトソーシング企業も皆同じです。実際、過去3ヶ月の業績下方修正幅は下のグラフのようにサティヤムが一番小幅です。このことは他のITアウトソース企業にとってサティヤム買収はアクリーティブ、つまりEPSにとってプラスになる可能性が高いことを意味しています。 ■玉突き的なM&Aの連鎖が起こるか? 先に述べたヒューレット・パッカードによるEDS買収、そして去年の12月に成立したTCS(タタ・コンサルタンシー・サービセズ)によるシティグループ・グローバル・サービセズの買収など、このところITアウトソーシングの業界ではM&Aが続いています。ITアウトソーシング業界ではなぜM&Aが起きやすいのでしょうか?その理由は同業界では長期の役務契約が多いので将来のキャッシュフローが読みやすいことが挙げられます。またひとたびフォーチュン500のような大企業と取引関係ができれば、将来別の色々なサービスを紹介する機会が生まれます。これらのことから買収によりなるべく幅広いサービスを取り揃えた方が事業展開上有利になるのです。さらに事業統合によるコスト削減効果もあります。いまインドのITアウトソーシング企業はどこも売上成長の鈍化に苦しんでいます。そういう環境下で一株当り利益を伸ばす苦肉の策としてM&Aは当然、各社が考える経営戦略だと思います。これらのことから若しサティヤムがどこかに買収されたら、それがきっかけとなって一層インドITアウトソーシング業界の整理統合が進む可能性もあります。
2009年01月05日
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 今日11月21日(金)の天気予報 太平洋…
- (2025-11-21 06:01:45)
-
-
-

- 政治について
- 中国EC大手 「アリババグループ」…
- (2025-11-20 21:20:58)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-20 17:35:54)
-







