2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
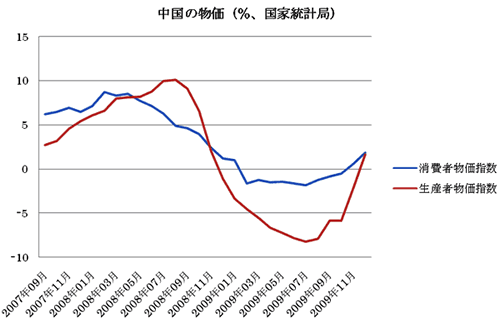
第199回 中国の12月の経済指標
今日のまとめ 1.インフレこそが最大の懸念である 2.その他の統計は申し分なかったインフレが経済政策の焦点に12月の経済統計が出揃いました。今月のデータ・ポイントの中でとりわけ市場参加者の目を引いたのは消費者物価指数ならびに生産者物価指数の急上昇です。消費者物価指数の内訳を見ると食品価格が+5.3%とジャンプしており、ひときわ目立ちます。中国政府にとって食品価格の上昇は民心が最も乱れやすい重要項目ですので、それが急角度で上がり始めたことに神経をピリピリさせていると思います。中国政府は既に対応中!既に中国政府はいろいろな引締め策を繰り出しています。1月13日にはリザーブ・リクワイアメント・レシオを50bp(ベーシス・ポイント)引き上げることが発表されています。リザーブ・リクワイアメント・レシオとは準備率のことを指します。つまり銀行が貸出をする際、貸出総額の一定の割合を中央銀行に「人質」として預けることを義務付けるルールなのです。その準備金の比率を示すのが準備率であり、準備率の引き上げは新規融資を抑制する意図でなされます。さらに中国人民銀行は売りオペにより3カ月物手形金利を数次に渡って引き上げています。前回中国人民銀行が売りオペを実施したのは去年の7月の第一週であり、このときはSHIBOR(上海インターバンク・オファーリング・レート)がオーバーナイト・レートで0.80%から1.1%にジャンプしました。その後銀行融資はざっくりと下がっていることが下のグラフからもわかります。好調なその他の指標その他の12月の経済統計には余りドラマチックな動きはありませんでした。下は小売売上高のグラフです。小売売上高の数字はこれまで若干モタモタした印象が否めませんでした。しかし12月はハッキリとピックアップしています。内訳的には自動車+57.7%、家具+37.6%などの好調が目につきました。ただ上に述べたように中国人民銀行は金融の引締めに転じてきていることから、住宅や自動車などの高額の商品の売れ行きは少し勢いが衰えることを覚悟しておいた方が良いかも知れません。次に鉱工業生産の数字のグラフを示します。ひと足先に1月10日に発表された貿易統計では輸出・輸入ともしっかり戻ってきていることが確認されています。
2010年01月22日
-
第198回 中国のQFII制度の適用厳格化の影響について
今日のまとめ 1.中国政府はQFII制度の適用の厳格化を打ち出した 2.これがA株市場に与える影響は殆ど無いと思われるQFII制度の「又貸し」自粛中国本土株の話題です。昨日、スイスの投資銀行、UBSがQFII(適格外国機関投資家制度)の投資枠の「又貸し」行為を自粛したというニュースが市場に流れました。結論から言えばこのニュースがA株市場に与える影響は殆ど無いと思われます。しかし一般投資家にはわかりにくい話題であり、誤解や不安を招く可能性がありますので解説したいと思います。QFII制度とは?先ずQFII制度のおさらいをしておきます。人民元建てで取引が行われる中国の国内株式市場、つまりA株市場では原則として外人投資家は自由に株を買えない規則になっています。それはなぜかといえば、無制限に外人投資家にA株を買ってよいという許可を与えると海外から資金がドッと押し寄せ、人民元のレートを一定に保つ操作が難しくなるからです。そこで外人によるA株投資は原則禁止とした上で、例外として適格機関投資家と呼ばれる、一定の条件を満たした優良国際機関投資家だけを対象に一定の枠内でA株に投資することが許されています。これがQFII制度なのです。同様の制度は過去にも台湾などでも採用され、新興国が段階的に資本市場を開放してゆく際のひとつの手段と考えられています。現在は世界の投資銀行、証券会社、投資顧問会社などのうち、86社だけが中国のQFIIの免許を持っています。「又貸し」とは?UBSは自社で獲得したQFIIの投資枠を自分自身で使うとともに、余った分を外部の機関投資家に「又貸し」し、A株投資の機会を提供することを行ってきました。ちょうど雨の日に隣人に傘を差し伸べるような行為であることから、これをアンブレラ(傘)という風に呼ぶ場合もあります。この「又貸し」はこれまで法的にはグレーな部分でしたが、慣習としては中国のQFIIはもちろん、他の国のQFIIプログラムでも日常的に行われてきた行為です。中国ではUBS以外にも10社近い投資銀行がQFII枠を「又貸し」していると言われています。しかし10月に中国の当局がQFIIの「又貸し」を禁ずると発表しました。そこでUBSがこの新しい指導を順守するために「又貸し」行為をストップしたというのが今回のニュースというわけです。実はUBSが余った枠を「又貸し」していた先の運用会社を見ると、例えばMCチャイナという機関投資家の名前が見られます。MCチャイナはエジンバラに本社を置くマーティン・カリーという投資顧問会社の中国現地法人です。マーティン・カリーはたいへん業界内でも尊敬されている国際機関投資家のひとつです。事実、マーティン・カリー自体もUBSがQFIIの免許を取った数年後に中国政府からQFIIの枠を貰い受けており、資格と言う点ではすでに合格しているのです。ただ、自分自身で貰った枠と、それ以前に投資銀行から「又貸し」されてきた枠を合算すると中国政府が公認した枠よりも実際には多い金額の投資をしていることになる可能性も出てきます。今回の措置はこのように期せずしてルールの援用があいまいになるのを整理し直すことが目的です。大事なことは海外の投資家に与えられている枠の総量は変わらないと言う点です。現在、QFIIの枠は全部で167億ドルあり、そのうちアンブレラという形で「又貸し」されているのは30億ドル程度に過ぎません。この程度の金額であればアンブレラ解消に伴う売り圧力は限定的であると考えられます。
2010年01月19日
-
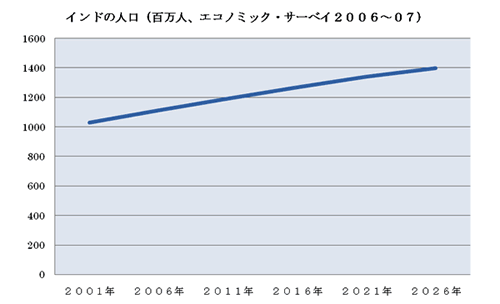
第197回 インドの人口動態について
今日のまとめ 1.インドの人口は若い 2.これから就業人口が増えるので購買力は増える 3.株価水準は割高なので調整を待ちたい■若いインドインドと言えば中国と並んで人口が多いことは皆さんもご存じだと思います。しかし同じ人口が多い国同士でも、その内容はかなり違います。インド準備銀行のKCチャクラバーティの最近のスピーチによると、2020年時点での国民の平均年齢はインドが29歳に対して中国は37歳になると予想されています。つまりインドの方が遥かに若いのです。■人口動態と経済へのインパクトインドで就業人口に達する人口がどんどん増えているということは新しく購買力を蓄えはじめる若いファミリーに対するいろいろな財やサービスの需要が急増することを意味します。その例としてインドではGDPが1%上昇するごとに住宅ローンは3%成長し、教育ローンは5%成長すると言われています。なお 2008年の時点での住宅ローン残高のGDPに占める割合はまだ5.74%に過ぎず、これは先進国や他の新興国に比べても低い数字です。これらの若い勤労層はローンも借りるけれど、貯蓄に対しても積極的です。■恩恵を蒙るセクターインドのこのような人口構成から恩恵を蒙るセクターとしては先ず消費財が考えられます。またこれまであまり浸透していなかった銀行サービスも今後どんどん浸透すると考えられます。問題点としては既にそのような良好な成長見通しを先取りする形で、インドの自動車株や銀行株は極めて高い株価評価がついてしまっている点です。現在の株価水準はそれらのセクターの潜在成長力を超えたレベルになっているので株式市場が調整するのを待ってから投資を検討したいと思います。
2010年01月12日
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- まち楽ブログ
- 山城ガールむつみさんの「北条五代特…
- (2025-11-20 23:23:43)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 今日11月21日(金)の天気予報 太平洋…
- (2025-11-21 06:01:45)
-








