2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
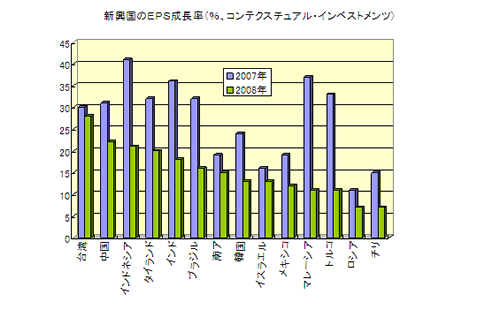
第116回 メキシコの株式市場(その1)
今日のまとめ 1. 現在のメキシコ株式市場の水準は米国経済の減速をかなり織込み済 2. メキシコ企業の多くはアメリカでADRを出している 3. アメリカ・モバイルのリスクは監督当局のルール変更 4. セメックスは米国経済の鈍化の影響を最も受けると考えられている■メキシコ株式市場の現況 今年のメキシコのEPS成長率は12%を予想しています。これは去年の19%成長より低いですが、今年は世界中の国で同様のEPS成長率の鈍化が見られる為、とりわけメキシコだけが悪いということではありません。実際、下のグラフのようにEPS成長率の減速幅はどちらかといえば軽微な方だと思います。 メキシコの現在のPERは約14倍です。去年、メキシコの株式市場は約10%しか上昇しなかったためブラジルをはじめとする他市場との比較では出遅れ感があります。米国の投資家は「米国経済が減速すると先ず真っ先にその影響を受けるのはメキシコだ」と考えており、これが特に去年後半、メキシコ市場が低迷した原因です。ただ、現在の株価水準はかなりそうした悪材料を織り込んだ水準になっていると思います。■メキシコのADR メキシコ企業は古くから米国でADRを出してきました。このため個別に買えるADRの種類も比較的豊富です。 そこで今回と次回の2回にわけて代表的なメキシコのADRを紹介してゆきたいと思います。■アメリカ・モバイル(AMX) アメリカ・モバイルはラテン・アメリカ最大の携帯電話会社です。同社は2000年にテルメックス(TMX)からスピンオフされました。2006年末の時点で1.25億人の加入者数を誇っており、その多くは所謂、プリペイド契約です。主な地域としては: ・メキシコ 『テルセル』(第1位) ・ブラジル 『クラーロ』(第3位) ・アルゼンチン 『CTIモバイル』 ・チリ 『クラーロ』 ・コロンビア 『コムセル』などが挙げられます。売上の46.6%がメキシコ、16.9%がブラジルから上がっています。同社株は潤沢なキャッシュ・フローや安定した成長など、大口の機関投資家が好みそうな特長を多く揃えています。メキシコの携帯電話市場に於けるアメリカ・モバイルの支配力の強さは下の市場占有率のパイ・チャートからも明らかです。 カルデロン政権はポピュリスト的な政策を標榜しており、その一環として大企業の寡占を摘発してゆく構えを見せています。このため携帯電話通話のターミネーション・チャージ(他社の電話ネットワークに回線を接続することに対して支払われる電話会社間の使用料の決済)が見直しされる可能性があります。現在のターミネーション・チャージは下記のようなスケジュールで漸次引き下げられてゆく予定です。しかし今後の展開によってはこのスケジュールにとらわれず一気に料率が引き下げられることも考えられます。 ターミネーション・チャージの大幅変更は必ずしもアメリカ・モバイルにとって一方的に不利になるとは限りませんが、政治的に不透明感が増していることは投資家にとってはマイナス材料でしょう。アメリカ・モバイルの売上高は今年約17%程度の成長、EPSは23%程度の成長が見込まれています。■テルメックス(TMX) 同社は1820万人の加入者を誇るメキシコ最大の固定電話会社で国内の市場占有率は93%です。1990年代前半に同社株がニューヨーク証券取引所に上場された際はメキシコ株ブームの火付け役となりました。しかしアメリカ・モバイルをスピンオフしてからは低成長の公共株として評価されています。テルメックスは2004年にブラジルの長距離電話会社であるエンブラテルを買収しました。現在はテルメックスの海外の資産を別会社として上場する計画が進行中です。同社の今年の売上高成長はほぼゼロで、EPSは8%程度の成長が見込まれています。■セメックス(CX) セメックスはラテン・アメリカ最大のセメント・メーカーです。同社はメキシコのみならずスペイン、ベネズエラ、パナマ、米国などに事業を展開しています。一般にセメントは景気敏感な業種だと考えられており、ラテン・アメリカの株の中ではサブプライム問題に絡む米国経済の減速の影響を最も大きく受ける銘柄であると理解されています。このため同社株は高値から45%程度調整しています。世界的な景気の減速を受けて今年のセメックスの売上、利益成長はかなり苦しいと思われますが現在のPERは8倍程度で取引されており、株価純資産倍率でもほぼ1倍の水準です。同社の経営陣は手堅い経営でウォール街の受けも良いことからいずれ来る景気回復局面では面白い投資機会を提供すると考えられます。今年の売上成長率は約10%程度、EPS成長はマイナスになると予想されます。■フェムサ(FMX) フェムサはラテン・アメリカ最大の飲料の企業です。有名なビールのブランド、『テカテ』、『ドサキ』の他、関連会社、コカ・コーラ・フェムサ(KOF)を通じて清涼飲料のボトリングを展開しています。さらに『OXXO』というコンビニエンス・ストア・チェーンも展開しています。原料費や操業コストの高騰を転嫁すべくフェムサは現在、製品価格を次々に値上げしています。これがどれだけ数量ベースでの売上に悪影響を与えるかが市場から注目されています。同社のビジネスは景気後退に強いディフェンシブな性格があります。今年の売上成長は12%程度、EPS成長は9%程度が予想されています。■グルーポ・テレビザ(TV) グルーポ・テレビザは世界最大のスペイン語圏のメディア・エンターテイメント企業です。メキシコが本拠地ですが広くラテン・アメリカに事業展開しているほか米国でもヒスパニック向けの事業を展開しています。同社の事業の中核をなしているのはテレビ放送で、総売上高の54%を占めています。次に重要な部門はスカイ・メキシコという衛星放送のビジネスで売上の約20%を占めています。その他に出版やラジオ局、番組の輸出などを手がけています。同社の今年の売上成長率は10%程度、EPS成長率は20%程度が見込まれています。
2008年01月21日
-
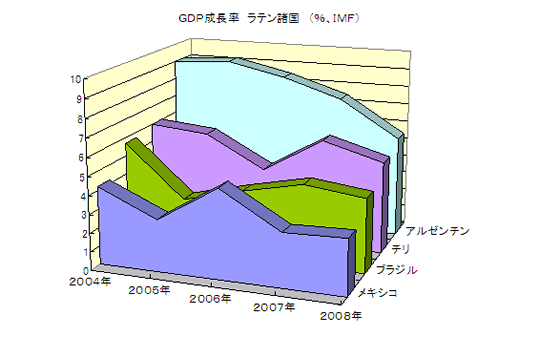
第115回 メキシコの経済
今日のまとめ 1. メキシコでは特権階級と庶民との間に大きな格差がある 2. トルティーア・ショックに代表されるインフレは貧困層の生活を圧迫する 3. 中国の台頭でメキシコは対米貿易における相対的地位の低下を見た■GDP成長率 メキシコはラテン・アメリカ諸国の中でも最も早く、1985年頃から経済改革に取り組みはじめました。しかしその成果は余り芳しくありません。1990年以降のGDP成長率は年率平均3%です。これはブラジルやチリなどの他のラテン・アメリカ諸国と比較しても低い水準です。■所得水準および格差の問題 国民一人当たり所得は2005年の時点で7310ドルであり、これは世界の中では中くらいに位置します。しかし同国は昔から特権階級層と庶民との間に著しい所得格差があり、これは現在も改善が見られていません。このため国民の約45%は貧困層に属しています。 下のグラフはどのくらい所得格差があるかの尺度であるジニ係数のグラフです。数字が大きければ大きいほど格差社会であると言えます。■インフレ IMFはメキシコの去年ならびに今年のインフレ率をそれぞれ3.9%、4.2%と予想しており、これは安定的な数字と言えます。 但し去年は世界的に穀物の価格が上昇しました。このためメキシコ人の主食であるトルティーアの値段も騰がりました。所謂、「トルティーア・ショック」です。食品の価格上昇はとりわけ貧困層の生活を圧迫します。■貿易 メキシコは米国に隣接しているので貿易に際しては諸外国より地の利があります。実際、メキシコの輸出の8割は米国向けです。しかし、最近では中国の台頭でメキシコの影が薄くなっています。下のグラフは米国の輸入に占める中国とメキシコの比率を示していますが中国がどんどんシェアを伸ばしている一方でメキシコの地位は低下していることがわかります。いまメキシコは原油などの輸出商品を持っていることを考えれば加工品などの比較的付加価値の高い商品分野でのメキシコの競争力低下は一層著しいと憶測されます。■米国経済の減速 サブプライム問題による米国経済の減速はメキシコ経済にも影響を与えることが予想されます。ただ、近年はメキシコのみならずラテン諸国全般に対外債務を大幅に圧縮したため、以前のように資本逃避を誘発するリスクはありません。メキシコの経常収支は同国が経済改革に乗り出した1990年代初頭にどんどん悪化し、これがペソ危機の原因のひとつとなりましたが、近年は着実に改善してきました。この理由は原油の輸出(GDPの2.7%程度に相当します)の好調ならびに米国に出稼ぎに行っているメキシコ人からの母国への仕送り(同じくGDPの2.7%に相当します)が寄与しているからです。 問題は今後メキシコの主力油田であるカンタレル油田の生産量が落ち込んだ場合、国庫の歳入ならびに外貨獲得の低減をどう埋め合わせするかということです。カンタレルは2004年のピーク時には日産210万バレルを超える生産量がありましたが現在は150万バレルを割り込んでいます。さらにメキシコは外国からの直接投資(FDI)の誘致に余り成功していません。最近のFDIのGDPに占める比率は2%程度です。また主要新興国では唯一、直接投資が先細りになっている国だという点も気になります。
2008年01月08日
-
第114回 メキシコの歴史
今日のまとめ 1. スペイン統治下での経済政策が封建的な地主制度のはじまりだった 2. メキシコ株ブームは米国投資家の新興国投資の火付け役となった 3. 格差是正の遅れがチアパスの蜂起を誘発した■古代文明 メキシコには古くから幾つもの重要な古代文明が栄えていました。紀元前1200年頃にメキシコ湾岸のサン・ロレンツオならびにラ・ベンダなどを中心としたオルメカ文明がその最初のものです。オルメカ文明は高さ3メートルもある巨石人頭像で有名です。またユカタン半島では紀元前200年頃からマヤ文明が栄えました。同じ頃、オアハカではサポテカ文明が栄えます。さらにメキシコ中央高原ではティオティワカン文明が紀元後200年頃展開しました。これらの文明の最後を飾るものが13~16世紀にわたって栄えたアステカ文明です。■スペインの登場 1519年、スペインのエルナン・コルテスが軍隊を率いて到着し、2年にわたる戦争の末、アステカはスペインに征服されます。スペインは君主国家制度のもとではじめて様々な王国がひとつの国家の下に統一されるわけです。征服者のスペインは軍功のあったスペインの兵隊に土地を与え、これが後々までメキシコの社会に影響を残す封建的な地主制度のはしりとなりました。エンコミエンダ制度と呼ばれるこの制度のもとでは農民は特権階級の地主の「私有物」として扱われ、貧富の差が生じました。■独立 1810年頃までにはそういう体制に対する不満は極点に達していました。ナポレオン戦争で欧州が混乱した機にメキシコは独立を成し遂げるわけです。しかし独立後も外国からの干渉は絶えず、1848年にはそれまで自国の国土であったテキサスやカリフォルニアなどの土地をアメリカに奪われます。■メキシコ革命 19世紀を通じてメキシコの大部分の国民は私有財産権を認められず、基本的人権も保障されていませんでした。そうした扱いに対する反感から10年に及ぶ内戦が続き、1917年に漸く憲法が制定されます。この一連の内戦をメキシコ革命と呼びます。メキシコ革命を推進したのはPRI(制度的革命党)と呼ばれる政党です。■ラテン融資ブーム PRIは保護主義色の強い、「大きな政府」による経済運営を目指します。しかし20世紀終盤までには「平等と成長」というPRIの政策目標は忘れられ、再び特権階級中心の、沈滞した経済になりました。1970年代のオイル・ブームで巨額のオイルマネーが米国のマネー・センター銀行に預金され、その余資活用先としてラテン・アメリカ諸国への融資ブームが起こります。メキシコもこのブームで大量の対外債務を抱え込むことになりますが1980年代に入ってからの原油価格の低迷でラテン・アメリカの諸国は債務危機を経験します。■メキシコ株ブーム この債務危機の解決法としてブレディー・プランが採用され、ラテン諸国はIMFなどが主導する所謂、ワシントン・コンセンサスに基づいた経済の建て直し策を採用します。メキシコはラテン・アメリカの諸国の中でも最も早く、1985年から経済改革に取り組みます。1988年の選挙で大統領に選ばれたカルロス・サリナス大統領はハーバード大学卒業で、勤勉だったことから一躍メキシコ国民ならびにウォール街のバンカー達の希望の星となります。サリナスは国有企業の民営化を推進し、保護貿易主義を排します。国有企業の株式化が債務のリスケジュールとセットになっていたことからメキシコ株ブームが起こります。サリナス大統領はNAFTA(北米自由貿易協定)を強力に支持し、これが投資家にとってひとつの目標となりニューヨーク市場ではメキシコ株ADRのIPOが相次ぎます。それまでの米国の投資家はどちらかと言えば海外投資に対する関心は低く、その意味では「井の中の蛙」のような存在でした。このメキシコ株ブームが多くの米国の投資家にとってはじめての国際分散投資体験となったわけです。■ペソ危機 NAFTAは1994年1月に発効しますが、メキシコ株式市場は高値波乱の局面に入ってゆきます。それというのもNAFTAについてはメキシコ国内では賛否両論あり、特に貧しい人々にとっては損な取り決めだという不満がありました。この国民感情を代弁する格好で南部のチアパス州でサパティスタと呼ばれる革命運動が蜂起します。このサパティスタというのは1910年台のメキシコ革命の時代の「革命の志士」、エミリアーノ・サパタの名前を借りた運動であり、その指揮にあたっているのは「マルコス副司令官」というあだ名の、正体不明の運動家で、頭からすっぽり黒い覆面を被ったその容貌は世界の投資家を震撼させました。このサパティスタ運動はメキシコの軍隊によって数日のうちに制圧されるのですが逃げ足の速い国際投機資金によって演出されていたメキシコのブームは終焉します。これが所謂、「ペソ危機」の顛末です。
2008年01月07日
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- ひとり言・・?
- PC入力時の手首・肘用ゲルクッション
- (2025-11-19 22:39:26)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-20 17:35:54)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- 今日は、歌舞伎座開業記念日ですよ!…
- (2025-11-21 06:30:05)
-







