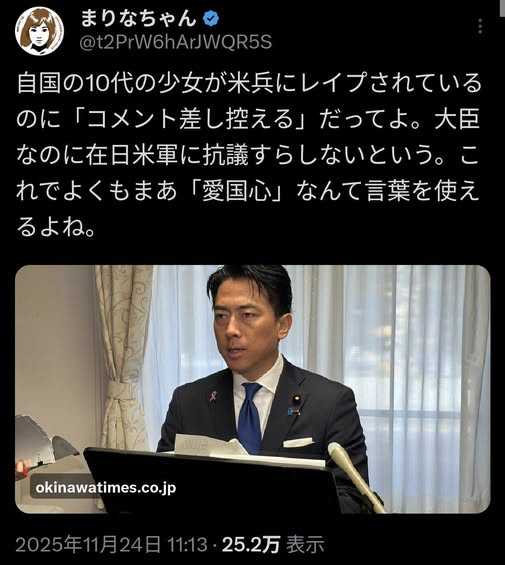-
1

手塚治虫「火の鳥」展
手塚治虫「火の鳥」展——火の鳥は、エントロビー増大と抗う動的均衡=宇宙生命の象徴——生物学者・作家 福岡 伸一 争いの歴史、生命と科学マンガを今読み返す意味 マンガの神様、手塚治虫(1928~89)のライフワークであったマンガ作品『火の鳥』を回顧し、その代表的意味を考える「火の鳥」展が、六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで開催されており、その企画・監修を務めた。エピソードには、光とkが焼を身にまとった不死鳥『火の鳥』が登場する。人々は、その生き血を飲めば不老不死が得られると信じ、必死に追い求めるが、果たされることはない。『火の鳥』全編に流れる通奏低温としてのテーマは、「生命とは何か」あるいは「生きることと死ぬことの意味は何か」という極めて哲学的な問題である。人類の歴史が始まって以来、私たちが求め続けた最も深遠な問題でもある。『火の鳥』の物語の中には、一貫した生命観・世界観がある。生命は、常に姿を変えながら、連綿と受け継がれてきたし、これからも続いていくという輪廻転生の生命観である。そして生命は、粒子的エネルギーとして、離合集散を繰り返しながら、あらゆるもの、あらゆる場所に建言するという汎神論的な世界観である。これは私の生命学である動的平衡論とピタリと重なる。生命は、絶えず自らの破壊と創造を繰り返しながら、エントロピー増大の法則に抗い続けているダイナミックな統合体、すなわち「動的平衡」であり、「動的平衡」としての生命はミクロの粒子として、拡散と収斂の中で、生命進化的の間を流れ続けるものである。私自身『火の鳥』と共に育ったと言ってよい。1970年、EXPO‘70が開催され、未来を夢見ていた10歳の少年は、『火の鳥』鳳凰編に出会って衝撃を受けた。こんなに深く人生を洞察したマンガを読んだことはなかった。以降、新刊が出るたびにわくわくしながら読んだ。つまり私は『火の鳥』世代のど真ん中にいた。大いなるオマージュを込めて、この展覧会の仕事をお引き受けした。そこで、動的平衡と、手塚治虫自身の造語である宇宙生命(コスモゾーン)を重ねて、展覧会の副題を作った。火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡=宇宙生命(コスモゾーン)である。火の鳥は、生命エネルギーの媒介者として、あらゆる時空に出現し、そこに命を吹き込むものだからである。火の鳥は、文字通り、鳥瞰的な存在として、人間のおかしな行為に対して一種の「メタ視点」を与えるものとして描かれている。それは国を巡る覇権争いでも(黎明編)、源平の合戦でも(乱世編)、無謬を誇るAI同士が対立の末、核戦争に突入する35世紀(未来編)でも同じである。宇宙的視点に立てば、人間的対立は取るに足らないものとして昇華できるはずだという手塚自身の希望が託されている。また『火の鳥』は、AIによる支配、クローン人間の是非、ヒトとロボットと人間、生命倫理の問題に鋭く切り込む。これはまさに今、私たちがより具体的に直面している問題である。いまいちど『火の鳥』を読み返す現代的な意味がここにある。ぜひ感情にお越しください。(ふかお・しんいち) 【文化】公明新聞2025.4.16
November 27, 2025
閲覧総数 18
-
2

策や要領のみの人生は、結局は行き詰まる
虚栄や策、慢心を捨てた「謙虚な心」。これほど強いものはない。最終的に頼りになるものはない。「謙虚な心」には余裕が生まれる。「傲れる心」には焦りのみが募る。「余裕の人」は自分を客観視し、そこから知恵が生まれる。信頼と安心感を育む。ゆえに勢いが出る。「焦りの人」は正確に物事を見ることができない。愚痴と不安を育て、周囲には迷いばかりが増す。ついには自分をも見失ってしまう。自分が見えなくなった人に、本来の自分の力も、他人の力も引き出せないのは当然である。 ありのままの自分となって、「十のものを十だけ出し切っていく」。その必死の「一人」に信頼は集まり、強固な結束が生まれる。そして、不敗の「勝利チーム」が形成されてゆく。 だが、持てる「十を出し切る」ことは決して容易ではない。人間はどこかで力を抜き、余力を残しているものだ。それこそ命懸けの必死の戦いでなければ、本当の爆発力は出てこない。 ある意味で、信心とは“手抜き”をしないことである。誰が見ていようといまいと、また、誰が何を言おうと、自分は自分らしく全力を尽くしてゆく。そこに信仰者の強さがある。今日の学会の発展も、全て「懸命な日々」の結実であり、勝利であった。 私もこれまで「まず自ら動く」「ベストを尽くす」「寸暇を惜しんで働く」――率先してこの姿勢に徹してきたつもりである。 策や要領のみの人生は、結局は行き詰まり、自ら墓穴に入るであろう。人生と一念を真っ直ぐに広布に向け、ひたすら行動してゆくところに、最高の充実と満足がある。限りなく力が湧いてくる。 ともあれ、本当の「自分」を発揮している人は美しい。輝いている。また、着実に勝利の人生を築いている。【京都平和講堂落成祝賀 京都記念幹部会 1989-10-18 京都平和講堂】
August 7, 2012
閲覧総数 307
-
3

一切を御本尊に任せて勝つ
長い人生、生老病死の苦悩は、誰人も避けられない。家族の病気で悩む場合もあろう。しかし、我らには妙法がある。苦しい時こそ御書を拝し、一切を御本尊に任せていくのだ。「南無妙法蓮華経は師子吼の如し・いかなる病さはりをなすべきや」(同1124頁)と断言なされているではないか。変毒為薬の仏法である。必ず打開できる。題目の師子吼を轟かせ、「常楽我浄」という永遠の幸福の軌道を勝ち開いていくのだ。【池田名誉会長が贈る「勝利の人間学」】創価新報2015.2.4
February 21, 2015
閲覧総数 4176
-
4

なぜ『祈り』は叶うのか――【教学】聖教新聞09・6・23
◎全宇宙に届く人間の一念一切を動かす妙法の力用池田名誉会長は次のように述べています。「大宇宙は、瞬時も止まることなく、妙なる音律を奏でながら運行している。その究極の力、法則こそ南無妙法蓮華経なのである。題目をあげ、妙法に生き抜くならば、この大宇宙のリズムに自身の生命が合致していく。宇宙の最極の力と智慧をわが身に顕現することができる。戸田先生は語っておられた。『この大宗教(日蓮大聖人の仏法)を信ずることによって、生命のリズムは宇宙のリズムに調和して、生きている幸福をしみじみと感ずるのである。生命の歓喜こそ、幸福の源泉力である』『幸福を感じ、幸福な人生を営む源泉は、われわれの生命力である』大宇宙が味方である。諸天が守る。広宣流布に尽せば、最高の功徳を得ることができる。その福徳は、子孫末代にまで伝わっていく」(つづく)
July 27, 2009
閲覧総数 913
-
5

見宝塔品第十一㊤
第15回 見宝塔品第十一㊤自行化他にわたって妙法を唱えるとき私たちの生命が宝塔となる■大要「見宝塔品第十一」では、冒頭、七宝で飾られた巨大な宝塔が大地から涌現し、空中に浮かびます。その塔の中から「多宝如来」が、釈尊の説法が真実であると証明します。さらに、会座に集った人々を、仏が神通力で虚空へ浮かび上がらせます。ここから説法の場が「虚空会」になります。そこで釈尊は、「六難九易」等を通して、滅後の法華弘通を進めます。それでは内容を追ってみましょう。 ●シーン1仏の前にこつぜんと、高さ500由旬、縦横250由旬もの、金・銀・瑠璃などの七宝で飾られた巨大な宝塔が、大地から涌現し、空中に浮かびます。(由旬はインドの距離の単位。1由旬とは帝王が1日に行軍する道のりとされ、およそ10キロメートルと考えられている)すると、その時、宝塔の中から大音声(だいおんじょう)が聞こえてきます。「すばらしい。すばらしい。釈尊は、よくぞ法華経を大衆のために説いてくださった。その通りです。その通りです。あなたが説かれたことは、すべて真実です」会座の四衆(出家・在家の男性と女性)は、宝塔が空中に浮かんでいるのを目の当たりにし、その中から響く声を聞いて喜び、また驚きつつ、宝塔に合掌します」 ●シーン2その時、大楽説(だいぎょうせつ)菩薩が、人々の疑念を知り、釈尊に問います。「どういうわけで、宝塔が大地から現れ、その中から声を発せられたのですか」釈尊は答えます。「この宝塔の中には、多宝如来という名前の仏様がおられる。この仏さまは、かつて菩薩の道を修行していた時に、大きな誓いを立てたのです。『法華経が説かれる所があれば、私はその塔の前に現れ、証明役となって、すばらしい、すばらしいと讃嘆しよう』と。だから今、法華経が説かれるところの場所に、多宝如来の塔が出現して、『すばらしい。すばらしい』と、讃嘆したのです」 ●シーン3それを聞いて、大楽説菩薩は、釈尊に要請します。「私たちに、多宝仏の姿を見させてください」釈尊は、大楽説菩薩に告げます。「この多宝仏には、『釈尊の分身となって十方世界(全宇宙)で法華経を説いている仏をすべて呼び戻したならば、私は姿を現そう』との深き願いがあるのだ。今、十方世界で説法している私の分身を集めようと思う」ここから、いわゆる「三変土田」が始まります。――まず、釈尊は、分身の諸仏が集まってこられるように、今いる娑婆世界を清浄にし、不信の人界・天界の衆生を他の国土に移して、分身の諸仏を集めます。しかし、入りきれなかったため、さらに2度にわたって、八方それぞれの二百万億那由他という無数の国土を清浄にして、人界・天界の衆生を他の国土に移し、十方の世界の諸仏を集め、一つの国土に統一しました。このように、3度にわたって国土を清めたことを「三変土田」といいます。 ●シーン4釈尊は、一堂に会した十方の世界の分身の諸仏が、〝宝塔の扉を開いてほしい〟と望んでいることを知り、空中に浮かびます。人々は起立し、合掌して、その模様を見つめています。釈尊は右の指で、宝塔の扉を開きます。すべての聴衆は、宝塔の中に多宝仏の姿を見ます。さらに、「すばらしい。すばらしい。釈尊は快く法華経を解いてくださる。私は法華経の説法を聞くために、ここに出現したのだ」と語るのを聞きます。 ●シーン5その時、宝塔の中の多宝仏は、自分の座っていた場所の半分を釈尊に与えて語ります。「釈尊よ。この場所にお座りください」釈尊が宝塔の中に座ります(二仏並座)。人々は「仏は高く遠い所にいらっしゃる。どうか仏の神通力によって、私たちを空中に引き上げてください」と願います。釈尊はその思いに応え、神通力によって大勢の人々を空中に引き上げると、大音声で皆に告げます。「だれか、この娑婆世界で、広く法華経を解くものはいないか。私は、もう長くは生きていない。法華経の弘通を託したいのだ」ここから、「嘱累品第二十二」まで空中での説法が続きます。これを「虚空会の儀式」と言います。 ●偈文これまでの説法の意義を繰り返して、偈(詩句の形式)として説かれます。見宝塔品では、ここに「令法久住」や「六難九易」「此経難持」といった大切な法理が示されます。該当の個所を追ってみます。◇宝塔が出現し、十方の諸仏が集まったのは何のためだったのでしょうか。それは「令法久住(法をして久しく住せしめん)」(法華経387㌻)のためであったと記されています。未来永遠にわたって妙法が伝えられるようにするためであったのです。さらに、仏の滅後に法華経を持ち弘めることが、他の経典に比べて、いかに難しいかを「六難九易」を挙げて説かれています。法華経では「諸余の経典は 数(かず)恒沙(ごうしゃ)の如し 此等を説くと雖も 未だ難しと為すに足らず」(390㌻)から「我滅して後に於いて 若し能く 斯く如き 経典を奉(ぶ)持(じ)せば 是は即ち難しと為す」(393㌻)までの箇所に、九つの易しいことと、六つの難しいことが具体的に記されています。それを受けて「此経難持(此の経は持ち難し)」(同㌻)と、仏の滅後に法華経を受持することがいかに困難であるかが示されています。だからこそ、法華経を受持しゆく大願を起す人こそが、無常の仏道を得ることができると教え、「自説誓言(自ら誓言を説け)」(同㌻)と、誓願を勧めているのです。(㊦に続く) 『法華経の智慧』から限りなく境涯が広がる妙法蓮華経の説法によって、妙法蓮華経の宝塔が涌現する。私どもが自行化他にわたって妙法を唱えるとき、私たちの生命が宝塔となる。宝塔が出現する。唱えられる法も妙法蓮華経。唱える私たちも妙法蓮華経です。◇依正不二ですから、我が身に宝塔を開けば、我が生きる世界も宝塔の世界であり、「宝塔の中に入る」ことになる。御本仏の世界の一員として、自在に活躍しているということです。このちっぽけな自分という身が、七宝で荘厳され、大宇宙へと限りなく境涯が広がるのです。これほどすばらしいことはない。◇広布への行動によって、初めて「法等」は立つ。観念ではない。現実との格闘であり、大難との真剣勝負です。そこに「聞・信・戒・定・進・捨・慚」の七宝で飾られた自分自身と輝くのです。 七宝わが身を輝かせる 「見宝塔品」に出てくる巨大な宝塔は、金・銀・瑠璃などの七宝で飾られていました。それは、尊厳なる生命を表現しているといえます。大聖人は、この七宝について「聞・信・戒・定・進・捨・慚」であると示されています(御書1304㌻)。「聞」とは、正法を求め聞き学ぶことです。「信」とは、妙法を信受することです。「戒」とは、末法にあっては妙法を受持することです。「定」とは、不動の心を確立することです。「進」とは、精進のことです。「捨」とは、煩悩などを捨てることです。「慚」とは、反省し、求道心を絶やさないことです。つまり、この七つの修行、私たちにとっては、自行化他にわたる唱題行によって、自分自身の生命を最高に光り輝かせていくことができるのです。 【ロータス ラウンジ Lotus Lounge 法華経への飛び】聖教新聞2020.6.16
April 28, 2021
閲覧総数 559
-
6

友岡雅弥さんのセミナー2
大事なのは相手をガンガンやるのではない。生き方を見直してもらいたいのです。生き方が変わらなかったら折伏ではない。信心して、「ああ、大事なことはお金儲けじゃなかったんだなー」、ここからがほんとの折伏です。 ガンガンいくか、ゆっくりいくかは関係ない。しんどいから、後ろさがるんじゃない。後ろにさがることができるのかどうかです。 私は海外の来客があって、信心を語るときまず、京都に行きます。京都の寺めぐりをするのです。はじめに太秦の広隆寺。日本の菩薩の第一号のあるところです。来客は喜びます。 像の顔は朝鮮系でなんです。そもそも太秦=ペルシャの意です。 そこで、庭掃除のおっちゃんに聞いてくださいといいます。 「信者何人いるのか?」 答えは「ゼロ」です。信者ゼロの宗教です。観光客で食べている。それはもう、博物館であり、宗教施設じゃない。 次は南禅時。徳川幕府、立派な建物。 「説明書きを読んでください」(英字でも書いてあります) 「○○将軍寄進」「△△天皇建立」 金閣寺でも、銀閣寺でも、□□将軍、◎◎将軍・・・・。パリの大聖堂では、「パリ市民がつくった」と書いてる。権力者が喜ぶ必要なんてない。そんなものではない。 だんだんガッカリされている来客を、今度は創価会館に連れて行く。おばちゃんがいっぱい。信者だらけである。他は観光客だらけで、修行者の声は聞こえない。 美術、芸術はすごいが博物館以外の何ものでもない。創価学会はすごいですね。生きていますね。と入信。 邪宗に連れていくことが折伏になる場合もある。見識のキッチリある人であればです。 人によっては、他の寺のすばらしい門を誉め、折伏につながる場合もあるということです。【つづく】
April 10, 2006
閲覧総数 1352
-
7

「私が体験から学んだこと」高山直子
11.「どうすればいいんでしょう」ときくと先輩は「仏界の生命を出すんだよ。そうしたら結核などは治る」といわれました。「どうすれば出ますか」ときくと「信心強きを名づけて仏界となすとあるが、信心強いということは広布のために闘うことだよ」といわれました。そうかと思いました。 次の日。そのころは、もう結核菌をばらまいておりませんでしたから、院長先生のところに行っていいました。「思うところありまして、本日で退院させていただきます」と。(笑声)それで、私は退院して、以後、学会活動をやる人生を始めたわけです。そして今は、妙法の「今くるよ」と名前がつきまして(笑声)。……それぐらい肥えてやっているというのが、私の体験談でございます。(おわり)
August 2, 2006
閲覧総数 2508
-
8

山田秀三のアイヌ語地名研究
山田秀三のアイヌ語地名研究千葉大学名誉教授 中川 裕蝦夷と呼ばれる人たちは、8世紀頃には太平洋側は仙台の北あたりまで、日本海側は秋田県・山形県堺の雄勝峠あたりにまで広がっていた。そして、それとぴったり重なるようにアイヌ語期限と思われる地名が色濃く分布していることを実証的に明らかにしたのは、山田秀三(1899~1992)である。現在でも、北海道の地名の8割はアイヌご機嫌だと言われているが、アイヌ語の地名はもともと「大きな川」や「桂の木の生えている処」などのようにその土地の地形や植生などに基づいてつけられたもので、固有名詞というより土地の説明といったほうが近い。したがって同じような特徴を持った土地は似た名前で呼ばれることになる。山田は東北と北海道で共通する地名の現地に赴き、その地名が何を表しているのかを自分の目で確認し、古老からそこにどのようないわれがあるかを聞き歩いた。それがアイヌ語の単語の意味や文法にピタリと合うと確信が持てたところで、アイヌ語地名であると判断を下した。実証的に、とはそういうことである。その一つの霊が青森県三内丸山遺跡の三内の解釈である。内という感じで表されるナイは北海道の地名にも数多く見られ、アイヌ語で「川、沢」を表す。一方、サンは「山を下る、前に出る」という意味だが、「出る川」では何が出るのかわからない。そこで山田は何か主語が省略されているのではないかと考えた。彼は東北・北海道のサンナイに似た名を持つ土地をつぶさに歩き回り、すべて大水・鉄砲水が「出る」川だという確証を得た。その名をつけた人たちには、何が出るかは自明だったわけだ。こうして三内もアイヌ語地名だということがはっきりした。このような膨大な手間暇をかけて、山田はアイヌ語地名の南限が蝦夷の居住域と一致するという結論を出したのである。 【言葉の遠近法】公明新聞2025.4.16
November 27, 2025
閲覧総数 23
-
9

魔界入り難し
魔界入り難し日本近代文学研究者 上田 正行 川端文学を説く難問の一つにドッベルゲンガー(分身)がある。駒子と葉子(「雪国」)、千重子と苗子(「古都」)のように。これと連動するような難問が「仏界入り易く魔界入り難し」である。川端康成の愛読者ならば、すぐに気づくであろうが一般にはノーベル文学賞受賞記念の講演、「美しい日本の私」で披露された言葉である。(昭和43年12月)。川端は一休禅師の言葉として引用しているが、一休の研究家・柳田聖山氏の言によれば、一休没後の言葉のようである。川端は講演で一休の書を二幅所持しており、その一つが「佛界易入(いりやすく)魔界難入(いりがたし)」であると言う。真筆ならば一休その人の言葉となり、没後の言葉ならば、偽筆ということになる。真贋は一先ず置くとしても、この言葉のリアリティは矢張り、凄いと言わざるを得ない。一般には魔界は入り易く仏界は入り難しのはずであるが、その逆である所が如何にも禅家の言らしい。渤海が入り易ければだれも苦労はしないし、魔界など見たくもないというのが一般の人の気持ちであろう。しかし、川端は敢えてこの一休の提唱にすがろうとする。余程、気に入ったのか、書でもその独特な書体でこの八文字を書いている。その痩躯に似合わない骨太な字である。この提唱を作品化したものの一つに「みずうみ」(昭和29年)がある。桃井銀平という名前も凄いが女子生徒久子や町枝に執着する妄念も尋常ではない。川端の読者が離れていったというのも頷ける。母の里の湖、父が変死した湖に深い謎があるのであろうが、銀平には癒されることのない深い心の傷、悲しみがあることも理解できる。魔界即仏界と「往生要集」は言うが、究極の禅の悟りでは「佛界易入魔界難入」も同じことかもしれない。後者の公案が解ければ、一視同仁、仏界、魔界の差別はないはずである。 【言葉の遠近法】公明新聞2020.11.11
November 4, 2021
閲覧総数 1077
-
10

報恩抄
報恩抄創価学会教学部編建治2年(1276年)7月、日蓮大聖人は出家の際の師匠であった道善房の死去の知らせを受け、その報恩と追善供養(死者の冥福のための祈念・仏事)のために、「報恩抄」を著されます。 「報恩抄」を御執筆同抄の冒頭、報恩の道理を明かし、「仏教をなら(習)わん者の、父母・師匠・国恩をわす(忘)るべしや」(新212・全293)と、仏教者は恩を知り、恩を報じなければならないことが示され後、報恩を行うために仏法を徹底的に学んで「智者」となることが重要であることを明かされます。そして、仏法を学んだ結果として、釈尊が生涯にわたって説いた諸経の勝劣を判定し、法華経が最も優れていると示されます。ところが、諸宗の祖師は法華経を誹謗するという謗法を犯し、「諸仏の大怨敵」となってしまっていると指摘し、その諸宗の謗法について、詳しく論じられていきます。法華経が最も優れていることを否定する謗法を犯す者は仏の大敵だということが、仏法の「第一の大事」なことだと示されます。このため、釈尊の時代から大聖人御在世の当時に至るまでインド・中国・日本の三国にわたる仏教を略述し、法華経が最高の経典であることを示した釈尊・天台大師(智顗)・伝教大師(最澄)の実践と、それによって起こった難を示されています。 慈覚・智証を破折この後、真言(密教)の謗法の破折へと進まれます。真言破折の分量は本抄全体の半分に及びます。弘法(空海)を開祖とする真言宗の破折とともに、密教化した天台宗を徹底して破折されます。師である伝教大師に敵対したものとして、その直弟子である第3代座主の慈覚(円仁)やその孫弟子である第5代座主の智証(円珍)を取り上げられています。伝教大師は、大日経は法華経に劣る教えであると判定し、真言を独立した宗として認めませんでした。一方、弘法は真言宗を立て、「第一真言・大日経、第二華厳・第三は法華・涅槃」(新229・全305)という誤った主張をします。大聖人は、慈覚・智証が「真言の方が優れている」と言ったり、「法華経の方が優れている」、あるいは『法華経に対して大日経は理同事勝〈注1〉である』と言ったりしていると記されます。また、「二宗の勝劣を論ずる人は勅宣(=天皇の命令)に背く者である」と言っていることから、「これらは、みな自語相違と言うほかない」(新231・全307、通解)と述べ、彼らの師である伝教大師の教えに背いていると指摘されています。慈覚と智証は、天台宗の座主として日本仏教界で大きな影響力を持っていました。大聖人は、このような慈覚・智証の主張と行動の結果、日本中の人々が法華経よりも密教を重んじて謗法に陥ったと糾弾されています。 天台・伝教が弘めなかった教え 三大秘法を明かすこのように、謗法の人々が不幸と社会の災難の根源であることを示し、「このひと、仁保国の中にただ日蓮一人ばかりし(知)れり」(新251・全321)と宣言されています。これは「報恩抄」の冒頭に言及されたように、「仏法をなら(習)いきわ(極)め智者と」(新212・全239)なったことを示されるものです。続いて大聖人は、末法に法華弘通を行えば為政者から迫害があると覚悟し、不惜身命で弘教を開始された御心境を述懐されます。伊豆流罪、さらに竜の口の法難、佐渡流罪へ至る大難の日々を回想されるとともに、その行動は、「父母のオン・師匠のオン・三法の恩・国の恩をほう(報)ぜんがため」(新253・全323)であったことを明かされます。そして、法華経の肝心は題目(経典の題名)の南無妙法蓮華経であり、それは、法華経の肝心であるとともに、釈尊が説いたあらゆる経典(一切経)の肝心でもあり、一切経の功徳の力用を全て具え、諸経の題目とは比較にならないほど優れていることを示していかれます。その上で、「天台・伝教の弘通し給わざる正法ありや」(新260・全328)との問いを立て、「有り」(同)とされ、末法の一切衆生のために初めて弘通される、未曽有の大法たる三大秘法を説示されます。すまわち、天台・伝教が弘通しなかった正法、三大秘法の具体的な形を次のように明かされます。「一には、日本乃至一閻浮提一同に、本門の教主釈尊を本尊とすべし〈注2〉。いわゆる宝塔の内の釈迦・多宝、ほかの諸仏ならびに上行等の四菩薩、脇士となるべし。二には、日本乃至漢土・月氏・一閻浮提に、人ごとに有智・無智をきら(嫌)わず一同に多事をす(捨)てて南無妙法蓮華経と唱なうべし」(新261・全328)と。大聖人は、この三大秘法は「いまだひろ(広)まらず」、しかも「一閻浮提の内に仏の滅後二千二百二十五年が間、一人も唱えず」(同)と、弘通もされず、実践する人もいなかったと指摘されます。だからこそ、「日蓮一人、南無妙法蓮華経・南無妙法蓮華経等と声もお(惜)しまず唱うるなり」(同)と、大難を覚悟で、ただ一人、大法弘通に立ち上がったと仰せです。そして、「日蓮が慈悲嚝大ならば、南無妙法蓮華経は万年の外未来までもながる(流)べし。日本国の一切衆生の盲目をひら(開)ける功徳あり。無間地獄の道をふさ(塞)ぎぬ」(新261・全329)と断言し、日蓮大聖人こそが、末法の全ての人を救う教主であることを明かされます。 「花はね(根)にか(帰)えり、真味は土にとど(留)まる。この功徳は故道善房の聖霊の御身にあつ(集)まるべし」 さらに、広宣流布の「時」の到来は必然であり、必ず実現して、日本国の人々は一致して南無妙法蓮華経と唱えると宣言されます。最後に、大聖人が法華経を忍難弘通する功徳、また未来に広宣流布して人々を救っていく功徳の全てが、師匠である道善房に帰していくと結ばれています。「花はね(根)にか(帰)えり、真味は土にとど(留)まる。この功徳は故道善房の聖霊の御身にあつ(集)まるべし」(新262・全329)と。——このように大聖人が、仏法の正邪を人々に示そうとされる中、これまで、大聖人を敵視し迫害の糸を引いてきた極楽寺良観(忍性)が、今度は大聖人門下の信心を破ろうと狙ってきます。 弟子たちが言論戦を展開 退転者たちの動き日蓮大聖人が身延に入られてしばらくした頃のことです。鎌倉の四条金吾が「名越のこと」(新1546・全1137)について、何らかの報告をしたようです。「名越のこと」とは「名越の尼のこと」とも考えられます。名越の尼は、文永8年(1271年)の竜の口の法難・佐渡流罪の時期に退転したと考えられていますが、大聖人は「おお(多)くの人をおと(落)とせしなり」(新1867・全1539)と、自らが信仰の道から退転しただけでなく、多くの人を退転させた者として記されています。四条金吾が「間越えのこと」を話題にしたのも、退転者たちに何らかの動きがあったかもしれません。 門下が狙われるその他にも門下を狙った動きがありました。その背後に、黒幕の一人として、良観がいたと大聖人は推測されています(新1583・全1163等、参照)。大聖人が佐渡から無事帰還し、他国侵逼難の予言が的中して、世間の注目の高まる中、日蓮門下の動向は、良観のみならず、諸宗にとって目障りなものであったと考えられます。文永12年(1275年)に鎌倉の極楽寺から出火し、堂舎が炎上します。また、良観を講演していた鎌倉幕府でも御所(将軍の住居)で火災が起きたようです(建治2年〈1276年〉に起きた火災とする見方もあります)。報告を聞かれた大聖人は、「良観房」を、二つの火災(両火)の元凶となったとして、発音の似た「両火房」(新1546・全1137等)と呼び、糾弾されています。一方、この頃、大聖人の門下たちが、果敢に言論戦を展開しています。再びお連ランを未然に回避するため、師匠の立正安国の闘争に連なろうとしたと考えられます。建治元年(1275年。4月25日改元)7月の「四条金吾殿御返事(法論心得の事)」によれば、金吾が他宗、おそらく天台宗の僧と「諸法実相」の法門について議論しています(新1548・全1139、参照)。金吾は、大聖人が鎌倉に帰還された文永11年(1274年)には、良観と関係が深かった主君の江間氏を折伏し、不興を買っています。その後も、同僚による主君への讒言(事実無根の告げ口)もあり、金吾は苦境に立たされ続けていました。そうした中で、大聖人の正義を訴えるため、在家でありながら他宗の層との法論に挑んでいたのです。建治2年(1276年)には、武蔵国の千束鴻池池上(現在の東京都大田区池上とその周辺)の門下である池上兄弟の兄・宗仲が、やはり良観と関係の深かった父・左衛門大夫から勘当されています。この時の感動の理由は定かではありませんが、良観による策謀の可能性も考えられます。さらには、日興上人が中心となって弘教を展開していた駿河国(静岡県中央部)でも、熱原郷(富士市厚原とその周辺)を中心に弾圧の手が伸びていました。門下たちが迫害に遭い、その報告を受けた大聖人が多くの書簡を身延に送り、激励を重ねられる中、建治3年(1277年)を迎えます。この年、四条金吾、池上兄弟ら、有力な弟子たちが、正法弘通のためにさらなる難を呼び起こしていくのです。(続く) 池田先生の講義から大聖人の修学時代の師である道善房は、最終的に念仏に対する執着を捨てきれず、また、大聖人が迫害されたときにも守ろうとしなかった臆病な人物ではありました。しかし大聖人は、そのような師匠であったとしても、師恩を感じ、大切にされました。道善房の死去の報を聞くや、追善と報恩感謝のために「報恩抄」を認められたのです。大聖人自らが「師恩」に報じ抜くお姿を示してくださいました。そして、まことの報恩の道とは、全人類救済のために末法の大仏法を確立することであり、その大功徳は師匠に帰ることを断言されています。日蓮仏法における指定とは、かくも深く峻厳なものです。反対に、報恩の人生を外れて恩を仇で返すような不知恩のものに対しては、厳格なる因果の理法を教えられます。(知恩・報恩は、人間を人間たらしめる極理といってよいでしょう(「わが愛する青年に贈る」) 〈注1〉 法華経と大日経を比較すると、理(説かれている法理)は同一であるが、事(修行における実践など)においては大日経が法華経に優れているとする説。〈注2〉 本尊の具体的な姿として、続く文の説明によれば、文字曼荼羅の相貌を指すことは明白である。「本尊問答抄」には、「法華経の題目をもって本尊とすべし」(新302・全365)とある。ここで「本門の教主釈尊」を本尊とするとの意は、南無妙法蓮華経の文字曼荼羅を本尊とすることであると解される。 [関連御書]「報恩抄」「上野殿御返事(梵諦御計らいの事)」、「四条金吾御返事(法論心得の事)」 [参考]「池田大作全集」第33巻](「御書の世界〔下〕」第十四章、第十八章)、同第28巻(「報恩抄}講義)、「世界広宣流布新時代の指針」(「師弟」の章、「報恩抄」を講義)、『わが愛する青年に送る』(「人間学}の章、「報恩抄」を講義」、「勝利の経典『御書』に学ぶ」第22巻(「報恩抄」講義) 【日蓮大聖人「誓願と大慈悲の御生涯」】大白蓮華2024年2月号
February 7, 2025
閲覧総数 74
-
11

研究現場の知財と研究者保護
研究現場の知財と研究者保護——内閣府が公表した取り扱い指針山田 剛志 活動の継続と管理のバランス示す公益に資する制度の整備こそ 「学問の自由」構造的課題今年3月25日、内閣府は「大学等研究者の転退職時の知財取り扱い指針」(以下「本指針」)を公表した。これは、これまで制度的な空白が続いてきた、研究者の転籍・退職時の知財の帰属や活用方法に関する全国共通のルールを初めて明示したものであり、現場でのトラブル防止と研究継続性の確保を目的としている。研究者は数年に一度、より良い研究環境を求めて転籍することが多いが、その際せっかくの特許等が活用されず、いわゆる「死蔵特許」となる現状が続いていた。本指針は、その改善に向けた一歩となることが期待される。同時に長年にわたり問題視されてきた研究継続の自由と大学等の知財管理とのバランスに対して一定の方向性を示した点で、実務的にも意義深い。従来、大学と企業の共同研究においては、大学と共同研究企業が出願者となり、発明者である研究者が特許権者とならず、また研究者が転職後には自らの発明であっても自由に研究や論文発表ができないという状況が散見されていた。拙著『搾取される研究者たち』でも詳述したが、この問題は単に知財契約の枠を超えて、研究者の職業選択の自由や、憲法に保障された学問の自由にすらかかわる深刻な構造的課題である。本欄の昨年8月20日付で筆者が紹介したⅰPS細胞技術の発見者である高橋政代氏の事例はその象徴である。発明者であるにもかかわらず、「自分が発明した技術を使わせてほしい」と、経済産業相に最低請求を行わなければならなかったという。現実は、制度の不備を如実に示していた。高橋氏が研究を継続しるためには、自身が作り出した技術を持つ企業との和解を経なければならなかった。これは決して特殊な事例ではなく、国内外の大学における産業連携の実務現場で繰り返されてきた課題である。 譲渡、返還等、5つの対応類型本指針では、知的財産の取り扱いについて、研究者の立場や移籍の状況に応じた五つの対応類型が明記された。具体的には、①転職先大学への権利譲渡、②元大学による権利維持、③両大学による共有、④大学による権利放棄、⑤研究者本人への返還、である。これまでのような一律管理から脱し、柔軟な選択肢を提示したことは、実務に即した制度設計への転換点といえる。中でも注目すべきは、「研究者本人へも権利返還」が明文化されたことである。大学が活用しない知財については、研究者の申請により本人に返還する仕組みが提示されており、研究者が転職後も自身の研究成果を引き継ぎ、再び研究活動をおこなえるよういなる。このように、研究成果の本人帰属と研究継続の自由を明確に意識した構成は、画期的な前進と評価できる。さらに、発明者の意向を丁寧に確認することや、他の共同研究者や共同研究者との調整も含めて合意形成を促すことが求められている。従来のように、技術移転機関(TLO)や知財部門の判断のみで独占的なライセンス契約が締結され、発明者の意思が無視されるといった事態への歯止めがかかることも期待される。また、本指針では米国における転職前大学と転職後大学との間で締結される契約(Inter-InstitutionlAgreement)、IIAと呼ばれる、大学間の知財移管協定を参考とした対応が推奨されており、日本の現場で不足していたテンプレート(ひな形)整備や制度的支援に関する方向性も示されている点は注目に値する。これにより、これまで日本では研究者の転職に伴う知財の移転について、属人的な判断や慣例にゆだねられてきた状況に、合理的基礎が示されたことは意義深い。 状況に応じ柔軟に選択が可能 法的拘束力を持たせるべきただし課題も残る。本指針は、あくまで「努力義務」として提示されており、法的拘束力はない。各大学や研究機関の裁量に任せているため、本指針を知らない担当者いることも予想され、実際にどこまで履行されるかには差が出る可能性が高い。大学によっては、組織が防衛や収益確保を重視するあまり、指針を形骸化させてしまう恐れもある。したがって今後は、研究者・大学・企業の第三者の趣旨を正しく理解し、現場で実効的に運用できるよう、教育・研修の強化や、契約ガイドライン・チェックリストの整備が必要である。さらに、履行状況を検証する第三者機関の設置や、研究者からの相談を受け付ける窓口の整備など、実務的なサポート体制の構築も求められる。本指針は、研究者の権利保護を知財の公益的活用という理念を制度化する上で、重要な第一歩を踏み出したものといえる。特に、研究者が、自らの発明をもとに研究を継続できる環境を制度的に整えることは、真に公益に資する知財制度の在り方として評価される。知財立国を目指す上で、研究者の権利保護と知的財産の有効活用は、今まさに取り組むべき喫緊の課題だ。今後は、本指針が各現場で確実に実施され、研究者が委縮せずに研究と向き合えっる社会的基盤となるよう、制度面・運用面の両面からさらなる充実が求められる。(成城大学教授・弁護士) 【社会・文化】聖教新聞2025.4.15
November 26, 2025
閲覧総数 21
-
12

「私が体験から学んだこと」高山直子
高山直子さんの体験談です。高山さんは関西ドクター部の重鎮。1. 私は昭和三七年に創価学会に入会させていただきました。入会のきっかけは、母親が折伏をしてくれたからであります。その母の折伏の論法はこうでした。「やくざでも一宿一飯の恩は忘れない。おまえは忘れたかもしれないが、十月十日、子宮をかした。この恩を返してくれ。」と(笑声)、このように責められまして、やくざに劣ってはいけないと、私はしぶしぶ入会いたしました。 だから、信心したことはだれにも知られたくなかったし、だれにもわかってほしくなかった。 大学に入って下宿しても、ご本尊を目立たないように隅っこの方に置いて、人が来たらぐっと閉めて、そこに本なんかを置いて、絶対に目につかないようにしているという隠れキリシタンごときの信仰を細々と続けておりました。(つづく)
July 24, 2006
閲覧総数 9604
-
13

「私が体験から学んだこと」高山直子
7. 「なぜですか」といったら、「高山君、君は病気を治したいと思って題目を上げたかもしれないが、病気が治ると信じていなかった。信心とは、信ずることだよ」といわれました。「そして、百万遍上げるから病気を治してくださいというのは、『百万遍』というお題目で治るという品物を買うようなもんだ。それは信心ではなくて、取引というんだよ」といいました。 そして「どこの御書の中に信心とは取引であると書いてあるか」というんです。 書いていません。取引だったら値段があるはずです。夫の酒乱回避六〇万遍とか、いきそびれた娘の結婚成就が一八○万遍とか、しゅうとの仲直り三〇万遍とか、書いていませんよ(笑声)。全然書いてないんです。値段がないんです。 (つづく)
July 29, 2006
閲覧総数 1924
-
14

池田先生「沖縄広布35周年開幕記念総会」スピーチ(1988年2月)㊤
池田先生「沖縄広布35周年開幕記念総会」スピーチ(1988年2月)㊤(日蓮大聖人は)安房の国(千葉県南端部)の一婦人に宛てた御手紙の中で、「うらしまが子のはこなれや・あけてきやしきものかな」——浦島太郎の玉手箱のように、あなたからのお手紙をあけたことが悔やまれるのである——と仰せになっている。懐かしい古里に住む一婦人からの手紙をいただき、喜んで開いて読んだ。しかし、それは、その婦人の最愛の息子に先立たれたという悲しい知らせであった。本当に残念でならない、と。亡くなった子息を悼む大聖人の御心情が、しみじみと伝わってくる御言葉である。御本仏の大慈大悲、また寄る辺ない婦人に対するこまやかな心遣いに、深い感動の思いを禁じ得ない。◇妙法は〝永遠の幸福〟への法である。しかも、わが身ばかりではない。先祖も子孫も、また国土をも永遠に栄えさせていける不思議な大法である。他にも功徳を及ぼしていくその原点が「回向」である。私は仏法者として、いずこの地にあっても、その地の人々の先祖代々の追善供養させていただいている。ここ沖縄でも毎日、皆様方のご先祖はもちろんのこと、戦争の犠牲になったすべての方々のために、追善の題目を唱えている。戦禍に逝いた民衆の兵士も、また米兵の兵も、すべて含めて、真剣に回向している。その人の立場に立てば、同じくみな悲劇である。仏法者としてだれも差別することはできない。◇沖縄の地には、ある意味で、度の地よりも、苦しみ抜いて亡くなった方々が多いといえる。(中略)沖縄の地に眠るそうしたすべての方々を「抜苦与楽」していくことによって、この国土の福運も増していく。いかなる国土も、妙法の光で包み込み、仏国土へと変えていける。これが妙法の「三変土田」に通ずる法理である。国土の宿命をも転換しゆく、この真実の平和と繁栄の大原理は、他の政治や化学や経済等の啓示かの次元にはない。ただ妙法による以外にない。(『池田大作全集』第70巻) 国土の宿命転換を説いて法華経の法理不戦を誓い「世界平和の碑」を建立 「沖縄は永遠の平和のとりでにしてまさに世界不戦の象徴なり」「願わくは 全人類の前途に安穏なる歴史の日の一刻も早く来たらんことを」——恩納村にある沖縄県周道場の「世界平和の碑」に刻まれた、池田先生の言葉である。碑の序幕後、池田先生がこの場所に初めて足を運んだのは、1988年2月16日だった。この年の1月2日に還暦を迎えた池田先生は、実業家の松下幸之助氏から次のような祝詞を受け取っていた。「本日を機に、いよいよの真のご活躍をお始めになられる時機到来とお考えになって頂き、もうひとつ(創価学会)をお作りになられる位の心意気で、益々ご健勝にして、世界平和と人類の繁栄・幸福のために、ご尽瘁とご活躍をお祈り致します」まさにこの言葉に応えるかのように、池田先生は以前にも増す勢いで、日本と世界に平和建設の波動を大きく広げるべく、日夜、奔走を続けた。 新たに「第1回」と銘打って行われた本部幹部会をはじめ、日本での緒会合に出席した後、1月27日からは香港と東南アジアを20日間にわたり歴訪した。タイのプーポミン国王、マレーシアのマハティール首相、シンガポールのリー・クアンユー首相と会見したほか、香港大学、チュラロンコン大学、マラヤ大学、国立シンガポール大学を訪問。また、香港、タイ、マレーシア、シンガポールの同志に、それぞれ長編詩を贈った。沖縄の「世界平和の碑」を訪れたのは、こうした海外での行事や激励を終えて、那覇空港に到着した翌日だった。2月16日、碑の前で沖縄の同志と記念撮影した池田先生が、休む間もなく、精魂を込めて取り組んでいたことがあった。一つは、長編詩「永遠たれ〝平和の要塞〟——わが愛する沖縄の友に贈る」の執筆である。17日の夕方の会合で池田先生が「長編詩を書いたよ」と伝えると、会場は歓喜と驚きの拍手に包まれた。その日の朝、北陸の同志への長編詩が聖教新聞に掲載されていたのを、皆が目にしたばかりだったからだ。「ああ 沖縄!忍従と慟哭の島よ誰よりも 誰よりも苦しんだあなたたちこそ誰よりも 誰よりも幸せになる権利があるそうなのだここに安穏なくして真実の世界の平和はないここに幸の花咲かずして人の世の幸福はない」翌日(18日)の新聞で長編詩を読んだ沖縄の同志は、〝沖縄に生まれ合わせたことの使命〟や〝沖縄の地で広布開拓の人生を歩むことができる喜び〟を共にかみしめ合ったのだ。*そしてもう一つ、池田先生が心血を注いでいたのが、「沖縄広布35周年開幕記念総会」のスピーチであった。総会の前日(17日)、沖縄の代表と懇談した際に、池田先生が総会にかける思いを込めて、「明日は長い話になるな」と語っていたように、そのスピーチは約1時間に及ぶものとなった。そこで重要なテーマとなっていたのが、法華経で説かれる「三変土田」とは、法華経の宝塔品において、釈尊が三度にわたって娑婆世界や他の国土を浄化して同じ一つの浄土へと変じさせたことを指す。池田先生のスピーチは5年前(83年3月)、沖縄県周道場を初訪問した折に、この「三変土田」の意義を現実の姿を通して示すべく、「世界平和の碑」を建立することを提案した。研修道場の敷地内には、かつて核ミサイル「メ-スB」が格納されていたアメリカ軍の発射基地があった。沖縄に設置された四つの発射基地のうち、三つは沖縄の本土復帰前に取り壊されていたが、研修道場にだけ、当時の姿のままで残っていたのだ。池田先生は、堅牢なコンクリートでつくられた発射台の内部を丹念に視察し、その施設も取り壊す計画があることを聴いた。熟慮を重ねた先生が、翌日に平和の記念碑として永遠に残すという、思いもよらない提案だった。「『人類は、かつて戦争という愚かなことをした』との一つの証しとして」「『戦争を二度と起こさない』との誓いを込めて」と。その提案から1年後(84年4月)、沖縄県周道場で「世界平和の碑」の除幕式が行われた。池田先生は、除幕式の前日からの5日間、東京で会見が続いたために出席はできなかったが、「この日こそ、沖縄の地が、全世界に平和を叫び行く原点の地となったことを、声高らかに宣言しておきたい」とメッセージを贈り、碑の誕生を祝した。心は沖縄と共にあったのだ。(㊦につづく) 連 載三代会長の精神に学ぶ歴史を創るはこの船たしか 聖教新聞2024.12.16
September 1, 2025
閲覧総数 49
-
15

「変毒為薬」の歓喜の劇を!
襲い来る艱難に飲み込まれてしまうか。それとも、押し返し、打ち勝っていくか。人生も社会も、その真剣勝負といってよい。いかなる試練に直面しようと、必ず乗り越えてみせる。のみならず、逆境を大転換し、それまで以上の境涯の高みへ跳躍する。この生命の大歓喜の劇を、万人に開いたのが「変毒為薬(毒を変じて薬と為す)」の哲理である。『大智度論』また天台大師の『法華玄義』を踏まえられつつ、濁悪の末法を生きゆく民衆のために、日蓮大聖人は宣言してくださった。「能く毒を以て薬と為すとは何物ぞ 三道を変じて三徳と為すのみ」(984ページ)どのような「煩悩」や「業」や「苦」であろうとも、それを変じて、仏の「生命」と「智慧」と「福徳」を勝ち開いてゆく究極の力こそが、南無妙法蓮華経なのである。変えられぬ宿命など断じてない。ゆえに、決して嘆かずともよい、そして絶対に諦めなくともよい希望の光が、ここにあるのだ。 ◇戸田先生は、悩める友を励まされた。「難が来たら喜べ! そのときが信心のしどころであり、宿命転換のチャンスである。仏法は百発百中の『変毒為薬』大法である。たとえ失ったものでも、元の十倍、百倍の大功徳となって取り返せるのだ」【巻頭言】大白蓮華2010年4月号
March 24, 2010
閲覧総数 1021
-
16

「私が体験から学んだこと」高山直子
5.結核療養所の廊下には張り紙が出ているんです。どのように出ているか。「物をいうな、口聞くな、あいさつするな」と。 要するに、肺を使うなということです。でも、まあいいやと思って一万遍唱題を始めました。そして、一〇〇日で百万遍。私は生まれて初めてあげ切りました。 そのあとすぐいろんな検査があって、主治医の先生に呼ばれました。不思議そうな顔をしていらつしゃいました。先生がおっしやったのは、「高山君、どうしたんだい。この三カ月間、どんなふうに過ごしていたの」と聞かれました。私は、「いい子でおりました」と、そのようにいうと、「不思議だね。僕も長年、結核の医者をしているけれども、入院して三カ月でこんなに急激に悪くなっている人は初めてだよ」といわれました(笑声)。 私は、よくなっているんじゃないでしょうかと聞くと、「いや、悪くなっている」というわけです。 「こんなに進みが早いのならそのうち左上肺をとる手術を考えたらどうかな」というお話まで出てきました。 「それは、もうちょっとお待ちください」といって、自分のベッドに帰ってご本尊様をじつとみました。 そして、思いました。「うそやったな」と(笑声)。(つづく)
July 27, 2006
閲覧総数 1287
-
17

「私が体験から学んだこと」高山直子
10. そして、先輩が聞かれました。「高山君、結核は何で起こるの」「はい。結核菌です」と私は答えました(笑声)。先輩、「そうだな。結核は結核菌でおこるよね」といわれました。「じゃあ、聞こう。結核菌ってどんな大きさ」と聞かれました。「はい、三〇〇倍の顕微鏡でみると一ミリ弱」「そんな小さいのじや、目にみえないんだね」「もちろん、みえません。小さなものです」といいました。「それがどこについているの」「鎖骨の下あたりに少々」「そうか。じゃ、結核菌は生物体だよね」「そうです。生物体です」「じゃ、何界の衆生」と聞かれました。「畜生界だと思います」(笑声)と私は答えました。 すると先輩は、「これで原因がわかっただろう」といわれたわけです。「さっぱりわかりません」と答えますと、「三〇〇倍にしても一ミリにも満たない、目にもみえない結核菌の生命力、それもたかが畜生界の生命力だが、それよりも君の生命力が劣っているから病気が治らないんだ」といわれました。 畜生界より劣るというと、あとは地獄と餓鬼しか残っていません。がっかりしました(笑声)。(つづく)################# 仏の別名を能忍という。よく耐え忍ぶ。 偉大なる仏界の生命を涌現させ、智慧を発動させ、厳しき現実を乗り切る。 そのためには、強き深き祈りしかない。 諸天を揺り動かす祈りだ。
August 1, 2006
閲覧総数 1427
-
18

「私が体験から学んだこと」高山直子
6. 願いは叶うといっていたのに治ってないどころか、病気は悪くなっている。百万遍をあげたのだから、ちょっとでも治っているのが筋と違うかなと思いました。と同時に、むらむらと疑いの心がわいてきました。 「やっぱりご本尊は、紙切れと違うかな、字が書いてあるだけと違うかな」と思いました。 そして、わざわざ外出願を出して先輩のところに行ったんです。かくかくしかじかでしたので、私、信心をやめさせてもらいますと、いいに行きました。その先輩は、「高山君はどのように祈っていたの」と聞かれたから、私は、「百万遍題目を上げますから病気を治してください」と祈っていましたといったら、その先輩が、「そうか。それだったら、百万遍上げても、五百万遍上げても、一億万遍上げても君の病気はよくなんないぞ」といわれました。一億万遍、約一〇〇年かかります(笑声)。(つづく)
July 28, 2006
閲覧総数 1749
-
19

賢者は喜び愚者は退く
賢者は喜び愚者は退く池上兄弟 2度の勘当に屈せず一家の宿命転換を成就後世に輝く「難を乗り越える信心」の鑑広宣流布とは、仏と魔の闘争である。日蓮大聖人は大難にも一歩も退かず、渾身の激励を門下に送られた。師の励ましを受け、門下たちは病苦や家族との死別、権力者からの迫害など障魔の嵐を乗り越えていった。日蓮門下の人間群像は、「師弟の絆」こそ、一切の苦難に打ち勝つ力であることを示している。企画「日蓮大聖人の慈愛の眼差し」の最終回は、志の御指導通りに三障四魔に屈せず、一家の宿命転換を成し遂げた「池上兄弟」を紹介する。 魔との闘争こそ成仏への直道池上兄弟の兄は宗仲といい、弟は宗長と伝えられている。池上とは、武蔵国・千束郷池上(東京都大田区池上とその周辺)のことで、兄・宗仲は池上の地頭であったようだ。兄は右衛門大夫志、弟は兵衛志という感触を持っており、日蓮大聖人はそれぞれの官職名で二人を呼ばれていた。康光(宗親とする説もある)に伝承される父と兄は鎌倉幕府に仕え、殿舎の造営や修理などの建築、土木に携わる大工(工匠)の棟梁に当たる立場にあったと考えられている。池上兄弟が大聖人に帰依した時期は定かではないが、立宗宣言の数年後、四条金吾らと同時期といわれている。入信から20年ほどたった頃、兄に大きな難が降りかかる〈最近の研究では建治2年(1276年)と考えられている〉。真言律宗の僧・極楽寺良観の熱心な信者だった父・康光が、兄弟に法華経の信仰を捨てるように迫り、兄・宗仲を勘当したのである。当時、親から勘当された子は家督相続や遺産相続を失った。それは社会的な身分を剥奪されることでもあった。つまり、宗仲にとっての勘当は、経済的保証を奪われ、社会的に破滅することを意味した。一方で弟・宗長は、父の意向に従って妙法の信仰をやめれば、兄に代わり家督を継ぐことになる。家督を継いで親に孝養を尽くすか信仰を選ぶか、悩ましい事態になった。このように兄・宗仲の勘当は、兄弟の信心を破り、二人の仲を引き裂こうとする陰湿なものであった。大聖人は、池上兄弟に長文のお手紙「兄弟抄」をしたためられ、兄弟が直面している難は法華経に説かれている通りであること示される。その中で、未来に大地獄に堕ちるほどの報いがあるところを、正法を行じる功徳によって現世で少苦として受ける「転重軽受」であるとして、「各各・随分に法華経を信ぜられつる・ゆへに過去の重罪をせめいだし給いて候」(御書1083㌻)と激励。仏道修行を妨げようとする魔性と戦うことが成仏への直道であることを教えられる。大聖人の御指導通り、池上兄弟は夫妻ともども心を合わせて信心に励んだ。そして翌年までには兄の勘当が説かれるのである。 弟・宗長への慈愛の御指導しかし、宗仲が再び勘当されてしまう。極楽寺良観が、自身の信奉者である父・康光をあおり立てたのだ。1度目の勘当の時と同様、大聖人が特に気にかけておられたのは弟・宗長の信心であった。本来、「信仰」と「孝養」は一方を選び取るようなものではなく、信仰を全うすることが真の孝養となる。しかし、宗長は選択を迫られているように感じたかもしれない。宗長へのお手紙「兵衛志殿御返事(三障四魔事)で大聖人は、宗長の迷いを振り払われるように、あえて厳しく戒められる。まず、「師と主と親とに従っては悪いときに、これを諫めるならば、かえって孝養となる」(同1090㌻、通解)と確認される。その上で、兄・宗仲は「今度、法華経の行者になるでしょう」(1091㌻、通解)と仰せになる一方、宗長には「あなたは目先のことばかり思って、親に従ってしまうでしょう。そして、物事の道理が分からない人々は、これを褒めるでしょう」(同㌻、通解)と心配される。さらには、「今度は、あなたは必ず退転してしまうと思われます」(同㌻、通解)等と繰り返し仰せになる。そして、「一筋に思い切って兄と同じように仏道を成じなさい」「『私は親を捨てて兄につきます。兄を勘当されるならば、私も兄と同じと思ってください』と言い切りなさい」(同㌻、趣意)と、まるで肩を抱きかかえて揺さぶるかのように、何度も何度も宗長の勇気と覚悟の信心を奮い起こそうとされるのである。〝幸福への道を断じて踏み外せまい〟との大聖人の言愛に呼応するように、宗長の胸中には、兄と共に信心を貫く決意が固まっていったことだろう。さらに大聖人は「潮の満ち引き、月の出入り、また季節の変わり目には、大きな変化があるのは自然の道理です。同じように、仏道修行が進んできて、凡夫がいよいよ仏になろうとするその境目には、必ずそれを妨げようとする大きな障害(三障四魔)が立ちはだかるのです」(同㌻、趣意)との原理を示される。その上で、こう仰せである。 「賢者はよろこび愚者は退く」(同㌻) 〝苦難は、いよいよ大きく境涯を開くチャンスだ〟と、喜んで立ち向かう「賢者」であれと、信心の姿勢を教えられたのである。池田先生は次のように講義されている。「一見、障魔から攻め込まれように思うことがあるかもしれない。しかし本質は逆です。私たちが自ら進んで成仏の峰に挑んでだがゆえに、障魔が競い起こったのです」「どこまでも、主体者は自分です。永遠の常楽我浄の幸福境涯を得るために避けて通ることのできない試練がある—こう覚悟した者にとって、障魔と戦うことは最高の喜びとなるのです」魔が競い起こるのは正法の実践が正しいことの証明であることを深く確信し、喜び勇んで立ち向かっていく。ここに、「創価の賢者」の生き方がある。 信仰を貫き通しついに父が入信池上兄弟は、前回の勘当の時にも増して信心に励み、父親に極楽寺良観の誤りを粘り強く指摘し続けたことだろう。その陰に、妻たちの揺るぎない信心による励ましがあったことは間違いない。その結果、ついに父・康光が法華経の信仰に帰依する時が来た。弘安元年(1278年)のことである。その報告を聞かれた大聖人は心から喜ばれ、宗長に送られたお手がもの中で、兄弟の団結を称賛される。師の真心に、二人はさらに報恩の決意を固めたことだろう。入信の翌年の弘安2年(1279年)、父・康光は安らかに息をひきとる。それを聞かれた大聖人は、こう激励される。 「あなた(弟・宗長)と大夫志(兄・宗仲)は、末法の悪世に法華経の大法を信じてきたので、必ずや悪鬼が国主と父母等に入ってそれを妨げようとするのであろうと思っていましたが、2度にわたる勘当という難が競いました。しかし、感動を許されて父を信心させたあなた方は真実の親孝行の子ではないでしょうか」(同1100㌻、趣意) 弘安2年といえば、大聖人は熱腹の法難に臨んで、厳然と指揮をとられていた頃である。その一方で、こうして門下をたたえ、さらに不退転の人生を歩めるよう、こまやかな激励を重ねられていたのである。弘安5年(1282年)9月18日、大聖人は常陸国(茨城県北部と福島県南東部)へ湯治に行かれる途中、宗仲の屋敷に立ち寄られる。そして10月13日、池上邸で御入滅される。翌14日に営まれた御葬送の際には、四条金吾と共に幡を持つ宗仲と、太刀を奉持する宗長の姿があった。池上兄弟と妻たちの「難を乗り越える信心」の戦いは、大聖人が仰せになった通り、「未来までの・ものがたり」(同1086㌻)として、700年以上を経た今も、私たち信仰者の鑑として不滅の輝きを放っている。 【日蓮大聖人の慈愛の眼差し】聖教新聞2020.8.10
July 14, 2021
閲覧総数 2061
-
20

伊東甲子太郎余談
伊東甲子太郎余談昔、有名な受験参考書が二つあった。一つは戸田城聖著「推理式指導算術」であり、もう一つは略称「小野圭の英語」である。前者は今日では高名な宗教家(故人)であるが、後者が実は伊東甲子太郎の弟鈴木三樹三郎の娘を奥さんにしている英文学者小野圭次郎氏(故人)である。この小野圭次郎氏が書き残した『伯父伊東甲子太郎武明』『岳父鈴木三樹三郎忠良』は、子母澤寛、平尾道雄両先学の新選組本記とともに、伊東兄弟事績を知る原点になっている。その中で、伊東は単なる新撰組参謀ではなく、新撰組隊士に英語まで教えていたというからおもしろい。ぐうとないと=こんばんは ぎぶみい=私にください せんきゅう=ありがとう あいらぶゆう=私はあなたが好きですと、教わった隊士がメモをとってのこしているのが、興味ぶかい。 【新撰組】童門冬二著/成美文庫
July 12, 2024
閲覧総数 83
-
21

友岡雅弥X
友岡雅弥X 基本的に、ことばの本当の意味で、大乗と言えるのは、龍樹の 中観派と般若経経典群であり、そこに、「マサラ・ムービー的盛り」を施した『法華経』の嘱累品までかな。 他の「大乗」経典は、むしろ、「根本説一切有部」の流れの後継に近い。 ただし『法華経』の安楽行品と普賢品は、ヘイト 大聖人の御書は、「法理」のエビデンス・アプローチではなく、「希望」のナラティブ・アプローチとして読んだらいいと思う。 日蓮大聖人も池田先生も「教え」を説いたのではない、 「希望」を語ったんです。 僕は、明確に「日蓮本仏論者」だけど、「久遠元初の仏様」という仏教ではない、日蓮正宗的一神教ではなく、旃陀羅が子として生まれ、犯罪者として遇され、掘建て小屋で門下の手紙に涙し、最後は置いて行く馬のことを心配しながら亡くなる、1人の人間を、人生の模範としようと言う「日蓮本仏論者」 もう一つ、何度も書いてるんやけど。 僕、日蓮本仏論者ですけど。 ばりばりの。 なんで「法華経の智慧」を読む!と決意してる、とか言ってるのに、「本仏」とやらにこだわるのかなぁ。 そういう日蓮正宗的考えを破るためのものなのに。 僕は、明確に「日蓮本仏論者」だけど、「久遠元初の仏様」という仏教ではない、日蓮正宗的一神教ではなく、旃陀羅が子として生まれ、犯罪者として遇され、掘建て小屋で門下の手紙に涙し、最後は置いて行く馬のことを心配しながら亡くなる、1人の人間を、人生の模範としようと言う「日蓮本仏論者」 「文底秘沈」なんて、バラモンの秘密主義だし、中古天台の台密。 それを、「とりいだし」「誰にでも出来る形」で命がけで、広めようとしたのがのが大聖人と違うの。 だから、大聖人は、「文上開示」 「文底」とか「久遠元初」に拘る人がいるけど、平成の宗教改革の意義がほんとに浸透していなかったんだなぁと思います 「文底」釈というのは、「久遠元初」とかいう、「絶対神的日蓮」的、「文上浮遊」的なものではなく、 「今、私は何をすべきなのか」の姿勢。 修行者が酒場に入れば 酒場が彼の修行場になるが、 酒飲みが修行場に入れば そこは彼の酒場となる ——エジプト生まれのスーフィー、ズーン・ヌーン もちろん飲酒のことと違いますよ。 「私」が何をするか、という話 ずっと「文底読み」という「皮相浅薄読み」の訓練受けて来られているので、しんどいですね 『法華経の智恵』のテーマが、「文底釈とは、人間釈である」だったことが、ほとんど忘れ去られてしまっているのは、とても残念。
July 11, 2025
閲覧総数 173
-
22

生命改変のリスクに対する責任も
生命改変のリスクに対する責任も科学文明研究論者 橳島 次郎マンモスの復活計画今年3月、米国のバイオ企業が、絶滅したケナガマンモスの遺伝子特性を組み込んで、マンモスと同じような毛むくじゃらのマウスを誕生させたと発表した。これは「マンモス脱・絶滅」という壮大な計画のワンステップだ。これまで、永久凍土から発掘したミイラ標本から採取した細胞を使い、マンモスを復活させようとする試みは日本を含めいくつか行われていた。だが保存状態のよい完全なゲノムを得るのは難しく、棚上げされた状態だった。それに対し、マンモスそのものを復元するのではなく、その遺伝子の特性を現代に生息する近縁種のアジアゾウに組み込んで、いわば「シン・マンモス」を誕生させようというのが、このバイオ企業による計画の狙いだ。そのためにまずアジアゾウの細胞からiPS細胞を作る。次にマンモスのゲノムを解析し、密生した体毛や分厚い皮下脂肪などを寒冷気候に適応できる特徴を発見させる遺伝子を数十個選び、ゲノム編集によりゾウのiPS細胞に組み込む。そこで編集してできたマンモスに似たゲノムを持つ細胞核をゾウの卵子に移植してクローン胚を作り、ゾウの代理母の体内で育てて誕生させる。この計画が野心的なのは、作り出したマンモスに似たゾウの群れを永久凍土に生息させ、広大な不毛日に生態系を蘇らせることを最終目的にしている点だ。さすがにそこまで実現させるのは難しいだろうが、そのために行う技術開発を通じて、絶滅が危惧される希少動物を保全し過酷な環境への適応を可能にする生物学的メカニズムを解明しることが、計画の現実的な目標とされている。人間の活動が原因になっている種の絶滅と地球環境の劣化に対応することは、確かに現代人に課された道徳的義務だろう。だがその大義名分の下で、遺伝子工学と生殖工学を総動員し、自然界には存在しない生物種を作り出すことは許されるだろうか。大量の異種の遺伝子を組み込まれ実験対象とされる動物にもたらされるリスクは正当化できるものだろうか。畜産分野での牛の研究で、細胞核の移植で作られるクローン個体は過体重など異常な発生をして死産する率が高く、生まれる子だけでなく代理母とされる動物の福祉も脅かされるリスクがることがわかっている。生命を改変する科学技術を手にした私たちは、地球で共に暮らす生き物たちに対し、どのように責任を果たせばいいだろうか。そんな観点から、このマンモス「復活」計画の成り行きを見守りたい。 【先端技術は何をもたらすか—41—】聖教新聞2025.4.15
November 26, 2025
閲覧総数 14
-
23

「私が体験から学んだこと」高山直子
9. ところが、一年入院していても病気は一向治る気配がないわけです。もう一度先輩のところに行きました。 「疑ってはおりません(笑声)。冬は必ず春となるとも確信しております。それにしても、春が来るのが遅いように思うんですが、どうしたら早く病気が治るでしょうか」といいますと、先輩は、「物事はすべて因果の理法だ。だから、病気になる原因、病気になり続けている原因があるんだ。原因を取り除ければ病気は治るんだ」といわれました。 原因さえわかれば、原因を取り除けばいいんだ。といわれました。「それは、そうだ。すべて原因と結果、因を消滅すればいい」、そのとおりだと思いました。(つづく)
July 31, 2006
閲覧総数 1166
-
24

自分が変われば相手が変わる
自分が変われば相手が変わる元中学校教頭 寒川 義文香川県で高知留中学校教員となって39年となる今年は、新型コロナウイルスの感染拡大という、経験したことのない状況に直面するなど、激動の一念でした。感染症の対策以外にも、学校現場には課題が山積しています。ある新聞で、全国の教育現場における昨年度のいじめ認知件数と不登校児童生徒数が、過去最多を更新したことが報じられていました。この記事を見たとき、90年前、教育者でもあられた創価学会初代会長・牧口常三郎先生が『創価教育学体系』の発刊に際してつづられた言葉が、思い浮かびました。〝一千万の児童や生徒が修羅の巷に喘いでいる現代の悩みを、次代に持ち越させたくないと思うと心は狂せんばかりなり〟どこまでも子供の幸福を第一に考えられた牧口先生。私も一人の教育者として、いかに大変な状況であっても、次代を担う子供に尽くしぬこうと、自らに強く言い聞かせる毎日です。 分かったつもり私が教員に採用された1980年代は、全国世校内暴力の嵐が吹き荒れていた頃。授業中に生徒が騒ぎ、老化をバイクが走り回り、学校にパトカーが来ることも日常茶飯事。私自身、担任として、寝る間もないほど多忙日々を送っていました。そんなある年、A君という生徒を受け持ちました。やんちゃな彼が問題を起こすたび、私は厳しく指導しましたが、A君は反発するばかり。〝なぜ分かってくれないんだ〟—私は次第に、自信を失っていきました。ある日、友人同士のけんかに巻き込まれたA君に、私はきつく指導しました。そると彼は、目に涙をためながら、「お前は俺のことを分かっているつもりやろうが、何もわかっとらん!」と、学校を飛び出してしまったのです。その夜、A君の家に行き、話を聞くと、彼は友人たちのけんかを、やめさせようとしていたことが分かりました。A君の言う通り、私は「分かったつもり」になっていただけでした。彼の行動を「問題」だと決めつけ、「彼のために」と言いながら、結局は〝教師として、良く見られたい〟という、私の自己満足にすぎなかったのです。A君に謝った後、帰宅して御本尊に向かった、自らの至らなさを反省しました。すると、〝彼のおかげで気づくことができた。彼のおかげで教師として一歩、成長できた。これからも彼に関わり続けよう〟と、感謝の持ちが湧いたのです。一念が変化した時、A君の長所が次々と見えてきました。その後、A君との信頼を深めることができ、彼は有意義な学校生活を送って、笑顔で卒業していきました。仏法には「一念三千」という法理があります。自身の一念が変われば、相手が変わり、ついには世界を変えといけるという「人間革命」の原理が示されています。どんな状況も、自分次第ですべて大きく変えていけるのです。実は、A君とは卒業後も年賀状などを通して交流は続きました。彼の卒業から20年ほどたったある日、相談を受けました。「息子が反抗期で困っている」と。私は、A君にアドバイスをしました。「子どもは親の言う通りには、なかなか育たない。親の背中を見ている。自分もそうだったと我慢して、よく話を聞き、愛情を注ぎ続ければ、いつかきっと、分かるときが必ず来る」安堵した彼の笑顔を見て、私自身も元気になりました。 大病を乗り越えて5年前に教頭に就きましたが、定年を間近にした昨年11月、大腸から出血し、緊急入院。一時は意識不明に陥りました。しかし、学会の同志が私の回復を五懸命に祈って下さるなか、治療が奏功して早期に職場復帰でき、職務を全うすることができました。定年退職後、再任用で職場に戻った今年6月にも再び出血しましたが、幸い、大事に至らず、今も教壇に立ち続けています。私がこれまで教師として心掛けてきたことの一つは、「子どもを尊重する」ということ。あいさつも、なおざりにせず、「おはようございます」と元気に声を掛け、きちんとお辞儀します。御書に「三千大千世界にみてて候財も・いのちには・かえぬ事に候なり」(1596㌻)とあります。一人一人の生命には、宇宙大の可能性が秘められています。それほど問うと以下の生を持った生徒たちを最大に輝かせていくことこそが、教育者の使命ではないでしょうか。「教育」は、すぐに答えが出ないものであるがゆえに、時に葛藤や自身の無力さを感じることもあります。それでも、子どもの可能性を信じて、どんな時も励まし続けることで、子どもは、自分のことを大切に思ってくれるその心を滋養として、おのずと成長の目を大きく開花させるのだと確信します。私自身、中学から大学まで過ごした創価の学びやでの、教職員の方々の励ましが大きな支えでした。とりわけ、創価大学時代、所属していた剣道部の恩師や先輩方の温かな薫陶があったからこそ、教育の道を志し、歩み続けて今日に至ることができました。これからも、太陽のように皆を照らし、育んでいく「創価の人間教育の体現者」を目指して、「黄金の日記文書」をつづっていきます。 [プロフィル]さんがわ・よしふみ 創価大学を卒業後、香川県の公立中学校教諭、教頭職を歴任して本年3月に定年退職。4月から再任用教諭として勤務。61歳。1962年(昭和37年)入会。香川県坂出市在住。副県長。四国教育長。 視点因果具時蓮華は花と実が同時に成長するが、同様に、仏の生命を開く原因と結果も同時に具わる—仏法の「因果具時」の法理です。具体的には、御本尊を信じ、自行化他の唱題行を実践することで、私たちは、いつでもどこでも、この身に仏の生命を開くことができるのです。それはまた、今この瞬間の一念こそが、未来を創る原因であるとも言えます。池田先生は小説『新・人間革命』でつづっています。「一念は大宇宙を動かす。『因果具時』であるがゆえに、今の一念に、いっさいの結果は収まっている」(第10巻「新航路」の章)学会員一人一人に「因果具時」の法理が脈打つからこそ、困難な状況にも臆することなく希望をもって挑んでいけるのです。 【紙上セミナー「仏法思想の輝き」】聖教新聞2020.112.5
December 6, 2021
閲覧総数 837
-
25

「私が体験から学んだこと」高山直子
3. ところが、現実に結核療養所に入ったら、例えば朝の話から嫌なんです。私は八人部屋だったんですが、みんなが大事に持ち寄って一カ所で見せ合うものがあるのです。 朝出た一番のタンなんです(笑声)。最初に入った次の朝、おみそ汁を吸っていると、みんなで「あんたのたん、ええ色しているな」とか「ちょっと黄色いね」、そういう話をしているのです(笑声)。 もうロマンチックも悲劇もないわけです。更に隣のおばさんに、「一体何年ぐらい療養所に入院しているんですか」と聞くと、「短いのよ、八年」といいました。療養所では一〇年、二〇年選手はざらなわけであります。 私は、それをみて、だんだんぞっとしてきました。そしてこれは宿命かなとその時初めて宿命ということを考えました。 4. 私の父も三〇年間、結核で悩みました。そういえば父と顔もよく似ているし、同じ宿命かなと思って、こんなところで自分の人生朽ちたら嫌だなと思いました。 そのときに思い出したことは、たまたま出ていた座談会で「願いとしてかなわざるはなし。 百万遍上げたら、どんな願いもかなうのよ」という言葉でした。どんな願いも百万遍上げたらかなうといってたな。朝から晩まで暇だから一日一万遍上げ切ってやろうと決意いたしました。そして、一日一万遍、三時間の題目を決意してあげ出しました。(つづく)
July 26, 2006
閲覧総数 1195
-
26

「自分」中心か「師匠」中心か
信心の大敵は「慢心」や「我見」である。牧口先生も厳しく言われていた。「我見の信心の人は、ちょうど尺八を逆に吹いているようなものだ。濁った音は出るかもしれないが、本来の美しい音色の功徳は出ない」「自分」中心ではいけない。どこまでも「法」中心、「師匠」中心で、最後まで生き抜くのが仏法の世界だ。また、正しい人間の世界だ。とくにリーダーは、この点を厳しく律しなければいけない。リーダーが自分中心になってしまうと、皆がかわいそうだ。【戸田先生生誕記念スピーチ】聖教新聞070203掲載「聖教新聞」宝さがし結局、「慢心」や「我見」は、自身の弱さに帰一するものではないだろうか。壮烈なる現実の闘争。それを勝ちゆくためには、どこまでも「法」と「師匠」を中心に生きぬかねばならないと固く決意をしている。
February 13, 2008
閲覧総数 917
-
27

「私が体験から学んだこと」高山直子
8. 疑わざるを信という。何があっても疑わない、信じ抜く強さ、これが信心だ。その信心に題目を唱えるという行力があってはじめて仏力、法力があらわれるんだ。 取引というのは信心ではないから信力はゼロだ。 ゼロ掛ける一〇〇はゼロ、ゼロ掛ける一億もゼロだといわれました。「そうか。信心とは、そういうものだったのか。医者がちょっといったぐらいで、ぐらっとするような、そういうすぐ疑いをおこす取引のような信心をしていたらだめなんだ」と思いました。 その先輩は、「高山君の今の心境は、取引と思っているから、やい、ご本尊、百万遍、毎日おがんでいるのに約束の品物が届かないじゃないの、といっているのと一緒なんだ」といわれました。「そうか、信心とは信じることなんだな」と思って、また信心を続けました。(つづく)
July 30, 2006
閲覧総数 1169
-
28

負けないという人生
戸田先生は、和歌を贈ってくださいました。「勝ち負けは 人の生命の 常なれど 最後の勝ちをば 仏にぞ祈らむ」仏法は勝負である。なればこそ、仏法の師弟は最後まで戦い続けねばならない。途中の勝ち負けはどうであれ、必ず最後に勝てるのが法華経の兵法なのです。◇「負けないという人生は、永久に勝ちです。勝つことよりも負けないことのほうが、実は偉大な勝利なのです」負けないとは、挑戦する勇気です。仮に何度倒れようと、何度でも立ち上がり、一歩でも、いや、半歩でも前に進んでいくのです。大聖人は、「此法門を日蓮申す故に忠言耳に逆らう道理なるが故に流罪させられ命にも及びしなり、然れどもいまだこりず候」(1056頁)と仰せです。いかなる大難が競い起ころうとも、「いまだこりず候」です。この不屈の精神、即「負けじ魂」こそ、日蓮仏法の骨髄なのです。【池田大作先生の講義「世界を照らす太陽の仏法」】大白蓮華2018年2月号
May 6, 2018
閲覧総数 3935
-
29

雄々しき勇者に
人生には、さまざまな苦難がある。どんな人も、何らかの苦難がある。 ユゴーは言う。その苦難に対して、①あきらめるか②傍観するか③飛び込んでいくか――これによって「未来」は大きく変わる、と。(『ユゴー全集』9、ユゴー全集刊行会、趣意) まず、何かあると、すぐに〝できない〟〝私には力がない〟とあきらめる人。それは「弱虫」である。その人にとって、未来は「不可能」でしかない。なにひとつすばらしいものを生めない。幸福もない。 次に、手をこまねいても何もせず〝私は知らない〟〝私には関係ない〟と傍観する人。それは「卑怯者」である。その人にとって、未来はいつまでも「不可知」なまま、分からないままである。 第三に、〝断じて私は負けない〟と雄々しく苦現実の真っただ中に飛び込む人がいる。ユゴーは、その人こそ「哲人」であり「勇者」である、と。 その人にとって未来は、「理想」として現れていると論じている。明るく美しい未来が約束されている。これは仏法に説く生き方にも通じよう。 三つの生き方に三つの未来。心ひとつで、行動いかんで。未来は変わっていく。 大聖人は、「臆病にては叶うべからず」(御書1193、1282㌻)と繰り返し仰せになっておられる。 妙法に無限の力がある。しかし、それを引き出す人の信心が臆病であってはならない。願いも叶わない。 (本部幹部会・群馬県総会1993年7月7日、渋川文化会館) 【勇気の旗高く】聖教新聞2019.3.25
October 7, 2019
閲覧総数 184
-
30

「ともかく批判」のジャーナリズムの愚
“良心的”ジャーナリスト「世論迎合」はジャーナリズムの劣化田原総一朗――世論も白か黒かというレッテル貼りを行いが、それは多分に情緒的な理由で判断されているようです。根拠も論理的な検証もなく、性急に結論を出すのは危険ですね。■ 田原 世論がイエスかノーかを単純に決めるのは、メディアの責任が大きい。最近は麻生内閣の支持率が低下しているので、麻生首相の悪口を言っていれば良心的なジャーナリストだと見られる雰囲気がある。麻生バッシングはまるでファッションです。――レッテル針をして批判する風潮は政治にかぎりませんよね。■ 田原 ええ。たとえば、創価学会の池田名誉会長を批判するような記事を書くと、タブーに挑戦する良心的ジャーナリストのようにいわれ、反対に少しでも肯定的に扱うと学会シンパだとレッテル貼りされてしまう。実際は批判するほうが楽で、評価すべきことを評価するほうが度胸がいるのですが。定額給付金の問題だってそうです。定額給付金をナンセンスだと言っているのは、実はメディアと野党だけで、国民の大多数はそんなことは思っていない。僕が各地で講演しても、みんなホンネでは喜んでいる。マスメディアは何を根拠に定額給付金は世紀の愚策と決めつけているのか。しかし、一度、定額給付金はナンセンスだとマスコミで決めつけられると、それに反対するのは、かなり度胸のいることです。――世論でも多くの国民が反対と答えているのも、そうした心情があるからかもしれませんね。メディアが反対といっているから、それに同調して世論も反対する。その世論を背景に、メディアはさらに強く反対する。そういう構造がありますね。■ 田原 そもそも、世論に同調するのが良心的なジャーナリストだと勘違いしているから、このような現象が起きているのだと思います。ほんらいジャーナリストは決して世論に迎合してはならない。世論迎合はジャーナリズムの劣化です。自分で考えて、自分の言葉で、自分の意見を述べるということは、ときに危険なことですが、だからといって、ジャーナリストは自己保身に走ってはならない。【世論と政治】第三文明09・5月号
April 27, 2009
閲覧総数 10
-
31

どう生かす職場の人間関係
やはた よう相手の行動パターンを知ることが大切周囲に依存する傾向の強い部下最後に挙げる依存パーソナリティーの部下は、私が目下増加中と考えているタイプである。ある若い女子社員は勤務時間開始30分ほどから、昼食を一緒にとってくれる人を探し始めている。「昼食を一緒に食べてくれる人が誰もいない」という事態を、はたから見れば異常なほどに恐れている。それどころか、しょっちゅう[ケータイ]を確認して、メールを確認して、メールが少ないと「私って嫌われている」と落ち込んでしまう。このタイプは「自分は半人前。他人が簡単にできることが自分にはできないに決まっている」と思っている。そのために、「他人に何とか助けてもらう」と人頼みになり、周囲に受け入れてもらうことに全力を注ぐ。なんでも相手に調子を合わせるから、扱いやすい。だが、件の女子社員はパソコン操作をすぐに投げ出して、いつも「わからない、教えて」と周囲に言ってくる。周囲の人は、説明しながら操作して見せて、何とか覚えてもらおうとするのだが、彼女は「スゴーイ」とは、口先で入っているものの、自分も覚えようとする姿勢はまったく伝わってこない。この調子なので年齢相応のスキルに欠け、常識知らずである。自らの実績で勝負する考えはなく、社内の人間関係をどううまくやっていくか、ということで頭がいっぱいである。だが、よく言えば協調性は非常に高い。こういう、危害がない、頼りない部下には「ほう、よくできているじゃないか。どうしてこんなに旨くできたのかね?」と「できていること」に目を向けさせ、自身を伸ばすことが必要だ。どんな性格も一長一短。そして、相手の行動パターンがつかめるというだけでストレスは軽くなる。パーソナリティー理論を日々の人間関係に大いに活用していただければ幸いである。(矢幡心理教育研究所所長)やはた・よう 1958年、東京生まれ。臨床心理士、西武文理大学講師。精神病院の相談室長を経て、現在、矢幡心理教育研究所所長。新聞・テレビなどで、コメンテーターとしても活躍中。近刊「困った上司、はた迷惑な部下」(PHP新書)など、著書は約30冊。【「こころ」のページ】聖教新聞07・4・15(おわり)
July 18, 2008
閲覧総数 27
-
32

自分の可能性を信じ抜く
大聖人の仏法は、“自分の中に偉大なる仏の生命がある”と、自覚するところから出発します。ゆえに、私たちの祈りとは、何かに助けてもらうというような、“おすがり信仰”ではありません。どこまでも自分自身の可能性を信じ抜く戦いです。自らの生命に具わる仏界の生命を涌現していくのです。その「月月・日日」(1190頁)の勝負なのです。大聖人は、「己心の外」に法を求めるならば、どんなに題目を唱えていても成仏は叶わず、むしろ無量の苦行になってしまうとまで仰せです。「己心の外」に法を求めるとは、自分の外に、幸・不幸の原因と結果を求めることです。“あの人が悪い”“条件が悪かった”といった、責任転嫁もそうでしょう。“まさか”という試練に遭った時、信心への確信が揺らぎ、億したり、境遇を嘆いたり、人を恨んだりする不信もそうです。たとえ、人生の途上で、自分の思い願った通りにならなくても、「負けじ魂」の人に決して悲観はありません。戸田先生は、女子部の友に語られました。「もったいなくも、御本仏と同じ生命を持っている自分自身に誇りを持ちなさい。気高い心で、人生を勝ちぬくことです。自分自身を卑しめていくことは、絶対にあってはならない」“自分なんてだめだ”“自分には無理だ”など、さまざまな人生の落胆や感傷に流されず、悠々と乗り越えてゆけるのが日蓮仏法です。本来、尊極な自身の生命を矮小化させようとする「元品の無明」を決然と打ち破るのが、妙法の功力なのです。いわば、唱題とは自分自身が仏であることを覆い隠す無明との闘争です。ゆえに真剣勝負です。唱題で不信をねじ伏せ、小さな自分の殻を打ち破ることです。題目こそ、悲哀さえも創造の源泉に変えゆく根源の力なのです。【池田大作先生の講義「世界を照らす太陽の仏法」】大白蓮華2018年2月号
May 5, 2018
閲覧総数 2462
-
33

議論する理由
専修大学法学部教授 岡田 憲治解釈や理解を共有するための確認これから何回かにわたって、議会政治の基本のお話をさせていただきます。最初は、そもそもの話の中でも、「本当にそもそもの」お話です。それは「政治において私たちはなぜ“議論”するのだろう?」ということです。議会は、「議」論をする「会」合ですから、議論するのが前提です。国会の会期中の今も議論がなされています。議論と聞くと、ああだこうだと自説の宣伝合戦をしている、あるいは誰しもがぐうの音も出ないように相手をやり込めようとしているのだと思うかもせれません。つまり、議論とは戦いだということです。しかし、政治において議論が必要な根本の理由とは、相手を叩きのめすことにあるのではありません。議論とは、私たちの現実をどう捉えるかをめぐる解釈や理解を共有するために、複数のものたちの考えが「どこまでは同じ道を歩み、どこから分かれ道になってしまったのかを確認する」ためになされるのです。政治とは(いろいろな意味で使われる言葉ですが)、「今、われわれが直面している現実とはどういうものか?」という問題に、「正しいと思った解釈を言葉にして他者に伝えること」です。当然「これが現実だ!」「それは幻想で、本当の現実はこっちの方だ!」と対立します。これが、政党が複数ある理由です。具体的な例で言えば、景気が冷え込み賃金も上がらない時に、「消費税を上げるか凍結するか」について、与野党の間でその現実判断を支える根拠はさまざまでしょう。この時、厳しい財政状況を考えたら「網羅的な(薄く広く税を集めやすい)消費税を活用すべきだ」という所までは同じ道を歩いていても、「その税率を上げるタイミング」という所で、「なるべく早くだ」という道と「景気回復後だ」という道に分かれてしまうのです。こういう筋道の違いは、「消費税率アップはどうか?」と尋ね「それは良いが時期が悪い」と返し、「手遅れになる前だ!」と反論し、それぞれの主張の根拠を示し合わなければ分かりません。そして、道が分かれたことの確認によって同時に「消費税率という問題には、たくさんの付随する問題(その時期、上げ幅、逆に所得税との連動など)が含まれているのだな」という発見にもつながります。つまり、議論をすることで「共有するもの」、そして「そこに含まれる別の問題」を確認するのです。とっちめるのではなく共有地平を見つけるというわけです。【議会政治のそもそも[1]】公明新聞2018.3.1
July 4, 2018
閲覧総数 109
-
34

環境問題と仏法
第17回環境問題と仏法創価大学理工学部教授 山本 修一さん 地球の破壊は全人類の苦悩菩薩の「慈悲」の実践を学会創立100周年である2030年は、国連のSDGs(持続可能な開発目標)の目標達成に定められている年でもあります。また、SDGsの中でも喫緊の課題でもある気候変動対策においては、2030年までの10年間が「決定的な10年」と位置付けられています。その10年の〝初陣〟となって本年は、イギリス・グラスゴーで行われた国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)をはじめ、国際社会で、気候変動に関する議論や取り組みが活性化された1年でした。宗教の社会的使命を果たす上で、今日、気候変動は第一に向き合うべき課題です。ここでは、私たちが信奉する仏法が、いかに課題解決への哲理と生き方を示すことができるかについて考察したいと思います。 現代は「劫濁」まず、環境問題が深刻化するこの時代を、どう捉えるべきでしょうか。法華経方便品第2には、生命の濁りや劣化の様相を5種に分類したものとして、「五濁」が説かれています。(法華経124㌻)。「劫濁(時代の濁り)」「煩悩濁(煩悩に支配される)」「衆生(個々の衆生の濁り)」「見濁(思想の濁り)」「命濁(寿命が短くなる)」の五つです。天台大師の「法華文句」に「煩悩と見と根本と為す」とあるように、人間の「煩悩濁」「見濁」から「衆生濁」と「命濁」に至り、時代全体の濁りである「劫濁」が生ずると考えることができます。すると時代は、際限なく利潤を追求する人間の貪欲(=煩悩濁)や、それに応える大量生産・大量消費を良きこととする価値観や人生観の混乱(=見濁)が、自然を破壊し、気候危機を引き起こした「劫濁」の時代に相当するといえます。地球的問題の原因は欲望や思想の乱れ、すなわち、自己の内にあるとする仏法の捉え方なのです。次に、人間と環境の関係性について考えます。大乗仏教の「縁起」の思想は、あらゆる生命が関係性の中で存在していると説きます。私は「生命圏平等主義の立場を取っており、五陰仮和合〈注〉の概念で捉えれば、人間も、動物も、植物も、等しく尊重されるべき生命であると考えます。それらの多様な生命が、網の目のように、互いに関わり合って生きているのです。網の目の一部が切れたり、太い網が細くなったりすれば阿見全体が安定性を失うように、自然破壊による影響は、必ず生態系のどこかに現れてくることを自覚して、人間活動を行うことが大切だといえます。また、人間と環境は別々のように見えて、根源においては不可分であると捉える「依正不二」の概念があります。人間を主体の外界にある環境が「依報」に当たります。ここで、「正報」「依報」の関係性はあくまで相対的な概念であり、人間が正報で自然環境が依報といった、固定的な概念ではないことについても述べておきます。日蓮大聖人は、夫十方は依報なり・衆生は正報なり譬えば依報は影のごとし・又正報をば依報をもって此れをつくる」(御書1140㌻)と仰せです。主体があるから環境があると仰せであるとともに、「正報をば依報をもって此れをつくる」——主体は環境との関わりの中でつくられていく、つまり、環境なくして人間はないと御指南されているのです。 注 ここの衆生は五陰(色・受・想・行・識という身心を構成する五つの要素)が仮に和合した存在(五陰仮和合)であると捉える概念 衆生濁とは、現代では無気力・無関心・無責任という面にも現れているといえるでしょう。一方で、地球環境に対するそうした姿勢を転じ、環境問題の解決に積極的に取り組むのが、「依正不二」や「縁起」の思想から導き出せる仏法者としての生き方だといえます。環境破壊は、人間を含めるあらゆる生命の存続を脅かすものであり、その苦悩を取り除くことが、菩薩道の「慈悲」の実践に通じるからです。その意味で、現代の危機である環境破壊や環境汚染そのものが、菩薩道を目指す仏法者にとっては、克服すべき対象であることができます。石に述べた通り、その環境問題の根本原因の一つは人間の際限なき欲望です。現代社会にはものがあふれ返り、絶えず人間の欲望を刺激し、煩悩を生み出し続けます。それが「因」となって環境を破壊し続け、者を手に入れられなければ苦しむといった「負の連鎖」に、多くの人たちが陥っているといえます。環境問題が事故の欲望を根本原因としているのであれば、その課題の根本的な解決にもまた、欲望の制御をはじめとする、自己の精神の変革が求められます。依正不二だからこそ、主体の業因を変革すれば、主体の「報(=報い)のみならず、環境世界の「報」の変革も可能になります。ここに、一人の変革が社会を変え、人類の宿命をも転換しゆくことを教える、日蓮仏法の現代的意義を見ることができるのです。 御聖訓「正報をば依報をもって此れをつくる」環境問題の解決は宗教の社会的使命 科学のあり方私が環境問題に関心をもち始めたのは、17歳の時でした。地元・岡山で行われた高等部の層階(1971年)で、環境問題について研究発表したのがきっかけです。当時、日本では、公害による被害が大きな問題になっていました。私が生まれ育った地域も大規模工業地帯に近接し、畑に流れる工場廃液の影響で、作物が育たないと評判になっていました。農家の人たちの話を直接聞き、発表した私は、「これからの環境問題はもっと深刻になる」と、17歳ながら実感したのを覚えています。その後、大学や大学院で環境問題について研究していくうちに、当時の実感はさらに強くなりました。原点から50年——。環境破壊は、地球がこの先も存続可能かを左右する深刻な問題へと発展してしまいました。危機克服の一翼を担いたいと、現在、創価大学では自然科学の立場から、東洋哲学研究所では仏法の社会貢献という視点から、環境問題の研究に取り組んでいます。◆◇◆この50年間で、世界は大きく変わりました。とりわけ科学技術の発展には、隔世の感があります。一方で、コロナ禍や気候変動に直面する現代は、科学のあり方の見直し、今まで以上に求められているのも事実です。従来の科学技術には、「ものをつくる」「物事を早く行う」「人間が楽をする」「思い通りに動かす」という四つの特徴があったと考えられることができます。どれも人間に恩恵をもたらした側面がある一方で、それらを過分に追い求めてきた帰結として、現代の危機があります。科学の発展が、そのまま人間の幸福につながるわけではありません。物質的な豊かさは、必ずしも幸福の指標ではないといえましょう。このことは、仏教を国教とするブータンが、経済規模では照国でありながらも、一時、世界一幸福度が高い国として知られるようになった事実が物語っています。全ての人が基本的ニーズを満たす少欲知足の暮らしの中で、経済成長よりも「国民総幸福量(GNH)」を増やすことを目指して、人間や自然との関係性の中に充足感と幸福を見出す国民の生き方に、学ぶべき点があります。こうして考えると、科学が進歩すればするほど、その果実を手にした人間自身も進歩しなければならないといえるでしょう。仏法は、その人間の進歩に貢献できると考えています。目に見えるものを扱う科学に対して、仏法は、心、生命、恩など、目に見えないものを大切にします。また、仏法では、苦労や悩みが何一つないような楽な人生ではなく、全てを価値へと転換しゆく「煩悩即菩提」「生死即涅槃」の生き方を教えています。そして、機械のように思い通りにはいかないのが人間社会です。思い通りにいかない現実に耐え、そこに意味を見出していくのが人間らしさだといえますし、そこに、仏法者としての生き方もあります。こうした仏法の人間観、自然観は、今日の人類が進むべき方向性を指し示すものであると思います。 他者や自然との関係の中に真の幸福と充足を見いだす 「中道」の智慧菩薩道とは、環境問題を〝自分事〟として捉え、自然との調和の関係性を築いていく生き方であることを確認しました。その実践は即、環境問題の解決への実践であるいえるのです。ところが、現実には、「そうは言っても……」と立ち止まる場面が少なくないように思えます。たとえば、「ものと心のどちらが大切か」と問われれば、多くの人は「心」と答えるでしょう。しかし、ものを目の前に詰まれれば、欲しいと思うのが人間です。あるいは、自然環境を破壊するのは良くないことだと思いながらも、大方の人は、大量生産された洋服を着なければ生きていけません。欲に目がくらんではいけないと分かりつつも、完全に欲を立つことは可能なのが現実です。しかし実は、「そうは言っても……」と逡巡した時に其の葛藤から逃げない姿勢こそが、正解なき時代を生き抜くために不可欠な姿勢であると、私は思うのです。大切なことは、白か黒かの一方を突き付けられ、あるいは選択せざるを得ない状況に直面しても、〝そうであっても……〟と悩み、逡巡する姿勢を失わないことではないでしょうか。あえて葛藤に向き合うことで、〝環境開発も、生態系の回復力を破壊しない程度に抑えよう〟といった、具体的かつ現実的な対策が生まれるはずです。仏法の「中道」の智慧にも通ずる姿勢こそが、持続可能な地球の未来を築くために、私たちが心掛けるべきものであると思います。◆◇◆忘れてはいけないのは、こうした中道の生き方は、妥協を強いられるような、息苦しい生き方ではないということです。法華経に説かれる菩薩の生き方は、「忍辱」、つまり、煩悩と不断の葛藤に象徴されます。悟りの境地にとどまるのではなく、あえて自らも悩み、葛藤し、衆生の苦悩を取り除く「慈悲」を実践し抜くのです。法華経で、そうした菩薩の姿を生き生きと描かれているように、相対立する両極端のどちらにも執着せず、地球のため、未来のためという姿勢を貫いて偏らない中道の生き方が、自他供の幸福の世界をいり開く鍵であるといえるのではないでしょうか。コロナ禍で、すぐに答えの出ない事態はあまりにも多い。その中で、こうした「菩薩道」を日々、実践しているのが学会員です。自らが葛藤しながらも、そのありのままの姿で広布の活動を前に進めてきました。そして、社会が変化し続けるからこそ、「誰も置き去りにしない」と心に決め、より一層、励ましの声を届けてきました。こうした一人一人の生き方が、コロナ禍や気候変動などの危機を克服する力となると確信します。創価大学創立者の池田大作先生は、創価教育の父・牧口常三郎先生が、「人道的競争」を展望されていたことに触れながら、自己も他者も益する「貢献的生活」とは、利他行の実践者として説かれる菩薩の生き方にほかならないといわれています。課題が山積する現代は、まさに、他者に尽くすことで自らの生命力も増すような、『菩薩道』「人道的競争」の精神が輝く時代であると思いを強くします。創価教育の遠大な構想に連なる誇りを胸に、多くの人と切磋琢磨しながら、持続可能な未来のために研究を続けてまいります。 【危機の時代を生きる■創価学会学術部編■】聖教新聞2021.12.23
April 20, 2023
閲覧総数 161
-
35

鬼胎の正体「統帥権」
鬼胎の正体「統帥権」近代日本を滅ぼしたドイツのこの薬物注射が、その後どのようにして日本という人体を蝕んだか。その仕組みを、司馬さんは特定していきます。原因物質は、ドイツ服に付着していた「統帥権」でした。統帥権とは、軍隊の最高指揮権を表し、大日本帝国憲法の一一条に定められています。統帥権は、天皇が持っている陸軍と海軍を指揮する権限で、具体的には、陸軍の参謀本部と海軍の軍令部が直接天皇とつながって、軍隊を運用する権限のことです。前述のように、日本軍はドイツから参謀本部というシステムを輸入しますが、そのために「軍の統帥権は国家の外側、君主の対外にある」という統帥権が自己増殖し、手が付けられない国内国家をつくり、ついには日本を崩壊させてしまった——というのです。司馬さんは『この国のかたち』で次のように語ります。 「統帥権とは、(中略)『軍隊を統べ率いること』である。/(中略)英国やアメリカでも当然ながら統帥権は国家元首に属してきた。むろん統帥権は文民で統御される。/軍は強力な殺傷力を保持しているという意味で、猛獣にたとえてもいい。戦前の、その当水機能を、同じ猛獣の軍人が掌握した。しかも神聖権として、他から嘴はいれば、『統帥干犯』として恫喝した」(四、85「統帥権(四)」「明治憲法はいまの憲法と同様、明快に三権(立法、行政・司法)分立の憲法だったのに、昭和になってから変質した。統帥権がしだいに独立しはじめ、ついには三権の上に立ち、一種の万能性を帯びはじめた。統帥権の番人は参謀本部で、事実上かれらの参謀たち(天皇の幕僚)はそれを自分たちが〝所有〟していると信じていた。/ついでながら憲法上、天皇に国政や統帥の執行責任はない。となれば、参謀本部の権能は無限に近くなり、どういう〝愛国的な〟対外行動でもやれることになる」(一、4「〝統帥権〟の無限性」) 司馬さんは、前章でふれたように、明治という時代を江戸時代の収穫時期ととらえました。が、昭和前期という時代をよく見ると、その収穫した実が腐ってく過程にも感じられます。腐敗の原因は、明治にあったのです。日本を「鬼胎」にした正体——それは、ドイツから輸入して大きく育ってしまったもの、すなわち「統帥権」でした。要するに「統帥権があるぞ」と言い立てることで、軍が帝国議会や一般人を超越した存在となり、統帥権が一人歩きをして、軍が天皇の言うことさえも聞かなくなっていくという仕組みです。軍の統帥権の実際の運用にあたっては、当然のことながら、政府と議会がチェックする必要がありました。まずは政府内閣が命令・人事で、そして予算決定権がある議会が、予算審議で軍隊を統御しなければいけませんでした。しかし、日本の場合、軍の統帥に関する予算について議会が主導権を持つことはありませんでした。さらに言えば、政府、内閣さえも軍の統帥権の外に置かれていきます。明治憲法下で、軍を抑えられるのは法による支配=人知をやっていた維新の功労者=明治国家のオーナーたち=元老でしたが、彼らが次々と世を去り、昭和になって、西園寺公望という元公家の老人ひとりになると、元老による軍統帥権の統制も利かなくなっていきました。明治国家の基本姿勢は、議会の意見は聞くが、最終決定権はない、というものです。軍の統帥に関する決定権は全て天皇にあると軍部は主張しました。ところが、実際には、天皇自身が決められるわけではありません。軍の中枢を挿す部課局が決定します。軍はその結果を天皇に上奏(報告)するだけで、天皇の意志をしばしば無視して押し切りました。このように統帥権は、昭和に入ると、やがてバケモノのように巨大化していきました。そして日本は迷走をはじめました。 【「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 歴史のパターンが見えてくる】磯田道史/NHK出版新書
July 10, 2025
閲覧総数 24
-
36

第七章 国家の岐路
第七章 国家の岐路安部龍太郎 いったい何が彼らを誤らせ、日本を破局に導いたのか。愚輩はそのことを明らかにしたくて物語の筆をとっているが、その真因を明らかにするのは容易ではない。ただ一つだけ言えるのは、時代がこれほど過酷でなければ、だれもが普通の社会人として人生をまっとうしていたということだ。それを許さない時代を招いた理由は二つある。一つは国際的、一つは国内的な問題である。国際的問題は、欧米列強による植民地を温存したままのブロック経済、ソ連をはじめとする共産主義国家の台頭、言論の自由を認めない全体主義の登場などによって、平和主義、国際協調主義が否定されたことだ。日本も昭和八年(一九三三)の国際連盟からの脱退によって、満州建国をめぐる国際紛争の平和解決をあきらめ、自国の利益と権益は自国で守る方針を取った訳だが、これが中国ばかりか米英までも敵にする外交的失敗につながった。国内的な問題について言えば、経済的な不況による農山村や下層民の困窮、重工業生産を支えるための資源不足、人口増加による働き口や食糧の不足などが挙げられるが、より根本的な原因は明治維新以来、日本が目ざした国家の在り方にあった。今日でも明治維新礼賛論が優勢のようだが、そろそろ見直さなければならない誤ちである。なぜなら明治維新は光と同じ程度に影の要素をもった、功罪半ばする革命だからである。何が影で罪なのか。愚輩はこの物語の中で朝河貫一の分析の結果として次の三点を挙げた。一、明治政府が作り上げた天皇中心の軍国主義体制。一、維新の指導理念となった吉田松陰の海外進出政策。一、薩長を中心とした藩閥中心の政治。おそらく維新を成し遂げた指導者たちは、この方針が当面の危機を乗り越えるための方便だと分かっていただろう。ところが時代が下がり、明治の元勲の子どもや孫の代になると、大局的な判断ができずに教条主義になり、次第に硬直化していった。 【連載小説「ふたりの祖国」157】公明新聞2025.2.11
October 6, 2025
閲覧総数 32
-
37

政策の哲学
政策の哲学中野 剛志 著 経済政策の対立理解に絶好明治大学 教授 田中 秀明 評 本書は、民主国家における全ての国民にとって必要な「政策哲学」を論じるものである。有権者全員が広い意味での「責任ある政策担当者」だからと著者は説く。政策は政治家や官僚だけがつくるものではない。本書は序論からはじまり、10章と結論で構成される。第1章は、経済政策に大きな影響を与えている主流は哲学の問題点を指摘する。第2~8章は科学・国家・制作などの基本的な概念を整理している。特に、本書の核となる「公共政策の実在論的理論」が展開される。これらを踏まえ、第9章では財政政策について、第10章では政治のあるべき姿について、具体的に議論する。結論では、公共政策の実在論的理論こそが21世紀に必要な政治哲学であると主張する。本書を読んで最初に驚くのは著者の博学である。化学、哲学、経済学、政治学、社会学など関連する論文や研究を丹念に紹介している。哲学などと聞くと読むのを躊躇するかもしれないが、本書は実践的な政策散る案のあり方を論じている。それは、近年に日本の経済政策に関係する。日本経済は、90年代初頭のバブル経済の崩壊以降、全体としては低迷している。長らくデフレに陥り、人々の所得は低下した。これを打開するべく登場したのが、異次元の金融緩和などを軸とした「アベノミクス」である。その効果を巡っては、経済学者の間で賛否両論が繰り広げられている。著者は、これまで経済政策の在り方を支配してきた「主流派経済学は科学ではない」と断じる。同経済学は、非現実的な前提を置いて、小さな政府、規制緩和、民営化、健全な時勢、貿易の自由化などの政策を実行したため、金融危機、長期停滞、格差の拡大、貧困の増大などをもたらしたと説く。また、健全財政という財政に規律の根拠も非科学的だと主張する。著書が拠り所とするのが公共政策の実在論的理論であり、「国家政策が成立し得る存在的な条件を明らかにする理論」だ。ここでは、政策担当者の「裁量」がいっそう重要となると指摘する。そうであれば、日本における政治・行政や政策過程の実際について、もう少し議論を期待したい。著者は国家公務員であり、実態を熟知しているからだ。元より税制債権が目的ではなく、日本が直面する当面の課題は人口減少をのりこえることである。しかし、「年収の壁」などが典型的なように、現実の政策は問題解決には遠い。10年以上にわたり毎年2兆円を使い地方創成が進められたが、東京一極集中は是正されていない。市場は完全ではなく、政府の役割は重要である。しかし、市場が失敗すると同様に制作も失敗する。政治家や官僚は神さまではないからだ。著者は、政府の問題を分析する公共選択理論も批判する。傾聴に値するが、現実として日本の政策過程には問題が多い。議論は尽きないが、それほど本書の問題的期はおもしろく、経済政策のあり方について知的興奮をよぶ。経済政策を巡る対立を理解するには絶好の本である。(集英社 1980円)◇なかの たけし 評論家。東京大学卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。エディンバラ大学大学院より博士号を取得。主著に『日本思想史新論』(ちくま新書)。 【読書】公明新聞2025.3.31
November 13, 2025
閲覧総数 17
-
38

森には魔法つかいがいる
森には魔法つかいがいる<震災でも、森は崩れませんでした。そして川は、森の鉄を海へと届け続けていました。>宮城県気仙沼市のカキ漁師でエッセイストの畠山重篤さんが中学の国語の教科書に書いた『森には魔法つかいがいる』にある◆森の落ち葉が腐葉土となり、それに含まれるフルボ酸が鉄に結び付き「フルボ酸」となって川から海へ運ばれ、植物プランクトンの成長を促し、豊かな海を育む。森と里と川と海の連鎖を、子どもたちにわかりやすくと耐えようと心を砕いたという◆畠山さんが3日、81歳で亡くなった。1989年、漁師仲間と気仙沼湾に注ぐ、大川需流の根室山(岩手県一関市)でブナの広葉樹を植える「森は海の恋人」を始める。流域住民の環境意識も高まり美しい海がよみがえった。リアスの海に面した舞根の自宅を訪ねると、いつもゴム長靴に笑顔をたたえて迎えてくれた◆東日本大震災では、大津波で母の小雪さんを失い、自宅も養殖施設も流される。油が浮く海を目の当たりにし絶望した。だが、海に植物プランクトンが繁殖したのを知り、再起する。「それでも海を恨まない」と◆」「人の心に木を植える」と畠山さんは環境教育にも取り組んできた。その木々を森へと育てたい。(川) 【北斗七星】公明新聞2025.4.14
November 24, 2025
閲覧総数 24