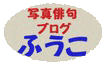2023年07月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

「恐怖のメロディ」(クリント・イーストウッド監督、1971年、アメリカ)
邦題「恐怖のメロディ」(監督 クリント・イーストウッド, 1971, アメリカ)。人気俳優クリント・イーストウッドの監督デビュー作。当時はまだ定義する言葉がなく「頭がおかしい人」くらいにしかとらえられていなかったストーカーに、自身も落ち度がなかったわけではないものの出会ってしまった男の困惑と恐怖を、カリフォルニアはモントレーの美しい景観と共にえがく。(あらすじ)地元のラジオ局でDJをつとめるデイブ。担当番組に決まってジャズ・スタンダード「ミスティ」をリクエストしてくる女性がいた。その女性イブリンとバーで出くわしたデイブは、成り行きで1夜を共に。デイブは全くの遊びだったが、イブリンはそうではなかった。翌日からイブリンはデイブに付きまとい始め、やがて常軌を逸した言動に、デイブはもとより、恋人のトビーなど、デイブの周りの人間をも巻き込まれていく、、、。まずは、当時アラフォーに足を踏み入れたばかりだったクリント・イーストウッドの、水もしたたるイケメンぶりが見もの。バシッと決めたスーツ姿も、ブリーフをはいただけのセミ・ヌード姿も、どちらも絵になる。そんなクリントにしつこく言いよるイブリンを演じたジェシカ・ウォルターの、時に狂気を感じさせる演技がまた迫真度200点。80年代に大ヒットした「危険な情事」に共通する怖さを秘めた映画だ。
2023.07.26
コメント(0)
-

足のむくみ〜その2
猛暑だった22日は、滋賀県南部の、源氏物語にゆかりがあるまちにあるスーパーで乳製品のデモ。心配していた足のむくみはあらわれず、心底胸を撫で下ろした。いったい何だったんだろうね、その6日前、業務を終えたあと突如おそってきた左足の痛みは。それでも、JRで地元の京都駅に帰ってくるまでは、「少し左足の前部分が靴に締め付けられているかな」程度の違和感だったのだ。なのに、約30分経って自宅にたどり着いた時には、熱っぽいものすら覚えたほどの痛みに変わっていた。靴(革靴)を脱ぎ、靴下をとるや、おやおや甲が明らかに膨らみ、腫れを帯びている。そこをおさえると、はっきりと窪みが出来、すぐには元に戻らない。むくんでいるのだ。「2日間の現場はさほど遠いところではないし、難しい案件ではないからいつもに比べてコンを詰めたわけでもなし」自分でも不思議だった。むくみは、やがて痒みに変わり、この症状が完全にとれるまでに2日を要した。ううむ???本当に何だったのだろう。聞けば、ビジネスマンの間で「パッと見は革靴と変わらないスニーカー」が人気なんだそうな。立ち仕事である以上、こちらの情報も集めていいかも知れない。写真は、22日の現場の最寄駅より撮ったもの。近くで夏祭りか花火大会でもあったのか、駅には浴衣姿の若者が溢れていた。
2023.07.24
コメント(0)
-

自分の「ウリ」を知って実践する大切さは、すべての職業に通じる。
前回の記事で、節度のあるお客さん(=基本的に試食しない)ほどイザ試食をして満足感を得ると買って下さることが珍しくないので、こんなタイプのお客さんが多い店では、「販売の前に試食。試食の前に試食をしたい雰囲気作り」を心がけなければやらないと書いた。では、お客さん目線で「試食をしたい雰囲気」とは、どんな雰囲気か? ここでは、「そのデモンストレーターが持つ強みを最大限にいかした雰囲気」と答えたい。すなわち、例えば推しの強さとクチのうまさで販売実績をあげてきた人の場合は、そんな時でもやはり少し強引かつオーバーと感じられる接客をした方が彼女(彼)の雰囲気となり、好成績をあげられる。なぜなら、推しの強さとクチのうまさは彼女(彼)の個性なのだから。 個性となれば、不思議なもので、人間は相手の短所をも受け入れてしまうところがあるのだ。ホラ、スーパーやデパート内で、見たことない? 試食した人にイソギンチャクのように食らいついている販売員に「おばちゃん(おっちゃん)、しつこいなあ、、、。でも、そこまで粘るからには、エエわ、買うたるわ」と、半分笑いながら返しているお客さんを。しかも、そんなお客さんに限って、カゴに商品を入れたあとで「頑張って売りや」などと、励ましの言葉を販売員にかけている。そもそも、売上成績のいいデモンストレーターは例外なく自分の「ウリ」を知っており、普段から現場でそれをプッシュしている。 もっとも、自分の「ウリ」を知って業務で実践する大切さは、すべての職業に通じることなのかも知れない。 写真は、1番下の孫(4歳)。
2023.07.19
コメント(0)
-

販売の前に試食。試食の前に試食をしたい雰囲気作り。
先週末の、滋賀県中部のまちにある大型スーパーでの仕事。とにかく終わった。「とにかく」とわざわざ付け加えて書くのは理由がある。他ならぬ売上実績。ぶっちゃけ。どちらの店も、メーカーが希望した数の半分強しか売れなかった。食品の値上げが続いている昨今。お客さんの財布の紐は固くなる一方だわ。もっとも2日目の店に限っては、試食数と販売数を照らし合わせた結果、対試食人数の購買確率は極めて高いことに気づいた。実に試食された方の人に1人が買って下さっているのだ(試食人数には家族数をも含まれているから、実質的な購買確率はもっと高い)。まあ、この店では何度もデモを行ったことがあり、当然ながらお客さんの層というか傾向というか、そちら方面の基本情報は得ているので、今回も自分なりに販売戦略を立てて売場には立ったんだけれど。その戦略とはこれである。「販売はとりあえす横に置いておいて、まずは試食してもらうための雰囲気を作る」。地域性なのだろうか。ここのまちにあるスーパーやドラッグストアなどの小売店に来るお客さんは、おおむねノンビリしていて、田園風景広がる田舎ならではの節度がある。つまり、「(タダで)食べたからには買わなあかん」との警戒心や義理感も強く、基本、試食はしない方々なのだ。そこをまず突き破らないと、デモンストレーションは前に進まない。こういうタイプのお客さんは、だが、いざ試食して味に満足し、商品に納得すると、あっけないくらいにポンと買ってくれることが多い。「販売の前に試食。試食の前に試食をしたい雰囲気作り」が要求されるゆえんである。写真は、記事に書かれたまちでの仕事を終え、家路につくため最寄駅で電車を待っている時に写したもの。メーカー側が示した販売目標数にははるかに及ばなかったものの、店の部門担当者、パートさん、偉いさん、店内巡回していた警備のおっちゃん、おまけに複数回店を訪れたお客さんからも「頑張ったね」と労われた、良い1日だった。
2023.07.19
コメント(0)
-

曲がり角〜天網恢恢疎にして漏らさず(てんもうかいかいそにしてもらさず)。
曲がり角に来ている?現状維持では「販売のおばちゃん」として土に還ることとなり、それも天からの命であろうからには誇りを持って従おうと決めていたが、ここへ来て、そうすることも難しくなってきた。宣伝販売の仕事は着実に復活してきていて、待遇もよくなり、仕事に入った先では私を覚えていてくれたお客さんや店員さんに「まあ、おばちゃん(又はおねえさん)、久しぶりやね! またおばちゃん(おねえさん)の声が聞けると思うと嬉しいわ」と言われるケースもちょこちょこあり、デモンストレーター冥利に尽きるのだけれど、悲しいかな、66歳になった現在、体力的に辛くなってきている、、、慣れでプロとしてのデモンストレーションはこなせるものの(現場に入ると、どんな時でも反射的にシャキッとする)。こんな状態では「販売のおばちゃん」でい続けることも、、、どうなんやろ?今の仕事をベースにしつつ類似の、何か拡張した内容の仕事を考えてもいいなとの案が芽生えた。プラス、自分にもっと自信を持っていいのだ、ともね(私の自己評価は恐ろしく低い)。なお、20年販売業の末端にして底辺に属するこの仕事をやってきて、しんからわかったこと。それは、世はけっきょく「天網恢々祖にして漏らさず」(てんもうかいかいそにしてもらさず。老子の言葉。漢文の授業でも習ったような)だということ。ハイ、天には網が張り巡らされてきて、犯した悪をごまかし通せるものではない。自分では「イヤッホー、バレなくて、トクしたぜぃ。ふふふ」と腹の底でほくそ笑んでいでいても、天はお見通し。遅かれ早かれ、必ず報いを受けるのだ。となれば、自分の心の声にじっくり耳を傾けるに限るか。写真は、真ん中の孫。
2023.07.16
コメント(0)
-

過疎地問題と東京一極集中は、合わせ鏡。
今日から2日間、仕事。どちらも滋賀県中部の大型スーパーに行く。週末は働き、他の日はのんびり。これが我がワークバランス面で最適のようだ。仕事柄、いわゆる過疎地と呼ばれる地域へもずいぶんと訪れた。そのたびに、そこの景観やバスの本数などから、年毎に深刻となる過疎地問題に触れるわけだが、これは、日本の「東京一極集中」と、実は密接に関連している。というか、合わせ鏡ね。東京一極集中。考えれば怖いことだ。何かの原因で東京が麻痺してしまえば、日本全体が機能しなくなるのだから。非常にハイリスクな現象。つまり、過疎地問題は過疎地に住む人ばかりでなく、日本人全体の課題なのだ。写真は、現在では超がつく過疎地と化したわが故郷を走るタクシー型バス。採算の関係で民間バスはとうに撤退し、その後に走らせた市の循環バスも同じ理由で数年で廃止。結局、地元のタクシー会社の大いなるボランティア精神のもと、日に数回、最寄駅までの道を走ってくれている。過疎地では、車が運転出来ない者は具合が悪くても医者にもかかれない。とは言え、彼らとてかつては「東京一極集中」となってしまった現在の日本を支えた人たち。その彼らの「生まれ育った地で死んでいきたい」気持ちを尊重して、どこに不都合があろう。
2023.07.15
コメント(0)
-

商品はもちろん、販売戦略(SP)も大事。
今日は、いや日付が変わってしまったから昨日か、とにかく底なしに暑い日だった。まだ梅雨も明けていないのに、身体の末端から溶けて自分が無くなっていくみたい。何なんでしょうね、この異様な感覚。さて、先だっての週末の土日は、大阪の下町(写真)にあるスーパーでキウイフルーツの宣伝販売。よく売れた、、、と言っても、天候の影響もあり、業務に入る前に自分が立てた販売目標には届かなかったのだけれど、それでもあの数字を出せたのだから。ぶっちゃけ、キウイフルーツの販売数は、デモ実施日が台風だったなど、よほどのナニカがない限りコケることはない。美味だし、食物繊維その他の栄養価も高いし、比較的に安価だからである。若者のフルーツ離れがささやかれるなど、全般に苦戦している果物類の中でよく健闘していると思う。これには、キウイフルーツを輸入して販売する側のプロモーション作戦も大いに関係していると、個人的に感じている。だって、それまでになかったことじゃないですか、販売商品、すなわちここではキウイフルーツそのものを擬人化してキャラクターに落とし込み、歌わせたり踊らせたり漫画の主人公にしたりして、その中で自分の特徴を語らせたりする宣伝方法。有名タレントを起用して巨額の制作費のもとに作ったCMを流すより、よほどインパクトがある。どんなに優れた商品があっても、その良さをPRする戦略がマズかったら、商品は大勢に埋もれてしまう。SP(セールス・プロモーション)の大事さというか価値を、今一度かんがえてみたいところだ。
2023.07.12
コメント(0)
-

過疎地ほどタクシーが来てくれない理由
滋賀県の近江鉄道沿線沿いにあるまち、豊郷を、19年前に仕事で訪れたことは述べた。私の記憶が正しければ、その時の店舗はユ◯ストア(現在のド△キホーテ)。今回同様、駅と店の間にはかなりの距離があり、17分か18分歩いたと記憶しているが、これまた今回同様、「行き」には全く人に会わなかった。初めて来た地なのに1度も迷わず店に着けたのは、当時の豊郷駅が有人駅だったことによる。すなわち、駅員が現在のスマホのナビゲーターアプリの役割を果たしてくれたのだ。歩いていて人に会わないということは、単純にそこの人口が少ないことを示している。さらに高齢化をも。こんなところで暮らすには、当たり前ながら自家用車必須。ところが悲しいかな、運転が出来ない人もいるし、出来ても年をとると難しくなってくる。公共機関たるバスがあっても、人口密度ぶんだけの本数しか走らず、運行経路から外れる地域も出てくる。となると、あとはタクシーしかなく、事実、地方のタクシー会社の中には、時刻やルートを固定化した、バスの小型版ともとれるタクシーを走らせているところもある。豊郷を含む地帯もその1つだ。ははーん。わかったよ、4日に豊郷駅からの予約を打診したタクシー会社の「午前8時から10時まではすごく混むので、予約時間通りに行けるとは限らない」との、事実上の断り文句の真意が。このおおもとに、観光者優先やら運転手不足やらの諸々の事情が加わった結果が、「過疎地ほどタクシーを呼んでも来てくれない」理由だろう。過疎地問題は一段と深刻になっており、その一端が、タクシー状況に反映されている。写真は、実は過疎地の我が故郷を走る、バス代行タクシー。採算の問題から民間バスはとうに撤退し、その後まちが循環バスを走らせたものの数年後に同じ理由でやっていけなくなり、結局は地元のタクシー会社の大いなるボランティア精神に甘え、このタクシーが走ってくれている。豊郷方面も、きっとそうなのだろう。
2023.07.09
コメント(0)
-

ニワトリはカメにならう
今週の火曜日は、滋賀県の近江鉄道沿線沿いにある豊郷で仕事。豊郷は、京都市内にある我が家からは電車に乗っている時間だけでも片道2時間近くかかる場所で、実に19年ぶりに訪れた(前回は2004年の9月に豆乳のデモンストレーションで)。ぶっちゃけ、遠方であるばかりでなく交通の便からも決して行きやすい場所ではないのだが、今回の案件は担当商品が冷凍食品だったことと、10時から15時までの勤務(休憩1時間)でありながらギャラは通常の18時終了と変わりなかったのでお受けした。「冷凍食品だから(試食品作りは)レンジでチンするだけでOK。楽だし、いつもより3時間も早く終わるし、それでいてギャラは変わらないし、うわーい、ラッキーな仕事だぜぃ」と、大喜びで赴いたところが、甘かった!業務日の翌日は、少なくとも午前中はずっと頭に芯があったほど、身体はダメージを受けたのだ。原因の1つに、豊郷駅(無人駅)から現場であるスーパーまで歩いたことがある。仕事の発注先であるメーカーは「スーパーへの行き帰りにタクシーを使用してくれてけっこうです」と言ってくれたのだけれど、そのタクシーが諸々の理由(この件は後に記事をあらためて述べる)で来てくれない。となれば、自分の足を使うしかないわけだ。幸いスマホの乗り換え案内アプリに到着地であるスーパーまでの地図と共に音声ナビもついているのだが、なにぶんにも知らない土地だし、誰かに尋ねようにも人が歩いていないんだよねえ、、、豊郷って。田畑が広がる中、民家やまだ開店していない個人店が並ぶ側を、朝っぱらからキツい陽射しにジリジリ焼かれながらスマホ上の地図を睨む私。その横を、トラックや企業名が入った営業車がビュンビュンと通り過ぎて行く。結局、地図上で徒歩20分とあるスーパーにたどり着くのに30分強もかかってしまった。仕事を終え、帰途につくべく、朝に歩いた道を駅に向かってテクテク。スマホの気象アプリは31℃をマーク。今度は歩いている途中で道路の検査をしているお兄さんや建物の工事をしているおっちゃん、下校中の小学生に会った。なぜだかホッ。いいもんだよ、人がいる光景って。暑さ疲れもちょっとマシになった気がする。豊郷駅に戻ってきて、駅を出てすぐの角にカメの石像があることに気づいた。それを見て、ハタ、と閃いたよ。高齢者となった今後のワーキングライフ(我が家は年金が少ないし、貯金も知れているため、夫婦共々死ぬまで働かないといけない)は、カメのスタイルでいこうとね。「ノロノロでも着実に」。ワタクシことこけこっこのニワトリは今日からカメにならうのだ。写真は、豊郷駅と駅前に設置されたカメの石像。
2023.07.07
コメント(2)
-

赤をうまく使えば、料理も美味しく感じられ、売上もあがる。
滋賀県中部にある大型スーパーでの仕事が終わった。土曜日と日曜日の連続2日間。確かに、心身ともに楽ちん。3日連続とは全く違う。ただ、家計との兼ね合いを考えれば、まだまだ理想のワークバランスとはいかず、その点に関しては未だ手探り中なのが本当のところ。さて。パプリカの話題をもう少し。近畿地方の、これはややローカルな店でパプリカ3種(赤、黄色、オレンジ)を浅漬けにして提供して宣伝販売をした時、業務終了後に店舗の部門担当者にパソコンから出してもらった売上データを見て、私は思わずもらしてしまった。「えっ、赤の数量が黄色やオレンジの倍以上? 何でなんでしょう、どの色も味は同じなのに」「いやぁ、やっぱり赤はインパクトがあるからじゃないの。ウチは普段の日でもパプリカは売上の7割までが赤やで」担当者は、特に疑問は感じていない様子で答えた。「ステーキやオムレツなんかの横にちょこっと添えるもんかて、緑の次に赤が多いしな。目立つ色やねん」確かに。もっとも、その他に「赤」という色自体が持つ特性があり、それが人間の本能を刺激した結果、食欲をそそるのだと思う。実際、赤い食べ物って、単純に美味しいものが多いよね。赤は、同時に購買欲もそそる。その証拠に、食品のセールやイベントの時には、垂れ幕から旗からテーブルクロスから、はては販売員のハッピにいたるまで、赤が大きな顔をしているよね。あれは興奮色でもある赤を活かすことで、消費者に財布を開けやすくしているのだ。となれば、この赤をうまく使えば、料理はもっと美味しく感じられるし、売上も上がるということだ。写真はパプリカ(フリー素材)。
2023.07.04
コメント(0)
-

パプリカ〜現場に立つ者と管理する者との乖離
振り返れば、コロナが全世界を襲う前まで、今頃の時期はしばしばパプリカのデモを担当したものだった。そう、旬なのである、パプリカにとって6月から8月までは。試食メニューは、サラダだったり、浅漬けだったり、マリネだったり、ソテーだったり、ラタトゥイユ(フランスはニース風の煮込み)だったり。この中で、ダントツ人気だったのは、マリネ。ポンポン試食が出て、ポンポン売れた。もっとも、裏話がある。この時は、試食皿をはじめとする備品、すなわちデモンストレーションに必要な資材は、派遣会社に案件をまわしたエージェンシー持ち。これが、、、とんでもない見当違いのものを送ってきたのだ。試食をつまむための爪楊枝はまだ理解出来る。問題はその試食を盛る器に、大皿を送ってきていたこと。すなわち、エージェンシーにすれば、こういうことだ。「大皿にパプリカやトマトや玉ねぎを使ったマリネを作って、そこから爪楊枝でお客様に取ってもらって」。ね? 驚くでしょう?素人判断からしてもわかるよね、そのやり方の不衛生さ。結局、私が念の為(届いているはずの試食キットが見つからないとか試食が出過ぎて試食皿やフォークが足りなくなった時に備える)用に持っていっていた小皿とフォークを使った。この点からして、仕事を出す者と、派遣会社という仲介を受けて現場に立つ者との乖離と言うか、コミュニケーション不足がわかるね。悲しいかな。これは、たびたびおこっていることなのだ。
2023.07.01
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1