PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(496)魔法の言葉
(16)今野先生
(2)知っておきたい故事
(4)イマジン
(1729)ネイチャー
(258)報徳
(1475)報徳の精神と札幌農学校精神
(11)五日市先生
(36)健康・元気
(676)鎌倉殿の十三人
(56)マザーとマハトマ
(31)札幌農学校精神
(32)青山士
(7)鈴木藤三郎
(208)宮沢賢治
(3)技術者シリーズ
(35)帝国農家一致結合
(1)報徳記を読む
(554)広井勇
(55)牧野富太郎
(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)
(220)八田與一
(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング
(91)ブギウギ
(11)光る君へ
(80)パリ・オリンピック
(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて
(4)CF 50歳から
(3)報徳の歌
(109)石破首相
(115)玉木氏
(30)坐禅
(296)安居院庄七と鷲山恭平
(246)W杯
(115)べらぼー
(44)大相撲
(40)USA
(204)朝ドラ
(79)遠州報徳
(28)文学
(43)怠れば廃る塾
(40)高校野球
(14)アン・シャーリー
(7)映画
(30)内村鑑三
(7)森 信三
(15)政治
(12)コメント新着
キーワードサーチ
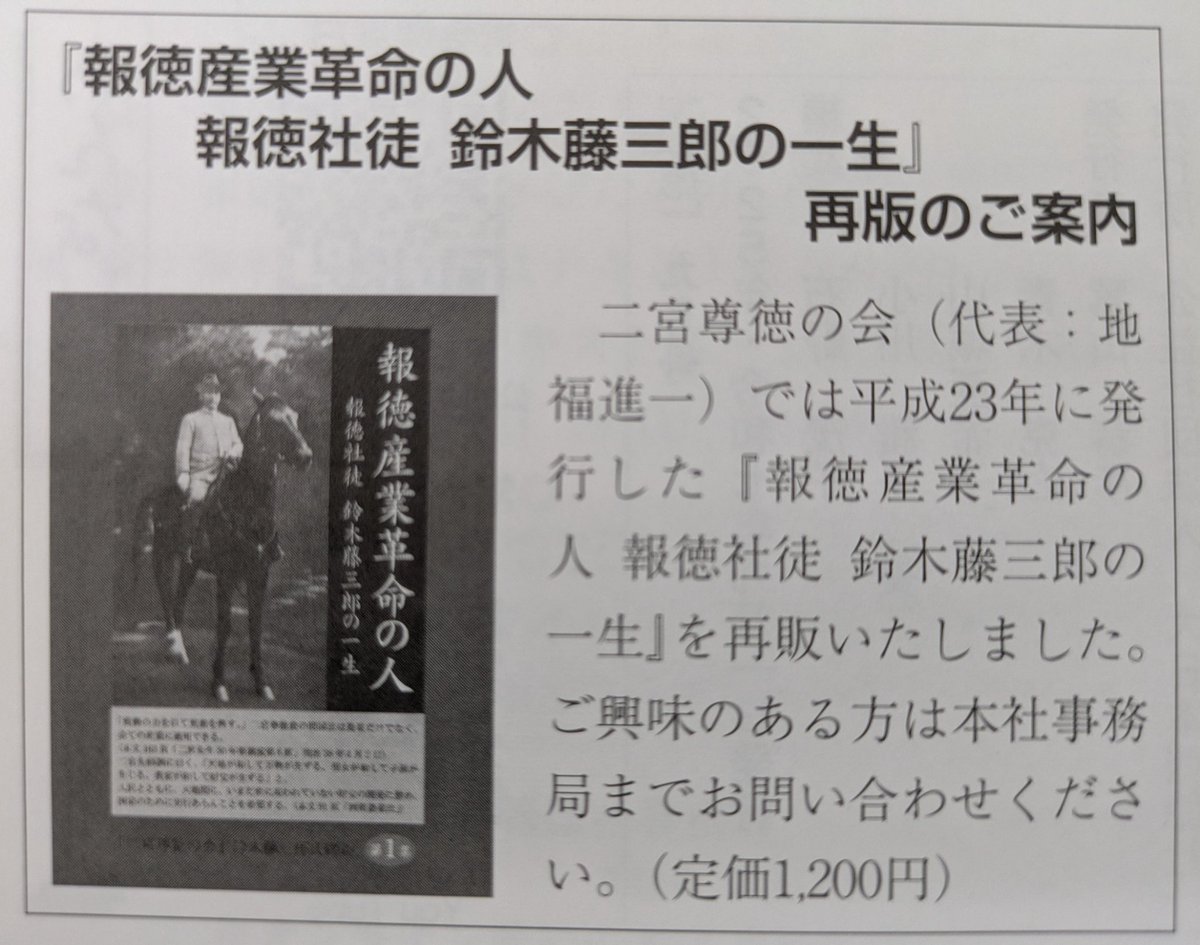
「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 77~79ページ
藤三郎の事業は、一昨(明治19)年から順風に帆をあげたような進展をして、毎年1万円に達する利益を上げるに至った。しかし、近く東京に工場を移転して、精製糖業に従事しようという希望を持っていたから、いたずらに事業に固定させないで、その時期の一日も早く来るようにと、全員それを目がけて働いていた。また、気づかわれた彼の健康も、昨年からの冷水摩擦や冷水浴で見違えるように回復してきた。この夏ごろには、東京移転のあらゆる条件は整ってきたので、彼は勢いこんで、その準備を始めていた。
明治9年(1876年)に15歳で嫁いで来てから13年間、藤三郎が氷砂糖製法発明の生みの悩みの時代を、養父母と夫との間に立って苦労のありったけを尽くしたあげくに、ようやく前途に光明もハッキリと見えて、さァ、これからというときに、寒椿の花が春風に吹かれてホロリと散るように、嘉一郎、次郎、みつの幼い三人の子を地上に残したまま急逝したのであるから、「おかんさんは、苦労をしに生まれて来たようなものだった。」と、お通夜の席で身内の女達が泣いたというが、全くそうに違いなかった。
藤三郎も、いまさらにともに過した十余年の辛苦を顧み、あとに残された三人の幼児の前途を思えば、涙を新たにせずにはいられなかった。しかし、いつまでも涙に浸っている訳にはいかない。事業は今、飛躍の一頂点に達して、一刻のすきもなく彼の活動を待っている。よしっ、精製糖の事業を完成して、わが国の産業の発達に貢献することで、養父にも妻にも、菩提を弔う手向けとしよう!彼は、そう覚悟をきめて、葬式を済ますなり、また東京移転の計画に没頭した。
この明治21年(1888年)という年は、藤三郎にとっては、吉凶並び来たった年であった。4月に養父を失い、9月に妻の急逝にあった反面に、5月には冷水浴を始めて健康の基礎を確立し、10月には多年待望の東京移転の第一歩を踏み出したのである。あらゆる意味で、この年は、彼の郷里生活の大清算期であった。
亡き妻の忌明(きめい;49日)の法要を10月24日に済ますとすぐに、藤三郎は東京で精製糖事業を開始するために、吉川の弟の安間熊重夫妻を伴って上京した。3人の幼児は養母に、氷砂糖工場は吉川をはじめ工場員に託して、土もよく乾かない二つの墳墓と、思い出の多い故郷の山河をあとにして、悲しみの涙にぬれた心を、前途に燃えている大きな希望の火で乾かしながら、彼は元気に出発したのであった。
東京へ着くとすぐに、先年、数ヶ所を候補地として選んでおいた中から、再びよく調査考究した結果、工場移転地を南葛飾郡砂村(現江東区北砂町)と決定した。ここは小名木川の南岸であって、この小名木川は、隅田川と中川とに貫流しているので、今のように鉄道やトラックの便の全くなかった時代には、原料や製品の運搬に、この舟運が非常に役立った。それであるから、その後20年程の間に、この小名木川の両岸には大小の工場が建ち連らなって、全くの工場地帯となったのであるが、この時代は、まだ文字通り狐狸のすみかであった。ことに不思議なことは、この地は、村人から「阿波様の下屋敷」と呼ばれて、江戸時代には蜂須賀侯の下屋敷のあった所で、八代将軍吉宗が享保12年(1727年)に琉球から取り寄せた甘蔗の苗を、浜や吹上のお庭で試作させたあとに、江戸近在では西の大師河原村と、東ではこの砂村新田へ初めて本式に栽培させたという、砂糖には深い因縁のある所であった。
藤三郎は、ここの土地数千坪の買収を終って、12月1日に地所内にある百姓家へ安間夫妻とともに引き移るとすぐに、その報告や今後の打合せなどのために、郷里へ帰った。森町では養母のやすが、老いの身で3人の幼児を養育するのに、一方ならない難儀をしていた。それを見かねて福川が、その縁続きである同町中町の質屋、比奈地久三郎の二女こと(慶応2年(1866年)8月13日生)を後妻に迎えるように勧めた。藤三郎も、その必要を認めたので、この恩人の言葉にありがたく従った。喪中のこととて式は内輪だけであげて、彼は、また、単独で上京した。
ことは極めて小柄で、身長は四尺六寸(1.4メートル)くらいであった。森町では祭礼をなかなか盛んにやって、その時は、町中を若い衆が勢いよく引き出す山車の上で、童女が手踊りをやった。幼い頃のことも、若い衆におぶって連れて行かれては、そこで踊らされた。色白で目鼻立ちのパッチリとした小柄のことが、高い山車の上で踊る姿は、まるで生きた人形のようだとはやされた。そして、質屋の箱入り娘に成長して、町の教員と結婚した。だが、間もなく夫が病没したので、生家へ帰っていた。それで、ことも再婚だった。
ことは22歳で鈴木家の人となると、その日から嘉一郎(9歳)、次郎(5歳)、みつ(1歳)の三児の母とならなければならなかった。嘉一郎はきわめておとなしい子であったが、次郎はその反対に極端な腕白小僧で、しかも「泣き次郎さ」といわれた位の泣き虫であった。また、みつは癇の強い子で、どうしても負うか抱いて寝かしつけなければ眠らなかった。冬の寒い晩に、家人の眠りを妨げないために、ことは、泣きむつかるみつを負ぶって1時間も2時間も外を歩いたものだった。
-
補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その… 2025.11.18
-
補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その… 2025.11.17
-
補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その… 2025.11.16









