-
1

シェイクスピア(福田恆存訳)『ヴェニスの商人』
シェイクスピア(福田恆存訳)『ヴェニスの商人』~新潮文庫、1993年改版~(William Shakespeare, The Merchant of Venice) 劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)によるあまりにも有名な作品(喜劇)です。 簡単にメモしておきます。 借金に苦しむ友人バサーニオーのため、いつもは批判していたユダヤ人シャイロックからお金を借りることにしたアントーニオーですが、シャイロックは約束を守れなかったらアントーニーの肉1ポンドをもらうという証書を書かせます。 一方、貴婦人ポーシャには、世界各地から求婚者が訪れますが、父の遺言で、3つの箱のうち正しい箱を開けた者のみが結婚できるというルールがありました。バサーニオーは、彼女と結婚し、アントーニオーへの今までの借金も返そうとするのですが…。 そして、アントーニオーの商船が難破するというニュースが入ってきて、約束の期日までにシャイロックへの借金が返せなくなったアントーニオーは、法廷でシャイロックと戦うことになります。 アントーニオーの分が悪い中、法学博士が法廷にやってきて…。 詳細な解題・解説を読むと、強欲なユダヤ人シャイロックに対する評価も様々なされてきたことが分かりますが、それを踏まえても、普段あそこまでアントーニオーから罵詈雑言を浴びせられ、あのような結末を迎えるシャイロックが気の毒に思えてしまいます。 とはいえ、アントーニオーも、法廷の議論の中で、反省する面があったなら良いのですが…。 意味不明なのはバサーニオーで、ぜいたく暮らしのためにアントーニオーから借金はするは(さらに、シャイロックに借金させてまで!)、貴婦人と結婚して金持ちになろうとするは、私には好きになれない人物でした。 解題から、『ゲスタ・ロマノールム』(ヘルマン・ヘッセ(林部圭一訳)『ヘッセの中世説話集』白水社、1994年の記事参照)に、三つの箱選びの題材があることを知りました。まだ目を通せていませんが、手元の『ゲスタ・ロマノールム』(伊藤正義訳、篠崎書林、1988年)では該当の話は第251話で、とりいそぎそこは確認して勉強になりました。 あらためて、訳者の福田氏の解題と中村保男氏による解説が詳細で、勉強になります。(2025.09.08読了) ・海外の作家一覧へ
2025.11.23
閲覧総数 10
-
2

乾くるみ『ジグソーパズル48』
乾くるみ『ジグソーパズル48』~双葉文庫、2021年~ 私立曙女子高等学院の生徒たちが様々な謎や事件に挑む作品集。それぞれ独立して読める7編の短編が収録されています。―――「ラッキーセブン」生徒会室に集まったメンバーで、トランプのゲームで遊ぶことになった。ところが、真のデスゲームになってしまい…。メンバーの持ち札を読み、危機を脱出できるのか。「GIVE ME FIVE」カラオケ店の2つの部屋に分かれていた生徒たちが知り合いだったため片方の部屋に集まって盛り上がっていた。ところが、空いたかっこうになった部屋で、置いていた高級いちごが食べられていたことが発覚する。探偵役をつとめることになるバイト店員がたどりつく真相は。「三つの涙」アパートで起こった殺人事件。同じアパートの別室に住んでいるため事情聴取を受けた住人、事件の担当となった刑事、被害者となじみのあったスーパーの店員という、事件に関係する3人のそれぞれの娘が学院の生徒だった。被害者が買い物の際に持ち帰ったはずのアイスだけが現場からなくなっていたという謎。彼女たちは事件の真相解明を目指すが…。「女の子の第六感」サッカーの試合で、同級生から頼まれていた限定グッズが当たるかもしれない福引に挑戦した生徒が、翌日から様子がおかしくなってしまった。依頼していた生徒の様子もどこかおかしく…。「マルキュー」経済上の事情でバイトを始めたところを見つかってしまったため、特別進路指導クラスの9組、通称マルキューに新たに異動してきた生徒をなんとかするため、彼女に特待生をとらせて学費を免除させようと結束したメンバーたち。スポーツ大会にも試験勉強にも全力を尽くすなか、スポーツ大会ではアクシデントに見舞われ…。「偶然の十字路」卒業式の後、防音棟に訪れた生徒たちのなかで、一つの事件が起こる。不祥事を起こして留年確定となった生徒が復帰したその日、その生徒が何者かに殴られ倒れているのが発見された。防音棟にいたメンバーに犯人がいるはずだが、方法にもアリバイにも謎が残り…。「ハチの巣ダンス」飲み屋にスマホを忘れ、取得した犯人から金銭を要求された同級生を救うため、犯人のもとに侵入したマルハチのメンバーたち。しかし、スマホは、開けるのが困難な、奇妙なかたちの引き出しにしまわれていて…。――― それぞれの短編集の登場人物は基本重複していないので(たまに言及されることはありますが)、冒頭にも書きましたが、それぞれ独立した短編となっています。殺人事件を扱うものもありますが、基本は日常の謎や困難な状況をなんとか乗り越えようとするタイプの物語です。 「ラッキーセブン」は『セブン』にも収録されています。これのみ独特な世界観です。 「GIVE ME FIVE」「女の子の第六感」は日常の謎ものとして、好みの作品でした。 唯一の殺人事件を扱う「三つの涙」はどちらかといえばホラーテイストの作品。 全てにはふれられませんが、全体を通じて「マルキュー」が一番好みの作品でした。 各短編タイトルの数字を合計すると48になるなど、凝った作品集です。 全体を通じて楽しく読みました。(2023.01.13読了)・あ行の作家一覧へ
2023.05.13
閲覧総数 196
-
3

西尾維新『栄光の仕様』
西尾維新『栄光の仕様』~講談社、2006年~「戯言シリーズ限定コンプリートボックス」の付録の一つ、豆本です。京極さんの豆本もいくつかありますが、それらより少し大きいです。 こんな話でした。 高校生になったばかりのわたしは、自分の趣味―読書を仕事にしようと考えた。いまの自分でもできそうなこと…ということで、わたしは書店でバイトをはじめた。 仕事にもなれてきて、レジ担当になったとき、わたしはある客に興味をもつようになった。部活帰りらしい女子中学生、富山たあとちゃんである。 初めて私がレジでたあとちゃんに接したとき、彼女は有名ミステリ作家のシリーズ最新作を買った。翌日、たあとちゃんはその前作を買いに来た。さらに翌日、さらにその前作を買いに来た。ついに、下巻から先に買う、という行動をされ、わたしは我慢できなくなった。本は順番に読むべきだ―そういう考えの自分には、たあとちゃんの行動は理解できなかったからである。わたしは言い訳をして先輩にレジを任せ、たあとちゃんを追った。 たあとちゃんの最初の発言を読んで、ぞくぞくしてしまいました。たあとちゃんの謎の行動が(本は順番に読むべきという考えがなければ謎でもなんでもないのでしょうが)描かれた後なのもあるのでしょう。発言を逆から読んでみましたが無意味でした。ランプライト語だそうです。あぁびっくりしました。 私も、シリーズものは順番に読むべき―とまではいわないまでも、やはり順番に読んだ方が良いよ、と思って本を読みますが、「シリーズものを順番に読んだ方が良い」ということさえ、異なる価値観に照らせば根拠薄弱なのかもしれないな、と感じました。登場人物など、順番に読まないとわかりにくいのは間違いないと思いますが、たあとちゃんのような考え方もあるな、と。 唐突な無意味な文章など、笑える要素もありました。面白かったです。
2006.10.01
閲覧総数 223
-
4

横溝正史『血蝙蝠』
横溝正史『血蝙蝠』~角川文庫、1981年~ 昭和13年(1938年)~16年(1941年)に書かれた、横溝さんの11編の短編を収録した作品集です。では、それぞれについてコメントを。ーーー「花火から出た話」打ち上がった花火から落ちてきた花を拾った男が、怪しい男たちにつけねらわれてしまう、という話。この手のラストが好きです。「物言わぬ鸚鵡の話」口がきけなくなった妹に友人から届けられた鸚鵡も、舌を切られていて鳴くことができなかった。鸚鵡の秘密を探る「私」は、恐ろしい背景を知ることになる。「マスコット綺譚」幸運の護符を持っている女性が、自分の本当の幸せを考える話…とでもいいましょうか。手に入れたら急に幸せになるけれど、失ってしまった途端に不幸が襲ってくる…そんなマスコットを持った女優の早苗さんが主人公です。素敵な話でした。「銀色の舞踏靴」映画を観ていた敏腕新聞記者・三津木俊助の上から、銀色の舞踏靴が片方落ちてきた。靴を落としたとおぼしき女を追うものの、女はきちんと靴をはいている。そんな中、当の映画劇場では、銀色の舞踏靴を履いた女が殺されていた…。 三津木俊助と白髪の名探偵・由利先生が活躍する物語です。つかみが良いですね。「恋慕猿」こちらも良かったです。いわゆるミステリとしての事件も謎解きもあるのですが、一途な猿の思いに、猿使いの男がもつ悲しい雰囲気、そして主役ともいうべき女給さんのひたむきな思いなどなど、読み物として面白かったです。「血蝙蝠」若い男女が肝試しの舞台に選んだ「蝙蝠屋敷」で、グループの女が女性の遺体を発見する、というところから始まります。第一発見者のその女は、その後、不審な男につきまとわれ、後には、密室状況で何者かに胸を刺されてしまいます。 本作も、三津木&由利先生の探偵譚です。こちらも、ラストが良かったです(ハッピーエンドとはいいませんが)。横溝さんの探偵小説には、事件に巻き込まれた人達のその後の人生にまで心配りがあり、それが魅力の一つだと思うのですが、本作でもそれを感じました。「X夫人の肖像」絵画展に出品された絵のモデルは、5年前に失踪したお澄ではないか…。妻とともに絵画展に出かけた隆吉だが、二人は、まさにその絵が盗まれたことを知る。そして、画家に出会い、悲しい事件について知ることになる。 こちらも良かったです。話の方向は違うのですが、どこか「恋慕猿」のような物語性を感じる作品でした。「八百八十番目の護謨の木」ボルネオが舞台の映画を観ていた美穂子は、そこに恋人の無実を証明できる証拠を発見した。ボルネオの農園の長、緒方とともに帰国していた恋人は、その緒方殺害の容疑をきせられながら、姿を消していた。関係者とともにボルネオを訪れた美穂子は、その証拠を求めてオガタ農園を目指す。 海外が舞台になる作品は、横溝さんの作品ではほとんど内容に思います。本作は、日本での事件の真相をおってボルネオに行くという、そのスケールの大きさが印象的です。「二千六百万年後」表紙見返しの紹介によれば、横溝さん唯一のSF作品です。オチが時代性を反映しているためか、ちょっと唐突な感じも受けましたが、楽しく読みました。ーーー 本書も数年ぶりの再読なのですが、最後の二編は、印象に残っていました。どちらもスケールが大きいですから…。 後の金田一耕助シリーズのような、ガチガチの謎解き物語は少ないですが、どれも面白かったです。(2008/08/01読了)*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2008.08.03
閲覧総数 1399
-
5

筒井康隆『ホンキイ・トンク』
筒井康隆『ホンキイ・トンク』~角川文庫、1973年初版(1983年、第25版)~ 久々に、筒井康隆さんの本の紹介です。本書は短編集で、8編の短編が収録されています。 印象に残った作品について、ふれていきたいと思います。「ワイド仇討」は時代物なのですが、こういう作品はいいですね。 江戸末期、父親を殺された敵を討つために、旅に出た高瀬典輔という侍と、従者のおれ。旦那様(高瀬)は腕はいいが、人を傷つけることは好まない。おれたちは、刀を使った見世物で収入を得ながら旅を続けていたが、そこで、仇討ちをしなければならない状況にありながら、仇討ちするには不向きの気性の猿使いが合流。ときは明治になり、仲間も増えた俺たちはマスコミに紹介され、仇討ち仲間がどんどん増える。そして、彼らの敵と彼らの合同仇討ち大会が、マスコミ主催で行われることに…。 仲間がどんどん増えるあたり、まるでドラクエの仲間が増えていくような印象を受けながら、にこにこと読みました。こちらは、みなさん戦意がないので、なごやかな大家族が形成されていくような感じです。 …ラストはなんとも凄惨で、最後のおれのつぶやきが余韻を残します。「断末魔酔狂地獄」こちらは、平均寿命が、女性は160歳、男性は145歳となった世界での話。マスコミは、老人向けのテレビ番組をどんどん作り、雑誌も、『老人パンチ』『プレイ・オールド』『老婆自身』など、老人対象のものがどんどん作られます。 …こちらも、壮絶な、それこそ地獄のような状況が描かれます。が、すさまじい老人たちを中心に描くことで、逆に社会のあり方の風刺になっているのはさすがですね。「雨乞い小町」も歴史物で、面白いです。 朝廷にとりいって調子にのっている藤原氏をこれ以上のさばらせないようにするべく、なんとか雨乞いの句によって雨を降らしたい小野小町。在原業平らと6人で悩んでいたが、20世紀からやってきた星右京の知恵で、雨を降らす装置を作ることになる。小町が斎戒に入ってからも、右京たちは必死で装置を動かす。 在原業平の一人称で物語が進みます。私は非常に日本史にうといので、うんちくの方はさっぱりですが、筒井さんの作品としていえば、「この時代には花札はまだない」ということを歴史上の人物が言うなど、その他の短編でも見られるような、時間軸を無視したような台詞があって楽しかったです(秀吉が新幹線に乗る「ヤマザキ」という短編を連想しました)。 また、星右京さん(分かりやすい名前ですね)が平安時代を訪れたために、もともと星右京さんが生きている20世紀の歴史は変わってしまうことになるパラドックス、それを解決する多元宇宙論など、その他の筒井さんのSF作品でふれていた話も織り交ぜられていて、またその話を小野小町たちが一緒になってするというところが良いですね。「小説『私小説』」も面白かったです。 大作家の能勢灸太朗は、小説とは私小説であるべきだとして、とにかく私小説を発表していた。しかし、彼が見下している若い作家たちからの批判も上がるようになり、ますます若い作家を嫌うことになっていく。そんな彼が、若者に対抗すべく、しかし、あくまで私小説で勝負したいと考えたとき、ある考えが浮かぶ。自分の妻はとにかく自分に尽くしてくれる。それなら、まず問題はないだろう…そう考え、彼は女中と浮気することを決意する。 その後、灸太朗が、その経験をおりまぜて発表した作品を紹介し、実際はどんな状況だったかという描写が続き、悲惨なラストを迎えることになります。 一つには、小説のあり方を問うような作品でもあると思うのですが、それ以上のなにかが感じられる作品でした。滑稽なドタバタシーンもありますが、読後感は良くないですね…。 表題作「ホンキイ・トンク」は、南欧の小国であるバカジアに、コンピュータをもっていく会社員が主人公です。予算の問題から、現地に入るのはその会社では彼のみ。そして彼は、依頼主の王女と仲良くなりつつ、コンピュータを彼女のために組み立て、使い方を説明します。バカジア国王女は、そのコンピュータを使って、政治的決定を行うのでした。 こちらは、途中は不安になりましたが、さわやかな読後感の物語でした。 本書には、なんとも不快になる作品もありましたが、それでいながら面白かったです。強烈な風刺、そして、時には不快感さえ与える文章(語彙、設定)さえも、筒井さんの大きな魅力の一つだと思うのですが、くせになります。
2007.11.04
閲覧総数 742
-
6

阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男』(紹介第二回)
阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男~ちくま文庫、1988年~ 昨日アップした感想の続きです。第一部(第一章~第三章)→紹介第一回(第四章 経済繁栄の蔭で) まず、都市の下層民について言及されます。<笛吹き男>についていった市民たちが、どういう状況にあったのか。第二章で少し隷属農民などがふれられていますが、ここでは下層民について詳しく論じられます。 下層民は、一般的には、「経済的に自立出来ず、都市内部で最も貧困な層」を指します。大部分は市民権を持たない人々ですが、没落した市民も含まれます。具体的には、徒弟、賃金労働者、貧民、乞食、婦人、賤民などです。 この賤民層が、下層民のなかでも最も軽蔑されていた、といいます。賤民とは「名誉をもたない者」であり、具体的には刑吏、墓堀人、遍歴芸人、司祭の子(聖職者は妻帯禁止だから、子供ができるはずないですものね!)などでした。 それよりもここで強調されているのは、寡婦と子供たちの受難です。寡婦は、仕事を探すことさえ一苦労だった、というのです。子供も、出生率が低いですし、生まれると洗礼の秘蹟などで様々な費用がかかったのです。学校もお金がかかるため、下層民の子供たちは学校へは行かなかったと考えられる、とのことです。 このように下層民の背景を見た後、仮説(3)子供の十字軍[前記事参照]、仮説(1)舞踏病について検討されます。 子供の十字軍。ほぼ同時期に、フランスとドイツで同様の現象が起こったのですが、この記事ではフランスの事例を紹介します。 1212年、羊飼い少年シュテファンが、自分にキリストが現れ、十字軍に行くよう説かれた、とサン・ドニ国王に告げ、数千人の少年・少女を集め、さらに若い司祭や年配の巡礼も加わり、出発します。マルセイユまで行進しましたが、運送船に乗り込んだまま、行方がわからなくなってしまった、というのです。子供たちは、アフリカで売られた、という説があります。 また、子供たちが夢中で踊り歩いた事例も紹介されます。これら、子供の十字軍や舞踏行列の背景には、祭がありました。謝肉祭(カーニバル)などの祭りでは、それはもう羽目を外してはしゃぎます。司祭なんかもはしゃいだみたいですね。なお、ここではキリスト教的な祭とゲルマンの民族的な祭りの関係についてもふれられていますが、記事では省略します。 この後の話との関連で重要なのは、6月24日のヨハネ祭です。この日、ドイツのほとんどの町や村で火が燃やされ、老若男女がみな集まり、歌い踊るのですね。 さて、ここでヴォエラー女史による、遭難説が紹介されます(169-175頁)。 彼女は、ヨハネ祭(失踪事件の二日前です)の際、町から2マイルほど離れたポッペンブルクの崖の上に火を点す習慣があったことから、子供たちは祭りの興奮のあまり火をつけに出かけ、その湿地帯にある底なし沼にはまりこみ、脱出できなくなった、と結論しています。 ヴォエラーの指摘で重要なのは、当時は<笛吹き男>が属する遍歴芸人の階層は社会から差別されており、あらゆる不幸な事件の責任を転嫁されていた、ということです。したがって、彼女は、この事件自体には笛吹き男の存在は不要だった、というのです。史料(2)『パッシオナーレ』に笛吹き男に関する言及がないことも、これで説明されます。 なお、後の伝説で<笛吹き男>が<鼠捕り男>に代わられるのは、15世紀末から遍歴芸人の社会的地位が高まったため、事件を彼らのせいにするのは不都合だと考えられた、という説があげられています。 ところで、なぜこの出来事が伝説として残ってきたのか。ヴォエラーは、難を免れた少数の子供によって出来事が説明されたにもかかわらず、幼い子供の説明がたどたどしく、また自分の子供の安否を気遣う親たちの激しい問い詰めに、恐怖のあまり黙ってしまった、と説明しています。事件発生当初から事件の全貌をつかむことが困難だったため、様々なファンタジーを生み出した、というのです。 阿部さんは、ヴォエラーの説に具体的な批判を挙げていません。むしろ、「沼地に沈んだという単なる事故のように見える事件でも、犠牲者が多数である限り、その背後には必ずその時代の庶民がおかれていた生活の厳しさがあったのではないだろうか」(175頁)と述べていて、現段階ではヴォエラー説を支持するように読めました。(第五章 遍歴芸人たちの社会的地位) ここでは、遍歴芸人の起源、その構成者などについてふれられた後、キリスト教によって非難され、社会的に差別される様子が述べられます。たとえば、遍歴楽師になんらかの損害が加えられた場合も、遍歴楽師は加害者の、地面に映った影に報復することを許されていただけでした。こういった描写の中で印象深かったのは、次の一節です。「このような愚弄は遍歴楽師の社会的地位の低さや差別の実態をまざまざと示す、というよりは彼らを差別する側の二人々の頽廃と貧しさをぞっとするほど明瞭に示している」(189頁)。 遍歴する者たちを差別する者たちには、「自覚されない何かへの怯え」がありました。中世ヨーロッパは、生得の社会的身分に人々が拘束されていました。このような社会で、その身分を保障する社会秩序を揺るがせかねない諸要因に対しては、きわめて過酷な弾圧が加えられた、といいます。しばらく前に読んだ赤坂憲雄さんの『異人論序説』を思い出しながら読みました。遍歴芸人は、まさに「異人」でした。 さて、ハーメルンの笛吹き男伝説と関連して、ここでの結論は次のようなものです。 芸人たちは祭の中で、興奮を盛り上げるなど、大きな役割を果たしました。彼らは祭りには関係あっただろうが、 1284年6月26日の「歴史的事件」自体にはほとんど関わりを持たなかった、というのです。祭りに彼らが関係していたとしても、それは事件の直接的原因ではなかった。だから、中世史料においては歴史的な存在としての<笛吹き男>は、その具体的な姿を現していないのだ、と。 以上で、第一部が終わり、第二部「笛吹き男伝説の変貌」に移りますが、今日の記事はこのあたりで。 紹介第三回(第二部)の紹介はこちらです。
2006.09.11
閲覧総数 183
-
7

御手洗潔シリーズ略年表
島田荘司さんの代表作、御手洗潔シリーズの略年表です。何年何月にどの事件があったか、という簡単な年表なので、何ヶ月あるいは何十年にもわたるような事件の場合などの細かい部分は伝えられません。そういう意味で、正確だとは言いませんが、少なくとも作品の時系列(出版年ではなく)は分かるかと思います。*短編は緑色の文字で示し、長編あるいは短編集のタイトルは、感想の記事にリンクしています。1948年11月27日…御手洗さんの生年月日(『本格ミステリー宣言』所収「御手洗潔研究家への手紙」参照)1950年10月…石岡さん生まれる (某作品参照)1954年6月…「鈴蘭事件」:御手洗さん、幼稚園児(5歳)(『Pの密室』所収)1956年5月…「Pの密室」:御手洗さん、小学二年生 (『Pの密室』所収)1960年代……「ボストン幽霊絵画事件」:御手洗さん、大学生、ボストン在住 (『御手洗潔のメロディ』所収)1969年10月…『摩天楼の怪人』 :御手洗さん、コロンビア大学助教授(語り手:ジェイミー・デントン)1975年………『鳥居の密室 世界にただひとりのサンタクロース』解決1977年………『ローズマリーのあまき香り』発生1978年………『異邦の騎士』1979年………『占星術殺人事件』解決1979年12月…「数字錠」 (『御手洗潔の挨拶』所収)1980年10月…「疾走する死者」 (『御手洗潔の挨拶』所収)1981年5月…「UFO大通り」 (『UFO大通り』所収)1982年5月…「山高帽のイカロス」 (『御手洗潔のダンス』所収)1982年冬……「セント・ニコラスの、ダイヤモンドの靴」 (『セント・ニコラスの、ダイヤモンドの靴』所収)1983年12月…『斜め屋敷の犯罪』1984年………『暗闇坂の人喰いの木』:松崎レオナさん、初登場1985年………「紫電改研究保存会」解決 (『御手洗潔の挨拶』所収)1986年………『水晶のピラミッド』1987年6月…「ギリシャの犬」 (『御手洗潔の挨拶』所収)1988年11月…「舞踏病」 (『御手洗潔のダンス』所収)1989年2月…「ある騎士の物語」解決(事件は1974年) (『御手洗潔のダンス』所収)1990年3月…「IgE」 (『御手洗潔のメロディ』所収)1990年4月…「山手の幽霊」 (『上高地の切り裂きジャック』所収)1990年7月…『アトポス』1990年12月…「SIVAD SELIM」 (『御手洗潔のメロディ』所収)1991年1月…『屋上の道化たち』1992年5月…『眩暈』1993年5月…「傘を折る女」 (『UFO大通り』所収)1993年8月…『ロシア幽霊軍艦事件』1993年夏頃…『星籠の海』1993年10月…『最後の一球』1994年春前…御手洗さん、日本を離れる (『龍臥亭事件』、「傘を折る女」参照)1995年春……『龍臥亭事件』(御手洗さん、ノルウェーはオスロ滞在)1996年頃……御手洗さん、ハインリッヒと出会う (「さらば遠い輝き」参照)1996年4月…「里美上京」 (『最後のディナー』所収)1996年5月…「大根奇聞」解決 (『最後のディナー』所収)1996年11月…『ハリウッド・サーティフィケイト』 (御手洗さん、スウェーデン)1997年1月…「最後のディナー」解決 (『最後のディナー』所収)1997年………「さらば遠い輝き」(語り手:ハインリッヒ・フォン・レーンドルフ・シュタインオルト) (『御手洗潔のメロディ』所収)1997年5月頃…『ローズマリーのあまき香り』解決(語り手:ハインリッヒ)2000年8月…「上高地の切り裂きジャック」 (『上高地の切り裂きジャック』所収)2001年6月…「溺れる人魚」:御手洗さんは特に登場せず(語り手:ハインリッヒ) (『溺れる人魚』所収)2001年12月…『魔神の遊戯』:御手洗さん、ウプサラ大学(スウェーデン)所属 (語り手:バーニー・マクファーレン…事件関係者、作家)2002年頃……「シアルヴィ館のクリスマス」 (『セント・ニコラスの、ダイヤモンドの靴』所収)2003年………「人魚兵器」:御手洗さん、ストックホルム大学(スウェーデン)にいた頃の事件(2003年以前??)(語り手:ハインリッヒ) (『溺れる人魚』所収)2003年11月…『ネジ式ザゼツキー』解決2004年1月…『龍臥亭幻想』2004年………「海と毒薬」:石岡さんから御手洗さんへの手紙 (『溺れる人魚』所収)2004年………「耳の光る児」 (『溺れる人魚』所収)2004年夏……『犬坊里美の冒険』(石岡さん、電話で登場)2006年2月…「クロアチア人の手」:語り手、石岡さん(『リベルタスの寓話』所収)2006年5月…「リベルタスの寓話」:語り手、ハインリッヒ(『リベルタスの寓話』所収)2020年2月…『伊根の龍神』(語り手、石岡さん)*1996年以降の事件の語り手は、主にハインリッヒ。*「クロアチア人の手」事件では、石岡さんももう55歳ですね。御手洗さんは57歳…。感慨深いですね…。*2025年刊行の『伊根の龍神』は2020年の事件。石岡さんも70歳目前ですね。※『御手洗潔のダンス』所収「近況報告」は、年表に反映していません。
2007.03.03
閲覧総数 10261
-
8

横溝正史『殺人鬼』
横溝正史『殺人鬼』~角川文庫、昭和51年(1976年)初版~ 金田一耕助シリーズの短編が4編収録された作品集です。 まずは、それぞれの内容紹介を。そして、感想を。「殺人鬼」探偵小説家、八代竜介が夜道を帰っている途中、女に声をかけられる。後に、加奈子という名前だと分かるが、その女は、義足の男にあとをつけられているようだった。後日、彼女が血相を変えて八代のもとを訪れたが、そのときも、義足の男がつきまとっているようだった。義足の男は、最近世間を騒がせている殺人鬼なのだろうか…。何かが起こるだろうと心配しているところに、ついに事件が起こる。加奈子の同居人の男が殺されたのだった。さらに、八代自身も何者かに襲われてしまう。「黒蘭姫」デパートの宝石売り場に、黒いベールで顔を隠した女がやってきた。不幸にも、そのとき売り場にいたのは新人の売り子。ベールの女が万引きをしたのを発見すると、あわて売り場主任に伝えるが、さらに不幸なことに、主任もまた新しく配属されたばかりの男だった。主任が女を事務所に呼ぼうとすると、女は主任を刺し殺した。デパート支配人は、万引きの常習犯であるベールの女を知っていた。しかし、今度の事件の犯人は、いつもの女性ではない…そう信じる支配人は、金田一耕助探偵事務所を訪れる。「香水心中」1959年(?)8月。金田一耕助は、大手化粧品会社の社長・常磐松代の依頼で、迎えの上原省三の車に乗り、軽井沢に向かった。彼は少々無理を言って、等々力警部も同行した。こちらは、いわば純粋な休暇のつもりだった。さて、一同が軽井沢についた翌日、松代は、金田一への依頼を取り下げる連絡をよこす。気が滅入った金田一と警部だが、数時間の後に、あらためて依頼がもちかけられる。彼女の長男・松樹が、人妻と心中しているように思われる事件が起こったのだった。しかし松代は、息子は心中したのではなく、殺されたのだと主張する。「百日紅の下にて」1946年9月。戦争のために、片足に義足をはめた男―佐伯一郎が、自分の家に戻ってきた。妻が愛していた百日紅の花が咲いていた。彼のもとに、復員者ふうの男が訪れた。戦友の川地からの伝言を伝え、佐伯も川地も関わった事件に関して話をするためであった。佐伯の妻―由美が自殺し、その一周忌。佐伯は、自分が留守にしていた間に由美のそばにいさせた四人の男を呼んだ。5人で酒を飲んで過ごしていたとき、男が急に苦しみだして、死んだのだった。現場の状況から、結局、男は自殺したのだという結論で落ち着いたが、川地は、それは事件の真相ではないと考えていたという。ーーー 今回本書を読んだ(数年ぶりの再読です)のは、「百日紅の下にて」を読みたくなったからでした。この短編は、横溝さんご自身、自選のベスト・テンに選んでおられるそうです。『獄門島』事件の直前の出来事ですが、戦時中に起こった毒殺(?)事件の再検討を、百日紅の下で行う二人の男。佐伯さんの回想は、どこか常軌を逸したところもあり。物語は、どこか詩的な美しさを帯びていて。全体に流れる不思議な美しさに心をうたれつつ、ラストでは切ない気持ちにさせられます。やはり素敵な物語でした。 本作の中で興味深かったのは、「黒蘭姫」事件で、金田一先生がついに事務所をかまえていることですね。京橋裏にある、古いビル―三角ビルディングの最上階、特にみすぼらしい五階に、その事務所があります。事件の年代が明記されていないのが残念ですが、解説の中島河太郎さんによれば、比較的初期の金田一シリーズの短編だそうなので、それほど新しい時期のことではないと思います。 とまれ、本書も楽しく読むことができました。*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2007.07.13
閲覧総数 1893
-
9

広瀬正『タイムマシンのつくり方(広瀬正小説全集6)』
広瀬正『タイムマシンのつくり方(広瀬正小説全集6)』~集英社文庫、1982年~ タイムマシンに関する著作を数多く発表した、広瀬正さん(1924-1972)の短編・ショートショート集です。 筒井康隆さんの『みだれ撃ち讀書ノート』に、本書に寄せた筒井さんの解説が再録されているのですが、私はまず『みだれ撃ち…』を読んで、広瀬さんの作品に興味を持ちました。 全集は、全6巻あるのですが、まずは取っつきやすいと思い、短編集の本書を読んでみました。 短編、ショートショート、評論を含め、全25編が収録されているので、すべてについて紹介するのではなく、印象に残った作品について、メモしておきます。 冒頭の「ザ・タイムマシン」は、タイムマシンによるパラドックス(多次元宇宙を想定してさえもすっきりしない点もあり)が描かれているのかと思いきや…。何も考えずに味わうには大好きなラストなのですが、考えるとちょっとわからないのが残念(自分の理解力の方が)。作品はとても楽しいです。「Once Upon A Time Machine」は、過去にさかのぼって自分の祖先を殺したらどうなるか?という、これもパラドックスをあつかった作品。ラストが良いです。 3番目に収録された「化石の街」は、タイムマシンこそ出ないものの、時間をテーマにした作品。どこか寂しい雰囲気ですが、味わいある作品でした。 ショートショート「オン・ザ・ダブル」は、ある青年が、社会と隔絶された空間で実験に挑むという話。好きな感じです。 本書には、SFではない作品も何作か含まれていますが、なかでも「にくまれるやつ」は面白かったです。 全体的に、面白い作品集でした。 全集6作はすべて入手しているので、他の作品も挑戦していきたいです。※2008年に改訂新版が出ているようです。表紙画像は改訂新版のものです。
2012.08.24
閲覧総数 204
-
10
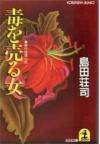
島田荘司『毒を売る女』
島田荘司『毒を売る女』~光文社文庫、1991年初版1刷(1995年7刷)~ 8編の短編が収録されています。中には、御手洗シリーズの短編も吉敷シリーズの短編も(1編ずつ)収録されているので、案外嬉しい一冊ですね。 それでは、内容紹介と感想を。「毒を売る女」主婦友達が私以外におらず、いつも私にかまってくる大道寺靖子が、梅毒を持っているかもしれないことが分かった。彼女の家族との交流を避けようとする私だが、私の夫が医者であるために、ますます靖子が接近してくるどころか、それまで既製品をおみやげにもってきた彼女が、手作りの食べ物ばかり持ってくるようになってきた。梅毒がうつされるかもしれないと、私は次第にノイローゼ気味になっていく。「渇いた都市」詐欺師の女にだまされながらも彼女にほれた男が、転落していく。「糸ノコとジグザグJigsaw And ZigZag」クリスマス特集として、リスナーが自由に3分間話すという企画をたてたラジオDJのもとに、リスナーから、自殺をほのめかす、暗号めいた言葉が届いた。番組中に行うとほのめかされている自殺を、DJはリスナーたちの協力をえて食い止めようとする。「ガラスケース」会社からもらったガラスケースの中でおたまじゃくしを飼い始めた私。ガラスケースの中では、生命の進化が再現され始める。「バイクの舞姫」15年前に亡くなった恋人が、バイクに乗って現れた―。私は、恋人が遺していた言葉をたよりに、入江長八について調べ始める。「ダイエット・コーラ」25時間周期の生活になじんでしまったダイエット・コーラの発明家に待ち受けていたのは…。「土の殺意」かつて国土庁につとめていた男が殺された。死亡推定時刻の前に、居酒屋で彼といさかいを起こしていた男が疑われたが…。「数字のある風景」ある日、目に入ってくる文字が、全て数字になってしまった。しかし、数字の規則により、私はいろんなことが予測できるようになる。ーーー いわゆるミステリーに該当するのは、「糸ノコとジグザグ」と、「土の殺意」ですね。前者は、明記はされていませんが、御手洗さんが登場、後者は吉敷さんが登場します。もっとも、特に「土の殺意」というのは、事件の犯人を暴くというよりも、社会的な問題を描くことに重点があるように思います。 表題作は、サスペンスホラーとでもいうのでしょうか。久しく見ていませんが、火サスの雰囲気ですね。このようにドラマに例えるなら、「渇いた都市」は、世にも奇妙な物語といったところでしょうか。「ガラスケース」は、綾辻行人さんのある短編を連想しましたが(もっとも、島田さんの作品の方が先に書かれています)、こういう話は好きです。「数字のある風景」は、『眩暈』の1シーンを連想させますが、この短編だけだと、ちょっと私にはよく分かりませんでした。 島田荘司さんの幅広い作風を感じさせてくれる一冊です。
2007.08.27
閲覧総数 456
-
11

筒井康隆『将軍が目醒めた時』
筒井康隆『将軍が目醒めた時』~新潮文庫、1976年~ 10編の作品が収録された短編集です。収録作品は以下の通り。「万延元年のラグビー」「ヤマザキ」「乗越駅の刑罰」「騒春」「新宿コンフィデンシャル」「カンチョレ族の繁栄」「注釈の多い年譜」「家」「空飛ぶ表具屋」「将軍が目醒めた時」 全てについて紹介するのは大変なので、印象的だった作品について、つらつらと書こうと思います。 最初の二作は、ドタバタ時代物(?)ですね。前者は、井伊直弼の首でラグビーする話、後者では、秀吉たちが新幹線に乗ります。「乗越駅の刑罰」は、解説で長部さんも絶賛しておられますが、印象的な話です。乗越料金をうっかり払えないままに地元の駅に戻ってきた主人公が、駅員にぼろくそに非難され、拷問じみたこともされ、家族からも非難される話です。いたたまれない気分になります…。「騒春」も、なんとも不快な話でした。男子学生たちが、金持ちの一人の家に二人の女子学生とともに集まり、さらには女子学生たちを乱暴しようとする話です。…どたばたの感じもないため、もやもやと不快な感じが残る話でした。「新宿コンフィデンシャル」は、おっ、これは面白いと思いながら読み進めました。人が驚くようなことは誰かがやっている、人が驚かないようなことはもっと多くの人がやっている。そこで、自分は、自分が何をやっているかも分からないことをはじめる、という男性が主人公です。初期、彼と行動をともにしていた珍子さんの協力で、事務所じみたものをもち、拾ってきたコンフィデンシャルという看板を掲げてみると、そこはコンフィデンシャルとして機能しはじめた。外から問い合わせの電話もかかるようになり、事務所も拡大し、どこからか謎の指令が届くようになる…という話。 冒頭から、これは面白そうだと思いましたが、自分が何をしているかも分からないことを初めながらも、そのことが自分の分からないまま機能するようになり、仕事も増えていくというあたりから、さらに物語に引き込まれました。「家」は、海に浮かぶ巨大な「家」に住むある少年が主人公の物語です。舞台は非現実的なのですが、純文学的な雰囲気が良かったです。「純文学的」という言葉を私ははっきりした定義を知らないままに使ってしまっていますが、雰囲気の楽しめる話でした。「空飛ぶ表具屋」は、現在の岡山県玉野市八浜出身の、浮田幸吉(1757-1847? Wikipedia参照)という歴史上の人物が主人公の物語です。彼は、鳥のように空を飛ぶことを夢見て、表具屋で身につけた技術で、空を飛ぶ道具の開発に情熱を注ぎ、ついには飛行を成功させた人物です。彼の生涯を、その飛行のための試行錯誤の過程とともに描きながら、ときおり、関連するような飛行機事故のエピソードが挿入されます。 まず、浮田幸吉を主人公とする話自体が面白く(ときには、史料や学説の紹介もあります)、岡山県という地元(本編に登場するところは、どこもなじみ深い地名です)が前半の舞台ということで、嬉しかったです。そして、先にもふれた、時折挿入される飛行機事故のエピソードと、ラストの幸吉の言葉が印象的でした。 表題作「将軍が目醒めた時」は、考えさせられる話でした。躁状態になり、自分が将軍だと思いこみ、精神病院に入院していた蘆原老人は、何十年もの躁状態からとつぜん目覚めます。大正という知らない年号に驚愕し、自分が入院していることにショックを受けますが、軍と院長の利害が一致し、しばらくこれまでのように将軍として振る舞ってほしいと言われます。正気に戻ってからも、狂気をもつふりをし続ける内に、疑問を覚える蘆原老人に、どこか感情移入しながら読み進めました。利権にしがみつく院長を批判する老人の主治医も、かなりテンション高いですが、言っていることには共感できる部分もありました。特に、院長を批判するのは良かったです。 正気と狂気については、先日夢野久作さんの『ドグラ・マグラ』(記事はこちら)を読んだりして、あらためて考えさせられていたところなので、本作も興味深く読みました。
2007.10.05
閲覧総数 1626
-
12

西洋中世学会『西洋中世研究』6
西洋中世学会『西洋中世研究』6~知泉書館、2014年~ 西洋中世学会が毎年刊行する雑誌『西洋中世研究』のバックナンバーの紹介です。 第6号の構成は次の通りです。―――【特集】中世とルネサンス―継続/断絶<序文>徳橋曜「中世とルネサンス―継続/断絶」<論文>出佳奈子「ピエロ・ディ・コジモの絵画における伝統と革新―15世紀フィレンツェにおける美術品受容の観点から―」徳橋曜「15世紀イタリアの文化動向と書籍販売」小林宜子「記憶の浄化と英文学史の創出―宗教改革期の好古家ジョン・リーランドをめぐる考察―」坂本邦暢「変容する存在の大いなる連鎖―中世とルネサンスにおける最善世界論―」伊藤博明「シビュラの行方―アウグスティヌスからパラッツォ・オルシーニまで―」上尾信也「音楽史におけるルネサンス再考―作曲家と作品の「越地域性」をめぐって―」【論文】高山博「中世シチリアにおける農民の階層区分」菊地重仁「複合国家としてのフランク帝国における「改革」の試み―カール大帝皇帝戴冠直後の状況を中心に―」辻部(藤川)亮子「「至純の愛」再考―オイル語宮廷風恋愛歌のレトリック解釈を通じて―」紺谷由紀「コンスタンティウス2世治世(337-361年)における聖室長官エウセビウスの位置づけ―宮廷宦官の人的関係に関する一考察―」【新刊紹介】【彙報】松田隆美「西洋中世学会第6回シンポジウム報告「西洋中世写本の表と裏―写本のマテリアリティと西洋中世研究―」」新井由紀夫・菊地重仁・町田有里「2013年度若手交流セミナー「マーガレット・ボニー氏による古文書セミナー」報告記」近江吉明「第8回日韓西洋中世史研究集会報告」――― 特集は、同題の2012年度西洋中世学会大会第4回シンポジウムでの5名の報告を踏まえた論考に、音楽の分野の上尾先生の論考を加えた6本の論文を収録(なお、同シンポジウムの概要は『西洋中世研究』4、2012、233-236頁参照)。 序文は問題提起と各論文の概観。 出論文は、財産目録と絵画の分析から、絵画に対するルネサンス期の態度の変化を指摘します。 徳橋論文は、印刷術の生まれる中世後期の教育的背景の確認から始まり、財産目録や書籍商の在庫目録を手がかりに、書籍販売の状況や読書傾向が14世紀から大きく変わるわけではないことを明らかにするとともに、印刷本による著者の意識変化など、まさに「継続と断絶」を示す興味深い論考。 小林論文は、イングランドでの修道院解散前後に、王から与えられた権限により教皇至上権を批判する目的で修道院写本の調査を行ったリーランドに着目し、過去との断絶を強調しようとする一方で、彼がいかに過去との連続性を見出そうとしたのかを明らかにします。 坂本論文は、哲学の観点から、神は世界を最善に作ったとの説と、これ以上善くすることができるという説がある「世界最善論」のあり方をめぐって、特にスカリゲルという人物に着目し、中世とルネサンスの継続と断絶を検討します。 伊藤論文は古代ギリシアの巫女たちの1人「シビュラ」がいかにキリスト教の著作などで描かれているかをたどり、古代からルネサンスにかけて、古代とキリスト教の連続性が強調されていたことを示します。 上尾論文は、音楽史における「ルネサンス」概念を研究史を丹念にたどりその位置づけを明らかにするとともに、ルネサンス期の音楽の諸相を論じます。 高山論文は、ラテン語、ギリシア語、アラビア語の史料の丹念な読みにより、中世シチリアにおいて農民が2つに分類されていたという通説を批判する興味深い論考。歴史学の営みの面白さをあらためて感じられる刺激的な論文です。 菊地論文はカール大帝の「改革」の様相を、特に君主の代理人ミッシ・ドミニキに着目して明らかにします。 辻部論文は、北フランスのオイル語宮廷風恋愛歌を史料として、そのレトリックに着目することで、詩人が愛を捧げる奥方を「封主」になぞらえる大前提を踏まえた論法による説得レトリックを用いていたことを具体的に示します。 紺谷論文は、宮廷宦官エウセビウスへの批判的な見方をとる先行研究に対して、宦官以外の官職の活動とも比較しつつ、彼の活動の具体的な側面と意義を再考します。 新刊紹介は43の洋書の紹介。中世地理・地図学を対象とした、ブレポルス社から刊行されている「中世学者のアトリエ」シリーズ第13巻についての小澤実先生による紹介や、栗原健先生による子供たちの謎かけなどを扱う書籍の紹介を特に興味深く読みました。 彙報は3本。第6回シンポジウムは実際に参加しましたが、八木先生によるご発表もさることながら、八木先生による特別展示「さわって体験―羊皮紙と中世写本」では、実際に羊皮紙にさわる経験ができましたし、羊皮紙片もいただけて、貴重な体験だったことを覚えています。また、若手交流セミナー(古文書セミナー)の報告、第8回日韓西洋中世史研究集会の概要報告のいずれも興味深いです。(2025.06.28再読) ・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.09.13
閲覧総数 35
-
13
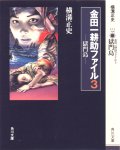
横溝正史『獄門島(金田一耕助ファイル3)』
横溝正史『獄門島(金田一耕助ファイル3)』~角川文庫、1996年改版初版~ 金田一耕助シリーズの長編です。『本陣殺人事件』の次に発表された金田一シリーズ作品ですね。 あまりにも有名ですが、内容紹介と感想を。 昭和21年(1946年)9月。「俺が死んだら、三人の妹たちが殺される。獄門島へ行ってくれ」―戦友の鬼頭千万太の言葉を受け、彼が託した紹介状を持って、金田一耕助は瀬戸内海に浮かぶ小島、獄門島を訪れた。 漁師の多い島のこと、網元の鬼頭家が大きな力を持っていた。また別格の人々が、千万太が紹介状をあてた和尚、村長、医師の三人。耕助は、和尚のもとにしばらくとどまることになる。 鬼頭家は本鬼頭と分鬼頭に分かれていた。絶大な権力を握っていた本鬼頭の前当主は亡くなり、息子は錯乱して家の座敷牢に入れられていることから、孫の千万太、そのいとこの一に期待がかけられていたのだが、その千万太が死んだ。跡取りをめぐる、血なまぐさい事件―千万太の最後の言葉が実現される嫌な予感を抱く耕助だが、ついに事件が起こる。 鬼頭家の、千万太の三人の妹―花子、雪枝、月代のうち、花子が、千万太の通夜の夜に行方不明になる。彼女の遺体は、寺の木の枝から、逆さに吊されていた。 さらに、事件は続く。花子の次の犠牲者、雪枝の遺体は、釣り鐘の中に閉じこめられていた。恐ろしい事件が続く中、本鬼頭をほとんど一人で支えている早苗も、不審な行動をとりはじめる。 私はどうにも、有名すぎる作品は敬遠する傾向があり、本書も、それほど繰り返して読んでいるわけではないのですが……ものすごく面白かったです。例によっていろんな筋を忘れてしまっていたこともあり、ぞくぞくしながら読み進めました。 獄門島の警察官、清水さんも素敵な人で、勘違いで金田一さんを留置場に入れてしまいますが、その人柄がよいので、まったくもやもやが残りません。なにより嬉しかったのは、清水さんが磯川警部に出会ったと聞いたときの、金田一さんのリアクションです。こちらまで嬉しくなって、もらい泣きしそうになりました。 金田一さんが犯人と語るシーンでも、じーんときてしまいました。 俳句、見立て……事件を彩る要素にもぞくぞくします。金田一さん自身も含め、登場人物たちの心情にも胸を打たれます。ミステリとしても物語としても、感動しました。 やっぱり面白い! 金田一さんの経歴について、あらたに分かったことをメモしておきます。 久保銀三さんの援助をうけ、アメリカで勉強していた頃、金田一さんは看護夫見習いみたいなことをしていたそうです。多少は自分でも稼ごうという意識もあったようですが、将来的には探偵になるということも意識されていたとか…。 さて、『本陣殺人事件』を解決した後、戦争がはじまると、金田一さんも召集されることになります。彼は、最初の二年間は大陸に行き、島から島へと送られ、終戦時には、ニューギニアにいました。そこで、千万太さんと出会い、良き戦友となったのでした。そして、千万太さんの遺言を果たすため、久保銀三さんに挨拶した後、獄門島へ向かったのでした……。 『獄門島』事件を解決し、東京に戻る汽車の中で、中学時代の風間俊六さんと出会い、「松月」で居候することになるあたりのことは、「黒猫亭事件」(『本陣殺人事件』収録。記事はこちら)で語られています。*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2007.07.12
閲覧総数 276
-
14

筒井康隆『朝のガスパール』
筒井康隆『朝のガスパール』~新潮文庫、1995年~ 朝日新聞朝刊で、1991年10月~1992年3月まで連載されていた長編です。新聞連載ということを活かして、読者からの手紙やパソコン通信での感想、提案を募り、それらを参考にして作られていくという、読者参加型の作品です。 まずは、遊撃隊が、他の惑星で謎の生物と戦うシーンから始まります。なるほど、この手のSFかと思いきや、それは大企業の重役たちが特に熱中している参加型のゲームで。作中でのそのレベルの主人公は、貴野原さんと、部下の石部智子さん。貴野原さんの妻での聡子さん。特に、貴野原さんがその他の重役さんたちと<まぼろしの遊撃隊>の話で盛り上がったり、聡子さんを中心に石部さんも時に参加するパーティーシーンがメインになります。が、そうした作品を書いている作家の櫟沢(くぬぎさわ)さん(=筒井康隆さんの第三の自己)と編集者の澱口(おりぐち)さんが、投書やパソコン通信での感想・提案についてコメントしたり、批評したり、怒り狂ったりするシーンも時に挿入されます。 いろいろ筒井さんの小説やエッセイを読んできて、その虚構性の追求という部分をとても興味深く思っているのですが、本作でもそれが追求されています。 現実と『朝のガスパール』という作品の関係性と、貴野原さんたちの世界と彼らが参加して楽しむゲーム<まぼろしの遊撃隊>との関係性が相似していたり、上にもふれましたように作中で現実の投書への言及があるなど、これぞメタ・フィクションだとも思います。おそらく、リアルタイムで連載を読み、しかも投書をしていた方々は、本としてまとまった形で読むよりも、もっともっと緊張感や臨場感を味わえたのではないかな、と想像します。 櫟沢さんによる怒りの罵詈雑言や、その中で展開される過去の文学作品への言及や批評、文学論などなど、こちらも大いに楽しみました。レベル4(貴野原さんたちの世界)、レベル5(ゲームの世界)などで進む物語自体も、とても面白く読みました。ある長編の人物も登場していて、その作品を読み返してみたくなったり(その作品も、ただただそのすごさに圧倒されたものです)。 物語の終盤、第百五十二回あたり以降では、思わぬ感動をさせられました。特に、314頁の台詞にはやられました…涙。 すごいです。(2008/08/17読了)
2008.08.22
閲覧総数 77
-
15

岩井志麻子『ぼっけえ、きょうてえ』
岩井志麻子『ぼっけえ、きょうてえ』~角川書店~(「のぽねこミステリ館」フリーページより再録)「ぼっけえ、きょうてえ」女郎が、客の男に話をする。妾の身の上話を聞きたいじゃて? きょうてえきょうてえ夢を見りゃあせんじゃろうか。うちのおっ母は間引き専業の産婆じゃったんよ。妾は4歳の頃からその手伝いをしとった・・・。「密告函」コレラが蔓延した町-もともと好かれていなかった町役場の助役が、病気にかかる。その様子はまるでコレラ病患者のようだった。そして彼は死ぬ直前に、コレラの疑いのある者を匿名で密告させるという「密告函」の設置を訴えた。若い弘三が、函をあらため、またそこに名を書かれた者のところを訪れるという嫌な役目を担うことになる。気丈な妻に支えられていた弘三だったが・・・。「あまぞわい」岡山市で酌婦として働いていたユミは、島から訪れる客に選ばれ、また心惹かれていき、結婚して島へと渡った。しかし、半年ほどで夫から殴られるようになる。島の女たちや男たち、さらには夫の親族にまで疎まれていた。「依って件の如し」村人に嫌われていた女の子供-利吉とシズは、まるで牛と同じように扱われていた。二人に優しく声をかけてくれるのは、竹爺と竹婆くらいだった。利吉が志願兵として中国に発ってからは、シズは彼女を嫌う人の元へ住み込みで働きに行く。ただ、彼女は牛小屋に住まわされた。 岡山弁で描かれた文章。私は岡山出身なのでさらさらと読めたが、岡山弁になじみのない人が読むとどうなのだろう。 ただ、「こわい」という独特の雰囲気は伝わることだろう。 帯にはものすごく怖いという風に絶賛されているが、私はそれほどに怖いとは感じなかった。 ただ、その雰囲気はいい。(岡山弁で描かれとる。私は岡山出身じゃけんすらすら読めたけど、岡山弁になじみのねー人が読んだらどうなんじゃろう。こえーという雰囲気は伝わるじゃろう。帯にはでーれーこえーと絶賛されとるけど、私はそがんにこえーとは感じんかった)*注:本書では「きょうてえ」が「怖い」の意味で使われていますが、私のまわりでは、特に同世代は「きょうてえ」なんて言いませんので、「こえー」と書きました。aiの音が、eeになまるのです。例。「でえこてえてえて」(大根=でえこ、炊いといて=てえてえて)まず言わないでしょうけどね。あら、oiの音もeeになってますね。さらに例。「誰なら?」(ああ、この時点で方言かも。誰だ?です)は、「でえなあ」になりますし。本書を読んだのは高校生の頃だったでしょうか。全く覚えていないので、表題作をぱらぱら読んでみたのですが、あら、面白そう。表題作だけでも読み返してみようかな。(*訂正*大学生の頃の読了記録を見ていたら、どうも大学二年生の頃に読んだようです。高校生の頃ではありませんでした)なにってかにって岡山弁です。18年間聞き続け、しゃべり続けた岡山弁です。それから仙台に行ったので、毎日のように岡山弁にふれることはなくなりましたが、岡山に帰ってくるたびやっぱり自分は岡山県民だ、と認識する岡山弁です。本書では、「おえん」とか普通に使われていますね。岡山県民以外が読んで分かるのでしょうか??(中国地方の方は案外分かるのかも知れませんが)これは、「いけない、だめだ」という意味です。「あ~、もうおえんわ!ええとこまで行っとったのになぁ!」みたいな。仙台の同期は-他にも、私と接した方々は-私の岡山弁に困っていました。県外の大学に行った高校の友人たちがほぼ全員経験した体験を紹介しましょう。例)A「島田荘司さんって、御手洗潔シリーズで有名だよね」B「じゃなぁ。ああ、でも、吉敷竹史シリーズがあるが」Bさんが岡山弁ですね。Bさんの中ではこれで完結しているのですが、Aさんは、言葉の続きを待つのだそうです。「~シリーズがあるが、しかし~」と、「が、しかし~」の部分はなんなんだ!?と思うのだそうです。でも、この「が」は逆接の助詞ではないのです。「吉敷シリーズもあるじゃない?」というニュアンスなのです。繰り返しますが、県外に出た友人はたいていこの「が」をめぐる他都道府県の方とのエピソードを語っていました。岡山県民にとっては標準語ですから、まさかこの助詞が方言だとは思ってもいなかったのです。「おえん」とか、「~じゃろ?」とか、「はようしねぇ」(早く死ね、ではありません。早くしなさい、という意味です)とかは、岡山弁だと認識していましたし、岡山弁はきれいな響きじゃないなぁ、と感じるところなのですが。ともあれ、本当に、県外に出て世界が広がりました。東北弁にもふれることができましたし☆
2005.03.13
閲覧総数 907
-
16

乾くるみ『林真紅郎と五つの謎』
乾くるみ『林真紅郎と五つの謎』~カッパ・ノベルス~「いちばん奥の個室」一部で有名なバンドのライブに、姪の保護者として連れ添った真紅郎。ライブの最後の曲の前に、ちょっとしたマジックが披露された。箱の中に入った女性。箱は鎖で空中に持ち上げられ、そして次に開いたときには、そこから女性がいなくなっていた。…ところが、その女性がライブの終了後、トイレの個室で、頭から血を流しているのが発見される。「ひいらぎ駅の怪」大雨の夜、友人とともにひいらぎ駅にいた真紅郎。そこで、女性が階段から転げ落ちるという事故が起こった。さらに、現場に居合わせた別の女性のカメラも紛失していた。小規模な駅で、そこにいる限られた人々以外に、外部からきた人がいないことが分かっているが、誰もカメラを持っていなかった。「陽炎のように」友人の妻が亡くなった。告別式に友人とその妻とともに参列した真紅郎。その帰り道から、周囲の人々が彼のあたりを怪訝に見ることが重なる。じーっと見つめてくる女性。窓際に座った真紅郎のあたりを見ながら、なにかの理由でお盆を落としてしまったレストランの店員。また、亡くなった女性とその夫をめぐり、真紅郎たちは、最近のテキリマ事件とからめながら、議論を進めていく。「過去から来た暗号」小学校時代の友人でばったり再会した真紅郎。友人は、真紅郎が暗号遊びをしていたことを懐かしげに語った。しかも、その解読表はなくしてしまったようだが、暗号文の一つは、まだ残っているという。届けてもらったその年賀状を見ながら、真紅郎は解読作業を進めていく。「雪とボウガンのパズル」大学で教えていた頃に知っていた学生と、初雪の早朝、ばったり出会った真紅郎。犬の散歩をしていたのだが、犬がその学生を気に入ったようで、二人は結局学生の下宿先まで歩く。ところがそこでは、変死事件が起こっていた。建物と塀に挟まれた狭い裏庭で、学生が死んでいた。ボウガンの矢が突き刺さっていた。怪しい足跡もなく、二階の被害者の部屋の玄関は、内側から施錠されていた。 法医学教室に勤務していた林真紅郎さん。彼は、最愛の妻を亡くしてから、職につかず、ぶらぶら生活しています。林家が裕福なために、そんな生活もできるのだとか。 どれも、謎解きの話として面白いと思います。一話目で、結局謎なんていうものは、ある観察者がそれを謎と認識しているだけで、他の人にとっては実は謎ではない、という実は当たり前のことを、ストレートに訴えてくるようなものを感じました。 二話目は、モラルの話がうまくからんできていて、面白かったです。 三話目は、かなり怖かったです。私が幽霊関係の話が苦手なのもあるのですが、テキリマをめぐる話は、小説という虚構の中でも、さらに想像の話なのに、どこかリアルで。しかもお食事中に、手を切ってどうこう、という話をするわけですよ。 …私も、一般的には食事中はふさわしくないんじゃないかな、という話でもって、食事中に盛り上がることはあるわけですが…。カニバリズムとか。 第四話。本書の中で一番面白かったような。たしかに、暗号解読自体は読んでいて退屈かもしれません。そうとう伏線、というか、真紅郎さんが暗号を解読する思考が忠実にトレースされているので、くどいとさえいえると思います。でも私はそこが楽しめましたし、そうした単調な作業の中に起こるある「ドラマ」がうまく生きているのに感動しました。 第五話は、やるせない結末です。それこそ今日西尾さんの作品の感想のところでずいぶん紹介したジョジョを例にとれば、第6部のマックイイーンの過去みたいな。 全体を通して、素直に楽しめる作品でした。
2005.12.28
閲覧総数 55
-
17

筒井康隆『宇宙衞星博覽會』
筒井康隆『宇宙衞星博覽會』~新潮文庫、1982年~ 短編集です。8編の短編が収録されています。 印象に残った作品に重点を置きながら、それぞれに、内容にもふれながらコメントを。ーーー「蟹甲癬」クレール星でほぼ唯一のクレール蟹が、絶滅寸前と知りながらも人々はクレール蟹を食べていた。そうすると、子ども以外の人々に異変が起き始める。顔の皮膚がぼろぼろになっていき、やがてクレール蟹の甲羅のようになる。その甲羅は取り外しができるようになり、裏には美味しいクレール蟹の「脳みそ」そっくりの脳みそが付着していた…。 * この話のように、地球外の星が舞台のSFはなんとなく読まず嫌いだったのですが、面白く読みました。ラストの哀愁漂う感じが印象的です。「こぶ天才」コガネムシ科の虫に似たランプティ・ダンプティを背負うと、その虫はやがて背中と一体化し、それを背負った人々は天才になる―そういう設定の話です。教育ママをはじめ、自分勝手な人間への風刺が痛快でした。「急流」時間の流れがどんどん速くなるという話。こんなラストが待っていたとは…!「顔面崩壊」シャラク星で主食となるドド豆は、調理が難しく、気をつけないと顔面がぼろぼろになってしまう…という話です。皮膚に穴があき、そこに虫が入ってきたり、壮絶な描写が淡々と語られるので気持ち悪くなりました。なんとなくへこみ気味の朝、通勤の電車で読んだのですが、割ときつかったです(それでも読むのがなんとも…)。「問題外科」タイトルの通り。勘違いで健康な看護婦(当時はまだ看護師の名称はないですので)を解剖し殺してしまう二人の外科が主人公です。すごいですよね…。「関節話法」関節を鳴らす癖のあるおれは、その癖を局長ににらまれていた。そんな折、関節を鳴らすことで会話をするマザングという星へ大使として行くことを命じられることに…。 主人公の言葉が、関節が上手に鳴らせなくなることで次第に支離滅裂になっていくあたりは笑ってしまうのですが、一方、彼が背負っている任務を考えると笑えなくもあり…。「最悪の接触(ワースト・コンタクト)」初めて地球にやって来るマグ・マグ人の代表者と共同生活をすることになったおれ。俺をいきなり殴ったり、毒入りの食事を出すかと思えば、ときに筋の通ったようなことを言い…。一週間のマグ・マグ人との共同生活の末、おれは彼らとの交流に反対するが、上司はマグ・マグ人の主張を信用し、交流をはじめることになる。 * この上司の判断や言動を読んでいると、ある種の人間関係(成績の悪い自分の子より、成績の良い他人の子が言っていることを信用する親や、この物語の通りの、ある種の上司とその部下)を連想します。何を信じるか、という基準は難しいと思いますが、なんらかの「権威」の言葉を信じやすいような気もします。うーん、難しいですね…。「ポルノ惑星のサルモネラ人間」本書の中で、最も分量のある作品です。ポルノ惑星と呼ばれる星では、全裸で生活する人間がある地域に集まって生活しており、地球人など外部との接触を拒もうとします。そしてその星では、あらゆる生物がどこか「いやらしい」性格を持っていて…。 価値観の多様性について、さらには自分たちのいわゆる「常識」がいかに閉鎖的・排他的であるかということなどについて考えさせられる作品です。本作の中で、地球ではそのものすごい性欲によって変な目で見られている男性が、ポルノ惑星の人々のある風習にいたく感動し、人間的に成長するようなシーンがあるのですが、これがとても印象的でした。 私自身はかなり保守的で考えも固い傾向にあるのですが、一方で革新や変化を望んでいる部分もあり(政治的な意味でなく、過去のサークル活動でもあったことなど、一般論として)、これまた考えさせられる一編でした。ーーー ホラー…というか、端的にいって「気持ち悪い」作品が割合多いですが、それでも興味深く読みました。筒井さんの作品には、いわば中毒にさせられるような性格があるように思います。もちろん好みは分かれるのでしょうが、私はかなりはまっています。(2008/02/21読了)
2008.02.25
閲覧総数 1946
-
18

長谷川貴彦『現代歴史学への展望―言語論的転回を超えて―』
長谷川貴彦『現代歴史学への展望―言語論的転回を超えて―』~岩波書店、2016年~ 著者の長谷川貴彦先生は北海道大学大学院文学研究院教授で、イギリス近現代史・歴史理論を専門にされています。小川幸司(責任編集)『岩波講座 世界歴史01 世界史とは何か』(岩波書店、2021年)に、「現代歴史学と世界史認識」という論考を寄せていらっしゃいます(冒頭略歴も同書の執筆者紹介から引用)。 本書は、先生が過去に発表した9本の論文を、3部構成+終章に編成した論文集です。重複する記述も多いですが、そこは逆に重要な部分と理解できます。 本書の構成は次のとおりです。―――はしがき―転回する歴史学I 社会史から言語論的転回へ 第1章 修正主義と構築主義の間で―イギリス社会史研究の現在 第2章 民衆文化史の変遷―「経験」から「物語」への転回 第3章 社会史の転回―都市史をめぐる考察II 転回する歴史学 第4章 物語の復権/主体の復権―ポスト言語論的転回の歴史学 第5章 文化史研究の射程―「転回」以降の歴史学のなかで 第6章 現代歴史学の挑戦―イギリスの経験からIII 戦後歴史学との対話 第7章 『社会運動史』とニューレフト史学 第8章 二宮史学との対話―史学史の転換点にあたって終章 現代歴史学への展望あとがき初出一覧索引――― はしがきは、本書の目的と構成の概要を示します。 第1部は、戦後イギリスにおける社会史研究の系譜を論じます(vii頁)。 第1章は、1960-70年代の社会史研究が、時間的・空間的に細分化した方向に向かうことで、長期的変動や歴史的全体像をとらえる視点の喪失に至るという「隘路」に陥っていた中、進歩主義史観などの見直しを迫る「修正主義」と社会そのものが言説=実践によって構築されたものだという視点を強調する「構築主義」の影響を受け、方法論的革新を迎えていることを、階級、ジェンダー、都市を扱う具体的な研究例を挙げて明らかにします。 第2章は、文化的マルクス主義として、経験を重視したトムスン『イングランド労働者階級の形成』(1963年)、言語論転回として、ステッドマン=ジョーンズ(この研究者は言語論転回の英語圏の嚆矢となる著作を発表したことで、本書で強調される人物の1人です)の『階級という言語』、そしてパーソナル・ナラティヴ(個人史の聞き語りに代表されるオーラル・ヒストリーだけでなく、自叙伝、日記、書館などのエゴ・ドキュメントを対象とする)として、牧師の日記から女性の家内奉公人の地位を見つめるスティードマン『マスターとサーヴァント』の3つの潮流と代表的著作を取り上げ、それぞれの背景、著作の概要、批判と射程を論じます。 第3章は、1950年代の(近代イギリス)都市史に関する諸研究を見ていく中で、方法論の変化を明らかにします。ここではとりわけ、トムスンによる社会的磁場の理論―社会を二極構成で捉えて磁場を発見し、その関係(と変化)のなかで中間階級の社会的性格を決定していこうというアプローチ(73頁)―についての具体的な紹介と重要性の示唆を興味深く読みました。 第2部は、「言語論転回以降の歴史学を射程に入れた理論的考察が中心」(viii頁)です。 第4章は、言語論転回以後に注目される、表題にもある「物語の復権」と「主体の復権」について、パーソナル・ナラティヴに関する主要な研究の紹介(第2章でも取り上げられるスティードマンの研究や、貧民、奴隷の語りに関する研究)を通じてその様相を見ていきます。 第5章は、ホイジンガ『中世の秋』などに代表される「古典的文化史」、人類学的関心が一つの特徴である「民衆文化史」、そして文化理論の台頭への応答として考えるべき「新しい文化史」という、文化史の3つの流れを概観した後、ピーター・バークの主要業績とジェンダー史研究から、近年の文化史の具体的実践を描きます。 第6章は、本書の標題にもある「現代歴史学」を、「言語論的転回」「文化論的転回」など様々な「転回」以降の歴史学とします(156-158頁)。そして、サッチャー政権の新自由主義など、現代イギリスを特徴づける様々な状況とイギリスにおける歴史叙述の在り方について論じます。 第3部は、以上の歴史学の動向を日本の歴史学の文脈に定位していきます(ix頁)。 第7章は、『社会運動史』という「1970年代から1980年代に一世を風靡した伝説の雑誌」の再検討をイギリスのニューレフト史学の発展との比較から行い(同頁)、第8章はアナール学派の紹介などで日本での社会ブームの火付け役となった二宮宏之氏の著作集(全5巻)から、史学氏の流れにその業績を位置づける試みです。 終章は、社会史の各国での状況を概観した後、ポスト「転回」の歴史学の状況を概観します。上の諸章で紹介された内容と重複する部分もありますが、ここでは特にグローバル・ヒストリーの位置づけが追加されているように思いました。 以上、はしがきでの各章の紹介を踏まえながら、全体の概要を紹介してみました。 長谷川先生のご専門がイギリス近現代史ということで、具体的な研究の事例はイギリス近現代史の業績からとられていますが、私はふだんあまり触れていない領域ですので、史学史の整理だけでなく、具体的な研究の紹介もたいへん勉強になりました。(2022.12.27読了)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2023.02.12
閲覧総数 193
-
19

O・ヘンリー『賢者の贈りもの―O・ヘンリー傑作選I―』
O・ヘンリー(小川高義訳)『賢者の贈りもの―O・ヘンリー傑作選I―』~新潮文庫、2014年~ あまりにも有名なO・ヘンリー(O. Henry, 1862-1910)の短編を表題作とする、傑作選の第1弾です。 O・ヘンリーの本名はウィリアム・シドニー・ポーター。牧場生活、不動産会社、銀行などで働きますが、横領の嫌疑で服役。服役中から新聞雑誌に原稿を送るようになり、以後、O・ヘンリーの筆名で活躍されますが、過度の飲酒から健康を害し、47歳の若さで亡くなったとのことです(以上、訳者あとがき、261-263頁参照)。 本作には、16編の短編が収録されています。 貧しい暮らしの中、美しい髪を切り売って夫のためのクリスマスプレゼントを買った妻と、夫からのプレゼントを描く「賢者の贈りもの」。 恋人からの連絡を待ちわびるタイプライターに訪れる出来事を描く「春はアラカルト」。 間借り先で一緒の少佐そっくりに舞台で演じた俳優と少佐のその後を描く「ハーグレーヴスの一人二役」。 20年前に意気投合した二人が再開の約束を果たそうとする「二十年後」。 高級ホテルに滞在する上品な女をめぐる「理想郷の短期滞在客」。 逮捕されてあたたかく冬を越したいのに、何をしても逮捕されない男の行く末を描く「巡査と讃美歌」。 娘が行方不明になってから水車小屋を教会に改装した男と、過去を失った女との出会いを描く「水車のある教会」。 価値観の相容れない姉妹の行く末を描く「手入れのよいランプ」。 千ドルという半端な遺産を相続した男の使い道を描く「千ドル」。 おぞましい所業で名高い「黒鷲」がとつぜん姿を消すことになった顛末を描く「黒鷲の通過」。 自分だけ「緑のドア」という謎のチラシを配られた男の冒険を描く「緑のドア」。 新しい速記係の採用を指示したことさえも忘れるくらい忙しいブローカーの恋を描く「いそがしいブローカーのロマンス」。 身代金目的で誘拐した少年のとんでもない所業に振り回される男たちを描く「赤い酋長の身代金」。 喪に服して真っ黒なドレスを着ているという女と、その話を聞いた男のその後を描く「伯爵と婚礼の客」。 強盗に入った家で起こった出来事を描く「この世は相身互い」。 公園で本を読む女と、彼女に声をかけた男を描いた「車を待たせて」。 訳者あとがきにもありますが、私は表題作を「子供向けに書き換えられたものだけで読んだつもりになってしま」(260頁)っていたので、邦訳とはいえ、いろいろ読んでみたいと思い、このたび手にとりましたが、どれも好みの話でした。こちらも訳者あとがきに触れられていますが、巧みなどんでん返しが味わい深いです。 なんとなく落ちが分かりながらも「水車のある教会」は感動的ですし、なぜか自分にだけ他の通行人とは違うチラシが配られるという、「世にも奇妙な物語」にも描かれそうな「緑のドア」は展開も落ちも好みでした。 「赤い酋長の身代金」「この世は相身互い」など、ユーモラスな作品も多く、とても楽しめる1冊でした。(2025.07.16読了) ・海外の作家一覧へ
2025.10.04
閲覧総数 42
-
20

シャルル・ペロー『眠れる森の美女―完訳ペロー童話集―』
シャルル・ペロー(巖谷國士訳)『眠れる森の美女―完訳ペロー童話集―』~講談社文庫、1992年~ シャルル・ペロー(1628-1703)による、1697年刊『過ぎし日の物語集または昔話集 教訓つき』と1695年刊行の『韻文による物語集』の全訳です。 表題作「眠れる森の美女」は、妖精の贈物により100年の眠りについた美女が王子によって目覚める…だけでなく、その後に王子の母が人喰い鬼の一族の出自で、王子夫婦を襲おうとするというエピソードが続きます。末尾の教訓はぴんときませんでした。「赤ずきんちゃん」は救いのないお話。 ジル・ド・レなどがモデルといわれる「青ひげ」は、夫が留守の間、決して開けてはならないと言われた小部屋を開けてしまった妻を待つ衝撃の展開です。「猫先生あるいは長靴をはいた猫」は、猫しか遺産をもらえなかった三男ですが、その猫が大活躍して…というお話。「サンドリヨンあるいは小さなガラスの靴」は、サンドリヨン=シンデレラの物語。「まき毛のリケ」は、ぶかっこうですが才知あふれる王子と、美しいけれど才知に欠けた王女のお話。「親指小僧」は、7人兄弟の末っ子で体も小さい「親指小僧」が、存在をうとまれながらも大活躍するお話です。 以上の8話が散文の物語で、後編には3編の韻文物語が収録されています。 最長の「グリゼリディス」は、美しい妃グリゼリディスと王の物語。作者は末尾にいろいろ書いていますが、王の非道さは、私には目に余りました。「ろばの皮」は、亡くなった妃の言葉で、美しい娘との結婚をくわだてる王と、王から逃れるためろばの皮をかぶり貧しい姿で暮らす王女の物語。これもなかなか…。「おろかな願い」は、3つまでなんでも願いごとを聞いてもらえることになった夫婦の話。 訳者解説もとても分かりやすいです。(2025.06.27読了) ・海外の作家一覧へ
2025.09.07
閲覧総数 31
-
-

- 読書日記
- 書評【ゆるこもりさんのための手帳術…
- (2025-11-20 00:00:13)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- Sports Graphic Number 2025年 12/4…
- (2025-11-23 14:44:55)
-
-
-

- お勧めの本
- ★「愛子天皇論3」にチューモク!★
- (2025-11-24 08:55:19)
-







