全2103件 (2103件中 1-50件目)
-
フェーヴル『大地と人類の進化―歴史への地理学的序論―(上)』
フェーヴル『大地と人類の進化―歴史への地理学的序論―(上)』~岩波文庫、1971年~(Lucien Febvre, La terre et l’évolution humaine, 1922) リュシアン・フェーヴルは1878年にナンシーで生まれ、1897年に高等師範学校に入学。1929年、マルク・ブロック(1886-1944)とともに『社会経済史年報』を創刊、アナール学派の第一世代を代表する人物です。1947年に高等研究実習院第6部門を創設、1956年に亡くなります。 彼の感性の歴史に関する論稿のいくつかは、・フェーヴル/デュビィ/コルバン(小倉孝誠編)『感性の歴史』藤原書店、1997年 に収録されています。 さて、本書は、彼に影響を与えたアンリ・ベールによる叢書「人類の進化」の1冊として、1922年に公刊されました。 本書(上巻)の構成は次のとおりです。―――解題第1版緒言(1922年)第2版緒言(1924年)序論 地理的影響の問題第1編 問題はいかに提起されるべきか。方法についての疑問 第1章 社会形態学か人文地理学か 第2章 原理の問題と研究方法。人類の進化、歴史的進化第2編 自然的区画と人類社会 第1章 区分の問題。気候と生活 第2章 自然的区画の決定 第3章 自然における人類、個人か社会か――― 原著は100年以上前の著作ですが、たとえばロベール・ドロール/フランソワ・ワルテール(桃木暁子/門脇仁訳)『環境の歴史―ヨーロッパ、原初から現代まで―』みすず書房、2007年でも本書に言及があること、アナール学派創始者の1人として関心があったことから、本書を手にとってみました。 正直、私の力量ではとても理解できたとはいえませんが、簡単にメモしておきます。 訳者による解題は本書の位置づけを簡潔にまとめています。 序論・第1編は、地理学の業績と、それへの社会学からの痛烈な批判を紹介しつつ、とはいえその批判が一部の研究者の業績を極端にとりあげたものであることなどを指摘し、全体として地理学の意義を認めるという論調と読みました。文庫本で約150頁に及ぶ重厚な議論です。 第2編からは、より具体的な議論に移ります。第1章は、旧来の環境・地理的条件と人間の肉体的特徴の関係などの議論を(批判的に)概観した上で、本書で採用する地域的区画は、環境的・植物的なものであるとの立場を明示します。それを受け、第2章は、熱帯、亜熱帯など、地球上の大きな気候的・植物的区画を提示し、そこには「一種のシンメトリーが成立している」(251-252頁)ことを指摘します。第3章は、いわば夫婦が先か・国家が先かといった議論の後、人類が食糧の獲得可能性によって居住地を決めているというよりも、明らかに食べられるものがあるのにそれを食べないなど、宗教的な事情などを含めて議論を進めます。 稚拙な紹介となってしまいましたが、以上からも分かるとおり、本書は、本書のタイトルから想像されるような、「大きな地理的単位、大きな自然的地域区分を出発点として――それを次ぎ次ぎに絞殺し、…たがいに入れ代わり立ち代わった諸民族の歴史に[その]諸特徴をいわば照らし合わせてみる」(65頁)という構成ではありません。そうではなく、地理学者の業績を踏まえて、歴史学者の観点からそれを批判的に研究することが、本書の計画・方針とされます(64-75頁参照)。※冒頭のフェーヴルの略歴については、以下の著作を参照しました。・竹岡敬温『「アナール」学派と社会史-「新しい歴史」へ向かって』同文館、1990年・ピーター・バーク(大津真作訳)『フランス歴史学革命-アナール学派1929-89年-』岩波書店、1992年(2025.09.13読了) ・西洋史関連(邦訳書)一覧へ
2025.11.29
コメント(0)
-
シェイクスピア『リア王』
シェイクスピア(福田恆存訳)『リア王』~新潮文庫、1967年~(William Shakespeare, King Lear) 劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)による四大悲劇のうちの1つです。 やや詳細にメモしておきます。 国事の務めを娘たちに譲るため、領土を三つに分けたブリテン王リアは、ゴネリル、リーガン、コーディーリアの3人娘それぞれに、自分への思いを語らせます。そして、ゴネリル、リーガンのような追従を言わないコーディーリアに激怒し、彼女を追放、コーディーリアへの態度に苦言を入れる忠臣ケントをも追放し、残る2人にすべてを与えます。 しかし、ゴネリルとリーガンは、リア王を冷遇しはじめます。 一方、グロスター伯の庶子エドマンドは、嫡子エドガーを陥れ、自分が伯を継ぐために画策を進めていました。 2人の娘に冷遇され、さまよい、狂気に陥っていくリア王、同じく息子の罠にかかり、両目を失い、さまようグロスター。一方、王をケントが、グロスターをエドガーが、ひそかに支えていきます。 そんな中、フランス王にとついでいたコーディーリアですが、フランス王がブリテンを狙っているとのうわさが広まっていき、ゴネリルたちは準備を進めていきます。 果たしてリア王を待つ運命は…。 例によって、訳者たちによる詳細な解題・解説が勉強になります。 その中でも指摘されていますが、子供に裏切られるリア王とグロスター伯が対に、親を裏切るゴネリル・リーガンとエドマンドが対になっています。 それぞれのパートが入り乱れ、『ハムレット』などと比べるとやや筋が追いにくい印象でしたが、リア王の判断により自身が苦しみに満ちていくという流れは印象的でした。(2025.09.13読了) ・海外の作家一覧へ
2025.11.24
コメント(0)
-
シェイクスピア(福田恆存訳)『ヴェニスの商人』
シェイクスピア(福田恆存訳)『ヴェニスの商人』~新潮文庫、1993年改版~(William Shakespeare, The Merchant of Venice) 劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)によるあまりにも有名な作品(喜劇)です。 簡単にメモしておきます。 借金に苦しむ友人バサーニオーのため、いつもは批判していたユダヤ人シャイロックからお金を借りることにしたアントーニオーですが、シャイロックは約束を守れなかったらアントーニーの肉1ポンドをもらうという証書を書かせます。 一方、貴婦人ポーシャには、世界各地から求婚者が訪れますが、父の遺言で、3つの箱のうち正しい箱を開けた者のみが結婚できるというルールがありました。バサーニオーは、彼女と結婚し、アントーニオーへの今までの借金も返そうとするのですが…。 そして、アントーニオーの商船が難破するというニュースが入ってきて、約束の期日までにシャイロックへの借金が返せなくなったアントーニオーは、法廷でシャイロックと戦うことになります。 アントーニオーの分が悪い中、法学博士が法廷にやってきて…。 詳細な解題・解説を読むと、強欲なユダヤ人シャイロックに対する評価も様々なされてきたことが分かりますが、それを踏まえても、普段あそこまでアントーニオーから罵詈雑言を浴びせられ、あのような結末を迎えるシャイロックが気の毒に思えてしまいます。 とはいえ、アントーニオーも、法廷の議論の中で、反省する面があったなら良いのですが…。 意味不明なのはバサーニオーで、ぜいたく暮らしのためにアントーニオーから借金はするは(さらに、シャイロックに借金させてまで!)、貴婦人と結婚して金持ちになろうとするは、私には好きになれない人物でした。 解題から、『ゲスタ・ロマノールム』(ヘルマン・ヘッセ(林部圭一訳)『ヘッセの中世説話集』白水社、1994年の記事参照)に、三つの箱選びの題材があることを知りました。まだ目を通せていませんが、手元の『ゲスタ・ロマノールム』(伊藤正義訳、篠崎書林、1988年)では該当の話は第251話で、とりいそぎそこは確認して勉強になりました。 あらためて、訳者の福田氏の解題と中村保男氏による解説が詳細で、勉強になります。(2025.09.08読了) ・海外の作家一覧へ
2025.11.23
コメント(0)
-
シェイクスピア『ハムレット』
シェイクスピア(福田恆存訳)『ハムレット』~新潮文庫、1967年~(William Shakespeare, Hamlet) 劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)によるあまりにも有名な悲劇作品です。『オセロー』『マクベス』『リア王』とともに、四大悲劇に数えられる作品です(本書「解説」213-214頁参照)。 簡単にメモしておきます。 前デンマーク王が亡くなり、その弟クローディアスが王位を継いだが、前王の息子ハムレットは新王に信頼を寄せられないでいました。 そんな中、城に幽霊が現れるといううわさがあり、ハムレットの友人ホレイショーも目撃します。そして話を聞いたハムレット自身も幽霊に出会い、父の死の事実を知ることとなります。 復讐を果たそうとするハムレットは、狂人のふりをしながら、新王や母にある仕掛けをしていくのですが、そうとは知らない新王の側も、ハムレットを陥れようと画策して行きます。 これは面白かったです。 かつての学友もハムレットを陥れる側に回る中、唯一信じられるホレイショーの協力を得ながら、復讐を果たそうとするハムレットの立ち回りに、手に汗握ります。 劇への仕掛けや、母との対話など、印象的なシーンも多く、興味深く読み進められました。 詳細な解題・解説なども付されていて便利です。(2025.09.06読了) ・海外の作家一覧へ
2025.11.22
コメント(0)
-
シェイクスピア『ロミオとジュリエット』
シェイクスピア(中野好夫訳)『ロミオとジュリエット』~新潮文庫、1994年改版~(William Shakespeare, Romeo and Juliet) 劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)によるあまりにも有名な悲劇作品です。 やや詳細に筋をメモしておきます。 ヴェローナにて、モンタギュー家とキャピュレット家は互いに敵視きていて、それぞれの家の召使同士もいがみあうような有様でした。 ある日、恋に悩んでいたモンタギューの息子ロミオは、キャピュレット家で開かれた仮装舞踏会に友人たちと参加します。そこでキャピュレットの娘、ジュリエットに出会い、二人は恋に落ちます。 フランシスコ会修道士ロレンスのもとで結婚をしますが、その後、キャピュレット夫人の甥ティボルトにからまれ、友人マキューシオを殺されたロミオは復讐を果たしますが、それによりヴェローナからの追放を受けます。 ロミオの追放を知り嘆くジュリエットは、さらに、意に沿わない人物との結婚を迫られることとなりますが…。 久々の再読ですが、いくつか気付いて面白かったのは、・ロミオは冒頭ではロザラインに恋していたこと・舞踏会でジュリエットを見ると一気に心変わりしたこと・ロミオとジュリエットは(形だけでも)結婚していたこと です。 翻訳もかなり思い切っていますが(「南無…」などの言葉も出てきます)、「日本語でならばどんな表現をするであろうか、勝手にしゃべらせてみるという手法をとった」(266頁)とのことです。また、シャレのような言葉については、詳細な訳注もついていて、原文を忠実に訳した場合も示されていて、便利です。 思い切った訳文であるため、違和感のあるところもないではないですが、読みやすく、また解説も充実しているので、この有名な劇にふれるには便利な1冊です。(2025.08.31再読) ・海外の作家一覧へ
2025.11.16
コメント(0)
-
フィリップ・フォール『天使とは何か』
フィリップ・フォール(片木智年訳)『天使とは何か』~せりか書房、1995年~(Philippe Faure, Les anges, Les Editions du Cerf, 1988) 著者のフィリップ・フォールは1958年生まれ、中世史、天使学を専門とする研究者で、オルレアン大学中世史講座の准教授でいらっしゃるようです(Wikipediaなど参照)。 本書は著者の最初期の単著のようです。 まず、本書の構成は次のとおりです。―――はじめに第1部 天使とは誰か 第1章 多神教世界の天使 第2章 聖書とヘブライ的伝統の中での天使 第3章 キリスト教黎明期の天使第2部 歴史の中の天使 第4章 中世の天使の隆盛と変遷 第5章 天使の消滅に向かって 第6章 イスラムの天使第3部 天使額のテーマと問題 第7章 天使と神性 第8章 天使とコスモス 第9章 天使と人間結論原・訳注訳者あとがき主要参考文献――― 全176頁、本文まわりの余白もゆったりしていて、読みやすい1冊。…でありながら、これまで何度となく記事が書けていなかったので読み返していながらそれでも記事が書けなかった1冊でもあります。 ごく簡単になりますが、今度こそメモしておきます。 第1部は、ヨーロッパ世界での天使の通史に先立ち、黎明期の天使の位置づけをみます。 第1章は、聖書に先立つ神話や非ヨーロッパ世界の多神教における天使の位置づけを概観します。 第2章は、旧約聖書などにおける天使の位置づけについて。ここでは、ガブリエル、ミカエルなどの天使の名前が、「接尾辞エル(神性)と天使の役割や資格を表す語幹に結び付ける方法」で作り出されたとの指摘が興味深いです(36頁)。 第3章は、キリスト教、そして新約聖書における天使の位置づけ。ここでは、天使の分類に関する議論が興味深く、とりわけ54頁で「天使のヒエラルキー」として提示されている図が便利です。 第2部は天使をめぐる議論や天使崇敬に関する通史。第4章は中世初期から中世末期までを論じ、中世末期には天使学の重要性が低下していく一方、世俗的・個人的な崇敬へ、いわば「より人間的な近づきやすい現実へと」(76頁)天使の立場が変わっていくことなどを指摘します。 第5章は近世から20世紀までを概観します。もはや天使は「個人的なファンタジーのおもむくままに想像的な存在」(89頁)へと変貌して行くといいます。 第6章はキリスト教世界における天使を相対的に見る視点として、イスラームにおける天使の位置づけを通史的に概観します。 第3部はやや形而上学的・神学的な議論も含み、私にはわかりづらい部分も多いです。それぞれ、章題のとおりですが、第7章は天使と神との関係、第8章は宇宙との関係、第9章は人間との関係を論じます。第8章で面白いのは、未確認飛行物体との関係で、たとえばケルビムは「高度に進化した宇宙船の乗組員であり、そしてその羽が自動推進装置を素朴な形で表象したものだ」(136頁)なんていう議論もなされていたことの指摘です。 参考文献を示す注はなく、原注・訳注では語句の説明がなされるという、一般向けの書物でありながら、内容としてはやや硬め、といった印象の1冊です。(2025.08.28読了) ・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.11.15
コメント(0)
-

ハリイ・ケメルマン『九マイルは遠すぎる』
ハリイ・ケメルマン(永井敦/深町眞理子訳)『九マイルは遠すぎる』~ハヤカワ文庫、1976年~(Harry Kemelmann, The Nine Mile Walk, 1967) 表題作があまりにも有名な、ハリイ・ケメリマン(1908-1996)による短編集です。 法学部教授をやめて郡検事になる「わたし」の一人称で物語は進みます。 探偵役は、「わたし」の少し年上の、スノードン基金名誉英語・英文学教授のニコラス・ウェルト(愛称はニッキイ)です。 それでは、簡単にそれぞれの内容紹介と感想を。―――「九マイルは遠すぎる」「9マイルもの道を歩くのは容易ではない、ましてや雨の中となるとなおさらだ」わずかな文章から、一連の論理的推論を引き出すと言ったニッキイに、「わたし」が言ったその言葉から、ニッキイが導き出す思いがけない事実とは。「わらの男」雑誌からの切り抜きで作られた脅迫状に、指紋がはっきりと残されていた理由とは。「10時の学者」10時開催の学位論文口頭試験に現れなかった大学院生が、ホテル(下宿)で殺されていた。凶器をめぐる奇妙な謎とは。「エンド・プレイ」チェスの途中、来訪者に殺されたと思われた被害者について、「わたし」と対立する刑事は自殺説を唱えていた。証拠があるという刑事に、ニッキイが示す真相は。「時計を二つ持つ男」常に時間を意識し、時計を二つ持っていた男が、同居するおいが呪いのような言葉を吐いた夜に死亡した。後日、そのおいも死亡。呪いのような事件の真相とは。「おしゃべり湯沸かし」大規模な学会に多くの学者が集まり、ニッキイの住む部屋の向かいにも2人の客が宿泊していた。ある日、その部屋から聞こえた湯沸かしの音から、ニッキイが推理してみせたこととは…。「ありふれた事件」雪が降り続いていた頃、雪の中に死体が埋められていた。被害者を恨む男もはっきりしていたが、その状況から、ニッキイは警察と異なる解釈を提示し…。「梯子の上の男」出版した著書がベストセラーとなった教授が、事故のような状況で死を遂げた。さらに、彼と共同研究していた男と「わたし」たちが一緒にいたとき、彼の知人が作業中に梯子から落下死する。被害者の死の真相とは。――― なにより、ずっと気になっていた「九マイルは遠すぎる」が読めたのが良かったです。あらためて、The Nine Mile Walkを「九マイルは遠すぎる」とした邦題の素敵さを感じました。 表題作以外で印象的だった作品として、「わらの男」は、正体を知られたくないはずの脅迫状作成者がなぜ指紋の残りやすい紙質の雑誌で、指紋だらけの脅迫状を作ったのかという魅力的な謎ですし、「おしゃべり湯沸かし」は、隣室から聞こえる湯沸かしの音を手がかりに裏にある事件を推理するという、こちらも魅力的な展開でした。 冒頭の表題作から好みの方向性で、収録作のどれも楽しく読みました。(2025.08.17読了) ・海外の作家一覧へ
2025.11.03
コメント(0)
-
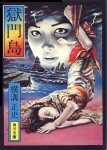
横溝正史『獄門島』
横溝正史『獄門島』~角川文庫、1971年~ 金田一耕助シリーズの長編です。 まずは、簡単に内容紹介を。(内容紹介は2007.07.12の記事から再録)――― 昭和21年(1946年)9月。「俺が死んだら、三人の妹たちが殺される。獄門島へ行ってくれ」―戦友の鬼頭千万太の言葉を受け、彼が託した紹介状を持って、金田一耕助は瀬戸内海に浮かぶ小島、獄門島を訪れた。 漁師の多い島のこと、網元の鬼頭家が大きな力を持っていた。また別格の人々が、千万太が紹介状をあてた和尚、村長、医師の三人。耕助は、和尚のもとにしばらくとどまることになる。 鬼頭家は本鬼頭と分鬼頭に分かれていた。絶大な権力を握っていた本鬼頭の前当主は亡くなり、息子は錯乱して家の座敷牢に入れられていることから、孫の千万太、そのいとこの一に期待がかけられていたのだが、その千万太が死んだ。跡取りをめぐる、血なまぐさい事件―千万太の最後の言葉が実現される嫌な予感を抱く耕助だが、ついに事件が起こる。 鬼頭家の、千万太の三人の妹―花子、雪枝、月代のうち、花子が、千万太の通夜の夜に行方不明になる。彼女の遺体は、寺の木の枝から、逆さに吊されていた。 さらに、事件は続く。花子の次の犠牲者、雪枝の遺体は、釣り鐘の中に閉じこめられていた。恐ろしい事件が続く中、本鬼頭をほとんど一人で支えている早苗も、不審な行動をとりはじめる。――― 何度目かの再読で、もちろんあの言葉の意味も分かった上で読み返しましたが、何度読んでも面白いです。 本題と関係ないところばかりになりますが、たとえば、金田一さんが屏風の俳句を読もうとするシーン。「ぼんやりとしていると、腹の底からいらいらしたものがこみあげてきそうなので、耕助は臍下丹田に力をおさめて、一意専心、これを読むことに努力することにきめる」。俳句を読む覚悟の描写のこの面白さ、抜群です。そして、がんばっているときに駐在所の清水さんに声を掛けられて現実の世界へ呼び戻されると、「其角などくそくらえであった」。大好きです。 床屋の親方と金田一さんの軽妙なトークも面白いです。 そして、物語としては、釣鐘に被害者が押し込められた時間の謎、何かを知っていながら不審な行動をする早苗さんの意図など、魅力的な謎が満載です。 あらためて、金田一耕助シリーズ、そして横溝作品の面白さ、魅力をふんだんに味わえる素敵な読書体験でした。(2025.08.16再読)・や・ら・わ行の作家一覧へ※表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディア様からいただきました。
2025.11.02
コメント(0)
-
R・W・サザン『歴史叙述のヨーロッパ的伝統』
R・W・サザン(大江善男・佐藤伊久男・平田隆一・渡部治雄訳)『歴史叙述のヨーロッパ的伝統』~創文社、1977年~(R. W. Southern, “Aspects of the European Tradition of Historical Writing”, Transactions of the Royal Historical Society, 5th Series, vols. 20-23, 1970-1973) リチャード・ウィリアム・サザーン(Richard William Southern, 1912–2001)は、イングランド北部ニューカースル生まれ。『中世の形成』『西欧中世の社会と教会』などの邦訳書があります。 本書は、サザーンが1969年から4年間、王立歴史学会の会長をつとめたとき、各年度に講演した内容をまとめたものです。 本書の構成は次のとおりです。―――凡例第1章 アインハルトからモンマスのジェフリに至る古典古代の伝統第2章 聖ヴィクトルのフーゴーと歴史的発展の理念第3章 預言としての歴史第4章 過去の意味原注訳者あとがき索引――― 第1章で、著者は、「歴史家の第一の任務は芸術作品を作成することだと言明」し、さらに「歴史家は情緒的・知的要求を満足させることを目指さなければならない」(6頁)という自身の立場を表明します。もちろん、「利用しうるデータの制約内」(同)でのことと述べた上で、ではありますが。ここから、先日読んだ兼岩正夫『西洋中世の歴史家』の中で、イギリスの歴史叙述として、「トレヴェリアンによれば歴史は科学であるとともに芸術である」(2頁)と指摘されているのを想起しながら読みました。 なお、同章では、『カール大帝伝』を著したアインハルトについて、彼が材料を改作しているとして近代の学者が非難する中、著者は、「帝国の偉大さのイメージを呼び起こすこと」(23頁)がアインハルトの意図だったとして、その意図の中でその作品を判定することが重要だという立場に立っていることが興味深いです。 第2章は、サン=ヴィクトルのフーゴーの著述に見られる(歴史の)「発展」の理念を丹念に見た後、特にその歴史観を受け継いだ人物としてハーヴェルベルグのアンセルムスとフライジングのオットーに着目し、それぞれの著作の特徴を論じます。 第3章は「預言」というキーワードで歴史叙述を見ていきます。預言の典拠として、大きく(1)聖書、(2)異教的預言(例としてシビュラとマーリン)、(3)キリスト教的預言=幻視、(4)宇宙的預言=占星、の4つを概観した後、これらを預言を研究した人物としてロジャー・ベイコン、フィオーレのヨアキム、そしてニュートンを取り上げます。 第4章はイギリスにおける歴史研究の意味を考えるにあたり、注目すべき時代としてノルマン・コンクェスト後の歴史叙述と、16-17世紀の歴史叙述の2つの時代を取り上げます。前者に関しては、複数の修道院で、「征服」以前から自分たちは偉大であったこと(と征服による不当な侵略)を明らかにするという実際的な動機、後者に関しては、様々な公職を歴任したウィリアム・ラムバードに着目して、彼が自身のついた職に関する歴史を精力的に調査・公刊したことを示した上で、彼らは「自分たちが[過去から]継承したものは一体何であったかを発見するため」に記録文書を探索した、と論じます。 タイトルから想像されるような、ヨーロッパにおける歴史叙述を通史的に論じるというよりは、歴史叙述の様々な側面に着目し、その観点ごとに意味を論じる試みであるように思われます。 解説では、サザーンの略歴と主著、そして本書成立の契機などが紹介されていて、こちらも興味深いです。(2025.08.15読了) ・西洋史関連(邦訳書)一覧へ
2025.11.01
コメント(0)
-
ゲーテ『ゲーテ格言集』
ゲーテ(高橋健二編訳)『ゲーテ格言集』~新潮文庫、1991年79刷改版~ ヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)の「全著作の中からと、最初から格言や警句として独立に書かれたものの中からと、ほぼ半々に」(あとがき、211頁)、日本人に興味深く感じられる格言的なことばをまとめた1冊。「愛と女性について」「神、信仰、運命について」「幸福について」など、15のテーマに分けて格言的なことばが集められています。 格言集という性格上、いつものような感想はまとめにくいですが、18-19世紀ドイツの作家が書いた言葉でありながら、21世紀日本にも通じる言葉がなんと多いことかと感じることもままありました。 ここでは、特に印象的だった言葉をメモしておきます。詳細はぜひ本書でご確認ください。「寛大になるには、年をとりさえすればよい。どんなあやまちを見ても、自分の犯しかねなかったものばかりだ」(43頁)「自分の知っていることは自慢し、知らないことに対しては高慢に構える者が少なくない」(134頁)「われわれには理解できないことが少なくない。生き続けて行け。きっとわかって来るだろう」(177頁) 巻末にはゲーテの主要な著作がジャンルごとにリストアップされていて便利です。(ただ、邦訳の有無や邦訳書の情報はないので、気になる作品があれば個別に調べる必要があります。)(2025.08.14読了) ・海外の作家一覧へ
2025.10.26
コメント(0)
-

吉本ばなな『キッチン』
吉本ばなな『キッチン』~角川文庫、1998年~ 吉本ばななさんのデビュー作「キッチン」を含む3編の短編が収録されています。 表題作「キッチン」は、幼くして両親を亡くし、祖父も亡くし、大学生になって同居していた祖母も亡くなり、近しい身内がいなくなってしまった、桜井みかげさんの視点で進みます。 祖母がよく通っていた花屋でアルバイトしていた田辺雄一さんが気にかけてくれ、田辺家で暮らすようになります。 雄一さんとの距離感や、雄一さんの父にして母のえり子さんの素敵さ、そして田辺家の台所が好みということもあって、みかげさんが少しずつ落ち着いてくる中、祖母の死に向き合ったり、不思議な夢を見たり、少し歩み始めます。「満月―キッチン2」は、「キッチン」の後日譚。 夏のあいだ、何かに憑かれたかのように料理に取り組んだみかげさんは、有名料理研究家のアシスタントとして仕事をしていました。そんな中、雄一さんからかかってきた一本の電話。それは、衝撃的な事件を伝える電話でした。 雄一さんと距離を置く必要があると考えていたみかげさんは、先生について取材の旅に出ます。旅先で食べたかつ丼の美味しさに感動したみかげさんは、ある行動に移ります。 表題作とは別の物語である「ムーンライト・シャドウ」は、恋人を亡くしたさつきさんが主人公の物語です。恋人を亡くし、眠れない中、早朝のランニングを始めたさつきさんは、ある朝、思い出の川で、うららと名乗る女性と出会います。不思議な現象がこの川で起こると伝えるうららさんの言葉を受けて、その朝、さつきさんを待つ体験とは…。 20年ぶりくらいの再読。「素敵な物語だった」ことは覚えていましたが、忘れているところも多く、あらためて新鮮な気持ちで楽しめました。 上でも書きましたが、みかげさんがある夜に見る不思議な夢と、その後の展開は特に印象的でした。「満月」は、かつ丼のエピソードが素敵です。 「ムーンライト・シャドウ」は、「キッチン」とは別の物語ですが、「死」「別れ」というテーマでは共通しています。100年に1回くらいの割合でしか経験できないその現象で、うららさんも含めて、みかげさんたちが新しく歩み始めるのが印象的でした。 あらためて、素敵な読書体験でした。(2025.08.09再読) ・や・ら・わ行の作家一覧へ
2025.10.25
コメント(0)
-

ゲーテ『若きウェルテルの悩み』
ゲーテ(高橋義孝訳)『若きウェルテルの悩み』~新潮文庫、1995年100刷改版~(Johann Wolfgang von Goethe, Die Leben des Jungen Werthers, 1774/1784) 詩人、作家、学者のヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)による、あまりにも有名な小説です。 物語は、「編者」が、ウェルテルから主にその友人(?)のウィルヘルムに宛てた手紙を整理して提示する、という形式で進みます。 若き絵描きのウェルテルが、ある悲しい出来事をきっかけに、一人故郷を離れます。 そこで、ウェルテルは、婚約者がいるという女性、シャルロッテに出会い、熱烈な恋をしてしまいます。 彼女の言動の一つ一つに一喜一憂しながら、何度も彼女のもとを訪れるウェルテルですが、話に聞いていたとおり、彼女には婚約者―アルベルトがいました。 アルベルトの人柄も認めながら、3人の奇妙な関係が続いていきますが、やがて少しずつすれ違いが起こり始め…。 という物語です。 この物語が刊行されたのち、自殺が増加するという現象があったようです。少し調べていると、著名人の自殺報道を受けて自殺が増加する現象を「ウェルテル効果」というそうですね。 作中でも、ウェルテルは、ある女性の死を念頭におきながら、自殺を擁護するような発言をし、アルベルトと対立する印象的なシーンがあります。 なんともやりきれない思いの残る物語です。(2025.08.05読了) ・海外の作家一覧へ
2025.10.19
コメント(0)
-

佐藤彰一『フランス中世史I カペー朝の革新』
佐藤彰一『フランス中世史I カペー朝の革新』~名古屋大学出版会、2025年~ 著者の佐藤彰一先生は名古屋大学名誉教授で、主に初期中世史をご専門とされています。 本ブログで紹介した近著に、次があります。・佐藤彰一『ヨーロッパ中世をめぐる問い―過去を理解するとは何か―』山川出版社、2024年 →こちらの記事に、本ブログで過去に紹介した佐藤先生の著作のリストも載せています。 さて、本書は、佐藤先生による、王統史を軸としたフランス中世史の通史第1巻です(第2巻ではヴァロワ朝がテーマとなる予定とのこと)。 すでにフランク史を扱う3巻本が同出版会から刊行されていますが、本書はその続編といえると思われます。 まず、本書の構成は次のとおりです。―――カペー朝系図はじめに第1章 10世紀の変動第2章 新奇なる遊弋第3章 新王朝の曙光第4章 城塞領主たちとの戦い―イル・ド・フランス地方―第5章 イル・ド・フランスの地平を越えて第6章 大国への道のり第7章 大西洋と地中海の眺望第8章 聖王の時代第9章 不運な治世第10章 挫折した世俗国家「革命」第11章 兄から弟へ―最後のカペー王たち―おわりにあとがき索引 図表一覧 引用文献 註――― 基本的に、1章につき1人の王に焦点を当てて議論が展開されます。 以下、簡単にメモしておきます。 第1章…カペー朝初代王となるユーグ・カペー(位987-996)。即位の背景にランス大司教アダルベロンの思惑。息子ロベールを自身の生存中に共同王として即位させる(共同王方式は以後しばらく継続)。 第2章…ロベール2世(敬虔王、位987-1031)。マルク・ブロックは、瘰癧の治癒という「王の奇跡」を行った最初の王と指摘。同時代、アダルベロンらによる身分論の展開。 また、アンリ1世(位1026-1060)について。反王権勢力との戦い、原状回復との評価(否定的な評価に対して、佐藤先生は肯定的な評価)。 第3章…フィリップ1世(位1059-1108)。東方由来の名を持つ初の王。7歳で前王が死亡し、初の未成年の王。宮廷官職の組織化、王領地の拡大。 第4章…ルイ6世(肥満王、位1100頃-1138)。カペー家が避けてきたカロリング朝にさかのぼる名の採用。各地の領主との対立。 第5章…ルイ7世(位1131-1180)。先行研究では批判的な評価も受けるが本書は肯定的に評価。各種統治機構の発展の萌芽など。 第6章…フィリップ2世(オーギュスト、位1179-1223)。十字軍、英王との対立、行政の整備など。政治的な安定からか、生前に息子ルイ8世を共同王として戴冠しない。 第7章…ルイ8世(位1223-1226)。即位前から精力的な遠征、アルビジョワ十字軍、人々の前に姿を現すなど様々な権力技術。 第8章…ルイ9世(聖王、位1226-1270)。死後に列聖、十字軍遠征。聖性が強調されるが政治的手腕も卓越していたことなどが指摘されます。 第9章…フィリップ3世(位1271-1285)。十字軍挫折から帰国時に、父、妻、死産の子など5名の棺を携えたというエピソードが印象的。佐藤先生も「歴史上の人物とはいえまことに同情に堪えないものがある」(316頁)と述べていらっしゃいます。地方行政、中央行政の整備。 第10章…フィリップ4世(位1286-1314)。財政悪化、教皇ボニファティウス8世との対立(アナーニ事件)など。 第11章…ルイ10世(位-1316)、フィリップ5世(-1322)、シャルル4世(-1328)の3兄弟。直系男子に恵まれずカペー朝断絶。 私の関心からのメモとなりましたが、いわゆる王を中心とした国内の諸領主や国外との関係、行政組織の展開などの政治史の通史を(恥ずかしながら)ほとんど読まないままに勉強をしてきてしまっているので、本書の重厚さからゆっくりと読み進めました。 上のメモでも触れましたが、王の名づけに関する議論がいくどかなされていて、大変興味深かった一方、王のあだ名に関する議論はあまりなされていなかったのは残念です。あだ名は、その王の特徴やその王へのまなざしを示すものでもあり、本書のような重厚な議論の中、どのように位置づけられるのか関心があります。(名づけやあだ名については、岡地稔『あだ名で読む中世史―ヨーロッパ王侯貴族の名づけと家門意識をさかのぼる―』八坂書房、2018を参照) ともあれ、本書は最新の成果も踏まえた政治史の通史であり、勉強になる1冊です。(2025.10.09読了) ・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.10.18
コメント(0)
-
上智大学中世思想研究所編『中世の歴史観と歴史記述(中世研究第3号)』
上智大学中世思想研究所編『中世の歴史観と歴史記述(中世研究第3号)』~創文社、1986年~ 以前紹介した上智大学中世思想研究所編『聖ベネディクトゥスと修道院文化』創文社、1998年同様、同研究所が刊行している紀要『中世研究』の第3号です。 序言に続き、9編の論考が収録されています。 本書の構成は次のとおりです。―――序言(K・リーゼンフーバー)1 K・リーゼンフーバー(酒井一郎訳)「『神国論』におけるアウグスティヌスの歴史理解」2 橋口倫介「中世の年代記―その著作意図をめぐって―」3 出崎澄男「中世初期の民族史―歴史記述にあらわれたシュタム意識―」4 池上俊一「十二世紀の歴史叙述と歴史意識」5 今野國雄「修道院の歴史叙述―Exordium Magnumについて―」6 森洋「聖者伝」7 坂口昻吉「ヨアキムの歴史神学とスコラ学者―トマスとボナヴェントゥラ―」8 J・フィルハウス(酒井一郎訳)「ビザンティン帝国における歴史記述」9 黒田寿郎「中世イスラームの歴史観と歴史記述」文献表索引――― 第1論文は、アウグスティヌス『神の国』を中心に彼の歴史観を探る論考。やや神学的な議論で私には難解でした。 第2論文は、「年代記」の諸類型(annales=年代記・編年記、chronica=編年史・年代記、historia=歴史)をあげ、ただしこれは便宜的な区分にすぎないことを指摘した上で、先行研究によりながら中世における歴史記述の構造を5つの時代に分けて論じる興味深い論考。 第3論文は、各種の民族史を史料として「シュタム(部族)」意識を探ります。 第4論文は、フライジングのオットー『年代記あるいは二つの国の歴史』がその代表である「世界年代記」と称されるジャンルを中心に取り上げ、「聖書解釈」の技法などを参照しながらその意義を論じます。 第5論文はシトー会の『大創立史』を史料とし、その成立背景をたどったのち、構造と内容を概観します。特に『小創立史』との比較から、両者の作成年代のあいだに歴史に関する認識上の変化が生じたことを指摘する点を興味深く読みました(123頁)。 第6章は聖者伝の類型や写本伝承の一例をあげるほか、歴史学においていかに用いられてきたかを論じます。 第7章はフィオーレのヨアキムの歴史観が、ドミニコ会士トマス・アクィナスとフランシスコ会士ボナヴェントゥラにいかに受容されたかを論じ、両者の相違点などを指摘します。 第8章はビザンティンの歴史記述について、(1)アッティカ方言による古典的な歴史記述、(2)コイネー(標準ギリシア語)による教会史、(3)庶民のギリシア語による年代記と、三層のギリシア語と歴史ジャンルの対応関係を上げ、それぞれについて概観します。 第9章は中世イスラームの歴史記述について、主観性を排除した叙述(客観性の追求)が重視されていたこと、そしてマスウーディーを例に情報の信ぴょう性を意識する事例がでてきたことを示した後、イブン・ハルドゥーンの『歴史序説』の位置づけを論じます。 約30年前の著作であるため、今ではアップデートされている内容もあるかもしれませんが、中世の歴史記述の基本的性格を把握することができる1冊だと思います。ビザンティン、イスラームにも目配りされていて、西欧の事情を相対的にみることもできるのが興味深いです。(2025.07.31読了) ・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.10.13
コメント(0)
-

魯迅『阿Q正伝』
魯迅(増田渉訳)『阿Q正伝』~角川文庫、1961年~ 魯迅(1881-1936。本名は周樹人)の有名な小説や雑感文を収録した1冊。 9編が収録されています。 まわりの人間が自分を食べようとしているという猜疑心にさいなまれる「狂人日記」。 気取った文章語を話し飲み屋の人たちに笑われ、さらに試験にも落ち貧しくなっていく男を描く「孔乙己」。 人力車に(わざと?)ひかれた老婆と彼女への車夫の対応を描く「小さな事件」。 異郷の地に引っ越すため、久々に故郷を訪れる。そこで、昔馴染みのルントウとの再会を果たすも、出生した主人公とは微妙な距離感が生まれてしまって…。(「故郷」) 表題作「阿Q正伝」は、辛亥革命前後を題材とする物語。主人公の阿Qは、人々に馬鹿にされながらも、心の中では自分自身が優れていると言い聞かせている人物です。なじみの客からの日雇いも得られなくなった阿Qは、城下に行くのですが…。 ロシアの盲詩人エロシェンコ君との思い出を描く「家鴨の喜劇」。 人々から変わり者と思われていた孤高の人、ウェイリェンシューと主人公は、彼の祖母の葬儀で出会います。伝統と異なる態度をとるウェイに、いつか惹かれ、彼を訪れるようになる主人公ですが、やがてそれぞれの環境の変化で没交渉になっていきます。その後、ウェイは意外な形で成功を収めるのですが…(「孤独者」) 魯迅が仙台の医学専門学校(現東北大学医学部)で教わった先生との思い出を描く「藤野先生」。 あまりに優れた刀を作ったがために、王に奉納するやその刀で殺された刀鍛冶の息子が、王に復讐を果たそうとする、昔話に題材をとった「眉間尺」。 作家としてのデビュー作「狂人日記」、表題作「阿Q正伝」はもちろんですが、「故郷」と「孤独者」、「藤野先生」など、多くの作品が印象的でした。 「眉間尺」はなかなか凄惨な情景が描かれますが、こちらも面白かったです。16歳になり、母から父の死の真相を聞かされ復讐に旅たつあたり、なんとなくドラクエ3を連想してしまいました(冒頭のねずみをめぐるシーンも主人公の成熟へのステップとして印象的です)。(2025.07.26読了) ・海外の作家一覧へ
2025.10.12
コメント(0)
-

オマル・ハイヤーム『ルバイヤート』
オマル・ハイヤーム(小川亮作訳)『ルバイヤート』~岩波文庫、1979年第23刷改版~ オマル・ハイヤーム(c. 1040-1123)は、数学者、天文学者などとして活躍した人物です。本書の表題「ルバイヤート」は、四行詩を意味するペルシア語「ルバーイイ」の複数形で、一般名詞とのこと。訳者解説にも、「今日ルバイヤートといえば、オマルの詩集の題名であるかのごとく思う人さえある」(152頁)とあります。 さて本書は、「オマルの原作として定評のあるものだけを厳選」した143首が収録されています。中には、オマルのものか多少疑いのあるものも含まれます(その点は連番をカッコ書きとすることで明示されています)。 なにぶん四行詩なので紹介しづらいですが、「自分が来て宇宙になんの益があったか?」(第3首より)などのように悲観的な言葉が多いことや、(イスラームに反しますが)酒を称える詩が多いことが印象的です。 詩自体は100頁弱で、訳注に続き、約60頁に及ぶ詳細な解説が付されています。 解説は、オマル・ハイヤームの経歴について記すのはもちろんですが、同時代の学問の動向を踏まえた上でその中にオマル・ハイヤームを位置付けたり、本書(初版は1949年)に先行する邦訳書を紹介したりと、かなり濃密で勉強になります。(2025.07.20読了) ・海外の作家一覧へ
2025.10.11
コメント(0)
-

マックス・ウェーバー『職業としての学問』
マックス・ウェーバー(尾高邦雄訳)『職業としての学問』~岩波文庫、1980年改訳~(Max Weber, Wissenschaft als Beruf, 1919) 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などの著作で有名なマックス・ウェーバー(1864-1920)が、1919年1月にミュンヘン大学で行った講演です。 訳者による分かりやすい解説も踏まえてメモをしておくと、本書の内容は大きく3つに分かれます。 第一は「職業としての学問の外面的事情」で、職を得たり昇進したりするには僥倖を待つほかないということや、評価基準として学生聴講生の多さがあるものの、ある教師のもとへ学生が多く集まる要因は声の調子やその人の気質など外面的な事柄にあるということなどが指摘されます。 第二は「学問を職業とする者の心構え」で、「自己を滅しておのれの課題に専心する人こそ、かえってその仕事の価値の増大とともにその名を高める結果となるであろう」(28-29頁)と述べ、一方で売名を目的とする態度を批判します。また、「自分の仕事が…いつか時代遅れになる」ことにこそ「学問的業績の意義は存在する」(29-30頁)とし、「学問上の「達成」はつねに新しい「問題提出」を意味する。それは他の仕事によって「打ち破られ」、時代遅れとなることをみずから欲するのである」と強調しています。 第三は「学問の職分と価値」で、ここでは、古代ギリシャからニーチェまでの学問観を概観した上で、やや乱暴にいえば、ある学問の意義はその学問自体が立証することはできない、と述べます(たとえば、「ある文化現象が興味あることかどうかを「学問的」に立証することはできない」(47頁)といいます)。次いで、教室では、教師個人の党派的立場を明らかにすべきではなく、それは政治的な集会などでなされるべきという立場を明らかにします。これを、「予言者や扇動家は教室の縁談に立つべき人ではない」(50頁)とも言っています。 以上、簡単なメモとなりましたが、印象的な議論の流れであり、興味深く読みました。(2025.07.17読了) ・西洋史関連(邦訳書)一覧へ
2025.10.05
コメント(0)
-

O・ヘンリー『賢者の贈りもの―O・ヘンリー傑作選I―』
O・ヘンリー(小川高義訳)『賢者の贈りもの―O・ヘンリー傑作選I―』~新潮文庫、2014年~ あまりにも有名なO・ヘンリー(O. Henry, 1862-1910)の短編を表題作とする、傑作選の第1弾です。 O・ヘンリーの本名はウィリアム・シドニー・ポーター。牧場生活、不動産会社、銀行などで働きますが、横領の嫌疑で服役。服役中から新聞雑誌に原稿を送るようになり、以後、O・ヘンリーの筆名で活躍されますが、過度の飲酒から健康を害し、47歳の若さで亡くなったとのことです(以上、訳者あとがき、261-263頁参照)。 本作には、16編の短編が収録されています。 貧しい暮らしの中、美しい髪を切り売って夫のためのクリスマスプレゼントを買った妻と、夫からのプレゼントを描く「賢者の贈りもの」。 恋人からの連絡を待ちわびるタイプライターに訪れる出来事を描く「春はアラカルト」。 間借り先で一緒の少佐そっくりに舞台で演じた俳優と少佐のその後を描く「ハーグレーヴスの一人二役」。 20年前に意気投合した二人が再開の約束を果たそうとする「二十年後」。 高級ホテルに滞在する上品な女をめぐる「理想郷の短期滞在客」。 逮捕されてあたたかく冬を越したいのに、何をしても逮捕されない男の行く末を描く「巡査と讃美歌」。 娘が行方不明になってから水車小屋を教会に改装した男と、過去を失った女との出会いを描く「水車のある教会」。 価値観の相容れない姉妹の行く末を描く「手入れのよいランプ」。 千ドルという半端な遺産を相続した男の使い道を描く「千ドル」。 おぞましい所業で名高い「黒鷲」がとつぜん姿を消すことになった顛末を描く「黒鷲の通過」。 自分だけ「緑のドア」という謎のチラシを配られた男の冒険を描く「緑のドア」。 新しい速記係の採用を指示したことさえも忘れるくらい忙しいブローカーの恋を描く「いそがしいブローカーのロマンス」。 身代金目的で誘拐した少年のとんでもない所業に振り回される男たちを描く「赤い酋長の身代金」。 喪に服して真っ黒なドレスを着ているという女と、その話を聞いた男のその後を描く「伯爵と婚礼の客」。 強盗に入った家で起こった出来事を描く「この世は相身互い」。 公園で本を読む女と、彼女に声をかけた男を描いた「車を待たせて」。 訳者あとがきにもありますが、私は表題作を「子供向けに書き換えられたものだけで読んだつもりになってしま」(260頁)っていたので、邦訳とはいえ、いろいろ読んでみたいと思い、このたび手にとりましたが、どれも好みの話でした。こちらも訳者あとがきに触れられていますが、巧みなどんでん返しが味わい深いです。 なんとなく落ちが分かりながらも「水車のある教会」は感動的ですし、なぜか自分にだけ他の通行人とは違うチラシが配られるという、「世にも奇妙な物語」にも描かれそうな「緑のドア」は展開も落ちも好みでした。 「赤い酋長の身代金」「この世は相身互い」など、ユーモラスな作品も多く、とても楽しめる1冊でした。(2025.07.16読了) ・海外の作家一覧へ
2025.10.04
コメント(0)
-

ジェームズ・バリ『ピーター・パン』
ジェームズ・バリ(本多顕彰訳)『ピーター・パン』~新潮文庫、1953年~(Sir James Mattew Barrie, Peter Pan) ジェームズ・バリ(1860-1937)はスコットランド生まれ、新聞記者をつとめながら作品を書き始めたそうです(訳者解説、107頁)。 ピーター・パンはあまりにも有名ですが、ティンカー・ベルやフック船長はこの小説には登場しません。そちらは『ピーター・パンとウェンディ』という小説(戯曲)のほうのようですね。 舞台はケンジントン公園。公園の門がしまり、人々がいなくなると、公園では妖精たちや、木々が歩き回ります。そんな中に、家から飛んでやってきたのがピーター・パンです。人として生まれる前の小鳥でもない、人間でもない、そんな存在になってしまいます。 ピーター・パンはある日、妖精に頼んで家に帰ります。お母さんをみて安心しますが、飛びたい思いの強いピーター・パンは、一度家をあとにします。ところが、次に家に戻ると、窓は閉ざされ、家には新しい赤ちゃんがいました…。 またある日、メエミという少女は、閉ざされた後の公園になんとか残ることに成功します。妖精たちや木々の会話に心躍らせるメエミは、舞踏会に参加しようとします。そんな中、ある妖精を助けることになり…。 正直、フック船長たちが登場するピーター・パンの冒険物語を想像していると、(翻訳なのか原文もそうなのか)この物語は少なくとも私にはかなり読みづらかったです。 語り手の「私」も、よく引き合いに出されるデイヴィッドも、この物語にふれる等身大の子供たちの象徴のような存在なのでしょうが、物語の筋の中でしばしば言及されるので、筋がまっすぐ追いにくいです。メエミが登場する節や、ピーター・パンが家に帰るお話は、比較的筋が追いやすいですが、特に冒頭のケンジントン公園の紹介部分は読みづらく、はじめて本書に挑んだときはそこで挫折したような覚えがあります。 今回、なんとか通読することができて、メエミとピーター・パンとのやりとりなど、印象的なエピソードにも触れられたのは良かったです。(2025.07.11読了)・海外の作家一覧へ
2025.09.28
コメント(0)
-
兼岩正夫『西洋中世の歴史家―その理想主義と現実主義―』
兼岩正夫『西洋中世の歴史家―その理想主義と現実主義―』~東海大学出版会、1964年~ 著者の兼岩正夫先生は東京教育大学名誉教授。ホイジンガ『中世の秋』や、トゥールのグレゴリウス『歴史十巻』の翻訳も手掛けていらっしゃいます。 本書は、中世の歴史叙述について、キリスト教的な「理想主義」と、実際を描く「現実主義」という2つの概念を参照軸として、「個々の歴史家の歴史作品について過去の現実をとらえる方法を明らかに」しようとする試みとされます(31,36-37頁)。 本書の構成は次のとおりです。―――I 方法論の問題II 中世歴史意識の理想主義と写実主義III 中世の歴史研究の方法IV 中世歴史記述と表現註あとがき――― Iは、まず、第二次世界大戦後のヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランスを中心)における史学史を概観し、文学としての歴史や科学としての歴史など、様々な立場を示します。次いで、学問としての歴史は近代になって成立したと述べつつも、近代以前にも存在していたある種の歴史研究の方法を探求することが本書の目標の1つだと述べた上で、中世の歴史記述に関する研究史を辿ります。 IIは本書の副題にもある、中世の歴史記述の特徴として著者が掲げる「理想主義」と「写実主義」の二元性について論じます。すなわち、中世の歴史記述には、キリスト教的歴史観による「理想主義」と、特に作者の同時代に関する描写にみられる「写実主義」がみられるという特徴を指摘し、主要な史料を具体的に見ながらその現れ方を見ていきます。 IIIは、まずイギリスの歴史記述としてベーダ(本書ではビードと記載)などを概観した後、歴史研究の方法として過去の著作の利用などをみた後、「歴史の説明の論理」として、トゥールのグレゴリウス、ベーダ、パウルス・ディアコヌス、フライジングのオットーなどの主要な著作家たちの作品を丹念にたどります。 IVは、記述言葉としてのラテン語と話し言葉としての俗語の関係について着目します。中世ラテン語の展開を概観したのち、特にトゥールのグレゴリウスの著作のラテン語の特徴を指摘するほか、俗語作品として武勲詩や宮廷物語をとりあげます。 以上、ざっと本書の内容を概観しました。 本書の中で気になったのは、現代(とはいえ、この記事を書いている2025年からいえば本書は60年前の著作ですが)の基準で、中世の価値判断をしている叙述がいくつか見受けられる点です。たとえば、IVでは、同一人物が日常では俗語を用い、書くときにラテン語を用いるという事情が、その思想の展開や表現に「好ましからぬ影響をあたえたと思われる」(148頁)とあります。また、IIIの末尾でも、「歴史の説明の能力において中世の歴史家は古代の歴史家に劣るといわざるをえない」(146頁)と記されています。 さらに、近年の研究状況からいえばアップデートされる内容も多いと思われますが、主要な著作家・著作の特徴を挙げていることから、概観を得るには便利です。 本書は、橋口倫介「中世の年代記」上智大学中世思想研究所編『中世の歴史観と歴史記述』創文社、1986年、39-67頁でも、「1960年代のいわゆる「中世ブーム」の華やかな所産に比して中世の歴史記述そのものに対する関心は必ずしも高まってきたとは言い難く……欧米の優れた研究書の翻訳を除けば、単行本としては兼岩正夫の『西洋中世の歴史家』がほとんど唯一の著作」(46頁)として言及されていることもあり、気になっていました。だいぶ前に購入はしたものの、なかなか読めずにいたので、このたび通読できて良かったです。(2025.07.10読了) ・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.09.27
コメント(0)
-
H・シュリーマン『古代への情熱―発掘王シュリーマン自伝―』
H・シュリーマン(佐藤牧夫訳)『古代への情熱―発掘王シュリーマン自伝―』~角川文庫、1967年~(Heinrich Schliemann, Selbstbiographie bis zu seinem Tode vervollst ändigt, 1892) 幼少期からホメロスの詩が史実と信じて、トロイアを発掘し、遺跡を発見したシュリーマン(1822-1890)の自伝的記録です。 「自伝」との副題ですが、実際には、著書『イーリオス』に含まれる自叙伝を抜粋しながら、アルフレート・ブリュックナーがシュリーマンの業績を時系列に紹介する体裁です。 幼少期、幼馴染のミンナと誓った結婚と発掘。しかし父が牧師職を退き、貧しくなったことを受けて様々な店で見習いをはじめ、やがて様々な縁もあり豪商となります。 貧しい見習い時代、シュリーマンはひたすら語学にいそしみます。「一生懸命に勉強すればこの貧乏から抜けだせるという確実な見通しこそが、なににもまして私をはげまして勉強させたのである」(22頁)。まず英語を、半年で身に付けます。ここでいうシュリーマンの勉強法は、声を出して多読すること、短文を訳すこと、一日に一時間は勉強すること、作文して先生に訂正を受けて暗記すること、などで、複数の語学を勉強していくくだりは印象的です。 やがて、実業家として成功して十分な収入を得た後は、仕事を退き、トロイアの発掘に専念します。その他、ミケーネ、ティリンスなどの発掘にも従事し、ギリシア考古学に多大な貢献をすることになるあたりが語られます。 誇張、思い違いなどもあるのでしょうし、このままうのみにはできないにしても、学問への思いの熱さが印象的な1冊です。(2025.07.09読了) ・西洋史関連(邦訳書)一覧へ
2025.09.21
コメント(0)
-

リチャード・バック『かもめのジョナサン』
リチャード・バック(五木寛之訳)『かもめのジョナサン』~新潮文庫、1977年~(Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull, 1970) 飛行家リチャード・バックが発表した小説です。 カモメのジョナサン・リヴィングストンは、まわりの仲間たちが食べることしか考えていないのに対して、いかに自分が飛べるか、スピードを上げたり様々な飛行法を試したりと、集団から離れて練習にいそしんでいました。両親からも心配されながら、練習を重ね、猛スピードで飛ぶことができましたが、ジョナサンは集団からの追放を命じられます。 一人になったジョナサンが練習に励んでいると、同じように高度な技術で飛ぶことができるカモメたちがやってきて…。「出る杭は打たれる」といいますが、集団とは明らかに異質の行動をとり続けたジョナサンは、上に簡単に概要を書いたように集団から追放されます。 その後出会った教師たちに学び、さらに能力を伸ばすジョナサンは、やがて同じような志をもつカモメたちを教え導く立場になっていきます。 そんな中、ジョナサンは、いわば「神」のようにみなされるのを好まず、あくまで誰にでも可能性があることを説きます。 いろいろな読み方があろうかと思いますが、努力の報いだとか、集団との関係性であるとか、いかに考えて生きるかとか、考えさせられる点は多いです。 豊富に挿入されたカモメの写真も素敵で、物語に彩りを添えてくれます。(2025.07.05読了) ・海外の作家一覧へ
2025.09.20
コメント(0)
-

メリメ『カルメン』
メリメ(杉捷夫訳)『カルメン』~岩波文庫、1960年第33刷改版~(Prosper Mérimée, Carmen, 1845) メリメ(1803-1870)による有名な作品。 調査のためスペインを訪れていた考古学者は、案内人がどんなに合図をしたにもかかわらず、盗賊のような男に話しかけ、親しくなります。その夜、考古学者は、案内人が盗賊をつかまえるために動き出したあと、ある行動に出て…。 後日。考古学者は、美しいボヘミアン(ロマ)の女性と出会った考古学者は、女に占ってもらったところで、あの男と再会します。 さらに後日。盗賊は、あの女―カルメンとの出会いから終局までを考古学者に語ります。 出世を目指していた騎兵の男―ドン・ホセは、美しい女、カルメンと出会ってから、運命が狂い始めます。女を逮捕すべき場面で、女を逃し、その後は女たちの窃盗団に加わることになります。やがてホセは女への思いから、人をも殺してしまうことになり…。 あまりにも有名でありながら、なかなか読めずにいましたが、読み始めたら引き込まれました。 考古学者の視点の1・2章に続く、第3章がドン・ホセの語りで、物語のメインを占めます。ホセが沼にはまっていく様子、そして彼を翻弄するカルメンの対比と、悲しい結末が印象的でした。(2025.07.04読了) ・海外の作家一覧へ
2025.09.15
コメント(0)
-

メーテルリンク『青い鳥』
メーテルリンク(堀口大學訳)『青い鳥』~新潮文庫、1960年~(Maurice Maeterlinck, L’oiseau bleu, 1908) モーリス・メーテルリンク(1862-1949)は、ベルギーのガン市生まれで、詩人・劇作家・エッセイストなどとして活躍し、1911年にはノーベル文学賞も受賞しています(訳者あとがき、192頁参照)。 あまりにも有名な『青い鳥』は童話劇。チルチルとミチルの兄妹が、「光」「イヌ」「ネコ」「パン」たちと、妖女の娘を救うため、「青い鳥」を探す旅に出ます。「思い出」の国では、おじいさん、おばあさんや、亡くなった弟妹たちと再会します。生きている人が思い出すだけで、「思い出」の国の人々は生きている人たちに会えるというおじいさんたちの説明で、なんだかぐっときます。「森」では、植物や動物たちが、人間にされてきたことの復讐を試みます。考えさせられる物語であり、また「イヌ」の活躍が素敵です。 また「幸福の花園」での、様々な「幸福」たちとの出会い。 旅の果てに、チルチルとミチルは「青い鳥」を見つけられるのでしょうか。(あまりにも有名なオチかもしれませんが) 妖女のセリフで、とても印象的な言葉があったのでメモしておきます。「石はどれでも同じなんだよ。どの石もみんな宝石なんだよ。だが人間はその中のほんの少しだけが宝石だと思ってるんだよ」(29頁) 久々に読みましたが、素敵な読書体験でした。(2025.07.01読了)・海外の作家一覧へ
2025.09.14
コメント(0)
-

西洋中世学会『西洋中世研究』6
西洋中世学会『西洋中世研究』6~知泉書館、2014年~ 西洋中世学会が毎年刊行する雑誌『西洋中世研究』のバックナンバーの紹介です。 第6号の構成は次の通りです。―――【特集】中世とルネサンス―継続/断絶<序文>徳橋曜「中世とルネサンス―継続/断絶」<論文>出佳奈子「ピエロ・ディ・コジモの絵画における伝統と革新―15世紀フィレンツェにおける美術品受容の観点から―」徳橋曜「15世紀イタリアの文化動向と書籍販売」小林宜子「記憶の浄化と英文学史の創出―宗教改革期の好古家ジョン・リーランドをめぐる考察―」坂本邦暢「変容する存在の大いなる連鎖―中世とルネサンスにおける最善世界論―」伊藤博明「シビュラの行方―アウグスティヌスからパラッツォ・オルシーニまで―」上尾信也「音楽史におけるルネサンス再考―作曲家と作品の「越地域性」をめぐって―」【論文】高山博「中世シチリアにおける農民の階層区分」菊地重仁「複合国家としてのフランク帝国における「改革」の試み―カール大帝皇帝戴冠直後の状況を中心に―」辻部(藤川)亮子「「至純の愛」再考―オイル語宮廷風恋愛歌のレトリック解釈を通じて―」紺谷由紀「コンスタンティウス2世治世(337-361年)における聖室長官エウセビウスの位置づけ―宮廷宦官の人的関係に関する一考察―」【新刊紹介】【彙報】松田隆美「西洋中世学会第6回シンポジウム報告「西洋中世写本の表と裏―写本のマテリアリティと西洋中世研究―」」新井由紀夫・菊地重仁・町田有里「2013年度若手交流セミナー「マーガレット・ボニー氏による古文書セミナー」報告記」近江吉明「第8回日韓西洋中世史研究集会報告」――― 特集は、同題の2012年度西洋中世学会大会第4回シンポジウムでの5名の報告を踏まえた論考に、音楽の分野の上尾先生の論考を加えた6本の論文を収録(なお、同シンポジウムの概要は『西洋中世研究』4、2012、233-236頁参照)。 序文は問題提起と各論文の概観。 出論文は、財産目録と絵画の分析から、絵画に対するルネサンス期の態度の変化を指摘します。 徳橋論文は、印刷術の生まれる中世後期の教育的背景の確認から始まり、財産目録や書籍商の在庫目録を手がかりに、書籍販売の状況や読書傾向が14世紀から大きく変わるわけではないことを明らかにするとともに、印刷本による著者の意識変化など、まさに「継続と断絶」を示す興味深い論考。 小林論文は、イングランドでの修道院解散前後に、王から与えられた権限により教皇至上権を批判する目的で修道院写本の調査を行ったリーランドに着目し、過去との断絶を強調しようとする一方で、彼がいかに過去との連続性を見出そうとしたのかを明らかにします。 坂本論文は、哲学の観点から、神は世界を最善に作ったとの説と、これ以上善くすることができるという説がある「世界最善論」のあり方をめぐって、特にスカリゲルという人物に着目し、中世とルネサンスの継続と断絶を検討します。 伊藤論文は古代ギリシアの巫女たちの1人「シビュラ」がいかにキリスト教の著作などで描かれているかをたどり、古代からルネサンスにかけて、古代とキリスト教の連続性が強調されていたことを示します。 上尾論文は、音楽史における「ルネサンス」概念を研究史を丹念にたどりその位置づけを明らかにするとともに、ルネサンス期の音楽の諸相を論じます。 高山論文は、ラテン語、ギリシア語、アラビア語の史料の丹念な読みにより、中世シチリアにおいて農民が2つに分類されていたという通説を批判する興味深い論考。歴史学の営みの面白さをあらためて感じられる刺激的な論文です。 菊地論文はカール大帝の「改革」の様相を、特に君主の代理人ミッシ・ドミニキに着目して明らかにします。 辻部論文は、北フランスのオイル語宮廷風恋愛歌を史料として、そのレトリックに着目することで、詩人が愛を捧げる奥方を「封主」になぞらえる大前提を踏まえた論法による説得レトリックを用いていたことを具体的に示します。 紺谷論文は、宮廷宦官エウセビウスへの批判的な見方をとる先行研究に対して、宦官以外の官職の活動とも比較しつつ、彼の活動の具体的な側面と意義を再考します。 新刊紹介は43の洋書の紹介。中世地理・地図学を対象とした、ブレポルス社から刊行されている「中世学者のアトリエ」シリーズ第13巻についての小澤実先生による紹介や、栗原健先生による子供たちの謎かけなどを扱う書籍の紹介を特に興味深く読みました。 彙報は3本。第6回シンポジウムは実際に参加しましたが、八木先生によるご発表もさることながら、八木先生による特別展示「さわって体験―羊皮紙と中世写本」では、実際に羊皮紙にさわる経験ができましたし、羊皮紙片もいただけて、貴重な体験だったことを覚えています。また、若手交流セミナー(古文書セミナー)の報告、第8回日韓西洋中世史研究集会の概要報告のいずれも興味深いです。(2025.06.28再読) ・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.09.13
コメント(0)
-

シャルル・ペロー『眠れる森の美女―完訳ペロー童話集―』
シャルル・ペロー(巖谷國士訳)『眠れる森の美女―完訳ペロー童話集―』~講談社文庫、1992年~ シャルル・ペロー(1628-1703)による、1697年刊『過ぎし日の物語集または昔話集 教訓つき』と1695年刊行の『韻文による物語集』の全訳です。 表題作「眠れる森の美女」は、妖精の贈物により100年の眠りについた美女が王子によって目覚める…だけでなく、その後に王子の母が人喰い鬼の一族の出自で、王子夫婦を襲おうとするというエピソードが続きます。末尾の教訓はぴんときませんでした。「赤ずきんちゃん」は救いのないお話。 ジル・ド・レなどがモデルといわれる「青ひげ」は、夫が留守の間、決して開けてはならないと言われた小部屋を開けてしまった妻を待つ衝撃の展開です。「猫先生あるいは長靴をはいた猫」は、猫しか遺産をもらえなかった三男ですが、その猫が大活躍して…というお話。「サンドリヨンあるいは小さなガラスの靴」は、サンドリヨン=シンデレラの物語。「まき毛のリケ」は、ぶかっこうですが才知あふれる王子と、美しいけれど才知に欠けた王女のお話。「親指小僧」は、7人兄弟の末っ子で体も小さい「親指小僧」が、存在をうとまれながらも大活躍するお話です。 以上の8話が散文の物語で、後編には3編の韻文物語が収録されています。 最長の「グリゼリディス」は、美しい妃グリゼリディスと王の物語。作者は末尾にいろいろ書いていますが、王の非道さは、私には目に余りました。「ろばの皮」は、亡くなった妃の言葉で、美しい娘との結婚をくわだてる王と、王から逃れるためろばの皮をかぶり貧しい姿で暮らす王女の物語。これもなかなか…。「おろかな願い」は、3つまでなんでも願いごとを聞いてもらえることになった夫婦の話。 訳者解説もとても分かりやすいです。(2025.06.27読了) ・海外の作家一覧へ
2025.09.07
コメント(0)
-

ボーモン夫人『美女と野獣』
ボーモン夫人(鈴木豊訳)『美女と野獣』~角川文庫、1995年改版~(Madame de Leprince de Beaumont, Le Magasin des Enfants, Paris, 1757) ボーモン夫人(ジャンヌ=マリ・ルプランス・ド・ボーモン)は1711年ルーアンに生まれ。ボーモン某という男性と結婚するも相手が性格破綻者で、1745年に離婚、その後筆を執るようになります。再婚後、イギリスに渡り、子供たちの教育事業に打ち込んだり、様々な作品を発表したりします。1780年に亡くなります(解説、256-258頁参照)。 本書は彼女の代表作『子供の雑誌』(Magasin des Enfants, 1757)の翻訳ですが、全訳ではなく、物語部分の訳出とのこと。というのも、『子供の雑誌』は単純な「童話集」ではなく、女教師と子供たちの対話があり、それに関連する物語が導入される、という構造になっていますが、本書の意図は、「作家としてのボーモン夫人の作品を紹介する」ことで、「教育家ボーモン夫人を語るための本では」ないため、物語部分のみを訳出したと訳者は述べています(265-273頁参照)。 と、前置きが長くなりましたが、本書には15の物語が収録されています。 全てを紹介すると煩雑になるので、印象的だった作品のみメモしておきます。 心優しい商人の末娘が野獣の住む館に送られることになるというあまりにも有名な表題作のほか、同様にいじわるなきょうだいと心優しいきょうだい、あるいは甘やかされて育って破滅する登場人物と若い頃に不遇な目にあって成長してから成功する人物の対比とそれぞれの行く末を描く物語がいくつもあります。 特に印象的だったのは「どれいの島」という物語。主人である令嬢エリーズと女どれい―ミラが船で出かけると嵐にあって漂流し、たどりついた島は、本国でどれいだった人たちが主権をにぎる「どれいの島」でした。そこでは、まず一週間、どれいが、主人に対して、今まで主人がしてきたようにふるまわなければなりません。エリーズはその一週間で、自分が今までしてきたことを反省することになります。一方ミラは、それでもエリーズに忠実で…というお話です。 その他、講談社文庫のペロー昔話集には「おろかな願い」と題されて収録されているのと同様の、3つまでなんでも願いごとをかなえてもらえることになった夫婦を描く「三つの願い」など、どれも興味深く読みました。(2025.06.21読了) ・海外の作家一覧へ
2025.09.06
コメント(0)
-
阿部謹也『中世の星の下で』
阿部謹也『中世の星の下で』~ちくま文庫、1986年~ 1975年から1982年のあいだに雑誌や新聞など各種媒体に発表された35の文章が収録されています。単行本としての初出は影書房、1983年です。 本書の構成は次のとおりです(35すべての見出しを掲載すると煩雑になるので、部のタイトルと収録数をメモ)―――I 中世のくらし[12編]II 人と人を結ぶ絆[12編]III 歴史学を支えるもの[11編]初出一覧解説 社会史研究の魅力(網野善彦)文献目録――― 第1部は、星、橋、暦、風呂、涙など、中世の人々の暮らしをいくつかの具体的なテーマに即してみていきます。本書の表題となっている「中世の星の下で」は、1480年頃の写本に描かれた土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月の7枚の絵を掲載し、それぞれの象徴性を紹介しています。 第2部は、これまでに本ブログで紹介してきた『中世賤民の宇宙』などでも強調されていた、阿部先生の問題関心の中心をなす「人と人の絆」をテーマとして、ユダヤ人、煙突掃除人、市民意識などを扱います。「ブルーマンデーの起源について」で論じられる休日の問題や、「人間狼の伝説」で扱われる悪口としての犬など、興味深い話題が豊富です。「鐘の音に結ばれた世界」は、中近世における音―特に鐘の音について論じていて、戦争の際に鐘が溶かされ弾丸として転用されたことなどが示されます。 第3部は学問・歴史学の営みについて。18世紀後期にドイツで成立した教師も一般市民も一緒に地域の歴史を調べたりするなどの活動をした様々な「協会」を紹介し、その意義を強調する姿は、一部学会のあり方を批判する文章と対をなしていて印象的でした。また、1980年前後に日本でも大きく注目されたジャック・ル・ゴフやエマニュエル・ル・ロワ・ラデュリなどのアナール学派の業績の位置づけも興味深いです。 エッセイ風の文章も多く、また表題作にもうかがえるように素敵なタイトルも多く、読みやすく興味深い1冊です。(2025.06.19読了)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.08.31
コメント(0)
-

池上俊一/河原温(編)『聖人崇敬の歴史』
池上俊一/河原温(編)『聖人崇敬の歴史』~名古屋大学出版会、2025年~ 本書は、総勢25名の研究者が、キリスト教聖人崇敬の展開と諸相を論じる論文集です。(とはいえ、いわゆる学術論文のように詳細な注は付されておらず、それぞれ主要参考文献の提示と重要な点について注が付される形式です。) 編者の1人、池上俊一先生は西洋中世史を専門とする東京大学名誉教授で、膨大な著作があります。近年の著作として、たとえば、・池上俊一『ヨーロッパ中世の想像界』名古屋大学出版会、2020年・池上俊一『歴史学の作法』東京大学出版会、2022年 などがあります。 編者のもう1人、河原温先生は放送大学教授で、中世都市史を専門とされています。このブログでは、単著として・河原温『中世ヨーロッパの都市世界』山川出版社、1996年・河原温『都市の創造力(ヨーロッパの中世2)』岩波書店、2009年 を紹介したことがあります。 さて、全体で650頁ほどある重厚な本書の構成は次のとおりです。―――総説 聖人崇敬の歴史(池上俊一) 第1部 起源と展開 A ヨーロッパ第1章 古代~フランク王国(多田哲)第2章 盛期中世~後期中世(後藤里菜)第3章 近世・近代(坂野正則)第4章 ビザンツ(草生久嗣)第5章 ロシア・東欧(高橋沙奈美) B アメリカ第6章 中南米(八木百合子)第7章 アメリカ合衆国(小檜山ルイ) C アジア・アフリカ第8章 日本(川村信三)第9章 フィリピン(古沢ゆりあ)第10章 アフリカ(飛内悠子) 第2部 多様な役割第1章 聖人崇敬の神学(山内志朗)第2章 聖遺物の奉遷・窃盗(北舘佳史)第3章 聖人名と聖人暦(梶原洋一)第4章 「荒れ野」に向かう修道士たち(杉崎泰一郎)第5章 子どもと聖人(池上俊一)第6章 乙女、妻、そして寡婦―聖女伝におけるモデルの拡がり―(三浦麻美)第7章 天使にして聖人―大天使ミカエル崇敬―(千葉敏之)第8章 列聖手続きと教皇の関与(藤崎衛)第9章 国家を護る聖人―中世イングランドにおける聖ジョージ崇敬―(唐澤達之)第10章 都市と聖人崇敬―中世ブルッヘの場合―(河原温)第11章 地方的聖人崇敬―ブルターニュの場合―(小坂井理加)第12章 疫病除け聖人の「執り成し」―セバスティアヌスを中心に―(石坂尚武)第13章 聖人崇敬と奉納文化(水野千依)第14章 多様なるフランシスコ(神崎忠昭)第15章 顕現する聖母マリア(宮下規久朗)あとがき(河原温)図版一覧索引執筆者一覧――― 全25章と膨大なため、以下ごく簡単にメモ。 総説は基本的な概念の確認と、各章を踏まえて、全体の見取り図を提示します。 第1部第1章から第3章までは西欧の、第4章はビザンツの、第5章はロシアの、それぞれ聖人崇敬の起源から現代までを展望します。第3章では、フランス革命期に非キリスト教化運動の一環として「聖」のつく地名が変更され、革命家の名称などに置き換えられたとの指摘が興味深いです。 第1部B、Cはそれぞれ、非ヨーロッパ圏における聖人崇敬の歴史を、第1部A同様、通史的にたどります。第8章(日本)で、神のみに対する「崇拝・礼拝」と、聖人に対する「崇敬」が厳密に区別されることがあらためて指摘されるほか、わが国での聖人崇敬の特徴として、初期キリスト教の時代と同様、聖人=殉教者という点が挙げられるとの指摘が興味深いです。 第2部は主に西欧における聖人崇敬の諸相を論じます。とりわけ名づけと暦に着目した第3章、聖人への奉納を論じる第13章を興味深く読みましたが、その他の章もいずれも勉強になります。 第1部で通史的概観を提示し、第2部で聖人崇敬をめぐる諸相を論じる本書は、それ自体興味深いですが、本書の目指すところは「今後の個別研究に役立つ基本書となること」(34頁)とあります。たとえば、地方的聖人について、本書ではブルターニュの事例(第2部第11章)が論じられていますが、その他の地域の個別研究の参照軸となりえると思われます。また、第1部の通史や第2部第8章の列聖手続きの基本的な流れは、今後聖人に関して勉強する上で押さえておくべき内容と思われます。 重厚でありながら、適宜補足説明的な注も付されているほか、基本的文献の紹介、充実した索引のおかげで、読みやすく、まさに聖人崇敬に関する「基本書」となる1冊です。(2025.08.17読了)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.08.30
コメント(0)
-

アンソニー・ホロヴィッツ『死はすぐそばに』
アンソニー・ホロヴィッツ(山田蘭訳)『死はすぐそばに』~創元推理文庫、2024年~(Anthony Horowitz, Close to Death, London, 2024) 元刑事で警察顧問のダニエル・ホーソーンと、その活躍を記録することとなった作家のアンソニー・ホロヴィッツが活躍する、ホーソーン&ホロヴィッツシリーズ第5弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。――― 新たにホーソーンの活躍する本を書く契約をされてしまったホロヴィッツだが、ホーソーンは新しい事件に関わっておらず、書くネタに困っていた。そんな中、ホーソーンが過去に扱った事件の話を思い出し、その資料をホーソーンに提供してもらい、書いていくこととなる。 舞台は、高級住宅地。穏やかに暮らしていた住民たちだが、ケンワージー一家が引っ越してくると事態は一変してしまう。何台もの車を所有し、通路に駐車して医者の出勤の邪魔になったり、明け方に爆音で音楽を鳴らしながら車で帰ってきたり、子供たちは危ない遊びをしたり…。困った住民たちが、全員で集まって話をしようとした夜も、ケンワージーは急用ができたと言って参加せず。 ますます不穏な空気になる中、ケンワージーは歯科医のクロスボウで殺害された。 捜査に乗り出すホーソーンと助手のジョン・ダドリーだが、住民たちは何かを隠しているようで…。 * 一方、少しずつ資料を提供されるため、真相が分からないホロヴィッツは、物語を書き進めながら、ダドリーや住民たちに興味を持ち、彼らに接触しようとするが…。――― これまでの4作では、ホロヴィッツがホーソーンとともにリアルタイムで事件にかかわるのに対して、今回は自分が関わっていない過去の事件を描くということで、これまでと異なり三人称の叙述から始まります。 また、ホロヴィッツには、資料が少しずつ提示されるため、真相が分からないままに書いていくという厳しい条件もありました。真相を知るために、自分自身でも事件の関係者に会いに行くなどの行動をとり、さらにはホーソーンのことをさらに知るため、ある組織にも近づこうとするのですが…。と、単に過去の事件を描写するだけでなく、はらはらするような展開も待っています。 今回の事件では、このシリーズとしては珍しく、密室状況の謎も提示されます。その中で、作中ホロヴィッツが、日本の作家(作品)として、島田荘司『斜め屋敷の犯罪』と横溝正史『本陣殺人事件』を例に挙げ、「最高の密室ミステリは日本から生まれていると考えるようになった」(298-299頁)と記しているあたりも興味深いです。 古山裕樹さんも解説も分かりやすく、この記事の一部は解説にも触れられています。(2025.06.16読了)・海外の作家一覧へ
2025.08.24
コメント(0)
-
阿部謹也『西洋中世の罪と罰―亡霊の社会史―』
阿部謹也『西洋中世の罪と罰―亡霊の社会史―』~弘文堂、1989年~ 以前紹介した『中世賤民の宇宙』の続編にあたる1冊。同書に「死者の社会史」という論考が収録されていますが、同様に本書は亡霊に焦点を当て、死生観・罪の意識について論じます。―――はじめに第1章 古ゲルマン社会の亡者たち第2章 死者の国と死生観第3章 キリスト教の浸透と死者のイメージ第4章 中世民衆文化研究の方法と『奇跡をめぐる対話』第5章 罪の意識と国家権力の確立第6章 キリスト教の教義とゲルマン的俗信との拮抗―贖罪規定書にみる俗信の姿第7章 生き続ける死者たち註あとがき―――「はじめに」は、本書が罪の意識と死生観を論じる問題意識を提示します。ここでは、日本で「世間をお騒がせしたことを謝罪する」場合が多いことを取り上げ、この発想が「罪の意識が共同体と結びついてしか現れないという考え方に基づいている」(6頁)ことを指摘し、日本とヨーロッパの罪の意識の違いを指摘する点が興味深いです。 第1章は、アイスランド・サガを主要な史料として、死後も生き続け、生者を守ったり生者に害を加えたりする死者について論じます。死者への裁判や金銀の副葬など、興味深い事例が豊富なエピソードを通じて紹介されます。 第2章も引き続き北欧について、亡霊のあり方や死生観を論じます。 第3章は、アウグスティヌスや、聖人伝集成である『黄金伝説』を主要な史料として、古代ローマの死生観からキリスト教的死生観に転換していく様子を見ていきます。主要な点は、第1・2章でみた、ときに暴力的な亡霊から、生者に自身の救済のためのとりなしを乞いに現れる亡霊への変化の指摘です。 第4章は、ハイステルバハのカエサリウス『奇跡をめぐる対話』を主要史料として、第1・2章でみたような亡霊観が生き続けていたことや、煉獄の誕生により高利貸しに救済の道が開かれたことなどが指摘されます。 第5章では、国家のあり方と民衆教化に関して、カール大帝が果たした役割が強調されます。 第6章は、贖罪規定書という史料類型、特にヴォルムスのブルヒャルトによる「矯正者・医者」を主要史料として、具体的な罪とそれに課される贖罪のあり方を見ていきます。159章からなる「矯正者・医者」のうち、本書でも取り上げられる贖罪規定は第5章に収録されていて、その194項目の規定については、現在では野口洋二『中世ヨーロッパの教会と民衆の世界―ブルカルドゥスの贖罪規定をつうじて―』早稲田大学出版部、2009年により邦訳を読むことができます。 第7章は、本書のまとめであり、贖罪規定書、『奇跡をめぐる対話』などに加えて、民間伝承にも目配りしながら、民衆レベルで古来の死生観が生きていたこと、一方でキリスト教が影響を与えていたことを浮き彫りにしつつ、1215年第4回ラテラノ公会議で、年1回の告解が義務化されたことの重要性を強調します。 註もあり典拠にあたることができると同時に、重厚な論文も含む『中世賤民の宇宙』に比べると一般向けというか、より読みやすい1冊であると思います。 上でも言及した野口先生の単著を読んだ際に、本書を一部読み返していたようですが、このたび全体を読み返してみて、その面白さを再認識しました。 ゲルマン的慣行を示すのに北欧の事例が中心となっていること(普遍的にいえるのか)、古代ローマに関する記述は北欧のそれに比べて短く、古代ローマ的な死生観の概観が得づらいことなど、気になる点もありましたが、あらためて興味深く、勉強になる1冊でした。(2025.06.09再読)・西洋史関連(邦訳書)一覧へ
2025.08.23
コメント(0)
-

西洋中世学会『西洋中世研究』5
西洋中世学会『西洋中世研究』5~知泉書館、2013年~ 西洋中世学会が毎年刊行する雑誌『西洋中世研究』のバックナンバーの紹介です。 第5号の構成は次の通りです。―――【特集】グローバル・コンテキストの中のポスト・ローマ期<序文>佐藤彰一「グローバル・コンテキストの中のポスト・ローマ期」<論文>宮坂朋「キリスト教考古学から古代末期考古学へ―ヴィア・ラティーナ・カタコンベへの新たな視点―」浅野和生「成立過程に見る「中世美術」の形成」佐藤彰一「キルデリクス1世とドナウ戦士文化―フランク族のエトノス生成をめぐって―」大月康弘「後期ローマ帝国における財政規律と法の変容―ユスティニアヌス勅法が律する寄進行為の位相から―」シュテファン・エスダース(村田光司訳)「コンスタンス2世(641-668年)、サラセン人、西欧部族国家―地中海世界大戦期の政治と軍事、および経済と財政の連関に関する試論―」【論文】梶原洋一「中世末期におけるドミニコ会教育と大学―アヴィニョン「嘆きの聖母」学寮の事例から―」井口篤「「心の扉を開ける」―中世後期イングランドの俗語神学―」【新刊紹介】【彙報】金沢百枝「西洋中世学会第5回シンポジウム報告「中世のなかの『ローマ』」」図師宣忠「2012年度若手交流セミナー【西洋中世学の伝え方―『薔薇の名前』の世界を語る】報告記」佐藤直子「「上智大学中世思想研究所」の歩みと使命」――― 今回の特集は、ポスト・ローマ期の世界をグローバルな文脈の中に位置づけて読み解きます。 佐藤先生の序文はグローバルヒストリーの潮流を概観した後、本特集の各論稿を紹介します。 宮坂論文は、古代末期考古学の成果を様々な観点から紹介した後、その文脈とからめて、題材とするヴィア・ラティーナ・カタコンベの分析を行います。例外的だった土葬が3世紀初めに逆転し土葬が主流になることを示す表が興味深いです。 浅野論文は、5世紀の象牙製ディプティック(筆記用具)と6~7世紀の円形競技場を礼拝堂に採用した場のモザイクを題材に、美術の観点から「中世」という時代意識が生まれたことを論じます。 佐藤論文は1653年に発見されたキルデリクス1世の墳墓を出発点として、フン族の影響など、東方世界とのつながりに目配りしながら、初期メロヴィング期の基本的なクロノロジーの確定と、その歴史的意義について論じます。 大月論文は、ユスティニアヌス勅法の分析から、特に寄進行為に着目し、財政規律の規制が「個人」に向かっていったことなどを明らかにします。 エスダース論文は、7世紀後半のコンスタンス2世の時期、彼による各地での戦いの意義や、敗者による勝者への貢納といった、経済・財政との関連を論じます。 梶原論文は、托鉢修道会(特にドミニコ会)と大学については対立関係が強調されがちですが、15世紀末に設置された学寮に着目し、両者の結びつきを浮き彫りにする論考。 井口論文は、1409年のアランデルによる俗語聖書の禁止がもたらした効果をやや相対化し、俗語神学に、それまでの伝統的神学からの連続性があることを明らかにします。 新刊紹介は、43冊の洋書と2冊の和書の紹介。とりわけ、山口雅広先生が紹介なさっている、枢要徳の歴史をたどる、I. P. Bejczy, The Cardinal Virtues in the Middle Agesが気になりました。 彙報は3本。2013年6月開催の西洋中世学会におけるシンポジウム「中世のなかの『ローマ』」の概要、2012年9月開催の若手セミナーの報告(こちらは、『薔薇の名前』を授業にいかに活用するかという事例報告で、興味深いです)、そして上智大学中世思想研究所の歩みと今後の使命を記した文章です。 特集は私が不勉強な時代を中心としていること、そして重厚な議論もままあり、十分に読み込めませんでしたが、今号では梶原先生の論考が自身の関心にも近く、とりわけ興味深く読みました。(2025.06.08再読)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.08.17
コメント(0)
-

有栖川有栖『捜査線上の夕映え』
有栖川有栖『捜査線上の夕映え』~文春文庫、2024年~ 犯罪社会学者・火村英生先生と作家・有栖川有栖さんが活躍するシリーズの長編作品です。 日本がコロナ禍で、「三密」を避けていた頃。 マンションの1室で、男の死体が発見されます。死体は、スーツケースに詰められていました。 マンションの防犯カメラの分析と、男の交友関係から、容疑者はかなり絞り込まれます。 恋人。三角関係にあった女。被害者から借金していた友人。謎のサングラスの男……。 しかし、関係者には、それぞれアリバイがありました。 犯人は、なぜスーツケースに死体を詰めたのか。なんらかのアリバイトリックがあるのか。謎の男の正体は……。 と、大掛かりな謎はなく、佐々木敦さんの解説の言葉をお借りすれば「一見地味とも言える」事件です。 ところが、どことなく据わりが悪く、早期解決も困難に思われていました。 そんな中、火村先生はあることに気付き、事件解決のために「旅」に出ます。 「コロナ」「旅」がキーワードといえるでしょう。 たしかに、スーツケースに死体が詰められた謎は不可思議ですが、密室とか、明らかに犯人と思われる人物に鉄壁のアリバイがあるとか、そういった「ハウダニット」の謎解きの要素は薄く、それよりもある人物をめぐる、抒情的な味わいのある物語です。 自分自身の年齢もあるかもしれませんが、がちがちの謎解きも好きですが、こういった味わいのある物語も好みになってきたこともあり、好みの物語でした。解説にもありますが、ある一文の衝撃たるや。 素敵な読書体験でした。(2025.06.06読了)・あ行の作家一覧へ
2025.08.11
コメント(0)
-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 人参は微笑む』
碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 人参は微笑む』~だいわ文庫、2024年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第6弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「文旦とためらい」川島さんと出かけているときに立ち寄った文旦フェスで、文旦の魅力に気づいた優希さんたち。菜の花食堂に野菜を卸してくれる保田さんも関わっているそのイベントに、以前は靖子先生も関わっていたそうなのですが、先生が身を引いた理由とは。「筍の胸さわぎ」小瀧さんが、犬の散歩をしていると、お化け屋敷と呼ばれているアパートのあたりで立ち止まり、吠えたり、動こうとしなかったりと、いつもと様子が変わってしまいました。それで料理教室に遅れたのだという小瀧さんの話を聞いて、靖子先生は、緊急を要するかもしれないとすぐに行動に出るのですが…。「ゴーヤは打たれ強い」料理教室の生徒の紹介で、謎解きの依頼にお店を訪れた柳原まりなさんは、母が遺してくれた指輪のありかを知りたいといいます。まりなさんの話から、靖子先生がたどりついた答えとは。「疑惑のカレーライス」ボランティアで運営されている野川まつりに、川島さんと訪れた優希さん。ですが、来場者が何人か体調を崩し、担架で運ばれていたことを知ります。さらに、カレーライスの屋台でがんばっていた奏太さんも体調を崩してしまい…。「人参は微笑む」わざと店員を転ばせ、自分の服を汚させて弁償を求める事案が発生したと聞いて、用心していた優希さんたち。ある日、菜の花食堂に怪しい男が現れたとき、優希さんはうっかりその男に水をこぼしてしまい…。――― 靖子先生の過去を描く「文旦とためらい」。これは、靖子先生の立場からいえば謎でもなんでもないのですが、先生の過去を知らない優希さんにとっては謎になるという、日常生活でもあるような物語で、味わいがありました。 アシスタントの香奈さんと、フロア・マネージャーの優希さんの、ますますの成長も描かれます。 その他、コロナなど、時事ネタも盛り込まれた作品もあり、バラエティ豊かな短編集です。(2025.05.30読了)・あ行の作家一覧へ
2025.08.10
コメント(0)
-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 木曜日のカフェタイム』
碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 木曜日のカフェタイム』~だいわ文庫、2022年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第5弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「こころを繋ぐお弁当」菜の花食堂でイベントにお弁当を出品した日、食堂に同じお弁当がほしいという客が訪れます。悪い人ではなさそうだけれど、何かわけありのようで…。「木曜日のカフェタイム」菜の花食堂の近所で空き巣事件が発生。知っている店にも、まわりのことを色々と聞き出す怪しい客が現れたとききます。一方その頃、前回の事件で知り合った少年に近づこうとする男の客が来店するようになり…。「キャラ弁と地味弁」料理教室の生徒の岸田さんが、靖子先生に相談を持ち掛けます。嫌いな食べ物でも、キャラ弁にすると食べてくれていた娘が、ある日、キャラ弁はもういらないと言います。それでもキャラ弁を作った岸田さんに、娘さんは激しい剣幕で怒ったとのこと。はたして岸田さんの娘の思いとは…。「インゲンは食べられない」キャリアウーマンの園田さんは、婚活で知り合った男性との結婚間近の様子でした。ある日、園田さんが、飼っているチワワがいなくなったと相談にきます。そこで靖子先生がとった方法とは。「大根は試さない」川島さんに料理を教えに行った優希さんですが、送られたリストにも書かれていない大根の味に困惑します。かなり苦味のあるその大根を、どのようにすれば美味しく食べられるのか。靖子先生に相談しながら、優希さんは工夫をこらします。ところが、大根の試食後、川島さんの様子がどこかおかしくて…。――― 上では「少年」と書きましたが、ある出来事をきっかけに菜の花食堂と縁の出来た奏太さんが、本書を通じての鍵となる登場人物になります。奏太さんの周辺の大人たちには色々思ってしまわなくもありませんが、本人の真っすぐで素敵な人柄が素敵です。 また、最終話は前作に引き続き、優希さんの今にスポットが当てられます。果たして、川島さんの不可解な行動の意味とは。 もやっと感じてしまう人物も出てきますが、全体として、本書も楽しく読みました。(2025.05.24読了)・あ行の作家一覧へ
2025.08.09
コメント(0)
-
阿部謹也『中世賤民の宇宙―ヨーロッパ原点への旅―』
阿部謹也『中世賤民の宇宙―ヨーロッパ原点への旅―』~筑摩書房、1987年~ 一橋大学名誉教授で、ヨーロッパ中世史家としてあまりにも有名な阿部謹也先生による初期の論文集です。 1982年以降に『社会史研究』などに掲載された論考が収録されています。 本書の構成は次のとおりです。―――私たちにとってヨーロッパ中世とは何かヨーロッパ・原点への旅―時間・空間・モノ死者の社会史―中世ヨーロッパにおける死生観の転換ヨーロッパ中世賤民成立論中世ヨーロッパにおける怪異なるものヨーロッパの音と日本の音註あとがき――― 冒頭の「私たちにとってヨーロッパ中世とは何か」は導入で、本書所収の各論文に通じる「大宇宙と小宇宙という二つの宇宙」「贈与・互酬関係」といったキーワードが示されます。 第1論文「ヨーロッパ・原点への旅」は、問題をたてるにあたり、自己省察から始まります。ここでは、社会史に関心を寄せることとなった背景などが語られます。また、冒頭でも論じられた贈与・互酬関係に関連して、わが国の汚職(40年近く前に刊行された本書ですが、いまなおわが国に通じることの悲しさを感じます)を例にあげ、西洋的近代化とわが国の習俗のあり方を理解する必要を説く点が興味深いです。 80頁近くある重厚な本稿は、「時間意識」「空間意識」「モノをめぐる関係」の3つの軸に沿って論じられます。今回久々に再読してみて、アーロン・グレーヴィチ(川端香男里/栗原成郎訳)『中世文化のカテゴリー』岩波書店、1992年(初版1972年。阿部先生はそのドイツ語訳版を参照)の議論に依拠しつつ、議論を展開していることに気付きました(もちろん、グレーヴィチの説をうのみにするだけでなく、批判的に議論を展開しています)。 第2論文「死者の社会史」も、約60頁に及ぶ重厚な論考。ヨーロッパと日本の死生観を対比するにあたり、心中を例に挙げた導入が興味深いです。そこから、初期中世のゲルマン的な「生ける死体」と「死者の取り分」に関する議論、キリスト教の浸透により死者への贈与から神への贈与へ転換すること、遺言書の分析による相続・財産分与のあり方、さらに現世観の変化と議論が展開します。ここでは、導入論文にあるように、「贈与・互酬関係」の視点から死生観・現世観が論じられています。 第3論文「ヨーロッパ中世賤民成立論」は、多岐にわたる「賤民」への賤視の根源をたどる試みです。具体例として、平和喪失者である「人間狼」を見た後、阿部先生は賤視の根源を二つの宇宙観にみます。すなわち、火、水、汚物などは自然=大宇宙に属するものであり、それらを扱う煙突掃除人、水車小屋の粉ひき、道路清掃人などは二つの宇宙のはざまにいる、特別な力を有する人々であって、畏怖のまなざしが向けられていました。ところが、キリスト教の普及により、大宇宙の捉え方に変換がもたらされたことで、その畏怖は賤視へと変わっていく、といいます。興味深い議論ですが、畏怖のまなざしに関する説明は丹念になされているものの、畏怖が賤視にかわる過程の議論はやや駆け足なのが気になりました。 第4の「中世ヨーロッパにおける怪異なるもの」は講演記録。彫刻、絵画、メルヘンに現れる怪物などや賤民などの「怪異なるもの」を、第3論文同様、「二つの宇宙」観から読み解きます。 第5論文はポリフォニーの成立に関する試論。冒頭の、騒音に対する日本とヨーロッパの比較が興味深いです。 学生時分に勉強した本ですが、その後いろいろ本を読み、あらためて読み返すとまた違った気付きがあり、興味深く読みました。(2025.05.23再読)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.08.03
コメント(0)
-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 裏切りのジャム』
碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 裏切りのジャム』~だいわ文庫、2021年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第4弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「春菊は調和する」料理教室の新規の生徒、水野さんは、夫のダイエットがなかなか進まないのを気にしていました。ある日、菜の花食堂に食事に訪れた水野さん家族ですが、ダイエットのことで夫婦は険悪な雰囲気に…。はたして水野さんの思いとは。「セロリは変わっていく」菜の花食堂に捨て犬がつながれていました。その日食事に来ていた小学生の六花さんは犬のことが気に入り、しばらく菜の花食堂で預かることになった犬の散歩の手伝いをします。ところがある日、六花さんがその犬を盗んだという子が現れて…。「裏切りのジャム」フロア・マネージャーの優希さんとシェフ見習いの和泉香奈さんが中心となって進めていた瓶詰も軌道に乗っている中、ジャムが腐っていたという苦情が立て続けに入ります。明らかに不審な状況の中、靖子先生がとった行動とは。「玉ねぎは二つの顔を持つ」新婚の小松原さんは、義母との同居も楽しみに結婚しましたが、なかなか同居の話が進みません。はたして義母が抱える思いとは。「タケノコは成長する」川島さんに実家から届く野菜をつかって料理を作るというアルバイトをはじめてしばらくした頃。優希さんが川島さんのもとを訪ねると、すでに一部の野菜を使って料理をしたあとがありました。また、川島さんから話があるとも。川島さんに素敵な人ができ、アルバイトも終わるのかと不安を覚えた優希さんは、事故で骨折してしまい…。――― 表題作が「裏切りのジャム」と、重めのタイトルだったので、いささかの不安をもって読み進めましたが、ビター感もありつつ、嫌な気持ちはほとんど残らなかったので、結果的にどれも楽しく読めました。 特に表題作は、不審な状況から人為的な事件だと判断した後の靖子先生が、いつになく凛とした姿で対応に向かうあたり、かっこよかったです。自分の仕事に誇りをもち、また優希さんや香奈さんを信じているからこその行動が素敵です。 また、前3作の最終話は、先生の過去に関するお話でしたが、今作では、優希さんの今(川島さんとの行方)に関するお話で、ほっこりする味わいです。(2025.05.17読了)・あ行の作家一覧へ
2025.08.02
コメント(0)
-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 金柑はひそやかに香る』
碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 金柑はひそやかに香る』~だいわ文庫、2018年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第3弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「小松菜の困惑」瓶詰をマルシェで販売することが決まった頃、香奈さんは彼氏のことで悩んでいました。香奈さんがお弁当を作るのを、彼氏が嫌がっているようなのですが、原因が分からずに…。「カリフラワーの決意」優希さんは、派遣の仕事と菜の花食堂の手伝いの両立で心が揺らいでいました。一方、いよいよ迎えたマルシェの日、瓶詰の酢だけをほしいと少女が頼んできた理由とは。「のらぼう菜は試みる」菜の花食堂の野菜の仕入れ先、農家の保田さんは、経営するアパートの隣に開いている無人販売所で、お金が多く残されていることを気にしていました。先生が明かすその理由とは。「金柑はひそやかに香る」優希さんのアパートの隣室に引っ越してきた男性の部屋から、異臭がするといいます。その頃、ニュースではアパートでの監禁事件も報じられていました。優希さんの身を案じた先生たちは、隣人との接触を試みることになるのですが…。「菜の花は語る」先生は、なぜ自分のお店に菜の花食堂という名前をつけたのか。先生は開店記念日も覚えていないといいますが、開店25周年を前に、優希さんは考えをめぐらせます。――― 今作も面白かったです。どのお話もビター感がほぼなく、安心して読めます。 特に好みだったのは「のらぼう菜は試みる」。誰も傷つかないのがほっとします。 今作は、優希さんに大きな変化が訪れます。最終話での優希さんのいらだちも印象的でした。 これからの展開がますます楽しみになる一冊です。(2025.05.09読了)・あ行の作家一覧へ
2025.07.27
コメント(0)
-

碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 きゅうりには絶好の日』
碧野圭『菜の花食堂のささやかな事件簿 きゅうりには絶好の日』~だいわ文庫、2017年~ 菜の花食堂の店主で、料理教室も開催している下河辺靖子先生と、先生の助手をつとめる館林優希さんが活躍するシリーズの第2弾。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「きゅうりには絶好の日」料理教室の生徒、瀬川さんは、いつ見ても駐輪場にある赤い自転車が、人にぶつかりそうな場面に遭遇したといいます。しかしその直後、駐輪場にはやはりその自転車がとまっていて…。「ズッキーニは思い出す」父子家庭で育った牧さんは、こどもの頃におばさんが作ってくれたお弁当が大好きでした。その話を聞いた帰り、牧さんのおばさんに出会った優希さんは、彼女から、牧さんの母親が重い病気であることを告げられます。母親を忘れようとする牧さんの気持ちを動かすために、先生が考えた方法とは。「カレーは訴える」地域のイベント「野川マルシェ」主催者の川崎さんと知り合い、出店を依頼された菜の花食堂。カレーを販売しましたが、朝から、慌てたようにルーだけを購入した客に、先生は何か気付いたようで…。「偽りのウド」ウド室のある農家、大倉さんのリクエストで、ウドを料理教室の食材として扱った後。たまたまインターネットでウドのレシピを検索した優希さんは、料理教室のレシピが掲載されているのを発見して…。「ピクルスの絆」香奈さんが菜の花食堂に弟子入りを依頼します。その頃、特別に料理教室の開催をお願いしてきた小島さんが、遺言状をめぐる謎について相談を持ち掛けてくるのですが…。――― 第1巻はビターな話もいくつかありましたが、今作は比較的マイルドな印象で、私は、より安心して読むことができました。 特に印象的だったのは「ズッキーニは思い出す」。これは、うっかり外で読んでいると危ういことになるところでした。また、「カレーは訴える」は、事件(?)の解決がとても前向きで、こちらも好みでした。 香奈さんが弟子入り志願したり、瓶詰の販売に向けて動き始めたりと、短編集でありながら、少しずつ物語も進んでいき、今後の行方がますます楽しみになります。(2025.05.05読了)・あ行の作家一覧へ
2025.07.26
コメント(0)
-

甚野尚志/踊共二(編)『キリスト教から読み解くヨーロッパ史』
甚野尚志/踊共二(編)『キリスト教から読み解くヨーロッパ史』~ミネルヴァ書房、2025年~ 堀越宏一/甚野尚志編『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』ミネルヴァ書房、2013年でも、編者はその書名ではイメージが伝わりにくいと冒頭で断っていますが、本書についても(甚野先生はいずれの編者でいらっしゃいます)、書名について断りがあります。 この書名からは、「従来の通史的なキリスト教史の概説」が想像されますが、「中近世ヨーロッパのキリスト教に関する重要な問題について、現在どのように理解されているのか、それによりヨーロッパ史の理解がどのように変わって来たのかを提示すること」(1頁)が本書の意図であると示されます。 本書の構成は次のとおりです。―――序章 甚野尚志・踊共二「キリスト教史がわかればヨーロッパ史がわかる」コラム1 印出忠夫「古代の密儀宗教」第1章 三浦清美「キリスト教の東と西」コラム2 中谷功治「イコノクラスム」第2章 甚野尚志「罪と贖罪」コラム3 齋藤敬之「瀆神」第3章 鈴木喜晴「禁欲と戒律―修道院」コラム4 石黒盛久「修道制と人文主義」第4章 後藤里菜「正統と異端」コラム5 佐々木博光「中世のユダヤ人迫害」第5章 多田哲「聖人と奇跡」コラム6 小林亜沙美「列聖」第6章 関哲行「巡礼―中近世スペインのサンティアゴ巡礼」コラム7 辻明日香「東方のキリスト教世界」第7章 加藤喜之「聖書―聖なるモノ、俗なるコトバ」コラム8 岡田勇督「メシアとキリスト」第8章 皆川卓「戦争と平和」コラム9 黒田祐我「レコンキスタ」第9章 踊共二「宗教改革」コラム10 坂野正則「近世のカトリシズム」第10章 小林繁子「魔女迫害とキリスト教」コラム11 黒川正剛「教会とジェンダー」第11章 安平弦司「寛容と多様性―思想・統治戦略・生存戦略」コラム12 押尾高志「「隠れムスリム」の世界」あとがき人名・事項索引執筆者紹介――― 初期から現代までのキリスト教の概観を示しながら本書各章の概要を紹介する序章に続き、ある程度時代の流れに沿いながら、テーマごとに見ていく本論が続きます。また、序章を含む各章のうしろには、その章に関連する4頁ほどのコラムがあります。 概説書であり、内容も多岐にわたるので、印象的だった点のみメモしておきます。 第1章では、心理学者ユングによる「ヨブ記」の解釈が紹介されていて興味深いです、 コラム2は、聖像破壊=イコノクラスムは、「イコン支持派が作り上げた神話に近いもの」とまで述べる学者の見解が紹介されています。イコノクラスムについては、以前紹介した図師宣忠/中村敦子/西岡健司(編)『史料と旅する中世ヨーロッパ』ミネルヴァ書房、2025年所収小林功「イコノクラスムのはじまりとレオン3世―8世紀のビザンツ帝国をとりまく世界―」でも論じられていて、あわせて読むとさらに勉強になります。 第2章は初期中世から宗教改革期までの贖罪・告解制度の概観。 コラム3は「罰当たりな言動」=瀆神を扱う面白いコラム。 第3章では、西方修道制の象徴となる『ベネディクトゥスの戒律』について、ベネディクトクス自身についての史料の沈黙(グレゴリウス大教皇『対話』が唯一の史料)が奇妙であると問題提起し、その戒律普及の過程に関する興味深い考え方が提示される部分が興味深いです。 第4章は、異端への暴力を正当化する根拠とされるアウグスティヌス『神の国』の記述について、アウグスティヌスの置かれた時代背景をもって理解すべきと説きます。 第5章は、それまで様々なジャンルの著作に収録されていた聖人の奇跡について、9世紀にはもっぱら奇跡のみを集めた奇跡伝というジャンルが確立したことを指摘します。 コラム6は古代から中世中期までの、列聖手続きの変遷を概観しており分かりやすいです。 第6章は、スペインのサンティアゴ巡礼を中心とした、巡礼についての概観。 コラム7では、「イスラーム世界」という表現の是非を問う議論が紹介されていて興味深いです。 ここまでの章が初期中世から盛期中世までを主に扱う中世末期以降を主に扱うのに対して、第7章以降は、中世末期以後を中心に扱います。 第7章は、モノとしての聖書を扱います。中世において権威であった「ウルガタ」=ラテン語訳聖書について、原語のギリシア語などと比較しその誤りを正そうとしたヴァッラの仕事と、彼を教皇ニコラス5世が支援していたというエピソードや、その後の聖書の俗語訳をめぐる流れなど、非常に興味深く読みました。 第8章は、そのテーマである戦争と平和をめぐり、宗教や国家の関係から見ていきます。 第9章は、宗教改革におけるルターの革新性を、ルター以前からの流れも追うことでやや相対化しつつ、各地の宗教改革の流れを追っていて、こちらも勉強になりました。 第10章では、「不当な裁判が横行することもまた、支配者にとって決して容認できないことだった」(242頁)とし、魔女裁判の行き過ぎを抑制する世俗支配者のあり方を指摘している点が興味深いです。 関連するコラム11は、魔女裁判をジェンダーの観点から読み解きます。 第11章では、カトリックとプロテスタントなど異宗派間の交流が日常生活上ではあったことを指摘し、フライホフという研究者による「日常生活のエキュメニシティ」という表現を引いています。 個人的な覚えになってしまいましたが、どの章も興味深く、私が専門に勉強している時代よりも後の時代を扱った第7章以降も大変勉強になりました。(2025.05.24読了)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.07.20
コメント(0)
-

小杉泰『イスラームとは何か―その宗教・社会・文化―』
小杉泰『イスラームとは何か―その宗教・社会・文化―』~講談社現代新書、1994年~ 著者の小杉泰先生は2024年度現在で立命館大学立命館アジア・日本研究所所長(本書執筆当時は国際大学大学院国際研究学研究科助教授)で、ご専門はイスラーム学、中東地域研究でいらっしゃいます。 本書の構成は次のとおりです。―――序 「イスラーム」の発見へ第1章 新しい宗教の誕生第2章 啓典と教義第3章 共同体と社会生活第4章 第二の啓典ハディース(預言者言行録)第5章 知識の担い手たちと国家第6章 神を求める二つの道第7章 スンナ派とシーア派第8章 黄金期のイスラーム世界第9章 現代世界とイスラームあとがき――― 20年ぶりくらいの再読ですが、はじめて読んだときから、序に記載の、教えそのものを「イスラーム」というため、「イスラーム教」というと屋上屋を架す感が強く、「イスラーム」と「教」を付けずにいうのが一般的という指摘が印象的でした。 第1章はムハンマド誕生前夜のアラビアの状況、ムハンマドの生活と啓示、マッカ(メッカ)からマディーナ(メディナ)への聖遷(ヒジュラ)などが概観されます。ここでは、啓示を受けて恐怖に震えるムハンマドを励ました妻のハディージャがいとこのキリスト教徒に相談にのってもらったというエピソード(30頁)が興味深かったです。 第2章はクルアーンの教えの概要など、イスラームの教義を概観します。本章では、当初はイスラームを嫌っていたウマル(後の第2代正統カリフ)が入信するエピソードが印象的でした(52-53頁)。また、クルアーンの教えを4つに大別して図示した60頁も便利です。 第3章は礼拝や、結婚などの社会生活についての概観した上で、ムハンマドの死から正統カリフ時代までを描きます。 第4章はムハンマドの言行を伝えるハディースについて。著者による脚色もあるとのことですが、膨大なハディースを記憶していたブハーリーに関する逸話(120-121頁)が興味深かったです。 第5章は、知識の担い手が社会で果たした役割について。いわゆる宗教学者であるウラマーと、共同体(ウンマ)の合意が物事を決定していく点について、コーヒーをめぐる事例が興味深かったです。ウラマーは、コーヒーを許されない飲料と考えましたが、共同体はそれにかまわずコーヒー文化を発達させ、ついに合法になった(155頁)という指摘(タバコも同様)は、合意のあり方を示す印象的なエピソードと思われます。また、「筆の人」であるウラマーは、「剣の人」である統治者などと、「職の人」である一般信徒のあいだで天秤のようにバランスをとる存在であるという指摘(171頁の図も分かりやすい)からは、「祈る人、戦う人、働く人」という中世ヨーロッパの3身分論を連想し、こちらも興味深く読みました。 第6章は神学と神秘主義について、第7章はイスラーム全体としては少数派(ではあるが一つの国家に着目した場合、その国では多数派である場合も)であるシーア派と、多数派のスンナ派について論じます。239頁にはスンナ派とシーア派の主要な特徴を対比的に示した図があり便利です。 第8章はやや通史的にイスラーム国家の発展を概観し、第9章は現代の現状と諸課題を論じます。とりわけ、中東問題に関する議論の中で、宗教問題と民族問題が複雑にからみあっているという指摘はあらためて認識しておきたいポイントです。 久々の再読でしたが、興味深い指摘も多く、また上で何度か言及したように適宜分かりやすく整理した図表も掲載されていて、勉強になる1冊です。(2025.04.17再読)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.07.19
コメント(0)
-

図師宣忠/中村敦子/西岡健司(編)『史料と旅する中世ヨーロッパ』
図師宣忠/中村敦子/西岡健司(編)『史料と旅する中世ヨーロッパ』~ミネルヴァ書房、2025年~ 本書は、高校世界史の教科書や概説書で記述される通説の裏にある、「史料を分析し、議論を通じて歴史像を作りあげてきた歴史家たちの積み重ね」(2頁)に焦点を当て、いくつかのテーマを取り上げて通説と史料の読解を提示する興味深い1冊です。 各章は、「概説」「史料と読み解き」「ワーク」で構成されています。まず、教科書などの記述を具体的に見て通説を確認し、次いでそのテーマに関する主要史料の確認と具体的な読み解きを試み、さいごにさらなる学びに向けて「ワーク」として課題を提示するという、分かりやすい構成です。 編者の1人、図師先生については、以下の著作を紹介したことがあります。・図師宣忠『エーコ『薔薇の名前』―迷宮をめぐる<はてしない物語―』慶応義塾大学出版会、2021年 前置きが長くなりましたが、本書の構成は次のとおりです。――― 序章 図師宣忠・中村敦子・西岡健司「史料を紐解き、過去の世界に旅しよう」第1部 権威と統治 第1章 中村敦子「王は「強かった」のか?―ノルマン征服とウィリアム征服王―」 第2章 小林功「イコノクラスムのはじまりとレオン3世―8世紀のビザンツ帝国をとりまく世界―」 第3章 藤井真生「聖性・儀礼・象徴―中世後期チェコの国王戴冠式式次第より―」 史料への扉1 松本涼「アイスランド・サガ―過去の真実を物語る」 史料への扉2 上柿智生「史料としてのビザンツ文学」第2部 教会と社会 第4章 西岡健司「辺境にみる西欧カトリック世界―13世紀スコットランドの一証書を通して―」 第5章 図師宣忠「正統と異端のはざまで―南フランスの異端審問記録にみる信仰のかたち―」 第6章 轟木広太郎「魔女裁判って中世ですよね?―例話集にみる魔術と悪魔―」 第7章 櫻井康人「「十字軍」とは何か?―12世紀の公会議・教会会議決議録より―」 史料への扉3 中田恵理子「社会を通して大学を、大学を通して社会を読む」第3部 都市と農村 第8章 青谷秀紀「都市と領主の付き合い方―中世のフランドル地方をめぐって―」 第9章 佐藤公美「つながり合う都市―ロンバルディア同盟にみる「都市同盟」の意味―」 第10章 髙田京比子「都市と農村のあいだ―北イタリア・バッサーノの条例集にみる自治―」 第11章 田中俊之「抑圧された農民?―中世ドイツの農村社会―」 史料への扉4 高田良太「公証人記録―名もなき人々の生きた痕跡を探る―」付録 中世ヨーロッパに関する史料の和訳図書リスト索引執筆者紹介――― 第1章は、王の権力とはなにか、という問題を取り上げ、証書史料の証人リストの存在から、「強力な王権」といわれる王も自由に物事を決定できたわけではなく、複数の有力者の承認が必要であったことを指摘します。 第2章は2つの歴史書を比較し、イコノクラスム(聖像破壊)の実態に迫ろうとします。 第3章は戴冠式の式次第を史料として、聖性・儀礼・象徴の一端を明らかにします。 第4章は、スコットランドで生じた争いに関する証書史料を取り上げ、教会や修道院の状況をみます。 第5章は、エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリによる『モンタイユー』でも主要史料とされる、ジャック・フルニエによる異端審問記録の分析から、異端とされた人々の考え方や、異端審問者たちの手続きを論じます。 第6章はタイトルが挑戦的で好みですが、魔女裁判の最盛期は16世紀後半から17世紀前半にかけて、つまり近世的な出来事であることを冒頭で指摘し、また中世では魔術を行う人は寛容に扱われていたと述べた上で、ハイステルバハのカエサリウスによる例話集『奇跡についての対話』を史料として、中世における悪魔・魔術への態度をみます。ここでは、聖職者が悪魔を呼び出す例話も紹介されていて、興味深く読みました。(この例話集については、たとえばVictoria Smirnova, Marie Anne Polo de Beaulieu and Jacques Berlioz (eds.), The Art of Cistercian Persuasion in the Middle Ages and Beyound. Caesarius of Heisterbach's Dialogus on Miracles and its Reception, Leiden-Boston, Brill, 2015の記事を参照)。 第7章は、公会議・教会会議の史料から、十字軍の本質、目的と対象を指摘します。その本質を「贖罪」とする点や、聖地十字軍と非聖地十字軍が同列に扱われたわけではないとする指摘を史料から導く鮮やかさが印象的です。 第8章以下は、都市と領主、都市と農村、農民と領主の関係などを扱います。編年誌からフランドル地方の都市・君主間の関係などをみる第8章、ロンバルディア同盟とハンザ同盟が教科書では同列的に扱われるが、実際はどうかをロンバルディア同盟に着目して論じ、また多くの問題提起を行い歴史研究の奥深さを示す第9章、条例を史料として都市・農村間の関係と都市の自治のあり方を論じる第10章、様々な史料から農民の主体的な行動を明らかにする第11章と、いずれも興味深く読みました。(序章でも、各章の難易度は一様ではないと指摘されていますが、やや難度が高めの章が多い印象でした。) 4つの「史料への扉」は、それぞれ記載の史料に関するコラム。 付録の、邦訳史料一覧も大変便利です。 最新の教科書での通説や、歴史学の営みの一端に触れられる興味深い1冊です。(2025.04.25読了)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.07.13
コメント(0)
-

西洋中世学会『西洋中世研究』4
西洋中世学会『西洋中世研究』4~知泉書館、2012年~ 西洋中世学会が毎年刊行する雑誌『西洋中世研究』のバックナンバーの紹介です。 第4号の構成は次の通りです。―――【特集】天使たちの中世<序文>池上俊一「天使たちの中世」<論文>稲垣良典「天使の存在論」池上俊一「天使の訪れ」金沢百枝「天使の肉体―天使イメージの変遷と天使崇敬―」山本成生「天上と地上のインターフェイス―奏音天使の学際的素描―」村松真理子「「天使のような貴婦人」の系譜―シチリア派、清新体派からベアトリーチェの誕生まで―」池上英洋「天使的イメージとルネサンス・ネオ・プラトニズム―レオナルドにみる錬金術とグノーシス主義―」【論文】杉山博昭「隠された実母―『モーセとエジプト王ファラオの聖史劇』に投影された社会的関心―」河野雄一「中世の継承者としてのエラスムス:1520年代の論争を通して」【講演】Lester K. Little, “Plague in the European Middle Ages”山本成生・後藤里菜「レスター・リトル氏講演会 報告と感想記」【新刊紹介】【彙報】赤江雄一ほか「2011年度若手支援セミナー報告記」伊藤博明「シンポジウム「中世とルネサンス―継続/断絶』要旨」――― 今号の特集は天使。池上先生による序文は収録論文の概観と天使研究の意義を指摘します。 稲垣論文は、哲学の観点から、トマス・アクィナス『神学大全』などの史料により天使の存在に関する議論をたどります(私には難解でした)。 池上俊一論文は、歴史学の観点から、種々の史料に基づきながら、天使の姿、役割の諸相を論じます。 金沢論文は美術の観点から、肉体を持たないはずの天使がいかに描かれてきたかをたどります。スフィンクスのような聖獣から有翼人像への移行、またケルビムとセラフィムが混同される図像など、興味深いです。 山本論文は、音楽の観点から、楽器を奏でる「奏楽天使」の図像分析を中心に、その役割を指摘します。 村松論文は、文学の観点から、ダンテの作品などを史料として、「天使のよう」と形容される貴婦人について論じます。 池上英洋論文はルネサンス芸術の観点から、グノーシス主義の受容から、君主が両性具有的に描かれる図像の分析を通して、完全性の表現が意図されていたことを指摘する興味深い論考。 杉山論文は、モーセを扱う聖史劇の分析から、モーセの実母が巧みに隠されていたことなどを指摘し、その効果・意義を指摘します。 河野論文は、先行研究において様々な位置づけをなされてきたエラスムスの諸著作の分析を通じて、カトリックだけでなく宗教改革者とも論争をしていたことを指摘し、その思想・立場の意義を論じます。 講演の部では、2012年3月4日開催の講演会における、Littleの(おそらく)講演原稿と、その報告・感想記を掲載。Little論考は中世ペストについて、先行研究のペスト論が誤解を招くこと(中世特有と論じられがちだったが、実際には18世紀まで断続的に続いたことを指摘)、従来重視されてこなかった初期中世のペストへの当時の対応、そして近現代におけるペスト菌の発見などを概観し、ペスト研究を再考します。山本・後藤両先生の報告・感想記は、当該講演会とリトル報告の状況・概要を明快にまとめています。 新刊紹介は39冊の欧語文献を紹介。赤江先生が紹介しているBynum, Christian MaterialityとŞenocak, The Poor and the Perfectの2冊が気になります。また、記事は書けていませんが、Jacques Berlioz, Pascal Collomb et Marie Anne Polo de Beaulieu (dir.), Le tonnerre des exemples. Exempla et mediation culturelle dans l'Occident medieval, Presses Universitaires de Rennes, 2010でも大きく取り上げられている、Ci nous ditという史料について紹介する文献も今号では紹介されていて(小林先生による紹介)、こちらも気になりました。 彙報は、第4回シンポジウムと、ポスターセッションなどが行われた2011年度若手支援セミナーの概要報告の2本です。(2025.04.09再読)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.07.12
コメント(0)
-
V. Smirnova, M. A. Polo de Beaulieu and J. Berlioz (eds.), The Art of Cistercian Persuasion in the Middle Ages and Beyound
Victoria Smirnova, Marie Anne Polo de Beaulieu and Jacques Berlioz (eds.), The Art of Cistercian Persuasion in the Middle Ages and Beyound. Caesarius of Heisterbach's Dialogus on Miracles and its Reception, Leiden-Boston, Brill, 2015 編者の1人、ヴィクトリア・スミルノヴァは、2006年にモスクワ大学で博士号を取得し、近年はバイエルン州立図書館研究員などをつとめている研究者で、本書の主題となるシトー会士ハイステルバハのカエサリウス(c.1180-1240)による著名な例話集『奇跡についての対話』についての論考を多数発表しています。(この例話集に関して、本ブログでは最近、次の書籍の紹介を記事にしました。ヘルマン・ヘッセ(林部圭一訳)『ヘッセの中世説話集』白水社、1994年) またマリ・アンヌ・ポロ・ド・ボーリューとジャック・ベルリオーズはフランスで中世例話研究を牽引する研究者で、共編著も多いです。本ブログでも(十分な紹介はできていませんが)Jacques Berlioz et Marie Anne Polo de Beaulieu (dir.), L'animal exemplaire au Moyen Age ― Ve - XVe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 1999の記事を掲載しています。 本書は、こうした中世例話研究を代表する3名の編による、『奇跡についての対話』からうかがえるシトー会士による説得技法や同作品の後世の受容などについて論じる論文集です。 本書の構成は次のとおりです(拙訳)。―――謝辞図版リスト引用写本リスト略号寄稿者一覧序論(Marie Anne Polo de Beaulieu, Victoria Smirnova and Jacques Berlioz)第1部 シトー会士による「信じさせる」(Faire Croire)技術 第1章 聞くことを愛した修道士―カエサリウス理解の試み(Brian Patrick McGuire)第2部 シトー会士のレトリックを探して 第2章 どの程度12世紀のシトー会士は修辞学概論に関心があったのか(Anne-Marie Turcan-Verkerk) 第3章 レトリックの規則に従う(あるいは従わない?)ハイステルバハのカエサリウス(Victoria Smirnova) 第4章 宗教的説得における視覚的想像―ハイステルバハのカエサリウス『奇跡についての対話』における心的イメージ(Marie Formarier)第3部 物語神学の洗練と普及 第5章 ハイステルバハのカエサリウス『奇跡についての対話』における物語神学(Victoria Smirnova) 第6章 例話と歴史記述:トロワ=フォンテーヌのアルベリックによるカエサリウス『奇跡についての対話』の読み(Stefano Mula)第4部 ドミニコ会説教活動におけるシトー会の遺産の使用 第7章 新しい「権威」の創造:ドミニコ会士リエージュのアーノルドによる『奇跡についての対話』の読みと再記述(Elisa Brilli) 第8章 『奇跡についての対話』:小ジャン・ゴビ『天の階梯』にとっての着想の最初の典拠か(Marie Anne Polo de Beaulieu)第5部 翻訳される『奇跡についての対話』 第9章 デーフェンテルの以前の市長について:Derick van den Wiel、「新しい信仰」、『奇跡についての対話』の中世オランダ語訳(Jasmin Margarete Hlatky) 第10章 ヨハネス・ハルトリープによる15世紀ドイツ語訳からみる『奇跡についての対話』(Elena Koroleva) 第11章 ニュー・スペイン(1570-1770年)におけるハイステルバハのカエサリウス(Danièle Dehouve)第6部 ラウンドテーブル:「信じさせる。物語と説得:持続性、再構成、断絶、13-21世紀 第12章 カエサリウスからチョン・ミョンソク(鄭明析)へ:メシアについての韓国の例話(Nathalie Luca) 第13章 例話の読み/教訓(Pierre-Anthoine Fabre)総索引――― 序論は本書の問題関心を提示した後、カエサリウスの略歴と『奇跡についての対話』の概要と受容、近年の歴史研究の動向を紹介します。ここでは、カエサリウスについて、肖像が例話集に残された唯一の著者だと指摘されます(p.11)。 第1章は自身の研究歴も交えながらカエサリウスの説得術を論じます。ここでは、各地の代表が集まるシトー会総会が様々な物語の交換の機会になったことを指摘し、現代の学会のシンポジウム集会などになぞらえているところが面白いです(学会でも、フォーマルな発表と、コーヒーや食事の際の情報交換がなされる)。 第2章はシトー会に修辞学の実践について論じ、第3章は『奇跡についての対話』序文からカエサリウスの修辞意識を確認した後にいくつかの例話から様々な修辞の事例を分析します。第5章はアウグスティヌスの理論を概観した後に『奇跡についての対話』のレプラ患者の例話を事例として心的イメージを分析。 第5章は『奇跡についての対話』を典礼(主に聖体)の観点から、他史料と比較しつつ分析し、第6章はトロワ=フォンテーヌのアルベリックの歴史叙述を史料とし、彼がその典拠としていかに『奇跡についての対話』を利用したかを論じます。 第7章はリエージュのアーノルド『アルファベット順物語集成』を、第8章は小ジャン・ゴビ『天国の階梯』を主要史料とし、それぞれがどの程度カエサリウスを典拠・権威としていたかを分析します。いずれも、カエサリウスだけでなく、その他の典拠についても分析しており、私が勉強を進めているジャック・ド・ヴィトリの利用についても言及があるため、個人的に特に関心をもって読みました。 第5部(第9章から第11章)は『奇跡についての対話』の翻訳について。今回は時間の都合もあり読めていませんが、ニュー・スペインの事例など面白そうです。 第12章は韓国の事例紹介、第13章は見開き2頁のみですが第12章と本書全体の関連から興味深いと思われる3つの側面を指摘します。 私は学生時分に例話について勉強していて、『奇跡についての対話』について扱う邦語文献(上述『ヘッセの中世説話集』の記事を参照)も読んでいましたが、欧語の専門論文を読むのはほぼ初めてで、あらためて勉強になりました。(2025.03.28読了)・西洋史関連(洋書)一覧へ
2025.07.06
コメント(0)
-
エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ『ラングドックの歴史』
エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ(和田愛子訳)『ラングドックの歴史』~白水社文庫クセジュ、1994年~(Emmanuel le Roy Ladurie, Histoire du Languedoc, Presses Universitaires de France, 1962) 南仏で話されていた「オック語」の地域を意味する、ラングドック地方の、旧石器時代から現代(20世紀)までの通史です。 著者のエマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ(1929-2023)は、アナール学派第3世代に属する歴史家です。多くの著作があり、邦訳もありますが、本ブログでは、次の著作を紹介したことがあります。・E・ル=ロワ=ラデュリ(樺山紘一他訳)『新しい歴史―歴史人類学への道―[新版]』藤原書店、1991年・エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ(稲垣文雄訳)『気候の歴史』藤原書店、2000年・エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ(稲垣文雄訳)『気候と人間の歴史・入門【中世から現代まで】』藤原書店、2009年・エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ(稲垣文雄訳)『気候と人間の歴史I―猛暑と氷河 13世紀から18世紀』藤原書店、2019年 著名な『モンタイユー』は過去に読んでいますが記事を書けていません。 原著刊行が1962年ということで、著者にとって最初期の著作です。 本書の構成は次のとおりです。―――第1章 起源第2章 中世の最盛期第3章 ペスト、戦争そして危機第4章 近代の最盛期第5章 大不況第6章 成長第7章 二十世紀の諸問題訳者あとがき参考文献――― 本書の目的や意図などの記述はなく、いきなり本論から始まります。 各章の紹介は省略しますが、興味深かった点をいくつかメモしておきます。 まず、第2章からは、ラングドック地方で二元論のカタリ派が流行した理由として、当地では、徹底的な修道院改革が欠如していた(45頁)ことを指摘しています。 第4章では、宗教改革後にカトリックとプロテスタントの間に生じた宗教戦争に関して、トゥールーズではカトリックの一分派が残虐行為に嫌悪感を示したこと、またカトリックでありながら役職保持のため改革派と同盟を結び、改革派の長に祭り上げられた人物の事例などが紹介されていて、興味深いです(カトリックとプロテスタントの対立という単純な構図だけでは読み解けないことがあるという戒めのように捉えて読みました)。 その他、パリやフランスという国全体との関わりでのラングドックの立ち位置が描かれています。 かなり流し読みになってしましましたが、150頁程度の読みやすい分量でもあり、ラングドック地方の事例研究としては出発点になりえる1冊と思われます。(2025.03.27読了)・西洋史関連(邦訳書)一覧へ
2025.07.05
コメント(0)
-

西洋中世学会『西洋中世研究』3
西洋中世学会『西洋中世研究』3~知泉書館、2011年~ 西洋中世学会が毎年刊行する雑誌です。 3年ぶりにバックナンバーの紹介です(前回、第2号の紹介は2022年4月30日でした)。 第3号の構成は次の通りです。―――【特集】イメージを読む中世<序文>松田隆美「イメージを読む中世」<論文>宮内ふじ乃「ベアトゥス写本におけるテクストとイメージ生成―黙示録8章1-5節の挿絵をめぐって―」福井千春「変身する戦うヤコブ像」木俣元一「『ホルトゥス・デリキアールム』における「神殿の垂れ幕」再考―イメージの可視性/不可視性を読む―」甲田芳樹「美徳の装い―ドイツ中世の教育文学におけるイメージとハビトゥス―」横山安由美「書かれざるテクスト―アンジェの黙示録タピスリーにおける無文字の「吹き流し」について―」松田隆美「テクストを見るディヴォーション―BL MS Additional 37049におけるイメージの機能―」【論文】奈良澤由美「マルセイユの古代末期から初期中世の教会遺構―祭壇、聖遺物、祭祀空間について―」黒岩三恵「聖トマス・アクィナスと修道女―ポワシー、サン=ルイ王立女子修道院長マリー・ド・クレルモンとトマス崇敬―」辻内宣博「14世紀における時間と魂の関係―オッカムとビュリダン―」【新刊紹介】【彙報】山本芳久「西洋中世学会第三回シンポジウム報告「ヨーロッパとイスラーム:文化の翻訳」」山本成生「2010年度若手支援セミナー報告記」朝治啓三「西洋中世学会と環太平洋中世学会の交流協定締結について」――― 簡潔に特集の意義を述べる序文に続く宮内論文は、黙示録注解写本における「天の沈黙」という図像表現が困難と思われるテーマがいかに描かれてきたか、その主要な描き方の分類と影響関係などを論じる論考。 福井論文は、従来敬虔な姿として表現された聖ヤコブが「戦う像」に変身し、その後新大陸に至るまでどのような変遷をたどったかを描きます。 木俣論文は既に先行研究で分析されているある写本図像の再解釈により、より深い読みを提示します。 香田論文は文学の視点から美徳の描かれたかを論じます。ここでは、主人公の失墜から宗教的徳操へ至る過程を象徴する「衣服」の機能について論じられている部分が興味深く、発表年は後になりますが、同じく文学作品における衣服の機能を論じた森下勇矢「道化服の機能―『パルチヴァール』にみる愚の象徴―」『西洋中世研究』16、2024年を連想しながら読みました。 横山論文はマンガの吹き出しの先駆的存在である、写本の中の人物のセリフや説明を描く「吹き流し」について、特に無文字の「吹き流し」に注目し、その機能を分析する興味深い論考。 松田論文は様々な作品を収めたあるミセラニー写本の図像分析から、図像が果たす複数の機能を分類し論じます。 奈良澤論文は2003年の発掘調査で発見された教会遺構に関する報告。 黒岩論文はある写本に描かれた女子修道院長の図像とトマス・アクィナスの図像の関係の分析を中心に、同修道院の位置づけやドミニコ図像の変遷を論じます。 辻内論文は「魂が存在しない場合に時間は存在するのかしないのか」という問題に対して、アヴェロエスの説を出発点として、人間の精神に全面的に依存するという立場により近いオッカムと、時間の存在は人間の精神に全く依存しないという立場により近いビュリダンというそれぞれの思想の相違を明らかにするとともに、この相違は時間に関する見解だけでなく、両者の哲学一般に通じることを指摘しており、哲学分野の論文はなかなか理解が追い付かないことが多いですが、本稿は具体例も挙げながら明快な議論の流れで、大変興味深く読みました。 新刊紹介では52の研究書が紹介されます。興味深い著作が多いですが、中でも、河原温先生から、ミシェル・モラの著名な『中世の貧民』(1978年。邦訳なし)から30年を経て、新たな中世の「慈善」の歴史をまとめたと評されるJ. W. Brodman, Charity and Religion in Medieval Europe, 2009が特に気になりました。モラの著作も入手したものの未読なので、勉強せねば…。 彙報は3本。第3回シンポジウム報告は図版も含めて、当該シンポジウムの概要が示されます。 2010年度若手支援セミナーは「文書館で西洋中世研究」というテーマで開催されており、山本先生による概要紹介の後、2名の感想記が掲載されています。 末尾はアメリカ合衆国の環太平洋中世学会(MAP)との交流協定の概要と締結の報告です。(2025.03.22再読)・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2025.06.29
コメント(0)
-

有栖川有栖『砂男』
有栖川有栖『砂男』~文春文庫、2025年~ 江神二郎&学生アリスシリーズの未収録短編2編、火村英生&作家アリスシリーズの未収録短編2編に加え、ノンシリーズの短編2編と、計6編の作品が収録された短編集です。(本ブログ「あ行の作家一覧」の有栖川有栖さんの項目では、便宜的に本書は火村シリーズのところに掲載しています。) それでは、簡単にそれぞれの内容紹介と感想を。―――「女か猫か」泊まるといけないと言われていた離れに肝試しで泊まることになった学生。密室状況の中、翌朝、彼の顔には傷ができていた。彼に思いを寄せる女性バンド3人組の仲は不穏になり始めるが…。「推理研VSパズル研」ある日パズル研メンバーと食事をともにしたモチと信長は、一つのパズルを出題される。頭を悩ませるが、江神部長の助けを借り、奇妙なパズルの設定自体を成立させる状況にまで推理を広げていくことになる。「ミステリ作家とその弟子」スランプ気味の作家が、弟子を志望する青年を家事手伝いも兼ねて雇い、ミステリ執筆の講義を行う。昔話に創造的な突っ込みを入れよ、との課題に青年が出した答えを受け、一緒に物語を膨らませていくが…。「海より深い川」口論する男女の声を聞いていた隣人は、「海より深い川」という気になる言葉を聞いていた。別の場所で同様の言葉を聞いたという有栖川の証言を聞いた火村の推理とは。「砂男」子どもたちの間に広まりつつある都市伝説「砂男」について研究を進めていた社会学者が何者かに殺された。被害者には、砂がかけられていて…。現場近くにいた彼の教え子や、なぞの男の思惑とは…。「小さな謎、解きます」商店街で探偵事務所を開いた男に持ち込まれる小さな謎たち。サークルで出されたミステリの答えや、ある音楽を不気味に思い始めた女性の謎とは。――― 冒頭2編は江神シリーズ。どちらも日常の謎系で好みでした。 2つのシリーズに間に置かれた「ミステリ作家とその弟子」は、『作家小説』などいくつかの作品をほうふつとさせるような、ユーモアあふれる作品…だけにとどまらないのにやられました。 第4~5話は火村シリーズ。どちらも社会情勢の変化で、短編集などに収録できなかった作品とのこと。どちらも興味深いですが、都市伝説を扱う「砂男」がより好みの作品でした。 最終話はほっこりできる味わいで、好みの物語でした。(2025.03.15読了)・あ行の作家一覧へ
2025.06.28
コメント(0)
-

京極夏彦『了巷説百物語』
京極夏彦『了巷説百物語』~角川書店、2024年~ 「巷説百物語」シリーズ第7弾にして最終巻。 これまでのシリーズで仕掛けに関わってきたほぼすべての人物が登場する、シリーズ最大の仕掛けです。 本作では、嘘を見抜く洞観屋の藤兵衛さん、そして拝み屋の中禪寺洲齋さんも活躍します。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。――― 世の中をよくするためと信念を持つ山崎は、藤兵衛に、改革を進める水野の邪魔をする化け物遣いたちの正体を見破るように依頼を持ち掛ける。遠くの音も察する源助、どこにでも溶け込めるお玉の2人の助力を得て、化け物遣いに探りを入れようとする藤兵衛たちを待ち受けるのは。 皿屋敷の怪異が伝わる空家での、おぎんたちとの出会い。(「於菊蟲」) 柳屋での、山岡百介との出会い。(「柳婆」) なんらかの事情で何人もの娘が命を落としている櫻木村の事件への関わり…このあたりから、もはや敵・味方の区別はなくなっていき、藤兵衛は事触れの治平たちと一部協力をしていくことになる。(「累」) 後日、大坂の一味から、ある人物を守るように依頼を受けた藤兵衛は、一方で、水野の周囲にいる福乃屋から、怪異が頻発する中、拝み屋の中禪寺の言った言葉が本当なのか見定めてほしいと依頼を受ける。福乃屋に雇われていると思われる、人を平気で殺す七福連の動きも激しくなっていき…。(「葛乃葉」) そして、全ての事件の裏にいる人物との戦いへと発展していく。(「手洗鬼」「野宿火」)――― 後日譚「百物語」も含め、7章からなりますが、これまでのシリーズのような連作短編(連作長編?)という趣が薄れ、全体でひとつの長編のような味わいです。 本文1149頁ととんでもない厚さですが、面白さも抜群です。 物語は藤兵衛さんの視点で展開していきます。化け物遣いたちは敵なのか味方なのか。依頼人の背後にいる水野は敵なのか味方なのか。敵・味方との立場が不透明になりながらも、藤兵衛さんは自身の思いにしたがって行動していきます。 本作では、中禪寺洲齋さんの活躍も見どころです。これは味わい深いです。 シリーズ初期の作品の再読から始め、未読だった作品も一気に読みましたが、シリーズ全体を通して素敵な読書体験でした。(2025.05.29読了)・か行の作家一覧へ
2025.06.22
コメント(0)
-

京極夏彦『遠巷説百物語』
京極夏彦『遠巷説百物語』~角川書店、2021年~ 「巷説百物語」シリーズ第6弾。 『前巷説百物語』などで活躍した長耳の仲蔵さん、『西巷説百物語』で活躍した献残屋にして、またの二つ名を亡者の柳次さんのお二人が主に仕掛けを施す物語です。 舞台は盛岡藩の遠野。物語は、主に城主南部義晋に命を受けて巷のはなしを聞きつける浪人、宇夫方祥五郎さんの視点で進みます。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「歯黒べったり」南部家御用達の御菓子司から座敷童が出て行ったという噂が流れていたその頃、山で歯が真っ黒でのっぺらぼうの女性が目撃されるという噂も広まっていた。勘定吟味改役の大久保平十郎も、その女を退治し損ねたと噂されていて…。「磯撫」遠野の米は豊作だったが、なぜかある一人の男が一手に取り扱うというお触れが出され、米商人や漁師たちの怒りは爆発寸前だった。その頃、巨大な魚が川を上るという噂も流れていた。町奉行是川五郎左衛門は、米問題に大いに頭を悩ましていたが…。「波山」鳳凰屋周辺で、上半身が焼かれた遺体が発見されるという事件が複数発生していた。事件の頃には、ばさばさという音がしていたという。町廻役同心の高柳剣十郎は、事件が怪異のしわざの場合に備えてと、鉄砲をあてがわれていたが、全く理屈が理解できずにいて…。「鬼熊」夜中に、行列になって歩く雪女を見たと震える男を介抱することになった医者の田荘洪庵。一方、その頃、巨大な熊が出没しているという噂が流れていて…。「恙虫」勘定方全戸が閉鎖された。中では複数の男が不審死を遂げ、間もなく感染病と判断された。ついには、勘定方全戸を焼き払うという暴挙がなされようという流れになるが…。「出世螺」前の事件の仇討ちを仲蔵たちに依頼した祥五郎。一方その頃、祥五郎にはなしを売っていた乙蔵は、金塊を掘り出すことに成功していた。しかし、乙蔵を狙う複数の勢力に、祥五郎も襲われてしまい…。――― シリーズの中では、仲蔵さん、柳次さんの2人以外がほぼ登場しないということで、『西巷説百物語』同様、読み始めるまではうまくなじめるか不安でしたが、こちらも杞憂に終わりました。 まず主人公の祥五郎さんの人柄が素敵です。 仲蔵さんたちの仕掛けも、優しさがあって好みでした。 過去の作品とのリンクや、大物(の敵)も現れ、次作にして最終作『了巷説百物語』も楽しみになる1冊です。(2025.04.29読了)・か行の作家一覧へ
2025.06.21
コメント(0)
-

京極夏彦『西巷説百物語』
京極夏彦『西巷説百物語』~角川書店、2010年~ 「巷説百物語」シリーズ第5弾。 『前巷説百物語』の後、大坂に戻った削掛(あるいは靄舟)の林蔵さんが主人公です。 献残屋にして、またの二つ名を亡者の柳次さん、どんな女にでも化けるお龍さんたちとともに、一文字屋仁蔵からの仕事を請け負う林蔵さんは、どのような仕掛けをしていくのか。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――「桂男」娘に縁談をもちかけてきた回船問屋の次男坊には、同様の手口で店をつぶしていくという悪評があった。悪評を聞いてもなお、かたくなに縁談を進めようとする舟問屋の旦那に、大番頭は珍しく意見をするが…。「遺言幽霊 水乞幽霊」倒れて、三カ月生死の間を彷徨っていたと聞かされた男は、けんかした父親が亡くなったと知らされる。一方、店から三千両が盗まれた事件はいまだ尾を引いていて…。「鍛冶が嬶」大切にしていた妻がある日から笑わなくなった。名刀を手掛ける鍛冶師は一文字屋に相談を持ち掛ける。自身の鍛冶場に伝わる伝説から、妻が狼にかわってしまったのではないかと男は訴えるが…。「夜楽屋」自身が演じる人形の首が壊れていた…。荒れた楽屋は、先代が亡くなった事件を彷彿とさせるような状況だった。男は、有名な人形師に人形の修復を依頼することになるが…。「溝出」10年前。村を襲った疫病で、多くの村人が亡くなり、地獄絵図のような状況の中、村に戻った男は遺体を山へ運び焼き払った。村のために動き、生き残った村人から感謝を受けていた男だったが、幽霊が出るという噂が広まる中、供養をしようという訴えには耳を貸そうとせず…。「豆貍」おいしい酒で有名な酒屋の主人は、ある事件をきっかけに子供を恐れるようになっていた。その店で、帳簿が合わないことが多発していた。話を聞いた人からは、豆貍―子供のしたことでは、との助言を受けるが…。「野狐」林蔵と又市が大坂を離れることになったきっかけの事件の真相とは。――― 又市さんがほとんど登場しないスピンオフ作品のようなかっこうなので、楽しめるか不安に思っていましたが杞憂に終わりました。こちらも面白かったです。 林蔵さんが主役で、仕掛けを施していくのですが、(以下文字色反転)その仕掛けの方向が、相手の出方に委ねられる(ここまで)のも興味深いです。又市さんの仕掛けよりも怖く感じました。 一話、二話で、なんとなく趣向が見えてきたと思えば、第三話でまた思わぬ展開になったりと、展開のバリエーションも豊富です。(2025.04.13読了)・か行の作家一覧へ
2025.06.15
コメント(0)
全2103件 (2103件中 1-50件目)
-
-

- 読書備忘録
- 死んだ山田と教室 金子 玲介
- (2025-11-27 17:02:34)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『どうやら腹黒王子の独占欲を煽って…
- (2025-11-29 00:00:13)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- ワイルド7第246回「魔像の十字路」#59
- (2025-11-29 07:22:37)
-








