2009年03月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
はたして同じものなのか、違うものなのか!?!?PART2
昨日は「ロケット」と「ミサイル」の違いを探ってみたのですが・・・。どうも同じもののような気がしてなりません。わが国のH2aロケットは、・・・今確かにロケットと書きましたが・・・使い方次第ではいとも簡単にミサイルに化けることが可能なしろものだと思えるのです。ただ、先端部分に何を搭載しようとしているのか、搭載しようとしているものの開発も含めて、他国にすべてをオープンにしているかいないかの一点で、ミサイルではなくロケットと言えるのだと思うのですが、皆さんはいかがお考えになるでしょうか?H2aロケットは過去何回か打ち上げられてきたのですが、一度打ち上げたけれども予定の軌道に乗せることができずに、地上からの指令で爆破させたということがあったと思います。これはそのまま放置しておくと制御不能に陥り、やがて地上に落下するときの危険を回避するために、「ロケット」にはこの種の自爆装置を必ず組み込んでおくものなのだということを 科学技術評論化がテレビで言っていたように記憶しています。・・・う~ん、そうか、わが国のH2aロケットは、ロケットといえるのだな。では、かの国が打ち上げると世界の国々に事前表明しているロケットは、あらかじめ前もって打ち上げの事実を公表していることだし、頭に「光明星2号」を載せて打ち上げるといっているので、やはりロケットなんですね。でも「光明星2号」って、名前は明るくてもいったいどんなものなのかまったく公表されていませんから、そして開発段階から全くオープンではありませんから暗いままです。そして、もし打ち上げに失敗したときは、地上からの指示で爆破させる仕組みが搭載されているのだろうかと思うと、このロケットはそれでも「ロケット」であるのだろうかと心細くなるのです。まぁ、余計な事は考えずに、かの国のロケット打ち上げ技術の高さなるものを信頼し、「光明星2号」が無事地球の衛星軌道に到達して、文字通り明るく光輝いてくれることを望むばかりです。◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月31日
-
はたして同じものなのか、違うものなのか??
一見似ているようだけれど、違うもの。・・・でもよくよく考えてみると、同じもの。「ロケット」と「ミサイル」ちょっと調べてみました。ロケットは軍事兵器ではなく、高温高圧の燃焼ガスを噴出させることによって得られる推力により、空間を飛翔するための装置を指すのに対して、ミサイルはまず第一に軍事兵器であり、攻撃する目標まで自らを誘導する装置と、自らを運ぶ推進装置を持った飛行装置であって、この推進装置として使用されるのが、ロケットということになるらしいのです。・・・!?!? 分かったようで分からない、もっともなようでそうでない、ちょっと怪しい言い回しのようにお感じになられませんか?ロケットにだって、当然自らと運搬物を目的地までに運ぶための制御装置があるでしょう。同じ誘導装置と推進装置をもった飛行物体ということになるじゃないか。では目的地が、地球の衛星軌道であったり安全な航海の海上であれば、ロケットといえるのかな?そんな解釈が通用するなら、ミサイルをあらかじめ目標まで届かないようにしておいて、公海上に落下させれば、これはロケットを飛ばしたと言えることになりますよ。あらかじめ世界中に○月○日~○月○日の間に、ロケット(ミサイル)を発射しますと案内しておけば、衛星打ち上げのためのロケット発射実験であるといえるの?世界に誇る日本のH2aロケットは、先端部に"まいど2号"などの衛星を載せないで、もっと他の怪しげで危険な匂いのするものを搭載することを前提にして、目的地を衛星軌道ではなくもっと短くして、安全な航海上に落下させるように打ち上げることだってできるはずだと思うのですが、その場合でも事前に案内をしておけば、ロケット発射実験になるのだろうか?・・・はたして同じものなのか、違うものなのか、考えれば考えるほど分かりません。。。◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月30日
-
トキの気持ちが分かりません
新潟県の有名な民謡に「佐渡おけさ」がありますが、確かこのような一節があったでしょう。 佐渡へ佐渡へと草木もなびくヨ 佐渡は居よいか住みよいか 來いと云ふたとて行かりよか佐渡へ 佐渡は四十九里波の上ところが、その佐渡より本土の方がやはり住みよいのか、はたまたオス鳥に魅力がないのか、佐渡で放鳥されたトキのメス鳥の中で残っていた最後の一羽が、28日新潟市内で確認されたという新聞記事を読みました。これで放鳥されたトキの内、佐渡にはオスばかり4羽、本土にはメスばかり4羽ということになり、今春の自然繁殖が困難になったというではありませんか。。。動物の中には、雌雄別々の群れをつくり、繁殖期になると群れどうし交わるという種類もいるようですが、鳥類は一緒に群れを作るように記憶しているのですが、トキも同じでしょ?やはりずっと人の手により育てられてきたということが、影響しているのでしょうか?しかし、このメス鳥たちは「四十九里」もの波の上を飛び越えるに耐える体力を持つ優秀な個体に違いありませんから、十分繁殖力があると思うのです。問題なのは、オス鳥たちです。いったい何をやっているのかと言いたい!思い切って海を渡る度胸のあるヤツは一羽もいないというのか。渡りきってしまえば、1対4の選り取りみどり、これを天国と言わずして何と言う、そんなシチュエーションが待っているのに・・・(笑!◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月29日
-
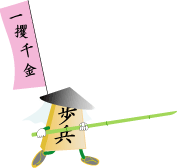
そばの食べ方
[PART1]そばが今のように細長く切られて食べられるようになったのは、以外に新しくて、江戸時代のはじめごろ。新しい食べ物"そば切り"が、当時の江戸で大流行したそうです。これに関連して江戸っ子気質をよく表しているたとえ話を本で読みました。これが大変面白い!!威勢よく暖簾をかきわけて入ってきた男が、「もりを一枚、急いどくれっ!」って注文する。蕎麦屋の主(あるじ)も心得たもので、さっと出す。ずるずる、ずるずる、ずるずるっ、ずるっと三口半でそばをすすり終えると、「勘定はここに置いとくぜぃ!」って言葉を残してさっと表へ飛び出していった。当時の江戸っ子はせっかちで、見てくれのかっこよさ、気風のよさが身上で、ゆっくりしたのが性に合わない。でもそれがために痛い目に合うってこともずいぶんあったようです。長屋のご隠居さんが、最後に本音を言って愚痴ったという落語の噺、ご存知ですよね。これも負けず劣らず面白い!臨終まぎわのご隠居に何か言い残しておくことはないか、と問いただしたら「最後に一度でいいから、つゆをたっぷりつけて蕎麦を食いたかった・・・」そばの食べ方は人それぞれ、その人がおいしいと思う食べ方が一番おいしいのではないでしょうか。ちなみに私は、たっぷりとつゆをつけて食べる派です。[PART2]そばにたっぷりとつゆをつけて食べる派をハッキリと宣言した私としましては、甘んじてご批判を受ける覚悟はできております。しかも、つゆは甘めの濃いめが好きなのでございますよ。(うっ!・・・言っちゃった!!)なんてヤツだ!そんなやぼったいそばの食い方あるものか!?そんなにたっぷりつゆをつけたら、そばの香りが死んじまわぁ~!!俺なんざぁ~、最初のひとすすりはつゆなしでぇ~!!そばは噛むもんじゃねぇ!呑み込むもんだ!のどで味わうものですよ!!・・・たいそうキビシイお声が聞こえてまいりますなぁ~。。。確かにPART1で話題にした江戸っ子のいなせなお兄さん、かっこいいですよねぇ~。「勘定ここに置いとくぜぃ!」・・って、一度は言ってみたいセリフですよね。でも、わたしの場合には、「あっ!お客さん!お客さん!!これじゃ勘定足りませよん!!」・・ってなことになりそうで、二の足を踏んでしまうのです。[PART3] PART2で話題にしたごとく、ご批判がかくもあまたにあると言うことは、やはりそばの先にほんの少しつけてすする派が、正統派と言えるのでしょうか?つゆをたっぷりつけて食べる派をハッキリ宣言してはみたものの、雲行きの悪さに、少なからず不安にかられるのであります。しかし、忽然と思い出したのであります。強い見方がいらっしゃったことを!将棋を指さない人でも、大山康晴十五世名人のお名前だけは、お聞きになったことはあるでしょう。そう!この不世不出の大名人が、実はつゆをたっぷりつけて食べる派だったという逸話を かって将棋雑誌で読んだことがありました。もう30数年ぐらいも前のことになろうかと思います。大名人にもようやく陰りが忍び寄ってきて、中原さんにその地位を明け渡さんとしていた頃に書かれた記事であったと記憶しています。話はこうです。そこから更にさかのぼること10数年、名人の全盛期のころの逸話のひとつ。名人と当時A級八段(確か後の将棋連盟会長丸田祐三九段であったと記憶しているのですが・・・)が、若い記者と連れ立って蕎麦屋に立ち寄った。そばを注文して注文のそばが出されるまで、丸田八段がそばの正統派の食べ方について、若い記者に講釈をしたというのです。名人は目を細めてその話に聞き入っていたそうですが、そばが来て食べる段になると、これ見よがしに丸田八段の目の前で、そばにたっぷりとつゆをつけて口に運んだ・・・というのです。棋士は商売柄自己主張が大変に強く、相手に迎合することを嫌う。盤上はもちろんのこと盤外でもいったん言い出したらあとに退かない・・・こういった棋士気質について書かれた記事だったと記憶しているのですが、さすがは大名人、並の人には真似のできないことですよね。はたして本当に大山名人は、たっぷりとつゆをつけて食べる派だったのでしょうか?残念なことに故人になられて久しいので、お聞きすることもかないません。これもまた私ごときにはかなわぬことですが、森内名人と羽生四冠にもお聞きしてみたいですね。でも結果は分かっています。一方がすする派なら、もう一方はたっぷり派に違いありません。ちなみに私も将棋を指しますが、悲しいことに・・・・頭に金を置かれるまで自玉の詰みに気がつかない・・・といったレベルなのですよ。金底の歩は岩よりも固いそうですが、玉頭の金は岩よりも重かったのであります・・・(涙![PART4] 日本を代表する明治の文豪といえば、漱石と鴎外ということになりましょう。今回はその漱石より題材をとってみたいと思うのです。PART3では、大名人を無理やり引っ張り出して、つゆをたっぷりつけて食べる派にしてしまった手前、つゆをほんの少しつけてすする派にも著名人を紹介しなければ、片手落ちというものでしょう。そこで漱石の登場となります。いや正確には漱石の著した「猫」、そう「我輩は猫である」の迷亭先生にご登場いただこうと思うのです。高校生の頃は、漱石と鴎外の作品を意味もよく分からないままに無理やり読まされたものです。・・・そのわりには、よく覚えていたものですなぁ~。迷亭先生だったかクシャミ先生だったか記憶が定かでなっかたので、図書館へ出向いて調べてまいりました。ありました!ありました!!迷亭先生がナントそばの食い方の講釈をしているではありませんか。「この長いやつへツユを三分一つけて、一口に飲んでしまうんだね。噛んじゃいけない。噛んじゃ蕎麦の味がなくなる。つるつると咽喉を滑り込むところがねうちだよ。」「奥さん、ざるは大抵三口半か四口で食うんですね。それより手数をかけちゃ旨くくえませんよ。」(仮名づかいは読みやすいように変えてあります)はたして漱石は、すする派だったのでしょうか?それともたっぷり派だったのでしょうか?・・・そして鴎外は?でも漱石は、若い時から胃潰瘍の持病持ちであったというではありませんか。さすれば、たっぷりとつゆをつけて食べる派の私としましては、そばといえどもよく噛んで食するにこしたことはないと思うのであります。[PART5]我ながらよくもまぁ~取るに足らないことを話題にして、4回(今回も入れると5回)もつまらぬことを書いたものだと思います。読者の皆さんは、そばの食い方なんぞどうでもいいだろうよ・・・と、さぞかしあきれかえっておられることでしょうね。この調子だと、とどまるところを知らないまま際限なくこのテーマで書き続けそうな気がしますので、いったんこのテーマに関しては筆をおくことに致しましょう。ただ、そば切りとしてそばが一般大衆に広く食べられるようになった江戸時代の初めより今日にいたるまで、結論が得られぬまま論じられてきたという一点だけは、間違いのないことであります。さしずめ、うまいものはうまく食いたいという、我がまま極まりない人間のなせる業・・・とでも言葉を濁して、たっぷりとつゆをつけて食べる派の私としましての結論とさせていただきましょう。◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月28日
-
春を迎えるということ
毎年この時期に「シマッタ!」と思い知らされること車のタイヤの入れ替え当地は雪国でありますので、当然のことながら冬季間はスノータイヤを履きます。12月初旬から年が明けて3月中・下旬まで、一度装着したものは取り替えるのが面倒なので、ずっとスノータイヤで走ることになります。近年はいわゆる暖冬と呼ばれる年が続き、今年も除雪を必要とした降雪は2回きり、それもその後数日で解けてしまいましたから、冬タイヤが必要だったのは、その2回の降雪をはさむ数日だけでよかったということになるのです。2月下旬から3月上旬は、春のように暖かい陽気が続き、どうしよう、換えようか、もう少し様子を見ようか、さんざん思い悩んだあげく、一昨日ついにこらえきれなくなって、夏タイヤに履き替えました。・・・するとどうでしょう、一転昨日から気圧配置は冬型、日中吹雪くような荒れ模様。そこで冒頭の「シマッタ!」という羽目になるのです。そこで過去の日記を探ってみましたら、やはり3月のこの時分に同様な愚痴を綴っておりました。そうか、毎年毎年こういう繰り返しの中で春を迎えているのだな、こうやって知らず知らず年月が経ってゆくのだな・・・となんとも不思議な感情に浸っております。◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月27日
-

酒中の仙人
当店のそばは、呼んで字のごとく「酒そば」、そこでお酒にまつわることも話題にしたいと思うのです。李白、杜甫、白楽天と言えば中国唐代の三大詩人。今さら言うに及びません。読者の皆さんは、この三大詩人がいずれ劣らぬ大酒飲みであったということをご存知でしたでしょうか。確か高校生の時漢文の時間に、先生が授業もそっちのけで話してくれたことをいまだによく覚えています。当の漢文の先生もきっと酒好きだったのに違いないと、先生のことを懐かしく思い出だすのです。内容については、歴史と文学としての解釈に関係することなので、正確をきして読者にご案内しなければと思い、図書館へ行って調べ直してまいりました。どう読んで、どう解釈したらいいのか分からない漢字ばかり並べられた文をうんうん唸って読むつらさったら、二日酔いの朝なんて、つらさのうちに入りませんよ。そこで、「中国古典詩聚花 美酒と宴遊」(山之内正彦、成瀬哲生共著)に、三人の飲みっぷりについて詳しく書いてありましたので、しっかり勉強してまいりました。しかし、エライ先生がいらっしゃるものですね。三人の残した酒の歌から、飲みっぷりまで分かっちゃうなんて・・・私の好きな白楽天は、自ら酔吟先生と称して酒をこよなく愛した。比較的少量の酒で陶然と酔うことができたといいます。(私の場合は、当然と酔ってしまいますがね・・・!?!?)酔うことに心の平安を求めたのが白楽天。理性派といえましょう。杜甫はどちらかと言えば、分かりやすく言うところのヤケ酒派。飲めば飲むほど心の平安は向こうに追いやられてしまう。ヤケ酒を飲んでもなお酔いきれない。酔っぱらってもあくまでこの世の人であろうとしたのが、杜甫の飲み方。苦悩派とでも言うのでしょうか。これはこれで、また凡人にはまねのできない飲み方ですよね。李白は、杜甫がその飲みっぷりを仙人だと言ったぐらいですから、飲めば飲むほど世俗を忘れ、酔郷をさまようことができたというではありませんか。超越派というのでしょうね。(うらやましい・・・)李白の飲みっぷりを仙人のようだと杜甫が詠んだ詩「飲中八仙歌」より、李白の部分を抜粋してお届けします。 李 白 一 斗 詩 百 篇 長 安 市 上 酒 家 眠 天 子 呼 来 不 上 船 自 称 臣 是 酒 中 仙酒を一斗飲む間に詩を百篇作っちゃうというのもスゴイですけど、天子の招きがあっても、「酒中の仙人に何の御用でしょうか、もう少し酔っぱらっていたいのです。またにしてください。」ってカッコ良すぎますよね~!◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月26日
-
永遠の松井ファンではありますが・・・
子供のころは言わずとしれた野球少年(他に遊びがなかった・・・)、長じては恥ずかしながらメタボリックシンドロームを気にするプロ野球大好きオジサンを自称する私としましては、やはりWBCの結果について触れておかなければなりますまい。まずはV2達成おめでとう!そしてありがとう!やはり超一流選手は、そういう星のもとに生まれてきているのだなと思い知らされたイチローの10回の表の決勝タイムリーでありました。一番最後に一番うまいところを持っていっちゃった・・・・。しかしながら、試合終了後の彼のコメントを聞くと、予選本選を通して自分自身思ってもいなかった不振につぶれそうになったと告白しておりましたね。決勝打を放ったあの打席に立ったときのことを「本当は無の境地で望まなければならないのに、いろんなことを考えてしまった。ここで打てたら、俺そうとう(運を)持ってるなぁ~などと・・・」このコメントには、少々驚きました。今までの私の知るイチローなら、「あの時は、今までと同じ、無心でボックスに立ちました。配球からしてあのカウントであの玉しかない、ドンピシャ読み通り、センター前へ持っていけましたね・・・」こんなコメントを予想していたのですが。・・・う~む、イチロー! 私は、永遠の松井ファンを自称するオジサンでありますが、君のファンになりそうです。◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月25日
-

月明蕎麦花如雪
今日は、私の好きな漢詩を紹介させてください。 月 独 村 霜 明 出 南 草 蕎 門 村 蒼 村 麦 前 北 蒼 花 望 行 蟲 夜 如 野 人 切 雪 田 絶 切 最後の節は、「月明らかにして蕎麦(きょうばく)花雪の如し」と読むんだそうです。「きょうばく」の響きが、何とも心地よいですね。この詩は、唐代の白楽天が長安より故郷に帰ったとき(811年)の作と伝えられています。白楽天といえども人の子、郷里に帰った安心感・安堵感が行間にうかがえますね。その一方で、都での志が叶わぬままに郷里にもどった失望感が、詠わせた詩だともとれます。今をさかのぼること1200年、白楽天は月明に照らされた蕎麦の花をどのような気持ちで眺めたのでしょうか?◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月24日
-
マイナス1個の光子!?!?
昨日同様に本日も新聞記事より「日本経済新聞」、略して「日経」は、読んでそのまま字の如く経済に関する記事を専門に取り上げている新聞と思われがちですが、意外や文化欄、科学欄についても傑出しております。本日も科学欄の紙面で興味引かれる記事がいくつも書かれておりました。その中からひとつ。昨日同様に、私にはどうしても分かりません。「マイナス1個の光子を大阪大学の大学院生、横田一広さんと井元信之教授が観測することに成功した」という記事。「実験で特殊な光回路に光子を入れ、この異常な現象を新しい方法で測定したところ、回路の一部を光子が通った確立が『マイナス1』となり、本来は存在しない”反光子”のようなものが通ったことを確認できた。」「著名な物理学者アハラノフ博士が予言していた現象を、実験で確認した」ということです。・・・まったくもって不可思議、理解不能。。。電気にプラスとマイナスがあるというのならまだしも、「マイナスの光」だなんて、私の脳みそにはそんな光を受け入れる視覚回路も思考回路もありません。井元教授は「量子力学の不可思議な部分を実験で確かめることができた」と話しておられるそうですが、私の脳みその回路では、不可思議がよりいっそう増幅されるばかりなのであります。◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月23日
-
銀河系ジェットらせん構造!?!?
新聞記事より本日の日経に次のような記事が載っておりました。「地球から約2万光年離れた銀河系の中心部で、ブラックホールなどの天体から高速で噴出する物質の流れ『ジェット』が、らせん構造になっている様子を、名古屋大学の福井教授らが電波望遠鏡でとらえた。」「銀河系ジェットらせん構造」!?!?これをバラバラにして「銀河系」「ジェット」「らせん」「構造」というふうに、単独でならば分かるのですがね。これがつながってしまうと、どうにも難しくて・・・。ブラックホールって、とてつもなく大きな密度の天体で、その巨大な重力のためにあらゆる物質を引き込んでしまう・・・あまりに一般的ではありますが、ブラックホールについて私の知るすべてのところであります。ブラックホールに一旦飲み込まれたら、その重力から脱出することは、光でさえもできないんでしょう。・・・!?!?そのブラックホールから「ジェット」が噴出している!?!?「延びるジェットは長さ百~千光年、質量は太陽の1万個分・・・」にいたっては、我々人間が生を営むこの時間と空間っていったい何なのだろうかと思ってしまいます。唯一このジェットの形が「ソフトクリームかサザエのよう」と、福井教授が言っておられるところだけは、私にも直ちに理解できましたが・・・。でも、この巨大なソフトクリームが、どうして「宇宙の高エネルギー現象を解明する突破口」になるのか、私にはどうしても分かりません。◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月22日
-

そばと蒸篭(せいろ)
2009年3月21日の日記より子供のころ、親に連れられて初めておそば屋さんに入った日のことを今でもはっきり覚えています。おそば屋さんといっても、定食・丼・麺類一式取扱っている・・・そう食堂なんです。懐かしいですね。暖簾をくぐって中に入ると、だしの匂いがぷ~んと鼻をつく。お品書きを見て、何を注文しようか?天ぷらうどんも食べたいな、ラーメンも食べたいし、・・・カツ丼も・・・ってなことになる。幼かった私にもラーメン、うどん、そばは、どういう食べ物かは分かっておりました。でも、ざるそば?・・・いったいどういう食い物だろう?・・・そばには違いないだろう?・・・と思ったものです。「ざ・る・そ・ば・・・?」自問自答を小声で発した時、店員さんが大きな声で言ったのでした。「はぁ~い!ざるそば一丁!!」それが、私とざるそばの最初の出会いだったのです。四角い蒸籠(せいろ)に盛られたそばを見た時、やったぁ~!ざるそばにして良かったと内心にんまりしたものでした。てっきり二段になっていて、竹で編んだスノコをめくれば、蒸籠(せいろ)の底までそばが盛られていると思ったのです。食い意地がはっていたんですね・・・お許しください。今でもハッキリ覚えています。おいしかった!!そして、ちょっとガッカリしたことも・・・これが、私とざるそばの運命的(・・!?)な出会いであったのですが、・・・でも私だけでしょうか?子供のころ、私のように食い意地がはっていたいないは別にして、蒸籠(せいろ)に敷いてあるスノコをめくってみた記憶のある人は、ずいぶんいらっしゃるのではありませんか?ところで蒸籠(せいろ)といえば、皆さん不思議に思われたことありませんか?もりそば、ざるそば、せいろもり・・・こういったそばは、どうして蒸籠(せいろ)にもられて出されるのでしょうか?そばが今のように細く切られて食べられるようになったのは、江戸時代の初めころなのだそうです。当時は「そば切り」と呼ばれて、大変人気があったそうです。当時のそばは、今と違ってつなぎに小麦粉を用いることを知らなかったために、めんが短く切れやすかったのです。ですから、いったん切ったそばを蒸籠(せいろ)にもって、しばらく蒸した後にゆでたというわけです。後に小麦粉をつなぎに使用する打ち方が一般に普及しても、蒸籠(せいろ)にもることは、そのまま残ったのでしょう。先人が苦労の末に生み出した知恵の名残り・・・それが今日の蒸籠(せいろ)もりに息づいているのですね。◆酒そば本舗トップページへ◆**貴方の共感できる生き方がきっとある**
2009年03月21日
-

粒と粉
日本では、そばは「そば」または「蕎麦」と書けば、それが何であるか分からぬ人はいないでしょう。これが、そばの原産地である中国ともなると、ご案内のとおりかの国は漢字の国ですから、土地土地によりいろいろな文字の表し方があるのだそうです。それがまた、土地土地のそばの品種ともからみ合って複雑ったらありゃしない。蕎、蕎麦、烏麦、花蕎、伏蕎、華麦、落麦、省麦・・・・・そばはタデ科の植物であり麦とは違うのに、麦と表現しているところが面白いですね。また、内陸部のチベットやヒマラヤでは古くから苦蕎麦(今、日本でも話題になっている韃靼〈ダッタン〉そば)が栽培されており、このそばと区別するために普通のそばを「甜蕎(てんきょう)」「甜蕎麦(てんきょうばく)」とよんで区別しているのは、興味をひかれます。「甜」は甘いという意味なのですね。日本で広く栽培されているそばが、甘蕎麦と呼ばれる所以です。突然ですが、話はフランスに飛びます。日本テレビ系列「世界マル見え特捜部」のファンの方多くいらっしゃることと思います。楠田さんに所さん、それにビートたけしのズッコケがおもしろいですよね。当地では毎週月曜夜8時から入ります。ずいぶん前に放映されたものなんですが、フランス人シェフがスタジオに来てクレープを焼いていました。ゲストが旨い旨いと盛んに食べていましたが、このクレープの生地にそば粉が入っていると楠田さんが言っていたのでちょっと驚きました。何という名前のクレープなのか忘れましたが、フランスのある地方の伝統料理だといっていましたから、昔からあるのでしょうね。ということは、フランスでもそばが栽培されているのだろうか?・・・と思ったのです。早速調べてみました。「蕎麦考」(永友 大著)より引用いたします。やはりフランスでもそばは栽培されているのです。「 Bre Sarrasin 」日本語読みで「ブレ サラザン」と発音するのでしょうか?「ブレ」は最終的には「ブレッド」に行き着きたくなりますね。そうすると「 Bre 」は小麦を意味することになるのでしょうか。「サラザン」は「サラセン」でしょう。しからば、サラセンの小麦ということになりますね。原産国中国からヨーロッパへそばを伝えたのは、サラセンの商人だったのでしょうか。同じヨーロッパでもドイツ語では、「Buchweizen」、「Buch」はドイツ語で「Buche」のことで、ブナの実のことを指すのだそうです。さすれば、ブナ小麦ということでしょう。では英語ではどうかというと、これが「Buck Wheat」。後半の「w」で始まる言葉はいづれも小麦を意味しますね。そばの原産地である中国でもやはり「麦」と表現していることを思えば、洋の東西を問わず、人間の思いつきや発想は同じなのかなと感心してしまいます。これは、世界の主食は何といっても小麦で、小麦は粉にして食されるものですから、同様にそばもやはり挽いて粉にして食べるということから、○○麦と表現するようになったのだと思いますが、読者はいかにお考えになりますか。日本では、そばは大陸より伝播してこの方、粒のまま煮てお粥のようにして食べていたそうで、粉に挽いても蕎麦掻き(そばがき)のように団子状にして、やはり煮るようにして食した。今のそばのように細く切って食べるようになったのは、江戸時代になってからというのですから、ちょっと驚きです。文字こそ中国から伝わったそのまま「蕎麦」と表しますが、長年にわたり粒のまま食していたというのは、これは何といっても日本は瑞穂の国、お米は粉になどせず粒のまま食べますからね、米の影響が大きいのでしょう。粒食と粉食の文化の違いは、こんなところにも影響しているのですね。そばっておもしろい!!◆酒そば本舗トップページへ◆
2009年03月20日
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- カフェ話。
- カフェでフレンチトースト
- (2025-11-22 10:28:26)
-
-
-

- 今日のワイン
- ボジョレーヌーボーでないけど11月…
- (2025-11-24 07:11:40)
-
-
-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆
- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…
- (2025-07-15 05:52:26)
-







