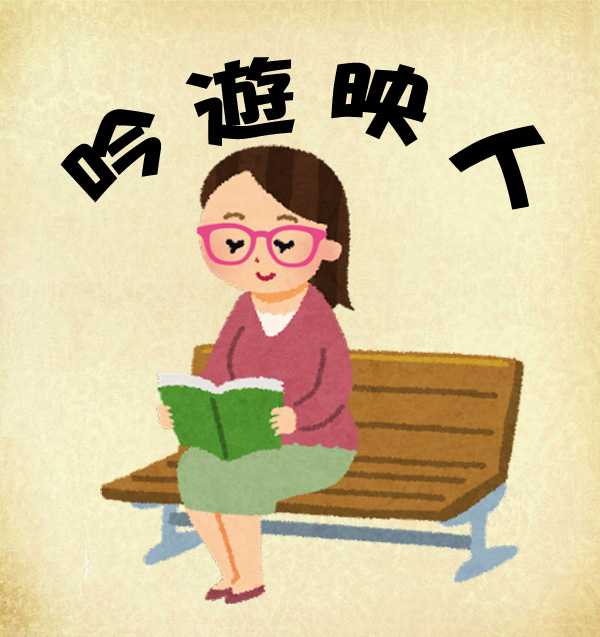PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
その他
(7)映画/アクション
(77)映画/ヒューマン
(97)映画/ホラー
(35)映画/パニック
(25)映画/歴史・伝記
(32)映画/冒険&ファンタジー
(41)映画/ラブ
(47)映画/戦争・史実
(41)映画/SF
(55)映画/青春
(23)映画/アニメ
(24)映画/サスペンス&スリラー
(143)映画/時代劇
(21)映画/西部劇
(4)映画/TVドラマ
(30)映画/コメディ
(15)映画/ミュージカル
(1)映画/ドキュメンタリー
(3)映画/犯罪
(12)映画/バイオレンス
(9)映画/ヒッチコック作品
(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』
(8)読書案内
(220)仏レポ
(2)コラム紹介
(120)竜馬とゆく
(9)名歌と遊ぶ
(70)名句と遊ぶ
(288)風天俳句
(5)名文に酔う
(16)ほめ言葉
(3)教え
(42)吟遊映人ア・ラ・カルト
(14)江畔翁を偲ぶ
(12)ガンバレ受験生!
(5)オススメの本
(3)月下書人(小説)
(6)写伝人(写真)
(6)写真
(18)名曲に酔う
(1)名画と遊ぶ
(2)訃報
(11)舞台
(1)神社・寺院・史跡
(13)テーマパーク
(2)カフェ&スイーツ
(23)要約
(23)聖地巡礼
(1)発見
(8)体験談
(1)お気に入り
(2)ヘルス&ビューティー
(4)読書初心者
(5)美術館・博物館
(1)テーマ: コラム紹介(119)
カテゴリ: コラム紹介
【適菜収の賢者に学ぶ】

~「正しい歴史認識」とは何か?~
韓国大統領の朴槿恵が、就任以来日本に対し「正しい歴史認識を持つべきだ」との要求を続けている。国連事務総長の潘基文も、日本と中韓の対立について「政治指導者は正しい歴史認識を持ってこそ、他国から尊敬と信頼を受けられる」などと述べている。
それでは「正しい歴史認識」とは何か?
歴史家のエドワード・ハレット・カー(1892~1982年)は、歴史とは「現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」(『歴史とは何か』)であると述べている。「事実はみずから語る、という言い慣わしがあります。もちろん、それは嘘です。事実というのは、歴史家が事実に呼びかけたときだけ語るものなのです」(同上)
シーザーがルビコン河を渡ったのは歴史的事実とされている。しかし、それは歴史家が厖大(ぼうだい)な「事実」の中から恣意(しい)的に選び出し、脚色したものである。それ以前にも、それ以後にも、ルビコン河を渡った人間は星の数ほど存在したはずだが、彼らについての資料は存在せず、誰の関心を惹(ひ)くこともない。
歴史家の選択や解釈から独立した「歴史的事実」など存在しないとカーは言う。都合のよい事実を選択し配列すれば「正しい歴史認識」などいくらでもつくることができる。つまり、 「正しい歴史認識」なるものが存在するというのは、あまりにナイーブな、もっと言えば子供じみた考え方なのだ。
カーは、ベネデット・クローチェ(1866~1952年)の「すべての歴史は『現代史』である」との言葉を引く。
歴史は現在の眼を通して過去を見ることで成り立つものであり、「歴史的事実」は歴史家の評価によって決まる。そしてその歴史家もまた、社会状況や時代に縛り付けられている。つまり、 歴史家という存在自体が中立ではありえないのだ。
過去の優れた歴史家たちを分析し、ここまで論じた上でカーは次のステップに進む。
そこでカーは歴史家の義務を規定した。
それは一切の事実を描き出す努力を続けること。そしてもう一つ大事なのは、歴史家自体を研究することである。歴史家の判断を生み出した社会的、時代的背景を明らかにするわけだ。
歴史を「事実の客観的編纂(へんさん)」と考えるのも「解釈する人間の主観的産物」と決めつけるのも一面的である。歴史家の仕事は、この「二つの難所の間を危なく航行する」ことであり、主観による「事実」の屈折を自覚することである。ましてや 歴史の専門家ではない政治家は過去に対し謙虚になるべきだろう。
最後にクローチェの言葉を。「歴史の物語をするという口実で、裁判官のように一方に向っては罪を問い、他方に向っては無罪を言い渡して騒ぎ廻り、これこそ歴史の使命であると考えている人たちは……一般に歴史感覚のないものと認められている」(同上)
より正しい「歴史認識」のためには、殊更に 「正しい歴史認識」を言い立てる人間の背景を研究する必要がある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『適菜収の賢者に学ぶ』は産経新聞のコラムだ。適菜氏のペンは正鵠を射る。
何より「賢者に学ぶ」というタイトルが示す通り、筆者お仕着せのコラムでないのがありがたい。
このごろの新聞各紙は片寄った思想が丸出しだ。根底にあるのは「私の考え」が即ち「正論である」という筆者の傲慢と読者軽視が読んで取れる。
そうしたコラムに辟易するとき、「賢者がこう言う」だから「私はこう考える」、或いは「私の考えはこうだ」それは「賢者がこう言うからだ」という適菜氏のスタイルには安心でき、おおいに納得するのだ。
多くの新聞は「正しい歴史認識」を書き立てている。
『 「正しい歴史認識」を言い立てる人間の背景を研究する必要がある。
どす黒くいびつに歪んだ新聞の宿痾が見えるかもしれない。
さて適菜氏の博覧強記ぶりを以前のコラムからご紹介する。
『もっとくちをつぐもう』では流行の市民運動についてキルケゴールを引く。
「弱い人間がいくら結合したところで、子供同士が結婚すると同じように醜く、かつ有害なものとなるだけのことだろう」
そして氏はこう喝破するのだ。
『意見を持たないことも教養の一つである。知らないことには口をつぐまなければならない。それは発言の価値を確保するためである。「たとえ素人であっても声を上げることが必要だ」という歪んだ考え方が社会に蔓延した結果、傍観者が退屈凌ぎに社会を動かすようになった。』
関連して『群れることの危険性』ではこう言っている。
『右派だろうが左派だろうが、市民運動的なものは劣化していく傾向をもつ。』
『孤立していたときには、恐らく教養のある人であっても、群集に加わると、本能的な人間、従って野蛮人と化してしまう』
(趣意)
適菜氏の孤高なペンに敬意を表する次第だ。そして今後のご活躍を願ってやまない。


~「正しい歴史認識」とは何か?~
韓国大統領の朴槿恵が、就任以来日本に対し「正しい歴史認識を持つべきだ」との要求を続けている。国連事務総長の潘基文も、日本と中韓の対立について「政治指導者は正しい歴史認識を持ってこそ、他国から尊敬と信頼を受けられる」などと述べている。
それでは「正しい歴史認識」とは何か?
歴史家のエドワード・ハレット・カー(1892~1982年)は、歴史とは「現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」(『歴史とは何か』)であると述べている。「事実はみずから語る、という言い慣わしがあります。もちろん、それは嘘です。事実というのは、歴史家が事実に呼びかけたときだけ語るものなのです」(同上)
シーザーがルビコン河を渡ったのは歴史的事実とされている。しかし、それは歴史家が厖大(ぼうだい)な「事実」の中から恣意(しい)的に選び出し、脚色したものである。それ以前にも、それ以後にも、ルビコン河を渡った人間は星の数ほど存在したはずだが、彼らについての資料は存在せず、誰の関心を惹(ひ)くこともない。
歴史家の選択や解釈から独立した「歴史的事実」など存在しないとカーは言う。都合のよい事実を選択し配列すれば「正しい歴史認識」などいくらでもつくることができる。つまり、 「正しい歴史認識」なるものが存在するというのは、あまりにナイーブな、もっと言えば子供じみた考え方なのだ。
カーは、ベネデット・クローチェ(1866~1952年)の「すべての歴史は『現代史』である」との言葉を引く。
歴史は現在の眼を通して過去を見ることで成り立つものであり、「歴史的事実」は歴史家の評価によって決まる。そしてその歴史家もまた、社会状況や時代に縛り付けられている。つまり、 歴史家という存在自体が中立ではありえないのだ。
過去の優れた歴史家たちを分析し、ここまで論じた上でカーは次のステップに進む。
そこでカーは歴史家の義務を規定した。
それは一切の事実を描き出す努力を続けること。そしてもう一つ大事なのは、歴史家自体を研究することである。歴史家の判断を生み出した社会的、時代的背景を明らかにするわけだ。
歴史を「事実の客観的編纂(へんさん)」と考えるのも「解釈する人間の主観的産物」と決めつけるのも一面的である。歴史家の仕事は、この「二つの難所の間を危なく航行する」ことであり、主観による「事実」の屈折を自覚することである。ましてや 歴史の専門家ではない政治家は過去に対し謙虚になるべきだろう。
最後にクローチェの言葉を。「歴史の物語をするという口実で、裁判官のように一方に向っては罪を問い、他方に向っては無罪を言い渡して騒ぎ廻り、これこそ歴史の使命であると考えている人たちは……一般に歴史感覚のないものと認められている」(同上)
より正しい「歴史認識」のためには、殊更に 「正しい歴史認識」を言い立てる人間の背景を研究する必要がある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『適菜収の賢者に学ぶ』は産経新聞のコラムだ。適菜氏のペンは正鵠を射る。
何より「賢者に学ぶ」というタイトルが示す通り、筆者お仕着せのコラムでないのがありがたい。
このごろの新聞各紙は片寄った思想が丸出しだ。根底にあるのは「私の考え」が即ち「正論である」という筆者の傲慢と読者軽視が読んで取れる。
そうしたコラムに辟易するとき、「賢者がこう言う」だから「私はこう考える」、或いは「私の考えはこうだ」それは「賢者がこう言うからだ」という適菜氏のスタイルには安心でき、おおいに納得するのだ。
多くの新聞は「正しい歴史認識」を書き立てている。
『 「正しい歴史認識」を言い立てる人間の背景を研究する必要がある。
どす黒くいびつに歪んだ新聞の宿痾が見えるかもしれない。
さて適菜氏の博覧強記ぶりを以前のコラムからご紹介する。
『もっとくちをつぐもう』では流行の市民運動についてキルケゴールを引く。
「弱い人間がいくら結合したところで、子供同士が結婚すると同じように醜く、かつ有害なものとなるだけのことだろう」
そして氏はこう喝破するのだ。
『意見を持たないことも教養の一つである。知らないことには口をつぐまなければならない。それは発言の価値を確保するためである。「たとえ素人であっても声を上げることが必要だ」という歪んだ考え方が社会に蔓延した結果、傍観者が退屈凌ぎに社会を動かすようになった。』
関連して『群れることの危険性』ではこう言っている。
『右派だろうが左派だろうが、市民運動的なものは劣化していく傾向をもつ。』
『孤立していたときには、恐らく教養のある人であっても、群集に加わると、本能的な人間、従って野蛮人と化してしまう』
(趣意)
適菜氏の孤高なペンに敬意を表する次第だ。そして今後のご活躍を願ってやまない。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.11.19 06:30:58
[コラム紹介] カテゴリの最新記事
-
コラム紹介『高知新聞 小社会』 2014.09.09
-
コラム紹介『北國新聞 時鐘』昭和天皇実録 2014.08.26
-
コラム紹介『朝日新聞 天声人語』~木田元… 2014.08.20
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.