
牡蠣が動くところを見たことがありますか?牡蠣の外套膜、上の図に示した黒い縁取りの部分が外套膜だ。この部分を箸やフォークでつついたり、レモン汁やヴィネガーをたらしたりすると生きている牡蠣は痛がるのか?あるいはしみるのか?この外套膜の部分が縮むような動きを見せる。
私など、牡蠣を剥いているときに一個一個外套膜をつついて生きているのを確認する癖がついているくらいだ。慣れれば、生きた牡蠣が動く姿をはっきりと見ることが出来る。
もっとも、それは牡蠣を痛めつけずに活きたまま剥く技術があってのことだが、、、。
さて、前回はギネスビールとスコッチウイスキーまででてきましたが、、。
ワインに話題を戻しましょうか、、。シャブリのときに書きましたが、牡蠣殻の堆積した石灰質の土壌で出来た白ワインがレモンを使わない生牡蠣には結構合うのだが、私の好みではシャブリを始めとしたシャルドネ種のワインより、同じような土壌で作られるソーヴィニヨン・ブランのほうがいっそう良いような気がする。例えば、シャブリと同じ地域で作られるサン・ブリ(saint Bris)など、実に心地よいミネラル感がキリキリと効いていて好ましいものだし、、、。ちょいと地図を見てもらって、、、。
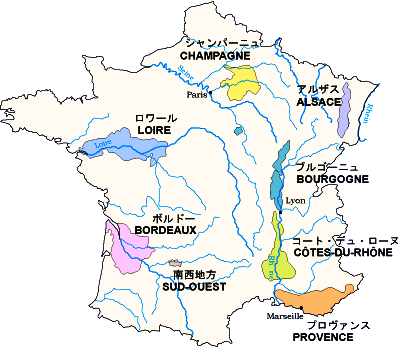
ブルゴーニュ地区の左上、シャンパーニュの真下にぽつんと青くあるのが、シャブリ地区。一応ブルゴーニュ地方のワインということになっているが、実はこんなに離れているのだ。地勢的には、シャンパーニュやロワールの上流域とむしろ地続きといえるくらいだ。つまり、シャンパーニュ地区もロワール上流域も石灰質の土壌の地域であるということで共通しているのだ。
ベルサイユ宮殿を始めとしたルイ王朝時代の建造物を作った大理石(大理石というのは牡蠣殻などの堆積した石灰岩が地下で熱変成を受けて出来たもの)は、シャンパーニュ地区の地下から切りだされ、セーヌ川の支流を使って船で運ばれた物だ。その地下の石切り場の跡が、シャンパーニュの熟成貯蔵庫の自然な地下セラーになっているのは有名な話だ。
もちろんシャンパーニュと生牡蠣というのも悪くない。ただし、あまり立派な物は必要ないと思う。シャンパーニュの場合、なんといっても炭酸ガスがあるのが強み!
というのは、よく言う「シャンパーニュはどんな料理にも合う。」というのも、炭酸ガスが一瞬舌を痺れさせるから、そのつど味覚をリセットするという作用が大きいと思う。ペリエなどのガス入りミネラルウォーターの良さもそこにあるのではないか?アメリカ式に食事にコーラというのも炭酸があればこそだろう。
その証拠に気の抜けたシャンパーニュや気の抜けたコーラやペリエなど、ちょいと厳しいものがあるでしょう?そういうわけで炭酸ガスというのは、かなりの強い作用を持っている。酎ハイやビールにしてもそうだろう。炭酸が無ければ飲めたもんじゃないですよね!
<続く>
-
夏ですねぇ Jul 31, 2009
-
ラタトゥイユもできました。 Jun 25, 2009
-
イナダ Apr 21, 2009
PR
Keyword Search
Calendar
Comments










