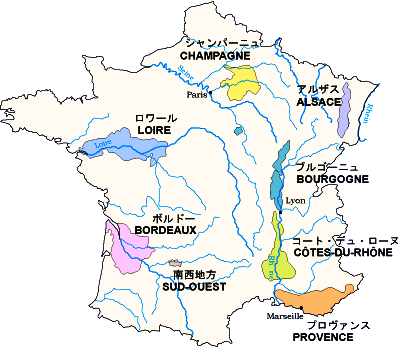
さて、生牡蠣とワインの続き、、、。美味しいワインだらけのロワール河流域の最後、河口にはミュスカデがありますね。元々は、ブルゴーニュの超二流品種だったムロン・ド・ブルゴーニュという品種をロワール河口のナント辺りに植えたらうまくいったのでここに根付いたということだ。ミュスカデという品種は、ミュスカド(ナツメグ)からきている。ミュスカドのミュスは、ムスク(じゃ香)のことで、カドは、木の実のこと。つまりじゃ香の風味の木の実のような香りのワインということになる。
このミュスカデは、河口の直前でロワールの本流に流れ込むセーブル川とメーヌ川の間本流より北側の地区のワインが一番珍重される。それが、ミュスカデ・ド・セーブル・エ・メーヌ・シュル・リである。
セーブル川とメーヌ川の間で作られている、ミュスカデをシュル・リ方式で作ったものだ。シュル・リとは、ベッドの上でという意味。Café au lait au lie、カフェ・オ・レ・オ・リといってベッドの上で(メイドさんなどに運んでもらった)カフェオレを飲むというのが、フランス人の甘い生活の理想なんだそうだが、そのリがベッドのこと。ワインがベッドで寝るのか?というと、もちろん布団を引いて寝かせるわけはなく、、、この場合のリとは、ワインの樽の中のオリのことだ。普通白ワインは、濁りを避けるために発酵終了後何度かオリ引きをしたり、場合によってはろ過したりして濁らせないようにするのだが、それをわざと遅らせ年を越して最大期間初夏(6月30日)までオリ引きをしないことによって、発酵を終えて死んだ酵母などが分解して出来るアミノ酸などが独特の風味を作るのだ。シャンパーニュの瓶内2次発酵のときもオリの上での熟成になるわけで、シャンパーニュのあのトースト香などの風味が生まれるのと一緒だ。炭酸ガスも少し残るので、グラスに注ぐと小さな泡が出来ることがある。ペルレといって真珠で飾ったような泡というらしい。
さて、このワインのように海の近くで出来るワインは、魚介との相性がよい。当然ながら、海の近くでは魚介料理が中心となるわけで、当然ワインも伝統的に魚介に合う物が作られるわけだ。どうも、私はミュスカデからじゃ香の香りを感じたことはないのだが、かすかな炭酸とともに生牡蠣に合うのは間違いないと思う。
-
先週末のシャンパーニュの会 Sep 2, 2009
-
先週のワイン会の話 May 20, 2009
-
スペインの怪物ワイン入荷! May 4, 2009
PR
Keyword Search
Calendar
Comments










