PR
X
カレンダー
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
キーワードサーチ
▼キーワード検索
フリーページ
テーマ: 携帯電話のこと(2728)
カテゴリ: 人工衛星
ご訪問ありがとうございます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。
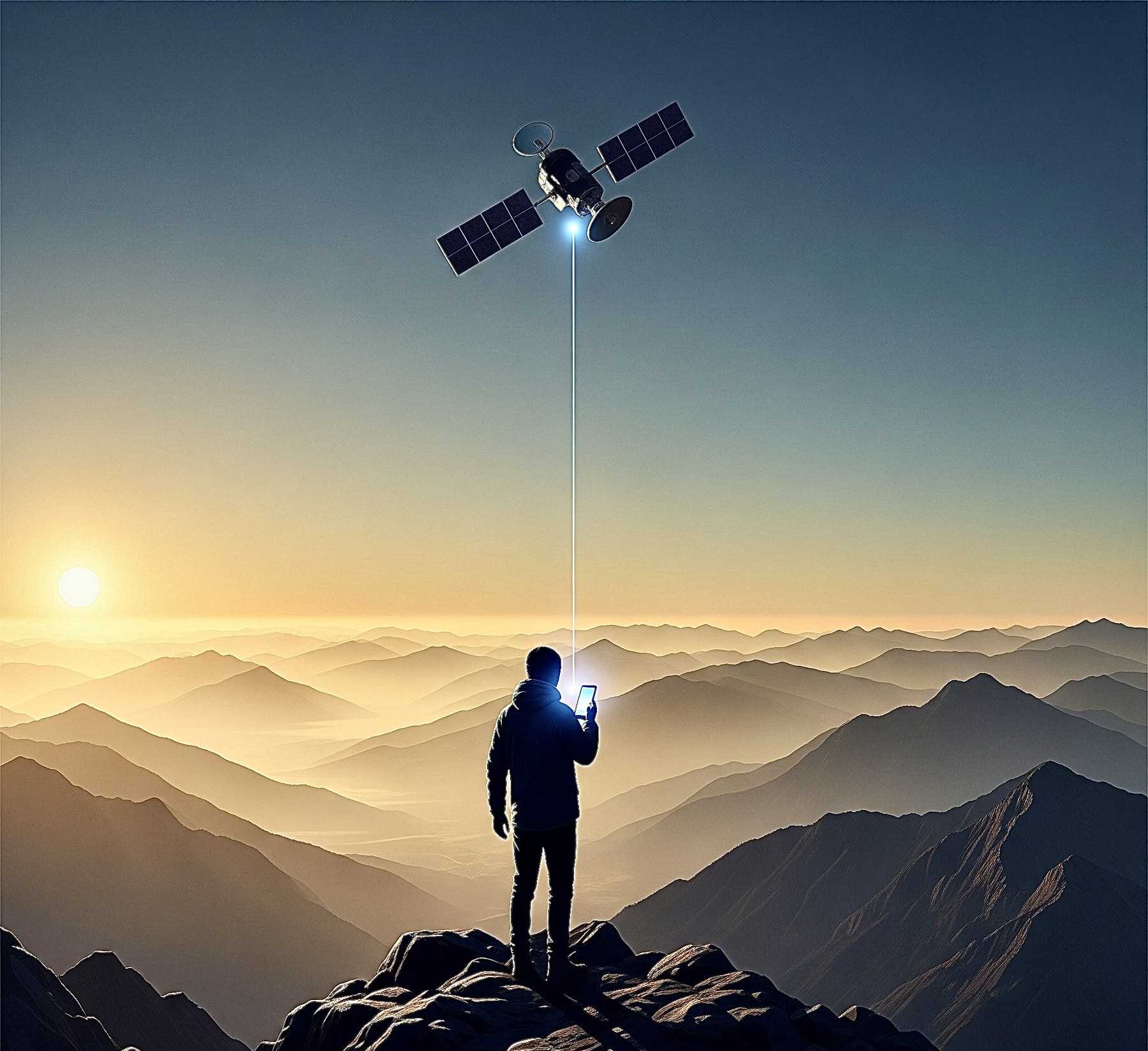
衛星通信とは?スマホのダイレクト通信で実現できることを解説
近年、通信技術の進歩により、従来の地上ベースの通信インフラに加えて、衛星を活用した新たな通信方式が注目を集めています。特に、各携帯電話会社では、通信エリア拡大や災害時の通信確保を目指し、スマートフォンと直接通信する「衛星ダイレクト通信」の取り組みが積極的に進められています。本記事では、衛星通信の基本的な仕組みから、スマートフォンの衛星ダイレクト通信で実現できることまでを詳しく解説します。
衛星通信の基本概念
衛星通信とは、地上と人工衛星の間でデータをやり取りする通信方式です。この仕組みでは、地上の無線局から送信されたデータを、低軌道・中軌道を周回する衛星や静止軌道上に配置された衛星が受信し、地上の目的地に送信します。通信衛星の軌道には、主に「周回軌道」と「静止軌道」の2種類があり、それぞれ異なる特長を持っています。
周回軌道
中軌道(MEO):約2,000~3万6,000km
低軌道(LEO):約500~2,000km
人工衛星1機における通信可能範囲:狭い
静止軌道(GEO)
高度:約3万6,000km
楽天の国内向け商用サービスでは、AST SpaceMobileの軌道高度約700kmを周回する商用衛星「BlueBird Block 2」を中心に活用予定です。試験衛星「BlueWalker 3」と商用衛星「BlueBird Block 1」については、高度約500kmを周回します。
衛星通信の方式
衛星通信には、大きく分けて2つの方式があります。1つは専用端末を利用する方式、もう1つはスマートフォンが直接衛星と通信する衛星ダイレクト通信です。専用端末を利用する方式の実例として、2024年に発生した能登半島地震では、基地局が停電で機能しなくなった地域の避難所や救急医療の現場に、衛星通信サービス「Starlink」の専用端末が提供されました。これにより通信環境が確保され、インターネット回線が利用可能となりました。一方、スマートフォンの衛星ダイレクト通信は、通信エリアの拡大や災害時の通信手段確保を目的に、各携帯電話会社で取り組みが進められています。現在、一部の携帯電話会社から商用サービスの提供が始まっています。
衛星通信で使われる周波数帯について
衛星通信で使われる周波数帯は、それぞれ異なる特性を活かして多様な用途に利用されています。提示された情報を補足する形で、各バンドの主な利用例を以下にまとめました。
Lバンド(1.215~1.71GHz)
特徴: 通信容量は小さいですが、雨や雨雲の影響を非常に受けにくく、安定した通信が可能です。小型のアンテナでも通信できるため、移動体通信に適しています。
主な利用例:
* 衛星携帯電話: イリジウムやインマルサットなどの衛星携帯電話サービスで利用され、地上ネットワークが届かない場所(海上や山岳地帯など)での音声通話やデータ通信に使われます。
* GPS(全地球測位システム): 衛星からの測位信号を受信するのにLバンドが使われています。
* 気象観測: 気象衛星からのデータ送信に利用されます。
Sバンド(1.71~2.7GHz)
特徴: Lバンドと同様に、雨の影響を受けにくいという特性を持ちます。Lバンドよりは広い帯域幅を確保しやすいため、より多くのデータ通信が可能です。
主な利用例:
* 衛星放送: 日本では、携帯端末向けの衛星放送サービス「モバHO!」でSバンドが使われていました。
Cバンド(3.4~7.075GHz)
特徴: 衛星通信が商業化された当初から使われてきた周波数帯で、大容量通信が可能です。雨の影響はKuバンドやKaバンドよりは少ないですが、通信安定性を確保するためには大型のアンテナが必要です。
主な利用例:
* テレビ局間の番組伝送: 地上の通信網を介さずに、テレビ局間で番組素材を送受信する際に使われます。
* 衛星ニュース中継: 災害現場などからの中継で、アンテナを搭載した中継車(SNG:Satellite News Gathering)がCバンドを利用することが多いです。
* 固定通信: 離島や僻地へのインターネット回線提供にも使われます。
Kuバンド(10.6~15.7GHz)
主な利用例:
* 衛星放送(BS/CS): 視聴者が家庭で利用する衛星放送サービス(BS放送やスカパー!など)で広く使われています。
* VSAT(超小型地球局): 企業や店舗のネットワーク構築、遠隔地の監視システムなど、多様な分野で利用されています。
* Starlinkなどの衛星ブロードバンド: ユーザー端末と衛星間の通信にKuバンドが使われています。
Kaバンド(17.3~31GHz)
特徴: 衛星通信で利用される周波数帯の中では最も高く、非常に大容量の通信が可能です。Kuバンド以上に雨や雪の影響を受けやすいため、通信の安定性を確保するための技術が求められます。
主な利用例:
* 次世代の高速衛星通信: 高速インターネットサービスや、通信容量を増やす必要のあるサービスで利用が進んでいます。
* Starlinkなどの衛星ブロードバンド: Starlinkの衛星間通信や、衛星と地上局を結ぶ通信でKaバンドが使われています。
* 軍事通信: 大容量のデータ通信が必要な軍事目的でも利用されます。
衛星通信端末の種類
日本国内で利用されている衛星通信端末の種類は、主に「パラボラ・平面アンテナ型端末」と「携帯電話型端末」の2つに分類されます。
パラボラ・平面アンテナ型端末
- アンテナを固定して設置
- 通信容量が多い
- 特定の方向に電波を集中させる「アンテナ指向性」が強い
- 通信の安定性に優れている
携帯電話型端末
- 通信容量やアンテナの指向性は劣る
- 小型で持ち運びやすいという利点がある
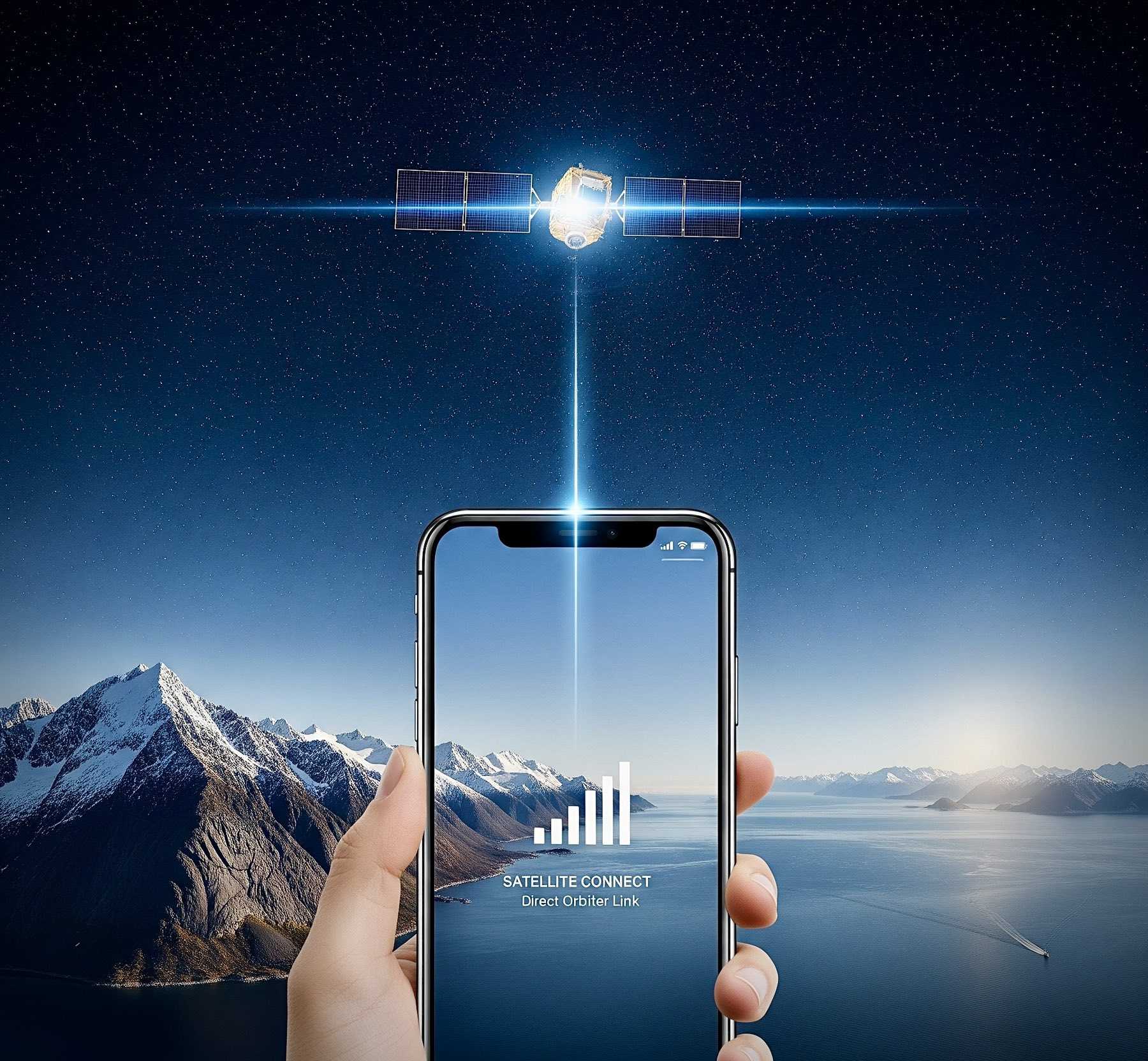
衛星通信のメリット・デメリット
衛星通信には以下のような特徴があります。
メリット:広範囲での通信可能性
地上通信網が整備されていない場所(山奥、離島、海上など)でも利用可能です。衛星通信を利用すれば、山奥や離島、海上など、地上通信網がない場所でもインターネット接続が可能になります。
メリット:災害耐性
災害の影響を受けにくいという特徴があります。災害時には被災地などに衛星用基地局を設置することで、迅速な情報伝達の手段を応急復旧できます。
デメリット:通信遅延
衛星との距離により通信遅延が発生することがあります。特に、地上と人工衛星の距離が遠い静止軌道(GEO)衛星は遅延が発生するため、リアルタイム性が要求される用途には不向きといわれています。これに対して、低軌道(LEO)衛星は、比較的遅延が小さくなります。
デメリット:天候の影響
周波数帯によっては天候の影響を受けやすくなります。KuバンドやKaバンドのような高周波数帯は雨の影響を受けやすく、通信が途切れることがあります。反対に、LバンドやSバンドは雨に強く、より安定した通信が可能です。
デメリット:通信環境の制約
衛星との見通しが取れない場所(トンネル、谷底、建物の陰など)では通信できないことがあります。
スマートフォンの衛星ダイレクト通信で実現できること
各携帯電話会社では、専用端末を介した衛星通信だけでなく、スマートフォンと衛星のダイレクト通信により通信エリア拡大などを目指す取り組みが進められています。
通信エリアの拡大
スマートフォンの衛星ダイレクト通信により、通信エリアの大幅な拡大が期待されています。現在、日本の携帯電話サービスは、人口カバー率が約99%に達している一方で、面積カバー率は日本全土の約70%にとどまっています。人口カバー率とは、全国の人口のうち携帯電話のサービスエリア内に居住する人の割合を指します。一方、面積カバー率は、日本の国土面積のうち、通信が届く範囲の割合を指します。スマートフォンの衛星ダイレクト通信が可能になれば、基地局の電波が届かない山奥や離島、海上など、従来は圏外だったエリアでも、専用端末なしでスマートフォンを利用できるようになる可能性があります。例えば、登山時に山奥で遭難時の連絡手段として役立ちます。これにより、迅速に救助要請を行えるようになるでしょう。各携帯電話会社は、衛星ダイレクト通信の実用化などを進め、日本全土をカバーできる通信インフラの構築を目指しています。
災害時の通信確保
スマートフォンの衛星ダイレクト通信が実用化されれば、災害時にも従来より安定した通信が可能になると考えられています。従来のモバイルデータ通信や光回線は、基地局や光ファイバケーブルが被災することで、通信が途絶えるケースが多くありました。しかし、衛星ダイレクト通信であれば、近隣に基地局がなくても通信できるため、普段使っているスマートフォンを非常時の連絡手段として活用できます。
楽天モバイルの衛星ダイレクト通信への取り組み
楽天モバイルは、米国のAST SpaceMobileとのプロジェクトを推進しており、日本国内で2026年第4四半期のサービス提供開始を目指しています。「Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobile」は、低軌道衛星と市販されているスマートフォンによる直接”高速インターネット通信”(音声・ビデオ通話など)を目指すプロジェクトです。楽天の国内向け商用サービスでは、AST SpaceMobileの軌道高度約700kmを周回する商用衛星「BlueBird Block 2」を中心に活用予定です。試験衛星「BlueWalker 3」と商用衛星「BlueBird Block 1」については、高度約500kmを周回します。
技術的な成果
楽天モバイルとAST SpaceMobileは、既に重要な技術的マイルストーンを達成しています。2023年4月には低軌道衛星によるモバイル・ブロードバンド通信を用いた市販スマートフォン同士の音声通話試験に世界で初めて成功しました。これは、宇宙から送信するモバイル・ブロードバンド・ネットワークと市販スマートフォン端末との通信において、2023年4月26日時点でのAST SpaceMobile調べによる世界初の成果です。さらに2025年4月には、低軌道衛星と市販スマートフォン同士のビデオ通話にも、日本国内で初めて成功しています。これも、宇宙から送信するモバイル・ブロードバンド・ネットワークと市販スマートフォン端末との通信において、現時点でのAST SpaceMobile調べによる成果です。この取り組みは、モバイル通信の広域エリアカバーや災害時の通信インフラの冗長性強化に向けた第一歩となりました。
まとめ:衛星ダイレクト通信の未来展望
衛星通信では、地上と人工衛星間でデータのやり取りができ、基地局からの電波が届かない場所でもインターネットに接続できます。スマートフォンの衛星ダイレクト通信が実用化すれば、光回線が接続できない場所や携帯電話会社の基地局では電波が届かない山奥や離島、海上などでも専用端末なしでスマートフォンで通信できるようになるでしょう。近い将来、通信エリアが広がることでスマートフォンの利用がより快適になりそうです。
衛星通信とは?スマホのダイレクト通信で実現できることもわかりやすく解説
https://network.mobile.rakuten.co.jp/sumakatsu/contents/articles/2025/00385/

下記からは私個人の私見と考察です。
AST SpaceMobileの衛星計画全体
同社は2024年9月に「BlueBird」商用衛星5基を打ち上げ済みで、さらに「Block 2 BlueBird」衛星を2024年11月に発表しており、最大で 60基の衛星を2026年までに打ち上げる計画であるとされています。
https://www.fierce-network.com/wireless/ast-spacemobile-and-problem-delivering-broadband-space
https://en.wikipedia.org/wiki/AST_SpaceMobile
周波数帯(バンド)について
• Light Reading(外部報道)
• 候補として「700 MHz(プラチナバンド)」または「1800 MHz(1.8 GHz帯)」のいずれかが検討されているが、決定は「来年中(2026年までに)」になる見込み、と報じられています。
https://www.lightreading.com/satellite/rakuten-targets-late-2026-for-mobile-satellite-launch-with-ast
https://forbesjapan.com/articles/detail/78869
• Impress Watch(業界報道)
• 三木谷浩史氏(楽天)は、プラチナバンド(700 MHz帯)で構築したい意向を示しており、低い周波数帯の電波伝播特性を活かすことで、屋内でもつながりやすい環境を目指しているとも報じられています。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2009449.html
「人口カバー率99%」でも“圏外”がなくならない理由
日本の携帯は人口カバー率こそ非常に高い一方で、面積カバー率は約7割前後にとどまります。理由はシンプルで、山間部・離島・海上など「人が少ない」「基地局の建設や保守のコストが高い」地域が広く残っているからです。この“最後の1割~3割”をどう埋めるかが長年の課題で、「空から覆う」衛星ダイレクト通信は、その抜けを一気に埋める有力手段だと思います。
なぜ衛星ダイレクト通信は難しいのか(でも実現しつつあるのか)
スマホは小さな電力・小さなアンテナで設計されています。ふつうは近くの地上基地局(数百メートル~数キロ先)に向けて電波を飛ばします。ところが衛星は数百~数千キロ上空。
このギャップを埋めるために、衛星側では次の工夫が使われます。
• 巨大なフェーズドアレイアンテナ:衛星が空から“細かいスポットビーム”を何十~何百本もつくり、地上のスマホに合わせて狙い撃ち(集中的に電力を届ける)します。
• 端末に近い周波数を使う:地上携帯と同系の周波数(例:700MHz帯や1.8GHz帯などの低~中周波)を使えば、建物内や森の中でも届きやすい特性を活かせます。
• ドップラー・遅延補正:衛星は秒速数キロで動くため周波数のズレ(ドップラー)やタイミングのズレ(遅延)が生じます。3GPPのNTN(非地上系)規格では、これらを端末・衛星・ネットワーク側で賢く吸収する仕組みが定義されつつあります。
結論として「端末はそのまま」「空側を賢く」が、直近のダイレクト通信の基本設計思想のようです。
軌道高度が違うと何が変わる?(GEO / MEO / LEOの実感値)
• GEO(静止軌道, 約3.6万km):1基で広く覆えるが、遅延が大きい(往復で数百ms)ため、動画会議やゲームでは違和感が出やすいです。
• MEO(中軌道, 数千~約2万km):カバーと遅延のバランス型。
• LEO(低軌道, 数百~数千km):遅延が小さく(往復で数十ms級まで下げやすい)、音声・ビデオ・データの汎用に向きます。ただし可視時間が短いため、多数の衛星で継ぎ目なく覆う発想が必須です。
私が調べたところ、スマホ直の使い勝手を高めるにはLEOが本命になりやすい、というのが近年の潮流のようでした。
周波数帯は“つながりやすさ”と“太さ”のトレードオフ
• 低い周波数(例:700MHz帯):回り込みやすく屋内・森林・雨天に強い。ただし帯域(通信の太さ)を広く取りにくいため、エリアの底上げ・音声・メッセージ・基本データに向きます。
• 中~高い周波数(1.8GHz帯、さらに上):容量(太さ)を稼ぎやすい半面、雨や遮蔽物に弱くなります。
衛星ダイレクト通信の黎明期は「まずつながること」「災害時に役立つこと」を重視するため、低周波優先→段階的に容量拡大という移行が現実的のようです。
1日中いつでも繋がるのか?(可視時間とセル容量の考え方)
LEO衛星は空を高速で流れます。いつでも頭上にいるわけではありません。実際の使い勝手は次の2点で決まります。
1. 可視時間:自分の頭上近くに「その周波数を照射してくれる衛星」が来る時間帯。初期は時間や方角の制約が残る可能性があります。
2. セル容量:ひとつのスポットビームに同時に収容できる端末数・スループットの上限。初期段階はメッセージ・音声中心、段階的にブロードバンドへ、という流れが現実的です。
「どこでも、常時、地上5G級の太さが出る」ではなく、“圏外を作らない”、“非常時でも連絡できる”価値から普及が始まり、徐々にリッチ化が進んでいくのではないでしょうか。
スマホ側は何を準備すればよい?
• ソフト更新(OS/キャリア設定):NTN対応や周波数・事業者情報の追加で、アップデートが必要になる場合があります。
• 周波数対応:お手持ち端末が対象バンド(例:700MHz帯や1.8GHz帯相当)をハード的に積んでいるかが鍵です。
• 料金・プラン:衛星リンクは地上より原価が高く、別枠の料金や容量管理になる可能性があります。
• 使い方のコツ:屋内なら窓際や屋上、屋外へ移動、端末は空の見える方向に。初期はメッセージ→音声→データの順で確実性が上がるようです。
よくある疑問Q&A
Q1. 星が見えない夜や雨でも使えますか?
A. 電波は可視光ではないので夜間でも問題ありません。雨の影響は周波数に依存します。低い周波数(L/S/700MHz帯)は比較的強く、Ku/Kaは影響を受けやすいです。
Q2. 屋内でもつながりますか?
A. 低周波なら屋内到達性は高いですが、建物の構造で変わります。窓際・高層階ほど有利です。初期は屋外に出る方が確実だとは思います。
Q3. 電池の減りは?
A. 端末は衛星まで届くよう送信電力や再送が増えることがあり、地上通信より消費が増える可能性があります。必要時のみ有効化・短時間利用がコツです。
Q4. 遅延はどのくらい?
A. LEOなら往復で数十ms~の世界が狙え、音声やビデオ通話でも実用が見込めます。ただしルーティングや地上区間の経路で体感は変動します。
Q5. 海外でも使えますか?
A. 衛星側の提供国・周波数ライセンス・ローミング契約に依存します。国境をまたぐとルールが変わる点は地上網以上に注意が必要です。
技術の現在地とロードマップの見方
• いまは「つながること」の実証から「音声・ビデオ・データの安定運用」へとステップアップしている段階です。
• 次に衛星数の増強・スポットビーム数/容量の拡大・コア網連携最適化が進むほど、可視時間の縛りが小さく、混雑に強くなっていきます。
• 規格面では3GPP Rel-17/18のNTN整備が進み、端末・ネットワーク・衛星が同じルールで賢く動ける時代へ。ここが普及のブースターになります。
最後に
今回ご紹介した日本国内の計画(例:低軌道衛星、対象バンドの検討、提供開始目標など)は、制度・打上げ計画・衛星製造・国際調整など多くの要因で様々変更される可能性があります。最新の公式発表を都度確認しつつ、まずは「圏外を減らす」「非常時の連絡を確保する」という現実的な価値から、生活や仕事に普及していくのでしょう。現在、私たちの生活になくてはならない存在であるスマートフォン。その通信はこれまで、地上の基地局が張り巡らされたネットワークに支えられてきました。しかし、日本の国土は山間部や離島が多く、広大な海に囲まれているため、どうしても電波が届かない「圏外」が残ってしまいます。そうした最後の“隙間”を埋める存在として、今まさに実用化への道のりを歩んでいるのが「衛星ダイレクト通信」です。これは、スマートフォンが直接宇宙の衛星とつながることで、場所を選ばずに通信できる未来のインフラ。携帯電話会社各社が、通信エリアの拡大や災害時の備えとして、この技術に熱い視線を注いでいます。この新たな通信技術は、まさに私たちの通信環境に革命をもたらす可能性を秘めています。災害時に安否確認がしやすくなるだけでなく、登山や釣りといった趣味、仕事での僻地での活動など、これまで電波が届かなかった場所での安心感を大きく高めてくれるでしょう。
将来的には、より多くの衛星が打ち上げられ、通信容量が増加することで、まるで地上にいるかのようにストレスなく通信できる環境が整っていくはずです。衛星ダイレクト通信が普及すれば、私たちは「圏外」という言葉を気にすることなく、より自由に、より安心してスマートフォンを利用できるようになるかもしれません。この技術が私たちの生活にもたらす変化に、これからも目が離せません。

ご訪問ありがとうございます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。
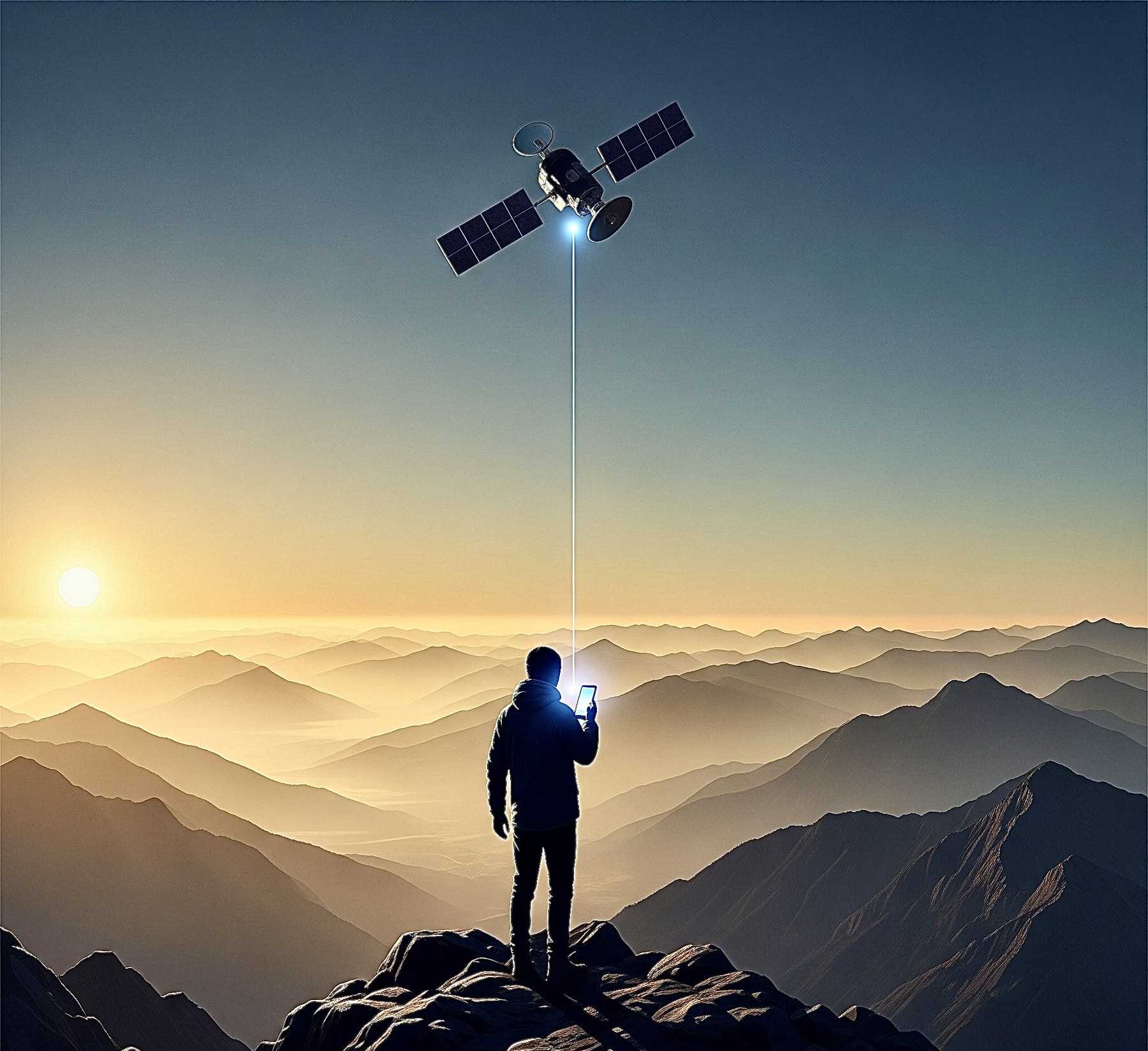
衛星通信とは?スマホのダイレクト通信で実現できることを解説
近年、通信技術の進歩により、従来の地上ベースの通信インフラに加えて、衛星を活用した新たな通信方式が注目を集めています。特に、各携帯電話会社では、通信エリア拡大や災害時の通信確保を目指し、スマートフォンと直接通信する「衛星ダイレクト通信」の取り組みが積極的に進められています。本記事では、衛星通信の基本的な仕組みから、スマートフォンの衛星ダイレクト通信で実現できることまでを詳しく解説します。
衛星通信の基本概念
衛星通信とは、地上と人工衛星の間でデータをやり取りする通信方式です。この仕組みでは、地上の無線局から送信されたデータを、低軌道・中軌道を周回する衛星や静止軌道上に配置された衛星が受信し、地上の目的地に送信します。通信衛星の軌道には、主に「周回軌道」と「静止軌道」の2種類があり、それぞれ異なる特長を持っています。
周回軌道
中軌道(MEO):約2,000~3万6,000km
低軌道(LEO):約500~2,000km
人工衛星1機における通信可能範囲:狭い
静止軌道(GEO)
高度:約3万6,000km
楽天の国内向け商用サービスでは、AST SpaceMobileの軌道高度約700kmを周回する商用衛星「BlueBird Block 2」を中心に活用予定です。試験衛星「BlueWalker 3」と商用衛星「BlueBird Block 1」については、高度約500kmを周回します。
衛星通信の方式
衛星通信には、大きく分けて2つの方式があります。1つは専用端末を利用する方式、もう1つはスマートフォンが直接衛星と通信する衛星ダイレクト通信です。専用端末を利用する方式の実例として、2024年に発生した能登半島地震では、基地局が停電で機能しなくなった地域の避難所や救急医療の現場に、衛星通信サービス「Starlink」の専用端末が提供されました。これにより通信環境が確保され、インターネット回線が利用可能となりました。一方、スマートフォンの衛星ダイレクト通信は、通信エリアの拡大や災害時の通信手段確保を目的に、各携帯電話会社で取り組みが進められています。現在、一部の携帯電話会社から商用サービスの提供が始まっています。
衛星通信で使われる周波数帯について
衛星通信で使われる周波数帯は、それぞれ異なる特性を活かして多様な用途に利用されています。提示された情報を補足する形で、各バンドの主な利用例を以下にまとめました。
Lバンド(1.215~1.71GHz)
特徴: 通信容量は小さいですが、雨や雨雲の影響を非常に受けにくく、安定した通信が可能です。小型のアンテナでも通信できるため、移動体通信に適しています。
主な利用例:
* 衛星携帯電話: イリジウムやインマルサットなどの衛星携帯電話サービスで利用され、地上ネットワークが届かない場所(海上や山岳地帯など)での音声通話やデータ通信に使われます。
* GPS(全地球測位システム): 衛星からの測位信号を受信するのにLバンドが使われています。
* 気象観測: 気象衛星からのデータ送信に利用されます。
Sバンド(1.71~2.7GHz)
特徴: Lバンドと同様に、雨の影響を受けにくいという特性を持ちます。Lバンドよりは広い帯域幅を確保しやすいため、より多くのデータ通信が可能です。
主な利用例:
* 衛星放送: 日本では、携帯端末向けの衛星放送サービス「モバHO!」でSバンドが使われていました。
Cバンド(3.4~7.075GHz)
特徴: 衛星通信が商業化された当初から使われてきた周波数帯で、大容量通信が可能です。雨の影響はKuバンドやKaバンドよりは少ないですが、通信安定性を確保するためには大型のアンテナが必要です。
主な利用例:
* テレビ局間の番組伝送: 地上の通信網を介さずに、テレビ局間で番組素材を送受信する際に使われます。
* 衛星ニュース中継: 災害現場などからの中継で、アンテナを搭載した中継車(SNG:Satellite News Gathering)がCバンドを利用することが多いです。
* 固定通信: 離島や僻地へのインターネット回線提供にも使われます。
Kuバンド(10.6~15.7GHz)
主な利用例:
* 衛星放送(BS/CS): 視聴者が家庭で利用する衛星放送サービス(BS放送やスカパー!など)で広く使われています。
* VSAT(超小型地球局): 企業や店舗のネットワーク構築、遠隔地の監視システムなど、多様な分野で利用されています。
* Starlinkなどの衛星ブロードバンド: ユーザー端末と衛星間の通信にKuバンドが使われています。
Kaバンド(17.3~31GHz)
特徴: 衛星通信で利用される周波数帯の中では最も高く、非常に大容量の通信が可能です。Kuバンド以上に雨や雪の影響を受けやすいため、通信の安定性を確保するための技術が求められます。
主な利用例:
* 次世代の高速衛星通信: 高速インターネットサービスや、通信容量を増やす必要のあるサービスで利用が進んでいます。
* Starlinkなどの衛星ブロードバンド: Starlinkの衛星間通信や、衛星と地上局を結ぶ通信でKaバンドが使われています。
* 軍事通信: 大容量のデータ通信が必要な軍事目的でも利用されます。
衛星通信端末の種類
日本国内で利用されている衛星通信端末の種類は、主に「パラボラ・平面アンテナ型端末」と「携帯電話型端末」の2つに分類されます。
パラボラ・平面アンテナ型端末
- アンテナを固定して設置
- 通信容量が多い
- 特定の方向に電波を集中させる「アンテナ指向性」が強い
- 通信の安定性に優れている
携帯電話型端末
- 通信容量やアンテナの指向性は劣る
- 小型で持ち運びやすいという利点がある
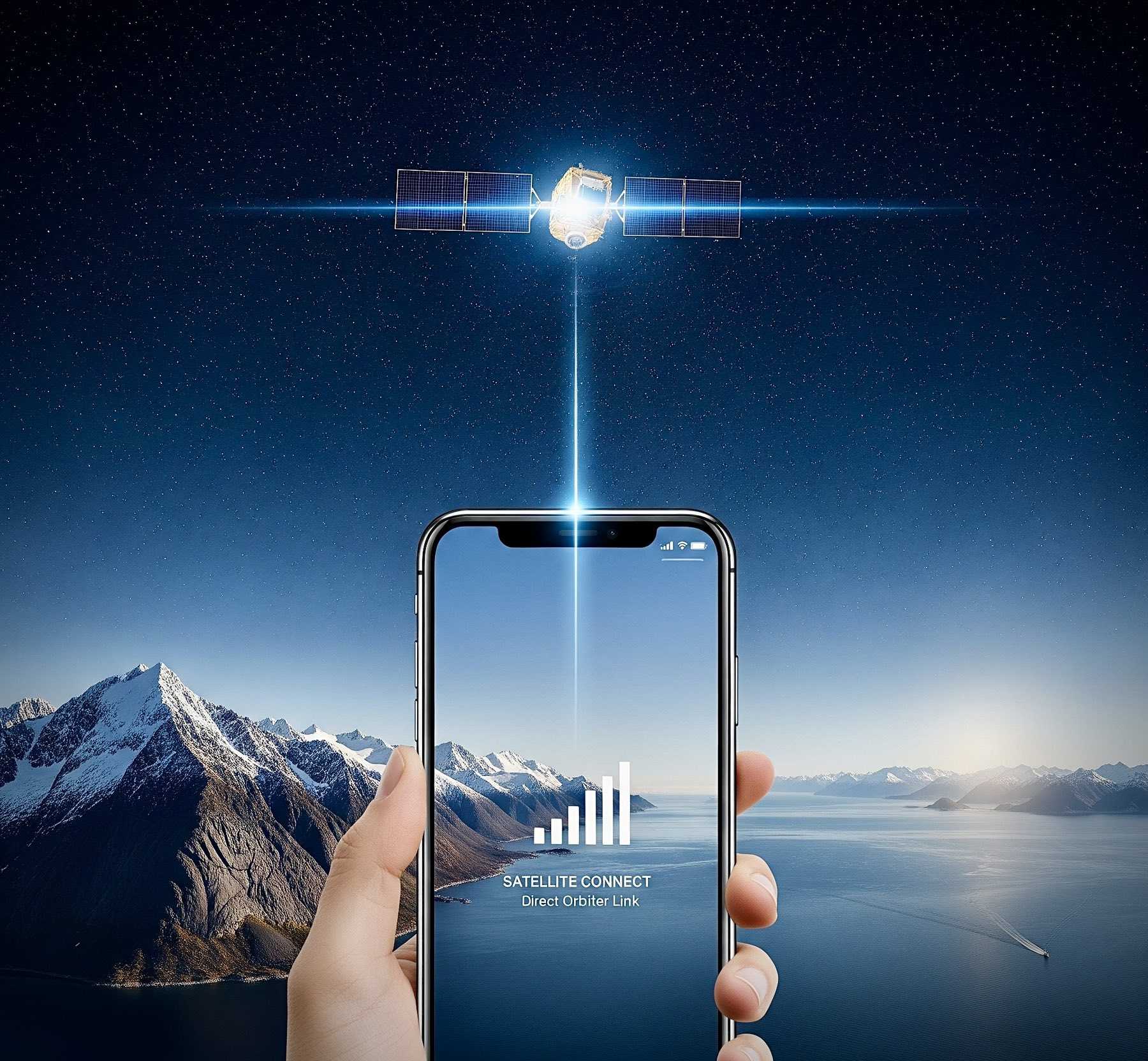
衛星通信のメリット・デメリット
衛星通信には以下のような特徴があります。
メリット:広範囲での通信可能性
地上通信網が整備されていない場所(山奥、離島、海上など)でも利用可能です。衛星通信を利用すれば、山奥や離島、海上など、地上通信網がない場所でもインターネット接続が可能になります。
メリット:災害耐性
災害の影響を受けにくいという特徴があります。災害時には被災地などに衛星用基地局を設置することで、迅速な情報伝達の手段を応急復旧できます。
デメリット:通信遅延
衛星との距離により通信遅延が発生することがあります。特に、地上と人工衛星の距離が遠い静止軌道(GEO)衛星は遅延が発生するため、リアルタイム性が要求される用途には不向きといわれています。これに対して、低軌道(LEO)衛星は、比較的遅延が小さくなります。
デメリット:天候の影響
周波数帯によっては天候の影響を受けやすくなります。KuバンドやKaバンドのような高周波数帯は雨の影響を受けやすく、通信が途切れることがあります。反対に、LバンドやSバンドは雨に強く、より安定した通信が可能です。
デメリット:通信環境の制約
衛星との見通しが取れない場所(トンネル、谷底、建物の陰など)では通信できないことがあります。
スマートフォンの衛星ダイレクト通信で実現できること
各携帯電話会社では、専用端末を介した衛星通信だけでなく、スマートフォンと衛星のダイレクト通信により通信エリア拡大などを目指す取り組みが進められています。
通信エリアの拡大
スマートフォンの衛星ダイレクト通信により、通信エリアの大幅な拡大が期待されています。現在、日本の携帯電話サービスは、人口カバー率が約99%に達している一方で、面積カバー率は日本全土の約70%にとどまっています。人口カバー率とは、全国の人口のうち携帯電話のサービスエリア内に居住する人の割合を指します。一方、面積カバー率は、日本の国土面積のうち、通信が届く範囲の割合を指します。スマートフォンの衛星ダイレクト通信が可能になれば、基地局の電波が届かない山奥や離島、海上など、従来は圏外だったエリアでも、専用端末なしでスマートフォンを利用できるようになる可能性があります。例えば、登山時に山奥で遭難時の連絡手段として役立ちます。これにより、迅速に救助要請を行えるようになるでしょう。各携帯電話会社は、衛星ダイレクト通信の実用化などを進め、日本全土をカバーできる通信インフラの構築を目指しています。
災害時の通信確保
スマートフォンの衛星ダイレクト通信が実用化されれば、災害時にも従来より安定した通信が可能になると考えられています。従来のモバイルデータ通信や光回線は、基地局や光ファイバケーブルが被災することで、通信が途絶えるケースが多くありました。しかし、衛星ダイレクト通信であれば、近隣に基地局がなくても通信できるため、普段使っているスマートフォンを非常時の連絡手段として活用できます。
楽天モバイルの衛星ダイレクト通信への取り組み
楽天モバイルは、米国のAST SpaceMobileとのプロジェクトを推進しており、日本国内で2026年第4四半期のサービス提供開始を目指しています。「Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobile」は、低軌道衛星と市販されているスマートフォンによる直接”高速インターネット通信”(音声・ビデオ通話など)を目指すプロジェクトです。楽天の国内向け商用サービスでは、AST SpaceMobileの軌道高度約700kmを周回する商用衛星「BlueBird Block 2」を中心に活用予定です。試験衛星「BlueWalker 3」と商用衛星「BlueBird Block 1」については、高度約500kmを周回します。
技術的な成果
楽天モバイルとAST SpaceMobileは、既に重要な技術的マイルストーンを達成しています。2023年4月には低軌道衛星によるモバイル・ブロードバンド通信を用いた市販スマートフォン同士の音声通話試験に世界で初めて成功しました。これは、宇宙から送信するモバイル・ブロードバンド・ネットワークと市販スマートフォン端末との通信において、2023年4月26日時点でのAST SpaceMobile調べによる世界初の成果です。さらに2025年4月には、低軌道衛星と市販スマートフォン同士のビデオ通話にも、日本国内で初めて成功しています。これも、宇宙から送信するモバイル・ブロードバンド・ネットワークと市販スマートフォン端末との通信において、現時点でのAST SpaceMobile調べによる成果です。この取り組みは、モバイル通信の広域エリアカバーや災害時の通信インフラの冗長性強化に向けた第一歩となりました。
まとめ:衛星ダイレクト通信の未来展望
衛星通信では、地上と人工衛星間でデータのやり取りができ、基地局からの電波が届かない場所でもインターネットに接続できます。スマートフォンの衛星ダイレクト通信が実用化すれば、光回線が接続できない場所や携帯電話会社の基地局では電波が届かない山奥や離島、海上などでも専用端末なしでスマートフォンで通信できるようになるでしょう。近い将来、通信エリアが広がることでスマートフォンの利用がより快適になりそうです。
衛星通信とは?スマホのダイレクト通信で実現できることもわかりやすく解説
https://network.mobile.rakuten.co.jp/sumakatsu/contents/articles/2025/00385/

下記からは私個人の私見と考察です。
AST SpaceMobileの衛星計画全体
同社は2024年9月に「BlueBird」商用衛星5基を打ち上げ済みで、さらに「Block 2 BlueBird」衛星を2024年11月に発表しており、最大で 60基の衛星を2026年までに打ち上げる計画であるとされています。
https://www.fierce-network.com/wireless/ast-spacemobile-and-problem-delivering-broadband-space
https://en.wikipedia.org/wiki/AST_SpaceMobile
周波数帯(バンド)について
• Light Reading(外部報道)
• 候補として「700 MHz(プラチナバンド)」または「1800 MHz(1.8 GHz帯)」のいずれかが検討されているが、決定は「来年中(2026年までに)」になる見込み、と報じられています。
https://www.lightreading.com/satellite/rakuten-targets-late-2026-for-mobile-satellite-launch-with-ast
https://forbesjapan.com/articles/detail/78869
• Impress Watch(業界報道)
• 三木谷浩史氏(楽天)は、プラチナバンド(700 MHz帯)で構築したい意向を示しており、低い周波数帯の電波伝播特性を活かすことで、屋内でもつながりやすい環境を目指しているとも報じられています。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2009449.html
「人口カバー率99%」でも“圏外”がなくならない理由
日本の携帯は人口カバー率こそ非常に高い一方で、面積カバー率は約7割前後にとどまります。理由はシンプルで、山間部・離島・海上など「人が少ない」「基地局の建設や保守のコストが高い」地域が広く残っているからです。この“最後の1割~3割”をどう埋めるかが長年の課題で、「空から覆う」衛星ダイレクト通信は、その抜けを一気に埋める有力手段だと思います。
なぜ衛星ダイレクト通信は難しいのか(でも実現しつつあるのか)
スマホは小さな電力・小さなアンテナで設計されています。ふつうは近くの地上基地局(数百メートル~数キロ先)に向けて電波を飛ばします。ところが衛星は数百~数千キロ上空。
このギャップを埋めるために、衛星側では次の工夫が使われます。
• 巨大なフェーズドアレイアンテナ:衛星が空から“細かいスポットビーム”を何十~何百本もつくり、地上のスマホに合わせて狙い撃ち(集中的に電力を届ける)します。
• 端末に近い周波数を使う:地上携帯と同系の周波数(例:700MHz帯や1.8GHz帯などの低~中周波)を使えば、建物内や森の中でも届きやすい特性を活かせます。
• ドップラー・遅延補正:衛星は秒速数キロで動くため周波数のズレ(ドップラー)やタイミングのズレ(遅延)が生じます。3GPPのNTN(非地上系)規格では、これらを端末・衛星・ネットワーク側で賢く吸収する仕組みが定義されつつあります。
結論として「端末はそのまま」「空側を賢く」が、直近のダイレクト通信の基本設計思想のようです。
軌道高度が違うと何が変わる?(GEO / MEO / LEOの実感値)
• GEO(静止軌道, 約3.6万km):1基で広く覆えるが、遅延が大きい(往復で数百ms)ため、動画会議やゲームでは違和感が出やすいです。
• MEO(中軌道, 数千~約2万km):カバーと遅延のバランス型。
• LEO(低軌道, 数百~数千km):遅延が小さく(往復で数十ms級まで下げやすい)、音声・ビデオ・データの汎用に向きます。ただし可視時間が短いため、多数の衛星で継ぎ目なく覆う発想が必須です。
私が調べたところ、スマホ直の使い勝手を高めるにはLEOが本命になりやすい、というのが近年の潮流のようでした。
周波数帯は“つながりやすさ”と“太さ”のトレードオフ
• 低い周波数(例:700MHz帯):回り込みやすく屋内・森林・雨天に強い。ただし帯域(通信の太さ)を広く取りにくいため、エリアの底上げ・音声・メッセージ・基本データに向きます。
• 中~高い周波数(1.8GHz帯、さらに上):容量(太さ)を稼ぎやすい半面、雨や遮蔽物に弱くなります。
衛星ダイレクト通信の黎明期は「まずつながること」「災害時に役立つこと」を重視するため、低周波優先→段階的に容量拡大という移行が現実的のようです。
1日中いつでも繋がるのか?(可視時間とセル容量の考え方)
LEO衛星は空を高速で流れます。いつでも頭上にいるわけではありません。実際の使い勝手は次の2点で決まります。
1. 可視時間:自分の頭上近くに「その周波数を照射してくれる衛星」が来る時間帯。初期は時間や方角の制約が残る可能性があります。
2. セル容量:ひとつのスポットビームに同時に収容できる端末数・スループットの上限。初期段階はメッセージ・音声中心、段階的にブロードバンドへ、という流れが現実的です。
「どこでも、常時、地上5G級の太さが出る」ではなく、“圏外を作らない”、“非常時でも連絡できる”価値から普及が始まり、徐々にリッチ化が進んでいくのではないでしょうか。
スマホ側は何を準備すればよい?
• ソフト更新(OS/キャリア設定):NTN対応や周波数・事業者情報の追加で、アップデートが必要になる場合があります。
• 周波数対応:お手持ち端末が対象バンド(例:700MHz帯や1.8GHz帯相当)をハード的に積んでいるかが鍵です。
• 料金・プラン:衛星リンクは地上より原価が高く、別枠の料金や容量管理になる可能性があります。
• 使い方のコツ:屋内なら窓際や屋上、屋外へ移動、端末は空の見える方向に。初期はメッセージ→音声→データの順で確実性が上がるようです。
よくある疑問Q&A
Q1. 星が見えない夜や雨でも使えますか?
A. 電波は可視光ではないので夜間でも問題ありません。雨の影響は周波数に依存します。低い周波数(L/S/700MHz帯)は比較的強く、Ku/Kaは影響を受けやすいです。
Q2. 屋内でもつながりますか?
A. 低周波なら屋内到達性は高いですが、建物の構造で変わります。窓際・高層階ほど有利です。初期は屋外に出る方が確実だとは思います。
Q3. 電池の減りは?
A. 端末は衛星まで届くよう送信電力や再送が増えることがあり、地上通信より消費が増える可能性があります。必要時のみ有効化・短時間利用がコツです。
Q4. 遅延はどのくらい?
A. LEOなら往復で数十ms~の世界が狙え、音声やビデオ通話でも実用が見込めます。ただしルーティングや地上区間の経路で体感は変動します。
Q5. 海外でも使えますか?
A. 衛星側の提供国・周波数ライセンス・ローミング契約に依存します。国境をまたぐとルールが変わる点は地上網以上に注意が必要です。
技術の現在地とロードマップの見方
• いまは「つながること」の実証から「音声・ビデオ・データの安定運用」へとステップアップしている段階です。
• 次に衛星数の増強・スポットビーム数/容量の拡大・コア網連携最適化が進むほど、可視時間の縛りが小さく、混雑に強くなっていきます。
• 規格面では3GPP Rel-17/18のNTN整備が進み、端末・ネットワーク・衛星が同じルールで賢く動ける時代へ。ここが普及のブースターになります。
最後に
今回ご紹介した日本国内の計画(例:低軌道衛星、対象バンドの検討、提供開始目標など)は、制度・打上げ計画・衛星製造・国際調整など多くの要因で様々変更される可能性があります。最新の公式発表を都度確認しつつ、まずは「圏外を減らす」「非常時の連絡を確保する」という現実的な価値から、生活や仕事に普及していくのでしょう。現在、私たちの生活になくてはならない存在であるスマートフォン。その通信はこれまで、地上の基地局が張り巡らされたネットワークに支えられてきました。しかし、日本の国土は山間部や離島が多く、広大な海に囲まれているため、どうしても電波が届かない「圏外」が残ってしまいます。そうした最後の“隙間”を埋める存在として、今まさに実用化への道のりを歩んでいるのが「衛星ダイレクト通信」です。これは、スマートフォンが直接宇宙の衛星とつながることで、場所を選ばずに通信できる未来のインフラ。携帯電話会社各社が、通信エリアの拡大や災害時の備えとして、この技術に熱い視線を注いでいます。この新たな通信技術は、まさに私たちの通信環境に革命をもたらす可能性を秘めています。災害時に安否確認がしやすくなるだけでなく、登山や釣りといった趣味、仕事での僻地での活動など、これまで電波が届かなかった場所での安心感を大きく高めてくれるでしょう。
将来的には、より多くの衛星が打ち上げられ、通信容量が増加することで、まるで地上にいるかのようにストレスなく通信できる環境が整っていくはずです。衛星ダイレクト通信が普及すれば、私たちは「圏外」という言葉を気にすることなく、より自由に、より安心してスマートフォンを利用できるようになるかもしれません。この技術が私たちの生活にもたらす変化に、これからも目が離せません。

ご訪問ありがとうございます。
ただいま楽天グループでは楽天従業員からの楽天モバイル紹介キャンペーンを実施中です。 下記からログインして楽天モバイルにご契約いただくと、最大14,000ポイントプレゼントいたします!よろしくお願い申し上げます。
https://r10.to/hYYGNa
【楽天従業員から紹介された方限定】楽天モバイル紹介キャンペーン!回線お申し込みごとにポイントプレゼント!上記URLからどなたでもお申し込みいただけます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[人工衛星] カテゴリの最新記事
-
宇宙からの電話:楽天モバイルとAST Space… 2025.08.01
-
🚀 宇宙からの電波でスマホがサクサク!? … 2025.02.12
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










