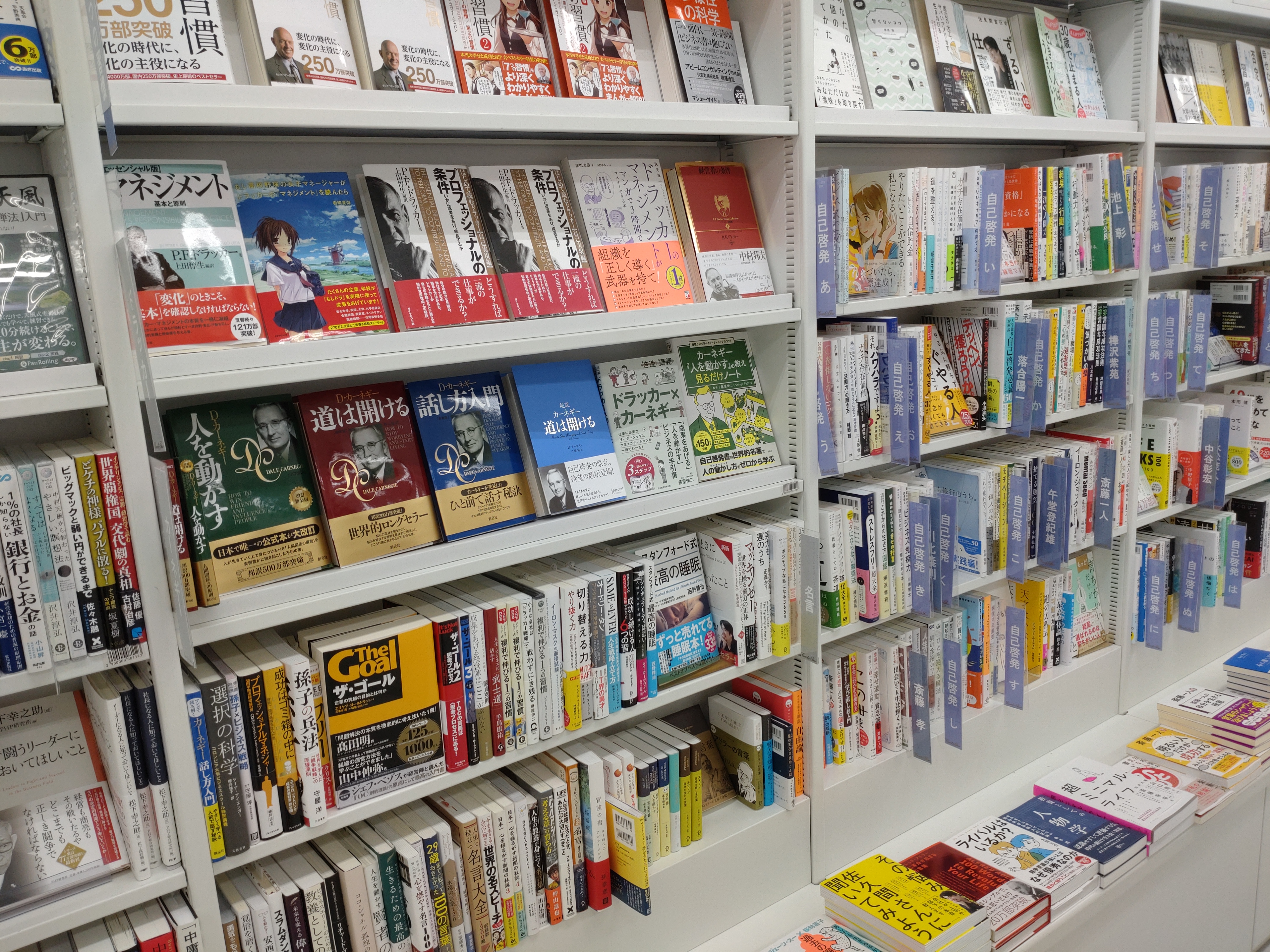全123件 (123件中 1-50件目)
-
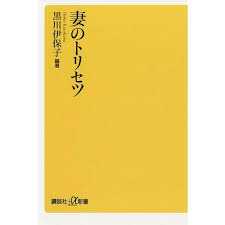
妻のトリセツ 黒川伊保子
黒川先生の「妻のトリセツ」を紹介します。この本を読んだきっかけは、妻との関係を良くしたいと思ったからです。十分に参考になりましたので紹介します。①女性の会話の目的は共感である。解決方法は求めていない。②「えこひいきされたい。」、「大切にされたい。」という気持ちは、女性の生殖本能である。③自分が気持ちいいい、自分が楽しい、自分がちやほやされるのが女子にとっては何より大切。④男性脳は「1番」と言われるのが好き。たくさんの人の中で、比較されて「あなたが一番」と言われたら気分が良い。⑤ゴール指向の男性脳は目標地点に最短時間、最短距離でたどり着きたい。⑥妻を侮辱する夫の対応は、娘の未来を幸せにしないし、息子の将来にも影を落とす。⑦家で一番偉いのはお父さんと言われる父親がいてこそ、息子のモチベーションは上がり、自我を確立する。以上の他にも参考になったことが多く書いてありました。男性と女性の脳(考え方や感じ方)は異なるから、その点を考慮した言動をすべきであるといった内容でした。また、夫が妻に対して不適切な対応をすることで子どもへの悪影響にまで触れていました。人間関係に悩んでいる方にもおすすめの1冊です。
2025.11.14
コメント(0)
-
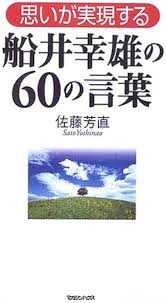
船井幸雄の60の言葉 佐藤芳直
佐藤芳直先生の「船井幸雄の60の言葉」を紹介します。数年前になりますが、S・Kワークスの社長である佐藤芳直先生のセミナーに何度か出席したり、月刊オーディオBOOKを購入したりと勉強していました。その中で佐藤先生の師匠である船井幸雄さんがよく登場していました。興味を持ちましたので、その方に特化した本を購入して読みました。心に響く言葉ばかりでした。特に共感した部分を以下に記述します。①長期楽観の見通しが必要である→目先は大切。でも未来はもっと大事。②素直、プラス思考、勉強好きが器を大きくする。③教育とは子どもの可能性を引き出すことでしかない。可能性は長所を伸ばし続けることである。④人間の能力にはほとんど差がない。性格で差がつく。⑤偉くなる人は相手の年齢や立場で対応を変えない。⑥未来は努力という蓄積からの利子によって変わってくる。⑦短所を直そうとすると自分の長所まで見失ってしまう。⑧失敗とは次の挑戦への入口に過ぎない。以上の他にもたくさんの言葉があります。「自分の成長が停滞しているかも?」と感じた時に読んでほしい1冊です。改めて気持ちが引き締まりました。
2025.11.08
コメント(0)
-
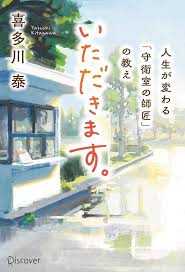
いただきます 喜多川泰
私が好きな作家である喜多川泰先生の新作「いただきます」を紹介します。喜多川先生の著作は読んだ後に清々しくなることが多いです。学園ものが多いのですが、読むたびに学生だった頃を思い出し、「こんなことを考えて学生生活を送っていたらな。」と過ぎた時間を後悔してしまうこともあります。主人公は高校卒業したての少年です。遊ぶお金がほしくて、楽して稼ぐ方法を常に考え、手を抜きつつバイトをしています。そんな主人公が大学の守衛の仕事をしますが、そこでの様々な年齢や経歴を重ねた人たちと出会い衝撃を受けます。自分と他人との比較に苦しむ中で、価値観を大きく変えて成長していきます。これ以上はネタバレになってしまいますので、ここまでにします。やはり喜多川先生の作品は前向きな気持ちになります。素敵な1冊でした。
2025.11.07
コメント(0)
-
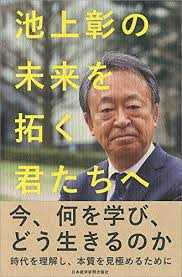
「池上彰の未来を拓く君たちへ」 池上彰
池上彰先生の「池上彰の未来を拓く君たちへ」を紹介します。テレビでよく見る池上先生。端的な言葉でわかりやすく表現する先生が教育についてどのような考え方を持っているのか興味が湧き読んでみました。共感できる部分がいくつかあったので紹介します。①現場での経験を積み、人間力を磨くべきである。②人生に無駄な時間などない。③人生は明確な正解のない難題ばかりである。自ら問いを立てて、答えを求めて学ぶことは、やがて人生の岐路に立ったときに答えを出す力になる。④教養を身につけ、自分の頭で考え抜く力をきたえる「リベラルアーツ教育」の役割が大切である。⑤戦いにおいては、戦わずに敵の兵を屈服させることが最上である。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。表紙からは、学生に向けてのメッセージが強い本と思いましたが、私も含め社会人になってからでも遅くない内容でした。改めて気持ちが引き締まる1冊です。
2025.11.02
コメント(0)
-
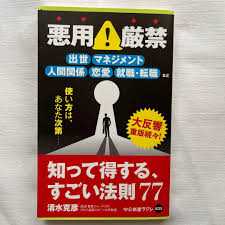
知って得する、すごい法則77 清水 克彦
清水 克彦先生の「知って得する、すごい法則77」を紹介します。悪用!厳禁と大きく表示されている表紙に衝撃を受けて思わず購入してしまいました。 この本は77の法則を6章(職場編、管理職編、人間関係編、自分を高める編、男女の人間関係編、子どもと自分を伸ばす編)に分けてあり、わかりやすい構成です。自分が気になっている部分を読むだけでも十分価値があると思います。私が勉強になった法則をいくつか紹介します。①職場編の「ロミンガーの法則」 人の成長は7:2:1=実践:上司や指導者:読書②職場編の「エメットの法則」 仕事を先延ばしすればするほど、時間とエネルギーを消耗する。③人間関係編「7対3の法則」 会話が相手が7割を意識することで良好な人間関係を築くことができる。④自分を高める編「1万時間の法則」 専門性を発揮し極めるためには1万時間必要である。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。是非、皆さんに読んでほしい1冊です。
2025.11.01
コメント(0)
-

「疲れない人」の習慣、ぜんぶ集めました。
工藤孝文先生監修の「疲れない人」の習慣、ぜんぶ集めました。を紹介します。「~」の習慣、ぜんぶ集めましたシリーズが大好きで、いくつか読書しました。寒さが厳しくなってきたこの時期に、疲れない習慣を手に入れようと思いました。この本は、第9章に分けられており、2ページに1つの習慣を取り上げています。運動、睡眠、考え方、姿勢、楽しみ方などすぐに実践できることばかりでした。挑戦しようと思った習慣をいくつか紹介します。①睡眠~寝る3時間前までに夕食を済ますことで睡眠の質が向上する。②運動~筋肉トレーニングするのならば、スクワットが良い。理由は下半身に筋肉が集中しているから。③考え方~コントロールできないことに悩むのは時間の無駄である。④考え方~楽に生きることのできる人は、まわりから「いい人」と思われなくても平気な人である。⑤考え方~心が疲れない人は、嫌な相手の良いところも探そうとする人である。以上の他にも参考になることがたくさん書かれていました。ちなみに、「疲れてしまう習慣」についての章もあり、3つぐらい当てはまっていたので、まずはそこを改善するように頑張ります。
2025.10.31
コメント(0)
-

新管理職1年目の教科書 櫻田 毅
櫻田先生の「新 管理職1年目の教科書」を紹介します。この本を読んだきっかけは、私が部下を持つ立場になり、日々四苦八苦しているからです。現状を良い方向にするためにこの本から学ぼうと思いました。共感する部分を紹介します。①必ずいつまでにするのかの期限を共有する。②「自分で成長して結果を出す」という気概無くしては、良い仕事ができない。③新しい仕事が来たら、少しだけ取り掛かり、難易度を測ったり、内容を理解し、ゴールからの逆算をする。④仕事ができる人のメールの返信は速い。⑤締め切り間際の滑り込みセーフをやめる。⑥上司が部下を見ることの10倍も部下は上司をよく見ている。⑦仮説・検証の繰り返しで正解にたどり着くことの繰り返しが成長する。以上の他にも勉強になることがたくさん書いてありました。私は外資系管理職ではありませんが、十分に参考になる1冊でした。
2025.10.25
コメント(0)
-
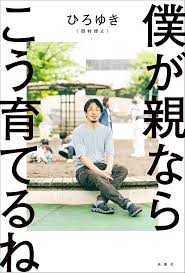
僕が親ならこう育てるね ひろゆき
ひろゆき先生の「僕が親ならこう育てるね」を紹介します。ひろゆき先生のユーチューブを何度か見ています。その中で、教育についてのコメントがなかなか本質をついているように感じました。子育て本を出していると知り、購入しました。面白いなと感じたところを紹介します。①日本の教育は昔ながらの正解に囚われている。②修復可能な失敗は子どものうちになるべく多く経験した方がよい。③子どもはその場だけの刹那的な判断で動くものである。④社会は自分が味わった苦難を次世代に味わせないように試行錯誤しながら進むことで発展していく。⑤健全な子どもを育てるためには、親が健全であることが重要である。⑥学習することの面白さをわからずに勉強しなかった親が子どもに学習することの面白さを教えることはできない。以上の他にも、スバっと切るような物言いで子育てや教育について述べています。言い過ぎだと感じるところもありますが、本質をついているところもあります。読んでいて、爽快になる1冊です。
2025.10.24
コメント(0)
-

リーダーの仮面 安藤 広大
安藤先生の「リーダーの仮面」を紹介します。本の表紙に「いい人になるのは、やめなさい。」という言葉に心を惹かれて思わず購入してしましました。参考になった記述を紹介します。①リーダーはルールと目標を設定して、部下との距離を置き、部下に仕事をまかせる。②リーダーは群れの先頭の鳥になってはいけない。プレイヤーにはなってはいけない。③集団一人一人の差が縮まりながら全体が伸びていく。これが成長である。④組織適応能力を含めて「優秀」と評価する。組織適応能力:能力=1:1⑤知識は経験と重なることで「本質」になる。だから、部下に経験させる。経験とともにしか、成長はありえない。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。私は特にリーダーはプレイヤーになってはいけない。という部分が心に響きました。管理職1年目の方におすすめの1冊です。
2025.10.18
コメント(0)
-
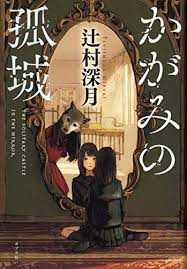
かがみの孤城 辻村深月
辻村深月先生の「かがみの孤城」を紹介します。辻村先生の作品はいくつか読みましたが、本屋大賞、映画化と多くの方が知っているであろう「かがみの孤城」をやっと読破しました。少しひねくれた性格の私は、みんなが読んでいる本、みんなが見ている映画を避けてしまします。もっと早く読んでおけばと少し後悔しています。あらすじは、不登校で部屋に閉じこもっていた中学1年生の女子の主人公の部屋の鏡が光り出し、鏡をくぐり抜けるとお城にたどり着きます。その城には同じ境遇の7人が集まっており、城の中の鍵を見つけたものが願い事を叶えることができると言われ、その鍵を探す中でいろいろなことに気付いていくお話です。あらすじだけ読めば、ドラえもんの秘密道具の鏡で、ドラゴンボールの願いが叶うシステムと感じてしまうかもしれませんが、そうではありません。登場人物一人一人の人生を掘り下げていく内容です。私が中学生の時に出会いたかった本です。中学・高校生だった頃を思い出す作品です。
2025.10.17
コメント(0)
-
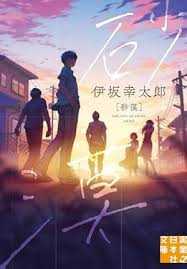
「砂漠」 伊坂幸太郎
伊坂先生の「砂漠」を紹介します。伊坂幸太郎のファンである友人の勧めで読みました。その友人曰く、「この本だけ伊坂先生らしくない。」「逆にそこが良いと言っていました。」私自身は伊坂先生の本を3冊程度しか読んだことがないので、「伊坂先生らしさ」に気づくまでに至っていないのですが、友人の熱量に負けて読みました。あらずじは、仙台市にある大学に入学したばかりの主人公を中心に4年間の大学生活を振り返っていきます。「スプーン曲げ」や「麻雀」など46歳の私が過ごした大学生活と似ており、「ノスタルジック」に浸ることができました。現在は、いつでもどこでも早く情報が手に入ります。情報がないと不安になる人も多いです。そのような時代の中で改めて、平凡な何もない出来事の中に喜びや悲しみを見つけていくことの大切さを感じました。ゆっくりと時間が流れていたと感じる自分の大学生活を振り返りながら、あの頃はよかったなと感じることのできる作品です。ちなみに私の息子も現在仙台市の大学2年生ですので、この偶然に驚きました。いろいろな意味で友人から紹介していただいて本当に良かったと思いました。
2025.10.12
コメント(0)
-
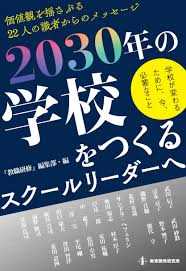
2030年学校をつくるスクールリーダーへ
22名の有識者が教育について述べている本です。あらゆる分野の有識者がこれからの教育のあるべき姿を様々な方向から論じています。共感できる部分が数多くありましたので、紹介します。①正解をほしがるのは、みんなと同じであることの安心感を得たいからである。②上から言われたとおりにやっている状態では、自分たちがなぜ、それをやっているか返答できない。クレームを跳ね返せない。③自分が幸せで満たされれば、不満を抱くこともなく、他人が何をしようと気にならない。④人と出会えば傷つく。でも、人と出会うことが人の幸せである。⑤上である管理職は、部下の持っている能力や知識をいかに引っ張っていくかが重要である。⑥指導者に求められる資質は知性、説得力、肉体的耐久力、自己制御能力、持続する意思の5つである。以上の他にも心に響く文がたくさんありました。改めて、22名の方の教育に関する見え方に感心しました。
2025.10.11
コメント(1)
-

「続けられる人」の習慣、ぜんぶ集めました。 吉井雅之
吉井先生の「続けられる人の」の習慣を、ぜんぶ集めました。を紹介します。吉井先生の著作をいくつか読みました。やはり、小さい生活習慣を積み重ねることで、理想の生活習慣になり、更に思考を良い方向に導いていくのではないかと感じております。この本では、「運動」、「貯蓄」、「ダイエット」、「読書」、「日記」、「早起き」など生活習慣にしたいが、なかなかできないことに特化して、始めるきっかけのコツや、長く続ける考え方を紹介しています。私は、「貯蓄」、「早起き」に興味がありましたので、その部分で共感したことを紹介します。①続けようと思ったことに、理想の自分像を描き「ゴール」を設定する。②「貯蓄編」…ネットショッピングで購入したいと思ったら、1週間待って、本当に必要かを考える。③「貯蓄編」…必要以上にコンビニエンスストアなど高い値段の物を購入しない。④「貯蓄編」…貯蓄を目的に毎日の食費を節約すると健康を損なってしまう。だから、外食を控えるようにする。⑤「早起き編」…起きる時刻を設定したら、逆算して寝る時刻を考える。⑥「早起き編」…寝る前にスマホの画面を見ない。⑦「早起き編」…寝室のカーテンを開けて寝ると朝の光が差し込んで快適に早起きができる。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。なにより、生活習慣にしたいことを項目に分けて解説しているのがわかりやすかったです。
2025.10.10
コメント(0)
-
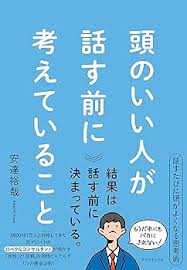
頭のいい人が話す前に考えていること 安達裕哉
安達先生の「頭のいい人が話す前に考えていること」です。自分の周りの仕事が速く効率的に行うことのできる方は、「話が短くて、わかりやすい。」です。逆に「話が長く、何を言っているか分からない。」方もいます。当然、後者の方は仕事効率が悪いです。仕事を効率的にこなすことのできる方の話し方には技術があると思い。この本を購入しました。重要だなと感じた部分を紹介します。 ①一方的に自分のことを話すのではなく、相手の求めていることに対しての話をすることができる。②まずは、相手の言っていることをすべて聞いてから求めていることを話す。③絶対に感情的にならない。④相手の話を言語化して要約できるようにする。⑤相手のレベルに合わせて説明できるようにする。⑥結論から話す⑦事実と意見を分けて話すことが重要である⑧褒められようとしてペラペラしゃべらない。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。私自身も部下に指導する立場でもあるので、わかりやすい話し方をしていきたいです。
2025.10.04
コメント(0)
-
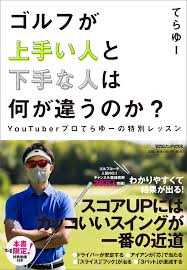
ゴルフが上手な人と下手な人とは何がちがうのか? てらゆー
てらゆー先生の「ゴルフが上手な人と下手な人とは何がちがうのか?」を紹介します。てらゆー先生の「スイング大全」、「スコアメイク大全」の2冊を読破し、実践しています。徐々にですが、ショットが安定して、再現性が高くなってきました。更に技術を高めるべく、もう1冊購入しました。ラウンド中に意識していることを紹介します。①スイング後のフィニッシュでしっかりと静止すること。②フィニッシュは左の足が伸び、左足のかかと寄りに重心が移動する。③ドライバーは肩の力、腕の力を抜いて、クラブを軽く握る必要がある。④つま先上りのショットはクラブを短く持ち、やや右を狙う。フィニッシュは振り切らないで途中で止める。以上の他にも技術が向上する部分がたくさんありました。ゴルフに伸び悩んでいる方にはおすすめの1冊です。
2025.10.03
コメント(0)
-
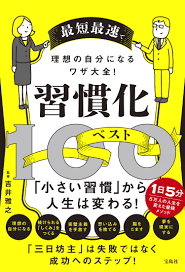
最短最速で理想の自分になるワザ大全!習慣化ベスト100 吉井雅之
吉井先生の「最短最速で理想の自分になるワザ大全!習慣化ベスト100」を紹介します。吉井先生の本の紹介は2冊目です。講演会で吉井先生のお話を聞いて、興味を持ちこの本を読んでみました。共感できる部分がありましたので紹介します。①より早く成功をつかむためには、うまくいっている人のやり方を調べて、徹底的に真似をする。②仕事に行き詰るのは、過去のやり方にこだわっているからである。③〇日までにやる。〇週間までに〇回やる。などやると決めたことの中に数字を入れるべきである。④健康を保つ基本は、いい睡眠をとって、朝日を浴びて、たくさん歩き、人とコミュニケーションをとることである。⑤自分ではどうにもならないことを心配しても意味がない。⑥「笑顔」、「感謝」、「コミュニケーション」がよい人間関係をつくる。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。内容ごとに分類化され、100項目が記述してありますのでとても読みやすいです。皆さんも生活習慣に取り入れてみたい行動や考え方があると思いますので、読んでみて下さい。
2025.09.27
コメント(0)
-
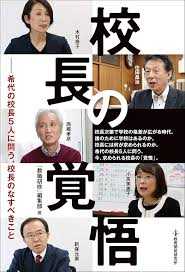
校長の覚悟
校長の覚悟を紹介します。5名の校長先生が記事を書いています。身近にある学校ですが、少子化、不登校、いじめ、モンスターペアレントと様々な課題を抱えていると報道で目にします。「教育は未来の投資である。」と経営者の多くが言っています。学校のリーダーである「校長」のマネジメントに興味を持ち、この本を読みました。共感する部分がありましたので紹介します。①学校が目指すべきゴールは「20年後の社会で活躍できる子どもの育成」である。②子どもの非認知能力をたかめるためには、否定しないこと、話を聞くこと、結果でなくて過程を評価することが重要である。③子どもの課題をその子の家庭や保護者のせいにしてはいけない。④先生が幸せでないと子どもに対して良い教育を提供できない。⑤理想の学校とは、「生徒・保護者から信頼される学校」、「教職員が安心して働ける学校」、「地域に貢献する学校」である。⑥「できない理由」よりも「どうすればできるか?」を考えるべきである。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。改めて、校長先生は「子どもの教育」、「職員の心身の健康」、「地域貢献」と求められるものが多いなと感心しました。
2025.09.26
コメント(0)
-
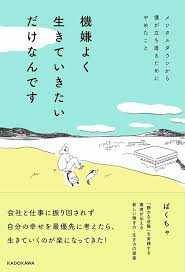
機嫌よく生きていきたいだけなんです ぱくちゃ
ぱくちゃ先生の「機嫌よく生きていきたいだけなんです」を紹介します。この本を読んだきっかけは、職場の人間関係に悩んでた時にユーチューブで紹介されていたので興味を持ち、購入しました。読後は気分も上がり、価値ある1冊となりました。参考になった部分をいくつか紹介します。①仕事はやりがいよりも環境を重視した方が長続きする。②嫌われる勇気を持つこと2:7:1 2=好かれている人 7=何も思ってない人 1=嫌われている人この割合は変わらないから、嫌われることは仕方がない。③苦手なことは克服しなくてよい。全力で逃げるべきである。④生活習慣を改善する。太陽の光を浴びる。運動をする。睡眠時間を確保するなど体調を意識すると気持ちが上がる。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。「過去は変えることができないが、未来は変えることができる。」と思っていた私ですが、「過去を失敗としていつまでも引きずっているか、それとも学ぶことができて良い経験だった」と捉えるかは自分次第であると書いてありました。こういう考え方もあるなと感心しました。
2025.09.20
コメント(0)
-
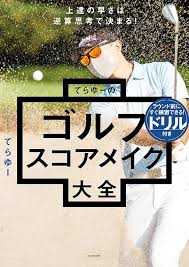
てらゆーのゴルフスコアメイク大全 てらゆー
てらゆー先生のゴルフスコアメイク大全を紹介します。ゴルフが趣味なのですが、なかなか上達しません。もう少し上手に打てないかなと悩んでいたところユーチューブでてらゆーさんの動画を拝見し、てらゆーさんが書いた「ゴルフスイング大全」を購入。熟読して、打ちっ放し場で試してみるといつもより真っ直ぐな打球が出ました。これは、上達したと思い翌日にラウンドしましたが、いつも通りのスコアでした。真っ直ぐな打球の頻度が少し上がったのにスコアが変わらない。スコアメイクには知識が必要と感じた私は続編の「ゴルフスコアメイク大全」を購入しました。数多くのスコアメイク方法が書かれていましたが心に大きく刺さった内容が1つあったので紹介します。①フルスイングで自信がある番手のクラブを見つける例えば、100ヤードが得意ならば残り100ヤードを残していくような逆算が必要である。以前の私はとにかくグリーンに近づくことばかり考えて、スプーンや大きい番手のアイアンを使用し、OBになったりバンカーに入ったりしていました。余計な打数ばかりでした。グリーンを直接狙うのは100ヤードからだと割り切ることが大切だそうです。これをはやく実践したくワクワクしています。以上の他にも写真付きでスコアメイクの方法が書かれてあります。とてもわかりやすいです。
2025.09.19
コメント(0)
-
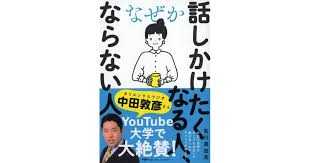
なぜか話しかけたくなる人、ならない人 有川真由美
有川真由美先生の「なぜか話しかけたくなる人、ならない人」を紹介します。有川先生の書かれた本はよく読みます。今回もわかりやすくて、前向きになる本でした。勉強になった部分を紹介します。①「肯定的な言葉」と「ゆっくり丁寧に」の2点を意識すると自分も気分がよくなるし、話しかけてもらいやすい。②挨拶は相手の目を見て、顔を見て、名前とセットで行う。③尊敬されている人は自分から功績や長所を語らない。④長い雑談より、短い雑談の回数を増やすことの方がよい。⑤自分の価値観を押し付ける人になってはいけない。⑥相手に「お願い」ではなく、「相談」をするように心がける。⑦人の運が開けるかどうかは、その人の努力よりも出会う人によって決まる。以上の他にも感銘を受けた記述がいくつもありました。是非、読書して、みんなから話しかけられる存在になってほしいです。
2025.09.13
コメント(0)
-

こころの薬箱 大谷徹奘
大谷徹奘(てつじょう)先生のこころの薬箱を紹介します。大谷徹奘さんは僧侶であり、奈良にある法相宗は大本山薬師寺の執事長です。この本を読んだきっかけは、大谷さんの講演会に参加し、感銘を受けたからです。素敵なことが書かれていましたので、紹介します。①クレームも素直に聞くことができれば、自分を強くすることもできる。②相手の心を忘れて、自分の思いだけで生きてはいけない。自分のことだけを主張して、相手を受け入れない。これを我が強いという。③自分が苦しいと思えば、苦しい世界が目の前に広がり、ありがたいと思えば、ありがたい世界が目の前に広がる。④幸せの条件は良い人間関係にある。他人の喜びを自らの喜びのごとく受け止めるとよい。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。大谷徹奘さんは、普段から「より良い生き方」を皆さんに説いていらっしゃる方ですので、書かれていることに重みを感じました。
2025.09.12
コメント(0)
-
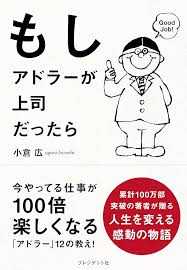
もしアドラーが上司だったら 小倉 広
小倉 広先生の「もしアドラーが上司だったら」を紹介します。この本を読んだきっかけは、もともとアドラーの心理学に興味があり、職場の人間関係に生かすことができないかと思いました。新入社員がアドラー心理学を学んだ上司と出会い、物事の考え方を変化させ、自分自身を成長させていく物語に解説としてアドラー心理学が書かれており、わかりやすかったです。共感できる部分がいくつもあったので紹介します。①できていないことより、できたことの注目すべきである。できなかったと嘆くよりも、できていることに注目して心を向上させる方がよい②仕事ができなくても、自分の存在価値は変わらない。仕事ができる機能価値と自分の人間性の部分の存在価値は切り離して考えるべきである。会社の評価が低い、仕事でミスをしたからと言って、自分自身を全否定することはない。③ 他人を喜ばせることを心がける人間は他人の役に立つことで自分の存在価値を確認している。人に感謝されるように心がける必要がある。④ 失敗から何を得ることができたのかを考える癖をつける。人は必ず失敗するものである。その失敗で落ち込むのか?それとも失敗から学ぶのかは考え方次第である。マイナス部分にあるプラスの部分を見つける習慣が必要となる。以上の他にも共感する部分がたくさんありました。本の帯に書いてある通りに仕事が楽しくなりそうな1冊です。
2025.09.06
コメント(0)
-
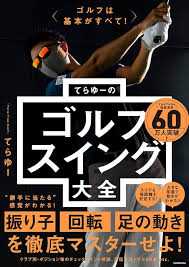
てらゆーのゴルフスイング大全 てらゆー
てらゆー先生の「てらゆーのゴルフスイング大全」を紹介します。趣味でゴルフをやっています。安定したショットができず、悩んでいました。ユーチューブでてらゆー先生がゴルフレッスンを配信しています。とてもわかりやすく、理論で説明しているので、本を購入しました。参考になった点を紹介します。①スイングを構成する3つの土台は振り子・回転・足の動き②振り子を適切に使うためには、クラブヘッドの重さにまかせること、そのためには、肩、腕、指を脱力する必要がある。③振り子の中心は首の付け根である。③正しい回転は背骨を中心とした体の入れ替えである。④フルスイングのトップ時は右足かかとに体重が乗るように心がける。⑤ドライバーは首の付け根を支点として、左腕を伸ばして大きなスイングアークをイメージする。⑥フェアウェイヴットやユーティリティーはダフらないことが重要であるので、体重を右足に残してはいけない。以上の他にも参考になる部分がたくさんありました。ゴルフはコースマネージメントが楽しいスポーツであると思います。楽しむためにはある程度の基本が大切です。基本こそ重要なことはないとこの本にも書かれていました。是非、購入してみてください。
2025.09.05
コメント(0)
-

イラスト図解ですっきりわかる国語 樺山敏郎
樺山敏郎先生の「イラスト図解ですっきりわかる国語」を紹介します。樺山敏郎先生の講演を聞き、興味を持ちこの本を読みました。樺山先生自身も大学教授であり、教科書の出版・編集に関わるなど実績がある方です。国語科が得意であり、私にとって難しい本でありました。しかし、共感できる部分がいくつかありましたので紹介します。①すべてを「やばい。」の一言で表現すると子ども、大人に関わらず語彙力の向上は望めない。②全国学力状況調査によると学力の高い子どもは定期的に読書を行い、新聞やニュースなどに関心がある。③言葉は相手の心を傷つけることもあるので慎重に使うべきである。それを指導するのも国語である。④時代は、「教師が一方的に教える」から「子どもが進んで学ぶ」にシフトチェンジしている。⑤子どもにとって居心地の良い教室空間を提供することで、子どもは自由に表現できるようになる。国語の専門的なことも多く記載されていました。知識がないと難しい本でした。ただ、筆者の情熱は良く伝わってきました。
2025.08.31
コメント(0)
-

教えるということ 出口 治明
出口 治明先生の「教えるということ」を紹介します。読んだきっかけは、雑誌を読んでいると「出口治明」先生の特集があり、この人に興味が湧き、この本を読んでみることにしました。とても熱意のある方で、実績も申し分ないので説得力があります。サブタイトルの「尖った人」を増やすには?にも興味が湧きます。共感を受けた部分をいくつか紹介します。①人間は「人、本、旅」からしか学ぶことができない。②男性は育児を行うことで愛情にあふれた一人前の男性に成長する。③「なんでそうしたいの?」の問いこそが、相手に考えさせ、答えを探させるきっかけの問いである。④「中・高校生」に対して答えるべき勉強する理由→①選択肢の拡大 ②生涯収入の向上⑤人間は言語化することでしか、自分の考えを整理することはできない。だから、人に話したり、書いた文章を人に見せるべきである。⑥経済的に恵まれない家庭の多くが子どもに「~しなさい。」という指示が多い、子どもが何を考えているのかを言語化して説明することを求めない。⑦好き嫌いに関係なく、部下と平等かつ公平に接するのが優れた上司である。⑧新しいことをすれば無能な人ほど反対する。なぜなら、新しいことは自分の無能さを露呈することである。そのような人たちの自主規制は昔からある。またまだ、勉強になる記載は多くありました。キレの良い文章で簡潔に表現しているので、読んでいる側も気持ちがよいです。すぐに実践したいことが書かれており、私にとり貴重な1冊となりました。
2025.08.30
コメント(0)
-

仕事ができる人が見えないところで必ずしていること 安達 裕哉
安達 裕哉先生の「仕事ができる人が見えないところで必ずしていること」を紹介します。本屋さんの棚の目立つところに置いてありました。タイトルがストレート過ぎで思わず購入してしまいました。私も仕事ができる人が見えないところで必ずしていることがあると思います。その秘密を知りたかったのです。仕事ができる人の秘密を紹介します。①「アウトプット中心」のスキルアップの仕方を身につけている。②話は結論から述べる。結論→具体性→聞かれたことを話す。③あまり優秀でない人をどのように扱うか。その態度を皆が見ていることを知っている。④まわりの人の自分より優秀な点をあげることができる。⑤成果が出ているときに「運がよいだけである。」と謙虚に考えることができる。⑥部下に同じような失敗をさせないように指導し、仕組みをつくる。以上の他にもたくさんのことが書かれていました。読みやすくて、勉強になった1冊でした。
2025.08.29
コメント(0)
-
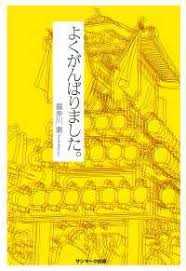
よくがんばりました 喜多川泰
喜多川泰先生のよくがんばりましたを紹介します。このブログでも何冊か紹介しています。喜多川泰先生の本です。読んだ後に前向きな気持ちになれる1冊です。この本も当然、読後にさわやかな気持ちになります。この物語は、私と同世代の男性が主人公です。その設定だけで、私は共感性を持ってしまいました。主人公が父の死により故郷に戻ることになります。私自身も小学生時に父母が離婚し、母に引き取られたので、父とは音信不通です。さらに共感が高まります故郷に戻り、地元行事のお祭りを見学したところから、父の知り合いに出会い、父の生き方や価値観を知っていくことになります。主人公にも家族があり、父の生き方と自分の生き方を照らし合わせながら、自分の考え方を広げ、深めていく展開です。喜多川泰先生は、何十冊が本を出していますが、どの本も読みやすいです。この本ももちろん読みやすい1冊です。下記の画像でも触れてしておりますが、自分ばかりうまくいってないと嘆いている人に読んでいただきたいです。是非、私と同世代の方に読んでいただきたいです。
2025.08.24
コメント(0)
-
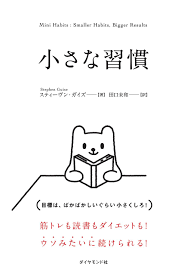
小さな習慣 スティーヴン・ガイズ
スティーヴン・ガイズ先生の小さな習慣を紹介します。このブログでも取り上げたことがありますが、喜多川泰先生の本が好きです。喜多川先生のブログも拝見しており、その中で「小さな習慣」を紹介していましたので読んでみました。とても参考になる部分が多かったです。①1回だけでいいのでやってみる。30回の腕立て伏せをやると決めているからサボってしまう。ハードルを低くして1回の腕立て伏せをやってみる。その勢いで3回できることもある。そうやって目標の30回に近づけていく。②習慣にしたい行動のハードルを低くする。歯みがきなどの習慣は安易な行動である。勉強や運動を習慣にしたい場合は、毎日1問、1回などハードルを低くすることが重要である。その積み重ねが習慣となる。③脳は新しい習慣に抵抗を見せる。大昔は新しいことをやることは命の危険があることである。そのため、脳は現状を維持したがる昨日となる。だから、急に新しい習慣を取り入れるのは難しいので、徐々に脳を慣らしていく必要がある。筋トレ、学習、読書などを習慣にしたいと考えている人は必見の本です。是非、読んでください。
2025.08.23
コメント(0)
-
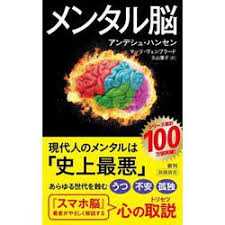
メンタル脳 アンデシュ・ハンセン
アンデシュ・ハンセン先生の「メンタル脳」を紹介します。アンデシュ・ハンセン先生の本はこのブログでも紹介しています。たくさんの知識を与えてくれる著者の本が大好きです。今回も参考になった部分を記述していきます。①脳は狩猟時代に暮らしていた頃の100万年前の機能にも関わらず、時代が急速に変化したためついていけず、不安やストレスを感じてしまう。②私たちの祖先は、集団生活をしないと生きていけなかったため、現代でも孤独になると不安を感じてしまう。③ある程度のストレスは緊張感があり、行動の活力になるが、ストレス状態が長く続くことが問題であり、その場合は体調を崩してしまう。④ストレスから脳を守るためには、①運動 ②信頼できる人といる ③7時間以上の睡眠 ④SNSを控える⑤集中して没頭できることに取り組むがあげられる。以上の他にも勉強になったことがたくさん書いてありました。やはりアンデシュ・ハンセン先生の本は学ぶことが多いです。
2025.08.22
コメント(0)
-
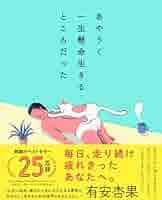
あやうく一生懸命に生きるところだった ハ・ワン
ハ・ワン先生のあやうく一生懸命に生きるところだったを紹介します。この本を読んだきっかけは、1年半前に大学進学のために自宅から引っ越しした息子の部屋の本棚に置いてあり、興味あるタイトルであったからです。とても読みやすく共感する部分も多かったです。紹介します。①努力したって必ず報われるわけではない。見返りはいつでも気まぐれである。②自分なりのポリシーを持って生きるべきである。③人と比べない。自分と同じレベルぐらいの人と比べやすい。どんぐりの背比べである。④自分にも人にも期待しすぎない。大きな期待しなければ、意外と楽に生きることができる。⑤他の選択肢がないと執着することで人生が辛くなる。⑥行動する後悔より、やらなかったことの後悔の方が大きい。だから、やりたいことをすべきである。⑦自分を過大評価しない。自分を過大評価するからうまくいかなかった時に傷つく。この本を読んだとき、私は少し疲れていました。読後に前向きになれました。息子からの素敵なプレゼントとなりました。
2025.08.17
コメント(0)
-
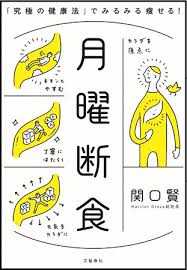
月曜断食 関口賢
関口賢先生の月曜断食を紹介します。この本を読んだきっかけは、東洋医学の断食や鍼治療に興味があり、よりパフォーマンスを向上させたく購入しました。健康・食事・睡眠の本を数冊読みましたが、新しく知ったことも多くあり、まだまだ学習が必要だなと感じました。勉強になった部分を紹介します。①断食は睡眠の質を高めてくれる。なぜなら、胃を空っぽにして眠りにつくと、消化作用にエネルギーが使われない分、体の回復にエネルギーが使用されるからである。②舌の表面の色が胃の状態を表す。ピンク→良好。白→食べすぎ。③成長ホルモンが活性化し、胃腸の働きも活発になる夜10時ごろに眠ることが理想である。④白米や麺類、パン、イモ類の炭水化物は消化に8時間かかるので夜に食べない方がよい。⑤意を冷やすことは食べすぎに繋がるので、注意が必要。以上の他にも新しく知ったことが多々ありました。タイプ別に分けた断食における1週間の食事メニューや体験談とうも記載されており、とても読みやすい本でした。
2025.08.16
コメント(0)
-

【中田敦彦・マコなり社長推薦】影響力の武器 ロバート・B・チャルディーニ
ロバート・B・チャルディーニ先生の影響力の武器を紹介します。この本を読んだきっかけは、私の好きなユーチューバー「中田敦彦」、「マコなり社長」が推薦しておりましたので、是非読書しました。この本は人はなぜ動かされるのかを実践をもとに証明していく本です。実体験等の記述もあるのでページ量がとても多いですが、とても勉強になります。勉強になった部分を紹介します。①返報性…人は恩を返そうとする。試食したら購入する。プレゼントをもらったらお返しをする。恩返し に義務感が発生する。②一貫性…行動を伴う人の意見の一貫性は信用される。事実に対して苦労していると意見を変えずらい。③社会的証明…みんながやっているから自分もやる。特に自分が情報のない時に有効的になる。また、自分と似ている存在であると有効的になる。④好意性…好意がある人の言うことは従う。容姿端麗や自分の似ている相手の場合は有効、お世辞を言われると有効⑤権威…肩書や服装、高級時計、高級車を身に着けている人の言うことは従う。スーツを着ると説得力がある。警察などの制服などを着た人の言うことは聞く。⑥希少性…数量限定、期間限定と書いてあるものは購入する。この手法で購入してしまったなどの苦い思い出が蘇ってきました。しかし、その出来事のすべてがこの6つの法則に当てはまるので、驚いています。悪用もできそうな知識がこの本には詰まっています。おすすめの1冊です。
2025.08.15
コメント(0)
-

科学的根拠で子育て 中室牧子
中室牧子先生の科学的根拠で子育てを紹介します。少子高齢化が急速に進む日本において、国の総生産は下がり、公共に費やす予算も削減されています。そのような現状の中で、未来への投資として教育の重要さを感じています。私には大学2年、高校2年の子どもがおり、子育ては最終段階ですが、改めて自分の子育てを振り返るよいきっかけになると思い読書しました。勉強になった部分を紹介します。①将来、自立するためにはテスト点数や学歴よりもチャレンジ精神やコミュニケーション能力、やりきる力などの非認知能力の方が重要である。②3歳から10歳までにスポーツをすることで高収入になる確率が高くなる。なぜなら、スポーツ活動により、忍耐力や協調性が身につくため。③高校卒業までにリーダー的な役割を経験した方が高収入になる確率が高くなる。④高校卒業までに音楽や芸術に触れていると感性が豊かになり、表現が上手になる。これも高収入に結びつく。⑤子どもが0~15歳の間まで親が能動的に子どもと関わる時間が多ければ多いほど、子どもの非認知能力が高い傾向にある。⑥高校などを選択する場合は、上位20%に属することができるかを考えて受験するべきである。極端に言えば、第一志望の最下位より、第二志望の1位の方が自己肯定感が上がる。以上の他にも共感できることや勉強になった部分が多く書かれていました。15歳までの子育てが中心の本でしたが、私は大人にも通用する部分が多くあったと思います。伸び率を考えたら幼少期からの取り組みが重要ですが、46歳の自分でも非認知能力を高めれるのではと、前向きになれました。
2025.08.11
コメント(0)
-
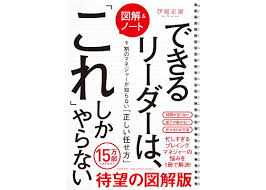
できるリーダーはこれしかやらない 伊庭正康
伊庭正康先生の「できるリーダーはこれしかやらない」を紹介します。この本を読んだきっかけは、仕事に悩み、苦労していたからです。私自身も管理職であり、部下との人間関係に悩んでいます。よいアプローチの仕方を学びたくこの本を手に取りました。私がすぐに実践できるのではと感じたことを紹介します。①部下を「下」に見ないで、最前線で働いているプロフェッショナルと思うこと②リーダーになったら、あえて弱みを見せるといったぐらいの適当さが必要である③仕事のしやすい年下上司の上位は「謙虚な姿勢」、「人の意見を柔軟に受け入れる」こと④新人には「一緒に、丁寧に」のスタンスで任せていく⑤いかに自分が速くやるのではなくて、いかに任せていくかを考えていく以上の他にも共感する部分や自分が疎かにしていたことがたくさん書かれていました。停滞していた状況を打破できる1冊になるようにまず自分が行動していきます。
2025.08.10
コメント(0)
-
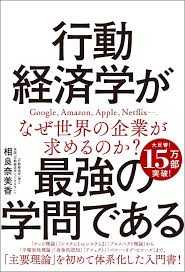
行動経済学が最強の学問である 相良奈美香
相良奈美香先生の「行動経済学が最強の学問である」を紹介します。この本を読んだきっかけは、経済学部に通う息子に薦められたからです。息子に本を紹介されたことに感動しつつも、興味がありましたので読書しました。勉強になった点をいくつか紹介します。①人間は非合理的な選択をする場合もある②多すぎる情報は人を疲弊させて、意思決定を妨げてしまう③重要な選択をする時は、脳が疲れていない朝にすることが良い④先が見えない不確実性に人は大きなストレスを受ける⑤成功者と自分を比べるとネガティブな感情になる。だから、比較するなら過去の自分と比較する。以上の他にも共感する部分や初めて知ったことなどが書かれていました。行動経済心理学は新しい学問なので、とても勉強になった1冊でした。
2025.08.09
コメント(0)
-
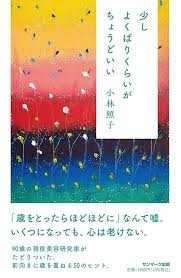
少しぐらいよくばりがちょうどよい 小林照子
小林照子先生の 少しぐらいよくばりがちょうどよいを紹介します。この本を読んだきっかけは、新聞の広告欄に載っていたからです。90歳を過ぎても、ハングリーさを感じ、興味が湧きました。感銘を受けた部分をいくつか紹介します。①つらくても、苦しくても、今が学びの時間であると考えることが大切である。②「怒り」はエネルギー、「悲しみ」は心の浄化となるが、「ねたみ」、「うらみ」は自分を苦しめ、どんどん醜くしていく。③自分を守るために、人を罵ったり、人のミスを追及したりとそんなことにエネルギーを使うのは非常に愚かである。④「外見力」は年を重ねれば重ねるほど絶大な力を発揮するのである。⑤年を重ねるごとに自分のステージを上げていくことが大切である。以上の他にも共感する部分はたくさんありました。改めて、人生経験が豊富な方の物事の捉え方に感心しました。気持ちが前向きになる本でした。
2025.08.08
コメント(0)
-
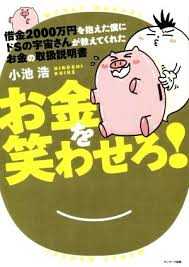
お金を笑わせろ 小池浩
小池浩先生のお金を笑わせろを紹介します。この本を読んだきっかけは、このブログでも紹介した小池先生の「奇跡を起こしまくる口ぐせ」に感銘を受け、購入しました。そして、正直にお金に愛されたいと思いました。相変わらずスピリチュアルなことが書かれており、惹きつけられました。期待通りに共感できる部分が多かったので紹介します。①安物買いの銭失いはお金が最も傷つく行為である。②しっかり稼いで家族を幸せにして、笑顔あふれる人生を送る。③まわりの人が笑顔になるよう。そして、自分自身が幸せになるようにお金を使っていくべきである。④お金の使い方の軸は、そこに「喜び」が生まれるかどうかである。⑤新しいお金の時代である。物質の時代が終わり価値観を再構築していく時代に突入している。以上の他にも感銘を受けた表現がたくさんありました。相変わらずですが、個性的なイラストのキャラクターがボケや突っ込みを入れていて本当に読みやすいです。軽い感じがとても良いです。
2025.08.03
コメント(0)
-
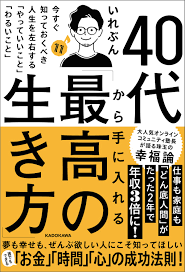
40代から手に入れる「最高の生き方」 イレブン
イレブン先生の40代から手に入れる「最高の生き方」を紹介します。この本を読んだきっかけは、YouTubeの本要約チャンネルで紹介していたからです。また、私自身も40代後半であり肉体的にも精神的にも衰えを感じているところでした。読書をきっかけに前向きになれればと思いました。感銘を受けたところを紹介します。①3つの余裕を手に入れることが重要である(1 時間 2 お金 3 心)②体調を自分で上手に整える(運動・栄養・休養)③一流に触れることで視野は広がり、視座が高まるのでどんどん自己投資すべきである④人は属するコミュニティによってどんどん変化していく。優秀な人がいるコミュニティを選ぶべき⑤「休みに仕事をすれば良い」は自分に対する逃げの思考である。以上の他にも共感するべき部分が多くありました。期待通りに、読後に前向きな気持ちになれました。40代だけでなく、年代に関係なく通じると思います。
2025.08.02
コメント(0)
-
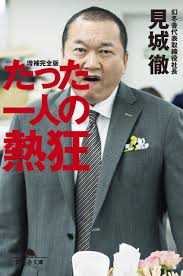
たった一人の熱狂 見城 徹
見城 徹先生の「たった一人の熱狂」を紹介します。この本をよんだきっかけは、会社経営をする方々が人生を変えた1冊であると言っていたからです。私も興味が湧き読んでみました。熱い思いが伝わる1冊でした。共感した部分をお伝えします。①つまらなくて地味な雑用でも自分の心がけ一つで黄金の仕事に変わる。②「義理」、「人情」、「恩返し」こそが仕事においても人生においても最も大事である。③自分で汗をかきなさい。手柄は人にあげなさい。そして、それを忘れなさい。④すべてはプロセスであるという人生哲学が大切である⑤小さいことを大事にしていない人は大きなことはできない以上の他にも感銘をうけた部分は多くありました。仕事に行き詰った方や悶々とした気分の方におすすめです。自分を大きく変える1冊になるかもしれません。
2025.08.01
コメント(0)
-

朝1分間 30の習慣 マツダミヒロ
マツダミヒロ先生の「朝1分間30の習慣」を紹介します。会社経営などで成功を収めている人は共通して、朝の時間に活動していると知りました。書籍の朝イチの「ひとりの時間」が人生を変えると同時に購入しました。心に響いたことをお伝えします。①人生の質は朝の過ごし方で決まる②朝日を浴びることで幸せホルモンのセロトニンが分泌される③ビジネスマンにとっては午前中が勝負の時間となる。なぜなら、アドレナリンやドーパミンが出るためである。④普段から「今日1日が人生に繋がること」を意識して生活することが大切⑤最もパフォーマンスの良い状態とは、リラックスしながらもやる気のある状態をさす。以上の他にも参考になった部分は多くありました。是非、皆さんに読んでほしいです。
2025.07.27
コメント(0)
-
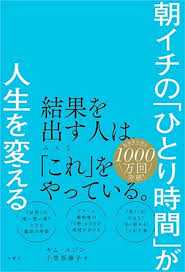
朝イチの「ひとりの時間」が人生を変える キムユジン
キムユジン先生の朝イチの「ひとりの時間」が人生を変えるを紹介します。この本を読んだきっかけは、会社経営などで成功を収めている人は共通して、朝の時間に活動していると本に書いていたからです。そこで、具体的にどのような活動をすればよいのかを知りたくこの本を読みました。勉強になった点をいくつか紹介します。①早起きをすれば、誰にも邪魔されない時間を確保できる。②朝の1時間は夜の3時間と同等の仕事量になる。③朝の時間に後回しにしていることや運動、読書をする。④朝は必ず一人で活動する。以上の他にも参考になったことが多く記述されていました。早起きするためにはまず、早寝することが大切です。早起きして有意義な時間を過ごしたい方におすすめの1冊です。
2025.07.26
コメント(0)
-
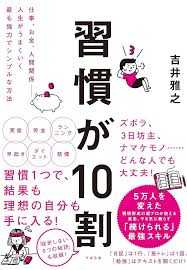
習慣が10割 吉井 雅之
吉井 雅之先生の習慣が10割を紹介します。9月に吉井先生の講演会が近くで開催されることを聞いたので、参加の前に吉井先生の本を読み予習してから臨んだ方が実りあるものになるだろうと考え読書しました。勉強になった点を紹介します。①人に能力の差はなし、あるのは習慣の差だけであり、今の自分をつくっているのは過去の習慣である②自分のプラスの出力に対して、プラスの出力で応じてくれる人と付き合うべきである。③人間の脳は「できる」と思ったことは全部できるようになっている。④部下に指導する際には「正しさ」よりも「楽しさ」を教えることが正解である。⑤意識的に物事の良い面に目を向ける習慣をつける。以上の他にも参考になった部分は多かったです。少しずつ今よりも成長しようと前向きな気持ちになりました。
2025.07.25
コメント(0)
-
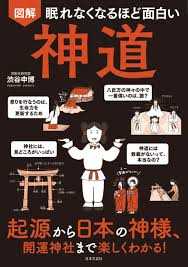
眠れなくなるほど面白い神道 渋谷甲博
渋谷甲博先生の眠れなくなるほど面白い神道の話を紹介します。年始には初詣、厄年には厄払いと私にとり神社は身近な存在であり、神社の神聖な空気間も大好きで御朱印帳を集めに神社を巡っていた時期もありました。その時に神社について学びを深めようと読書しました。新しく知ったことを紹介します。①神社で子どもに関わる儀礼が多いのは、昔は子どもの死亡率が高かったから②神社は神様のための場所であり、お寺は人のための場所である③狛犬は神社の境内に悪しきものが入らないように見張る役目がある④狐は神のお使いである。この他にも、ためになることを図解でわかりやすく紹介しています。とても読みやすいので是非、読んでほしいです。
2025.07.21
コメント(0)
-
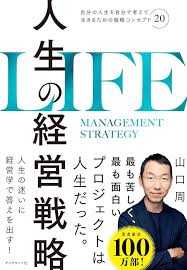
人生の経営戦略 山口周
山口周先生の人生の経営戦略を紹介します。この本を読んだきっかけは山口周先生がゲストとして出演していたユーチューブを視聴したからです。内容は、人生を4つ段階に区分とし、それぞれの時期に適した行動の仕方があると説明していました。とても興味深かったので購入しました。勉強になった部分を紹介します。①AIに勝つためには「正解のある仕事を避ける」、「感性的・感情的な知性を高める」、「問題を提起する力を高める」必要がある②人生は膨大な仮説の集合体であり、その仮説をひとつひとつ検証し、破棄・修正することでしか前に進めない③「頑張る」は「楽しむ」に勝利することはできない④資質や能力よりも根気よく粘り強く続けることのほうが大切である。⑤新しいやり方、考え方を受け入れようとしなければ、成長はそこで止まってしまう。⑥学習とは経験を通じて自分の信条・習慣・思考様式を変化させることで、同じ出来事に対して、アウトプットの質を高めていく。以上の他にも参考になることがたくさんありました。おすすめの1冊です。
2025.07.20
コメント(0)
-
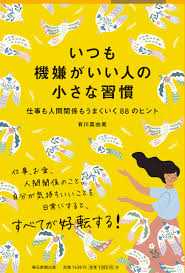
いつも機嫌がいい人の小さな習慣88のヒント 有川真由美
有川真由美先生のいつも機嫌がいい人の小さな習慣を紹介します。機嫌の良い人の周りにはいつも仲間がいます。そんな人になりたくてこの本を手に取りました。88の項目別に分かれているので非常に読みやすかったです。共感できた部分を紹介します。①自分がイライラしたら、客観視する。②財布の中身を整理する③誰にでも挨拶をする④いつもと違う行動をしてみる⑤使わないものはすぐに捨てて、目の前に入らないようにする以上の他にも参考になることがたくさん書いてありました。とても読みやすかったです。
2025.07.19
コメント(0)
-

幸せがずっと続く12の行動習慣 ソニアリュボミアスキー
ソニアリュボミアスキー先生の「幸せがずっと続く12の行動習慣」を紹介します。今、ウェルビーイングという言葉が流行っています。身体的、精神的、社会的に良好的な状態とは具体的にどのような状態のことか?そのような状態になるためにはどのような考え方が必要なのかを知りたくてこの本を読みました。心に響いた部分を紹介します。①「感謝の気持ちを表す。」、「楽観的になる」、「考えすぎない」、「他人と比較しない」ことを心がける。②幸福だと自覚している人の多くは家族や友人と良好な人間関係を築いている。③幸福だと自覚している人は、何らかの目標や計画をもっており、パートナーと分かち合っている。④他人の成功を心から喜び、他人の失敗を目のあたりにしたら、気を遣う。⑤運動をすることで不安感やストレスが減る。以上の他にも参考になった点がいくつかありました。人生において良好な状態を持続するための考え方がわかりました。早速意識して、日常生活を送ってみます。
2025.07.18
コメント(0)
-

人生の結論 小池一夫
小池一夫先生の「人生の結論」を紹介します。この本を読んだきっかけは、「成熟した大人とは具体的にどんな人?」と疑問に思い、人生経験が豊かである小池先生の見解を知りたかったからです。共感した部分を書き留めました。①「人を助けること」、「人に助けてもらうこと」どちらも身についているのが成熟した大人である。②今の自分がいるところが自分の実力である。③人生の一部の仕事が上手くいくことが、他の部分の人生の質を引っ張り上げてくれる。④上質な物を買って長く使う。これが理想的なお金の使い方である。⑤人の悪口を言う人は、「自分で悪口を言う人ですよ。」と自分の評判を広めている。⑥成熟した大人とは、「それは何ですか?」と知らないことを素直に聞ける余裕がある。以上の他にも心に響く表現がたくさんありました。是非、みなさんに読んでもらいたい1冊です。
2025.07.13
コメント(0)
-

17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと びーやま
びーやま先生の「17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと」を紹介します。2年前に息子が大学受験でした。びーやま先生とふーみんのユーチューブ動画「WAKKAってTV]の大学情報や学歴情報で息子と大学受験についてコミュニケーションをとっていました。無事に息子の大学受験が終わったちょうど1年後。店頭にこの本が陳列されていましたので思わず購入してしまいました。46歳の私でも共感することがありましたので紹介します。①学歴が「頑張れる人」であることを証明してくれる。②大学は利害関係のない友達を作ることのできる最後の場所である。③大谷翔平や前澤社長のように圧倒的な才能や覚悟があれば大学に行く必要はない。④やりたいことがないならシンプルに学力に挑むべきである。なぜなら、選択の幅を広げて軌道修正ができるから。熱いことが分かりやすく書かれ、読後に前向きになれる1冊でした。
2025.07.12
コメント(0)
-
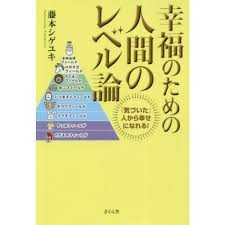
幸福のための人間レベル論 藤本シゲユキ
藤本シゲユキ先生の「幸福のための人間レベル論」を紹介します。ズバリ!タイトルが攻めている。その理由のみで読みました。読んでみるとなかなか面白く、すぐに読破してしまいました。共感できるところです。①人間は調子に乗ると必ず「感謝」を忘れてしまう。②人間の心は筋肉と同じで傷つかないと強くならない。③失敗を繰り返しながら新しいルートを見出して、なりたい自分や幸せに近づいていく。④なりたい自分になるためには、トライ&エラーを繰り返す必要がある。⑤世間体や人の評価を気にする生き方が悩みの原因となる。⑥今すぐに恩を返そうとしない。万人に好かれようとしない。以上の他にも心に響くところがたくさんありました。人間の考え方をピラミッド型に表現し、レベル分けをする感覚に藤本シゲユキ先生のセンスを感じました。
2025.07.11
コメント(0)
-
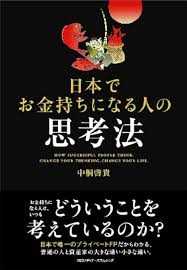
日本でお金持ちになる人の思考法 中桐啓貴
中桐啓貴先生の「日本でお金持ちになる人の思考法」を紹介します。この本を読んだきっかけは、お金を持っている人の思考を知りたかったからです。参考になった点をいくつか紹介します。①徳のある人は決して孤立せず、必ず良き協力者に恵まれる。②お金持ちは失敗談を語ることで親しみやすさを出そうとしている。③お金持ちは常に動き続けている。④お金持ちは仕事に打ち込むことができる環境づくりを家族が支えている。⑤経営がうまくいっている会社ほど経営理念がよく浸透している。私はお金持ちではありませんが、以上の他にも共感できる部分が多くありました。お金持ちこそ考え方をシンプルにして、周りの方に感謝して過ごしているようです。
2025.07.06
コメント(0)
全123件 (123件中 1-50件目)