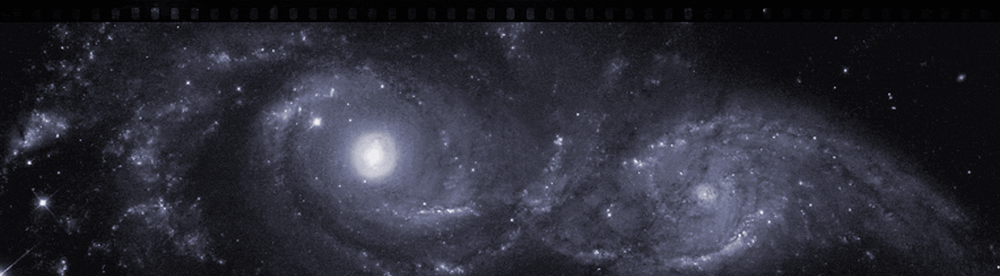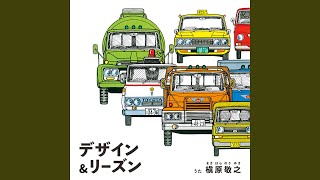2008年12月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
葬儀の心構え
先の日記で葬儀について触れましたが、ではどういう心持で臨むべきなのかを考えてみたいと思います。 よく引導が大切と言われますが、「引導秘訣」に「示して云はく引の字をひくと読むなり、譬へば糸の曲り巻き居たるを引き出して一切衆生煩悩悪行の縄につながれて曲り居たるを引き出して霊山へ送り届ける心なり。其の姿は導師無二の慈悲心に住して精霊に回向すべきなり、秘すべし、秘すべし」(富士宗学要集1巻270ページ)とあります。 煩悩にまみれた凡夫の罪深き生命を引っ張り、悪道へつながる縄を霊山へつながる方向へと転換するほどの意義があると示されています。導師はひたすら慈悲心に住し、故人へその引導の功徳を回向すべきであると示され、その深い意味について端的に示されていますが、葬儀に臨む者の心持ち、なかんずく、導師の心地が重要であると読み取れます。 正法の導師による引導でなければ、故人は苦しみを増すだけであるのは言うまでもありませんが、例え正法の導師であっても、普段より故人はもちろん、その他の信徒と同じ目線で積極的に関わってくださる方でなければ充分な意義が顕れてこないとも取れます。 私たち日蓮正宗信徒は幸いにして、師弟相対が大切なことを充分に教えていただいておりますので、信徒側の方も普段から御僧侶に親近し、積極的に真実を求める姿が理想だと感じます。 御供養の貢でも触れましたが、そのような空気が当たり前という状況が宗内全体を覆ってくれたら、どんなにか嬉しいことと思いますが、寺院によってはその点も不十分なところがあるようです。理想を現実とするためにも、明年の大総会までにそういう空気が宗内にいっそう充満することも、仏様が御嘉納遊ばされる事の一つのように思います。
2008.12.16
コメント(41)
-
志し
「一紙半銭も百貫千貫も多少ともに志あらはす物なり、あらはす処の志は全く替るべからず・然る間同等に多少軽重の志を取り次ぎ申すべし・若し軽重の心中あらば必ず三途に堕在すべし云々」(日有上人化儀抄・富士宗学要集一巻142ページ) 有名な日有上人のお言葉です。これを59世日亨上人はこのように解釈されておられます。「一紙半銭とは信仰帰命の顕れたる形の軽少なるを云ひ百貫千貫とは其顕れの形の重大なるを云ふといへども、軽少なるが故に志の薄きにはあらず・重大なるが故に志の厚きとのみ思ふべからず」(化儀抄註解・同書143ページ) 御供養はただ単純に量が多ければそれで事足れりとしてはいけない、少ない御供養でも志であるから、その志こそが重大であれば良いのである。慈悲に溢れたお言葉です。これこそが本宗の御供養の精神そのままでしょう。そこには何も不純なものを足したり引いたりすることもなければ、御供養の少ない人はダメだと仰せられているわけでもありません。ましてや、「これくらい御供養しなさい」というのは言語道断というべきでしょう。 顕正会ではいまちょうど、広布御供養が推進されている時期だと思いますが、この日有上人のお言葉、日亨上人のお言葉をどのように見るでしょうか?ましてや、顕正会は「取次ぎ申すべし」の部分を誰がどのように御供養をどなたに取り次ぐことだと解釈するでしょうか? この取り次ぐことに関して日亨上人は続いて、「取次ぎを為す僧分にては」として、まず御僧侶が御供養を取り次がれる任にあられることを示され、その御僧侶の振る舞い方について仰せられています。「多くの御供養をする信徒に対しては特別な席まで設けて激励し、さらにその信徒を例に出して、皆の前で暗に多くの供養をするようにその信徒を見習えと言ったり、少ない御供養しかできない信徒に対しては、取次ぎ自体が面倒くさいといって疎かにする。御宝前に奉告する時にそういう差別をつけたまま奉告するのは良い取り次ぎ方ではない」(取意・同書144ページ)とまず仰せられ、「取次の僧分が一念も軽重に偏執して或は懇に或は疎かにすることあらば、其罪に依りて三悪道に墜ちて永く信行権を停止せられ浅間敷苦労を為すべしと告誡し給へり」(同ページ)と決判されておられます。 顕正会や創価学会などは僧侶がいらっしゃらないから、この取次ぎの部分で論外ですが、正信会は一応は僧侶主導の団体ですから、当てはまるやにも見えますが、問題は御供養申し上げる正しい対象が存在しているか否かです。当宗においてはすべての御供養が、宗旨の根幹である本門戒壇の大御本尊様に対し奉って御供養申し上げるところにその深い意義が存在するのですから、その大御本尊様が存在していない団体は当然、正しい御供養はできません。 正信会は寺院の御本尊様に御供養すると言うかも知れませんが、それも大御本尊様とそれを受け継がれる唯受一人の御法主上人を尊崇申し上げてこそ、初めて意義を成して来るのです。正信会はこの一番大事な根幹を否定しているために、いくら寺院や僧侶がいたとしてもそこに正しい血脈の流れ通う道理は微塵も存在しないのです。正しい血脈が流れなければいくら御本尊様がいらっしゃり、僧侶がいたとしても形だけのもので、そこに御供養などすればかえって甚大な罪を作ることになるのです。さらに正信会は新たな寺院を増やし、そこにも当然本尊を安置するのでしょうが、破門以後に新たな御本尊が日蓮正宗より下付されているはずが無いのですから、顕正会・創価学会と同じで「魔仏」を安置する「魔縁の住処」を増やすだけで、そんな所に御供養しても同じく、功徳があろうはずがありません。 こう見てくると、やはり日蓮正宗総本山のみが大聖人の御意に叶った御供養の出来る団体であることは明白になりますが、それでも御供養を取り次いでくださる御僧侶には心得違いをなさって欲しくないと思うのが信徒の心情です。 この御供養の精神が日蓮正宗の隅から隅まで浸透して行ってくれる事を願っています。
2008.12.16
コメント(0)
-
昨日の続き
昨日は日蓮正宗で自分が体験したことの一部を書かせていただきましたが、私の友人はこんなことも言っていました。「亡き父親の車椅子をだいぶ前にお寺に御供養申し上げたんだけど、たまたまお寺の物置きに目が行ったら、なんとその車椅子がまったく使われずに置かれていた。亡き父の形見のようなものだから、お寺で使っていただきたいと思って御供養申し上げたのに、本山へも行かず、お寺でも使われずにいたことがショックだった」と。 たまたま、車椅子の人がいないのかもしれないけど、これを聞いたときは私もがっかりしました。単なる車椅子じゃない、特別の思いがこもった車椅子なのに・・・。と思うと、友人の気持ちが理解できます。 また、少々暴露的になりますが,「夏は本堂に麦茶があるんだけど、参詣した信徒がのどが渇いて麦茶をいただいていたら、御住職が来て、ただじゃないんだからあまりがぶがぶ飲まないで」と言われたり、さらには僧侶であるのに勤行の姿勢やけいの打ち方が滅茶苦茶であったり、ということがあるとも聞いています。大事な修行途上にあられる所化さんたちもそれにつられて滅茶苦茶な勤行をされたり・・・と、聞いているだけで気分が悪くなってきそうな事実もあるようです。 私のお寺では「御供養は恥ずかしくない相応の金額を」という指導が行われており、それは御住職が仰っておられるわけでは無いですが、役員の方が言っておられますし、理由があって移籍を申し出る方がいらっしゃっても、心無いことを言われて留まらせたり、ということもありますし、何より霊山浄土へ向かわれる故人の葬儀の場で葬儀の開始時間に遅れ、読経・唱題のみされてそそくさと本山へ帰られた事に対して、皆が疑問に思っております。 日蓮正宗は慈悲の宗派では無いのでしょうか?ほんの一部の例のみですが、こういった声は他のところにもあると思います。私たちは贅沢を望んでおりません。ただ御書等に示される師弟相対を純粋に実践したいだけです。このようなことがあっても従うのが師弟相対なのでしょうか?だとすれば、信心とはいったいなんなのでしょうか? 純粋に師弟相対が出来ているお寺の方には気分が悪いかもしれませんが、こういった事実もあるところがあります。もしこういう体質が古くから根付いてしまっている体質なら、広宣流布のために根絶やしにしなければいけません。こういう体質があるのに、「正しい宗派」と言っても、世間知らずなだけで、物笑いの種にもなりましょう。こういうこととは無縁のお寺の方々にも「そういうことがあるんだ。自分たちも気をつけないと」と自戒するための参考になれば幸いです。 昨日も言いましたが、自分たちは日蓮正宗そのものは正しいという認識は変わりません。宗教に正邪があることを世間に教えている徳は何物にも変えがたい徳だと思います。しかし、対象者は自分たちの振る舞いを第一に見てくるため、そこで日蓮正宗そのものを誤解させるような振る舞いをしないためにも、来年の慶事に向かって前進しなければならないと思います。 このようなことを書けば、異流儀と化した者たちは喜ぶことでしょう。しかし、魔に魅入られた者たちが何を言おうとそれはまた説得力を持ちませんし、あくまで日蓮正宗の法そのものは正しいのですから、余計な突っ込みは入れないほうがあなた方のためになります。私は日蓮正宗に来て妄信はしたくないため、見てきた事実をありのままに書かせていただいています。 正宗の一部がこのような体質を改善できれば広宣流布も大いに前進することと思います。それを願って筆を置きます。
2008.12.12
コメント(9)
-
信仰の意義
仏様は一切衆生に仏性という無上宝珠があることをお示し下され、それが引き出されることによって成仏という最高の境界に誰もが到達できるということを説いてくださっています。仏様は人々を成仏の境界に導き入れんとされるために、時には凡夫のお姿で、時には三十二相を以て御身を飾られ、時には方便権経を以て種々の化導をされ、いつの世にあっても衆生がいる限り、御慈悲を垂れ給うていらっしゃいます。 その中で、この末法における最高の教えである三大秘法を建立されたのが日蓮大聖人であり、この大聖人を末法の御本仏と尊崇申し上げている宗派が日蓮正宗です。されば、日蓮正宗を除いては他に正しい宗派無く、比肩する宗派また無しなのです。 私たち元顕正会員は顕正会こそ日蓮正宗の中で最も正しい団体と信じて活動してきましたが、その実態はあまりにも逸脱だらけであり、それは他の元顕正会員の方が披露されている通りです。およそ、正しい信心をしている団体の会員とは言えない無慈悲な他会員の言動、妄信の姿を目の当たりにし、それとは正反対の本物の信心とそれに裏打ちされた暖かい慈悲を求めて本家本元の総本山大石寺に帰伏させていただいたのが元顕正会員だといっても過言ではありません。 「本山に帰伏すれば本当の信心と慈悲に出会える」元顕正会員なら誰しもが、そのように考えていると思います。実際に他宗にはとても真似できない信心の本質を見せていただいておりますが、一部では心無い一部の方の心無い言動によってがっかりする場面も実際にあります。 「凡夫だから」と言ってしまえばそれまでかもしれませんが、これが人を導く立場である御僧侶から受けたものであるならば全く印象が違います。実際に私の知り合いが所属している寺院でも往々にして信徒と御住職の信頼関係の欠如が露骨に見られ、私の友人は「法そのものは正しいという確信はあるが、御住職にはもう少し信徒の立場に立って考え、慈悲に満ちた御指導をいただきたい」という声も聞かれます。 ただ単に在家と出家の方の違いということでは済まない実状があります。「折伏対象者をお寺に連れてきたいけど、今の雰囲気では連れてこれない」との嘆きも聞かれます。 誰もが胸を張って正しい宗派と言える雰囲気をみんなが求めています。在家は在家の本分に準じて本当の意味での師弟相対を目指せる空気を皆が生み出したいと思っているのに、期待通りに行かないことほど歯がゆいことはありません。 当ブログももしかしたら、御僧侶がご覧になられているかもしれませんが、それを承知で書かせていただきました。自身のつたない行体を思えば、恐れ多い思いですが、私もその方も日蓮正宗は正しい宗派であることへの確信は強いのです。それを不動の物へと変えられるほどのあと一歩を求めているだけです。 これは日蓮正宗への批判でもなければ、御僧侶批判でもありません。信心弱き一信徒の所見を書かせていただきました。
2008.12.11
コメント(1)
全4件 (4件中 1-4件目)
1