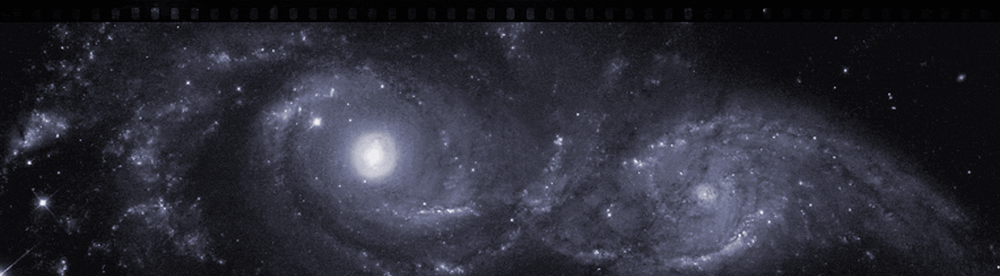全79件 (79件中 1-50件目)
-
誤った広宣流布観
顕正会では、「広宣流布したら、1日3時間働けば良い。あとは仏道修行に使うのだ。国民全員が入信するのだから、折伏もしなくて良い。勤行だけで良くなる。少しの災害も起きなくなる。」と、誤った広宣流布観を会員に植え付けております。これは大変な誤りです。 まず、広宣流布の定義を顕正会は「国民全体の入信」と勝手に決め付けてしまっておりますが、これが誤りの1です。 要は、ある程度の入信者が、純粋に信心する人たちが増えてきて、その人たちの総意が国にも伝わり、そういう総意を以て戒壇建立する時が広宣流布の時ですが、御書にも「1人残らず入信」とまでは定義されていません。あくまで、戒壇建立さえ成される時が広宣流布ということで、それの必要絶対条件が国民1人残らずの入信とはなっていないわけです。 従って、広宣流布された時点でも謗法の人たちもいる可能性は大きい故に、多少の災害は起きるということです。 誤りの2は「1日3時間働けば良い」ということです。そうなると、あらゆる機関がマヒしてしまい、例えば病院で救急患者が出たら医者が「いや、もう3時間過ぎてるから後は仏道修行に使いたい」と言って患者を見捨てたらどうでしょうか?あるいは、交通機関に従事されている方が、「3時間過ぎたから電車やバスを止める。」と言ったら、大事な信心の行事にも参加できない人も増えてくるし、それ以前に世間的にも大混乱の事態を引き起こすでしょう。 これは誤った思想です。あくまで、外見は今までと変わらない世間の姿があると思われます。ただ、信心を基調とした世の中ができてくる。例えば、「御講日割引」等などが誕生するかもしれませんが、「○○時間働けば良い」などという世の中にはならないでしょう。 もちろん、梵天・帝釈も戻ってきて日本国を守護するということは確実でしょうが、顕正会ではそういうことに絡めて、何か現実とかけ離れた広宣流布後の国の姿を会員に想像させています。 やはり血脈相伝の教えから離れてしまうと、広宣流布観も狂ってくるということの証明です。
2011.10.31
コメント(5)
-
開眼供養について
御本尊様のことを語る上で欠かせないのが、「開眼供養」ということです。 私ごとき在家がその重大事を詳しく知る由もありませんが、書籍の御指南等を元に少し書かせていただきます。 大聖人様は「法華を心得たる人、木絵二像を開眼供養せざれば、家に主のなきに盗人が入り、人の死するに其の身に鬼神入るが如し」(木絵二像開眼事)と仰せられ、単に「本尊を書写するだけで良い」等の考えを戒めておられます。 これは顕正会に当てはめれば、「自分たちで印刷して、そっくり同じ姿をした本尊ならばそれで良い」と考えているところを戒めておられるということです。ましてや、破門された団体においておや、であります。 例え、姿は仏に似ていても、法華経の極理を以て開眼供養しなければ衆生を成仏に導く力は無いということであります。 では、誰でもがこの開眼供養をできるのか?というと、その答えは「否」です。 その資格をお持ちの方は、「日蓮聖人乃至日因に至るまで三十一代、塁も乱れず相伝これなり」(日因上人御指南)と言われるところの、代々の猊下様がそれに該当するのであります。現在で言えば、御当代・日如上人猊下様がまさしく、この大事至極の開眼供養をなされる資格をお持ちなのです。 具体的にどのように開眼されるのかは、在家ではわかることでは無いし、触れるのも憚られますが、大事なのは一般の僧俗に手が出せる分野では無いということです。我々がどのような儀式めいたことを行ったとしても、勝手に印刷した本尊には人を救う力などは宿りません。 むしろ、上記にあるように、鬼神の入った札として、不幸を招く乱神、怪神のまたとない住処となるでしょう。 そんなものを拝んだらどうなるのか?これ以上は言わなくてもわかりますよね? 別の視点から考えれば、「正直の人の頭に諸天善神は住む」と言われていますが、正法に背いた逆謗の衆生の元からは善神は離れ、悪いものが住み着くのです。ニセ本尊はそういうものに「おいで、おいで」しているようなものであります。これがひいては、国をも傾ける原因になることを顕正会は知らなければなりません。 御本尊の一切は富士大石寺にのみ、ましますのです。
2011.10.27
コメント(0)
-
ニセ本尊に関して
先回のようなことを言うと、ひねくれた人は、「本尊の書写などはしていない。印刷ならわからないが」というかもしれません。 しかし、大聖人様は「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承唯受一人の血脈なり」(百六箇抄)と仰せられています。 くどいようですが、御本尊に関する一切の権能は猊下にあらせられるのです。それも御当代猊下にです。その猊下が仮に「皆が自由に御本尊を印刷してよい」等と仰せられたのなら、許されるでしょう。しかし、史実に照らして今後も絶対にそのようなことは無いと断言できます。 されば、その権能も無い者が勝手に印刷した本尊などには何の力も無いことがわかるでしょう。また、以下の御文 「御筆の本尊を以て形木に彫み不信の輩に授与して軽濺する由・諸方に其の聞え有り」(富士一跡門徒存知事) これは当時、同じ日蓮門下の弟子たちが御本尊を勝手に版木に刻み、それを元に大量に御本尊を刷り、信心も無い輩に授与していたことがあったことを示し、それを戒めておられる御文です。 さて、今の顕正会の疑惑がかかった御本尊はどうでしょうか?まったく同じではありませんか? 形木に刻んでそれを元に大量に御本尊を刷る=現代では精巧な印刷技術を用いて大量に御本尊を印刷する。こういうことを戒めておられるのです。 先回は血脈の切れた御本尊について述べましたが、今回はニセ本尊に焦点を当ててみました。 言えることは、どちらにも人を救う力は無いということです。所詮は日蓮正宗に帰伏して真正御本尊の功徳に浴させていただくしか成仏できる道は存在しません。 念を押しますが、こういう本尊を拝んでいると、自分自身の大切なものを失うことにもなります。手遅れになる前に日蓮正宗に帰伏しましょう。
2011.10.24
コメント(0)
-
血脈の切れた本尊について
顕正会所持の本尊については、さまざまな議論が交わされています。それは、大体が「本物か偽物か」という議論ですが、仮に顕正会の御本尊を全て本当の御本尊と仮定しましょう。 しかし・・・・ それでも顕正会が正しい理由には成り得ません。なぜか?それは・・・ 一例を挙げれば、「当代の法主の処に本尊の体有るべきなり」(当家法則文抜書)という日寛上人のお言葉がございます。 これは、その代の猊下の元に御本尊の実態が存在するという意味です。古来から大石寺では御隠尊猊下でさえも、御当代の猊下に遠慮されてなるべく御本尊の書写はされなかったそうです。いわんや、それ以外の僧俗においておや、です。宗門屈指の弘通者である日尊師でさえ、御本尊に関しては手出しをされなかったという史実もあります。 それだけ、御当代猊下の御本尊に関しての権能というものは日蓮正宗では重いものなのです。されば、その御当代猊下の元から離れた本尊も全て血脈を失うのです。 顕正会員も日蓮宗等にある御真筆御本尊を拝めないでしょう?なぜ拝めないのか?それは、暗にその御本尊に血脈が無いことを知っているからです。 それを知っていながら、では、自分たちが日ごろ拝んでいる御本尊はどうなのか?を考えることができず、思考停止している状態なのです。 顕正会は今の日如猊下をも認めていません。また、過去に顕正会に渡った御本尊は本当は全て日蓮正宗にお返ししなければいけない御本尊なのです。破門時に返すようにと、当時の日達上人から通達が出ています。つまり、その当時の日達猊下に背いている時点で顕正会の御本尊はすでに血脈が切れているのです。加えて、上記の日如上人にも背いていることになり、この背反によって、顕正会の御本尊は人を不幸へと誘う堕獄魔神の働きをなすことは必定なのです。 心ある顕正会員さんにはぜひとも、この本尊問題を深刻に考えて頂き、真正な御本尊様の存在する日蓮正宗へ帰伏していただきたいと強く念願するものです。
2011.10.24
コメント(0)
-
久々の更新
二年くらい更新していませんでした。 何もテーマが思いつかずにいたのが、その理由です。 信仰歴も進み、いまだに微弱な信心ではありますが、御住職様、周りの方々のお力添えによって、なんとか信仰を保てています。 最近の体験を一つ・・・ 同じ地元の講員の方と最近、折伏活動を始めるようになりました。自分ではなかなか、勇気が出ず、折伏しなきゃと思うだけで悶々とした日々が続いていましたが、入信五年目に突入した最近、地元の講員さんから折伏の応援依頼があり、その方の知り合いの顕正会員を折伏しました。 その方はすでに顕正会に疑問を持っており、さまざまな疑問をぶつけてこられたので、私にわかるなりに精いっぱいお答えいたしました。同時に折伏ですから、顕正会こそが仏法を破壊していること、そこにいても不幸になるだけであることを強く言い切りました。 結果は、その場では入信できませんでしたが、後日、「日蓮正宗に行きたい」と連絡がありました。しかし、先日入信する予定だったのが、顕正会員の妨害で流れてしまいました。 ただ、顕正会を完全に辞めることはできたとの報告を聞き、必ずや近いうちに日蓮正宗にと思っております。 地元の講員さんも残念がっておりましたが、今度は御住職様も来てくださり、再度の折伏になるので、その時に決めたいと強く強く願っています。 それにつけても、日蓮正宗の折伏と顕正会の勧誘はまったく別物であることが体験の上でわかりました。 ・相手を無理やりにその場で入信を迫らず、時間をかけて入信を勧めるということ ・逆縁でもありがたい御縁として、対象者をも大事にできること ・大聖人様お示しの本当の血が通った折伏である この三点を自身の体験の上で実感することが叶い、ありがたい気持ちでいっぱいになったものです。 顕正会員に言いたい。 これこそが、本物の折伏であると・・・
2011.10.24
コメント(1)
-
顕正会員さんへ
顕正会員は浅井会長を無上の指導者として尊敬しており、会長を通して御本尊を拝むという体制になっています。しかし、果たして在家の指導者が正しいのか?道を誤ることは無いのだろうか?と素朴な疑問から持っていただきたいのです。 26世日寛上人は「金口の相承と申して一器の水を一器に移すがごとく富士大石寺にのみとどまれり」(寿量品談義)と仰せられ、大石寺にだけ金口の相承が相伝されていると御指南されています。その金口の相承の中には「別して12箇条の法門あり」と言われている猊下のみに相伝される秘奥の法門があるとも言われています。 つまり浅井会長は「先生の教学は富士の地下水まで達している」と言われていますが、このような仰せがある以上は浅井会長が「富士の地下水」になど達していないことが明らかになるし、そこから会員の皆さんには色々なことに疑問を持って欲しいです。 そもそも、顕正会には三大秘法の実体は存在していません。本門の本尊=根本の大御本尊様、大御本尊様と血脈のつながっている御本尊様、本門の題目=本門の本尊が存在しない以上はいかなる本尊に向かって唱えるお題目は本門の題目にはなりえない。、本門の戒壇=大御本尊様のまします場所が最上の戒壇で、その大御本尊様に通じる御本尊様のまします場所はすべて義の戒壇、顕正会の所有する御本尊はすべて大御本尊様と血脈が切れている、或いは最初からつながっていないために、顕正会の本尊を安置する場所は戒壇とはなりえないため。 さらに仏法の根幹である三宝も存在しません。それは御僧侶もいなければ本尊も疑惑が濃厚、猊下もおられないという現状を見れば歴然です。仏法ではいかなる時代にも必ず三宝が存在してきた経緯があります。その中で在家が三宝の一つに加えられていた事実はありません。つまり浅井会長がいかに教学を勉強していようが、大総会を開こうが、浅井会長が真の指導者になる日など絶対に来ません。 かかる事実を踏まえられて是非会員の皆さんには正邪を考えていただきたいと思います。もし自分のブログに寄って下さる会員の方がいらっしゃれば、メール下さい。自分で分かる範囲ならば喜んで相談に乗らせていただきます。
2009.09.30
コメント(21)
-
通りすがりさんへ
コメントありがとうございます。確かに自分の日記は見苦しい面もありますね。外に向かって話すべき事柄ではありませんでした。ありがとうございます。 ただ、実際問題として僧俗間の信頼関係の問題を解決していかなければ広宣流布はできないと思います。所属寺院の御住職様が手継ぎの師匠であられ、本師である猊下様の命を受けられ、自分たちに信心の指針を示してくださる・・・。化儀抄等に書かれている通りに自分も認識しています。
2009.09.30
コメント(1)
-
信仰者としての資質
法華講員も顕正会員も学会員も、「我こそが正義なり」と主張しています。日蓮正宗系は特にそういう性質があると聞いた事があります。 確かに日蓮正宗は宗教に正邪があることを明示し、世間に対して破邪立正を訴えて来ています。その功績というのは仏様のよくよくご存知のことであると思います。 しかし、いま「日蓮正宗は学会や顕正会を生み出した親である」という意見も巷にあり、日蓮正宗そのものの資質が問われる時期に来ているという感を強くしています。顕正会や学会と差があることを示したいのなら、本宗伝統の慈悲の精神をもっと前面に強く打ち出すべきであると思うのです。難しい教学を知っていようと、百万遍の題目を唱えたとしても、人間としての人格や品性が疑われるような方も日蓮正宗内に(自分もまだまだひねくれた人格ではありますが)いらっしゃるようです。 口では異体同心と言っても、実際に行われているのが講員同士の陰口の言い合いや、御僧侶が信徒を疎んじたり、信徒がそれを受けて御僧侶に信を置けなくなっていたりという現状の寺院も私が知る限りはあります。特に御僧侶は「厳しい修行をしてきたはずなのに、どうしてこのような人格の方がいらっしゃるのか?」という方もおります。そこで、そういう御僧侶に意見を申し上げたら「信徒が悪い」となり、異体同心などできなくなるのです。 法華講は今まで、僧俗一致を掲げ、実際に御僧侶と信徒がお互いを支えあい、ここまで来たはずであります。なぜ何百年も続いたのかを考えれば、信徒と御僧侶の間に本当の信頼関係があったからだと自分は思います。それがなぜ今、信徒の陰口を言うような方が出るのか? 時代が下がってくるにつれて衆生の機根も下がるからなのでしょうか?単純にそれだけの理由からなのでしょうか? いかな時代にあっても、日蓮正宗だけは白蓮華のような集団であってほしいと願います。実際に御本尊のお給仕一つとっても、他宗では味わえない充実感が涌いてきます。これは法そのものは本物だからだと思います。顕正会や学会では絶対に体験できないことです。 こういったすばらしい体験ができる人が増えるように、自分たちも人格を磨いて、「あの人のやっている信仰なら」と自然に入信してくる人が出るような、そんな人間を目指さなければいけないと思いました。
2009.03.31
コメント(31)
-
葬儀の心構え
先の日記で葬儀について触れましたが、ではどういう心持で臨むべきなのかを考えてみたいと思います。 よく引導が大切と言われますが、「引導秘訣」に「示して云はく引の字をひくと読むなり、譬へば糸の曲り巻き居たるを引き出して一切衆生煩悩悪行の縄につながれて曲り居たるを引き出して霊山へ送り届ける心なり。其の姿は導師無二の慈悲心に住して精霊に回向すべきなり、秘すべし、秘すべし」(富士宗学要集1巻270ページ)とあります。 煩悩にまみれた凡夫の罪深き生命を引っ張り、悪道へつながる縄を霊山へつながる方向へと転換するほどの意義があると示されています。導師はひたすら慈悲心に住し、故人へその引導の功徳を回向すべきであると示され、その深い意味について端的に示されていますが、葬儀に臨む者の心持ち、なかんずく、導師の心地が重要であると読み取れます。 正法の導師による引導でなければ、故人は苦しみを増すだけであるのは言うまでもありませんが、例え正法の導師であっても、普段より故人はもちろん、その他の信徒と同じ目線で積極的に関わってくださる方でなければ充分な意義が顕れてこないとも取れます。 私たち日蓮正宗信徒は幸いにして、師弟相対が大切なことを充分に教えていただいておりますので、信徒側の方も普段から御僧侶に親近し、積極的に真実を求める姿が理想だと感じます。 御供養の貢でも触れましたが、そのような空気が当たり前という状況が宗内全体を覆ってくれたら、どんなにか嬉しいことと思いますが、寺院によってはその点も不十分なところがあるようです。理想を現実とするためにも、明年の大総会までにそういう空気が宗内にいっそう充満することも、仏様が御嘉納遊ばされる事の一つのように思います。
2008.12.16
コメント(41)
-
志し
「一紙半銭も百貫千貫も多少ともに志あらはす物なり、あらはす処の志は全く替るべからず・然る間同等に多少軽重の志を取り次ぎ申すべし・若し軽重の心中あらば必ず三途に堕在すべし云々」(日有上人化儀抄・富士宗学要集一巻142ページ) 有名な日有上人のお言葉です。これを59世日亨上人はこのように解釈されておられます。「一紙半銭とは信仰帰命の顕れたる形の軽少なるを云ひ百貫千貫とは其顕れの形の重大なるを云ふといへども、軽少なるが故に志の薄きにはあらず・重大なるが故に志の厚きとのみ思ふべからず」(化儀抄註解・同書143ページ) 御供養はただ単純に量が多ければそれで事足れりとしてはいけない、少ない御供養でも志であるから、その志こそが重大であれば良いのである。慈悲に溢れたお言葉です。これこそが本宗の御供養の精神そのままでしょう。そこには何も不純なものを足したり引いたりすることもなければ、御供養の少ない人はダメだと仰せられているわけでもありません。ましてや、「これくらい御供養しなさい」というのは言語道断というべきでしょう。 顕正会ではいまちょうど、広布御供養が推進されている時期だと思いますが、この日有上人のお言葉、日亨上人のお言葉をどのように見るでしょうか?ましてや、顕正会は「取次ぎ申すべし」の部分を誰がどのように御供養をどなたに取り次ぐことだと解釈するでしょうか? この取り次ぐことに関して日亨上人は続いて、「取次ぎを為す僧分にては」として、まず御僧侶が御供養を取り次がれる任にあられることを示され、その御僧侶の振る舞い方について仰せられています。「多くの御供養をする信徒に対しては特別な席まで設けて激励し、さらにその信徒を例に出して、皆の前で暗に多くの供養をするようにその信徒を見習えと言ったり、少ない御供養しかできない信徒に対しては、取次ぎ自体が面倒くさいといって疎かにする。御宝前に奉告する時にそういう差別をつけたまま奉告するのは良い取り次ぎ方ではない」(取意・同書144ページ)とまず仰せられ、「取次の僧分が一念も軽重に偏執して或は懇に或は疎かにすることあらば、其罪に依りて三悪道に墜ちて永く信行権を停止せられ浅間敷苦労を為すべしと告誡し給へり」(同ページ)と決判されておられます。 顕正会や創価学会などは僧侶がいらっしゃらないから、この取次ぎの部分で論外ですが、正信会は一応は僧侶主導の団体ですから、当てはまるやにも見えますが、問題は御供養申し上げる正しい対象が存在しているか否かです。当宗においてはすべての御供養が、宗旨の根幹である本門戒壇の大御本尊様に対し奉って御供養申し上げるところにその深い意義が存在するのですから、その大御本尊様が存在していない団体は当然、正しい御供養はできません。 正信会は寺院の御本尊様に御供養すると言うかも知れませんが、それも大御本尊様とそれを受け継がれる唯受一人の御法主上人を尊崇申し上げてこそ、初めて意義を成して来るのです。正信会はこの一番大事な根幹を否定しているために、いくら寺院や僧侶がいたとしてもそこに正しい血脈の流れ通う道理は微塵も存在しないのです。正しい血脈が流れなければいくら御本尊様がいらっしゃり、僧侶がいたとしても形だけのもので、そこに御供養などすればかえって甚大な罪を作ることになるのです。さらに正信会は新たな寺院を増やし、そこにも当然本尊を安置するのでしょうが、破門以後に新たな御本尊が日蓮正宗より下付されているはずが無いのですから、顕正会・創価学会と同じで「魔仏」を安置する「魔縁の住処」を増やすだけで、そんな所に御供養しても同じく、功徳があろうはずがありません。 こう見てくると、やはり日蓮正宗総本山のみが大聖人の御意に叶った御供養の出来る団体であることは明白になりますが、それでも御供養を取り次いでくださる御僧侶には心得違いをなさって欲しくないと思うのが信徒の心情です。 この御供養の精神が日蓮正宗の隅から隅まで浸透して行ってくれる事を願っています。
2008.12.16
コメント(0)
-
昨日の続き
昨日は日蓮正宗で自分が体験したことの一部を書かせていただきましたが、私の友人はこんなことも言っていました。「亡き父親の車椅子をだいぶ前にお寺に御供養申し上げたんだけど、たまたまお寺の物置きに目が行ったら、なんとその車椅子がまったく使われずに置かれていた。亡き父の形見のようなものだから、お寺で使っていただきたいと思って御供養申し上げたのに、本山へも行かず、お寺でも使われずにいたことがショックだった」と。 たまたま、車椅子の人がいないのかもしれないけど、これを聞いたときは私もがっかりしました。単なる車椅子じゃない、特別の思いがこもった車椅子なのに・・・。と思うと、友人の気持ちが理解できます。 また、少々暴露的になりますが,「夏は本堂に麦茶があるんだけど、参詣した信徒がのどが渇いて麦茶をいただいていたら、御住職が来て、ただじゃないんだからあまりがぶがぶ飲まないで」と言われたり、さらには僧侶であるのに勤行の姿勢やけいの打ち方が滅茶苦茶であったり、ということがあるとも聞いています。大事な修行途上にあられる所化さんたちもそれにつられて滅茶苦茶な勤行をされたり・・・と、聞いているだけで気分が悪くなってきそうな事実もあるようです。 私のお寺では「御供養は恥ずかしくない相応の金額を」という指導が行われており、それは御住職が仰っておられるわけでは無いですが、役員の方が言っておられますし、理由があって移籍を申し出る方がいらっしゃっても、心無いことを言われて留まらせたり、ということもありますし、何より霊山浄土へ向かわれる故人の葬儀の場で葬儀の開始時間に遅れ、読経・唱題のみされてそそくさと本山へ帰られた事に対して、皆が疑問に思っております。 日蓮正宗は慈悲の宗派では無いのでしょうか?ほんの一部の例のみですが、こういった声は他のところにもあると思います。私たちは贅沢を望んでおりません。ただ御書等に示される師弟相対を純粋に実践したいだけです。このようなことがあっても従うのが師弟相対なのでしょうか?だとすれば、信心とはいったいなんなのでしょうか? 純粋に師弟相対が出来ているお寺の方には気分が悪いかもしれませんが、こういった事実もあるところがあります。もしこういう体質が古くから根付いてしまっている体質なら、広宣流布のために根絶やしにしなければいけません。こういう体質があるのに、「正しい宗派」と言っても、世間知らずなだけで、物笑いの種にもなりましょう。こういうこととは無縁のお寺の方々にも「そういうことがあるんだ。自分たちも気をつけないと」と自戒するための参考になれば幸いです。 昨日も言いましたが、自分たちは日蓮正宗そのものは正しいという認識は変わりません。宗教に正邪があることを世間に教えている徳は何物にも変えがたい徳だと思います。しかし、対象者は自分たちの振る舞いを第一に見てくるため、そこで日蓮正宗そのものを誤解させるような振る舞いをしないためにも、来年の慶事に向かって前進しなければならないと思います。 このようなことを書けば、異流儀と化した者たちは喜ぶことでしょう。しかし、魔に魅入られた者たちが何を言おうとそれはまた説得力を持ちませんし、あくまで日蓮正宗の法そのものは正しいのですから、余計な突っ込みは入れないほうがあなた方のためになります。私は日蓮正宗に来て妄信はしたくないため、見てきた事実をありのままに書かせていただいています。 正宗の一部がこのような体質を改善できれば広宣流布も大いに前進することと思います。それを願って筆を置きます。
2008.12.12
コメント(9)
-
信仰の意義
仏様は一切衆生に仏性という無上宝珠があることをお示し下され、それが引き出されることによって成仏という最高の境界に誰もが到達できるということを説いてくださっています。仏様は人々を成仏の境界に導き入れんとされるために、時には凡夫のお姿で、時には三十二相を以て御身を飾られ、時には方便権経を以て種々の化導をされ、いつの世にあっても衆生がいる限り、御慈悲を垂れ給うていらっしゃいます。 その中で、この末法における最高の教えである三大秘法を建立されたのが日蓮大聖人であり、この大聖人を末法の御本仏と尊崇申し上げている宗派が日蓮正宗です。されば、日蓮正宗を除いては他に正しい宗派無く、比肩する宗派また無しなのです。 私たち元顕正会員は顕正会こそ日蓮正宗の中で最も正しい団体と信じて活動してきましたが、その実態はあまりにも逸脱だらけであり、それは他の元顕正会員の方が披露されている通りです。およそ、正しい信心をしている団体の会員とは言えない無慈悲な他会員の言動、妄信の姿を目の当たりにし、それとは正反対の本物の信心とそれに裏打ちされた暖かい慈悲を求めて本家本元の総本山大石寺に帰伏させていただいたのが元顕正会員だといっても過言ではありません。 「本山に帰伏すれば本当の信心と慈悲に出会える」元顕正会員なら誰しもが、そのように考えていると思います。実際に他宗にはとても真似できない信心の本質を見せていただいておりますが、一部では心無い一部の方の心無い言動によってがっかりする場面も実際にあります。 「凡夫だから」と言ってしまえばそれまでかもしれませんが、これが人を導く立場である御僧侶から受けたものであるならば全く印象が違います。実際に私の知り合いが所属している寺院でも往々にして信徒と御住職の信頼関係の欠如が露骨に見られ、私の友人は「法そのものは正しいという確信はあるが、御住職にはもう少し信徒の立場に立って考え、慈悲に満ちた御指導をいただきたい」という声も聞かれます。 ただ単に在家と出家の方の違いということでは済まない実状があります。「折伏対象者をお寺に連れてきたいけど、今の雰囲気では連れてこれない」との嘆きも聞かれます。 誰もが胸を張って正しい宗派と言える雰囲気をみんなが求めています。在家は在家の本分に準じて本当の意味での師弟相対を目指せる空気を皆が生み出したいと思っているのに、期待通りに行かないことほど歯がゆいことはありません。 当ブログももしかしたら、御僧侶がご覧になられているかもしれませんが、それを承知で書かせていただきました。自身のつたない行体を思えば、恐れ多い思いですが、私もその方も日蓮正宗は正しい宗派であることへの確信は強いのです。それを不動の物へと変えられるほどのあと一歩を求めているだけです。 これは日蓮正宗への批判でもなければ、御僧侶批判でもありません。信心弱き一信徒の所見を書かせていただきました。
2008.12.11
コメント(1)
-
顕正会の折伏
顕正会の折伏については以前も取り上げたと思いますが、折伏理論解説書等に書かれている、「折伏は慈悲を以て柔和に順々と仏法の話を相手に説き聞かせるべきである」ということと、現場の会員の実際の折伏活動が一致していない現状があります。 確かに「柔和に順々と説き聞かせるべき」ですが、現状は「入信しない相手の胸倉を掴んだり、帰ろうとする相手の手を掴んで帰さなかったり、罰が出るぞの一点張り」であることは現場に身を置く会員なら誰もが知っているはずです。さらに自宅拠点等で入信を迫る場合は、違う部屋に幹部が待機していて、後輩が論に詰まったら出てきて説得するというパターンもあります。かくいう私の組織もそうであり、後輩が連れてきた対象者が帰ろうとしたら、自分と同じ部屋にいた上長が出て行って、引き止めて入信せしめたということがありました。それ自体は悪いことではないかもしれませんが、その内容によっては、「監禁、入信強要」と取られ、結果、ニュースで取り上げられる事態を引き起こしてしまうのです。 さらには、自宅拠点が無い地方の会員は御本尊様を奉持して車の中やカラオケボックスで入信勤行という、まさに数を追うだけの活動に追われています。後輩に対しても、折伏の約束が取れないと、般若のような形相になり、言動も荒くなる上長もいました。自分もあまりの上長の変わり様に、涙を流しながら約束を取り続け、生き地獄にも似た体験をしたこと、昨日のように思い出されます。ホームレス折伏も話題に上り、まさに縦横無尽でありました。 顕正会の皆さんに言いたいのは、「大聖人様お示しの折伏とはそんなちゃちなものではないよ」ということです。もし顕正会が正しい団体なら、そのような「折伏」活動が展開されるはずはありません。いくら日本に危機が迫っているといっても、身近にいる後輩一人に正しい折伏も教えてやれない、後輩を追い詰めている団体に果たして日本は救えるのでしょうか? それもこれも、すべて顕正会の本尊と教義に起因するのです。日寛上人は「境能く智を発し、智また行を導く乃至、発心真実ならざる者も正境に縁すれば功徳なお多し」と仰せられています。顕正会の教義と本尊が正しければ、どうして折伏活動をして後輩を追い詰めるでしょうか?どうして般若のような顔をして約束取りを「監視」するでしょうか?どうしてそこらにみだりに御本尊様を奉持して入信勤行などできましょうか?どうして縦横無尽に縁のない人に声をかけて、恐れ気も無く入信を迫ることが出来ましょうか? これら折伏活動一つの中にも顕正会の教義と本尊が誤りであることが暗示されているのです。もし御本尊が正しければ、例え信心の無いような者にさえ信心を起こさしめるのである。もし本尊が正しくなければ、純粋な信心のある者さえ、その行動と方向性が狂って行ってしまう、と日寛上人は仰せです。顕正会も日寛上人を賛嘆しているのですから、この御金言を深く拝すべきです。 ニセ本尊、あるいは血脈の通っていない本尊を拝むと、それによって邪心が深まり、感覚はマヒし、信心しているつもりでもその考えも方向性も狂って行ってしまうのです。その反面、本当に正しい存在を誹謗するようになる。創価学会も正信会も同じです。 顕正会員は早く本当の本尊と信心活動ができる環境を求めるべきです。
2008.11.27
コメント(4)
-
御加護
御加護をいただくためには、もちろん仏様の仰せのとおりに信心しなければいけません。そうすることによって、仏様の御化導を助け参らせる諸天善神が仏前で立てた誓いを遂行するゆえに、正法の行者は守られ、以て成仏の果報を賜ることが出来るのです。 しかし、いまや世界中に誤った思想・宗教は蔓延し、諸天の働きも全世界的に弱まっている状態と言えます。この諸天の働きを失ってしまえばいかなる個人・国家も衰退していくのです。では、諸天をそのまま崇めれば御加護はあるのか?といえば、ありません。天照大神や八幡大菩薩等の善神を祭っている神社は多数あるといえども、神社などで祭られている善神の実体は単なる「紙」に過ぎません。その「紙」は正法の行者による祈祷や正法を護持される御法主上人による開眼供養も当然、施されておらず、そのようなただの「紙」に善神が住まわれる訳がありません。そこには逆に人を不幸にする悪鬼が住みついており、国土と個人を汚す働きをしてしまうのです。さらに付言すれば、神社で言うところの善神は上で書いたように、あくまで仏様の御化導を助け参らせる存在であるのですから、本来崇めるべき仏様を脇に置いて善神を主に祭っても、仏様も善神も喜ばれる訳が無いのです。「神は非礼を受け給わず」とある通りです。 さらに、諸天の中でも有名な帝釈天等を祭るところもありますが、これも善神と同様に諸天を主に祭っても詮無いのです。 このように、いま現在は一国がこぞって正法を汚している状態ですから、そこに個人と国家の衰退がますます加速度をつけて行っているのです。年始の神社仏閣参詣には今年も様々な場所にたくさんの参拝者が訪れることになるでしょうが、本当の幸せを願うのだったら宗教の正邪と影響力をもっと深く考え、正しい法のある場所に参詣すべきなのです。あたら不浄な法によって年始から自身の生命を汚し、年々不幸の根本原因を積んでいるのが世間の人たちであり、個人の衰退が個人で成り立っている国家の衰退にもつながり、日本には凶悪犯罪や不祥事などが相次いでいくのです。また、人心と天地の間にはお互いが影響し合うという働きがありますから、人の心が汚れていけば行くほど、天災等も相次いで起ってしまうようになるのです。 いわゆる、神仏の「御加護」を信じている他宗派や一般の方はかかる事実を認識せられ、改めて神仏や御加護という事を考えていただければ幸いです。
2008.11.26
コメント(1)
-
登山
顕正会員は必ず、「今の大石寺に参詣すると逆に罪を作るから参詣しない」と言います。逆にお聞きしたいのですが、どうして罪を作るのでしょうか? 本宗信徒に限って参詣を許されることは変わり無いし、御開扉料だって昔と変わりません。また、浅井会長が「付け願いという、お金さえ出せば登山したことになる制度が出来ました。こんなのは金儲けです」みたいなことを述べていますが、登山したくてもどうしても出来ない方のための特別な計らいであり、日常的に誰に対しても行われているわけではありません。宗門側の慈悲を誤解させるような指導はすべきでは無いでしょう。 「御遺命を破壊したから、そんな状態でお目通りしても功徳は無い」というのが顕正会の結論だと思いますが、国立戒壇という言葉を言わなくなっただけで実際の本門戒壇建立の御遺命は宗内から消えてはいません。 純粋な会員はぜひとも真実を確かめていただきたいと思います。御開扉の形式は昔と何ら変わっていないのです。
2008.11.18
コメント(3)
-
逸脱
今日、自宅近くの茶店で「創価学会のことを聞かせてください」という人二人と話をしてきました。彼らは「学会が今、色々と世間に影響を及ぼすことをしているけど、土底浜さんの視点から学会をどう思われますか?」と尋ねられたので、日蓮正宗で学ばせていただいていることを基に、こちらの学会観を伝えました。 私は世間の情勢に疎く、逆に向こうから教わることもありましたが、教義的な面ではしっかりと学会の脱線を伝えることができたと思います。向こうも前もってこちらがお渡しした本をしっかりと読んで下さっていて、「学会が脱線したことは、正本堂という建物も関連しているんですね」、「二代会長の頃までは学会も正しかったんですね」等の所見を聞かせていただきました。 さらに学会葬についても話が出たので、「僧侶不在の法要など本来は有り得ない。僧侶に来ていただいて故人を霊山浄土に送る儀式をしていただかなければ、故人は成仏できない」と伝えました。今の学会は(顕正会もそうですが)「僧侶がいないので在家だけで法要をせざるを得ない」という現状にあり、会員も無茶を承知で借り出されているのでしょうが、大聖人様は「仏宝、法宝は必ず僧によりて住す」と仰せのように、法要一つ取ってみても、僧侶同席の下に執り行うことにより、仏法の生きた姿が顕れるのですから、在家葬などはあってはならないことなのです。 池田会長の各所での言動についても話が出る中で、「池田会長はこんな発言をしているのに、学会員はおかしいと思わないのでしょうか?」と聞かれたので、「内部にいると分からないものです。」とだけ答えました。自分も顕正会時代は会に誤りがあるなど、気づこうともしなかったし、認めたくない心理が働いていたので、学会員もきっと同じ気持ちなんだろうなと感じる部分がありました。 「そちらの近所の学会員と会う機会があったら、私も同席させてください。こちらは教義的な部分で、そちらは世法的な部分で学会員を正しい道に戻し、救っていきましょう」と伝え、別れました。今日、お会いした二人は正しい信心を教えてくれという理由で来たのではないから、いきなり入信を勧める展開にはなりませんでしたが、「信心での正邪が一切の正邪を左右します」ということは伝え、「正しい宗教と信仰」を渡し、信仰そのものにも興味を持って頂けるように伝えましたので、これから「同じ信心をする同志」としてお付き合いできる日が来るように、祈りたいと思います。 ともかく、顕正会のように「今日中に入信まで持って行かなきゃ」などという、脅迫観念を抱かずにすっきりした時間を過ごせたので有り難かったです。また、次につながるご縁を頂いて無上の喜びでした。 ここで顕正会の皆さんにも伝えたいんですが、日蓮正宗の折伏は有り難いですよ。上にも書いたみたいに「折伏締切日」なんてものも無いし、自然に出来たご縁を大切に出来る折伏です。顔も知らない人に電話をかけて無理やり入信させること等はしません。日曜や祭日だからと言って、仕事を休んでまで活動を強いられることもありませんし、愚痴にもなりません。自画自賛ではありませんが、これぞ仏様の御意に叶った折伏だと思いました。 せっかくご縁が出来た大事な対象者を一回きりの折伏で「あいつは入信しないから捨て置け。次の対象者を当たろう」みたいな無慈悲な決め付けをし、対象者に勝手に見切りをつけ、そうやって誰からも孤立していくのが顕正会の活動の実態です。正しい折伏をしていれば完全に孤立するはずがありません。法華経にも「変化の人を遣わす」とあるように、怨嫉を受ける中でも本当に自身の向上のためになる人のみが自身の周りに現れるようになるのです。 顕正会員の方、このブログをいま見て下さっているあなたはいかがですか?ご自身に当てはまりませんか? 孤立していくことによって、居場所を同じ顕正会内に求めてしまう人もいますが、日蓮正宗にご縁できれば、そんな心配も無くなります。 勇気を出して法華講員と接触してみてください。すべてご自身のために・・・。
2008.11.14
コメント(1)
-
成果至上主義
何ヶ月も更新を怠ってしまいました。書くことも他の方とダブり、目新しいことも書けないので・・・。 久々に書くのは、成果至上主義ということです。顕正会時代からこのことには疑問を持っていました。折伏数の競争、御供養の多さの競争、教学試験の順位の競争などなど・・・。「果たして大聖人様はこのような数を絶対視するようなことを言われるだろうか」と。その数の状況を報告するのが週一の定例報告でした。数が上がっている組織はさして緊張も無かったでしょうが、私の組織のように長の私自身が幽霊会員みたいな組織にあっては苦痛この上ないことでした。私の上長は数が上がっていなくても、頭ごなしに怒鳴りつけたりする方ではありませんでしたが、それがかえって怒鳴りつけてくる上長よりも申し訳なく、丁寧にアドバイスをしてもらえることもまた、ますます苦痛でした。そうして「数に上がらないこと=だめ人間」という心理状態になっていくのです。 中でも御供養の多さを云々するのは御書に真っ向から背く大謗法です。土の餅でも仏様は喜ばれたという故事もあるくらいですから、そういう仏様の御前で金額の大小云々を論じることはそれ自体が恥さらしな行為と言えるでしょう。顕正会では私自身が入信して初めて参加する御供養の時に上長から「あの組織の○○さんは入信して初の御供養で上限を出している。誰に言われることなくだ。だから君も下限で良いなんてことは思わないように」と無慈悲な指導をされたことを思い出します。上限や下限などと区切ることも不自然だったし。 日蓮正宗の御供養は御書に則って推進されていますが、それでも「失礼の無い金額を」などというところもあるようです。信徒がお寺に気を使いすぎる例かも知れませんが、仏法上の御供養は本当に真心からさせていただきたいと願うのが正しいあり方だと思います。ましてや、日蓮正宗信徒はその浄財が大御本尊様への御供養ともなるのですから、そこに不順な心得違いが微塵もあってはならないと思うのです。私自身はその時に御供養できるぎりぎりの金額をあり難い気持ちで御供養させていただけているので、幸せです。 折伏に関しては、折伏で得た同志というのは本当の友人や伴侶にもなりえるのですから、まず自身が生活していく中で自然にできた縁故をたどって進めていくというのが常識のはずです。仏法は世間法でもあるのですから、やはり本来は縁の無かった人と無理やり縁をつくろうとすると、色々な面で歪が生じてきます。ましてや成果のために入信数だけ上がれば事足れりとし、その後の育成が無関心の状況も現実にあります。やはり育成しないと人材でも伸びては行かないですし、信徒数は増えてるけど広宣流布は進まないという矛盾した状態になってしまうのです。見た目の数だけが飛躍的に伸びても、それが直接広宣流布につながるわけでは無いのですから、育成も入信と同様に重視されるべき事柄だと思います。 (中途半端な形ですが、次回に続く)
2008.10.20
コメント(12)
-
顕正会の存続路線
顕正会では最近の会合等で、またしきりに「近年の御開扉は御聖意に背くものである」と批判しています。 こういうことを行う理由は大別して、(1)宗門に目を向けさせないため(2)会と会員の維持存続を図るため(3)破門に付した宗門に対する怨念の三つに絞られるのではないかと思います。要は最近、顕正会員が大勢宗門に帰伏している現状を見ていて、焦ったのではないかと思います。また、大聖人様や御歴代上人が参詣を勧められている文証は否定しきれないため、「御開扉は本来は良いことではあるが、今の日蓮正宗で行う御開扉は腐敗堕落した金集めに過ぎない」と批判することで、顕正会員に宗門帰伏の念を起こさせないようにし、以て「顕正会にこそ正義があるのだ」と言いたいのでしょう。 しかし、大石寺への参詣、大御本尊様へのお目通りを拒否・批判すること自体がすでに信心の筋道に外れており、それをせずして「正義」などありえません。それは例え顕正会が正しい団体だとしても、もしお目通りしなくても良いとなれば、各自宅拠点・会館等へいくら足を運んでも成仏の道場の意義は生じないからです。それは逆に人を不幸へと誘う「魔の住処」としかならないことを顕正会員は今一度、見つめなおすべきです。 各家庭・会館や寺院等に御安置される御本尊様はすべて「本門戒壇の大御本尊」様の御内証をお写しした御本尊様であり、本門戒壇の大御本尊様をお慕い申し上げるところに、初めて各家庭や寺院、会館等も成仏の血脈が流れる道場となりうるのです。今の顕正会はこのような基本道理も教えてもらえないような団体になってしまっています。 さらに顕正会はその大御本尊様のお写しである御本尊様を書写される、猊下の批判にまで転じるようになってしまいました。「66,67のニ代の貫首は創価学会に諂って大聖人の御遺命を曲げた。そのような者たちに果たして御本尊を書写する資格があるだろうか」と。しかし、もしこのお二人が本当にそのようなことをする方たちであれば、大聖人様が登座を許されないのではないか?と思います。いくら魔の力が強大とはいえ、正系門家の貫首の立場にあられる方を騙す事などできようはずもありません。そんなことがあれば、大聖人様の仏法の流れは65代までで止ってしまい、顕正会のいう「英邁な御法主」が出るまで衆生は大御本尊様に結縁することも、成仏することも出来なくなってしまいます。魔にできることはせいぜい、大御本尊様を恨む輩を輩出することぐらいではないでしょうか?仏法の流れを止めてしまうことまで出来よう筈がありません。 私のこの所感が間違っていなければ、顕正会員はとんでもない大謗法を犯していることになります。顕正会の皆さんにはぜひとも、「もし66代の日達上人が御遺命を破壊しておらず、67代の日顕上人も正式に血脈を受けられ、御遺命を堅持しておられたら・・・」と、顕正会で教えられているのとは逆の発想をしていただきたいと思います。 そのような発想ができるようになることが、大御本尊様にお会いできるための一歩となることを知ってください。
2008.02.18
コメント(56)
-
御法主日如上人猊下御指南集
徳のある人ない人 大聖人が喜び給う信心とは自行化他にわたる信心であり、この自行化他にわたる信心をもって正月を迎え、正月をもてなすところに、初めて「とくもまさり人にもあいせられ」るのであります。 徳が勝るということは、人にとってまことに大事なことであります。徳のある、なしは、その人の人生を大きく変えることがあります。俗に「徳あれば以て興り易く、徳なければ以て亡び易し」と言われるように、その人に徳があればおのずと栄え、徳がないといくら努力しても亡びてしまうものであります。 徳にも先天的に、その人が生まれつき身につけた「性徳」と、後天的に、その人の努力、修行によって身につけた「修徳」とがあります。どちらも徳としてはこの上なく大事なことでありますが、この修性のニ徳は「法華玄義釈箋」に「性は本爾なりと雖も、智にかって修を起し、修に由って性を照し、性に由って修を発す。性に在るときは則ち修を全うして性を成じ、修を起すときは則ち性を全うして修を成ず」(玄義会本下二〇一ページ)と説かれ、この両者は一体不二の関係にあることが示されております。つまり、本来的に衆生には性徳が具わっておりますが、それは修行によって照らし出され、その性徳があるが故に修徳を起こすことができるのであると示されているのであります。したがって、妙楽大師はこのあとに、両者の関係は水と波の如き関係であると仰せであります。 しかし、我々の仏道修行の上から言えば、性徳を照らし出す修行こそ最も肝要であって、この仏道修行がなければ、性徳も修徳も共に顕れてこないのであります。よって、もし仮に先天的に勝れた性徳を持っていたとしても、それだけでは徳としての用きはなく、また、性徳でけでは、その人の人生は生まれながらにして確定してしまい、人間の幸、不幸は修正のきかない機械論的な運命論になってしまいます。これでは人間の努力が評価されない偏頗なことになってしまいます。 しかし、徳のなかには、仏道修行によって身につけることができる修徳があり、我々の努力精進によって人間は大きく変わっていけるのであります。つまり、人間の幸、不幸は先天的に確定しているのではなく、仏道修行によって修徳を身につけ、これによって転迷開悟し、煩悩・業・苦の三道を法身・般若・解脱の三徳と転ずることができるのであります。 しかして、その仏道修行とは、すなわち自行化他の信心であります。
2008.02.18
コメント(0)
-
注意
最近、特に悪質と見られる書き込みが目立っております。当方はあくまで、私のブログに対して賛成でも反対でも、真摯なコメントを述べてくださることを期待しているのに、当ブログとは何の関係も無いご意見が多数書き込まれております。表現の自由というのも、限度があります。 末法の三毒の大衆が巣食う時代だから、必然のことかもしれませんが、今後は悪質と見られる書き込みは随時、書き込む側の許可なく削除させていただきますので、諸氏におかれましてはご了解を賜りたく存じます。 勝手に削除されて不快だと思われる方は、どうぞ当方まで申し出下さい。
2008.02.08
コメント(1)
-
昨日は温泉旅行
先日の職場の同僚との新年会では、「正しい宗教のすすめ」を渡すことができ、「やっと1ミクロ前進したな」という少し嬉しい気持ちになりました。世間の欲望を満たすのと違って、折伏行をやろうとすることは仏様のお手伝いをさせていただくことになるのですから、意義も功徳も計り知れません。 本を手渡すだけで折伏行をやったとは到底言えませんが、それでも少しでも日蓮正宗のこと、宗教の大事なることを知ってもらえる機会を同僚に与えることができて、有り難いです。ここからいかに進展させていけるかがポイントだと思います。また折を見て、未入信者向けの冊子等を手渡し、話ができれば良いな、と思います。 ところで、昨日は「愛する人」と近場で一泊の温泉旅行をしました。そこで早速注意されたのが、「あんた、お数珠とお経本は大事なものなんでしょ?そんな紙袋に入れて他の物と一緒に持ち歩くなんてダメよ!」ということでした。もちろん、いつも使用しているお数珠入れに入れて持って行ったのですが、それを他の物が入っている紙袋に入れて持っていってしまったのです。 「そんな大切なものは金庫にでもいれておかなきゃ」と続き、部屋の金庫にしまいました。さらに、「今度私がお数珠入れごと入れられる大きな袋を作ってあげようか?裁縫は苦手だけど、ミシンは得意だから縫ってあげる」と、思わずにんまりする言葉が この言葉を聞いて、お数珠とお経本の大事を改めて見直すことができ、「数珠は仏のごとくせよ」との言葉が脳裏をよぎりました。同時に「未入信の人に注意されるとは、気をつけないと日蓮正宗自体が低いものに見られてしまうことになる」と気を引き締めることができました。 短いやり取りではありましたが、とても印象に残りました。そう言えば、彼女の実家は創価学会で、彼女が子どもの時にお姉さんとお母さんが入信して信心していた、という話を以前に聞きました。学会も当時は日蓮正宗の中の団体でしたから、彼女自身は入信も信心もしていないと言っても、自分と彼女は「日蓮正宗つながり」と言えなくもありません。そう考えると、不思議な因縁を感じます。 その彼女のお母さんとお姉さんは早くに亡くなり、二年立て続けに葬儀を出したという話を聞いて、「大変な思いをしてこの人は生きてきたんだな」としみじみ感じ、今はただ「この人を幸せにしてあげたい」一心でお付き合いさせてもらっています。自分もこのあいだ父を亡くし、そういう面でも彼女とは共有できる部分があると思います。 彼女は肉親の葬儀に際して、「学会員が非常識な言動をしている姿を見て、自分はこんな信心絶対やるもんか!」と幼心に思ったそうです。当時の学会は日蓮正宗の中の信徒団体と言っても、板本尊模刻事件や会長本仏論等々、正宗の教義から逸脱してしまっている部分が多くあり、熱心な学会員ほど不幸の原因を積み重ねてしまっていたようで、彼女の心を傷つけるような言い方かもしれませんが、彼女のお母さんとお姉さんもおそらく、そのような状況にあったのだと予想できます。だとしたら、悔やんでも悔やみきれません。お二人の遺骨は幸い、日蓮正宗の寺院に納めてあるということですので、それだけでも、と思います。ぜひ、自分の大事な人の肉親の方たちには安らかに眠っていただきたい、と自分も御祈念しようと思います。 こう考えると、大聖人様が自分と彼女を引き合わせてくださったのかな?と思うし、彼女自身がもし正しい筋道の信心ができるようになれば、彼女の肉親のお二人も喜んでくださると思います。 何とか、一緒に信心ができる日が来るよう、願っています。ちなみに、彼女はチョビンさんと同い年で、性格も同じように明るく前向きな性格です
2008.01.16
コメント(5)
-
顕正会の折伏について
年が明けましたが、顕正会はまた「本年は折伏誓願数○○としたい。これが出来れば、十有余年後の三百万がぐっと近くなる」という発表をしているのでしょうか? 対象者がいなくなれば出身学校の名簿や街頭に繰り出して、誰でも手当たり次第捕まえてまで成果に挙げようとするその体質が変わらない限り、三百万が出来ても「数だけの団体」との批判は変わりません。否、それ以前に顕正会所持の御本尊がすべて血脈の通った正しい御本尊だということを証明できなければ、何をどのように変えようと、無駄な徒労に終わることでしょう。 私も会員時代は名簿やら街頭やらやっていたことは、これまでの日記にも書いておりますが、本当に辛い日々でした。折伏(勧誘)の約束が取れなければ、上長が目の色を変えて怒り出すわ、不機嫌になるわで・・・。そしてある日、「本部職員や先生は折伏法戦に連なっているのですか?」と聞いたことがあるのですが、「先生は自分たち弟子とは違った戦いをされているし、本部職員の方々は本部業務が忙しくて折伏する暇が無いし、対象者もいない。やり尽くしているから。自分たち一般会員はこういう戦いをするのが一番お役に立つ道なんだ」と言われ、腑に落ちなかったことが思い出されます。 ある掲示板で皆さん書いておられますが、「上長は折伏を下の者にやらせる」ということも実感してきました。まだ折伏の意味もよく分からない時にいきなり、「折伏をやってみようよ、莫大な功徳があるから」と言われ、やりましたが、今思えば「上長には対象者がいなくなっているから、成果を挙げるためには下の者に頼るしかないんだな」と感じております。 そのようなものは折伏ではないし、慈悲もあるわけがありません。いま宗門に来て、折伏とはもっと広い意味のことなんだな、と勉強させていただいております。実際に相手を呼んでしっかり話ができるのがベストの形というのは変わらないでしょうが、それ以外にも例えば、日々の生活の中で信心の会話をしていく、日蓮正宗の話を相手にしていく、日蓮正宗の書籍を渡して読んでもらう等等・・・。これらがすべて折伏成就に結びついていくということを勉強させていただきました。 明日は職場で良くして頂いている同僚二名(うち一名は先日書いた、愛する人です)と飲み会です。その場を利用して、未入信者向けの書籍を渡したいと思っております。
2008.01.07
コメント(1)
-
新年明けましておめでとうございます
皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。特に今回コメントをいただきました、コットンあめさん、南風さん、山門入り口さん、サンセイさんにはネット上、信仰上で非常に勉強させていただいております。今年もいろいろと勉強させていただけたらと思います。 去年は振り返れば自身にとって、二つの大きな出来事がありました。一つは父の死、一つは日蓮正宗への帰伏です。「明暗の来去同時」ということがありますが、まさに今それを実感しております。「明」とは日蓮正宗への帰伏、「暗」とは正法に付かせてやれずにあの世へ旅立たせてしまった父の死です。父は今頃、須弥山を中心とした四州八海の大陸のどこかに転生しているであろうことは想像できますが、いかなる果報を受けていようとも、こちら側の信心の功徳が父へも廻し向けられていると嬉しいと思います。そして、父の死が私を日蓮正宗へ導いてくれる原因の一つとなったのであれば、何としても生涯、日蓮正宗から離れず、臨終まで信心を貫きたいと思います。 今年はそれ以上に何かが起りそうな、そんな年になる気がします。(もちろん、良い意味で)大切なのは、自分を高めてくれる良き縁に遭うこと。今年もまた、良き縁により多く出会えることを期待しているところです。 私生活でも「愛する人」が出来ました。この人は一年前の職場立ち上げ時からずっと、自分のことを見守っていてくれている人で、少し前に二人きりで旅行に行きました。もちろん、一年前は顕正会時代でしたが、その時はさして素直に自分の気持ちを打ち明けられずに普通の人間関係を過ごしてきましたが、日蓮正宗に帰伏してから仲が深まったような、そんな気がします。「こういう状況になりたい」と思ったときに即法界が動いてくれているような、顕正会時代には感じられなかった不思議を感じております。この人も近いうちに私の家族と一緒にお山へ案内できたらなと考えているところです。とにかく、今年は去年出来なかったことを実行したいです。密かに、「法華講員の実践手帳」を購入して、本年の予定を立てているところです。
2008.01.02
コメント(9)
-
本尊の持つ影響力2
続きです。では日蓮宗を信仰するとどのような結果になるのか?日蓮宗は現在多くの流派に分派しており、新興系団体も多くあり、宗教界を雑乱させている要因の一つとなっております。また、そこで立てる本尊も多種多様で(多くは釈迦像あるいは不相伝のままに書き散らした曼荼羅を掲げているようですが)まさに、「諸宗は本尊に迷えり」の御金言のままです。 仮にも日蓮宗を名乗るくらいなのですから、本尊と教義については大聖人様の仰せを根本とすべきなのですが、御書の拝し方も解釈もばらばらで、大聖人様に近い存在と思わせておきながら、大聖人様に遠いという様相を呈しております。これは「この経は相伝にあらざれば知り難し」の姿そのもので、いかに日蓮宗を名乗ろうと題目を唱えようといつまでたっても真実の教えに到達できないのは、唯受一人の血脈相伝が日蓮宗には存在しないからにほかなりません。 そもそも、「法華経は尊い」と言っても、文上の法華経は本門・迹門ともに、すでに天台・伝教が広め尽くしており、この末法においては文上には顕れない、文底に秘し沈められた妙法蓮華経の五字のみがよく衆生を救う力があるのです。このことは大聖人様が「末法においては余経も法華経も詮無し只南無妙法蓮華経なるべし」と仰せられていることから拝されます。また、大聖人様は「法華経を広める」と御書のほとんどの部分で仰られており、末法に広まるべき妙法蓮華経の実体である「三大秘法」の名前は御書にほとんど出てきません。これらも相伝が無ければ決して知ることができず、「大聖人は天台等の後を継いで法華経を広める方」程度の認識しか出来なくなってしまうのです。さらに、大聖人様が末法の御本仏であられるという事に至っては、まさに正しい相伝のある日蓮正宗大石寺のみが知ることが出来ているのです。 以上のように、日蓮宗は真実の教えに似せてある分、その罪もまた大きく、これを信仰すると外見と中身の一致しない人格や生き方になってしまうのだそうです。顕正会員だった頃、日蓮宗系の立正佼成会の人と接したことがあるのですが、その一年前にこちらが顕正会に勧誘したことをまだ根に持って、下校の際に道が偶然同じになったら、こちらの乗る自転車に向こうの自転車が故意にぶつかってきて、「宗教バカ!」と一言残して立ち去っていきました。同じ道なのですから、こちらが後から追うような形で向かったら、「反撃されないだろうか?」という様子でこそこそと後を振り返りながら、逃げるように家まで帰って行ったのです。 その子は大学ではたまに講義で取り上げられるような、少し有名な子で、周りからの信頼も厚そうな子で、みんなの前ではいつもにこにこしておりましたが、二人きりになればこのように顔色を変えて変質し、またこちら側が勧誘した際には足を組みながらタバコを吸い、終始ふて腐れたような態度を取っておりました。 最後に、元々は日蓮正宗の流れに従っていた団体について書いてみようと思います。三者ありますが、代表として創価学会を挙げます。この団体は元々は日蓮正宗を外護していた最大の団体だったのですが、池田名誉会長に代わってからは、徐々に日蓮正宗の流れから逸脱していきました。どのように逸脱して行ったかといえば、(1)池田名誉会長を大聖人以上の仏とし、暗に会長本仏論を立てたこと。(2)「日蓮がたましひ」であるところの御本尊様を大石寺の許可なく勝手に模刻・変造し、今となっては学会員に無造作にコピーしたニセ本尊を大量に配布していること。(3)末法の僧宝を日興上人一人のみと立て、あるいは「正しく前進している和合団体である学会にこそ僧宝の資格が具わっている」として、独自の僧宝を立てたこと。(4)僧侶を単なる「法要執行係」と捉えて、僧侶抜きの「学会葬・友人葬」を開始したこと。(5)他宗との交流を全面的に認め、謗法与同したこと。(6)猊下を散々に誹謗し、止まることを知らないこと。等の項目に大きく分けられると思います。 完全な異流儀と成り果てた創価学会を信仰する人は上記の日蓮宗を信仰する人以上の害毒を受けていきます。世間をにぎわせた有名な犯罪者の中にも学会員が何人かおり、あの有名な「宅間守」やトリカブト混入事件で有名になった「八木茂・武まゆみ」等も学会員であるとのことですし、それ以外にも例えば、知的障害者施設の施設長で、そこの利用者にわいせつな行為をして妊娠させ、さらに中絶させた、という話も聞きますし、あるいは学会の職員同士で恋愛関係がこじれ、お互いを殺傷しあうという事例も聞きます。また、学会特有の害毒ではないでしょうが、邪宗を信仰する人は極端に短命である、という話を聞きます。落とさなくても良いところで命を落としたり、あるいはもう少し早く処置をすれば助かったというところで突然命を落とすのです。 池田名誉会長の息子も「胃穿孔」という病気にかかり、普通に治療すれば治る病気であるところを、息子が病気になったという事を知られたくなかったのか、偽名を使い、なぜか産婦人科に受診させ、そうこうしているうちに命を落としてしまったとのことです。 このように謗法者は大聖人様が嘆かれる、「早く有為の里を辞して無間の獄に墜ちなん」の御金言そのままの姿になって行ってしまうのであり、いかに信仰の正邪が大事であるかが伺われます。以上、簡単ではありますが、宗教の性質について書いてみました。 これらはこれから信心の道に入ってくる人もまだ入らない人にも、真剣に考えていただきたい議題です。
2007.11.26
コメント(4)
-
本尊の持つ影響力
先日は宗教が個人に与える影響力と題して書きましたが、今回はなかんずく、本尊の影響力について少し書いてみたいと思います。 歴代上人は「宗教は本尊と教義によって成り立っている。而して、本尊と教義の正邪がその宗教が正しいか間違っているのかを決定するのである」と仰せられ、決してその宗教が新興宗教か既成宗教なのかで正邪を決めるのでもなければ、信者の数の大小で正邪を決めるものではないと断じられております。その中で「本尊の正邪が一切の正邪を決める」と仰せられ、宗教の道に入るものは、その団体で立てている本尊がどういう本尊なのか探求していくことが肝要であると判じられております。 本尊とは文字通り、「根本尊敬」の意であり、自身の人生の根本に尊敬すべき存在として、どの宗教団体でも本尊を立てております。その本尊を拝むことによって自身とその本尊とのあいだに、「感応動向」という作用が働き、自身とその本尊とが一体化するという現証が必ず顕れるのですが、もし低級な本尊を拝めばその人自身の人格も人生も自ずと低級なものとなり、死後には地獄に墜ちるのです。反対に高尚な本尊を拝めば、その人自身の人格や人生が向上し、死後には成仏という無上の幸福境涯を得ることができるというわけです。 何を拝むのか、たとえば稲荷を拝んだとしたら、稲荷の持つ通力が拝む本人にも影響してきて、「こんな不思議なことがあった」という現証をもたらすこともありますが、深みにはまった頃には身も心もぼろぼろになっており、さらには「如是相」で、顔の相や自身の人生まで狐に似てきてしまうのです。つまり、人間の本来持っている理性や道徳が失われ、動物的な行動しかできなくなり、死後には悪道に堕するということです。 もう一つ、たとえば浄土宗の阿弥陀仏を拝んだらどうなるのか、浄土宗は「この汚れた娑婆世界を去って、早く死んで極楽浄土に生まれ変わりたい」と説いている宗派ですから、阿弥陀にもそうした退廃的な魔の通力がこもっており、これを拝むとちょっとしたことで「自殺したい」とか、「俺なんて早く死ねば良いんだ」といった被害妄想にとりつかれ、また、ちょっとしたことで攻撃的になり、周囲のものを破壊するかのような攻撃的な性格になってしまうのです。ちょうど、私の家も浄土真宗なので、それが良く分かるのです。自分は幸いにも日蓮正宗に巡り会えましたが、先祖代々の浄土の因縁は自身の生命にも深く影響しているわけですから、私も未だにちょっとしたことがあると、どんよりと落ち込んでしまうといったことを何回も体験しております。早く邪宗の因縁を断ち切り、私の代から日蓮正宗に改宗せねばと思うところです。 そして既成仏教のうち、禅宗は「経文も何も要らない。我が心こそ仏なり」と立てる宗派ですから、この宗派の本尊になっているダルマを拝むと、自ずと思いあがりと慢心が強くなり、「我こそ優れた存在なり」といって、現実を弁えられず、周囲から孤立していってしまうのです。 真言宗は大日如来を本尊としており、この宗派は法華経の極理・一念三千を天台宗から盗み取って自宗の肝要としているのですから、真実の法華経の教えを困惑するものであり、既成邪宗の中でも取り分け、罪が深いと言わざるを得ません。真実の教えを倒すものですから、この真言宗と大日如来を信仰すれば、一家においては主が急死したり、男性が立たなくなってしまうのです。そして女性が強い一族となっていってしまうのです。一国にはびこれば、必ず国を亡ぼす原因になり、日蓮大聖人はこのことを「真言亡国」と厳しく断じられているのです。(次回に続く)
2007.11.13
コメント(1)
-
宗教が人に与える影響力について
我々は生きて生活を営む中で様々な体験をいたします。まず生まれて来て、自分の家族との人間関係から現世における自身の生活が始まっていくわけですが、成長するにつれて保育園、小学校、中学校、高校、大学もしくは就職と自分を取り巻く環境も人間関係も多種多様になってきます。そのあらゆる段階で自分たちは様々な出来事を通し、時には喜び、時には悲しむ等、自身の持っている命を染めこんでいく働きを営んでいます。 この「命を染めこむ」というのはどういうことかと言えば、自分が人生を送る中で出会う人間や出来事によって、自身の持っている生命がその出来事や人間と会う前とは違った状態になる、ということです。この原理から言えば、もし自分を不幸に追いやるような悪い出来事や人間に出会ってしまえば、自身の命もその影響を受けて不幸な方向に染められてしまうし、逆ならば、自分を高めてくれるわけです。 一例を挙げれば、「自分はこの人と出会う前は怒りっぽくて、みんなから敬遠されていたのに、この人と出会ってからは不思議と穏やかな平和な気持ちになれた」とか、「自分はこれまではそれなりに幸せだったのに、あんな出来事があってから不幸の連続だ」という身近な事例が挙げられます。 じつはこれら現証こそが「自身の命を染める」ということであり、誰でも何らかの影響を受けながら日々生活しているのです。さらに突き詰めて言えば、「生命には周囲の事象を絶えず取り込んでいく働きが本来具わっている」と申せましょう。されば、自分を高めてくれる良き縁に出会うことこそ、人生の最大目標であるはずなのです。 この「縁」の中でも自身の生命に重大な影響を与えるのが宗教なのです。それはなぜかといえば、宗教が天地人を貫く大法則であるからです。この宇宙法界に存在しているものすべてが宗教の持つ大法則の輪の外にあることはありません。ことごとく宗教で説くところの因果の上に成り立っているのです。されば、自身の三世の因果を決めるほどの力が宗教には備わっているのですが、宗教ならどれでも良いというわけにはいきません。 もしその宗教が正しい宗教ならば自身の人生をこの上なく高めてくれ、成仏という無上の幸福境涯を得る存在となりますが、反対に邪宗を信じてしまえばその害毒はその人自身の人生に深刻な影を落とす結果となるのです。つまり、邪宗を信じたひとの生命をこの上なく不幸な方向に変えてしまうことになり、死後は無間地獄に墜ちると仏様は説いていらっしゃいます。また、一国にはびこれば計り知れぬ三災七難(地震や諸々の災害)を引き起こすことになり、今の日本がまさにこの三災七難が頻発しているのが、日本にも邪宗が多くはびこっている証拠なのです。 以上のようなことから、あらゆる「縁」の中でも宗教こそが最も、その影響力が大きいこと、そして正しい宗教の選択こそが自身が本当に幸福になるための唯一の手段だということがまとめられます。 私が所属している日蓮正宗は仏教の基本からあらゆる宗教の教義、正邪を判別し、道理を以って自身の宗派の正当性を示している唯一の宗派です。また何より本尊が優れていることが正しい理由の一つとして挙げられます。宗教を始めようかな?と思っておられる方、そして宗教に興味は無いという方、様々おられると思いますが、是非我が日蓮正宗総本山に一度足を運ばれることをお勧め致します。 私にメールでもいただければ、喜んでご案内させていただきます。
2007.11.10
コメント(4)
-
離反者の体質について
日蓮正宗から離反していった者たちの体質を見ていると、必ず本宗の最重要たる本門戒壇の大御本尊様、そして唯受一人の血脈相伝を否定しにかかっています。そして化儀も改変し、独自の教義を作り、最後には不相伝の日蓮宗や外道と同様の、日蓮正宗とは似ても似つかぬ完全なる独立教団と化していってしまうのです。 近年の異流儀の代表といえば、創価学会でしょう。宗内にいた時からたびたび、独自の教義を立て、本山から指摘を受けていたようですが、本山から破門されるやその本性をむき出しにして直ちに日蓮正宗への誹謗を開始したのです。池田名誉会長は、「破門されようが何でも無いんです、そんなことは」と言って、自ら断仏種の大謗法発言をし、学会員を不幸の路線に乗せてしまいました。そしてニセ本尊作成、僧侶不要、勤行の形式改変、同士葬、選挙に勝つためだけの「折伏」と、今や日蓮正宗とはまったく別の集団に成り下がってしまったのです。 そして、私が所属していた顕正会も今や学会と同様の路線をとり始めています。あれだけ「学会は日蓮正宗の教義を曲げてけしからん」と批判していたのに、今日は同じく日蓮正宗批判を開始し、しかもその批判するための情報が学会の使用しているデマ情報と同一であるというのですから、もはやため息も出ません。そして「僧侶は要らない」「勤行形式も非常事態だから変える」「塔婆は坊主の金儲けの手段」「日顕上人と日達上人のあいだの血脈は断絶している」「顕正会版本尊作成」等々、まったく体質が学会と似てまいりました。そして活動のためにすべてを犠牲にし、人間関係、自身の健康等、すべて失ってしまう会員が後を絶たないのです。さらに法華講員から道理を突きつけられても、「浅井先生が正しいから」の一点で、しかも繰り返し教え込まれている、「顕正会に背くと罰が当たる」等の論理を気にして大勢の会員が正しい信仰につけなくなっているのです。指導者と首脳部の罪は重いと言わざるを得ません。 三番目に正信会ですが、僧侶でありながら本山に離反し、あろうことか血脈否定に走った第一人者となってしまったのです。この正信会の論を学会が真似て、さらにその学会の論を顕正会が真似るというなんとも言えない「連携」が成り立っている様には、「異流儀はこうなってしまうのだな」と断ぜざるを得ません。今回の大白法で取り上げられていましたが、今また正信会は新たに拠点を作り、そこに正体不明の本尊を安置するとか何とかいうそうですが、何を安置しても日蓮正宗に背いたのですから、そこに功徳も成仏もありえません。 いまこれら異流儀が国を乱している片棒を担いでいる様を見るとき、当ブログを通して少しでも異流儀の恐ろしさ・誤りに気づける人が出ることを願ってやまないものです。
2007.11.07
コメント(4)
-
改めて「直結論」を考える
ここ最近の顕正会は「大御本尊直結」を打ち出し、「戒壇の大御本尊様は一閻浮堤総与であるから、私たち一人ひとりは戒壇の大御本尊様と直接つながっているのです」と主張します。 しかし、日蓮正宗従来の考えはどうなのか?結論を言えば直結などありません。必ずその中間に取次ぎをしてくださる御法主上人がましまさなければ、我々は大御本尊様との血脈をつなげていただけず、結果、成仏に迷うことになるのです。血脈に総別の二義があることは信徒であれば弁えなければならないことですが、この別しての血脈というのは大聖人様以来、代々の猊下にのみ伝えられる、「唯受一人」の血脈相承のことで、その中には広宣流布の暁でさえも公開されないと言われる秘伝法門も存在すると伺っております。 対して、総じての血脈というのは、この唯受一人血脈を尊崇するところ、大衆にも流れてくる血脈のことで、この総別の意義を弁えて信心に励むところに成仏があるのです。さらに具体的に言えば、御内証が大聖人様と同様である代々の猊下の仰せに随順して初めて成仏できるということなのです。されば、この猊下を誹謗したりすればどうなるのか?その瞬間から成仏できる道が断ち切られてしまうのです。いま顕正会や創価学会、正信会はこの猊下を散々に誹謗しております。そして、日蓮正宗から破門されることによって、中間の「御法主上人」ということを叫ぶと自らの立場や存在意義が無くなるから、「自分たち団体と大聖人は直接つながっている」とし、正当性を無理やり打ち出そうとしておりますが、それ自体が狂っているのです。 創価学会と正信会が大御本尊様さえも否定する中で顕正会のみが一応、大御本尊様を尊崇する言辞を述べておりますが、「大聖人」直結と「大御本尊」直結の文字が少し変わっただけで、本質的には同じです。なぜなら、大聖人様の御魂はそのまま人法一箇の大御本尊様と成り給うて大石寺にましますからであります。 彼らが今日、主張しているようなことに対して大聖人様、歴代上人様は何と仰せなのか?まず大聖人様は、「総別のニ義少しも背けば成仏思いもよらず」と仰せられ、日興上人は「大聖人の直弟子と勝手に名乗っているような者は謗法である、無間地獄に墜ちる」(取意)と厳しく仰せられております。また、日淳上人は「仏法において相承を立てるのは法が混乱しないためである」(取意)と仰せです。これらの仰せに照らせば「直結」などありえないし、無理に直結を主張し、その中間の唯受一人血脈を否定したり無視すれば、「法が混乱する」ということになるのです。ましてや、「一閻浮堤総与だから我々は大御本尊と直接つながっている」などと言ったら、信心のまったく無い邪智の者でもいくらでも「つながっている」ことになってしまいます。 そうならないために、総別の血脈があるのであり、「別」を無視して「総」はありえません。まとめれば、日蓮正宗に入信し、時の猊下を師匠とし、信心修行に励むところ、初めて大聖人様の御内証、大御本尊様の御内証に自らも入れていただくことができ、成仏が叶うのです。日蓮正宗から離れた上記の三団体には改めて「この基本から学びなおせ」と言っておきます。
2007.11.06
コメント(0)
-
10月度総幹部会会長講演について
早速、山門さんがアップしてくださった会長講演を見ましたが、ひどいものでした。主な要点を挙げれば、(1)日達・日顕の両上人を二代の悪貫首と罵り、「このような二人に御本尊を書写する資格はない」と改めて断じたこと、(2)不敬の御開扉を止めよと相変わらず叫んでいること、(3)御本尊下附というのは、身命も惜しまぬ信心の者にのみ許されることであって、今の日蓮正宗の御本尊下附は不信の者にまで押し付ける「坊主の金儲け」の手段であると断じたこと、(4)顕正会を「陥れる」ために御本尊を下附はしない、御開扉は受けさせないと宗門が言ったということ(5)三大謗法について(6)日布上人と日達上人の臨終の様を比較したこと(7)大御本尊直結論(8)血脈断絶発言にまとめられると思います。(1)について言えば、どの猊下の書写された御本尊様も差別などありません。仮に両上人が本当に御遺命に背いていれば顕正会の主張どおりでしょうが、両上人は背いていないことは他の皆様も論証されている通りです。それより何より、平然と日号を呼び捨てにできる自らの無道心を恐れるべきなのでは?と思います。(2)大聖人様の御元に参詣することは信徒ならば当然の行為です。もちろん、「いつでも大聖人様にお会いできる」などと慣れの心を起こしてはいけませんが、足を運ぶこと自体は信心があれば自然にやっていることです。顕正会が「御高徳の上人」と称える日寛上人も「志有らん人は登山して拝し給え」(寿量品談義)と仰せであり、どこに登山するかといえば「本門戒壇本尊所住の処」=大石寺とお示しです。御遺命はなんら破壊されていないのですから、御開扉もいつの時代も変わらずの精神です。堀上人の「富士日興上人詳伝」を引いていますが、これとても文意を取り違えております。堀上人は御開扉そのものを否定されていないのです。むしろ、「近年においては常例となっておる」とお示しです。(3)御本尊下附については、身命も惜しまぬ者に授与されるのが「常住御本尊」であり、そこまでの信心が確立するまでは「御形木御本尊」を頂いて信行に励むというのが従来の教えです。顕正会はこの「常住様」と「御形木様」の違いをあえてなのか、論じようとしません。混同させてまるで、「御形木様を頂くことさえも許されない」かのように言っています。これは遥拝勤行を正当化させるための論法でしょう。大聖人様は「本尊流布」をせよと仰せられており、「遥拝勤行」を弘めよとは仰せられておりません。故に、顕正会も妙信講時代(破門前)には皆が御形木様を頂いてきたはずです。それを今になって「遥拝勤行こそ正当である」などとは、ためにする論と言わざるを得ません。ましてや、現日蓮正宗の本尊下附を「金儲け」と言うなど開いた口がふさがりません。確かに御入仏式の時に若干の御供養はしますが、それも御僧侶に自宅まで来ていただいたこととかに対するこちら側の気持ちであり、「いくらよこせ」などという薄汚い世界では無いのです。「御供養」そのものを即「金儲け」などと思っているとしたら、すでにその者は信心がありません。(4)顕正会に対して本尊下附をしない、御開扉を受けさせないというのは、顕正会が本山の教導を無視した行動を取り続けたからです。ましてや、除名処分以降は日蓮正宗信徒では無くなっているのですから、日蓮正宗に対してそのようなことをいうこと自体、おかしな話でしょう。そのような形になりたいのだったら、顕正会員を本山に帰伏させてあげられるような計らいを顕正会首脳部がしてみたらどうでしょうか?(5)と(7)については論じ尽くされていることなので今回はあえて触れません。(6)と(8)については関連がある事柄だと思います。日達上人のご臨終の様はもちろん自分ごときがうかがい知ることはできませんが、顕正会の言い方は明らかに日達上人を悪し様に言うことが目的だと感じました。また、ご臨終の詳しいご様子など側近の方にしか分からないはずなのに、どうして浅井会長がまるで実際に立ち会ったかのようなことを言えるのか?立ち会うことなど絶対に不可能であり、さればそれは他から聞いた情報を元に言っているだけであり、その情報元とは誰なのでしょうか? そして、日顕上人が「相承を受けていない」と繰り返し言っていますが、その情報元もどこなのか?逆に日達上人が「次は阿部に譲る」と言っておられたとする証言もたくさん有りますよ。ましてや、顕正会も過去に「代を重ねること67」と言っていたではありませんか。「67」とはもちろん、日顕上人以外におられません。いい加減に破綻した論法を繰り返すのは止めにしていただきたいものです。今回は今後の顕正会の基本方針みたいなものを会長が整理して、改めて示したような内容の講演に見受けられました。もしそれが図星だとすれば、まさに「大謗法路線」ということになるでしょう。御当代・日如上人の御事には相変わらず、一言も触れずにいたのも気になりました。「二代の貫首の御本尊は拝んではいけない」とならば、御当代・日如上人御書写の御本尊様はどうなるのでしょうか?自分の家に御下附いただいた御本尊様は日如上人御書写の御本尊様なのですが・・・。
2007.10.31
コメント(5)
-
御法主日顕上人猊下御講義「創価学会の偽造本尊義を破す」2
学会側の主張 この「導師本尊」がニセモノである以上、「ニセ本尊」を形木(印刷物)にした「未来本尊」こそ本物の「ニセ本尊」ではないでしょうか! 日顕上人の破折 これについては、逆にこの導師本尊が血脈付法の上の衆生救済の正しい本尊であるから、したがって、その形木本尊も正しい本尊であった、ということを述べておきます。 学会側の主張 この「ニセ本尊」を。古来より当たり前のように、しかも「未来本尊」という名前をつけて、棺や骨壷の中に入れて、土葬、火葬等を行っていたことが、宗門の「正しい化儀」のマニュアルに明確に書かれているのです。 日顕上人の破折 「教師必携」において「過去においては未来御本尊を発行していたけれども、今は行わない」ということを書いた理由は、過去のある時期に、冥界に趣く御信徒の信心の上からの安穏救済のために歴代上人が大慈悲の上から御形木の未来本尊の授与を許されたことがあったのであります。すなわち、「寂日坊御書」の、「此の御本尊こそ冥土のいしゃう(衣裳)なれ」(御書一三九四ページ)という大聖人のお言葉の文義からも、土葬、火葬等、死者の精霊が曼荼羅のお供をするという意義であります。しかし、これはその時代時代の機に対する化導の変遷によるものである。したがって、下種の法体たる金口血脈の一貫せる伝承は万年不動であるけれども、その経過の中の時と機に対する化導方式には、時代によってある変化が存しているのは当然であります。 そこで、日達上人の代、私が教学部長のころでしたが、「教師必携」を新たに作製するに当たり、時代状況から鑑みて、これから以降は行わないということに定められたのであります。ですから、その元の一貫する正しい化導ということにおいての間違いは、いささかも存在しないのであります。 学会側の主張 これは日興上人が富士一跡門徒存知の事で「曼荼羅なりと云って死人を覆うて葬る輩も有り」と破折された五老僧の末裔が、宗門に古来より多く巣くってきたことの証明ではないでしょうか! 日顕上人の破折 ここに引く日興上人の「富士一跡門徒存知事」についても、彼らは文の意を正しく拝することができず、誤った見方より誹謗しています。「存知事」に、「曼荼羅なりと云ひて死人を覆ふて葬る輩も有り」(御書一八七二ページ)というのはことごとく、前後の文から拝して大聖人御自筆の御本尊についておっしゃっていることなのです。つまり、その本義を弁えない五老門流が造仏本義に執われた結果、大聖人様の御自筆本尊を非常に軽く見、卑しめるという事例を述べられた所なのは明らかです。だから、日興上人門下においては重大な決意をもって、大聖人様の御本尊を「これ以上の大事大切な御法体はない」という信仰のもとに守護すべきことを示された文なのであります。 それと、歴代の血脈伝承の上の時代による化導方式としての未来本尊とを一緒にする頭の悪さは、救いようがない。まさに創価学会の素人解釈であり、噴飯の錯誤と言うべきである。だから「五老僧の末裔が宗門に古来より巣くってきた証明だ」などの悪口は、全く当たっていないのであります。 何よりもかによりも、日寛上人は「五道冥官」を入れた、お前らが「ニセ本尊」と称する導師本尊を書かれている以上、不当の法主となるはずだから、さっさと今の「ニセ本尊」を取りやめ、大逆賊の池田大作にでも本尊を書かせたらどうだ、と言っておきます。
2007.10.22
コメント(2)
-
御法主日顕上人猊下御講義・「創価学会の偽造本尊義を破す」
学会側の主張 また、住職になる者が必ずマスターしなければならない正しい化儀について書かれた日蓮正宗教師必携においても、(第5章 葬儀回向)の箇所で、(古来末寺において、御形木の未来本尊を発行する習いがあったが、今は行わない。)と書かれています。この「未来本尊」とは、邪宗日蓮宗が葬儀専用に開発した「導師本尊」という「ニセ本尊」を形木にしたものです。これには大聖人が書かれた御本尊とは明らかに異なる「五道冥官」等の偽の経文の悪鬼とも言えるものが書かれており、江戸時代より古くから邪宗日蓮宗で始めた葬儀向けの化儀を、宗門でも江戸時代になって取り入れたものです。 日顕上人の破折 次に教師必携の(古来末寺において、御形木の御本尊を発行する習いがあったが、今は行わない・同書八〇ページ)という文を取り上げています。これは一往、前にこういう例が宗門にあったから、このように教師必携に書いたわけです。これについて、この(未来本尊)とは邪宗・日蓮宗が葬儀用に開発した導師本尊という(ニセ本尊)を形木にしたものだ、と誹謗し、(これには大聖人が書かれた御本尊とは明らかに異なる(五道冥官)等の偽の経文の悪鬼とも言えるものが書かれており、江戸時代より古くから邪宗・日蓮宗で始めた葬儀用の化儀を、宗門でも江戸時代になって取り入れたもの)と言い、この導師本尊がニセものである以上、それを形木にした未来本尊もまた(ニセ本尊)であると言うのです。 しかるに、それならば第一に、邪宗・日蓮宗の葬儀用の化儀が導師本尊であって、これを宗門が江戸時代に取り入れたと言っておるが、そういう事例の明らかな証拠があるなら提出してみよ、当て推量は慎めということを、はっきりここに言っておきます。 次に(五道冥官等は偽の経文の悪鬼だ)ということを言っておるのですが、欲界、色界、無色界の三界・二十五有と六道十界の衆生はことは広く経文に説かれており、その上の論釈に五道等が存することは古来の通義であります。悪鬼ということを言うのであれば、大聖人御本尊中の鬼子母神、十羅刹女も、その元は悪鬼ではないか。御本尊の中に入って本有の尊形となっておるけれども、その元の形は悪鬼であります。 要するに、冥府における五道冥官も三界の外ではなく、本仏所有の法界の中にあるのです。特に大聖人様は「戒法門」という御書のなかに、五道冥官を挙げられております。創価学会の認識は素人だましの、狭小の眼識によるところの迷見であります。 次に「大聖人が書かれた御本尊とは明らかに異なる」とも言っておるが、これは本尊の内証口伝を受けていない者が形式だけを見て、その曼荼羅弘通の規模の大きさを知らない偏見であります。 冥界へ向かう衆生への化導救済の意義より、天照大神、八幡大菩薩の代わりに閻魔法皇、五道冥官を書かれることは、「南無妙法蓮華経 日蓮在御判」を中心とする一念三千の本尊にあってはいささかの違法もないのであり、これを「ニセものの本尊」とすることは、本尊相伝のない創価学会の短見・邪見なのであります。 創価学会は歴代上人のなかで、日寛上人こそ大聖人直結の方であると讃しているが、その日寛上人の在家に授与された数幅の御本尊に、明らかに天照、八幡の代わりに閻魔法皇、五道冥官と書かれておる御本尊が現存しております。また、日寛上人の御師・二十四世日永上人の書写にも閻魔法皇、五道冥官の書き方が拝され、さらに上代の御先師にも存在しております。その血脈の上からの流れは、近年では日応上人、日亨上人、日開上人にも同様の書写の御本尊が拝せます。特に先師日達上人はこの意味において導師御本尊をお示しであり、私もその上から伝承して、冥界へ向かう信徒の化導のための本尊として、いわゆる導師曼荼羅として「閻魔法皇・五道冥官」を書写申し上げておるのであります。 創価学会では日寛上人のお徳を特別に取り上げて、「大聖人直結」などと珍妙な語を捧げるが、この日寛上人に五道冥官の本尊書写があるのは、一体どう言い訳するのか。日寛上人も創価学会で言う「ニセ本尊」を書かれたことになるわけです。ということは、日寛上人もまた「ニセ本尊」を書いたインチキ不当の法主となるはずであり、今回の「ニセ本尊」もそれに類する悪法主の書写だということになるではないか。 常に目先だけのところを取り上げて誹謗を繰り返すから、このような論旨の破綻をきたすのである。恥を知れ、と言っておきます。
2007.10.22
コメント(0)
-
支部総登山
昨日は支部総登山があり、私も御登山させていただきました。初めてお目にかかる方々がたくさんいらっしゃり、活気に溢れておりました。特に南風さん、AKIRAさん、AKIRA2さん、チョビンさんにお目にかかれたことは非常に嬉しかったです。 チョビンさんとは、軽く挨拶を交わすくらいでしたが、トチロ~さんの仰るように、また今まで自分にいただいたメールから伝わってくるように、「元気の良い方」であるという印象がとても強かったです。 南風さんは「紳士」という印象が外見から伝わってきて、また性格も穏やかそうな方で、初対面でも気楽にお話をすることができました。 AKIRAさんたちは、御開扉に向かう直前に自分に声をかけてきてくださいまして、「土底浜さん、お久しぶりです」と明るい感じで挨拶してくださったので、気持ちが和みました。AKIRAさんの横にいらっしゃる方がAKIRA2さんだったとは最初は気づきませんで、てっきり女性の方だとばかり思っておりました。他にもニシケンさんご一家やつるまるさん、サンセイさん等もいらしており、まさに「ネット上のそうそうたる面々」を前にして緊張しまくりでした。 しかし、このような嬉しいこともあった反面、落ち込んでしまうこともありました。それは「自分より後に入った方たちでもどんどんと折伏成果を上げて明るく前進しているのに、自分は何をやっているのだろう、まだ0じゃないか。顕正会でも役立たずで、また宗門に来ても役立たずになるのか・・・。」と少し涙を流してしまったことです。世法の面でも自分は行動力と積極性に欠け、そのためにチャンスを逃してしまうことも多々あり、今また信心の面でもこれが災いしていることになるとは、仏法即世法、世法即仏法であることを痛感いたしました。 そしてもう一つが、「一人で登山することのわびしさ」です。皆さんほとんど、同士を引き連れて御登山なさっておりました。自分も同士を連れてきて共に喜びを分かち合いたい、家族や大事な人も連れてきて笑顔いっぱいの御登山にしたいという願望はあるのに、気持ちばかりが焦って実行に移せません。それが歯がゆくて悲しくて、昨日は休憩時間に呆然としていました。 これから自分がどのようになっていくのか、仏様はすべてご存知でしょう。しかし自分には分かりません。果たして自分には使命があるのかどうか、たまたま、日蓮正宗に縁できただけではないのか?等々を深く考えさせられる一日でした。 感激でいっぱいの気持ちで帰路につかれた方々には湿っぽい話で非常に申し訳ありませんでした。自分が登山のたびにこのような気持ちになるのは、罪障が吹き出ている姿なのでしょうかね。だったら嬉しいのですが、もし違っていたら・・・。 昨日は終了後に御住職様や皆様にさしたるご挨拶もせずに帰ってきてしまい、非常に申し訳ありませんでした。この場をお借りして皆様にお詫び申し上げます。
2007.10.22
コメント(7)
-
顕正会との決別と正宗への入信3
正宗への入信を断ってから、一ヶ月目くらいに父が突然しゃべれなくなり、入院、そしてさらに一ヵ月後に死亡したということは以前書いておりますので、あえてここでは省略いたします。最大の悲しみの中に葬儀は実家の宗旨である浄土真宗で上げることとなりました。当時は「顕正会で上げてあげたかった」と思いましたが、今思うと「どっちで上げても同じようなものだったな」と感じ、当時はどのみち父を正しい宗旨で送ってあげることが出来なかった状況だったんだなと、悔やまれます。 父の死を顕正会の同士に知らせたら、「何もしてあげられなくて申し訳なかった。自分も父を亡くしているので気持ちは痛いほど分かる。お父さんが成仏できるように頑張っていこう」と励ましてもらい、ある同士からは香典までいただきました。 こういった同士の姿を見ているので、同士に対する不信はあまり感じなかったのですが、未だに会の問題部分に対しての説明をしようともしない、浅井会長と顕正会組織全体に対しての不信感は強まっていきました。「もしかしたら、これは罰なのではないか」とようやく思い始めることができ、そのような中で、以前からメールのやり取りをしていた東京在住のある顕正会員の方が先に正宗に帰伏され、連日のように「顕正会とはまったく違う!」と感激メールを送ってきてくださっていたのも相まって、ついに6月9日に御受戒を受ける決心がついたのでした。 その前夜は職場の飲み会でして、まるで次の日の御受戒を職場のみんなが祝ってくれているかのような、そんな楽しい飲み会になりました。そして、迎えた当日、遠路はるばるトチロ~さんが自宅まで迎えに来てくださり、自分も前日の酔いがすっかり抜けてしっかりとした体調で所属末寺に向かうことになりました。 到着して本堂にて御受戒となりました。頭上に御本尊様を頂き、「汝この大法を持ち奉るやいなや」等の戒文が奉読されるたびに厳粛な気持ちになり、顕正会で受けた入信勤行とはまったく別次元のものであると実感しました。終了後は御住職様、奥様、トチロ~さん、講頭さんから「これからが本当のスタートですから、しっかりと頑張ってください」と激励していただきました。その際、御住職様より「今までは大御本尊様との血脈がつながっていない立場で、代わりに泥水が自身に流れ込んでいるような状態だったけど、今日からはいきなり正しい血脈がつながるのですから、その反動もあると思います。罪障がどんどんと噴出してきて苦しくなるでしょう。覚悟はしておいてくださいね」と恐怖の一言(!?)をいただき、身が引き締まる思いでした。 翌日はいきなり大御本尊様にお目通りが叶い、御講にも参詣させていただけまして、貴重な二日間となりました。そしてそれからしばらくして、御本尊下附もしていただき、今に至ります。ここまで顕正会時代からの軌跡を述べましたが、正宗の信仰に出会って少しづつ、自身が変わりつつあることを実感しています。この世界を知らない人たちに感激を伝え、自身の宿命に苦しんでいる人たちを正宗の信仰に導くのが自身の使命であることをもっともっと自覚し、これからやっていきたいと思います。(終)
2007.10.16
コメント(1)
-
顕正会との決別と正宗への入信2
トチロ~さんと出会い、そちらのブログに殴りこむようにコメントを書いていったのですが、そのときは「御遺命を破壊した宗門に行ってしまうなんて不憫だ、何とか彼の命あるうちに顕正会に戻してあげたい」と本気で思ったこともありましたので、考えつく限りのことを彼に言いましたが、ことごとく反論されるのです(笑) しばらくトチロ~さんとやりとりを続けていくうちに、「何で御遺命を破壊した宗門がこんなに反論できるのだろうか?本当なら生命力を失って、顕正会員に簡単に屈伏させられているはずなのに、おかしいな。それと浅井先生や本部はどうしてネット上の学会員や法華講員の暴論を放っておくのだろうか?教学室が出来たのだから反論すればよいのに」と自分の中で動執生疑が起きてきました。そこにきて、ネット画像で妙観講の大草講頭と浅井会長の電話のやり取りで浅井会長が「貴様、馬鹿だの、馬鹿だの」と大草氏を口汚く罵っている姿、それと、顕正会員が妙観講本部や妙観講員に襲撃をかけた一件などを併せてみたら、どんどんと会に対する疑問が湧き上がって来たのです。 しかしまだ、妄信の徒でしたので、それだけで宗門に気持ちがなびくことはありませんでした。むしろ、「みんなが反論しないならば俺がネット上で反論してやる!」と意気込んで茶寮掲示板等で無茶な論を展開するようになったのです。そうしたら、法華講員から散々反論され、こちらも負けないようにとやり返しておりましたが、どうしても宗門側の論を崩せないのです。今から思えば、七百五十年の伝統を崩せなかったのは当たり前だと思えるのですが、当時は「何とか突破口があるはずだ」とそればかり模索しておりました。 そして、顕正会側のトップ弁士である櫻川さんさえも法華講に対して苦しんだ論を展開している姿を見て、妄信の中にもやや法華講寄りの考え方をするようになりました。こうして徐々に法華講側に誘引されるような、目に見えない何かが自分の身の周りに起きつつありました。 迎えた平成十九年、前年よりもトチロ~さんとやり取りする機会が増え、大石寺にも初めてご案内していただき、その時の印象は今でも忘れられません。その時に今の所属寺院の御住職様、奥様、講頭さんの三人ともお会いし、顕正会の誤りを指摘され、法華講で信心に励まれるようにと言って頂いたにも関わらず、その時はまだ顕正会を信じていたため、入信を断ったのです。それがその後の父の死という悲劇となって返ってくるとは思いもしませんでした(続く)
2007.10.13
コメント(1)
-
顕正会との決別と正宗への入信1
以前に「日蓮正宗への入信と親」と題して書きましたが、もう少し書いてみたいと思います。 自分が初めて法華講員と接したのは、大学時代でした。そのときは「法華講員てガラが悪いんだなあ、まるでチンピラじゃないか!やはり御遺命を破壊した害毒を受けているんだな」と思いました。その人は自分と同学年の子でして、一家が日蓮正宗なんだそうです。「君はちゃんと勤行しているのか?」と聞いたら、「勤行?そんなもの、亡くなったじいちゃんの法要の時くらいだね」と答えたので、「だめだ!法華講員は浅井先生の言うように信心がまったく無い!」と強く思いました。今から思えば、おそらくその家は墓檀家に成り下がっているのではないかと思います。いくら正しい団体に身を置いていても、御本尊様を拝まない、お給仕もしないでは、宿命は変わりませんし、罰も受けるでしょう。今どうしているのかは知りませんが、どうか正しい信仰につけたありがたさを思い起こし、やっていってほしいと念願しております。 次に会った法華講員は父の友人でした。その方は学会を経て法華講に移られたらしいのですが、これまた、「信心の話はいいよ」と逃げ腰で確信が感じられない方でした。そのようなこともあって、そのときは「やはり顕正会が正しいのだな」と洗脳の真っ只中におりましたので、ほかの団体に目が行くことなどありませんでした。 そんなこんなで、顕正会での会合参加、折伏、新聞啓蒙、二大項目参加と、一通りのことを六年間やってまいりました。しかし、顕正会での活動にも正直、疑問を感じていました。特に、休日は早朝から翌明け方までずっと戦っている姿勢、対象者がいなくなったらなりふり構わず、街頭で声をかける姿、自宅拠点を構えている上長自ら、メル友やホームレス折伏等の危険なことに手を出していること、「額はその人が出せる金額でよい」と言いつつも、「下限で良いとかは間違っても思わないように」と正反対の事をいう上長、あるいは、自分たちは折伏活動に携わっているのに、浅井会長や本部職員は折伏をやっているのか、折伏が流れた瞬間の上長の豹変した態度等々、書きつくせないほどの疑問がありました。 いつの頃からか、ネットも見るようになり、顕正会内以外の情報にも触れる機会ができてきました。最初に大衝撃を受けたのはトチロ~さんのブログでありました。ありのままの顕正会の姿をえぐり出しており、最初は反感の目で見ておりましたが、トチロ~さんのお人柄にも触れ、「法華講の方が正しく見える」と思い始めてきました。(続く)
2007.10.12
コメント(4)
-
日亨上人講述・追考聖訓一百題
一閻浮堤第一の御本尊を信じさせ給へ。相構へて相構へて信心強く候て三仏の守護を被らせ給ふべし。行学の二道を励み候べし。行学絶へなば仏法はあるべからず。我も致し人をも教化候へ。行学は信心より起るべく候。(諸法実相抄の末文) 宗門で一信二行三学と云ふ大則はこの御文から来るのである。信は何を信ずるやと云ふに、一閻浮堤第一の御本尊を信ずる。即ち観心本尊抄に仰せらるる所の「一閻浮堤第一の本尊此の国に立つべし」とあるのがその始めである。本尊抄は文永十年卯月二十五日の御作で、此の実相抄は、それから間もなき五月十七日である。賜はりは、吾開山日興上人であるが、普通の版木はこの末文の辺が入れ違ひになっておる。それに又最蓮房宛の、追伸が後に付いて二重の錯誤を生じてるが、このことは他日に委しくする考へであるから、ここには略する。 併し一閻浮堤第一の本尊とは御曼荼羅の総名である。宗祖のお認めなされた御曼荼羅は何れにせよ一閻浮堤第一の本尊で本尊抄の次下の文にもある通り「月支震旦に未だ此の御本尊有しまさず」とある意である。別して云ふ時は、この閻浮第一に何分の差等あるべきである。宗祖御真筆の御本尊の今に現存するもの、恐らく百幅とはあるまい。最もその道の者が調べ上げた上でのことで、その中に相伝の処で種々の名称を着けて、それぞれ特殊の尊敬を払ってをる。それは即ち別名である。その別名の中に、吾山の本門戒壇の大御本尊在します。併しこれは吾山限りの別名ではない。現に分分になってる八教団共同して尊敬すべきものである。この時こそ「一閻浮堤第一」の本尊の名が相応する。 古来賞美の語に、日本一、三国一、等の慣用語がある。今では、世界一、の語も出来た。御開山は老輩の弟子檀那を称して、「日興が第一の弟子」と云はれ、又その中から選びて「一が中の一の弟子」と云はれた 一閻浮堤第一は総名、戒壇本尊は別名であるが、日寛上人は内容の上から、宗祖の御真筆の本尊の総てを別相の本尊とし、戒壇本尊を総相の本尊と云はれた。近年荒木翁が、戒壇本尊は、未来の満天下の一切衆生に授与せられたものであるから、総与の御本尊と云ふべきと主張した。これも大いに、意義ある語であるから、追々と用ひらるる。但し私の云ふ総名と別名と、寛師又は荒木翁の云ふ総相総与とは、少しばかり総別の使ひ所が違ふのみで往ひては同じことである。総々於別などを振り廻すにも及ばぬ。只管一日も早く、一天広布の日を念じ奉って、吾も信じ、人も信じ、又吾が国人も信じ、外国人も信じ奉りて、諸仏の慈光に包容せられて、平和に消息したいものである。 この信心の下に、修行と学問との二の道がある。如何に正義な熱烈な信心を有っていても、修行と学問とで、それを助長してゆかぬと、或いは落着もなくなり、進歩も覚束なくなる。そこで、「行学絶えなば仏法は有るべからず」と御警告なされた。小乗経の三十七道品は、一寸迂遠のやうであるけれども、その意向を常に用いて、行学に励まねばならぬ。自行学だけでは、利他の益を失して信心者の行為でなし。「自行化他に亘りての南無妙法蓮華経」と特持せらるる大則に背くことである。(続く)
2007.10.11
コメント(0)
-
創価学会「ニセ本尊」破折100問100答2
7・戒壇の大御本尊と各家庭の御本尊との関係を教えてください。 「本門戒壇の大御本尊」は、根本となる究極の御本尊であり、「各家庭の御本尊」は、御本仏日蓮大聖人より日興上人、日目上人へと、大聖人の御内証の法体を唯受一人血脈相伝される御歴代上人が、根源たる本門戒壇の大御本尊の御内証を書写して下付される御本尊です。総本山第五十六世日応上人が「弁惑観心抄」に「此の金口の血脈こそ宗祖の法魂を写し、本尊の極意を伝えるものなり、これを真の唯受一人と云ふ」(同書二一九貢)と指南されているように、代々の御法主上人に伝えられる血脈相承によって、はじめて本門戒壇の大御本尊の法魂・極意が書写されるものです。したがって血脈相伝の教えに信順し、本門戒壇の大御本尊を信ずる一念をもって拝むならば、書写された御本尊もその功徳に変わりはありません。しかし信仰が戒壇の大御本尊から離れ、血脈相伝の教えから離れるならば、いかに各家庭の御本尊を拝んでも功徳は生じません。かえって罪障を積むことになるのです。
2007.10.11
コメント(0)
-
創価学会「ニセ本尊」破折100問100答
1・日蓮正宗の正しい本尊について教えてください 日蓮正宗の正しい本尊は、「日蓮正宗宗規」第三条に「本宗は、宗祖所顕の本門戒壇の大曼荼羅を帰命依止の本尊とする」と、明確に定められている「本門戒壇の大御本尊」です。この大御本尊は、宗祖日蓮大聖人が「聖人御難事」に「此の法門申しはじめて今に二十七年・弘安二年なり、仏は四十余年(中略)余は二十七年なり」(全集一一八九頁)と仰せのように、御本仏の出世の本懐として顕わされました。日興上人の「日興跡条条事」に「日興が身に宛て給わるところの弘安二年の大御本尊は日目に之れを相伝す」(聖典五一九頁)と仰せのように、この大御本尊は、日興上人、日目上人と唯受一人血脈付法の御歴代上人によって相伝されています。日寛上人は「就中、弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟中の究竟、本懐の中の本懐なり。既に是れ三大秘法の随一なり」(富要四ー二二一貢)と説かれ、弘安二年十月十二日に御図顕の本門戒壇の大御本尊は、宗旨の根本となる本尊であると教示されています。代々の御法主上人は、その相伝の権能のうえに本門戒壇の大御本尊の御内証を書写され、本宗僧俗に下付されるのです。 2・なぜ学会で授与する本尊が「ニセ本尊」なのですか。 たとえば、精巧なカラーコピーの機械で、紙幣をコピーして「お札」を作製するとします。意かに本物の「お札」と見分けがつかなくても、そのコピー札は「ニセ札」であり、それを使えば法的に罰せられます。なぜかといえば、1・正式な政府の許可なく、2・日本銀行から発行されたものではなく、3・自分で勝手に作ったものだからです。「ニセ本尊」はこれとまったく同じ道理です。1・御法主上人の許可を受けず、2・総本山から下付されたものではなく、3・学会が勝手に作製したものだからです。学会では「自分たちが和合僧団だから、その資格がある」と主張しますが、一体その資格はどなたから受けたのでしょうか。御歴代上人の中で、創価学会に相承された方などおられません。もし「広布を願う一念があればその資格が具わる」などというのならば、誰でもいつでも勝手に本尊を作ることができることになり、大聖人の仏法は混乱し、滅亡してしまうでしょう。ニセ札は法律で罰せられますが、「ニセ本尊」は仏法破壊の大罪として、必ず現罰をこうむるのです。3・総本山第二十六世日寛上人の御本尊を「ニセ本尊」と呼ぶのは日寛上人に対する冒涜ではありませんか。 宗門では、浄圓寺所蔵の本證坊個人に下付された日寛上人御書写の真正の御本尊を「ニセ本尊」といっているのではありません。御法主上人の許可なく、勝手に複写されたものを、私たちは「ニセ本尊」と呼んでいるのです。そのうえ、創価学会は日寛上人の御本尊にしたためられていた「授与書き」を勝手に削り、会員に販売しているのですから、学会が日寛上人のお心に背き、日寛上人のお徳を汚す大罪を犯しているのは明白です。これこそまさに、日寛上人に対する冒涜以外の何ものでもありません。4・日寛上人の御本尊を複写したものを、なぜ宗門では「日寛上人の本尊ではない」「日寛上人のお心に背く大謗法」というのですか。 宗門でいう「日寛上人の御本尊」とは、「日蓮がたましひをすみにそめながしてかきて候ぞ」(全集一一二四貢)と仰せの、大聖人の「たましい」が、血脈相承のうえから、正しく写されている御本尊のことです。しかし、今回学会が勝手に複写して作ったものは、姿・形は日寛上人の御真筆とそっくりであっても、血脈付法の御法主上人の許可がないので、大聖人の「たましい」が写されておらず、「日寛上人の御本尊」とはいえないしろものです。たとえば自分が勝手に御本尊を写真に撮って、それを拝むのと全くおなじことであり、大謗法なのです。また、学会では日寛上人の御真筆御本尊にしたためられていた「大行阿闍梨本證坊日證」という授与書きを勝手に抹消し、変造しており、これが「日寛上人のお心に背く大謗法」になるのは当然です。5・「ニセ本尊」を拝むとどうなるのですか。 「ニセ本尊」には、仏法に敵対する魔の力があり、これを拝むと魔の通力によって現罰を受け、その謗法の罪によって永く地獄に墜ちる結果となります。大聖人の仏法において「似て非なるもの」を用いるということは、大謗法です。その理由は、仏に似ているがゆえに、正しい教えが隠され、多くの人々が真実の仏を見失ってしまうからです。大聖人は、真言宗が天台の一念三千を盗み入れて「大日経第一」と立てたことに対して「真言亡国」と破折されていますが、今回創価学会が作製した「ニセ本尊」は日蓮正宗の御本尊を盗み取り、日寛上人の御本尊に姿・形を似せているだけに、その罪もまた大きいのです。第二代戸田会長は、御本尊について、「ただ、大御本尊だけは、我々は作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、唯受一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない。だから、仏立宗や身延のヤツラが書いた本尊なんていうものはね、ぜんぜん力がない。ニセですから、力がぜんぜんない。むしろ、魔性が入っている。だからコワイ」(大白蓮華九八ー九頁)と指導しています。6・「ニセ本尊に功徳がない」ということは、学会員が拝んでいる従来の御本尊には功徳があるということですか。 三宝を誹謗する謗法団体となった創価学会に所属している人は、従来の御本尊でも功徳は積めません。「ニセ本尊に功徳はない」というのは、その本尊自体が、最初から大御本尊の血脈が通じておらず、仏力・法力が具わっていないからです。従来の御本尊は正しい血脈のもとにまさしく仏力・法力が具わっており、御法主上人の御指南に従って正しく信仰をすれば、功徳があることはいうまでもありません。しかし、従来の御本尊であっても、拝む人が血脈付法の御法主上人を誹謗するならば、四力(仏力・法力・信力・行力)が合せず、功徳はありません。かえって、拝むほどに罪業を積み重ねることになります。さらには今までの信心による一切の功徳が消えてしまうことを恐れるべきです。「信心の血脈なくんば法華経を持つとも無益なり」(全集一三三八貢)とは、このことです。
2007.10.11
コメント(2)
-
高橋公純師著・仏教と女性1
性と仏教の諸問題1 「結婚はなぜするのか」という問題に関して、今の若者の意見はどうであろう。「そんなことナンセンス。好きだから一緒にいるだけ。愛しているから離れられないだけのこと」などという答えが多かろうと思う。だが、特に戦国時代など、結婚ということは、その一族の浮沈興亡に大きくかかわった。 結婚して、多くの子孫を残すということは、その一族の戦力につながることであり、優秀な子供をたくさん持つことは、その一族の繁栄につながる。 また、江戸時代においても、子供のない者は、幕府は承継権のないものとして、領地を没収した。 領地を没収されれば、自分の一族及び、自分に従ってきた家来たちまで困窮させてしまう。 ゆえに、一族の長としては、少しでも早く結婚して、まず子供を得て一族の安泰の基盤をつくる。一族の長としては、結婚、子供をつくるということは、絶対必須条件であった。 この一例を見ても、実は結婚の目的、結婚はなぜするか、という命題は「子孫の繁栄、民族の維持と発展」と言うことがいえよう。 大正九年暮れ、昭和天皇(当時皇太子)の妃に内定した久迩宮良子女王に、島津家に由来する色盲の血があると内定取り消しを強便に主張した、山形有明は、これによって、枢密院議長の椅子も投げ出す決意をするが、山形の「勤王に出て勤王を討死した」という言葉の示すように、山形にとってみれば皇室の発展、即日本の発展というのを念頭において、至誠を示したのであろう。 仏教では、男女の性交に関して、菩婆多論「久しく煩悩を習う故と父母の性交を利して福徳の子を得」とされている。 簡単にいえば、一つは人間としての本能であり、もう一つは種族の保存である、と。仏教は、種族の保存と決めながら、現在からすれば異常なまで、男女間における厳しい戒律を設けた。それは何度か述べたように、修行にとって最大の敵は女性であるとされたからである。 日蓮聖人の御義口伝という論の中に、「宝浄世界とは我等が母の胎内なり。胎内とは煩悩を言うなり。煩悩の汚泥に真如の仏あり。我等衆生の事なり」という御文がある。これを、簡潔に訳すと、宝浄世界という、仏教で説く安穏な理想の世界は私たち母の胎内である。しかし、一義に胎内というのは、煩悩そのものであるが、その煩悩という汚い泥の中に、真如の仏が存在する。それはまぎれもなく我等衆生そのものなのである、というのである。 もう少し説明を加えよう。まず、キリスト教やイスラム教では人間と神の存在は全く隔離されているが、仏教では、仏の存在というものは人間の存在なくして考えられない、いかなる仏でも人間の修行した結果である、という論法を頭の中に入れておいてもらいたい。 さて、宝浄世界とは多宝如来の住む清浄なる世界とされるが、ほんとうの仏説というものは、決して架空なものを説かないから、宝浄世界が母の胎内である、ということは、母の胎内、即ち、すべての人間が出生するところ、これ本来なら何物にも代えられぬ宝で飾られた浄らかな世界でなくてはならないはずである。 伝教大師は、「国宝とは何物ぞ。宝とは道心なり。道心ある人を名づけて国宝となす」と言ったが、いかなる金銀財宝より、人間の生命が尊く、大切であり、たとえ、魏王が所持していたとされる経寸の珠であれ、世界最大のダイヤモンドであれ、人間という宝から比べれば、なお木石である。 この地球よりも重い人間の宿るところ、即ち、母の胎内は何よりも尊い宝浄の世界でなくしてなんであろう。しかし、母の胎内というのは煩悩にもなりうる。なぜならば、男女の性交という者は、種の保存にあるが、快楽のために行うは人間だけであるからである。つまり、人間の快楽のために行うものと、種の保存のために行うものと圧倒的に、快楽のためにのみ行う方が多い。 さらにこれが不倫であったり、大事な修行中の者をたぶらかすような性行為ならば、女性の胎内というのは、まさに単なる煩悩そのものであって、女性の胎内がどれほどの不幸を生んだことであろう。不幸や混乱を生む胎内ならば、これ煩悩そのものである。しかし、正常な夫婦における性交、種の保存、民族の維持と発展という明確な目的であっての性交であるならば、なんら恥じることはない。煩悩と見える女性の胎内にこそ、真如の仏、つまり、次への後継の人、民族の未来のために、なくてはならない人がいらっしゃるわけである。ゆえに、「煩悩という汚泥の中に、真如の仏がある」のである(続く)
2007.10.10
コメント(0)
-
お伺い書
顕正会是正協議会が作成した文書で明らかにおかしい点が二つ存在ほど存在していることは、一読すればお分かりになるかと思いますが、いちおう指摘してみたいと思います。(1)法華講等の御遺命違背を諌めんとするに・・・。 御遺命を破壊したのは学会で、宗門は当時、信徒の増加に伴って「正本堂は御遺命の戒壇になるかもしれない」と大きな願望を懐いていたことは事実でしょうが、諸般の情勢を鑑みて、「未だに正本堂は御遺命の戒壇にあらず」として、日達上人が「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。すなわち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」とお示しになられました。 当訓諭の意味を拝察申し上げるならば、根源の大御本尊様が格護される大殿堂なる故に、現時における事の戒壇であり、それがそのまま、日蓮正宗を信ずるものがこの先、遠い将来ではなく、近くに日本国の動向を左右するほどに増加するならば、正本堂はそのまま、本門寺の戒壇となるべき堂宇であるということであると思うのです。しかし、その後の学会は日蓮正宗の純真なる信徒を増やすどころか、自ら日蓮正宗の教義に逸脱する行為を次々と行うようになり、「本山よりも自分たちが上」との転倒の念を懐くようになり、そのような状況下で、正本堂は御遺命の戒壇となるかもしれない意義重大な堂宇であったけれども、発願主の学会の念、すでに謗法味を帯びてき始めたとあっては、とても、御遺命の戒壇の意義を持つ建物とはいえなくなったとして、宗門は結局は正本堂を御遺命の戒壇とはいえないというスタンスを取って来たと見るべきでしょう。 要するに、当時の宗内は妙信講も含め、全体が「御遺命が実現するかもしれない」という空気であったのであり、故に妙信講も正本堂のご供養を募るに際しては、「私たちの身に生涯二度とは無い大福運」といって、暗に正本堂が御遺命の戒壇になるかもしれないということに大きな期待を膨らませていたのでしょう。だから、「学会と宗門が御遺命を破壊しようとしたのを妙信講だけが止めた」などという考え自体が根本から誤っているのです。そもそも、正本堂建設委員会での日達上人の御説法を「同管長はこの時、正本堂を御遺命の戒壇とする旨の説法をされたのであった」と言っていることは、その御説法があった後に行われたご供養に妙信講も正本堂を御遺命の戒壇と認識した上で参加していることになります。かかる指摘を受けると、「同管長はこの時、正本堂を一言も御遺命の戒壇とはいわれず」と、苦し紛れに正反対の事を言うのですから、何が真実か分かりません。 是正協議会の方々には、ぜひとも「御遺命守護」ということにこだわることなく、会員という思いも捨てて、外部から諌めるような冷静な諌め方をしていただきたいと念願しております。この辺りのことも会長への質問事項に織り込まれてはいかがかと思いますが、それは彼ら自身の立場も否定することになるので、難しいでしょうね。(2)暫時の化儀として新たに御本尊を作成しているのだったら、その正当性を示し・・・。 これは正当性など証明できないでしょう。なぜなら、猊下のみに御本尊に関する一切の権限があることが示されている文証があるからです。おそらく、是正協議会の方々もそういう文証はご存知だと思いますが、ご存知でありながら、なぜこういう質問をするのか理解に苦しみます。御当代猊下の命を受けて、御隠尊猊下が書写あそばされたり、あるいは時代によって末寺住職が書写されたり、各末寺で御形木御本尊が下付されたとか、様々な歴史的事実はありますが、資格の無いものが勝手に御本尊を書写したり、あるいは印刷したり、あるいは、まったく宗史に存在しない御本尊を作成しても良いという文証はどこにも無いと思います。こういう御本尊に関する問題が起こってくるところ、まさに、「諸宗は本尊に迷えり、本尊に迷うゆえに色心に迷う、色心に迷うゆえに生死を離れず」の御金言どおりではありませんか。 いま自らの色心に迷い、入信前より苦を増している顕正会員の姿を見ますとき、ますます、そういう思いを強くします。是正協議会の皆様にはぜひとも、この二点を特に練り直していただきたいと、個人的には思っております。
2007.10.05
コメント(2)
-
日亨上人御談・三大秘法と戒壇の歴史4
国立戒壇建立の時は 小平・先ほども、ちょっと、出ましたんですが、最後の国立戒壇の義について。 猊下・どういうことです。それは・・・。 小平・将来の予想について・・・。 猊下・将来の予想だからヨソウかな(笑) 池田・その前に、三大秘法抄の中の「懺悔滅罪の戒法のみならず大梵天王・帝釈等も来下して踏み給うべき戒壇なり」の中の大梵天王・帝釈天王を、印度とか支那とか朝鮮の、総帥とか内閣総理大臣とかいわれる意味は考えられないですが・・・。 猊下・それは考えられない。大梵・帝釈天等というのは、日本仏教の王朝時代からというものはね、大分親しくなって外国の神様ではなくなっている。そのくせでしてね、帝釈や大梵というのは、印度では仏教以前の神様ですからね。帝釈はいくらか小さいけれどもね。大梵なんていうのは印度の国をつくった神様ですからね。日本でいうと天照大神じゃ。 池田・はあ、 猊下・仏教の中で何かその神というようなものをつくると、必ずこの大梵・帝釈が出てきますからね。ですから、来下して云々なんていうことは、むしろですね、その神様が来下するんじゃなくてね、印度人がくるとみてもいいでしょう。馬鹿に梵天・帝釈は日本仏教に親しみがありますね。不思議なくらいですね。各宗が分裂していますけれどもね、どの宗門だって梵釈ということをいっている、梵釈が一般の人の言葉の中に入っているんじゃ。格別仏教の信仰が深くないものにもですね、梵釈の用語はいろいろの場合に使われているでしょう。普通の仏法の教理以外にね。 池田・題目の流布とか、本尊の流布とかは実際考えられますし、話してもきていますが、時代によって、戒壇の建立の姿が変わるであろうと先程いわれましたけれども、戒壇の流布というのは考えられないものでしょうか。 猊下・戒壇の流布は考えられんね。それは「時を待つべきのみ」の国立戒壇じゃから・・・。 池田・国立戒壇は第一歩だからいいんですけれども、朝鮮とか支那の戒壇の建立の時期ですね、流れ方です。流布になれば、日本人が行って教化していって、建立するか・・・。 猊下・それは考えられんね、考えられんというのは、今の支那仏教でも、朝鮮仏教でも、そういうようなことは、毛ほどもないからね。朝鮮など、例の山岳仏教でね、金剛山とか何とか有名な山があるけれどもそこに戒壇を建立するという意見は、どこにも吐いていないからね。つまり、支那でいうと、五台山なんていうのが、山の姿といい地理といい、そうとうに支那では有名じゃけれどもね、そこに戒壇をどうこうということは殆んどないからね。各種の仏像はおいてあるけれどもね、戒壇の思想はないね。 小平・今はなくとも、将来日本に刺激されてそういうことがおきてくる・・・。 猊下・それは後の問題だ。 龍・これから題目が流布されていって・・・ 猊下・ええ、題目が流布され大聖人の教義が流布されるというと、その三大秘法の中に含んでいるからね、どうしても、その授戒を求めるというような考えは必ずあるにちがいない。 池田・義の戒壇が先ず・・・。 猊下・ただ国立の戒壇という言葉にはならんけれどもね。国でなくても、私の戒壇というのは、できるだろうと思う。それから又昔の仏教の歴史を考えるとね、支那の仏教には時の皇帝が戒壇を建てたということは少ないからね。戒壇はもっと、こう小部分にできた。 池田・「霊山浄土に似たらん最勝の地」まあ最勝の地は日本は大日蓮華山でわかりますけれども、「時を待つべきのみ」の時ですが、その辺について・・・。 猊下・それは摂受によって時をつくるのもあれば、折伏によってつくるのもある。観心本尊抄の末文なんかはですね、摂受・折伏の両方をあげてあるね。折伏のときは国家が武力でもって折伏して、摂受のときは僧侶がでておだやかに布教をする。両方の面をやっていくわけだね。両方の面になっているけれども、大聖人のすべての御書にあらわれているところのものは、まあ折伏になるね。布教の徹底するということは、摂受で布教の徹底というのは、まあないですからね。折伏一手です。その折伏はですね、極端な折伏は武力ですから、それは国王がやらなければならん。それ以外には武力はないから。 龍・それはつまるところ国家対国家ということになるんでしょうか。 猊下・ええ、国家対国家になる。 辻・賢王愚王になるわけだな・・・。 池田・国立の戒壇のできた場合の形式というか、原論は本山にあるんでしょうか。 猊下・ああ、戒壇をつくる趣意かね。それは本山にある。 辻・六万坊が建つんですか。 猊下・六万坊はですね、それは、六万恒河沙なんという数からくるというと、六万恒河沙というのは、百億、千億どころじゃないです。大数を示したんじゃよ、ガンジス川の砂の数は数字で表せるかね、君。それで一恒河沙だもの、その六万恒河沙の上の数をとっただけで、六万坊などというのは、そりゃ夢だよ。ずっと測量して見給え(笑) 池田・それから、もったいない話だけれども広宣流布の暁のような気が、私どもにはするのでございますが、お肉牙の問題は、これはもう考えられない不思議な問題だと思います。 小平・お肉牙のことは、ずいぶん昔から・・・。 猊下・そう、文献にのこっているのは、古くからのってるね。 池田・本因妙抄や百六箇は、そうとう早くから引かれているんでしょうか。 猊下・ええ、そうとう早くから引いてありますね。早くから引いてありますけれども、本山では余り使わなかったね。 池田・仏法の住処という問題なんでございますが、「富士山に本門寺の戒壇を建立すべきものか」という戒壇建立の住処という位置が、どういう位置か・・・。 猊下・そうね、これは実際問題じゃからね。実際問題だけにどうも分からんね。わからんけれども、そうなってくるとね、実際に地理をもとにしなけりゃ仕様がないでしょう。それは、富士なら富士群とすればね。富士群の中の良い地理を調べてやるんでしょう。 池田・皇居が関係することがもう、きまっていますね。 猊下・きまっています。それはですね、門徒存知抄始め明らかにいってあります。天台山や平安城の例をひいていっていますよ。 池田・必ず仏法というと山に関係ありますよね。 猊下・そうそう。 池田・何か、そこに由来があるんでしょうか。 猊下・それはね、印度の仏教はですね、昔から市中におかない、その山がですね、秀麗な山におくということになっている。 小平・それじゃ、お疲れのところ、長い時間にわたってどうもありがとうございました。予定の項目も終わりましたので、これで閉会に致します。 一同・どうもありがとうございました。(以上)
2007.10.05
コメント(0)
-
九月度総幹部会会長講演2
そしてもう一つ、気にかかったのは、長野大会でも講演された「大御本尊直結論」と誤った御本尊下附観、それと、「御在世のごとくの信行に帰ろう」ということについてでありました。大御本尊直結論については、おそらく、学会の「大聖人直結論」を真似たものであろうことは予想できます。今回の大白法にも、この顕正会の大御本尊直結論が取り上げられ、破折されておりましたが、その通り、顕正会は信仰の根本を大御本尊に置いているという点では学会と相違がありますが、「直結信仰」を唱えているという点ではまったく相違がなくなってしまいました。日興上人は「このほうもんはしでしを、ただして、ほとけになるほうもんにて候なり」(佐渡国法華講衆御返事・歴代法主全書1-182ページ)と仰せられ、続けて、「あんのごとくしやう人の御のちも、すゑのでしどもが、たれはしやう人のぢきの御でしと申やからおほく候。これらの人ほうぼうにて候也」(同184ページ)と、直結信仰を厳しく戒めておられ、必ずその中間に手継ぎの師を仰いでいくべきことを示されております。詮ずる所、学会や顕正会は本山から破門になり、中間の「手継ぎの師」という事を論ずると都合が悪くなったから、「直結」を唱えるより仕方がなくなったのでしょう。かかる指摘を受けて「会長こそが手継ぎの師」などという新たな邪説が出てこないよう祈ります。どのみち、付嘱の法体たる大御本尊様は大石寺にましまし、その法体相承を受け給うた御法主上人猊下も同じく大石寺にましますのでありますから、その流れから外れていくら直結を叫んでみてもその思いが大御本尊様に通じるはずもありません。ましてや両団体はこの法体相承を受け給うた猊下を散々に誹謗しているのですから、総じての信心の血脈も通わず、結果、年々に異流儀化するという現証となって現れているのです。次に「各個人は遥拝に徹するとしても、主要な拠点や会館にだけは御本尊様はなくてはならない。」という講演が引っかかりました。従来はまず個人が信仰していくための、一機一縁の御形木御本尊の御下付を願い出て、個人の信仰の基本とし、信行が進んできて不惜身命の信心が確立した後は常住御本尊の御下付を賜ることになるというのが大石寺の化儀であったはずです。さらに遥拝の意味についても、宗門で言う遥拝とは、猊下が丑寅勤行の後に遥拝所でされる勤行を指しており、一信徒が御本尊を御安置できる環境に無い時にする勤行は「内得」と言っております。学会は各会員に御形木にしたニセ本尊を配布し、形だけは従来の大石寺のように「一人ひとりに御本尊下付」というスタンスを取っているのに対し、顕正会は「主要な場所にだけ」というスタンスですが、これまたいずれも異流儀化を物語って余りあるものです。上記のように法体相承を無視していては、両団体ともいつまで経っても正しい本尊観に立てないことでしょう。最後に「御在世のごとくの信行に帰ろう」については、御在世どころか、いつの時代にも見られなかった独自の信行を作ってしまっていると感じます。御在世のごとくと言いたいのなら、大御本尊様の御下へ参詣し、親しくお目通りをさせていただき、常日頃から五座・三座の勤行に励むべきであります。参詣の意義や功徳を称えられた文証もいくつもあります。また、五座・三座の形式については日寛上人が、「開山已来化儀化法、四百余年全く蓮師の如し」(当流行事抄・大石寺版六巻抄193ページ)と仰せられ、続いて「開山の勤行全く蓮祖の如し」(同ページ)と仰せられていること、そして「五座三座の格式相守るべし」(福原式治状)とを合わせて考えれば、大聖人様の時代より五座三座の勤行が存在したことが想像できます。これを勝手に略式勤行に変えてしまったことのどこが「御在世の信行」なのでしょうか?方便品・自我掲のみに変えてしまった学会も同じであります。逆にそのような学会の姿を見て「方便品・自我掲のみに変えてしまった学会の勤行を見て驚いた」と体験発表する顕正会員も、目くそ鼻くそを笑う姿そのものであります。以上が簡略ではありますが、総幹部会を見ていて自分が思った感想であります。さらに詳細な面での誤りというのもあるかと思いますが、それはまた随時取り上げて行きたいと思います。
2007.10.03
コメント(1)
-
九月度総幹部会会長講演
私もつい先ほど、山門さんが載せた会長講演を見ました。見てみて、感じたのは「明らかに是正協議会、及び脱会者の訴えに対して大きな影響を受けている講演だな」ということでした。あまり口を開きたくないであろう、本尊問題にまで言及せざるをえないところに会長の焦りが見えます。「導師曼荼羅六幅」ということを初めて言い出し、また、問題になっている日布上人大幅御形木本尊に関してはまったく口を開かず、ただ、「日寛上人と日布上人の御形木御本尊」という抽象的な表現に終始していましたね。これが顕正会が公表できる限界と自分は睨みました。おそらく浅井会長は亡くなるまでこういう論法で行くことでしょう。また、宗門批判も激しかったですね。改めて、「細井日達・阿部日顕」と両猊下を下し、また、「このような輩に御本尊を書写する資格があるのかどうか・・。顕正会はこの二代の貫首の御本尊に縁することなく、清らかな日寛上人、日布上人の御本尊を拝する立場になれたことはまことに幸いである」として、暗に両猊下の御本尊まで蔑視する発言をしていたことには、「何と恐ろしい発言をするものよ」と驚きを隠せませんでした。両猊下が本当に御遺命破壊に加担していたならそれは顕正会の主張どおりかもしれませんが、顕正会だって当時は正本堂を「意義重大」、「その意義は凡眼の伺うにあたわざるところ」、「正本堂の御供養に参加できることは私たちの身に生涯二度とは無い大福運」などと言って称えていたのですから、宗門への批判は的外れです。御遺命を破壊したのはあくまで学会であり、宗門はぎりぎり一線のところで学会の魔手からその御遺命は護られ、今に伝わっており、両猊下は顕正会や学会が何とか良い方向に向かってくれる様、様々なご苦心をされたと伺っております。結局、その深い御慈悲を知ることができなかったから、かえって反発し、顕正会も学会も破門になり、今は両方とも御本尊も自前のものを作るしかなくなった、大石寺従来の化儀も改変し、年毎に異流儀化してしまっているのです。かかる現実を自分達の都合の良いふうに解釈し、「猊下がおかしいのだ、自分たちは正しい」などと言ってその御本尊をも否定することはまさに、「およそ謗法とは謗仏・謗僧なり、三宝一体なるゆえなり」(真言見聞)の謗三宝罪を被ること疑いありません。御本尊は「日蓮在御判と嫡々代々と書くべしとのたまうこと如何、師の云わく深秘なり、代々の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(御本尊七箇之相承)と仰せられるところの猊下が大聖人様と同じ御内証の上から、その大聖人様の御魂を文字を以って書写遊ばされるのですから、軽々と破門になった者たちが論ずるところでは無いし、また、御本尊に差別をつけるなどとは大謗法と断ずるものであります。さらにさらに、御隠尊・日顕上人への批判は特にとどまるところを知らず、相変わらず破折されつくした内容を繰り返して、「阿部日顕はこれだけ悪いことをしたんだぞ」という印象を改めて顕正会員に植えつけるためにやっていると自分は感じました。また、光久御尊能化が日達上人のお側に仕えていたという事実を悪用し、「阿部日顕が御相承を受けていないということをよく知る人物なるが故に、今回も阿部は光久の存在は恐ろしいと思ったことでしょう。」などと言っていますが、事実は光久御尊能化は「御相承の断絶など有り得ない」と仰せられており、両代の御相承を全面的に認められております。また、光久御尊能化の今回の一件を顕正会はどうやって知ったのでしょうか?また、聖教新聞や創価新報などででしょうか?いい加減に他団体の受け売りは止めるべきでしょう。根拠の無い批判や悪意の批判、ためにする批判はすべて自分たちに返ってくるという事を自覚すべきです。まだまだ、取り上げたいことが今回の講演にはありましたので、次回も引き続き、総幹部会講演について考察してみます。
2007.10.03
コメント(2)
-
顕正会是正協議会
すでに話題になっておりますが、茶寮さんをはじめ、数名が「富士大石寺顕正会是正協議会」というものを作って、それを広くみんなに公表されたみたいです。要旨は、現顕正会が抱える主な問題について、会長はじめ、本部に糾弾し、全国の各会館、事務所などにも同じ諌状を送付し、以って顕正会浄化・改革を目指す、という内容に自分は受け取れました。確かに、妄信する会員が多い中で茶寮さんたちは一線を引いて、何とか顕正会に変わってほしいという思いで、こういう行動を起こされたということ自体は否定できるものではありません。しかし、果たして浅井会長が、顕正会がそれを真摯に受け止めてくれる存在なのかどうかということが非常に重要です。おそらく、「こんなものを送ってきおって、不愉快である」と浅井会長は思っていることと思いますし、全国の会館や事務所、拠点には組織を通じて「是正協議会に関わってはいけない」旨の通達が内密に出ているのではないかと思います。総幹部会で浅井会長がこの件について触れたようですが、どういった内容だったのでしょうか?一番触れられたくないことに触れられた故に、その講演内容も苦しい内容だったのではないかと想像します。今後も法華講員として動向を見守りたいと思います。
2007.10.01
コメント(5)
-
日亨上人御談・三大秘法と戒壇の歴史3
受戒の儀式は何時頃からか 池田・大聖人様の門下でも、天台仏法や伝教大師より推して、常識としても戒壇について考えられなかったのかなあ、思うんですけれども。 猊下・それはですね、大体この時代は迹門の戒壇が廃れておった。それでも第一老の日昭などは、叡山の戒壇をふませるといって、大聖人の滅後、自分も行った。 しかしこっちの玉澤に移ってからは、あんまり日昭門下だからといって、叡山に行って戒を受けるなんていうことはなかったね。日昭が叡山で戒を受けて、日昭の直弟子がそうしたといった程度でしょう。一つはですね、叡山に行って戒をうけるということは不便だったんでしょう。授戒が衰えちゃった。 小平・叡山がそういう状態だから、大聖人様の御門下だって、なおさら戒壇に対する関心がなかったとはおかしい・・・。 猊下・そうそう、それで大聖人の戒壇はですね、国立戒壇が主ですからな。 一同・はあ。 猊下・ですから、佐渡で例の最蓮房に受戒させたということはあるけれどもね、大聖人自身に、各地方で受戒させたという記録はない。ちょっともない、身延で授戒されたという記録もない。大聖人の戒壇はですね、もっと、この門下が広くなって、そして、そういうような儀式をして、僧侶の行体を正しくするというような意味が充分にあってですね、真新しい御弟子で相当に信仰をもって人つたんだから、殆んど受戒の必要がないというような思し召しであったかも知れない。それでお弟子の数も少ないからね。ですから、時を待つべきのみ、ということになったんじゃ。 龍・では御授戒をする必要がなかったんですね。 猊下・もう、授戒を受けんでもよかった時代じゃ。授戒をうけてですね、戒定慧の戒をもととして、だらしないことをしないで、ぴったりと戒にはまるような、一つの規を作るようなことを、しなかったんじゃ。その方があるいは、いいかも知れん(笑)色でなく、精神的に戒を作っていたかも知れん。 今じゃ、これと違って、私の考えでは、普通の授戒じゃなくてね、本山で堂々たる授戒をしてはどうだといったことがある。つまり、一つの戒壇の御本尊様を御安置するところの道場があるんだから、道場の中に堂々たる事壇をこしらえて、そして大勢一しょにやらんで、一人づつ壇の上にのっけて、やったらよいと思う。 私が本山へ登ったのが明治二十一年ですが、その当時御宝蔵で御授戒を受けたものは殆んど少なかったですね。 辻・御宝蔵で? 猊下・ええ。 龍・それは御僧侶だけですか。 猊下・いや、御信者も。それから授戒を沢山やるようになったのは、日応上人の法道院時代からですね。
2007.09.30
コメント(0)
-
日亨上人御談・三大秘法と戒壇の歴史2
国立戒壇の学説は・・・ 池田・日導や日統ですね、本山の戒壇説を知って唱えられたんですか、それとも、やはり大聖人様の三大秘法抄や何かの御書で・・・。 猊下・ええ、綱要日導の綱要には、「時を待つべきのみ」という題号で、国立戒壇のことをいってありますけれども、大石寺ということはいってないらしいね。 池田・ああそうですか。 辻・国立戒壇というのは、やはり、国家の法律でできるものなんですか。 猊下・国立戒壇はそれはいろいろな段階がありますよ。つまり日本国において王仏冥合して政治上に本宗の正義を用いる場合ですね、まず手始めとして日本国に戒壇ができるでしょう。 しかし大聖人の戒壇は日本国だけではないですからね。世界中の戒壇だから・・・。世界中の戒壇となるとですね、日本だけが大聖人の仏法を国教としても、支那が果たして用いるか、アメリカが用いるか、それはわからない。全国が揃って大聖人の教義を遵奉するということが果たしてどうだかわからん。日本が主になってやったからといって、外国がそれを真似するということは、歴史がそれを許さないんじゃないかと思いますね。外国がまだ充分に大聖人の教義は信用しないけれども、日本はまず日本の国状として一般に差支えないというぐらいに、日本の国立戒壇は外国の如何にかかわらずできるだろうけれどもですね。それとまた時代の流れで、日本が正法に帰依するならば、外国もそれと同様に正法に帰依するということがあるかも知れん。ないとは云えないからね。 それで三大秘法抄には、大梵天王、帝釈天王というぐあいに、印度人も戒壇をふむということになっている。他の仏法はそんなことはいってないね、日本なら日本の広宣流布もいっていないからね。 辻・梵天帝釈だと印度になりますか。 猊下・ええ、印度です。
2007.09.30
コメント(0)
-
日亨上人御談・三大秘法と戒壇の歴史
参加者・堀日亨上人、学会幹部(池田大作、辻武寿、龍年光、小平芳平の四氏) 田中智学の戒壇論 小平・田中智学なんかは、どういう考えだったんですかね?富士戒壇論なんか唱えて。自分は身延にお詣りに行っているくせに・・・。 猊下・そうですね。あれがどうもわからんです。あの人は富士だからね。富士戒壇をいって、北山を取り込むくらいのこんたんじゃなかったかね。 辻・なるほど、そういうことが考えられるな。 猊下・というのはね、大阪で大会があったんですね。あの時に大石寺からは誰も行かなかったが、要法寺から行く、北山から行くね、大分青年が行ったんですよ。行くとすぐ若い連中が田中崇拝になってね。それから田中を崇拝する青年層が、北山がさびれていたからね、田中をもってきて、田中は山師ですからね、北山を立派にしてもらおうというのでね、連合して策動した。今その人間がニ、三残っているですよ。そして田中の方にきてくれっていったわけです。、田中はそれで動いてね、やろうか、やろうかということになった。そんなことが富士戒壇のもとなんですね。 ところが、その青年たちの興論が、だめになった。というのはあっちの方で、要法寺から出た近藤勇道、あの男がつまり、その時代の本門宗の青年の支配力を集める男で、近藤日義という。それに青年部が相談にいった。相談に行ったら怒られちゃった。「なんだ、貴様たち、そんな馬鹿なこと、お前たちは富士の門徒じゃないか。富士の教学を立てんけりゃならない。田中みたいなあんな雑輩に心許す奴があるか。あいつは策士だから、何をやるか分からん。田中はインチキ野郎だ」なんて叱られちゃった。それで、この運動はおじゃんになっちゃった。 小平・要法寺でも、そういうしっかりしたのを頼りにしたわけですね。 猊下・ええ、しっかりし過ぎて困る。実はその教義上の違いからきたのじゃなくてね、行政上の恨みを応師にひどく持っている。 小平・ええ、日応上人に? 猊下・その以前からね、興門宗制時代からね、大きな考えがあった。八山を下において、八山の上に興門の大学林を建てる金を集めた。何しろ貧乏本山だからね、永いことかかって金をそうとう集めた。集める前に興門清規というものを作って、大石寺から一人、西山から一人、北山から一人、要法寺から一人、優秀な青年僧を集めて、そしてその宗門の学校へやって、大学林を作るときは、その講師をつかうつもりでやった。随分金を使ったんですよ。とにかく彼は策士でうまいからね、筆もたてば口もうまい、頭もいい、青年たちがゴマカサれちゃってね、大石寺の有名な人で、すっかりゴマカされちゃったのもあった。その人があまり働きすぎるから、いろいろの人から擯斥っていうわけではないがね、あまり好かれなくなった。一種の擯斥ですね。それで蓮華寺の方にかがんでいて、それから後に目白の例の法林寺へ行って、そこで焼け死んだがね。 一同・へえ・・・・・。 猊下・ええ、もう、何をやってもね、ちっともうまく行かんもんじゃから、ヤケ酒飲んで酔っ払って、ランプをひっくり返しちゃった、それで焼け死んだ。 辻・自分でひっくり返して・・・。 猊下・ええ、自分で・・・。そんなわけですから、ことあるごとに、応師に反感をもった。 辻・日応上人を怨嫉した罰だなそれは。 猊下・応師が管長時代に、あの時代は各宗の順番管長だったからね。大石寺管長時代に七山の貫首を篭絡してね、そして宗制の改革をやった、というのは応師は前からね、勇道がこしらえておいた金をみんな七山の管長に分配しちゃった(笑)だから応師は、ばかに歓迎されてね。そんなふうですからね、勇道はことあるごとに応師に反感をもった。それで勇道は要法寺でも、ちょっと擯斥の形だったんですからね。要法寺の寺でも喜んで金を頂戴していった(笑)そんなふうですから、勇道の半生の努力が一朝にしてフイになったんですから、怒るわけなんですよ。 龍・山川智応なんかは、全然、富士門の教えなんかは知らないわけですね。 猊下・そうです。富士門徒とのつきあいが全くない。
2007.09.30
コメント(4)
-
日達上人お言葉集6
昭和五十年七月二十六日・於総本山大客殿・連合会夏季総登山会お目通りの砌 皆さん今日は、お暑いところを御登山なされまして、まことに有難うございます。大変今日は暑いしまた、九州の方はより以上暑いことと思います。しかし東北、北海道の方は、涼しいところから、暑いところへお出になって、今日はさぞ、暑いことと存じております。 仏教では、六度の修行ということを、爾前経において説かれております。これはまず、布施・持戒・忍辱、この忍辱ということは、堪え忍ぶことであります。暑さに堪え、寒さに堪え、これも一つの仏道修行でございます。この仏道修行の忍辱ということについて大事なことは、無生法忍ということであります。この生死の法を、涅槃に悟り変えること、生死即涅槃というふうに悟って行くところに無生法忍というのがあります。 この忍ぶということに、生忍と法忍と二つに分ける場合があります。生忍とは生きる忍、あらゆる反対に対して堪えていくのを生忍。法忍というのは、今度はさらに二つに分けることができます。法忍に対して、心の忍と心でない外界的の忍、すなわち非心忍と心忍、この二つに分けることができます。 心でないところの非心忍という方は、この色々の寒さ、暑さあるいは病気、あるいは飢えというような、心から出たものではなくて外界的のあらゆる苦に対して忍んで行くというのが、一つの忍び方であります。これに対して心の忍、心忍、それは、今度は色々の煩悩とか、怒とか、瞋恚そういうものに対して忍ぶということが説かれております。そうすると、あらゆる仏教はこの心ばかりの問題でなくして、あらゆる外界的なる色々のことに対しても忍んで行かなきゃならない。そこに本当の忍辱の姿がある。これは大事なことでございます。 我々は、暑いからといって怠けてしまったならば、今度はそれだけの忍辱ができない。修行ができないということになる。暑くても平常通り修行して行く、寒くてもして行く。あるいは憎まれても、悪口を言われても、何ら動揺せず、忍辱をもって自分の信心を進めて行く、これが最も大事です。 これによって、始めて本当の修行ができるのであります。寒いからと言って信心をやめ、暑いからと言ってお経を怠ける。そうすればそこからすでに信心が崩れていくのでございます。 まず、仏教は自らを仏にするということが、最も大事なのでございます。広宣流布という言葉は大事でございますが、とかく人はその広宣流布という言葉に魅せられて、自らの信心を忘れがちの人があります。色々、最近の破邪新聞など出ておる通りに、自分が人をごまかし、金をごまかし、そして今度は口では広宣流布だとか、何だとか言っている。それは本当の仏道修行者では言えないのであります。 自行化他という言葉は、自行を忘れたところに化他はないのであります。南無妙法蓮華経は自行化他にわたってのお題目であります。それは、自らの修行をがっちりして行くところに、自然とそのお題目の利益によって化他が生ずる。いかにも立派な化他だけを見て、自行を忘れてしまったならば、真実の広宣流布というものはあり得ないのであります。だから自分の修行をきちっとし、自分というものを厳格に修め、そして信心して行くときに、口では言わなくても自然とその人の姿が外界に流れて、妙法の功徳を人々に勧めて行くことができるできるのであります。その姿こそ、真実の自行化他の南無妙法蓮華経の姿でなければならないのであります。 ある人が、広宣流布が大事だお寺へ行って拝んだって、自分だけの功徳を願うのは、乞食の信心だといって悪口をいった人があったそうです。とんでもない間違いであります。そういう考えを持って広宣流布ができるわけがない。もっともっと自分を律することを厳にし、自分の信心を堅固にして行く時に、必ず人々にその徳が慕われて行くのです。外典の言葉に、「徳は孤ならず、必ず隣有り」という言葉があります。まことにその通りだと思います。暑さ寒さは、これは日本においての四季の違いによって当然であります。 大聖人は四条金吾殿御返事に「苦をば苦とさとり楽をば楽とひらき苦楽ともに思い合せて南無妙法蓮華経とうちとなへゐさせ給へ」(全集一一四三貢)と。 その通り我々が夏は暑い、冬は寒い、そういう暑さも寒さも色々の飢えのときも、あるいは満腹の時も、思い合わせてともに南無妙法蓮華経と唱えて、そのところに常寂光の世間を認めて行かなければならない。そこが信心であります。 どうか、そのつもりで、今日明日の暑いのを忍んで信心に励み、せっかく本山へ来たときの時間は、一生を通じれば短いのでありますが、その短い時間を信心の上から充分に活用せられて、お帰りにならんことをお願いいたします。
2007.09.26
コメント(2)
-
日達上人お言葉集5
昭和四十九年八月二十五日・於総本山大講堂・連合会第十一回総会の砌 法華講第十一回総会は、盛大に行われまして誠におめでとうございます。私は、戒壇は、本門の戒壇は誰が建てるか、ということについて、少々述べたいと思います。戒壇ということの定義は、既にご承知の通り、三大秘法抄に、「戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時勅宣並に御教書を申し下して霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か時を待つべきのみ事の戒法と云うは是なり」(全集一六〇〇貢)と、仰せになったのであります。 この戒壇建立にあたって、ある人は、天皇陛下の国立戒壇でなければならないと、言い張るのでございます。この国主ということを考えてみますと、三大秘法抄で説かれる有徳王・覚徳比丘の話は、涅槃経からとられたのであります。 今、涅槃経の国主のことを引いてみますのに、涅槃経第十七に、「法に二種有り、一は出家、二は王法、王法は所謂其の父を害し、即ち国土の王となる。是れ逆なりといえども、実に罪有ること無し。迦羅々虫のまさに破腹を破りて、然る後に即ち生るが如し。生法は是くの如し。母身を破すると雖も、実に亦罪無し。騾の懐妊等、是れ亦是くの如し。治国の法、法は応に是くの如し。父兄を殺すと雖も、実に罪有ること無し。出家の法は、乃至蚊蟻を殺すも亦罪有り」と説かれております。 国王には、それぞれの力と、特権が認められておるのでございます。故に。安国論に涅槃経を引かれ、「正法を護る者は当に刀剣器杖を執持すべし刀杖を持すと雖も我等是を説きて名けた持戒と曰わん」(全集二八貢)と説かれております。 法を外護することは、国王に付嘱せられ、僧は法を保持するのでございます。それは、国王にはそれだけの権威があるからであります。有徳王が刀剣を持って弘法している覚徳比丘を助け、謗法者と大いに戦って、これを亡したことが説かれておる。その涅槃経でいう国王とは、子が父を殺して王位についても罪は無い。国王となって厳然と存在するのであります。これは、阿闍世王の例をとってもわかる通りでございます。この思想は、印度・中国において、古来からの思想であります。国中が治まらない時は、天の命すでに革まる、という故に革命があり、次の国王ができるのであります。涅槃経でいう国王とは、かくのごときであることを、考慮しなければならないのであります。 それはともあれ、現今は、我が国の憲法において、主権在民と定められている以上、本門の戒壇が民衆の力によって建立されておっても、少しも不思議はないのであります。あえて、天皇の意志による国立で無ければならないという理由はないのであります。一期弘法抄の、「国主此の法を立てらるれば」(全集一六〇〇貢)とは、現今においては、多くの民衆が、この大聖人の仏法を信受し、信行することであり、そして、本門寺の戒壇を建立することを御命じになった、と解釈して差し支えないと思うのであります。 故に、百六箇抄に、「三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺本堂なり」(全集八六七貢)と、明らかにお示しになっておるのでございます。その本門寺とは、我が山、大石寺のことであります。この我が山の、本門の戒壇の大御本尊のましますところが、本門の事の戒壇であります。その事の戒壇が、総講頭池田先生が大願主となって、我々の民衆の、正宗の信者の信心の結晶によって建立せられた、あの正本堂が、事の戒壇、本門事の戒壇と称して何の不思議があるのでありましょうか。 現在、我が山に、正本堂が建立せられてある以上、本門戒壇の大御本尊を安置し奉ってある以上、ここに参詣し、南無妙法蓮華経と唱えることが、事の戒法であります。幸いに我々は、本門の事の戒壇に参詣し、事の戒法たる南無妙法蓮華経を唱え奉って、即身成仏の本懐を遂げることができるのであります。 法華講の皆さん、今後ますます異体同心に信行に励まれ、世界平和、広宣流布に邁進せらることをお願いして、今日の挨拶と致します。
2007.09.26
コメント(0)
-
日達上人お言葉集4
とにかく宗門のことは、他の人をたのむ必要は何もありません。私は、必要なことは全部自分でしますし、自分の意見は自分でいいます。よけいなおせっかいは無用であります。皆さん方には私がだれの指図でもない自分でいっていることはよくおわかりいただけると思います。又、一人の信者に差別して特別のことをいったり、使命を与えるようなことをするはずがないではありませんか。 「御遺命の戒壇について」浅井らは、執拗に国立戒壇、国立戒壇とくりかえしております。戒壇についての私ならびに本宗の見解は、訓諭をはじめとして既に何回も公にしたとおりであります。大聖人の仰せは本門事の戒壇である。本宗相伝の戒壇の御説法に「弘安二年の大御本尊とは即ち此の本門戒壇の大御本尊の御事なりー中略ー本門戒壇建立の勝地は当地富士山なる事疑なし、又其の本堂に安置し奉る大御本尊は今眼前に当山に在すことなれば此の所即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土云々」と、常に説き示されておるごとく、本門事の戒壇の御本尊在すところが本門事の戒壇で誰が建てたからという理由で事の戒壇となるのではありません。このことは既に数年前から私が申し述べているところであります。 右のことを日寛上人の三大秘法御説法を日相上人が科段に分けた御文を参考として、ここに添付します。 本門本尊ー人本尊・日蓮大聖人、法本尊ー事一念三千之御本尊 本門題目ー信受・智妙、口唱行・行妙 本門戒壇ー在々処々本尊安置之処は理の戒壇也、富士山戒壇の御本尊御在所は事の戒也 浅井らは何ら教義上の反ぱくもなく、ただ先師がどうの、私が昔云ったのというだけであります。私は、昔いったことはあるが、今はいわないといっておるのであります。私の信念は不動であります。未来永遠に国立ということはないと確信しておるからであります。 浅井らは、人のやることに干渉せず、自分達の力で、やれるものならやってみればよいと思うのであります。但し、国立というのは本宗の教義ではないので、元妙信講が日蓮正宗と名乗ることだけは、今日限りやめてもらいたいのです。法律がどうのこうのという問題とは別の次元で、管長として、法主としてもはや、日蓮正宗信徒でないものが、日蓮正宗という名称を使うことを止めよと命ずるのであります。
2007.09.22
コメント(0)
全79件 (79件中 1-50件目)
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- Black friday限定!もち吉 超お買得…
- (2025-11-19 22:16:48)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 毎日お弁当
- (2025-11-19 22:36:10)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- プレッシャーに打ち勝つ方法
- (2025-11-19 07:37:30)
-