全741件 (741件中 1-50件目)
-
ドキュメンタリー映画
日本映画専門チャンネルで、ドキュメンタリー映画の特集を放送していて面白く観た。◎「ヨコハマメリー」 2005・中村高寛・監督◎「バック ドロップ クルディスタン」 2007・野本大・監督 ◎「選挙」 2005・想田和弘・監督若い監督たちの仕事、3作ともそれぞれに心をゆさぶられた。劇映画とドキュメンタリー映画をならべると、私はドキュメンタリーのほうが印象が深く刻まれることのほうが多い。監督の個人的な興味から始まり、その納得のいくまでを撮り続ける。出演者たちは、スタッフとカメラの前で自分を演じきっているようだ。さらけ出すことによって、関係を増幅させ自らをきたえているみたいだ。俳優は自己を演じる実物には、かなわないんじゃないかしら。編集と出演者の魅力、それは実在感と言うのかな、その技術と勇気も、監督の腕のみせどころなのだと思う。映画と言うものに、新しい目線を覚えて今月はあと2本のドキュメンタリー映画を観る予定だ。
2010.04.20
コメント(2)
-

4月17日の雪
昨夜よりの雪が、今朝も残っていました。春はどこへ行った? 昨年もらった鉢植えのカーネェーションが、越冬して花を一つつけた。アイスランドでは火山が噴火。地震も世界で多発。地球はまだまだ壮年期。
2010.04.17
コメント(0)
-

夜桜
ほろ酔い気分で撮影しました。桜満開です。昨日午前中、雨の桜を見に行こうと近所を歩いたのですが、傘ごと吹き飛ばされるような強風で、花を見るより傘を掴んでるのに必死な状態。用だけ済ませて、早々に帰宅しました。で、夜再びぶらりと出かけてきました。
2010.04.03
コメント(0)
-
「風のかたち」
市の図書館で自主上映された「風のかたち」--小児がんと仲間たちの10年--- 監督:伊勢真一 監修:細谷亮太を観ました。* 十年前、我が国では、病名を告げられ、病気の説明を受けた小児がんの子は、がんの子供たちの中で絶対的なマイノリティであった。「君だけじゃないんだよ。仲間と話してみようじゃないか」というような気分で、1998年の夏に彼らのためのスマートムンストンキャンプが始まった。* 世の中の流れも大きく変わり、インフォームドコンセントが常識になり、病名を知らされ、病態の説明を受けているがんの子供たちはマイノリティではなくなった。* 現在では八割ほども治るようになったとは言え、小児がんの子には発病当初から、死ぬかもしれないという人間の根源的な不安がのしかかる。それを日常のあたり前のこととして暮らしているところに、この子供たちのすごさがある。 細谷亮太(小児科医・聖路加国際病院副院長)この細谷先生乞われて、10年にわたってキャンプを撮り続け、一本のドキュメンタリー映画にされたのが、伊勢真一監督。* 十年間の歳月が語りかける、小児がんと闘う仲間達の生きる力・・・不断に蘇る命そのものの力ではないでしょうか。定点撮影のようにキャンプに通い、時間をかけて、ひとりひとりの命を見続けることで見えてきた「再生」という希望。 伊勢真一「再生」 パンフレットより子供たちが、偏見や差別と闘っていることも知りました。差別や偏見は、私達の心のうちのどこにでもある。優越感のしのびこんだ同情心も。子供たちが越えねばならないハードルは、高いです。仲間の死にも、涙をみせることは少ないそうです。かれらの笑顔や会話のひとつひとつが、人を惹きつけ考えさせる力を持っていました。亡くなった子供たちの名簿を背負って、遍路みちを歩き、この子達に支えられて医者の私がある、と言われる先生にも心を打たれました。上映後、監督と羽賀諒子さん(小児がん体験者)のトークタイムもありました。明るさや、笑い飛ばす強さ、芯の通った誠実さに心あらわれた気がしました。病気は私達だれもが対局せねばならないことで、決して他人事ではないのです。サインも頂いてきました。このような映画を「かすみを食って」撮り続けている方もいるのですね。子供たちも、子供たちを支える周りの方たちも、立派です。死が近くに感じられるところにいると、より強く生きることも近くにあるのだと気づかされました。
2010.03.30
コメント(2)
-
例年になく
なんだか忙しい3月。お目当てのパソコン・windows7の購入も、6月以降になりそう。手間ひまの余裕がなくて。でも親しい友人知人に会うことの機会もあって現実の世界に浸るのも大切なことと思う。普段は回避することに、慣れすぎていて。娘も仕事を再開し、パートから始めることに。予想通り、マーゴ君はしょっぱなから保育室で風邪をもらい、家で預かっていたら、夕方から発熱。早退したママと病院に駆け込むことに。今は元気をもてあます程らしいが、新しい生活の軌道に乗るまで親子で大変だろう。でも子供が小さいうちは、一緒に、なんでもなんとかなっていくもんだと思ったりする。写真は有名な渋谷の交差点。眺めていると、時間を忘れます。
2010.03.28
コメント(0)
-

医学と芸術展
六本木ヒルズの森美術館で、「医学と芸術展」を観てきた。人体ほど身近で親しく、禍々しくもきわどい物はない。と常々思っているが、そんな意識をさらに刺激してくれる中味のつまった展覧会だった。手術や解剖を密室でではなく、一大イベントとしてすら公開してきた医療の歴史が、皮膚に覆われた内臓の闇を暴き出すように、人間の真実性を「学と芸術」に方向ずける手助けともなったのであろう。過去においては、処刑や拷問も公衆の広場で行われていたのである。陳列されている昔の医療機器をみていると、拷問の器具を連想してしまい、何か表裏一体のものを感じて、緊張してしまう私であった。このドキドキ感は、義足や義肢をみていてもつきまとった。しかし、蜷川実花作のカラフルな義足を見たとき、ふっと気持ちが楽になった。ヴァルター・シェレスの「ライフ・ビフォア・デス」の写真の前では涙ぐんだ。ジル・バルビエの「老人ホーム」では思わず笑ってしまった。ステラークやマーク・クインの作品には、言葉にし難いものがあった。そのほかの作品ひとつひとつにもその批評性以上に、リアルに五感に響くものが多かった。(あたりまえのことなのだが)逃れたくとも避けて通れぬ、わが人体なればこそ。
2010.02.27
コメント(8)
-
三浦マホロバマインズへ
息子の冬休みにのっかって、二家5人、マホロバマインズ三浦で、一泊してきた。部屋の広さが何よりの魅力。この日も3部屋に各自好きに分散して就寝。マーゴ君も部屋中駆け回って、大はしゃぎ。食堂が混雑していて落ち着けなかったことを除いたら、スパも楽しめたし、マーゴ君との一泊旅行初体験は、まずまず成功か。車で出かけたため、寒冷強雨の悪天候にもめげず、雨ですもの、城ヶ島。雨ですけど、観音崎。海軍カレーですよ、横須賀。と足を伸ばして、それでも夕方には帰宅できた。楽天トラベルを利用して(←たまには宣伝)近場で遠出の気分を味わってきました。
2010.02.15
コメント(0)
-

さくひん
さて、実務のほうも一段落した頃、マーゴ君がやってきました。この日は風邪気味だったため外出せず家の中で目一杯遊んでお夕飯を食べながら寝てしまい爆睡したまま、帰って行きました。 かきかき(くれよん)ぺったんぺったん(スタンプとスタンプ台と手)四角いのは好物の(味付き)海苔だそうです。
2010.02.10
コメント(2)
-

雪が降る
昨夜の雪です。
2010.02.02
コメント(0)
-
ぜいぜい
今年も確定申告の季節がやってきました。先週より、ミニ按摩器に助けられつつ、実務に励んでいます。マーゴ君は国立の病院で手術したのですが、この時ほど、税金を支払っていて良かった、と思ったことはありません。収めた税金の一部が、このような施設に生かされていると思うと税の大切さも実感です。しかしわが身に降りかからなければ、見えてこないことが多いのも実情です。また、降りかかる火の粉は人様々で、結局はわが身を生きることが優先され、それが次のステップ、人のために、につながる大きな力にもなるのだと思われます。健康診断は、特別悪いところもないとの診断でした。悪いのは頭及び心理、ということかも知れません。
2010.01.31
コメント(0)
-
健康診断
年に1度の、市の誕生日健康診断を受診してきました。今回で2度目。メタボの逆の痩せすぎは、生まれつき。結果は後日にわかりますが、消化器内視鏡検査は前回同様ポリープ程度でそれほどでなく、特に異常はありませんでした。心電図は完全右脚ブロックが、いつもどうり。禁煙成功のおかげか、清く正しい心肺眼だと先生に言われてしまいました。ははは。先週はマーゴ君が来ていました。深大寺にお参りがてら、名物深大寺そばをいただきました。麺類大好きは、おじいさんに似たのかな。麺を食べてるときが、一番静か。黙々と手づかみで(食べさせてもらうのが嫌)「つるつる」を食べました。神代植物園にも足をのばして、枯葉のなかに埋もれたり、芝生の広場ではいずったり、バラアイスをほおばったり。アイスにもめがありません。わんぱく・わがまま・甘えん坊・天邪鬼・強情をセットで発揮。いけないと言われていることをわざとして、大人を呼んで反応を見たりする。「怒らせたらばーばが一番怖いんだよ」などと、皆がマーゴに囁いても、私達のらぶらぶはまだまだ続く……?言葉も随分増えました。お友達も増えたそうです。
2010.01.25
コメント(0)
-
今読もうと
読んでいる本と読もうとしている本●「知能の誕生」ピアジェ は完全にギブアップ。読めんかった。●「幼児の対人関係」メルロ=ポンティ、は面白い。 母親していたときは、主に母親幻想についての岸田秀氏の著作を読んでいたが、子供に関する心理学や科学的な本は読む余裕がなかった。ここに来て、身近な問題としても興味が強く湧いてきた。●「唯脳論」養老孟司氏の著作は何冊か読んでいるが、肝心のところにやっと近づいてみたくなった。●「意識とは何か」避けていた茂木健一郎氏の本にも挑戦してみよう。フッサールさんのおかげで、視界が開けたようで、はり切ってますが根が怠け者なので、ここに書いておいても忘れちゃうかも。(いつものこと・汗)
2010.01.19
コメント(0)
-
哲学初体験
竹田青嗣氏による、フッサールの「現象学の理念」を読む講座全5回に、通っていました。全回満席の大盛会、その熱気に圧倒され続け、聴講生との双方向性を重視した授業にも仰天。初回は、このまま帰ろうかしら、と思ったほど場違いなところへ迷い込んだ気持ちでした。でも欠席することなく終了。家で予習しようとしても、1ページ読むのに1週間くらいかかりました。まず言葉が理解できない。竹田氏の「はじめての現象学」は非常に興味深く読んだのに、それがフッサールの難解な哲学用語と結びついてくれない。終盤になってはじめてなんとなく、これはこういうことか、と納得できたかな?という状態でした。またそれを理解できたとしても、実践することは更に大きい労苦を伴うと思われます。すでに何もかも手遅れかもしれません。でも引きこもっていた穴蔵からの始まりだ、と思うことにしています。少しでもモノを書く、という行為をしていると、現象学という学問は知らなくても似たような構造を知っている、と感じることもありました。また、私はやはり私の受けた自然科学の教育に傾いているし、それに親しい、ということも感じました。読書計画をまた続行しなくては。
2010.01.17
コメント(0)
-
ゴーリーの絵物語本
これも、1月9日朝日新聞の、「もっと本を再読ガイド」のコラムで紹介されていて興味を覚えて買ってみたものです。エドワード・ゴーリー(1925-2000)シカゴ生まれ。独特の韻を踏んだ文章と、独自のモノクローム線画でユニークな作品を数多く発表している。『おぞましい二人』は、訳者柴田元幸氏のあとがきによると、1965年明るみに出た「ムーアーズ殺人事件」に、心底動揺させられ、その陰惨な出来事が頭から離れなくなり、資料を読み漁った。そしてそれを物語にせずにはいられなかった。「どうしても書かずにはいられなかった」のはこの本だけ、と作者が語っているそうだ。「ムーアーズ殺人事件」と呼ばれる事件とは、イアン・プレディ、マイラ・ヒンドリーという男女が、4年にわたり5人の子供を残虐に殺して荒野(ムーア)に埋めていたというもので、イギリス中の人々の憎悪を買ったという。最近2年以上にわたって、主に英米の犯罪捜査ドラマを見続けていたせいか、あまり驚かなかった自分が、ちょっと怖い気もする。だが、ゴーリーの絵本という形態で目の当たりにすると、心に食い入ってくるものが違うようだ。クリミナルマインド、ロー&オーダー、CIS 、法医学教室、などのドラマはこの絵本に味付けしたものみたいに感じるほど、事実の原型が抽出されているように感じる。少年による児童殺傷事件が神戸で起きた時も、その衝撃が演劇や小説その他に多くの作品を残した。だが「絵本」という媒体では私は知らない。私も神戸の事件をもとに詩を書き、今も整理できていないので、また見直してみたいと思う。映画の『誰も知らない』も、事件をありのままに描こうとしていた部分はあると思ったが、この絵本はもっとシリアスでリアルなものを感じさせる。細かなところまで分け入っていかねばならない、という気持ちにさせられる。『うろんな客』はどこかで読んだ記憶がある。ネットで紹介されていたのか、病院や調剤薬局の待合室でだか。こちらはくすっと笑ってしまう。そして、まあまあ、でもほんと、いかんともしがたいのですよね、なんて。
2010.01.14
コメント(0)
-
「コミュニケーションと社会」
もうひとつ気になっている、1月3日の朝日新聞の記事。2010年代 /どんな時代に/ ネットが世界を縛る 写真家・作家 藤原新也 インタビューより*1* タレントの人気が「好感度」によって査定されるという、あの不可思議な評価基準。いまやタレントのみならず一般人、企業やマスメディア、政治までもが、その好感度という尺度で査定される。*2* その目に見えない風圧にさらされ、いい人を演じて波風の立たない気持ちの良い人間関係を作ることに個々人が腐心する。そこには、相手の言葉や行為を正面から受け止め、たとえ軋轢が生じても自らの思い、考えを投げ返すという、本当の意味のコミュニケーションが希薄だ。*3* こういった空気読みの風景は、2001年の9.11同時多発テロ事件以降の一般的傾向のように思う。*4* 強まる相互監視 波風立てず「空気読み」*5* 今後のコミュニケーションはどうなるか。*6* ネット社会が臨界に達したときに、ゆり戻しが来るのではないかと期待をしている。*7* 「ライブ感」再び注目*8* 今後10年それに似た身体性の復活は方々で起きるのではないか。*9* ブログがタイムラグのある「文章」ならツイッターはライブで発している「声」や「呼吸」に近い。*10* だが僕個人は、このツイッターに可能性を感じながら警戒もしている。それは逆に考えると究極の相互監視システムでもあるからだ。あののどかなブログでさえ自分の居場所や思考が不特定多数の人々の目に曝されるわけだ。ツイッターはさらに「タイムスライス」で刻々と自分の行動が明らかになる。自分の身体をCTスキャンで輪切りにして白日の下に曝すようなものだ。*11* ツイッターが新しいメディアにもかかわらずその使用者の中央年齢値が高く、子供や若年層が意外と参入していないのは、「学校裏サイト」などで彼らが死活問題とも言える辛酸をなめているせいかもしれない。 (聞き手編集委員・四ノ原恒憲)「いい人、いい子への過剰適応」というのは、私にも覚えのあることで、耳が痛い。またその延長線上に、「いい子」を子に強要する母親であったともいえる。子育ての間中、そのことを思い知らされてきた。それが、いい意味でも悪い意味でも*2*につながってきていると思う。人間が本当の意味でコミュニケーションをとろうとしたら、行き着く果ては命がけの殺し合いになってしまうのではなかろうか。そこを埋めるように、警戒しながらもコミュニケーションを求めて私達は、ブログやツイッターにはまっていく。ライブ感の復活が、「相手の言葉や行為を正面から受け止め、たとえ軋轢が生じても自らの思い、考えを投げ返すという」ある意味成熟したコミュニケーションにつながる演習になればよいのだが、と思う。ここで私のツボにはまったのは、「のどかなブログ」という言葉。「のどか」もその裏に潜むものは人間である限り、こわいものなんですよね。のどかなブログさん。ツイッターは私はまず能力的に、だめですね。のどかなブログが向いています。
2010.01.11
コメント(0)
-
「芸術は神聖」?
昨年の朝日新聞で読んだ記事が、ずっと気になっている。経済学者・アーティストとして、芸術と金、権力の関係を研究するオランダ・アムステルダム大学名誉教授のハンス・アビング(63)さんのインタビュー。著書に「金と芸術 なぜアーティストは貧乏なのか?」が07年に出版、初来日ということだった。*「芸術は神聖」との「神話」がアーティストを金の問題から遠ざけ、さらには芸術の「保護者」である国家や資本を神聖化する仕組みに利用されている、と論じる。「芸術の経済とは、非商業性がステータスとなって利益を生む、非常に例外的な仕組みです」 *「レベルの高いアマチュア、つまり他に仕事を持つ人をもっと社会的に評価してよい。他方、プロのアーティストは、創作だけでなく、作品をいかに広めるかにもっと関心を持つべきです」確かに私は、「芸術神話」をすり込まれている、と思う。というより、自分ですり込んでいたのかも。「芸術」という言葉も、自分の眼で解体して考えていくべきなのだと、遅まきながら感じたことだった。
2010.01.08
コメント(0)
-
御用始
あっというまに2010年も4日目となりました。にぎやかに、また、あわあわと。昨日は、すっかりご無沙汰していた、lomo-fisheyeトイカメラを持って、江ノ島へ初詣に出かけてきました。年末、冷蔵庫の中を掃除していて、感度400*2008年7月*使用期限切れのフイルムを10本ほども見つけたからです。これはもったいないと、lomoくんを取り出したのですが肝心のスキャナをパソコンからはずしてしまっているのでここに取り込めません。それに、がしゃパシャ撮ったわりには勘が戻らず気に入った写真は少なかったです。フイルムの現像代、プリント代、高くなりましたね~期限切れのフイルムで撮影するのは、これまたもったいないことかも。(↑の写真はデジカメで撮影後画像処理したものです。)さて、今年は自分の時間をもっと上手に捻出することを目標にしてまいる所存です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2010.01.04
コメント(2)
-
誕生日ウイーク
12月第3週は、孫君・息子君・私君、団子3世代の誕生日ウイークだった。とりわけ、病快癒したマーゴ君2歳の誕生日は感慨深く、周りもセーブしていた愛情を全開してのお祝いとなった。その後、息子君と私君の誕生祝いに来てくれて、3泊して帰っていった。孫は来てよし、帰ってよし。と、言うらしい。で、第4週は天皇陛下とイエス・キリストさまの誕生日ウイークだった。こちらは、年末の掃除や整理をボソボソして過ごした。ああ。世の常、人の常の道の遥けさよ。
2009.12.26
コメント(0)
-
「花美術館」 vol 12
「花美術館」vol 12 特集正岡子規が発行されて、送られてきました。子規の自画像を使った表紙が、とてもよいです。テレビで「坂の上の雲」も放映されているし、正岡子規に改めて興味をもたれる方も、多いと思われます。中村不折や浅井忠との交流も図版とともに、紹介されているので書店で見かけられましたら、手にとってご覧になってみてください。他に100人を越える有名無名(無名は私のことです)の俳句、川柳、短歌、現代詩、現代工芸の作家の方々の作品が収録されています。このようなアンソロジーの中に身をおくと、いたたまれないような気恥ずかしさを覚えますが、自分の立ち位置を確認するのによかったかも知れません。他の方の作品もこれからゆっくり鑑賞したいと思っています。
2009.12.07
コメント(2)
-
「先端で、さすわさされるわ そらええわ」
川上未映子著 2008年 青土社第14回中原中也賞受賞「先端で、さすはさされるわ そらええわ」ゆさんからお借りして読みました。*手垢にまみれた言葉、モノやコトを、自分の言葉で名づけていく 意味や価値を付加して超越へと運んでいく 名づけの詩法のようです。*思わず突っ込みを入れたくなる親しみのある語り口。*首、手首、足首カットする、コワくなるほどやわらかな目線です。*性交という言葉を連発する、今風枕絵若者語りあり。*焚書あり、言葉批判あり。*自分の肉体にまとわりつくしがらみの紐やリボンや縄を、 ひとつづつはがしていくような、快感とコワさを 覚えます。*息子と同じ世代の作者に、従来の詩人の詩よりも 共感や感受性のかぶさる部分が多々あって、驚きました。*文句なく面白い、新しい「詩」の力と息吹きを読ませていただきました。 スゴイデス。
2009.11.26
コメント(5)
-
予想外
意表をつかれてしまったのだけれど、マーゴ君がこのブログの写真を見たそうだ。野良ちゃん猫の写真を指して「チロ」と分かったという。不特定多数の誰が見ているかもわからないブログを、時には恥じ入りながら、時には自己嫌悪に襲われたりしながら、何年も続けてこられたのは、それなりに自分のためになっているからだろう。一度始めた事は、簡単には止められないものでもある。私生活をさらけ出しているような不快も越えて、脚色を楽しむこともある。書いているうちに客観化できることもある。そして何より出会いと応答の楽しさ。しかし、マーゴ君が見るとは全く想定していなかった。いや、でも、決して不思議なことじゃないのですね。日に日に成長しているのですから。あれこれ考えるとうろたえてしまって、果たしてきちんと整理整頓できるか、自信が無い。。。。。。。
2009.11.14
コメント(2)
-
95年製ブラウン管テレビが
半年前から故障していた、ビデオ・DVDレコーダーに続いて長年愛用の、ブラウン管テレビが映らなくなった。バン!と叩いて、叩いた場所がよければ一瞬映るという、ドラマや映画でよく見かける症状。色々な選択肢を考えた末、家はケーブルテレビを視聴しているので、コンパクトデジタルからHDR+の契約に切り替えて、HDD内臓型でない液晶テレビを購入することに。こうすると、月々の視聴料は高くなるが、レコーダーも必要なくなりテレビも低価格のものが買える。故障の場合もチューナーを交換してもらうなりして簡単だ(と思われる)。月額料の支払いがきつくなれば、WOWOW視聴を中止することにしよう。ということになって、我が家に最新型フルハイビジョンテレビがやってきた。テレビの字幕が老眼鏡ナシで読めるようになった。目下は内容を見るより、鮮明な画像を楽しんでいる状態だ。少し色がきつく感じられる場面もあるが、奥行きが感じられるのは驚きだった。37型でも十分シアター気分が味わえる。しかしながら、デジカメでSDカードに撮られたワタクシの写真をフルハイビジョンで見せられたときは、言葉がでなかったですね。やめてほしいですね。シミシワに対応できるカメラが欲しいですね。急な出費で、パソコンが遠くなったと嘆いていたら、テレビは主人が買ってくれました。ありがとうございます。シャラポワは強し。WOWOWよ、テニスファンに感謝すべし。
2009.11.08
コメント(5)
-
そろそろパソコンを
身の程をわきまえず、分厚い専門書を読み始めて、行き詰ってしまった。あhhh、あhhh、あhhh~だが、そもそもブログをはじめたのだって、身の程知らずなことではなかったか?そうだ、身の程知らずで、よいのだ!わが愛機、VAIO Windows XP も使い始めて6年になる。なぜかひらがな入力ができなくなって、ローマ字入力に切り替えたこと。ハードディスクCの空き容量が2GBをきってしまったこと。私が修復不能なヘマをしたままにしていること。をのぞいては、よく持ちこたえていると思う。しかし、これ以上何かすると、突然動かなくなるのではないかと不安がつのる。と言うのを言い訳にして実は、Windows 7 の発売を待っていたのである。色々調べてから、来年早々には購入しようと思っている。先にパソコンがダメになりかかっていた息子は、「7」の発売日に「XP」を買ってきてうっすら笑っている。XPで何にも困ることはないよと。彼は沖縄のタワーレコードで、世界同時発売だったリマスター、ザ・ビートルズBOXの輸入盤を買うことができて、大事に胸に抱えて帰京したのだった。沖縄旅行の最大の収穫だったとか。独身貴族じゃ。何を書いているのかわからなくなってしまったけど、兎に角「7」に触れるのを楽しみにしている。写真は私の頭の穴のつもりじゃ。
2009.10.25
コメント(4)
-
箱根・彫刻の森美術館
電車に興味を持ち始めたマーゴ君を、小田急ロマンスカーに乗せたくてじいじが計画。箱根の彫刻の森美術館へ行ってきた。ここは、子供達が小さい頃何度か遊びに来たことがある。また、一人でぼんやり訪れたこともあるなじみの場所だ。山並みに囲まれた丘陵に吹く風や、数々のアート作品が日常からの解放感をもたらせてくれる。十数年ぶりに訪れたのだが、子供の遊戯施設が増えたようだ。往きのロマンスカーLSEでは乗るなり爆睡、箱根登山鉄道に乗り換えてからも、彫刻の森駅に着くまで起きなかったマーゴは、お昼ご飯をもりもり(食べさせてもらうのより、自分で好きに食べたいのでほとんど手掴み。)食べて、全開。広い園内を小走りに歩き回った。ピカソ館の先に温泉足湯のスポットができているのを発見。子供も可だと係りの方に勧められて、皆で足の疲れをとったり温まることができた。この日はオレンジ湯になっていて、オレンジやレモンがぷかぷか浮いてる。マーゴ君、それを拾うべく足湯から歩き出し、全身浴になってしまった。風邪を引かぬようあわててタオルでくるんで、ギャラリーカフェでスッポンポンにして、全身おきかえ。付き添いもなりふり構っていられないわね~帰りはせっかくロマンスカーVSEに乗るのだから、眠るなよ。とじいじがしきりに耳元で訴えたのが功を奏したか、起きていて1号車からの展望を楽しむことができた。夜景だったけどね。「くらい」という言葉も覚えていたよね。VSE弁当もゲットできて、日帰りフルコースの旅だった。マーゴといると自分の幼児性が引き出されると、以前にも書いたことがあるけれど、白痴性にも及ぶことに、気がついた。
2009.10.23
コメント(2)
-
「内在するカラッポ」 「飛行する沈黙」
1年半ほど前から、浜江順子さんから朗読会や詩とジャズの会などの案内を頂いていた。浜江さんとは20年以上前に、荒川洋治さんや正津勉さんなどの詩の教室でご一緒したことがある。浜江さんはパワフルで才気にあふれていて、私などは近寄りがたい存在であったが、剛毅さと繊細さを併せ持つお人柄に魅かれていたので、朗読会に一度はお伺いしてお目にかかりたいと思っていた。が、私事にかまけてまだ果たせていない。その案内で知ることになった、第五詩集である●「飛行する沈黙」 思潮社 2008年発行が、第42回小熊秀雄賞を受賞されていたのだ。おめでとうございますそれで以前頂いていた、第二詩集●「内在するカラッポ」 思潮社 1990年発行も取り出してきて、2冊の詩集を読んでみた。昔読んだときは、内在するカラッポ、とは子宮をイメージしていたのであるが、実は、バタイユやメルロポンティなども内在している哲学する“カラッポ”だったのだ。比喩する言葉でさらけ出し、はじけて飛んで着地し、ねじふせる。強弱に、存在する何ものかをひそませているような。種のような実のような。拝読して力量はすでに認められている通りだと納得したし、栞やネットの批評でも読む糸口は得られるので、ここでは私の力量ではポカンと立ち止まって困惑してしまった箇所を挙げてみたい。 蒼ざめた顔が連続する悲劇を 逆転するある律動のなか 白昼片隅に見つける (白昼の爪) *“ある律動”の、ある、に立ち止まってしまった。 できれば私もそれを見つけたい。笑 茅の目をした少年 *“茅の目”のイメージが定まらなかった。 盲目の木 *3、6、9連目に“ナ”ではじまる木の名前が9個でてくる。 ナナミノキの眼もなくなり ナナカマドの眼もなくなり ナンキンハゼの眼もなくなり 以下、ナツツバキ、ナガジイ、ナツコガ、ナシ、ナンジャモンジャ、ナギ。 この意味するところがよくわからない。 だいたい木に眼があるのだろうか。 なぜ“ナ”ではじまる木の名前ばかり選ばれているのか? “内在も不在もゆっくり腐っていく” 沼から泥への流れは好きでした。ということで、失礼を省みず稚拙な感想を書いてしまいました。好きな詩が沢山あって、総じて私はちょっと興奮しながら、読ませていただきました。ますますのご健筆を、さらなる飛躍を
2009.10.18
コメント(0)
-

庭仕事
ぼうぼうと繁ったままだった雑草や植木の刈り込みを、3日かけてした。年のはじめ、5本の落葉樹を伐ってもらったので、晩秋の落ち葉掃きが楽そう。切り株がどんどん変化していく。 今年は夏場の水遣りを怠ったのと、春の肥料の失敗と、害虫の蔓延で沢山の鉢植えを枯らしてしまった。植物を育てるのに向いていないと、つくづく思う。だが植物もつねに病害虫と戦っていることに、生き物の業を知らされる。キンモクセイ ホトトギス 最近うるさく鳴いて顰蹙をかってるチロ ベロペロネ 狂い咲き?したクンシラン カリンの実 さて、冬準備。
2009.10.17
コメント(0)
-
障子の張替え
障子が古くなって張替え時だったのだが、その前にマーゴ君を遊ばせたくてそのままにしておいた。つかまり立ちを始めた頃から、障子を破くことと剥がすことを覚えた。もともと手先を動かすことが好きなタチらしく、それは熱心に破いてくれた。無心に破いている、といった風情だった。しかしさすがにこれでは、真冬の隙間風が厳しい。秋風が冷たくなる前にということで、表具やさんに張り替えてもらった。おかげで部屋は明るくすっきり。さて、「破いてもいいよ。」から「破いちゃダメよ。」にマーゴがどのように反応するか、楽しみなのだが、先日来た時は、新しい障子にへこんだ指あとを付けたところで、「ダメ!」が間に合った。本人は、新しくなったことに感づいていて、大人の反応をうかがっているみたい。悪さをするときはすばやく隙をつくので、いつまで持つかそれもまた楽しみだ。などと、ばあばは、これからのまーごにどうありうるか、などとなどなどと、考えてしまう昨今なのでありますが。
2009.10.15
コメント(0)
-
読書のメモ
中断していた読書計画に立ち戻って、読書のリズムを模索しながら読み進めています。●「今こそアーレントを読み直す」 仲正昌樹 講談社現代新書●「ナショナリズム」--名著でたどる日本思想入門 浅羽通明 ちくま新書●「アナーキズム」--名著でたどる日本思想入門 浅羽通明 ちくま新書●「日本の現代思想」--ポストモダンとは何だったのか 仲正昌樹 NHKブックス●「アメリカ現代思想」--リベラリズムの冒険 仲正昌樹 NHKブックス●「はじめての現象学」 竹田青嗣 海鳥社●「1Q84」book1、2 村上春樹 新潮社長い間、活字恐怖症+怠け病だった私が今までとは異なる方向の読書を始めて、2年近くになった。まだまだ歩みは蝸牛のごとしだけれど、私にとっては大冒険。先の時間が少なくなったので、心臓に毛をも生やして進もうぞ。「1Q84」は、ちょっと埴谷雄高の「死霊」を思い出させた。情報がびっしり詰っていて、どこを取り出しても論が立つような。だが未消化な気分を引きずったので、ネットで検索したらbook3が来年出るそう。なんとなく納得、出たらやっぱりまた読まずにはいられないだろう。
2009.10.13
コメント(0)
-

食事と買い物
若者のパワーに圧倒された、ステーキハウスのあやしい雰囲気 居酒屋で沖縄民謡の演奏 お土産は那覇国際道り・平和通りの、南国市場、ハブボックス、マンゴーハウス、塩屋などで。お気に入りのTシャツ、アロハ、が買えました。塩屋は日本初ソルトソムリエのいる塩の専門店だとか。オリジナル塩を三本購入。昔、辺見庸さんの幻の岩塩の文章を読んで以来、旅行するとその地の塩が目に留まるようになった。塩は命のみなもとだ。大規模なアウトレットモールも行ってきました。ブランド商品に無知なので、物珍しくて歩き回りました。そうそう、ホテルの玄関で、中尾彬さんが撮影隊といるのを見かけました。テレビの撮影だったのかな。
2009.09.27
コメント(2)
-

沖縄美ら海水族館
ジンベエザメやマンタたち。ひろい、ひろい館内のほんの一部です。これっ!ナポレオンフィッシュ ニシキアナゴにチンアナゴ ハタの仲間怪我してる?ハナミノカサゴひれの棘に毒あり 沖縄は若者達のエネルギーに満ちていました。暑かったです。
2009.09.27
コメント(1)
-

ぶせな海中公園
ブセナ海中公園、海中展望塔付近 めんそーれ膝がすりきれててごめんね~
2009.09.27
コメント(0)
-

沖縄本島にて
ホテルからの夕景沖縄旅行について書くべきことが定まらなくて。写真をアップするのも、ぬるーく、そっけなく、うしろめたいような、沖縄に対する自分の立ち位置がざわめいてしまう。沖縄旅行は5回目くらいになるかな。石垣、宮古、由布島、西表島、久米島、本島を、娘とレンタカーなどで観光した。娘と来たときは、沖縄の抱えている問題や、歴史について地元のタクシー運転手の方や、娘の仕事関係の方に聞く機会があった。だが今回は息子との異色な組み合わせ。彼は多忙な日常をはなれてリゾート気分なので、あえてそのような話はしなかった。あまりしゃべることもないと予想して、本を携帯した。羽田空港で「ガラスの仮面」44巻を見つけて、購入。そのほかに、浅羽通明著「アナーキズム」「ナショナリズム」--名著でたどる日本思想入門いずれも、ちくま新書。この2冊は睡眠薬代わりに持って行ったのでは、ない。?海辺の夜 有明の月
2009.09.27
コメント(0)
-
やはり
息子と沖縄へ行くことになった。同行予定の友達が仕事でダメになったため、ピンチヒッターで私が行くことに。息子とは、彼が10代のときに喧嘩をし尽くして、もはやお互いに疲弊し沈静化している状態。あっさりと、干渉もしあわずに、個人行動することになるだろう。久しぶりの沖縄。本島はあまり知らないのだが、少し休養もしたいな。詩は何とか書き上げた。同人誌を休刊して以来、「お金を出して詩を掲載してもらう」というお誘いを2度受けた。最初は広報堂からで、高額だったのでお断りした。今回も断るつもりだったのだが、マーゴの病気が私を詩への気力に、立ち戻らせた。雑誌に興味を持った事と、金額的にはわからないながら納得したかたち。紙の活字にするという、緊張感は大切だ。納得のいくものが書けるわけではない。だが詩を書いているときが、もっとも私らしい私を生きている気がするのだ。
2009.09.06
コメント(4)
-
ほっ
先週、退院後初めて二泊でマーゴ君が来ていたが、元気活発食欲旺盛。もりもりうんちの大サービス。涙でうんちの記念撮影となった。数ヶ月にわたった水溶性下痢が、ナオッタのだ。苦しみの後の喜びは大きい。幼い子の回復力はめざましい。ばあばを卒業するのも、もうすぐだろう。おばあさんのお団子あたまに憧れて、伸ばしていた髪を切った。マーゴの手術が済んだら、髪を切ろうと決めていた。一緒に軽くなろうね。羅生門に出てくるお婆さんのようなバサラ髪になっていたのでオリーブオイルとかヘアクリームをつけて調整中。それぞれが感動を見いだして、そして少しずつ普段の生活に戻っていく。
2009.09.04
コメント(2)
-
うっ
●炊飯器に入っていた残りご飯を、覚えのないまま再炊飯してしまった。 おこげが炊けた。●電ノコで怪我した植木屋さんが、蜂にまで刺されてしまった。●4割方目減りしているへそくりの投資信託を、如何にすべきや。●花美術館という雑誌からの電話を受けて、お金を出して詩を掲載してもらう、 という過剰な行為を、またしてもすることに。●もしかしたら、息子と沖縄に行くことになるかも。●数冊買いこんであった本のことを、すっかり失念していた。● ●▼◇◎△■
2009.08.23
コメント(2)
-

スタミナアップのために
マーゴの退院も決まったので、ひと足先に骨休め。主人と息子と私の3人で箱根湯本のステーキ屋さんへ。そこからさらに欲張って、延命祈願の黒ちゃん卵を食べるため箱根登山鉄道・ケーブルカー・ロープウェイと乗り継いで大涌谷へ。大涌谷は地すべり防止工事のため、すっかり様変わりしていたが内外の観光客で賑わっていた。お盆の混雑と暑さにまぎれて食べる黒ちゃん卵は、格別の味がした。富士山も炎天にかげろっていた。 この2ヶ月のあいだ、私ははじめて積極的に食べることをしたように思う。兎に角、食べると、力が湧いてくるのだった。
2009.08.16
コメント(2)
-
判明してから
マーゴの下痢の後ろに、大きな病気が隠れていたことが判ってから1ヶ月、無事に手術を終えることができた。順調に回復に向かっている様子だ。原因が分からなかった数ヶ月も苦しかったが、診断が下ってから手術までの1ヶ月は、もっと苦しいものだった。無事に乗り越えられて、やっと胸の閊えが軽くなった。まれな症例として、医学雑誌に足跡を残すことになるかも知れない。同じ病で苦しむ小児たちの、早期発見につながることを切に願わずにはいられません。尽力頂いた医療関係の皆様に、深く感謝いたします。
2009.08.09
コメント(4)
-
「私とマリオ・ジャコメッリ」
本書は2008年5/25NHK教育テレビで放送された新日曜美術館「この人が語る私の愛する写真家 辺見庸 私とマリオ・ジャコメッリ」の内容を再構成し、大幅に加筆、修正したもの。「私とマリオ・ジャコメッリ」 <生>と<死>のあわいを見つめて 辺見庸 日本放送出版協会 2009年5/30発行この新日曜美術館の放送は見ていて、目に焼きついた写真だった。紹介記事を見て、即購入していた。不吉なものから出て異界に佇む私とであったスカンノの少年よ不吉なものとは共同体の決まりごとか母の母の母の母の胎内の冥さを巡ることか「美しいものは恐ろしい」ならば、不吉なものも美しいか発光する異形のものよスカンノの少年よきみのその眼差しのただようところ空虚の向かうところ私を呼ぶところのそのまなざしに入って行こう↑これは脈絡も無くただ浮かんだ言葉。他の写真にも魅かれるものが多い。手元に置いて時々眺めよう。
2009.07.20
コメント(2)
-
「水晶の人」 追記
詩人、入江亮太郎氏の詩集は「入江亮太郎遺稿集」 三好豊一郎・山本定祐編 詩学社 1987年選詩集「風の姿」 金井直編 思潮社 1991年が出版されています。2002年、同人誌に小長井さんの手で掲載された『冬』と言う詩が手元にあるので引用してみます。冬 入江亮太郎冬が来た すべての幻想は秋の日のほこりのように消えていったひとは 大きかった希望の蔭から近づいて来る明日の顔と向き合わねばならぬ物の形は明朗なのに ひとばかり陰鬱なのはそのためだひとは急いだ 頬に冷たく 日の終わりに触れながら冬が来た 暗い夢のような葉の蔭に 枇杷の白い花がひらいたわたしの思い出は 沈黙に閉ざされた寂しい蛇のような日々この国の長い冬 目にしみる冬 かたい心を焼き尽くす炎のような凍えるひとをぼおぼおとあたためる熾火のような 怒りの声を聞いていた冬が来た それはあかぎれを彫る金象嵌の果物ナイフ心をとがらすひき割飯 死んでゆく結核患者 脱走する兵士 引き裂かれた恋それは柵 スト破り 河や海を埋め立てるやつら どんらんな門此の世の自由を隔てるコンクリートの長い塀そいつらだ そいつらこそ冬なのだ冬が来た 目には泥 耳には枯葉今人々はもの言う自由さえ奪われようとしているのだ再び しかし 人々はもはや深く信じていた 真実は重いとそれは世界の心が手綱のように結ばれているからだとそしてこれが 最後の冬なのだとこの生きている歌を 寒気の下でひび割れる 石のような言葉にわたしは刻もう (『日本ヒューマニズム詩集』三一書房・1952年)より焼き尽くす→尽くすは旧字体ひき割飯→ひきは、石+展と書きます戦後、戦争賛歌の協力詩を書いたとして、激しく糾弾された高村光太郎の、「冬が来た」を踏まえて書かれていることは、明らかでしょう。そして、敗戦直後の占領軍による言論統制に対する抵抗も。今の時代も、この詩と共通項が多いことに気づかされます。昭和という激動の時代の苦難を、ご夫妻で文学と共に寄り添い生き抜かれて詩人亡き後も、その痕をたどるかのように次々とご本を出された、まるで道行きを完遂されているかのような、残された妻の生き様に胸が熱くなります。
2009.06.29
コメント(2)
-
「水晶の人」 「たそがれのうた」
同人誌でご一緒だった小長井和子さんが、詩人で亡夫、入江亮太郎(本名・小長井裕雄)氏の生涯と作品をたどるご本を、幻冬舎ルネッサンスから出版された。2008年10月発行。没後23回忌に、その生き方と作品を風化させるに忍びず書き留められたと、お葉書にあった。詩作を絶った晩年の二年間に、入江亮太郎氏がものされた俳句も「小裕句集」として卯辰山文庫よりすでに平成9年に出版されており、亡きご主人への鎮魂と深い想いをたどる旅を続けていらっしゃる。ご自身もご主人の亡きあと俳句をはじめられ、現在「海程」同人としてご活躍され、平成13年に句集「絹雲」を上梓されている。入江亮太郎(1925-1986)1948年脊椎カリエス発病1950年『詩学』新人賞受賞、北杜夫との共同受賞、選者村野四郎1951年~61年『零度』参加、新日本文学会入会、詩人会議、『現在詩評論』『彼方』などに参加、文芸春秋社出版部社外校正のお仕事にも従事される。その後再び健康を害され、詩文を公にすることなく俳句、江戸文学などに親しみつつ、1986年食道癌のため逝去。享年61。私は浅学のため入江氏についてなにも存じ上げず、和子氏を介してその片鱗をうかがうばかりなのだが、その詩人としての孤独で頑迷な生き様は、和子さんにとって修羅の地獄のようなときもあったであろうと推察する。恋愛から結婚後も高校教師として生活を支えられ、夫への尊敬と愛、そしてさまざまな葛藤を抱えられていたことであろう。このような夫婦のありかたは、私に故郷の恩師Mご夫妻を思い出させた。M先生も肺結核で50年にわたる闘病生活を送られた。女の先生は小学校の教師をされ、生活のほとんど全てを担われた。男の先生は小さな、自称寺小屋塾を開かれて、村の悪がきたちを教えていた。女の先生は小学1年生の私の担任だった。男の先生には小学6年生から教えを受けた。お二人に受けた影響は計り知れない。平成9年、男の先生が72歳で永眠され、その後1年かけて男の先生の残された104冊の日記をもとに女の先生が遺稿集としてまとめられたのが、「たそがれのうた」だ。喪失の寂しさ哀しさを埋めるために、男の先生が女の先生に言い置かれたことだったのかも知れない。結核菌は世界中の人の人生や、思潮に大きな影響を与えて沈静化した。私の世代では周りに結核の死の淵から蘇った人たちが沢山いて、私達に生きる指針を示してくれた。またご本から話がそれてしまったけれど、身近な人への思い出が、紹介文や批評めいた感想文を書かせてくれない。
2009.06.27
コメント(0)
-
お祖父さん・お祖母さん奮闘しました
娘達が引越しした。その間家に泊まったり、孫を初めて終日あずかったりした。マーゴは風邪気味の上、お腹の具合が悪くて、1日9回も下痢したためお祖父さん、お祖母さん交代でうんちと奮戦。油断すると紙おむつから漏れるし、お尻が真っ赤にかぶれてしまう。シャワーで流したり、オロナイン軟膏を塗ったり。梅雨の晴れ間だったので、1日何度も洗濯可、は幸いだった。うんち以外はすこぶる機嫌よく、片言のマーゴ語を話しては笑わせてくれる。確かに赤ん坊も時代によって違うことを(進化だと言えるか?)実感。それ以上に、私自身が内なる変化を強いられているようだ。子育てで抱え込んでいたトラウマを、マーゴによって癒されているようなのだ。もうしばらくはここにいて。ソフトタッチの小さな手よ。そして婆離れのときはクールに行こうぜ。今日は病院に行っているはず。はやく良くなーれ。
2009.06.17
コメント(4)
-
血と暴力の国
コーマック・マッカーシー著 黒原敏行訳「血と暴力の国」No Country for Old Men 扶桑社ミステリーを読んだ。ここ2年くらいアメリカの犯罪ドラマをいくつか見続けて、カルチャーショックを受けていたのだが、この本にも通じるものがあった。テレビドラマの背景にある、アメリカ社会の歴史や市民の生活観を知る手がかりも与えてもらった気がする。映画『ノー・カントリー』はほぼ原作に沿った形で作られていたようだ。細かい違いは映画を再見してから、考えたい。ベル:保安官/朝鮮戦争経験モス:退役軍人。ヴェトナム帰還兵シュガー:殺人者(映画ではシガーと発音されていた)国籍不明古きよきアメリカ的モラルの保安官。ベルは国がバラバラになったのでヴェトナム帰還兵は不幸だと、言っている。ベルは大金を持って逃亡するモスも、それを庇って待つ妻も好きなのだ。だがシュガーには関わりたくない。保安官も辞めたいほどに。シュガーは国籍も人種も不明、自らのルールだけで生きている。出合った人はほとんどが彼のルールに従って殺される。屠殺される家畜のように。眼は魂の窓だとよく言うだろう。すると魂のない人間の眼はなんの窓なのかおれは知らないしどちらかというと知りたくない気がする。しかしこの世には普通とは違う世界の眺め方があってそんな眺め方をする普通とは違う眼があってこの話はそういうところへ行く。おかげでおれは考えてみたこともなかった場所へ連れていかれた。この世界のどこかには本物の生きた破壊の預言者がいるんだがおれはあいつと対決したいとは思わない。あの男が本当にいることは知っている。p.8つまり私が映画を見終わって頭を抱えてしまったのは、こいうことだったのだ。しかも終わり方も原作のほうがよりリアルに感じてしまう。子供に甘い希望も持たせていない。解説によると「外の闇」Outer Darkについて近代的思考は「内なる闇」と戦えと主張してきた。悪魔だの怒れる神々だのが支配する「外の闇」など存在しない。問題は人間の心であり、人間と人間の関係なのだと。不都合があるなら心を治療し、社会を変革すればいいのだと。「対人間、対社会の次元」を超えた何かの秩序について--外の闇について--私たちは普段ほとんど何も考えていないように思える。シュガーはそのことを考えてみろと迫ってくるのである。p.422また、作者マッカーシー本人はインタビューで、シュガーを「純粋悪(pure evil)」と呼んでいるそうだ。そうだ、pure evil は野放しにされている。野放しにされた世界に普通の人間も生きているのだ。そして、pure evil も予想不能の突然の事故にあったりするのである。彼は事故で出合った子供に何を手渡したのか。子供は何を拾ったのか。そして息子を導くベルの父のかがり火は、どこまで続くのだろう。この3者を演じた俳優さんたち、緊張感にあふれてそれぞれの魅力が見事に表現されていたと思います。魂を持たない眼、それはどんな色をしているのでしょう。
2009.06.02
コメント(4)
-
ノーカントリー
この映画も楽しみにしていた。が、「ノーカントリー」 2007/米監督:ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン主演:トミーリー・ジョーンズ、ハビエル・バルデム、ジョシュ・ブローリンなにー、この終わり方あ~あ~わからん!映画観るのが嫌になってしまうではないか!なんていうことで、引きずることはなはだしく、ネットで検索していたら町山智浩さんのブログによると、映画の原題「No Countory for Old Men」はイェイツの詩の一行からとられているとのことだった。アイルランドの詩人W・B・イェイツ(1865-1939)の詩「ビザンチウムへの船出」の冒頭That is no country for old men.に始まる有名な詩らしく、たまたま私の持っていた「世界名詩集」にも載っていて高松雄一訳で読むことができた。この詩の訳も解釈も三者三様で難しいのだが2節が映画にも通ずるものを感じたので、高松訳のものをここに書きおきたい。(1節は町山さんのブログで読める。訳されたのはご本人だと思われる。) 2 老いぼれというのはけちなものだ、 棒にひっかけたぼろの上衣にそっくりだ、 もしも、魂が手をたたき、うたうのでなければ、 その肉体の衣が裂けるたびに、さらに声高くうたうのでなければ。 それに、魂の壮麗さの記念の碑をまなぶほかに、 歌の学校などあるはずがない。 だから、おれは海をわたって、 聖なる都ビザンチウムへきたのだ。 また同じ「ビザンチウム」「青金石」という詩のなかにも、この映画の感想を語ってくれる行があったので、好き勝手に抜書きしておく。* 夜歩く者たちの歌が。 星明りの、または月明りの円屋根(ドーム)は蔑視する、 人間存在のすべてを、 ただの錯雑にすぎぬもののすべてを、 人間の血管の狂暴と汚辱を。 おれの前にひとつの幻が、人が、あるいは影が、ただよう。 人というよりはむしろ影、影というよりはむしろ幻。 ミイラの布をぐるぐる巻きつけたこの冥府(ハーデーム)の糸巻きは、 曲がりくねりゆく小道をときほぐすかもしれぬ。 湿りけもなく、息もしないひとつの口が、 息のとぎれた数多くの口を召喚するかもしれぬ。 おれはこの超人的なるものに挨拶を送る。 おれはこれを生のなかの死、死のなかの生と言う。* 舞踏場の床の大理石が打ちくだく、 錯雑の苦い狂暴を、 なおも新しい幻を生みだす あの幻どもを、 * 悲劇は極限に達した。 たとえハムレットがしゃべり、リヤが猛り狂おうと、 十万もの舞台で、 すべての幕切れがいちどきにこようと、 悲劇はもうこれっぽっちも高まりはしない。随分映画の内容からもそれてしまったが、機会があればもう一度見直したい。それと原作「血と暴力の国」コーマック・マッカーシーも読んでみたい。
2009.05.19
コメント(4)
-
花屋さんの間違い
母の日の翌日、娘から予告通りピンクのカーネーションの鉢植えが届いた。母の日と言うものに素直になれないのは、イツモのことなのだが今回は笑ってしまった。きれいに包装されている赤いリボンに、バーコードつきの値段のついたシールが堂々と貼ってあったのだ。いわく、680円也嬉しくなって、送料の方が高かったんじゃない?と娘にお礼のメールすると、の返信がすぐ戻ってきた。しかも、680円ではなく880円だったはず。レシートもそうなってる。とのこと。母の日当日に花屋さんに行ったので、凄く混んでいたらしい。何かの弾みに紛れ込んだ値段のシールを、それも他の品の値段シールを間違って貼ってしまったのか。どうせ間違うなら、値段を高く間違えてほしかった。と、娘はプンプン。その後、マーゴとやってきて一泊して帰って行った。花屋さんも母も母の母も680円分のお祝いとお疲れさん。で、ちょうどいいのかも。
2009.05.15
コメント(2)
-
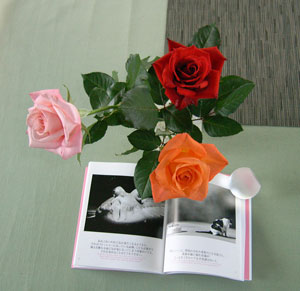
自由猫
長い間野良猫たちの消息を書かなかった。スージーが来なくなって、ノラ、チロ、フテだけになっていたが三者の性格は変わらず、喧嘩しながらも近隣の庭界隈に共生共存しています。2ヶ月ほど前、長老ノラとの大激闘にも怖じることなく登場した威丈高な黒猫をここに登録しておかなくては。名前はまだありません。地域猫とか呼ばれる彼ら。最近は自由猫とも呼ばれるそうな。人間たちの羨望もこめられて。我が家の家計費に占める重みも増すような。不況のあおりか、野良猫規制の強化を受けてか最近食欲旺盛な彼らです。でも食欲の無い時だってありますよ。お母さん。ブラッドリー・トレバー・グリーブの本「Motherhood」のなかにフテを見つけました。
2009.05.10
コメント(3)
-
とぎれとぎれにテレビで映画を見る
5月はテレビで観たい映画が目白押しなのだが、ずっとdvdコーダーが故障していて録画ができない。そのため時下に観ることになるのだが、まだ一応主婦の端くれしているので、途中で席をはずさねばならぬことも多い。しかしそんな中だからこそ、よい映画が持っている訴えてくる力に、鼻が利くようになるってこともあるようだ。●「ピアニスト」2001/仏・オーストリア監督:ミヒャエル・ハネケ主演:イザベル・ユベール、ブノワ・マジメルこの映画は最近観た中でベストに入る。昨年観た●「やわらかい手」2006/英・仏・ベルギー・独監督:サム・ガルバルスキ主演:マリアンヌ・フェイスフル、マノイロヴィッチも性を描いた中でも大好きな映画だったが、こちらはさらに音楽家の心の奥底に潜むものを露出させていて、ピアニストの愛が痛切な衝撃をもって迫ってくる。両方の女優さん、マリアンヌ・フェイスフルとイザベル・ユベール女性の凄さを教えていただきました。大好きです。昨夜は●「アイム・ノット・ゼア」2007/米監督:トッド・ヘインズ主演クリスチャン・ベール、ケイト・ブランシエット、ヒース・レジャー、リチャード・ギア、マーカス・カール、フランクリン・ベン・ウイショー6人が演じるボブ・ディラン、面白かったけど疲れてて途中で居眠りしちゃった。でも映像が、演出が楽しめた。ローリング・ストーンズとかジョンレノンとかの伝記的映画をみても感じたが、世界的な名声や人気と言うのは、富も競争も破滅的生活も孤独も理論もスケールが違う。引き続きやっていたのが●「ボブ・ディラン ニューポート・フォーク・フェスティバル1963-1965」学生時代ラジオで聞いていた名曲を映像で聞きながら、はじめて容姿も確認できた。ジョーン・バエズやピーター&メアリーなんかの顔も見えて懐かしい。そう、あの頃、あの時代。誰もが反戦・平和・愛を歌っていた。今日はネットでディランのことも調べてみたのでした。私は学生時代、思うところあってテレビを持たなかったので音楽はひたすらラジオで聞いていました。そのせいか今でも画像と音楽が脳の中で統一できません。
2009.05.09
コメント(10)
-
数独(5/16追記)
最近算数の能力がとみに落ちていることを感じていた。クイズ番組などを見ていても、買い物していても、計算する意志や気力がわかない。これは計算機とパソコンのせいだ。昔ならったそろばんや暗算も、使わなければ退化する。すごく頭が錆び付き、かたーくなっているようだ、と。なんとなく焦りを(早く言えば老化への焦り)を持っていたものだからゴールデンウイーク定番の、新聞掲載クロスワードクイズの「数独」というのに目がとまってしまった。昨夜夕食後、はじめたものの、これは算数というより頭の回転なのか。私の不得意とする分野で、今まで避けて通っていたことに気がついた。ならば、年取ってからの挑戦とは、これ凄いでのはないか。えんえん3時間は費やしたのに解けなかった。げっそりして、寝た。そして今朝は難易度★★★の数独からはじめてみた。解けましたよ、解けました。すっきりシャワー、空は蒼いよ、洗濯物も風に戦ぐよ。で、昨夜解けなかった数独に再挑戦するぞ。「数独」って、パズル制作会社ニコリの登録商標なのだそう。数の独って意味がよくわからないところが、面白いな。**********昨夜(5/15)、テレビ東京「世界を変える日本人」という番組で▼オバマ夫人もハマるパズル数独を偶然見て、SUDOKUは世界中に流通していることを知った。命名はニコリ社長の鍛冶真起さん。‘数字は独身に限る”という意味からきているとか。そうなのか、そうきたか。テレビで拝見した世界中を飛び回る鍛冶さんにとても感銘を受けたので、ネットで検索したらブログを発見。テレビよりさらに面白そうな人物みたいなので、お気に入りにいれておいた。遅れていたのか、進んでいたのかわからない私、です。
2009.05.04
コメント(2)
-
音盤考現学/音盤博物誌
これも昨年書こうと思っていたもの。故原田力男さんのご縁から、ピアノ調律師のIさんより紹介されて読んだものです。「音盤考現学」「音盤博物誌」 片山杜秀著 アルテスパブリッシング音楽関係ではじめて読んだ本です。縦横無尽に綴られた音楽論集。特に「ゴジラ」の映画音楽を作曲された、伊福部昭氏へのオマージュに心打たれます。門外漢の私がとやかく言うこともはばかられますので、苅部直氏による書評の後半部を引用しておきます。現代音楽は難しくてどうも、という人や、武満徹がこの分野で日本唯一の巨匠だと思っている人は、2冊を通読すれば、まったく考えが変わるだろう。そして読了後、「近代」や「日本」を視る視点も、いつのまにか新しくなっていることに気づくはずである。(2008.7.20 朝日新聞)うわさ以上に面白かったです。変人といえば、原田力男(はらだいさお)さんも変人だったな。もはや、伝説のピアノ調律師と形容されても不思議ではないだろう。原田さんが武満徹氏から譲り受けたエラールのピアノを、I氏が保管されているのですが、その処遇について憂慮されていると話されていました。私は「なんでも鑑定団」に出されたらどうでしょう、などと無責任にミーハーしてお勧めしたのでしたが、できることなら武満徹記念館のようなところに寄贈したいとのことでした。
2009.05.02
コメント(2)
-
あいも変わらず
一泊の予定だった娘達が二泊して帰って行った。連休に家族旅行、その後引越し、その後求職活動と、娘もますます忙しくなりそうだ。今月は町内会の当番で会費の集金に回ったりした。こちらに越して30余年、人々との移ろいのなかにもなんとか定住してきたのは、閉じこもっていられたこと、またある時はパートで働くこともできたこと、などが可能だったからだと思う。セコムしているお宅が増えた。人々の暮し方も変化した。息子は日曜・祭日関係なしの仕事なので、相変わらず今年のゴールデンウイークも、草むしりなどして過ごすことになりそうだ。
2009.04.29
コメント(4)
-
イロニー
竹田青じ氏のポストモダン批判は有名らしいが、「人間の未来」ちくま新書・にもポストモダン思想は「イロニー」の思想だと書かれている。「イロニー」は、この社会の矛盾を深く知っている。しかし、一切は相対的であるという論理によって自分を支えているから、矛盾を克服する「原理」を見出すことはできない。このため「イロニー」は現実に対する否定的・退行的・皮肉的・逃走的態度をとる。その態度の本質は、論理相対主義を最大限に活用して社会の矛盾を批判しつつ、しかしそれに距離をとって「精神の内的自由」を確保することにある。これは、それと自覚せずとも多くの現代人の生き方・考え方だったと思う。私の詩も無自覚、無意識に近いが、この位置にあろうとしていたと思う。ここからまた読み継いでいきたい。**********明日から一泊でまた娘達が来る。娘もいよいよ求職活動を本格的に始めるようだ。
2009.04.21
コメント(10)
全741件 (741件中 1-50件目)
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-12 17:20:55)
-
-
-

- 楽天写真館
- 2025年 1-3月 フラワーケーキ VOL.3
- (2025-11-14 04:30:22)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…
- (2025-11-14 14:35:53)
-








