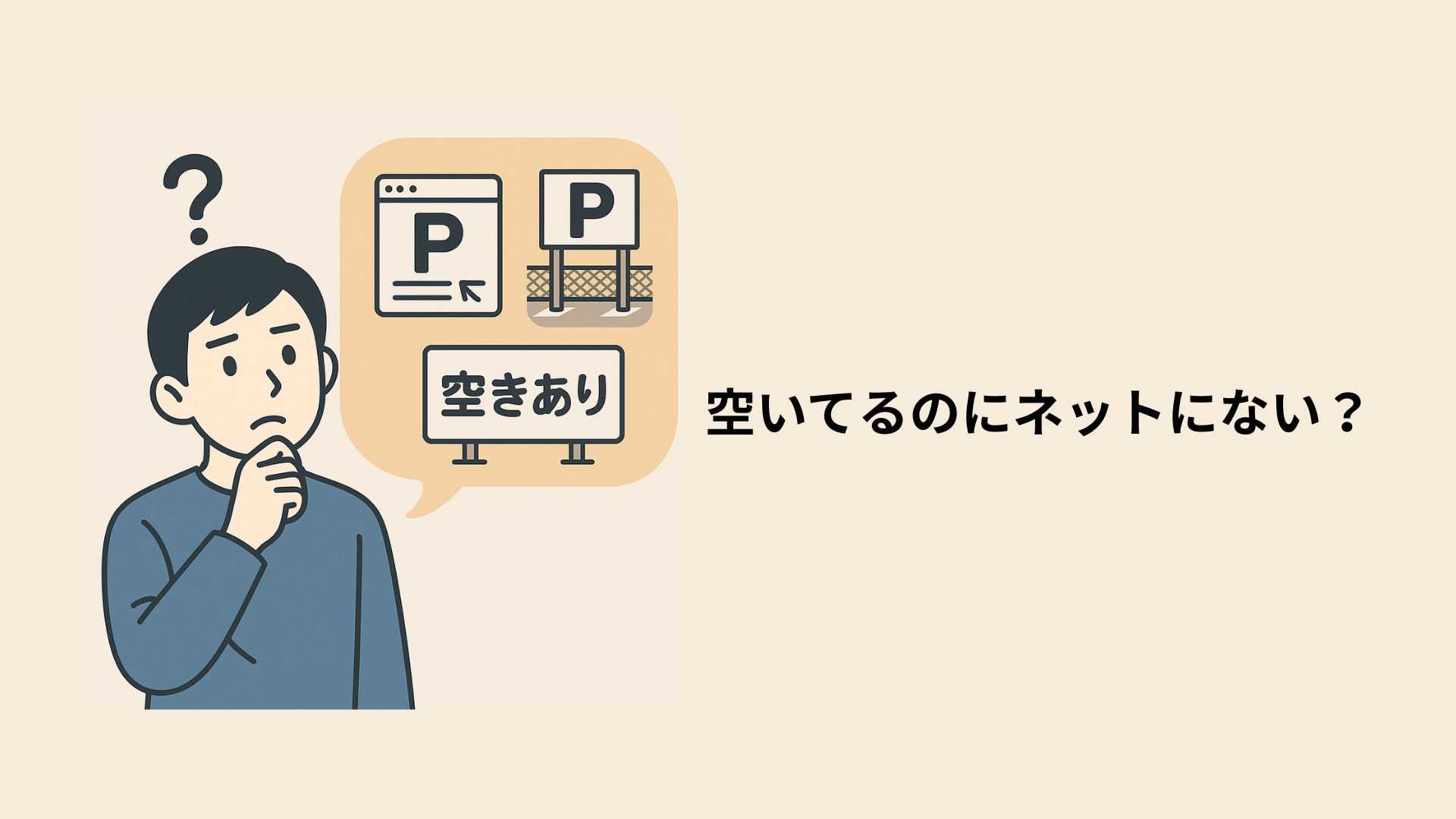
引っ越しにともなって月極駐車場を探したとき、ちょっと不思議な経験をしました。ネットでいろいろ検索しても、なかなか「今空いてます」という駐車場が出てこないんです。
ところが実際に近所を歩いてみると、「空きあり」の札がいくつも見つかる。
――このギャップ、いったい何なんだろう?と感じた話です。
ネットに載ってない駐車場は意外と多い
私が住んでいるエリアは、いわゆる住宅地。決して特別な地域ではありません。
ネット検索では候補が数件しか出なかったのに、現地を歩いてみたらその3倍以上の駐車場が見つかりました。
しかもそのうち何件かは「空きあり」と看板が出ていて、電話番号も明記されており、実際にかけたら即対応OK。
ネットでは見つからなかった物件なのに、現場には“生きた情報”があったわけです。
なぜネットに載せないのか?
これは、月極駐車場という業態の「性質」が関係していると感じました。
特に理由として大きいのが、 ネット掲載におけるコスト構造です。
多くの駐車場掲載サイトでは、月額掲載料や仲介手数料が発生します。
さらに写真撮影や空き状況の管理など、手間もかかる。
月1万円前後の収入しかない小規模駐車場の場合、これらのコストがバカにならないんですよね。
要するに、 空きが出てもすぐ埋まるような人気物件は、ネットに出さずとも自然に契約が決まる。
だからあえて掲載しない、あるいは昔ながらの“貼り紙+電話”スタイルで管理を続けている。
これ、特に 個人オーナーが運営している駐車場に多い印象です。
空きが“紹介”や“つながり”で埋まっていく
また、もう一つ大きいのが 空き待ちリスト文化や、 地元ネットワークでの契約。
例えば私が問い合わせた駐車場の管理人さんは、
「ここは空きが出るとすぐに、昔からの住人さんや近所の方から連絡がくる」
「ネットに出す前に埋まっちゃうから、基本的に載せてない」
と言っていました。
実際、長く同じ場所に住んでいる方や、近所の人づてで情報が流れるような地域では、
ネットに出る前に“顔の見える誰か”で埋まっていく
新参者にとっては少しハードルが高いように感じますが、それも地域の“慣習”なんでしょう。
歩くことでしか見つからない情報もある
私は結局、ネットでは見つからなかった月極駐車場を、近所を30分ほど歩いて見つけました。
Googleマップで航空写真やストリートビューを見ながら「ここにありそうだな」と目星をつけて、現地で確認。
すると本当に「空きあり」の看板が出ていて、その場で電話 → 翌日から契約完了、という流れでした。
この体験から感じたのは、 ネットがすべてではないということ。
特に月極駐車場のようにローカル性が高く、利益幅の小さい業態では、
“古い方法”のほうがむしろ合理的だったりします。
ネット時代でも「足」を使う価値
私たちは何かを探すとき、まずスマホで検索するクセがついています。
それは間違っていませんし、便利な手段です。
でも今回のように、 ネットには載らない情報がリアルの中にまだたくさん残っていることも事実。
駐車場探しに限らず、「現地を見て、話して、感じて」得られる情報って、今も価値があるんだなと実感しました。
ゴルフ場の予約やホテルの手配は、ネットでサクッとできる時代。
けれど、月極駐車場は今もなお、“アナログ最強”な分野の一つなのかもしれません。





