カテゴリ: メキシコ
今日のまとめ
1. メキシコでは特権階級と庶民との間に大きな格差がある
2. トルティーア・ショックに代表されるインフレは貧困層の生活を圧迫する
3. 中国の台頭でメキシコは対米貿易における相対的地位の低下を見た
■GDP成長率
メキシコはラテン・アメリカ諸国の中でも最も早く、1985年頃から経済改革に取り組みはじめました。しかしその成果は余り芳しくありません。1990年以降のGDP成長率は年率平均3%です。これはブラジルやチリなどの他のラテン・アメリカ諸国と比較しても低い水準です。
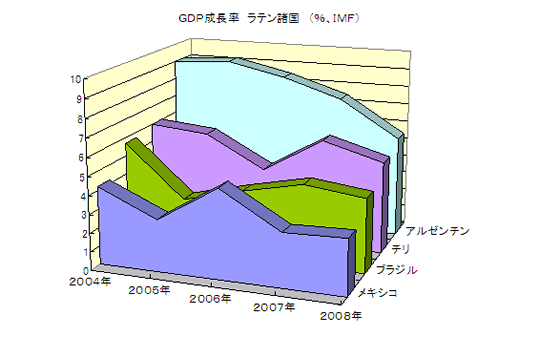
■所得水準および格差の問題
国民一人当たり所得は2005年の時点で7310ドルであり、これは世界の中では中くらいに位置します。しかし同国は昔から特権階級層と庶民との間に著しい所得格差があり、これは現在も改善が見られていません。このため国民の約45%は貧困層に属しています。
下のグラフはどのくらい所得格差があるかの尺度であるジニ係数のグラフです。数字が大きければ大きいほど格差社会であると言えます。
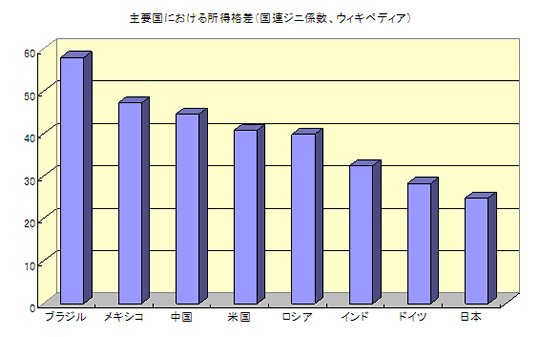
■インフレ
IMFはメキシコの去年ならびに今年のインフレ率をそれぞれ3.9%、4.2%と予想しており、これは安定的な数字と言えます。
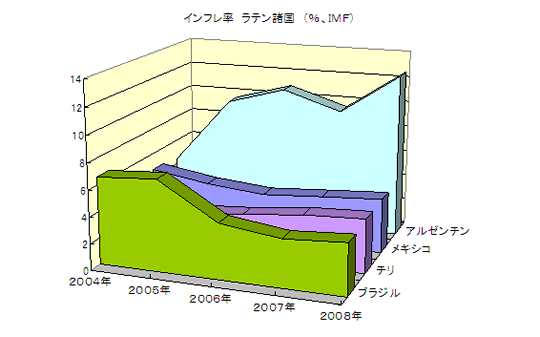
但し去年は世界的に穀物の価格が上昇しました。このためメキシコ人の主食であるトルティーアの値段も騰がりました。所謂、「トルティーア・ショック」です。食品の価格上昇はとりわけ貧困層の生活を圧迫します。
■貿易
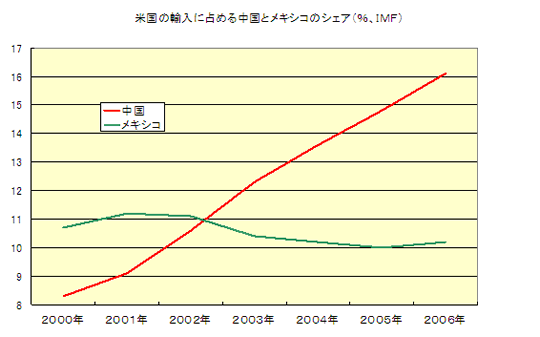
■米国経済の減速
サブプライム問題による米国経済の減速はメキシコ経済にも影響を与えることが予想されます。ただ、近年はメキシコのみならずラテン諸国全般に対外債務を大幅に圧縮したため、以前のように資本逃避を誘発するリスクはありません。メキシコの経常収支は同国が経済改革に乗り出した1990年代初頭にどんどん悪化し、これがペソ危機の原因のひとつとなりましたが、近年は着実に改善してきました。この理由は原油の輸出(GDPの2.7%程度に相当します)の好調ならびに米国に出稼ぎに行っているメキシコ人からの母国への仕送り(同じくGDPの2.7%に相当します)が寄与しているからです。
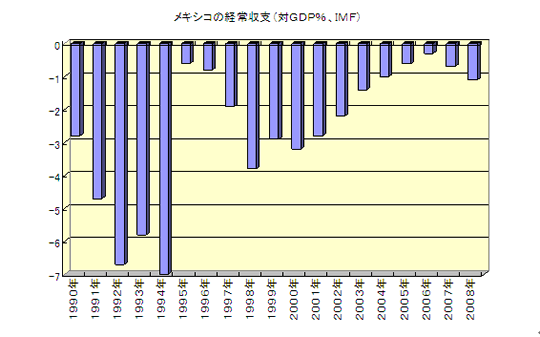
問題は今後メキシコの主力油田であるカンタレル油田の生産量が落ち込んだ場合、国庫の歳入ならびに外貨獲得の低減をどう埋め合わせするかということです。カンタレルは2004年のピーク時には日産210万バレルを超える生産量がありましたが現在は150万バレルを割り込んでいます。さらにメキシコは外国からの直接投資(FDI)の誘致に余り成功していません。最近のFDIのGDPに占める比率は2%程度です。また主要新興国では唯一、直接投資が先細りになっている国だという点も気になります。
1. メキシコでは特権階級と庶民との間に大きな格差がある
2. トルティーア・ショックに代表されるインフレは貧困層の生活を圧迫する
3. 中国の台頭でメキシコは対米貿易における相対的地位の低下を見た
■GDP成長率
メキシコはラテン・アメリカ諸国の中でも最も早く、1985年頃から経済改革に取り組みはじめました。しかしその成果は余り芳しくありません。1990年以降のGDP成長率は年率平均3%です。これはブラジルやチリなどの他のラテン・アメリカ諸国と比較しても低い水準です。
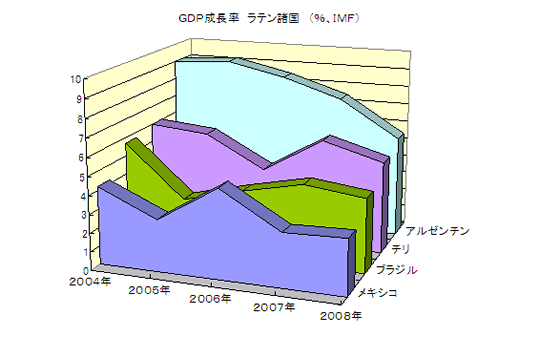
■所得水準および格差の問題
国民一人当たり所得は2005年の時点で7310ドルであり、これは世界の中では中くらいに位置します。しかし同国は昔から特権階級層と庶民との間に著しい所得格差があり、これは現在も改善が見られていません。このため国民の約45%は貧困層に属しています。
下のグラフはどのくらい所得格差があるかの尺度であるジニ係数のグラフです。数字が大きければ大きいほど格差社会であると言えます。
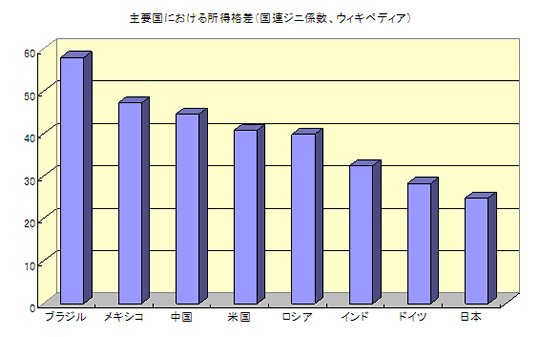
■インフレ
IMFはメキシコの去年ならびに今年のインフレ率をそれぞれ3.9%、4.2%と予想しており、これは安定的な数字と言えます。
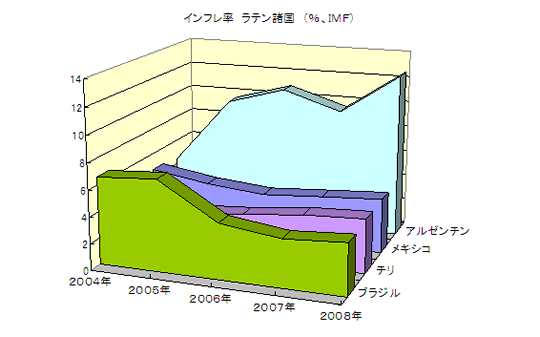
但し去年は世界的に穀物の価格が上昇しました。このためメキシコ人の主食であるトルティーアの値段も騰がりました。所謂、「トルティーア・ショック」です。食品の価格上昇はとりわけ貧困層の生活を圧迫します。
■貿易
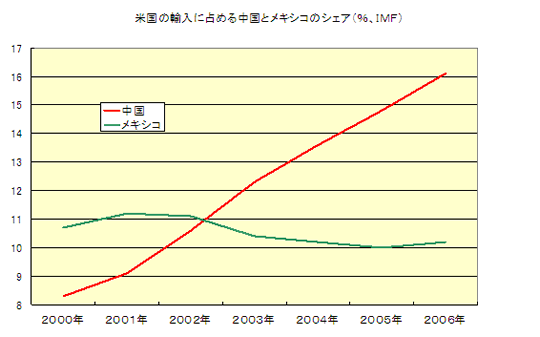
■米国経済の減速
サブプライム問題による米国経済の減速はメキシコ経済にも影響を与えることが予想されます。ただ、近年はメキシコのみならずラテン諸国全般に対外債務を大幅に圧縮したため、以前のように資本逃避を誘発するリスクはありません。メキシコの経常収支は同国が経済改革に乗り出した1990年代初頭にどんどん悪化し、これがペソ危機の原因のひとつとなりましたが、近年は着実に改善してきました。この理由は原油の輸出(GDPの2.7%程度に相当します)の好調ならびに米国に出稼ぎに行っているメキシコ人からの母国への仕送り(同じくGDPの2.7%に相当します)が寄与しているからです。
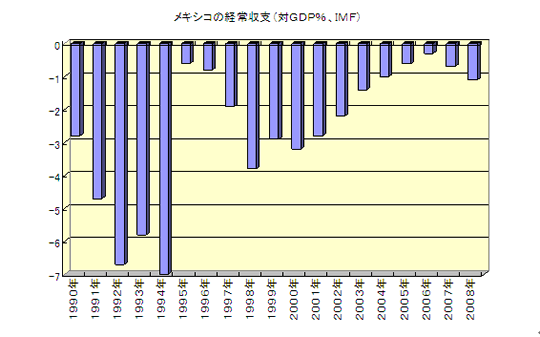
問題は今後メキシコの主力油田であるカンタレル油田の生産量が落ち込んだ場合、国庫の歳入ならびに外貨獲得の低減をどう埋め合わせするかということです。カンタレルは2004年のピーク時には日産210万バレルを超える生産量がありましたが現在は150万バレルを割り込んでいます。さらにメキシコは外国からの直接投資(FDI)の誘致に余り成功していません。最近のFDIのGDPに占める比率は2%程度です。また主要新興国では唯一、直接投資が先細りになっている国だという点も気になります。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年01月08日 18時43分35秒
[メキシコ] カテゴリの最新記事
-
第117回 メキシコの株式市場(その2) 2008年02月04日
-
第116回 メキシコの株式市場(その1) 2008年01月21日
-
第114回 メキシコの歴史 2008年01月07日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
© Rakuten Group, Inc.









