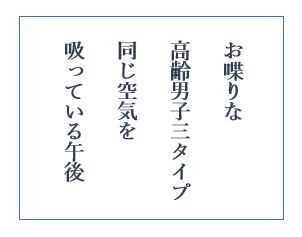2008年03月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
家の熱損失を求めてみる 熱損失係数Q値
(続きです)前回の熱損失を延床面積で割った値である熱損失係数Q値を求めると、次のとおりです。換気1で計算の場合:1.32W/m2K換気2で計算の場合:1.17W/m2Kということで、熱交換の換気計算が釈然としませんが、1.2~1.3W/m2K程度ということでしょう。ここで、かれこれ3年近く前になる2005年7月に、ファーストプラン作成してもらうため間取り要望書と同時にまとめた仕様要望書をひっぱりだしてみると、Q値:1W/m2K目標、1.3W/m2K以下と書いていました。うーむ、仕様要望ぎりぎりくらいというか・・1W/m2K目標は、今のようにQ1住宅も未だ聞かなかったと思いますので、単に数字のきりが良かったからでしょう。あまり良い数値にはなっていない要因をあげてみると、・防犯合わせガラス仕様の3層ガラスサッシが使えなくなっていた・・・サッシメーカー(代理店)の断熱意識低し・全館空調ダクトスペース確保のための1階ハイスタッド化・・・全館空調の欠点の一つ・小屋裏収納追加での壁と窓の増加・・・収納スペース大きくなってこれは良かった・断熱性能不十分な窓を減らす努力不足・・・外観に目をつぶれば、あと5枚サッシを減らせたかもなどでしょうか。2x6程度の壁と複層サッシでは、Q値1W/m2Kをクリアするのは、かなり厳しいものです。。
Mar 22, 2008
コメント(0)
-

家の熱損失を求めてみる 熱交換換気
(前回の続きです)前回、風量に対する熱交換の負荷減を係数0.6(=換気回数低減0.3回/hに相当する)として、計画換気の熱損失を求めましたが、もう少し詳しく考えてみます(情報が無く良く分からないのですが・・)。Web北海道新聞の記事によれば、次世代省エネルギー基準では、「回収熱から第一種換気による動力エネルギーの増加分、具体的には空気抵抗と消費電力の増加、その他のロスなどを割り引かなければならないことになっている。」一方、新住協方式では、「カタログ上の熱交換効率が90%の機械の場合、熱交換率をやや低めの80%とみて、換気廃熱の8割を回収するという考え方で計算している。0.5回の8割、つまり0.4回を熱回収した残りの0.1回が換気負荷となる」換気負荷[回]=0.5 *(1-熱交換効率)とあります。どちらを使うのか、統一されていないと、Q値の比較もままならないのではないでしょうか。次世代省エネルギー基準の場合、実際の総合評価をする場合には有効と思いますが、熱交換しない場合の消費電力をどう見積もるかによっても結果が変わってきます(ダクトの圧力損失増加もあり、単純に半分とはいかないでしょう)が、どうするのでしょう。また、新住協方式では、熱交換効率をカタログ値より低めをみて計算するとありますので、これも、実際の熱損失とは異なってきます。さらに、我が家の換気装置の熱交換効率は、単に70%以上としか記述がありません。しかし、Webで調べてみると、一般的に、熱交換の換気装置の熱交換効率は、風量と反比例の関係になるようです。風量に対する熱交換効率の値を公開すべきではないでしょうか。こんな状況では、実際に即した正確な換気の熱損失を求めることは、不可能です。また、住宅メーカーが宣伝文句にしているQ値ですが、どんな計算で出しているのか分かりません。信用も比較も出来ないように思えます・・気を取り直して、熱交換効率70%とし、上の式で出してみましょう。換気負荷(回)=0.5 * (1 - 0.7) = 0.5 * 0.3 = 0.15この値ですと、前回の風量に対する負荷減の係数0.6に対し、半分の係数0.3となります。この結果、換気の熱損失は、218[m3/h] * 1.293[kg/m3] * 0.24[kcal/kg℃] * 0.3 = 20.29[kcal/h℃] = 23.60[W/K]これで前回の結果を「換気2」として、出し直し、グラフにすると、次のとおりです。前回より、今回の方が、実際の熱損失に近いはずですが、Q値は、どちらを使って出せば良いのでしょう?・・ (次回に続きます)
Mar 8, 2008
コメント(0)
-
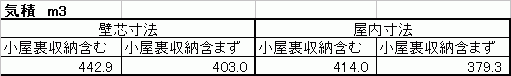
家の熱損失を求めてみる 計画換気の熱損失
(前回の続きです)次に計画換気(24時間換気)の熱損失を求めてみようと思います。ここで必要なのが家の気積ですが、ここで、ふと気がつきました。今まで各部の熱損失を求めるのに、家の寸法として、図面に載っている壁芯寸法を用いていましたが、屋内側の寸法を寸法を使うのが、実際に即しているはずと。東急ホームの図面では、壁芯寸法は、2x4の壁の場合の中心にとっていますので、我が家のように2x6の壁の場合、さらに約50mm内側に室内側に出ています。つまり、屋内側の石膏ボード表面は、壁芯から約107.5mmも内側になっています。これで、気積を求めたら、かなりの違いが出るはずです。で、求めた結果ですが、次のようになります。この気積ですが、非換気部分となる空調機室、ダクトスペース、下り天井などを家の容積から差し引いたものです(図面から大よそで読み取って盛り込んでいます)。壁芯寸法と屋内寸法を見比べると、約5.5~7%の差が出ていますので、適正な換気量を決める上で、かなり差が出ると言えそうです。0.5回/hの必要換気量は、これら屋内寸法の気積から、屋内寸法では、212m3/h(小屋裏収納含む)、189.7m3/h(小屋裏収納含まず)となります。ここで、空調業者による必要換気量計算書を見てみますと、気積が407.08m3で必要換気量が204m3/h(小屋裏収納含まず)となっています。この気積は、壁芯寸法から求めたものであることが分かります。さらに実際の換気量は、換気装置の給排気量207m3/hでの圧力損失に安全率20%を掛けた値をもって決められており、大きめの218m3/hが設定値となっています。この実際の換気量218m3/hは、屋内寸法を用いた換気回数で見ると、0.53回/h(小屋裏収納含む)、0.57回/h(小屋裏収納含まず)となり、小屋裏収納含まない計画にもかかわらず、小屋裏収納含んでの必要換気回数以上の値となっていることが分かります。小屋裏収納が換気ルートに入っていないのは、換気装置の換気能力が厳しいとのことからだったのですが、屋内寸法からの気積を用い、もし圧力損失の安全率20%に目をつぶることが許されるのであれば、小屋裏収納も換気ルートに含んだ計画も出来たことでしょう。次にこの換気量の熱損失を求めますと、次のとおりです。218[m3/h] * 1.293[kg/m3] * 0.24[kcal/kg℃] * 0.6 = 40.59[kcal/h℃]ここで、1.293[kg/m3]は0℃の空気の密度(温度上がると下がります)、0.24[kcal/kg℃]は乾燥空気の比熱、0.6は熱交換分の負荷減です。また、これをワットに変換すると、次のとおりです。40.59[kcal/h℃] * 1.163 = 47.21[W/K]ここで、少し疑問が沸いてきました。これは乾燥空気の負荷です。実際の空気は水蒸気を含んだ湿り空気ですので、この影響はどの程度あるのでしょうか。東京1月の平均気温は5.8℃、平均相対湿度は50%です(理科年表、1971-2000年の平均)。この時こちらから飽和水蒸気量は、7.18g/m3なので、相対湿度50%での水蒸気量は3.59g/m3となります。水蒸気の定圧比熱は、0.441kcal/kg℃なので、218[m3/h] * 3.59[g/m3] * 0.441[kcal/kg℃] = 0.345[kcal/h℃]となり、乾燥空気に対し無視出来る値です(間違っていないか??ですが・・)。なお、夏はこの数倍になりますが、冷房負荷としては、水蒸気が水に変わる熱量(潜熱)の影響が大きくなります。話を戻して、設定換気量での家全体の熱損失をまとめると、次のとおりです。前回の壁芯寸法のものと屋内寸法のものを出しなおしてみました。この屋内寸法での熱損失の割合をグラフ化すると、次のとおりです。換気の熱損失は、とても大きいということが分かります。窓と同じくらいあります。(次回に続きます)
Mar 2, 2008
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1