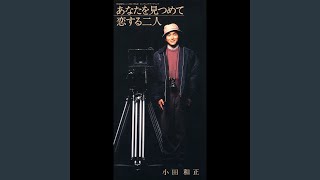2008年05月の記事
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
木花咲耶姫命~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
大事な事を忘れてた《大平山神社》《御祭神》『星』…瓊々杵尊『日』…天照皇大神『月』…豊受姫大神《相殿》…伊邪那岐大神・伊邪那美大神・大己貴命・御食津神・大物主神…他。また、別天神として月夜見尊を祀る。 慈覚大師は日月星それぞれを振り当てた三つの寺院を建立し、天下太平を祈る祈祷所としたもよう 境内摂社脇からの山道が気になりましたので登ってみることにします。途中で出会った方に伺うと山頂に浅間神社があるとのことo(^-^)o頑張って歩きますすんごく見晴らしのよい場所(つまり歩くには怖い場所)もあります途中光り輝くような波打つ岩がありましたので(どう考えても磐座としか思えないんだけど…とくに祀ってはなかったですが)そこでしばし休憩壬生寺でいただいてきたお水を飲みながら…ふと思いついて磐に垂らしてあげましたそこからさらに歩くと二本の木の間にしめ繩が張ってありました鳥居みたいくぐってさらに道ならぬ道を登り頂上に到着『富士浅間神社』が鎮座ましておりました。なにがどうとは表現しがたいのですが…とっても素敵社の裏にまわってみると…ちょっと小高い磐の空間があり神木のような存在感あふれる木がありました。何故かとてつもなくうれしい気分になっちゃって…木に抱きついたりほお擦りしたり風もないのにパタパタ揺れる周囲の笹の葉や木々の枝が、まるで『ワ~イ』と手を振ってくれているように思え…つい『みんな~来たよ~ん』とこちらも手を振ってしまいましたf^_^;(みんな…って誰だろ)しばし境内でまったり看板によると《木花咲耶姫を祀る大元の神社》とのこと。この時は…嘘だろ~~…とあまり気にしていなかったのですが…どうやらまるきり嘘でもない様子。ここからかなりややこしくなるのですが…富士山本宮浅間大社は元は《富士大神》という富士山を御神体とする神を祀っていたものを、木花咲耶姫命を大々的に祀るようになったのがどうやら江戸時代のようで、これは吉田神道の影響大の模様。で…松尾芭蕉が『奥の細道』で室の八島明神(栃木県栃木市の大神神社とされている)に参拝した際、同行の曾良がいはく、『この神は木の花咲耶姫の神と申して、富士一体なり。無戸室に入りて焼きたまふ、誓ひの御中に火々出見の尊生まれたまひしより、室の八島と申す。また煙をよみならはしはべるも、このいはれなり』と語ったと記されています。実際、栃木市の大神神社一帯がその室の八島の伝説の地であると伝わっており、式内社の『大神社』とは現大神神社であるとされております…。…が、芭蕉が参拝したのが実際に現『大神神社』であると確定できるものはなく…平安の頃に音に聞こえた歌枕である『室の八島』に必ずあるはずの涌き水もなく…そして現大平山神社の旧号が式内社の『大神社』とあり、涌き水もあるし…んんんこうなると単純な私は…『大平山が奥宮で、大神神社が里宮でいいんじゃないかえ』…なんて考えてしまいまするm(__)mさてさて…とりあえず、栃木市は木花咲耶姫命の伝承地ってのは間違いないようです。頂上の富士浅間神社で深夜に空を見上げると、きっちり社の真上に北極星が見えるそうな…☆下の本殿では旦那さんの瓊々杵尊が金星として祀られておりますし…ん~~やるな円仁たん(ん円仁たんが祀った時は大平大権現かな) 元来た道を戻ります。そして『剣宮』にも参拝(すみません参拝してしまいました…言い訳になりますが、おいでおいでと導く者というか光についてったら…ちっこいのになんだここはと不思議に思いよくみると…剣宮と裏書きしてありびびりました…禁足地ぢゃん…参拝終えた途端ダッシュで出ましたよ)夏に熊野に行くことが決定しておりましたので、これはぜひとも熊野行きの前に天目一箇神さんにご挨拶にいかねばと考えてたんですね(熊野と天目一箇神についてはまたあとで…もしくは「一本ダタラ」で調べてみて下さいませ)思いもよらずご挨拶できて大満足さてさて…ムフ やることやったので…次はお楽しみの《大平山の旨いもん食べようじゃないか》の時間がやってまいりました疲れちゃったので謙信平は今回諦めて、境内近くの茶屋に陣取りました(^O^)/大平山の名物は…『卵焼き』…地鶏の卵を使い、注文してから焼く逸品意外にデカイそしてかなり美味『焼鳥』…同じく地鶏を使い注文してから焼く。ジューシーでうま~これ食べる為だけに来てもいい…と思いました『お団子』…あんこからめただけのシンプルな団子。結構量がありましたがぺろりと平らげてしまいましたその上ざる蕎麦までいただいてしまいましたf^_^;うお~こんなに旨いもんばっかり巡り逢えるとは…歩くの大変だったけど栃木に来てよかったよ~(/_;)神様ありがとう(^O^)/絶対また来るぞ~
2008.05.31
コメント(2)
-
日月星の聖地・大平山~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
栃木駅からバスで国学院に向かいます。途中で巨大な鳥居を通過終点の国学院で降り、坂をえっちらおっちら登ります。この日の目的地《大平山神社》に向かいます。写真左上…《六角堂》連祥院ともいう。本尊は『虚空蔵菩薩』。山城国山崎国宝寺にあった聖徳太子作と伝わる仏像。慈覚大師円仁が夢で観見し、淳和天皇に願い大平山に移したという。明治以前は山頂の『本地堂』に祀られていたものである。虚空蔵菩薩は金星であり、またアカシックレコードでもあるという。お使いは『うなぎ』右上…大平山神社境内には多くの社殿があり、四十二柱の神が祀られているとのこと。左下…山頂の《富士浅間神社》への山道の途中の情景。右下…《富士浅間神社》木花咲耶姫命を祀る。全国浅間神社の元社であり、木花咲耶姫命は鎮まりやまぬ富士の御霊を鎮めるために、ここから富士山へ移し祀られたのだとか。 まず六角堂に参拝多くの方が参拝にいらしています。ここから長い…およそ千段…階段を登り山頂を目指します頑張るぞ~o(^-^)o坂の名を《あじさい坂》といい、両脇には紫陽花がずうっと植わっております花の頃にはさぞかし素敵でありましょうな~紫陽花…むっちゃ好き~…なんですけどね~一月早かったようで…ま、いずれ花を目当てにまた参りましょう 坂を登っていると、途中に『窟神社』がありました。天然の窟に涌き水が溜まって、奥まで続いているようです。怖いくらいに清らかな霊気昔は弁財天が祀られていたとか。 途中何度か直角に曲がる階段なのですが…それ以外は直線で、かなり急な階段でもあります。随神門に着いた頃には全身汗びっしょりで…ちょいとねっころがってバタンと休憩~ふぇ~~~きついです~~~いつものことですので、すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが…本当は、大平山神社本殿そばまで車で一気に行くこともできますタクシーでサクッと行く手もあるのですが…マゾなのか阿呆なのか、私はいつも変わらず自分の足で歩いて上がっちょる訳です…『できれば楽してこなしたい』てのが他分野に関する私の基本的スタンスなんですけどね~何故か参拝の時には自ら進んで大変な回路を選んでしまうのは…何故なんでしょうか自分でも不思議は~ヒ~フゥ~~頑張れ自分あとちょいだ~あんまり休んじゃうと根が生えそうなので休憩は5分で切り上げ、ラストスパート着いた~《大平山神社》第十一代垂仁天皇の頃、大物主、天目一箇神が三輪山(現大平山)の剣宮に鎮座されたことに始まる(現奥宮=禁足地)古くより祭場であった場所であるようで、『日月星の三光天子』が本来の祭神であるという。旧号を『大神社』とする。天長四年(827年)勅命をもって慈覚大師円仁が創建。天下太平を祈る神仏混合の場として造営されました。現在は神社として四十二座の神様をお祭り申し上げております。境内社には、交通安全社の道主貴之神(配祀・猿田彦之神)福神社=大國主之命・事代主之命天満宮・文章学社=菅原道眞 (配祀・思兼命)星宮=天加背男命 (配祀・磐裂神)子易神社・易産社=子易大神(木花咲耶姫命)稲荷神社=太平稲荷大神・伏見稲荷大神・蔵稲荷大神(宇迦之御魂神・大宜都比賣神・保神)三輪神社=大物主神足尾神社=日本武尊(配祀・少彦名命)皇大神宮稲荷神社=笠間稲荷大神厳島神社=宗像三女神上宮神社=聖徳太子大杉神社=大杉之大神(大山祇命)機姫神社=機姫大神(天八千千比賣命、配祀・稚日女尊)浅間神社=木花咲耶姫命愛宕神社=火産霊神・埴山姫神八幡神社=八幡大神奥社剣宮=天目一箇神(配祀・天津神八百万・国津神八百万)下社二ツ木神社=祓戸四柱之大神など… いっぱい並んだお宮を一つずつ参拝中でも『星宮』がよかったな~どこかの高校の野球部らしきメンバーがユニホーム姿で参拝してました甲子園目指して頑張れよ~ここでもお宮参りさんに遭遇…てゆうかなんちゅうか、参拝者がやたら多いんですけど…f^_^;大社でも一宮でも総社でもないのに…凄いそして《夏越祓》の人形が既に用意されておりましたので、私も…撫で撫でぺたぺたふ~ふ~…して納めてまいりましたおはらいしたらお札を送って下さるとか。300円でまさかそこまでするとは(後日本当に送られてきました玄関に貼るお札が)大平山神社は御朱印がまたカッコイイ~のです四神(青龍、朱雀、白虎、玄武)が全員集合しておりましたすっかり気に入っちゃって…『住んでもいいなあ~』…と思いました大平山での話はまだ続きます
2008.05.31
コメント(0)
-
壬生寺~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
翌日は…お宿のおばあちゃんが握ってくれたでっかいお握りと若芽の味噌汁の朝食が意外な美味しさで…うれしいスタートとなりましたo(^-^)o全然期待していなかったのでびっくりこの日、宇都宮の街は見事に躑躅が満開でしたパッと華やかでよろしいですね~ 日光では、どうしてグジグジ文句たれていたのかというと…f^_^;当初の計画では、円仁ゆかりの地を中心に宇都宮を基点に二泊三日でまわる予定でした日光は、夏あたりに、中禅寺湖や奥日光まで一気にやろうと考えていたんですねそれが……私の思惑どうりにはならず…どうにもいろんなことが滞り…仕方なく直前になって一泊を日光にし、今回は宇都宮と日光を半分ずつまわることで妥協してみたら~(¨;)~あれよあれよと全てが上手く回転しはじめましたは~掌の上で転がされちょりますな~頭では『委ねちゃえば楽ちん』と分かってはいるのですが…私の希望はそっちのけで…ちょっと反発もしてみたい気分にもなりまする…しかし…行くと決めたのは当日朝なのですf^_^;それなのに突如N氏まで登場しちゃったり、振り返ればマリアな方が座禅してたり…と、なかなか愉快なサプライズに満ちた旅となりました さて、《宇都宮・二荒山神社》からスタートこちらも下野国一宮です《宇都宮二荒山神社》《御祭神》豊城入彦命《相殿》大物主命、事代主命豊城入彦命は第十代崇神天皇の第一皇子です。崇神天皇には慈愛厚く優れた二皇子があり、どちらを皇太子とするか夢占いをされました。その結果、活目尊が皇太子となり(垂仁天皇)、豊城入彦命は子孫とともに東国守護に下向したとされています。祭神は武徳に優れ、藤原秀郷源頼義・義家源頼朝源義経徳川家康が篤く信仰したと伝えられ、先勝祈願や寄進が多く残されております。 参拝にあがるとお宮参りの赤ちゃん抱いた家族が二組も~かわええ~(すすす~っと近寄って赤ちゃんのご尊顔を拝し愛でるの、大好き)ここはサクッと済ませ次に向かいます 東武宇都宮線壬生駅で下車し、1kmほど歩きます。慈覚大師円仁の生誕地《壬生寺》に参拝しました写真左上…《紫雲山壬生寺山門》円仁誕生の際その家の上に紫雲が広がり、それを目撃した大慈寺の広智により将来高僧になると予告された。この縁により円仁は9歳で広智の弟子となり、大慈寺で修行を積み、後に最澄に学ぶための素養を養うことになる。右上…《壬生寺境内にあるライシャワーさんお手植えの桜》ライシャワーさんはアメリカ駐日大使であり、日本研究者。円仁の日記『入唐求法巡礼行記』を二十年の歳月をかけて英訳し、世界にその存在を知らしめた方です。左下…《大師堂》右下…《円仁産湯の井戸》とっても美味しい水でしたなんと『甘』かったまさに甘露境内はそのほとんどが幼稚園となっておりまして…はじっこにお堂や井戸があるという感じでしたf^_^;円仁さん…子供好きそうだし、案外これで嬉しいのかも《円仁展》でも、祭りあげられて、居心地悪そうな困ったような様子でしたし 壬生の街は…子育てによさそうな街という感じがしました。江戸時代からすでに蘭学が盛んであった土地柄なのだそうで、町並みもちょっといい感じ歩道がとっても広く歩きやすい。あちこちにベンチが置かれています史跡案内板も充実。日光に入る前に家康の柩を供養したというお寺もありました。(ちらっと参拝)これから川に釣りに行くらしい少年たちとすれ違いました。自然もあり、街もしっかりして凄くいいな~(和歌山市も子育て&教育にはよい環境と感じましたが、ちょっと甲乙つけがたいな…)
2008.05.29
コメント(0)
-
摩多羅神と北斗七星~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
新宮を軽く回り…N氏を大猷院及び慈眼堂へ見送り…私は近くの茶屋でコーヒーと味噌田楽で一服させてもらいました(∪o∪)。。。さすがに朝から歩きどおしで疲れたよん(でもあと5kmくらいなら歩けるな)時間がかかりそうですので、もう一度《常行堂》に入りしばし座ってみることにいたしました。参拝者も少なく、堂内に坊様もおらずのんびり普賢菩薩さんの印象がクッキリとしたお堂です。裏にまわると摩多羅神が祀られております。《摩多羅神》唐から帰国する際、慈覚大師の前に出現し…『我は障碍の神である。我を崇拝しなければ、往生の願いは達せられないであろう』と告げたという。慈覚大師は比叡山の常行堂にこの神を祀り護法神とした。摩多羅神は阿弥陀如来の裏に祀られ、秘されることが多い玄旨帰命壇の本尊である。(西方の壁に祀られます)摩多羅神は笑顔で鼓を持ち、童子二人を歌い踊らせている姿で描かれ、その上には北斗七星が瞬いている。摩多羅神は大黒天ないしダキニ天であるとされる。何故、精神修養の妨げとなる障碍神を崇拝するのか…清く正しく光りに満ちた世界を目指す人はびっくりするかもしれませんが…『それが唯一の道』だからです。んこの言い方は誤解を呼ぶな…困ったぞ一応私なりに説明してみるとします…ちなみにあらゆる宗教や精神修養メソッドがありますが、無神論者も含め…どの回路を使おうとも、ちゃんと最終地点へは辿りつけます。摩多羅神を崇拝することが唯一の道なのではありません。(それぞれの宗派やメソッドの中でそれぞれの言葉で表現されております) ☆北斗七星…魂の故郷である清浄なる世界、阿摩羅識《九識》…人間の本体☆摩多羅神…ぶっちゃけていえば潜在意識である阿頼耶識《八識》…集合意識。☆二人の童子…我執や無意識的な情念、欲望《六&七識》…分離した個別の意識。これらは人間の意識の地図でもあり、煩悩即菩提、凡聖不二を表しています。…で、これが正しいこっちは間違ってるですとか、綺麗ないいことばっかり追い掛けていたり、よくない(と判断したもの)を癒したり直そうとしたりしてる状態ってのは…まだ鼓の音に踊らされている二童子のレベルで遊んでいる状態でありますf^_^;(これやってるかぎり永遠に同じところをぐるぐる回り続けます…陰陽の回転から抜け出すには陰を消すのではなく太極に立つしかありませぬ)意識を磨き、第九識の聖都(ニルバーナ)へ飛翔するためには、甚だ逆説的ではありますが…煩悩や執着をまるごと受け入れる(障碍神を崇拝する)ことが絶対不可欠です。『愛するまで、あなたはそれに縛られる』という真理と同じ。我執や情念、集合意識すらも(コントロールしようとせず)それがあることを有り難く受け入れ、崇拝(愛)する時、私たちは聖なる星の意識である静かで限りなく豊かで純粋な世界に到達します。ある程度修養を積んで、あと一歩ってところで行き詰まってしまったぞ…(:_;)という方にしか理解できないかも…という形而上学的な内容ですので一般には秘されておりますが…う~ん、今なら表に出してもわかる人多いんじゃなかろうかあらゆるものに『ありがとう』と感謝する境地…ともいえます。身体が『ある』ことに感謝。不安や恐れ、問題や孤独が『ある』ことに感謝。ご飯や住まい車、仕事、衣服や家族友人、太陽や海や月や星、動物たち植物鉱物地球が『ある』ことに感謝。病が『ある』ことに感謝。不足が『ある』ことに感謝。今ここに『ある』ことに感謝。もう一つ別の言い方をすると《嫌いなものや怖いものは好きになっちゃえば大丈夫》とも言えるかも《ハートを開く》…とは価値判断せずに欠点も含めてまるごと愛し受け入れる状態ですので、これも同じ『恐れ』はじっと見つめているといずれ消え去ります。問題を処理しつづけている限り、どこにも行き着くことはできません。 さて、N氏が慈眼堂より下りてまいりましたN氏…慈眼堂は絶対気に入るはずと思ったら…案の定o(^-^)oとってもお気に召したようで、左回り&右回りの二回も参拝してきたそうなふふふんそういえば慈眼堂は北斗七星の気配ただよう静かで清らかな空間でしたな~もはや暗くなりかけてまいりましたが、せっかくですのでN氏を神橋と本宮、四本龍寺などにご案内~N氏…四本龍寺では紫雲石にちょこんと座ってるし…(@_@)(せっかくですので私もちょっと真似してみました…)ここで古峰ケ原土産の胡桃ゆべしをいただいてしまいました(^O^)/(うまかった~)N氏は私の為にわざわさ日光に来た訳ではなく…(私にも合わせて一石二鳥して下さったのだと思いますが)…ご自身のライフワークである日本武尊に関する全国行脚の一つとして、日本武尊を祀る《古峰神社》に参拝。余った時間を使って日光にも足を延ばして下さいました~(^O^)/古峰神社…数万といわれる日光の天狗(一説には十万)の本拠地にして、勝道上人ゆかりの地でもあり、現在も日光修験道の大道場として機能している聖地です。一般には古峰は火伏せの神様として信仰を集めております。にまそうかN氏は霊的にバランスが取れており、龍さんも天狗さんも鳳凰さんもなんでもOKの人なので古峰から天狗ドワッと連れてきてくれたのかも\^o^/どうでもいいことですが、元来アバウトな私にとっては、天狗も天使も似たよなもんじゃと思っちょりますf^_^;(最近は神様と御先祖様の違いがよ~わからなくなってきたし…遠い祖先か近い祖先かの違いしかないような気がするんだが…) さて、最後は《日光ビール》と《ゆばパスタ》と《ます寿司》で乾杯し、東武日光駅で握手してN氏とは別れましたこの日は宇都宮泊宇都宮の美味しい餃子でビールしちゃいました本当にうまいよ~海老餃子~おかわり~家康さんの供養その他が済んだのですっかりお気楽極楽~
2008.05.28
コメント(2)
-
剣と日光~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
家康御廟には意外に多くの人が参拝()に登っておりました。拝処は雨もあってか、どんよりじっとりグズグズとして暗い感じです。脇から宝塔にまわりました。事前に知ってはおりましたが…実際に見るとかなりショックでした。奥の院拝処まで観光客が上がれるのはともかく…墓の周囲をぐるりと歩くことができます。敬う心の微塵もない物見高い人々の列がぞろぞろと…死後数百年を過ぎてなお…墓を土足で踏み荒らされているようで、急に家康さんが気の毒になってしまいました。ここまでされる程悪いことはしてないよな~目の前の立て看板がぐらぐら揺れています。訴えるようにこちらに向かって何度も…あれと見回しましたが、周囲の人々は騒ぐ様子もない………地震…じゃないのかなしばらく看板が揺れているのを見ているうちに、周囲は気にならなくなり、お数珠を取り出して参拝を始めました。すると…修学旅行らしき小学生が数人後ろに来て看板を読んだりしているようでした。後ろをとおりかかりながら珍しげにこちらに向かって……『信奉者なんだね~』…とつぶやく声も聞こえましたが、(-.-;)とんでもね~それどころか宝塔に上がる直前までは…『京都の天子(天皇)に霊威で勝る為に仏製の新三種神器まで造りおって~~、アマテラスをも越える東照大権現ですと~…ムカムカ…熾盛光法は皇室や国全体の為のもんだぞ~ムカッ…百歩譲って当時は時勢ゆえしかたないとしてもだな~やっぱりこれはエゴイズムの極致ですぞ家康さん…くそ~なんで私がこんなとこに来なきゃいかんのだ~』などと文句たれておったとですよ…通行人様f^_^;結局宝塔の周囲三箇所でお数珠取り出してもみもみ…(+_+)その都度、行きつ戻りつしていた元気な小学生たちが後ろに控えるという摩訶不思議…ん…供養は子供が有効なんですか…よ~わからんが…『眠り猫』まで戻り、本殿参拝本殿にはなぜか織田信長と源頼朝が合祀されているようです。(東照大権現の眷属なんだってさ…ははは…は~あ)そういえば以前Oさんが来た時に、剣展をやっていたとかいってたな~何故か足利直義くんのもあったとか…『鳴龍』飛ばして(参拝しないで)輪王寺にダッシュそして輪王寺境内でキョロキョロすると…梅の木の影からまるで梅の木の精霊か、清らかな童子のような風情で、N氏登場神様ありがとう~(T_T)わ~い…\^o^/まさか来て下さるとは…『東武日光に着きました』のメールだけでドワッと開いちまいました日光の結界内に入っただけでパッキリとはさすがですわざわざ助っ人に駆け付けて下さり有り難きこと…感謝m(__)mN氏登場がなかったら一度で済まなかったんじゃなかろうかと…f^_^;しかもナイスタイミング早速一緒に輪王寺三仏堂を参拝。お坊様がついて説明して下さいます《日光山輪王寺》今から1200年以上前、天平神護2年(766年)、日光開山の祖である勝道上人が現在の神橋のそばに建てた四本龍寺を始まりとする。平安時代、慈覚大師円仁が入山し、以降天台宗の大道場となる。坂上田村麻呂や弘法大師も来山。江戸時代には天海大僧正によりおおいに栄え、比叡山を凌ぐありさまであったという。現在も天台宗三本山の一つとして信仰を集める。 慈覚大師は死後、比叡山から日光に飛び、そして山形県の山寺に飛んだ…という伝説もあるとか。三仏堂はその慈覚大師が建立。現在のものは家光が新しく建てたもの。本尊は8mもある巨大なものです。《阿弥陀如来》=《滝尾神社》=女峰山権現(弁才天)《千手観音》=《新宮》=男体山権現(大黒天)《馬頭観音》=《本宮》=太郎山権現(毘沙門天)真言は各仏尊の真言があてられ、また三所権現総真言として『オン バサラタラマキリク ラジャキリ ソワカ』がありまする。修学旅行で来た時には《東照宮》しかまわりませんでしたので、なんと初参拝意外によかったですまだ小雨は降り止みませんが、傘はささずテクテクN氏東照宮参拝中…私は歩き疲れたので外で五重塔と遊んでおりましたほほほ…また雨がちょいと強くなったよ多分今頃中で参拝してるんじゃろな~o(^-^)o
2008.05.28
コメント(0)
-
十人十食
種をまいておいたバジルがすくすくと育ってまいりました《園芸ミニ知識》トマトの苗の間にバジルを植えておくと…トマトが美味しく実ります去年試してみたら本当でした~(^O^)/今年もそうする予定ですo(^-^)oトマトとバジル…畑でも仲良しなのね …で、畑を開けて次の作物を植えるため、蚕豆さんたちの片づけをしましたらほよよ…意外にたくさん残っているぞな…(¨;)母様より『友人知人お世話になった方たちに送ったげなさい』と指令が下りましたので…昨日、あっちやこっちやそっちに今年最後の蚕豆さんたちを献上させていただいたところ…早くもびっくりの報告が~O(≧∇≦)o『去年は全部茹でて食べましたが…今年はさやごと焼いてみました』ひょえ~そんな食べ方があったとはわたしゃ知りませんでしたよ…蚕豆といえば、茹でるか、かき揚げか、甘く煮るか…だと思っておりました。『サヤごと網で焼いたら、サヤの中で蒸されたようになって、水っぽくならず茹でたよりも良い…』とのこと…よっしゃo(^-^)oいいこと聞いた早速やってみよう写真は蚕豆と海老のかき揚げと、タラの芽の天麩羅、胡麻入り素麺です 前に『鯛せんべい』というお菓子を差し上げた方は、砕いてサラダにかけて食べたそうですし…切り花として菜の花をさしあげたら、味噌汁に入れたという方もいらっしゃいましたし…(菜の花食べるけど…あんなに花が開いたものは食べないものだと思ってました…f^_^;)お風呂に入れる用に柚子を送ったら、皮を乾燥させて柚子胡椒を自分で作っちゃった話もありました人にさしあげると意外なフィードバックが帰ってきて楽しい~これまでの枠がとっぱらわれて可能性がどわ~っと広がるような気分になりまする~ 今日はAma-laさんのところから来てくれたお塩を使っておこわを炊いてみましたふんわりしっとりとして…うまうまでした韓国のお塩なのですが…ミネラルたっぷりで、嘗めるとすう~っと清らかな味がします一瞬、天に昇りそうな気分になりました(゚▽゚)羽衣みたいなお塩だな~と思いました。
2008.05.26
コメント(6)
-
天海と東照大権現~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
左上…家光墓所《大猷院》右上…慈眼大師天海の墓《慈眼堂》左下…四本龍寺の《紫雲石》右下…《日光二荒山神社新宮》楼門 さて…大猷院に到着すんばらしいです(建物は)家光くんの位牌がありました。向こうはあったかい空気全開で大歓迎~~(^O^)/だったのですが…(-.-;)…小言の一つもぶつけたくなるような坊主の低俗っぷりにウゲゲゲゲま、いいや…人間には用はないし興味もなし…丸無視すれば足りること…よっしo(^-^)oさて、次 天海さんのお墓《慈眼堂》へは大猷院の入口で拝観料を払います。300円法華堂と常行堂の間を抜けて石段を上ります。(二社一寺共通拝観券1000円では入れません)急げ急げ~ゴロゴロ~の後、うっすら曇ってまいりましたし、時間が押しておりますので…それそれ急げ到着してみると…予想外に素敵な空間でした。天海らしい質素なお堂とお墓。周囲を囲む六部天もみんなニッコニコでとろけそうな笑顔…にびっくり仰天(☆_☆)へっ~天海さんの歓迎は全く期待しておりませんでしたので…こちらは肩透かしのあまりずっこけちまいました…f^_^;《慈眼大師御遺訓》人馬を得、武具を用意し、役儀を欠けまじとおもはば美麗を好まず、無用の費をなさず、正に倹約を守るべし、仕方は唯わが身不自由を堪忍するに在ると知るべし。事たればたるにまかせて事たらず、たらす事たる身こそ安けれ。仁過ればよわくなる。義すぐればかたくなる。礼すぐればへつらいとなる。智過ればうそをつく、信すぐれば損をする。気はながく、つとめはかたく、色うすく、食ほそうしてこころひろかれ大僧正天海~慈眼大師遺訓より~そのまんまのお墓でした結構気にいったのでちょいと長居をしてしまいました正直なところ…二社一寺はもういいけどこの慈眼堂にはぜひ何度でも来たいぞと感じました さて次《日光二荒山神社新宮》一般に二荒山神社と思われているのがこの新宮ですここは…大国たんが主役この日は『大黒祭り』の日でもあり、境内に到着すると和太鼓の演奏が始まりましたデンドコ、デンドコ、デンデン、デンドコ…カラッ、カンお~~カッコエエ~~しかし…先を急ぎますのでここはサクッと参拝して…と思ったらそうもいかず、御朱印に時間がかかるとのこと…暇を持て余し、出店で焼きそば買って食べたりしてましたf^_^;境内では龍の画の実演販売もやっておりました\^o^/すんごいカッコイイ画です日光独特の《一筆龍》という特別な技法で、あっという間に目の前に龍が生まれます興味のある方は《一筆龍・晄秋家》で調べてみて下さいませ~(^O^)/この時は見るだけでしたが、秋には一枚購入しました(#^.^#)ちなみに《一筆龍》は東武日光駅前にもう一軒あります(こちらは女性が書いていらっしゃいます)せっかくの祭の日ですので、社務所で販売していた大国たんの画(確か500円)を購入してみましたここの大国たんは俵の上に乗っかって、おいでおいでをしています通称《招きだいこく》それにしても…初めて来た時に比べたら大分よくなったよな~新宮以前はヒュードロドロ~でした 次は大ボスの東照宮へ…天台宗は《星の宗教》でもあります。灌頂に際しては魂の故郷が金星もしくは北極星にあり、そこへ帰るのだと教えられるそうです。細かいことはともかく…東照宮はよく知られているとおり北極星のパワーを取り込む構造になっております。陽明門前の写真屋さんの前あたりが強い…という説がありましたが…全然(-.-;)ま、いっか第二の目的地、奥の院へ向かいます。《眠り猫》をくぐり階段を登ってゆきます。陽明門に着いた頃からさらさら細く降り始めた雨…ん~~なんとかよろしく頼むよ~降ってもよいけど、回れる程度にしといておくれ~いつものことながら傘持ってきてないし…。大国たんの画濡らしたら怒るかんね~と、空に向けて思いつつ登っていると…そこへメールが一通やってきたその途端雨がパラパラとやや強く降り始めました…
2008.05.22
コメント(4)
-
日光二荒山神社別宮・滝尾神社~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
《日光二荒山神社別宮・滝尾神社》祭神は、本宮、新宮と同じ…豊城入彦命・田心姫命・大己貴命ですが、ここは日光三山の一つ女峰山の遥拝所としての機能が強く、主役は田心姫命。弁ちゃん三姉妹の一柱ですしか~し…異説もありまして、もしかしたら古くは『高志沼河姫命』だったのではという説もあります。こちらは魚沼の翡翠の女神様です(田心姫命も高志沼河姫命も、どっちも大国たんの奥さんってとこがポイントだな)弘法大師空海が開いた霊場として伝わっておりまする 橋を渡り白糸滝の脇の階段をかなり登ります。これがまた次元変動の激しい階段で、ちょっとした洗礼を受けまする。距離も高さもわりにあるけど…そのせいじゃないだろこれ…ていう俗気削ぎ落しゾーンがございます…(*_*)めんどくさそうだぞ…と敏感に察知した方は白糸滝だけ見て帰っちゃったりしてましたが…登りきってしまえばスッキリ軽やか~になるのでめげずに登ってみて下され 空海が修行した場所には梵字の石碑がありました少し歩くと石の鳥居がございますこの鳥居…旅番組で何度か紹介されて有名になりましたが…石を三つ投げて穴を通った数で運をはかるという《運試しの鳥居》です。やってみましたとも一投目……スカ!鳥居にカスリもしなけりゃ届きもしない(O_O)(T_T)いいもんもうてきとお~に投げてやる二投目……へっと、通っちゃったよ(☆_☆)うほ~三投目……カツーンと鳥居に当たって跳ね返るも、二個目に入った思いがけない嬉しさは変わらず《てきとお~に投げた時が大当り》って…私の人生そのまんまな気もするんですが…f^_^; 写真左上…滝尾神社楼門右上…空海修行場所および女神示現の場所にある梵字石左下…この日の太陽右下…子種石 本殿に参拝。本殿は女峰山を遥拝する為に裏戸が開く特別な作りになっているらしい。本殿脇には《縁結びの笹》がありますさらに裏にまわって、小さい石の橋を牛歩で渡ります(自分の年齢と同じ数の歩数で渡るべし…だそうな)石橋を渡ると神木とされる三本杉があります。石の囲いの中に三本立っておりまする。倒れてもそのままにしておくのだそうで…今は何代目だったかの三本杉だとか…ん…なるほどここと女峰山を繋げばよいのだなさて…どうしよう…(^^ゞとりあえず『大祓』でもあげておくかと、祝詞奏上を始めると…背後に誰かいらっしゃいました。ご用の時はたいてい一人きりになるのに珍しいな…神木の向こうにも誰かいらっしゃるようだし…後の予定も詰まっておりますので…気にせず続行~大祓の後、三本杉を通して女峰山山頂に意識を飛ばすと…ゴロゴロ…ゴロゴロ…雷音が来た……(-.-;)あの~こんな簡単でいいんですかま、いいか…はいここは終わりと、一礼し、背後にいらした方に場を譲ろうと振り返ると…そこには、美しい外国人女性が蓮華座を組んで法界定印を結び、にっこり微笑んでおりました(゜▽゜)中東系のエキゾチックな美女で…目が合った瞬間なぜか、『マリア様だ』と思いましたもしかして…この方は呼ばれてここへ来たのかも三本杉の裏へ廻ってどうなっているのか見ようと歩いてゆくと…向こうから背の高い外国人男性が歩いてまいりました。あ~さっき裏にいたのはこの人か~と会釈すると…目の奥行きの深い精神鍛練の行き届いた…イエス様を感じさせる方でした…なんだろこの符合は…神橋の前に一つキリスト教の教会にも寄ってご挨拶してきたんだよな~私(西参道の真光教会)とにもかくにもありがとうございましたm(__)m心の中でお二人に頭を下げてその場所を離れました。なんとなく、助けてもらったような気がするので… 河の側にある御神水の湧く池にご挨拶お酒の味がするとかしないとかの霊水で、酒造業者の篤い信仰を得ているのだとか飲んでみたいけれど…柵に囲まれ、入口は施錠されておりましたので断念河を渡ります。Oさんが前年の初冬に訪れた際、龍を入れたのはここだなと感じたのが『子種』をもたらすという石その脇の泥道が気になるので登ってゆき、そこにあった大きな木がピカピカしていましたので、抱き着いたりほお擦りしたりして愛でてきました(#^.^#)さてこんなもんでいいかなと来た道を戻りかけると…先程のマリア様な女性が三本杉をびっくりしたように目を開いて見つめておりました口を手で押さえ、固まっちゃったように…ぽか~んなにか神秘体験があったのかな 白糸滝そばまで戻り、水の女神である《水波能女神》を祀る神社にもご挨拶ここ…清らかで素敵なバイブレーションです さて…『大小べんきんぜい』の碑まで戻り、今度は山を越えて徳川家光公の墓所《大猷院》に向かいます。途中寄った《行者堂》では役行者さんが待っておりました行者堂脇は女峰山登山口になっていますん…登った方がよいかしらでも今回時間ないし…(看板を読むとかなり時間がかかりそうな様子)役行者さんにお尋ねすると…登るのは私の役目ではないようなので…よかった~しかし、行者堂の階段も短いのになかなかハード階段の途中でちょいと休暇近くではおにぎり食べてるハイカーもいらっしゃいます(^O^)なんとなくのんびりしたい気分になる行者堂周辺です
2008.05.20
コメント(2)
-
日光水の聖地…白糸滝と三本杉~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
聖域を巡る旅は、《夏休みの宿題》のようなものだよな~といろいろ考えているうちに思いいたりましたやんなきゃいけない気がするし、喜んでやる訳ではないのだけれど、やってるうちにけっこうハマってしまうとこなんてとくに…(^^ゞ夏休みの宿題は、夏休みに入る前に終わらせてしまうのが常でしたで、余った時間で終わってない子の分を手伝ってましたf^_^;あとは力いっぱい遊んでましたけどねo(^-^)o さて、お宿を出て近くの安良沢バス停所に行くと…次のバスは40分後はいわかりました…ずるしようとしてすいません…歩いてまわらせていただきまする。 テック、テック、テク…田母沢御用邸を過ぎ、途中で出会とた小さな神社にかたっぱしから挨拶してまわりました。どれも凄い社はボロボロだけど中身がとんでもないんですけど…八幡神社では先行させておいた存在とも再会。 神橋に到着~深沙大王さんにご挨拶m(__)m頑張りますのでどうぞよろしく~♪先を急ぎます… 太郎杉を触ってからすぐそばの…《二荒山神社本宮》へ参拝ここは日光三柱の神の中でも、下毛野開拓の祖:豊城入彦命の存在感がとっても強い 裏の《四本龍寺観音堂》へ向かいますと…なにやら三重塔の近くがシャワシャワちらちらしています近付いてみると《紫雲石》なるものがありました日光開山の勝道上人が深沙大王の助けにより川を渡り、最初に建てたのがこの《四本龍寺》そこで祈っているとこの《紫雲石》から紫雲が沸き起こり男体山へと流れていったらしい…ふうんさて、次 二社一寺は観光客の皆様にお任せして私は先に行者道を進みます。日光世界遺産登録をきっかけに、勝道上人ゆかりの修験道の聖地としての史跡も見直され、今はそれを巡る道が整備されておりますo(^-^)o便利で有り難いけど…作りたてなのか歩きにくいよ~(>_<)ゴツゴツの石が並んでいて、足元をしっかり見て歩かないと怖いくらい…。(秋には道はこなれて少し歩きやすくなっておりました)勝道上人墓所前に立つ《開山堂》ほかにも立ち寄ってご挨拶m(__)mここは崖の下にあたり、崖の上には徳川家康公墓所である《奥社御宝塔》があります。もとは勝道上人が眠る墓所であったのを、勝道上人を移動させて家康墓所にした…とのこと。ん~そこまでするか~普通。 開山堂では山伏さんに遭遇車で乗りつけて、一人の女性の為に祈祷を初めました。ふと空を見上げると太陽に虹の輪がかかっておりました。さて、勝道さん次行くよ~ 隣の北野神社にもご挨拶菅さん見るとすんごく嬉しくなっちゃって、無茶苦茶元気が湧いてきますo(^-^)oやれそうな気がしてきたぞヨシッ 田心姫が手をかけたという《手掛石》に触り…(字が上手になるとか)《神馬の碑》や《飯盛杉》にもご挨拶《大小べんきんぜいの碑》に着きました(^O^)/日光の中でも特別な聖域として崇められてきたこの奥にある二荒山神社別宮《滝尾神社》…ここから先は聖地であるため用をたすことは昔から固く禁じられてきたのだとか その碑を過ぎてしばらく行くと白糸滝に着きます第一の目的地に到着~\^o^/この滝のそばで弘法大師空海が修行し、女神の出現を得たといわれています白糸滝のそば(橋を渡らず滝近くまで歩いていった左手)にある三本杉です特になにかした訳ではないのに…だんだん降りてきました(ぽけら~っと見てただけだよな…確か…(-_-))関東でも三指に入る強力なスポットと伺っておりましたが…ナルホド
2008.05.19
コメント(0)
-
鳳凰美田…そしてベッドで私も考えた~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
お宿は『森のうた』というペンション風のかわいいところでした(^O^)/いきなり当日予約してポンと泊まったのですが…大当り~\^o^/すっかり気に入ってしまい、今となっては日光の常宿~なにより食事が凄いラストのデザートにしてこれですよ~前菜のプレートから有機栽培の野菜をシンプルに料理してあり、お野菜の味が濃くてびっくりしました普段自家製の美味しくて新鮮なお野菜をいただいている私が…ムムム…とちょいと悔しくなる程…(>_<)赤米のご飯も嬉しいし、日光でぜひ食べたかった湯葉料理も一品ついていて~古代史好き現地のおいしいもの大好きな私はニッコニコお肉もジビエ好きな人なら泣いて喜ぶようなしっかりとした味絶品でした命がぎゅっと詰まったような、そして優しい地球の味がいたしましたデザートも地の果物や牛乳、チーズをふんだんに使っているようです。口に入れると、草露の薫りを含んだ草原の風が吹いてくるような~~(゚▽゚)『大切な人を連れてまたきたいな~』と思いながら一人でのんびりディナーを楽しみました(好き嫌いのある人は駄目だな…)他のお客様は…この日は年配のシックなご夫婦が何組かいらっしゃいました…で、大切な人で浮かぶのはまず『両親』なのですが…f^_^;いつか本当に二人を連れて来てあげたいよ~(結局秋に、妹と私で行っちゃったのですが) ディナーの時にいただいたのが《鳳凰美田》という日本酒金賞を取った逸品ということで、興味が湧いて注文し、一口飲んでみると…日本酒なのにマスカットの香りと味が~(゚▽゚)なんでなんでなんで日本酒これ~でも…うま~(#^.^#)淡い金色のお酒です 因みにこの時は…一泊二食付き(ディナーはハーフコース)+高価なお酒を二杯飲んで、貸し切り岩風呂入り放題…で一万円でお釣りがきちゃいました\^o^/いいとこ見つけた~去年秋の日記にもアップしてありますが…朝は焼きたてクロワッサンと手づくりハム、搾りたてミルクに手づくり苺ジャムの朝ご飯がつきまする♪あ~また行きたい 月は満月をちょい過ぎて、十八夜くらいの月。深夜、庭に(こっそり)出てここでも瞑想~神橋を渡ったこちら側の日光は、聖域のこゆいバイブレーションに満ちているようで、そのせいか頭の中心から光が溢れ出すようで…眠れないよ~f^_^;ま、眠れない時は寝ないに限る。(人間一週間までなら寝なくても死なないらしいから…)お部屋に戻っても眠気が起きないので…ベッドの上で蓮華座組んで…考え事~考えるは明日のこと…今回の日光での高い目的の確認と優先すべきことと手順を整理して…と考えてみても、実際その場に行かないとはっきりしないしな…う~ん思いは、天海が日光東照宮に施した諸々に至り…天台の玄旨帰命壇と摩多羅神~阿弥陀~一字金輪~北辰~山王一実神道と称して…も~o(><)o~天海のじいちゃんってば~……(-.-;)文句たれるのは時間の無駄だな…前に進もう 「私はなんで一人でこんなとこでこんなことしてんだろ」とまたもや疑問が湧いてきてしまいました…誰かに指示命令された訳ではないけれど、嬉々として来た訳でもない…。こんなことしたって一銭の得にもならなければ、誰かに褒められる訳でもなし…仕事上なにかプラスになればいいけど、なんもならんしな~(*_*)ん~~でも日光の恵みが凝縮された、とっても美味しいものをいただけたのでそれは嬉しいぞここに居る理由をしいてあげれば…出羽三山踏破の後、『他の人でも可能なことを私がやる必要がはたしてあるのだろうか』と感じ…既に楽しく感じることが出来なくなっていた《人を助ける》活動をスパッと止めて手放し、方向転換した…んだよな…『もう個別に助けるのはやめた自分の能力を最大限に生かし、自分にしかできない形で全体に貢献する』…ってやつに…(^^ゞそれか…で、日光で天海ですかいな~(T_T)ん~~~(>_<)しかし世の中には本気で日本や地球のカルマを解いてまわっている方たちがたくさんいらっしゃるしな~無償で嬉々として自分の道を邁進されている方も知っているが…(どうもそういう人は表には出たがらないし…自分がどれほどのことをしたのか自分から宣伝しない傾向が強いようだ…アテはここに書いている時点で既に見栄坊丸出しです…)褒められなくてもよいけれど…どうせなら私も無茶苦茶楽しい道でありたいぞよにままた変更しようそうしよう~楽しい道を突き進むぞ~
2008.05.17
コメント(0)
-
『インカの目覚め』
収穫したジャガ芋~これが『インカの目覚め』です母様いわく…かわいい名前でしょ…だそうです。源種に近い黄色でギュウッと力の詰まったおジャガさんで、触感はもっちりむっちりしています(昨日肉じゃがにしてみました)でも今回は不作…ちっこくて実付きが少ないんです…。左上が『インカの目覚め』左下が、ジャガ芋の花(これは『きたあかり』という種類の花。右下がジャーマンカモミール。右上は収穫したカモミールの花。これを乾燥させてお茶か化粧水にしようと思っています…もしかして、乾燥したジャーマンカモミール欲しい方っていらっしゃいます乾燥し上がるのは来週ですが、80円の切手一枚で送れる量でよろしければプレゼントいたしますよ~希望者は御一報下さいませ
2008.05.16
コメント(4)
-
大日堂跡から憾満ケ淵~'07,あらたうと青葉若葉の日光めぐり~
今度は去年の六月にまわった日光のお話… ある日、友人のOさんに…『猿が呼びに来たのでいよいよ日光に行ってきま~す♪』と事情を知らない人には意味不明な一通のメールを残し、一人日光へ向けて旅立ちました(そんなに遠くはないけど)まず向かったのは宇都宮市にある栃木県立博物館。何故かこの時は宇都宮まで新幹線でビューンと一気に行ってしまった私。いつものケチケチ旅行とは打って変わって太っ腹いやあ~少しでも早く円仁さんに会いたくってさあこの時、栃木県立博物館では『円仁とその名宝展』が行われておりました。薔薇の彩る庭園を抜けて博物館へ到着してみますと…小雨の中びっくりするほど大勢の方が来館しておりましたうれしいな館内には国宝をはじめとする慈覚大師円仁ゆかりの品々が沢山膨大な展示物を一つずつ丹念に見てまわりました。(三時間以上かかりましたが…)円仁は…って説明始めると止まらなくなりますので、頑張って短めにいたしますf^_^;《慈覚大師円仁》天台宗を大成させた山門派の大徳です。九年にわたる入唐求法の旅により、五台山、長安に師を尋ね、天台円教のみならず最澄の欠を補完すべく密教も学び、胎蔵金剛両大法に加え、空海も伝えなかった蘇悉地大法も受け日本に伝えることとなりました。請来した教典、仏像、曼陀羅、仏具は夥しい数にのぼり、その後の日本の音楽に多大な影響を与えたと言われる天台声明を伝えたのも円仁です。帰国後、第三代天台座主となり興隆に尽くしました。遷化の後、日本で初の大師号を贈られました。 会場内には日光山で慈眼大師天海が修法に用いた『熾盛光曼陀羅図』がありましたうおっしゃ~~o(^-^)o幸先いいぞぉ勇気百倍その前でちょっくらまったりいろいろと…入山前にガツン 大倉集古館の普賢菩薩像とも再会(以前チベット密教展の時に東京でお会いしました)国宝にして日本最高の普賢像とのこと会場で仲良くなった仏像彫刻がご趣味という素敵なマダムとお話しながら駅に向かいました。 宇都宮からJR線で日光に到着もう夕方で、日も落ちかけておりましたのでお宿に向かいました夕食前にどうしても散歩したかったので、ふらりと出かけようとすると、お宿の方が…「すぐ下にある《大日堂跡》が素敵ですよ」と近道を教えて下さいましたので下りてみると…(☆_☆)はひゃ~これまた凄い浄域がひっそりとこんなところにあったものだと、びっくりするような空間が現れました現在は跡を残すのみで何もありませんが…かつては瑞巌寺のように川(中禅寺湖から神橋へと流れる大谷川)の中に浮御堂があったのだとか。明治天皇が休憩した場所でもあるとのこと。清らか~な水気の中でしばらく瞑想させてもらいましたちょっと離れたところに咲く藤の下には…べったりうっとりラブラブモード全開のカップルがおりましたので…う~んうらやましい~(ノ><)ノいや…そうじゃなくてお邪魔にならないよう彼らから見えない位置まで川淵に下りて…ゆっくり瞑想~(¨;) 写真ではまだ明るいように写っておりますが…もうかなり薄暗い状態の中、頑張って橋を渡って600mほど行ったところにある《化け地蔵と憾満ケ淵》にも行ってみましたo(^-^)o薄暮の中で肉眼では先がよく見えないくらいでしたのに(既に6時近くでした)、写真では明るく写っていてびっくりしました写真左下…《神橋》右下…《大日堂跡》左上…《化け地蔵》右上…《憾満ケ淵と憾満の滝》 薄暗い中をこんな風に石像が百ほど並ぶ道を一人で歩いていたのに、ちっとも怖く感じなかったんです。うまく表現できないのですが…予想外の大歓迎を受けているような不思議な気分になりました。日光に来るにあたっては、目的が目的であるため当初厳しい状況になることを覚悟して乗り込んだのですが……あれもしかして、そんな意気込まなくても器に撤してればオートでうまくいくのかもそんじゃあ気楽に流れに身を任せてみようかしらふう~。肩の力抜いて…あとは天にお任せしちゃえ~(^O^)/
2008.05.16
コメント(2)
-
たんぼ
我が家のたんぼこれからすくすく伸びてゆきますよ~オタマジャクシが泳いでいました右手向こうに蚕豆畑が見えますね~ 《香りの話》みかんの花や薔薇の花がよい香りを漂わせておりますが…岡一つ越えたところにある近所の家では敷地の隅に牛の糞を大量に積み上げております。堆肥にするのか、時々それを掻き混ぜるものですから近所では勿論不評。そんなある日、隣の家のお兄さんが畑で草を集めて火燃しをしておりましたところ…牛の糞を積み上げている家が役所に連絡してしまいました。『煙りが家に向かって流れてきて迷惑』とのこと。ははは…。『牛の糞の臭いの方が迷惑だ…といつか言ってやる』と息巻いていらっしゃる方も近くにおりますが…f^_^;この話から得た私の教訓は『人の迷惑を考えよう』ではなく…『よい香りに喜ぶのも、不快な臭いにぷんぷんするのも、結局は人間のエゴなんだな~』…てことです。綺麗なものが好きな人は汚いものに攻撃的になりがち…快適さを求める人は不快なものに批判的になりやすい…幸福を感じる基準を外の物に委ねると(香、味、景色、音)こんどはそれらに依存し振り回されることになります。しばしば人はこれに陥りがちですが…幸福を感じるには幸福であればよく、そこに介在すべきものは本来なにもありません。昔の聖者に《糞尿が大光明を放っているのが悟りの境地》と言った方がいるそうですが…そゆことだよな、と納得してしまいました私は…というと、以前はよい香りに包まれて快適に暮らそうといろいろしてきましたが…やっぱり同じとこに陥りましたf^_^;おもしろいことに、よい香りに意識を向けるほど不快な香りに敏感になるんです。そうすると今度は不快な香りが気になって、さらに不快感が増してゆき、その発信源に向けて自分の中から嫌悪感と批判的精神が生まれ……ま…ひとしきりぐるっと経験してみましたよ…で、《よい香りの中でしか生きてゆけない》という脆弱な心と身体を作り上げようとする不自然なことはもうやめてしまいました(^O^)/勿論今でもよい香りは大好きですし…香水はず~っと《ROMANCE》を愛用しています(あ…今切れてるわ…)牛の糞の香りがしてくると…『よい堆肥になって美味しい野菜や美しい薔薇を咲かせてね~』と思えるようになりました牛の堆肥は薔薇の色を美しくする為に有効なすばらしい肥料です。園芸をされている方はご存じかと思いますが…化学肥料では叶わない力を堆肥は持っています。(土をフカフカにしてくれますし)『牛さん素敵な肥料をくれてありがとう(^O^)/』と、そばをとおるたびに思います(こう思えるようになったのは薔薇のおかげだな~育ててよかった~)牛の糞の臭いと煙りのモクモクでぷんぷんしている人々にこの考えを押し付ける気はさらさらなく…ただ…私自身はそういうものに左右されないようになりたいな…と、思いました。 さて、近所からくるあらゆる迷惑な事象に対して、それでは黙って我慢しろていうのかいというと、そうではありません困ったことは《はっきりと》伝えるべきただし、怒りや不満のエネルギーを溜め込む前に…早い段階に相手にも事情のあることをこちらも理解していることを前面に出し、穏やかにお願いすれば、譲歩して下さるケースがほとんどです。この場合ですと、牛の糞を積み上げる場所を変えてくれるとか、風が煙りをそちらの家へ運ばない位置で火燃しをするとか…譲り合ってお互い納得できる余地が簡単に見つかるのは…初期の段階です。《言わなくても分かるはず》という期待がえてして泥沼の感情的対立へと発展してゆきます。して欲しいことがあるなら、明確に表現して下さい。表現もせずに結果を期待するのは無理というもの…(あれだんだん違う領域の話に入ってしまいましたまあいいか…) ついでなので昔話を…鑑定および指導の仕事をさせていただいていた頃、クライアントとして多かった人々は…占術家、各種ヒーラー、霊能者、精神科医、宗教家…など実に半数近く、《プロ》の方たちがいらして下さっておりました。その方たちの相談の99%がコミュニケーションに関するものだったのは非常に興味深いところです。この際だから《はっきり》云うぞ~問題の多くは《相手と向き合って、直接自分の要求や期待を素直に伝えること》を避けて、スピリチュアルの世界に逃避している…ただそれだけのことです。《素直に伝える》たったそれだけであっという間に問題は解決し、その日からすっきりハッピーになるものを…その世界のプロである故か自分のメソッドに固執して、それを使ってなんとか状況を動かそうとしてみなさま停滞しておりましたf^_^; 勇気を出して《自分の想いを自分で相手に伝える》ことができた方は前進してよい結果を得ることができておりました恋愛においても、仕事上の人間関係においても…勇気を振り絞るまでにかかった時間はそれぞれではありましたが さて、これからグリーンピースを収穫してきますo(^-^)o今年は蚕豆は数が少なめですが、グリーンピースは豊作です収穫が追い付かないほど
2008.05.14
コメント(3)
-
すべての道がインドへ…
近江阿育王山石塔寺について調べているうちにおもしろい話がわんさと出てきましたo(^-^)o南房総石堂寺にあるアショーカ王の石塔(水晶製)は石堂寺のパンフレットでその姿を拝見することはできます…が、実物は秘宝の為、拝見はできませぬ同じくアショーカ王の石塔を祀るという阿育王山の方はどんなじゃろと調べてみると…日本最古といわれる大きな石塔があるらしい…。インドから飛んで来たものが一条天皇の霊夢により発見された…とか、インド人が建てた…などと言われているのだとかもう一つの石塔寺と云われた上州白雲山は、現在妙義神社となっており、アショーカ王の石塔があるのかどうかは不明です。しかし、今年行くつもりの荒船山について、この際ついでに調べてみると…インドから空飛ぶ船に乗ってやってきた絶世の美女神様とタケミナカ神にまつわるの伝説があるとのこと…う~む。神話の国譲りの段で、タケミナカ神が荒船山に陣取り、経津主命と戦った話は存じ上げておりましたが…ここもやっぱり元は女神様でしたかしかもインドの女神様。男体山といい、大宮氷川神社といい、神田明神といい…元は女神であったというところが多いよな…あとは…那珂湊に強力な女神様がいらしたら個人的に完璧なんですがおいおい調べてみよう あと、ひょいとひっかかってきたものには…南インドのタミル語が日本語の語源ではないかとの説が…(☆_☆)(トルコやモンゴルとの類似は既に定説ですが…タミル語は知らなかった…因みに日本語は他の言語と全く違う部分の脳細胞とパルスを使う特殊な言語なのだそうで、六歳までに音のシャワーによって日本語を基本言語として習得した脳と後から学んだ脳とでは機能が大きく違ってくるのだそうです…日本人独特の色彩感覚や音への繊細さはどうも日本語という言語に由来しているようです…人種よりも言語が大切で、幼い頃から日本語をメインにして育った場合、同じ脳機能になるそうです大学時代にこれを知った私は日本語の文語体の詩や古典文学への傾倒にさらに拍車がかかりましたが)南インド…ババジの生誕地でもありますし、昔から無茶苦茶親しみのわく地域なんですけれど(行ったことないけどf^_^;)言語や血の繋がりからくるものもあるのかしら那智の滝はインド人の裸形上人が開いた霊場ですし…。(ゆえに修験道の自然崇拝思想はインドのサドゥから直接たまわったものではないかという可能性を指摘する声も…)う~ん…インドに行きたい…という欲求はなぜか湧いてこないのですが…大好きな日本の文化の中にインド的なものを見つけると…うっほっほ~…とうれしさで血が沸き立つような気分になるのは、なんでかね~(#^.^#) そうそう、高野山出身のお坊様が修行中に体験した倍音読経についてもおもしろいものでしたJCBホールで体験した法悦としか思えない感動的なライブもこれだ~と納得みなの読経の声とリズムがぴたりと合った時、共鳴作用で誰も発していないはずの倍音の音が現れ、うっとり…となることがあるというお話(『住職のひとりごと』というblogですので興味のある方は探してみて下さい) 今日は(も)まとまりのない話になってしまいましたこんなマニアックでとりとめのない話をいつも読んで下さってありがとうございますm(__)m私の日記が、縁あって読んで下さる皆様の暇つぶしや何かのきっかけになりましたら幸いです
2008.05.13
コメント(2)
-
みかんの花
甘夏の花が沢山咲いています(^O^)/ほかのみかん類の木は、今年は花づきが少なめですのに、この木だけはた~っぷり。よい香りこのところ妙な感覚が続いております片付けるべき問題や心配すべきネタはあるにもかかわらず…あったか~い満たされたようなのんびりした気分なんだろこれ
2008.05.12
コメント(0)
-
善福寺と飛鳥鍋~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~
ここで、今回大変お世話になった善福寺さんについてアップしておきますね紀伊半島一周の旅の際、ご縁をいただいていろいろとお世話になるようになりましたm(__)m《善福寺(高野山真言宗)と井光井戸》善福寺の創立は不詳。(院主さんによると天海さんが建てた寺院とのことです。江戸幕府創立時、一大勢力であった吉野山金峯山寺衆人を抑えるため天海が吉野に遣わされた記録がありますから、その時に拠点として建てたのかも)葬儀を行わず祈祷を旨とする修験道寺院が多い吉野山にあって、江戸時代の初期から吉野山の住民の菩提寺として存在していたと思われます。修験道との関わりも深く、本堂内には蔵王権現や役行者像が安置されています。明治初年の廃仏毀釈神仏分離に際して、金峯山寺やその塔頭寺院が廃寺に追い込まれる中、廃寺の仏像を集めた諸仏堂(現桜本坊)の管理や、山上蔵王堂(現大峯山寺)における吉野山の権益を保つために、当時の住職川勝教嶽が活躍したことが知られています。本堂の北側の谷間には、井光井戸といわれる小さな井戸跡があります。これは記紀に見える、神武天皇御東征の際、天皇をお迎えし案内したという吉野首の祖、井光(いひか)が出現した跡と伝えられています。~善福寺案内板より~本尊は薬師如来です。ほかには…私の知る限りでは十一面観音役行者お大師様三宝荒神 などが祀られ…千手観音真言宗高祖十二神将などの絵図が祀られていたかと… 本当に不思議な空間です広はありませんがのんびりしたくなるような癒しの気配に満ちていますつい惹かれてす~っと入っていってしまうような魅力と風情があります写真左下:道から見た善福寺入口。坂を少し下りたところにあります。左上:善福寺の入口。右下:緋牡丹の蕾と本堂(牡丹はもう終わったそうです)右上:室内から見た善福寺境内。美しい光があふれています さてここで…善福寺で教わった《飛鳥鍋》を紹介させていただきます昨日我が家でも試してみましたが…やっぱり美味しかったです~!(^^)!郷土料理なのだそうで、明日香あたりでは食べさせてくれるお店もあるようです《飛鳥鍋》材料牛乳: 500ml~1L和風だし(濃いめ):同量程度鳥肉(本来は大和地鶏を使う):食べたい分野菜いろいろ(白菜・ネギ・人参・茸ほか):同じく食べたい量をご用意くだされ冷凍うどん:人数分作り方1)和風だしをとります。善福寺では昆布だしでしたが、鰹だしでもよさそう2)鳥肉や野菜を食べやすく切っておきます3)鍋に半量程度の牛乳を入れ和風だしを加えながら温めます沸騰させないように注意。牛乳と和風だしが調和してなんともいえない美味しさになるように加減してくださいね好みで塩味を加えてもOK4)野菜と鳥肉、うどんを入れて煮込みます5)野菜からのだしが充分でたところで、まずスープだけを椀に注いで七味をふっていただいてみます…うま~6)あとはお好きにどんどんどうぞ特に和風だし+牛乳のスープで似た鳥肉の美味しさには目をみはるものがありました鳥肉の食べ方として一級品ですなんてハイカラな鍋なんだろうと思ったら、明日香地方に昔から伝わる郷土料理で、むか~しは牛乳ではなく山羊の乳で作ったのだそうです簡単ですのでよろしかったらお試しあれ~(^O^)/ 善福寺の院主さんは惜しみなく力を分け与えて下さいます。人々に安心を与えて、その人の人生が好転するのを見るのがこの上ない生き甲斐なんだそうです。(いや…写真もこの上ない生き甲斐なのでしょうけれど)院主さんのすばらしいところは…決して『自分が~をした』と驕らないところです全ての力は大日如来とお大師様から来るものとして、自分はその力を流す通路に過ぎないことを、遜って表現されます。すばらしい~『人々の為に役に立つこと』本当にそれしかないようです。尼様もまたしかり…なにやら聞くところによるとお二人の人柄に惚れ込んで、遠路はるばる訪れる方たちも大勢いらっしゃるのだとか…。さらに多くの方が縁を得て、院主さんと尼様の持つ深い慈悲のトーンに触れることができますようにm(__)m
2008.05.11
コメント(0)
-
八坂神社・京都駅~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~
懐かしいわ~サン・ホワ~ン~飯はいつも残飯~京都駅直結、京都劇場では『WEST SIDE STORY』が上演されているようでしたこの演目大~好きなんです(以前の自分ならご褒美にラストは観劇で〆たろうな~)特にアニタ達の掛け合いのシーン『AMERICA』が大好きで…プエ~~ルトリコ~う~つ~くしい~~と~こ~なつのし~ま~よ~~と始まると……来た来た来た~((o(^-^)o))と大興奮くわ~っやっぱり見てぇ~~(でもかつてのあの感動は味わえないだろうからな…いいや♪)『AMERICA』の次に好きなのがトニーの独唱『マリア』マリア~マリ~ア~マリア~とリフレインしながら歌いあげるところが…ぬっふっふ生~きることの、喜~びを知った~マ~リア『OH! クラプキ巡査!』も楽しいしな~はっ回想に心を持ってかれてる場合ではないぞよ知らない方には訳のわかんない話ですみませぬ。しかし…二つの対立するエネルギーの融合に向けての二つの流れ、『恋』と『流血』とをともに織り込んだこの作品を上演中とはなかなかに考えさせられるものがありまする。 さて、八坂神社に参拝久しぶりですが…そんな感じがしないな~源九郎稲荷にて、ポンと神泉苑が浮かびましたので…神泉苑と繋がる八坂さんにて〆ることにいたしました(^O^)/(神泉苑は義経と静御前が出会った場所といわれております)神泉苑…この時間(夜8時過ぎ)はもう閉まってますのでこれで許してくだされm(__)m ふと知恩院さんの方角にあやしい光がまっすぐに立ち上っているのを見つけ、行ってみると…青蓮院(でよかったかしら)の夜間特別拝観が行われており、それを彩るライトアップの一つでありました中には入らなかったけど…。 妙なルートを通って京都駅に戻りました(^O^)/途中まで歩いていたのですが、めんどくさくなって公共機関を使ってしまいましたがf^_^;京都駅到着~ふ~っ…これで完了 ご褒美に、グランヴィアのカフェに行って抹茶のケーキで…うま~(#^.^#)(大阪と京都ではグランヴィア、名古屋はアソシア内のカフェで休憩してから帰路につく変な癖がついてしまいました博多や札幌の時にはどこにも寄らないんだけどな~我ながら不思議)以前利用した時よりも店員さんの接客マナーが凄くよい感じになっていて驚きました前は、まあまあいいな~と感じた程度でしたが、今回は、痒い所に手が届く細やかな接客に嬉しくなりましたこちらが思う前に先手先手で気を配ってくださり、そしてほどよくほおっておいてもくれる…うわ~いこういう接客に出会うと疲れもふっとびます(^O^)/お兄さんやお姉さんたちの自然な笑顔に癒されましたし(#^.^#)(因みに『Le temps』というお店です)おかげで旅の疲れをすでに京都で落として帰ることができましたバンザ~イ\^o^/ 落としすぎて、帰りに寄ろうと予定していた静御前の墓に行く気がなくなってしまいましたが…f^_^;またの機会にいたします 余談…行きに桜の苗木を詰めてゴロゴロ引っ張っていたカートですが、帰りはからっぽになるかと思いきや…檜のお箸と葛の打ち菓子をどっさりいただいてしまい…やっぱりゴロゴロ引っ張って帰ることになりましたしかし…帰ってみれば吉野や明日香より寒いぞなぜだ頑張れ南房総 そして後日談ですが…某氏は先日檀之浦へ行ってきたそうな(O_O)平家の武将を『あなたは男の中の男だ』と讃えてきたのだそうで…その器の大きさに…う~ん、凄い方だ…と感銘を受けてしまいました私もこの次はもっと讃えてみよう(^O^)/と思いました
2008.05.11
コメント(0)
-
源九郎稲荷神社~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~
長谷駅に到着してみると…待っていたかのように電車が滑り込んでまいりました今、旨く流れに乗ってるなよかった~一人で旅をする時には、私は時刻表などは気にしないようにしていますそれでいつもうまくいってますo(^-^)oというか…考え方の問題で、例えば乗り換えの待ち時間が40分あった場合…『これは近くに寄った方がよい場所があるのかも』と探します。(たいていあります)で…一度改札を出てそこに行って帰ってくると、ちょうど電車が来たり…反対に思っていたよりも移動に時間がかかってしまい予定していた場所に寄れそうもない時には…『この予定は外してもいいものなのかも』とフレキシブルに予定変更~あんまり細かいことにこだわらず、流れに任せてしまっていますので、何処へ行っても楽しく過ごせまする さて…郡山にサクサクっと到着かわいい商店街ですその商店街を進んで右に曲がってゆくと、ほどなく源九郎稲荷神社に到着しました源九郎ちゃん来たよ~ん(^O^)/《源九郎稲荷神社》当社の祭神は宇迦之御魂神で、伊勢外宮、伏見稲荷大社の御主神と御同体です。日本三社稲荷の一つとされています。元は寛平稲荷といいました。天智天皇の白鳳年間、平群の真鳥が反逆を企て帝位を奪おうとした事件が起こりました。この時、大伴金道麿が勅命をたまわり征伐に出向きます。大伴金道麿が天地神明を念じ、特に寛平稲荷を祈って出陣すると、明神はたちまち武人と化し、数多の白狐を遣い、大敵真鳥を討ち平らげたのでした。また、武勇絶倫なりし源九郎判官義経は日頃深くこの明神を信仰し、神護によりしばしば奇異の戦功を著したことは人のよく知るところです。義経千本桜の狐忠信は、この源九郎稲荷の化身なのだそうです。義経は奥羽に下る際、崇敬と感謝を込めて訣別のあかしとして源九郎の名を贈ったのだとか。以降、源九郎稲荷と呼ばれるようになりました。『緋おどしを かたみに残す 源九郎』(古句)~源九郎稲荷略縁起より~これ…夕方6時頃なんですが、実際肉眼で見る景色よりも明るめに写っていますo(^-^)o今回はここを〆にして郡山でのんびりしてから夜京都にいけばいいやと考えていましたが…源九郎稲荷に参拝してみて…ちょっと閃いたので予定変更とっとと京都に向かうことにしました 何故稲荷さんが戦を助けるのかちょっと不思議ではありますが…なんと伊勢神宮にも戦勝の霊験話があるのだそうで…平将門征討の祈願をしたところ、正殿内で弓矢や甲冑を賜る声がしたり、二見浦から白馬に乗り甲冑に身を包んだ人々が海上を東へ進軍してゆく有様が目撃され、翌日将門は討たれたのだとか…。外宮は豊受姫さんですし、中世においては天之御中主神、国之常立尊と同体といわれたこともあるそうですし…妙見様や神功皇后…いろんなものがからんできますし…単純に考えると…稲の豊饒を司る神様なので、一粒を万倍にする勢いが戦にも作用するのかもな~特に畑や田んぼを荒らすような戦をする相手には黙ってられないのかも さて、無事参拝を済ませましたのでまた近鉄電車に乗って京都へGo
2008.05.11
コメント(0)
-
長谷山口坐神社~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《26》
長谷寺参道をさらに下ってゆきますと…ふと横を見た瞬間、橋と鳥居が目に入ってしまいました(☆_☆)やばい…甘い水に呼ばれてふらふら飛んでゆく蛍になった気分~え~い、いっちゃえ~~い橋は初瀬川にかかるもので、橋の上から眺める川景色はなかなか風流です。川を渡るってのは、それだけでもう清めの作用がありますし、異界に入ってゆくようでいいですな~渡ってみると…『元伊勢伝承地』を示すものが…なんですと~今回は(呼ばれているのはわかっておりましたが次回にまわし)参拝しませんでしたが、近くにある《飛鳥坐神社》は…天照大神を初めて宮中の外に祀った『倭笠縫邑』であるとの伝承があり、近世には元伊勢を称していたといういわれがあります。(その飛鳥坐神社の元社地とされる『雷岡』を通りました)『倭笠縫邑』については現在は大神神社の摂社である檜原神社が有力とされています(去年行きました)伊勢神宮の古名である『磯宮(いそのみや)』と石上神宮との関係を指摘する説もありますし…。そして《長谷山口坐神社》周辺は倭姫が八年間神を祀った地と伝えられ、それに関係した神社のようです…。う~ん面倒なので由緒は今回写真にて…でもなんだか核心を省いて詰め込んだような妙な文章ですが…。今の御祭神は大山祇さんと豊受姫さんのようです階段をたくさんのぼり疲れましたのでちょっとここで休憩させてもらいました(^O^)/小さいですが気持ちの良い境内でした
2008.05.10
コメント(0)
-
法起院~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《25》
『極楽はよそにはあらじわがこころ おなじ蓮のへだてやはある』これは法起院の御詠歌(西国三十三観音霊場を開いた徳道上人作)です。《極楽は遠くにあるものではありません。あなたの心の中に求めなさい。この世に咲く蓮の花と、あの世の蓮の花とはともに同じ蓮の花なのです》一方、四国八十八ケ所巡礼をお始めになった弘法大師様のお言葉に、『それ仏法はるかにあらずして心中に近し』という部分があります。共に、悩める人々を救うために求道の道を歩まれた両大徳のおっしゃらんとするところは、同じであったというところに、今さらながら驚嘆するものであります。 ~法起院パンフレットより~ 院主さんの強いお薦めもあって長谷寺参道途中にあるこちらにも寄って、ご朱印をいただくことにしました。長谷寺の参道は約1kmにわたって門前町をなし、お土産もの屋が軒を連ねております♪ふと、どなたの句であったか失念してしまいましたが…《草餅を焼く 天平の色に焼く》…という素敵な句を思い出しましたo(^-^)oあちこちで焼いた草餅が売られていて美味しそう(でも我慢)吉野葛や三輪素麺、山菜の佃煮や牡丹の苗木なども売られていました法起院を見つけました重みのある門構えです。水子供養用に赤い蝋燭があるのを見つけ、そうだと思い立ち、義経と静御前の息子さんに手向けることにしました頼朝の命により埋め殺されたのは由比ヶ浜ですが…吉野潜伏の時にはすでに宿っていたはずですから、またここで供養してもよいのかも…《法起院》西国三十三観音霊場を開いた徳道上人の廟所であり、西国三十三観音霊場の番外でもあります。徳道上人は観音信仰に篤く、大和の長谷寺、鎌倉の長谷寺をはじめ諸国に四十九ケ所の寺院を建立されました。大和の長谷寺に本尊大観音を御造立したのもこの方です。西国三十三観音霊場を開いた由縁はとっても不思議なお話です。養老二年(718年)の春、突然の病により上人は仮死状態にありました。この時上人は夢の中で閻魔大王にお会いになり、悩める人々を救う為に三十三ケ所の観音菩薩霊場を広めるように委嘱され、そして三十三の宝印を与えられて仮死状態から開放されました。上人は三十三ケ所の霊場を設けましたが、人々は上人の話を信用しなかったので、やむなく宝印を摂津中山寺にお埋めになったそうです。二百七十年後に、花山法皇がこの宝印を掘り出し、今の三十三ケ所を復興なさいました。法起院は上人が隠棲されたところであり、御廟の十三石塔がございます。上人は晩年当院の松の木から、法起菩薩と化し去ったといわれ、当院の名前もそこからつけられました。~法起院パンフレット・巡礼のふる里から~
2008.05.09
コメント(0)
-
今日のこと~
ゴールデンウイークは田植えで終わりました今年は妙に苗が愛おしい~ひと掴みずつ撫でるような気持ちで植えつぎしてゆきました きょうは…なんとなく思いたって日蓮くんの石碑の前に遊びに行きました。帰ってからは、チューリップとヒヤシンスとフリージアの球根を掘り起こし、陰干しにする作業を一気に実行(^O^)/それから、さくらんぼの収穫今年は烏に取られず、たくさん収穫できましたので、ジャムやコンポートも作れそうですo(^-^)o右上がさくらんぼ左下が咲きはじめた薔薇の花たち左上が玄関前の『アリラン』というガクアジサイ。右下の白いこんもりしたところが…敷地内で毎年勝手に増えて雑草化してしまったカモミール「地球に優しいコンポスト」も見えますね~我が家ではお風呂のお水はいったん大きな水桶に移して、花や野菜にかける水として再利用しておりますと、いいますのは、入浴剤にHB101の製品を使用しているので…これ、植物の成育に非常によいエキスがたっぷり入っているのです流しちゃったら勿体ないせっかくのよきお水ですので、薔薇たちにたっぷりかけてあげています だんだん紫陽花の季節が近づいてきています今年はどこに行こうかな~
2008.05.09
コメント(2)
-
長谷寺~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《24》
《長谷寺》『花の御寺』として全国に知られる長谷寺は、春は桜に牡丹、夏は紫陽花、秋は紅葉、冬は寒牡丹…と、一年を通じて花が彩りを添える寺です。中でも『牡丹の長谷寺』としてよく知られ、今では約7000株の牡丹が咲き競っています。「観音様と牡丹」…これは唐の皇妃、馬頭夫人が観音さまの霊験を得たお礼に牡丹を献木したことがはじまりだそうです。「長谷寺の観音さまに牡丹を献木すると美しくなる」といわれているのだそうです♪ご本尊は《十一面観世音菩薩》近江国高島から来た楠の霊木をもちいて三日で造り上げたといわれています。身の丈、三丈三尺(十メートル余り)右手に錫丈を持ち、平らな石の上に立つ独特のおすがたです。両脇には難陀龍王と雨宝童子が仕えています。長谷寺は、天武天皇の時代に開かれ、聖武天皇の勅願により十一面観音が祀られました。現在は関係寺院三千ケ寺を有する、真言宗豊山派(覚鑁さまの流れを汲む真言宗の一派)の総本山として人々の信仰を集めています。~長谷寺パンフレットより~長谷寺の門前に立った時、友人からメールが届きました(^O^)/この方、本当に面白い方で、ツボにはまる瞬間にばかりメールを送ってきますある時には某八幡宮で柏手を打った瞬間…またある時にはとある山の頂上に到着したその瞬間…あまりのタイミングのよさに笑ってしまうこと数度今、長谷寺にいることを告げると…「頑張ってね~」のエールが返ってまいりましたうれしいな(またそのエールは京都八坂神社の拝殿で参拝している時に届いたのですが…)……ふと…去年の秋、橿原神宮前での酒盛りの後、この方は長谷寺~三輪山~松尾大社と流れていったことを思い出しました(私はこの時は千早赤阪の楠木正成生誕地&産湯の井戸~建水分神社~湊川神社と回り、もう一人の某氏は源九郎稲荷~一言主~いろいろへ…とそれぞれの流れに乗って前進してゆきました)うぬぬ…そうじゃったこの人はここに来てるんだわにゃるほど…なんとな~く、蜘蛛の巣の横糸繋いでる気分になってきましたよ~ 本尊の十一面観音さんに参拝し、御朱印をいただきにゆきますと、窓口にいらしたお坊様方が『凄い…凄い…』と感嘆することしきり…普段身近に接している文字だけにその凄さ、大変さが実感できるのでしょう…お坊様方が感嘆していたのは、私が出して御朱印を下さるようにお渡しした《白衣》それには院主さんの手によって、《梵字般若心経、梵字佛頂尊勝陀羅尼、梵字無量寿如来根本陀羅尼、各種梵字陀羅尼、各種梵字真言、四国八十八ケ所霊場の種字(梵字)》…が墨書されたすばらしいものでした。(布に書くのは本当に大変なのだそうですm(__)m)この白衣の開眼供養には私自身も参加させて頂きました宝物ですo(^-^)oこの白衣を院主さんから授かって、各地を巡り、白衣を朱印でいっぱいにした結果…癌が直っちゃったなんて話もあるそうです(☆_☆)詳しくお知りになりたい方は吉野山の善福寺へ直接ご自分で足を運ばれて、院主さんに伺ってみて下さいませ。ご縁あってすばらしい白衣を授けて下さった院主さん尼さま両人に深く感謝。自分の天命を成し遂げるために、有効に使わせていただきます。m(__)m さてさて、ぐるっとまわってまた牡丹回廊に下りてくると…素敵な雰囲気のカップル発見うほ~すてき~(゚▽゚)その近くに行ってみますと…ここも浄土のキラキラだ~ 出口に下りてゆくと…総受け付けの建物では、さきほど『よくお参りくださいました』と参拝者に声かけしていた若いお坊さま方が、なにやら建物の奥に集まってお経をあげているところに出くわしましたこんなことがなければなにかが祀られていることを知らずに通り過ぎてしまうところでした…よくみると…『秋葉山大天狗三尺坊』さんが祀られているではありませんかこんなところにも秋葉山建物の外から遥拝させていただき、長谷寺を後にいたしました
2008.05.08
コメント(0)
-
長谷寺の牡丹~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《23》
長谷寺の牡丹はこの日は三分咲きといったところでしたでもでも…なによりうれしかったのは、お坊様たちの直ぐな心観光地化しちゃった神社仏閣は商売気たっぷりでゲロゲロと思う場所も多いのに…う~んさすが『よくお参りくださいました』という言葉にこめられた謙譲と奉仕の心のトーンが珠のように美しく、エゴは微塵もなく、つやつやとした絹のようななめらかさ~思わず…尊敬~このトーンはそのままご本尊の十一面観音さんのトーンでもありました 長谷寺はただ今本尊御開帳中でありました。こりゃ凄い(゚▽゚)その前に立つと、人は自ずから敬謙な気持ちになり信心が沸いてくるようで、そのえもいわれぬ貴い風情を前にみな自然と手を合わせているようでした。長谷の観音さんはすばらしいでもこれって…御前に至るまでの長い回廊と、その周りの牡丹景色の心理的作用もあるのではないかと思われます。美しい花の海の中を、異次元の世界に登ってゆくような緩やかな階段(それも数回直角に曲がる…これ次元上昇に詳しい方ならピンとくると思います…説明はしませんが)その過程の中で意識を観音菩薩とリンクできるレベルに自然とシフトできるように作られているんだな~と思いました 左上の写真はこの日もっとも美しく輝いていた花です女性がずっとスケッチしておりました貴婦人のような花でした そうそう…西国三十三観音霊場は、今年一年かけて全ての寺院で秘仏開帳を行うそうです。もう終わってしまったところもありますが、今年は西国三十三観音巡りにはチャンスです
2008.05.08
コメント(2)
-
岡寺:龍蓋寺~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《22》
お次は花の寺、岡寺に参拝します牡丹がもうすぐ満開そしてシャクナゲが見ごろで、大勢の人が訪れておりました。日本人はお花好きだよな~《岡寺》西国三十三観音 第七番札所、東光山龍蓋寺とも申します。本尊は、如意輪観音我が国最大にして、如意輪観音像としては最古の作品。インド、中国、日本の三国の土で弘法大師が作られた塑像です。岡寺は、元は草壁皇子の住まいであった岡の宮を仏教道場に改め、義淵僧正に下賜され、創建された寺院です。義淵僧正は、良弁僧正(奈良東大寺の基を開いた)や菩薩と仰がれた行基、その他奈良時代の仏教興隆に尽くした多くの僧の先駆者である。また、義淵僧正の父母が観音に祈って生まれたのが義淵とされ、この有り難い話を聞かれた天智天皇は、岡の宮で義淵を草壁皇子と共にお育てになったという。義淵僧正は優れた法力の持ち主でもあった。その頃、農地を荒らす悪龍がいたのを法力で小池に封じ込め、大石で蓋をした。この池が本堂前の『龍蓋池』であり、岡寺の正式名称が龍蓋寺である由来です。こうした伝説は『災いを取り除く』信仰に発展し、それまでの観音信仰に厄除け信仰が加わり、日本最初の厄除け霊場が形成されました。~岡寺パンフレットより~う~む。石上神宮では、二上山の大津皇子の墓参りに行かなくちゃ…と思い、桃尾の滝では義淵の創建した三龍寺の一つ《龍福寺跡》に上り…そして二つ目の龍蓋寺である現岡寺は、大津皇子のライバルとされた草壁皇子ゆかりの地大津&草壁の本人同士は仲はよかったのですが、当時の外来勢力の暗躍にひっかかっちゃったり、親のエゴも絡んできたりと…いろんなことが重なって、大津皇子側が消されてゆく流れになります。吉野では院主さんと柿本人麻呂の話で盛り上がりましたし…石上神宮では人麻呂さんの碑がやたら気になってしばし眺めてしまいましたし。吉野花矢倉の近くには人丸塚もありますし…人麻呂もかよ~(-.-;)今回…義経絡みのつもりでしたが、蓋を開けてみれば、白鳳年間ですか…そうですか…(飛鳥時代はまだやらねぇぞ兵衛が終わってからじゃ…って誰に宣言してんだろ自分)う~ん白鳳もか~…そうか~じゃあやっぱり宮滝と桜木神社も今度行っとかないとな~因みに義淵僧正の三つめの龍の寺《龍門寺》は、吉野川上流、宮滝の吉野宮の北、龍門岳との間にあったようです。 ふう~
2008.05.07
コメント(2)
-
明日香~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《21》
岡寺への道の途中、明日香をドライブ写真が趣味でプロ級の腕を持つ院主さんが、『観光客の知らない素敵な光景を味わえるスポット』のいくつかに案内して下さいました(#^.^#)天気もよく、風も柔らかで、輝くような明日香村の景色を楽しむことができました右下の写真は、柿若葉の丘から見下ろす《石舞台古墳》です実際に明日香の地に立ち、その風に吹かれてみて初めて、多くの人が明日香の地に憧憬を覚える理由がわかったような気がします本来の日本のバイブレーションはこのトーンなんだろうな…
2008.05.07
コメント(2)
-
奇跡の桜の吉野神宮~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《20》
村上親子の墓と吉野神宮本殿の写真もあるのですが…う~ん…今回は自粛しますf^_^; さて、早朝散歩の時のこと…勝手神社前で軽く捕まってしまいましたはて…なぜかしらと辺りをみまわすと、今回は行くつもりのなかった村上義隆の墓へと続く、勝手神社前から曲がる道がちょいと気になるので、ひょいと覗いてみましたら…うわあ~道沿いにちらほら桜が咲いてるよやばい…行きたくなってきたぞ(桜には弱い自分)しか~し、勝手神社から義隆の墓まではなんと片道徒歩20分(私の足なら12~3分てとこかな)う~ん普通の人はまず行かないとこなので、つまり人気のない道を延々と行くことになりまする。途中に人家もほとんどない鬱蒼としたくねくね曲がった道だしな~でもちょっと行ってみようかな歩きはじめると…ところどころに満開の桜がちりばめられておりました(¨;)まるで、引き返す気が起きないように…そおっと桜で引きつけて、先へ先へと導くようにも思えます…村上義隆の墓に到着墓のそばには一本の山桜がひっそりと咲いておりました。(#^.^#)桜の香りのお線香をあげました。遠くには蔵王堂の姿が朝霧の中に浮かんで見えています。朝のお勤めが始まる音が聞こえてきました。 さてさて、あれこれ用事を終えて、てんやわんやを乗り越え…院主さんと尼様に助けられ(:_;)…深く深く感謝m(__)m…院主さんの車に乗って、みんなで明日香に向かいました牡丹を求めていざ出発~(^O^)/途中、お願いして村上義光の墓と吉野神宮にも寄ってもらいました。 村上義光の墓は駐車場と吉野神宮の間の小高い丘の上にあります。ここでも桜のお線香をあげて参拝。 次に吉野神宮に参拝。なんと…境内は桜が満開写真は吉野神宮の桜たちです夢にも思わなかった桜を前に…ぽか~ん(゚▽゚)神様って…その気になったら本当になんでもできるんだな~。 ちょいとここで吉野の桜について軽く説明させていただきますm(__)m吉野山の桜は三月下旬に下千本から始まり約一ヶ月かけて奥千本まで咲き上ることで有名でございます下千本(近鉄吉野駅~蔵王堂の辺り):三月下旬~四月上旬中千本(蔵王堂~吉水院~竹林院):四月初め~上旬上千本(竹林院~高城山の辺り):四月上旬~中旬奥千本(金峯神社~西行庵の辺り):四月中旬~下旬その年によって変動はありますが、ま、だいたいこんな感じが見ごろと理解していただければ結構です今年は4月23日に奥千本が満開であったそうですからわりと早めに終わった年のようですね実際…私が上った4月26日~27日には、名残の山桜が少し見られた程度で、後は八重桜や牡丹桜の花の時期でありました さて、その前の義隆の墓の桜や、如意輪寺を彩る桜にもいたく感動しましたが…《下千本よりもかなり下に位置する日当たりの良い》吉野神宮で、奥千本が終わってるこの時期に…満開の桜がどで~んと\^o^/いかに有り得ないことなのか少しは感じていただけましたでしょうか吉野神宮境内には山吹の花も満開でありました 満開の桜を用意して待っててくれるなんてヤバイ…o(><)o後醍醐さんのこと好きになってしまいそうだ……… あえて吉野神宮の桜を引き立たせる時期を選んで吉野へ呼ばれたような気もするな~『今、自分が完全に正しい道の上にいる』ことを感じた吉野神宮参拝でありました後醍醐さんありがとう\^o^/ 一応吉野神宮の由緒もつけておきますね。《吉野神宮》御祭神:後醍醐天皇明治天皇は後醍醐天皇の御偉業を深くお偲びになられ明治二十二年吉野神宮の御創立を仰せだされました。次いで明治二十五年九月に執り行われました御鎮座祭に勅使を遣わされ御霊代を御奉納されると共に、後村上天皇がお作りになられたと伝えられ、それまで吉水神社に奉安せられていた後醍醐天皇の御尊像も吉野神宮の本殿に奉遷されました。~吉野神宮パンフレットより~現吉野神宮の場所は、元は丈六山一の蔵王堂があり、大塔宮護良親王が吉野山に陣を構えられた時、北条幕府方の大将二階堂道蘊に占領されて、本陣となった所と伝えられております。 去年参拝した折りには…参道の玉石の間から草がいくつもにょきにょきしていて、その荒れた気配にショックを受けましたし、拝殿前の空間はさすがに掃除が行き届き立派なものの…参拝者が誰もおらず…ガランとしていて広さがかえって寂しい感じをいやますような気配でありましたが…今回は桜ばかりか人々もたくさん集まる空間になっておりまして…ホッとしましたよかったなぁ~
2008.05.07
コメント(0)
-
金峯山寺蔵王堂~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《19》
さて、次は大変お世話になった井光山善福寺を書きたいのですが…なぜかフリーズしてしまいますので、善福寺はトリにまわして蔵王堂を先にいたします《金峯山と金峯山寺》吉野山から山上ケ岳(大峯山)に至る金峯山は万葉の昔より聖地として知られ、多くの修業者や貴族が足跡を印しています。白鳳年間(7世紀末)修経道の開祖、役行者がこの金峯山を道場として修行され、蔵王権現を感得し、そのお姿を桜の木で刻み、お堂を建ててお祀りしました。これが蔵王堂であり、金峯山寺の草創です。山上ケ岳の頂上で役行者は「乱れた世を救う尊」を求め祈り続けました。すると、千手観音が現れました。しかし役行者は千手観音では満足せず、さらに祈り続けました。すると、次に釈迦如来が現れました。それでも足りぬと覚えた役行者がさらに祈り続けたところ、三体目に弥勒菩薩が現れました。弥勒でも安心できず、さらに祈り続けていると…最後に金剛蔵王権現が悪魔降伏の忿怒の相で出現しました。その姿を山桜の木に刻み、大峯山と金峯山寺に祀りました。故に金剛蔵王権現は、千手観音、釈迦如来、弥勒菩薩の三尊が、過去・現在・未来にわたり衆生を救済する為に仮りの姿として現れた権現として、蔵王堂に三体祀られています。吉野の蔵王堂は前宮、大峯山は奥宮、の関係にあたるそうです。金峯山は、多くの修行者が宗派を越えて入山修行しています。また、役行者が蔵王権現の像を桜の木に刻んだことから、桜が保護・献木されて吉野山が桜の名所となり、人々の心の安らぎの場となりました。現在の金峯山は金峯山修験本宗の総本山です。~金峯山パンフレットほかより~夕食の後、蔵王堂まで歩いて暗闇の中で参拝してみました(゚▽゚)(今回こんなのばっかりだな~)だれもおりませんので蔵王堂の階段に座り、一人で四本桜をじっくり眺めました。四本桜(写真右下)は大塔宮の酒宴跡です。五万の北条方に数千で戦い続けた大塔宮でしたが、さすがに持ちこたえきれず…もはやこれまでと覚悟を決めて蔵王堂前で最後の酒宴を始めると、そこに駆け込んできた満身創痍の村上彦四郎義光と、吉水院宗信に諌められ、天川へと落ち延びてゆくことになります。大塔宮の龍頭の兜と鎧を身につけた村上義光は、二天門に上り、宮の身代わりとなって割腹してみせ、北条方の目を引き付け、時間を稼ぎ宮を落とすことに成功。《太平記》の名場面の一つです。二天門跡には現在石碑が立っております。(写真右上)時を経て…今は静かに葉桜を繁らせているのみ。戦とは無縁の吉野山です 話は変わりますが、吉野山一帯は太古においてマチュピチュを思わせる巨大な山上都市であったことが発掘によりわかってきたそうです…。そこは何故か「山の民」ではなく「海の民」が住まう場所であったようなのですが…。神武天皇や大海皇子の動きを思うと、吉野は「どこでもドア」のような場所…と言っていた方がおりましたが…そうかもな~と思いました。 さて…翌朝も早朝参拝にまわりますo(^-^)oまずは《桜本坊》から桜本坊さん…大好きなんです双身の聖天さんもおりますし、ガーネシア神もおりますし、徳川家の菩提堂もあります。円空仏や天武天皇神霊も祀っているそうですし…びっくりしたのは《秋葉大天狗》が祀られていることです三尺坊さんが一体どういうご縁で…(でもうれしいな) 蔵王堂にもまた参拝堂は開いておりましたが、中に上がれるのは8:30からとのことですので、あとでまた来ることに…。(堂内では朝の祈祷が行われておりました) ガンジーに贈られたお釈迦様の御真骨を祀る佛舎利宝殿、後醍醐天皇の行宮となった実城寺跡に建立された南朝妙法殿を遥拝あたたかで、なごやかでよき風情です前回(去年秋)ジメッとした雰囲気だったのが嘘のようですようやく北朝方との蟠りのエネルギーが全部溶けたのかもしれないな~と思いました 朝食の後…三度目の蔵王堂参拝今度は中に上がっていろいろ見せていただきます拝観料400円。本尊の巨大な金剛蔵王権現は秘仏ですので拝見することはできませんが、美しい瑠璃色です堂内に写真が展示してありました(^O^)/親切だぁ~私は御開帳の際に拝ませてもらいましたが…結構いい感じです(#^.^#)(なにが…)裏へまわると…聖徳太子さんがおります前回はとろけるようなニッコニコの聖徳太子さんでしたが…今回は、う~ん上手くいえませんが、ワクワク((o(^-^)o))しているような風情でありました。その奥には《安禅寺金剛蔵王権現》が祀られております。今回、安禅寺金剛蔵王権現前に《発露の間》が設けられておりました。ついたてで囲まれた空間で、金剛蔵王権現とじっくり対話できます入らせていただきました。余談ですが…個人的に秘仏の本尊よりもこの安禅寺金剛蔵王権現の方が好きなのです。木肌に爛々と金色に輝く眼と口を見ていると、なんとなく落ち着いてゆくような気がします 裏手の本地堂に降りて、大塔宮護良親王ご生誕700年記念「吉野南朝を偲ぶ特別展」を拝見しました展示物の数は多くありませんが…堪能しました特に十津川郷で錦旗を奪い返す義光の勇姿を描いた「村上義光公奮闘之図」と、最後の酒宴で大盃を傾ける大塔宮と荒武者たちを描いた「大塔宮吉野城陣中図屏風」を拝見することができて満足
2008.05.06
コメント(0)
-
吉水神社その二~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《18》
参拝は後にして、先に上がらせてもらいました左下の写真入ってすぐの《義経潜伏の間》と《弁慶思案の間》です。今回は特別に義経と静御前の着物が展示されておりました(最初四月いっぱいの予定と言っておりましたが…ゴールデンウイーク中も展示してくださことになりました。義経&静ファンはお急ぎあれ~)この部屋には今も義経と静御前の魂が宿っているのだそうです。前回、某氏と参った際には…義経の清らか~な、渓流を思わせる澄んだ純粋な気配がいっぱいに満ちておりましたが…今回は、着物があるためか、より濃密で人間的な想いでいっぱいの空間のようでした写真左上その着物です義経の鎧も並んでおります多分…ここから山伏姿に身をやつして逃げたので、余計なものは吉水院に置いていったのでしょう。先に進んだ部屋には他にも義経の武具の数々や、弁慶の七ツ道具、静御前の鎧などが多く展示されております。 義経潜伏の間を曲がると、太閤花見の間としても使われた、《後醍醐天皇御座所》があります。後醍醐天皇の行宮となった場所だけあって、その先の展示室には直筆の数々、後醍醐天皇が修法に使った両界曼陀羅はじめ、水晶をはめこんだ宝塔など、南朝にまつわる遺品がどっさりございます 写真右下…ちっちゃくてわかりにくいのですが、左から《小野篁の千体地蔵》《楠木正成所蔵の銅像毘沙門天》《伝教大師(最澄)作、ダキニ天像》《弘法大師(空海)作、灰仏弁財天像》ですこんなにすごいものがどうしてここに~と、初めて見た時にはたまげてしまいました(私だけですかね~)小野篁・楠木正成・伝教大師・弘法大師…この並びには、う~んとうなってしまいました。縁ある方がたばかり…楠木正成のものは他に…矢入れや家系図なども見ることができます。 写真右上《大塔宮の陣羽織と茶碗》宮の陣羽織…黄色ですぬふふやっぱり黄色だ~ ひと回りして、義経潜伏の間に戻ってまいりました(^O^)/キョロキョロ………うっふっふ(このあたりのことは皆様のご想像にお任せいたします某氏の真似してみただけですが…因みに着物に触ったりなどの、やっちゃダメなことをした訳ではありませぬのでご安心を…m(__)m)
2008.05.03
コメント(0)
-
吉水神社その一~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《17》
吉水神社に間に合いました~《吉水神社》元は吉水院といい、天武天皇の白鳳年間に役行者が創建したものと伝わります。格式高い僧坊でありましたが、明治八年、寺号を廃して吉水神社と改めました。《御祭神》後醍醐天皇・楠木正成・吉水院宗信法印当社は、吉野の歴史を代表する殿堂です。文治元年(1185年)源義経が、兄頼朝の迫害を逃れて最愛の静御前、弁慶らと共に身を隠され、世にその純愛物語を伝えています。また延元元年(1336年)後醍醐天皇が京の花山院を逃れて吉水院宗信のもと当社を行宮とされ、血涙の歴史を記された南朝の大舞台でもあります。降っては文禄三年(1594年)太閤秀吉が当社を本陣として大花見の盛宴を催し、天下にその権勢を示したのは有名です。したがって、これらの歴史にまつわる当社に所蔵する宝物はすこぶる多く、百二十数点を数え、重要文化財の宝庫といわれています。その由緒もさることながら、吉水神社の書院は、初期書院造の代表傑作とされております。いまもなお、書院内に、『義経潜伏の間』『弁慶思案の間』『太閤花見の間』が残されております。 ほんと…呆れるほどとんでもない宝物がたくさん陳列されております。吉野に来たら必見です拝観料:400円 参拝は無料です。真ん中が後醍醐天皇右手に勝手神社の神様左手に楠木正成と吉水院宗信境内には義経の蹄跡(もちろん馬のですが)や一目千本といわれる桜の眺望のよい場所もあります。鳥居から坂を下り、谷底からまた階段をのぼると到着する…というおもしろいつくりにもなっておりますお土産屋さんの立ち並ぶ中いきなり鳥居がありますのでお見逃しなく(^O^)/
2008.05.02
コメント(0)
-
勝手神社~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《16》
一度善福寺に戻り、世に二つとないすばらしいものを授けていただきましたそれを持って今度は吉水神社へと急ぎます拝観終了時間が9:00~5:00ですので、急げ急げ(この時、4:30過ぎでした)途中勝手神社前を通ります。《勝手神社》御祭神:天忍穂耳命(正勝神)・大山祇命・久々能智命・木花咲耶姫命・苔虫命・葉野姫命吉野八社明神のひとつで、金峯山の山の入口にあたるので山口神社ともいいます。文治元年の暮れ、源義経と雪の吉野山で涙ながらに別れた静御前は、従者の雑色男に金銀を奪われ、山中をさ迷っているところを捕らえられました。平家方の者たちは、義経の名を辱めんと、静御前に舞をまわせたのがこの勝手神社境内です。しかし、雅た姿で法楽の舞をまう静御前に、かえって居並ぶ荒法師たちは感嘆させられたという話が伝わっています。この神社は、勝運の神、山の神、五節の舞の起源から芸能の神、として有名な神社です。五節の舞の起源というのは…天智天皇の十年(672年)大友皇子に対抗して吉野に兵を挙げた大海皇子が、この神前で琴を奏でていると、天女が後ろの山から袖を翻して舞いながら現れ、吉兆を示しました。この故事により五節の舞が宮中で行われるようになりました。勝手神社後ろの山はこれゆえ振袖山と呼ばれております。 現在勝手神社は放火により社殿が焼失し、吉水神社内に仮に祭られております。社殿という形はなくとも、神様はしっかりといらっしゃるようでした…形が壊れたように見えたかて…あるものはある
2008.05.02
コメント(0)
-
吉野山の遅桜~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《15》
重たいものが続きましたので、ここらで一つ可憐な花たちを…右下の谷向こうに見えるのが如意輪寺。裏に後醍醐天皇稜があります(結局行けずじまいでしたので遥拝しました)
2008.05.02
コメント(0)
-
花矢倉と桜~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《14》
花矢倉から横川の覚範の首塚に下りてゆきます。ここは桜満開の頃には絶景のはずこの日は道沿いにある八重桜が見事に満開でありました《佐藤忠信の花矢倉》文治元年(1185年)12月、兄頼朝の怒りに触れた源義経が、武蔵坊弁慶をはじめ、佐藤忠信、伊勢の三郎、常陸坊海尊、鷲尾の七郎、片岡の八郎といった一騎当千のつわものたちとともに、愛妾静御前を連れて、雪の吉野山に潜入し、吉水院に身を隠していました。金峯山衆人の味方を得ることができず、途中で静と別れてこの上の子守の宮まで逃げのびてきましたが、豪僧・横川の覚範が追いすがってきましたので、家来の一人、佐藤忠信が義経の身代わりとなって戦い、そのすきに義経一行を逃げのびさせたのでした。佐藤四郎兵衛忠信は奥州の庄司、佐藤元治の子で、源義経が平泉に身を寄せたときに、兄継信とともに義経の家来となった侍で、弁慶と並んで義経の片腕としておおいに活躍したのでした。忠信はここで攻め来る敵を追い散らした後、命ながらえて京都に潜入し、身を隠していたところを襲われ、自殺し果てました。28才だったと伝えています。佐藤忠信が一人ふみとどまり、追いすがる敵を切り防いだ戦場は、花矢倉として上千本~中千本~蔵王堂までも見晴らせる、吉野随一の展望所となっております。
2008.05.02
コメント(2)
-
吉野水分神社~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《13》
高城山から少し下ると吉野水分神社(よしのみくまりじんじゃ)に到着しますこちらの桜も葉桜ではありましたが、咲き残っていてくれました《吉野水分神社》主祭神:天之水分大神配祀:(右殿)天萬たく幡千幡姫命、玉依姫命、天津彦火瓊々杵命(左殿)高皇産霊神、少名産神、御子神子守宮ともよばれています。玉依姫の神像は日本一の美女神像で国宝 ここでちんたら一つずつ拝礼しつつ、それぞれに違うトーンの風がわき起きるのを楽しんでおりましたところ、最後のお宮を拝していたその時…「いた~」との声が…振り返ると西行庵と苔清水でお会いしたご家族が楼門を入ってきたところでした…素敵な再会です苔清水への道をお伝えしたり、お水が飲める(しかも美味)ことをお話しさせていただいただけで、後は私はタッタカ来ちゃったのですが…なんというか、うれしいですね~こういうちっちゃなご縁は…(゚▽゚)妙な親近感もわいてきます三人とも目の光が強くて素敵な家族でありましたお互いににっこり微笑んで、また分かれましたさあ~まだまだ行くよ~ん(後で思い返すと多分子守宮に帽子忘れたんだよな~私玉置では扇子忘れたし…なんじゃろな~しょうがない、神様に奉納したものといたします)
2008.05.02
コメント(0)
-
高城山~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《12》
金峯神社に戻り、次は大塔宮の吉野山城の司令部及び詰め所であった高城山を目指します(高城山は義経隠れ塔そばから見えます)てってけ歩いてサクッと到着~ここを歩くのも二回目ともなるともはや全然平気勝手知ったるなんとやら(けっこう急坂がありますから歩き易い靴必須ですバスは金峯神社下の奥千本バス停から竹林院前までは、バス専用の別ルートを走りますので、歩き始めたら下までいくしかありませんのでお気をつけて…)しかし…景色がよいなぁ~新緑が綺麗です桜もチラホラピクニックの家族がのどかにお弁当を食べてますいやぁ~平和っていいですね~《高城山(ツツジが城)》鎌倉時代末期、腐敗した鎌倉幕府から天皇に政治を取り戻すべく、後醍醐天皇の皇子大塔宮護良親王が吉野山にたてこもり、寄せ来る北条方五万を相手に、激しい戦闘を繰り広げました。その時、砦の一つとなったのがこの山で、山頂からは蔵王堂をはじめ、金剛山を一望できます。《牛頭天王跡》牛頭天王とは、釈迦の説法道場である、祇園精舎の守護神であった。日本ではスサノオのことである。城下にあってツツジが城の鎮守として創立されましたが、今は跡を残すのみとなっております。 吉野山内はあちこちの寺院内に牛頭さんがいらっしゃいます景色がよいのでのんびりしたいところですが、先を急ぎまする
2008.05.01
コメント(0)
-
宝塔院跡~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《11》
左下が愛染宝塔跡、右側二つは大峯奥駈道で大峯山へ向かう道です。《宝塔院跡》このあたり一帯を宝塔院跡と呼んでいますが、今では詳細な位置は定かではありません。明治はじめまでは、多宝塔、四方正面堂、安禅寺蔵王堂など大小の寺院が点在していたようです。安禅寺の木造蔵王権現は、今は蔵王堂内陣にまつられています。ここから奥へ続く山道は大峯山への修験の道で、1kmほど行くと慶応元年建立の女人結界碑があり、またその後ろの山が吉野山で一番高く、万葉集にもうたわれた標高858mの青根ケ峰です。 西行庵から苔清水を経て至る、愛染宝塔跡は、大塔宮が吉野山にて北条軍と戦った際、住まいとしていた場所です。前回はここで号泣(:_;)これがあるから一人で回るしかないんだよな~同行者に迷惑かけちまうといかんし…それにどうも一人で回る方がうまくいくことが多いような気がする…何人かいた方がうまくいく時にはそうしますがま、時と場合によりけりかな 因みに…義経はこの道を通って大峯山へと逃れました(^O^)/
2008.05.01
コメント(0)
-
奥千本~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《10》
奥千本にはまだ桜が少しありました《義経隠れ塔》義経がここに隠れていたところ、追っ手に塔を囲まれて、上の方面の窓()を蹴り破って義経が逃げた場所…。ん~でもここは、現在も俗気を抜く為の修験道の修業場として機能しておりまして、それゆえの清らかな迫力の方を強く感じました写真は撮りませんでしたが…次は義経隠れ塔から歩いてすぐの《金峯神社》に参拝。祭神:金山彦命金精明神ともいい、『金』の神様吉野の地主神様であり、鉱山の神様です。(本地は少彦名命との説もあり)吉野山は弥勒思想の地でもあり、この神様も大いに関係あり。ん…まだ時ではないと見え…てことはまた私はここに来るんですねふう~まだか~金峯神社の拝殿前には、立派な桜木がかつてあったのだそうです。金峯神社が火事にあった際(放火)その桜の木は燃えて、社殿焼失は助かったのだとか…桜が神社を守ったんだね~。 金峯神社から西行庵までは階段の山道を20分ほど歩きますが…西行庵へはぜひとも足を延ばして欲しいところです西行が三年間を過ごした空間は、なんともいえない落ち着きの中に、鄙びた華やぎがたゆたっております。時の経つのを忘れてしまいそうな、それとも時が止まってしまったような…(どっちも同じか…)それにつけても今回は、奥千本にも人々が沢山いらしていました(#^.^#)家族連れももちろんですが、素敵な雰囲気のラブラブカップルをた~くさん見かけました~有り難いことo(^-^)oおかげで私のやりたいことがやり易い深い信頼関係で結ばれたカップルや家族、純真な子供たちの持つバイブレーションには、行った先々でしばしば助けられております感謝m(__)m(本人たちに自覚はないだろうけど…)
2008.05.01
コメント(0)
-
吉野山~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《9》
橿原神宮前から特急さくらライナーに乗り換えて、吉野に到着駅までなんと院主さんが車で迎えに来てくださいましたび・びっくり吉野山のは、新緑の間にところどころに残る山桜がぽつぽつと浮かぶ姿も美しく…そして八重桜は満開わたくしはもう大満足でしたo(^-^)o(見れないと思っておりましたので…)まずは善福寺に寄って、持参した桜の苗木を奉納~役行者は感得した金剛蔵王権現を山桜の木に刻みました。それゆえ吉野では桜がことに大切にされ、昔から人々は桜の苗木を吉野山に献じたのだそうです私も真似して奉納~持ってきたのは我が家で増えた枝垂れ桜の木で、山桜ではありませんが…。善福寺の由緒については後で詳しく書きますね院主様も尼様もまれに見る素晴らしい方たちです。境内は狭いのですが、お花の大好きな尼様が境内を綺麗な花でいっぱいにしています。ほっこりする素敵な空間です今回、一歩境内に入った途端、「うわあ~極楽浄土に来たみたい~~」と叫んでしまいましたf^_^;吉野山にお越しの際にはぜひ善福寺にも寄ってみて下さいね~場所は竹林院近くで桜本坊のはすむかいの坂を下ったところです。吉野のへそのような気もする…光溢れる空間です さてさて、思いもよらず美味しいお昼をご馳走になり、それから私は奥千本へと向かいました写真を撮りにゆくという院主さんが義経隠れ塔のそばまで送ってくださることになりました(写真が趣味で、詩的な美しい吉野山の写真を沢山撮影されています運よく院主さんに会えた方はぜひ見せてもらって下さいませ素敵ですよ~)うひゃ~竹林院前からバスで行こうと思っておりましたので…願ってもない超時間短縮できましたので、頑張って行ける範囲は全部ゆくぞ~(^O^)/ 写真は奥千本へゆく途中、院主さんが案内してくださった吉野の中でもことに素敵な場所です観光コースから外れた場所にもこんなに素敵な情景が吉野にはあります
2008.05.01
コメント(0)
-
石上神社~'08,日本の心染み入る奈良めぐり~《8》
大親寺から下り、桃尾の滝を通過して、今度は石上神社に参拝しました。石上神宮の元宮とも云われる社です小さな社ですが…パワフル~うん、これなら納得の石上石上の神様と大和の神様ははじめは二上山に祀られたものを、東側に二つに分けて祀ったのが今の石上神宮と大和神社である…という説もありまして、こうなったら二上山も登りたいよなぁ~大津皇子のお墓もあるしでもまた今度にしよう 天理駅から近鉄に乗って吉野に向かいます はい…私は今回近鉄電車の回し者です~近鉄には奈良巡りにとっても便利な『奈良世界遺産フリーきっぷ』がございまして…その紹介をさせていただきますこのきっぷはゆき先エリア別に何種類か設定があります。有効日数も一日~三日あるようです。今回は吉野に行きますので…《奈良・斑鳩・吉野エリアきっぷ》を利用しました(^O^)/※ほかに《奈良公園エリア》《奈良・西の京・斑鳩エリア》も発売しています。このフリーきっぷは、スタート地点の駅に必ず戻らなくてはいけないのが唯一の難点(それゆえ前回のように、松阪~河内長野へ抜けて神戸まで行きたいぞというような東→西パターンの時には使えませぬ)その条件と、有効期間中はフリー区間内で宿泊するという条件さえクリアーできるならあちこち回れて超便利 《奈良世界遺産フリーきっぷ:奈良・斑鳩・吉野エリア》有効期間:乗車開始から三日間。フリー区間内の近鉄電車・奈良交通バスが自由に乗降できる。拝観料やレンタサイクルの割引特典もあり。料金近鉄難波~鶴橋・大阪阿倍野橋:2800円(大人):1400円(こども)京都:3000円(大人):1500円(こども)近鉄名古屋:4840円(大人):2420円(こども)注)名古屋方面からは四日市からなどの細かい料金設定もありますので詳しくはお調べください。 私は今回京都からスタート大阪から行くつもりでしたが…何故か帰りの夜行バスが満席で、京都だったら取り放題という不思議な状況でありましたので…有無をいわさず京都私、大阪に嫌われるようなことなにかしたかしらう~む。 で、その便利なフリーきっぷを使っての二日目…天理から吉野に向かおうとしたのですが…はひゃ~(☆_☆)乗り過ごしてしもうた『平端』で乗り換えだったのに~。起きてたのに…平端駅…ぽけら~としてしまい、気がついたら扉が閉まって次に向かって走り出してしまいました。京都行き急行でしたので、次の停車駅は…『郡山』はて郡山になにかあるのかしら因みに…電車に乗っているとたまにびっくりするようなことがあります。日光からの帰り、東武線栗橋付近で信号機故障で10分間ストップその後、内房線木更津駅手前でも機関故障により8分間ストップ近くになにかあるのかしら~と戻ってから調べてみると…栗橋には静御前の墓木更津には弟橘姫を祀る吾妻神社単なる思い込みならとっても有り難いんだけど…もしかして呼ばれてるのなら早いとこ行ったほうがよいよな~郡山もお呼ばれかなと、地図取り出して探してみると…ワッハッハ『源九郎稲荷神社』いた~ここだわ源九郎稲荷は義経が篤く信奉した稲荷神社で、元吉野川近くにあったもの。吉野山内の脳天大神に降りてゆく階段の途中にも祭られております去年秋に橿原神宮前で分かれた後、義経な某氏が参拝したとこだわ郡山だったのかあ~はいはいじゃあ、最終日の帰りに夕方になるけど寄るからね~と、新たな予定を一つ入れて…郡山から吉野へ…。橿原神宮前あたりまでくるともはや我が家な気分になります懐かしいような、ホッとするような…。奈良って…なんとなくそんな風に人を寛がせる雰囲気があります
2008.05.01
コメント(0)
全38件 (38件中 1-38件目)
1