2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

【鎌倉の女将の日記】 梅一輪
白梅 光則寺「梅一輪 一輪ほどの暖かさ 服部嵐雪 」あっ! 梅が一輪咲いた! ほんの僅かだけど春を感じるね♪・・・と、この句を女将はこう解釈をしていましたが、梅の花が、一輪また一輪と咲く毎に暖かくなっていきますね・・・という句でした。でも、やはりこの一輪を見つけた時は、少しだけの春を感じました。 今年の冬は寒い日が多いですが、これが平年並みなのでしょうか?梅が一輪咲いても、この寒さは月が変わっても続くそうです(涙)
2008年01月28日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 侘助
侘助 「数寄屋」 光則寺「侘助」は椿の一種ですが、大まかに分けると「一重咲きで、筒型に半開」に咲きます。その慎ましさから、利休好みの茶花として好まれていますが、豊臣秀吉の家来が朝鮮から持ち帰ったもので、その男の名から「侘助」とよばれる様に・・・一昨日(23日)は、起きてみたらうっすらと雪景色でも、その後の天気は雪と雨を行ったり来たりだったので、雪はあっという間に姿を消してしまいました。雪景色になったら見てみたい「冬ぼたん」(鶴岡八幡宮)次のチャンスは29日(火)に雨マークがありますが・・・雪になるかな?
2008年01月25日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 大寒
光則寺のロウバイ(蝋梅)ロウバイは字の如く花びらが「蝋細工」の様そして、ほのかに良い香り 今朝は雪景色?と期待してカーテンを開けたのですが夜中に雨かみぞれだったのでしょうか、道路が少し濡れているだけでも、首都圏では少しの積雪でも交通がマヒしてしまうので、積もらなくて良かったですね。 しかし、寒い!大寒です!今が一番寒い時立春の声を聞くまでは耐えなくては・・・ 「寒中水泳」「寒稽古」・・・「寒卵」寒の入りから節分まで産み落とされた卵を「寒卵」とか「大寒卵」とも昔から滋養に富むといわれているそうです。風水では「寒卵」は金運アップ寒卵を食べる事によって体内に金運が宿り、日毎に大きく膨らんでいくそうなそりゃ 金運アップだからと言って一日に何個も食べれば、嫌でも体は膨らむはな~(笑) ぬく飯に 落として円か 寒玉子 高浜虚子
2008年01月21日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 女正月
今日1月15日は「女正月」暮れからお正月にかけ忙しく働いた主婦達をねぎらう日です。・・・という訳で、今日は仕事が休みの日でもあるので、適当に家事を済ませ「着物」と奮闘今日のコウデはクリーム色の紬に柿渋色の織りの名古屋だいぶ着物は着慣れてきたとはいえ、やはり「奮闘」という言葉を使いたくなります。早くさくさくっと着られる様になりたいな~ 知り合いの方がちりめん細工などのお教室をやっていて、生徒さんの作品展のご案内を頂いていたので行ってみました。「女正月ー布に魅せられて」 鎌倉今村 お教室作品展ちりめん細工・ミニ着物・押し絵・袋物・・・どれも着物や帯の生地で作った物手仕事もさること乍ら、古布の魅力を存分に引き出した素敵な作品ばかりでした。 ・・・で、着物を着て出かけた訳ですが、ウールの着物コートを着ていて、それを何処でも脱がなかったので、「奮闘」した意味がなかったのです。早い話が帯など結ばず、ランドセルを背負ってても分からなかったって事(笑) 当店では、好評だった「鎌倉ゆかた日和」に続き「鎌倉着物日和」開催中です。な な なんと! 着物のお客様は「お食事代が半額」に!(条件はHPで確認してね)着物を着たら・・・鎌倉へ♪皆様のお越しをお待ちしていますm(_ _)m
2008年01月15日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 どんと焼き
今日は甘縄神明宮の「どんと焼き」「どんど焼き」とも言われ日本各地で行われる小正月(1月15日)の火祭りお札・松飾り・だるま・お守りなどを焼き、その火にあたって無病息災を願います。お習字を火に投じ上達を願うというところもあります。 そして、火が落ち着いてきた頃、長い棒に差した餅を焼いて食べる・・・のですが今は、パックに入った赤白緑のお餅はテイクアウト 三色のお餅とキンカンを枝に刺した飾りつけ本日お正月にお迎えした歳神様をお送りして、松の内は明けます。 1月15日は「女正月」とも・・・暮れから正月にかけて忙しく働いた女性を1日だけ休ませてあげようという、ねぎらいの日 さ~て!明日は「女正月」♪家事はやらず(いつもの事?)何処に遊びに行こうかな~~~♪♪♪
2008年01月14日
-

【鎌倉の女将の日記】 あらっ!梅が!
お正月頃から、我が家の盆栽の梅が咲き始めました。 今年のお正月は晴天に恵まれ、穏やかな日々でしたね。でも、やはり1月鎌倉もここにきてグッと寒さ本番となりました。明日の明け方は-2度 昼間の気温は6度にしか上がりません。風邪をひかない様気をつけて下さいね。 明日は成人式という皆さんおめでとうございます!甥っ子のS平ちゃんも ふふ 明日は成人式ですね♪(まだ中学生位にしかみえないんですけどね)おめでとう!!!
2008年01月13日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 本えびす(十日えびす)
今日は1月10日えびす様を祀っている鎌倉の本覚寺では、1月1日~3日を「鎌倉えびす」、今日10日一日だけを「本えびす」として、祈祷会や福餅つきが行われます。 今日のお目当てのイベントは「福餅つき」 夷堂前のステージ前に陣取った多くのカメラマンは、福娘の登場を待っています。振る舞われる撞き上がったお餅を待つ列も今日は長い! えびす様のお祭りに欠かせない「福笹」関西では「商売繁盛で笹持ってこい」というかけ声鎌倉では「商売繁盛 家内安全 お祈り申し上げま~す」との口上と共に福娘から手渡されます。「十日えびす」は初春らしい、華やかな行事です。 ・・・ん~ やってみたかったな~「福娘」のアルバイト・・・ただあの着物姿に憧れているだけなんですけどね(笑) 当店では、好評だった「鎌倉ゆかた日和」に続き「鎌倉着物日和」開催中です。着物を着たら・・・鎌倉へ♪皆様のお越しをお待ちしていますm(_ _)m
2008年01月10日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 トンネル工事
藤沢方面から長谷へ車で来るとこの「大仏隧道」をくぐります。上下線が別のめがねトンネルなんですが・・・おや? めがねとはいえ左右の大きさが違いますよね?左のトンネルは大正10年に開通したものですが、何年か前にトレーラーがトンネルの天井にひっかかり立ち往生した事があります。老朽化している事もあり神奈川県では、昨年12月から平成21年3月15日(予定)まで、「大仏ずい道改築工事」を行っています。明日7日から2月29日までは、終日片側交互通行になります。暫く渋滞等混乱はすると思いますが、最近観光バスの車高も高くなってきるし、雨の後はトンネルの壁からの漏水が大量に流れます。改築工事も必要ですよね。できれば、歩行者も通るので「明るく」「楽しい」トンネルにしてほしいです♪大仏隧道改築工事の詳細はこちらで
2008年01月06日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 鎌倉えびす
話は遡りますが・・・ 12月31日の「年越しそばパーティー」の後、これも恒例皆で本覚寺へ「本えびす」は1日からですが、31日夜半には準備も整い福娘達が御神酒を振る舞ってくれます。 今年はちょと早く本覚寺へ行ってしまったので、まだ福笹は売っていませんでしたが、ラーメンや甘酒・焼き大福、凧やにぎり福などを売る露店はもう準備万端「にぎり福」は、愛・健・財・学・福と五種類の御利益があり、一日一回掌に握って願う小さなお守り この「にぎり福」は本覚寺で何時でも買えますが、干支やえびすの置物はこの「本えびす」か「十日えびす」でしか手に入れる事ができないので、今年も干支のネズミを一匹買いました。 ・・・じつを言うとこの日記3日の夜から書き始め、書いては保存書いては保存を繰り返し今に至っています(^^;)もう何を書きたかったか分からなくなって(笑)・・・で、何を書きたかったのかって言うと毎年1月3日に、福娘が福笹を女将の店に授けにきてくれるのです。福娘の口上の後、店長に福笹を渡し店内のお客様に福銭を配ってくれます。「お正月ここ一番!」を撮ろうとデジカメを構えたのですが・・・カメラはウンともスンとも・・・押せど引けど?作動不能接触不良でちゃんとバッテリーに充電出来てなかったようで・・・(/_;)・・・というドジ話でした(>_<)
2008年01月03日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 舟おろし
鎌倉駅を出て若宮大路を右折して歩いていくと海に出ます。滑川を挟んで左側が材木座海岸、右側が由比ガ浜海岸そして、由比ガ浜の先が坂の下海岸です。坂の下海岸は小さいですが漁港でもあります。毎年1月2日、船霊様にその年の豊漁と海の安全を願う「船おろし」という神事が行われます。「船おろし」は10時からですが・・・時既に遅し!10時15分頃に行ったらもうぞろぞろと人が引き上げてきているではないですか~皆手には膨らんだスーパーバックをぶら下げて・・・神事の後は一艘づつ船主らが善男善女に、黄金にみたてたミカンや福銭や袋菓子を撒きます。皆これがお目当て! 結構フィーバーします(笑)常連さんは、スパーバック持参です。あ~ァ 拾われ損ねたミカンが無惨に・・・ でも、今朝もすっきりした青空なので、はためく大漁旗が綺麗です。 来年は、もう少し早く来ることにしましょ♪
2008年01月02日
-

【鎌倉の女将の瓦版】 元旦
今朝の空は雲一つ無く、限りない青空富士山もくっきり!穏やか~な 元旦です。昨日大晦日の強風が昨年の悪い事を吹き飛ばしてしまったかの様でもあり「なんだか縁起のいい」1年の始まりです。 長谷の鎮守様は「甘縄神明宮」鎌倉で一番古い由緒ある神社です。 毎年初詣はこの「神明さん」にお詣りし、「長谷睦」の方々が振る舞って下さる「お汁粉」にほんわかと舌鼓今年1年が良い年となりますように♪ さてさて、初詣などで頂いたお札やお守りは?お札やお守りの有効期限は、「1年間」授かって1年たったら買い改めるのが基本とか願いが叶った場合はお礼参りをして、お焚き上げしてもらいます。「甘縄神明宮」では、古いお札等のお焚き上げは14日に行います。 「どんと焼き」ですね。「左義長」とか「どんど焼き」ともお札の他に松飾りなどもお焚き上げしますが、門松や松飾りに宿った歳神様を、炎と共にお見送りする意味もあるそうです。
2008年01月01日
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-
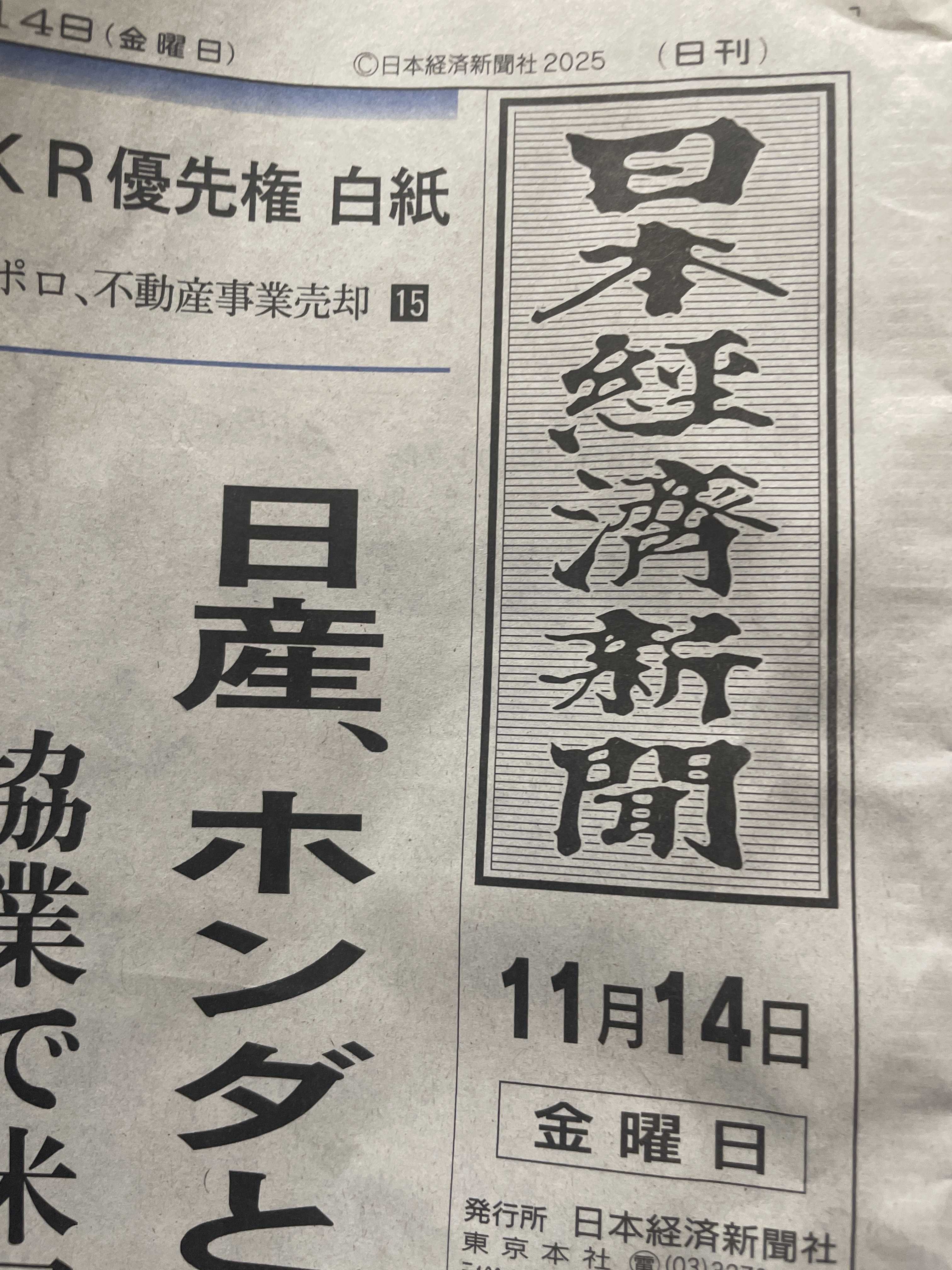
- ★つ・ぶ・や・き★
- 戦争やりたきゃ、てめえがやれ
- (2025-11-15 01:07:19)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- トム・フェルトン、舞台版「ハリポタ…
- (2025-11-14 23:00:04)
-








