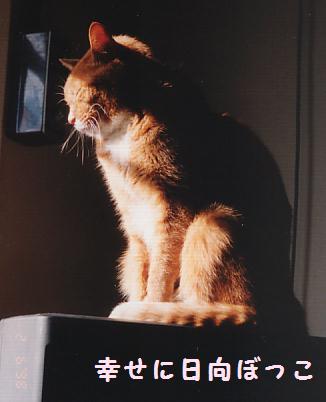テーマ: どんなテレビを見ました?
カテゴリ: 気になるTV番組
2025年NHK大河ドラマ
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 のあらすじ及び感想日記です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
寛政2年(1790)最愛の妻・きよを失い半ば狂ったようになった
歌麿(染谷将太さん)は何日も食事をとらず、まるできよの後を
追うかのようでした。
歌麿を案じた蔦屋重三郎(横浜流星さん)は母・つよ(高岡早紀
さん)を呼び、つよには少し心を開く歌麿の見守りを頼み自身は
仕事がたまっている店に戻っていきました。
老中首座の松平定信(越中守;井上祐貴さん)による出版統制が
続き、なんとかしなければと考える地本問屋の皆は鶴屋喜右衛門
(風間俊介さん)が代表になって、水面下で奉行所の初鹿野信興
(田中美央さん)らとやり取りを重ね、寛政2年10月、正式に
地本問屋の株仲間が発足となりました。
これにより自主検閲での本の出版が許され、やはり定信の改革の
せいで苦しい状況にあえぐ吉原の皆を救うために、重三郎はその
内容に好色が含まれる本を出そうとしました。
行事の吉兵衛(内野謙太さん)と新右衛門(駒木根隆介さん)は
この本は出せないと判断しますが、重三郎は「教訓読本」の袋に
入れて中を見せないようにして出せばいいと強く主張。
吉兵衛と新右衛門は渋々認めて出版となりました。
重三郎が打ち合わせから帰宅すると、栃木に行く歌麿に同行する
ためにつよが旅支度をしていました。
自分から離れたいと言う歌麿に、あの時の言葉の真意をわかって
もらおうと重三郎は歌麿に会いに行こうとしました。
しかしつよから、それは重三郎が自分の気持ちを歌麿に押し付け
たいだけだと叱られ、重三郎は思いとどまりました。
明けて寛政3年(1791)、重三郎は山東京伝(本名は北尾政演;
古川雄大さん)が書いた『錦之裏』『仕懸文庫』『娼妓絹籭』の
3作を袋に入れて販売し、売れ行きは好調でした。
しかし3月、その内容がお上に知られて重三郎と京伝は奉行所に
連行され、本は絶版となりました。
奉行所での詮議では、重三郎はご公儀を謀ったとして老中首座の
松平定信が見分に出てきました。
重三郎は定信に対し、臆するどころか皮肉を交えた挑発するかの
ような物言いで自分の考えを堂々と述べていきました。
ただやはり、その不遜な態度は定信のカンに障って怒りとなり、
重三郎は引っ立てられて厳しい責めを受けることになりました。
夫・重三郎の身を案じるてい(橋本愛さん)のために地本問屋の
仲間が公事宿の知り合いの飯盛の男を呼んでくれていました。
飯盛は「厳しい裁きは朱子学の説くところと矛盾している。」と
教えてくれ、ていは重三郎の命乞いをするために長谷川平蔵宣以
(中村隼人さん)を介して、定信の師である柴野栗山(嶋田久作
さん)に会い、栗山に朱子学で問答を挑みました。
てい: 子曰
導之以政 齐之以刑
民免而無恥 導之以德
斉之以礼 有恥且格
栗山: 君子中庸 小人反中庸
小人之反中庸也 小人而無忌憚也
「重三郎は二度目の過ちであり、赦しても改めぬ者を許し続ける
意味がどこにある?」と問いました。
てい: 見義不為 無勇也
重三郎は、女郎は揚げ代を倹約令のために値切られ嘆いていると
言っていた、だから本で遊里での礼儀や女郎の身の上などを伝え、
礼儀を守る客を増やしたかったのだろう、と栗山に述べました。
さらに「女郎は親兄弟を助けるために売られてきた孝の者であり、
不遇な孝の者を助けるのは正しきこと。」と考えを述べ、最後に
「どうか儒の道に損なわぬお裁きを!」と強く訴えました。
その後、それぞれに裁きが下りました。
京伝は手錠鎖50日、吉兵衛と新右衛門は江戸所払いに、そして
重三郎には「身上半減」という罰が下りました。
ただ奉行所のお裁きが下る場であっても重三郎には真摯な態度が
見受けられず、ていはたまらず進み出て重三郎に平手打ちをして、
いつも自分の考えを言いたいだけだと泣きながら責めました。
そして後日、地本問屋の皆に詫びを入れるときでもまたふざけて
しまい、その場の誰もが腹立ちの顔になって、ふだん温厚で声を
荒げない鶴屋喜右衛門から「そういうところですよ!」と叱られ
てしまいました。
さて身上半減で重三郎の店がどうなったのかというと、金だけで
なく店にある全てのもの---看板・のれん・畳・版木・在庫の本
など、あらゆる物が半分にされてしまいました。
定信の几帳面さに呆れたり、ていは情けなくて涙したり。
しかしその様子を見に来た大田南畝(桐谷健太さん)は面白くて
たまらず大笑いし、集まっていた町の人たちも笑い出しました。
「世にも珍しい身上半減の店」でひらめいた重三郎はこの状況を
逆手にとって「罰を受けても生き残る。縁起がいいよ!」と店に
残る本を売り出して賑わっていました。
その様子は松平定信にも報告が入っていました。
定信は「あまりに厳しい処分は朱子学との矛盾を生み、ご公儀の
威信を損なう。身上半減を与えられる者こそ賢者にふさわしい。」
という栗山の助言を受けいれたのでした。
ところでそのころ江戸では押し込み強盗が市中を荒らしていて、
強盗は平蔵が捕らえて厳しい処罰をしたものの、この件について
老中たちからは定信に、これらは倹約令の反動であり、倹約令や
風紀の取り締まりを切り上げるべきだ、と進言がありました。
本多忠籌(矢島健一さん)は定信に「帰農令があっても、生活が
苦し過ぎる百姓にはもう戻りたくない。人は正しく生きたいとは
思わない。楽しく生きたいのです。」と切に訴えました。
また松平信明(福山翔大さん)は、このままでは田沼以下の政と
誹りを受けると進言し、老中2人の言葉は「自分は常に正しい」
と信じて強気で改革を進めてきた定信には堪えるものでした。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
今回、蔦屋重三郎(横浜流星さん)を見てつくづく思ったこと。
それは何かにつけてすぐにおちゃらけて笑いを取ろうとする人は、
時と状況を間違えるとマイナスになって、周囲を凍りつかせるか
怒らせるかになる、ということでした。
また奉行所で松平定信(井上祐貴さん)に詮議を受ける場面では、
一言一言いちいちカンに触る言い方をして定信を怒らせ、自分で
罪を重くしています。
重三郎は自分の考えに自信があり、自分が必死に訴えれば相手は
わかってくれると信じる人なのでしょう。
でも自分に思いがあるように、相手にも思いがあるのです。
重三郎の必死の訴えを「受け入れる」かどうかは相手次第です。
歌麿(染谷将太さん)は今は聞きたくなくて重三郎から物理的に
距離を置いたし、定信は自分に逆らうとは許せん!となりました。
このドラマはこれまで、重三郎のプラス思考で困難を乗り越えて
きたようでしたが、今回は重三郎のこのおめでたい思考が各所で
相手をイラつかせた感じがしました。

『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 のあらすじ及び感想日記です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
寛政2年(1790)最愛の妻・きよを失い半ば狂ったようになった
歌麿(染谷将太さん)は何日も食事をとらず、まるできよの後を
追うかのようでした。
歌麿を案じた蔦屋重三郎(横浜流星さん)は母・つよ(高岡早紀
さん)を呼び、つよには少し心を開く歌麿の見守りを頼み自身は
仕事がたまっている店に戻っていきました。
老中首座の松平定信(越中守;井上祐貴さん)による出版統制が
続き、なんとかしなければと考える地本問屋の皆は鶴屋喜右衛門
(風間俊介さん)が代表になって、水面下で奉行所の初鹿野信興
(田中美央さん)らとやり取りを重ね、寛政2年10月、正式に
地本問屋の株仲間が発足となりました。
これにより自主検閲での本の出版が許され、やはり定信の改革の
せいで苦しい状況にあえぐ吉原の皆を救うために、重三郎はその
内容に好色が含まれる本を出そうとしました。
行事の吉兵衛(内野謙太さん)と新右衛門(駒木根隆介さん)は
この本は出せないと判断しますが、重三郎は「教訓読本」の袋に
入れて中を見せないようにして出せばいいと強く主張。
吉兵衛と新右衛門は渋々認めて出版となりました。
重三郎が打ち合わせから帰宅すると、栃木に行く歌麿に同行する
ためにつよが旅支度をしていました。
自分から離れたいと言う歌麿に、あの時の言葉の真意をわかって
もらおうと重三郎は歌麿に会いに行こうとしました。
しかしつよから、それは重三郎が自分の気持ちを歌麿に押し付け
たいだけだと叱られ、重三郎は思いとどまりました。
明けて寛政3年(1791)、重三郎は山東京伝(本名は北尾政演;
古川雄大さん)が書いた『錦之裏』『仕懸文庫』『娼妓絹籭』の
3作を袋に入れて販売し、売れ行きは好調でした。
しかし3月、その内容がお上に知られて重三郎と京伝は奉行所に
連行され、本は絶版となりました。
奉行所での詮議では、重三郎はご公儀を謀ったとして老中首座の
松平定信が見分に出てきました。
重三郎は定信に対し、臆するどころか皮肉を交えた挑発するかの
ような物言いで自分の考えを堂々と述べていきました。
ただやはり、その不遜な態度は定信のカンに障って怒りとなり、
重三郎は引っ立てられて厳しい責めを受けることになりました。
夫・重三郎の身を案じるてい(橋本愛さん)のために地本問屋の
仲間が公事宿の知り合いの飯盛の男を呼んでくれていました。
飯盛は「厳しい裁きは朱子学の説くところと矛盾している。」と
教えてくれ、ていは重三郎の命乞いをするために長谷川平蔵宣以
(中村隼人さん)を介して、定信の師である柴野栗山(嶋田久作
さん)に会い、栗山に朱子学で問答を挑みました。
てい: 子曰
導之以政 齐之以刑
民免而無恥 導之以德
斉之以礼 有恥且格
栗山: 君子中庸 小人反中庸
小人之反中庸也 小人而無忌憚也
「重三郎は二度目の過ちであり、赦しても改めぬ者を許し続ける
意味がどこにある?」と問いました。
てい: 見義不為 無勇也
重三郎は、女郎は揚げ代を倹約令のために値切られ嘆いていると
言っていた、だから本で遊里での礼儀や女郎の身の上などを伝え、
礼儀を守る客を増やしたかったのだろう、と栗山に述べました。
さらに「女郎は親兄弟を助けるために売られてきた孝の者であり、
不遇な孝の者を助けるのは正しきこと。」と考えを述べ、最後に
「どうか儒の道に損なわぬお裁きを!」と強く訴えました。
その後、それぞれに裁きが下りました。
京伝は手錠鎖50日、吉兵衛と新右衛門は江戸所払いに、そして
重三郎には「身上半減」という罰が下りました。
ただ奉行所のお裁きが下る場であっても重三郎には真摯な態度が
見受けられず、ていはたまらず進み出て重三郎に平手打ちをして、
いつも自分の考えを言いたいだけだと泣きながら責めました。
そして後日、地本問屋の皆に詫びを入れるときでもまたふざけて
しまい、その場の誰もが腹立ちの顔になって、ふだん温厚で声を
荒げない鶴屋喜右衛門から「そういうところですよ!」と叱られ
てしまいました。
さて身上半減で重三郎の店がどうなったのかというと、金だけで
なく店にある全てのもの---看板・のれん・畳・版木・在庫の本
など、あらゆる物が半分にされてしまいました。
定信の几帳面さに呆れたり、ていは情けなくて涙したり。
しかしその様子を見に来た大田南畝(桐谷健太さん)は面白くて
たまらず大笑いし、集まっていた町の人たちも笑い出しました。
「世にも珍しい身上半減の店」でひらめいた重三郎はこの状況を
逆手にとって「罰を受けても生き残る。縁起がいいよ!」と店に
残る本を売り出して賑わっていました。
その様子は松平定信にも報告が入っていました。
定信は「あまりに厳しい処分は朱子学との矛盾を生み、ご公儀の
威信を損なう。身上半減を与えられる者こそ賢者にふさわしい。」
という栗山の助言を受けいれたのでした。
ところでそのころ江戸では押し込み強盗が市中を荒らしていて、
強盗は平蔵が捕らえて厳しい処罰をしたものの、この件について
老中たちからは定信に、これらは倹約令の反動であり、倹約令や
風紀の取り締まりを切り上げるべきだ、と進言がありました。
本多忠籌(矢島健一さん)は定信に「帰農令があっても、生活が
苦し過ぎる百姓にはもう戻りたくない。人は正しく生きたいとは
思わない。楽しく生きたいのです。」と切に訴えました。
また松平信明(福山翔大さん)は、このままでは田沼以下の政と
誹りを受けると進言し、老中2人の言葉は「自分は常に正しい」
と信じて強気で改革を進めてきた定信には堪えるものでした。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
今回、蔦屋重三郎(横浜流星さん)を見てつくづく思ったこと。
それは何かにつけてすぐにおちゃらけて笑いを取ろうとする人は、
時と状況を間違えるとマイナスになって、周囲を凍りつかせるか
怒らせるかになる、ということでした。
また奉行所で松平定信(井上祐貴さん)に詮議を受ける場面では、
一言一言いちいちカンに触る言い方をして定信を怒らせ、自分で
罪を重くしています。
重三郎は自分の考えに自信があり、自分が必死に訴えれば相手は
わかってくれると信じる人なのでしょう。
でも自分に思いがあるように、相手にも思いがあるのです。
重三郎の必死の訴えを「受け入れる」かどうかは相手次第です。
歌麿(染谷将太さん)は今は聞きたくなくて重三郎から物理的に
距離を置いたし、定信は自分に逆らうとは許せん!となりました。
このドラマはこれまで、重三郎のプラス思考で困難を乗り越えて
きたようでしたが、今回は重三郎のこのおめでたい思考が各所で
相手をイラつかせた感じがしました。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
October 15, 2025 09:02:14 PM
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
星に願いを・・・。☆…
りえりえ0527さん
柴犬さくらとカント… さくらパパ&ママさん
犬太とお散歩 a-totoroさん
チョコのちょこちょ… むんぞうさん
気ままなラブラドール max&daiママ♪さん
鳥の家 さくら113さん
バカネコ日記 海獣トドさん
じゃじゃ馬のつぶやき soniasさん
モフニャゴ通信 @… みぃ *さん
柴犬さくらとカント… さくらパパ&ママさん
犬太とお散歩 a-totoroさん
チョコのちょこちょ… むんぞうさん
気ままなラブラドール max&daiママ♪さん
鳥の家 さくら113さん
バカネコ日記 海獣トドさん
じゃじゃ馬のつぶやき soniasさん
モフニャゴ通信 @… みぃ *さん
Keyword Search
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.