PR
サイド自由欄

義経黄金伝説 イメージイラストラフ 本田トヨタ作
『YG源義経黄金伝説■一二世紀日本の三都市(京都、鎌倉、平泉)の物語。平家が滅亡し鎌倉幕府成立、奈良東大寺大仏再建の黄金を求め西行が東北平泉へ。源義経は平泉にて鎌倉を攻めようと』 山田企画事務所・YG源義経黄金伝説■ ●源義経黄金伝説全編にリンクシテマス。
山田企画事務所 は、ビジネス・マンガ制作事務所です。
■ユーチューブ■youtube.com●how to draw manga●
● http://www.youtube.com/user/yamadakikaku2009
山田企画事務所・関連サイト
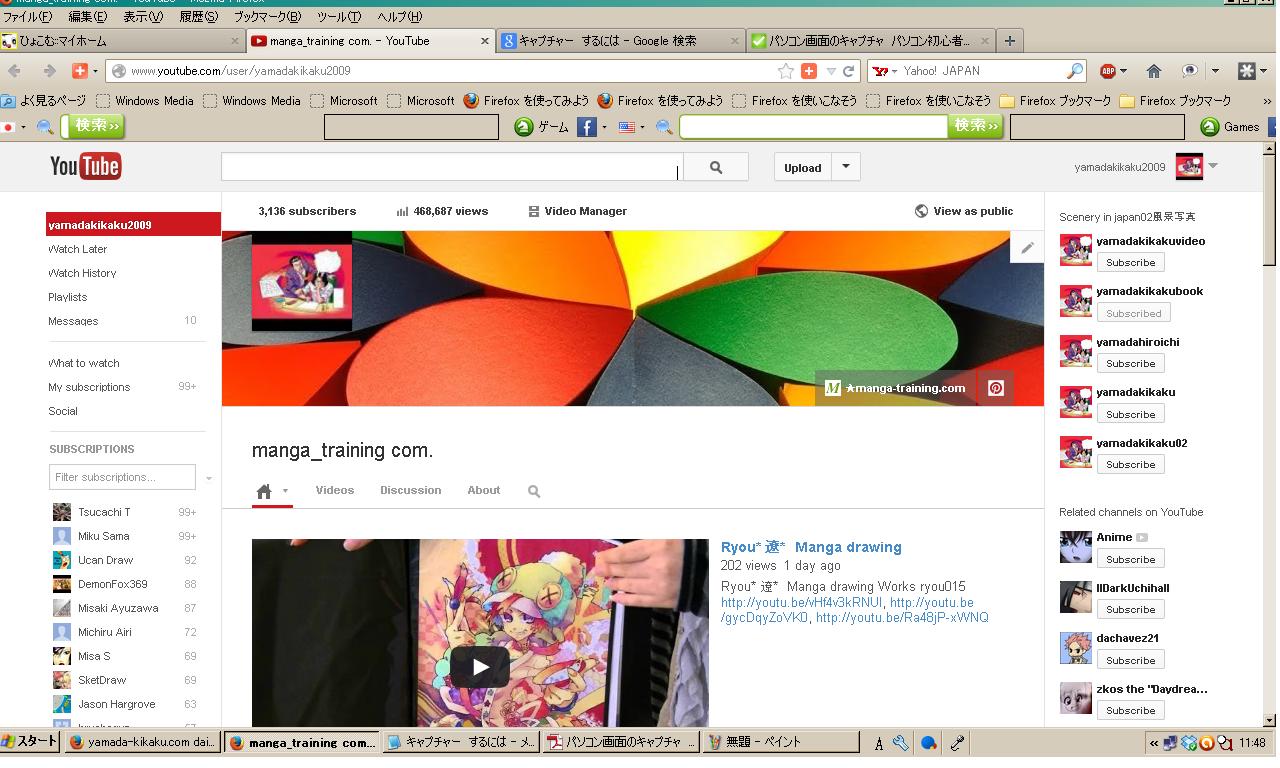
● how to draw manga
jedis.org

● manga-training.com ● manga-agency.com ● suzuki-junko.com ● mekamushi.com

● yamada-hiroichi.com ● how to draw manga ● event-art seminerイベント案内 ● Scenery in japan01風景写真 ● 風景写真Scenery in japan02
● 風景写真Scenery in japan03 ● 風景写真Scenery in japan04
『マンガ家になる塾』ナレッジサーブ
!山田企画事務所ピンタレストーすべてyoutube動画にリンクしてます!
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/ 御覧ください
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
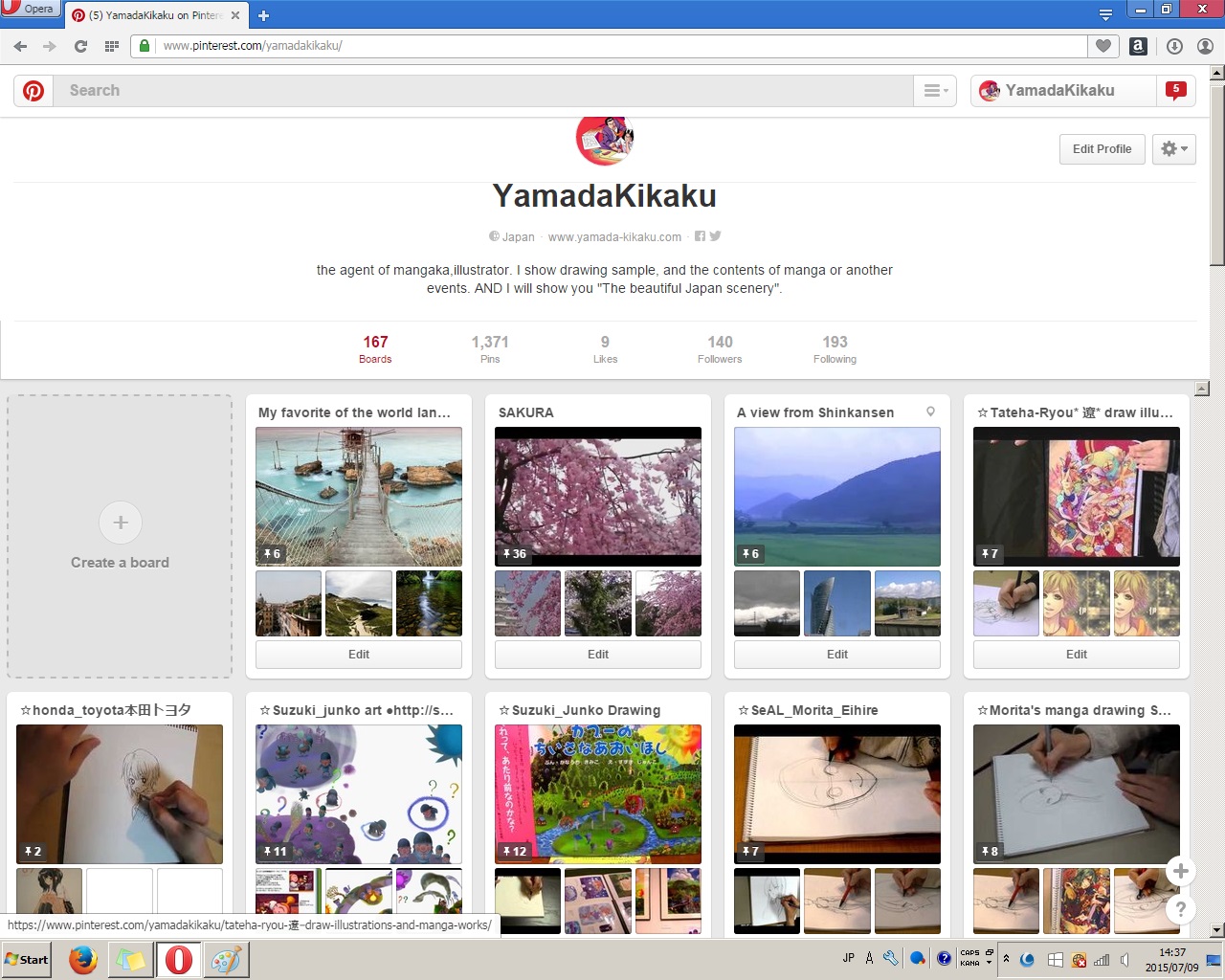 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
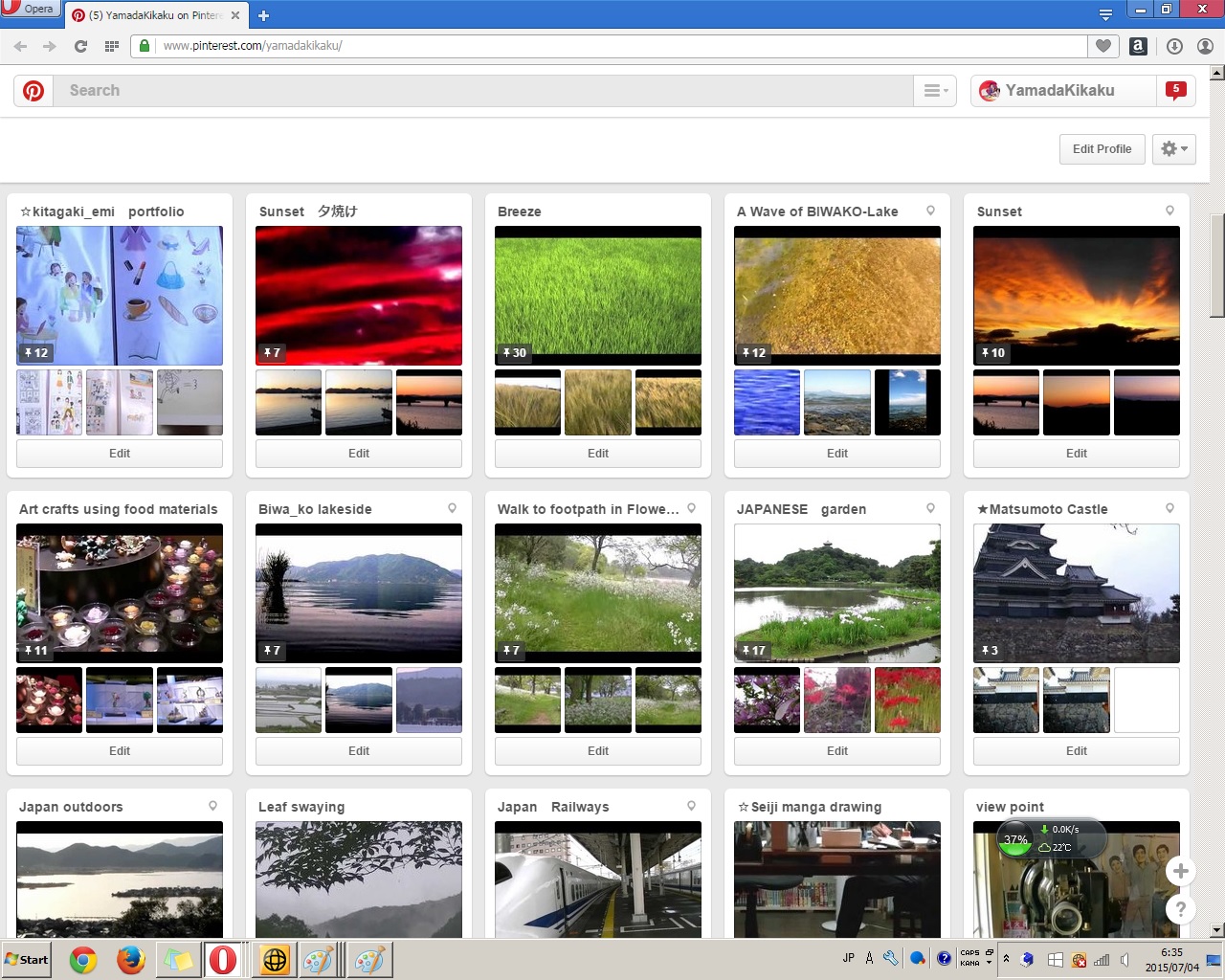 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
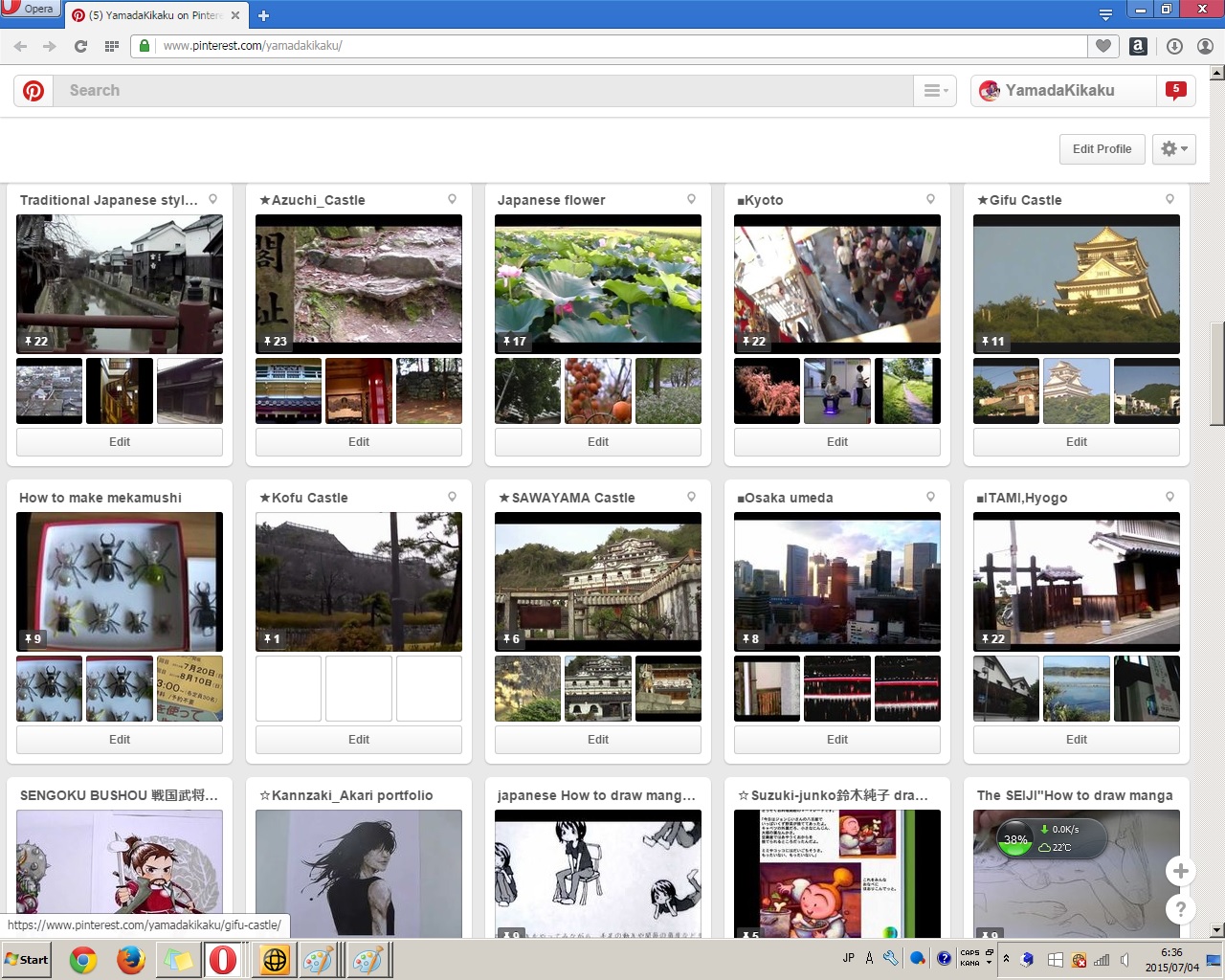 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
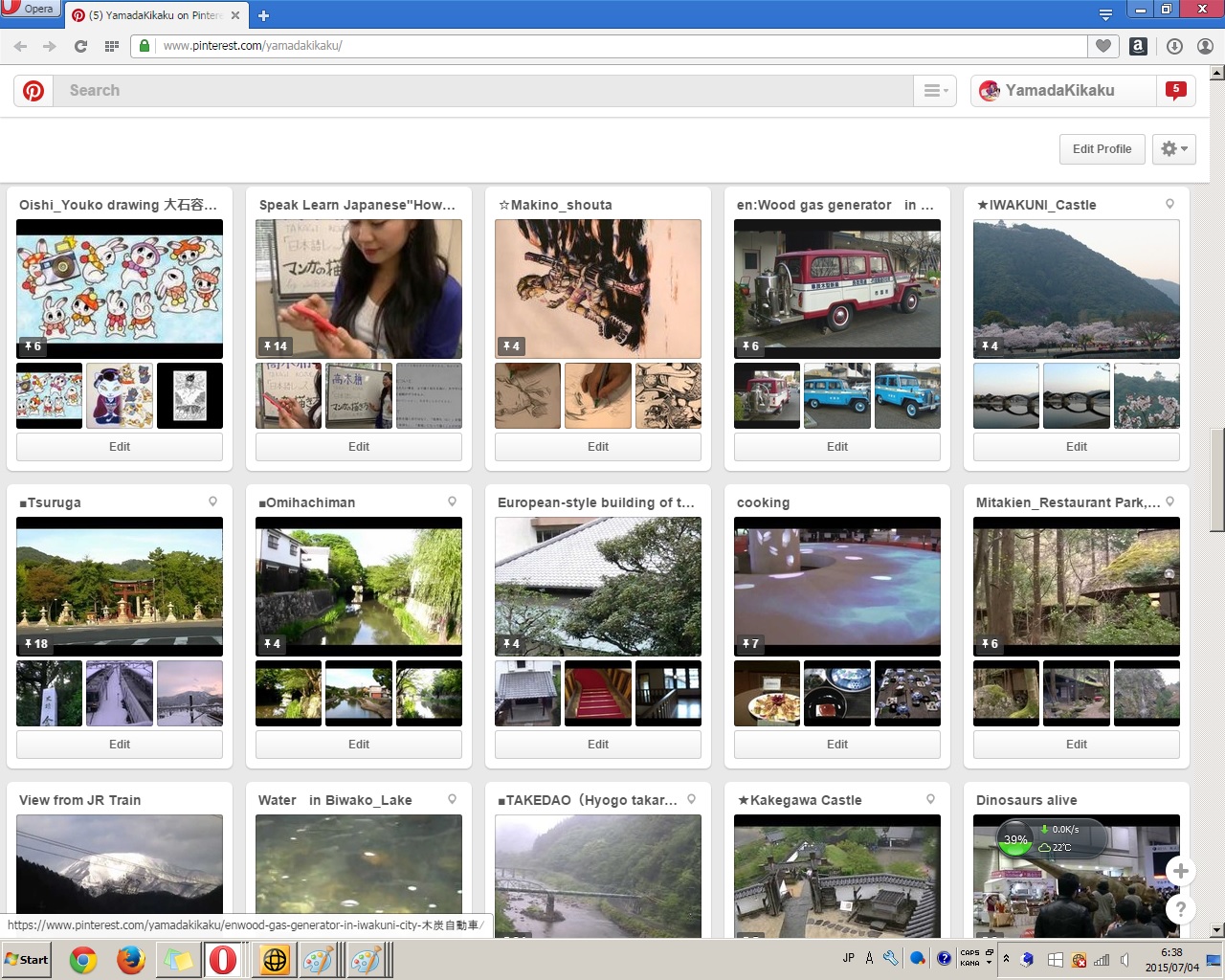 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
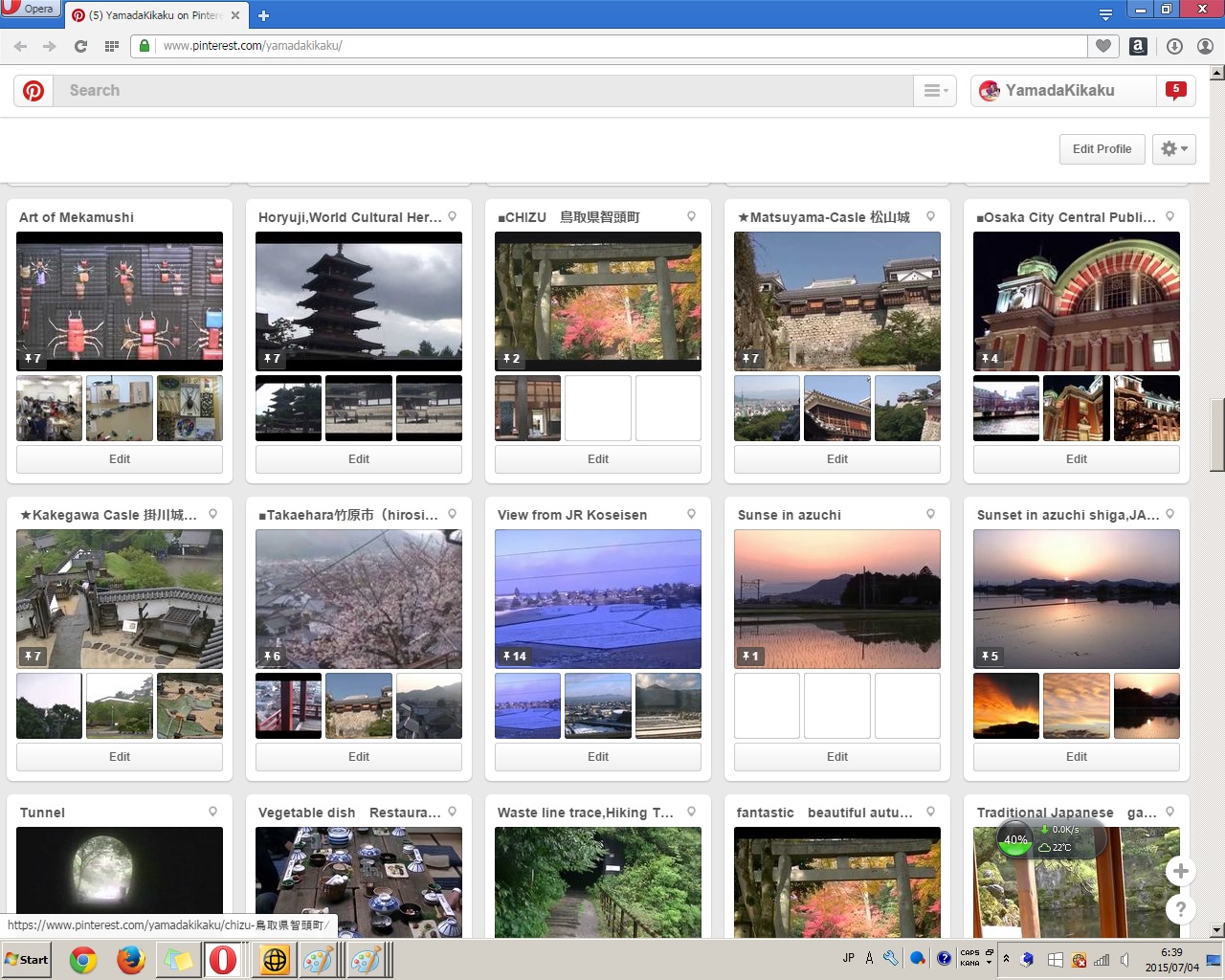 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
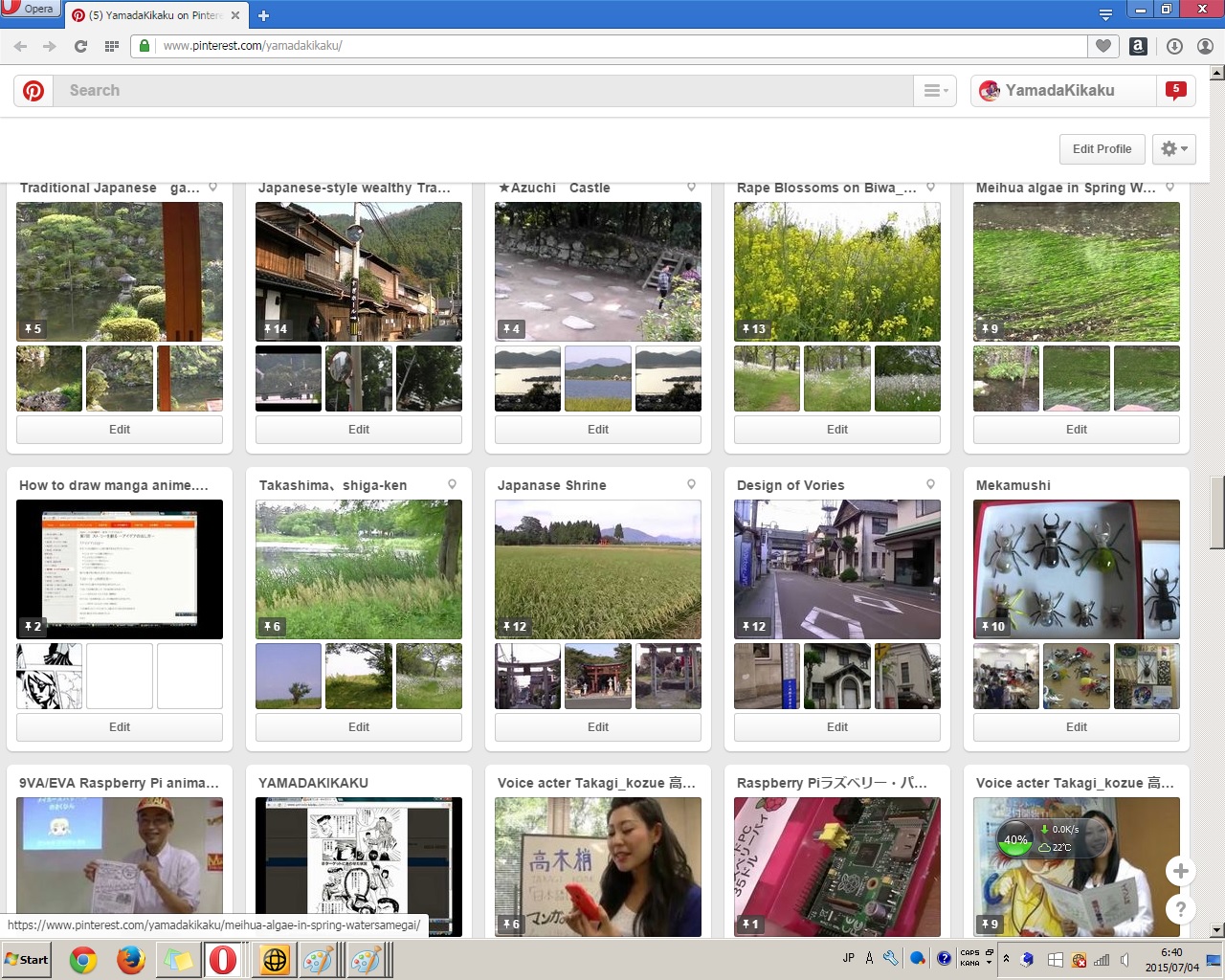 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
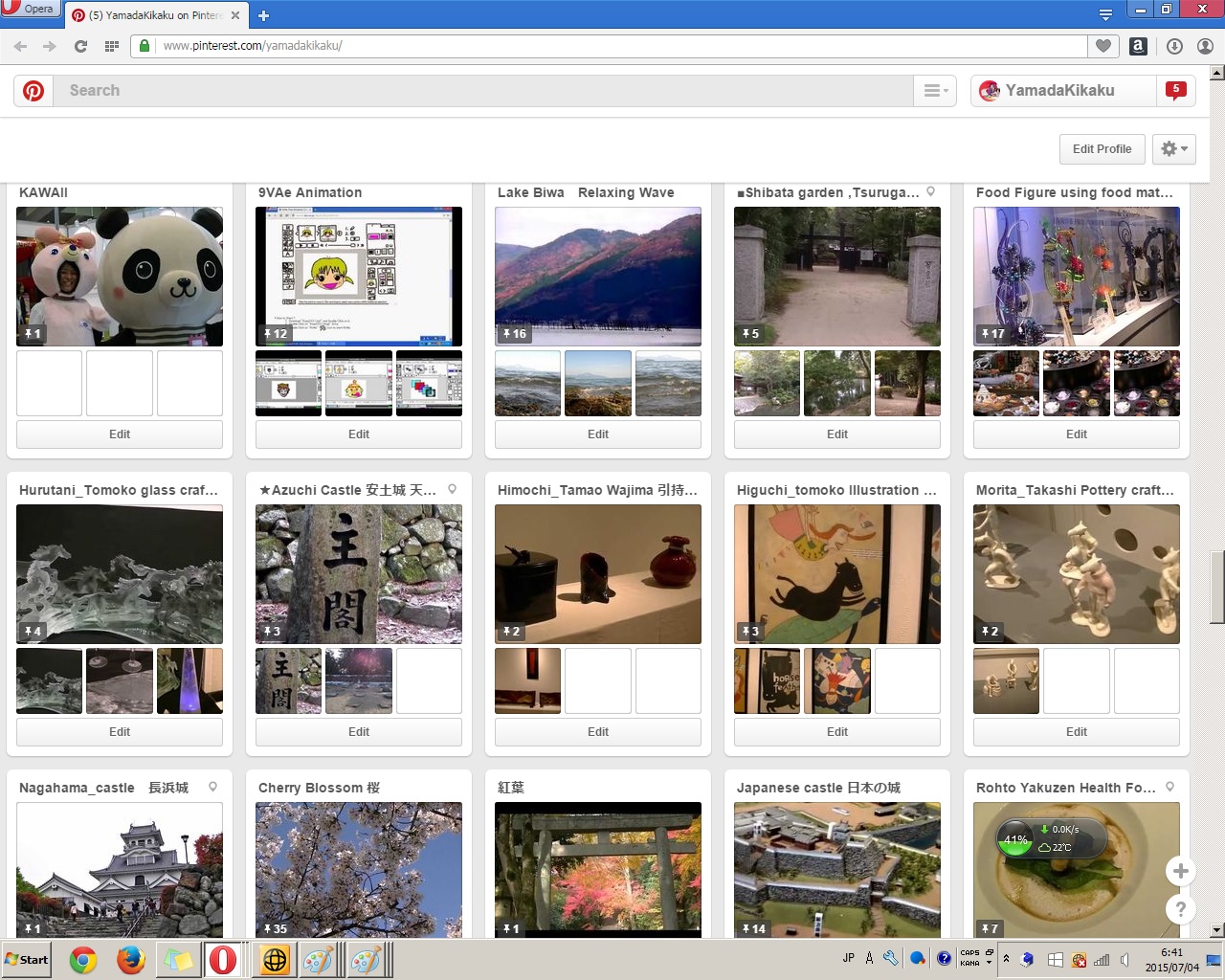 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
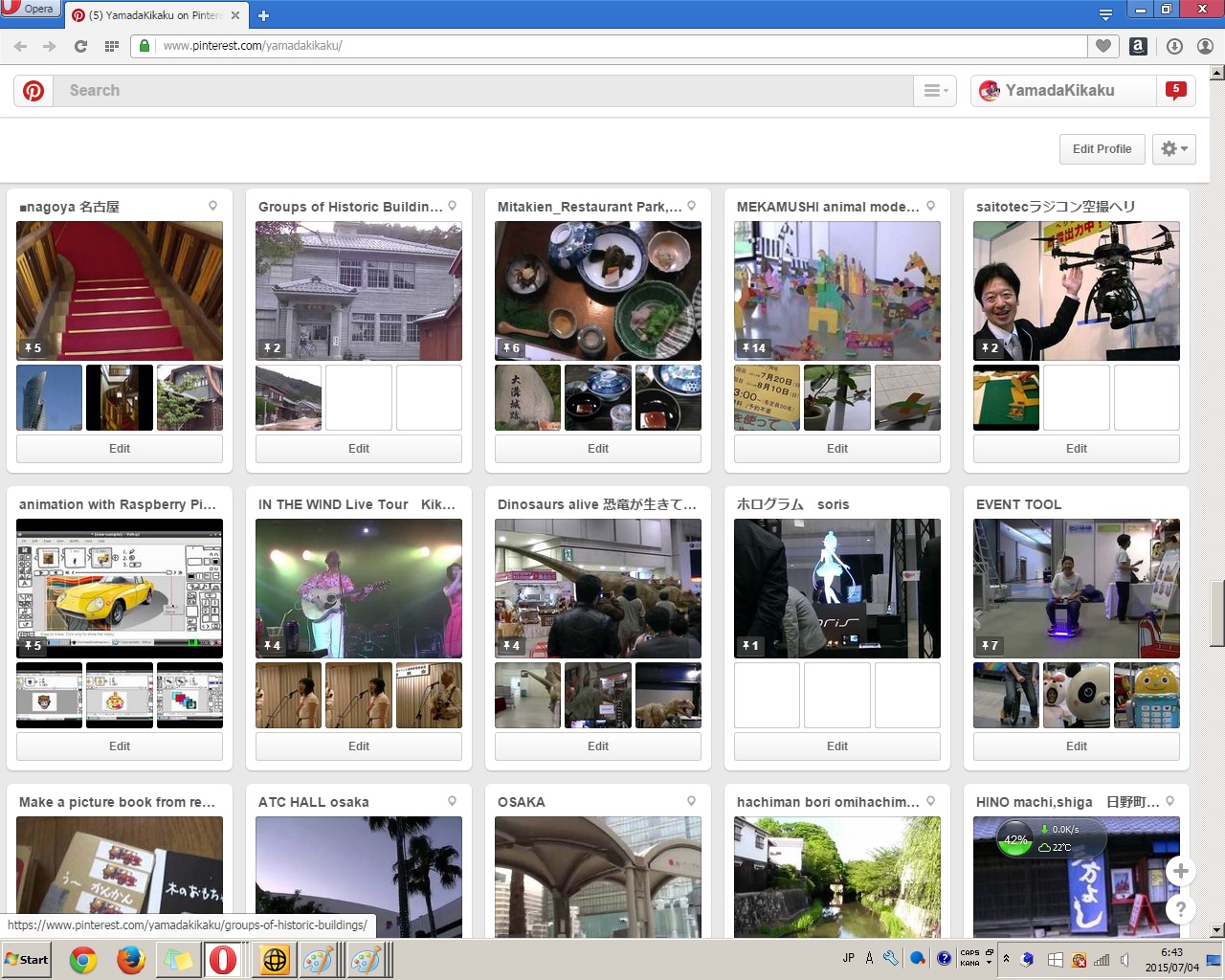 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
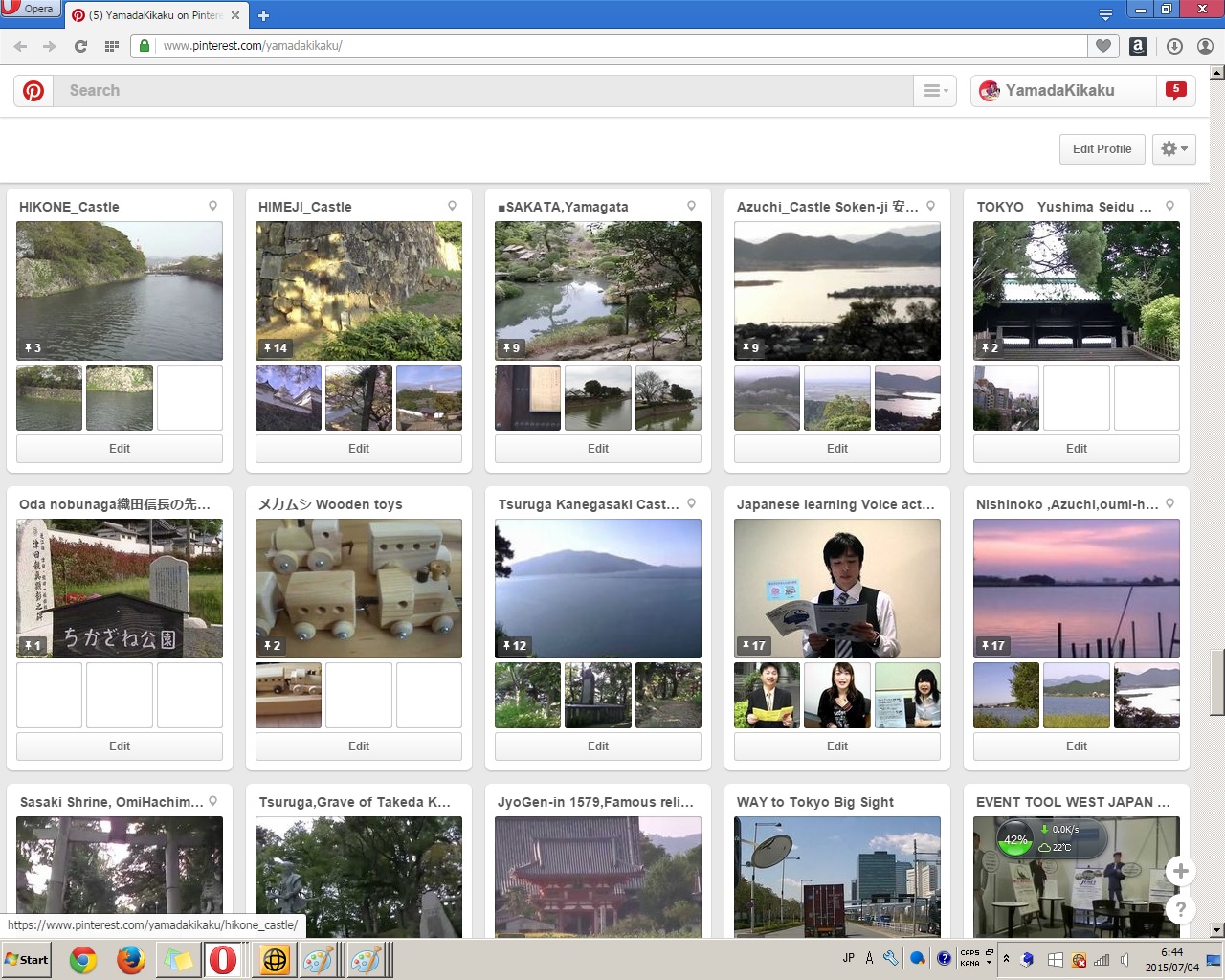 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
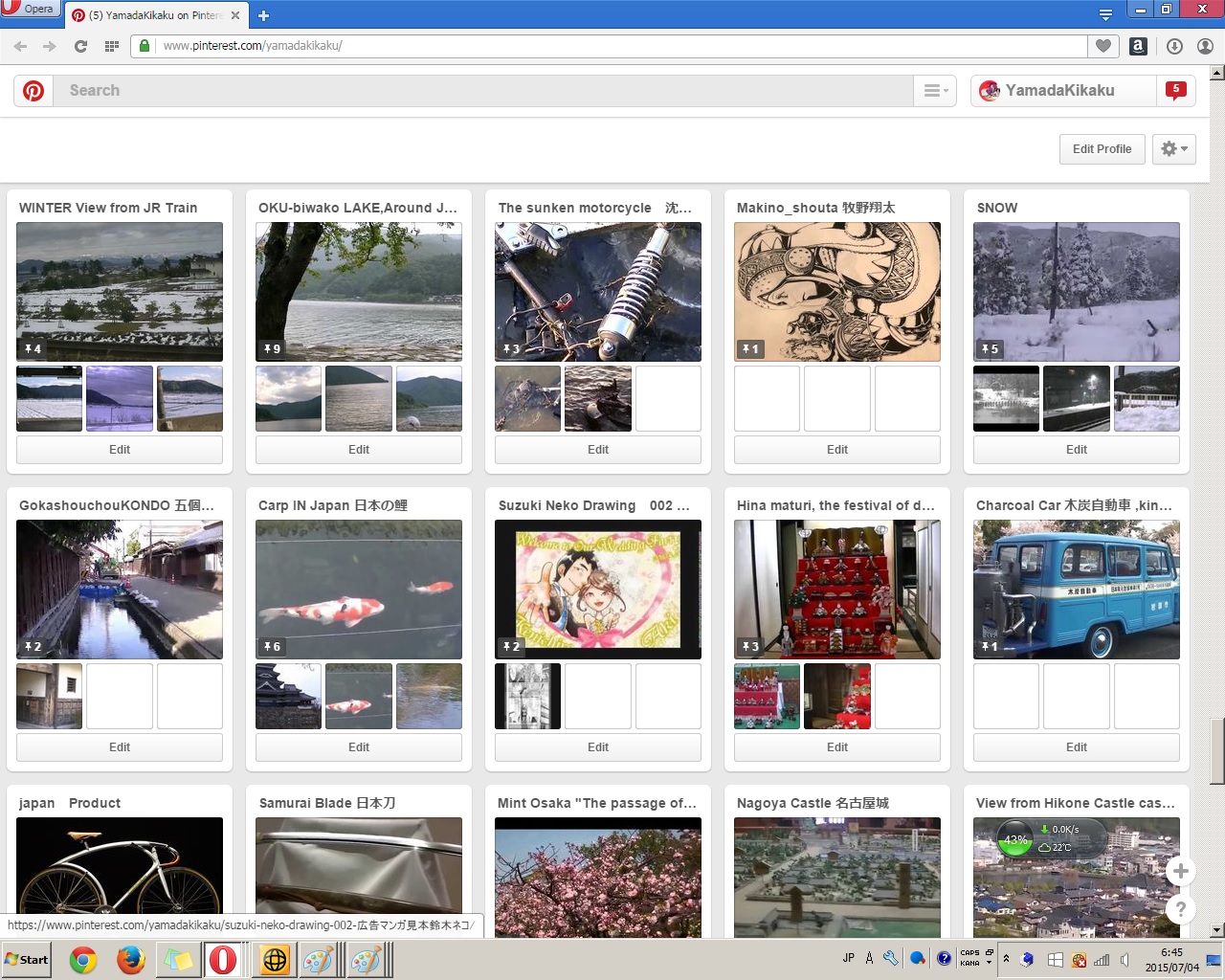 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
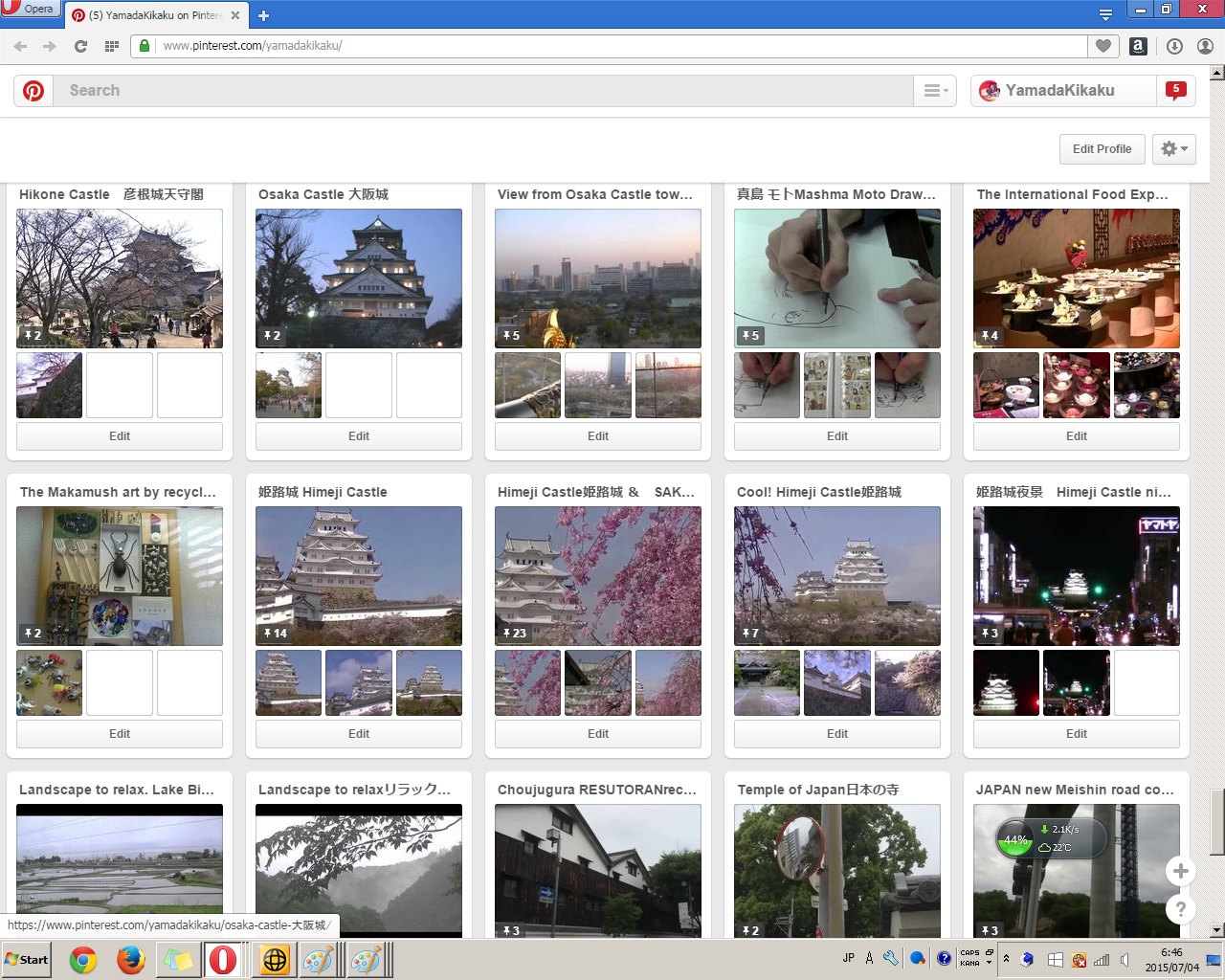 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
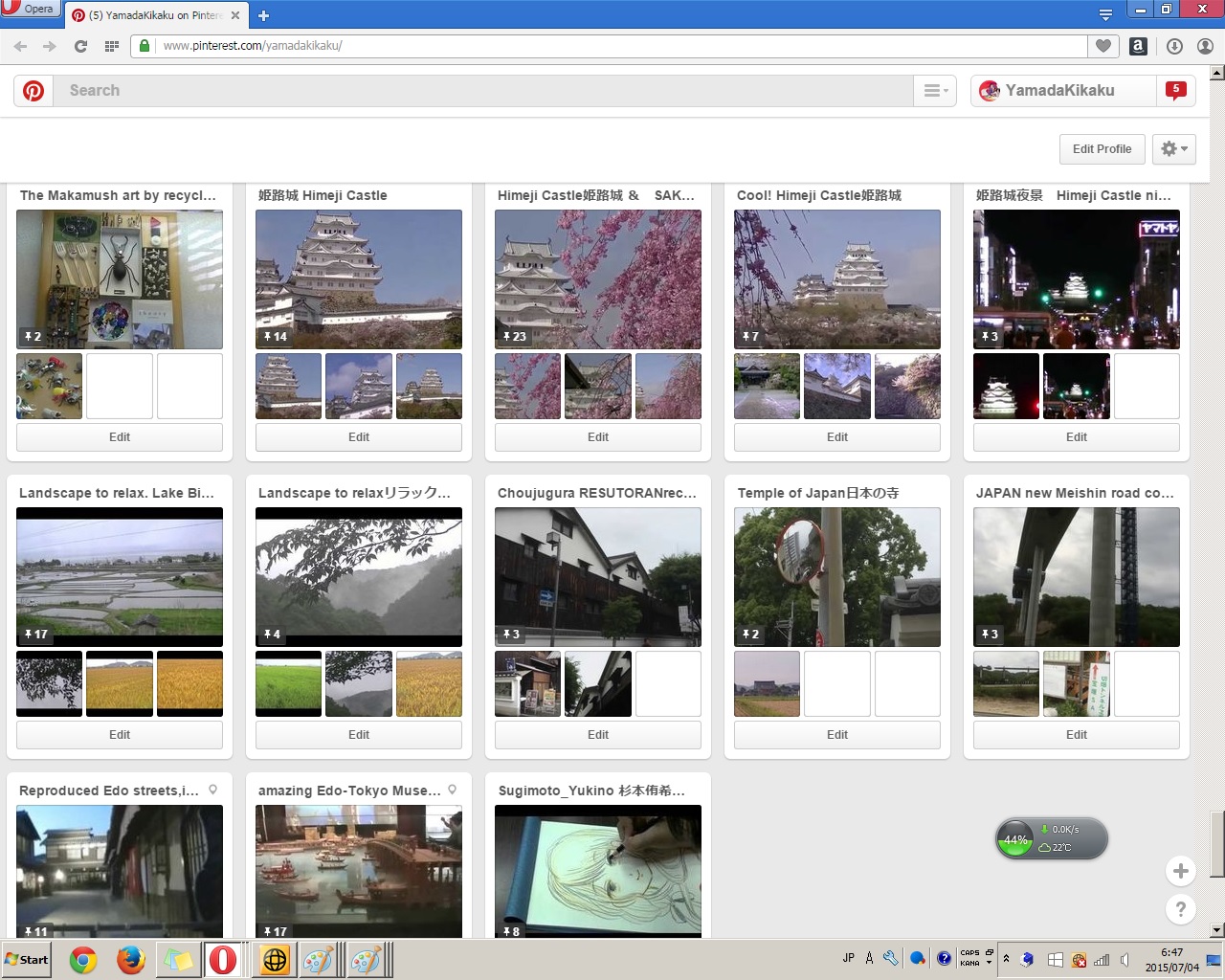 http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
yamadakikaku 山田企画・山田博一の写真帳を御覧ください・
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/ 御覧ください
http://www.pinterest.com/yamadakikaku/
フリーページ
義経黄金伝説ーー作者独白ーー
海からの歴史●発行者独白●
プロローグ■西行、崇徳上皇の霊に会う!

プロローグ02■3つの都市と3人の騎士
第1回■静、頼朝の前で舞う!

第2回■静、鎌倉戦場で勝つ!

第3回■静を取り巻く鎌倉の暗闘!

第4回■後白河法皇の跳梁と深謀は?

第5回■黒田の悪党がたくらむ!
第6回■西行、重源に頼まれる!

第7回■頼朝、西行を驚かす!

第8回■西行、文覚と争う!

第9回■西行、東大寺闇法師重蔵と出会う!

第10回■大江広元、磯禅師とたくらむ!
第11回■義経、奥州平泉にて安堵する!

第12回■磯禅師、過去を思いいやる

第13回■吉次、昔を思いやる!

義経黄金伝説■第14回

「義経黄金伝説」 第15回
義経黄金伝説■第16 回

義経黄金伝説■第17回

義経黄金伝説■第18回

義経黄金伝説■第19回

義経黄金伝説■第20回■
義経黄金伝説■第21回■

義経黄金伝説■第22回 ■

義経黄金伝説■第23回 (改稿)

義経黄金伝説■第24回 (改稿)

義経黄金伝説■第25回
■義経黄金伝説■第26回

義経黄金伝説■第27回

義経黄金伝説■第28回

義経黄金伝説■第29回

義経黄金伝説■第30回
義経黄金伝説■第31回

義経黄金伝説■第32回

義経黄金伝説■第33回

義経黄金伝説■第34回

義経黄金伝説■第35回
義経黄金伝説■第36回

義経黄金伝説■第37回

義経黄金伝説■第38回

義経黄金伝説■第39回

義経黄金伝説■第40回
義経黄金伝説■第41回

義経黄金伝説■第42回

義経黄金伝説■第43回

義経黄金伝説■第44回

義経黄金伝説■第45回
義経黄金伝説■第46回
■■作品解説■■
●スマートフォン用小説hp
●漫画トレーニング、漫画の教科書
山田企画事務所のビジネス日記
山田企画事務所「小説工房」他ブログ
2024.11
2024.10
2024.08
カテゴリ
カテゴリ未分類
(7)源義経黄金伝説(●2010年年代順短縮版)
(109)源義経黄金伝説(2009年版)
(84)義経黄金伝説
(108)お知らせ
(11)源義経黄金伝説●(2012版短縮版)
(109)日本の美しき風景
(6)youtube・HPにマンガの描き方
(9)源義経黄金伝説■2014
(29)日本イベント業務管理士協会
(1)源義経黄金伝説2019年版
(3)YouTube
(2)作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
第1章 一一八六年 鎌倉八幡宮
1
文治二年(1186)四月八日のことである。 鎌倉八幡宮の境内、音曲が響いてくる。
「京一番の舞い手じゃそうじゃ」そこに向かう
「おまけに義経が愛妾とな」
「それが御台所様のたっての願いで、八幡宮で舞うことを頼朝様がお許しになられたのそうじゃ」
「大姫様にもお見せになるというな」
「おう、ここじゃが。この混み様はどうじゃ」
鎌倉の御家人たちもまた、この静の白拍子の舞を見ようと、八幡宮に集まって来ている。
大姫は頼朝と御台所・北条政子の娘であり、木曽義仲の子供である許婚を頼朝の命令で切り殺されたところでもあり、気鬱になっていた。
去年文治元年(1185)三月平家は壇ノ浦で滅亡している。その立役者が義経。その愛妾が話題の人、静。平家を滅ぼした源氏の大祝賀会である。その舞
台にある女が登場するのを、人々はいまか今かと待ち兼ねて、ざわついている。
季は春。舞台に、観客席に桜の花びらがヒラヒラと散ってきて風情を催させる。
その時、どよめきが起こった。
人々の好奇心が一点に集中し、先刻までのどよめきが、嘘のように静まっている。舞台のうえにあでやかな人形があらわれた。
頼朝から追われている源義経の愛妾静その人であった。この時、この境内の目はすべて静に注目している。
衣装は立烏帽子に水干と白い袴をつけ、腰には太刀より小振りな鞘巻をはいている。
静は、あのやさしげな義経の眼を思っている。きっと母親の常盤様そっくりなのだろう。思考が途切れる。騒がしさ。ひといきれ。
静の母親の磯禅師は今、側にはしり寄って執拗に繰り返す。
「和子を救いたくば、よいか、静、頼朝様の前での舞は、お前の恭順の意を表すものにするのです。くれぐれもこの母が、どれほどの願いを方々にしたか思ってくだされ。わかってくだされ。よいな、静」涙ながら叫んでいる。
が、静にも誇りはあった。
母の磯禅師は白拍子の創始者だった。その二代目が静。義経からの寵愛を一身に集めた女性が静である。京一番といわれた踊り手。それが、たとえ、義経が頼朝に追われようと…。
静は母の思わぬところで、別の生き物の心を持った。
要塞都市、鎌倉の若宮大路。路の両側に普請された塀と溝。何と殺風景なと静は思った。その先に春めいた陽炎たつ由比ガ浜が見えている。その相模の海から逃れたかった。
かわいそうな一人ぼっちの義経様。私がいなければ、、
そう、私がここで戦おう。
これは女の戦い。知らぬうちにそっと自分の下腹をなででいる。義経様、お守り下させ。これは私の鎌倉に対する一人の戦い。別の生き物のように、ふっきれたように、静かの体は舞台へ浮かんだ。
しかし,今、舞台真正面にいる源頼朝の心は別の所にある。
頼朝は、2つの独立を画策していた。ひとつは、京都からの独立、いまひとつは、階級からの独立である。武士は貴族の下にいつまでもいる必要がない。とくに、東国では、この独立の意識が強いのだ。
西国からきた貴族になぜ、金をわたさなければいけなにのか。だれが一番苦労しているのか。その不満の上に鎌倉は成り立っている。
しかし、義経は、、あの弟は、、義経は人生において、常に逃亡者である。
自分の居場所がない。世の中には彼に与える場所がない。義経は、頼朝が作ろうとしている「組織」には属することが不可能な「個人」であった。その時代の世界に彼を受け入れてくれる所がどこにもない。
頼朝はまた平泉を思う。
頼朝に宿る源氏の地が奥州の地を渇望している。源氏は奥州でいかほどの血をながしたのか。頼朝は片腹にいる
なぜなら、彼の曾父は
さらに別の人物頼朝は眺める。
その想いの中を歩む心に、声が響いて、頼朝はふと我にかえる。
「しずや、しずしずのおだまき繰り返し、昔を今になすよすがなる。吉野山
みねの白雪踏み分けて、入りにし人の跡ぞ恋しき」
ひらひらと舞台の上に舞い落ちる桜吹雪の中、静は妖精のようだった。人間ではない、何か別の生き物…。
思わず、頼朝をはじめ、居並ぶ鎌倉武士の目が、静に引き寄せられていた。
感嘆の息を吐くのもためらわれるほど、
それは…、人と神の境を歩んでいる妖精の姿であった。
●続く●2014版
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
-
源義経黄金伝説■第2回 2019.01.02
-
源義経黄金伝説■第1回2018版改稿 2019.01.01








