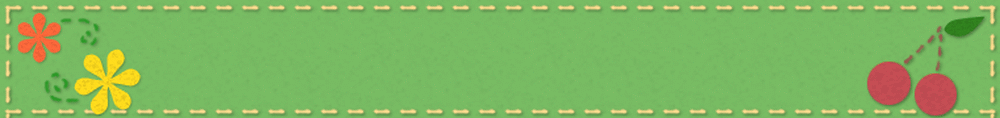2008年11月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
難関校入試について思うこと
私立中学の説明会に行って来ました。中高一貫教育。教育方針、設備、雰囲気・・・どれをとっても最高の環境。もし娘がこの環境の中に入れたら、本当に大きく成長出来るんだろうな。それにしても、私立中学の試験は大変。なぜこんなに難しいのか考えてみた。目的は2つだと思う。目的の一つは基礎学力をしっかりと身に付けた子を選ぶ為。一定のレベルの学力を持った子を選ぶことで入学後の教育をスムーズに進められるから。そしてもう一つの目的は、長い期間頑張り続けられる人を選抜する為。いろいろなことを我慢してずっと勉強を続けられた子は、きっと他のいろいろな困難にも耐える力があると考えられているから。でも、頑張れる子かどうか、そんな方法でしか本当に見分けられないのかなあ。私には、入試は頑張れることを証明するために子供たちがチキンレースをしているようにしか見えない。どこまで我慢できるかを競う我慢大会みたい。ひどい人は、それが大学に入るまでずっと続く。大学に入るまでずっと我慢大会をしてた子が本当に自分の行きたい道に行けるんだろうか。子供の間にやっておくべき大切なことがあるのではないか。子供が経験すべきことをきちんと経験しながら、行きたい学校に行くことって本当に出来ないのかなあ。二兎を追うものは一兎をも得ずというけれど、娘にはあえて二兎を追って欲しい。その結果、うまくいかなくても、またそこから別の道が続いてる。頑張ったことはけして無駄にはならない。人生には無駄なことは何一つないんだから。
2008年11月30日
コメント(2)
-
娘の手作りデザート
今、娘はアイスクリーム作りにはまってます。初めは、ココアや牛乳、バターを使って、何かお菓子を作ろうとしたことが始まりでした。たまたま冷凍庫に入れて固めたところ、アイスクリームみたいになりました。こうやればアイスクリームみたいになるんだ。それから、いろいろな味に挑戦するようになりました。コーヒー味、抹茶味、バニラ味。抹茶はちょっと失敗だったけど、みんなそれなりのアイスクリームになりました。娘は、コーンフレークとシロップを混ぜて固めたり、クルトンにフルーツソースをかけたり、ありものを混ぜ合わせてデザートにしてしまいます。私を驚かせようと、私にないしょで作っています。会社から帰ったときに「冷蔵庫見ちゃだめだよ」と娘が言ったときは何かを作った合図です。ひとつだけ問題があります。本当においしく出来たとき、「パパもうそれ以上食べちゃだめ」と言って、4分の3くらい娘が食べてしまうこと。おいしく出来たときこそ、いっぱい食べたいんだけどな。
2008年11月24日
コメント(0)
-

ラグーナ蒲郡はもうクリスマス
昨日、娘とラグーナ蒲郡に行って来ました。飾りつけもショーの内容もすっかりクリスマスでした。劇にはまっている娘はここのショーが大好きです。いつもは海の冒険物語のショー。その他にハロウィンの時期はハロウィンのショー。そしてクリスマスの時期にはクリスマスのショー。1年の中で3種類のショーがあるために昨年から1年に3回ラグーナ蒲郡に行っています。ショーのメンバーの方が何人かやめられたので、どんなショーになるか心配しましたが、娘は今年のショーも気に入ったようです。ショーはしっかりとビデオに収めてきました。娘は、友達といっしょに歌と踊りを覚えてみんなに見せるとはりきっています。車で片道1時間半。疲れましたが、娘の笑顔を見てると、また連れて行きたいと思ってしまいます。娘の眼はしっかりと輝いています。
2008年11月16日
コメント(0)
-
「どうせ」なんて言わないで
私は、「どうせ」という言葉が大嫌いです。すべての可能性を消し去ってしまう魔法の言葉だから。この言葉を使ったとたんに、人はそこに立ち止まって、一切の努力も思考もやめてしまいます。人はどんなときにこの言葉を使うのだろう。何かをやりかけて、うまくいかないとき。カベにぶつかったとき。どちらにしても、まだ結果が出る前、スタートを切る前に言ってることさえある。なぜ、こんな言葉を使ってしまうのだろう。失敗する可能性を感じ取るから。自分が傷つく可能性を感じるから。人が成長していくものだということを知らないから。背伸びして、やり切ったときの感動を知らないから。たくさんの選択肢、可能性が見えていないから。失敗したときにどうすれば良いかを知らないから。どんなことだって失敗することも成功することもある。だけど、失敗も成功も、必ずその続きがある。どちらにしても、その先にまた、選択肢が広がっている。失敗したあと、どうするか。成功したあと、どうするか。それが見えないから一歩目を踏み出せない。人の成長は階段を上るようなもの。成功は1段上がる。失敗は1段下がる。ただそれだけのこと。そこからまた、いろいろな方向に向かって階段が続いてる。自分がどこに行きたいか。よく考えて次の階段に進めば良い。そして、1段下りたところには、より多くの上りの階段がつながっている。どこの階段を進んでも、どこかでは下る場面がある。下ったときは、一休みしてまた上がれば良い。最後に行きたいところにたどり着けば良い。行きかたは無限にある。そして、行きかたは「生き方」につながる。どうやってそこにたどりつくかは、そのまま、その人の「生き方」になる。ゆっくり行っても、急いで行って、最短距離で行っても、遠回りしても、全部の行き方に意味がある。私がカベにぶつかったとき、私の父が行ってくれた言葉がある。「人生に無駄なことはひとつもない」悪いことがあっても、それは必ず将来の良いことにつながっているのだと教えてくれた。「どうせ」という言葉は、この言葉の反対側にある。こんな言葉は誰にも使って欲しくない。そして、娘にも「人生に無駄なことはひとつもない」と、心の底から考えられる人になって欲しい。
2008年11月09日
コメント(2)
-
叱りの強弱
叱り方の強さを1から10までで表現すると、どんなときが1でどんなときが10になってるか考えたことがありますか?常に10で叱ってたら、子供にとっては、いつもすごく悪いことをしている気持ちになります。そうなると、反応は次の2種類のどちらかになりがちです。1.自分はだめな子だと考えてしまう(原因は自分と考える)2.また怒ってると考えてしまう(原因は相手と考える)どちらにしても、叱られている本当の原因には向かわないことが多くなると思います。逆に、いつも1ばかりで叱っていたら、何をしても叱られないのと同じ。叱る強ささは1が良いか10が良いかというのではなく、叱る内容によって強弱を意識的につけることが、ものすごく重要なことだと思います。強弱は言い換えると「変化」。変化することで違いを感じる。違いの意味を考える。内容に意識が向かう。もちろん、どちらにしても1度注意しただけでは行動は変わりませんが、それでも、ずっと強弱を意識して叱るのと、いつも同じ強さでしかるのとでは、長い間にきっと大きな差が生まれると思います。いつも怒ってしまうのならなおさらです。怒るのは叱るのとは明らかに違います。腹が立ったら叱らずに黙る。冷静になってからきちんと叱る。そうしないと強弱は付けられません。難しいことですが、私はそういう叱り方を理想と考えています。
2008年11月03日
コメント(6)
全5件 (5件中 1-5件目)
1