2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年04月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
ルパン対ホームズ
ときどきお邪魔しておりますむらきかずはさんのブログでルパン派?ホームズ派?の日記がありました。わーい、ホームズ好き。コメント書こう!と思って書き始めたら、コメントどころでない長さになってしまったので、こりゃ失礼だと、自分のブログにとって返し。以下、ホームズへのラブレター。ルパン対ホームズっていったら、私は絶対にホームズ派!一番好きな長編は「恐怖の谷」、短編だったら「赤毛連盟」に「まだらの紐」かな。宮崎アニメも好きでした。映画も見に行って、パンフレットは宝物。「空からこぼれたストーリー」は、そらで歌えます。音ははずれてるかもしれないけど。エンディングもよかった。「24時間 頭の中で 何かがダンスしている人だから」ルパン派の友人に「ルパン対ホームズ」(ルブラン)を例にとられて、ホームズをさんざんにこきおろされたときには、乱歩の「黄金仮面」(明智対ルパン)で敵をとったりしたもんです。ホームズのパステーシュといえば忘れ難いのが、ねずみの探偵、ベイジル。221B在住のねずみで、ホームズの探偵術を足元でお勉強した結果、ねずみ界の名探偵になって快刀乱麻を断つ活躍…って児童書です。相棒はドースン博士。そこかしこ、聖典(ドイル作ホームズ)からの引用やパロディがちりばめられていて、ホームズ好き小学生の心をくすぐったものでした。今は絶版みたい。もったいない!「わが愛しのホームズ」とか「わが愛しのワトソン」とか、BL風味のパスティーシュもありました。BLっていっても、わが愛しのワトソンの方は、ホームズは実は女性だった!っていう、とほほな解釈。でもそれなりに切なくておもしろかったような。ジャンクな小説だったから、たぶん、もうどっちも手に入らないでしょう。マンガだったら、酒井美詠子の「少年はその時群青の風を見たか」がお気に入り。寄宿舎に住んでいる同い年のホームズとルパンの少年友情物語で、ひじょうにワタクシの好みど真ん中ついてきてました。ホームズとルパンが同い年のはずはないので、年表が大胆にずらしてはあるのですけど、知的冷静な黒髪美少年ホームズくん(愛称・シャール)と、ふわふわ巻き毛のお人よし少年ルパンくん(愛称・ラウール)のコンビがとっても愛らしくてよかったのだ。当然、寄宿舎は同室。お互いの正体は知っているので、元気に今日もケンカする。気の毒なのは、スコットランドヤード。二人に憧れて、二人の活躍を記録している少年が、モーリスくん。当然苗字はルブランです。かわいかったなあ、続きでないのかなあ。白泉社のコミックスです。いしいひさいちの「コミカルミステリーツアー」も好き。だけど、読書量がついていってないので、いまのとこ、一冊目しか読んでない。いっぱいミステリ読んでから読んだほうが、おもしろいと思うので。うちの積読本の中には「シャーロックホームズの宇宙戦争」(読みかけ)と「ホームズ対ドラキュラ」があります。河出文庫で「ホームズ贋作展覧会」ってあったのも懐かしい、買い損ねた、くやしい!大和心をくすぐる、漱石とホームズの対決も見たことあります。島田荘司の「漱石と倫敦ミイラ殺人事件」、おもしろかった。あと新潮コミックスで、ほんまりうが絵を描いてた「漱石事件簿」これは漱石とドイルの取り合わせですけど。たぶん、他にもあったと思う。切り裂きジャックとホームズ、ピーターパンとホームズの話も読んだことある。犬の探偵の話もなかったっけ?名前がシュルックホームズとか、そんな感じ。日本人の作家さんで。あー、思い出せない。くやしい!!はんぱにマニアックなこと書いて(だってシャーロキアンな方々の足元にも及ばない)ごめんなさい。でも大好き。ホームズさん。
2006年04月29日
コメント(7)
-
すみれ
かたまって薄き光の菫かな 水巴ひさびさのいい天気だったので、ブライスつれて出勤して、お昼休みに近くの川土手でとってきました。ときどき自転車で通り過ぎる道ですが、ブライスいないと、スミレになんて目をとめることもなかったよ。ありがとね、ロッタ。ワタクシ、幼稚園のときスミレ組だったので、この花をみるとノスタルジックな気持ちになります。幼稚園、好きだったなあ。ものすごく早く登園して、幼稚園の門がまだ開いていないので、フェンスよじ登って中に入り込んで遊んでました。私が子どもの頃は今ほど送迎にうるさくなかったから、一人で幼稚園に通っていたのよ。早起き仲間は何人かいて、先生がくる前に気をきかせてニワトリの世話をしようとしたら、うっかり逃がしてしまったこと、あったなあ。園児5人、泣きながらニワトリの後を追いかけて園庭中を走り回りました。やっと追い詰めると、ニワトリったら、羽根を広げてこちらに飛び掛ってくるし。怖かったなあ。そのときの仕返しで、鶏の唐揚げが好きなのかしらん。あら、なにやらブラックだわ。冒頭の句は「美しい日本の詩 和歌・俳句編」(岩波書店)からの孫引きです。いろんな人の詩歌が載っていて、たのしいです。
2006年04月28日
コメント(2)
-
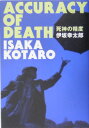
死神の精度
伊坂幸太郎 文藝春秋雨男の死神さんのおはなし。連作短編集でした。死神の話らしく「死」が必ず影を差す話でしたけど、軽い読み物でした。拍子抜けするくらい。こういうが、ライトノベルって奴なんだろうなーって思いました。この死神さん、特段誰かを罰するために現れているわけではないし、懊悩するわけでもない。ただ淡々、「調査対象」の人間と一週間ばかりお知り合いになって、「可」ないし「見送り」の報告をするだけ。可の報告がされた人は、時おかずして、事件事故による不慮の死に見舞われるのです。うーんとマンガで説明すると、えんどコイチの「死神くん」みたいなほのぼの系ではなく、あしべゆうほの「デイモスの花嫁」みたいなセンチメンタル系でもなく、あえていうと明智抄の「仕事人シリーズ」のような淡々不可思議衝撃系?さあ、オタクっぽくなってきた。でもマンガって感じなんだもん。コバルト文庫の「優しい悪魔」(鳴海丈)も思い出したよ。(こちらの悪魔さんは、お間抜けなお人よしでしたけどねえ。レア・ミディアム・ウエルダンって名前の魔女三姉妹が出てきたことくらいしか覚えてないや。)読んだ時期も悪かったんだろうなあ。小説だってわかっていても、不愉快な設定で、読むのにどこか抵抗がありました。収録作のなかでは「恋愛と死神」と「老婆と死神」が好きでした。これを好きだっていうの、ロマンチストぶりを告白しているようで恥ずかしいんですけど。私は特別おもしろかった!って感想ではないので申し訳ないのですが、とても人気のある本らしく、図書館に予約出して半年たって読めましたよ。100人待ち!だったの。たぶん、次の人もてぐすね引いて待ってるだろうから、早く返しにいかなくちゃ。ワタクシが10年をかけて発見しました雨男雨女の法則ってのがありまして、お天気ってのは掛け算で決まるのですよ。雨女(マイナス)×雨男(マイナス)=晴れ(プラス)雨女(マイナス)×晴男(プラス)=雨(マイナス)だから、楽しい行楽に当たって、晴れのお天気をお望みのときには、どうぞ雨体質の人は偶数人でお出かけくださいませ。けっこ、当たります。(あたしの周りでは。)
2006年04月27日
コメント(2)
-
少年・卵
谷山浩子 サンリオ出版図書館で借りました。一度復刊ドットコムで見かけたことがあるので、絶版なんでしょう。サンリオ出版から出ていた谷山浩子の小説、きれいで気持ち悪くて透き通るものが多くて、好きだったんだけどな。「電報配達人がやってきた」とか、「悲しみの時計少女」とか。特に「悲しみの時計少女」はアヤツジの「時計館の殺人」と対をなす作品だそうなので(だって綾辻がどっかに書いてた。)アヤツジストには必須書物だと思います。実際おもしろいのよ、これ。絶版だけど。「少年・卵」は、多重人格のお話。猫也くん、という名前の男の子が出てきて、その魅惑的な名前だけでも、当分、遊べます。猫也くんはねえ、留守番電話を凝視したら、留守番電話になりきることができるんだよ。彼のものっすごい思い込みの力で、本物の留守番電話は破壊され、家族の人たちは、猫也くんという「留守番電話」を通じてしか話ができなくなっちゃうのだ。どうだ、想像できないだろう。(と、自分の要略力不足を棚にあげる。)ヘンな話です。興味おありの方は、古本屋で見かけたら、のぞいてみてください。文庫化しなかったから、あんまり流通してないかもしれないけど。(新潮文庫の「猫森集会」は時々、古本屋でみかけますけどねえ。これの解説はアヤツジが書いてます。)今日はねえ、支所の先輩(といっても、同い年)から指名電話かかってきて、仕事のことを聞かれたので、ウキウキなのですよ。顔がよくって、頭がよくって、仕事ができる人なので、憧れているのだ。体重が私より軽そうなので、恋愛感情は覚えないんですけど。そんな難しいことを聞かれたわけではなかったので、さらりと答えられたのですが、「この子なら知ってるだろう」って期待をかけられたのも、ちゃんと応えられたのも、素直に嬉しかったなあ。ヨロコビついでに本屋によって、寺田寅彦随筆集(岩波文庫)を買って帰りました。十年前から、いっぺん読んでみたかったんだよね。って、のんきすぎです。でも、ウキウキ。
2006年04月26日
コメント(6)
-

兄おとうと
井上ひさし 新潮社劇脚本です。吉野作造兄さんと、そのおとうと、官僚・信次の話です。弟の友達に吉野くんっていたなあ、あだながサクゾウだったなあ、などと思いながら読みました。吉野作造って、何をされた方だかよく知りませんでした。歴史の勉強で、単語として覚えただけ。吉野作造→大正デモクラシー→普通選挙法。この本を読んで、その手触りがほんの少し変わりました。生存権。幸福追求権。日本国憲法の祈りの礎を築いた人だったのですね。明治から昭和へ、その間のわずか15年の個の時代に足場を持って、しっかと目を見開いて、理想だけを追った人だったのですね。吉野作造は昭和に入ってすぐに亡くなったみたい。もし、病に倒れなければ、彼はどうなったのかな。転向したのかな。たとえば芥川や賢治、戦争の時代の前に、命を終えた文学者。ときどき、時代の空気を読んで、死んでいく日本に先んじて旅立つことを選んだんじゃないか、ずるいな、なんて思うときがある。芝居のラスト、歌で終わるけれど、その歌詞はずっしり重い。おしまいの歌だけれど、何も終わらない。私たちは、まだ足掻きの時代のさなかにいる。誰もが、三度のご飯を食べて、夜に温かな夢を見ることができなければ、まだ戦いは終わらない。戦後はいつまでも続く。姿勢を整えたくなる物語でした。さて。井上ひさしなので、笑いの場面もちゃんとあります。ユモレスクの節でへそくりの歌って。思わずごきげんで歌っちゃったよ。「へそくり始めて あれこれやりくり かれこれ10何年」奥様の歌に、「へそくりやられて あれこれからくり かれこれ10何年 笑顔でおねだり 男を丸めて せっせと溜めていく」 旦那の返し。素敵だわ、奥様。
2006年04月25日
コメント(0)
-

密やかな結晶
小川洋子 講談社。(文庫もあるけど、私はハードカバーのこの装丁がとても好き。文字が金で押してあって、ひかえめにひかる。)再読です。10年ぶりかな。一番さいしょに読んだのは、春の初めの風の強い晩のこと。まだ寒かったから、おこたにもぐって一気に読みました。読み終わり、気がつけば、涙がすうっと流れてた。静かに泣いた、初めての経験。半年後くらいに一度読み返したのですが、そのときは、心を滑りました。最初読んだときのインパクトのまま、記憶が残っていて、うまく物語に乗っていけなくて、ちょっとつまんなかった。そろそろ、いいかな。うん、いい具合に忘れているぞ。というわけで、ひさしぶりの読み返し。内容、忘れてませんでした。忘れられるわけない。でも表現のそこかしこを忘れていました。「雪があまりにもきれいに積もっているので、踏みつけるのが怖いほどだった。途中で振り返って足跡がちゃんと自分の後ろをついてきているかどうか、確かめないではいられなかった。」なんでもない場面だけれど、好きです。筋はとっても単純です。はかないファンタジー。「この島から最初に消え去ったものは何だったのだろうと、時々わたしは考える。」ひとつひとつ、何かが消えていく。たとえば、香水。たとえば、いんげん。たとえば、リボン。存在が消滅する。記憶も。女の子の髪を結わえるのは、ゴムだけ。布で結わえることなんて、発想すらできなくなる。揮発していく世界の中で、人々は、淡々と生活をする。けれど異端の人もいる。消滅に侵されない、忘れることができない少数の人たちは、秘密警察に狩られていく。逃れるために、隠れ家にひそむ。どこかナチスのユダヤ人狩りを、彷彿とさせます。小川洋子は、アンネのレポートも書いているし、実際この小説は全体主義の批判でもあるのでしょう。ケストナーの言葉が引かれる壮絶な場面もでてきます。だけど、それだけの話でもないと思う。反ファシズム、と単純にジャンル分けするには、この小説に出てくる人たちは、あまりに無気力です。違う世界を持った人たちが、共通の言語で語り合いながら、決して分かり合うことができない物語でもあるのです。そうしてラブストーリー。とびっきり閉鎖的で、エロティックな。411ページある小説ですが、長さは感じさせません。いま、私が微熱を抱えているのは、この世界に持っていかれたからだと思います。小川洋子の小説の中で、いちばん好きです。
2006年04月24日
コメント(6)
-

びっくり館の殺人
ひっさしぶりの、アヤツジ体験。「びっくり館の殺人」講談社ミステリーランド。「かつて子どもだったあなたと少年少女のためのミステリーランド」の中の一冊です。このシリーズって、何よりも本の雰囲気が好き。びっくり館の装丁、いいですよー。背表紙の文字の金ぱく押しが、なにやら懐かしい感じです。こういう綴じだと、夢中になってなんべんも読んでいるうちに、表紙と背表紙のあいだが緩んで、糸が見えてきたりします。小学校の図書館で、読み込まれたこういう本をみつけると、放課後のにおいがたくさん詰まっているようで、好きでした。だけど、館シリーズを、ミステリーランドで出しちゃうと、常のノベルズ版を本棚に並べている方々は、バランスとれなくて困るんじゃないかしら?まあ、どうせ、ノベルズ版も出るんでしょうが。内容は……正直、不完全燃焼。おもしろいんですよ。ちゃんと、おもしろいんだけど、消化不良の読後感が何がしか残ります。「暗黒館」や「最後の記憶」の流れを汲むのか、オカルトっぽい仕上がりです。幻想的なミステリは好きですが、幻想的な解決はあんまり好きじゃないので、そこが消化不良感のあるところかしら。初期の館シリーズは、途中で本を置いて「勝負!」って提示された材料でもって推理していける設計がおもしろかったのにー。(一時間ほど考えて、おもむろに続きを読み始める。水車は勝って、迷路は負けた。時計は引き分け←負け惜しみ。)暗黒館からこちら、「勝負」できる雰囲気がないのが、さみしいです。幻想の海で溺れそうだよ。びっくり館は一人称です。地の文ではウソを書かない、書けば真実がわかる描写はあえて書かない、ウソをつかずにウソをつく。って、綾辻お得意のミスリード、どうするのかしらと思いつつ読んでいたのですが……そうきたか!綾辻節、健在。そこは、楽しかったです。以下、ネタバレにつき、反転。なにが消化不良って、寄木細工の中に入っていた「HELP US!」の解読ができてないところ。いや、勝手に私が勘ぐっただけなのですが。これ、ほんとにそのまま、(僕たちを助けて、)でいいのかな?もっと深い呪いとかじゃないのかな。寄木細工をもらったあと、三知也くん、水疱瘡にかかったけれど、ヘルプス・ウイルスが原因ですよね。「HELPS!」の綴り誤りってことはないのかなあ。綾辻だし、「楽器」と「鈍器」の読み違え、みたいなものがあってもおかしくないと思うんですけど。三知也くんは英語習ってたけど、俊生くんはまだ英語はわかってないんだもの。ローマ字つづりしたんじゃないのかな。三知也くんの病気そのものが、俊生くんの策略ってどう?三知也くんのお兄さんが自殺した事情と、俊生くんのお姉さんが殺された事情、絶対関わりがある!と思うんですけど、違うのかな。最初、十志雄が巻き添えにしたのが梨里香だと思って読んでたせいもあるんですけど。この二人の不可解な死は、宙ぶらりんのまま。そうして、島田潔は、なんのために出てきたのだ?俊生たちの母、美音は、どこに消えた?「あの事件の犯人は誰だったのだろう。」三知也がこの本のラストで繰り返す自問。「クリスマスの夜の本当の犯人は、誰だったんだろう。」って、ことは。ねえ、綾辻さん、「びっくり館」はこれが全部じゃないでしょう?本当のラストは、他にあるような気がする。綾辻、そういうの、好きそうだし。ノベルズ版の袋とじで、島田潔の語りがついてきたりして。いや、いっそのこと、全書き換えしそうだな。子ども版びっくり館のラストから話が始まる、三人称大人版「びっくり館の殺人」講談社ノベルズ。さてこの推理。穴掘るためのスコップ準備完了なので、はずれたときには、さっさと穴に逃げ込みます。3年後(綾辻の執筆ペース推測。)が楽しみだなあ。どきどき。
2006年04月23日
コメント(6)
-
成分解析
流行ってますね、成分解析。うちのブライスちゃんたちの名前いれて、適当に遊んでみました。どの子も、ほどほどに良いもので出来ていたので、ちょっと嬉しい。ほら、名付け親に感謝しなさいよ、あなたたち。ちょっと気に入った成分だったのが、カフェの木綿ちゃん。トップの写真の子です。木綿の77%は魔法で出来ています木綿の9%は着色料で出来ています木綿の5%はマイナスイオンで出来ています木綿の5%は成功の鍵で出来ています木綿の4%は言葉で出来ています9パーセントの着色料が、不思議なピンク髪の元かしら、なんて。アジアンの実音(この日記の写真の子)の成分解析結果が、実音の89%は大阪のおいしい水で出来ています実音の6%は気の迷いで出来ています実音の4%はミスリルで出来ています実音の1%は言葉で出来ていますなのも、ちょっと笑いました。さすが実音!我が家随一の哲学娘・トラベラーだけのことはあるじゃない。ブライスばっかりネタにするのもなんなので、ワタクシの本名で。*****の97%はビタミンで出来ています*****の3%はマイナスイオンで出来ていますワタクシがこんな体に良さそうな成分でできてるなんて、にわかには信じがたい。胡散臭い。ありえない。じゃ、今度は、とおり・ゆうで。とおり・ゆうの66%は電波で出来ていますとおり・ゆうの26%は祝福で出来ていますとおり・ゆうの6%はお菓子で出来ていますとおり・ゆうの1%は言葉で出来ていますとおり・ゆうの1%は成功の鍵で出来ていますあらん、結構いいじゃない。素敵じゃない。66パーセントが電波だなんて、ブログネームにぴったりだわ。お遊びですけど、ちょっと楽しいです。いかが?追記。フリーページの、我が家のブライス紹介、やっとミギワと連理と実音、載せました。うわあ、気がつけば7人もいたよ。
2006年04月22日
コメント(9)
-

りかさん
再読です。でも一回目に読んだときは、偕成社のハードカバーで読んだの。今回読んだのは、新潮文庫。偕成社「りかさん」に加えて、文庫書下ろしの「ミケルの庭」が併録されています。 物語の時系列で拾うなら、「りかさん」から「からくりからくさ」そして、「ミケルの庭」。「りかさん」と「からくりからくさ」は独立した物語として読めるけれど、「ミケルの庭」は、「からくりからくさ」読んでから読まないと意味がないです。それくらい、純度が高い。朝、起きぬけに読んで、今までぼうっといます。(かなしい)感情が、心臓の下のほうで、ふつふつとしてしまう。もしも願いがかなうなら、小学校5年生のときに偕成社の「りかさん」読んで、二十歳過ぎてから、「からくりからくさ」読んで、社会人になって少しくたびれたころ、新潮文庫の「りかさん」みつけて「ミケルの庭」を読みたかった。それくらい時に馴染む。手を伸ばして、狭間を越えたくなる。「からくりからくさ」で共同生活を営む4人の女性は、みんな、感性豊かで、センシティヴで、陽気でご機嫌。そうして、当たり前にそれぞれの事情を抱えています。過去だったり、家庭の事情だったり、ルーツだったり。漠然とした曖昧な悩み、困難、不安を抱える4人のなか、いちばん手触りのはっきりした世俗の困難にぶち当たっていたのが、紀久さんです。紬の研究家。こつん、こつん、根気強く時をかけて機を織る彼女。彼女なら耐えられる。だから、天命により、彼女には困難が与えられた。彼女なら、昇華できるから。ミケルはマーガレットの子供です。文庫についている解説は人形史解説家の小林すみ江さんが書かれています。「ミケルの庭」は、ミケルの話だ、という解釈のようです。なるほど、そうも読めるのかな。だけど、私は違うと思う。「ミケルの庭」は、紀久の話だ。はたから見たら哀れにも思える、けれど、叶えられた紀久の祈り。使い古された言い回しだけれど、ミケルの庭のラストは、瞬間の永遠。泣き出すことも、できやしない。
2006年04月21日
コメント(2)
-

比類なきジーヴス
いやはや、ジーヴス、腹黒だわ。だめだめ坊ちゃんバーディくんと、世界最高の執事ジーヴスの、華麗なる日常が、黄昏の大英帝国にて描かれます。お人よしバーディが巻き込まれるトラブルを、ジーヴスは、自分だけが傷つかない方法で、スマートに悪趣味にすりぬけていく。ジーヴスって、トラブルの収拾はしているけど、解決はしてないよねえ。トラブルの大本は、ほっといてるんだもん。根本的に解決するのは、たぶん、めんどうくさいんでしょう。「はい、ご主人さま。」「かしこまりました、ご主人さま。」丁寧な物腰で、バーディの要望に完璧に答えながら、バーディの世間的な評価を地の底にアタックで叩き落す執事ジーヴス。すごいです。メアリー・ポピンズの方が、よっぽど性格がいいです。メアリは意地悪でうそつきで虚飾家で自信家だけれど、悪気はないし。あー、でも、ジーヴスにも悪気があるわけじゃないのかな。朝、自然に目が覚めるまでバーディを眠らせて、起き抜けには紅茶をいっぱい差し上げて。ベッドの中で、まずおめざ。お昼にお友達と遊びにでかけ夜にお酒を呑んでごきげんで帰るお坊ちゃんに、おおせのままのウイスキー・アンド・ソーダをご提供。でも、決して坊ちゃんを甘やかしているわけではないのです。職務だから、やっているのよね、ジーヴス。バーディの人間性を認めているわけではこれっぽちもなく、執事という職に屈辱を感じているわけでもなく。バーディはお人よしのお馬鹿さんで、世間のためにはちっとも役に立ちません。働かなくても食べていけるし、スポーツといえばギャンブルだし、お酒は好きだし美食家だし、なんて退廃的な英国貴族の生き残り!気のきいた言い回しができて、膨大な警句の引用ができて、頭が悪い人ではないと思うんですが。どうやっても、賢くはない人です。作品中、やたら贅沢をするのですが、ちっともうらやましいと思えない。だけど彼は、絶滅寸前の、英国紳士。生温かい目で、見守ってあげなければ。なんかねえ、ジーヴスの仕事って、トキのお世話係さんみたいなものかもしれない。ヘンリーのような給仕を求める人には向いてないと思います。メアリー・ポピンズが好きな人にはお勧めです。(映画版の優しいメアリじゃなくて、本の方のメアリね。ふんと鼻を鳴らすメアリの方。小学生のとき、一緒にメアリーポピンズ読み始めた友達は、途中でメアリの性格についていけなくなって本を投げ出した。私はメアリー・ポピンズが好きでシリーズ読みきりましたが、彼女に家庭教師はして欲しくない。こわいもん。)黒後家蜘蛛の会(1)
2006年04月20日
コメント(2)
-
野球観戦
日常と冒険のあいだのドアを細くあけて、今夜、小さな冒険に滑り出してみました。「ただいま!」広島市民球場に行ってきました。残業中の無駄話。「今日、ちびまる子ちゃん、ドラマの放送あったよね?」「あ、ビデオ撮るの忘れた。」「だいじょうぶ。広島は今日、カープ中継だって。」「うそ!?カープの中継じゃ、数字とれないじゃん。絶対、ちびまる子、やってるって。」子持ちの先輩方が騒いでいるのに、ひょいと口を出しました。「ちょっとテレビつけてみれば判りますよ。客溜りのとこのテレビ、もうお客さんいないし、2,3分ならいいんじゃないですか?」で、しばらくして、先輩たちが興奮して帰ってきたのですね。「ちびまる子ちゃん、やってなかった。野球中継だったよ。」「へえ。カープ、勝ってました?」「うん。10点とってた。」「10点!?」今季のカープはほんと打てなくて、2点までしか取れない試合ばっかなのに。一回だけ、4点とったっけ。むずむずしてきました。「それでね。カープのピッチャー、まだノーヒットのピッチングなんだって。」がまんできない。「……私、今から、球場行ってきます。」「えっ、今から?」「この書類、整理したら、行きます。」「……一人で?」「はい。」だって今日、ケータイ、家に忘れたんだもん。思いつきで、友達も誘えないよ。で、飛び出しました。職場から市民球場までは自転車で8分。外野自由席1500円と、内野自由席2000円。ちょっと迷って、内野の方を選びました。広島市民球場は、基本がガラガラなんですけど、特に内野自由席は空いていていいのです。広島カープ応援名物、トランペットと山びこ応援も、内野ではないし。青いベンチにぽつんと腰掛けました。夜なのに、変に明るい緑の球場。ぼやけるような白い照明。電光掲示板。劇場に散らばるユニフォームを着た選手たち。夜空がぽかんと開けていました。ものすごい開放感。生ビールを買って、こくりと飲みました。外で飲むビールって、どうしてこう美味しいんだろ。私、気持ちのいい場所に一人でいると、無性に本が読みたくなるんですけど、おかしいですか?人がわあって騒いでる中にいる孤独に、落ち着けるときがあるんです。高橋直子の競馬エッセイが大好きなんですけど、一番さいしょ、確か「競馬の国のアリス」のあとがきに、神宮球場に通っていた頃のエピソードがあります。直子さんは現代詩手帳の編集をしていて、原稿のゲラをかかえてタクシーで球場に行って、人少なな球場の上の方の席に陣取って、西日と照明で校正をしてたって。(誰も私にかまわない場所。)似た感覚なのかなって、思いました。ダグラス投手のノーヒットノーランはならなかったのものの、カープはめでたく勝ちました。つったって、「ぼくらのカープ」を高音で歌って、気持ちよかった。またやっちゃうかも。一人でカープ。
2006年04月18日
コメント(6)
-
五条の縁
月の光の降りしきる夜、少年は少年に出会う。彎曲する橋の欄干に、かの少年は腰掛けていた。裾短な、白の上衣。白の袴。昔、鞍馬で己が着ていたような。僧兵くずれか?欄干に長刀を立てかけて、可憐な少年は月を見ていた。とても数多の武士の刀を狩る者には見えぬ。けれど、太刀を奪われた者たちは、皆震えながら言った。初めは少女のようだと思った。だが、それはまぎれもない鬼だった、と。俺はだまされぬ。義経は息を潜めて問いかけた。「お前が、鬼か?」華奢な少年は、微笑んでこちらを見返した。「なつかしや。そういえば、鬼子と呼ばれたことも、ありました。」刀でぷっつりと凪いだのだろう、彼のざんばらな髪先のひとつひとつに、月のしずくが宿っていた。不覚にも、美しいと思った。少年は欄干の上に立つ。ふわり両手を広げると、両の袖が夜風を受けてはためいた。「鬼とも魔とも、天子とも。月の光の化身でしょうか、花の精とも呼ばれたことも。宵の夢かもしれませぬ。僕はうつつか、まぼろしか。ただひとつある、たしかなまこと、」彼は手をさし伸ばし、歌うように告げた。「この橋は、刀を持っては、渡れません。」「なにゆえに。」太刀に手をかけ、問いかけた。「我は九郎義経なり。武士の子なれば、太刀を手放すこと、できず。」朗々と、名乗りをあげる。すると、少年は、うっすらと笑った。「魔に名乗るとは、無用心。いっそ、言の葉に、呪をかけましょうか。」「呪など、いらぬ。それよりも、俺の問いに答えよ。なぜに、刀を狩る。」「問うたことすべてに、答えが返ると、君は信じているのですか。」「問うことをやめれば、真実は手に入らぬ!」「真実では、人を救えません。だが、問うことをやめぬ君に聞こう。君の太刀は、何のために?」「兄者のために。」「兄のためには、この橋の先にいる、太刀持たぬ人を切るか。答えよ!」彼は、足音を立てない軽い身のこなしで、義経の目の前に飛び降りてきた。「切らぬ。」「なにゆえ。」「お前が欲しいからだ。」少年は目を瞬かせた。「ひとつ。技量の差を見定め、長刀での勝負を挑んでこなかった。ひとつ。俺の度量を試すため丸腰で俺の前に立った。ひとつ、隙のない身のこなし。懐に短刀でも隠していたか?その技量、知力、胆力。見逃せようか。お前、俺の友になれ。」ふっと少年は気をゆるめた。一歩を退いて、懐から抜き身の短刀を取り出してみせた。「僕の名は、武蔵坊弁慶。」笑った。ライトノベルとして書いてみました。ネオロマンスゲーム「遥かなる時空の中で 3」をやってから一度書いてみたかった、義経と弁慶の出会いです。ハルトキ抜きにしても、義経・弁慶って好きなので。源平時代に五条大橋がなかったことくらい、知ってるもん。ハルトキのおかげで、何やったっていいって気分になっちゃったし。というわけで、とっても自由に書いています。弁慶についてはいまだ、実在すら確定していないとか。義経と弁慶・同一人物説をどこかで読んで、物語としてとても気に入っています。二人の幼名は、牛若と鬼若。二人とも、早くに親から引き離されて寺に預けられた子。そこで暴れて飛び出した少年。刀狩をしているのが義経で、弁慶が止めにきたとしてもおかしくない。それなら、役割はそのままに、容姿を取り替えちゃえ。いやまて、それよりいっそ、二人とも華奢な少年にしちゃえ。(弁慶のが可憐になっちゃったのが、ハルトキの影響。)ってんで、こんなお話です。途中、弁慶の惑いの台詞はちょっと鏡花をもじりました。へたくそですが。
2006年04月16日
コメント(4)
-
喜久屋があった場所
「喜久屋」って名前の料理屋さんが、ありました。大学移転のため、人少なになった町の片隅にある、古い木造の黒い家でした。すすけた木の看板に、くすんだ金の文字で「喜久屋」とある。料亭です。でも商店街にあるだけあって、庶民的。一階はカウンターで、近所のお年寄りが、ちょっと寄って、お酒を呑んで話をしていました。透き通ってきらめくコップ。まったりと眠い酒。一番すみっこにあるレジの横では、娘さんが本を読みながら、お客さんが立ち上がるのを待っていました。二階の広間は、忘年会で使ったことがあります。十人で行って、二十畳はある広い部屋に通されました。祖父母の家に、似てました。掃除はきちんとされているけれど、薄暗い。飾りのない蛍光灯。ふかって踏み込みそうになる畳敷きの床。お手洗いも広い。けど、男女共用。床の間にかかる掛け軸。活けてある紫の花。いなかの家。(ねえ、ここで酔っ払ってつぶれても泊めてもらえそうだね。)はしゃいだ声がひどく響いて、タイミングよくふすまを開けて挨拶にこられたご主人がくすくす笑われました。(泊まっていかれますか?座布団はあっても、お布団はありませんよ。)なんて。きちんとしたお料理が出ました。ふぐのお刺身。上品で控えめな出汁のきいた煮物焚物。冬だったので、メインはお鍋。阿波尾鶏の鍋。(これってそのまま、あわおどりって読んでいいのかな?)(ええっ、まさか。あ、でも。)今でもデパートのお肉屋さんで、阿波尾鶏の名前を見ると、ふふふって笑ってしまう。薄暗くて広くて、声が響いて、あっけらかんとした無邪気な夜を。水曜日、その町を通りかかったら、お店があった場所に、小さな空き地と、緑色のショベルカーがありました。ふわっと空まで伸びる空間に不吉な予感はしたけれど、裏の仕出しの店舗は崩さず残っていたし、だから建て替えなのかな、と思いました。確かめようと、職場の先輩にメールしました。ここの店主さんは、彼と同級生だったはず。「火事で倒産。」短い返事が来ました。家族でずっと続けてこられたお店でした。どなたにもお怪我はないそうです。雨が。その日、激しく落ちれば、よかったのに。
2006年04月15日
コメント(2)
-
からくさ・まねっこ
「からくりからくさ」を読んでいると、雑草が食べたくなります。口の中かたく当たる葉。カラスノエンドウのお味噌汁。以前「雑草を食べる」ってハウツー本、図書館で借りて、職場で読んでたら、家計を心配されました。いや、確かに心配されるに足る家計ですが。(同情するなら金をくれ。古い。)広い庭がなければ雑草も採れません。祖母の家の裏庭で、今年こそはスギナのお茶を作りたいな。それから、読んでるうちに、なんとなく手も動かしたくなったので、紐を結びました。お話に出てくる人達の、草木染めや機織り、の手仕事。そうっと添いたくなったので。そして、横にはブライス。最初に「からくりからくさ」読んだ四年前には家には人形いなかったのにな。市松人形のりかさんほど不思議な力はないけれど、すっと内側に切り込んでくるような人形が、今、側にいます。ざわりと静かな世界。とおくに雨はおちていきます。
2006年04月12日
コメント(2)
-
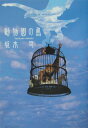
動物園の鳥
坂木司 東京創元社ひきこもり探偵シリーズ、第三作。三作の中で、一番、好きでした。ひきこもりの鳥井くんと、その友人坂木くんが、少しずつ自立を模索し始めたからだと思う。前二作は、繊細に繊細に二人の関係がつむがれているのがどこか内向きだったけれど、今回はじめて、空に向かってベクトルが伸びたような。その印象も、本の表紙の、空色のせいかもしれませんが。籠の中の楽園が崩れていくようで、ほんのすこし、さみしい感じもおこるのだけれど。でもいいんだよね、鳥井くん、坂木くん。君たちは砂糖菓子のお城をくずすかわり、とびきりの紅茶を淹れて、今度は甘みを体内に取り込むんだ。君が困ったときに、手を差し伸べることが、できるように。今回、初めてかな、人の悪意が描かれました。さきの二作は、ずるさや卑怯が隠れる事件もあったけれども、理解を求めての足掻きに付随するものだったので、あんまり不快じゃなかったんです。いや、やっぱり今回の悪意も、理解・共感を求めての足掻きかな。でも嫌だった。その悪意は、弱い者への、いじめだったから。鳥井くんを、ひきこもりに追い込んだ、銃だったから。想像力のなさは、殺意なく悪意のみで、人を殺せる。人の心をひねりつぶせる。その「彼」と、誰からも好かれようとする「いい子」を、同じ種類の人間だと指摘する鳥井くん。ちょっとぐらぐら考えちゃった。大体、人に好かれようとしない人なんて、滅多にいないでしょう?私は「いい子」になりたかった。「いい子」でいると反発くらう。知らない訳ではないけれど。思春期に読んだら、きつかったかもなあ。高校生のとき、「あなたはいい人だと思うけど、好きになれない」なんてクラスメイトに言われてしまって、ずいぶんと落ち込んだことありました。誰からも好かれるなんて無理だって、わかっているけど。せめて胸に秘めててくれたらいいのにな、なんて。結局、そんなこと言った彼女もいい人で、2,3日後には普通に話もしてましたけどね。(彼女の友人と私が仲良くなったことに嫉妬めいた感情があって、それで八つ当たりされたんだと思う。で、私がそういうの察してしまうから、また疎ましがられるのだ。ごめんね。でも、しかたないんだよ。)部活の後の夜道で肉まんを頬張りながらした「神様」の話、図書館の机に腰掛けて足をぶらぶらさせて話した「道徳」の話、テストの点に落ち込んだとき背中に抱きついてきた友達の温みを感じながら話した「見栄」の話。の、かけらが物語の後半、これでもかって突っ込まれていて、懐かしいような、むずかゆいような。ひきずっていたもやもやを、鳥井くんに、きちんと言葉にして取り出してもらった気持ちです。ありがとう、鳥井くん。ところでね、君の尖がった話ぶりは、苦手だよ。ひととなりが好きだからいいけどさ。ふふん、大人になった私は、今や怖れずにそれくらいは言えちゃうのさ。ひきこもり探偵は、部屋を出て、世界へ向かう窓へ向かって歩き始める。だいじょうぶ。涙もろい友達は、君を待っている。
2006年04月11日
コメント(0)
-

「青空の卵」と「仔羊の巣」
坂木司 東京創元社いつから「創元クライム・クラブ」はソフトカバーになったのかしらん。次の「円紫さんと私」のシリーズがいきなりソフトカバーになったら、さみしいな。北村薫の本って、ぱさぱさした紙の文庫か、きっちり角のとがったハードカバーか、どっちかのが似合っていると思うんです。まあ、「街の灯」はソフトカバーだけどさ。続編、出ないのかなあ。出て欲しいなあ。っと、脱線。坂木司には、ソフトカバーのが似合うと思う。やわらかくて、かるい。小説の内容に合います。ひきこもり探偵・鳥井くんと、彼の心の拠り所・坂木くんの物語。一部でBLぎりぎりって言われているという、ふたりの友情。この二人、共依存の関係だと二人して自覚して開き直っているので、少々タチが悪いです。現実を描いている割に、リアリティは薄め。系統としては、北村薫、加納朋子の流れを汲むんでしょうが、同じ牧歌的風景にも坂木司の物語では紗がかかります。「こんな夢のような話、絶対にない。」読みながら思ったのが、「少女マンガに似ている。」それも、70年代から80年代にかけての雰囲気。細いかすれた線で密に書き込みされた、けれどトーンを使わない白っぽい画面、ふわふわとしたお話に似ています。夜の空にはいつも三日月。塀の上をネコが歩く。目を合わせて、ふっと笑いあう。かようシンパシー。センシティヴでセンチメンタル。リリカルで、弱い儚い物語。だから、逆に、鳥井くんと坂木くんの関係が気持ち悪くないんです。少年期、いじめられていた鳥井くん、彼に手を差し伸べた坂木くん。「ぼくだけを、必要として。」かけた呪い。「君だけが、世界の窓。」かけられた、魔法。もしかしたら、誰もが思春期、すがったことのある依存の糸に、輪をかけて輪をかけて、20代後半まで維持し続けたいびつな関係。いくらでも歪んだ話になりそうなのに、暗い話ではありません。いい人ばっかり出てきます。「日常の謎」のお話なのですが、謎が主眼じゃないと思う。ミステリとしては、最新作の「切れない糸」の方が、絶対におもしろい。でも、なんだか、惹かれるシリーズです。私が今よりもう少し子供で、もっと繊細だった頃(が、たぶん、私にもあったと思う……)なら、手放せないシリーズになったんじゃないかなあって。新井素子の「星へ行く船」に夢中になった感覚で、浮かされるように読み続けそうです。離れがたく思うので、今から最終作をかばんに入れて、出勤です。
2006年04月10日
コメント(2)
-
花曇り
花くもりの日は、桜のひとつひとつ、内側から光る。皆が上を見て歩くの、不思議。そうして、ぶつからないのが、不思議。赤江瀑の「春泥歌」って小説を思い出して、連れにあらすじを話そうとして、ふとやめる。怖くなったから。そういえば彼には「平家の桜」って短編もありました。もしかしたら一緒に収録されてたのかな。講談社文庫の「春泥歌」。人に貸すと、みんな、目をぽおっとさせて夢に迷って返してくるのがおもしろかった。阿刀田高の「恐怖コレクション」だったかにも、桜が魔に見えるってエッセイあったっけ。花の一つひとつが「目」に見えて、怖いって。違ったかな?木が全体、女の顔に見えるんだったかな?つらつら考えていたら、うわあ、梶井の「桜の木の下に」を思い出してしまった。どうしよう、怖いんだ、これ。たらたらたらたら、にじんでいく液。「桜の木の下には、死体が埋まってゐる!」これは信じていいことなんだよ。坂口安吾の「桜の森の満開の下」も怖い桜の話として有名ですね。渡辺淳一の「桜の木の下で」はどうでもいいや。(読んだこと、あります。中年男の妄想話だと思った。映画も観ました。映画は割りと良かったと思う。子供は見ちゃいけないマークがついていたけど。この小説が、お好きな人には、ごめんなさい。)願わくば花の下にて春死なむ その如月の望月のころ伸び上がる気持ちで歌おうか。魔を払うように。
2006年04月09日
コメント(7)
-
さくら、満開
ばたばたばたっと、お仕事が立て込んでおります。昨日もお昼休みがとれなくてふてくされていると、上司が時間ずらして一時間、お休みとってきていいよ、と言ってくれました。遠慮しないで、自転車に飛び乗って、図書館へゴー。坂木司の「ひきこもり探偵三部作」と「比類なきジーヴス」「よしきた、ジーヴス」をゲット。ここんとこ、ものっすごく気になっていた本なので、とっても嬉しい。のに、いつ読めばいいのだ?土曜日も出勤確定してるのにー。学生のときは、授業中、教科書広げている上に本を開いて小説を読んでいました。あと、机の下、ひきだしのときに本の背ひっかけて、隠れて読むのも得意でした。たぶん、ばれてたと思うけど。さすがに今は、そうもいかない。でもね、時間がなくてもちゃんと読む。読むのが好きだから。楽になれるから。夕飯食べながら、どうしようもない眠気が襲ってきて、ちょっと横になろうと思ったとこまで、覚えてる。気がついたら、朝でした。枕元に「ひきこもり探偵」三作が積まれてて笑っちゃった。どうも自分で持ってきたらしい。記憶がない。ちゃんと電気も自分で消して寝たらしい。これまた記憶がない。図書館のとなりには、公園があります。桜でいっぱい。ピクニックシートを敷いて、お弁当を食べる人たちがいました。お母さんと子供たち。老夫婦。土日のお花見とちがって、バーベキューしている人やお酒を呑んでる人がいない。静かで牧歌的で、輝いている声だけが空に響いていきました。 日曜日だけ、本を読まずに、花見に行こう。もう少しだけ、散らないでね。桜さん。
2006年04月06日
コメント(4)
-
イメージバトンは、暖炉の横で。
日記リンクさせていただいてます、ままちりさんから、イメージバトンをいただきました。実は前から、ちょっとやってみたかったバトンだったので、小躍りしちゃうくらい嬉しかったり。いえーい、イメージバトン!【バトンのルール】 イメージでつながっている言葉(キーワード)の最後に 自分のイメージを1つ新しく付け加え それを新たに『3名様を指名』した上でお渡しする。ということで、現在のとこ、イメージは、海⇒川⇒水⇒雨⇒雲⇒空⇒青⇒ポカリスエット⇒ スポーツ飲料⇒潤う⇒汗⇒夏⇒クーラー⇒寒い⇒ 冬⇒雪⇒雪だるま⇒白⇒白熊⇒カキ氷⇒祭り⇒混雑⇒ ラッシュアワー⇒電車⇒通勤⇒会社⇒深夜残業⇒ 深夜営業⇒コンビニ⇒新商品→春物⇒ピンクの唇⇒ かわいい⇒犬⇒ワンパク⇒子供⇒宝物⇒思い出⇒写真 ⇒笑顔⇒黄色⇒ひまわり⇒太陽⇒麦畑 だ、そうです。なんか、物語、感じますねー。「クーラー」で「寒い」をイメージしたのは、きっと華奢なお嬢さん。夏でも家に帰ると、毛糸の靴下、履いていたりして。会社のイメージで、深夜残業って、ナミダを誘われます。なまじお仕事ができる人であるばっかりに、便利に使われちゃうんですよねー。大変だあ、うんうん。ひまわり、太陽、麦畑。金色の、輝くイメージが続いています。きれいに続けていけるかな?麦畑、といえば、一番最初に思い浮かんだのは歌でした。ほら、「誰かさんと、誰かさんが、麦畑」これ、一昔前は「夕空晴れて、秋風吹く」だったそうで。ローラ・インガルス・ワイルダーの「大草原の小さな家」シリーズ読んで、知りました。父さんのバイオリンで、メアリーやローラが歌う歌。講談社青い鳥文庫、「農場の少年」の解説に載っていたんだっけ?(ちょっと自信ない。)青い鳥文庫は、「農場の少年」以来、出版が休止されたので、ローラ一家の続きの話は岩波少年文庫で読みました。(結局、「長い冬」以降の話は、青い鳥文庫で出たのかなあ?アマゾンで検索したけどみつからない。もう絶版なのかなあ。一回見かけたことある気がするんだけれど。)「大きな森の小さな家」「大草原の小さな家」「プラム・クリークの土手で」「シルバー・レイクのほとりで」ここまでは、いろんな出版社で出ているので、読む機会も多いのですが、もっと、続きが、あるんですよ。「長い冬」「大草原の小さな町」「この楽しき日々」「はじめの4年間」岩波少年文庫で出ています。とりわけ、「長い冬」は、スリリングでおもしろい。冬の町に閉じ込められたローラたち。その閉塞状況の中で、いかに生き延びるか。物語初めの不吉な予感。事故を回避する少年の閃き。やりくりの知恵。死ぬか生きるかの飢えの駆け引き。青年の冒険。こらえて迎えた、爆発する春。いや、読んでない人は読んでください。絶対、おもしろいから。ほんと!訳文、荒っぽいけど、お話がおもしろいので気になりません。ローラと娘ローズの確執(ローラの物語はローズが手直しして出版している。ローズは必ずしもローラの生活を肯定している訳ではなかった。確かにローラの自慢話っぽいエピソード、多いしね。反発しながら手を入れるのは、ローズも難儀だったでしょう。)など、いろいろ語られておりますが、訳文で読んだ外国人のワタクシが言い切りますに、このシリーズは素材の妙が生きている!ローラじゃなければ、生まれなかった作品なのです。実際、ローズが手を入れなかった「はじめの4年間」だって、ちゃんとフツウにおもしろいし。荒っぽいなりの切なさがあって、好きでした。(でも一回しか読んでない。他の話は結構読み返してるのに。あれ?)イメージバトンから、ずいぶん脱線しております。麦畑から続くイメージは、やっぱり父さんが弾くバイオリンで。ローラが赤ちゃんだったときから嫁いだ日まで、暖炉の横、家族を守り支え続けた暖かい蜜の色と音色を、つなげます。海⇒川⇒水⇒雨⇒雲⇒空⇒青⇒ポカリスエット⇒ スポーツ飲料⇒潤う⇒汗⇒夏⇒クーラー⇒寒い⇒ 冬⇒雪⇒雪だるま⇒白⇒白熊⇒カキ氷⇒祭り⇒混雑⇒ ラッシュアワー⇒電車⇒通勤⇒会社⇒深夜残業⇒ 深夜営業⇒コンビニ⇒新商品→春物⇒ピンクの唇⇒ かわいい⇒犬⇒ワンパク⇒子供⇒宝物⇒思い出⇒写真 ⇒笑顔⇒黄色⇒ひまわり⇒太陽⇒麦畑⇒バイオリン次にまわすお三方は、こないだトラベルバトンを拾わせていただいた紅ずきん様、17歳バトンを拾っていただいたショコラ・ベル様、バトン大好きを表明されてます(前にリンク貼ってくださってありがとうです)むらきかずは様。よろしければ、お受け取りくださいませ。
2006年04月04日
コメント(6)
-
実音のおしゃべり 2
ねえ、とおりさん。世の中に悪い人っていないんだと思うの。当たり前に、いい人ばっかりの世界なんだけど、ご機嫌とか環境とかのために、ときどき悪い人になっちゃう人がいるのよね。私は、いい人になりたい。ずっと、いい人で、いたいよ。
2006年04月04日
コメント(4)
-

格闘する者に○
三浦しをん 新潮文庫しをんさん、同世代なんだなあ、としみじみ。かつては、就職氷河紀の女子大生だったのよ、ワタクシも。ゆるい、だらだらとした文学部の学生が、気合入れつつ本気出しつつ、だけどやっぱり自らのプライドにかけゆるゆると、就職活動する物語。どうせ働くんなら、好きな仕事。でなければ、長く働ける仕事。と、思って探したよ、私も。連戦連敗。文学部の学生のご他聞に漏れず、私も出版・マスコミ関係を少々回りましたけど、けっこう、ぐしゃぐしゃでしたね。あの世界。小さな出版社に行くと、男女別々の部屋に通されて、「うちは男女差別あります。女の子は使い捨て。結婚したら、やめてもらいます。」言い切られてびっくりしたことも。ずっと、だめだだめだと、就職試験に落ち続けると、なんだかとっても落ち込んでしまいます。私、そんなにダメ人間?で、ほんとに嫌になって、就職活動途中で放り投げて、就職浪人することに決めた夏休み。そっからは、卒業論文にいそしんだ記憶しかございません。周りから見ると、モラトニアムそのものだったかもしれませんが、あれでも必死だったんだよ。両親へ。心配かけて、すみませんでした。担当教官の「君たちはいい子だ。自分を安売りしないように。」って言葉。ありがとうございました。さて「格闘する者に○」デビュー作だけど、上手いです。こなれてます。少し、誰かに似てる。吉本ばななかな。もうちょっと軽くって、非現実的だけれど。オカルト抜いた吉本ばななって感じ。(なんでその方が非現実的なのかなあ。変なの。)三浦しをんさんの小説、幻想に寄れば「月魚」真ん中に「むかしのはなし」現実に寄って「格闘する者に○」?この三つしか、読んだこと、ないけれど。とりあえず、男の人には「格闘する者に○」を薦めます。だって、主人公可南子が、とってもチャーミングなんですもの。脚がきれいで、老人と恋人同士なのよ。なんでもない毎日だって、日々これ格闘。明日も、私でいるために。みつけきれなかったけど。文庫もありますよ。
2006年04月03日
コメント(0)
-

「からくりからくさ」買いました。
買っちゃった。からくりからくさ 新潮文庫 梨木香歩私はこの話が好きで好きで、なんべんか図書館で借りて読んでます。手元に置いて、いつでも繰り返し読めるようになると、いつか読み飽きる日が来そうで怖かった。昨日から降っていた雨が急にあがって良いお天気。緑の色をぴかぴかにした木や草を見ている内に、本屋に行きたくなったんです。枕元にこの文庫があるとなんだか嬉しい。花のいろがふわり夢に入ってきそう。いのちは巡る。宙のかなたで。卵は割るものじゃない、温めて孵すもの。あふれる悪意は現実のものだけで十分です。かなしみが繰り返されないよう、幾度祈ってもなぜだかひどいニュースは絶えなくて。美しい物語はこの手の中に。どうぞとどまって。そして祈ることはやめない。ひとしく優しい夜明けが生きる人に訪れますように。かなしいことがあった人々が安らかな眠りを得ますように。
2006年04月02日
コメント(2)
-

月魚
三浦しをん 角川文庫和服を着たきれいな青年が古本屋店主を勤める無窮堂。三代続いた老舗の古本屋。そこに出入りする、幼馴染の飄々とした若者。彼は古書の卸を生業としている。二人の間にずっとある緊張感。鈴が時折、ちりちりと鳴る。お互いが、お互いを、認めているのに。お前を(君を)傷つけたのは、私(俺)だったのか?蔵いっぱいに演劇の本を溜め込んだ一人の男が死んだ。彼の住む家に残された本を二人は買い取りに行く。運命がきしみはじめる。――というのが、一作目の月魚です。ゆるゆるとしたお話でした。うまく小説が書ける人が、うまく書こうとしたのがよくわかる。ので苦手な人もいるかもしれません。「妄想炸裂」の三浦しをんさんの作ですので、深読み歓迎!な店主・真志喜と幼馴染・瀬名垣との会話がちょっとあざといし。そこをはずせば、古典的な物語。クライマックスの掛け合いには、頭の中、声が響きました。演劇で見てみたい。私はホモは十代まで、が基本です。ストイックに恋心は抑圧、というタイプのBLが好きでございます。で、この嗜好にどんぴしゃだったのが、次に収録された「水の中の私の村」。夏を、走ってく。真志喜や瀬名垣たちの17歳の夏休みの一日が、変わり者の男性教諭の目をもって語られます。少年たちの突っ走る宵。気まぐれに声をかけられ巻き込まれ、目を丸くしてついていっても、彼らのバリアの中には入っていけない。私の体は重い。かろやかに階段を駆け上り、風を体いっぱいに受け、顔中で笑って、高いところから飛び降りる彼らの瞬間を、網膜にやきつけることで精一杯。刹那的で、ロマンチックでよかったです。「月魚」で時々は激するものの、総じてゆるりと落ち着いていた白皙の美青年・真志喜が、(やるな、こいつ)と思わせる元気に企む美少年だったところがまた楽しかった。少年ってのは、こうじゃなくちゃね。解説があさのあつこでした。このお方、やっぱり男の子の話、好きなんだなあと思いました。
2006年04月01日
コメント(2)
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
-

- 楽天ブックス
- 【ポチ♪】SPU攻略兼ねてkoboでポチ
- (2025-11-27 01:40:05)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-
-
-
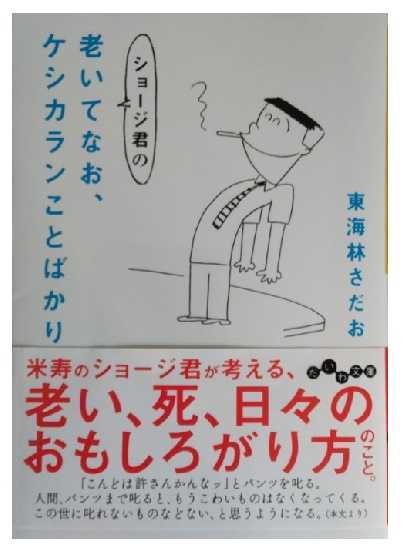
- 最近、読んだ本を教えて!
- ケシカラン こともおもしろがれる じ…
- (2025-11-27 10:58:21)
-







