2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
なんであるんだか解ってるけど、解らないもの。
哲学的な話じゃなくて、即物的に粗大ゴミの話です。ちっちゃな事情がございまして、ただいま乙女のプライドにかけて、我が家を大掃除中。恥ずかしながら、お掃除は苦手です。お洗濯はしないと着る服がなくなっちゃうし、お料理はおなががすくので割りとするけど(油と塩が濃いのが苦手なので、コンビニ弁当が食べられない。)お掃除はねえ。散らかってても、居場所があればいいじゃん。散らかってるのは、本とかCDとか。「散らかってても見苦しくないのは本というけれど、それも程度問題である。」北村薫の言葉がぐるぐる頭の中まわったりして。でも今の方がまだまし。その昔、卒論なんぞを書いてるとき、部屋の中、泉鏡花の全集文庫資料、私のメモや原稿用紙でいっぱいでした。母親が部屋を覗いてあきれたもんです。「足の踏み場もないわねえ。」「足の踏み場しかないって言ってくれ。」言い返して、ワープロにかじりついてました。締め切りギリギリで書き終わって提出を終えたあとに、本通の二階にある不二家レストランで甘ったるいケーキを食べたのを覚えてる。人通りをぼんやり見てた。(どれだけの選択を繰り返して、ここまできたのかな。)壁一面の窓、大きな風景に気持ちがついていかなくて、もてあますような思いでいたのを思い出す。片付け、というのは、ノスタルジックな気分に浸っていけません。要は、私が「捨てる」ことが下手なだけだって解ってるんですけど。で、捨てよう捨てようと思いつつ、いまだもってるちょっぴり大きなお荷物。なんであるんだ、こんなもの。「壊れたプレステ」これ、燃えないゴミですか?それとも大型ゴミ?「室内ステッパー」プレステに接続して遊ぶダイエットゲームのコントローラーでした。いつかダイエットする日のために捨てずにとっていたのだけれど、もう二度とこのゲームでは遊ばない気がするので、いい加減捨てようかなと。「インラインスケート」インドア派なのにどうして持っているんだか。結構高かったし。職場の先輩に誘われて買ったんですけど、4,5回しか使ってません。最後にひどい怪我をしたので、もう絶対に二度としないと思う。怖いもん。もう4年もケースから出してません。従兄弟にあげようと思ってたのに、あげる機会がないまま、いとこが大きくなっちゃった。これ、別々に捨てたら燃えないゴミでもいけるサイズだろうか?やっぱり大型ゴミ??大型ゴミは電話して予約して、券を買って貼って、指定された日に捨てないといけないんです。いつかまとめて捨てようと思って、「いつか・いつか」で今日まで来てる。えい、片付かないじゃないか。魔法つかえたらいいのにな。指を鳴らすと、ものたちが自主的に自分の場所を探しておさまってくれる。いらないものは、空中分解して消える。空飛べなくてもいいや、なんか怖そうだし。私は、お片づけの魔女になりたい。
2006年01月31日
コメント(8)
-

ねじの回転
恩田陸 新潮社こないだ文庫化してましたね。二冊分冊。私は図書館で単行本一冊借りて読みました。そんな長い話じゃないので、文庫で買っても一気に読むのをオススメします。キュルキュルってねじ巻いたら、手を離して一気にぐるりんってほどけるのか、カタルシスじゃないですか?そんなお話。手の中に納まる、不完全な懐中時計。まわる時計の針を、人差し指で押さえたことありますか?指の下、前に進みたくて震える針。だめだよ、許さないよ。むしろ逆まわし。ほら、ざまあみろ。まだ三時。って、周囲を見ると、あれれ、夕焼け。お家に帰らないとだめ?もう、放課後はおしまいなの??ってね。このお話は、2・26事件をぐるぐる回ります。いやだわ、そんな寒い日の繰り返し。凍る路、暗い明日。だけどこの日をやり直さないと(そうして歴史を修正しないと)僕たちが消えてしまう。僕らは、未来の大人たち。国連の名の元に、正義を行うよ。(なんて、うさんくさい。)文庫の紹介には、SFって書いてあった。でもあんまりサイエンスっぽくないです。とにもかくにも、幾重に重なる時間の描写がおもしろい。最後の章で、作者が「さあ、つかまってらっしゃい!」って叫ぶ声が聞こえる。張り詰めた伏線がぶつかってつながっていく。それが楽しい。設定に甘いとこ、展開の無理はもちろんあるけれど、それを超えて暴力的に作者が創作を楽しんでいて、乗せられて、読者も楽しい。うん、恩田陸、本領発揮!物語に、巻き込まれる。どうせ読むなら、冬に読むのがいいと思うよ。夏に読むと、公園に逆上がりの練習しに行きたくなりそうで、大変、危険です。(意味わかんない人、読めば解ります。たぶん。)
2006年01月30日
コメント(2)
-
(今読んでいる本のことを小声で言ってみる)
今、すごい本読んでます。あんまりすごすぎて、読み終わる前にパソコン開いちゃった。大笑いして、お腹いたい。三話連作みたいなんですけど、一話目で、もお降参。でも多分これ、作者の意図としては笑える内容の本ではないんです。だから、この先、お好きな人は読まないでね。素直じゃない楽しみ方をしています、ごめんね。でも書きたいの。神永学 心霊探偵八雲 と、いうわけで、以下白文字。「一つ言い忘れました」 八雲はそう言うと、ポケットの中からデジカメのメモリーカードを取り出して高岡に見せた。「フィルムはここです」(原文ママ)フィルム?その前にデジカメだけもらって、証拠を手に入れたーって威張っている高岡センセもどうかと思ったんですけど。もっとその前の場面、人質とデジカメの交換ってのもどうよ。宙に放り投げられたデジカメを両手で受け止めたためにやむをえず人質を放す真犯人。別にデジカメ、壊れたっていいじゃん。この場合手に入れて消去しなきゃならなかったのは記録の方なんだからさ、デジカメはむしろ壊れた方が良い。内臓メモリも心配だしね。現場検証に、わざわざ日が暮れてから訪れる。現場百辺を否定しませんが、まず明るい昼間に一回見ておいてからの方がいいんじゃないのかな?別に立ち入り禁止地区じゃあないんだし。案の定、そこで謎の黒い影に襲われる八雲たち。この「影」はどうしてわざわざ背後から八雲を襲うのかしら。気づかれてないんだから、逃げた方がいいじゃん。襲ったら、「はい、ここに秘密がありますよ」って教えてるようなもんだし。一対二で、しかも武器が鈍器しかなかったら、逃げられる可能性のが高いでしょう。錆びたスコップで人を殺すには、難儀なもんがあります。そしてスコップで殴られてぼたぼた血を流す八雲くん。というのが見て取れる明度はあるようなんですが、謎の襲撃者は「黒い影」としか判別つかない。別に覆面してたわけでもなさそうなんですが。あのさ、体格くらいは解るでしょ?読みながらずっと、どうしようどうしようって思っちゃう。八雲くんの幽霊についての考え方。「人間の記憶や感情はつきつめると、ただの電気信号だと言われている。インターネットを流れる情報の渦は、人間の脳の仕組みに酷似しているなんて言う奴もいる。その考えが成立するなら、器をなくしてしまった瞬間に、人間の感情がすべて無に帰すってわけでもないないだろ。電気は器がなくたって流れるし、インターネットの情報は元々の器が失われても、他の器に移りすむわけだ。」(原文ママ)先生、そのたとえ話、意味がわかりません!著者プロフィールがまた愉快。「各新人賞の候補になる等、その実力を認められながらも、天性の運の悪さから受賞には至らなかったが、」いや、先生、充分にお強い運をお持ちでしょう。なんでこの本、復刊してんだか。いろいろ言いましたけど、この本が今、人気あるのは事実だし、おもしろいって感じることを否定しません。うん、どんな本でもあっていいんだ。楽しみ方は、ひとつじゃないし。あーでも、どうしよう。続き読むの、やめよっかな。(小声)
2006年01月29日
コメント(6)
-

切れない糸
坂木司 東京創元社装丁がきれいで、図書館にリクエストを出して借りました。タイトルにも惹かれたし。切れない糸。もつれた糸やからまる糸より、素敵でしょう?ほどけても、結びなおせばいい。つながる糸電話。もしもし、君は元気ですか?アライクリーニングの跡取り息子、新井くんの春夏秋冬。放っておけない「日常の謎」をお友達の沢田くんの手を借りて、解きほぐしていく物語。新井くんは、いい子です。落ち込んだり愚痴ったり、ひがんだり無神経だったりするけれど。誰かがつらいなら「俺が、嫌なんです。」かないません。私、とっても弱いんです。こういう善人に。私以上に、新井くんにめろめろなのは、沢田くん。おさまりの悪い癖っ毛で、細い目をして、優しく笑う男の子。頭が良すぎて優しくて、何でも先回りしてわかっちゃう自分を少し持てあます。(どうせ君も、僕のこと、怖がるようになるんでしょう?)だから最初から、さらりと距離を置く。いつも、笑ってる。でも、だいじょうぶ。沢田くんは、新井くんの友達だから。からまる糸をほぐしていくのは沢田くんだけれど、新井くんは沢田くんのほどいた糸をいつもきちんと結びます。その糸は切れない。つながる、つながり。「もしかしたらもう会えないかもしれないけれど、君がいるなら、世界は捨てたもんじゃない。」いい人ばっかり出てきます。でも、甘ったるい小説ではありません。リリカルだけど、センチメンタルじゃない。地に足のついたお話です。好きだなあ、とても。
2006年01月28日
コメント(2)
-
ひまわり
広島市中区八丁堀の「ひまわり」ってお店にいきました。「つけ麺、焼肉 ときどきシンガポールナスカレー」って看板が出ています。職場のお姉さんの行きつけのお店で、予約とってくれてたの。メニューのほとんどないお店で、焼肉はお店がおすすめを出してくれました。最初がびっくり、霜降りのお肉。「生でも食べれるよ、」って言いながら、マスターは生わさびを摩り下ろしてくれました。炭で表面を焼いて、まだ中身がとろりんとレアなところにわさびをのっけて、お醤油をちょっとつけて食べる。おいしかったー。続いて出してくれた手造りソーセージ。かじるとびっくりするくらいシソの味がします。ほとばしる肉汁。だけど、さっぱり。ホルモンも出してくれました。これがまた、おいしい。ぜーんぜん、臭みがないの。最後に野菜がたっぷりのったつけ麺を出してくださったのですけど、私はお腹いっぱいになりすぎて、途中でギブアップ。美味しいのに悔しいってじたばたしていると、周囲から箸が伸びて、食べるの手伝ってくれました。良かった。完食!ダイエットは、明日から。えへへ。
2006年01月27日
コメント(4)
-
私の乙女本。
日記リンクさせていただいてます紅ずきん様が、このたびネット古書店 笑琳舎 をオープンされました。ぱちぱちぱち。机に肘ついて、あんなこといいなこんなこといいなと夢見てばかり、実行力不足の私としては、かの方の夢を叶える力を仰望してしまいます。乙女ちっくでお洒落なお店なので、ぜひ覗いてみてくださいね。さて、笑琳舎でお取り扱いされている乙女本の中に、吉屋信子先生の「花物語」がございます。乙女を自認される文学少女なれば、一度は耳にしたことあるタイトルではないでせうか。わたくしも、伝説の「花物語」を読んでみたくて焦がれ焦がれておりました。この恋を耳にした友人が、お母様の本棚の片隅にひっそりと仕舞われていたのを見出して、白いハンケチにくるむと、そっと手渡してくれました。「お母様には、ないしょよ。早く読んで、返して。」嗚呼!学生時代の美しき思ひ出!ちょっとくたびれたので、いつもの調子に戻ります。花物語、現代読むと少々単調ではありますが、伏せたる少女の眼差しが愛おしいお話です。玉石混合ではありますが、玉はまさに珠!繊細だった頃を思い出します。新しい靴が汚れるのが嫌でそろそろ歩いたこととか、ほどけてもゆるんでもいない三つ編みを、休憩時間毎に編みなおしたりしてたこととか。ヘアピンで横髪を止めるのを何度もやり直した。うつむいて。真剣だったよ。ちょっとずつ通り過ぎて、今では振り返ってる少女の時代。思い出したい方、笑琳舎へいらっしゃい。画像は私が持ってる吉屋信子の少女小説。乙女気分になりたくて、本棚から引っ張り出して撮りました。うちの乙女代表、ミギワと一緒にパチリ。十年くらい前に古本屋で見つけたの。まだ全部読んでないんですけど、「わすれなぐさ」は傑作ですよー。実は持っているのが自慢でもある。どーだ、乙女な装丁!男の子には読ませたくないなあ。宝物箱に仕舞っておきたい、乙女本、あります。
2006年01月26日
コメント(8)
-

現代の民話
松谷みよ子 中公新書怪談、大好き。昔話、好き。ありえない話が、まさしく「あったること」として語られる。また抑圧された感情が、魔を生んで物語となり1人歩きする。ひそやかな、しめった感情。さぐる気分が、おもしろい。私は子供を相手に大まじめに嘘をつくのが好きである。「あのね、コンピューターの中には小人が入っていて、キイをたたくと小人さんは機械の中をアルファベット持って走り回ってるんだよ。」フリーズしたあって舌打ちしてる人の後ろを通るときには「あーあ、小人さん、くたびれたんだねえ」って。ちっちゃい、現代の民話。子供の頃には、もどかしいほど、物語がたくさんあった。川沿いの廃屋に忍び込めば、8月6日で止まった日めくりカレンダーがかかっていたとか山の中奥にある洋館のチャイムを押せば、体中レンガ色にヤケドした人がドアを開けてくれ、その人は幽霊だったとか(私の住む町はヒロシマでもあった)今は廃屋も洋館も取り壊され、もはや、物語の影もない。語り、書き、書かれた物語がまた語られ。松谷さんはその連環こそが民話を生み民話を文学に近づけると語られる。生きていく、物語。てのひらサイズの新書の中に、幾重に物語がつづられていく。時を超えて、生きる語り。いじめで死んだ子の姉さんから手紙を受け取った松谷さんは「わたしのいもうと」という絵本を作る。私は、その絵本を母から与えられて10年以上前に読み、「あっ」と思ったはずなのに、物語をすっかりと忘れていた。「わたしの妹の話。聞いてください。」ものも言わず、本も読まず、音楽も聞くこともなく、閉じこもった子が記したメモ。「わたしをいじめたひとたちは、わたしをもうわすれてしまったでしょうね。あそびたかったのに。勉強したかったのに。」淡い水色のページを思い出す。その中、白い色はなかったろうか。飛んでいった紙飛行機だったか、散っていった白い花だったか。この普遍性。確かめるのが怖い、民話。
2006年01月25日
コメント(4)
-

チャペックおじさん
カレル・チャペックの「山椒魚戦争」を読んでから、ぼうっと抜けた魂がまだ戻りません。チャペックといえば、私にはずっと「長い長いお医者さんのはなし」の作者でした。母の本。愛蔵版岩波文庫、黄色くてかちりとしたハードカバーの文庫本。私はこのお話のあふれるイメージや、大真面目で大仰な言い回しが大好きでした。まるい線で書かれたイラストがついています。にかーっと顔中口にして笑う河童の絵。お兄さんのヨゼフがつけた挿絵。骨折した妖精のために、虹の光を七本にわけて、青い光で添え木をつくる。宛名のないラブレターを届けるために、世界を一周するゆうびん屋さん。たのしくてやさしい、イメージの遊び。少年版ファーブル昆虫記の前書きじゃなかったっけ。「人が成長するためには、パンが必要です。心が成長するためには、心のパンが必要です。」「長い長いお医者さんのはなし」は心のご飯だと思う。ダイレクトに戦争が批判されているわけじゃない。逆に、ちっとも影を落とさない。お説教くさいわけでもない。教訓はどこにもない。読んでいて、楽しい。あの時代に、書かれた。ナチス侵攻を前にして、ファシズムを批判した「山椒魚戦争」は発表された。脅迫が届き、亡命を進められても、チャペックたちは逃げなかった。カレルはナチス侵攻の一年前に病に倒れ、ヨゼフは強制収容所に捕らえられる。終ってからなら、いくらでも言える。人は後悔する美しい生き物だ。最中に、声を挙げる。戦争で戦う人は、悲しいけれど、たくさんいる。戦争と戦う人は、あまりいない。私に、その勇気は、あるか?日本にいるのは、与謝野晶子。「少女と申すものは、戦争嫌いにて候」最中、言い放つ勇気は、私にあるか?心のパンを食べよう。心のパンを作ろう。チャペックおじさんは、学校図書館のかたすみに、公園の砂場の山の上に、川原の花陰に、今日もいます。遊ぶ子供をにこにこと見守っている。朝、校庭に大きく書かれた落書きは、ヨゼフ兄さんのいたずら書きかもしれません。山の向こうの気配を案じ、海の向こうの脅威に眉をひそめながら、心のパンを子供たちに配り続けるおじさんたち。すべての子供が笑うまで、チャペックおじさんは虹を超えない。いるんでしょう?そこに。ここに。もひとつ、リンク貼ろうとしたら、もう絶版だったみたい。なだいなだの「おっちょこちょ医」。これ、未読の方、古本屋で見かけたら、ぜひどうぞ。対ファシストの話として、大絶賛の傑作名作です。日本人がこれを書いたということが誇らしい、私の「読まずに死ねるか!」本。
2006年01月24日
コメント(4)
-
生協の白石さん
講談社お友達から貸してもらいました。「興味あるなあ、」なんて言ったら、「持ってるよ、貸そうか?」って複数から。みんな持ってる、「生協の白石さん」テレビでの本の紹介から、過剰におふざけを期待していたのですが、意外とまじめな印象を持ちました。いや、まじめだから、こんなおもしろいんだ。だって白石さん、生協の商品アピールがとってもじょうず。重くならず、硬くならず、押し付けがましくならず。決シテイカラズソウイフ人二私ハナリタイ学生さんたちにも、おおらかな空気を感じます。形而上的な悩み(恋とか運とか)に振り回されて、明日のパンより今日の課題と漫画の続きが気になって。要求と応答。どちらにも、大学らしい雰囲気を感じました。みんな、なやんで、大きくなーれ。
2006年01月23日
コメント(8)
-
島根ふるさと祭り
ただいま島根ふるさと祭りの会場に来ております。 年に一回、広島で開催されますお祭りです。グリーンアリーナってアジア大会のときに作った巨大体育館の中と外を使った、大物産展! なんといっても楽しいのは外まわり。食べ物屋さんの屋台がたくさん。 おそばでしょ、おにぎりでしょ、お餅でしょ。コロッケ、カレーに、にぎり天。和牛の串焼きシャモの串焼きやまめの串焼き鮎の串焼き。 で、これがとっておき!毎年楽しみにしてるのがサバの串焼き! ひねりもなにもなく焼きサバという名前です。串に刺されて炭火焼きされる小振りなサバちゃん。愛してるわ、八百円。 連れは今日も可哀相に休日出勤。会場で待ち合わせしてるのにまだ来ない。 素知らぬ振りで釜あげそばを先にいただいちゃいました。 私は蕎麦をすすれないのでかみ締めがいのある出雲蕎麦が大好きです。次はさんべ蕎麦にしようか。隠岐蕎麦でもいいな。島根のお蕎麦の食べ比べ。 さあて、まだまだ食べ歩くぞ!酒もビールも売ってるし。
2006年01月22日
コメント(12)
-

山椒魚戦争
カレル・チャペック早川書房から出ている「世界SF全集 9巻」に収録。1970年発行。私より年上なのに、開き癖もあんまりなくて、ぴかぴかの本でした。ページがちょうどいい感じに黄ばんでて、古い本の乾いた紙のにおいがします。図書館で、借りました。初読です。すごい小説読んじゃったなあ、と読み終わってしばし呆然としました。アイモフ先生のアイ・ロボットを読んで、居酒屋「さんしょううお」に行って、「山椒魚戦争」を読んだ自分も褒めてあげたい。いや違う。力のある物語は自分から読んで欲しい時期を指定してくるものなのです。いま、今日、読んで、良かった。酔いどれふとっちょ船長が、原住民から怖れられている「魔の入り江」で、二足歩行の大きな爬虫類を発見。真珠の眠る湾にすみつきながら、貝を割り食べる知恵も道具も持たず、サメにおびえて暮らす哀れな化け物。太っちょ船長はこの「山椒魚」を使って真珠を採取することを思いつきます。孤独な船長は山椒魚を愛し、サメを撃退する道具を与え使い方を教え、天敵がいなくなって増えすぎた山椒魚のため真珠採取のスポンサーを探し、世界中の海に山椒魚を連れ出していきます。(そんなこと、やっちゃいけない。)読みながら、かすか、思います。(バランスが―――くずれる!)ここまでが、第一章。道具として使われる山椒魚、個を問われない山椒魚、無制限に増え続ける山椒魚。言葉を覚え、思考し、教育を受ける。山椒魚に精神は有りや無しや。人間は議論するが、山椒魚は不気味なまでに無言。山椒魚は労働力として虐げられ、使い捨てられ、搾取され、人の利便になくてはならないものになり―――ここまでが、第二章。第三章は、戦争です。間違ってる、と思っても引き返せない。坂道を転がる石。100匹の山椒魚は、翌年には500匹。翌々年には2500匹。生き残るための蠕動がはじまる。動物の本能に、人の言葉は届かない。リセットボタンはどこにもなくて、一つの行為、きっかけを後悔し続ける人がいる。他方、不気味に笑うファシスト。腹を肥やす悪。構成はアシモフの「アイ・ロボット」と似ているのです。人間以外の高次な存在を人間が見出し改良し、またたくまにそれは進化を遂げ、傲慢で愚かな人の影をはっきりと映し出す太陽になる。太陽の恩恵なくば、もう人は生きられない。なかったことには、もう、できない。崩壊や堕落は、目の前に迫る。小説の技法についても一言。第一章は童話。「長い長いお医者さんのはなし」を彷彿とさせる、冗長にも思えるユーモラスな文章。第二章は、ルポルタージュ。たくさんの証言を集め、資料を提示し、山椒魚の生態や現状、未来の予想を組み立てていく。第三章は、戦争の記録。第一章とはうってかわって、簡潔に押さえた文章。過剰にならない描写。まとめに作者自身が登場し、作者の内なる声と対話する。これは1936年に発表された小説なのです。山椒魚の短期間の進化に伴い、小説の表現方法も進化していく。完璧な計算。この奇蹟のような小説は、ナチスの侵攻により禁書となり、世界大戦後、再び出版されるものの今度は共産党による言論統制から「部分的削除」をほどこされる。何一つ無駄のない、完璧な小説が、政治に蹂躙されたのだ。ここで、もう一度。この小説は、1936年に出版された。ナチスの侵攻(39年)を目の前にした、チェコで。命をかけて。なんか、もう、すごい。何をとっても、参る。私ひとりで滅入るのはいやだ。みんな、読んでくれ。すがりつきたくなるような小説です。低い興奮が、心の中、ずっと続いてる。
2006年01月21日
コメント(2)
-
さんしょううお
新年会、新年会。広島市は中区十日市にある居酒屋さん、「さんしょううお」へ晩ごはんを食べにいきました。女性ばかり、三人で。まだあたらしいお店なので、お客さんはさほど多くありませんでした。ビールのんで長話してると、4時間もたっちゃった。さんしょううおって変わった名前だな、と思う。別にさんしょううおの煮つけだの、お刺身だのは、メニューになかったですよ。大根と水菜のサラダを頼んだら、水菜の入荷がなくて、サービスですって拍子に切った大根のサラダを出してくれました。この大根、全然、繊維が口にさわらなくて、甘いの。あれれってびっくりしていたら、お店のお姉さんが「特別に仕入れさせてもらってるんですよ。」って、ほっこり笑って言いました。お刺身のつまにも使うみたい。よかったら、食べてくださいって。ああ、好きになれるお店だな。コロッケおいしかったなー。薄切りタコのお刺身もよかったなー。おでんも塩辛くなかったし。ビールがすすむ、すすむ。よく飲んでるからおつまみにって、野菜を薄く切って揚げた野菜チップスもサービスで出してくれました。これもおいしかった!お勘定のとき、店長さんが出てきて「いつもこんなに飲まれるんですか?」「大体、こんなもんです。」じゃあって、名刺の裏に生ビールサービスって書いたのを記念にくれました。で、結局、何杯のんだんだか、覚えてないんですけど。7、8杯?もっとかも。酔っ払ったのは、たしか。あー、うまかった、うしまけた。
2006年01月20日
コメント(4)
-
アイ・ロボット
アイザック・アシモフ カドカワ文庫かの方の名には、つい先生をつけて呼んでしまうの。だからこれは、アシモフ先生のご本。奇妙な職業が出てきます。ロボット心理学者。このお話に出てくるロボットには頭脳があって、心があるかはわからないけれど、どうやら感情があるのです。短編が時系列で並べてあります。ロボット心理学者スーザン・カルヴィンの回顧録。2058年からの、回顧録。アイモフ先生、ごめんなさい。ロボット工学は、先生が物語ったほどには進化しなかったよ。もう火星で、ロボットたちがシェイクスピアの戯曲を暗唱しながら、運河を掘っていてもいい頃なのにね。最初は、完全に道具としてのロボットの話。人に疎外される道具の話。次は、道具としてのロボットを使いこなすまでの話。それから、ロボットがジレンマに陥る話。人よりも優秀なロボットは、人のプライドを守り、なお自らの優位性を保たなければならない。このあたりから、ロボット心理学者スーザンの眼力が冴え渡ります。知能ゲーム。SFですけど、ミステリとカテゴライズしたっていい。いえ、完全にミステリでしょう。ロボットとの、かけひき。なぞとき。ロボットは、誤らない。ロボット三原則(ロボットは人を傷つけない。ロボットは人の命令に従う。ロボットはみずからを守る。)を守りえるロボットは、高潔な人格を持つ人間と相違しない。ロボットが管理する世界では、環境破壊は起こりえない。なぜなら、環境破壊をおこす世界構築は、ロボット三原則第一項に反するから。「ロボットは、人を傷つけること能わず。」最後の2話では、宙ぶらりんな心地になった。ロボットを作ったのは人なのに、ロボットは間違えなくて、人は間違えるの。なんで?今だって政治や経済のシステムわかってるわけじゃないし、世界を安定させるシステムがあるのなら、それがロボットに統治されることになったとしても……いいのかな。やっぱり、いやかも。ロボットに頭脳と感情と心があったら、それは人だよね。だから、ロボットには感情や心を与えてはいけないのではないかしら。生きるもの皆死に絶えたあと、心のあるロボットだけが嘆いて生き続けるのなら、あんまりむごくはないですか?
2006年01月19日
コメント(6)
-
ヘンなはがきがきた。
民事訴訟最終通告、なんて赤字で書いてありました。普通の官製はがきにチープなプリンタ使って刷ってあります。ドットが荒い。「貴方の利用されてた契約会社、または運営会社側からの契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました。」なんだそりゃ。原告はどこなんだ。「12日までに連絡しなければ原告の主張が全面的に受理されます。」でっかい字で電話番号が書いてあります。ザンネン。はがきが届いたの、18日なんですけど。わあ、給料の差し押さえしますって書いてある。裁判所ってそんなひどいことするの?(ワケガナイ)意味が一番わからなかったのは「尚、書面での通達になりますのでプライバシー保護の為、ご本人様から連絡頂きますようお願い申し上げます。」ってとこ。もしもし?じゃあ、どうしてこれ、封書じゃなくて、ハガキなの?法務省管轄機構 民事訴訟管理局ってところが出してます。住所が千代田区霞ヶ関なんですけど、はがきの消印は練馬です。(ツメガアマイ)一応ググってみたんですけど、この民事訴訟管理局っての、架空請求でよく使われる架空の名前としてヒットしました。絶対連絡しちゃだめよって。この葉書、警察に持っていくのがいいのかな。それとも消費者相談センター?そこはかとなく黒いオーラを感じるはがきなので、気分的には神社に持っていって、魔を払いたい感じ。えい、嫌な気は全部、発したものにかえれ。バチあたれ!アラブのことわざ。一生しあわせになりたいなら、正直に生きろ。
2006年01月18日
コメント(6)
-
ぼくはロボット
「アイ・ロボット」を今読んでます。表紙がかっこいいの。アイザック・アシモフ。カドカワ文庫。これ、映画になったんだったっけ?読み始めてすぐ気がついた。というか、読む前から気がついて当然だったんだけれど。この本、「ぼくはロボット」だわ。児童向けの翻訳で、小学生のとき、読んだことがある。こども図書館で、借りたっけ。小学生のとき、週に一度、バスにのってピアノのレッスンに通ってました。音痴でリズム感のない父が、子供が音楽の授業でつらい思いをしないようにって、兄弟三人にピアノを習わせたの。ピアノの練習がいやでいやで、でもその大嫌いなレッスンが終ったあとのお楽しみは、「こども文科学館」へゴー!市立の建物で、入り口をくぐって右側がこども図書館。左側がこども科学館。屋上にプラネタリウム。好きなものでいっぱいの建物。毎週行っているのに、ちっとも飽きなかった。自動ドアが開くと、おしゃべりロボットが出迎えてくれてた。今でも彼は健在なのかな。15分に一回、おもむろにロビーに進み出て、館内のご案内をしてくれる。5分くらい、勝手気ままに話をすると引き下がる。ロボットくん。突然、プログラム以外の言葉を話し出すことないかしら。油断してまばたきすること、ないかしら。ロボットの前に陣取って、がんとして離れなかったことがある。だって、お友達になれると思ってた。オーバーオールなんか、着てた頃のこと。中学生になって、友達と本屋さんに入ったとき、彼女がハヤカワ文庫の「われはロボット」を探して買った。「貸そうか?」言われたけれど、「ぼくはロボット」のタイトルに馴染んだ私は手を出せなかった。SFよりもミステリが好きになり始めていたし。確かこのとき、私は「そして誰もいなくなった」を買ったのだ。「アイ・ロボット」を開いて、最初のロボット工学3原則を読んだとき、さあっと記憶が蘇った。本の記憶じゃなくて、周囲の記憶。こども文科学館は、広島市民球場の裏側にありました。野球をやっているときは、場外ホームランのボールが飛んでこないかなって。いっつも空を見上げて歩いてた。
2006年01月17日
コメント(6)
-
真冬のひざし
冬の光の色は白く、陽だまりになろうと足掻くいとやかなものに止まりし光は、夜の星にかえるオリオン。祈り。木も草も土もかわく耳をすます凍らない水の音がする
2006年01月16日
コメント(2)
-
稲生神社
広島駅からぐーっと駅前の大通りを抜けて行くとあります。稲生神社。おいなりさんです。小さな神社でコンクリの無愛想な階段を昇ると小さなお社があります。味とか素気とか、あんまりありません。階段のふもとに寄進の幟がはためいています。右側にあるのは、我が広島カープの誇る鉄人・衣笠さん寄進の幟。左側は……荒巻・水木・京極。3者連名の幟。一人一本じゃないなんて、意外にケチ……じゃなくて!なんで?広島には縁もゆかりもなかろう面々。よく聞かれるんだろうなあ。鳥居くぐったとこに、神社の縁起について、歴史愛好家が書いたコラムのコピーが置いてありました。一際目に付く三者連名幟については毎年寄進があるそうです。私が見たのは17年の寄進。もうすぐ新しくなるのかな?この神社にはどんな怪事も打ち破る、「ばけもの槌」がご秘宝としてあるそうな。20センチほどの小槌。異国の魔を退ける霊。ウインズが近くにあります。先週お祈りしてから稲荷特別の馬券を買いに行ったのですが、あっさりはずれました。神様が悪いんじゃないと思うの。ひどいわ豊さま。それとも馬券代よりお賽銭をはずみなさいってことかしらん。狂気の沙汰も金次第。ばーい、ツツイヤスタカ。(縁起については雑誌「旬遊」10号掲載 原田実さんの「広島不思議物語」を参照しました。)
2006年01月15日
コメント(2)
-
薬菜飯店
筒井康隆 新潮文庫筒井を読むには、体力いるぞ。でも現実から遊離できるので、がつんと毒が効いて、元気に帰ってこれちゃいます。ただいま!短編集。最初が文庫のタイトルにもとられた「薬菜飯店」おもしろかったです。下品だったけど。なるほど、ツツイだわー、表題作にするはずだわーって読みました。容赦ない汚物の描写とか、うわあ食事中に読んじゃいけませんって感じ。食事中に筒井を読む勇気のある人はそんなにいないとは思いますけど。でもこれ、食べ物屋の話なんです、どうだ参ったか。料理の描写はありえないほど、美味しそう。不思議なんだけど、美味しそう。嘘か真実か、食材の薀蓄がまた楽しい。絶対に嘘なんだけど、ツツイのことだから、一つくらいホントが混じってるのかもしれない。いや、全部うそ?わかんない。「ヨッパ谷への降下」ふたりだけに通じる言葉を手に入れた二人。二人の共通の言葉は、読者にすら理解できない。「何もかも失ったように思っていたんだけど雨が降ったりした時は君が本当に好きなんだよ」ここだけは意味が解るような気がして、いとおしい。細かな白い虫の死骸の降る谷の底、川のほとりでの会話。「法子と雲界」この短編集のなかで一番好き。高校生のときに筒井に挑発(十代でフロイトやユングを読まないヤツは馬鹿だ。)されて、なにくそと心理学の本を読んだことがある分、逆に、過剰なユングの影響がはなにつく。アニマが出てくるのが、解りやす過ぎて、なんだか馬鹿にされてる気分。でも好き。夢の話。えせ中国説話集。抑制された語りが、めずらしく下品じゃないです。不思議で奇妙な雰囲気がいい。切り取って、宝物にしたい。筒井康隆による「夢十夜」だと思う。筒井のは九話目までしかないけれど、この九という数字も筒井らしいと思う。昨日の午後からずっと雨降り。やむのかな。やまないのかな。ねえ。「雨が降ったりした時は君が本当に好きなんだよ」
2006年01月14日
コメント(6)
-
夢のはなし あれこれ
最近、不快な疲労感が強いので、眠りが浅いです。眠りの記憶はなく、夢の記憶だけが、朝、けだるくまぶたを押し上げます。お仕事で、怒られる夢。受話器にぎりしめて、何度も謝るのだけれど、なかなかご理解いただけない。頼りにならない上司が、目の前で無駄話をしている。私が尻拭いしているのは、あなたのミスなのに。ちっとも役に立たない上司。目が醒めて、お仕事行くのがいやになっちゃう。夢なのか、現実なのか、わかんない。不倫中の、中年男になった夢。風呂掃除は、家庭内のオレの仕事。夫婦での夕食後、一息ついてから、「風呂、洗ってくらあ、」風呂場にたつ。浴槽に、昨日の湯のくもり。風呂洗い洗剤を吹き付ける前に、たわむれで、昨日初めて抱き寄せた後輩の女の子の名を書いてみる。もう中年と呼ばれる年なのに、思春期の少年めいたことをしている自分が気恥ずかしい。だが、彼女は、少女のようにひたむきにオレを慕うのだ。オレが恋の気分を思い出して、何が悪い。タカコ書いた名をスポンジでこすって消した。シャワーからお湯を出して、さっとかける。―――消えない。指の油のせいなのか。タカコの文字がお湯のけむりに曇る浴槽のなか、うっすらと浮き上がる。ここに文字があることを知っているから、オレは気づいたんだろうか。妻は気づかないだろうか。むきになって、ぐいぐいこする。消えない、消えない、消えない。ふっと振り向けば、浴室の壁いっぱいに「タカコ、たかこ、孝子、タカコ」大小さまざまな文字が浮かび上がり、それぞれが湯気の雫をたらして泣いている。(気づいていたのか)縮み上がって、目が醒める。昨日は、なんでだか、夢の中で一生懸命、中学高校の学校図書館に生徒を集める方法について考えてました。漫画を置いてみる、ライトノベルを置いてみる、ついでに個々人の本の交換市を開いてみる。学校図書館くらいのサイズの図書館なら、図書館として発信するブログができるかもしれない。月に一回しか出ない図書館便りなんかより、よっぽど有効。だって出版って情報でしょ、速さが大事でしょ。今日の一冊、って毎日一冊ずつ学校図書館司書がレビューを書いて、生徒からの書き込みもできるようにして……ネットに常時接続のパソコンは貸し出しカウンターの側においといたらいいかな。他のサイトは見れないようにしとかなくちゃ。一台で足りるかな。コンピューター室のパソコンでも見れるようにしてもらってと。図書館のパソコン、一人の生徒が独占するようでも困るから、時間制にしてみようか。でも図書館の自由の雰囲気は残しときたいし。目が醒めて、びっくり。別に私は、学校や図書館のお仕事をしているわけではないのよ。ちっとも眠った気がしない。やっと、土曜になりました。
2006年01月13日
コメント(2)
-
天下一品
ここのとこ、お仕事が立て込んでいて、ばたばたばたとした毎日です。お昼休みもちゃんととれないし、なかなかお家に帰れません。ピアノのレッスンはさぼったし、図書館にも行けてません。なにより問題は、銀行のキャッシュコーナーに行けないことでしょーか。お財布が薄っぺらになっちゃって、いい加減おろしにいかなくちゃ。うわあ、手数料払いたくないよう。明日はなんとか、お昼に外に出れるかな?忙しくなると、むしょうに体に悪いことしたくなるんですよねえ。お仕事からの帰り道、「天下一品」でラーメン食べてきました。こってりしてて、塩辛くって、ヘンな匂いもする、ざらざらっとした舌触りのスープ。黄色い色の、断面の円い、太い麺。濃い味だなー、と感涙にむせぶ。最初はインパクトに驚き、半分食べ終るころには、味に飽きる。スープは飲まない。だって、濃いんだもん。このラーメン、美味しいのかまずいのか、よくわかんない。でもなんでだか、半年にいっぺんくらい食べたくなるんです。サービスで、食べ放題の小さなゆで卵がテーブルのカゴに積んであって、いっつも、ふたっつは食べます。コレストロールなんかに、負けないもんね。ふふん。闘志かきたてられて、お店を出る感じ。あと半年は「天下一品」のラーメン食べなくてすむかな。えい、がんばるぞ。がんばるぞ。
2006年01月12日
コメント(4)
-

アクアリウムの夜
稲生平太郎 角川スニーカー文庫年末にふらふらと購入した本です。帯に惹かれたんですよね。「ノスタルジーに満ちた青春小説。行間からにじみ出てくる恐怖と不安の表現。両者の奇跡的な融合。この「切なさ」この「恐怖」を未読で済ますのはあまりにももったいない!」宣伝文句として、ちょっと傑作だと思います。買っちゃった。1990年に水声社から刊行された単行本の文庫化らしいです。この文庫は平成14年発行。ノスタルジーも当然。おそらく90年代にすでに郷愁をもって語られた小説だったと思われる……すなわち今読むと、すでに古くさい。だけど気になる。ちゅうぶらりんの心地。水に満ち満ちた小説ながら、性的な描写がないところがとても気に入りました。ストイックなホラー小説です。セルロイドの下敷きに摩擦で貼り付くノートのページ、引き剥がすとき感じる温い空気のような物語。こっくりさん。不吉な予言。気が狂う同級生。幼馴染のセンシティブな少女。初めてのキス。喫茶店の美人マスター。図書館の美女。邪教の影。科学の不思議。薔薇の匂いのする香水。劇中劇。殺人。呪い。迷路。洞窟。そして、夜の水族館。キイワードどれか一つ、心にかすれば読んでみてください。ああ、でも、落ち込んでいるときは読まない方がいい。別の世界にトリップして、帰ってこれなくなりそうだよ。この話、完結しないんです。問いかけても、答えは返らない。できそこないの小説と言ってもいいと思う。だけど、なんだか悔しい。(私なら)このお話の意味が解るかも。再読したくなる魔法。もどかしい読後感。定まらない。
2006年01月11日
コメント(0)
-

ライオンハート
恩田陸 新潮社。どうもライオンハートってタイトル、スマップの歌を思い出しちゃっていけません。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。この歌、あんまり好きじゃなかったり。メロディラインが動かないから、聞いてて飽きちゃうんだもの。何が「あきれるくらい側にいてあげる」だ。親しき仲にも礼儀ありだぞ、なんて思っちゃう。ああ、鬱陶しい。連想で、この本に好感もてなくて、今まで読んでなかったのでした。ごめんなさい。あ、私スマップ大好きです。これも、ごめんなさい。―――くるくる、螺旋の中を歩きましょう。鏡で出来た家のなかで迷いましょう。行き止まりの鏡の壁に両のてのひらをあてて覗き込めば、鏡に映る私の瞳の中に黒髪の少年の像が立つ。あらら、私は何を見ているのかしら。あなたはだあれ?あなたはわたしのまことのこいびと。そんな話。生まれ変わり死に変わり、夢を過去を未来を恋は回る。もしかしたら、すべてが少女の妄想。もしかしたら、すべては初老の男の幻想。強く抱きしめるとはじけて消えるかもしれない。やわらかく包もうとすると、するりと逃げ出すかもしれない。虹。恩田陸らしいな、と思いました。剥離していく現実をわざと風にさらして七色に光らせるような、せっぱづまった感情の描写が冴えます。「夜のピクニック」も好きだけど、なんだかいっちゃってる、こんな夢の話も好き。ライオン・ハートはケイト・ブッシュの歌からとったらしいんですが、多分、聴いたことがありません。「ジェニーの肖像」へのオマージュだそうです。読みながら似てるなあ、とは思ったけれど。「飛ぶ夢をしばらく見ない」や「夢館」も同じテーマかな。あしべゆうほの「悪魔(デイモス)の花嫁」とか。違う?
2006年01月10日
コメント(2)
-
17歳バトン
いつもお邪魔しているtuitelさんから、17歳バトンをいただきました。17って数字がいいですよね。割り切れない数って、好きです。1.17歳の時、何をしていた?本を読んでた。多分。佐々木丸美を初めて知ったのが、17歳のときだった。世界史の先生が大好きで、授業のある日は髪にリボンを結んで通学してた。15歳年上の人のところに、お嫁に行くのが夢だった。2.17歳の時、何を考えてた?そんなに丈夫じゃなかったから、雨が降る日は熱が出ていた。特に四月は、家に帰って扉を開けると板の間にくらりと倒れる。気疲れ。こんなに弱くて、ちゃんと二十歳になれるのかな、なんて思ってた。……意外と丈夫でしたけどね。まだ酒も競馬も知らない17歳。祖父が亡くなったのが18のときだったから、人が死ぬってことを何にも判っていなかった。3.17歳でやり残したことは?そりゃまあ、恋でしょう。歩道橋の上で待ち合わせしたり、手をつないで学校から帰る途中同級生を見かけてぱっと離れて他人の振りしたり、うっかり9時過ぎて家に帰って父親に怒られたり、10時に電話してねって約束してコードレスホンの子機を確保して部屋にこもったり、制服の袖口のボタンをはめてあげたり襟元のボタンをはめてもらったり、ああ、してみたかった!4.17歳に戻れたら何をする?駆け落ち!5.17歳に戻っていただきたい人どうぞ、どなたでも。けっこうお馬鹿さんだったので、もう一回はしたくないなあ。17歳。
2006年01月09日
コメント(4)
-
たーすーけーてー
私は祖父母に育てられたようなものなので、食べ物の感覚が少し古いです。お大根なら、葉っぱを食べるところからはじめる感じ。ゆで卵を醤油につけて食べるのって、親はしないけれど、私はします。おかずがないときは、白飯に醤油を一差ししてかき混ぜて食べたりとか、するもんね。醤油やお味噌は酒屋さんから年末に一年分をまとめて買ってた。今思い返すと、あのお醤油もおいしかったんだなあ、と思う。島根の方からかごを背負って、昆布や若布や干物を売りに来ていた人もいました。ぱりぱり板若布あぶって食べるのが三時のおやつだった……っていうと、十歳年上の人から、「自分だって知らないぞ、君はいつの時代の子供なんだ」って突っ込まれます。同級生とはハナから話が合いません。いーの、私が子供のころは、卵は量り売りで、月に2回くる軽トラックからカゴで買ってたんだから。ときどきポン菓子の機械が農協にくることがあって、祖父が甘いぱらぱらの弾けた米を持って帰って来るのが楽しみでしょうがなかった、やーい、うらやましいでしょー。(そうか?)今、悩みがあるんです。贅沢な、悩み。畑仕事をなさっている連れのお父様お母様が、年始に、おっきくて立派な白菜を丸のまま、二つ、くださったのですね。それから大根二本にブロッコリ、ピーマンとニンジンとたまねぎとシイタケと……。見た目は悪いんですけど、ポリバケツサイズのビニール袋あるじゃないですか、それ2袋分いっぱいのお野菜をいただきました。ブロッコリ・ピーマンなどの青物類はなんとか3日で片付けました。そんでもって、ここ一週間、毎晩毎晩、白菜たっぷりの鍋ナベ鍋……。あと大根一本、白菜一個、というとこまでこぎつけて、この三連休の鍋コンポで片付くぞと安心していたのですが、今朝、連れの実家から宅配便が届きました。……段ボール一つ、まるまるお野菜。もう一箱はお餅と味噌とお惣菜。たいっへん、ありがたいのですが、このままじゃ白菜、腐ってしまいます。初めてのお漬物に挑戦、とも思ったのですが、うちはあんまり漬物食べないし、お惣菜一箱の中に、白菜のお漬物の樽を一つ入れてくださっているんです。大根は、切って干そうと思うんですが、白菜!とにかく白菜!!腐らせちゃったら、天国の祖父に顔向けできないじゃないですか。「また、鍋?」なんて、ついに連れは言い出すし。今晩はお母様が送ってくださった、赤飯とお煮しめと伊達巻と魚の煮付けをお膳に並べて、私は白菜のお味噌汁しか作らないからね!あーん。白菜みっつ、どうしよう。
2006年01月08日
コメント(4)
-
最初の日
昨夜、ぼくはたけるとケンカをした。最初はたけるとミカンでキャッチボールみたようなことをして遊んでいたんだ。手元がくるってタケルの顔にぶつけてしまった。ごめんってちゃんと謝ったのに、タケルが2個も3個もミカンを立て続けにぼくに放ってぶつけてくるんだもの。なんて奴だ。ぼくも応戦して、ミカンをたけるに投げつけた。居間は雪合戦ならぬミカン合戦の様相を体していき、ただのケンカに変わった頃に勝が入ってきて、ものも言わずにぼくとたけるに一発ずつ拳骨を入れた。唇をかみ締めてミカンを拾い集めるたける。たけるが悪いんだ、と勝にくってかかるぼく。食べ物を粗末にしたことを怒ってるんだ、と勝がまた僕を殴る。たけるは口をきかない。収拾がつかなくなってきたところ、居間の肘掛け椅子に腰掛けて静かに本を読んでいた幸が、手にした本の背の角で、机をコツンとたたいて硬質な音を立てた。「うるさい。」それだけ言って、自室に帰るべく立ち上がった。うずくまったたけるの頭をすれ違いさま、くしゃりと撫でる。「二人とも、悪い。」それだけ言って、ふわりと笑った。きれいだった。たけるがすうっと泣き始めた。「ごめんなさい。」やっと二人して言って、ぼくたちのケンカはけりがついた。朝、たけるが起こしにこないから、ぼくは眼が覚めてもずっと眠っていた。うつらうつら、ぼくは怠けるのが大好きだ。カーテンを超えてまぶしいような光が部屋を満たしていた。雪が降ったのかな、と思った。昨夜はとても寒かったし。(そんなら、たけると雪合戦しよう。)たけるは簡単に熱を出すから、しっかり厚着させて、外に連れ出そう。大声をあげて騒いで、幸にうるさいと怒られて、服をすっかり汚して帰って勝に叱られて。でも、いいんだ。たけると、いっぱい遊ぼう。あんまり長いこと、たけるが来ないから、ぼくはついにお腹がすいて自発的にベッドを抜け出した。こんなこと、百年にいっぺんくらいしかない。台所では、勝が食卓に肘をついて、がっくりと頭を落としていた。台所には火の気が全然なかった。サラダが4皿あって、生卵が8個転がっていた。油が引かれたフライパンが(いつでも卵を割ってください)って、ぴかぴか光っていた。7時5分で、台所の時間は止まっていた。びしょぬれの本が、勝の前にあった。不吉な予感がして、ぼくは勝に声をかけずに、たけるを探した。居間の出窓のカーテンの向こうにもぐりこんで、たけるはうずくまっていた。庭にも道にも、うっすらと雪が積もっていた。足跡はひとつもなかった。幸がどうなったのかは、聞けなかった。気配のかけらも残ってなかった。濡れた本。それだけ。たけるが透明な目でぼくを見た。(泣かないの?)声にしようとしたら、涙がこぼれた。「僕は、昨日、泣いたから。」たけるは強くカーテンを握り締めていた。指が、真っ白になってた。家の中を見ないたけるの脇で、僕は嗚咽をこらえず泣きじゃくった。
2006年01月07日
コメント(0)
-
新年会と日本人
今朝、お財布の中をのぞいたら、千円札が一枚だけ。(あー、年末年始で使いすぎちゃった。)反省しながら取り出すと、そのお札はなんと5千円札だったのでした。まあ、すてき。4千円ほど、儲けた気分。新年最初の金曜日、誰か呑みに誘ってくんないかなー、なんて思いながら残業してました。かねてからの懸念の電話が一つつながって、問題の解決を得てやれやれと肩の荷を降ろしていると、ばーんと現れた先輩。「おい、呑みに行くか?」「行きます!」いやーん、なんて素敵なタイミング!あんまり話したことはない、だけどいつもすれ違うときにニコニコ挨拶を交し合う、後輩の男の子も同じ席にいました。何、話そうかな。なんて思ってたんですが、先輩が「この男の子、おもしろいんだよ。本を読む子なんだけど、先般、同僚(美人)におもしろい本・おすすめ本貸してって言われて何を持ってきたと思う?」「?」「『日本人とユダヤ人』だよ!」「……イザヤ・ベンタザン?」「ほら、知ってるじゃないですか。皆、知ってますよねー、大ベストセラーですもんね!」意気揚々と参戦する彼。「私は読んだことないけど。胡散臭いんでしょ?」「胡散くさいです。」「二十代で『日本人とユダヤ人』読んでる人、初めて見た……」ちょっと絶句。というか、感歎。先輩が、「ね、おっかしいでしょ?せめて辻仁成のピアニッシモとか、持ってくればいいのに。」「「あれはおもしろくない!!」」彼と私は同時に言って、ん?と顔を見交わして。「とおりさん、読む人ですか?」「割と、好きです。そちらは?」「カミュとかカフカとか、不条理なやつが好きです。」「私は日本近代文学あたりをよく読みます。」それでカフカと夏目漱石の話で盛り上がりました。同じ座の先輩二人はあきれかえってた。居酒屋でする話か?って。小説の話を嬉々としてするなんて、親元はなれて初めての一人暮らし体験中の彼の孤独は本物だ、なんて。でも多分、彼はほんとに楽しかっただけじゃないかなと。読むのが好きな子なんだなあ、としみじみ判りました。とりあえず、私は楽しかった!共通の話題を探しながらじゃない、真剣勝負の会話だったので。この日のお料理は水菜と白身魚と湯葉のサラダが絶品でございました。わさび醤油のノンオイルドレッシングがぴりりと効いて、いくらでも食べちゃえます。あのドレッシング、どうやって作ってるのかしら。醤油辛くもなかったんですよね。ちょっと、気になる。
2006年01月06日
コメント(8)
-
ちょっとだけ、じまん。芥川の本。
芥川龍之介に関する、本・雑誌・叢書。小声で言い添えれば、全部じゃないです。実家に帰って拾い読みしていたのですけど、ちょっと自慢したくなって、写真に撮ってみました。うふふ。芥川本人の小説はあえて入れてません。あ、でも上、左から2冊目の「河童」は芥川。これ、はじめての中国旅行で買って帰った、中国語に翻訳された短編集。後期作品が収録されてます。漢字だけが重ねられた文で正確には読めやしないのだけど、元の日本の小説を知っている分、意が汲めるのが嬉しいのでした。右上の本は「追想 芥川龍之介」 芥川の奥様、文さんの語りがまとめられています。家族として、一番近くにいた人として、我が夫の死に焦がれる様、追い詰められ消え行こうとするところ、気づく。鈍い振りをして必死に夫を引き止める文さんの言動はひどく切ない。二人とも聡い。お互いの芝居も見抜いて、嘘がつけない。(僕はもう、死ぬよ。)(まって、もう少し。生きて。)声に出せない駆け引きのすえ、ついに旅立った芥川の枕元、安らかなデスマスクに「お父さん、良かったですね。」呟いてしまう。凄絶。だけど文さんの語りは、ほのぼのとして、温かい。きれいな人だな、と思う。この本、文庫化もしてて、絶版ではあるけれど、古本でなら、かなりお手ごろ価格です。一つの夫婦の形として、悲しくも美しい、ほんとうにあった話。もし見かけたら、ぜひに読んでみてください。星のかなたを見たくなる。そんな愛があります。他の本の紹介は、またいつか。
2006年01月05日
コメント(7)
-
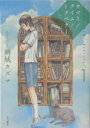
タイム・リープ
高畑京一郎 メディアワークス95年の出版だよ。こりゃまた、10年前の小説なのですね。しまった!筒井康隆の「時をかける少女」を初めて読んだのは、中学生のとき。小学生のときにはもう、歌ってましたよ。「とーきーを、かーけーる少女 あーいーは」原田知世ちゃん。で、よかったっけ?古本屋でやっと手に入れて読んだんです。ブーイング承知で言っちゃうけど、「時をかける少女」そんなにおもしろくなかったです。だってあれ、題材だけのお話でしょ?ドラマや映画になったとき、演じた少女の初々しさが輝いて名作になっただけ。お話としては、大したこと、ございません。いまさら「時をかける少女」を読むくらいなら、「七瀬シリーズ」をお読みなさい、って。わあ、石投げないで!でもね。多分、少年少女の読むお話のなか、わくわくしたタイムトラベルを教えてくれた最初の本が「時をかける少女」だったのだと思う。遅れて読んじゃった私は地団駄を踏む。やだやだ、もっと前に読んでたら、もっともっとおもしろかった小説だった!この「タイム・リープ」も。10年前に、読んでたら良かったな。『タイムトラベルならラベンダーの香りのやつも車に乗るやつも知ってる』なんて、和彦少年は言います。私はこの小説は『ラベンダーの香り』のやつのオマージュだと思った。10年前にしても古くさい文体。ジュブナイルSFってタイトルの脇につけようか?なんだか懐かしいの。無性に懐かしいの。じたばたと甘えるだけの女の子。けれど彼女が事件の中心で。黙して語らず、あくまで知的な男の子。いつでも彼が切り札で。パズルのような時間。組み立てられる事件。追いかけろ、追いかけろ。昨日に追いつけ、謎を解け!新城カズマの「サマー・タイム・トラベラー」に「タイム・リープ」のタイトル出てきたんだよね。うん、あの子らが読んだ本ならやっぱり読んでみなくっちゃって読みました。タイム・リープしか読んでない人にはサマー・タイム・トラベラーをどうぞ。未来かもしれないお話です。
2006年01月04日
コメント(5)
-
ミギワの憂鬱
彼女の名は月待 汀 (ツキマチ・ミギワ)。ブライスドールのラブミッションである。通称ミギワ。黒髪ブライス・チェリーベリー(仮名・月待 港)とともに我が家にお迎えされる予定のところ、哀れ、金銭の事情によりミギワ嬢のみ我が家へ来たれる。すなわち彼女は、あらかじめ失われた双子となる。彼女は二階にこもりて出ること好まず。お洋服はデフォルトのドレスのみ身につける。しっとりとした濡れたような黒髪に手を触れること許さじ。ロッタ、ぴあの、バニラ、木綿、とおり家のブライスに馴染むことできず、孤高にして一人たたずむ。幻想的な小説を好む。ストイックでありたいと望む。もしかしたらロッタとは友達になれるかもしれない、と夢想する。ぴあの、バニラ、木綿の無邪気には、自らは馴染まないと、距離を置く。而して、バニラ、木綿は引っ込み思案なやさしさから、ぴあのはその天真爛漫な残酷さでもってミギワと関わろうとしない。ロッタは誰とも同じく距離を持つ自立したブライスがため、少女でありながら天使に近い。周囲となじめない個性を静かに受け入れるロッタは、とおり家ブライスから羨望の意をこめて少々の距離を置かれている。ミギワはロッタの孤独を私こそが理解できると意気込むが、ロッタの自然の孤独にまけて声をかけられない。(あの寂寥たる雰囲気を私も身につけたい。こんな荒涼たる淋しさではなく。)ロッタの方から話しかけてくれたらいいのに。祈る夜がまた過ぎて、ミギワは一人窓際に立つ。
2006年01月03日
コメント(6)
-
つれづれなるままに
テレビがあんまり好きじゃなくって、今年のお正月は本を読む読む読む。といっても、拾い読みのつまみ読み、再読くりかえして、積読本はちっともへっていないんですけど。えーと、「日本近代短編集」をまず開く。林芙美子の「晩菊」を読む。もうおばあさんになりかけた妖かしい女が、かつての年下の恋人(彼ももう若くはない。が、女よりも若い)と再会するために自分を美しく装うところが何度読んでもおそろしい。化粧というのは化けるってこったな、なんて。横光利一の「蝿」を読む。こんな話だったっけ。すくいあげようとして救いあげきれない事実。どうも苦手な読後感。だから忘れていたのかな。中井英夫の「幻想博物館」のなか「大望ある乗客」もこんな話だったかな。読み返そうか。ちょっと大儀かな。あ、でもこの一瞬の崩壊の手妻は原民喜の原爆文学にもあるってどっかで小耳に挟んだな。原民喜の本は私の本棚になくて、この短編集から「夏の花」を拾い出して読む。こうの史代の「夕凪の国」で皆実が逃げた町の風景と同じ。(アレハホントウニアッタコトナンダ。)みずから間近に設定していた死を、この惨劇のため原は引きのばす。幾編かの死と散文を残した後、かねてのぼんやりとした不安のとおり自殺する。彼は原爆により永らえた人なのだと信ずる。負けたわけじゃない。志賀直哉の「ハンの犯罪」(ハンはクサカンムリに氾。)も収録されていた。サーカスのナイフ投げの話。妻を殺したのは、事故か殺人か。人は死んだ。罪はあるやなしや。息詰まる。さて、ここで「昭和ミステリー大全集」に飛ぶ。あれ、「ハンの犯罪」収録されてないじゃない。芥川の「開化の殺人」もないや。じゃあ、こっち。河出文庫「文豪ミステリ傑作選」。これには採ってあった。あ、やっぱりこっちにも谷崎の「途上」入ってる。おもしろいもんね。語りの妙、畳み掛けるサスペンス、をちょっと味わいたい気分になったので本屋に出かける。アイリッシュを探したけど、ない。帰ってきて本棚をあさる。みっけ。再読だけど、「黒いカーテン」。あまりのご都合主義の展開にちょっと嫌になる。あれれ、こんな話だったっけ?小学生のときはクリスティよりエラリー・クイーンより、いちばん大好きだったのに。なんかちょっと昔の映画的。読んでたら、作者の演出が鼻につくんだけれど、有無を言わせず映像で見せられたら文句なくドキドキしそう。2時間半くらいでまとめて欲しいなあ。さて、文豪ミステリにもどって。川端の「それを見た人たち」太宰の「犯人」三島の「復讐」。けっこ、おもしろい。今の推理作家って、文章が下手なんだなあ、と思う。筋が面白いからいいんだって言ってたら、結局ミステリと小説のカテゴライズ分けはなくならない。そんなの、ミステリを殺すよ。おおっ、ミステリ作家によるミステリ殺人事件だあ、わはははは。われにかえって、三島といえば、レター教室。ごそごそまた本棚をあさる。林芙美子の「晩菊」からの連想も働いたんだなあ、なんて氷ママ子(45歳)の「裏切られた女の激怒の手紙」を読みながら気づく。こっちは朗読劇にしてほしい。私は空ミツ子ちゃんの手紙を読むよ。結構たくましくて性格悪くって、頭悪そうだけれど計算はしっかり。でもやっぱりかわいい。私、読んでいい?やっぱだめ?氷ママ子さんの手紙読めって?いくらなんでもあそこまで悪女じゃないと思うんだけど。それにしても、この本、ほんとうに好きだなあ。性格が悪いか頭が悪いかの人しか出てこない小説(?)なのに、毎年読んでるような気がするよ。鏡花の「眉かくしの霊」を読む。うわ、こわっ。怪談だよ、これ。どうかKWAIDANと発音してくださいって感じ。明治の小説ですけど、近代を感じます。鏡花先生の意地っていうか。美しいって、怖いでしょう?つづいて内田百間の「サラサーテの盤」を読む。これはまた……怖いよう。たそがれ。怖い話を続けて読んで、小説読むのがいやになったので、新潮選書の「古書街を歩く」紀田順一郎を読み返す。天下一本と言われた「楚囚の詩」を古書市で30銭で手に入れた学生の逸話は何度読んでも興奮する。最近本を買うのをすっかりやめてしまったのだけれど、こんな本を読んでしまうとまた古書店通いをしたくなる。そういえば「アンドロギュロスの裔」渡辺温、薔薇十字社。昨日楽天フリマで検索したら2万円で出てました。図書館で博文館から叢書で出てたのは読んだんだけど、薔薇十字社の本にはお目にかかったことがない。30年くらい前に出版されているんです。2万で買えるんなら、もしかしたら安いのかもしれないな。でも高いな。華やかなショッキングピンクの装丁の写真をしばし眺めて、なんとなく思いついて尾崎翠の「アップルパイの午後」を検索してみた。これもかつて薔薇十字社から出てて、こっちはレモンイエローの装丁だったそう。(今は全集が出てるから、尾崎翠の方はそう苦労せずに読めますけどね。だからあんまり高くないんじゃないかなって。)ピンクとイエロー、2冊並べて本棚におけたら至福かもしれないな、なんて。みつからないから、あきらめる。目がさめる。薔薇十字といえば、薔薇十字探偵社。このあと、京極堂シリーズに流れるか、それとも芥川の評論と全集を積み上げてつまみ読みを続けるか。文豪ミステリにとられてたのが「開化の殺人」ってのが、腑に落ちないのよね。「藪の中」とか「地獄変」とか、だめ?芥川といえばその死の原因が私にとって、永遠のミステリー。ひさしぶりにたどってみようかなあ。なんかすっごい長文の日記になったけど。ひさしぶりにインプット多かったので、ごめんなさい。
2006年01月02日
コメント(6)
-
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます!新年最初に何の本を読もうかな、なんて思いながら寝付けないでぱらりぱらりと文庫本をめくっていたら鳴り出しちゃった除夜の鐘。「昭和ミステリー大全集 上巻 新潮文庫」が今年の年越し本になりました。上巻しか持ってないんですけど、「新青年傑作選」と「文豪ミステリ」の中篇短編をミックスしたつくりになってて好きなんです。だってすごいんだよ、巻頭は佐藤春夫の「指紋」だもん。谷崎潤一郎の「途上」なんか大好きです。大晦日に「刺青」も読んでたんですけど、「途上」はエンタメなので余計な描写がなくて実に読みやすい。河出文庫の「文豪ミステリ傑作選」にもとられてたと思う。それにしても新年早々切ったはったの小説なんて物騒だわ。水谷準の「お・それ・みお」渡辺温の「嘘」。かわいて透明な幻想小説を選んで読みました。乱歩や夢野は、ちょいと避ける。渡辺温はいいなあ。燕尾服とシルクハットの正装で畳敷きの博文館の編集室に出勤した人。27か28歳で事故で死んじゃって、その透き通る不思議な短編小説はわずかしか残っていない。プレパラートのガラス越しに別の日常にまぎれこむような短編を、私は愛します。ためいき、ひとつ。あわい息。我が家のお雑煮は、すまし汁仕立てで、煮た丸い餅が入ります。カキがふたつ、はまぐり一つ。ざくざく切った水菜。それからカマボコ。おいしゅうございました。お母さん、ありがとう。さて、汽車に乗って、初詣にでかけましょうか。ブライス代表ロッタとともにご挨拶。今年もよろしくお願いします。
2006年01月01日
コメント(8)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2026年 1月号』 ガメ…
- (2025-11-26 21:00:05)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- お勧めの本
- 首都圏は米軍の「訓練場」 [ 毎日新…
- (2025-11-27 07:40:04)
-







