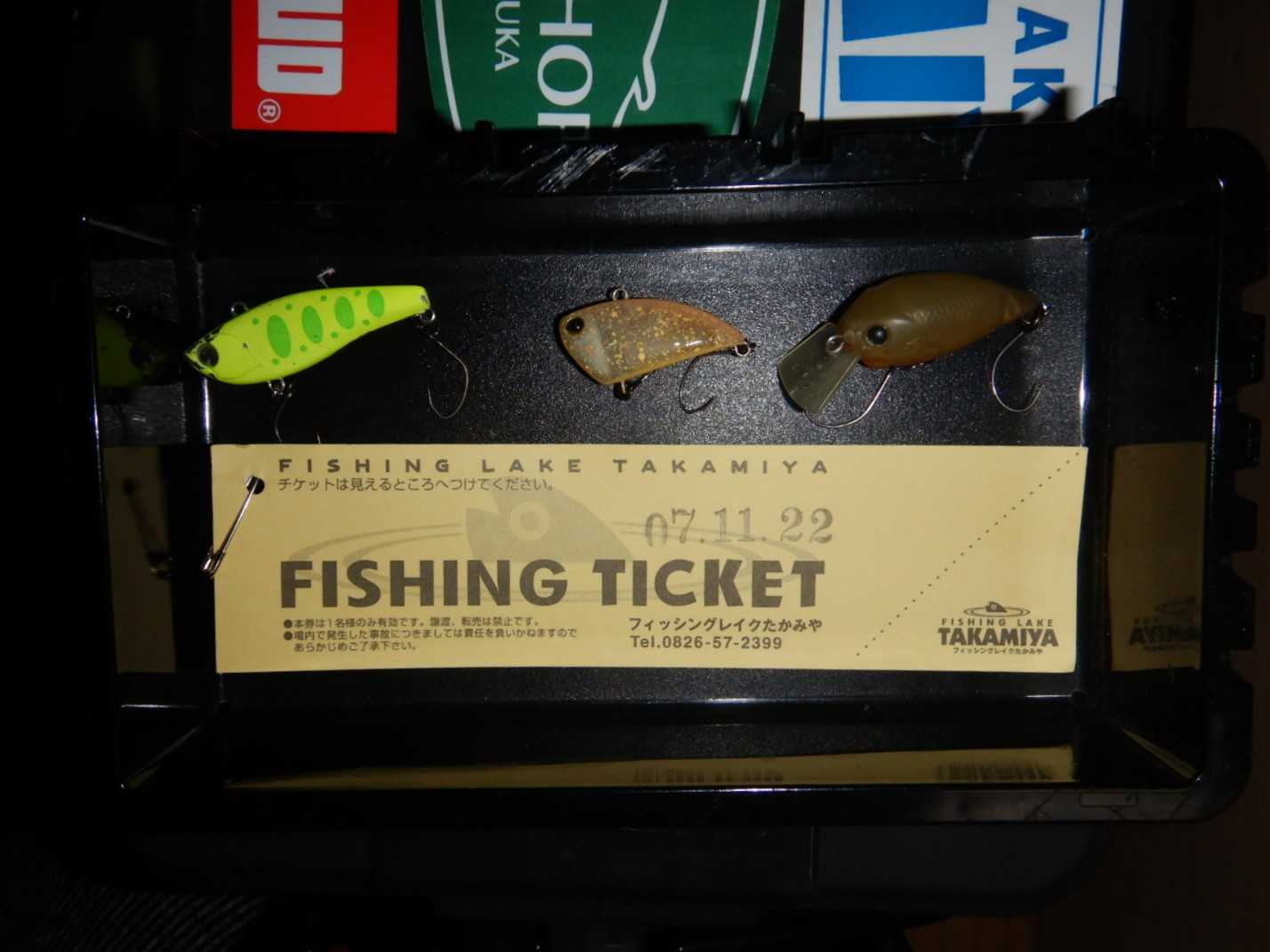-
1

大きすぎる獲物に四苦八苦のミサゴ
先週金曜日から4日間は珍しく釣りを休んだ。連休明けの火曜日から3日間は連続で釣りをするも、無残な結果に終わって、28日は釣りをする気にもならなかった。 それでも徘徊はしたが、寒気が流れ込んで雲が多く、いよいよ冬の福岡日和になって写真撮りにも良くない日々が多くなってきた。 そんな中、今津でミサゴが増えてボラを捕る姿を見られてそれなりに楽しんでいる。 28日は今津から糸島の加布里湾まで行って見た。どこもカモ類は例年より少なく、他の冬鳥も少ないような気がする。雷山川下流では1羽のコハクチョウを見た。 帰りも今津湾へ再度行って見れば、ミサゴが数羽ボラを狙って飛んでいた。その1羽が降下ダイブしてどうやらボラを捕らえたらしいが水面から飛び立たない。こんな時は大物を掴んでいることが多い。しかし飛び立てない程大きいのはあまり無い。結局飛び立てずに水面を泳いで、少し離れた所にあったゴミの塊かカキ礁に上がった。姿を見せたボラは60cmも有ろうかという大物で、これを食ってしまうのかと見ていると、アオサギがやって来てボラを横取りしようとした。ミサゴは驚いたのか飛び上がってボラを運ぼうとしたが重さに耐えかねたのか水面に落としてしまった。 ボラはゆっくり下流に流れていて、ボラを落としたミサゴが一度戻って来て、獲物を回収しようと掴んでは見たもののやはり落としてしまい諦めて去ってしまった。 アオサギはボラを嘴で挟もうとしても、大き過ぎてどうにもならなかった。おこぼれ狙いのユリカモメ1羽が未練げに水中のボラを突っついていた。結局大ボラはどれにも食われずにゆっくり流れてしまった。 釣りでも言えることだが、身に余る大物は釣れても良いことは無いのは同じ。28日行きカイツブリ小物のボラを捕ったミサゴヘラサギ糸島雷山川下流のコハクチョウしばらくしてコハクチョウは突然飛び立っていなくなった。一時的な休憩だったのだろう。加布里湾のクロツラヘラサギは毎年10羽ほどいるが、1羽しか見られなかった。小型のシギホウロクシギが3羽摂餌していたハヤブサの若鳥ハヤブサの手前をカルガモが飛ぶ。ハヤブサの獲物はハトぐらいの大きさまでが殆どで、通常中型のカモ類は襲わない。雷山川と長野川の合流地点。潮が引いている状態。キジバト今季は見ることが無かったハイタカが上空を飛んだ。モズ雄野辺のクロガネモチこの木の下に地蔵様が祀られていた。顔が定かではない。晩秋、あるいは初冬の可也山。帰り道で見たチョウ。ウラギンシジミのようだが色と模様が異なる。タテハモドキがまだいた。水路のクサシギノスリが2羽いた元岡の水田背中に発信機か何かついているノスリ。以前に見た同じ個体か。ミサゴ獲物を掴んで飛び上がれないミサゴ。落とした獲物を回収しようとするミサゴ。持ち上らないアオサギがボラを嘴で挟もうとするが大き過ぎて出来ない。アオサギは悪食で大きいものでも食ってしまう。流石のアオサギでも大ボラは無理。別のミサゴ狩りに失敗このボラも大きいが掴んで飛んでいる。突然飛んで来たカワセミに対応できない。ハシビロガモ26日ミゾソバセリの若葉が出ている。何年も釣ってなかったサヨリが1匹釣れた。27日サヨリを釣ろうと仕掛けも作って唐泊で試みたが、バンチャゴとスズメダイが湧いて1匹も釣れなかった。小型のボラを2匹捕っているのは珍しい。興徳寺
Nov 28, 2025
閲覧総数 25
-
2

薄暗い山道を抜けると、眼前に広い海と岬が現れた。
6日は先日蒙古山に登った際に、山頂に向かう道とは別にやや下る、車1台が通れる道があったので、その先へ行ってみることにした。蒙古山には西浦崎へ行ける道があると聞いていたのでそれだという確信が有った。 西浦漁港から灘山を見ると、強い北風のせいか山頂には霧のような雲がかかっていた。蒙古山はこの左にある。 電波塔の所まではバイクで登り、そこからは歩くことにした。マダケで杖を2本作って歩い始めた。いつも行く釣り場の近くに行ったことが無い場所があるのは不思議な感じがする。西浦崎は2年前に対馬へ行った時に船上から見たが陸上から、陸上からは決して見ることが出来ない糸島半島の最北東端なのだ。道は薄暗く、ダンチクが覆いかぶさるように垂れ下がっている。ぬかるんだ道に真新しい轍が残されていた。常緑広葉樹がうっそうと茂っている。昔植林されたのか杉も少し生えていたが、枝打ちされていないのでスギのようには見えない。車で運んで来たらしいゴミが捨てられていた。木々はかなりの大木になっていて、タブやモッコクなど海岸近くの山に見られる木々が多い。車まで捨てられていて、苔むすままながら朽ち果てることも無く原形をとどめていた。多くの山道でこのような車などの遺棄が相次いだために、通行禁止になっている。歩いても歩いても開けた所は無く、やぶ蚊に悩ませられながら1kmぐらい歩いた。突然道が明るくなり、海が見えた。さらに進むと道は下り、車が1台止まっていて、その先は満ちは人一人がやっと通れる狭さになった。車の主は釣りに来ているのだろう。ここまで畑も無く、車が通れるこの道は,釣りに来るためだけに作られたようだ。誰が張ったのかロープがあった。車道の終わりから200mぐらい狭い道を歩いたら、一気に視界が開けて左に西浦崎らしい岩が現れた。それまでずっと暗い道を歩いて来たので、突然の解放で大いに感激した。北東方向には玄界島が頂に雲をまとって浮かんでいた。玄界島の手前には机島と小机島があって、この場所からは2つは重なって見える。西から壱岐対馬航路のヴィーナスが走って来た。博多港へ向かう。飛行機雲のような航跡を残して。海から蒙古山山頂へはなかなかの急傾斜だ。海への下りは急勾配で、ロープを掴んで岩を下らなければならない。釣り道具一式を持って降りるのは難儀なことだろう。膝が悪いので降りるのは断念した。ハマナタマメの花が咲いていた。眼下で釣りをする人がいた。見ているとコッパグレが釣れた。オニユリが1輪。 しばらく心地よい風に吹かれてから引き返した。また訪れることがあるのだろうか。岬へ通じる道も途中にあったようだから、今度はそちらへ行ってみたい気がした。アカウシアブ。途中のベンチに止まった。キクラゲを見つけて採取した。 蒙古山を下りてから、帰りは山道を通った。パンパスグラスの穂が出ていた。あちこちに咲くヒメヒオウギズイセン。ツバメシジミ。キタキチョウの交尾。ムラサキシジミ。タラの花。 さんざん徘徊したのに夕方には小戸公園へ夕日を見に行った。ネジバナが例年より遅く沢山咲いていた。干潮で潮間帯には紅藻類がびっしり付いていた。外海よりはるかに海藻が多い。近くに下水処理場が有るし、湾内で栄養分が多いのだろう。外海の磯焼けは深刻な状態なのにこの辺を研究すれば出口がありそうな気がする。とかく食害動物が磯焼けの原因と言われるが、主因と副因を取り違えている。4日月。日暮れのコウモリ。
Jul 7, 2019
閲覧総数 1388
-
3

この春の釣り場の魚異変。
水木金と3日連続で西浦へ釣りに行った。雨か曇りの日が多いが気にはならないが、港内ではもう大しては釣れない。イカ釣りにもちょっと色気を出しても、ヤエン釣りでは相変わらず1度も当たりが無いままで終わりそう。 9日金曜日は豆アジを釣ってヒラセイゴを釣ってみようと、何時もより30分早く着いて、例年豆アジが多いポイントで餌を撒いて探ってみた。予想していたとはいえ、トウゴロイワシばかりで豆アジは1匹も見えなかった。35年間で初めてのことで、昨秋からアジが港周辺から消えて以来全くアジというものが消えてしまった。 しようがないから何時もの場所でコッパメジナを釣ることになる。ここでもトウゴロイワシが席巻していてあまり釣れない。時々釣れるコッパメジナは10cmぐらいしかなく、持ち帰るものは極少ない。 そのメジナが70%クロメジナだった。年々クロメジナの割合が殖えてはいても、通常のメジナの方が多かったのに逆転してしまった。まだ足裏サイズのクロメジナは少ないので、今後どうなるのか見ていきたい。上がメジナ、下がクロメジナ。 トウゴロイワシを泳がせてヒラセイゴを1匹釣った。秋には40cmぐらいになるがまだ小さい。 まだマダケの筍が生えつつある竹林がある一方、殆ど生えないまま終わった竹林も多い今年。迷彩の皮はイノシシには通用しない。キヌガサダケを再び見た。これまで1度も見てなかったのに、最近2度目となった。この頃よく見かけるムラサキシジミ。疲れたイチモンジチョウ。アブの仲間チャイロムシヒキ。しばらくして、イチモンジチョウをこのアブがあっという間に捕まえた。恐るべきハンター。ハナバチはガクに隠れた本当のアジサイの花を知っている。花粉を大きな団子にして足に付けている。めっきり見ることがなくなったシマヘビ。1.5mはある。瞳孔の大きさが変化している。メスグロヒョウモンの雌。雄のメスグロヒョウモンが現れて、執拗に雌を追いかけた。逃げても逃げても雄は追いかけた。恋が成就したかどうかは不明。最近流行りの未利用魚の利用にもなりそうなトウゴロイワシを甘露煮にしてみた。小さい割に背骨が硬いので30分間圧力なべで煮てから煮詰めた。十分美味い。干物、揚げ物、刺身など何れも美味く、魚体が小さく鱗が堅いのがネック。8日。ヒラセイゴが多くいたせいかメジナは釣れなかった。7日。ツルマンネングサ。シロコブゾウムシ。完全に保護色。イタドリの花。ザクロの花。畑に生えたマダケ。伸びるのは相当早い。放置すると2,3年で竹やぶになる。水路のオオカナダモ。原産地はアルゼンチン。雄雌異株で日本には雄株しかないらしい。ムスジイトトンボの産卵。前が雄。
Jun 9, 2023
閲覧総数 305
-
4

糸島市福吉漁港で初めて釣りをした。
これまで30年以上糸島方面で徘徊やら釣りをしてきても、まだ行ってない場所がある。その一つが二丈の福吉漁港だった。近くに道の駅の福ふくの里があり、この夏以降何回かカマスを買いに行った。自宅から原付バイクで1時間近くかかり、いつも釣りに行っている唐泊や西浦の2倍の距離がある。 大型のカマスがこの秋は釣れないので、加工して自分で食ったり送ったりしたい時には少々遠くても苦にはならない。それでも往復2時間かけるだけでは芸がないとふと気が付いて、店から2分で行ける所に福吉漁港があることに気付いて、釣りと買い物を絡めたら楽しいだろうと6日に実行した。 朝6時に出た。道中バックミラーには、高架の隙間の東の空が朝焼けになっているのが見えて、バイクを止めて写真を撮った。高祖山が日の出位置にある為、なかなか朝日が出ない。福吉漁港には7時頃に着いた。漁港は広く、漁船は思いの外多かった。その上最近流行のプレジャーボートはほぼ皆無で、この地区の漁業が盛んなことが分かる。防波堤は長く、先端近くの50mぐらいはテトラが無く平場で、ここで釣ることにした。初めてなので何が釣れるかも分からず、サゴシ狙いの竿と反転籠用の竿を準備した。 福吉は地形的には広い唐津湾の東に位置し、外海とも言えるので2日前の強風によるうねりがあった。海も濁りが残っていたので潮も悪く条件は良くなかった。 店が開店するのは9時だから、2時間近く釣りをする時間があった。まずサゴシを狙ってジグを投げてみた。跳ねてもおらずサゴシは釣れなかった。すぐに反転籠に切り替えて釣ってみると、何投目かで小さい当たりが有って、仕掛けを揚げてみると針が無い。どうやらフグがいるようで、以後はフグとの攻防だった。 釣り場には数人の釣り人がいて、アジゴはよく釣れていた。9時までの2時間はあっという間に過ぎて、針を5本失いながら15~25cmのナシフグが20匹ほど釣れた。 釣り道具一式を置いたまま、福ふくの里へカマスを買いに行った。開店時には20人の客がいて、その多くは魚目当てだった。 時化の後だから魚は少なかった。カマスも少なく、大小25匹購入して福吉港へ引き返した。後半戦もフグばかりで、食いは低調になっていた。11時まで釣って、終わりに近い時点でサゴシが跳ねたのでジグを投げてサゴシがヒットした。30cm位のが多かった中で、幸運にも釣れたのは46cmあった。 結局ナシフグは30匹釣れて、人によっては最悪の外道だろうが、肉には毒は無いので捨てはしない。北の海上に姫島がある。筑肥線の電車。線路脇にはオシロイバナが咲き誇っていた。 港で昼飯のパンを食ってから真っ直ぐ帰った。帰宅後は魚の処理に2時間を費やした。7日。 朝から曇り空で出かける気にならない。それでも目的も無く今津方面へ出掛けた。長垂れの道路上で、カラスが轢死して内臓や肉が露出した多分アナグマに殺到していた。車もこれを踏みたくないので避けている。ハシブトガラス電線や電柱にも多く止まっていて、食い意地がひときわ強い個体だけが数羽危険を冒して肉や内臓に食らいつく。カラスもいろいろな性格がある。横浜の海岸のダイサギ。獲物がいるのだろう。7月以来見ていなかったクロツラヘラサギが2羽いた。最近渡って来たものだろう。ダイサギとほぼ同じ大きさ。モズ。セイヨウカタバミ。ホシアサガオ。これも外来種。 追加。今ハチクが開花しているという情報を聞いた。120年に一度開花し、その後枯死するという。2年前にも破竹の竹やぶ全体が枯死し、薬液を人間が地下茎に注入したせいと思っていた。竹は一つの竹林が地下茎で繋がっていて、竹を駆除するには地下茎1か所に枯死薬剤を注入すれば林全体が枯れると聞いていた。 今の開花の情報を聞けば、これもそのせいかも知れないが、既に確かめようがない。そこで7日に別のハチクの林に行ってみると、花らしきものが多数付いていて、もう終わったように見えた。 ハチクはマタケによく似ていて、タケノコでは皮の模様が全く異なるので区別は容易で、近年マダケに駆逐されているように見える。
Oct 7, 2023
閲覧総数 2797
-
5

毘沙門山と長垂海岸に行く。
今日は旧暦28日で、午後2時が干潮になり、そこそこ潮が引くから長垂海岸に磯物とテングサを採ろうと思って、道具一式持参して10時半に出掛けた。 時間が早いから毘沙門山に登った。山頂は相当に暑いし、木々の葉が生い茂り、視界がかなり遮られている。眼下の海上では流行りの水上バイクが縦横無尽に走り回っている。小型ヨットレースも開催されていて、ヨットの群れの間を縫うように横断したり、海水浴場の渚近くでも走るのが見えた。何故これ程増えたのか知らないが、事故が起きなければ良いがと思う。IMGP0780_NEW posted by (C)雨釣の釣日記IMGP0785_NEW posted by (C)雨釣の釣日記IMGP0794_NEW posted by (C)雨釣の釣日記 暑い中で写す動物も無く佇んでいると、聞き覚えがあるピックイ、ピックイという鳴き声が頭上から聞こえて来た。サシバの鳴き声に違いないと見上げると、若いサシバが帆翔しながら南から北へ飛んで行った。IMGP0800_NEW posted by (C)雨釣の釣日記腹の羽毛の模様から若鳥と分かるが、今年生まれかどうかは不明。IMGP0811_NEW posted by (C)雨釣の釣日記IMGP0812_NEW posted by (C)雨釣の釣日記IMGP0788_NEW posted by (C)雨釣の釣日記ミサゴは時々現れる。 1時間近く居た後、少し降りて毘沙門堂の日陰でパンを食ってから下山した。IMGP0768_NEW posted by (C)雨釣の釣日記夏の暑さと乾燥に耐え切れず、土中から飛び出して自殺?したミミズがアリの大群に取り付かれている。さすがに大き過ぎて運べないので細切れにされるのだろう。ミミズにとっては今頃が受難の季節。IMGP0815_NEW posted by (C)雨釣の釣日記ヨツスジトラカミキリ。ハチの擬態をしている。トラの威を借りたネコならぬ、ハチの威を借りたカミキリ。IMGP0819_NEW posted by (C)雨釣の釣日記街中では見られないニイニイゼミ。樹皮と見分けがつかない。小型のセミ。IMGP0821_NEW posted by (C)雨釣の釣日記IMGP0826_NEW posted by (C)雨釣の釣日記木陰で休むアオスジアゲハ。IMGP0829_NEW posted by (C)雨釣の釣日記IMGP0838_NEW posted by (C)雨釣の釣日記コノシタウマ。カマドウマの仲間で翅はない。1mぐらいジャンプした。 1時半に長垂海岸に着いた。200mほど歩いて岩場に行って海パンにTシャツ、水中メガネにゴム草履きという出で立ちで海に入った。ここは潮が引くといつも濁っていて海中ではよく見えない。テングサはすっかり少なくなっていた。磯物という巻貝も余り無く、レイシかイボニシか肉食の貝を少し採った。 水中メガネで濁った海中を見たらアンドンクラゲの小さいのがうようよいて嫌になり、おまけに波に揺られ船酔いまで兆して1時間で切り上げた。海水温が異常なほど高くなっていて、クラゲの当たり年になるかもしれない。IMGP0842_NEW posted by (C)雨釣の釣日記浜の一番高い所に咲いていたタカサゴユリ。劣悪な環境に強いのか、唐津の虹の松原でもかなり殖えている。 夕飯のおかずに午前中に友人に頂いたキスと磯物を天ぷらにし、ヒイラギを澄まし汁にした。IMGP0851_NEW posted by (C)雨釣の釣日記貝を塩ゆでにして身を取り出し、かき揚げにした。IMGP0852_NEW posted by (C)雨釣の釣日記磯物のかき揚げ。IMGP0853_NEW posted by (C)雨釣の釣日記キスと冷蔵庫の残り野菜あれこれの天ぷら。エノキダケは意外に美味い。IMGP0849_NEW posted by (C)雨釣の釣日記ヒイラギは精々10cmの小魚ながら身に小味がある。高知市当たりではニロギと呼んで大いに珍重する魚で、浦戸湾内でサビキで良く釣れる。江戸時代には土佐藩の殿様山内侯が小舟で釣りに出たそうな。澄まし汁に丸ごと入れて、汁と身を食べることが多い。IMGP0848_NEW posted by (C)雨釣の釣日記名前の由来は植物のヒイラギの葉のような鋭い棘が似ているから付けられた。口は伸縮するようになっていて、海底の小動物を捕食し易いようになっている。もっと暖海性のサギの仲間も同じ構造。小さくても味は良いので珍重される。魚には不味なものも多く、煮ても焼いても食えないとか、猫またぎとか言われるものがある。
Jul 31, 2016
閲覧総数 892
-
6

初冬の佳日に、もう終わりが近い紅葉を見て回る
今回の冬型は思ったより厳しくなかった。8日の未明は時雨たが日中は晴れ間が広がり、季節風も次第に収まって来た。雑用もあったので遠出はしなかった。 7日はもう見納めになるはずの紅葉を見ようと糸島の火山瑠璃光寺に行き、帰りに先日も行った姪浜の興徳寺へも立ち寄った。どちらも見物客はいないので、心行くまで愛でることが出来た。 6日 唐泊へ釣りに行った。潮が悪くなっているし、海水温も下がりつつあるのであまり振るわなかった。釣った小アジの20cm未満のものは丸干しにしている。7日 今津から糸島へ向かう時に水田地帯を通る。干潟にはクロツラヘラサギはいなかった。あちこちに分散して餌を探しているようだ。ヘラサギはクロツラヘラサギと混生群を形成している。海岸を歩く。この時期は朝の潮はよく引く。野北海岸へ立ち寄った。桜井川の河口付近に波紋が砂に刻まれていた。オニサザエこの海岸にはイソシジミが多い海岸から火山瑠璃光寺へ移動した。もう終わりつつあるカエデの紅葉は何とか見ることが出来た。伐採されて放置された木にキノコが生えていた。食べられるヒラタケのよう。サルノコシカケ見晴らしがよい場所で太陽光を浴びながら、パンを食ってから下山した。キク属の花。シマカンギクに似ているが花がやや大きく花弁も長い。初めて見たスイセンシマカンギク生の松原のイチョウ地面に接することなく横に伸びたクロマツ前日は曇天だったがこの日は時々日が射した。博多土塀枯れる前のオオバギボウシアツバキミガヨラン門の木彫りのハス
Dec 8, 2024
閲覧総数 223
-
7
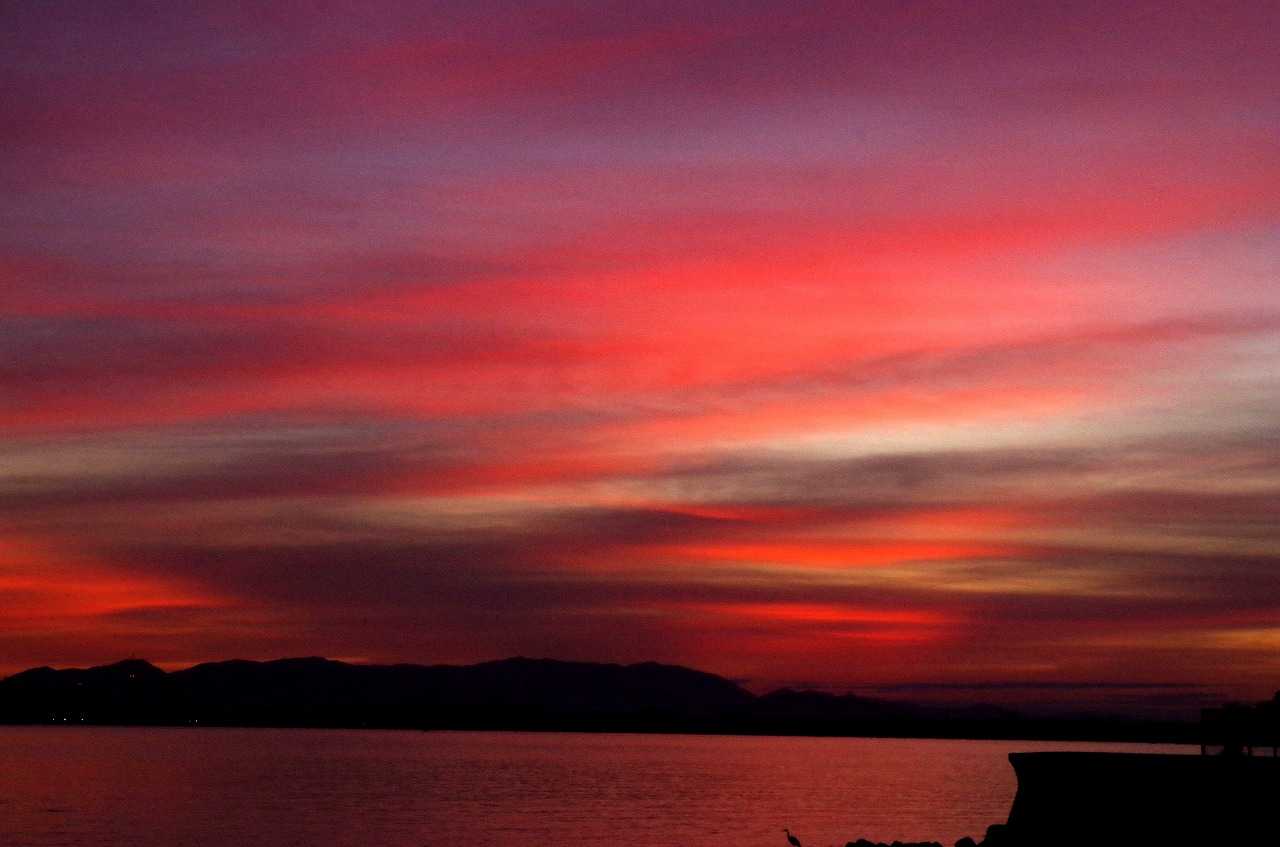
北からの強風下、野北漁港でアジ好漁。
3週間前の暑さがまるで遠いことのように懐かしい。本格的な冬型天気に変わって3日目、北風が強く吹いて釣り場の漁港の外側は時化て濁り、北風が強く釣りにならない。世は3連休なので釣りはしないのが通常ながら、写真も不適な天気の為1,3日と釣りをした。1日は西浦でセイゴ釣りをしてヒラセイゴは遂に当たりすら無くなり、諦めて止める前に港内で試みて、もうすっかり釣れなくなった通常のセイゴがまぐれで釣れた。 3日は風が強く、野北の港内なら釣りは出来るとコッパグレかバンチャゴでも釣れればと行って見た。7時半に着いてみれば、港内の釣り場はファミリー釣り人が一杯で、入り込むことさえ出来ないほどの盛況だった。僅かに空いていた先端部まで歩きながら見れば、20cm余りの中アジがサビキで相当釣れていた。 アジを想定していなかったので、撒き餌のアミや付け餌のオキアミは持参しておらず、前回残った僅かにアミが混じった撒き餌と、付け餌用のアミとパン粉の団子しかなかった。これで釣ってみることにして、延べ竿での餌包みで釣ってみればそれなりに釣れた。途中はほぼ入れ食い状態で、25cm位のサバゴに邪魔をされながら、11時まで釣って40匹余りのアジと30匹のサバゴを釣って止めた。 思わぬアジの好漁はやはり冬の到来によるものだろう。この秋野北漁港が釣り場に加わったことで、釣りの漁場が広がったことが不漁を補う結果になっている。11月1日土曜日久々のナミセイゴ。50cmだった。ウミネコ海岸のキセキレイようやくツワブキが咲き始めた。色付き始めたムベ。ムカゴ。自然薯を掘らなくなって10年以上になる。この時期が来ると食いたくなるが、激減していて掘って見る気にならない。野生のアズキのようなマメ科植物。図鑑で調べるとタンキリマメかトキリマメらしい。2日少し徘徊したノスリキタテハタカ渡があるか山の下で見ていたら、ミサゴだけがやって来た。番のミサゴが繁殖期以外でも一緒にいる仲の良さ。風の強い海はウミネコのものダルマギクタテハモドキはキタテハと近縁多年生アサガオの花に入り込んで蜜を吸うホシホウジャク。通常はホバリングしながらハチドリのように蜜を吸う。3日水路で漁をしていたカワウ小鮒らしき小魚を咥えているダイサギ。ノスリトビとノスリ魚を食っているミサゴ帰りに二見ガ浦でサーフィンをしばらく見る。サップの波乗り冬になるとやって来るカツオドリ。ピンク色のソバの花チョウゲンボウ雌すっかり冬空の今津湾
Nov 3, 2025
閲覧総数 135
-
8

海水温の低下でウスバハギの漂着繁し。
7日はやっと冬型が緩んできたが、5,6日とかなり寒かった。それでも釣りもせず糸島方面に出掛けている。寒ければ寒いなりに、その中に我が身を晒さずにはいられない。 気温は低かったが風は10m未満で波は期待したほどには大きくならなかった。糸島の海岸では貝も拾ったし、羽子板と呼ばれるウスバハギも打ち上げられた様をさんざん目にした。 5日。雪雲が流れ時々弱い雪が舞った。花びらの下に水滴のように溜まっているのはツバキの蜜だった。実に甘露だった。滴り落ちた蜜が葉を光らせている。アコヤガイ。クロアワビ。サザエ。 6日。ノスリ。カルガモが波間に浮かんでいるが、サーフィンはしなかった。 7日。カラスにいちゃもんを付けられているノスリ。別の電柱へ移動したノスリ。ツメタガイに殺された二枚貝。貝殻に穴が開いているのがツメタガイの襲撃跡。大型のテングニシ。謎の欠けら。ユーモラスな形の欠けら。砂に埋没しているウスバハギ。サンゴだろうか。割れたタコノマクラ。タコノマクラの内部構造は複雑な建築構造のようで美しい。川沿いの砂上に哺乳類の足跡があった。死んだばかりのウスバハギ。まだ生きていたホシフグ。まだ腐敗していないが目玉は食われたウスバハギ。韓国漁船の漁網。引き摺って海から引き揚げたが、重すぎて上まで上げられなかった。シロハラ。朝見たノスリがいた。
Feb 7, 2022
閲覧総数 786
-
9

ハタタテダイに再会する。
散々もたついた台風6号は10日に去って、この時期の台風は涼しい風を運ぶことも無く、残暑のきつい夏が戻って来た。もう台風7号が接近中で、今年は台風の当たり年になるかも知れない。 10日の朝9時に台風6号の海の残骸を求めて糸島市の芥屋まで行った。毎度のことながら波はせいぜい2mぐらいしかなく、冬の嵐より小さかった。初めから期待してなかったので、落胆もなかった。突風が海面を走る。明るいブルーの晴れ間が早々に雲間に広がった。名前不明多肉植物。赤色が濃いベンケイガ二。 11日は釣りに行く。大して雨は降らなかったのに、今津湾にホテイアオイがどこからか流れ出して、浮島のようになっている。ホテイアオイは塩分にも抵抗力が有るのか、すぐには枯れない。西浦で釣ると、35cmのチヌ(福岡ではこのサイズはメイタと言う)が釣れた。2匹目は40cm以上のチヌ。ひどい皮膚病に罹っていて、この状態で餌に喰いつくのが信じられない。海に返した。しばらく見ていなかったハタタテダイが岸壁近くにいた。潮が引いて岸壁近くには大型のチヌが集まって来て、見ているとハタタテダイはチヌにまとわり付いて、魚の皮膚の掃除屋として知られるホンソメワケベラのような動きをしていた。チヌはそれを嫌っているふしもあるが、身を委ねる場面もあった。いつの間にやらタカサゴユリが咲いていた。繁殖力が強いが、それなりに奇麗なので嫌われにくい。12日。土曜日でもハタタテダイを見るという口実で西浦へ釣りに行く。ハタタテダイは海面近くにいた。20cm以上のカワハギ。コッパグレを干物用に少し持ち帰った。帰り道でクヌギの大木で樹液に集まる昆虫を見た。オオスズメバチ。アオカナブン。クヌギの樹液は発酵して強烈な臭いを発していた。これを指の付けて舐めてみると甘くアルコール成分も確かにあった。ルリタテハ。アオカナブンとカナブン。サトキマダラヒカゲ。コガタスズメバチも甲虫のアオカナブンには分が悪い。ゴマダラチョウ。
Aug 12, 2023
閲覧総数 399
-
10

小春日和に誘われて21,22日紅葉鑑賞などで過ごす。
長く晴天が続き、冬型が緩んで穏やかな天気になっている。晴れた分早朝は冷え込む。山では紅葉も見頃になって名所は紅葉狩りで混んでいるだろう。中国とのごたごたで中国人客が減っているかも知れない。 人出が多い場所を避けてあまり遠くない所へ行って見た。迂闊にも訪れる時間が悪く、日陰になってしまい日光を透かす紅葉の輝きを見ることが出来なかった。 22日はスコップ持参で自然薯を探してみた。以前に何度か行った場所だったが、木々やニガタケが茂ってすっかり様子は変わっていて、思うような収穫は出来なかった。何とか自然薯を味わうことは出来るだろうが、生涯の食い納めになるかも知れない。21日 福岡市早良区の脊振山麓へ行って見た。個人所有の山荘にあるモミジで毎年行っている。訪れた時間が遅過ぎた。山荘の所有者がおられたので声を掛けたら快く敷地へ入ることが出来た。金武の古墳らしい丘陵に生えていた笹が黄葉していた。陽だまりにタテハモドキがいた。暖地性のこのチョウは朝晩の冷え込みに耐えているのか。ノブドウドバトが田んぼで餌を食っていた。室見川の支流椎原川お茶の花渡り鳥のミヤマガラス22日毘沙門山コサギヘラサギダイサギミユビシギ幼鳥?漁を終えたカワウゴイサギ首が短い。ゴイサギは夜目が利く。ゴイサギ幼鳥自然薯の黄葉姪浜の禅寺リュウゼツランの花が咲いていた。オオバギボウシ葉脈が血管のように紅葉している。ゴクラクチョウカ 太陽光が当たる時に再度挑戦したい興徳寺。漁をしている時のカワウの目は瞳孔が大きく開いている。暗い水中で逃げる魚を追うのには優れた動体視力が必要で、瞳孔を目いっぱい開いてそれを可能にしている。濁った水や暗い水中で魚を捕らえる技は大したもの。各水系でアユなど有用魚を食害している害鳥扱いのカワウながら、本質的には彼らには罪は無い。カラスのゴミを食い散らして散乱させる行為、ヒヨドリの野菜果物食害、イノシシの狼藉,シカの森林食害、今大問題化しているクマ被害など多くが、同じように人と動物との不幸な関係から起きている。漁を終えて休憩しているカワウの目の瞳孔は点のように収縮している。この極端な瞳孔調節はハイタカでも見られ暗い林内では大きく開いた瞳孔になり、明るい空を飛ぶ時にはウルトラマンの目のように瞳孔は点になっている。
Nov 22, 2025
閲覧総数 62
-
11

2025年1月31日は寒波の前の穏やかな一日。
早いもので1月も今日で終わり。寒暖が交互にやって来る冬本番の今頃の、穏やかな一日に駄目とは思いつつ唐泊へ行く。魚は釣れずとも帰りにブラブラ道草をすればいい。 港内でまずアジを釣るべく7時前に着いた。すでにアジ釣りの人が数人いて聞けば釣れないという。餌で釣ってみても全く釣れず、1時間半で一時中断してテトラでフグ釣りをしてみた。まだうねりが残り濁りもあって、一度も当たり無しの完全坊主だった。 止める前にアジ釣りに復帰してみて、意外にも2匹釣れて坊主を回避した。日の出前の空にミサゴが出漁する唐泊から見て能古島の中辺りから朝日が昇る。次第に北へ移動する。 10時頃に帰途に就いたが、天気は下り坂で薄い雲がもう広がっていた。遠回りし今津の東海岸へ行って見た。そこにはなんと、望遠レンズ付きのカメラを持ったバードウォッチチャーが何人もいた。聞けばウミアイサを見に来たという。ヒメウ飛翔海で漁をするヒメウウミウ飛翔ヒメウヒメウ4羽の編隊は珍しい29日冠雪した脊振山系西風が強かったので、糸島市の芥屋方面の幣(にぎ)の浜へ砂の風紋を見に行った。防風柵が壁のように続く。東、野北方面を見る。浜は砂が減って小規模な風紋しか見ることが出来なかった。渚までなだらかに続いていた砂浜は浸食されて小さな崖が長く続いていた。砂に埋もれた鳥の死骸があった。見れば掘り出してみたくなる。ウかと思ったらはるかに大きい。翼部分しかなかった死骸は翼長1.5m以上あった。風切り羽は40cm以上あった。下列の羽は縞模様がある。芥屋大門の東面の玄武岩柱状節理。芥屋と岐志の間の水田や畑にいるカラスは一見ハシボソガラスに見えるが嘴がやや小さく色も真っ黒ではない。ハシボソガラスの亜種のように見える?岐志に新道が出来ていて初めて通ったが、大きいモクレンがあった。この道路沿いで珍鳥ヤツガシラが近くを飛んでいるのを見たが、残念ながら写せなかった。過去に2度しか見ていない。見ただけで写せなかった鳥は幾らもあって、その後も再会できない場合が多い。飛ぶのが苦手なダイサギは強風を遡れない。雷山川下流のマガモ。芥屋から今津へ戻った。中央が浅くなっている海岸では波が分かれて違う方向から寄せてぶつかる。波の進行スピードが浅いと遅く、深いと速いため起こる現象。ウミアイサの番イソヒヨドリ雄30日若いハヤブサ。オナガガモやや高い波が立っていたので北崎で見る。雲が多く日が陰って思うようにいかなかった。中国の春節休みでやって来る大型船。ノスリモズ
Jan 31, 2025
閲覧総数 130
-
12

予想外にサバが釣れた。
何日か釣りをしていないと、随分間が空いたように感じる。23日は土曜日ながら釣りに出掛けた。 雨は早朝には降っていなかったが、東の風が強く吹いていた。西浦へ着くと、土曜日とあって若い釣り人が何人もいたが、風が強いので釣りにならないで、早々に帰る人がいた。 外側でサバを目当てに釣ってみた。良い時間帯の日の出頃は、潮が大きく引いていて釣れそうにない。やはり食いはさっぱりで、1時間以上釣ってもコサバ1匹とコアジ10匹の貧漁だった。潮が満ちて来るまで待つほど気が長くないし、待って釣れ出す見込みもない。釣りを中断して港内の釣れ具合などを観察した所、港内でサバが1匹釣れるのが見えた。 迷うことなく外側テトラから港内へ釣り場所を変えた。向かい風で釣りにくいながらもサバは良く釣れた。2時間ほど釣るとサバは消えて、コアジばかりに変わったので止めた。25~30cmのサバを45匹釣った。小田あたりの畦に咲いていた外来種らしいキク科の花。去年気が付いて、この春は一段と殖えている。2cm位の花で、それなりに綺麗。いつも見るノスリも近々いなくなる。しばらく見なかったコブハクチョウ。もう1年近くになる。コブが大きくなってすっかり成鳥になった。22日は桜井神社近くをブラブラした。ハクモクレンがもう咲きかけていた。10日ぐらい早い気がする。切通の道の脇に植えられた栽培種のツバキ。ジンチョウゲももう咲いている。自生のユキノシタ。食べられる。野生化したツルニチニチソウ。これも早い開花。ノスリ。 24日は山で今季初のハイタカ渡りを見ようと思う。見られそうな気がする。
Feb 23, 2019
閲覧総数 470
-
13

チョウチョウウオ3種を写す。
秋の気配が漂いつつも暑さがぶり返して、昼も夜も暑い。この夏の暑さは一筋縄ではいかない。 21日は久し振りに唐泊へ釣りに行った。もう延べ竿での釣りに見切りをつけて、反転籠での遠投釣りを、この夏の終わりに初めて試みた。そろそろボラも釣れ始める頃でもあるし、釣れても釣れなくても季節の移ろいとともに釣法も変わらざるを得ない。 先にカマスのサビキ釣りを試みた。結果、爪楊枝のようなカマスしかいなかった。まだ時期尚早のようで9月中頃まで待つ必要がある。 7時頃から釣り道具をそのまま唐泊へ置いて、西浦へハタタテダイとチョウチョウウオを見に行った。潮が引いてないと見辛いので、朝が丁度潮時が良かった。 港内の岸壁のヘリを見ると、相変わらずチヌが多くいて、まずハタタテダイが見つかった。しかも2匹。しばらく見ていると、何処からか3匹現れて、合計5匹のハタタテダイが乱舞する豪華版になった。 やがて3匹は何処かに去って、代わりにトゲチョウチョウウオの幼魚が現れた。別の場所ではチョウハンと並チョウチョウウオの幼魚も見つかって、前に写せなかった3種のチョウチョウウオをピンボケながら写すことが出来た。5匹同時に見られたので、ムレハタタテダイかもしれない。トゲチョウチョウウオの5cmの幼魚。チョウハンの3cmの幼魚。チョウチョウウオの5cmの幼魚。カワハギ。アオリイカの幼イカ。 8時に唐泊へ戻り反転籠釣りを4時間やって、バリ2匹、コッパグレ5匹を持ち帰っただけで、小型の多さとボラもいなかったので次回は西浦で釣ってみようと思う。オニヤンマ。18日。今期最初のクエ子。ツチイナゴの幼虫がオオブタクサの葉を食っていた。オオブタクサは北米原産で3mにもなる1年草で、とても草には見えない大きさ。クズとともに獰猛な植物。イナゴが少々食ってもどうにもならないぐらいはびこっている。モンキアゲハ。20日。野ゴイ。クロマダラソテツシジミ。クツワムシ。柑子岳もナラ枯れが見られる。あちこちでマテバシイが枯れている。パンパスグラス。青いアケビ。獰猛なクズも食われる。ヌスビトハギ。今年もタヌキマメが咲き始めた。
Aug 21, 2023
閲覧総数 414
-
14

この秋初めての本格的な冬型の下、3日連続で釣りをする。
一時的とはいえ18日から冬型の天気になって気温が下がった。釣りに出掛ける早朝は寒くなったので、上下とも防寒服を着て初めて靴下も履いた。風は北西から強く吹いていたが、釣りが出来ない程ではなく、波がそれほど大きくないことが、この冬型が一時的であることを示している。 3日とも唐泊で日の出前からアジをまず釣って、つづいてセイゴを釣って昼前に止めるというパターンになっている。アジは20cmあるかなしかの小型で、サビキで容易に釣れるので釣り味は無い。日が出て7時半頃になると釣れなくなる。突然食い初めて突然終わるその1時間ぐらいで40~50匹釣れるので、加工原料調達としては悪くない。3日も続けると加工もパンクするので知人にも配ったりしている。 セイゴは唐泊では西浦ほどは多くはいないので大して楽しめない。17日は遠投のグレ釣りもしてみたがバンチャゴとスズメダイが邪魔をして、釣れない日もあってバラツキがある。17日18日ヒラセイゴの肝臓に寄生虫がいた。この寄生虫は10数年前からスズキの内臓に多数寄生するようになって少なからず悪影響を与えている。ヒラスズキには見られなかったのに今後増える可能性がある。これはアジにも寄生していることも多く、カタクチイワシが中間宿主になっているようだ。19日冬の朝の典型的な雲と光。40cm足らずのヒラセイゴセイゴは3匹釣れて1匹は口に針が掛かっていたので外してリリースした。稀にブリの若魚ヤズが群れでやって来た時は活餌に食い付く。 2時間釣って最後はサゴシが食い付いてハリスが切られた時点で終わりにした。その後二見ガ浦でオシドリが来るか見たがやって来なかった。久し振りに山道を走って帰った。 この秋は柿が豊作で、渋柿がたわわに稔り収穫されず熟れるに任せている。これを見れば何故か取りたくなるが、放置されてはいても出来ないのがもどかしい。持ち主がいればなぜ採らないのか聞いてみたくなる。成り物は採ってやってこそ功徳になるのにと思う。 渋柿の熟柿は大好物で、微かな渋みを残しつつねっとり甘く、甘がきのそれよりはるかに美味い。今や国民の敵にされたクマの気持ちが分かる。柿は美味い果物なのだ。ツワブキの花を追いかけてシマカンギクが咲き始めた。冬の到来を告げる小菊。しくじったミサゴ。釣りと同じく上手下手がはっきりしている。ミサゴの数が増えた。 今週は3日連続の釣りで魚がだぶついたので、来週まで休漁する。天気も回復するので紅葉巡りでもしてみたい。
Nov 19, 2025
閲覧総数 101
-
15

一念発起、いつも遠望していた小呂島へ行く。
思いの外ここ数日は台風の影響も無くて、安定した夏空が戻っている。西浦で20cmぐらいのアジが大漁と聞いても釣りに行く気がしない。何不自由ない日常を過ごしていても、気分の高揚も無く過ぎ行く日々に変化が欲しくて、ふとした思い付きで一念発起西浦の北の海上30kmに浮かぶ小呂島へ行って見たくなった。 小呂島は西浦近くの里山から肉眼でも見えるし、視程が良ければ望遠レンズで見ると高い防波堤も認められる。以前から一度は行って見たいと思いつつも、福岡に来て35年以上になるのに訪れることは無かった。 8月10日の朝9時に姪浜港発の福岡市営能古島渡船に乗った。週末は姪浜~小呂島を2往復していて、午後1時過ぎの便で帰れば日帰りできたが、野宿で1泊することにした。 持参したものは2日分のパンと飲料、クーラーボックスと氷、釣り道具と一番肝心のカメラとレンズなど。釣りをする気はあまり無かったが、時間を持て余すことが目に見えているので餌釣りとルアー釣りの準備は一応した。 姪浜から小呂島までは渡船で約1時間かかる。船窓から見える景色はいつも行っている場所ばかりながら、海上から見ると違った感じがする。博多湾内は海水が薄い醤油色になっているのが、外海に出るにしたがって海本来の青い色になって行く。50トンも無いような渡船。今津の毘沙門山。大小机島と西浦崎。柱島。波しぶきに虹がかかる。小呂島の船着き場。船が着くと島民が注文していた品物を受け取りに来る。島には周回道路は無く、西側はすぐに荒磯になっている。 取りあえず荷物を持って、港の南に城壁のようにそびえる大波止へ歩いた。先端まで歩くと数百メートルもあって遠い。荷物一切を先端近くの波止の低い場所に置いて、島の東の港周辺を散策した。波止の幅は10mぐらい、高さは15mもありそうで、内地では見られない規模だった。海水は澄んでいるが、コンクリートブロックには海藻が全く着いていない。防波堤から船着き場と集落を見る。 荷物を防波堤の先端に置いて、港内の岸壁に珍しい魚がいないかと覗き込みながら集落の方へ歩いた。距離が長いので悪い膝の調子が悪い。漁船のエンジンオイルを流したのか港内の海面はオイルレインボウで広範囲に染まっていた。虹は好きだがこの虹はいただけない。がんぺき岸壁近くの海面近くにソラスズメダイがあちこち出掛けた。泳いでいた。日光の当たり方で美しい空色になる。これを水槽で飼育すると、どす黒くなって海での美しさが見られない。突然現れた15Cmぐらいのキンチャクダイ。この仲間は亜熱帯から熱帯に多く、美しいものが多い。鰓蓋の下側に棘があるのが特徴で、キンチャクダイは広く温帯域に生息しているが、福岡の釣り場近くでは見かけない。港周辺に生えていたこの植物は先日西浦崎で少し生えていたものと同じで、ここでは多く見られた。港の一隅に放置されていたウニの仲間のタコノマクラの骨格。家は島の南中央部から南東部に固まっている。意外にも集合住宅らしき建物もあった。東の海岸も道は無く、荒磯が続いている。小呂島の漁港は渡船の船着き場がある外港と、その東側にほとんどの漁船が係留されている内港があり、小型の巻き網船が1艘とイカ釣り船か、5トン以上の立派な漁船が10隻ぐらい繋がれていた。ここでは漁業が唯一の生業だと分かる。内港の上に民家が斜面にも並んでいる。総数は50戸を超えないように見えた。東側の堤防の外はテトラポットが幾重にも大量に積まれて、しかも大きさや形も多様で、テトラポットの城塞のような感じがした。外洋に面しているので波除けの重要性が別格に高いのだろうが、巨大な防波堤と莫大な規模のテトラポット群と合わせると数百億円もの税金が投入されている。住人一人に数億円が投資されている計算になる。日本各地に同じ構図があるだろうし、次々に消滅しつつある山間の集落と際立っている。昼頃には海女さんが数人づつ乗り合った小型漁船が何隻か帰って来た。ここでは女性による海女漁が今でも盛んに行われているようだ。姪の浜に向けて出港する能古島丸。島には軽自動車が何台かあって、ナンバーは付いていない。自動車免許は必用なのか聞いてみたかった。原付バイクは多いがナンバープレートは無い。 2時頃から釣りを始めた。巨大な防波堤上では気後れがして、港内の先端部で得意の延竿での餌包みで釣ってみた。すぐにスズメダイが多数集まって来た餌を取り釣りにならない。辛抱して2時間釣り、22cmのクロメジナ2匹とメジナ1匹を釣って止めた。他にも雑魚を数種類釣って撮影して逃がした。キタマクラの雄。やや暖海性で西浦近辺では釣れない。スズメダイ。産卵間近で腹部が膨れたササノハベラの雌。イトフエフキの幼魚。対岸に子供たちが現れた。思った以上に若い家族が多くいるらしい。島で大活躍のネコと呼ばれる一輪車。 夕方5時頃から大防波堤の上からジグを投げてみた。余りに水深が深いので中々着底しない。1時間ほどで一度も当たりは無く断念した。 その後は水平線に沈む夕日を期待して待つも、水平線近くに張り付いた雲に邪魔をされて叶わなかった。西には意外なほど近く対馬が見えた。半月を過ぎた月が昇った。 7時過ぎから港内でアジを期待して、延竿での餌包みで浮き下3mにして釣り始めた。初めはアジゴばかりだったのが、突然強い引きで釣れたのがなんと35cmの大アジで、その後25cm~30cmのアジが次々に釣れた。思わぬ大漁になると思う間もなく、ネンブツダイとクロホシイシモチばかりに入れ替わってしまった。 10cmの小魚は唐揚げにすると相当美味なことは知っていたので辛抱して20匹釣って止めた。上がクロホシイシモチ、下がネンブツダイ。これらの雄は口内で卵を孵化させるマウスブリーダーとして知られている。 9時頃にはすることも無く、波止のコンクリートの上にブルーシートを敷いて服を着たまま寝転がった。正真正銘の野宿で、顔の上は星空天井ながら薄雲が広がって暗い星は見えず、満天の夏空とはいかなかった。唯一流れ星が真上を横切るのを幸いにも見ることが出来た。 いざ眠ろうとすると、風がやや強く吹いてシートをバタバタあおるし、体温を奪って予想以上に寒くて殆ど眠れずに長い長い夜を実感することになってしまった。 ろくろく眠れぬうちに、東の空が明るくなり始め、早朝のアジ釣りを始めた。夕方釣れれば朝も釣れるのがアジの性質だから、予想通り釣ら始めた。10匹ほど釣った時に、いきなり竿が大きく曲がって大物が食い付いた。それの動くほうに移動して何とかしのいで海面まで引き上げると、40cm以上の青物だった。電燈が無いので正確には分からなかったが、ヒラマサの若魚ヒラゴかカンパチの若魚ネリゴらしく、荷物になるので掬い網も持参していなかったので糸を握って引き揚げに掛かると、海面から魚体が上がった時にプツリと1.5号のハリスが切れた。 急いで仕掛けを直して釣り始めるとすぐにまた食った。今度は持ちこたえることも出来ずにあっという間に道糸が切れてしまった。 空は次第に茜色に染まって写真は写したいし、堤防の上に登って朝焼けの空を写し、下って釣りをすると忙しくしているうちに、ルアーで釣れば良かったことに気が付いた。 遅いながらもジグを振ってみると数回目で当たりがあって、思わずやったと叫んだ刹那にばれてしまった。それで青物は終わってしまい、日の出を写すことに専念した。夕方と早朝の2回の釣りで35匹のアジを得た。 10日の朝の便では釣り人は自分も含めて3人だったのが、11日の朝には10日の午後の最終便で来たのか10人に増えていた。もう巻き餌も底をついたので朝6時45分の始発船便で姪浜に帰ることにした。 逃がした魚は大きかったが、夜の長さに耐える自信は無く、もう訪れることはないだろうと思いつつ、移り行く朝の海面を見ていた。 小呂島は遠く南に本土は見えるから絶海の孤島とは言えないだろうが、どこにも逃げ場のない小さな島でよく生活が出来るものだとつくづく思った。五島や対馬は島数は多いし何より広い。津々浦々には町もある。しかし小呂島は生活の場は余りにも狭いし、本土とは30km以上離れて心もとない小さい渡船が通っているだけだ。 漁師だから海の上は広いし、本土へも漁船で行けはするだろうが、漁獲の出荷も手間暇が掛かるし何かと不利なことは間違いはなく、少ない島民同士の濃密な関係で支え合っているのだろう。 根無し草の私には到底出来そうもない島の暮らし。遠い故郷を思い出すこともあまり無いが、今のように台風が近づくと、かつて時を忘れて見ていた大波を思い出す。帰りの海上で見たミズナギドリ。低く海面すれすれを巧みに飛ぶ。同じく孤島の玄界島は過去の地震を境に建物は全て新築された。小呂島より大きいし本土にはるかに近い。姪浜港へ入る前にすれちがった能古渡船。これはフェリー。過去に西浦近くの山から見た小呂島。以前に島の西に上がった煙が火事に見えたが、今回の訪島でこの場所は大きな穴を掘っていて、ゴミなどの野焼き場所だったことが分かった。ゴミ収集車が海を越えて来ることは有りえない。しかし西浦や唐泊にも設置されている小規模汚水処理場は建設されていた。水は天からのもらい水とイオン交換による海水淡水化で賄われている。電気はどうしているのだろうか。風力発電施設は無い。
Aug 13, 2019
閲覧総数 13018
-
16

今だ冬型天気終わらず、徘徊叶わぬ日々貝殻と戯れる。
1級寒波は去っても冬型の天気が続いて晴れもせず、季節風が吹いて寒い日々が続いている。釣りはすっかりに諦めていても、せめてもの徘徊も曇天ではする気にもならず、ほとんど毎日籠っている。 28日は気分転換に糸島半島の西端まで貝殻拾いに出掛け、29日は今津へ一寸行ってそれなりの収穫があった。福岡市西区から糸島市の貝殻拾いを始めてもう1年になる。30数年暮らしてこれまで見向きもしなかったのが、去年の2月に突然始め、釣りのついでも含めて何十回出掛けたのか分からないぐらいになった。 海辺での採集は宝探しのようで楽しいし、今のように出られない時に整理するのもそれなりに悪くないので良かったと思える。どうやら何にでも入り込んで依存してしまうオタクの性分が原因らしい。しかも金が掛からないので貧民の私に向いている。 ビョウブガイ加布里湾のカブトガニ死骸。ナツモモ。芥屋の浜にて。ベニハマグリ。トリガイトリガイ内側。ビョウブガイ。ヒオウギ。割れている。エマイボタン。キヌタアゲマキ。マルヒナガイ。ツメタガイに穴を開けられている。ハイガイ。アコヤガイ。別名真珠貝。天然真珠が作られることは殆ど無い。美しい虹色は写真にはうまく写らない。ウチムラサキ。シドロガイ。ヒラタブンブク。右が本来の姿で左は棘やらなくなった状態。ウニやヒトデの仲間。荒れると多く打ち上げられる。イトマキヒタチオビと思われ福岡ではごく稀。
Jan 29, 2023
閲覧総数 424
-
17

天気は梅雨前に戻ってしっまった。
2週間前から各地に大きな爪跡を残した梅雨前線は、ここにきて南下して気圧配置は梅雨前に戻ってしまった。北から冷たい高気圧が張り出して、梅雨前線を南に押しやって、福岡は雨からしばし雨から開放された。 太平洋高気圧が強まらない限り、梅雨が長引きそうな展開になりそうで見通しが立たなくなった。 見通しが立たないと言えば、新型コロナウイルスの感染もここに来て急増しつつある。症状が不顕性の若年層感染拡大が、さらなる感染者の増加を誘発してこれも見通しが立たなくなって来た。 あれやこれやの人間界の受難をよそに、空は色んな表情を見せている。14日夕方のヨットハーバー。15日釣りの帰り。西浦付近の県道脇には毎年早くヒガンバナが咲くが、今年は一段と早い。ハマユウの花の先に横たわる能古島と志賀島。ハマユウはヒガンバナ科。小さい流れで砂と砂鉄が分離している。高さ1mにも満たない砂鉄混じりの砂の崖が、雨で複雑に削られている。
Jul 16, 2020
閲覧総数 203
-
18

まずまずの天気で連休も終わりへ
連休後半はまずまずの天気で各地の観光地は大いに賑わって終わりつつある。晴れる特異日の5月5日は朝から曇っていたが何とか雨はわずかしか降らなかった。 世間は内外の観光客で大いに潤ったことだろう。人出の多い所は苦手なのでいつもは避けているのだが、3日は電車とバスで久留米の百年公園へ行った。行きは9時頃の下りで混んでいなかったが、帰りは昼過ぎになり博多どんたくの人出が多く電車は混んで座れなかった。40年近く福岡に住んでどんたくも山笠も見に行ったことは無い。 4日は糸島半島を1週しながら海岸と溜池を巡った。5日はどうにか雨は降らなかったので、今津近辺にクサイチゴを採取しに行った。3日 久留米の百年公園へ出掛けた。電車とバスで自宅から1時間ほどで行ける。ツツジはすっかり終わり、広い公園を歩いて筑後川まで行って見た。気持ちがいいくらい広く、ごたごたしていない公園は久留米特有のように見える。久留米は暑い所なので、木立の日陰と芝生が好ましいことを十分承知している。 木陰で持参の弁当を食ったのが良かった。アカバナエゴノキ。ヨーロッパ原産のブタナ筑後川に架かる3号線の橋河川敷で咲いていたクサフジ。福岡では見たことが無い。筑後川、上流側を見る。流れが無い淀んだ大河。下流は有明海に注ぐ。キツネアザミムラサキツメクサ。ヒナギキョウ。4日毘沙門山東海岸。例年ならヒヨドリの群れが見られるが、今年はもう終わった模様。カイメンを朝日にかざすノイバラ。右が咲き始め、左は時間が経過していて花粉が黒くなっている。セリ科植物朝露が降りているコバンソウ、ヨーロッパ原産。休日は浜辺で遊ぶ人が多いので貝殻拾いは不可。踏まれて割れたベニガイ。キリの花可也山頂上の電波塔孟宗竹が竹が無い法面に勢力を伸ばしている。クロイトトンボの産卵合体カップルに割り込む別の雄。後から奪った雄。コサナエ25cmほどのブラックバスノゴイベニカミキリ大麦北西から見た可也山確かにアカショウビンの鳴き声を2度聞いた。30年前に1度見たきりのアカショウビン。陸にもカエルは多い。ギンヤンマの産卵横恋慕で別の雄が襲い掛かるトラフトンボ。止まらずに飛び続ける。溜池の水面を泳ぐシマヘビ。北から見た可也山またシマヘビが泳ぐ東から見た加也山アマサギが南からやって来ていた。5日2時間掛かって700gのクサイチゴを採取した。クサイチゴは遷移植物で前年にあった場所でも次の年には消えていることも多く多くを採取することは困難。栽培イチゴと混ぜてジャムにする。
May 5, 2024
閲覧総数 163
-
19

小春日和に誘われて21,22日紅葉鑑賞などで過ごす。
長く晴天が続き、冬型が緩んで穏やかな天気になっている。晴れた分早朝は冷え込む。山では紅葉も見頃になって名所は紅葉狩りで混んでいるだろう。中国とのごたごたで中国人客が減っているかも知れない。 人出が多い場所を避けてあまり遠くない所へ行って見た。迂闊にも訪れる時間が悪く、日陰になってしまい日光を透かす紅葉の輝きを見ることが出来なかった。 22日はスコップ持参で自然薯を探してみた。以前に何度か行った場所だったが、木々やニガタケが茂ってすっかり様子は変わっていて、思うような収穫は出来なかった。何とか自然薯を味わうことは出来るだろうが、生涯の食い納めになるかも知れない。21日 福岡市早良区の脊振山麓へ行って見た。個人所有の山荘にあるモミジで毎年行っている。訪れた時間が遅過ぎた。山荘の所有者がおられたので声を掛けたら快く敷地へ入ることが出来た。金武の古墳らしい丘陵に生えていた笹が黄葉していた。陽だまりにタテハモドキがいた。暖地性のこのチョウは朝晩の冷え込みに耐えているのか。ノブドウドバトが田んぼで餌を食っていた。室見川の支流椎原川お茶の花渡り鳥のミヤマガラス22日毘沙門山コサギヘラサギダイサギミユビシギ幼鳥?漁を終えたカワウゴイサギ首が短い。ゴイサギは夜目が利く。ゴイサギ幼鳥自然薯の黄葉姪浜の禅寺リュウゼツランの花が咲いていた。オオバギボウシ葉脈が血管のように紅葉している。ゴクラクチョウカ 太陽光が当たる時に再度挑戦したい興徳寺。
Nov 22, 2025
閲覧総数 38