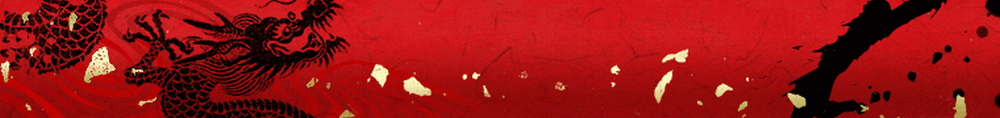2007年01月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
血の轍、八重山民謡。
「うた」とは「うったえる」ことだと思っている。なにを訴えるのか。それはそのつど違うと思うが。蝶に菜の花にとまってほしいと訴える。日でりの中で雨が降ってほしいと訴える。愛しい人にふりかえってほしいと訴える。圧政に対して自由の権利を訴える。いろんな訴えるがあると思うが、訴えるうたでなければうたではない、と思っている。そして、みんなで訴えることによって、うたは最高のエネルギーを得る。だから、うたは必然的に民のうたになる。ボブ・ディラン。「時代は変わる」で「Come gather 'round people…」と歌った。この出だしの文句が最高に好きだ。ワンフレーズでフォークソングの真髄をついている。そして、八重山民謡、「鳩間節」。鳩間中岡、走リ登リ クバヌ下ニ、パリ登リ(訳)鳩間島の中岡に走り登って クバ林の下に走り登って。収穫を終わって荷をいっぱいに積んで西表島からやってくる船を見るために、島民はみんなで狂ったように鳩間島の高台である中岡に上る。一般的には雄大な西表島の風景、そして収穫の喜びを歌った唄であると説明される。しかし、この解釈からは曲の印象はかけ離れている(と思う)。その裏には、強制移住、苦しい開拓、そして理不尽な人頭税を強要される民衆の怒りと、収穫の神への血の訴えがあるのではないか。八重山民謡にはこんな歴史を照射する「うたの力」に満ちている。「ボブ・ディランがフォークソングだ」という意味で、この民謡は最高にフォークソングだ。
2007年01月31日
コメント(0)
-
結婚指輪が抜けない。
結婚以来、何年も指輪をとったことがない。別に変わらぬ愛の証とか、カミさんが怖いわけではない。(まあ、これはそうだが。)物理的に抜けないのだ。見た目、鬱血状態で、人からは「大丈夫?指先まで血が行ってないんじゃない?」と心配されるほどだ。結婚してふとったわけではない。手足だけがぽちゃっとしているのだ。自分でもかわいい手だな、と思っていたが、最近どうもこれは何か病気と関係あるのではないか?と思うようになった。ぱっと、浮かんだのが「腎臓」。腎臓が悪いとむくむそうだ。そこで、やちまた道、最近こっている足つぼくるくるマシーン(かってに名付けました)で湧泉(ユウセン)というツボを集中的に押してみた。これが、めちゃくちゃに痛い。普通に押していてはわからなかったが、この100円ショップで買った足つぼくるくるマシーンだとかなり効く。そのまま気持ちよく寝たら、夜なんと5回おしっこで目が覚めた。(決してねつ造してません。)これは、きっと腎臓が働いて体内の余分な水が出たにちがいない。そして、翌朝、指輪を抜いてみると、なんと気持ちよく抜けるではないか。(決してねつ造してません。)「すごいな~ツボって」。やちまた道はいたって単純にできている。喜びのあまりカミさんに「やったぞ。指輪が抜けたぞ」と自慢する。カミさんの答えは「まだしてたの?」という冷めた一言だった。
2007年01月30日
コメント(0)
-
いろんな思想
街は朝の薄明、あるいは、夕まぐれが美しい。写真を撮るとわかるが、昼の光線は絵にならない。夜のネオンは煌びやかだが、街の奥深さを写すことは難しい。西洋では昼と夜が思想の枠組みとしてはっきりと出てくる。ニーチェは「昼の光に、夜の闇の深さがわかるものか」と言い、ゲーテは「人間は昼と同じく、夜を必要としないだろうか」と、昼に対する従来の価値観に対し人間の夜の深さを提出したが、どうも日本人の感性には「それだけじゃない」という気になる。日本の哲学者三木清は、西洋人の場合、昼の世界と夜の世界であるのに対し、東洋人の世界は、薄明の世界であると言った。西洋の昼夜の対立思想には善悪などの二元論が下敷きにあるように思う。それに対し、日本はなんか中途半端なところに「奥深さ」を求める。「善悪」に対し「弱い」思想ではあるが、「強い」だけの思想には人間至上主義の「危険」があるのではないか。昼は人間を働かせ、夜は人間を眠らせる。しかし、朝、そして夕刻は、街にいるのは人間だけでないことを知らしめてくれる。日本の古い言葉では、夕刻を「逢魔が時」というらしい。
2007年01月29日
コメント(0)
-
本日は日曜日なり。
ということで、やちまた道の好きなホイットマンの詩の一節をお贈りする。Forever forward, forever alive.ずっと前へ、ずっと生き生きと。
2007年01月28日
コメント(0)
-
立ち退き。
やちまた道が住んでいる街は、いま駅裏再開発が進んでいる。ここは古くからの職人の街。玩具、鍛冶屋、薬屋など風情のある店が並び、モノクロの写真撮影でよく使わせてもらった。1軒1軒と立ち退きにあい、その分じわじわと舗装された大きな道路が延びていく。その中には、立ち退きを拒否しているのか、歯抜け状態の古い民家や商店が、息をひそめるように無言で荒れ地に残っている。その中の中華そば屋に入った。何年か前に入って記憶の中にあったのだが、正直もうなくなっているのでは、と思っていた。初老のご主人と奥さんの二人で切り盛りしている。他の客も小声で「なつかしいな~」と言っている。立ち退きを前にこの味をしっかりと記憶に残しておきたいとやってきたのかも知れない。前に来たとき、親しげな常連客から、「この店立ち退かないの」と言われていたの想い出す。「いや~、今から新しいところで商売する元気はないわ~」と苦笑混じりで答えていた。立ち退きをするとそれなりの補助が出るだろう。でも、大切にしてきた「のれん」をもう一度掲げるのは、我々には計り知れないエネルギーがいるのだと思う。こんな人々がまだまだたくさん残っているのに、再開発は進むのか。引くに引けない意地みたいなもので、道路は迷走しながら伸びていく。もしかしたら、市のお偉方は、もうすぐ来ると言われている大地震で、この街が一掃されるのを待っているのかも。そんなことを、訝しんだりする。
2007年01月27日
コメント(0)
-
おれのポンコツ車
偏頭痛の症状をご存じだろうか。偏頭痛でない方は、まあ頭の片方が痛いんでしょ、と思うかも知れない。しかし、偏頭痛の症状はそんなカンタンなものではない。やちまた道の偏頭痛の到来は突如視覚からくる。本などを読んでいて、ある部分が見えにくくなる。「なんか見えにくいな~」と思っていると、光のような1点が現れる。その光は序々に大きくなる。感じは液晶画面をさわったときのようなチラチラした光。これが、最終的には目の前いっぱいに広がる(書いているだけで気分が悪くなってきた)。2~30分続くが、どうしようもない。何も見えない。光は去っていくが、その後こめかみから頭の後ろにかけて激痛が走り、ひどい時は嘔吐に悩ませるようになる。この症状が月に1度ぐらいあり、人知れず、「俺の頭はおかしくなったんじゃないだろうか」と思った。誰にも相談できず悩んだものだ。ルイス・キャロルは偏頭痛の妄想のなかで『不思議の国のアリス』を書いたというが、確かに自分だけが違う世界にいるような感じだった。しかし、ある時ホームページで偏頭痛の人がまったく同じ症状だと知り、驚いた。「なんだ、別に普通のことなんだ」と安堵する反面、今まで他人とは違う「自分だけの体」が、なんか既製品のような、なんか借り物のように思えてきた。例えるならカタログスペック通りに作られた、どこにでもゴロゴロしている大衆車。「ここを動かすと、こうなる。う~ん、確かに。」みたいな。その後、今まで他人ごとと思っていた病気や症状に出逢う度、自分の体だけが特別ではないという事実を思い知らされた。そして、この大衆車のカタログの最後には、「100年あまりで、寿命がきます。ご了承ください」と書いてある。文句を言いたいが、お客様サービスセンターの問い合わせ先は書かれていない。
2007年01月26日
コメント(0)
-
麺は国境を越える。
いや、正確に言うと麺への食欲は国境を越える。やちまた道の生まれは、いわゆる麺どころ。麺には目がない。麺だったら、日本全国はおろか、どんな国のものでも食べてみたい。いわゆる麺が生まれたのは、いつごろなのだろう。青海省の喇家(ラーチア)遺跡から約4000年前のものとみられる土器と麺の遺物が見つかったという。直径約3ミリで、長さは50センチ以上だったらしい。西アジアから中国に伝わった1粒の小麦が麺に形を変えて、シルクロードによって西域にもたらされたという…。麺も長い旅をしてきたんだ。でもなぜ麺になったんだろう。そもまま食べる白米はわかる。すりつぶして「だんご」みたいにするのもわかる。細く、長い形になったのはなぜか。まあ、だんごよりは煮えやすかったんだろう。しかし、そういう機能性だけではなく、なんか「のどごし」みたいなものが良かったんだろうな。ささやかな穀物をさらにおいしく食べる、飽くなき食欲が麺を創ったのかも知れない。麺にスープに具。このシンプルな形態から広がる無限の可能性。ベトナムのフォー。タイの「バーミー」「クイッテオ」…。ほとんどは小麦・米・そばで作ったものだが、それ以外もある。緑豆から作られた春雨。ジャガイモやサツマイモが使われる冷麺。コンニャクやドングリを使った麺もある。こんなにいっぱいある世界の麺。シャッフルしたらおもしろいかも。ビビン麺でスパゲティ。きしめんで冷麺。日本蕎麦でフォー。ペンネで担々麺。おいしいかどうかはわからないが、楽しそうではある。さあ、万国の人々、麺のもとに国旗を降ろそう。
2007年01月25日
コメント(0)
-
600円でも一生もん、フェリーニ「道」。
学生の頃、映画館浸りだった。いわゆる名画座というところ。今でも憶えているが、600円で3本だての古い白黒映画が見られた。安いだけになんと椅子がなく、背もたれだけのところにみんなが立って観ていた。親父が昔映写技師だったからか(それは最近知ったことだが)妙に映画館の暗闇が落ち着いて「自分だけの隠れ家」にいるような気になった。その名画座でみたフェデリコ・フェリーニの「道」。今でも好きな映画を1つあげろと言われたらこの映画をあげるだろう。フェリーニ夫人ジュリエッタ・マシーナ演じる知恵遅れのジェルソミーナ。貧乏家族のために大道芸人ザンパノに売られ、彼からひどい仕打ちを受けながらも「この世に役に立たないものなんてひとつもない。この石ころだって何かの役に立っている。君だって、きっと誰かの役に立っている」という綱渡り芸人のことばに目覚め、彼のために、彼といっしょに旅しながら大道芸で金を稼ぐ。しかし、ザンパノは「人間の業」を捨てられず、修道院で盗みを働いたり、挙げ句の果て喧嘩で綱渡り芸人を殺すことに。気が狂うジェルソミーナ。どうしようもない大道芸人は冬山の寒さの中に彼女を残していく。…何年か後、興業にきたある街で「ジャルソミーナ」の懐かしいメロディを聞く。ジェルソミーナはこの街で暮らしていた。一人寂しく死んでいったと言う。ラストシーン。どこまでも暗く、波の音だけの砂浜。「すでに時遅し」という癒すことのできない寂寥に、慟哭する大道芸人。そして、流れるエンドロールに、観客はまた同じ深淵を観ることになる。ストーリーはいたって簡単だ。昔の名画はだいたいそんなもんだ。一番心に残るのはジュリエッタ・マシーナの白痴の演技。イノセンス(無垢)。映画だけが創ることのできる美だ。このイノセンスが好きで、これを映画の善し悪しのバロメーターにしている。イノセンスを感じないものは映画じゃない。(いいすぎか?)奇をてらったストーリーが心に響かない魑魅魍魎映画。そんなのテレビでやれよ、というおちゃらけタレント映画。暴力シーンが芸術だとばかりの日本が世界に誇るB級映画。映画がフェリーニが言うところの「純真さへのノスタルジー」を失ったのはいつからだろう。
2007年01月24日
コメント(2)
-
街ねこ、ちゃー。
近所の公園に街ねこがいる。野良猫というのは語感が好きでないので、街ねこと言おう。茶色い毛なので「ちゃー」と名付けている。別にかわいいわけではない。むしろいつも泥まみれで、栄養が良くないからか毛並みも良くない、ちょっぴり臭ったりもする。気にいっているのは、妙にか細いいたいけな「にゃー」というなき声とそして、がんばって生きているな、って感じのおでこの力じわだ。こちらが気にいっていても、別になついてくるわけではない。「ご主人様」という感じで人間を見ない。逃げるわけでもなく、じゃれるわけでもない。その天性の「無関心」にやちまた道は惚れ惚れしてしまうのだ。そんな「ちゃー」は結構人気がある。まずはおばさんが餌を与えにくる。「チャコ、ご飯よ」という声にうれしそうでもなく食べている。そうか「おまえはチャコと呼ばれているのか」。と、次に現れた猫おじさんは、「ほら、あいこ、食べれ!」。「あいこ!?あいこはないだろう」と思うが当然のように普通に食べている。こんな風に愛されている「ちゃー」だが、出逢って4年ぐらいなので、あと何年元気な姿を見せてくれるのか。何者にもこびることなく、何者にも知られることなく消えていく。やちまた道の本筋を会得している「ちゃー」をうらやましくも思う。
2007年01月23日
コメント(0)
-
高速バスの旅
やちまたの旅には高速バスがいい。先日、仙台から大阪へ夜行バスに乗った。7:30出発。明朝8:00大阪着の予定。ゆったり寝ていくにはお酒の力を借りよう。ビール・ワイン・焼酎。こんなに飲んでトイレは大丈夫かと思われがちだが、長距離の夜行バスにはトイレがついているので安心だ。仙台~大阪だと東京を通りそうだが、渋滞を回避するために北陸を通るようだ。(途中寝ていたのでよくわからない…)朝7:00くらい。目がさめると…、うん?まだ高速を走っている、というよりは高速の渋滞で完全に止まっている。突然の雪で米原あたりで立ち往生のようだ。まいった。この分でいつ大阪につくのか。ちんどん通信社のライブも2時からだ。あせってもしょうがない。というか自分以外だれも焦っていない。高速バスを選んでいる時点で、誰も時間に追われる旅を考えていないようだ。…結局大阪についたのは12:30。正味17時間乗っていたことになる。まあ、計らずして17時間くらいはふつうにバスに乗れることがわかったのが幸いだ。
2007年01月22日
コメント(0)
-
こんなカメラを持って旅に出たい。
中古カメラがずっと好きだ。選ぶ基準は、このカメラ1台あれば、ジャングルの奥地にも、北極にもいけるぞ!と思えるようなカメラだ。となると、電子化が進んだカメラは候補に上がらない。ライカもコンタックスというブランドカメラもやちまた道にはふさわしくない。デジカメも安心感という意味では心もとない。やっぱり中古銀塩国産マニュアルカメラということになる。すっぽり手に収まる感じ。ファインダーの見え。シャッター音。巻き上げのスムーズな感じ。そしてやちまたらしく古びた街に似合うカメラでなくてはならない。今あるカメラでは、キャノンのf-1(旧)というところ。一番気に入っていて好きな八重山の離島にもよく連れていった。でもすべてに納得しているわけではない。このカメラは巻き上げに難がある。それ以外はクリアしているのだが。オリンパスOM-1もいい。すっぽり手に入る感じが好きだ。でも、全体的に安心感がなのと、やちまた感もちょっとかな。結局今あるカメラで納得しているわけではない。うーん。次はペンタックスのMXかな。物欲に満ちたやちまたカメラ道には、なかなかゴールがないようだ。
2007年01月21日
コメント(0)
-
歩く音たち
途上の音楽。大道の音たち。これほど心に響くものはないのでは。道の音楽として、すぐ心に浮かぶのがコンポステラ。大好きなレーベル「オフノート」からの「歩く人」は、このやちまた道のイントロとしては最高かも知れない。故篠田昌已が盟友、中尾勘二、関島岳郎と共に残した名演集。「個別の死を乗り越えて生々と音楽が歩きだす様を捉えたドキュメント。その後のオフノートの活動を方向づけた重要なアルバム」だと言う。そう言えば同じオフノートから「北村大沢楽隊」もやちまた音楽にあげたいもの。東北のおじいちゃんたちが、農作業とともに刻んできた生活の音。人生の道の応援歌として聞いてほしい貴重な音源だ。
2007年01月20日
コメント(0)
-
本日よりやちまた道
本日よりやちまた道はじまります。よろしくお願いいたします。
2007年01月19日
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-20 17:35:54)
-
-
-

- 楽天市場
- 開けるまでドキドキ。蔵王くじで当た…
- (2025-11-21 00:00:15)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- “首アイロン”で首元にも自分時間◎
- (2025-11-20 19:10:08)
-