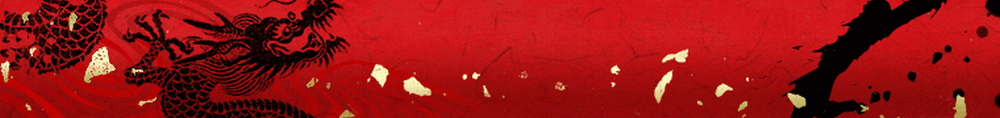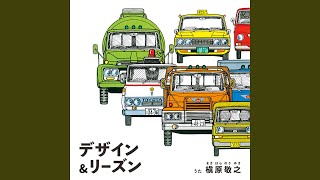2007年08月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
雨乞い。
わが三線の会に、雨男か雨女がいるんじゃないか、という話しを書いた。今週も屋外のイベントがあるのに、うーん、またしても雨模様。ここ何年もイベントを続けているが、ほとんどと言っていいぐらい天気が悪い。ここまで来ると、きっと何かある。絶対何かある。よく考えると、演奏メンバーが違うのに毎度雨というのは、もしかしたら、演奏する八重山民謡の方に関係があるのでは。うーん、きっとそうだ。沖縄の民謡のカテゴリーは以下のとおり。神を崇べるもの、五穀豊穣、狩猟、雨乞い、造船、航海安全、牛馬の繁昌、新築祝い、婚礼祝い、誕生祝い、家内繁昌、葬送、羇旅、島ぼめ・村ぼめ、恋、時勢の風刺、教訓、風物、反戦、観光音頭…等々。そうか、雨乞いか。沖縄は実に水不足との格闘の歴史でもあった。雨水は天水として大切にされた。沖縄の中でも、雨乞いと言ってすぐ浮かぶのが、宮古の「クイチャー」。クイチャーとは声(クイ)と合わせる(チャース)とをくっつけた言葉。かけ声をかけながら、みんなで輪になって踊る。雨乞いを中心に豊年祈願や労働の喜び、良いことがあった時などに踊られてきた宮古島の伝統的な民俗芸能だ。このクイチャーは巻踊りとして竹富などの八重山にもある。そして、八重山民謡の雨乞いの唄。「夜雨節」。雨が唯一の水源だった波照間島のもので、農作物には夜降る雨が豊作をもたらすとして唄われた。この波照間島では「雨願い(アミニゲー)」という行事が行われる。フサマラーという雨の神様が出現し、村の井戸を巡って潤沢な水量を保証し、また異境に帰ってゆく。八重山には、雨乞いなど農耕儀礼を行った雨乞御嶽もいっぱいある。もしかしたら八重山民謡を唄い継いできた人々のまぶい(魂)がわが三線の会にも応援に来てくれているのではないか。これは実にうれしいことだ。雨が降るということは、わが三線の会が少しは認められてきているということかも……などと、淋しく慰めている次第です。明日、晴れないかな~。
2007年08月31日
コメント(0)
-
原型が心地よい。
やちまた道、最近<原型>が心地よいということに気づいた。例えば、夜寝る時。仰向けに寝るとどうしても、腰がいたくなって、朝方暗いうちに目が覚めてしまう。寝ているのが苦痛だ、というのは本当になさけない。いろいろ、寝る姿勢を試してみる。すると、使っていない普通の枕を抱き枕のように抱いて寝ると腰が痛くないことに気づいた。そう、いわゆる胎児姿勢というやつで、母親のお腹の中にいたときと同じようにかっこうをすると、重力がうまく分散されるからか、心地よい眠りにつける。朝起きても腰が痛くなくて爽快だ。胎児姿勢はどんなときでも気持ちいいらしく、胎盤の形を再現した椅子もあるとか。どの位置からもすっぽり自由に座れて、様々な方向に回ることもできる。母親の胎内と同じように包まれる感じが気持ちいいらしい。こういう、母胎回帰は心理療法でも使われている。ホロトロピックブレスワークというらしく、横になってヒーリング音楽などを聞き、胎内にいたときと同じように深い呼吸を繰り返す。体内酸素を高め、炭酸を増やし、LSD飲用と同じ効用を脳にもたらす。脳に誕生以前の原型的体験をさせることにより、再誕生を体験させ、心の奥底にあるトラウマを治癒するとか。この原型回帰は、社会全体にも必要かも知れない。社会が進化して、いろいろなところに手足をのばし、無理に背伸びしていることにより、 社会という身体にひずみが生まれてきているように思う。もっと、人類史における母型概念=〈原型〉を問い直さなければいけないのでは。吉本あたりが言っている<アフリカ的段階>というのも、こういうことじゃないか、などと思う。人間は生きるというあり方の〈原型〉を考えざるをえない時期に来ている。
2007年08月30日
コメント(2)
-
食(くら)うべき唄。
ナマコは、深い海底の砂を食べて生きているらしい。もちろん、砂そのものを栄養にしているのではなく、砂の中にいるバクテリアを食べているわけだが…。なにかしら、はかなく、なにかしら、美しい、太古のざわめきのような生命の神秘的な営みを感じる。「いのちなき 砂のかなしさよ さらさらと握れば 指のあひだより落つ」こう唄ったのは岩手は渋民村が生んだ天才歌人・石川啄木。一握の砂という歌集を書いた啄木にとって、砂粒は、はかなくも美しい一瞬の命の象徴だった。石川啄木は、「食うべき詩」を自らの詩の理想とした。「…両足を地面(じべた)に喰っ付けて歌う詩という事である。実人生となんらの間隔なき心持をもって歌う詩という事である。珍味ないしはご馳走ではなく、我々の日常の食事の香の物の如く、然(しか)く我々に『必要』な詩という事である。…」両足を地面(じべた)に喰っ付けて歌う詩。我々に「必要」な詩。さすがに土の匂いのする岩手の詩人、いいことを言うと思う。やちまた道も、最近八重山民謡を「必要な唄」として標榜していたので、同じ言葉を天才歌人の中に見つけてうれしくなった。この時代に生きる人々に「必要な唄」を届けられたら、それはすごく幸せなことだと思う。
2007年08月29日
コメント(0)
-
漂泊のやちまた家。
やちまた家、結婚してからすでに5回引っ越しをしている。新婚の引っ越し、転職の引っ越し、転勤の引っ越し、などなど。人生の節目節目に引っ越してきた感じ。2年に1度くらいの計算だな。この状態が続いていると、どこかに永住するという感覚になれない。ただ、今の場所がなかなか気に入っていて、一番長くなっている。繁華街には近いし、大きな公園もあるし、まわりの道路も広く渋滞もなく運転もしやすい。建物がボロだということを除けば、意外に好きな場所で、ずっとここに住んでもいいかな、と思っていた。ただ、図らずして、その人生計画は消え去った。な、なんと、「立ち退き」。昨日、市長印の入った文書がポストに入っていた。区画整理で廻りがどんどん立ち退いていき、道路がどんどん拡張していく中で、うちのアパートだけ残っていて大丈夫かな?とは思っていた。しかし、本当に立ち退きの通知が来ると、う~ん、ちょっぴり複雑な気分だ。まあ、お互い根無し草のやちまた家には、こんな運命がふさわしいのかも知れない。数年前秋田に転勤が決まった時、ちょっぴりブルーに帰宅したが、カミさんの「面白そうじゃん」の一言に、「そうか、面白いかも」と前向きになれた。今回も、そろそろ新しい風を入れる時だ、と神様が与えてくれたプレゼントかも知れない。この立ち退き話、今後どういう展開になるか。どうせだから、6回目の引っ越しを楽しもうと思う。
2007年08月28日
コメント(0)
-
ストッパー。
火事場のバカ力という。命を脅かすよう本当に大変な時に、思いもよらないような力がわき出る。普段は、肉体が無理な動きをしないように衛本能というストッパーがかかっている。このストッパーが外れる瞬間があるわけだ。このストッパーはいろんなところにある。例えば、広告を作る現場。通常コピーライターとデザイナーが別々にいる。それぞれの専門なわけだが、たまに煮詰まってきた時など、担当を入れ替えてみると意外に面白いものができる。プロのコピーライターでは考えられないような「ありえない」コピーを考えたり、逆にあまりにプロのコピーライターだったら恥ずかしいような「素朴な」コピーをデザイナーが考えたりして、すごく新鮮なものになったりする。つまり、コピーライターには知らず知らずのうちのプロのコピーの「常識」という「ストッパー」にかかっていて、どこかしら型にはまったつまらないコピーになってしまっているわけだ。このストッパーは、普段の生活の中でもいろいろある。例えば、唄を唄うとする。酔っぱらったり、喧嘩したりしたらすごい声を出す人が、恥ずかしいという意識なのか、喉を守ろうとするのか、間違えたらどうしようという意識なのか、なかなか人前で声がでないときがある。唄を唄うというささやかなことにも、人の目から自分を守るという防衛ストッパーがかかる。このストッパーを外したとき、はじめてその人の声がでるような気がする。知らず知らずにできてしまっている日常生活での様々なストッパーを、一度外してみると新しい可能性が生まれるのかも知れない。ただ、この防衛本能に打ち勝つには、計り知れない強い力がいるだろう。その力は、本能を超えるような強い意志なのか、守るべき自分が消えてしまうぐらいの「自分」を超えた本能なのか…。
2007年08月27日
コメント(0)
-
エキゾチック・ベリーダンス。
ひょんなことで、ベリーダンスをやっている人とお話をした。数年前から、ブームになっていることは知っていたが、いまいち縁遠かった。若い女性を中心にすごい人気で、ベリーダンス人口も増えているとか。ちょっぴり踊りを見せてもらったが、母胎信仰を起源としているからか、かなりお腹から腰あたりの動きが特徴的。(ベリーというのは英語でお腹という意味だそう)かなり官能的な女性の身体の線を活かした踊りという印象だ。エジプト式だとか、トルコ式だとかいろいろ分類があるという。完全に定形化した踊りではなく基本の動きをベースに即興でおどられる。剣を使って踊るワイルドなのもあるらしい。生の創造への歓び、はかない運命への悲しみなど、抑圧された女性の歴史と情熱がわき出てくるような踊りだ。やちまた道的には演奏の方も気になる。日本あたりだといっしょに生演奏で踊ることがあまりないのかな。できれば、生演奏をバックに踊ってほしいものだ。調べてみると、ベリーダンスの楽器としては、ダルブッカという酒杯形の太鼓がリズムを刻む。もう一つのリズム楽器は、ダッフと呼ばれる枠太鼓。そして、リュートや琵琶のような弦楽器ウード、東ヨーロッパのチターや、中国の琴、朝鮮のカヤグム、日本の琴などの源流と思われる弦楽器カーヌーン、尺八にそっくりな葦笛ネイ等が美しいメロディーを奏でる。太鼓に小太鼓に弦楽器に琴に笛。これはもう沖縄民謡・八重山民謡と同じような編成ではないか。そして踊り手は金属でできたカスタネットのような「ジル」を両手に持って踊る。沖縄民謡でも四つ竹をカスタネットのようにして踊るので、これも似ているぞ。ベリーダンスミュージックと八重山民謡との合奏なんてすっごくエキゾチックで楽しそうだ。こんないわゆる伝統芸能らしい編成をもった民俗芸能を世界中で探していくと面白いかも知れない。
2007年08月24日
コメント(0)
-
アジアな気分。
うちの会社でここ2日間、電気が切れるという事態が起きた。(節電なら偉いが別にそうではない。ブレーカーが落ちてしまうらしい。)まっくらの中で、系統が違うのかなぜかパソコンだけ付いている。これが、意外に集中できて心地いい。(まあ、目には悪いんだろうが。)そう言えばこの前、外注のプロダクションに行ったとき、意図的に電気を消して間接照明で仕事していたな。暗い方がアイデアが浮かんだり、仕事がはかどるらしい。心なしか涼しい感じも受ける。これは面白い取り組みだと思った。最近、小さな田舎街のスーパーに入った時、なぜか、アジアな感じがした。なにが、そうさせるのか…。においかな。でも、特にそんな感じもしない。「なんだか、アジアのスーパーに来ているような気がするけど、なんでだろうね」とカミさんに聞くと、「照明なんじゃない」というお返事。なるほど、そう言われると街中のスーパーよりちょっぴり暗い感じだ。この暗さが、アジアの雰囲気を作っているらしい。ということがあったからか、うちのアジアびいきのカミさん、最近家でも電気を暗くしている。思わず、「なんか暗いな~」とばかりに電気を付けてしまうと「なんで、明るくすんのよ。アジアな感じを楽しんでいるのに~」というお叱りを受ける。部屋が明るくないと落ち着かないやちまた道にとってちょっぴり苦痛だったが、何日間かこの状態を続けていると、だんだん目も慣れてくる。気分も心なしか落ち着くようだ。晩酌も心地よく回って、寝付きもいいようだし。日本はちょっぴり部屋が明るすぎるのかな。そう思うようにもなってきた。夜、なかなか寝付けない不眠症の日本の皆さん、ぜひお試しあれ。
2007年08月23日
コメント(0)
-
国境が溶けている。
南極の氷が溶けている。政治資金の問題にあくせくする政治家たちも、モンゴルに帰りたい朝青龍も、摩天楼で乾杯する金持ちも、戦禍に巻き込まれる中東の子どもたちも、この地球規模の環境問題の前では、みんな平等だ。環境問題に国境はない。日本の、東京の、霞ヶ関でうなるエアコンが、いとも簡単に南極の氷を溶かす。工場から出る煙も、中国の黄砂も、海に捨てられたゴミも、放射能汚染も、みんな簡単に国境を越えて、全世界に広まっていく。この地球規模の大惨事に、唯一プラス面があるとしたら、環境問題のような人智を超えた問題の前では、白人も、黒人も、金持ちも、貧乏人も、戦争で戦っている敵も味方も、みんな仲良く同じ運命に落ちてしまう、ということを知らしめてくれたことだ。世界中みんな環境難民という同胞だ。もう小さな差別にこだわっていないで、みんなで考えて、みんなで問題に立ち向かわなくてはいけない時期に来ている。南極の氷は悲しく溶けながら、そう人類に訴えているような気がしてならない。
2007年08月22日
コメント(0)
-
あなたの健康年齢は?
吉本隆明の「幸福論」を読む。最近の彼の問題意識は、高齢化社会に向かっているらしい。実際に齢を重ねた人間らしい、実直な文体・内容になってきていて好感が持てる。その中で、最近の高齢化社会に対する考えが述べられていた。高齢化社会。それははもちろん、お年寄りが増えることなんだけど、単にそれだけじゃなくて、実際の年齢と身体の健康年齢があまりにアンバランスに格差が大きくなってきている事態を言うらしい。例えば、70歳ぐらいでも20・30歳ぐらいの健康年齢の人がいれば、逆に、若者でも70・80歳ぐらいの身体になってしまっている人がいる、という具合に。高齢化社会を見るとき、この「健康年齢」を考えなければならないということかも知れない。この前テレビで、財政破綻をきたした夕張市の公的医療施設が閉鎖し、民間に委託されたという話題が取り上げられていた。その民間病院を引き受けた熱血医師が、これからの財政難の地方や僻地の医療に必要なものもは「予防医療」だと訴えていて、とても興味を持った。予防医療により病院にかかる人が少なくなれば、自治体の負担も少なくなるわけだし、健康になった人が労働力になって、税金収入の助けにもなるわけだ。う~ん、なるほど。これからの地方の財政にとって、住民の健康年齢を若く保つことがとても大事になるわけだ。(これは、きっと年金問題でも同じことだ。)加速化する高齢化社会の唯一の対応は、『健康年齢における高齢化社会をつくらないことだ』と言えるかも知れない。これは、個人レベルはもちろん、自治体も国も力を合わせてやっていくべきことでないか。医療の分野だけに限ったことではない。例えば、スポーツの分野でも、レジャーの分野でも、食品の分野でも、音楽などの分野でも、そして文学や思想や宗教の分野でも、歳をとった人が健康年齢を保ち、さらには若くすることができるぐらいに、元気を与えたり応援をしたりする必要があるのではないだろうか。この問題は、日本のこれからにとってとても大事な国をあげての「政治」的な問題だと思う。
2007年08月21日
コメント(0)
-
楽天イーグルス応援。
週末、楽天イーグルスの本拠地、「フルキャスト宮城」にてわが三線の会の演奏。球場でどうやって演奏するのかな、と心配していたが、リハで出向くと球場前に特設ステージみたいなのができている。東京、沖縄などからプロのアーティストがいくつか集まってのイベントらしい。イーグルスは久米島でキャンプをしていることもあるからか、沖縄関係が2チーム。(というか、もうひとつは、全国的にも有名な女性ボーカルの人でしたが…)そんな中での、八重山民謡。試合前に向けてテンションがあがっている野球ファンの前で、しぶい八重山民謡がうまく合うかどうか心配だったが、今回はあえてアコースティック(?)にやってみることに。一曲目に選んだのは、八重山民謡の座開きでよく唄われる「鷲ぬ鳥」。まさに正月の初日の出に向かって鷲が飛び立つ勇壮な姿を唄ったものだ。フルスタで唄うにはピッタリではないか(?)そして、楽天イーグルスとファンの皆さんの繁盛を願って「繁盛節」。最後のカチャーシーは、予想していたようにそんなには立ち上がって踊ってくれなかったけど、まあ、全体的にはいい感じで演奏できたのでは。普段聴くことのできない八重山民謡を多くの人に聴いてもらえたと思う。この日音楽の演奏以外になんと地元のちびっ子シンクロチームによる演技もあった。どんな形で演技するのか興味津々だったが、なんと球場前に巨大なプールというか、水槽が用意されていて、その中で見事にシンクロをやっていた。これには、親御さんやお客さんもやんやの大騒ぎだった。とにかくあの手この手で球場を盛り上げている楽天イーグルス。この日球団最多勝記録も作ったし、その次の日の連勝にもつながったし、我々も頑張って演奏した甲斐があったというものだ。この勢いで「鷲ぬ鳥」のごとく、Aクラスに向けておおいに飛び立ってもらいたいものだ。(というか、また是非演奏させてください!)
2007年08月20日
コメント(0)
-
記憶は、あまりに美しい。
過去の写真を見る。決してうまい写真ではなくても、その写真から蘇ってくる記憶はだいたいにおいて美しいものだ。例えば、わが三線の会の過去の演奏シーン。決していい演奏でなかったものも、時間が立つにつれて都合のいい美しい想い出だけが残ってしまっている。「とりあえずこの時は頑張ったよな」「まあ、お客さんには楽しんでもらえたよね」みたいに、どんどん記憶は美化されていく。これは写真だけじゃない。最近、動画を撮るようになって思うのだが、実に過去の映像は惚れ惚れするぐらい美しいのだ。なんか、プロの演奏シーンをみているようなスター気分になってしまう。人間はほんとうに都合のいいものだ。広島・長崎の記憶。いま、戦争体験者がどんどんいなくなり、戦争の悲劇の記憶を伝える人がいなくなっているという。でも、本当にそうか。多くの人が心配しているようには、人間は決して都合良く記憶を「失えない」のではないか。こんなに情報化・データベース化が進む時代において、過去は自由に再編され都合良く記憶されていくのではないか。今後「戦争の最大の被害者=日本人」という美しい記憶だけを増長していくような気がする。日本人は大いなる被害者であると同時に、いやそれ以上に大いなる加害者でもあった。この「痛い」記憶のみを都合良く風化させて心地よい部分のみ残していく日本人。この美しい記憶は、新しい「力」にならないとも限らない。
2007年08月17日
コメント(0)
-
気仙沼で島気分。
お盆休み。カミさんがいろいろ用事があった関係で、今年は特に遠出はなし。とは言っても、どこにも行かないのも淋しいので、近場の気仙沼に1泊のプチ旅行に行ってきた。気仙沼と言うと「気仙沼ちゃん」で有名な大島がある。気仙沼からフェリーが出ていて、20分ぐらいで行けるとのこと。7時ぐらいまで、フェリーの行き来があるみたいなので、とりあえず行ってみることに。夏にフェリーに乗ると、どうしても八重山を思い出す。石垣から竹富・黒島などいろんな所に出ているわけだが、そのフェリーに乗って島々を巡るときのワクワク感はたまらない。そんなワクワク感を今年はあきらめていただけに、ちょっぴり手軽な島めぐり気分を味わえたわけだ。大島に着く。面積約9キロ平米、周囲24キロ。八重山諸島でいうと黒島あたりの大きさか。思っていた以上に観光地だし、人も多い。カーフェリーで気仙沼から車で来ている人もいる。いろいろ巡るのも歩きだと大変なので、車で来ても良かったな、と思った。(今度来る時はそうしよう)20分ぐらい歩くと浜に出る。こちらは沖縄の海と言うわけには行かないが、仙台近隣の浜よりは数段キレイで雰囲気もあった。海パンを持ってきていないので泳ぐわけにはいかなかったが、とにかく島からの水平線を見ながら潮の香りを味わえたのは、とてもラッキーだった。気仙沼の旅館では、フカヒレを中心とした海の幸を堪能できた。この辺は北の海の醍醐味だ。今回の旅で感じたこと。やっぱり島は夏の旅には最高だということ。いつかわが三線の会の合宿もこの島でできたらと思った。(八重山までみんなで行くのは現実的ではないからな~)あと、東北の島で、南国気分を味わえるぐらい、やっぱり温暖化が進んでいるということか。旅の途中、車の中にいても地球が燃えているという感じがした。国道沿いの温度計が39度を指していたのは、決して温度計が壊れていたわけではないのだろう。全国的に有名になった「氷の水族館」の中で、マイナス20度の中で氷漬けになった魚たちが、なぜかとっても幸せそうに見えてしまった。
2007年08月16日
コメント(0)
-
飲み屋で人生ゲーム。
「…だからさ。オレの人生に意味があるのか。生きる価値があるのかって話しよ。」「うるさいな…。じゃあ、そもそも意味と価値ってどういうことか考えてみろよ。」「…あん?」「例えばここに鉛筆がある。この鉛筆の価値はなんだ? 何か文字を書くことじゃないのか。でもこいつみたいに芯が出てなかったらどうなる? ちゃんと削って書けてこそ価値があるのに。」「そりゃそうだ。これじゃ文字かけないもんな。ちゃんと削っとけよ。ほんとに…」「じゃ、この鉛筆の意味はなんだ?」「意味?飲み屋に鉛筆なんか意味ねーよ。飲むことも食べることもできやしねえ。」「確かに飲み屋に鉛筆は意味がない。じゃなんで飲み屋に置かれているんだ?お前が、このアンケートにちゃんと書き込んで、この店が良くなれば、それは意味があることじゃないか?」「まあね。オレがアンケートに答えれば意味があるわな。でも、オレ書かないよ、アンケートなんか。もう、べろべろに酔ってるし…。こんな店なんかくそ食らえだ。」「そうさ。つまり、この鉛筆は意味も価値もないってことだ。」「そうだ。この鉛筆には意味も価値もないって…ちょっと待て、今の例えで、オレの人生には意味も価値もないっていいたいわけ…なの?」「そうだね。」「ちょっ、ちょっと。こんな鉛筆といっしょにすんなよ。」「いっしょさ。」「でも、この鉛筆だってちゃんと削れば価値はあるんだろう。アンケート書けば意味もあるんだろ?」「そりゃそうさ。でも、飲み屋で誰が削る?誰がアンケートなんか書く? 結局、意味も価値もないってことさ。…なんだ泣いてるのか。よし、今日は朝まで飲みあかそう。」<飲み屋に残されていたメモ>価値を持つには努力・精進・錬磨が必要だ。意味を持つには使命・神託・召命が必要だ。声なき声を聞く必要がある。***************************ふ~暑い。脱水症状だ。お盆休み前の最後の週末。キューっとビールで、乾きを潤したいもの。「でも、ビールは水分補給にはならんよ」とカミさんに教えられた。「じゃ、何を補給するんだ」と聞くと、「そりゃ、笑顔補給よ!」と勝ち誇ったように言った。暑気払いして、笑顔のお盆休みを!
2007年08月10日
コメント(0)
-
身体が教えるバランス。
人間の耳は2つあるのに比べ、口は一つしかない。他人の話を「2」聞いて、自分の意見は「1」だけ言いなさい、と昔母親に聞いたような気がする。人間の身体は、人間のあるべき姿を示しているということか。例えば、歯。人間の歯は、臼歯20本、門歯8本、犬歯4本。割合で言うと、臼歯が62.5%、門歯が25%、犬歯が12.5%。 この割合が人間が食べるべき食物の割合を示すらしい。臼歯は穀物をすりつぶす歯。門歯は海草や野菜をかみ切る歯。犬歯は肉や魚を食べる歯。 だから、62.5%は穀物、25%は野菜や海草、12.5%が肉や魚というのが望ましいという。偏りの多い現代人。こんなバランスで食べている人はそうはいないだろう。うちの会社の若い連中の半分ぐらいが、毎日のようにカップラーメンを食べているが、他人事ながら、大丈夫かと思ってしまう。頭はどうか。頭があって、手足が4本ある。ということは、頭の働きが「1」で手足の働きが「4」と安易に考えてみる。脳の消費するエネルギーは、全体の平均代謝エネルギーの19%~24%程もあるといわれているから、あながちやちまた道の脳1/5説は間違っていないのでは。となると、考えて、動いて、動いて、動いて、動いて、考えて、動いて、動いて、動いて、動いて…ぐらいのリズムがいいようだ。どうも現代人、このバランスが悪いように思える。全然動かず、頭でっかちに考え込んで胃に穴があくタイプ。何も考えてなく、脳まで筋肉じゃないかと思える体育系タイプ。このどちらかに二極化しているような気がする。昔、ベルグソンという哲学者が考えながら動き、動きながら考えるという行動主義哲学を打ち立てた。閉塞的な現代社会において見直されるべきバランス感覚のある思想かも知れない。
2007年08月09日
コメント(0)
-
ラッセルの幸福論。
疲れがたまると栄養ドリンクが飲みたくなる。決して身体にいいと思っていないが、年に1回か2回飲んでしまうことがある。よく効くと思う。栄養を極限的に欲している状態だから、乾いた大地が水をよく吸収するように、実際の成分以上に効くのかも知れない。これと同じように、人はたまに幸福論なる人生の点滴を打ちたくなる時がある。その時ぼろ雑巾のように人生に疲れていると、うまく言葉が心に沁みてしまう。ただ、気をつけないといけない。幸福論という媚薬ばかり飲んでいると、効き目がまったくなくなってしまう…。ラッセルの幸福論。形而上学者としてはあまり好きな人ではないが、文章が明確でわかりやすい人だとは思う。即効性を求める幸福論などには適していると思い読んでみた。「人間、関心を寄せるものが多ければ多いほど、ますます幸福になるチャンスが多くなる」「人生に対して熱意を持っている人は、持っていない人よりも有利な立場にある。不愉快な経験ですら、彼らにはそれなりに役立つ」「男性にとっても、女性にとっても、熱意こそは幸福と健康の秘訣である」「熱意(Zest)」か。確かにこの冷め切ったというか、しらけた世の中で一番必要なのはこの「熱意」かも知れない。北村透谷も熱烈な「熱意」論者であった。「すべての情感の底に「熱意」あり。すべての事業の底に熱意あり。凡(すべ)ての愛情の底に熱意あり。若しヒユーマニチーの中に「熱意」なるもの無かりせば、恐らく人間は歴史なき他の四足動物の如くなりしなるべし。」ラッセルのページを進める。「あきらめには、2つの種類がある。 1つは絶望に根ざし、もう1つは不屈の希望に根ざすものである」ようは、絶望して努力をやめるいわゆる「あきらめ」と、くよくよ悩まずに現実をすぱっと受け入れた上で次の幸せを目指して邁進する「不屈のあきらめ」があるというわけだ。「不屈の希望」。 う~ん、いい点滴。病気にも屈し、会社でも屈し、人生の荒波にも屈している「屈しぐせ」のついたやちまた道には、よ~く効くお言葉だ。ただ、幸福論なるもの、本当の人生で活かされなければなんの意味もない。どこで読んだか忘れてしまうぐらい自分の血肉になった時こそ、本当の幸福論だ。
2007年08月08日
コメント(0)
-
日本の夏が寝苦しい。
仙台に来たとき、「なんて夏が涼しんだろう」と思った。引っ越して一応クーラーをつけたものの、使うのは年に1回か2回だった。名古屋や東京の熱帯夜の中で生きてきた人間には信じられない快適さ。しかし、この状況も少しずつ変わってきているように思う。やはり、温暖化なのだろうか、仙台でも寝苦しい夜が増えつつある。この暑さの正体は何か。まあ、ひとこと夏の暑さなんだけれど、自然の暑さではなく、人工的な暑さのような気がする。日中ガンガン付けられるクーラー。夜もやめられず付けるクーラー。このクーラーから出る排気がますます都市を熱く寝苦しくしているように思う。クーラーは涼しくする機械というより、涼しいところと暑いところを暴力的に線を引き、人工的にその温度差を付け、中にいる人間だけが涼しいという特権を得ようというファシストのような機械だと考えた方がいいようだ。自分だけが涼しくなればいい、というエゴの塊によって、人工の涼しさがあちらこちらで創られているわけだ。考えてみると、欲望の都市において生まれるどんな幸せや快適さもだいたいにおいてこんなカラクリにある。だれかが恋人をゲットすれば、だれかが失恋の涙を流す。だれかが宝くじを当てれば、だれかが外れてやけ酒をあおる。日本の子どもたちがファミレスでなんでも好きな物を選んでいる時、どこかの国の子どもが飢餓の中で死んでいく。この欲望の線引きに守られて、日本人は小さく小さく、その場しのぎの幸せや快適さにしがみついて生きていきているわけだ。クーラーの涼しさは、こんな後ろめたさを感じる涼しさで、実に気持ちが悪い。とりあえずこのすっきりしないクーラーの涼しさをみんなでやめたらどうだろう。1日でもみんなが外で草に埋もれて寝たら、日本は涼しくなるんじゃないのかな。
2007年08月07日
コメント(0)
-
中途半端なお祭り気分。
いま、七夕の真っ最中。街のアーケード街は七夕飾りと観光客でごった返している。朝の通勤も、たぶん昼の移動にも影響がある。仙台の街が変わっているというか、面白いな~と思うのは、すべてが一つの街に集中していること。100万人都市クラスで、すべての機能がこれぐらいコンパクトに集中している街もないだろう。だから、祭りもビジネスも同じ土俵で行われることになる。これが、祭り好きな街(例えば竿灯が行われる秋田なんかもそうだったが)だと、仕事そっちのけで祭り一色になるが、仙台あたりだと、どうも観光客とビジネスマンがしっかり2分されて街に混在しているようだ。だから、お互いがお互いを「うさんくさそう」に見ている。これぐらい、大きな祭りなのに、地元の人にあまり愛されていない祭りもないんじゃないかな。まあ、前夜祭の花火はそれなりに人が来るようだけど。これは、どう考えても、七夕飾りだけの祭り囃子や御輿などの「動き」「踊り」や「音」「炎」などがない「静かな」祭りだからだと思う。いかにも手っ取り早く商店街が客寄せ用に残している祭りのようになっている。この、はっちゃけられない仙台っ子の祭り気分を補完するのが、よさこい祭りやすずめ踊りということになるが、この祭りもかなり演奏する側だけで楽しむ祭りになっていて、個人的に観に行きたい祭りにはなっていない。なんか、演奏する側と見る側がひとつになれるような祭りはできないものなのかな~。まあ、この中途半端な感じが仙台らしいのかも知れないが…。
2007年08月06日
コメント(0)
-
ニライ・カナイ ー 遠くへの想い。
最近見た沖縄映画で心地よかったのが「ニライカナイからの手紙」。美しい沖縄・竹富島を舞台にした母と娘の物語。わけあって東京に旅立ち、会うことのできない母親からの毎年誕生日に届く手紙。この手紙に見守られるように、少女は成長する。20歳になったらすべてを説明するという約束を信じて…。これを、沖縄らしく、遠く美しいニライ・カナイからの手紙として描いている。ニライ・カナイ。南西諸島の各地には、毎年遠く彼方の理想郷ニライ・カナイから神が渡来してきて、豊穰や幸福をもたらすという信仰がある。一般的に海の向こうにあると思われているが、多良間島の「ニッラ」のように地底深くというのもある。どちらにしても、人間界とは隔絶された遙かかなたの「異界」がニライ・カナイだ。どこか、遠くからやってくるという想い。これは形は違うにしても、どの民族でも持ってきた想いではないのか。しかし、交通手段やインターネットやケータイの発達によって、この距離感というか、「遠く」感が失われているように思う。ニライカナイからの手紙。映画で手紙がよくテーマになるのは、映画が本来決してこの世には「現前」しないはかなく手の届かないものを扱うからであり、手紙がその「現前」しない「遠くからくる」ものの象徴だからではないか。遠く。どうしようもないぐらい遠く。この自分を踏みつぶしてしまうぐらいの距離感があるからこそ、人は感傷的にもなれるし、やさしくもなれるし、詩人にもなれるし、冒険家にもなれる、と思う。もっと、遠くを想い、遠くを目指して、日常を生きていくのもいいと思う。
2007年08月03日
コメント(2)
-
ちょっと怖い話し。
うちの会社で朝ちょっとした騒ぎがあった。前の日の朝、誰のものかわからない、ラッキーストライクの煙草が、ある人の机の上に置いてあったらしい。2・3本吸った吸い殻が吸い殻入れにもあったという。とりあえず、昨日はそのまま帰ったらしい。と、今日、さらに、同じ煙草から2・3本抜かれ、吸い殻に変わっていたという。鍵はもちろん、閉められていた。セコムにも異常通報はなかった。真夜中に若者でも入ってきて煙草をすっているのだろうか。しかし、どうやって?それとも、幽霊か。う~ん。なぞだ。どちらにしても物騒な世の中だ。知り合いの家にどろぼうが入ったとも言うし。暑い日が続きますが、戸締まりには気をつけてください。
2007年08月02日
コメント(0)
-
かせいでますか。
岩手弁で働くことを、「かせぐ」という、らしい。例えば、カミさんの実家で庭掃除を手伝うとする。すると母親が出てきて「かせいでるね~」と言う。稼いでる? いや別にお小遣いをもらおうなんて思ってないぞ…。もしかしたら、点数稼ぎと思われている? 別にそこまで気に入られようなんて思ってないよ、といろんな考えが瞬時に頭を駆けめぐり返す言葉に困っていると、隣で気づいたカミさんが「岩手では、かせぐは働くことよ」と笑っていう。ふーん。一説によると、「かせ」というのは「綛」と書き、紡いだ糸をかけて巻き取る道具のことをいうらしい。自給自足的な生活をしていた昔は多くの農家で使われていたという。となると、本来「かせぐ」とは汗水たらして働くことを言うのかな。それが労働等価としてお金が払われるようになり、それがいつのまにか、金を得ることだけを「かせぐ」というようになってしまったのか。この等価ということでの稼ぎ(お金)ならまだいい。最近では、なんの苦労もなしに金を儲けようという輩も出てきている。(そういうやちまた道も、なんか簡単に儲けられることないかな~、なんて常日頃思うようになっているが…)岩手は普代村の方言かるたに「かせぎっとの でんびにひかる たまの汗」というのがあるらしい。かせと汗。これこそが本当に等価なものなのかも知れない。ここで、具志頭村出身の仲本稔がつくった戦後沖縄の復興の精神的な支えになった有名な沖縄民謡「汗水節」を思い出した。汗水ゆ流ち 働らちゅる人ぬ心うれしさや 興所の知ゆみ(汗水流して働く人の心のうれしさは、他の人にはわかるまい)かせぐ。地道にもくもくと「汗しかせいできた」、そんな地域に残っている、いい言葉だと思う。
2007年08月01日
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1