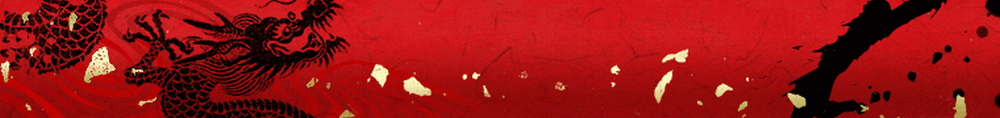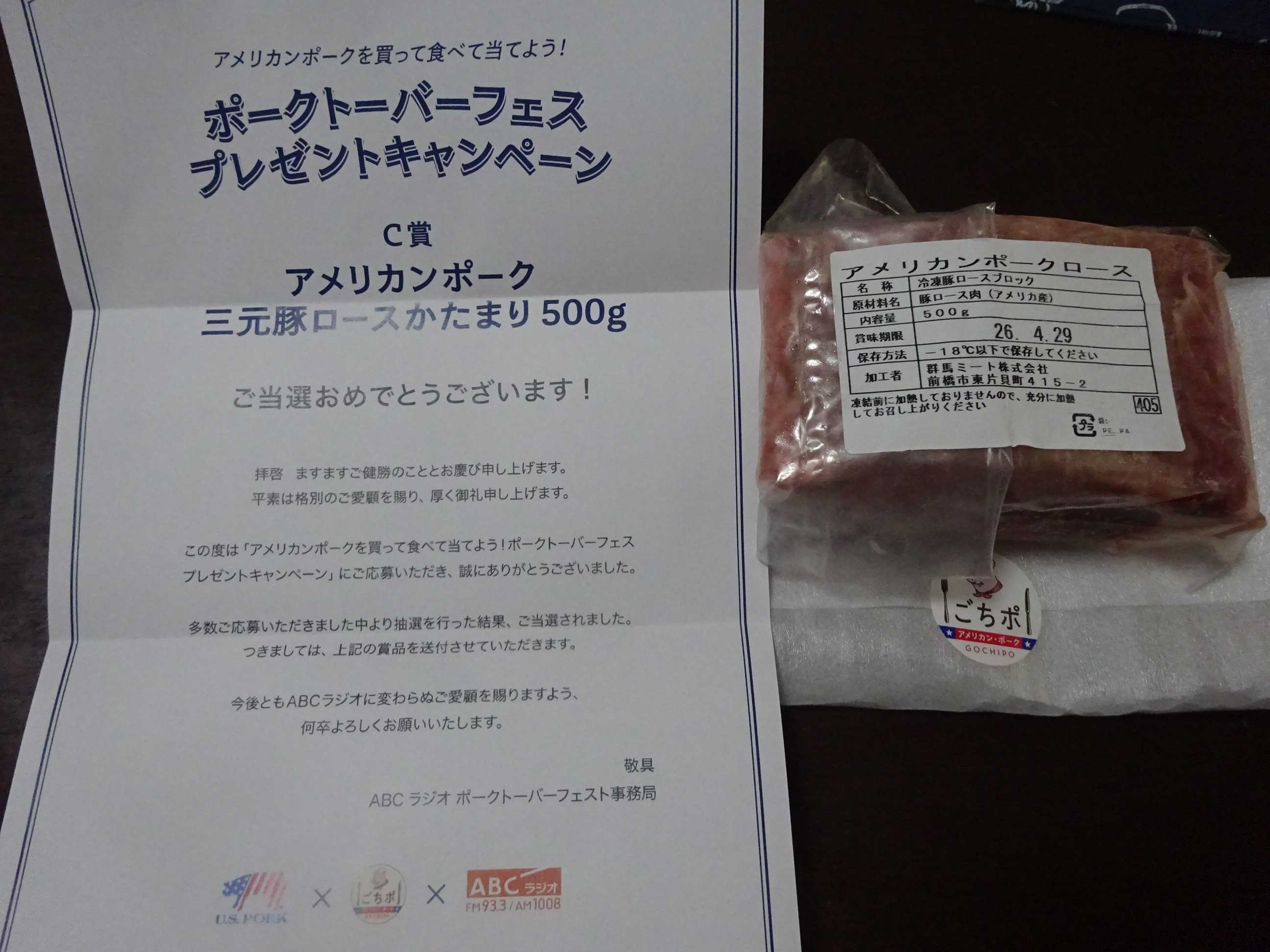2008年01月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
ずんだ(づんだ)餅。
東北の言葉と言えば、鼻濁音だ。耳にキンキンする名古屋弁を聞いたあとで、柔らかい湿度を感じさせるような鼻濁音を聞くと、妙に力が抜けて、癒され、東北に帰ってきた、という感じになる。聞き取りにくい感もあるが、温もりを感じさせる「やさしい音」だ。西の人間には、うらやましい音でもある。昨日、老舗の和菓子のおばあちゃんと話をした。「ずんだ(づんだ)餅」が自慢のお店。北海道中札中村で作られた「大袖の舞大豆」という自慢の枝豆と牛50頭の堆肥をしたブランド米「みやこがね」を使用したこだわりの一品らしい。「亡くなったじいちゃんが、材料だけはこだわらねば、と言ってからね。これだけはこだわらねばね。」おじいちゃんへの想いが、「ずんだ(づんだ)餅」への想いになっているようだ。おばあちゃんの口からでる「ずんだ(づんだ)もつぃ」という音がやさしくていっぺんに愛着を持ってしまった。仙台に来るまで、ずんだ(づんだ)餅のことを知らなかった。枝豆を塩茹でしてすり鉢に入れ棒等ですりつぶし、砂糖を加えてまぜたものを餅にからめるという和菓子。枝豆でできているので、色は緑だ。ちょっとこの色が芋虫になったような気分で、最初はとまどうが、ちょっぴり青臭い自然な香りと甘さがとてもいい。なぜ、ずんだ(づんだ)というか。豆を打つことから「豆ん打(ずんだ)」からきたという説や、伊達政宗が出陣の際に用いた「陣太刀(じんたとう)」で豆をつぶして食したことから「陣太刀」→「陣太」→「ずんだ」となまった、などの諸説があるらしい。栄養価も高い。カルシウム・ビタミンB1・B2・Cを多く含むので健康・美容食品としても見直されている。特に夏バテにはいいらしい。全国から注文できるので、ぜひ甘さひかえめが好きな和菓子ファンには食べてもらいたい。
2008年01月31日
コメント(0)
-
外に点を置く。
ある時、いい言葉を聞いた。会社のセミナーだったか、お客さんとの会話の中で出た言葉だったか。いい言葉だったが、その言葉の出どこさえわからない。その言葉とは「円の外に点を置く」というもの。これだけだと何のことかわからない。円とは、「今の自分」の能力だったり、可能性だったり、価値観だったり、散歩の範囲だったり、好きな音楽のジャンルだったり、政治的信条だったり、交遊範囲だったり、行きつけの飲み屋の範囲だったり、属している組織だったり、営業範囲だったり、支配力だったり、いろんな場面でいろんな円を考えることができるだろう。この範囲を広げることが大事で、それが自分を成長させることなんだろうけど、なかなか円の中にいると、その円そのものを広げるのは難しいものだ。じゃ、思い切って、自分の円の外にとにかく「やみくも」にでも、新しい点を置いてみよう。自分の円とはまったく違うところがいいし、むしろ遠いところに点を置く方がいい。そして、この点を目指して円を広げるわけだ。最初は円にならない。1点が突き出た変な円になる。楕円になる、ひょうたん型になる。そしているうちに一皮むけた、新しい大きな円になるのだろう。それが自分の可能性を広げるという仕組みだ。う~ん、なんかどこそこの能力開発セミナーみたいになってきた。まあ、しかし、今の自分という円の外に点を置くということは、すごく難しいことだし、すごく大切なことのように感じるので、この言葉ちゃっかりもらっておこう。ちょっと頭の片隅に置いておくと、いろんなところで使える気がする。
2008年01月30日
コメント(0)
-
東方に落語あり。
落語と言えば大阪の上方落語、江戸の江戸落語。ある意味すご~く地域限定のものだと思っていたが、仙台でも落語が聞けると知り、驚いた。「東方落語」。元フリーアナウンサーさんが立ち上げられた落語。立ち上げから10年。東北の訛りを使って東北ならでは落語をつくっていこうということらしい。へえ、東北に落語か~。口べた(失礼。いい意味ですよ!)な東北人と落語がなんか合わないな、という勝手な感があったが、東方落語の中のおひとりに岩手県・遠野の出身の方がいるので、はたと気づいた。そうか、「語り部」というものがあった。遠野を筆頭に「語り部」の多くいた東北は、ある意味「はなし」のすご~く長い伝統があったわけだ。大阪や江戸のような「噺」とは別の心あたまる「語り」というものの伝統を活かせば、新たな落語の伝統が生まれるのかも知れない。そして上方落語や江戸落語のように歴史と伝統がないだけに、0からの出発、いろんなチャレンジができるのが東方落語の魅力。民話をもとにした創作落語。落語に漫才があってもいいではないかということで取り入れたトリオ漫才。照明やBGMを駆使した演劇のような演出。とても面白い。観客も温かく、見守っている。ちりとてちんに飽きたら、東方落語を見てみるのもいいのでは、と全国に向けてPRしてみる。
2008年01月29日
コメント(0)
-
ケルトの音楽。
アイリッシュ音楽をすこし知りたいと思っている。週末、アイリッシュ音楽のライブがあることを聞いて、アイリッシュパブに行ってみた。演奏される方は3人。フィードル・アコーディオン・ホイッスルの編成。パブで聞く生演奏は初めてなので、良い経験をさせていただいた。アイリッシュの音を聞きながら、頭に浮かんだことがある。一つは「泣き」の音だな~ということ。フィードル・アコーディオン・ホイッスルも日本人の心を揺さぶる「泣き」の音色をしていると思う。ただ、その音は決してクラッシックのように悲痛な「重さ」を感じさせない。「泣き」から「笑い」へ。抑圧された分だけ、沸き上がるような歓喜のリズム。そこにはいわゆる「泣き笑い」の「軽さ」があるように思った。このあたりが日本人の感性にぴったりくるのではないだろうか。もう、一つは、「有機的な音」であること。アコースティックとか生の音というレベルではなく、もっとケルトの奥深い自然の営みを感じさせる音といったらいいだろうか。有機的ということ。これの特徴は「生きているもの」という感覚だ。決してひとつひとつの音やパートに分割できない、有機的な結合。そして「ケルトの森」に象徴されるような、生命のつながり。生み出されながらも、何かを生み出すような創造的な「生の躍動」を感じさせる音色。この深い森の息づかいを感じさせる有機的な音が、アイリッシュの特徴であるのではと、漠然と感じながら聞いていた。この音を聞きながらホワイトヘッドの有機体の哲学というのをおぼろげながら頭に浮かべていた。後で調べていると、イギリス人のホワイトヘッド、自分では「ケルトの血が流れているのではないか」と思っていたらしい。ホワイトヘッドの有機体哲学とアイリッシュの出逢い。う~ん、この符合はちょっと面白い感じがする。
2008年01月28日
コメント(0)
-
流通するものから贈与するものへ。
中沢新一がいいことを言っていた。一般に考えられているような、貨幣を媒体とした交換行為である現在の「経済」はおかしいと。もともと「経済」というのは、人間関係を作りながらものを移動させること。ものの富だけでなく心の豊かさと一体となって贈り与えるものだった、というわけだ。これは、「芸術」にも言える。「芸術」が生み出されると世界の豊かさが増す。ものの豊かさを生み出すそのことが「芸術」だった。経済と芸術。素朴な時代に於いては、一体となったものだった。今、人間の一生も流通される時代。流されることなく、いいように使い古されるのでもなく、素朴に何かものの豊かさを創り、贈り与えることができる、そんな人生を送りたいものだ。
2008年01月25日
コメント(0)
-
プロパガンダ。
最近、映画を2つ見た。見たと言っても、ビデオをかりてきただけだが。ひとつは「パッチギ!2」。もうひとつは黒沢監督第2作品という「一番美しく」。「パッチギ!」は前作は良かった。暴力シーンは正直イタイが、「イムジン河」を軸にした現代版ロミオとジュリエットという切ないストーリーが涙をさそった。(沢尻エリカも今見るとほんと良かったね。)その次回作ということで、かなり期待したが…、ちょっと期待はずれかな~。まあ、「戦争美化映画」に対する強烈な「反対運動映画」という思い入れはよーく分かるし、全く、大賛成なんだけど、その思いが強すぎて、本筋の映画としてのドラマづくりにおいてちょっと空回りという感がした。(やちまた道的には「イムジン河」をもう一度使って欲しかったが…)そして、2本目の黒沢映画。1944年作という第二次世界大戦の日本の戦局が悪くなってきている時代の作品ということもあって、戦意高揚映画としての位置づけにあるもの。黒沢もこんなものをつくっていたんだね~。主人公の女学生が舞台の神奈川県平塚にある光学兵器製作所で、一生懸命兵器の一部となるレンズづくりをしている。母親の危篤死去にも関わらず帰省せずに働く子もいる。戦時中の勤労奉仕などの様子を伝える記録映画としても貴重だ。だが、この映画を作りながら、黒沢自体はどう思っていたのか。ちょっとそのあたりが見えなくて、感情移入できないで終わってしまった。戦争賛成にしても戦争反対にしても、何かプロパガンダとして利用されている映画には映画としての力や世界観がないように思う。両方とも周囲に目配せしながら作っている映画という感が否めない。もっと映画の世界にどっぷりつかって作って欲しかった、と思う。そういう意味で、不幸な映画2本だったと言える。
2008年01月24日
コメント(0)
-
糸は切れやすいーちりとてちん。
いや~いいね~ちりとてちん。和久井映見好きだからずっと観ているが、それだとあまりミーハーなんで、ブログには書かないでおこうと思ったが、本日のシナリオは切れ切れに切れているので思わずこの話題に。やちまた道、観るポイントは、和久井映見演じる母親「糸子」。そして、落語や塗箸などの伝統を伝えることの難しさという2点。糸子という名は落語の「たちぎれ線香」の中の幸薄い芸者・小糸からきている、と思う。この「たちぎれ線香」のあらすじ。若旦那が芸者遊びをしている。困った店の者が、旦那を蔵の中に幽閉。そこに芸者の小糸から手紙が来る。が、番頭、手紙を渡さない。80日目の手紙。中には「この手紙が最後になります。もうこの世で会うことも無いでしょう・・・」。その手紙を若旦那100日目に知る。慌てて茶屋に駆けつける若旦那。そこには小糸の位牌。驚きと後悔にさいなまれる若旦那。仏壇に向かって線香をあげ、手を合わせ詫びる若旦那。生涯妻を持たないと約束する若旦那。…と、置いてあった若旦那が贈った三味線が地唄の「雪」を奏で始める。「あれは小糸が弾いているんですよ。」と、涙するおかみさん。ぷつっと音が消えた・・・・・・・・「おい。どうしたんだい。糸でも切れたのかい。わしの好きな唄、最後まで弾いておくれ。」「若旦那。丁度、線香が立ち切れました。」…というような内容。昔芸者遊びする時、線香を焚いて、消えると終わりという決まり。線香が消えるまでの「おつきあい」という儚いものだった。糸か…。この儚い世の中には、切れやすいものがいっぱいある。芸者と若旦那の縁という糸も、三味線の弦も、儚い命の糸も、そして伝統というものの糸も。その切れやすい糸を、なんとか一生懸命紡いでいこう、というのがちりとてちんのテーマではないか。しかし、このちりとてちんのシナリオライターはなかなか素晴らしいね~。
2008年01月23日
コメント(0)
-
真夜中のストレッチ。
身も心も柔軟性が必要だ。やちまた道、すこぶる身体が硬く、そのためか、腰痛もひどい。夜普通に仰向けに寝ているだけで、腰がいたくなり、夜中に目が覚めることがある。(腰が伸びた状態で負担がかかるのが悪いのか。)試しにうつぶせになると腰はいたくない。でも、うつぶせだと胸が苦しい。顔も枕の中に埋もれて息ができなくて、死にそうになる。う~ん、どうしたものか。真夜中に考え出したらまた目が冴えてきた。ここで、頭のやわらかいやちまた道、いいことを考えた。身体が求める通り、上半身を仰向けにして、下半身はうつぶせにして寝れば万事OKなわけだ。(う~ん、素晴らしい!)つまり、腰のあたりで180°からだをくねる形。通常だと、かなり苦しいように思われるが、重いかけ蒲団でサンドイッチ状態になっているので、その状態でキープしていても全然苦にならない。かけ蒲団にストレッチをサポートしてもらっているような寸法。時間を見て、ひねり方を左右交互に変えてみると効果的だ。このストレッチのメリットはいくつかある。○ベッドが柔らかいので、無理な体勢でも腰に負担がない。○蒲団の重さで、身体の硬い人も無理なく腰がひねられる。(というか戻らない)○蒲団の中だと温かいので、筋肉にもやさしい。(むしろポッポしてくる)○真っ暗闇の中なので、誰に見られるわけでもなく、恥ずかしい格好も思いっきりできる。○他にすることがないので、ストレッチに集中できる。○気持ちよくなって寝てしまっても誰にも迷惑をかけない。せっかくなので、このストレッチ方法を「ベッドイン・ストレッチ」と命名してみた。ぜひ、遠慮なさらず今夜から試してみてください。
2008年01月22日
コメント(0)
-
器であること。
「私の一生はただ恵みをうけるための器であった」神谷美恵子の美しい言葉だ。自分を「器」であると感じられることは、素晴らしいことだ、と思う。「うつわ」とは「うつ」と関係あるのかな?自分を捨て、自分という入れ物を空しくする「うつ(空、虚)」。そして、空っぽになることによって、自然と何かが現れることとしての「うつし(現し、顕し)」。人間を器に例えることは昔からある。人間の大きさ、度量みたいものだ。ただ、本来の人間の器というものは、量的なものだけでなく、質的なものも示すのではないだろうか。日本人の美意識「用の美」の象徴である器。ここからは、強引な話。唄を唄う時、自分を「器」だと感じられると、いい唄が唄えるのでは、と思っている。人間には物理的にも、3つの器がある。口の中(咽喉腔)。胸郭。頭蓋骨。(三種の神器!)その3つの器をつなぐのが背骨や頸骨。一般的に口や鼻の中の器だけで音が出ると思っているが、響きのいい広がりのある声は、低い音域では「胸の器」で響き、高い音域では「頭の器」で響き、倍音が生まれ、増振する。自分という空っぽの器の中で、自然に何かが満たされ、あふれでるように共鳴している、という感じだ。そしてその器の響きは、部屋や音楽ホールという器の響きに共鳴し、最終的に聞く人の器に共鳴する。ただ、ここでも、最終的に共鳴しなくていけないのは、量的・物理的なものではなく、もっと質的・精神的なもののはずだ。
2008年01月21日
コメント(0)
-
著作権。
公共の場で誰かが作った歌を演奏すると、著作権にひっかかり、使用料を払わなくてはいけない、らしい。ちょっと名の通った人に演奏会などをやってもらうと、どこで調べたかわからないが、「日本音楽著作権協会」(ジャスラックというらしい)からしつこく電話がかかってきて、楽曲によっては、「お金を払え!」と言ってくる。まあ、民謡なんかだと、作られてから長い年月がたっているので、著作権はとうに失効しているだろうし、そもそも八重山民謡なんて、作者不詳がいっぱいある。著作権という所有の力から解放された唄。誰のものでもない、みんなの唄。それが民謡…、のはず。ある楽曲に著作権があるかどうか、だれの管理になっているかを簡単に調べることができる。ジャスラックのホームページで「作品データベース検索」という機能があるので、名前を入れると権利者情報や管理状況が一目瞭然だ。例えば、「おふくろさん」と入れてみる。お~出てくる、出てくる。作詞でかの川内 康範先生が出てくる。作曲で猪俣 公章、管理状況としてジャスラックの全信託となっている。八重山民謡なんてないんだろうな、と思い試しに入れてみる。有名どころで「安里屋ゆんた」。おっ、意外にもいっぱい出てくるゾ。もちろん本歌の作曲は沖縄県民謡で信託状況は消滅。まあ、これはわかるが、新・安里屋ゆんたの作詞の星克さんの権利が残っている!?(新・安里屋ゆんたで唄う時、ジャスラックにお金を払わなくてはいけない?うそ!?)その他の作曲に真島俊夫(だれ?)編曲に坂本龍一なんてのものある。(勝手に編曲して登録すれば、「安里屋ゆんた」の権利者になれるわけ!?)なるほどね~。坂本龍一の編曲バージョンで演奏する時は、使用料をジャスラックに払わなければならないんだね~。八重山民謡と世界の坂本龍一か…。ちょっと、聞いてみたい気もするけど。
2008年01月18日
コメント(0)
-
いぼとり地蔵。
仙台東照宮の近くにある延寿院。ここには、いぼとりの神様がいる。羽黒山から背負ってきて祀ったもので、供えてある小石を持って帰り、仏前に供え、毎日その小石でなでるとイボがとれる、と書いてある。お返しは1個借りたら2個、2個借りたら4個と倍返しする。その辺の川原の石でいいそうだ。こんなその辺にある石で御利益があるのか、と思われるかも知れないが、やちまた道、「いぼとりの神様」を信じている。というか、実際小さいころいぼとり神様にお世話になったことがある。小学生ぐらいの時。兄貴の手とか鼻(だったと思う)にイボができた。薬を塗っても直らない。親父が近くの有名な「小山のいぼ地蔵」に連れていった。こちらはその辺にある葉っぱをこする。結局なんだっていいのだ。数日するとポロッと落ちるようにイボがなくなった。そんなこんなするうちに、やちまた道自身にイボができた(ウィルス性なので他人にうつるらしい)。ということでもう一度、いぼ地蔵さんへ。今回はそのすごい霊力を知っているだけに、おまいりも真剣。葉っぱでこすって帰ると、兄貴よりはやくポロッと落ちた。「すごいぞ、いぼ地蔵!」と感心したものだ。まあ、人智を超えたすごいできごとに出会ったのは、これが最初にして最後だったが…。この前、名古屋に帰って、小学校のころの兄貴と映った写真を見て、このイボ事件を思いだした。ほんとうに、イボ地蔵は霊能があるのか?気になってネットで調べてみるとなんとなく納得のいく説明に行き当たった。イボはそもそもウィルスによるもの。インターフェロンという物質がこのウィルスの働きをシャットアウトするのだが、このインターフェロンは体内でも作られる。一種の免疫療法だが、「いぼ地蔵」のような暗示にかかるとこのインターフェロンがたくさん作られ、イボがポロっと落ちるというわけだ。なるほど、インターフェロンか。まあ、たしかにあの時点で兄貴のイボが直ったのを目の当たりにして完全にイボ地蔵様を信じていたので、インターフェロンだしまくりだったのかも知れない…。何にしても、すごく不思議て、すごく懐かしい出来事だった。
2008年01月17日
コメント(0)
-
気になる木。
朝通勤途中に見る、青葉通りのケヤキ並木。ケヤキというと新緑の季節ということになるが、意外と凜とした冬のケヤキもフォトジェニックで、好きだ。細かい血管のように伸び、曇天に何かを訴えるように突き刺さるケヤキの枝々。冷たい冬を静かに耐える生命の脈動を感じるようだ。このケヤキも地下鉄の工事のために何本か伐採されるらしい。移植の話もあったが、莫大の費用がかかるということで、仙台市民もグーの音も出ない感じ。いま、CO2削減ということで国を挙げて取り組みがされている。CO2削減ももちろんだが、CO2を吸ってくれる森の復活の方がもっと必要なのでは?(やちまた道、これからの世界に必要なのは「世界中みんなで1本植樹しよう!」だと思っている。)そんな時に、杜の都とうたっている仙台が木を切っていいのかね~。もっと、お金の使い道、頭の使い道があるのでは?と思ってしまう、寒~い冬の朝だ。
2008年01月16日
コメント(0)
-
防犯カメラ。
やちまた道、マンションというものに住んだことがない。ただ、仕事がら、よくマンションには出かける。マンションというものでいつもすごいと思うのが、オートロック。とにかく入る時にドキドキしてしまう。あと、エントランス付近にある防犯カメラ。高級マンションだと、10台ぐらいの防犯カメラがマンション全体を監視しているとか。中央監視センターみたいなところで、24時間映像を監視している。そして、監視しているだけでなく、その映像が録画されて、万一の時に再生できるようになっているらしい。やちまた道、ある時ふと、人間自体も防犯カメラみたいなものかな、と思ったことがある。宇宙のすごーい遠くに神様がいて、いそがしいので、地球を監視させるために人間を遣わした。何億というカメラから神様に映像が送られる。地球に何か起きていないか、遠くで監視できるわけだ。その映像は録画もされているので、神様が暇な時、自由に再生することもできる。ただ、この人間という防犯カメラ、マンションにある防犯カメラと違うところがある。マンションの防犯カメラは監視するだけで犯罪を犯さないが、人間という防犯カメラは自らが犯罪を犯してしまう。これは神様にとって誤算だった。
2008年01月15日
コメント(0)
-
こんな童話の夢を見た。
ある村に神様がいた。何でも叶えられる神様は、村人のために一生のうちで一度だけ願いを叶えてあげることを生業にしていた。だから、いつも神様の家は、朝から晩まで願いごとを聞いてもらおうと村人の行列ができている。小屋を建ててもらうものもいる。家畜の豚をもらうものもいる。子どもの病気を治してもらうものいる。みんな神様のもとで幸せにすごしていた。村には左吉という賢い若者がいた。左吉もそろそろ神様に願いごとをしようと考えている。「左吉は何をお願いごとするんだい?」「オレはお前らとは違う。もっと賢いお願いをする。」ある日、左吉が神様のもとへやってきた。「神様、今日は願いごとを叶えてもらうためにやってまいりました。」「おう左吉か。で、お前の頼みは何じゃ?」「…どんなことでも叶えていただけるので?」「ああ、そのかわり一つだけじゃぞ。」「では、私の願いは、『今後、どんな願いごとでもすべて叶えられるように』というものです。」「…なんと。それで良いのか?」「はい、まさにこの一つの願いだけでよろしゅうございます。」しばらく考えごとをしていた神様、にこりと笑うと、いつも願いごとを叶える時に使う「おおぬさ」を振って何やら呪文を唱えた。「よし、これで願いが叶ったぞ。」「そ、そうですか。」すると、神様、おもむろに「おおぬさ」を左吉に渡し、神様の家を出て行こうとする。「神様、どちらへ。」「だから、これからはお前が私の代わりに神様になるのじゃ。村には神様は一人だけと決まっとる。わしは引退してお前に神様の座を渡す。これからは、村人の願いをしっかり叶えてやるのだぞ。」そう言うと、神様はセイセイした顔で、村を出ていった。
2008年01月11日
コメント(0)
-
数字好き。
日本人は数字好きの計算好きだ。特に金勘定となると、もういてもたってもいられない。「願いましては…」といわれる反射的にそろばんをはじいてしまう。この習性によって大事な政治問題が、すぐに経済問題に転化してしまう、悲しい国だ。例えば、米兵のグアム移転の際の住宅費1戸7000万円。ぼっちゃん石破防衛相は「どう考えても高すぎる。積算を精査したい」と鼻息も荒い。7000万円。この数字を見せられると日本人は本能的に金勘定になる。「確かに7000万円は高い」「グアムだったら4000万でいけるんちゃう」「いや3000万円で十分いい家に住めるよ」「うちらの税金なんだし、もっと安いとこに住んでほしいわ~」…もう、この時点で米兵の家を建てることが前提になっている。うま~く政治問題が経済問題にすり替わっている。こうして、最終的にそこそこの金額で落ち着いて「いや~アメリカさんにまけてもらってトクしたわ~」となるわけだ。本来は、もっと本質的な政治問題であるはずだ。
2008年01月10日
コメント(0)
-
ヴィヴィアン・リー。
名古屋からの帰りはフェリーに乗った。フェリーではソファに座って自由にCS放送を見ることができる。テレビ前の椅子を陣取り、ワインで乾杯をしながら、チャンネルをCSの映画に合わせる。やっていたのは「風と共に去りぬ」。さすがは名作中の名作ということで、外国人のカップルも含め数人が集まってきた。「風と共に去りぬ」。そのストーリーと映画の壮大さはさることながら、目玉はなんと言ってもヴィヴィアン・リー。タラの大地の豊穣さを示すような奔放な女性像を実に名演していた。ヴィヴィアン・リーと言えば、最初に見た映画は「哀愁」。ガラス細工のような繊細な演技で悲劇のヒロインを演じきった。それ以来、女優と言えばヴィヴィアン・リーと言うことにしている。人はヴィヴィアン・リーのどこに惹かれるか。やちまた道的には、ずばり「眉毛」と言いたい。すべての人に理解されることを拒むような左右非対称な眉毛。「日本人の感受性」をフラクタル幾何学によって分析すると、非対称なものに惹かれる「非対称アシンメトリー原理」があるらしい。確かにひん曲がった盆栽も、よく分からない陶芸作品も、自由奔放な書も、アシンメトリーな美がある。ただヴィヴィアン・リーの眉毛の魅力はそれだけではない。そのアシンメトリーな中に何を見るか。決して安穏とした平衡状態に収まらない炎のように沸き上がるような激情。彼女の体内にある混沌(カオス)を見せつけられているような気がするのだ。「わたしはさそり座です。さそり座の人間は、私のように自分を食べ尽くし、燃やし尽くすのです。」この言葉通り、54歳の若さでスクリーンの中に生きる情熱と愛憎、気高さ、美しさを燃やし尽くし、旅立った。ヴィヴィアン・リーの眉毛はその炎のように燃え尽くした人生の象徴でもあった。そして「そんな人生を送れたら…」と彼女を見るものを誘惑し続ける。ちなみに、やちまた道もさそり座です。
2008年01月09日
コメント(1)
-
大阪人情。
年末恒例の東西屋ちんどん通信社さんの年末公演を見た。場所は、大阪は飛田オーエス劇場。飛田と言えば有名な色町。地下鉄動物公園前で駅員さんに「飛田オーエス劇場ってどこでしたっけ?」と聞くと、「今日なんかあるんですか?いろんな人に聞かれるけど…」と目を点にして逆質問されてしまった。場末の会場は、立ち見が出るほどの大盛況。ファンの皆さんはみんな「これを見ないと年を越せない」という感じになっているらしい。ちんどん屋さんというと、奇抜な衣装・仮装で街を練り歩く、締太鼓と鉦(当たり鉦)を組み合わせたチンドン太鼓の演奏が思い浮かぶ。…が、この東西屋さんの年末公演は、歌あり、大道芸あり、寸劇ありの何でもありの大衆演劇のるつぼ状態だった。気に入ったのが人情劇「忠太郎月夜」。いわゆる大衆演劇の面白さは、名シーンに出てくる名台詞。会場のおじさんおばさんはこの名台詞のために来ているといってもいい。…尋ね 尋ねた母親に 倅と呼んで もらえぬようなこんなやくざに 誰がしたんでぇ……俺にゃおっ母は、いねぇんでぇおっ母さんは、俺の心の底に居るんだ上と下との瞼を合わせりゃ 逢わねぇ昔のやさしい おっ母の面影が浮かんでくらぁ逢いたくなったら逢いたくなったら 俺ァ瞼をつむるんだ…この名台詞が出ると会場から「よっ日本一!」「東西屋!」というかけ声がかかる。会場全体が一体になれてほんとに面白かった。なんでちんどん屋さんがこんな寸劇まで一生懸命練習して演目として加えているのか?東西屋の林社長さんは「それは、ちんどんの先輩たちが、大衆芸能や大道芸あがりで、みんないろんなことができたから。少しでもその先輩たちに近づきたいという気持ちでやってます」と言っていた。公演後、ジャンジャン横丁で串かつ屋さんに。こじまりとした店内では、カミさんがすぐに隣の常連客らしいおじさんと仲良くなる。「飛田に行ってきたんですよ。」「このお嬢さん飛田に行って来たって!」とお店の人も混じって笑っていた。知らない人とすぐに知り合いになれるのが大阪下町人情というものかも。ただちょっと気になったのは、ジャンジャン横丁の串かつも新しいチェーン店らしい店が増えて来ていること。「味も人情も落ちたらしい…」というおじさんの言葉が寂しそうだった。
2008年01月08日
コメント(2)
-
はじまりの祝福。
少し遅いですが、明けましておめでとうございます。正月ボケというが、まさにボケが入っている。10日ぐらいも世間から離れていると、どうも世間の時間の流れについていけない。正月の間、いろいろなことがあったり、考えたりした。そのあたりは追々書いていこうと思う。その中で一番感動を覚えたことを書こう。正月2日目。親父とカミさんとで、犬山モンキーセンターに出かけた。(おじさんおばさんで出かける場所か?)一番の目当ては、全国的に有名になった、たき火をする猿。しかし、期待していたわりには、こじんまりしていて、観客も盛り上がっていない。やっぱり、人間がやっているたき火を「猿まね」している猿なんてあんまり面白くないのかも。…で、一番感動したもの。テナガザルたちの歌だ。誰か一人(いや一匹)が、リズムを刻む。そのリズムに合わせ、大地のうねりのような低い音でベースを音を奏でる。そして、その音を土台にして、他のメンバーがまるでフリージャズのように、旋律を重ねていく。みんなそれぞれが、全体の音の中のパートを演じていることをしっかり意識しているようだ。もう、鳴き声の範疇を越えて、れっきとした「楽団」になっている。自然の音や野生の動物たちの鳴き声が、音楽の原初だとは思っていたが、これほどまで、完成度のある音楽を聴いたことはなかった。人間の音楽の方がちいさなちいさな「猿まね」であったと認識できた瞬間だった。一年のはじまりに、大地から祝福の音楽を聴かせてもらったようで、「よし、今年も頑張ろう」という気持ちになった。
2008年01月07日
コメント(2)
全18件 (18件中 1-18件目)
1