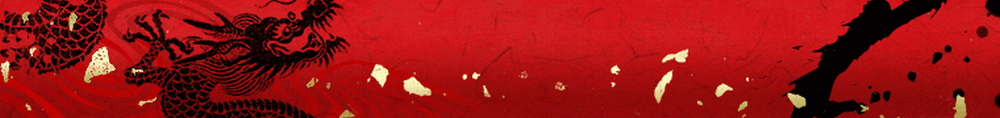2007年07月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
難死、そして小田実の死。
小田実の死。「何でも見てやろう」は、やちまた道にとって、ある意味人生のバイブルであった。日本という枠組みではなく、アジアという枠組み、世界という枠組みで考えなければならないな、と教えられた人だった。難死という思想には、共感を得た。死ぬ必要のない人が死ぬ。圧倒的な力の前になすすべをもたぬまま虫けらのように殺される人々の死。そして「被害者=加害者」の構図。被害者であることによって、知らず知らずに加害者になる。この殺戮の連鎖によって、死ななくてもいい人が死ぬ。この弱いものたちの死に、なんの意味があるのだろう。あまたの「無意味の死」。この死に意味を持たせることができるとしたら、戦争全体を見極めることだ、という。そして、小田実の死。政治が悪いなら、市民自らが動かなければならない。その信念とともに、ずっと行動の人だった。その死に意味があるとしたら、その行動を後の人々が受け継ぐことだけなのかも知れない。
2007年07月31日
コメント(0)
-
浜のまつり。
やっぱり海洋民族の芸能は、海に近いところでやるのが一番。いつもは、屋根のあるところや、街の中で演奏しているだけに、はじめて海の風を感じながらの演奏で、やっぱり八重山の芸能はこうあるべきだと思った。週末の天気。一週間心配しつづけた結果は、曇りのち小雨。(ぜひ、青空のもとで、と思っていたが、最悪の事態はまぬがれた。空の神様に感謝せねばなるまい。)イベントの方は無事開催できたし、お客様も雲行きのあやしいなかでたくさん集まってくれていた。宮城県というか、東北の地で、エイサーや沖縄ポップス、古典民謡などが集まる沖縄だけのイベントは、もしかしたらこのイベントだけかも知れない。少なくともわが三線の会としてははじめの参加だ。参加できて本当に楽しかった。エイサーの人や、三線のお師匠さんや、スタッフの人など、いろいろな人たちと知り合いになれたのもうれしい。いつもは音楽祭というとジャズやロックという中で、「完全アウェー状態」でやっているので、なんか始めて「ホーム」でやったという感じ。お客さんも沖縄好きが集まってくれて盛り上がりも良かった。各チーム(?)のカチャーシー合戦で、お客さんも何度踊ったかわからないだろう。でも、とにかく、沖縄料理に、泡盛、オリオンビールを飲んで気分よく帰っていただけたのでは。(スタッフの人たちは、これだけのイベントだと大変だろう。本当にお疲れ様でした。会のメンバーも泡盛飲み過ぎで、めちゃくちゃにはしゃぎ踊っていたのが若干名いたが…。まあ、おまつりということでお許し願おう。)わが会の演奏としては、その昔行く船を鐘を持って応援したという「しょんかに小」という踊りが一番かっこよく場所に映えていたような気がする。宮城県の海人たちの心にも響いたのでは。なんとなく場所にふさわしい演奏というのが本当に気持ちいい。また、来年も呼んでいただけるかな? 八重山には、他にも浜のまつりにふさわしい演目がいっぱいあるので、宮城の海に向けてもっともっと響かせたい。
2007年07月30日
コメント(0)
-
天気予想屋。
週末に屋外でのイベントがあるので、天気が気になっている。今週はずっと週間天気予報サイトを見ている。うちの三線の会には、絶対雨男か雨女がいるな…。今回も雨模様だ。週間天気予報を見ていて、最近多いパターンは、1週間前ぐらいは天気と言っていたのに、だんだん週末に近づくにつれて曇りになり、最後には雨になるパターン。最初から雨って言ってくれればあきらめもつくのに、この外れ方がものすごくむかつく。週間天気予報の精度はもっと上がらないものか。そもそも、降水確率がよく分からない。予報区内で一定の時間内に1mm以上の雨が降る確率らしいが、どうもその予報の信頼性のパーセンテージとごちゃごちゃになっているような気がする。そして、さらにむかつくのは、天気予報のサイトはいっぱいあるのに、みな同じ内容だということ。ひとつぐらい「うちはピーカンいち押しです!」みたいに言えないものか。そこで、やちまた道、こんな週間天気予報を提案する。月、降水確率10%(今日ぐらいちゃう?)、自信◎100%、鼻くそほじくっててもあたりますって。明日のことやもん。水、降水確率80%(なんか大荒れの予感)、自信△10%、いや~、この日は難しいわ~。なんか高気圧3つあるし、低気圧4つもあるし、分け分からん台風も出てくるし。外れても堪忍やで。土、降水確率20%(そこそこ)、自信○80%、これ結構自信あります。いけるんちゃいます。日、降水確率・0%(どんど晴れ!)、自信×0%、正直お手上げですわ。でも、運動会とかあるし、自分もゴルフあるし、晴れてほしいな~。信じる力があれがきっと晴れるんちゃいます!夏美もそう言ってるし。なんか、自分がわけわからんくなってきた。とにかく、なんとか今週は晴れてほしいな~。雨の神様、よろしくよろしくお願いいたしやす。
2007年07月27日
コメント(0)
-
コアニチドリ。
秋田にいたころ。今日はどこにドライブに行こうかと観光ブックを見ていて、鳥好きなやちまた道、「コアニチドリの里」と書かれているのに目がとまった。コアニチドリ。そんなチドリがいるんだな、と思って見ていると、そこには、花の写真しか写っていない。白くかすかに薄紅紫をさしたような、実に可憐な花だ。飛ぶ姿がチドリに似ているからついた名なのか。小阿仁という名はその時、実に可憐な名として記憶された。最近、上小阿仁村が全国的に有名になった。高レベル放射性廃棄物の最終処分場の誘致。財政再建のために村長がその検討に入るという。あの一帯が秋田杉に包まれた、まさにマタギとかがいたと思われる山深くに核処分施設…。なぜか、ピンと来ない。なんども迷子になりながら、観光マップを頼りに、あの辺りをドライブしたのを感慨深く想い出す。大きく強い力は、小さく弱いところを狙って、突如暴力のようにやってくるものだ。コアニチドリは逃げ出したくても、鳥のように飛んで逃げるわけにはいかない。
2007年07月26日
コメント(0)
-
しろうと藪医者道。
やちまた道、からだが弱い。ねんがら年中、どこかが痛い、どこかが調子悪い、と言っている。にも、かかわらず、病院が大の苦手ときている。となると、必然的に病院に行かなくても自分の病気を見極める能力がついた。(ほんとか?)やちまた道が最近発見した病気のポイントが2つあるので伝授したい。ひとつは、身体の不具合は、すべて「鬱血」からくる、ということ。(ほ、ほんとか?)東洋医学でいうところの「於血」。血の巡りが悪い状態だ。この鬱血状態のために、経絡の流れ、気の流れ、水の流れなどが悪くなり、それによって様々な症状があらわれる。したがって、身体中のすべての血の巡りやリンパの巡りや気の巡りをよくすることで、かなり症状は改善されるであろう。ポイントは「どこで巡りが悪くなっているか」、これを見極めることだ!?もうひとつは、病気は悪くなればなるほど、様々な症状があらわれ複雑に絡みあう、ということ。(ほんとうに、ほんとでしょうか?)いわゆる合併症的になる。病気の悪循環、悪のスパイラルだ。したがって、「なんか薬を飲んでも治りにくいな」、という時は、他に症状はないか、それを引き起こす他の原因はないか、を調べた方がいい。ひとつずつ絡んだ糸を解きほぐすように、いろんな原因をひとつずつ取り除き、治していくといい!?この2つを念頭において、健康に気を付ければかなりの病気が防げるはず、だと思われる、ような気がする。みなさん、健康にはくれぐれも気をつけてください。
2007年07月25日
コメント(0)
-
母性の社会。
すべての生命は、個体保存の本能と種族保存の本能を持つ。この本能が人間によって極端なまでに先鋭化され、しかも歪められ、幾多の残虐な犯罪を生んでいる。最近見たテレビで、めす猫が生まれたばかりのカルガモの雛を、自分の子どものようにいとおしく舐めているシーンが流れていた。ちょうどこのめす猫は、自分の子猫を失ったばかりだったという。このシーンを見て、猫には個体識別能力がないから、カルガモの雛と自分の子猫と勘違いした、という結論を持つ人もいるだろう。しかし、そうだろうか。子猫を失ったことにより高められた母性本能が、個体保存の本能や種族保存の本能を越えて、「弱いものへの憐憫と救済の感情」を生み出したのではないか。この感情のもとでは、そもそも個とか種とかという概念は、どんな意味を持つのだろうか。母性本能。自分の生命よりわが子の生命を優先しようとする本能。この「自己犠牲」というか「滅私」とも言える本能と個体保存の本能や種族保存の本能とはどうバランスを取ればいいのだろうか。異常なまでに個体保存の本能と種族保存の本能によって支えられている現代社会。この歪んだ社会の救世主となるのは、この「母性」という能力かも知れない。しかし、最近の人間はこの母性本能さえ歪められているような気もするが…。
2007年07月24日
コメント(0)
-
三線王子。
日曜日、朝。来週は朝からイベントのため、はじめての期日前投票に出向く。思っていた以上に普通に人が来ている。まあ、投票に行かないよりはいいことだろうが。この1票にどれだけの意味があるのだろう。いけないと思いながらも、その思いが沸いてくる。たかが1票。されど1票。チリも積もれば山となる。力のない1票も、束ねることができれば力のある票の山になる。ただ、いまその束ねることをできるのが、特定の政治団体だったり、マスコミの報道だったりするわけだ。投票する市民の中から束ねる運動が生まれてくれば、政治も変わるのかも知れない。夜。ソウル・フラワー・アコースティック・パルチザンを観に行く。アコースティックということで、ギターにピアノにアコーディオンというシンプルな構成。新曲も実にシンプルで骨太のメロディーライン。中川も年相応に曲の好みが変遷しているようで、同世代としてはなぜか感慨深いものがある。でも、ギターもいいけど、三線を持ったときの中川がいいね。自分でも冗談で「三線王子」と言っていたし。辺野古の阻止運動参加の折に作ったという「辺野古節」が良かった。やっぱり、社会的あるいは民衆的メッセージのあるのがソウル・フラワーという感じだ。パパになっても、あの「満月の夕べ」のような時代を見つめ、時代に訴える曲を作りつづけてほしいものだ。
2007年07月23日
コメント(0)
-
禁止、禁止、禁止。
広告の世界に使ってはいけない言葉が増えている。例えば、不動産広告における最上級表現。頂点・日本一・最上・最高・唯一無二・日本ではじめて、などなど。何を根拠にこの物件が最上と言えるのか、そんなおこがましいことはやってはいけない、というわけだ。まあ、このあたりはバブルの時代になんの根拠もない「おいしい言葉」にだまされてきた消費者にとっては大切な防衛手段ではある。しかし、この禁止のエリアがどんどん広がっているのだ。安全という言葉がだめだという。例えば、「このマンションの構造は安全です。」というのはだめな訳だ。安全神話の崩壊。何が安全か分からない時代、とにかく責任のとれないものなだめだという。まあ、100歩ゆずってこの辺はわかる。しかし、どうやら「安心」という言葉もだめらしいのだ。「安心」なんて心情の問題なんだからいいじゃないか、と思う。が、すべてクレームが付きそうなものはフタをしてしまえ的発想になっている。もう、物理的事実やスペックのみを伝えるしかなく、いわゆる独自の価値観を訴えるキャッチフレーズ的な広告表現できなくなるではないか。こうなってくるとどうせ広告できないのなら、逆に他社にはない価値観の創造なんてことをデベロッパー側がしなくなってしまうのではないだろうか、とも思ってしまう。トラブルや事故やキズを負うことを徹底的に排除する社会。子どもがけがをするから危険な遊具はなくす。個人情報保護のためか、画面に写っている一般人の顔をすべて消す。(取り巻くのっぺらぼうの大群は正直気持ち悪い。)…現代社会は、この大規模な去勢手術によって、創造力・生産力・繁殖力のすべてをなくするだろう。
2007年07月20日
コメント(0)
-
不条理の選択。
いまだに、自分の中でモヤモヤとしっくりこない映画がある。「ソフィーの選択」。メリル・ストリープ主演の悲劇のユダヤ人女性を描いた映画。第二次世界大戦、ユダヤ人女性ソフィーと2人の子供たちが、ナチスの強制収容所へ移送される。ナチスの軍医が、ソフィーに言う。「お前に選択の特権を与える。子供のうち一人を残してよい。どちらかを選べ。選べなければ、ふたりとも連れて行く」と。ソフィーは泣き叫び、選ぶことができない。「それじゃふたりともあっちへ」と軍医は部下に言う。そして、ついにソフィーは「この子をとって!あたしの女の子を連れていって!」と言ってしまう…。この選択の罪という十字架を背負い、ソフィーは後世を生きていくことになる。そして、最後に自らの死という選択を選ぶ。戦争。暴力。時代の悲劇は、どちらも選ぶことができないという「不条理の選択」をつきつける。この映画は、その不条理性を実によく描いていた。ただ、じゃ、どうすればいいのか、という気持ちもあって、この映画を思い出すと自分の中でちょっぴりすっきりしない気になる。出口のないというか、答えのない映画もある。それを教えてくれた映画ではある。この不条理な選択は、この不条理な世界の中で、ささやかな日常生活の中でも増えてきているのでないか。そして、その不条理に気づかず知らず知らずのうちに(責任を感じず)選択してしまってはいないだろうか。
2007年07月19日
コメント(0)
-
一期一会。
うちのカミさん、たまに天才的なきらめきで料理を創る。究極のありあわせ料理。そこにあったものを、そこにあった調味料で、そこにあった気分で創作する。はじめは「えっ」と思うが、それが意外においしかったりする。ただし、この自由奔放な自然児料理で困ったことがある。二度と同じ料理が出てこないことだ。「この前の料理作ってよ」と言っても「いちいち作り方覚えてないよ」というお答え。「えっ~!?」「だって料理は一期一会でしょ。」う~ん。一期一会の意味合いが違うような気がするが…。そう言えば最近、中島みゆきの「一期一会」が街でよく流れている。見たこともない月の下 見たこともない枝の下見たこともない軒の下 見たこともない酒を汲む人間好きになりたいために旅を続けてゆくのでしょう忘れないよ遠く離れても 短い日々も 浅い縁(えにし)も忘れないで私のことより あなたの笑顔を 忘れないで(2番の歌詞です。)心に沁みる歌詞。血の滲む魂の叫びのようなメロディ。さすがはずっと人生の裏通りを歩いてきたような、場末の飲み屋が似合う孤高の女吟遊詩人。ローラースケートやシンクロとの競演で日本全国に絢爛の大スペクタルショー見せつける同世代の某ポップス女王とは大違いだ。平間至という宮城県出身のカメラマンが「表現者は不幸でなくてはならない」と言っていた。なかなかいいお言葉。不幸が身体に染みついている中島みゆきだからこそ、この時代の不幸な魂たちを元気づけるような一期一会の唄を唄い続けられるのだと思う。
2007年07月18日
コメント(0)
-
夜明けのシュプレッヒコール。
夜明け、轟くような声で目が覚めた。「いまどきの洗剤は漂白剤を使っている!大人たちは、漂白剤を使い続けている!!」カミさんの寝言である。いや、寝言というより、拡声器を使ったシュプレッヒコールだ。ロックかパンクのような歌詞を発しつづけている。いい加減にしてくれよ、とばかりに揺り起こす。「あっ夢見てた」と、またスヤスヤ眠りに入っていった。とり残されたやちまた道は、もはや安眠の世界に戻ることができない。このロック主婦の環境意識はなかなか見上げたものだ。マイバッグはもちろん、コンビニから割り箸をもらってくるだけで怒られるし…。今、自然環境がおかしくなっている。誰もが、異常事態を感じているのではないか。「自然が怒って異常気象を起こしているんだ」「いや、なんとかこの状況を改善しようとして自然が一生懸命がんばっているんだ」自然が持っているのは、善意か、悪意か。どちらにしても、なにか、人間の後ろめたさというか、やましさみたいなものが、より自然の意志を強く感じさせているのではないか。自然の猛威というか、強い意志に圧倒される弱い人間の姿がそこにいる。もちろん、自然をすべて自分たちの思いままになる、という近代的な、人間主義的な発想はまちがっている。ただ、もっと、ささやかではあるが、強い意志を持って自然な心で自然と向き合うことが必要ではないか。自然の大脅威とかあおる前に、マイバッグとか、マイ箸とか、日常生活でできることからはじめていく必要があるのでは、とロック主婦の寝言から教えられた。
2007年07月17日
コメント(0)
-
泡盛の季節。
泡盛の季節だ。泡盛の週末だ。ビールや日本酒とは違い、泡盛や焼酎の良さは、好みやその時の気分でいろんなもので割ることができること。いろんな飲み方を楽しめるし、いろいろな土地の雰囲気や効能も味わえる。とくに泡盛は、南国だけにトロピカルに楽しむのが似合う。うっちん茶やさんぴん茶やゴーヤー茶、マンゴやシーカーサーなどで割れば、どこで飲んでいても、島気分になれる。健康に気をつけたいなら青汁や柿の葉茶などで割ることもできる。そして、なによりも日頃の鬱憤を忘れて幸せになりたいなら、泡盛は夢で割りましょう。(ソウルフラワーぱくり!)それでは、よい3連休を。あり乾杯!
2007年07月13日
コメント(0)
-
招福グッズ。
福がほしい。そう思うのは全世界共通らしい。世界各地に招福グッズらしきものがある。フランス。「ウサギの手」が幸運を呼ぶという。お守りがわりに「ウサギの手」をポケットに入れているとか。アメリカ生まれの福の神。ビリケン。女流美術家が奇怪な神の姿を夢見て造った像。アメリカ第27代大統領ウィリアム・ハワード・タフトの愛称がビリーだったことにちなんでいるという。ちょっぴりふとった愛嬌のある姿。足の裏をなでて願をかける。なぜか、大阪の新世界の名物にもなっている。サイパンのボージョボー人形。サイパンに生息するツル草の実で作られた男女ペアの人形。恋愛の守り神的存在。ヒモ状の手足の結び方でご利益が違うそう。日本にも招き猫、沖縄のシーサーなどがあるが、実は仙台にもある。「仙台四郎」。江戸末期仙台に生まれた実在の人物で、いつもニコニコして仙台の商店街を歩いていたらしい。そして寄る家や人々に福をもたらした。とにかく仙台では有名で、様々な仙台四郎グッズが売られている。しかし、この「仙台四郎」人気を脅かすものが生まれた。今、仙台でブームになっている「仙台幸子」。仙台駅前のロフトには専用のコーナーもできているとか。仙台在住の女性が、自分の母をモチーフに作ったもの。「仙台四郎」の二番煎じなのに、今では本家本元を追い抜く勢いで、グッズも大いに売れて儲かっているらしい。どうやら、招福グッズは、持っている人間よりも、創りたもうた創り主が一番福をいただいているよう。福をほしい方。いっそのこと新しいオリジナルの福の神を作られてはいかがだろう。
2007年07月12日
コメント(0)
-
どんど晴れ。
やちまた道、朝の出勤は8時30分。東京にいたときは、正味1時間50分通勤というものをしていたので、仙台正味20分通勤は実に快適に感じる。首都圏の人々に申し訳ない気もするが。8時30分出勤ということで、出勤前にNHKのテレビ小説「どんど晴れ」などを見てしまっている。岩手が舞台ということもあり、けっこうハマッている。ほんものの岩手人のカミさんはなんかあきれ顔だが。(でも、最近NHK頑張っていると思うなぁ。サラリーマンNEOも面白いし…)あき竹城(山形)とか、金八先生のおまわりさん役(青森)とか、喫茶店のマスター(青森)など、脇役にしっかり東北の役者を使っている。岩手なまりを知っている人間には、東北なまりの中でも若干の違いを感じてしまうが…。なまりという意味では、大女将が意外と頑張っているのかな。やちまた道的人相学からいくと、南部鉄器職人の長門裕之と、長男の東幹久が、目が出ていたり、ずんぐりむっくりだったりするところが、岩手っぽいと思う。もしかしたら、そのあたりも考えてキャスティングしているのかな。演技でいいなと思うのは、板前役の蟹江一平。とても、間のいいクレバーな演技をしているように思う。ホームページを見たら、「『謙虚に、大胆に…感謝。』というのが僕のテーマです。謙虚に現場に入って、大胆に芝居をして、スタッフや共演者のみなさんに感謝。そしてお茶の間のみなさんに『見ていただいてありがとうございます』という感謝」なんて言うインタビューが載っていた。『謙虚に、大胆に…感謝。』か。なかなか、いい言葉ではないか。芸能一般に通じる言葉だと思うので、ちゃっかりもらって置こう。そして、主役の比嘉愛美。沖縄人らしいピュアな感じがいい。岩手を舞台にしたドラマに沖縄人を持ってくるとは、センスがいいぞ、どんど晴れ!
2007年07月11日
コメント(0)
-
忘れられたアジアの風景。
藤原新也がある本で、日本のどこかの小さな町の古いフィルムを見てあることに気づき、驚きを感じたと書いていた。その町にあった風景。それは、彼がいろいろ旅で出逢ってきたまさに「アジアの風景」があったという。この話しを読んで思い出したことがある。カミさんの生まれ故郷、岩手は久慈市。お盆などでたまに行くことがあるが、その時家にあった久慈市の古い写真を見て驚いた。なんとそこにいる人々は、まさに東南アジアの海洋民族といういでたちなのだ。どうみてもいわゆる日本人というかっこうではない。こんな本州の北の外れの町に、こんな南方系の顔がち、体型をしている人たちがいたんだと、新鮮な驚きを覚えた。それ以来、岩手と東南アジアとはぜったいにつながっていると、やちまた道は提唱している。宮沢賢治は、労働と芸能の融合を夢見た。すべての農業労働を冷く透明な解析によってその藍いろの影といっしょに舞踊の範囲にまで高めよ ー「生徒諸君に寄せる」このように、「農業舞踊」というような形態を人間の活動の理想として掲げた。そして、そのこの世にその理想を実現している例として、バリの芸能をあげたという。宮沢賢治とバリというつながりは意外だ。やちまた道、この思想は頭によって考えられたものではなく、岩手県人・宮沢賢治のアジア的身体・アジア的DNAから自然に発酵してきた思想だと思っている。(やちまた道的には、八重山の芸能も賢治の理想に近いと思うのだが。八重山の芸能も見てもらいたかった…。)日本がアジアだったという当たり前の事実。今の日本人が忘れてしまったアジア的なものを、もっと見直してもいいのではと、思う。
2007年07月10日
コメント(0)
-
慰問。
日曜日。郊外にある高齢者向け施設に三線の演奏で慰問に行く。ずっとお年寄りを前にしたボランティア演奏を続けているが、今回の施設は、特に元気なお年寄りも多く、いつも以上に盛り上がることができた。「新安里屋ユンタ」や「十九の春」あたりの定番ものは、演奏する側よりも、日本全国で売れた当時を知っているわけなので、みんな「なつかしい~」という感じで聞いてくれていた。当時のことを聞けてこちらも勉強になる。身体は自由自在に動くという感じではないけれど、一生懸命唄ってくれた。演奏の方も自然と力が入った。今回の新しいチャレンジは童謡「ふるさと」を入れたこと。ビギンとかBoomはすでに封印しているので、皆さんわかりやすい唄となると童謡かな、ということでやってみた。これが一番皆さん唄ってくれた。涙を浮かべながら唄っている人もいる。三線のやさしい調べが、郷愁を誘うのかな。いろいろな人の脳裏に、いろんなふるさとの情景が映し出されたことだろう。一番拍手も大きかった。カチャーシーも元気に踊ってくれた。「六調」をどこかで聞いたことがある、と言っていた人がいた。いろんな祝い唄に出てくる「若松様」。もしかしたら、「六調」と同じような歌詞で同じようなメロディで唄われたものがあったのかも知れないない。唄を必要とする場所。唄を必要とする人。そして必要とされる唄。演奏する側にとって、こんな場で演奏できることほど幸せなことはないな、と思った。
2007年07月09日
コメント(2)
-
この夏着たいもの。
この前、カミさんにバーゲンに連れて行かれた。やちまた道、あまり着る服に興味がない。だから洋服屋に長居するのがつらい。なかなか買い物が終わらないカミさんを待ちながら、ふと目にとまったものがある。作務衣・甚平。和服ブームということもあるのか、かなりの店で作務衣・甚平コーナーを出している。やはり、そこは日本人、ずっと和的なものを一度は着てみたかった。ゆったりとして、涼しそうだし、年齢的にも似合う年頃(?)になってきたような。なんか、興味が出てきて、いろいろ、眺めてみる。ふと疑問が?そもそも、作務衣と甚平は何が違うんだ?一見構造的には同じように見えるが、良く見ると作務衣は、長袖、長ズボン(?)という感じ。手足、手首を絞れる紐がついている。神社仏閣で掃除などで使用されたものらしい。作業着だけに動きやすさにも考慮されているよう。一方の甚平は、庶民の服で半袖の筒袖に、半ズボン。夏向きという感じで、薄地のしじら織が多いようだ。となると、冷え性のやちまた道、なんとなく作務衣がいいような気がしてきた。作務衣か。響きもいいね~。家の中はもちろん、外に出る時もいいような気がする。イベントでも使えそうだし。よし、ことしの夏は作務衣にしよう。
2007年07月06日
コメント(2)
-
まくら道。
やちまた道、いま、枕にはまっている。というか、枕に取り憑かれている。ここ何年間、枕があわなくて、それが気になって眠れない。気になるとどうしてもアレコレ試したくなり、さらに眠れなくなるという悪循環になる。最初は素材にこだわっていろいろと試してみた。羽根・シルクの綿・ポリエステル綿・竹・ひのき・い草・そば殻・ビーズ・パイプなどなど。どれも最初はいいなと思っても、一週間もすると「だめだわ~」ということになる。やっぱり高さかな?と思い、座布団などで高さを変えて試してみたがこれも効果がなかった。いろいろ試しているうちに、よく言われるように床面と頸部の間に隙間があると、部分的に強い反発(圧迫)受け寝苦しいことが分かってきた。枕の真ん中がへこんでいるものを使ってみる。これも一瞬いい感じだが、頭がすっぽり穴にはまりすぎで、かえって寝返りが打ちにくい。難しいのは、どんな状態でも頭から頸椎にかけての湾曲した形状を完璧にフィットさせることだ。隙間の形状は非常に複雑で、少しでも頭の位置や角度、方向が変われば変わってしまう。仰向けの状態と横を向いた状態が一緒の湾曲のわけがない。さらにやっかいなことに、やちまた道、頭が絶壁で、さらに右に傾いている。どうしても普通にしていると右に傾いてしまう。左向きに寝返りを打つと無理な力が首にかかり、朝起きると、顔の左半分がつったようになっていたり、ひどいときは偏頭痛になったりする。さて、どうしたものか。頭の形に左右されないために、首のところが高くなった逆傾斜型の低反発枕がいいと思って試してみた。寝返りも打ちやすく全体にフィットしているように思えたが、実際には単に素材が圧縮されているだけで、その反発力は強く、自分の頭の重さと同じ力で下方から突き上げられている状態。特に頸椎部分が高くなっているので、首が圧迫されたようになり、苦しくなって目が覚めてしまう。これではダメだと、頸椎部分に注目してみた。首は丸太のように円柱になっている。だから盛り上がった部分に、円柱にそった窪みが必要だ。ここまでわかって、首の部分に半円柱の窪みをつくってみた。なんとなくいい感じだ。しかし、寝返りを打たずこのフィット感をずっと保とうとして、かえって眠れなくなってしまった…。このあたりの問題は、ウォーター枕や格子状ジェル枕では解決されているのだろうか。いつか試してみたいものだ。このように、まくら道は厳しい。簡単に極められるものではない。これからも、もっと精進していきたい。…と真夜中に馬鹿なことをやっている隣で、カミさんは何年も前に買った普通の枕でグーグー気持ちよく眠っている。
2007年07月05日
コメント(0)
-
訴えるジュゴン。
一昨日だったか、ニュースでジュゴンを見た。米軍普天間飛行場の名護市辺野古沖への移転。これによって、美しい海岸、珊瑚礁、海草藻場などが破壊される。西太平洋の北限とされるジュゴンの餌場を奪い、そして、絶滅に追いやる可能性が高いという。辺野古では漁民や市民団体が基地の移転反対、調査ボーリングの中止を求めて活動をしている。テレビには、紺碧の海に、あまりにも美しい、まさに人魚と言われるのがうなずけるような2匹のジュゴンが映されていた。今は国の天然記念物になっているジュゴン。昔から沖縄、とくに八重山地方ではジュゴンと深い関わりの中で生活してきたらしい。新城島では琉球王朝への人頭税として米ではなく、ジュゴンを納めた。(当時の八重山の人々は収穫物のほとんどを税として納めなければならぬほどで「生きた納税機械」と言われていたから、かなり過酷なジュゴン捕獲を強いられたと思われる。)ジュゴンは「不老長寿の霊薬」として重宝され、琉球国王の食膳に出たり、幕府や中国にも献上されたという。今、島にはジュゴンの頭蓋骨を祀った御獄がある。豊漁を祈願する御嶽。たくさん祀られていたが、学術研究の名のもとに沖縄国際海洋博覧会の時にいくつか持って行かれたらしい。この御獄には今も誰も近づくことができない。ジュゴンの漁の様子を唄った唄がある。「ザンとる歌」(「まーじゃみやらび」)。「ザン」とはジュゴンのことだ。島の「節祭」のときに円になり唄われるという。ぜひ、島で聞いてみたい唄だ。
2007年07月04日
コメント(0)
-
ひとりの死 VS 一般論としての死。
死はひとりひとりのものだ。しかし、人はその固有の死を直視できないとき、死を一般化する。誰しもに訪れる、別に特別なものでもない、でも誰のものでもない死。それによって、死の持つ本質的な部分を掴み損ねることになる。顔のない死は、もはや死ではない。光市母子殺害事件。弁護士の「作戦」変更で、一転殺す気がなかったという加害者。死刑反対論者で有名な弁護士は、この事件はでっちあげられたものだ、という。真実がどこにあるのか。それは殺された人と殺した人にしかわからないだろう。また、死刑反対というのも、世の中えん罪があるという事実を考えれば、当然の動きと言える。ただ、あくまで第三者としてテレビのインタビューを見ていて、奥さんと子どもを殺された本村さんと、その有名弁護士の「言葉の真摯さ」の違いを感じて、どうしようもなかった。この弁護士はこの加害者の言うことを「ほんとうに信じて」、その加害者の死を「ほんとうに救いたい」と思って弁護しているのだろうか。それとも、一般論として、死刑を反対しているのだろうか。それは、きっと、まちがいなく、後者だろう。ひとりの顔のある死に向かっていない人間の言葉がいかに「うすっぺら」に聞こえることか。「ひとりの妻」を殺され、「ひとりの子ども」を殺された本村さんの「言葉」に叶うわけがないと思った。
2007年07月03日
コメント(0)
-
音楽で国際交流。
週末、市民センター主催の国際交流イベントに参加した。ネパールやインドネシアなどの民俗音楽とともに、日本の琴、尺八、三味線、三線などの演奏を絡めるというもの。どこの国も女性の踊りが目をひいていたよう。わが三線サークルも、踊りができれば良かったのだが、参加メンバーの関係で唄中心。踊りの競演をお見せできなかったがちょっぴり残念だった。今回のイベントでの収穫としては、アカペラで唄う楽曲が、意外にアジアっぽくって場になじんでいたことを教えられたこと。三線とか三味線は、唄や踊りに付随して発達してきた楽器だが、もっとも原初的な「声」という楽器は普遍的で世界共通のものだ、という当たり前のことを認識した。八重山民謡で言うところの「ゆんた(労働歌)」はもともとアカペラだった(仕事をしながら唄うわけだから当然!)。音楽で労働の苦しみを少しでも和らげようとした。これが音楽の原点のひとつであることはまちがいない。この「ゆんた(労働歌)」のアカペラをもっとレパートーリーとして増やしたいと思った。この「ゆんた」、仙台の「大漁唄い込み」なんかともうまくなじんでくれるので東北のお客さんにも受けがいいようにも思う。やっぱ、まずは「唄」だな~と認識した週末だった。
2007年07月02日
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- UNIQLO感謝祭、開催中☆
- (2025-11-23 09:50:05)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 説教のプロになることです。
- (2025-11-23 07:30:51)
-