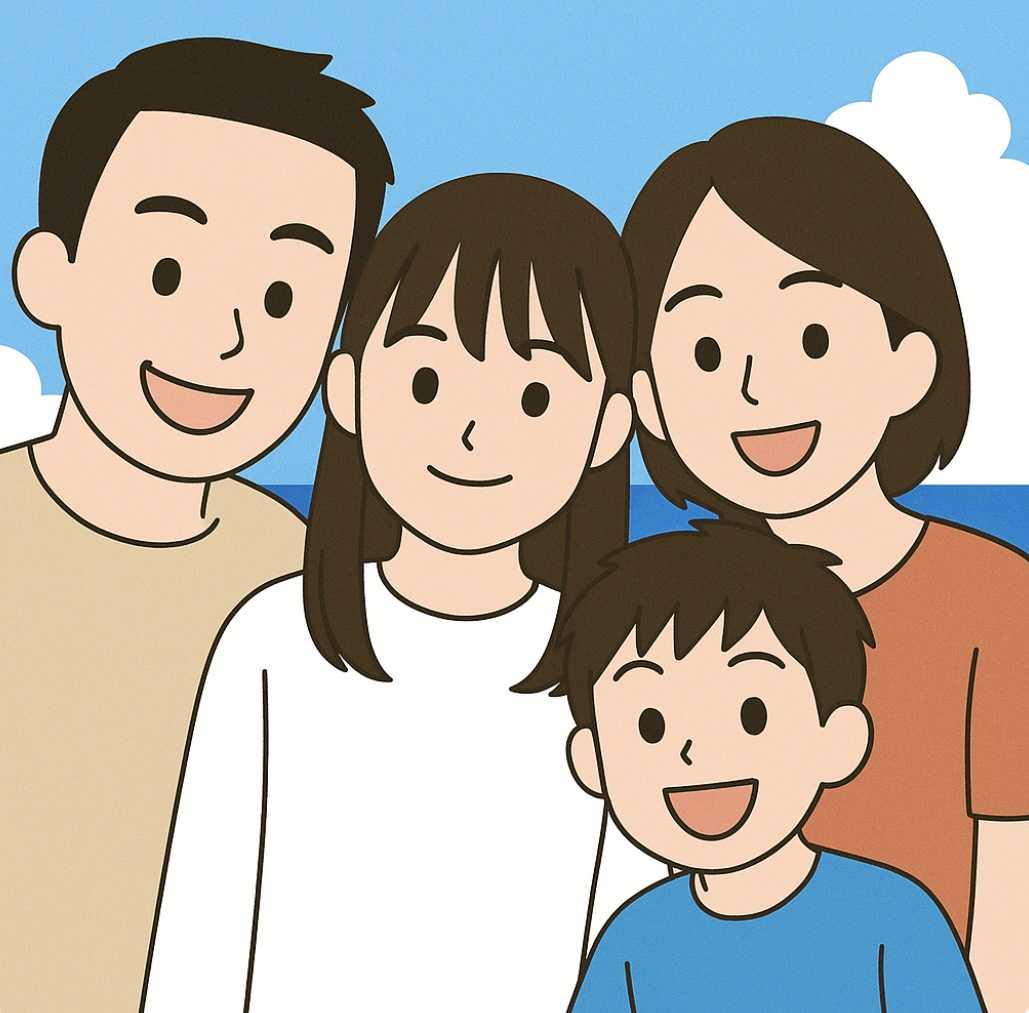PR
X
カレンダー
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 小学生の勉強(1398)
カテゴリ: こどもの勉強
◎ 幕府が揺らぎ始める背景
- 江戸時代の後半、 人口増加・飢饉・財政難 などで幕府の支配が安定しなくなっていきます。
- 特に米の収穫が天候に左右されやすく、幕府の収入源である 年貢 が不足。
- そこで歴代将軍の時代に、幕府を立て直そうとする「 改革 」が行われました。
◎ 享保の改革(徳川吉宗・1716〜1745)
- 第 8 代将軍 徳川吉宗(米将軍) による改革。
- 目安箱 を設置し、庶民の意見を取り入れる。
- 上米の制 (大名に米を納めさせる代わりに参勤交代を緩めた)。
- 倹約令 で質素倹約をすすめる。
- 公事方御定書
を作り、裁判の基準を整えた。
👉 成功と評価されるが、庶民には負担が大きい面もあった。
◎ 寛政の改革(松平定信・1787〜1793)
- 将軍 家斉 のとき、老中 松平定信 が実施。
- 倹約令 で贅沢を禁止。米を備蓄する 囲米の制 を導入。
- 朱子学以外の学問禁止(寛政異学の禁)。
- 農村復興をめざしたが、きびしい政策で評判はイマイチ。
👉 「きびしすぎて人心離反」とよくまとめられる改革。
◎ 天保の改革(水野忠邦・1841〜1843)
- 将軍家慶のとき、老中 水野忠邦が 実施。
- 株仲間の解散 (商人の組合を禁止)。物価を下げようとしたが逆効果。
- 人返しの法 (江戸に出てきた農民を村に戻す)。
- 上知令
(大名・旗本の領地を幕府に取り上げる)を出したが失敗。
👉 結果的にうまくいかず、改革は短期間で終了。
◎ 一揆・打ちこわしの増加
- 18世紀以降、農民や町人の不満が高まり、 百姓一揆 や 打ちこわし が各地で発生。
- 代表例: 大塩平八郎の乱 ( 1837年 )。元大阪奉行所の役人が、飢饉に苦しむ人々を救うために反乱を起こす。
- 幕府の統制力が弱まり、 幕末へと続く不安定さ が増していった。
まとめ
- 幕府の三大改革:
- 享保の改革 ( 徳川吉宗 ) → 目安箱・公事方御定書・倹約令。
- 寛政の改革 ( 松平定信 ) → 倹約令・囲米・寛政異学の禁。
- 天保の改革 ( 水野忠邦 ) → 株仲間解散・人返しの法・上知令。
- 18世紀以降:一揆や打ちこわし増加。** 大塩平八郎の乱(1837年) **も重要。
- 幕府は財政難や農村の疲弊を立て直せず、力を失っていった。
テストに出そうなポイント(一問一答)
- Q:享保の改革を行った将軍は? → 徳川吉宗
- Q:庶民の意見を取り入れるために設置されたものは? → 目安箱
- Q:寛政の改革で他の学問を禁止した政策は? → 寛政異学の禁
- Q:天保の改革で解散させられた商人の組合は? → 株仲間
- Q:1837年、大阪で乱を起こしたのは誰? → 大塩平八郎
- Q:三大改革をすべて答えよ → 享保・寛政・天保
これで「江戸幕府シリーズ(全5回)」は完結です🎉
👉 ひなじさ流まとめ:
江戸幕府は三大改革で立て直しを試みたけれど、成功しきれずに力を失っていきました。
「安定 → 栄え → 揺らぎ → 幕末」へと流れをつかむと、歴史が一気に頭に入ります📚
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[こどもの勉強] カテゴリの最新記事
-
【小6社会】江戸幕府④|江戸の町と文化②… 2025.10.07
-
【小6社会】江戸幕府③|江戸の町と文化①… 2025.10.06
-
【小6社会】江戸幕府②鎖国 2025.10.03
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.