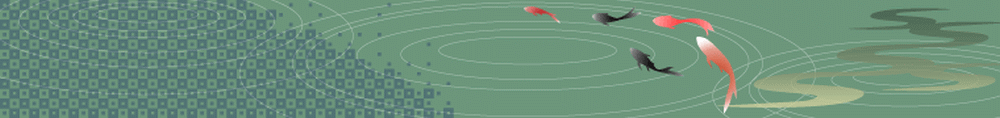カテゴリ: 身辺雑記
最近読んだ本で面白かったものを紹介。日本語の本に限ってある。
1・自壊する帝国

佐藤優という人は一時ずいぶんマスコミに登場していたので知っていたが、この人の書いたものは初めて読んだ。しかしまあすげー面白いじゃないですか。翻訳家の 米原万里 (故人)とか元NHKの手嶋龍一の本を初めて読んだときの感激に似ている。そういえば手嶋氏と佐藤氏は書く内容も似ているが。僕は陰謀論は大嫌いだが、こうした確かな裏付けのある国際情勢ものは大好きである。
ムネオ疑惑でこの人が左遷されたとき「ムネオはどうでもいいがこの人はもったいない」という感想を僕はブログ(いまは無きライコス日記)に書いた。しかしそのおかげでこうしてこの人の書くものが読めるのだが、この人のこだわる「国家」である日本にとっていいことなのか悪いことなのか。
書かれていることは「ふむふむ」と頷くことばかりである。後輩にやはり外務省で専門官になった人がいるが、僕には語学力や筆力があってもとても務まりそうにないやと思うことしきりである。僕はものぐさで人付き合いが億劫だし(酒は好きだが)、こう言ってはなんだが人が好いのでうっかり騙されやすい。ソ連共産党に限らず、官僚(キャリア組)の世界というのは誰が言ったか伏魔殿のようなところだと思う。
佐藤氏はそうした世界で生きてきた人である。その書くことは傾聴に値し、全国民必読ではないかと思うくらいなのだが、そうした情報操作がなされる世界で生きてきた癖で、彼自身の書くものが情報操作の一環なんてことはないんだろうね?
2.ノモンハンの夏

この本はヨーロッパで第二次世界大戦が勃発するのと同時期(1939年)に発生した、日本とソ連(正確にはその保護国である満州国とモンゴル)国境での武力衝突と、その政治・外交的背景を描いている。暴走する辻政信少佐ら日本軍の参謀将校、大戦を前に互いに疑心暗鬼の独裁者スターリンとヒトラー、ソ連軍の戦車に火炎瓶一本で立ち向かわされる日本兵の苦闘、無力な日本の政治、反英・親独に熱狂する日本国民・・・などなどが、時に筆者自身の義憤のこもった筆致で描かれる。半藤氏は文芸春秋の編集者だった当時に辻政信(なんと戦犯としての訴追を遁れたばかりか、戦後国会議員にまでなっている)に会っていたそうだ。へえ。
この当時のソ連もドイツも独裁国家で、責任(権力)が一か所に集まりすぎていた。対する日本はよく「軍国ファシズム」などといわれるものの、最前線で敢闘した軍人たちが敗戦の責任を負わされて更迭され自決を強いられる一方で、本当の責任者(権力者)が責任を取らされない、不思議な国だった。無責任体制という点では奇しくも上に挙げた佐藤氏が描く末期のソ連共産党に似ているかもしれない。今の日本は大丈夫なんでしょうね??
惨めに敗北した日本のダメっぷりを描く点では五味川純平「ノモンハン」と共通するが、より大局的な観点から描かれている。さらに、五味川版の頃には公開されていなかったソ連側の資料が現在はあるので、独裁者による粛清におののきながら戦うソ連側にも目は向けられていて(死傷者の数ではソ連軍のほうが甚大だった)、日本に限らず息の詰まる時代だったことが想像できる。
日独防共協定を結んでいた日本はドイツにあっさり裏切られ、ノモンハンでの戦いの最中に独ソ不可侵条約を結ばれてしまう。その二年後に日本はソ連と不可侵条約を結ぶが、その直後にドイツはソ連との条約を無視してソ連に侵攻する。挙句の果てに、1945年にソ連は日本との不可侵条約を破って侵攻し、日本人多数が犠牲になった。ドイツやソ連が悪辣すぎるとはいえ、日本外交は何をやっていたのだろうか。いや、今はどうなんだろう。
最後の「人は歴史から学ばないということを痛感させられる」という言葉が重い。
少々気になったのはドイツに関する記述で、駐日ドイツ大使の姓が「オットー」になっていたり(Ottだから最後の音は伸ばさないと思う)、マンシュタイン、ボック、ハルダーらの将軍の肩書が元帥になっていたり(前二者はノモンハンの翌1940年に元帥になったが、ヒトラー暗殺計画に加わったハルダーは元帥になっていない)などである。まあ些細なことです。
3.琉球の王権とグスク 安里進

これはまあ僕の専門に近いかな。巨大グスク(城)や浦添ようどれ(王墓)の発掘調査・整備を手がかりに、考古資料を使いながら沖縄における国家形成・王権の発達を探った実証的な研究が、コンパクトにまとめられている。お買い得。
「おもろさうし」を研究した伊波普猷以来、琉球を統一したのは15世紀初頭の尚巴志で、それ以前は島内各地に豪族(按司)が戦国時代さながらに割拠していたというのが通説になっていたが、考古学調査を手がかりに、それ以前の13世紀には全島の統一的な王権が成立していたのではないかとする。しかもその背後には躍動する大陸(中国や朝鮮半島)との交易があるという。しいて日本の国家形成論(日本に統一的な国家が成立した時期をめぐり、「七・五・三論争」と呼ばれる)で例えるなら、3世紀に国家形成がなされたというようなものか。
島という限られた空間の中での国家形成モデルとその分析手法は、対象とする時代も地域も違うとはいえ、僕にもとても参考になる。しかも琉球王の遺骨を納めた石櫃を飾る彫刻の文様がイスラム起源だとは、なんとも刺激的ではないか。やはり13世紀は面白い。
沖縄行きたい。

これもまあ専門に近いと言えば近いが、研究書ではない。史書を基にした物語である。
しかしただの史書を読むのとは違い、登場人物が生き生きと描かれている、今日的な歴史叙述からすれば学問的ではないのかもしれないが、逆に人間の物語としての歴史の叙述としてははるかに面白いし、ある種の真実を衝いているのではないだろうか。この本を読んでいると、人間の行動に感情がナマなむき出しの時代という印象を受ける。時代性というものか。
メロヴィング朝(5世紀末~8世紀半ば)というのは現在のベルギーからフランス北部辺りを本拠地とした、初期中世の王朝である。ローマ帝国はよそから来た征服者であるから、フランスの地に成立した最初の地生えの国家であるといえ、この本が書かれた当時、つまり国民国家を目指していた当時(19世紀)のフランスでは一時もてはやされた。しかし困ったことに、メロヴィング家の起源はゲルマン系のフランク族であり、むしろ隣国のドイツに縁がある。困ったフランス人(ナポレオン3世)は、代わりにフランス地元の太祖・英雄として、ローマ人に抵抗したケルト(ガリア)人ウェルキンゲトリクスを持ち上げるようにのだが、それはまた別の話。
メロヴィング朝は日本でいえば大和朝廷(王権)の時代である。どちらも国家形成の時代であるといえる。メロヴィング朝がキリスト教を受け入れたのと同様、大和朝廷は仏教を国の礎にしようとした。メロヴィング朝がビザンツ帝国(さらにはその向こうのイスラム文明)を意識せざるを得なかったのと同様、日本は中国文明の影響下にあった。ユーラシアの東西両端に成立した国家であるこの両者を比較研究して、何か面白いことがいえないかと以前から企んでいるのだが、まだ果たせずにいる。
・・・・・・・
1・自壊する帝国

佐藤優という人は一時ずいぶんマスコミに登場していたので知っていたが、この人の書いたものは初めて読んだ。しかしまあすげー面白いじゃないですか。翻訳家の 米原万里 (故人)とか元NHKの手嶋龍一の本を初めて読んだときの感激に似ている。そういえば手嶋氏と佐藤氏は書く内容も似ているが。僕は陰謀論は大嫌いだが、こうした確かな裏付けのある国際情勢ものは大好きである。
ムネオ疑惑でこの人が左遷されたとき「ムネオはどうでもいいがこの人はもったいない」という感想を僕はブログ(いまは無きライコス日記)に書いた。しかしそのおかげでこうしてこの人の書くものが読めるのだが、この人のこだわる「国家」である日本にとっていいことなのか悪いことなのか。
書かれていることは「ふむふむ」と頷くことばかりである。後輩にやはり外務省で専門官になった人がいるが、僕には語学力や筆力があってもとても務まりそうにないやと思うことしきりである。僕はものぐさで人付き合いが億劫だし(酒は好きだが)、こう言ってはなんだが人が好いのでうっかり騙されやすい。ソ連共産党に限らず、官僚(キャリア組)の世界というのは誰が言ったか伏魔殿のようなところだと思う。
佐藤氏はそうした世界で生きてきた人である。その書くことは傾聴に値し、全国民必読ではないかと思うくらいなのだが、そうした情報操作がなされる世界で生きてきた癖で、彼自身の書くものが情報操作の一環なんてことはないんだろうね?
2.ノモンハンの夏

この本はヨーロッパで第二次世界大戦が勃発するのと同時期(1939年)に発生した、日本とソ連(正確にはその保護国である満州国とモンゴル)国境での武力衝突と、その政治・外交的背景を描いている。暴走する辻政信少佐ら日本軍の参謀将校、大戦を前に互いに疑心暗鬼の独裁者スターリンとヒトラー、ソ連軍の戦車に火炎瓶一本で立ち向かわされる日本兵の苦闘、無力な日本の政治、反英・親独に熱狂する日本国民・・・などなどが、時に筆者自身の義憤のこもった筆致で描かれる。半藤氏は文芸春秋の編集者だった当時に辻政信(なんと戦犯としての訴追を遁れたばかりか、戦後国会議員にまでなっている)に会っていたそうだ。へえ。
この当時のソ連もドイツも独裁国家で、責任(権力)が一か所に集まりすぎていた。対する日本はよく「軍国ファシズム」などといわれるものの、最前線で敢闘した軍人たちが敗戦の責任を負わされて更迭され自決を強いられる一方で、本当の責任者(権力者)が責任を取らされない、不思議な国だった。無責任体制という点では奇しくも上に挙げた佐藤氏が描く末期のソ連共産党に似ているかもしれない。今の日本は大丈夫なんでしょうね??
惨めに敗北した日本のダメっぷりを描く点では五味川純平「ノモンハン」と共通するが、より大局的な観点から描かれている。さらに、五味川版の頃には公開されていなかったソ連側の資料が現在はあるので、独裁者による粛清におののきながら戦うソ連側にも目は向けられていて(死傷者の数ではソ連軍のほうが甚大だった)、日本に限らず息の詰まる時代だったことが想像できる。
日独防共協定を結んでいた日本はドイツにあっさり裏切られ、ノモンハンでの戦いの最中に独ソ不可侵条約を結ばれてしまう。その二年後に日本はソ連と不可侵条約を結ぶが、その直後にドイツはソ連との条約を無視してソ連に侵攻する。挙句の果てに、1945年にソ連は日本との不可侵条約を破って侵攻し、日本人多数が犠牲になった。ドイツやソ連が悪辣すぎるとはいえ、日本外交は何をやっていたのだろうか。いや、今はどうなんだろう。
最後の「人は歴史から学ばないということを痛感させられる」という言葉が重い。
少々気になったのはドイツに関する記述で、駐日ドイツ大使の姓が「オットー」になっていたり(Ottだから最後の音は伸ばさないと思う)、マンシュタイン、ボック、ハルダーらの将軍の肩書が元帥になっていたり(前二者はノモンハンの翌1940年に元帥になったが、ヒトラー暗殺計画に加わったハルダーは元帥になっていない)などである。まあ些細なことです。
3.琉球の王権とグスク 安里進

これはまあ僕の専門に近いかな。巨大グスク(城)や浦添ようどれ(王墓)の発掘調査・整備を手がかりに、考古資料を使いながら沖縄における国家形成・王権の発達を探った実証的な研究が、コンパクトにまとめられている。お買い得。
「おもろさうし」を研究した伊波普猷以来、琉球を統一したのは15世紀初頭の尚巴志で、それ以前は島内各地に豪族(按司)が戦国時代さながらに割拠していたというのが通説になっていたが、考古学調査を手がかりに、それ以前の13世紀には全島の統一的な王権が成立していたのではないかとする。しかもその背後には躍動する大陸(中国や朝鮮半島)との交易があるという。しいて日本の国家形成論(日本に統一的な国家が成立した時期をめぐり、「七・五・三論争」と呼ばれる)で例えるなら、3世紀に国家形成がなされたというようなものか。
島という限られた空間の中での国家形成モデルとその分析手法は、対象とする時代も地域も違うとはいえ、僕にもとても参考になる。しかも琉球王の遺骨を納めた石櫃を飾る彫刻の文様がイスラム起源だとは、なんとも刺激的ではないか。やはり13世紀は面白い。
沖縄行きたい。

これもまあ専門に近いと言えば近いが、研究書ではない。史書を基にした物語である。
しかしただの史書を読むのとは違い、登場人物が生き生きと描かれている、今日的な歴史叙述からすれば学問的ではないのかもしれないが、逆に人間の物語としての歴史の叙述としてははるかに面白いし、ある種の真実を衝いているのではないだろうか。この本を読んでいると、人間の行動に感情がナマなむき出しの時代という印象を受ける。時代性というものか。
メロヴィング朝(5世紀末~8世紀半ば)というのは現在のベルギーからフランス北部辺りを本拠地とした、初期中世の王朝である。ローマ帝国はよそから来た征服者であるから、フランスの地に成立した最初の地生えの国家であるといえ、この本が書かれた当時、つまり国民国家を目指していた当時(19世紀)のフランスでは一時もてはやされた。しかし困ったことに、メロヴィング家の起源はゲルマン系のフランク族であり、むしろ隣国のドイツに縁がある。困ったフランス人(ナポレオン3世)は、代わりにフランス地元の太祖・英雄として、ローマ人に抵抗したケルト(ガリア)人ウェルキンゲトリクスを持ち上げるようにのだが、それはまた別の話。
メロヴィング朝は日本でいえば大和朝廷(王権)の時代である。どちらも国家形成の時代であるといえる。メロヴィング朝がキリスト教を受け入れたのと同様、大和朝廷は仏教を国の礎にしようとした。メロヴィング朝がビザンツ帝国(さらにはその向こうのイスラム文明)を意識せざるを得なかったのと同様、日本は中国文明の影響下にあった。ユーラシアの東西両端に成立した国家であるこの両者を比較研究して、何か面白いことがいえないかと以前から企んでいるのだが、まだ果たせずにいる。
・・・・・・・
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
フリーページ
Vortrag 18.6.2003

Einfuehrung

Yayoi-Zeit

3/4 Jhdt. n. Chr.

5/6. Jhdt. n.Chr.

7. Jhdt. n. Chr.

日本語版
過去の日記

考古学・歴史日記03年

考古学・歴史日記02年後半

考古学・歴史日記02年中頃

考古学・歴史日記02年前半

考古学・歴史日記01年
各国史

EU-25/2004(南欧)

EU-25/2004(中欧)

EU-25/2004(東欧)

EFTA諸国

ヨーロッパのミニ国家

EU加盟候補国

西アジア

アメリカ史(上) 建国

アメリカ史(中) 大国

アメリカ史(下) 超大国

カフカス諸国

バルカン半島(非EU)

EU加盟国(北欧)

スペイン史(1) 前近代

スペイン史(2) 近現代

EU-27/2007

中央アジア
ヘロドトス「歴史」を読む

その2

その3
「真田太平記」(池…
 New!
七詩さん
New!
七詩さん
宗教 葬式 友人と… New! alex99さん
分かるかなぁ分かん… シャルドネと呼ばれた三浦十右衛門さん
絨毯屋へようこそ … mihriさん
韓国ソウル!文家の掟 shaquillさん
 New!
七詩さん
New!
七詩さん宗教 葬式 友人と… New! alex99さん
分かるかなぁ分かん… シャルドネと呼ばれた三浦十右衛門さん
絨毯屋へようこそ … mihriさん
韓国ソウル!文家の掟 shaquillさん
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.