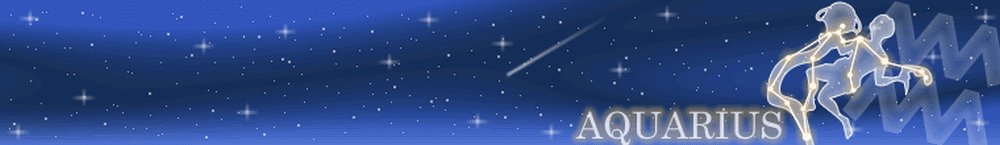PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
クリニックの過当競…
New!
七詩さん
みすまだかお とは… 目玉おやじさん
ワイルドキャットの… f4ffmさん
私の故郷は 「ふく… おばかんのさん
SALT OF THE EARTH slash555さん
「きのうの常識はき… santaro-さん
☆Pure mind☆ ☆pure mind☆さん
新時事爺 楽天_幽さん
みすまだかお とは… 目玉おやじさん
ワイルドキャットの… f4ffmさん
私の故郷は 「ふく… おばかんのさん
SALT OF THE EARTH slash555さん
「きのうの常識はき… santaro-さん
☆Pure mind☆ ☆pure mind☆さん
新時事爺 楽天_幽さん
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(1840)麻雀大好き!
(51)福島・宮城の地元ネタ
(2290)野球大好き!
(504)お仕事の話
(598)家族の話
(2141)芸能大好き!
(814)この日記について
(502)企画モノ
(408)マヌケな昔話
(229)その他の都道府県の話
(940)早朝散歩
(517)イーグルス日記
(246)鉄道忌避伝説
(18)困った時の静岡県ネタ
(38)東日本大震災
(196)decade(s)企画
(118)株式投資大好き!
(33)同窓会(仙台市立高砂中学校 1987年3月卒)
(15)首都圏別荘(?)日記
(168)新型コロナウイルス
(83)困った時の千葉県ネタ
(10)Comments
カテゴリ: カテゴリ未分類
とりあえず、宮城県内からの進学者数の多い16大学についてそのデータを見てきましたが、国立大を除く各大学の強みと弱みがなんとなく見えてきたようにも感じます(国立大は宮城県外の状況についても調べないと確かなことは言えません)。これまでのエントリでも折に触れて書いてきましたが、ここでまとめてみたいと思います。
【宮城大】
入試要項を確認する限りでは一般選抜での筆記試験が重量、また学校推薦型選抜や総合型選抜においても共通テストの受験を義務付けるなど、基礎学力を重視した学生選抜を行っている様子が伺える。ただ、恐らく宮城大サイドで「入って欲しい」と思っている高偏差値校、とりわけナンバースクールと呼ばれる5校(仙台一、仙台二華、仙台二、仙台三、宮城一)からの進学者数は少なく、これらの高校から受験してもらえるようになるかどうかが今後の鍵。
1997年開校と歴史は浅いがそろそろ卒業生の子息が大学入試を迎える時期に差し掛かっているだけに、その卒業生が母校に対してどのような評価を下しているかも、今後の受験動向に影響するかもしれない。
【東北学院大】
宮城県内の大半の高校から進学者がおり、恐らく将来にわたって大学運営面での死角はないと思われる。ただし、その一方で、高偏差値校から積極的に学生を確保しようという考えが薄く、「国公立大落ちを拾う」という消極的なスタンスに甘んじているようにも感じる。
問題となるのは系列の東北学院中高の存在で、生え抜きとなるこの学校の卒業生に将来の東北学院大のリーダーを託したいと大学サイドは考えているのかもしれないが、昨年共学化して以降入試難易度が上昇し、東北学院大に進学する学力レベルの生徒との学力面での乖離が見られるようになったように感じる。東北学院中高の卒業生は今後、東北学院大の学生供給源として機能しなくなるのではなかろうか。
【東北福祉大】
規模こそ大きいがどの高校から重点的に入学させたいのかが不明確。附属・系列の高校を有さないだけに、将来のスカウティング戦略はもっと重要視されてしかるべきだろう。
【東北医薬大】
医学部と薬学部は宮城県内の他私立大には設置されていないこともあり、この分野では安泰。ただ、少子化傾向が今後進むゆえ薬学部の規模を維持するのであれば、東北福祉大同様附属・系列の高校を有さないだけに、現状進学者数が少ない偏差値40台の高校にも積極的なスカウティングが必要になってくる。
【東北工大】
工業高校を中心に偏差値40台の高校からの進学が多い。偏差値40台の高校の生徒は辛辣な言い方をすれば「理数系科目が苦手だからこそその高校にしか進学できなかった」側面があるので工業高校から重点的にスカウティングする戦略は正解だと思う一方、工業高校は大学に進学しない生徒も多く、今以上の学生数上積みは厳しい状況。系列の仙台城南高校からの進学者も多く年間100人前後進学することもあるが、この高校は難関大から就職までの多彩な進路が売りになっている側面があり、これ以上東北工大への進学者を増やすのは至難の業かと思われる。
少子化が進む今後は、学部学科を絞りダウンサイジングしての大学維持を余儀なくされるのではないだろうか。2020年に工学部建築学科を建築学部として独立させたが、ひょっとしたら「建築だけは残したい」というダウンサイジングの布石かもしれない。
【宮城学院女子大】
恵泉女学園大や神戸海星女子学院大が相次いで募集停止を発表するなど全国的に苦境にある女子大の中では比較的健闘している感がある。宮城県では2000年代半ばまで公立の別学校が多かったため女子大にも比較的理解がある土地柄なのかもしれないが、公立高校共学化完了後に高校生活を迎えた世代が受験生の親となるであろう2030年代になればひょっとしたら逆風が強まるかもしれず、不安が残る。系列の宮城学院中高(女子校)も生徒数の減少傾向に歯止めがかからず、苦戦している。
先述した東北福祉大の攻勢次第では、最悪募集停止という道をたどる可能性も考えられる。そうでなくても、すべての学部で他大学とコンテンツが被っており、先行きが暗い。創設者が同じ東北学院大に統合される可能性もあり得る。
【尚絅学院大】
こちらは女子短大が改組して共学の大学になったケース。名取市にキャンパスを有し仙台都市圏南部に地盤を築いているため、学生確保上の安定感は宮城学院大よりも上なのではないかと思われる。また、系列の尚絅学院中高(こちらは仙台市中心部にキャンパスがある)も定員充足率が高く、毎年50人前後の進学者を輩出するなど尚絅学院大の学生供給源として機能している。
この大学の泣き所は、宮城県外での知名度が低いこと。東北福祉大とは対照的に大学も中高も部活に熱心ではないため、対外的なPR不足の感が否めない。この辺が克服されれば、今以上に安定感が増すのだが。
【仙台大】
東北・北海道で唯一の体育系大学というオリジナリティーを有しているものの、偏差値50以上の高校からの進学が極端に少ないのは致命的。知的好奇心が刺激されるような学問コンテンツとしてはスポーツ情報マスメディア学科という学科もあったりするだけに、進学校向けにこの学科を積極PRしていくのも一つの手かもしれない。この学科から著名なスポーツジャーナリストが輩出されれば、風向きが一気に変わるかも。
【石巻専修大】
地元石巻ですらも進学校から避けられる傾向があるだけに、存続に向けて打つ手が限られてくる。もっとも有効と思われる打開策は仙台市内の高校生へのPRだが、彼らからは「はるばる石巻に進学」することに抵抗感を覚える反応が多数を占めるかもしれず、ひょっとしたら打つ手は打った上での現状なのかもしれない。となると、このまま地域の過疎化とともに閉校を待つしかない運命なのか?
本家の専修大には設置されていない理工学部を有している点は興味深く、専修大に統合した上で理工学部だけ石巻にキャンパスを設置すれば…と恐らく少なからぬ人が考えただろうが、郡山市にある日大工学部の惨状を見ると、とてもそれだけで校勢が上向くとも思えないし…
【東北文化学園大】
宮城県の高校に対するPRは正直打つ手なしで、このままでは閉校まっしぐら。工学部を有しているのでそれだけは至近にある東北福祉大に引き取ってもらえるかも…というぐらいしか、将来の期待が見いだせない。
ただし、仙山線国見駅から徒歩圏内というキャンパスのロケーションを最大限に活用するならば、宮城県ではなく私立大が不足している山形県の高校へのPRを積極的に行うことによって、ひょっとしたら存続にも光明が見いだせるかもしれない。

【中古】 地方大学再生 生き残る大学の条件 朝日新書710/小川洋(著者) 【中古】afb
【宮城大】
入試要項を確認する限りでは一般選抜での筆記試験が重量、また学校推薦型選抜や総合型選抜においても共通テストの受験を義務付けるなど、基礎学力を重視した学生選抜を行っている様子が伺える。ただ、恐らく宮城大サイドで「入って欲しい」と思っている高偏差値校、とりわけナンバースクールと呼ばれる5校(仙台一、仙台二華、仙台二、仙台三、宮城一)からの進学者数は少なく、これらの高校から受験してもらえるようになるかどうかが今後の鍵。
1997年開校と歴史は浅いがそろそろ卒業生の子息が大学入試を迎える時期に差し掛かっているだけに、その卒業生が母校に対してどのような評価を下しているかも、今後の受験動向に影響するかもしれない。
【東北学院大】
宮城県内の大半の高校から進学者がおり、恐らく将来にわたって大学運営面での死角はないと思われる。ただし、その一方で、高偏差値校から積極的に学生を確保しようという考えが薄く、「国公立大落ちを拾う」という消極的なスタンスに甘んじているようにも感じる。
問題となるのは系列の東北学院中高の存在で、生え抜きとなるこの学校の卒業生に将来の東北学院大のリーダーを託したいと大学サイドは考えているのかもしれないが、昨年共学化して以降入試難易度が上昇し、東北学院大に進学する学力レベルの生徒との学力面での乖離が見られるようになったように感じる。東北学院中高の卒業生は今後、東北学院大の学生供給源として機能しなくなるのではなかろうか。
【東北福祉大】
規模こそ大きいがどの高校から重点的に入学させたいのかが不明確。附属・系列の高校を有さないだけに、将来のスカウティング戦略はもっと重要視されてしかるべきだろう。
【東北医薬大】
医学部と薬学部は宮城県内の他私立大には設置されていないこともあり、この分野では安泰。ただ、少子化傾向が今後進むゆえ薬学部の規模を維持するのであれば、東北福祉大同様附属・系列の高校を有さないだけに、現状進学者数が少ない偏差値40台の高校にも積極的なスカウティングが必要になってくる。
【東北工大】
工業高校を中心に偏差値40台の高校からの進学が多い。偏差値40台の高校の生徒は辛辣な言い方をすれば「理数系科目が苦手だからこそその高校にしか進学できなかった」側面があるので工業高校から重点的にスカウティングする戦略は正解だと思う一方、工業高校は大学に進学しない生徒も多く、今以上の学生数上積みは厳しい状況。系列の仙台城南高校からの進学者も多く年間100人前後進学することもあるが、この高校は難関大から就職までの多彩な進路が売りになっている側面があり、これ以上東北工大への進学者を増やすのは至難の業かと思われる。
少子化が進む今後は、学部学科を絞りダウンサイジングしての大学維持を余儀なくされるのではないだろうか。2020年に工学部建築学科を建築学部として独立させたが、ひょっとしたら「建築だけは残したい」というダウンサイジングの布石かもしれない。
【宮城学院女子大】
恵泉女学園大や神戸海星女子学院大が相次いで募集停止を発表するなど全国的に苦境にある女子大の中では比較的健闘している感がある。宮城県では2000年代半ばまで公立の別学校が多かったため女子大にも比較的理解がある土地柄なのかもしれないが、公立高校共学化完了後に高校生活を迎えた世代が受験生の親となるであろう2030年代になればひょっとしたら逆風が強まるかもしれず、不安が残る。系列の宮城学院中高(女子校)も生徒数の減少傾向に歯止めがかからず、苦戦している。
先述した東北福祉大の攻勢次第では、最悪募集停止という道をたどる可能性も考えられる。そうでなくても、すべての学部で他大学とコンテンツが被っており、先行きが暗い。創設者が同じ東北学院大に統合される可能性もあり得る。
【尚絅学院大】
こちらは女子短大が改組して共学の大学になったケース。名取市にキャンパスを有し仙台都市圏南部に地盤を築いているため、学生確保上の安定感は宮城学院大よりも上なのではないかと思われる。また、系列の尚絅学院中高(こちらは仙台市中心部にキャンパスがある)も定員充足率が高く、毎年50人前後の進学者を輩出するなど尚絅学院大の学生供給源として機能している。
この大学の泣き所は、宮城県外での知名度が低いこと。東北福祉大とは対照的に大学も中高も部活に熱心ではないため、対外的なPR不足の感が否めない。この辺が克服されれば、今以上に安定感が増すのだが。
【仙台大】
東北・北海道で唯一の体育系大学というオリジナリティーを有しているものの、偏差値50以上の高校からの進学が極端に少ないのは致命的。知的好奇心が刺激されるような学問コンテンツとしてはスポーツ情報マスメディア学科という学科もあったりするだけに、進学校向けにこの学科を積極PRしていくのも一つの手かもしれない。この学科から著名なスポーツジャーナリストが輩出されれば、風向きが一気に変わるかも。
【石巻専修大】
地元石巻ですらも進学校から避けられる傾向があるだけに、存続に向けて打つ手が限られてくる。もっとも有効と思われる打開策は仙台市内の高校生へのPRだが、彼らからは「はるばる石巻に進学」することに抵抗感を覚える反応が多数を占めるかもしれず、ひょっとしたら打つ手は打った上での現状なのかもしれない。となると、このまま地域の過疎化とともに閉校を待つしかない運命なのか?
本家の専修大には設置されていない理工学部を有している点は興味深く、専修大に統合した上で理工学部だけ石巻にキャンパスを設置すれば…と恐らく少なからぬ人が考えただろうが、郡山市にある日大工学部の惨状を見ると、とてもそれだけで校勢が上向くとも思えないし…
【東北文化学園大】
宮城県の高校に対するPRは正直打つ手なしで、このままでは閉校まっしぐら。工学部を有しているのでそれだけは至近にある東北福祉大に引き取ってもらえるかも…というぐらいしか、将来の期待が見いだせない。
ただし、仙山線国見駅から徒歩圏内というキャンパスのロケーションを最大限に活用するならば、宮城県ではなく私立大が不足している山形県の高校へのPRを積極的に行うことによって、ひょっとしたら存続にも光明が見いだせるかもしれない。

【中古】 地方大学再生 生き残る大学の条件 朝日新書710/小川洋(著者) 【中古】afb
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.