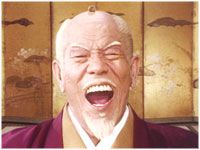PR
X
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(69)ラーメンの食べ歩き:高田馬場、早稲田
(384)ラーメンの食べ歩き:足立区
(72)ラーメンの食べ歩き:荒川区
(27)ラーメンの食べ歩き:板橋区
(24)ラーメンの食べ歩き:江戸川区
(11)ラーメンの食べ歩き:大田区
(128)ラーメンの食べ歩き:葛飾区
(300)ラーメンの食べ歩き:北区
(37)ラーメンの食べ歩き:江東区
(35)ラーメンの食べ歩き:渋谷区
(82)ラーメンの食べ歩き:品川区
(23)ラーメンの食べ歩き:新宿区
(186)ラーメンの食べ歩き:杉並区
(49)ラーメンの食べ歩き:墨田区
(23)ラーメンの食べ歩き:世田谷区
(20)ラーメンの食べ歩き:台東区
(132)ラーメンの食べ歩き:中央区
(109)ラーメンの食べ歩き:千代田区
(615)ラーメンの食べ歩き:豊島区
(152)ラーメンの食べ歩き:中野区
(28)ラーメンの食べ歩き:練馬区
(9)ラーメンの食べ歩き:文京区
(1000)ラーメンの食べ歩き:港区
(106)ラーメンの食べ歩き:目黒区
(19)ラーメンの食べ歩き:東京23区外
(12)ラーメンの食べ歩き:千葉県
(900)ラーメンの食べ歩き:埼玉県
(17)ラーメンの食べ歩き:神奈川県
(10)ラーメンの食べ歩き:関東
(6)ラーメンの食べ歩き:中部、関西
(57)ラーメンの食べ歩き:中国、四国、九州
(15)ラーメンの食べ歩き:北海道、東北
(1)ラーメンの食べ歩き:催事、イベント
(68)ラーメンの食べ歩き:一条流がんこ
(363)ラーメンの食べ歩き:自家製中華そば 勢得
(5)ラーメンの食べ歩き:支那そば きび
(44)ラーメンの食べ歩き:天神下大喜
(160)ラーメンの食べ歩き:兎に角
(136)ラーメンの食べ歩き:バッソ ドリルマン
(20)ラーメンの食べ歩き:丸長大勝軒系
(72)ラーメンの食べ歩き:ラーメン二郎
(30)ラーメンの食べ歩き:横浜家系
(243)光圀の食べ歩き:そのほか
(67)光圀の食べ歩き:台湾
(214)光圀の諸国への旅
(151)光圀のスポーツ観戦の旅
(82)光圀の勉強生活
(170)カテゴリ: 光圀の諸国への旅

聖橋は「ひじりばし」という発音で、湯島聖堂とニコライ堂を結ぶ橋という意味で多くの方に公募へ出されたという。聖橋から丸の内線、総武線、中央線の電車が交差するタイミングを狙って写真を撮ろうとする方も多いが、仕事が控えてあるので、このようなタイミングを待つ時間がない。

ただし、せっかくだから、 湯島聖堂 へ参拝。元々上野忍ヶ岡にあった幕府儒臣・林羅山の邸内に設けられた孔子廟を元禄3年(1690年)、五代将軍綱吉がここに移し、規模を拡大・整頓し、官学の府とした。この時から「聖堂」と呼ぶようになった。

一般見学なら正門は、仰高門となる。

楷樹。中国の曲阜にある孔子の墓所に植えられている木。大正4年(1915年)、林学博士白澤保美が曲阜から種子を持ち帰り、東京目黒の農商務省林業試験場で苗に仕立てた。そして苗は湯島聖堂をはじめ儒学に関係深い所で植えられたという。

世界最大と言われる孔子銅像。昭和50年(1975年)台湾台北市のライオンズ・クラブからの寄贈。

入徳門。宝永元年(1704)に建造。聖堂で唯一の木造建築という。聖橋から降りるなら仰高門ではなく、入徳門から直接に湯島聖堂への参拝ができる。ただし御朱印をもらうなら、仰高門の近くにあり、湯島聖堂を管理する斯文会の事務所へ行かなくてはならない。

大成殿。孔子廟の正殿ということ。中へ見学できるが、時間がないので参拝だけした。ここは現地に移転された時にも林家の学問所であったが、寛政9年(1797年)に、11代将軍徳川家斉の時の幕府による規模拡大で、幕府直轄の「昌平坂学問所」となった。この時の設計は、かつて中国の明王朝の遺臣である朱舜水が徳川光圀のために製作した孔子廟の模型を参考にしたという。構内に神農廟という施設もあるが、神農祭を行う11月23日にのみ見学できるという。なお、学問所は明治維新の後にも新政府に引き継がれ、のち創立された東京大学の系譜にもつながる。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[光圀の諸国への旅] カテゴリの最新記事
-
大聖山東朝院 南谷寺(目赤不動尊) 2024.05.04
-
諏訪山 吉祥寺 2024.05.04
-
駒込天祖神社 2024.05.04
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.