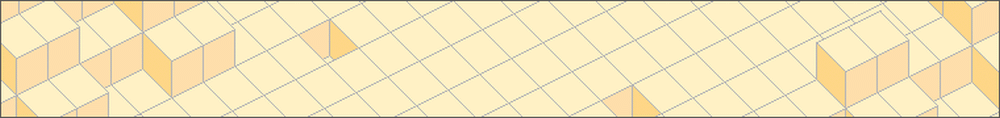2017年10月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
【東京六大学2017秋】早稲田大が70年ぶり最下位に!~早稲田、その70年前のこと「関白還る」
30日、早慶2回戦が行われ、慶應義塾大が7-2で早稲田大を降し、7季ぶり35回目の優勝を決めた。通算9勝3敗1分けで明大(8勝3敗)と勝ち点4で並び、勝率で上回った。早大は3勝8敗で東大と並び、1947年秋以来、70年ぶり2回目の最下位。 (以上、毎日新聞)■ボクは早稲田の「1947年秋以来、70年ぶり2回目の最下位」に興味をもちました。調べると、このシーズンは慶應が9勝1敗で優勝、早稲田が2勝8敗で最下位。東大は2勝7敗1分で5位でした。当時、早稲田の主なメンバーには、1944年に入学した蔭山和夫さん(市岡中、後に南海)がいたようですが、試合に出ていたか定かではありません。また、調べるうち石井藤吉郎さんが1943年入学組と知り、この年はベンチ入りしていただろうか? と想像しましたが、これは間違いでした。wikipediaによれば、石井藤吉郎さんは1943年のいわゆる「最後の早慶戦」にベンチ入りし、将来のエースとして嘱望されるも応召、1947年まで約2年シベリアに抑留された。そして、日本に帰国したのが1947年秋。そのまま早大に復学するも、栄養失調の影響でブクブクに太ったその姿ではさすがに即復帰とはいかなかった。その年暮れのキャンプからチームに合流し、周囲の度肝を抜く豪打を連発。その当時早大は創部以来初の最下位に沈んでいたが、「関白還る」の一報は大きな希望をもたらした。森茂雄監督の期待通り翌年からチームの4番打者に座り、最下位の屈辱にまみれたチームをたちまち優勝に導き、甦らせた。(以上、wikipedia)「関白」石井藤吉郎さんが戦列に加わった1948年春、さっそく早稲田は優勝しました。今季最下位に転落した早稲田も、石井さんのような大打者が加われば、すぐに優勝できるのですね。あ、KIYOMIYA君が、再生の神に適任だったのでしょうが・・・。
2017.10.30
コメント(0)
-

【東都大学4部】東京工大、2017秋 観戦記
現在、東都4部はまだ1試合を残すものの、順位が確定しました。優勝は芝浦工大、2位は東京都市大、そして最下位(3位)は東京工大。今季、東工大の試合を2度観戦しました。どちらもエース・笛田斗眞(2年、佐賀・東明館)が先発した試合でしたが、両極端の結果となりました。■まず9月23日の対都市大戦、笛田の投球は圧巻でした。スライダーを駆使した緩急自在の投球術で、5-0の零封勝利。142球、与四死球3、奪三振6、被安打はわずか1本のみ。打っては4番・福田一石(4年、光陵)や6番・瀬古健太(3年、札幌北)の長打などで着実に加点しました。(9月23日 芝浦工大G)都市大 000 000 000 =0東工大 010 000 04X =5■しかし一方の対芝浦工大戦。笛田は序盤から球が浮き制球を乱すも、被安打は3番・笈川の中前安打1本のみで凌ぎます。しかし、この笈川との対戦が後々まで尾を引きました。2つの四球で二死二・三塁のピンチを作ると、ここで笈川に中前にはじき返されてついに2点を失いました。実は前の打席でも笈川は同じ直球を同じ中前に安打しており、今回はファールで粘り最後の最後に待っていた直球を仕留めたのです。さらに続く4回も一死二・三塁の場面で、三度(みたび)笈川に中前へ安打され、笛田はマウンドを降りました。分かっていても、勝負どころで笈川の魔術に操られたように笛田は同じ球を投げ、同じ中前にはじき返されました。この笛田ー笈川の対戦が勝敗を分ける決め手になりました。(10月8日 芝浦工大G)芝工大 002 400 200 =8東工大 000 000 000 =0東京工大も好機はありました。6点を失った直後の4回裏、この回先頭の2番・淵脇空輝(2年、湘南)がヘッドスライディングで内野安打を勝ち取ると、続く3番・瀬古健太が中前安打で出塁して中軸につなぐも、後続が凡退し好機は潰えました。東京工大、今季の成績は2勝6敗、勝ち点1となり、最下位(3位)に終わりました。主力打者たちが今季をもって引退しますが、来年こそ4部優勝を目指してほしいものです。(写真)エース笛田、9.23完封目前。(写真)堀内俊太郎。(写真)4年生投手、寺澤穂高。(写真)4番・福田一石。(写真)軽快な守備をみせたセカンド・谷村優斗。
2017.10.29
コメント(0)
-

【東京六大学2017秋】母さん、法政大のあの投手たち、どうしたんでせうね?
今日の早慶1回戦は、慶應の1年生投手陣が踏ん張り、優勝に王手をかけました。先発した関根智輝(城東)、締め括った佐藤宏樹(大舘鳳鳴)、どちらも見事な投球でした。慶應は投手陣は弱いと見ていたもので、私はまさか今季優勝を争うとは思いもしませんでした。が、こうした若手の台頭は立派です。来年以降、一層飛躍するのでしょう、きっと。その一方で、最近の法政大のスコアを眺めてみました。鈴木昭汰(1年、常総学院)、高氏祥太(2年、立命館慶祥)、柏野智也(1年、広陵)、落合竜杜(1年、常葉菊川)など、あまり見慣れない若手投手たちの名前を見つけました。あれ、では昨季まで神宮のマウンドに立った若手投手たちはどうしたのだろう?そんなことを考え、映画『人間の証明』で有名になった西条八十の詩『ぼくの帽子』を思い出してしまいました。(以下、パロディー。何とか復活してほしいと願いを込めて)『法政大の若手投手』(西条九十)母さん、法政大のあの投手たち、どうしたのでせうね?ええ、ここ3年ほど、神宮のマウンドに立った若手投手たちですよ。母さん、あれは好きな投手たちでしたよ、でも、ぼくはずいぶん悔しい思いをしているのですよ、だって、最近はとうとうその名前さえ見なくなりましたから。昨年は内沢航大(当時1年、八戸工大一)、新井悠太朗(当時1年、折尾愛真)、そして上條将希(当時2年、市立川越)もいました。とくに上條は高校時代、地元埼玉ではヒーローでした。だから六大学でどれほどの活躍をするか楽しみで仕方ありませんでした。けれど今年は、とうとう駄目だった。一度も登板していないんですもの。母さん、ほんとに法政大のあの投手たち、どうしたのでせう?一昨年は森田駿哉(当時1年)がいましたね。いきなり開幕投手で勝利したのですが、それ以降、その名前さえ聞かなくなりました。母さん、そして、きっとまた雪が積もるでせう。むかしつやつや光った、あの投手たちの名前を、そして今の一年生投手たちまでも雪が埋めるのでしょうか、静かに、寂しく。(写真)2015年4月13日、法政大の当時の1年生投手たち。上條将希(左)と森田駿哉(右)。
2017.10.28
コメント(0)
-

【東京六大学2017秋】もうすぐドラフト! 岩見雅紀は上位指名か、谷田成吾と宮台康平はどうかいな?
10月17日、慶大義塾大・岩見雅紀が対立教大戦の1回に7号本塁打を放ち、1シーズン最多のリーグ記録に並びました。また年間本塁打は単独最多の12本、さらに通算本塁打が21本で単独3位となり、高橋由伸(慶應大)の持つ最多記録まであと2本となりました。岩見は滋賀・比叡山高から一浪して慶應大に入学したそう。合格するまでの苦労話は WEB SPORTIVAに詳しいのですが、そのインタビューで答えた岩見の一言が印象的でした。浪人したことは遠回りではなかったか?という質問に対し、岩見は「絶対に浪人してよかったです」と言い、そして「だって、タイプのだぶる谷田さんや横尾さんと2年ズレましたから。試合に出るチャンスが2年あるのは大きいです」と。まさにそのとおり。もし現役で慶應大に入学していたら、谷田や横尾と重なる分、まず間違いなく本塁打21本はなかったでしょう。岩見は一浪してよかった・・・そして谷田成吾(JX-ENEOS)のドラフトはどうなりますか、また、東京大の宮台康平は?※宮台、ウッチャンナンチャンの南原に似ているといった話もありますが、どうでしょうか(笑)?
2017.10.22
コメント(4)
-

【東京六大学2017秋】慶應・岩見雅紀が5試合連続本塁打の新記録達成!
慶應義塾大・岩見雅紀(4年、比叡山)が、対明治大戦でリーグ史上初の5試合連続本塁打を放ちました。この本塁打は今年春5本、秋6本となり、94年の丸山泰令(慶應)に続く年間最多タイ記録の11本目。そして今季6号は田中彰(法政)のシーズン最多7本塁打に王手。それだけでなく、さらに通算20号となって岡田彰布(早稲田)に並ぶ史上3位タイに浮上しました。ちなみに通算最多記録は高橋由伸(慶應)の23本。まさに記録尽くめの一打が生まれたのは10月8日、対明治大戦でした。スコア0―0で迎えた5回、カウント2ボール1ストライクから変化球を引っ張ると、左翼ポール際の中段にすさまじい打球が飛び込みました。結構難しそうな球でしたよ、それを一瞬で仕留めたのは見事でした。2年前の9月26日、彼のピンポン玉のようにスタンドに飛んでいく打球(第1号)を見たとき、ボクはブログにこう書きました。「そのスイングは気迫とか、根性とか、技術とか、理論とか、そういったものとはまったく無縁に見えました。まるで別次元で野球をやっています。白鵬が軽くバットを振ったら、球がピンポン玉のようにはるか遠くへ飛んでいった・・・とでも言いましょうか。いやはや驚いたのなんの」と。でも、今は違います。10月8日の一打はちゃんと根拠あっての一打に思えました。
2017.10.15
コメント(0)
-

【東京六大学2017秋】東大が法政に連勝し15年ぶりの勝ち点!
今日行われた東京大ー法政大2回戦は、昨日に続き東大が連勝し、2002年の対立教大戦以来15年ぶりの勝ち点を挙げました。今日の試合を観ていませんが、この結果は決して驚くほどではありません。東大はエース宮台だけでなく、他の投手や打者たちも確実に力をつけてきていました。試合運びも以前は肝心な局面でエラーをしたり焦りが見えましたが、今季私が見た試合ではそれがありませんでした。今季の東京六大学は「一弱(東大)」状態を脱して、6つの大学がすべてがぶり四つに組んで戦っているように見えます。従い、東大が勝つこと自体にニュースバリューはさほどないように思えるのです。今日の勝ち点で一番喜んだのは浜田一志監督でしょうか。この監督さんは神宮のグラウンドを自らのステージのようによく動き回ります。ベンチ前やマウンドはもちろん、ブルペンだって平気で足を運ぶ。その姿は往年の近鉄・仰木監督を思い出させます。この勢いに乗って浜田監督が次に描く自作自演のシナリオは、再来週に明治をやっつけるドラマなんでしょう、きっと。さて、東大が法政に連勝して勝ち点を挙げるのは1928年秋以来89年ぶりとか。このシーズン、法政は0勝8敗で最下位に低迷し、法政に勝った帝大(東大)は3勝8敗で5位に終わりました。当時法政はまだ弱かった、強くなったのはその翌年から。29年にハワイ生まれの若林忠志が入学したことで一気に戦力がアップし、30年に初優勝を飾るのです。そもそも東京六大学リーグが結成されたのが25年、あの有名な「リンゴ事件」ですら33年ですから、東大が法政に連勝して勝ち点を挙げたのはそれほど昔の出来事なのです。
2017.10.08
コメント(4)
-

【東京六大学2017秋】慶應、岩見雅紀の4試合連続本塁打(リーグ最多タイ記録)などで、明治を下す!
首位をひた走る明治は、まだリーグ戦中盤ながら、今週の慶應戦に勝ち点を挙げればほぼ優勝を決める。一方の慶應はBクラス転落回避のため、お互いに絶対に負けられない一戦でした。(10月7日 慶應ー明治1回戦)慶應 000 020 200 1 =5明治 003 000 010 0 =47回、1点差を追う慶應は3番・柳町達(2年、慶應)の本塁打で同点に追いつくと、続く4番・岩見雅紀(4年、比叡山)が右翼へ勝ち越しとなる本塁打を放ちました。この岩見の本塁打は通算19号だとか。2年前の9月26日、ボクは彼の第1号を神宮で見ていました。巨体を揺らして代打で登場しフルスイングすると、あらら・・・あっ!いう間のスタンドインでした。隣にいた慶應OBのオジサマが「あいつ(岩見)は体がデカいだけで全然打てねぇんだ」なんて呟く最中の、一瞬の出来事でした。さらに、今日の本塁打は岩見にとって4試合連続となる本塁打、これはリーグ最多タイ記録(4人目)。1人目が明治・広沢克己、そして法政・田中彰、慶應・横尾俊建。広沢が記録を作ったのは昭和58年春季リーグ戦でした。当時は明治と法政がガチで優勝争いを繰り広げていましたが、このシーズンは広沢(小山)の活躍で明治が完全優勝をしました。明治には広沢のほかに竹田光訓(日大一)、森田洋生(高知商)などもいましたね。岩見の本塁打が懐かしい記憶を甦らせてくれました。(写真)慶應・岩見雅紀。 ~9・18対東大戦より~
2017.10.07
コメント(2)
全7件 (7件中 1-7件目)
1