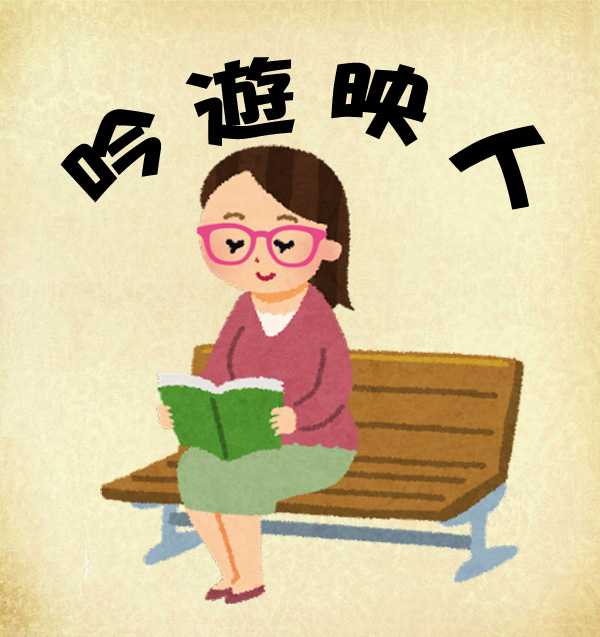PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
その他
(7)映画/アクション
(77)映画/ヒューマン
(97)映画/ホラー
(35)映画/パニック
(25)映画/歴史・伝記
(32)映画/冒険&ファンタジー
(41)映画/ラブ
(47)映画/戦争・史実
(41)映画/SF
(55)映画/青春
(23)映画/アニメ
(24)映画/サスペンス&スリラー
(143)映画/時代劇
(21)映画/西部劇
(4)映画/TVドラマ
(29)映画/コメディ
(15)映画/ミュージカル
(1)映画/ドキュメンタリー
(3)映画/犯罪
(12)映画/バイオレンス
(9)映画/ヒッチコック作品
(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』
(8)読書案内
(217)仏レポ
(2)コラム紹介
(120)竜馬とゆく
(9)名歌と遊ぶ
(70)名句と遊ぶ
(288)風天俳句
(5)名文に酔う
(16)ほめ言葉
(3)教え
(42)吟遊映人ア・ラ・カルト
(13)江畔翁を偲ぶ
(12)ガンバレ受験生!
(5)オススメの本
(3)月下書人(小説)
(6)写伝人(写真)
(6)写真
(18)名曲に酔う
(1)名画と遊ぶ
(2)訃報
(11)舞台
(1)神社・寺院・史跡
(12)テーマパーク
(2)カフェ&スイーツ
(20)要約
(23)聖地巡礼
(1)発見
(8)体験談
(1)お気に入り
(1)ヘルス&ビューティー
(3)読書初心者
(5)テーマ: DVD映画鑑賞(13974)
カテゴリ: 映画/TVドラマ

「わいは戦をしに行くとってなかっ!!」
「そんつもりでも、戦になるやもしれもはん! そん時は・・・!」
「よかっ!! 国が潰れても、人が死に絶えるわけではなかっ! 人が死んで死んで、国を焼き尽くして、そん中から生き残ったもんがもう一度新しか日本国を造れば良かっ!!」
「そいは暴論ごわす!!」
愛読する司馬文学について少しだけ語りたい。
歴史というのは、それを捉える後世の人物たちによって検証され、良くも悪くも評価される。
それは、その時代背景にもよるし、作家や学者らの歴史観によってずい分異なる。
動乱の幕末時、幕府側に立っていた新撰組などは、狂暴な野犬の如き人斬り集団として捉えられていたイメージを、作家司馬遼太郎は一新。
こうして、それまでは勤王の志士たちに抵抗する反逆者、いわば賊軍でしかなかった新撰組は、幕臣意識に燃える忠義の士としてドラマの表舞台に立つようになったのだ。
「翔ぶが如く」では、西郷や大久保などにスポットが当てられ、魅力あふれる人物として描かれているが、それは決して「官軍」だからと言うような安易な見識からではないことが理解できる。
その点を踏まえてこのドラマを鑑賞すると、さらに司馬文学を堪能することができるのではなかろうか。
総集編第二部前編は、「両雄対決」と題される。
王政復古によるクーデターの後、名目上、政府は徳川幕府から朝廷へ移ったものの、中央集権国家を確立するにはいまだ難題が残されていた。
それは「藩」の存在をどうするかという問題であった。
そこで、現状の政局を打破するべく、西郷隆盛、大久保利通、西郷従道(隆盛の弟)、大山巌、木戸孝允、井上馨、山県有朋の薩長の7名が木戸孝允邸にて「廃藩置県」案を練った。
その後、岩倉具視、板垣退助らの賛同を得て廃藩置県が制定。
こうして土地と人民は明治政府の所轄するところとなったのである。
明治6年になると、対朝鮮問題が浮上。
これは、明治元年に李氏朝鮮が維新政府の国書受取り拒否に端を発しているが、その後、明治政府の使節を侮辱したとあって、武力行為に及ぶか否かが審議される。
(しかし西郷の当初の主張としては、あくまでも出兵ではなく使節として赴くというものだった。)
この主張は一度は閣議決定したものの、太政大臣の三条が急病のため岩倉具視が代行役に立ち、白紙に戻される。
西郷らの朝鮮出兵は、無期限延期となった。
「翔ぶが如く」もいよいよ佳境に入って来た。
それまで、兄弟のように仲睦まじい西郷と大久保であったが、ここへ来て徐々に方向性の違いが明白になってくるのだ。
しかし、それは両者のうちどちらが正しく、どちらが間違っていると白黒つけるのではなく、史実として捉えてみたらどうだろう。
人間は情感に流される動物である。
愛すべき登場人物に感情移入せずにはいられない場面も出て来るだろう。
だが、西郷も大久保も坂本竜馬も新撰組も、皆等しく、激動の時代を生きた「志士」たちなのである。
1990年TV放送
【原作】司馬遼太郎
【脚本】小山内美江子
【出演】西田敏行、鹿賀丈史
また見つかった、何が、映画が、誰かと分かち合う感動が。
See you next time !(^^)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[映画/TVドラマ] カテゴリの最新記事
-
刑事コロンボ 〜二枚のドガの絵〜 2023.04.29
-
刑事コロンボ〜ホリスター将軍のコレクシ… 2023.04.15
-
刑事コロンボ 〜指輪の爪あと〜 2023.03.25
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.