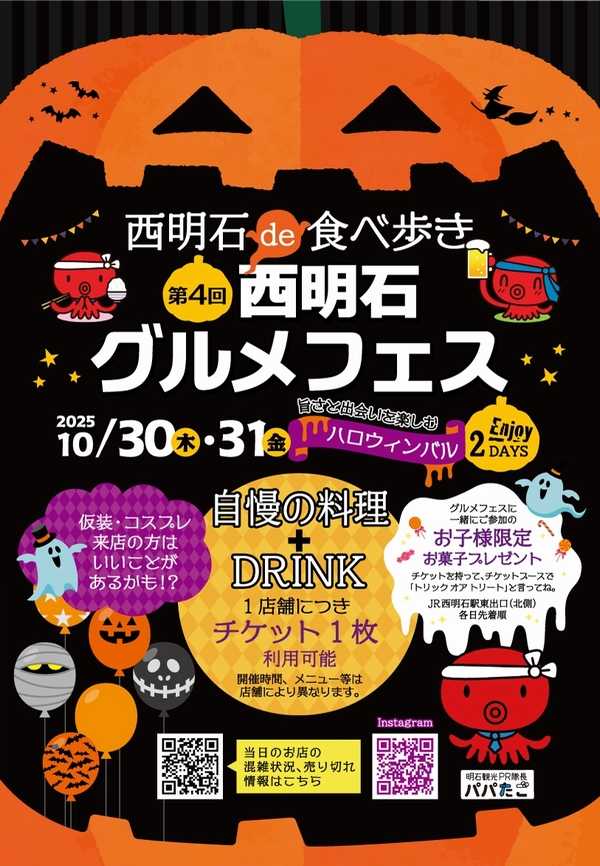2013年04月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

筍!
去年から使っている伊勢産の筍です。アクが少なくて美味しい筍です。どうも関西系のほうが美味いような気がしますね。ずいぶん前に京都で食べた筍懐石の信じられないような美味しさが思い出されます。アクが少ないので、出汁の旨味がきいた薄味の味付けがよく合うんですね。 震災前までは、成田の自家菜園のそばの竹林で筍が取れたので、多い時にはワンシーズンで100キロ以上もしくは200キロ近くも使っていたかもしれませんが、震災後は千葉県のかなりの地域が放射能汚染で出荷自粛になり、その後宅地造成などで畑のそばの竹林もなくなってきて、放射能汚染が収まってももう筍は取れなくなりました。 春を代表する野菜と言うと、思い浮かぶのは和食なら筍やワラビやタラの芽やコゴミと言った山菜系ですかね、ほかにも春キャベツや菜の花や新ニンジン新玉ねぎなどいろいろありますが、、ヨーロッパで春野菜と言ったら、やはりアスパラガス!特に白や紫のアスパラは珍重されますね。パリ郊外のアルジャントゥイユのアスペルジュ・ヴィオレ(紫アスパラ)は有名です。それから、アーティーチョーク(フランス語ではアルティショ)も、重要な春野菜です。アルティショは、食感が筍に似ていたりもしますがアザミの仲間の花のつぼみを食べる変わった野菜です。 春野菜の共通点は、山菜なども含めてアクやほろ苦味がる物が多いことでしょうか、、? 特に筍とアスパラとアルティショは、収穫してから時間がたつとアクが強くなって固くなり風味が悪くなるということ。筍やアスパラやアルティショは、取りに行ったらお湯を沸かして待っていろというくらい鮮度が大切なのが特徴なんですね。ですから、成田で筍が取れた時は掘って1時間以内くらいに茹でることができたので、かなり美味しかったんですが、もともと自然の竹林なので、栽培物の筍にはかなわない感じがします。この伊勢の筍は明らかに成田のものより美味しいですね。 こんな風にフォアグラの付け合わせにしたり、、、 前菜のサラダにマリネにして入れたりしてます。ちなみにこの皿は、マグレ鴨の自家製スモーク生ハムです。マグレ鴨は、フォアグラをとるために肥育した北京ダックとバルバリー鴨の掛け合わせのフォアグラ用の品種の胸肉のことです。その肉を軽く塩漬けにして、冷燻にかけて、氷温熟成します。赤身の味が濃くて、脂が溶けて美味しいです!今、シェフスペシャル前菜でやってます。
Apr 29, 2013
-

薩摩黒豚の長時間ロースト
豚肉のロース(背肉、牛でいえばサーロインの部位)の150gといったら、ちょいと厚めのロースカツ程度の大きさの肉です。それを30分もかけてゆっくり焼くとこういう感じに柔らかいロゼ色に焼き上がって、しっとりしていて美味いです。脂身はカリカリパリパリで、肉はしっとりという理想的な焼きですね。以前は、最低500gは焼かないと、こういう風には焼けませんでしたが、近頃は1人前でもなんとかできるようになってきました。 ブルターニュのゲランド産のフルール・ド・セルをパラリと振りかけ、ソースはディジョンマスタードと肉汁に自家製のポン酢を少しにオリーヴオイルを乳化させたもの。 ホロホロ鳥が売れたので、そのあとのシェフスペシャルメインディッシュでやってます。
Apr 19, 2013
-

錦爽鶏のポワレ 包丁の話
しっとり焼けた錦爽鶏の胸肉。先日アップしたホロホロ鳥もそうですが、上手に焼ければ鶏肉はモモ肉より胸肉のほうが上品で美味しいと思います。皮はパリパリで身はしっとりととろけるくらいに焼けていればの話ですけどね、、、。 一番上が魚をおろす出刃(ドイツ、ドライザック)次が牛刀26cm(ドイツ、ギーザー)一番でかいのが、河童橋鍔屋の本焼き牛刀39cm、細長いのが、サーモンナイフ(ドイツ、ギーザー)、その下が河童橋鍔屋の本焼き筋引き、同じく本焼き骨すき、ドライザック18cmサンドイッチナイフ、ソールナイフ(ドイツ、ギーザー)、一番小さいのが、もとは14cm位のペティナイフが使いこんで10cmになったやつです。この小さいのが鶏をさばくのに重宝してます。 まあ、ふつうの人よりは結構たくさん包丁を持っているほうかもしれませんね。以前は、技術のなさを道具でカバーしようとしていたことがありましたから、、、でもこれらはサンク・オ・ピエを始める前に買ったものがほとんどで、一番小さいのは20年以上も使ってます。 さっきこれを全部研いだんですが、かかった時間は30分程度。つまり1本につき3分くらいしかかけてません。プロ用の包丁、特に本焼きの固い刃は少し切れなくなっても、せいぜい数十分の一ミリか百分の一ミリ位削ってあげれば(つまり研げば)切れ味は回復するんです。ほとんどの人が、時間をかけて削り落すほど包丁研ぐので、刃がやせて10年ももたずに使えなくなってしまう。包丁1本を1時間以上も研いでいる人を見たことがありますが、あれでは大事な道具を捨てているに等しい。包丁のことを書いた本にも、毎回粗砥、中仕上げ砥石、仕上げ砥石と使って手入れしなさいなんて書いてあるのを見たことがありますが、あれでは庖丁屋のまわし者か?と思ってしまう。 料理人のみなさん、包丁の研ぎすぎには注意しましょう。刃が復活したらそれ以上研いではいけません。
Apr 18, 2013
-

マッシュルームのトゥルネ
左が息子、右が私。息子も15個に1個位この程度切れるようになりました。 ついでにyutubeに動画もアップしました。
Apr 17, 2013
-

フランス産パンタード(ホロホロ鳥)
フランス産のホロホロ鳥のポワレです。鶏ガラとホロホロ鳥のガラで取った鶏のジュとサルディニア島産の極上オリーヴオイルがソースです。仕上げにブルターニュのゲランド産のフルール・ド・セルと荒挽き胡椒。これは胸肉です。胸肉というとパサパサしたイメージがあるかもしれませんが、実は上手に焼いた胸肉のほうがモモ肉より上品で美味しいです。 ホロホロ鳥に限らず、鶏類つまり鶏、ホロホロ鳥、ウズラ、鳩、鴨などをポワレする時の原則は、皮は入念に身はしっとり柔らかく余熱で仕上げるということ。 鶏の皮や豚の背肉や仔羊の背肉や牛のサーロインなどの脂身(背脂)はその動物の体温を守るためのものという一面があります。特に鴨の皮は水鳥ですから、冬場の冷たい湖水に浮かんでいても凍えないようにとても厚くてしっかりしていて断熱効果が高い。 断熱効果が高いという事は、火が通りにくいという事なんですね。だから、皮の側からじっくりよく火を通すことが肝心です。それによく焼けて香ばしくカリカリの鶏の皮は、非常に美味いものですよね! 皮はやや多めの澄ましバター(バターをゆっくり溶かして水分と不純物を取り除いた黄色の純粋な脂肪分)とサラダオイルで、結構強めの火で焼きます。半部以上皮の側から火を通す気持ちです。 皮がカリカリに焼けると、鍋の中の脂はかなり高い温度になっています。190℃くらいにはなっているかもしれません。そこで、肉を返してその熱い脂で身のほうをジューっと焼いたら、脂を捨てて鍋を温かい場所(60℃くらい)で休ませます。この段階ですぐに肉を切ったら中はまだ生焼けです。あとは余熱でゆっくり火が入るのを待ちます。鴨や鳩などは赤身肉ですから、ホロホロ鳥や鳥やウズラよりは火入れがやや浅目ですから、裏返して身を焼いたら鍋から取り出してバットなどに移してから温かい場所で休ませます。 余熱が上手に使えないと、鶏系は美味しく焼けません。まあ、私にとっては毎日やっていることなので、さほど難しいことではないのですが、習得するにはかなり長い訓練が必要でしょうね。 一般的に出回っているフランス産のホロホロ鳥は、小ぶりでちゃちな感じのやつが多いのですが、このホロホロ鳥は一クラス上の品物で、サイズも大きめで肉質もしっかりしています。美味しいですよ!今、本日のスペシャルメインディッシュでやっています。
Apr 16, 2013
-

サンク・オ・ピエ4月5月のコース2013
やっと画像が撮れたので、4月5月コースの詳細です。まずは、 Proscuitto di PARMA Pio Tosini ,LOMBATELLO di Cinta-senese etBresaola fumé du chef avec saladeパルマ、ピオ・トジーニ社の生ハムとトスカーナ産チンタセネーゼ豚のロース生ハム"ロンバテーロ"と自家製ブレザオラ風甲州ワイン牛のスモークハムのサラダ添え 一番手前が、チンタセネーゼのロンバテーロ。背肉(牛でいえばサーロイン)の生ハムです。これがフォアグラの倍もする高価なもので、、、長期熟成でうまみがが複雑で、ハーブやスパイスの香りもします。その右側の赤いのが、ブレザオラ風の自家製スモーク牛ハム。本当のブレザオラは、塩漬けした牛肉を乾燥熟成した生ハムなんですが、本場北イタリアのブレザオラは結構くせがあります。何というか、牛肉臭さがあるんですね。そこで甲州ワイン牛で自家製のスモークハムを作りました。生ハムではなく、軽く火を通してからスモークしてあります。それから、パルマのピオ・トジーニの生ハムですね!これについてはこちらを見てください。詳しく書いてあります。こういうハム系には、やはりシェリー酒それもマンサリーニャやフィノが合いますね! 2皿目は、、、 Foie gras chaud avec purée de pommes de terre nouvellesフォアグラのソテー、新じゃがいものピュレ添え カリッと香ばしく焼いたフォアグラのソテーの下は、新じゃがのピュレ。牛乳とほんの少しのバターで仕上げてあります。ピュレとかピューレとかいうのは、英語でいえばピュア(純粋な物)のことなんです。つまり野菜などを裏ごしして、本来の食感を取り除いた純粋な味わいということなんでしょうね。 フォアグラの脂と新じゃがのピュレが合わさって、いい感じの組み合わせです。ソースは無しで、ブルターニュのゲランドのフルール・ド・セル(塩の華)をパラリと荒挽きの黒胡椒。華やかな香りと強めのボディーのダックポンドセラーのシャルドネがフォアグラと新じゃがには合うと思います。 3皿目は、、、 Risotto sepia aux boutargue Sardegna avec calmar de HOTARU美味!イカ墨のリゾット、サルディニア島産ボッタルガ風味富山湾産ホタルイカ添え 自分で言うのもなんですが、私のイカスミリゾットはヤバ美味です!(笑)美味すぎて死ぬ。と言った友人がいました。(もちろん死にませんが、、)イタリアンをやっている後輩が食べて、この味は絶対に出せないと悔しがっていました。 仕上げにサルディニア島産のボッタルガ(唐墨)の粉をたっぷりかけてあります。これは地中海の黄金のキャビアともいわれる高級珍味です。美味いです!それからスペイン風にピメントン(パプリカ)で味付けしたホタルイカは、1匹1匹全部ピンセットで、目玉と軟骨とクチバシを取り除いてあります。こうすると、口当たりが良くなりホタルイカの味がぐんと良くなります。外で食事をするときにホタルイカの目玉や軟骨が付いているとものすごく腹立たしいのは私だけでしょうか? ワインは、オーソドックスにオルヴィエート・クラシコ。イタリアの辛口白ワインですね。 メインは、、、 Tagliata de Boeuf de KOHSHU de vinA la vieille Bqlsamico et parmigiqno甲州ワイン牛のタリアータ仕立て熟成バルサミコとパルミジャーノチーズ風味 タリアータというのはクラシックなイタリア料理です。タリアートが切るという意味で、タリアータは切ったものということ。まあ、肉を焼いて薄く切るわけですな、、。熟成バルサミコソースを下に敷いて、低温ローストでゆっくり焼き上げた柔らかい甲州ワイン牛を薄切りで盛り付けまして、ゲランドのフルール・ド・セルをパラリと荒挽き黒胡椒を振りかけ、ガーリック風味のオリーヴオイルを回しかけ、薄削りのパルミジャーノチーズを散らします。 とても美味しい牛肉ですから、さっぱりとシンプルな味付けが活きてきますね。ワインは、イタリアンですからロッソ・ディ・モンテプルチアーノ、イタリアの赤ワインです。あまり重くなくて華やかな香りが、料理とうまくマリアージュしますよ! デザートは、、、 Soupe aux fraises avec granite au vinaigre de coing et miel花梨のヴィネガーと蜂蜜のグラニテを添えたフランス産イチゴのスープ 上に乗っている薄茶色の氷菓が、花梨のヴィネガーと蜂蜜のグラニテです。グラニテというのは御影石という意味でシャーベット(ソルベ)の仲間です。ちょっとざらついた感じが御影石のようだということからきているようです。これに使った花梨のヴィネガーは1リットル¥6000以上もする高級品!とても良い香りで、酸味も複雑で綺麗です、。 イチゴのスープはフランス産の完熟イチゴのピュレを使っています。生のイチゴは長崎産幸の香をグランマルニエ少しで和えたもの。このデザートには、、、 さかもとこーひー、サンク・オ・ピエ4月5月コース専用ブレンド!豆は、ホンジュラス・カップ・オブ・エクセレンス・グアカラル、モカ・イルガチェフェ、グァテマラ・エルインフェルト・バカマラ!という豪華版。これが、酸っぱいものやイチゴなんぞに普通は絶対に合わないはずのこーひーが、、、、合うんです!これがまた実に面白いです。 去年も同じデザートで、その時のこーひーもよかったんですが、今回もいいですよ!とてもナチュラルなマリアージュですし、昨日もコーヒーはあまり好きでないというお客様が、こんな美味しいこーひー初めて!!と喜んでいました。
Apr 14, 2013
-

パルマ、ピオ・トジーニ社の生ハム
生ハム始まりました!やはりピオ・トジーニの生ハムは美味いですね! 冷蔵庫が一般に普及したのは、第二次大戦後ですからまだ100年もたっていません。世界を見渡せば、冷蔵庫どころか電気すら通っていない地域もまだあるんですから、食品が生鮮のまま保存できるようになったのはつい最近のことなんですね。 その前は、肉や魚などは塩漬けにするか、干物にするか、コンフィなどのように塩漬けにして火を通してラードで固めて空気から遮断するか、ワインやそのほかのアルコール類に漬け込むなどの方法しかなかった。 缶詰ができたのは19世紀後半で、ナポレオンが行軍用の保存食の開発を命じて、滅菌の瓶づめが開発され、その応用で缶詰が開発され、アメリカの南北戦争の行軍食として活躍して以来一般にも広がったそうです。(ちょいと調べました) で、生ハムというのはかなり古くからある保存食なわけです。塩漬け肉であり干し肉でもあります。歴史は古く、紀元前5年の生ハムの交易の記録があるとパルマハム協会のホームページに書いてありましたから、人が豚を飼育するようになり、塩田ができて一定量の塩が手に入るようになれば製造可能ですから、有史以前からあるのかもしれませんね。まあ、今のように洗練された味わいの生ハムが安定してできるようになるのはもっとずっと後のことでしょうが、、、。 パルマには、大小合わせて200くらいの生ハム会社があるそうですが、最近はほとんどの会社が、生ハム熟成庫の温度湿度をエアコンや冷蔵庫を使って管理しているそうです。まあ、そのほうが楽ですし、衛生面だけを考えれば安心なのかもしれませんが、味わいや風味的には実は大きな問題があるんです。生ハムは、1年半から長いものは2年位熟成させるんですが、必ず夏を越すわけなんですね。冷蔵庫のない時代に熟成庫の中につるしてある生ハムが、腐敗しないで済むのは塩漬けの効果だけではなく、蔵付きの乳酸菌の作用が大きいんです。日本の馴寿司などもそうですが、乳酸菌は腐敗菌を排除する力があります。ある種の抗生物質を作ったり弱酸性の環境を作って、雑菌の繁殖を抑えるわけです。それに乳酸発酵による独特のうまみや風味も見過ごせません。 ところが、エアコンや冷蔵庫を使うと肝心の乳酸菌が死んでしまったり活動が弱まったりして風味のないハムになってしまうんですね。それで、最近の生ハムは全体的にレベルが下がっているといわれています。つまり乳酸菌がつかない生ハムなんて、ただの干し肉なんですね。 このピオ・トジーニ社の生ハムは、200もある生ハム会社のうち今や3社ほどしかない“一切エアコンや冷蔵庫を使わない”という会社です。それができるのも、パルマの中でも生ハムの聖地と呼ばれるランギラーノ村にこの会社があって、その中でも一番山側に位置しています。アペニン山脈から山おろしの冷たい風が吹くので、生ハム熟成庫の窓を開閉することで、温度湿度をコントロールできるわけです。まあ、聖地たる所以ですね。窓の開閉を担当する係は、一番熟練の職人が当たるそうです。 じっくり19カ月乳酸熟成した生ハムは最高の味わいですよ!お値段のほうも平均的なパルマの生ハムの倍近いんですが、特に追加料金は頂かずにお出ししてます。レギュラーメニューに載せていますからお昼でも夜でもいつでも食べることができます!ぜひ召し上がってみてください。
Apr 7, 2013
-

蕪のポタージュ
蕪のポタージュです。蕪は皮を剥いて薄いブイヨンで煮るんですが、つなぎは米を使います。私が作る野菜のポタージュにはつなぎの定番が決まっています。 その前に、ポタージュpotagesというのは、フランス料理の汁もの全般のことでコンソメやコーンポタージュみたいなとろみのついたものやミネストローネみたいに具沢山のものもすべて含む言葉です。(ミネストローネはイタリア料理ですけど、同じようなキュルティバトゥールというスープがあります) で、ポタージュは、ポタージュ・クレール(澄んだポタージュ)つまりコンソメ系ですね。ポタージュ・リエ(つなぎの入ったポタージュ)これが、普通イメージするポタージュです。という風に大きく二つに分かれます。 さらに、ポタージュ・リエは、ピュレといって裏漉しした野菜などで作ったもの。クレームといって仕上げに生クリームをたっぷり使うもの。ヴルーテといって、小麦粉とバターで作ったルーを使ってとろみをつけ、仕上げに卵黄を加える濃厚なものなどがありますが、ヴルーテというのは今はあまり見ないですね、、、。ほぼ廃れてますね。クレームも今はヘルシー志向が強いので、あまりやらないかもしれません。ピュレは、野菜をミキサーにかければ出来るのでこのタイプが一番多いと思います。ただ、ピュレとクレームは最近は境目が無いという感じで、ピュレに少しクリームを入れるというのはよくあるパターンです。 よくあるのが、ピュレ・マイス(コーン・ポタージュ)、ピュレ・クレシー(ニンジンのポタージュ)、ピュレ・ポティロン(かぼちゃのポタージュ)、ピュレ・ポワロ(ポロ葱のポタージュ)、ポタージュ・サンジェルマン(グリーンピース)などなどまあ、いくらでもあります。 それで、野菜のピュレのポタージュは、野菜単体だけではとろみが足らなかったり滑らかさに欠けることがあるので、何かのつなぎを入れることが多いです。そのつなぎが、私の場合自分定番が決まっているんです。 蕪とニンジンはお米。ポロ葱とグリーンピースとカリフラワーは小麦粉。カボチャやサツマイモはコーンスターチという感じです。ちなみにジャガイモの時はつなぎは入れません。 なぜそうするのかという理由については、カボチャとサツマイモの場合は明確な理由があって、コーンスターチで軽くとろみをつけることによって液体の浮力がまして、カボチャやサツマイモの粒子が浮き上がって滑らかに感じます。米は、とてもニュートラルなつなぎで存在を主張しすぎないことが良いです。小麦粉の場合は、少しコクが出るような感じがします。 まあ、非常に微妙なニュアンスなんですけどね、、、。
Apr 5, 2013
-

Ca Marche 神戸サ・マーシュの西川シェフご来店
昨日は、神戸のパン屋さんサ・マーシュの西川シェフが一家でご来店。春休みに子供さんたちとディズニーランドに来たついでに、サンク・オ・ピエに食事に来てくれました。 西川シェフは、日本ではトップクラスのパン職人で、著書も数冊出していてテレビや雑誌などにもよく出ている有名シェフです。311の震災の少し前に幕張メッセでパンとパン焼き窯の大きなイベントがあったときにデモンストレーションできていた西川シェフが、小麦粉関係やパン焼き窯のメーカーの方たちと偶然サンク・オ・ピエに食事に来てくれた以来の御縁です。その時一発で私の料理を気に入ってくれて、パンの話や料理の話で意気投合しました。 昨夜もまずは再会の固い握手から、、、。最後は職人仕事の継承の難しさなどを話し合って、とても楽しい時間でした。「神戸の仲間を紹介したいから、中村シェフも神戸に遊びに来てください」と誘われました。神戸にはソムリエの友人もいるので、近いうちに行こうかな?と思ってます。 さて、桜が咲いたと思ったら急に寒くなったり今日は爆弾低気圧が来てるようで、天候が不安定なのは春らしいのかもしれませんが、毎日何を着て出ようか悩みますね。 4月から恒例のパルマ産生ハムピオ・トジーニを始めました!私が大きな包丁で、切りたてをお出ししてます。やはり生ハムは切り立てが香りも風味もあっておいしいですよ!ぜひ味わいに来てください。 それから、サンク・オ・ピエ4月5月のコースも好評ご予約受付中です!よろしくお願いします。
Apr 3, 2013
全9件 (9件中 1-9件目)
1