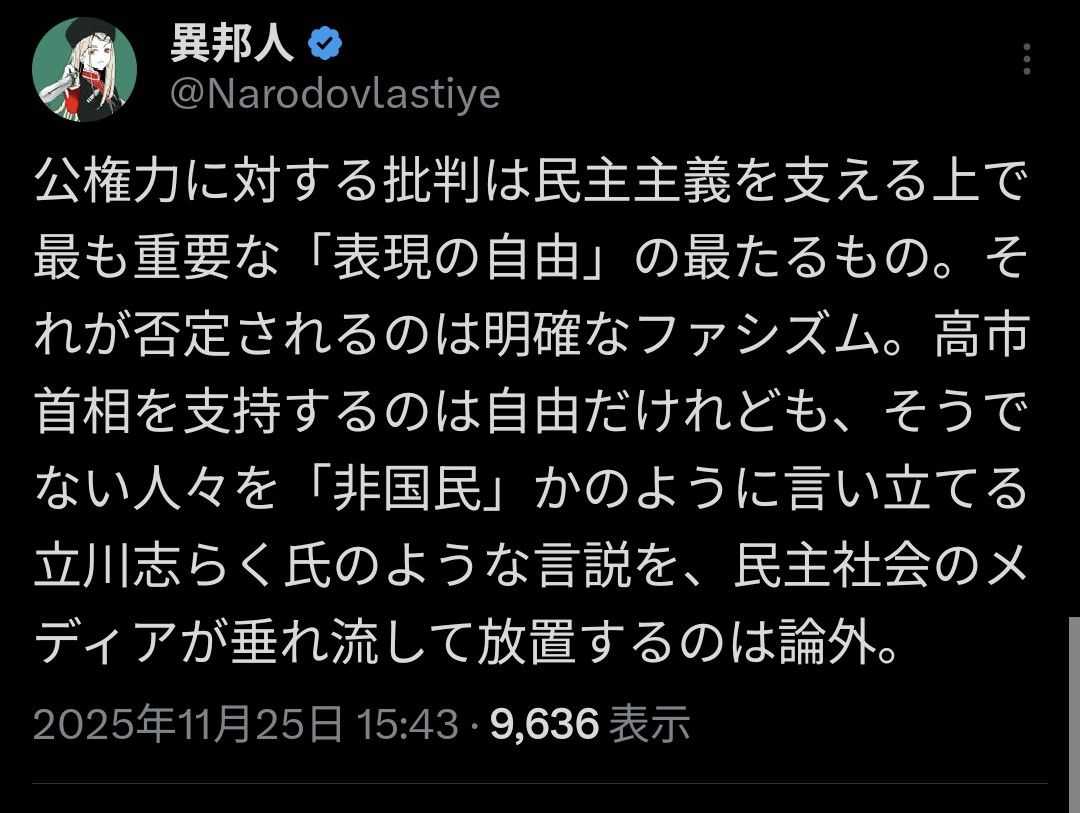2009年04月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
引越しました。
このたび住みなれたこの場所からラジオデイズ界隈の長屋へと引っ越しました。新しい住所はhttp://www.radiodays.jp/blog/hirakawa/です。店主敬白
2009.04.23
コメント(4)
-
『経済成長という病』重版決定。
川治さんからお電話があり、重版決定ということで、うれしい限りです。
2009.04.21
コメント(5)
-
いつか、鉄の匂いのする本を。
なーんか、調子悪い。食道のあたりが、しくしくと泣いているのである。お客さんにご心配をおかけするのも何なのだが、病院にいくとするか。めんどうだけど。『経済成長という病』は、お蔭様で好調な出足のようである。BK1の、経済・ビジネス部門の四位にランクインしてきた。講談社の岡本さんからも、心温まるメールをいただいた。「週末に改めて『経済成長という病』を通読しました。 本当にいい本だなあと、嬉しくなりました。」嬉しくも気恥ずかしい限りであるが、よい本であるとの声をちらほらといただき、著者としては冥利に尽きるというものである。で、もうひとつ書いているものがあってこちらはまだ発表の予定が無いのだがタイトルは『店主の囁き』(仮)というものでこのブログに近い内容の、どうでもいい話を、俺にとってはどうでもよくねぇんだといったスタンスで書き綴った、極私的社会時評(すでに言語矛盾だね)なのである。このラインは俺が最もやりたい仕事なのであるが、出版社の営業的にはもっとも手を出したくないジャンルの本なのかもしれない。だから引き取り手がいない。バジリコの安藤さんには、ビジネス原理論三部作の最終作を書きますからとお約束しているのであるが、こっちは、まだ時間がかかりそうである。生きているうちに書けるかどうか(みたいな)気の遠くなる作業なのである。「春は鉄までがにおった」と、小関智弘さんは小説『錆色の町』を結んでいる。そして、後にルポルタージュ作品『春は鉄までが匂った』を書き上げる。まさに、鉄の匂いがする本だが、この鉄の匂いをありありと実感できる読者がどれだけいるのだろうかとも思う。鉄の匂いを肌身に感じることのできる人々の多くは、小関さんの小説を読まない。ただ、あまり多いとは思われないごく少数の読者にとっては、この作品が語りかけてくる風景は、もはやつくりものの世界(虚構)であることを超えた確かさと重さをもったものとして実感されるはずである。俺も、こんな本が書きたいがなにぶん才能がないので、原理論のようなものを書いているのである。
2009.04.21
コメント(1)
-
ラジオの庭の百花繚乱。
店主の新本、好評(贔屓目ですが)発売中です。さて、自分で言うのもおこがましいが、ラジオデイズのラインアップの充実振りが凄い。トップの電子紙芝居に出てくる面々は立川談笑(店主イチオシ)米粒写経(一平君の顔が笑える)加藤和彦(あの加藤和彦でんがな)大瀧詠一(ご存知師匠)大貫妙子(ご存知歌姫)柳家小ゑん(卒業写真って)三遊亭白鳥(だいじょうぶなのか)半藤一利(昭和史の語り部)田中宇(国際経済解説まくしたて)雨宮処凛+湯浅誠(格差社会批判の旗手)といった具合である。『ラジオの街で逢いましょう』では内田樹教授と店主の漫才を二週連続でインターFMから放送したものもインターネット放送している。と云うわけで、騒がしくも、活気に満ちた風景が展開されているというわけだ。本日より書店に『経済成長という病』が並んでいる。いつもながら、うれしいような、はづかしいような、先行きが思いやられるような、新鮮な気分である。自分で言うのもなんですが、この本、けっこう面白い。「終章」の「本末転倒の未来図」だけでも、立ち読みで、是非お読みいただけると幸いです。さて、長年住みなれたこの長屋とももうすぐお別れである。現在某所に新築中の長屋へ引っ越すことにしているからである。大家さんの楽天さんには随分お世話になりました。お世話になっておきながら、なんなんですが、ここのデータは、エクスポートできないのでこのままこの長屋に塩漬けにして残しておくことにします。もうひとつは、ある日から突然、店子に無言で、コマーシャルが居座り始めたことです。無料長屋とはいえ、せめて店子にひとことあってもよろしいんじゃないのかと思うわけですよ。でもまあ、「いろいろあるよいろいろね」ってことで、大家さんのお陰で、随分面白い体験をすることができました。感謝しております。ええ、感謝しておりますとも。新天地の住所は、後日当ブログにてお知らせいたします。お客様におかれましては、今後とも、引き続きご贔屓に。
2009.04.17
コメント(6)
-
本、できました。
来週あたまには書店に並びます。よろしくです。講談社現代新書。777円。スリーセブンですな。140Bの中島社長が、最初の心温まる書評を書いてくれました。
2009.04.15
コメント(6)
-
腐ってもミシュラン。
ミシュランガイドの阪神間格付けに関して地元で格付け拒否があったり、格付けされることへの反発があったりと、ちょっとした騒動になっているらしい。で、騒動の中心には、いつもこの男がいる。江弘毅。岸和田で、だんじり遣り回しという伝統的騒動の中心にいる男である。その、江さんから興奮した電話があり、メールが飛んでくる。「週刊誌に頼まれて、こんなん、書きましてん。もう、えらいこっちゃ」何がえらいことなのか、不明であったが、漸く事の次第が飲み込めてきた。事の顛末に関しては、やはり江さんから襲撃を受けていたウチダ教授が江理論の分析も含めてブログで書いている。阪神間の料理人、関係者、一般人の気持をひとことでいえば、「ミシュラン、なにを偉そうな」ってことだろう。「てめえらなんぞに、格付けされてたまるか」ということである。でも、「ミシュランはやっぱり偉くなくはないわけであって、影響力もあるし、星くれたら嬉しいし、でもくれなかったらえらいこっちゃし・・・」ってな気持もどこかにある。文句をいいながらも、それが顔に出ている。この微妙な心理が面白いところである。もし、何の権威も無いやつが、偉そうに「格付けしたるわ」と言ったとしても「あほか」といった感じで、誰も相手にはしないだろう。ミシュランは腐ってもミシュランなのである。問題は、ミシュランは本当に腐っているのかどうかということである。で、江さんの記事を読むと(全文は、たぶんどこにも掲載されないとおもうが)どうも、腐りかけているという印象である。責任者の態度が、どことなく横柄になっており、料理の本質について知悉しているとは思えないような覆面調査員が街場をうろついていたり、調査と称して、客としての最低のマナーを逸脱したりといった話があちこちから聞こえてくるようになる。そのどれかは、ガセネタであり、どれかは真実であるだろう。だが、それらのほとんどすべてがガセネタだったとしても、格付けをやっているミシュランが腐るのは当然だと俺は思うのである。長い間、人様の仕事を格付けし、しかも、その格付けがある程度の権威を獲得しているとなれば、そこにかかわる人間は当然のように、自分には格付けする資格があると思い込んでしまうだろう。俺がその立場にあったとしても、おそらく事情は変わるまい。格付けという言葉には、そこにすでに格付けするものとされるものという上下序列の関係が含まれている。そして、絶対的な権力は絶対的に腐敗するように格付けするものもまた絶対的に腐ってくるのは世の常なのだ。料理を「もてなし、もてなされる」というコミュニケーションだと考えれば、料理人と客は、相互に対等であり、相互に相手に対して敬意を贈与するというのが理想だろう。威張って客を選ぶラーメン屋とか、店を格付けする調査員とかは、はなからコミュニケーションの邪道なのである。邪道がいけないと俺はいいたいのではない。邪道を楽しむ自分は外道であるとの自覚があれば、邪道も外道も案外楽しめるものである。ただ、邪道を自覚せずに権威だと勘違いしたり、外道なのに、食通ぶったりしているのを見るのはご勘弁願いたいということである。だいたいさ、星が何個とか、ミシュランが選んだとかの講釈を垂れられたら酒が不味くなるじゃねぇか。酒は静かにのむべかりけり。これが基本というものである。
2009.04.14
コメント(3)
-
牛ぷらす牛カレーの男。
午後護国寺の講談社で、週刊現代の取材を受ける。来週末より発売予定の『経済成長という病』の著者インタビューである。久しぶりの、講談社。随分立派なタワーになっている。待っていてくれたインタビュアーは、なんと、ミシマ社の大越くんであった。確か以前は、S会議という出版社におられたが、「いやぁ、ヒラカワさんの『反戦略ビジネスのすすめ』を読んで会社を辞めちゃったんです」と第一声があった。そういえば、あの本は、随分ひとさまの人生の決断に関わったようである。恐ろしいような、申し訳ないような心持ちである。で、質問の第一声は「この本を書いた動機は?」というものであった。リーマン・ショック以後、経済的な問題点に関しては、いろいろな人が、様々な媒体で発言し、総括をしている。その総括の仕方そのものに対しての疑問がひとつ。もっと重要なことは、ここに至るまでの、おれ自身をふくめて人々の心理的な問題点に関してはまだ総括の糸口さえ見出せてはいないということである。経済成長至上主義、市場万能主義を下支えしたのは、消費者の欲得そのものであり、その欲得と無縁であったといえるものはいないだろう。そのこと自体が悪いといっているのではない。ただ、過剰な欲得をうちに抱いている俺たちは意図してであれ、否応無くであれ、「時代の加担者」であったのであり、そのことを抜きにして、心理的総括などできないだろう、というようなことを、一気にまくしたてる結果となった。夕方、大阪の140Bのいがぐり社長中嶋さんから携帯に電話。今晩はかれとお会いする約束をしていたのである。当然のように、忘れていたのであるが、「了解了解、目黒あたりでね」と答えて目黒へ向かう。いつも大阪で飯をおごってもらっているので、今日は俺が日本一うまいと思っている「こんぴら茶屋」の牛カレーうどんをおごる番なのである。「どうだい、うめぇだろ。で、中嶋さんは大食いなの?大食いのひとは、残り汁にご飯を入れて食べるといいぜ」と解説しはじめたら、「じつは、ちょっとお待ちしている間に吉ぎゅうで牛丼を軽く・・・」との返答である。あきれた、いがぐり社長である。それでも、最後の一滴まで汁をすすってけろりとしているのである。「来週あたり、新しい本が出る」と本の宣伝をしたら「こんどのは、なんちゅう病(やまい)でしたっけ」ときた。俺も、すっかり病が板についてしまったようである。
2009.04.10
コメント(3)
-
白髭橋。
写真は、白髭橋に沿って立つビルの谷間のビオトープに浮かぶ桜の花弁2枚。地上は、本日満開。今週日曜日夜11:00よりインターFM(76.1MHz、関東エリアのみ)で、ウチダくんと漫才やります。
2009.04.09
コメント(3)
-
飼い犬の遺言(再録)。
まるの一周忌である。(合掌)以前にも掲載した、『飼い犬の遺言』を再録して、桜の季節に西行のように逝った(そんなかっこよくはないか)まるを偲ぶこととする。「犬を飼おうと思うが、どうだろうか」何となく発した一言は、食卓での会話ではなく、オフィスでの管理部員たちとの世間話の中においてであった。会社で犬を飼おうというのである。駄目ですよ、無理ですよ、という答えが返ってくるかと思ったら、意外にも社員たちは歓声を上げたのである。それが、私と駄犬まるの不思議な道行きの発端だった。 それからほどなくして、生まれたばかりの真っ黒いラブラドール犬がダンボールの箱に入って会社にやってきた。よちよちと歩くぬいぐるみのようなその生き物が現れたときには、社員全員が息を飲み、拍手が起こった。何でも両親はアメリカのチャンピオンなんだそうである。血統書つきである。代金不要、しかもとんでもない器量よし。 数日は、私が家に持ち帰ってその犬の面倒を見ていた。 ところが、である。 「会社でラブラドール・レトリバーを飼うなんて、無謀だと、捨て犬救助のボランティアの方に言われました。犬にもかわいそうだって。レトリバーは、いつもそばに人がいられるような環境で、走り回れるような場所がないと神経衰弱になってしまうそうですよ。」奇特なボランティアの方は金木さんという方で、その方面では有名な方であった。 確かに私の会社のオフィスは秋葉原の電気街の真ん中にあり、とてもではないが運動量の多い大型犬を飼うような場所ではなかった。週末に飼い犬禁止の私のマンションにつれて帰るわけにもいかない。黒いちび犬は、丸い目で私を見つめている。どうしたものかと唸っていると、金木さんからひとつのアイデアが出された。 彼女の家には、保健所から救い出した雑種犬がおり、レトリバーは別の引き取り手を見つけるので、その雑種犬と交換したらどうかというのである。 そんないきさつがあって、まるが会社にやってきた。レトリバーの子犬は、築地の刑事さんが引き取り手となった。(二年後に送られてきた写真を見たら、すでに面影は消えて堂々たる大型犬になっていた。)さて、アメリカズチャンピオンの令嬢と交換されてやってきたのは、人の目を直視できないおどおどした冴えない雑種犬であった。何処をうろついていたのか、痩せていて、毛並みはあまりよくない。年齢不詳。ミッキーマウスのような黒柴犬模様だが、耳は垂れている。いや、垂れているというよりは、グライダーの羽のように水平に広がっている。無様だが、歩くたびにそれがひらひらと揺れる姿は愛嬌があった。特徴といえばそれくらいのもので、いつも伏目がちで何かに怯えているようでもあった。聞けば、保健所で、あと二日後に処分される運命だったところを、金木さんが救い出し、里親を探していたということであった。 出会った最初の頃は、目を合わせようとすると顔を背けた。助手席に乗せると、立ったまま身体を硬直させている。声は全く出さない。どこか、人間を避けている風でもあった。虐待という言葉が浮かんだ。私は当分の間、こいつと一緒に会社に寝泊りすることにした。どうも、目が離せないような心持ちになってしまったのである。時折自宅へ連れ帰ったが、自宅マンションは飼い犬禁止なので、夜中にそっと自室へ入り、早朝は車に乗せて家を出るという生活であった。どこかに留め置くことができなかったので、いつでも、どこへでもこいつを連れて回るということになった。客先へ回るときも連れて行き、商談の間は車で待たせた。平日は会社に泊まり、休日は広尾にある、ドッグ入店可の喫茶店で何時間も過ごすという変則的な日常であった。この難民生活が三ヶ月続いた。人と目を合わせなかったまるが、私には徐々に心を開くようになり、散歩をねだったり、食べ物を要求するようになった。何より、多摩川の川原を走るのが大好きで、尻尾を振って跳ねるように駆ける姿を見ていると、こちらまでうれしくなったものである。「元気になりやがった・・・」 そして四年半が経過した。昨晩、夜中の一時二十分まるが死んだ。唐突な死であった。一週間前あたりから急に歩行が覚束なくなり、昨晩八時ごろ、三宿の病院へ運び込んだときには自分の足で立てない状態で、荒い呼吸がお腹を波打たせていた。日曜日で、休診日であったが、外出先から急遽戻ってくれた先生は、白衣に着替える閑も無くすぐに点滴を開始し、検査をしてくれた。ひどい貧血状態で、体内で出血している様子であった。しばらく小康状態となったが、時折、悲鳴のような泣き声を出して、手足をばたつかせた。動かすこともできず、とりあえず一日は、入院して様子をみようということになった。夜十時ごろ先生から電話があった。大量に吐血したという。その後は苦しがる力も無くなって脈が遅くなり、月曜の朝を迎えることは無かった。多臓器不全ということであった。 享年、不明。野良犬らしい死に方であった。 「始めより今にいたるまで、曾て端首無し」空海の『三教指帰(さんごうしいき)』の言葉である。われわれは、何処から来て何処に行くのかを知ることはできない。端首は、人間の知性の埒外に朦朧と霞んでいる。まると私には、そんなに、哲学的な話は、似合わないが、まるもまた、何処から来たのか分からない野良犬であった。今にして思えば、不思議な機縁が重なって、私のところへやってきた。私は、生まれも、育ちも、年齢もわからない野良犬をハッチバックに乗せて東京の町を放浪し、会社に寝泊りした。食うことと、走ることだけに貪欲な、取り柄のない犬であったが、ただひとつだけ美点があった。それは底抜けに優しいということであった。どんな犬に寄せていっても、吼えたり、噛みついたりすることはなかった。吼える犬の前を通るときは、見て見ぬ振りをしていた。噛みつかれたこともあったが、反撃することはなかった。それでも、どんな犬にでも、誰にでも寄って行って頭をなでられるとすぐに踵を返して帰ってきた。まるが吼える声を聴いたのは四年半で数えるほどしかない。 優しさとは何だろう。レイモンド・チャンドラーではないが、強くなければ優しくはなれないというのは尤もな気がする。しかし、まるに限っていえば、どこをどう見積もっても強い犬ではなかった。弱い犬ほどよく吼えると言うが、まるは臆病者だが吼えることもなかった。カウリスマキの映画の主人公のように、ハードボイルドとは無縁な、臆病を絵に描いたような負け犬ぶりであった。そして、そのことと、優しさは表裏しているように見えた。臆病なものには、臆病者の領分というものがある。征服欲や上昇志向などは、はなから断念している。そんな風であった。それはこの犬の意図せぬ美徳であると言ってもよいと思えた。わたし(たち)は、どこかで勇気のある強い男になりたいと思って生きている。しかし、もし臆病であるがゆえに、優しさを獲得できるのだとすれば、勇気など必要ないのかもしれない。臆病もまた力になりうる。それが、まるの遺言であったと思う。
2009.04.07
コメント(20)
-
店主の見解。
上野の杜の花見のように、カフェ・ヒラカワのコメント欄が騒々しい。理想化された読者のお一人であるまろさんの貴重なご意見もあって、店主の見解も、書いておきたいと思う。ここのコメント欄に関していえば、いや、どこのコメント欄も、コメントと呼べるものもあれば、どうでもいいような雑言の類もある。何だか意図がよく判らないような、サイト誘導もあれば、笑えないおちゃらけのようなものもある。まことに誠意のある助言もあれば、人の背後から石を投げるものもいる。要するに味噌も糞も一緒に落ちているのが、コメント欄というものの宿命であり、インターネット空間の可能性であると同時に限界でもあるということだ。ここは、その名前のとおり、バーチャルなカフェであるから原則としてどんな客がこようと、お客はお客である。ただ、原則としてお金を戴いている商売をしているわけではないので、お客はお客だが、実商売におけるお客様に対する前だれ精神は、このカフェの店主にはない。面倒になれば、すぐにでも店を閉じることにしている。どんな客が来ているのかは、確かに店主の責任でもあるが、ほとんどのお客はコメント欄に書き込みをしない方だろうから、実際のところは、どのようなお客さんがいるのかはよく判らない。どんな書き込みがあるのかに関しても、店主の責任という考え方も理解できなくはないが、俺はどんな書き込みを残すかに関しては、一切の責任はないと考えている。どれを俺が読んで、どれを嗤って、どれを無視して、どれを晒しておこうがそれは俺の密かな楽しみであり、あらゆるブログ主が持つべき愉悦のひとつだろうと思っている。興味深く思うこともあれば、つまらないと思うこともある。客が店を品定めするのと同じように、店主も密かに客を品定めしているだけである。人間には実にいろいろな思考をするものがあり、実にいろいろな言葉を発するものがあるものだと思うだけである。それでも前に、面倒くせぇなぁと思って一度店を閉じた。しかし、そのことによって、大切なご指摘や、俺のカン違い、いい間違いのご指摘まで封鎖してしまうことには、躊躇があった。このブログに書き込む記事に関していえば、昼休みに喫茶店で大急ぎで書き込んだり、ほとんどメモ代わりに速攻で書き付けることもあって、いや、そもそも俺は、よく間違えるのであり、それをご指摘いただけるのはまことにありがたい事なのである。ただ、このコメント欄で何か議論をしたいとは到底思わない。議論を尽くすには、はなはだ不便な場所であるし、条件反射的な反応をする野次馬も多い。議論のための議論にはほとんど意味はないだろうし、興味も無い。もし、本当に議論が必要であれば、お互いの重要なものを賭して、実名を持って、言葉のやり取りをしたいと思う。場合によっては、生存を賭して、言葉に全重量を賭けなければならないこともありうる。だか、その場はこんな場末のカフェの片隅ではないはずである。異論は、ご自分のブログで思う存分発信していただければよい。それが、意味のある意見であれば必ず人はそれを発見し、その言葉は届けられるべき人に届くはずである。もし、それほどにも「言葉」というものを信じていなければ、まだるっこしくも、迂遠な道すじを経て届けられる「言葉」を使ってやりとりする必要もまたないだろう。「言葉」のやりとりに関していえば、自分が相手の「言葉」から受け取れたものと同等以上のものを相手に届けることもまたできないだろうし、自分が相手に届けようとしている「言葉」の水準以上のものを、相手から届けられると期待することもできないということである。というわけで、このコメント欄は今までどおり、カフェの裏手に放置された空き地のようなものと俺は考えているし、お客さんもそのようにお考え戴きたい。空き地には、素敵な拾い物が落ちている場合もあれば、ガラクタが吹きだまることもある。必要なものがあれば、俺が取りに行くだけである。お客さんが必要なものを、店に取りに来るようにである。
2009.04.06
コメント(17)
全10件 (10件中 1-10件目)
1