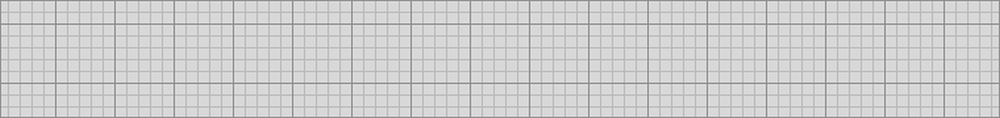2025年06月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

氏物語〔29帖 行幸11〕
源氏物語〔29帖 行幸11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。多くの役人たちが付き従っており、その場には十数人の身分ある者たちが内大臣を取り巻いていた。やがて酒宴となり、何度も杯が回るうちにその場の人々も次第に酔いがまわってきて、皆が内大臣の豊かな身の上と幸運について語り合い、褒め称えた。源氏と内大臣は久しぶりに面と向かって話をし、自然と昔の出来事や若い頃の思い出が語られることになった。普段、世間ではそれぞれが一つの柱として並び立っているがゆえに、お互いに競争心を抱くこともある。だが、こうして顔を合わせて語り合うと、そんな意識は薄れ、古い友情の感情が自然とよみがえってくるのだった。この場面は、人間関係の微妙な心理の綾や、身分や立場の違いがあっても共に過ごした時間の記憶によって和らぐ感情の描写が際立っており、源氏物語が単なる恋愛や政治だけでなく、人間の心の動きに深く踏み込んだ物語であることをよく示している。源氏と内大臣が親しく語り合っているうちに日は暮れていき、杯も引き続き人々の間で回されていた。内大臣は、今日は自分から訪ねてきたが、正式な招待があったわけでもないため、無礼にあたるかもしれないと少し恐縮していた。そして、あとで叱られるのではないかと冗談めかして言った。すると源氏は、自分のほうこそ責めを受けるようなことが多いと意味深に返した。その言葉に内大臣は、先ほどから気にかかっていた話題がこれなのかと直感し、口をつぐんだ。源氏はさらに、昔から内大臣以上に自分に親しかった人はいないと語り、かつては同じ志を持って政治に関わっていこうとまで考えていたことを振り返った。しかし年月が経つにつれ、かつての友情とは思えないような行き違いもあったと認めつつ、それは些細なことに過ぎず、根本の気持ちは変わっていないと話した。そして、もう年齢も重ねた今、昔のことが懐かしく、なかなか会えないのが寂しくてならなかった。
2025.06.30
コメント(23)
-

源氏物語〔29帖 行幸10〕
源氏物語〔29帖 行幸10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。内大臣の家では、自分の子だと名乗り出てくる者を広く面倒見るようなところがあるが、それでもなぜ源氏が彼女を迎えたのかと尋ねた。源氏は、そうなるだけの理由があるのだと答えた。詳しいことは内大臣の方がよく知っているはずだし、これが明るみに出ると世間の好奇の目を集めて噂が立つに違いないと思われるので、中将にさえ詳しくは話していない。だから大宮にも、このことは他言せず秘密にしてほしいと念を押した。一方、内大臣の方でも、源氏が三条の宮を訪れたことを知っていて、簡素な暮らしをしているその宮のもとに、太政大臣である源氏が来たとなると、その待遇に苦労するのではないかと気にかけていた。家にいる人手も少なく、前駆(先導する従者)の応対や座敷の用意もままならないだろうと案じて、自分の息子たちや殿上人などを三条の宮に差し向け、酒や菓子なども持たせて、もてなしが不足しないようにと指示を出した。自分自身が訪ねるのはかえって騒がしくなりすぎるだろうから控えようと考えていたところへ、大宮から手紙が届いた。その手紙には、六条院の源氏が見舞いに来てくれたけれど、こちらは人も少なく十分な応対ができないことが恥ずかしく思われる。だから、わざと誘ったようには見せずに、自然なかたちで訪ねてきてくれないかと書かれてあった。大宮は、内大臣と源氏とが直接会って話す機会をつくろうとしているのだった。この手紙を読んだ内大臣は、ひょっとするとこれは雲井の雁と中将の縁談について、許しを得ようとするための口実なのではないかと推測した。大宮の体調が悪く、長くは生きられないかもしれない中で、その遺志として頼まれる形になれば、源氏がそれとなく中将のことで触れてきた以上、今さら断るのも難しくなるだろうと内大臣は考えた。中将は表面的には落ち着いていて無理に結婚しようとはしていないが、その内心を思えば、親としては何かの機会に一歩譲る形で許しを与えてやりたいという気持ちもあったのである。
2025.06.29
コメント(23)
-

源氏物語〔29帖 行幸9〕
源氏物語〔29帖 行幸9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。自分の家の子女としても特に見劣りするとは思っていなかったので、その出仕を引き受けてもよいと考えるようになった。たしかに尚侍という役職は、貴族の女性にとっては後宮の華やかな存在ではないかもしれないし、行政的な事務を任されることもある。しかし源氏の考えでは、どのような職でも、仕事の内容ではなく、その職についている人の人格が職の価値を決めるのであって、玉鬘のような人物であれば尚侍という役職も立派に果たせると確信していた。そうした思いをもって玉鬘の年齢を確認しようとした時、初めて、彼女が自分の子ではなく、大臣の実の娘であるという事実を知った。この語りは、源氏が玉鬘を育ててきた理由と、そのうえで彼女を宮中に出仕させようとする意図を正直に打ち明けるものであると同時に、大臣への真摯な謝意と配慮の現れでもある。自分の娘だと信じて引き取った過去を悔やむのではなく、縁として大切にしてきたこと、そしてその結果として今のように才色兼備の女性に育ったことを誇りに感じていることが読み取れる。また、宮中での役職の意味や、それに対する源氏の価値観もよく表れており、単なる個人的な感情ではなく、政治的・社会的な視点から玉鬘の将来を考えていることが分かる。源氏は、大宮の容体が少し良く見えたこの機会に、祝いの儀式である玉鬘の裳着を予定通りに行いたいと考え、その旨を伝えた。これまでの事情をきちんと話したうえで、内大臣にもぜひ来てほしいと思っていたが、自分から言い出すのはためらわれた。だから、大宮からさりげなく内大臣へ手紙を出してほしいと頼んだ。大臣が病気を理由に儀式への出席を断っていたが、今こうして大宮の様子も悪くはないと知ったので、このまま計画を進めたいというのが源氏の考えだった。これに対して大宮は、少し驚いた様子で、どうしてその女性(玉鬘)が源氏のもとに引き取られたのか疑問を口にした。
2025.06.28
コメント(26)
-

源氏物語〔29帖 行幸8〕
源氏物語〔29帖 行幸8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。だが、内大臣はどうやらきっぱりと関係を断とうとしている様子で、それを見て、自分が口を出したのは軽率だったと後悔している。とはいえ、どんな問題にも「清める」ということがあり、大臣が本気で取り消すつもりなら噂などは抑えられるのではないかと思う。しかし、実際に起こったことを人々の記憶からきれいに消し去るのは簡単ではない。そして、どんな立派な親であっても、子の代になるとその威光や評価は落ちてしまうもので、親ほどには尊敬されず、愛されることも少ない。だから中将のことを思うと気の毒でならない、と語った。そうしたやりとりのあとで、源氏は本来の目的――玉鬘の出自の件や裳着の儀式についての説明へと話を進めていった。源氏は、大臣に伝えたいと思っていることとして、まずはっきりさせたい過去の経緯を語り始めた。ある時、玉鬘という娘を自分の娘かもしれないと考えて引き取った。もともとその娘は、大臣の血縁者だったわけだが、その事実を最初の段階では誰も教えてくれなかった。だから源氏は、そのことをよく調べもしないまま、子どもが少ない自分にとっては何かの縁かもしれないと思い、世話を始めたのだった。ただし、玉鬘とあまり近しく接することもないままに時間だけが過ぎた。ところが、最近になってどういうわけか、この玉鬘のことが宮中に知られ、そこから正式な沙汰が下った。その内容はこうだった。今、尚侍(ないしのかみ:女官の最高位の一つ)の職が空いており、そこに任命すべき適任者がいない。そのため、現在任にあたっている数人の女官では力が足りず、実務もままならないという現状に対して、貴族の家柄で、評判もよく、家庭の雑事に煩わされず職務に専念できる女性を新たに選出すべきだというのが宮中の意向で、源氏はこの事情を聞かされ、玉鬘をその候補として推すよう求められた時、まだ彼女の素性を深く知らないままでいた。
2025.06.27
コメント(25)
-

源氏物語〔29帖 行幸7〕
源氏物語〔29帖 行幸7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。もう自分の命に未練はない。周囲の人々が次々と亡くなっていく中、自分だけが長生きして取り残されているのは、他人から見ても見苦しいだろうと思っていたので、いっそ早くあちらへ行きたいという気持ちもあったのだが、そんな中、中将が驚くほどに親身に尽くしてくれて、心から気遣ってくれる姿を見ていると、それも捨てがたくて、もう少し生きていようという気にもさせられるのだった。大宮は、最初から最後まで涙を流しながらそう語った。その声の震えや、言葉の一つひとつが、源氏には深く胸に沁みた。昔話や今のことをひとしきり語り合ったあとで、源氏は言った。内大臣は毎日来ているだろうが、自分がここにいる間にもし来てくれることがあれば、ぜひ会って話がしたい。どうしても話しておきたいことがあるが、きっかけがなくてそのままになっているのだと。すると大宮は、内大臣は最近あまり見舞いにも来ない。公務が忙しいのか、それとも情が薄いのか分からない。話したいこととは何だろう。中将が不満に思っていることもあるが、自分は初めの事情は知らないものの、あの子に対してあまりに冷たい態度を取り続けていた。それを見るにつけ、いったん立った噂というものは、何もしなくても自然に消えるものではないし、逆に下手に扱えばかえって人からあれこれ言われるものだから、そうならないよう忠告したこともある。でも内大臣という人は、一度こうだと思ったことは決して変えない性格で、自分は不本意ながら見ているだけなのだと答えた。源氏はそれを聞いて、これは中将の件に違いないと察し、笑みを浮かべながらこう返した。いまさらどうしようもないことだから、もう許してやればよいと思って、自分もそれとなく願いを口にしたことはあった。
2025.06.26
コメント(23)
-

源氏物語〔29帖 行幸 6〕
源氏物語〔29帖 行幸 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。内大臣からは、昨年の冬から病気をしている大宮がいつ亡くなるかわからない状況なので、祝いの席に出ることは遠慮したいという返事が来た。中将も昼夜を問わず三条の宮に詰めて看病しており、心にも体にも余裕がない様子だった。源氏は、それなら裳着の儀式も延期すべきだろうかと一度は考えた。だが、大宮が万一亡くなれば、玉鬘は孫として服喪の義務が生じる。それを知らないふりで儀式を行えば、自分にとっても罪深いことになる。だからこそ、宮がまだ生きているうちに、裳着を済ませ、大臣に真相を伝えようと決意した。源氏は、三条の宮を見舞うついでに、大臣に会うことにした。表向きは内密の訪問という形だったが、その様子はまるで行幸のように威儀を整えたものになってしまった。近頃の源氏はますます光り輝くような美しさを増しており、それを見た大宮は、病苦が少し和らいだように感じた。体を脇息に預け、弱々しいながらも落ち着いて言葉を交わすことができた。源氏は、「そう悪いご様子ではないようで安心しました。中将がとても心配しているので、どれほどおつらいのかと案じておりました。私も特別なことがない限りは御所などへは出ないし、まるで朝廷の人間ではないかのように引きこもっています。思ってもすぐに行動に移せなくなってしまい、失礼してばかりです。世の中には私よりずっと年上でも、腰を曲げながら役目を果たしている方もいますが、私は体力的にも気力的にも弱くて、怠けているのではなく、どうしてもできないのです」と語っていた。大宮は、年のせいだと思ってずっと我慢してきた体調の悪さが、今年に入ってからはどうもただの不調ではない、病が深刻なものかもしれないと感じるようになっていた。そして、もう一度こうして源氏に会うこともできずに終わるのかと不安に思っていた。だからこそ、今回の見舞いにとても感激し、命が少し延びるような気さえした。
2025.06.25
コメント(24)
-

源氏物語〔29帖 行幸 5〕
源氏物語〔29帖 行幸 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。源氏は、「そんなことはない。あなた(玉鬘)だって、もし帝のお姿を拝見すれば、おそばに仕えたくなると思う」と言って、また手紙を書いた。手紙には、「あかねさす光が空に曇ることなどないのに、どうして昨日の行幸で目をそらしてしまったのだろう」という歌を添え、どうしても宮仕えを決意するようにと、粘り強く勧めていた。そして源氏は、まずは裳着の式を行うことに決め、その準備に取りかからせた。自分では特別な儀式にするつもりはなかったが、源氏の家で行うこととなれば、どうしても自然に大規模で華やかなものになってしまう。しかも今回の裳着は、これを機に玉鬘の実の父である内大臣に真実を知らせようという意図もあったため、準備も格別に豪華になっていった。源氏は、この儀式を来年の二月に行おうと考えていた。そもそも女の子は、姫君のうちはどれだけ世間に有名であっても、親の姓や出自を明らかにしていないことも多い。玉鬘も今までは「藤原の内大臣の娘」とも「源氏の娘」ともはっきり言わずに通してきた。しかし、もし本当に宮仕えさせるなら、それは春日の神の氏に属する娘を帝の側に差し出すということになってしまう。それは制度上の問題にも関わることで、やがては知られることになるのだから、今さら取り繕っても仕方がないし、それを隠したまま出仕させるのは、自分の信用を損なうことにもなる――そう源氏は考えた。世間の普通の家では姓や家系を簡単に変えることもあるが、血のつながりというものは作為で断ち切れるものではない。だから源氏は、自然な流れとして、自分の寛大さを内大臣に示し、裳着の際にはその紐を結ぶ大役を内大臣に頼もうと決意した。
2025.06.24
コメント(23)
-

源氏物語〔29帖 行幸 4〕
源氏物語〔29帖 行幸 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。この歌は、おそらく昔、太政大臣が野への行幸に同行した時に詠んだ前例にならって作られたものだろう。源氏はこの和歌を送ってきた使者を丁重に扱い、その返歌として、「みゆきの雪が積もる小塩山の松原に、今日だけの足跡ではないでしょう」という歌を返したようだが、この歌の細かいところは筆者の記憶違いかもしれない。翌日、源氏は西の対にいる玉鬘に手紙を書いた。その手紙には、「昨日、帝のお姿を拝見しましたか? 以前話していた件について、どう決めるつもりですか」と、宮仕えの件に触れる内容が書かれていた。手紙は白い紙に気取らず簡潔に書かれていたが、その文字はとても美しく、玉鬘はそれを見て「もう、ひどいわ」と笑った。しかし同時に、自分の心がまるで見透かされているように感じて、少し恥ずかしくも思った。前日に源氏から届いた手紙には、「朝の曇った空のようにぼんやりしていた昨日の行幸では、空の光もはっきり見えなかった」といった内容の歌が添えられていた。玉鬘は、「何がどうということか、私にはよくわかりません」とだけ返していた。その手紙は紫の女王も一緒に読んでいた。源氏は、玉鬘に宮仕えを勧めている件について、紫の女王にも語った。「中宮は私の娘だから、同じ家からそれ以上の身分の者が出て行くことを、あの人(=玉鬘)は気後れしているのだろう。内大臣の娘という立場で宮中に出仕するにも、すでにその家から女御がいる以上、やはり引け目を感じるという気持ちもあるようだ。でも、まだ若くて宮仕えにふさわしい女性が、あれだけ気高いお方(=帝)を拝見してしまえば、もう断る理由なんてなくなると思うんだよ」そう言う源氏に、紫の女王は笑って、「まあ、あなたってば。たとえ帝がどんなに美しくても、それを理由に恋の気持ちで仕えるなんて、ちょっと失礼すぎると思わない?」と冗談めかして返した。
2025.06.23
コメント(24)
-

源氏物語〔29帖 行幸 3〕
源氏物語〔29帖 行幸 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。右大将は世間でも評判の高い重鎮ではあったが、今日の武官としての姿、つまり櫻を巻いた衣装に弓袋を背負った出で立ちは、非常に優雅で見栄えがした。ただし、その顔が浅黒く、髭が多く濃いことに、玉鬘は個人的に好感を持てなかった。男が白粉を塗った女のように白い顔をしているのは好ましくないとされてはいたが、それでもまだ若い玉鬘の感覚としては、色黒で髭の濃い男はあまり魅力的に感じられず、むしろどこか粗野な印象に見えてしまい、心の中で軽んじる気持ちさえ抱いていた。こうした中で、源氏は最近、玉鬘に宮仕えを勧めていた。これまでは、玉鬘自身が進んで勤めに出たいと思ったこともなく、特に無理に新たな苦労を背負うような気持ちにもなれず、御所に仕えるなど考えられなかったのだが、ただの一人の女房として後宮に入るのではなく、正式な高位の女官として帝に仕えるのであれば、それは自分にとっても立派なことであり、考えてもよいのではないかという気持ちが、少しずつ芽生えはじめていた。ちょうどその日、大原野で鳳輦(ほうれん=天皇の乗り物)が停まり、高官たちが天幕の中で食事をとったり、儀礼的な正装から直衣や狩衣に着替えたりしていた。その最中、六条院の源氏から酒や菓子などの献上品が届けられた。もともとこの行幸には源氏も供奉するようにと命じられていたが、その日は謹慎中であったため、参列を断っていた。そのかわりとして、使者に選ばれた蔵人の左衛門尉が、木の枝に括りつけた雉子を一羽、源氏のもとに届けた。このとき天皇から源氏にかけられた言葉は、女性である筆者がここにそのまま記すのは不敬になるかもしれないという配慮から、省略されている。帝は、雪深い小塩山にちなんで「しほの山に立つ雉子の古い足跡を今日はたどってみよう」という意味の和歌を詠まれた。
2025.06.22
コメント(21)
-

源氏物語〔29帖 行幸 2〕
源氏物語〔29帖 行幸 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。左右の近衛、衛門、兵衛に属する鷹匠たちは、大柄で目立つ摺衣を着ていた。ふだん見慣れないこのような壮観な行列に、都中の女性たちはだれもが見たくてたまらず、競って見物に出かけた。けれども、粗末な造りの車は人混みに押されて車輪が壊れるようなこともあり、無残な姿で立ち往生していた。行列を見るには、桂川の船橋のあたりが最もよい場所とされていて、立派な車が多く集まっていた。六条院の玉鬘も、この場所に見物に出ていた。彼女は多くの朝臣たちを目にした。皆が美しい衣装をまとい、化粧も施していて立派に見えた。天皇が鳳輦にお乗りになった姿のように、真に端麗で気品ある存在に比肩できるような人は、そこには一人もいなかった。玉鬘は、自分の父である内大臣のことを人知れず注意して見つめていた。評判どおりに華やかな雰囲気と貫禄のある、人生の盛りにある男には見えたが、だからといって誰にも圧倒的に勝っているほどの完璧さは感じられず、ただ周囲の臣下たちの中ではひときわ目立つ、優れた人物だと思える程度だった。周囲では、身なりの整った中将や少将、殿上の役人たちが、美男だの、格好いいだのと若い女房たちの間で噂になって騒がれていた。玉鬘にとってはそのような人々は特に心を引かれる存在ではなく、むしろ目にも入らず自然と関心の外に置かれてしまっていた。一方、天皇の姿は源氏とよく似ていたが、不思議とさらに一段と気高く、神々しいほどの美しさが感じられた。玉鬘はそれを見て、これこそが人間の世界で最も優れた美と呼ぶべきものだと感じた。もともと玉鬘は、源氏や頭中将など日常的に見慣れた美しい貴族の男性たちを基準としていたため、今日のような正装姿の朝臣たちはかえって平常よりも見劣りして映り、同じような顔立ちであるはずなのに、どれもこれも似たような印象の顔ばかりに思えてしまった。その中には兵部卿の宮もいた。
2025.06.21
コメント(24)
-

源氏物語〔29帖行幸 1〕
源氏物語〔29帖行幸 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔29帖 行幸〕 (みゆき) の研鑽」を公開してます。源氏は玉鬘に対して、できるかぎりの好意を注いでいた。しかし、その思いは公にできない恋であり、南の女王が以前に想像していたような不幸な結末を迎えるのではないかという不安を抱かせるものだった。内大臣は、どんなことにおいても形式や体裁を非常に重んじる性格で、少しでもそれを欠いた行いには耐えられない性分である。だから、もし源氏が婿という立場で玉鬘と関わるような形で世間に知られることになれば、内大臣は同情などまったく寄せず、むしろ非難するに違いない。そうなれば、源氏としても今さら世間から見て体裁の悪い、恥ずかしい立場に追い込まれることになるだろうと心配し、その気持ちが源氏の行動を慎重にさせていた。そうした状況のなか、十二月には西の郊外、大原野への行幸が行われた。このときは、都中の人々がこぞって見物に出かけた。六条院からも夫人たちが車を仕立てて見物に向かった。天皇は早朝六時に宮中を出発し、朱雀大路から五条通りを西へと進んでいった。沿道には人々が出した車があふれ、行列を見るための場所取りで混雑していた。ふだんの行幸ではここまでの盛況にはならないのだが、この日は親王たちや高官たちも皆、特別に立派な馬具や衣装を整え、随行する若者たちの背丈や装束まで美しくそろえられていた。左右大臣や内大臣、納言以下の人々まで全員が供に連なった。殿上の役人から五位、六位といった官人たちも、浅葱色の袍に紅紫の下襲という艶やかな衣装を身につけていた。時おり雪が舞い、空から舞い落ちる白い粒が一層華やかさを添えていた。親王や高官のなかには鷹狩の嗜みを持つ者もいて、野に出てからのためにきれいな狩衣を用意していた。
2025.06.20
コメント(26)
-

源氏物語〔28帖 野分 16 完〕
源氏物語〔28帖 野分 16 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。今はまだ幼さが残るが、もしも妙齢になったときにはどれほどの美貌になるのかと想像がふくらむ。昨日見た二人の美女を、もし桜と山吹に例えるなら、この姫君は藤の花だろうと中将は思った。高い木にからみつきながら、風にゆられて優雅に咲く藤の姿のように、しなやかで儚げで、見る者の心を静かに奪う。こんな美しい人々を、ただただ眺めて暮らしていけたらどれほど幸せかと思う一方で、彼女が異母妹であり、しかも義母の子という関係ゆえに、それが叶わないことを思い出すと、現実の冷たさが心に染みる。分別を持つ自分ですら、魂のどこかがふっと夢のほうへ引き寄せられていくような、不思議な感覚にとらわれていた。三条の宮のところへ行くと、宮は静かに仏事の勤めをしていた。若くて美しい女房たちもいたけれど、身なりや態度は盛りの家の夫人たちに仕えている人たちと比べるとどうしても見劣りしてしまう感じがした。顔立ちの整った尼女房が墨染めの衣をまとっている様子は、むしろこういう静かな場にはよく合っていて、なんとなく好ましく思えた。内大臣も宮を訪ねてきて、灯をともしてゆっくり話し相手をしていた。すると宮はふと、「姫君に長いこと会っていませんね。本当にどうしたのかしら」とぽつりと言って涙を流した。それを聞いて内大臣は、「近いうちにお伺いしましょう。あの子は自分で物思いにふけるようになって、だいぶ弱ってしまっています。女の子というものは持たないほうがいいものかもしれません。何かにつけて親の苦労が絶えませんからね」と言った。しかし宮は、まだあの昔の過ちを内大臣が完全には許していないのを感じて、それ以上話を続けることができなかった。内大臣の方はさらに続けて、「どうにもならない娘が一人いて困っているのです」と母宮に訴えた。宮は、「娘という名前がついている以上、そんなにおとなしくないわけがないと思うのですが」と返した。すると内大臣は、「そうはいかない。みっともない姿で、もう笑い話にでもししたいくらいですよ」と言っていた。(完)明日より29帖 行幸(みゆき) を公開予定。
2025.06.19
コメント(24)
-

源氏物語〔28帖 野分 15〕
源氏物語〔28帖 野分 15〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。中将は「これは良すぎて、俺にはもったいないな」と苦笑しつつ、それでも筆を手に取った。姫君の生母が明石の君であることを思うと、どうしても構えてしまう自分をどこか滑稽に感じながらも、淡い紫の薄様に向かって丁寧に墨をすり、筆の穂先をじっと見つめながら、しばし考えこんで手を動かした。その姿は物静かで、まるで絵のような色気があった。その手紙には「風騒ぎむら雲迷ふ夕べにも忘るるまなく忘られぬ君」という歌が添えられていて、中将はそれを穂が乱れた刈萱に結びつけた。すると女房の一人が、「交野の少将は紙の色と同じ花を添えたことがあるそうですよ」と言った。それを聞いて中将は「俺にはそんな風流なことはできないんだ。相手のほうも、そんな趣のある人じゃないしな」と答えた。その口ぶりには、女房たちに対しても一線を引いて打ち解けすぎないようにする彼らしい品のある態度がにじみ出ていた。中将はもう一通書いてから右馬助を呼び出し、手紙を託した。右馬助はそれを、身なりの良い童侍や心得のある随身の男に手渡し、使いとして送り出した。若い女房たちは、誰に手紙を出したのか、どんな内容だったのかを気にしてざわついていた。ちょうどその時、姫君がこの座敷に来ると言われて、女房たちは急いで動き出し、几帳の裂け目を引き直したりして準備に取りかかっていた。中将はいつもならあまり興味を持たないのに、この時はふと、昨日から今日にかけて見た美女たちと比べてみたくなり、妻戸の御簾に身を半分だけ入れて、几帳のほころびからそっとのぞきこんだ。姫君が入ってくるのが見えたが、女房が前を横切るのでその姿ははっきりとは見えなかった。淡紫の装束をまとい、髪はまだ裾までは届かないが、意識的に広げたような末のあたりが美しく、全体的に細く小柄な姿がいじらしく映った。おととしあたりにわずかに顔を見た記憶があるが、そのころに比べて格段に美しくなったように思われた。
2025.06.18
コメント(21)
-

源氏物語〔28帖 野分 14〕
源氏物語〔28帖 野分 14〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。秋が深まるのはいいことだが、こうも激しい気候では風情もあったものではないと、どこか諦めまじりに話していた。その散らかった染め物や織り物の色合いの美しさに目をやりながら、こうした微妙な色の取り合わせや見立ての巧みさにおいても、花散里は南の御方にも決して劣ってはいないと源氏は思った。たとえば、自身の直衣の材料となっている支那渡りの紋綾なども、初秋の草花を摘んで作った染料で手染めに染め上げたもので、その色のよさは目を見張るものがあった。「これは中将に着せたら似合うだろうな。若い人の肌によく映える色だ」そんなことを言って、源氏はそこをあとにした。一方そのころ、中将は母や姉など夫人たちの訪問にあちこち同行していたため、思いのほか時間がかかり、気がかりな思いで妹の姫君のもとへ向かった。風が強く肌寒い朝だったこともあって、まだ寝所にいると聞かされると、やはり気にかかって仕方がなかった。乳母が言うには、「まだお床にいらっしゃいます。今朝の風をとても怖がっておられて、起き上がることもできなかったのです」とのことだった。それを聞いた中将は、「今朝はひどい天気だったからな。本当はこちらで夜を過ごしてそばにいてあげたかったのに、宮様がひとりで心細がっていたもんだから、そちらの方へ行ってしまったんだ」と答えた。するとそばにいた女房たちは、事情を分かっているのか、「お雛様の御殿は、ほんとうにたいへんだったでしょうね」と、くすくすと笑いながら言葉を交わしていた。そうした様子にも、家の中に流れる柔らかで親密な空気が感じられた。「扇の風でも辛いくらいなんだから、あの野分の風なんて私たちはどれほど困ったことか」と女房たちは言っていた。中将はそれを聞き流しながら、「何でもいいから紙がないか。それと、君たちが使っている硯も貸してくれ」と頼んだ。女房の一人が棚から紙を巻物ごと取り出し、蓋付きの容器に入れて、硯とともに差し出した。
2025.06.17
コメント(23)
-

源氏物語〔28帖 野分 13〕
源氏物語〔28帖 野分 13〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。誰一人として女房もそばに現れず、しばらくの間、二人は親密なふうで言葉を交わしていた。だが、どうしたことか、ふと源氏の表情がまじめになり、立ち上がった。すると玉鬘が歌を口にした。「吹き乱る風のけしきに女郎花萎れしぬべきここちこそすれ」これは直接中将の耳に届いたわけではなく、源氏がその歌を口にしたことで、その内容を中将は知ることになった。不愉快さの中に妙に掻き立てられるような興味も感じて、さらに先を見届けたい気もしたが、近くにいたことを悟られまいとしてその場を離れた。ホープが虹の橋を渡り荒んだ私の心を癒しに我が家へ訪れたももは10才になった源氏が続けて、「しら露に靡かましかば女郎花荒き風にはしをれざらまし 弱竹をお手本になさい」と、そう言ったように中将には聞こえたが、それは僻耳による思い違いだったかもしれない。ただ、そのように甘く私的なやりとりに思えた会話の響きは、どうしても気味が悪く、不快で仕方がなかった。源氏はそこから花散里のもとへ向かった。朝から少し肌寒さを感じさせる空気のせいもあってか、年配の女房たちが何人も集まり、彼女の座敷で裁縫に精を出していた。若い女房のひとりは細櫃の上に真綿を広げて丁寧に扱っていたし、その周囲には、色よく染め上がった朽ち葉色の薄物や、淡い紫の打ち絹が無造作に散らかっていて、作業の途中であることがよく分かった。これらはただの布ではなく、手間と工夫の結晶のような美しさを持っていた。源氏はそれを見て、「これは中将の下襲か?」と問いながら、いかにも秋の風が強まりすぎているこの頃では、御所の壺前栽に咲く草花を眺めながらの宴も、今年は開かれそうにないなとつぶやいた。こんなに風が強くなってしまっては、何もかも風に飛ばされてしまうし、草花を楽しむどころの話ではない。
2025.06.16
コメント(20)
-

源氏物語〔28帖 野分 12〕
源氏物語〔28帖 野分 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。その端からのぞくと中央の部屋との間には何も遮るものがなく、思いのほかよく見通せた。そこで目に入った光景は、ただならぬものがあった。じゃれ合っているふうではあったが、親子でありながら、しかもまだあどけない幼子でもない者同士があんなに親密なふるまいをしているのは、常識的に考えて到底許されるものではない。見てはいけないと恐れつつも、好奇心が抑えられず、さらに目を凝らしていると、姫君が柱の陰に身を少し引くようにしているところを、源氏がぐっと自分の方へ引き寄せていた。彼女の髪が波のように揺れて、はらはらと肩にこぼれかかる様子は、見る者の心を捕らえるほどに美しかった。女の方もまるで困ったふうに見せながらも、どこかしら柔らかに源氏に寄りかかっており、それがあたりまえのように続いている様子から、中将は二人の間に日常的にこのような親密なやりとりがなされていることを察した。どうにも受け入れがたい光景であった。中将は心の中で、源氏の好色な性質を思い、ああした関係が芽生えるのは、小さいころから手元で育てなかった娘だからなのかと、真相を知らぬままに浅はかに推し量って、あさましさを感じた。もっとも、それほどまでに美しい玉鬘を目にすれば、たとえ異腹とはいえ心が揺れるのも無理はないのかもしれないと、半ばあきらめるように思った。実際、彼女の美しさは、前日に見た女王に比べればわずかに劣るようにも見えたが、人を引きつける華やぎという点では劣らず、思わず微笑みたくなるような魅力にあふれていた。中将の心には、八重に咲き乱れた山吹の花が夕映えの中で露を帯びていた光景がふと蘇った。季節は違うのに、彼女を見ているとまさにあの花に似ていると思わされた。山吹の花はその盛りにあっては華麗であるが、蕊が乱れていたりすることもある。だが、人間の美貌にはそうした一時の乱れというものがなく、永く印象に残るものであると、花と人との違いを思わずにはいられなかった。
2025.06.15
コメント(25)
-

源氏物語〔28帖 野分 11〕
源氏物語〔28帖 野分 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。ちょうど目を覚まし、鏡の前で身づくろいをしているところへ源氏はそっと忍ぶように入ってきた。騒がしい先払いの声は避けさせ、静かに座敷へと現れた彼の姿に、秋の日差しが差し込む中で座る玉鬘の美しさが際立っていた。屏風も畳まれて、部屋の中はすっきりとしており、その空間の中で彼女の姿はまるで秋の陽光を集めたように輝いていた。源氏はすぐ近くに席を取ると、まるで風が恋の言葉の使者であるかのように、玉鬘との会話を始めた。彼女は少し機嫌を損ねた様子で、「あんなふうなことばかりおっしゃるから、私は風に吹かれてどこか遠くへ行ってしまいたいと思いました」と言った。源氏はそれを面白がりながら笑い、「風に吹かれてどこへでも行こうというのは、いささか軽率なことですね。でも、どこかに行きたい目的地があるからこその発言でしょう? あなたも自分の気持ちを隠さずに示すようになった。私のことを愛していないと、もうはっきり言えるようになったわけですね。まあ、それも無理のないことですが」と言った。玉鬘は、自分の発言が思いがけず真意と違ったふうに取られてしまったことに気づき、内心おかしくなって笑い出した。その笑みの中に浮かぶ頬の色が、いつにも増して華やかに見え、秋の光の中で彼女の美貌はいっそう引き立っていた。彼女は海酸漿のようにふっくらとしていて、髪の間からちらりとのぞく肌の色がたいへん美しく、まるで透きとおるようだった。ただし目がいささか大きすぎるのが唯一品のなさとして惜しまれる点だったが、それ以外にはこれといった欠点は見あたらず、全体としてはきわめて整った美貌の持ち主であった。中将は、源氏がゆったりと語らいながらそこにいる間、この異腹の姉の顔を一度でいいから見てみたいという、かねてからの願いを遂げようと、そっと隅の部屋の御簾を持ち上げた。几帳が添えてあるとはいえ、部屋のしつらえは乱れたままだった。
2025.06.14
コメント(30)
-

源氏物語〔28帖 野分 10〕
源氏物語〔28帖 野分 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。再び中将も供をして歩き出したが、源氏が御簾の中に入って中宮と話している間、中将は渡殿の戸口の近くへ行き、女房たちの集まっている気配を感じながら、冗談を言ったりして過ごしていた。しかしその姿には、いつものような軽やかさはなく、新たに生まれた想いの重みを心に抱えたまま、どこか沈んだ面持ちで、気づかぬうちに遠いものを見つめていた。源氏はそこから北へ向かい、明石の君の住まう町へと足を運んだが、そこには家司らしい格式ある人物の姿はなく、下働きの女たちが庭の乱れた草花を整えながら忙しく立ち働いていた。童女のひとりは感じのよい様子で、夫人が大切にしていた竜胆や朝顔が他の葉にまぎれてしまっているのを丁寧に選び出して手入れをしており、その光景にはどこか胸を打たれる静かな物哀しさが漂っていた。そのころ、明石の君は縁側近くに出て、十三絃の琴を爪弾いていた。心に沈む思いを抱えていたのだろう。人払いの声が聞こえると、日常の装いの上からそっと小袿を肩に掛けて出迎えに出た。そのさりげない振る舞いの中にも、突然の訪問に対して敬意を失わない明石の君の人柄がにじんでいた。源氏は座敷の端に腰を下ろし、風の見舞いをひと言だけ告げると、それ以上の言葉も交わさずにあっさりと立ち去った。その態度に、明石の君は胸を冷たく締めつけられるような寂しさを覚え、淡く口ずさむようにして心の内を詠んだ。「おほかたの荻の葉過ぐる風の音 もうき身一つに沁むここちして」誰に聞かせるでもなく、ただ風に乗せて呟かれるその歌には、源氏への恨めしさと自らの身のはかなさが込められていた。そのあと、源氏は東の町にある西の対、つまり玉鬘のいる住まいへと向かった。あの激しい風の夜、玉鬘は恐怖で明け方まで眠れず、ようやく浅い眠りに落ちた後は寝過ごしてしまっていた。
2025.06.13
コメント(21)
-

源氏物語〔28帖 野分 9〕
源氏物語〔28帖 野分 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。中将は階段のところまで行って中宮からの返事を伝えた。「あの激しい風からも守ってくださるでしょうと、若い気持ちで頼りにしておりますので、お見舞いを頂けたことでようやく心が落ち着きました」という言葉であった。それを聞いて源氏は、「あの宮様は体も弱々しい方だからね、きっとそうだっただろう。あの夜は女たちにとっては誰でも本当に怖くてたまらないと思ったはずだから、無神経に感じられても仕方がなかったかもしれない」と言い、そのまますぐに訪問することに決めた。直衣を着るために源氏が向こうの室へ入っていこうとした。御簾の近くに立てられた短い几帳の陰から、ふと見えた袖口があった。それが女王のものであろうと察すると、中将の胸はどきりと音を立てて高鳴り、思わず外のほうに視線を向けて気を紛らわせた。源氏は鏡に向かいながら、ふと笑みを浮かべて夫人に語りかけた。「中将の朝の姿はなかなか美しいと思わないか。まだ若いけれど、もうどこか洗練されて見えるような気がする。私がそう思うのは、親心のせいだろうか」などと、自分の美貌に自信を持ちながらも、他人を褒める余裕を見せる源氏は、身なりを整えるのにも念入りで、その様子はやはりただ者ではない気品に満ちていた。やがて、装いを終えた源氏は御簾の外に出ようとしたが、中将が何かを思い詰めたように一方をじっと見つめて、自分が立ち上がることにも気づいていない様子に気づき、鋭い感受性を持つ源氏はただならぬものを感じ取った。そして、ふと立ち止まって夫人に向かってこう言った。「昨日の風の混乱の中で、中将はあなたの姿を見てしまったのではないか。渡殿の戸が開いていたはずだ」と。女王は驚いて頬を赤らめ、「そんなことありません。渡殿のほうには誰の足音もしませんでしたから」と否定したが、源氏は一人ごとのように「いや、やはり疑わしいな」と呟きながら中宮の御殿のほうへ向かって歩いていった。
2025.06.12
コメント(20)
-

源氏物語〔28帖 野分 8〕
源氏物語〔28帖 野分 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。東の対の南縁に立ち、中央の寝殿のほうを眺めると、格子が二間ほど上げられ、まだぼんやりとした朝の光の中で御簾が巻き上げられ、女房たちが出ていた。若い女房たちが高欄にもたれて庭を見ているのが見えたが、その出で立ちは気の抜けた様子ではなく、裳を重ねた美しい装いで整っていて、皆きちんとした姿で連れ立っていたので、そこにはだらしなさよりも、かえって趣深さが感じられた。中宮は童女たちを庭に降ろして虫籠に露を集めさせていた。紫苑色や撫子色など、濃淡さまざまな袙を重ね、その上に女郎花色の薄物を羽織るといった季節に合った装いの童女たちが、四、五人ずつ集まり、あちらこちらの草むらに虫籠を持って歩きまわっていた。彼女たちは折れてしまった撫子の哀れな枝なども丁寧に拾い上げており、その光景はまるで季節の移ろいと人の心の哀しみが重なったようで、中将の目には静かで美しいものとして映っていた。霧の立ち込める中、そこかしこにかすかに姿が見える庭の風景は、まるで夢の中のように静かで幻想的だった。座敷の中を通り抜けて吹いてくる風には、ほのかに侍従香の香りが混じっていて、その香りだけでもこの屋敷に漂う洗練された女の世界の奥ゆかしさや気品が感じられた。あまりにも気高い空気の中へ踏み込むことにためらいを覚えた中将だったが、静かに歩を進めていくと、女房たちは驚くそぶりも見せずに、すっと中へ引っ込んでいった。この場所は、中将にとっても親しみのあるところで、宮の御入内の際に童形でお供した縁から顔なじみの女房も多かった。源氏の挨拶を伝えたあと、宰相の君や内侍らとしばらく話し込んだが、この中宮の御殿には、他のどこにもない澄みきった高貴な空気が漂っており、その清らかな雰囲気のなかにあっても、中将の胸の中には昨日からの重苦しい想いが消えることなく残っていた。南御殿に戻ると、格子はすでにすべて上げられており、夫人は昨夜心を留めていた草花が、荒れた風のせいで見る影もなく乱れてしまっているのを見つめていた。
2025.06.11
コメント(25)
-

源氏物語〔28帖 野分 7〕
源氏物語〔28帖 野分 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。空はまだ曇りがちで、濃い霧があたりを包み込み、あたり一帯に物悲しい気配が漂っていた。その光景に心を動かされた中将は、涙がこぼれそうになるのを必死にこらえ、何でもないような咳払いでその気持ちをごまかそうとした。そんなとき、奥から源氏の声が聞こえた。「中将が来ているらしいな。まだ早いのに」と言って起き出したようである。何やら夫人も話している気配はあるが、その声までは届かず、源氏の笑い声だけが庭に響いてきた。「昔はあなたに経験させなかった夜明けの別れを、今ようやく知って寂しいでしょう」と言っているのが耳に入り、そのやりとりからして、まだ二人の間には初々しい緊張感があることを中将は感じ取った。やがて源氏が格子を自らの手で開けようとする気配がしたので、中将はあまり近くにいるのをはばかって、すこし後ろに退いた。源氏は中将に向かって、昨晩訪ねた三条の宮の様子を尋ねた。中将は、「何でもないことでも涙を流されるほどで、お気の毒でなりません」と答えた。それに対して源氏は微笑しながら、「もう長くはいらっしゃらないだろうから、誠意を尽くしてお仕えするのがよい。内大臣はそういうところが足りないと以前にも嘆いておられたよ。彼は外から見て華やかで目を引くようなことばかり好んで、親への孝行も世間の注目を集めるような形にしか表そうとしない。心を込めて親に尽くすということができない人だ。非常に聡明で、末世の大臣には過ぎた器量の持ち主ではあるが、やはり人間には誰しも欠点というものがあるからな」と語った。それから源氏は、「あの大風の中で中宮付きの役人たちは無事だったかどうか心配だ」と言い、中将を中宮のもとへ様子を見に行かせることにした。「昨晩の風の強い頃はどうしていたか、私は体調がすぐれず今はまだ参上できない」という言葉を伝えるように指示を与え、中将を送り出した。朝のまだ光が淡い時間、中将が立ち廊下を抜けて中宮のいる町へ向かう姿は、しんとした空気の中でもひときわ美しく、清々しい印象を与えた。
2025.06.10
コメント(22)
-

源氏物語〔28帖 野分 6〕
源氏物語〔28帖 野分 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。中将は、恋心を抱こうとまでは思わないが、ただひたすらに「あのような人が妻であれば、自分の人生も長く、豊かになるだろうに」と切実に願ってしまうのだった。そして夜が明ける頃、風は少し湿気を帯びた音に変わり、村雨のような冷たい雨が混じるようになった。「六条院では離れの建物がすべて倒れそうです」と侍が報告してきた。風が吹き荒れている間、六条院の大臣の住まいには人が多く詰めているだろうが、東の町の方は人手が少なく、花散里の夫人はきっと心細くしているに違いないと、中将は気になって、まだ夜の明けきらぬうちに三条の宮を後にして東の夫人のもとへ向かった。横殴りの雨が車に吹き込んできて、空の色までもが不気味な様子を見せる中、中将は道中ずっと魂が身体から離れかけているような、不安定な気持ちに襲われていた。これはいったい何なのか。まるで自分の心にまた一つ、重い思いが積み重なってしまったような気がして、恐ろしくなった。理性では「そんなはずはない」と否定しながらも、心の中にはあの幻のような面影が確かに残っていた。これは正気を失ってしまったのか、そう自問自答しながら六条院にたどり着いた中将は、まっすぐに東の夫人を見舞いに行ったのだった。昨晩の大風のあと、心細く震えていた花散里に対して、中将はやさしく声をかけて慰めてやった。気を落ち着けたあと、すぐに家司を呼び寄せて壊れた場所の修理を命じ、自分は南の町のほうへ向かった。そこではまだ朝が早いために格子も上げられておらず、屋敷の者たちも目覚めていない様子であったので、中将は源氏の寝室の前にある高欄にもたれて、しばらく庭の景色を眺めていた。昨夜の風の猛威で、築山の木々の枝は折れ、草は乱れ、檜皮や瓦の破片があちこちに散らばり、立蔀や透垣の類も多数倒れていた。かすかに差し込んでいた朝の光を受けて、乱れた草の露が恨みを含んだようにきらめいていた。空はまだ曇りがちで、濃い霧があたりを包み込み、あたり一帯に物悲しい気配が漂っていた。
2025.06.09
コメント(23)
-

源氏物語〔28帖 野分 5〕
源氏物語〔28帖 野分 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。風が騒がしく吹き荒れる日で、中将は三条の宮から六条院へ向かう。お見舞いの使いが先に立ち、「騒がしい天気ですから心配ですが、この朝臣が付き添っておりますのでご安心ください」と伝言していた。道中の風は激しく、心細いものだったが、中将は真面目な青年で、三条の宮と父である六条院への挨拶を欠かすことがなかった。宮中が慎みの日で外出できない時以外は、どんなに多忙な日でも、まず六条院に顔を出してから宮中へ向かうのが常で、その規則正しい習慣は乱れることがなかった。今日のような暴風の日でさえも、彼は迷うことなく身を呈して見舞いに赴いた。三条の宮は中将が訪れたことを大いに喜び、安心した様子を見せた。「こんなにひどい野分は、年老いた私でもこれまでに経験したことがない」と震えており、木々の枝が折れる音や、家々の瓦が飛ぶ音があちこちから聞こえていた。そんな中を訪ねて来た中将を、宮は危険な冒険をしてくれたものだと感謝しながらも、かつての華やかな暮らしが過去のものとなり、今はただこの一人の子に頼って生きている現実を前にして、中将自身も無常を感じざるをえなかった。宮の尊厳が世間で薄れたわけではないが、ただ一人の子である内大臣の接し方には、どこか情の薄さが感じられた。その夜、風は一晩中吹き荒れ、中将は眠れなかった。自然の激しさに心を打たれながら、なぜか今日は恋人のことが思い浮かばず、代わりにあの嵐の中でふと見てしまった継母である紫の女王の姿が、頭から離れなかった。こんなことがあってよいのかと、自分を責めようとするものの、その姿があまりにも美しく、幻のようにまた心に浮かんでくる。過去にも未来にも現れることのないほどの美しさを持つ人であり、六条院にすでに並外れた夫人たちがいるにもかかわらず、その中でもひときわ光を放っていた。東の夫人が不憫に思えてならず、そんな女性をそばにおいている父の高潔さが、また一層感じられた。
2025.06.08
コメント(24)
-

源氏物語〔28帖 野分 4〕
源氏物語〔28帖 野分 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。中将の様子を見た源氏は、「だから私が言った通り、不用心だったのだ」と言い、そこで初めて東の妻戸が開いていたことに気づいた。長い年月のあいだ、こんなふうにふと彼女の姿を目にする機会はなかったのだが、まさに「風は巌をも動かす」といわれるように、普段は人目を避けて奥にいる慎み深い紫の女王が、今日の風のせいで思いがけず縁の方に出てきていた。そのおかげで中将は、これまでにないほどの喜びと驚きを得たと感じていた。その間にも、家司たちがやってきて報告を始めた。「たいへんな風です。北東から吹いているようですが、こちら側は比較的安全です」と。「馬場殿や南の釣殿などは危険な状況に思われます」とのことで、下人たちには次々に指示が出されていた。源氏はふと中将に声をかけた。「中将はどこから来たのか」と尋ねると、中将はこう答えた。「三条の宮におりました。けれど、風が強まりそうだと聞いて心配になり、こちらに参りました。あちらではお一人きりでおられるので、心細そうにされており、風の音などにもおびえていらっしゃいました。お気の毒で、またすぐに戻ろうと思っています」と。それを聞いた源氏は、「ほんとうにそうだ、早く行ってあげなさい」と。「年を取ると、かえって若い子のようになってしまうというのは、一見不思議だけれど、結局は誰もがそうなっていくものだよ」と言って、大宮のことを思いやっていた。この場面では、風という自然の要素が、人々の行動や感情にさまざまな影響を与えている。紫の女王の姿が偶然中将の目に触れるという稀な出来事が、風の強さによって引き起こされ、抑えていた感情や意識が露になる。また、老いによって感情が若返るような人間の在り方にも言及され、自然と人生の関係が静かに、しかし深く描かれている。源氏の冷静さと慈しみ、中将の揺れ動く心、それを取り巻く人々の気遣いが、風という共通の状況下で交差していく。
2025.06.07
コメント(25)
-

源氏物語〔28帖 野分 3〕
源氏物語〔28帖 野分 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。父である大臣が、自分にその女王――つまり継母である紫の上と近づく機会を与えなかった理由が、この時になって初めて理解できた。父は自分の理性を信じていなかったのではなく、あまりに美しいこの継母を、男の目にさらすことが危険であると考えていたのだと気づき、中将は自分の無意識の行動、つまり盗み見るという行為の罪深さを思い、ぞっとした。立ち去ろうとしたその瞬間、源氏が西側の襖を開けて、ちょうどその部屋――紫の上の居間へと入ってきた。秋の嵐という自然の力と、それに翻弄されながらも気高く立つ女性の姿を背景に、男の恋情の芽生えと、理性との葛藤を繊細に描いている。風に舞う草花と、そこに佇む紫の上の姿とが重なり、見る者の心を奪う美の象徴として昇華されている。また、中将の視点を通じて、抑えきれない恋の感情と、それを抑えるべき立場としての意識との狭間に揺れる心理が、非常に人間らしい。風の強い日で、源氏は、「いやな日だ、落ち着かない風だね」とつぶやき、格子をすべて下ろすようにと指示を出した。周囲には男の用人もいるだろうから、不用心のないよう気を配れというのだった。その声を耳にして、中将は再び元の場所に戻り、そっと中の様子を覗いた。紫の女王が何か話しており、それを源氏が微笑みながら見つめていた。その光景を見た中将の心には、ただならぬ感慨が湧き起こっていた。源氏は親というよりは若々しく、美しい男の絶頂期にあるように見えた。そして、その傍らにいる女王の美しさもまた、まさに女としての完成を迎えたようで、互いに映し合うような美がそこにあった。中将はその二人を見つめながら、自分の立っている東側の格子が風で吹き散らされてしまい、もしかすると中から自分の姿が見えてしまうかもしれないと恐れて、慌ててその場を離れた。そして、あたかも今来たばかりのようなふりをして、咳払いをしながら南の縁のほうへ歩いて出ていった。
2025.06.06
コメント(25)
-

源氏物語〔28帖 野分 2〕
源氏物語〔28帖 野分 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。南の御殿の庭は、ちょうど修理が終わったばかりで、そこには元からあった小萩の枝が野分の風にあおられて自由奔放に乱れ揺れていた。あまりに激しい風に手の施しようもなく、その様子をただ黙って見ているしかなかった。秋草の枝は折れてしまい、朝露を宿すこともできないような姿になってしまった。女王はそんな草花の様子を、縁の近くまで出てきて静かに見つめていた。その頃、源氏はまだ若く、小さい姫君のもとにいた。そこへ中将が訪ねてきて、東の渡殿にある衝立の上からふと妻戸の開いた奥の方を何気なく覗き見た。そこには女房たちが大勢いたが、中将は足を止めて、音を立てないようにしてその様子をしばらく眺めていた。風が強かったため、屏風もすべて畳まれており、遠くの部屋の様子までよく見通せた。そうして視線を送っていた先に、ひとりの女性の姿が目に入った。その姿は女房たちとは明らかに違って見え、上品で美しく、ただそこにいるだけで空気に香りが立ちのぼるような存在感を放っていた。それはまるで春の朝靄の中に、ふと現れた満開の樺桜を見たような感覚で、中将は思わず夢中になって見つめてしまった。その女性の美しさは、見る者の表情にまで影響を及ぼすほどで、自分の顔が惹かれてゆくのを中将自身が感じていた。今まで見たどんな女性よりも美しい、そう確信できるほどの麗人だった。風に吹き上げられた御簾を、女房たちが押さえて歩いている様子の中、その女性がふいに笑った。その笑みがまたあまりに美しく、中将の心を強く揺さぶった。その女性こそ、草花に同情して部屋の奥へも入らず、そこに留まっていた紫の女王であった。その場にいた他の女房たちも皆美しいのだが、不思議と中将の目は彼女たちには向かず、ただその女王だけに釘付けになっていた。
2025.06.05
コメント(24)
-

源氏物語〔28帖 野分 1〕
源氏物語〔28帖 野分 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔28帖 野分〕 (のわけ) の研鑽」を公開してます。秋、中宮が住まう六条院の庭には、例年にも増して多くの秋草が植えられていた。その草花の間には、黒木や赤木を用いた風情ある柵が所々に設けられており、それが朝夕の露に濡れているさまは、あたかも優美な野辺の景色をそのまま写し取ったようで、人々は春の山の景色すら忘れてしまうほど、その美しさに心を奪われていた。もともと四季の中で秋を最も風情があるとする意見が古くから多かったが、それでも六条院の春の庭の見事さを前に、春を称える者も少なくなかった。しかし、今ではその人々もすっかり秋の美に心を移してしまっている。驚かせてしまい申し訳ありません。それは、まるで世の中の人の心の移ろいやすさを映すかのようでもあった。中宮はこの美しい秋の庭に強く惹かれ、実家である六条院での生活を続けていた。しかし、音楽の催しなどを楽しむにはふさわしい季節ではあっても、八月は中宮の父である前皇太子の命日がある月でもあり、それを憚って慎ましく過ごすうちに、庭の草花はますます見ごろを迎えていった。そんな折、例年よりも強い勢いで野分の風が吹きはじめ、空の色までも変えてしまうほどだった。風にあおられてしおれていく草花の姿を見ると、自然に対して特に深い愛情を持たない人ですら心を痛めるほどである。ましてや繊細な感性を持つ中宮がそれを目にしたときには、気がかりのあまり病に伏してしまわれるのではないかと心配されるほどであった。秋の空を前にして、涙をぬぐう袖が春の桜の季節以上に必要に思えるほどに、中宮は深い哀しみを覚えていた。日が暮れるにつれて、打ちひしがれた草木の影は次第に見えなくなり、ただ風の音だけが高まり、不安を煽るようであった。格子などもすべて下ろされていたため、中宮はただ、風に散らされて無惨な姿となった草花を、哀れに思うしかなかったのであり、自然と人の心の共鳴、また季節の移ろいの中にある美と儚さ、そして哀しみを巧みに織り交ぜた描写となっており、紫式部の繊細な感性と文才が如実に現れている。
2025.06.04
コメント(26)
-

源氏物語〔27帖 篝火 1〕
源氏物語〔27帖 篝火 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔27帖 篝火〕 (かがりび) の研鑽」を公開してます。最近、世間では内大臣の新しい娘のことがよく話題にされていた。源氏はそれを耳にして、「あんなふうに深窓で大事に育てられていた娘を、大騒ぎして迎えたくせに、今になって世間の笑い者にしている内大臣の気持ちが理解できない」と感じた。内大臣は自尊心が強く、他人の家で育った娘の人柄や能力を確かめもせずに急いで引き取っておきながら、今は気に入らなかった不満を世間に晒すことでまぎらわせているのだろう。たとえ本人がどうであれ、周囲の人々がうまく扱えば世間体もよく見せることができるはずなのに、と源氏は考えて、内大臣に愛されない玉鬘の境遇に同情していた。そのような話を聞いて、玉鬘自身も、自分の父であるとはいえ、どんな性格なのか分からない人に軽々しく近づいては恥をかくことになるかもしれないと不安に思った。右近もそれを強く感じさせるような意見を玉鬘に伝えた。源氏は、玉鬘に恋心を抱いていたものの、それを無理やり押しつけることはなく、むしろますます深い思いを寄せていた。そのため、玉鬘も少しずつ安心して源氏に親しめるようになっていった。季節は秋になり、涼しい風が吹いて物思いにふけりやすい時期となったので、源氏は頻繁に玉鬘のもとを訪れ、一日中一緒に過ごすこともあった。琴を教えることもあり、ある五、六日頃の夕方には、早めに月が沈み、曇り空の下で荻の葉がさびしく音を立てていた。源氏と玉鬘は並んで仮眠を取っていたが、源氏は「こんなつらい状況はない」と嘆きながら夜更かししていた。けれども、人に怪しまれるのを避けて帰ろうとすると、庭の篝火が消えかかっているのに気づいたので、付き添いの右近衛の丞に命じて火を焚かせた。涼しげな水辺のそばに広がる木の下に美しく火が灯り、その明かりが部屋の中に差し込んで、玉鬘の姿がより美しく浮かび上がった。
2025.06.03
コメント(23)
-

源氏物語〔27帖 篝火 2 完〕
源氏物語〔27帖 篝火 2 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔27帖 篝火〕 (かがりび) の研鑽」を公開してます。冷たい髪の手触りも色っぽく感じられ、恥ずかしそうにしている様子がとても愛らしかったので、源氏はなかなかその場を離れる気になれなかった。そして源氏は右近衛の丞に、「庭の篝火を絶やさないようにしてくれ。暑い季節でも、月のない夜に庭が暗いと不気味だからね」と言った。さらに玉鬘に向かって、「この篝火に寄り添うように立つ恋の煙は、世間からは消えない燃える思いそのものなんだ。こんな状態をいつまでも続けなければならないのだろうか、まるで心の中でくすぶる炎のようだ」と語りかけた。それに対し、玉鬘は、「人が不思議に思うようなことを言われるのは嫌です。篝火の煙のように、行く先のない空に消えてしまいたい」と返した。その言葉に、源氏は困ったような表情を浮かべた。「さあ、帰ろう」と言って御簾から出たとき、東の対の方角から、笛の音が十三絃の琴に合わせて聞こえてきた。それは、頭中将らが集まって遊んでいた音だった。源氏は「これは頭中将に違いない。上手い笛の音だ」と言い、そのままとどまってしまった。東の対に使いをやり、「こちらにいる。篝火の涼しい光に惹かれているのです」と伝えさせると、公達三人がこちらへやって来た。源氏は琴を取り出して、「秋風の音がする今の季節に、笛の音が私を誘ったのだ」と言いながら懐かしげに琴を弾いた。源中将が盤渉調で笛を吹き、頭中将は少し気後れして合奏に加わろうとしなかった。源氏が「遅いね」と促すと、弟の弁の少将が拍子を取り、鈴虫の声のように澄んだ声で歌い始めた。源氏はそれを二度繰り返させた後、和琴を頭中将に渡した。頭中将はその父である大臣にも劣らない見事な演奏を披露した。源氏は、「この御簾の中に、琴の音をよく聞き分ける人がいる。今夜は私に杯を多くすすめないでくれ。青春を過ぎた者は、酔って泣きながら昔を思い出して、取り乱してしまうから」と言った。その言葉は姫君、すなわち玉鬘の心にも深く沁みた。この兄弟たちは、源氏と玉鬘の関係に特別なつながりがあることなど夢にも思っていなかった。中将は抑えきれない恋心を音楽に託して、思い切り琴をかき鳴らしたい気持ちを押さえ、控えめに演奏していた。(完)明日より28帖 野分(のわけ) を公開予定。
2025.06.03
コメント(0)
-

源氏物語〔26帖 常夏 16 完〕
源氏物語〔26帖 常夏 16 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔26帖 常夏〕 (とこなつ) の研鑽」を公開してます。「もしも嫌がられるようでしたら、ご容赦を」という文に続き、「草が生い茂る常陸の海の、いかが崎、どうにかしてあなたに会いたいものです」という和歌や、「大川の水が思いをたたえて波を立てるのも当然だ」というような意味の和歌もあった。青い色紙に漢字多めの文体で、しかも筆跡は肩が張ったように力んでいて、でもどこか頼りなく、文字は曲がっていて倒れそう。「し」の字を妙に気取って長く書いていた。そんな自分の字を満足そうに読み返し、撫子の花に巻きつけて、女御の元へ届けさせる。使いには、厠係りの新参の童女が選ばれ、台盤所にそっと手紙を差し出す。対応した下仕えの女はその童女のことを知っており、手紙を受け取って女御の女房・大輔に渡す。女御はその手紙を見て、少し笑みを浮かべながら内容を女房に見せる。中納言という女房は、「新しい書き方ですね」とやや皮肉交じりに言いながら読む。女御は、「漢字が見つからなかったのかしら、内容も前後がばらばらで意味が通じない」と困ったように言うが、「そんなふうに書いた返事を出せば軽蔑されるだろう。あなたから書いてちょうだい」と頼む。中納言はそれを受け、「駿河の海の須磨の浦に波が立っていくように、恋しさが募る」という意味の和歌で返事を書く。女御は「私の言葉だと思われたら困る」と苦笑するが、中納言は「大丈夫、聞いた人がわかってくれます」とあっけらかんと答える。この返事を読んで、新令嬢は「上手なお歌だわ、松と言ってくださったから」と嬉しそうにし、香をたっぷり焚き込んで紅をさし、髪を整える。その姿には、ややけばけばしさもありながら愛嬌もあるが、女御との面会では何をしでかすかわからず、周囲には不安が漂っていた。(完)明日より27帖 篝火(かがりび) を公開予定。
2025.06.02
コメント(22)
-

源氏物語〔26帖 常夏 15〕
源氏物語〔26帖 常夏 15〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔26帖 常夏〕 (とこなつ) の研鑽」を公開してます。大臣は「別に吉日を選ばなくてもいい、思い立ったら今日でもいい」と言って出ていく。その後ろ姿を見送った新令嬢は、「なんて立派なお父様なんでしょう。そんな方の子なのに、私は小さな家で育ってきたなんて」と感慨深げに言う。すると、側にいた五節という女房が、「でも少し偉そうにしすぎですわ。もっと見劣りする父親でも、愛情深い人に育てられたほうがよかったかもしれませんね」と皮肉を交える。これに新令嬢は怒って、「あんた、自分と私を一緒にしないで。私はあんたなんかとは違うのよ」と言い返すが、その表情や姿にはどこか憎めない愛嬌があった。ただし、新令嬢は非常に身分の低い環境で育てられていたため、言葉遣いも作法も知らず、何気ない言葉も軽々しく聞こえてしまう。もし話し方に落ち着きがあれば、あるいは技巧のない和歌でも、声の調子や間の取り方一つで印象が変わっただろうに、彼女はそのどれも備えていない。育ちのままで教養が加わっていないために、真価を誤解されやすく、実際は決して愚かなわけではなく、三十一文字の歌を即興で作るくらいの才も持っている。彼女は、「女御のところに行けと言われたのだから、嫌そうなそぶりを見せては大臣の気分を損ねてしまう。今夜のうちに行ってしまおう。大臣が訪ねてきても、女御たちに冷たくされるようでは、この家で立場がなくなってしまう」と言い、手紙を先に出すことにする。その手紙には、典型的な古風な仮名文で、点を多く打ち、ぎこちない文体で「近くにいながら、これまで影を踏むようにひっそりとしていたのは、まるで関所でも置かれていたのではと存じます。武蔵野という名は尊いものですが…」と書かれている。裏にはさらに、「本当に、今夜にも参ろうと存じております。
2025.06.01
コメント(26)
全31件 (31件中 1-31件目)
1