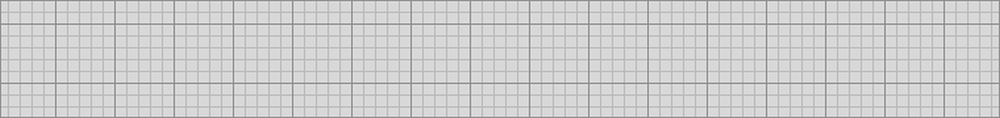2025年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 2〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。一方で、夫人は東の対の中の人目につかない離れにこもり、八条の式部卿の宮が伝えた秘伝の方法で香を調合していた。つまり、源氏と夫人は夫婦でありながらも、それぞれに秘密を持って調合し合い、どちらの香が優れているかを競い合おうとしていた。姫君の親としてはやや子どもじみた競争とも言えるが、二人とも本気で取り組んでいた。それぞれの香の調合には、限られた信頼のおける女房しか立ち会わせず、作業は非常に慎重に行われていた。裳着の式のために準備された数々の道具の中でも、源氏が特にこだわったのは香合の箱の形や壺、火入れの作り方で、そこに芸術的な意匠を凝らしていた。壺の中には、あちこちの調合室で完成した香の中でもとくに出来の良いものを試して選び抜き、入れようと考えていた。二月十日、雨が少し降っていた。庭の紅梅が色も香りも見事で、名木らしい風格を見せていた。そんな中、兵部卿の宮が訪ねてきた。裳着の式がもう間近に迫っており、準備で忙しい源氏を気遣って訪れたのだった。この宮は源氏の兄でもあり、昔から仲の良い兄弟だったので、久しぶりに語らいながら庭の花を愛でていた。すると、前斎院からの使いが来て、半ば散った梅の枝に手紙を添えて届けてきた。兵部卿の宮は、源氏と前斎院の間に昔噂があったのを知っていたので、「どんなおたよりがあったのですか」と興味深そうに聞いてきた。それに対して源氏は、「私が先日お願いした香のことを、すぐに調合して送ってくださったのです」とだけ言い、手紙の中身は見せずにさっと隠してしまった。源氏は、薫香を贈るために、沈香を入れる特別な箱を用意した。その箱には、瑠璃の脚付きの鉢が二つ置かれており、香はやや大きめに粒状に丸められて入っていた。一方の鉢は紺瑠璃で、そこには五葉の枝が添えられ、もう一方の白い瑠璃の鉢には梅の花が添えられていた。
2025.08.31
コメント(28)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 1〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔31帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。源氏が十一歳になる姫君の裳着(もぎ)の儀式のために準備していたことは、普通の家とは比べものにならないほど豪華だった。同じ年の二月には東宮の元服も予定されていて、それに続いて姫君が東宮のもとへ入内する話も進んでいたらしい。一月の末、公的な仕事も私生活も比較的静かな時期だったので、源氏はふと思い立って香の調合をしようとした。以前、大弐から贈られていた香木の原料を倉から出させてみたが、それよりもっと前に渡来したものの方がいいかもしれないという思いが浮かび、二条院の倉を開けさせ、支那から入ってきた古い香木類をすべて六条院へ運ばせた。そして、それらを新しいものと比べてみた。源氏は、「織物も古いもののほうが芸術的で味わいがある」と考えていて、裳着の式で使う覆いや敷物、褥(しとね)などの縁取りに、故院の時代の初めに朝鮮人が献上した綾や、緋色の金襴などを使うことにした。これらの織物は最近のものよりもはるかに美的で価値があり、それぞれの布にふさわしい使い方を考えて配置した。一方、今回大弐から新たに贈られてきた綾や薄物は他の人に贈り分けた。香の調合については、昔の原料と今の原料を両方混ぜて、それを六条院に住む夫人たちや、源氏が尊敬する女性たちに送った。そして、それぞれ二種類ずつ薫香を作ってほしいと伝えた。裳着の式に贈る品々や、身分の高い人々に贈る衣服の仕立ても夫人たちのところで分担して進めていた。そのかたわらで、香の原料を鉄の臼で挽く音があちこちから聞こえ、まるで六条院全体が忙しく活気に満ちているような雰囲気だった。源氏は、南の町の寝殿に引きこもり、夫人たちの部屋から離れて一人で香を調合していた。どういうわけか、昔の承和の帝だけが知っていたという特別な二種類の調合法を独学で習得しており、それを使って香を熱心に作っていた。
2025.08.30
コメント(24)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 40 完〕
源氏物語〔31帖 真木柱 40 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。大将がこれまでに生んだ長男・次男と比べても、今回生まれたこの子の顔立ちは少しも劣っていなかった。頭中将は兄弟として玉鬘のことを深く愛していたが、何も疑わずに喜んでいる内大臣とは違って、彼女の境遇には少し物足りなさを感じていた。もし尚侍として宮中で天皇に仕えていたなら、どれほど高貴な立場になったことかと思っていた。しかも今回生まれた三男の美しい顔を見れば見るほど、頭中将は考えてしまうのだった。「もし今、まだ皇子のいない天皇のもとにこんな子供が生まれていたら、どれほど家の名誉になったことだろう」と、ついにはっきりそう口にして、残念がった。しかし現実には、尚侍としての公的な務めもすべて自宅で差し支えなく行われており、玉鬘が再び宮中へ上がることはないだろうと見られていた。それもそれで悪くないことだった。一方、かつて内大臣の娘で尚侍になりたがっていた近江の君は、才覚の乏しい者にありがちなように、恋愛に妙に興味を持ち始め、まわりを不安にさせていた。女御も、自分の家の恥になるようなことをこの近江の君がやらかすのではないかと心配で、気が休まらない。大臣からは「もう女御のところには来ないように」ときつく言われていたにもかかわらず、近江の君は出入りをやめなかった。ある日、女御の居所に、選び抜かれたような殿上役人たちが大勢集まり、雅楽の遊びが開かれていた。源宰相中将(源中将)も来ていて、いつもよりくだけた様子で女房たちと気さくに話していた。それを見た女房たちは、「やはり身分が違うわ」と感心していた時、近江の君が他の女房たちの座を押しのけるようにして御簾の方へ近づこうとしていた。女房たちはこれを見て「何かとんでもないことを言い出すのではないか」とひそひそ話し合っていた。そのうちに近江の君は、源中将の姿を指差し、「これよ、これ、まったくきれいね」と声高に褒めそやすので、男たちのいる外の座敷にまでその声が聞こえてしまった。女房たちは困り果てていたが、近江の君はさらに大きな声で語る。「沖の船 寄るべ波路に 漂はば 棹さし寄らん 泊まりをしへよ」「棚無し小舟 漕ぎ返り」と、和歌の続きをふざけて言い、「同じ人にでも恋してるのかしらね、いやだわ」とまで言い出した。源中将は驚いた。女御のもとには気品ある女房たちが集っているはずなのに、こんな露骨なことを言う者がいるのはおかしいと思って、よくよく見れば、噂に聞いていたあの近江の君だった。彼はすぐに歌を詠み返した。「寄るべなみ 風の騒がす 船人も 思はぬ方に 磯づたいせず」つまり、「あなたのような風まかせの人は、思いがけぬ方向に進もうとしても無駄ですよ」という意味である。そして「そんなはしたない真似をして、恥ずかしくないのか」とも言った。(完)明日より(32帖 梅が枝 うめがえ) を公開予定。
2025.08.29
コメント(24)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 39〕
源氏物語〔31帖 真木柱 39〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。もとの大将夫人の夕霧の生母である葵の上は、年月が経つにつれて気分がふさぎがちになり、ぼんやりして過ごすことが多くなっていた。夕霧はそんな母に対して、金銭的な支援や日々の気遣いを忘れず、以前と変わらず子どもたちも大切にしていたため、彼女は夫に未練があり、他に頼る人もなく、今も彼を唯一のよりどころとして思っていた。大将は玉鬘に会いたくて仕方がなかったが、玉鬘が暮らしている宮中のほうではそれを一切許そうとしなかった。玉鬘自身も、本当は父に会いたい気持ちがあるのに、祖父や祖母、周囲の大人たちが皆そろって父の悪口ばかり言うのを聞きながら、ますます会う望みを失っていく現状に、ひどく心細く思っていた。その一方で、男の子たちの、おそらく夕霧の兄弟たちは、しばしば玉鬘のもとを訪れて尚侍(紫の上)の様子などを楽しそうに話し、「僕たちもとても可愛がってもらっているし、毎日楽しく暮らしているよ」と言っていた。それを聞いた元夫人は、自分にはそんなふうに人生を楽しむような気持ちの余裕がなかったことを残念に思い、自身の性格を嘆いていた。尚侍は、男にも女にもそれぞれに深い思いを抱かせ、心を乱させるような存在だった。誰もが彼女に関わることで心に複雑な感情を抱かずにはいられなかった。十一月、玉鬘はたいへん美しい子供を産んだ。大将(蛍兵部卿)は何もかもが順調に運んでいることを喜び、愛する妻から生まれたこの子供をとても大事にしていた。産屋の祝いも豪華に行われたが、その様子はあえて書かなくても、読者が想像すればよいだろう。内大臣も、娘である玉鬘が幸福な暮らしをしていることに満足していた。
2025.08.28
コメント(26)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 38〕
源氏物語〔31帖 真木柱 38〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。手紙は、あくまで父親らしく体裁を整えて書かれていた。そして、「同じ巣に帰ってきた雁の姿が見えない、いったい誰があの人を引き留めているのだろう」と詠まれた和歌も添えられていた。源氏は、そんなに気取らずとも、もう少し素直になってくれればいいのに、とくやしく思っていた。その手紙を見た大将は笑いながら、「女というものは実の父親に会うのでさえ、正当な理由がなければ軽々しく出かけて行かないものなのに、どうしてこの大臣はいつも逢いたい逢いたいと恨んでばかりいらっしゃるんだろう」と、いかにも批評めいた口ぶりで言った。こんな物言いが、玉鬘には癪にさわった。返事を書くように言われても玉鬘は渋って「私には書けません」と答えた。すると大将は、「今日は私が返事を書こう」と自分が代わりに書くと言い出したので、玉鬘が内心でばかばかしく思ったのも当然だった。玉鬘のことを心から思っている源氏は、彼女のことを自分の子のように大事にしているつもりでいたが、実際には恋愛感情が強く混じっていた。その心情を、彼は風流を装って、ある歌に託して玉鬘へ届けた。「巣に隠れて目立たない雁の子を、いったいどこに隠せばよいのだろう」といった趣旨の歌だった。それはつまり、表立っては世間の目をはばかって玉鬘を自分のものとは言えないが、それでも隠しておくのはつらく、どうにもならないという思いが込められていた。そんな源氏の気持ちを汲み取って、大将(夕霧)は「気を悪くなさっているようなので、気晴らしになるかと思って、風流ぶった手紙を送ります」と前置きして、自分もまた一通の文を書いた。その内容は少し冗談まじりで、軽い調子ではあったが、玉鬘を慕っている気持ちがにじみ出ていた。源氏はそれを見て笑いながらも、心の中では「まるで玉鬘を自分のもののように書いている」と苛立ちを覚えていた。
2025.08.27
コメント(26)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 37〕
源氏物語〔31帖 真木柱 37〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。彼女は、自分の運命に希望が持てなくなり、こんな遊びのような恋愛はもう自分には似合わないと感じ、帝からのご厚意に対しても、ありがたいというような返事をすることはなかった。そして今になって、源氏が常に清らかな気持ちで親切にしてくれたことが、心の底からありがたく思えてならなかった。三月になり、六条院の庭では藤や山吹の花が夕日の中で美しく咲いていた。それを見ていると、すぐに玉鬘の美しい姿が思い出された。源氏は南の春の庭を離れて、東の町の西の対にやって来て、玉鬘に似た山吹の花を見ようとした。竹の垣の間から自然に咲き出た山吹がとても感じよく目に映った。「思ふとも恋ふとも言はじ山吹の色に衣を染めてこそ着め」という歌を口ずさみながら、玉鬘への思いを噛みしめていた。源氏は、心の中ではっきりと「井手の中道が隔てるようなことがあっても、言葉に出さずに恋し続ける山吹の花のようだ」と思っていた。それはつまり、距離があっても気持ちは変わらず、ただ黙って恋い慕っているということだった。そして「夕方になると野辺で鳴くというかほ鳥の顔が思い出されて忘れられない」などと、恋心を抑えきれずに口ずさんでいたが、そんな気持ちを分かち合える人も近くにはいなかった。ここまで徹底的に玉鬘を恋人として意識したのは、源氏にとっても初めてのこと。自分自身のことながら少し風変わりだと感じていた。そんなある日、雁の卵がたくさん贈られてきたのを見た源氏は、蜜柑や橘を贈るような気持ちで、それらの卵を籠に入れ、玉鬘への贈り物とした。ただ、頻繁に手紙を送れば周囲の目が気になってしまう。そこで彼は、あくまで戯れのような、言い訳がきくような調子で「お逢いできない日が長く続いています。あなたの冷淡さが恨めしく思えたりもしますが、でもご主人の同意がなければ、すべてはあなた一人の意志ではどうにもならないことも分かっています。ですから、特別な機会でもなければ、許しが得られないのだろうと思うと、残念です」と文を書いた。
2025.08.26
コメント(22)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 36〕
源氏物語〔31帖 真木柱 36〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。玉鬘は返事を書くのが恥ずかしくてたまらなかったが、何も書かないとがっかりさせてしまうだろうと思って、覚悟を決めて手紙を書いた。そこには「ながめする軒の雫に袖ぬれてうたかた人を忍ばざらめや」と詠まれていた。長く会えない時間が続いて、気持ちもふさいで退屈になってきてしまい、つい失礼をしてしまいました、というような内容で、きちんと丁寧に書かれていた。その手紙を前に広げて見ていた源氏は、その雨だれの音すら自分の涙のように感じられてしまい、こぼれ落ちそうになる気持ちをぐっとこらえていた。誰かに余計な詮索をされるのも嫌だったので、自分を抑えていたのだ。昔、朱雀院の母后が尚侍のことを厳しく見張っていて、源氏に会わせようとしなかったときのことを思い出した。そのときの苦しさと今の状況とを比べてみたが、今の方がもっとやる瀬ない気がしてきた。こういうつらい思いをするのは、自分で望んで好色の道に足を踏み入れたからなのだろう。もう自分にはこういう恋の苦しみはふさわしくないのではないかとも思って、気持ちをまぎらわせようとして琴を弾いてみた。しかし、玉鬘が弾いたときの爪の音がなつかしく思い出されて仕方がなかった。和琴をきれいな調べで弾いて、「玉藻はな刈りそ」と歌っている自分の姿を、もしも恋しい相手に見せられたなら、どんな相手の心も必ず動かされるだろうと思われた。帝も、かすかに見た玉鬘の美しさを忘れられず、「赤裳垂れ引きいにし姿を」という歌を、感情をそのまま言い表したような古歌ではあるが、ずっと口ずさみながら物思いにふけっていた。玉鬘のもとには手紙がこっそりと何通も届いた。しかし彼女は、自分の運命に希望が持てなくなってしまい、こんな遊びのような恋愛はもう自分には似合わないと感じていた。
2025.08.25
コメント(25)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 35〕
源氏物語〔31帖 真木柱 35〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。もとより、どうしようもない宿縁というものはあるにしても、自分があまりに気遣いすぎて遠慮していたせいで、こんなつらい結果を招いてしまったのだと、昼も夜も彼女の面影を思い浮かべて過ごしていた。今頃は、あまり風流心のない大将と一緒にいる玉鬘のことを思うと、手紙でも書いて、冗談めかして最近の気持ちを伝えたいと思うのだが、気持ちがうまく定まらず、それさえもためらってしまう。雨が降って静かな日が続く時期、こんな退屈な時間を、以前なら玉鬘のもとでまぎらすことができていたと思うと、当時のことが次々と思い出されて、いよいよ恋しさが募り、とうとう手紙を書いた。こっそりと右近のところへ送ったものの、右近が不審に思うのではないかという気持ちもあって、心にあることを全部は書き綴れなかった。だが、気づいてくれるかもしれない内容だけを選んで書いたのだった。「かきたれて のどけきころの 春雨に ふるさと人を いかに忍ぶや」(春雨がしとしとと降るこの静かな頃、昔親しく過ごした人のことを、どれほど懐かしく思うことでしょう)「私も退屈していて、ついあれこれ恨めしい気持ちになってしまうこともあるのですが、それをどうお伝えしてよいのかわからないのです」とも書かれていた。右近は、人目のないときを見計らって玉鬘にその手紙を見せた。玉鬘は、涙をこぼした。時がたつほどに、源氏のことが自然と心によみがえってくる。恋しい気持ちはあるのに、相手は自分の親という立場にあるため、思いのままに「逢いたい」と言えず、現実的にもそう簡単に会える状況ではないのが、やるせなくて悲しかった。ときどき、源氏が不意に不適切なふるまいをしそうになって困ったこともあったが、それを人に話すわけにもいかず、右近だけはなんとなく感づいているようだった。だが右近は、まだすべてを知っているわけではなく、ぼんやりと疑っているに過ぎなかった。
2025.08.24
コメント(23)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 34〕
源氏物語〔31帖 真木柱 34〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。風邪気味なので自宅で休みたいが妻も心配でしょうから、一緒に帰らせてくださいと申し出た。源氏の許しを穏やかに得ようとしたのである。こうして大将は尚侍をそのまま自邸へ連れ帰った。内大臣(玉鬘の育ての親)は、こうした急な引き取り方に多少の不満を感じたが、些細なことにこだわれば、婿である大将との関係にひびが入ると考えて、「もう私の手の届かない娘になったのですから、どうするかは任せるほかありません」と答えた。源氏は、思ってもみなかった展開に驚き、残念な気持ちを抱いたが、もはやどうすることもできないと諦めるしかなかった。玉鬘も、好きでもない相手の妻になったことをつらく思いながらも、もう奪われた形で連れて来られたのだから仕方がないと自分を納得させ、大将の邸に入って初めて心の安らぎを感じた。だが、帝が長く玉鬘のもとにいたことが大将の嫉妬心を強く刺激し、さまざまなことを口にするようになった。その様子があまりに俗っぽく、玉鬘には冷めた気持ちしか湧かなかった。愛情が持てず、不機嫌さが増していった。式部卿宮も以前は強気な態度をとっていたが、大将が一度きりの行動でそれきりになってしまったことを内心では悔しく思っていた。一方の大将は、もう玉鬘とのこと以外に関わろうとはせず、理想の妻を得たという満足感の中で、日々玉鬘に尽くしていた。二月になり、源氏は、こうした一連の流れを見て、大将を情のない男だと深く失望していた。源氏は、まさかここまではっきりと自分のもとから玉鬘が引き離されることになるとは思っておらず、油断していたことが恥ずかしく、人からどう見られるかも気になって、何より自分自身にとってとても悔しいことだった。玉鬘のことが恋しくてたまらず、どうしても忘れられなかった。
2025.08.23
コメント(29)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 33〕
源氏物語〔31帖 真木柱 33〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。距離を縮めようとする帝の態度はありがたく、玉鬘も心の中で複雑な気持ちになっていた。結婚したとはいえ、自分の心まで完全に夫に明け渡したわけではない、心はまだ自分のものである、そんなふうに感じていた。退出のために牛車が門に寄せられ、内大臣家や大将家から付き添って行く人たちが、出発の準備が整うのを今か今かと待っていた。大将自身も、緊張と焦りを隠せない表情で、人々に細かく指示を出したりしながらそのあたりを歩き回っていたが、その間も帝はなかなか玉鬘の部屋から離れようとせず、名残を惜しんでいた。帝は「近衛が近すぎる、これではまるで見張られているようではないか」と不快に感じていた。そういう気分のときに、九重の宮中に霞がかかっているという風情を歌に託し、梅の花の香りもほのかにしか届かないように、あまりに距離が近いと感じられるものはかえって美しさも損なうという気持ちを詠んだ。歌自体は平凡なものであったが、美しい帝の口から語られたことで、尚侍(玉鬘)には特別な意味をもって響いた。帝は、本当はずっと話していたい気持ちだが、私の立場に同情してくれる人が、あまりに引き止めるのもつらいと思ってくれるだろうから、もう帰りなさい。手紙をどうやって渡したらよいだろうと言い残したが、このように心配する帝の様子に、尚侍はもったいないほどの思いを抱いた。それに対して尚侍は、花の香りが弱くても、せめてこの場に立ち並んでいたいという気持ちを込めて歌を返した。そんな様子を見て、帝は名残惜しげに何度も振り返りながら、彼女のもとを離れた。一方、大将(髭黒の大将)は、前々から玉鬘を自分の邸に迎え入れようと決めていたが、初めからその意志を口にすれば源氏の反対に遭うと見て、このときまで黙っていた。そして突然、風邪気味なので自宅で休みたいと話した。
2025.08.22
コメント(26)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 32〕
源氏物語〔31帖 真木柱 32〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。いずれは彼女も自分に心を開いてくれるだろうと期待して、その日はただ静かに様子を見るだけにした。この場面は、帝の一方的でまっすぐな恋心と、それを受け止めきれずに距離を保とうとする玉鬘との、もどかしいやり取りが丁寧に描かれている。源氏のような複雑な恋愛とは違って、立場のある者同士の駆け引きや配慮が表面に出る、張り詰めた場面だと言える。大将は、帝が玉鬘の部屋(曹司)を訪れていたと聞いて、不安がいっそう強くなり、早く退出させるようにと何度もしつこく急かしてきた。もっともらしい言い訳を作って、実の父である大臣をうまく説得し、いろんな手を使った結果、ようやく今夜、玉鬘を退出させることが許された。「今夜、退出を認めてくれなければ、気分を害して、もう二度と彼女をよこしてくれなくなるだろう。自分が誰よりも先に愛した人を、後から現れた男に奪われた上、その男の機嫌をとっているような現状は、本当に耐えがたい。まるで、かつて平貞文が時平に妻を奪われた時に詠んだ歌(昔の誓いが今になってこんなに悲しいものになるとは、という内容)のようで、どうしようもなく絶望的な気持ちになる」と帝は言い、本気で悔しがっている様子を見せた。実際、帝が人づてに聞いて想像していたよりも、玉鬘はずっと美しかった。その姿を直接見れば、たとえ最初は恋愛感情がなかったとしても、ただの女官としてだけで済ませようとは思わなかっただろう。ましてや、最初から特別な関心を抱いていたのだから、玉鬘が別の男と結ばれるのは、嫉妬せずにはいられなかった。自分こそが最初に求婚した立場だということを、はっきりと主張したい気持ちをこらえて、軽い恋愛感情のように見られたくないという思いから、帝は抑えた言い方で、情熱的な思いを伝え続けた。
2025.08.21
コメント(24)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 31〕
源氏物語〔31帖 真木柱 31〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。「どうしてこんなにも、思いが通じ合わない紫のような人を、本気で好きになってしまったんだろう。深い色に染まることができないのは、もともとの運命なのか」ここでいう「紫」とは、濃い色に染まらない、つまり想いが通じにくい相手という意味に重ねられている。そしてまた「紫」は三位の官位を意味する色でもあって、玉鬘が尚侍(ないしのかみ)になって間もなく、まだ何の功績もないうちに、帝が特別に昇進させたことを指している。つまり帝は、昇進という形でも自分の愛情を示していたのだ。 玉鬘は、それを理解しながらも、自分の本当の気持ちを悟られないように冷静なふうを装い、こう詠む。「どんな色なのかもよくわからない紫を、人は心して染めるものだと聞いています。今になってようやく、あなたのご恩を深く感じています」帝はその返歌に笑みを浮かべる。でも、笑いながらも恨みの気持ちは隠さず、「その『今になって』という言葉が、もう遅すぎるんだよね」と言い、さらに「もし誰かが私に異議を唱えるなら、理由を言ってみろと言いたい。だって私の方が源氏より先に、君を愛していたんだから」と続ける。玉鬘が源氏の養女だったことを思えば、この言葉には深い皮肉もある。帝の言葉は、単なる冗談ではない。玉鬘は、帝の真剣さを感じ取って、「これはまずいことになった」と思う。自分の中にある帝への感謝や尊敬といった正直な気持ちを、ここで見せるべきではないと判断する。帝といえども、結局は男であり、感情に振り回される部分があると見抜いて、玉鬘はひたすらまじめな態度で黙って座っているだけだった。帝はもっと大胆な愛の話を持ち出したくて、わざわざこうしてやって来たのだが、玉鬘がそっけなく応じないので、それを言い出せずにいる。
2025.08.20
コメント(27)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 30〕
源氏物語〔31帖 真木柱 30〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。ちょうどそのとき大将は別室にいたので、使いが手紙を持って尚侍のもとに届けた。しぶしぶ手紙を開いた玉鬘の目に飛び込んできたのは、歌の一首だった。 深山木に 翅うち交はしゐる鳥の またなく妬き 春にもあるかな(深い山の木々の中で翼を打ち交わしている鳥のように、あなたを思って嫉妬に苦しむ春が、他にはないほどつらい)そして、「あなたのさえずる声にさえ、心を乱されずにはいられません」と、しみじみと綴られていた。あまりに率直な思いが詰まっていて、玉鬘は顔を赤らめ、返事を書くどころか、どうしてよいか分からず戸惑っていた。そんな気まずい空気の中、なんと帝(冷泉帝)が突然訪れた。月の光に照らされた帝の顔は、あまりに美しく、まるで源氏の顔を写し取ったようなそっくりさで、玉鬘は「こんな顔がもう一つあったのか」と驚いた。源氏の玉鬘に対する愛は確かに深かった。しかしこの若き帝を前にしたとき、玉鬘は自分の身に降りかかる様々な障害の多さを、改めて重く感じたのであった。愛が深ければそれで済むような話ではなかった。玉鬘と帝の関係には、源氏との間にあったような恋愛の障害はなかった。たとえば親子のような血縁の関係とか、複雑な過去とか。だからこそ帝は、真剣に玉鬘に気持ちを伝えてきた。自分の想いが受け入れられず、あてが外れたことに対して、しみじみとした残念さや恨みのような感情をにじませて語る。でも玉鬘は、そんな気持ちを受け止めきれず、顔を赤らめて、どう返していいかわからず、うつむいて黙ってしまう。帝はそんな玉鬘に対して、「そっけない人だな」と思って、こう言う。「自分が好意を示しても、それを何とも思わないでやり過ごすのだね。いつもそうなんだね。あなたは、そういう人なんだね」と。そして和歌を詠んだ。
2025.08.19
コメント(24)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 29〕
源氏物語〔31帖 真木柱 29〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。たとえば頭にのせる纏頭(てんとう=頭飾り)も、基本はどこも真綿であるけれど、尚侍側のは意匠が凝っていておもしろみがあった。こちらの御殿は、単に通りすがりに寄った場所にすぎないのに、あちこちに華やかな空気が感じられる空間だったから、若い貴公子たちは何となく気持ちが引き締まり、晴れやかな気分で踏歌(とうか=舞踏)の演奏をしていた。儀式上の決まりはちゃんと守られながらも、演者へのもてなしはとても丁寧で、しっかりとねぎらわれた。それはすべて大将(夕霧)の配慮によるものであった。大将はこの時、禁中の詰所に控えていて、尚侍のもとを今夜限りで退出しようと思っていた。けれど、いったん宮仕えに出てしまったからには、なおもとどまり続けなければならないだろうと、自分でも思っていた。しかし、そうした宮仕えの生活そのものが、自分にとってはやはり苦痛でしかなかった。玉鬘が男たちから求愛の手紙を受け取っても何も返事を書かない日々が続いていた。そんな中、大将の元に女房たちから手紙が届く。内容は、源氏の大臣が、しばらくぶりに宮中に出仕された折、陛下が「もう帰ってよい」と言われるまで滞在するようにという事だった。ゆえに、それに従うのが筋ではないか、今夜のようにあっさり退出するのはあまりに冷たく無愛想な印象を与えますよという遠回しな釘刺しだった。これを読んだ大将は苛立った。「あれほど言っておいたのに、自分の意思などはまるで無視された」と、尚侍(=玉鬘)に対して恨めしく思い、深いため息をついた。そのころ、兵部卿の宮もまた宴に参加していたが、心はまるで穏やかではなかった。頭の中は尚侍のことでいっぱいで、どうしても忘れられない。とうとう我慢できなくなり、想いを手紙に託して送った。
2025.08.18
コメント(28)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 28〕
源氏物語〔31帖 真木柱 28〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。身分がそれほど高くない更衣たちはあまり出てこられず、中心になっていたのは、中宮(藤壺系)、弘徽殿の女御、式部卿宮の王女、左大臣の娘などの高貴な女性たちであった。そのほかに、中納言と宰相の娘のふたりが更衣として仕えていた。踏歌の際には、女御たちの実家の人々も大勢見物にやって来ていた。この踏歌は、御所の中でも特に見ごたえのあるにぎやかな行事だったため、見物に来た人々も皆、服装や身なりに趣向を凝らし、華やかさを競っていた。東宮の母である女御は、見栄えのする華やかな性格の女性で、他の誰にも引けを取らないほど派手な存在だった。東宮はまだ幼く、宮中の中で権威や中心を担うのは、事実上この女御だった。今回は夜遅くなることもあって、源氏は六条院に立ち寄るのを断っていた。朱雀院から引き返し、東宮の御殿を二か所ほど回った頃には、すでに空が白み始める夜明けの時間になっていた。その明け方の薄明かりの中、酔いもあって乱れた調子で「竹河」を歌っていた人々の中に、内大臣(頭中将)の息子たちが四、五人も混ざっていた。彼らは皆、声も良く、顔立ちもそろって美しく、特に目立っていた。中でも八郎君は正妻の子で大事にされていて、まだ童の姿をしていたが、その可愛らしさは際立っていた。彼は、大将の長男と並んでおり、このふたりを見た尚侍(しょうじ/源典侍)も、他人とは思えず、思わず目が惹きつけられてしまった。東宮の御所の中でも、古くからいる女御たちが住む曹司(女房たちの部屋)よりも、新しく迎えられた尚侍が見物することになった御殿のほうが、なんとも華やかに見えた。似たような場所ではあるけれど、たとえば女房たちの袖口の重ねの色など、細部にいたるまで尚侍側のほうが洒落ていて、洗練されているように見えたのだった。尚侍自身も、その女房たちも、このように物事が良く見える、いかにも都風の御所の暮らしをしばらく続けてみたいという気持ちになっていた。
2025.08.17
コメント(27)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 27〕
源氏物語〔31帖 真木柱 27〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。結局は、恋の噂は隠していても漏れるものだから、自分が全面的に責められるようなことにはならないだろう」と自分に言い聞かせるように語っていた。玉鬘としては、大将が元の妻とまだ揉めていたり、自分のことが世間からどのように見られるのかが気になって、憂鬱になっていた。だからこそ、大将は彼女のことを気遣い、今まで尚侍として宮中に出仕することには反対していた。しかし、帝がそれを礼を欠く態度だと感じているような様子もあり、また左右の大臣(内大臣と左大臣)も一度はそれに賛成した。大将としても「夫を持つ女性が公職に就くのは世間でも珍しいことではない」と判断して、最終的に出仕に賛成した。こうして春になり、正式に玉鬘が尚侍として宮中に入ることが決まった。その時、ちょうど男踏歌(おとことうか:正月の宮中行事)があり、それをきっかけに玉鬘は御所に参内した。行事は非常に華やかに行われた。というのも、彼女の後ろには左右の大臣という有力者たちの後ろ盾があり、さらに大将の庇護も加わっていたから当然のように豪勢になった。源宰相中将は非常に真面目に玉鬘の世話をしていた。彼の兄弟たちも、玉鬘に近づく絶好の機会だと考え、こぞって集まり、非常に賑やかで華やかな雰囲気が広がった。玉鬘の住まいとしては、承香殿の東側が彼女のために用意されていた。西側には式部卿宮の王女が住んでいた。同じ建物内で、中廊下ひとつを隔てただけの距離だったが、実際の心の距離は大きく離れていただろうと語られている。というのも、ふたりは微妙なライバル関係にあったからだ。この頃の後宮は、女たちが互いに美しさや教養を競い合い、まさに華やかな時代であった。身分がそれほど高くない更衣たちはあまり出てこられず、中心になっていた。
2025.08.16
コメント(26)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 26〕
源氏物語〔31帖 真木柱 26〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。大将は宮(妻の母)に面会を申し出たが、「風邪でこもっているから」と断られ、気まずさを感じながら宮邸を後にした。二人の息子を車に乗せて話しながら帰る途中、六条院(源氏の屋敷)へ連れて行くことはできず、自分の邸宅に彼らを置くことにした。そして「ここにいなさい。お父さんはいつでも会いに来られるから」と言い聞かせた。子どもたちは悲しそうに心細い目で父を見送った。それがあまりにいじらしく、大将も思わず胸が詰まるような思いがした。しかし、それでも美しい玉鬘(現在の恋人)と、精神的に不安定で自暴自棄になっている正妻を比べてしまう。自分の今の幸福の方が断然大きいと感じざるを得なかった。このようにして、大将はそれきり正妻に対して何の言葉もかけなかった。あのとき自分が受けた侮辱的な仕打ちがあまりにも強烈で、その反動として冷淡な態度をとることになり、宮邸の人々は悔しく思っていた。このことは紫の上(大将の継母)にも伝わり、彼女の耳にも入ったのだった。この場面は、夫婦の愛が壊れてしまったこと、親子の情と夫婦関係の断絶、そして大将の心の揺れ動きが繊細に描かれていて、光源氏の時代とはまた違った世代の愛と苦悩が浮き彫りになっている。玉鬘が尚侍(ないしのかみ)として宮中に出仕することになった背景や、その時の周囲の人々の思いや状況が描かれている。まず、大将(内大臣)は、かつての正妻とのいざこざによって玉鬘が不安や憂鬱な気持ちになっているのを見て、気の毒に思っていた。彼女が「私までも恨まれることになるのがつらい」とつぶやいたことに、大将は同情しつつも、「恋愛や人間関係というのは思うようにいかないものだし、この件で帝(陛下)も機嫌を悪くしておられる。兵部卿の宮も最初は怒っていたようだが、事情を知って納得されたらしい。
2025.08.15
コメント(23)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 25〕
源氏物語〔31帖 真木柱 25〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。夫人は会おうとしなかった。右大将(夕霧)とその正妻との関係が冷えきってしまい、修復の見込みがない様子が描かれている。まず、大将の母である御息所(宮)が、正妻に向けてこう忠告をした。「もう夫に会う必要はない。新しい女性に心が移っているという話は、今に始まったことじゃない。あの人が若い女を求めているという話はずっと前から聞いていたことで、そんな人が今さらあなたのもとに戻ってくることなんて望むだけ無駄。しかも、あなたが情緒不安定でまともじゃないということを、ますます世間に認めさせるだけになる」と。これは、正妻にとってはかなり突き放した言い方だったが、事実でもあり、反論できる内容ではなかった。大将自身も、こうした家の内情を恥ずかしく思っていて、「若い夫婦の喧嘩みたいなことで、事の重大さが分かっていなかった。子どもがいるということで妻の気持ちを信頼しすぎた自分の甘さは、どう言い訳しても許されないと思う。でも、これからのことはなるべく穏やかにしてもらいたい。もし今後、妻のほうに問題があれば、そのときは世間が黙っていないだろうから、その時に思い切った対応をすればいい」と困った様子で周囲に伝えさせていた。大将は、せめて娘の姫君にだけでも会いたいと願ったが、姫君は出てこなかった。長男の男の子はすでに十歳で、童殿上として宮廷にも出仕しはじめており、見た目は特別美しいわけではないが、貴族の子らしい品があって評判もよかった。彼は、すでに両親の不和をそれなりに理解できる年齢になっていて、父の様子にも複雑な気持ちを抱いていた。次男はまだ八歳くらいで、顔立ちが母親である姫君に似てとても愛らしかった。大将は彼の髪をなでながら、「お前だけが父にとっての大切な形見だ。これからは、お前を見て過ごすんだよ」と涙ながらに言うのだった。
2025.08.14
コメント(28)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 24〕
源氏物語〔31帖 真木柱 24〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。もともと穏やかに家の片隅で慎ましく暮らしていけるような、そんな素直さが妻にはあると思っていた。急に話もなく宮家から迎えが来たのだろう。こういうことは世間にも知れ渡り、自分が悪いと誤解されかねないから、まず一度は話を通してみようと思う」と語って出かけることにした。このとき、大将は上等な袍をまとい、柳色の下襲、青鈍色の中国製の錦の指貫を身に着け、すっかり正装していた。立派で重厚な身なりはまさに高位の官人らしく、女房たちから見ても、姫君の夫として決して見劣りするような人ではなかった。しかし尚侍(妻)は、自分の家庭の悲劇が人に知られるようになったことで、自分の立場がいたたまれず、大将の親切ささえも煩わしく感じていて、大将が出かけていくのを見送ろうともしなかった。宮家へ抗議に行く前に、大将はまず自分の邸に立ち寄った。すると、木工の君などの女房が出てきて、夫人が去った日のことをいろいろ語ってくれた。大将は、娘のことを聞いたとき、ずっと自制していた心がついに抑えきれず、ほろほろと涙を流し始めた。その姿は非常に哀れだった。「いったい、どうしてこんなことになったのか。病弱で普通ではないあの人を、私は長い年月、どれほど気遣ってきたことか。それがまったく伝わっていないというのか。軽々しい男ならとっくに見限っていた。でも、もう仕方がない。あの人は、どこにいたって心は死んだも同然だ。だけど、残された子どもたちはどうなるんだろう」と、涙をこぼしながら語った。そして、真木柱の歌を読んだ。筆跡は稚拙だったが、その中に込められた娘のやさしい気持ちはしっかりと伝わってきて、大将は途中の車中でも涙を拭いながら、宮邸へ向かった。
2025.08.13
コメント(23)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 23〕
源氏物語〔31帖 真木柱 23〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。聡明な人は、誰かが悪いことをしても、目の前でそれを責めるようなことはせず、自然に報いを受けるものだと見守っているものだ。そう考えていた私自身が不運だったのだ。あの方は冷静に物事を見ていて、過去のことの報いとして、ある時は手厚く、ある時は厳しく対応しようとしているのだろう。私のことも、ただの妻の父ではなく、大切な存在として扱ってくれて、一度は驚くほど華やかな祝いの宴まで開いてくれた。それだけでも、私はありがたいと思っている。それを生きがいとして、あとのことはもう諦めるしかないのだろう」こう言った父宮の言葉にも、母はますます怒りを燃やし、源氏とその妻に対する呪いのような言葉を次々に吐いた。彼女にはもともと穏やかさや寛容さといったものがなく、いつも激情に任せて振る舞う性格だった。この場面では、家を離れる別れの悲しみと、娘を傷つけられた母の怒りが対照的に描かれている。特に、母の激しい言葉と、父の冷静で諦めに満ちた姿勢が印象的で、源氏物語の中でたびたび描かれる「感情と理性」「女の立場の弱さ」「人間関係の複雑さ」が鮮明に表れている。そして、「愛されなかった女の恨み」というものがどれほど深く、醜くなりうるかが強く伝わる場面でもある。大将は、自分の妻が宮家に帰ってしまったと聞いて、まるで若い夫婦の痴話げんかのような出来事だと呆れた。自分の妻はそんな突飛な行動を取るような性格ではないと思っていたし、こんなふうに家を出るなど、妻の意思というより、宮家が軽率に迎えを寄越した結果ではないかと考えた。子どももいるし、妻の立場を思えば世間の目も気になる。自分が動いてなんとかしなければならないと心を悩ませた末に、こうした異常な出来事があったことを人に話しながら、「気持ちとしては、かえって吹っ切れたような感じがまったくないわけではない。
2025.08.12
コメント(24)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 22〕
源氏物語〔31帖 真木柱 22〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。源氏物語の中でもとりわけ情感が濃密で、少女の純粋な思慕と、母の抑えた苦しみ、女房たちの忠誠と別離の悲しみが交錯している。道具のように使い捨てられる女たちの現実と、それでもなお言葉と歌に想いを込めて生きる彼女たちの姿が、しみじみと胸に迫る場面である。正妻がついに屋敷を後にする時、車が引かれて出ていく。その姿を、屋敷の人々は木々の間から姿が見える限り、ずっと見送っていた。この先、自分たちがこの場所を再び目にする日はないのだろうと思うと、やるせない気持ちがこみあげてくる。ただ屋敷の主人である夫人と別れるからというのではなく、この家そのものに長く住んで愛着があり、そこでの思い出が胸に迫って、涙がこぼれそうになるのだ。夫人が実家に戻ると、父宮はひどく悲しんだ。そして母(夫人の母)は泣きながら取り乱して、次々と不満をまくし立てた。「あなたは太政大臣(源氏)が親戚になったことを喜んでいるようだけど、私には前世からの因縁のある、憎むべき敵のように思えてしかたがない。あの人は、女御に対しても明らかに冷たい態度を取ったことがあったじゃない。あなたはあれを“須磨時代の恨みがまだ残っているから”なんて言ってたけど、そんな理由づけは私には納得できなかった。なのにまた今になって、玉鬘を養女にして、自分の寵愛が薄れた女に代わって、今度はまじめな男を婿に迎えようとするなんて…。これが恨めしくなくて、何だっていうの」母は感情が抑えきれず、こうした言葉を止めずにぶちまけ続けた。それに対して父宮は冷静にこう言った。「そんなに感情的に悪口を言うのは見苦しいよ。あの方(源氏)は、世間的には何一つ非難されるようなことのない立派な人物なんだから、出まかせのようなことであれこれ悪く言うのはやめた方がいい。
2025.08.11
コメント(25)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 21〕
源氏物語〔31帖 真木柱 21〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。姫君がいつも寄りかかっていた東の座敷の柱、その柱さえも、まるで誰かに奪われてしまうような気がして、それすらも悲しく感じていた。姫君は、檜皮(ひわだ)色の紙を何枚も重ねて、小さな文字で歌を書き、それを髪を結う笄(こうがい)の端で柱の裂け目にそっと押し込もうとした。「今はとて宿借れぬとも馴れ来つる真木の柱はわれを忘るな」(もう今日でこの家を出なければならないけれど、長年なじんできたこの柱よ、私のことを忘れないで)そう書きながら、泣いたり書いたりして、何度も涙で文字をにじませていた。母もそれを見て、「そんなことを…」と戸惑いながらも、自分も歌を詠んだ。「馴れきとは思ひ出づとも何により立ちとまるべき真木の柱ぞ」(たとえあなたのことを思い出したとしても、いったい何があってこの柱に心が留まるというの)母娘それぞれの別れの歌が詠まれ、女房たちの胸にもまた様々な悲しみが押し寄せてきた。庭の草木でさえ、思い出とともに忘れがたいものになっていくだろうと、誰もが感じていた。この屋敷に残る女房のひとり、木工の君は初めからこの家の者で、今後もここにとどまる。中将の君は夫人に付き従って屋敷を出ることになっていた。そんな中、別れを惜しんで中将の君が歌う。「浅けれど石間の水はすみはてて宿守る君やかげはなるべき」(浅い流れでも清らかな石間の水のように、あなたはこの家にとどまり、この家を守る人の影となるのでしょうね)「まさか、こうしてあなたと別れることになるなんて、夢にも思っていなかった」と中将の君が言うと、残る木工の君も応じて、「 ともかくも石間の水の結ぼほれかげとむべくも思ほえぬ世を」(どうなってしまうのか…石間の水のように、こんなふうに別れる運命なんて、思ってもみなかった)と言って泣きながら返した。女たちの別れの場面は、静かに、しかし深い悲しみと諦めに満ちて進んでいくのだった。
2025.08.10
コメント(23)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 20〕
源氏物語〔31帖 真木柱 20〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。無理やり出家したら、それは死後も罪になるという考えもあって、それも避けたいと思っている。そんなことを語りながら泣く母親の姿を見ても、子どもたちはまだ年若く、言葉の重みや意味までは理解できない。ただ、母が泣いている、その雰囲気を感じて、皆一緒になって悲しみ、泣き出してしまう。一方、乳母たちも母親のそばに集まり、昔の物語などでも、どんなに子どもを愛する父親でも、母親と離れて育つ子どもというのは、周囲の影響で次第に冷たく扱われるようになるのが世の常だと語り合う。そして、今現在でさえあの大将(父親)はあのように冷淡であるのだから、将来子どもたちのことを思って何かしてくれるような人ではないだろうと、みな声を落として嘆いている。その夕方、日はすでに落ち、空は雪でも降りそうな暗く重たい雲に覆われ、心細さの極まる夕暮れとなっていた。母と子、そして乳母たち、皆が涙にくれ、これから起こる別れに怯え、寒さと不安の中に沈んでいた。天気がどんどん悪くなってきたようで、雪でも降り出しそうな空模様の中、夫人の弟たちは「もうそろそろ出発しないと」と急かしながらも、涙をぬぐって別れを惜しんでいる。血のつながった家族が目の前で悲しんでいる様子に、場の空気はとても重く切ないものになっていた。姫君(夫人と大将の娘)は、父である大将にとても可愛がられてきた子で、そんな父に何も言わずにこの家を出て行くことがどうしてもできなかった。今日、父にきちんと顔を見せて言葉を交わしておかないと、次にそういう機会がいつあるか分からない、もしかしたらもう二度とないかもしれない。そう思って、顔を伏せたまま泣いて動こうとしなかった。その様子を見た母(夫人)は、「そんなふうに思い詰めると、お母さんの方がつらくなるよ」となだめるしかなかった。姫君は、もしかしたら父が今からでも帰って来てくれるのではないかというかすかな望みを捨てきれずにいた。しかし、もう日はすっかり暮れ、夜も更けてきた時間帯に、父である大将が今さら戻って来るはずもない。それは姫君も本当はわかっているのに、諦めきれなかった。
2025.08.09
コメント(23)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 19〕
源氏物語〔31帖 真木柱 19〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。「もう今までのような暮らし方はできません。たくさんの者がついて行くこともできません。何人かの者だけが一緒に行って、他の者は自分の家へ帰り、夫人が落ち着かれるのを待ちましょう」と女房たちは言い合い、それぞれ自分の荷物を運ばせて、別れ別れになる覚悟をした。夫人の持ち物もそれぞれ荷造りされて運ばれていき、身分の高い人も低い人も皆声を上げて泣いている様子は非常にもの悲しかった。そんな中、姫君と二人の男の子は、何も知らないように無邪気に家の中を歩き回っていた。夫人はその子どもたちを呼んで、目の前に座らせた。母親は、自分が不幸な運命のせいで夫から見捨てられてしまったことを自覚していて、もうどこかに行かねばならない、つまりこの家を出ていかねばならないと言う。そして、まだ幼い子どもたちを母の元から引き離さなければならないのは本当にかわいそうだと涙ながらに語りかける。姫君(長女)については、将来どうなるかまだ分からないが、とりあえずは自分と一緒にいてほしいと願い、男の子たちには、自分と一緒に行動するのではなく、父親の元に通って顔を見せる程度にしておいたほうがいいと言う。なぜなら、そうしておかないと父親に可愛がられなくなり、成長しても出世の道が閉ざされてしまうかもしれないと、先のことを見据えて忠告する。今は祖父である宮様が健在だから、最低限でも役人の末端くらいには取り立ててもらえるだろうけれど、世の中は父親が新たに親類になった二人の大臣の影響下にあり、その大臣たちは自分のことを良く思っていない。そんな自分についてくる子どもたちは、損をするばかりで、将来出世など望めなくなるだろうと、母親は現実を直視して子どもに語る。だからといって、世をはかなんで出家して山や林にこもるようなことになってしまうのは、母として耐えがたい。
2025.08.08
コメント(25)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 18〕
源氏物語〔31帖 真木柱 18〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。大将は、妻のためにも、自分の世間的な名誉のためにも、そばにいればきっと何か不名誉なことが起こると恐れて、屋敷に近づこうとはしなかった。たまに家に帰っても、正妻のいる棟には寄らず、離れた棟で暮らし、子どもたちを呼び寄せて見て楽しむだけだった。子どもは、十二、三歳くらいの女の子が一人と、あとに男の子が二人いた。ここ数年は夫婦としてもほとんど断絶したような暮らしになっていたが、それでも正妻という地位だけは昔のまま尊重していた。それが今ではこのような事態となり、正妻もついに終わりが来たのだと感じ、女房たちもそのことを悲しく思うよりなかった。そのことを耳にした妻の父親(朱雀院)は、「そんな冷たい仕打ちを受けてまでまだじっと我慢しているのか。それでは自尊心も名誉心もない女だ。わしが生きているうちは、そこまで屈辱的な思いをする必要はないのだ」と伝え、急いで迎えの使者を出した。ちょうどそのころ、妻は少し回復し、自分の不幸な境遇をしみじみと悲しんでいた。そのときに父からの言葉が届いたものだから、「今になってまで父の言葉に逆らってここにとどまり、夫に完全に捨てられる日を迎えるなんて、これ以上の恥はない」と思い、ついに実家へ戻る決意をした。妻の弟たちのうち、左兵衛督は高位の官職についていたため人目を避けて、それ以外の中将・侍従・民部大輔などが三台ほどの車を用意して迎えに来た。結局こうなることは予想していたが、いざ今日限りでこの屋敷を出て行かねばならないと思うと、女房たちは皆悲しくなって泣き合った。
2025.08.07
コメント(23)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 17〕
源氏物語〔31帖 真木柱 17〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。日が暮れるとすぐ、大将は外出の準備を始めた。しかし、着るもの一つとっても、夫人はろくに世話をしない。彼女の用意する衣服は、流行遅れで柄や色も不釣り合いなもので、大将は内心不満だった。昨夜着た衣装も、火にあたっていたために焦げ臭さが抜けず、香の移った小袖類までもそのにおいが染みついていた。これでは、嫉妬に狂った妻に襲われたとでも言っているようで、先方に不快な思いをさせるのではないかと思い、結局すべて脱ぎ捨てて風呂を沸かし、ひと風呂浴びてから出かけることにした。木工の君は、主人のために香を焚きながら、和歌を詠んだ。「一人ゐて 焦るる胸の 苦しきに 思ひ余れる 焔とぞ見し」――あまりに露骨な態度をとるから、見ている私たちまでいたたまれなくなります。そう言いながら、袖で口元を覆う木工の君の目は、大将に対してきつい非難の色を宿していた。それを受けながらも、大将の心にはただ一つ――「どうしてこんな女と夫婦になってしまったのか」との後悔ばかりが渦巻いていた。まことに情けない話である。大将は、「自分のことでいろいろ悩んで苦しんでいると、煙のように心もやもやと悲しみが立ち上ってくる。こんなみっともない騒ぎが世間に広まったら、相手の家族だって自分を悪く思うだろうし、自分はどっちつかずの情けない立場に落ちるしかない」と嘆いて、屋敷を出ていった。たった一晩明けただけで、玉鬘は以前にも増して美しく見え、大将の愛情はますます彼女だけに向かっていった。そのため、もう自分の家に帰る気にもなれず、そのままずっと玉鬘のもとにとどまり続けていた。一方、正妻の病気は相変わらずで、修法などの祈祷をしてもまったく効果がなく、時には取り乱して大声で人を罵るという知らせも届いていた。
2025.08.06
コメント(25)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 16〕
源氏物語〔31帖 真木柱 16〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。夫人はといえば、夜通し僧に数珠で肩を打たれ、引きずられ、泣き叫び、わめき続けていた。その声を聞いていれば、大将が気味悪がってうとましく思うのも無理はないと思えるほどだった。ようやく少し落ち着き、まどろんだのを見計らって、大将はその隙に玉鬘に宛てた手紙を書いた。その手紙にはこう書いてあった。「昨夜から急に病人が出てしまい、しかも雪がひどく降っているので、出かけるには忍びないと考え、やむなくお訪ねするのを断念しました。しかし、理由は雪ではなく、私自身の心の中が凍りつくような寂しさに包まれたからです。あなたは信じてくださるとは思うのですが、そばにいる人たちが適当なことを言って、誤解させていないかと心配しています」そして最後に和歌が添えられていた。「心さへ そらに乱れし 雪もよに 一人さえつる 片敷の袖」この苦しみは耐えがたい、と結んであった。白い薄様の紙に、重く湿ったような筆跡で書かれたこの手紙は、大将らしい品格のある筆致で、学識のある男の書いたものだった。だが、当の玉鬘は大将が来なかったことについて、何の痛みも感じていないようで、情熱のこもった手紙をただ何気なく目を通しただけで、返事さえ寄越さなかった。一方の大将は、そんな気持ちの差にも気づかず、家の中でどんよりとした一日を過ごした。夫人はまだ今日も苦しんでいたので、大将は修法をさせたりして、その場を取り繕った。彼の心の中では、せめてしばらくの間だけでも、夫人に発作のない静かな状態でいてほしいと祈る気持ちがあった。物の怪に取り憑かれていない時の妻は、もともと愛すべき穏やかな性質の女であることを知っていたから、それを思えば我慢できた。ただ、もしそうでなかったら、もうこんな女など見捨ててしまっても惜しくはないと、正直な気持ちもあった。
2025.08.05
コメント(25)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 15〕
源氏物語〔31帖 真木柱 15〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。一方で、夫人は静かに横になっているように見えたが、ふと身体を起こすと、衣装をあぶっていた籠の下に置いてあった火入れをつかんで、そっと夫の背後へ近づいた。そして、誰の目にも止まらぬ一瞬のうちに、その火入れを大将に向かって投げつけた。大将は、何が起こったのかも理解できず、ただ呆然として立ち尽くした。火入れの中の細かい灰が目にも鼻にも入り込み、すぐには何も見えず、何も感じられなかった。しばらくして灰を振り払ったが、部屋じゅうはもうもうとした灰で包まれていて、体にも衣服にもすっかり灰が降りかかっていた。結局、大将は身にまとっていた衣をすべて脱ぎ捨てざるを得なかった。もしもこれが夫人の正気の上での行動であれば、誰が彼女を憐れむだろうか。ただ、これはいつもの「物の怪」が夫人に取り憑いてさせたことなのだと、女房たちは思っていた。だからこそ、女房たちはただ同情し、騒ぎながらも大将に急いで着替えをさせていた。しかし大将の頭から肩から、髪の先にいたるまで灰が積もっていたので、どこまでも灰だらけになった気がして、あの美しく整った六条院へこのまま行くわけには到底いかなかった。気持ちを冷ます間もなく、見苦しい姿で足止めを食らった大将は、恨めしさと不快さでいっぱいになっていた。大将は、爪弾きにされるような目にあい、怒りと憎しみが心に満ちていった。さっきまでほんの少しでも感じていた妻への情など、すっかり消え失せた。ただ今は下手に感情を荒らげても損にしかならない時で、下手に動けば、ようやく手に入りかけた新しい幸せに水を差すことになるかもしれない。そう思って、大将は夫人に対して腹を立てながらも、夜中にもかかわらず僧を呼び寄せ、加持祈祷をさせていた。
2025.08.04
コメント(22)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 14〕
源氏物語〔31帖 真木柱 14〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。私の凍りついた涙もきっと解けていくと夫人はそう言いながら、火入れを運ばせて、大将が外出する衣服に香を焚き込めさせていた。自分自身は、もう構うこともなく着古した衣服をまとい、ひどく痩せた弱々しい姿で、気持ちが沈み込んだようにじっと座っていた。その姿を横目で見ながら、大将の胸には申し訳なさと後ろめたさが重くのしかかっていた。どうしてこんな健気な人に、心が冷めてしまったのか、自分でも割り切れないままでいた。夫人の目が泣きはらされて腫れているのは、見た目としては確かに美しくはなかったが、それすらも大将にとっては決して悪いとは感じなかった。長い間、ただ二人きりで寄り添いながら生きてきた年月を思えば、今になって別の女に心を奪われている自分のことがどうしようもなく軽薄な男に思えた。そうは思うのだが、それでも新しく思いを寄せている相手に会いに行くという興奮はどうにも抑えることができない。ため息をついてはみるものの、そのため息もまったく心から出たものではなかった。やがて大将は着がえを始め、小ぶりの火入れをそっと袖の中へ滑り込ませ、香の匂いをしっかりと身にまとった。身につけた衣装は、着慣れていて自分によく馴染んでいた。顔立ちは源氏ほど華やかではないが、くっきりとした男らしい輪郭には気品があり、いかにも貴族らしい風采を備えていた。侍所には供の者たちが集まっていて、誰かが「雪が少しやんできたようですね。もう出かける時間ではありませんか」と、大将の顔色をうかがいながら声をかける。それはあくまで遠回しで、真正面から外出を促すような言い方ではなかったが、誰もが大将の心を察していた。中将の君や木工の君といった家人たちは、「悲しいことになってしまいましたね」と顔を曇らせながら、それぞれ自分の床へと戻っていった。
2025.08.03
コメント(23)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 13〕
源氏物語〔31帖 真木柱 13〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。だが、実際には妻はあまりにも静かでおおようで、抗議も執着も見せてこない。そうなると逆に心が痛むだけで、大将はもどかしさと罪悪感に悩まされていた。だからこそ、格子も下ろさせずに縁側近くに座って、降りしきる雪に染まる庭をただ黙って見つめていた。そんな様子を、妻は遠くから見ていた。そして、やがて静かに言った。「雪はますます深くなっていくようですよ。もう遅い時間ですし」その言葉には、外出を勧めるような響きがあった。大将に対してもう執着など持っていない、引き止めても無駄だとどこか諦めたような様子があって、その哀れさが大将の胸に沁みた。大将は「こんな夜にどうして」と、いかにも行く気のないような口ぶりで返した。だがそのすぐあとには、まるで反対のことを言い出す。「しばらくはあなたの気持ちがわからなくて、身近にいる女房たちからいろんなことを吹き込まれたりして、あちらも疑ったりするだろう。それに、大臣も双方からこちらの動きを見張っているわけだから、間をおかずに通って信用を得る必要があるんだ。あなたには悪いけれど、少し気長に見ていてほしい。もしあちらに通っても、すぐにこちらへ連れてくることになれば、偏って一人を愛しているようには見られずに済む」「それに、今日のようにあなたが落ち着いていて、物の怪も起こらない時なら、私の気持ちも外に向かわなくなって、自然とあなたのことだけが愛おしく思えるようになる」そんなふうに、自分の浮気を正当化するようなことを、少し苦しげな様子で語っていた。それを聞いて妻は、やわらかく、しかし確かにこう言った。「たとえ家にいてくださっても、お心だけが外に向いていては、私はかえってつらいのです。どうか、どこにいらしても私のことを思ってくださるなら、それだけで……私の凍りついた涙もきっと解けていくと思います」
2025.08.02
コメント(25)
-

源氏物語〔31帖 真木柱 12〕
源氏物語〔31帖 真木柱 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 31帖 真木柱 まきばしらの研鑽」を公開してます。宮様がいろいろ気に病んで、私の名誉や世間体のことまで心配してくださるのが、ただただ申し訳なくてなどと、だから私は、もう実家へは帰りたくないと思っているんです。六条の大臣の奥様、紫の上様は、私にとって他人じゃありません。外で育ったあの方が、大人になってから養女である玉鬘のために、姉である私の夫を婿として与えたということを、宮様は怒っていらっしゃるようですが、私はそんなふうに思っていません。私はただ、あちらの様子を静かに眺めているだけです。その言葉を聞いた大将は、少し寂しげに笑って、「こんなに君が筋の通った話をしっかりできるのにね、病のせいで時々取り返しのつかないことになるんじゃないかって、それが気がかりなんだ。あの六条院に住んでいる紫の上は、この件に何も関係してないよ。今も、大臣にとってはとても大事なお嬢様として大切にされている人だ。だから、玉鬘のことなんて、別に気にしてるわけがないんだ。君が恨んでるなんてことが、あの方の耳に入ったら、それこそ困るだろう?」そんなふうに言って、大将は一日中、夫人のそばにいて、優しく語りかけていた。だが、どこか自己中心的で、世間体や体裁ばかりを気にする彼の言葉には、利己的な響きが滲んでいて、完全に心からのものとは思えないようなところがあった。日が暮れると、大将の心はもう抑えがたくうずいていた。どうにかして一刻も早くこの家を抜け出したいと、気ばかり焦っていた。しかし外では雪が激しく降っていた。こんな悪天候のなかを出歩くのは、周囲の目に非常識で薄情な振る舞いと映るだろう。もし妻が嫉妬深く感情をぶつけてくるような人なら、それを口実にこちらも堂々と応じて、言い合いの末に出ていく理由にもできる。
2025.08.01
コメント(22)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- ポメラニアンとの毎日
- 💝【メルカリ】宛名シール 差出人シ…
- (2024-07-04 08:35:07)
-
-
-

- 海水魚との生活
- 海水水槽は今年で14年になります(*…
- (2025-01-05 15:26:03)
-
-
-
- ◆かわいいペットと泊まれるお宿~◆
- 「🐾愛犬と一緒に山の温泉へ🏞️|湯山…
- (2025-03-30 09:00:10)
-