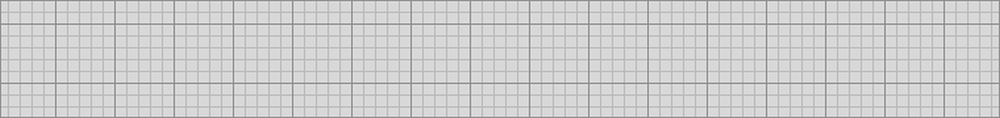2025年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 20 完〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 20 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。帝の容姿はこの頃ますます麗しく、源氏と見紛うばかりで、そばに仕える源中納言までもが同じ美貌を映すように見えた。中納言にとってはこれ以上ない幸運であったが、一方でその美は源氏に比べると気高い気品にはわずかに及ばず、ただ鮮やかで際立つ美しさだけは中納言の方に勝っているようにも思われた。彼は笛を奏で、その音色が合奏に加わって響き渡った。階段のあたりでは殿上人たちが歌を合わせ、弁の少将の声がひときわ優れて耳に残った。六条院に集まった人々の姿が描かれ、そこに居合わせた者たちは、ただ偶然に集まったのではない。まるで前世において善い行いを積み、その功徳によって華やかな世界に生まれ合わせた者たちであるかのように感じられた。六条院の夜は華やかで、贅を尽くした調度や衣装の美しさが人の目を奪い、そこに響く音楽は高雅で深い余韻を残し、人々の心を大きく揺り動かした。その場の空気は、ただの宴というよりも、この世の栄華の極みが凝縮された夢のような光景であり、見聞きする者の胸に強い感銘を与え、まさにこの瞬間を生きることこそが人間の幸福なのだと思わせるほどであった。六条院の夜のまばゆい光景がただ華やかに描かれているだけでなく、その背後には世代の移り変わりという深い意味が込められている。そこに集う若い人々は、あたかも自分たちの力で得たかのように、父の代が長い年月をかけて築いてきた権勢や名誉を自然なものとして受け取り、その栄華のただ中で遊びや歌や舞を心から楽しんでいる。彼らの姿には、未来への希望や勢いがあふれ、今を生きる喜びに満ちている。しかし一方で、その場を見守る年長者にとっては、自分たちが築き上げてきたものがすでに次の世代に引き継がれ、自分たちは過ぎ去ろうとする時代の側に置かれているという現実を否応なく感じさせる。まばゆい灯りや音楽に包まれた六条院の夜は、若さに支えられた幸福の象徴である。しかし、その背景には、父の世代がすでに感じ始めている衰えや隔たりがあり、自分たちが過ごしてきた時代の重みや限界を痛感している。そのため、若い世代の無邪気な幸福が強調されればされるほど、年長者にとってはかつての栄光が過ぎ去っていくことを実感させ、心に寂しさや哀感を呼び起こすことになる。六条院の夜は、きらめく音楽や華やかな衣装、優雅なふるまいによって極致の美を示しているが、その美しさは同時に儚さを抱え込み、父と子の世代の対比によって、一層鮮やかに幸福と哀しみが交錯する場面として描かれている。(完)明日より34帖 若菜(わかな上) を公開予定。
2025.09.30
コメント(23)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 19〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 19〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。「色あざやかな籬の菊も、折にふれて袖を触れた秋を恋い慕うように咲いている」という歌が詠まれる中、かつて源氏と共に舞った右大臣は、自らもこの世の幸福を得ている身でありながら、帝の御子として生まれた源氏が今や到達している栄光の高さと、自分との間に横たわる大きな隔たりに改めて気づかされるのだった。ちょうどその時を待っていたかのように時雨がしとしとと降り始め、大臣の胸の思いを映すように庭を濡らしていった。大臣は「紫の雲にまがう菊の花は、澄んだ世に輝く星のように見える。まさに今こそ咲くべき花だ」と歌を詠んで源氏を讃えた。夕風が庭を吹きわたり、散り敷かれた紅葉の赤や黄、渡殿に掛けられた錦の濃淡と入り混じり、どれが自然でどれが人工の色かわからないほどの華やかさとなっていた。その庭では、高貴な家の少年たちが白橡や臙脂、赤紫の衣を着て、額にみずらを結い、短い舞をひらひらと舞いながら紅葉の木蔭へと入っていく。その光景は、夜の闇に呑まれてしまうのが惜しいほどであった。奏楽の場も大げさにしつらえたものではなく、帝の御前で管弦がそのまま奏される。御所の楽器が持ち出され、夜が更けるとともに演奏が本格的に始まった。朱雀院は「宇陀の法師」の古い曲を久々に耳にし、昔を思い起こして胸に沁み入るような感慨を抱いた。その折に「秋を経て時雨が降るこの里の人も、紅葉の折にこそ心を寄せるものだ」と、今の境遇を寂しげに映す歌を口にされた。帝はそれを受けて「この庭の錦を、ただの紅葉と見るだろうか。昔のためしを引き継いで咲き誇る色なのだ」と返された。
2025.09.29
コメント(21)
-
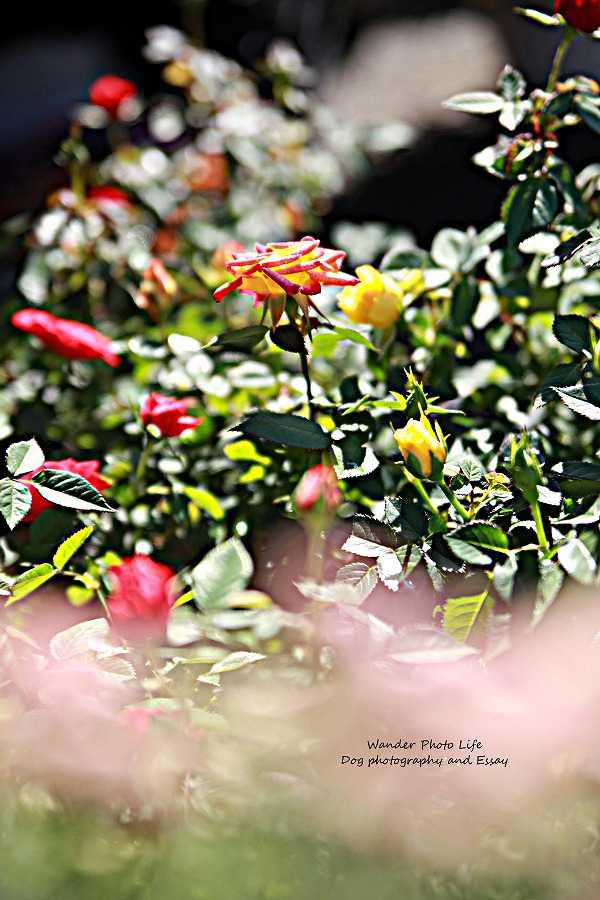
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 18〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 18〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。六条院では万端の準備が整えられ、当日、午前十時に行幸が始まった。まず馬場殿に入御があり、左馬寮・右馬寮の馬が整列し、そのそばに左近衛・右近衛の武官が立ち並んだ様子は、まるで五月の節会の作法を思わせる壮観さだった。午後二時には帝が南の寝殿へ移る。その通り道となる橋や渡殿には錦が敷き詰められ、視線が触れる場所には幕が張られて、すべてが美しく整えられていた。東の池には船が浮かべられ、御所の鵜飼や院付きの鵜飼が鵜を放って、小魚を捕らせる。特別に献上するほどの大事ではなく、通りすがりの目を楽しませる余興であった。さらに、西の町の庭は紅葉の色が際立って美しく、南の町との間の壁を取り払い、中門を開けて余すところなく眺められるようにした。二つの御座が設けられたが、主人である源氏の御座は帝より低く作られていた。ところが宣旨によってこれが改められた。世の人々から見れば限りない光栄のしるしだが、帝はなお六条院を一段高く扱うことにためらいがあり、その隔たりを残念に思っていた。宴では、左近少将が池の魚を台に載せて差し出し、右近少将は北野で狩った鷹飼の鳥を献上した。太政大臣の命でそれらは大御馳走として調理され、列席した親王や高官たちの膳には常とは違う珍しい料理が並んだ。やがて人々が酔いに浸るころ、伶人が呼ばれ、控えめで洒落た奏楽が響き、御所の童子たちが舞を披露した。朱雀院の紅葉の賀の日が人々の脳裏に甦るようであった。「賀王恩」の曲が奏されると、太政大臣の十歳ほどの息子が舞い、帝は感激して御衣を脱いで与えた。父の大臣もその場で舞を披露し、祝いの場は一層華やかになった。主人の源氏は、その折に菊の花を折って大臣に授けたが、その時ふと「青海波」の舞の場面を思い出していた。あのかつての舞台と今が重なり、歳月と栄華の移ろいを自らしみじみと感じていたのである。
2025.09.28
コメント(24)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 17〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 17〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。中納言は「自分こそは岩間から湧き出る真清水のように、かつての主の行く先を知っている」と詠み、雲井の雁は「亡き人は影すら見えず、冷ややかに流れる水に心を託す」と返した。その時、太政大臣が宮中からの帰途に立ち寄った。かつて宮が住んでいた時と変わらず、いくつもの棟を見事に使いこなしている様子を見て、大臣は胸を濡らす思いがした。中納言は少し頬を赤らめて舅の前に立ち、夫婦は若々しく美しかった。女は、絶世の美女というほどではないが、十分に愛らしい美しさを備えていた。男はとにかく華やかで整っていた。年老いた女房たちは、大臣が来たことを喜び、古い話を持ち出した。その折、二人の交わした歌の紙が目に入り、大臣はそれを読んでしみじみとした気分になった。そして「この水にも私が問いたいことはあるが、今日は祝い事ゆえ言わないでおこう」と言い、老木と小松に寄せた歌を詠んだ。その場にいた中納言の乳母である宰相の君は、当時の大臣の処置に今も恨みを抱いていたから、この場を好機とばかりに声を発した。「二葉より名高い園の菊だから、浅い露にも色あせることはない」という歌は、雲井の雁と源中納言の結びつきを「揺るぎない根を張った松」にたとえて寿ぐものであった。集まった女房たちの口から同じような感想がもれて、源中納言は心地よく受け止めたが、雲井の雁は恥ずかしさに顔を赤らめるばかりであった。かつては引き裂かれた恋の記憶を持つ二人にとって、周囲から「根強い結びつき」と認められることは慰めである一方、雲井の雁にはまだ気恥ずかしさが拭えないのだった。十月下旬、六条院での行幸が予定された。これは帝自らが訪れる大きな盛儀で、しかも源氏が朱雀院までも招いて開くという、類を見ない華やぎの日であった。人々は今までにない珍しい催しとしてこの日を待ち望んだ。
2025.09.27
コメント(22)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 16〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 16〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。乳母は恥ずかしさを感じつつも、その言葉には痛みを含んだ愛らしさを覚え、かえって胸を打たれた。宰相中将にとって、今や官位も家柄も十分に備わり、誰もが羨む立場となった。だが胸の奥には、かつて卑しい出自と嘲られ、未来を疑われた自分への忘れがたい記憶が横たわっていた。今の栄光はその反動としての自負を強めるが、それは同時に、過去に染みついた「卑しさへの劣等感」を決して消し去ることはなかった。源中納言は、自分の出自をめぐってかつて辛辣な言葉を浴びせられたことを忘れてはいなかった。乳母の大輔に渡した白菊の枝に託して過去を思い出し、「あの時は惨めに言われたが、今は違う」と晴れやかに笑ったものの、その背後には、劣等感と反発心が折り重なった複雑な思いがあった。乳母は恥じ入りつつも、その言葉の裏にある切なさを理解した。昇進して中納言となったことで訪問客も増え、元の邸では手狭になった。そこで源中納言は亡き祖母の宮が住んでいた三条殿へ移り住んだ。荒れていた邸を修理し、かつて宮の御殿だった部屋を新たに夫婦の居所とした。二人にとっては、引き裂かれた少年の日の恋を取り戻したような住まいである。庭の木々は年月を経て大きく成長し、広がった茂みを整え、水の流れも清めて、すっきりとした眺めに仕立て直した。ある夕暮れ、美しい庭を眺めながら二人は語り合った。かつて冷たい力によって引き裂かれた恋の日々を思い返すと、切なくもあり、今こそ叶ったことが夢のようでもあった。雲井の雁は、あの頃女房たちが自分をどう見ていただろうと考えると恥ずかしさがこみあげた。祖母に仕えていた年老いた女房たちも、かつての主の孫が夫婦となって戻ってきたことを喜んだ。やがて二人は水を題材に歌を交わした。
2025.09.26
コメント(23)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 15〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 15〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。紫の上には、姫君の将来がつねに気がかりであった。しかし養女として中宮の位にある女が姫君を支える存在であり、形式上の母は自分以外にはいない。そのため自然と誠意をもって仕えていくだろうと源氏は考えていた。また花散里のことは宰相中将がそばにいるので安心であると見ていた。翌年、源氏は四十を迎えることになり、賀宴の準備は朝廷をはじめ各所で進められた。その秋、三十九歳で源氏は準太上天皇の位を得た。官からの支給物は増え、権勢はますます拡大した。すでに思うままにならぬことはほとんどない状態であったが、古例に従い院司なども選ばれ、その人材も群を抜いて有能で勢いのある者たちばかりであった。けれどもこうして院の位を持ったことで、六条院に気軽に戻ることもできなくなり、源氏自身も物足りなさを覚えた。帝もまた位を譲れぬまま世間の目を気にして歎いており、その気持ちは源氏にとっても重くのしかかった。そのころ内大臣は太政大臣となり、宰相中将は中納言に昇進した。任官の礼に赴く中納言の姿は、いっそう華やかさを増し、振る舞いや容貌にも欠けるところがなかった。舅である大臣は、その姿を見て「後宮での地位争いに敗れて不遇な宮仕えを強いられるより、このような婿を迎える方がよほどよい」と考え直すようになった。宰相中将の心には、ふと昔の一場面がよみがえった。かつて「姫君は六位の男と結婚なさる運命だった」と乳母の大輔が嘆いた夜のことである。今や自分は中納言となり、世に光彩を放っている。その思いを込めて、白菊の花に紫の色が差してきた枝を手に取り、大輔に渡しながら、「あさみどり若葉の菊を露にても濃き紫の色と掛けきや---昔あなたが口にした惨めな言葉は忘れない」と朗らかに笑って告げた。
2025.09.25
コメント(19)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 14〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 14〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。だがそれは悲嘆の涙ではなく、これまで自らの出自や境遇を苦にして死にたいとまで思った命を、もっと長らえたいと願わせるほどの晴れやかな涙であった。すべては住吉の神の加護のおかげだと明石は感じた。姫君は理想的な教養と麗質を兼ね備え、東宮から格別の寵愛を受けた。宮中では、実母が正妻ではないことを陰で噂する声もあったが、それが東宮の愛に陰を落とすことはなかった。桐壺の曹司には気高くも華やかな空気が漂い、殿上人たちもここを理想的な遊び場のように思い、女房たちを恋の対象にして通うようになった。紫の上も折々に姿を見せ、明石との関係は次第に深まっていった。お互いに分をわきまえ、出過ぎることも軽蔑することもなく、まるで理想的な調和を体現するような友情がそこに成立した。その一方で、宰相中将の胸には別の影が射していた。彼は晴れやかな場に列する勅使として周囲から大きな期待を受け、典侍との密かな関係も続けながら、妻を得てようやく世間的な安定を掴んだ。だがその心は決して満ち足りてはいなかった。姫君が東宮の御息所として輝きを増すほどに、自分の子として生まれたわけではないのに、どこかで自分と結びついてほしかったという淡い願望が拭いきれなかった。源氏が娘を託す場に居合わせ、紫の上や明石が母としての位置を分かち合う姿を目にするたびに、自分の立場の限界を思い知らされる。男として出世を遂げ、恋も手に入れ、家も固めたはずなのに、なぜか心の奥底には物足りなさが澱のように残る。源氏は、このすべてを見届けながら「もう自分も出家してよい時が来た」と感じていた。彼の視線の先には、娘の未来の輝きと、それを取り巻く女たちの複雑な心があった。紫の上の愛惜、明石の劣等感と自負、そして宰相中将の満たされぬ葛藤。表向きは華やかに整えられた姫君入内の場面は、同時に、人々の心の深層に潜む不安や欲望を浮き彫りにする瞬間でもあった。
2025.09.24
コメント(24)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 13〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 13〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。自分自身が入内の式に出入りする際、輦車を許される紫の上と違い、徒歩で行かねばならない不体裁を想像すると胸が痛んだ。姫君の生母が自分であることが、磨き上げられて太子に奉られる娘にとって「玉の瑕」と見なされるに違いない。そう思うと、晴れの舞台に立つこと自体が心苦しかった。源氏は華美を避け、式を質素にしようと心がけたが、それでも姫君の晴れ姿は並みのことではなく、限りなく美しいものとなった。紫の上は姫君を真心から可愛らしく思いながらも、やがて生母に譲らねばならないことを考えると、この子を実の娘として抱き続けられたらどんなに良かっただろうと胸を締めつけられた。源氏自身も、そして宰相中将も、この一点だけはどうしても満たされない思いを抱えた。三日後、紫の上は東宮から退出し、代わって明石が御所に入る。その場で二人の夫人は、桐壺の曹司で初めて顔を合わせた。ここに至り、表向きの安定と華やかさの陰に、それぞれの女の胸に去来する痛みと譲り合えぬ母性の葛藤が、物語の核心として立ち現れるのであった。紫の上は、姫君を東宮に託す節目で明石と顔を合わせた。お互いに初めての会見でありながら、紫の上は長く知り合いであったかのように打ち解けた言葉をかけ、明石もその誠意を素直に受け止めた。二人のあいだに育ち始めた友情は、敵対や嫉妬に傾きがちな女の関係には珍しいほどの温かさを帯びていた。紫の上は、明石の気品や物腰に「なるほど源氏が惹かれるのも当然だ」と感じ、明石はまた、華やかな紫の上を見て「この人こそ正妻にふさわしい」と納得しながらも、同時に自分もまた特別な地位を得たことへの自信を抱いた。けれど、輦車に守られ華やかに退出していく紫の上の姿を目にしたとき、女御に比肩するその威容に思わずため息が漏れた。姫君は夢のように美しく、明石はその姿に涙した。
2025.09.23
コメント(22)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 12〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。勅使の出発地である内大臣家には多くの人が集まり、宮中や東宮からも特別の贈り物が届き、六条院からも厚い贈与がなされ、頭中将の後ろ盾の大きさが際立った。その一方で、宰相中将は祭礼の華やぎのなか、自身の使いを通して藤典侍へ手紙を送っていた。二人は互いに思い合う恋人同士であったが、宰相中将が雲井の雁を正妻に迎えたことで、典侍は深い悲嘆を抱えていた。表向きの晴れやかさとは裏腹に、彼女の胸には敗北感と寂しさが満ちており、宰相中将の新たな人生の安定と彼女自身の孤独とが、鮮やかな対照を成していた。宰相中将は、藤典侍との密やかなやりとりをまだ続けていた。祭礼の慌ただしい中にも彼女から返歌を受け取ると、結婚後もこの人とは隠れた恋人として関係を保つのだろうと感じた。表向きは雲井の雁を正妻に迎え、世間体を整えた宰相中将だが、内心ではまだ典侍との縁を断ち切れない。その執着は、自分にとっての「本当の心の寄る辺」をどうしても見捨てられないという迷いを示している。一方で物語の大きな焦点は姫君の入内である。紫の上は母として姫君に付き添わなければならないが、自分の立場や体力を考えると長く務めきれないとわかっていた。源氏もまた、この機会に明石を姫君に付けておくべきではないかと考える。紫の上も同じ思いを口にした。「この子はまだ小さいし、女房たちだけでは心細い。実の母である明石がいてくれれば安心できる」と。源氏は夫人と心が一致したことを喜び、明石に伝えると、明石は涙が出るほど嬉しく思った。長い間胸に抱いていた望みがようやく叶うと感じ、自分の女房たちの装いも紫の上に劣らぬほど華やかに準備させた。しかしその喜びの裏で、明石は苦しい思いも抱いていた。姫君の祖母の尼君は、孫の晴れ姿をもう一度だけ見たいと願いながら命をつないでいて、その切なさを明石は哀れに思った。
2025.09.22
コメント(23)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 11〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。表向きは盛大な祭礼と参詣の華やぎですが、そこに過去の記憶、無常観、恋の残酷さなどが折り重なっている。姫君の入内が二十日過ぎと決まると、紫の上はその安泰を祈って上賀茂に参詣した。六条院の妻たち、花散里や明石の君にも声をかけるが、彼女たちは紫の上に並ぶとどうしても見劣りがすると思い、誰も同行しない。結局、紫の上の行列は二十台ほどの車と控えめな前駆であったが、それでも十分に目を引くものであった。祭礼の日であったから、一行はその後桟敷に入り、勅使の行列を見物した。他の夫人たちもそれぞれ女房を車に乗せて見物に出していたので、桟敷前には豪華な車が並び立ち、どれが誰の夫人のものであるかが一目で分かるほどであった。その光景を目にして源氏は、若き日に六条御息所の車が左大臣家の人々に押し潰された葵祭の屈辱を思い出す。彼は紫の上に向かって、「権勢に頼んで人を押しのけるような振る舞いは結局身を滅ぼす。あの時の人も恨みを背負って亡くなってしまった」と語る。そして「残された者だってどうだろう。中将(頭中将)は凡庸な出世しかできぬ人臣でしかないのに、中宮は比類なき地位を得た。当時を思えばなんという変わり方か。人生とはもともとそういうものだ。無常の世だから、生きている間は華やかに暮らしたいと思うけれど、私が死んだあとにあなたが寂しい暮らしをするようなことになれば、今の派手さがかえって惨めに見えるだろう。だから私は必要以上に贅を尽くすことを控えているのだ」と言い、しみじみとした無常観をにじませる。やがて高官たちが桟敷に集まってきたので、源氏は男子席のほうへ移る。その日の勅使は近衛の将官を務める頭中将で、内侍の役は藤典侍だった。
2025.09.21
コメント(25)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 10〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。源氏は「艶美」、宰相中将は「威容」とでも言うべき特色を際立たせ、比べることでそれぞれの個性が浮き上がる。六条院では灌仏会が営まれ、御所と同じ厳粛な作法が再現された。多くの公達も参会していたが、むしろ内裏よりも六条院での行事のほうが晴れやかに感じられた。宰相中将は落ち着かず、化粧や装束を整えて新婦のもとへ急ぐ。その一方で、かつて彼に思いを寄せながらも結ばれなかった若い女房たちは恨めしく感じていた。だが、長年の苦難を経てやっと結びついた二人の間には、すき間も許さぬ堅固な結びつきがあり、もはや誰も介入できなかった。内大臣は、かつて強硬に婿選びを拒んできたにもかかわらず、最終的に宰相中将に譲らざるを得なかったことを「自分の負け」と意識し、自尊心を傷つけられた。しかし一方で、宰相中将が今まで他の縁談をすべて退け、雲井の雁を誠実に思い続けたことを評価し、納得せざるを得なかった。彼にとってその誠実さは、不満を補って余りある価値を持っていたのである。雲井の雁は、女御よりもかえって幸福そうに見え、その華やかさに他の夫人や女房たちは内心おもしろく思わなかった。しかしそんな嫉妬は取るに足らぬことだった。雲井の雁の実母である按察使大納言の夫人も、娘が良縁を得たことに心から喜んだ。こうして宰相中将は、執念深く守り続けた恋をついに成就させ、内大臣の誇りすら屈服させた勝利を得る。しかしその勝利は単なる情熱の産物ではなく、長い忍耐と誠実さの積み重ねによるものであった。源氏の冷静な助言が添えられることで、宰相中将の喜びはただの歓喜にとどまらず、責任と自覚を伴う「成熟した結婚」として描かれている。源氏の姫君(紫の上の養女)が太子の后として入内する日程が決まり、賀茂詣でや葵祭見物をめぐる華やかな場面と、その背後に潜む人々の思いや対比が描かれている。
2025.09.20
コメント(21)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 9〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。宰相中将の手紙を運んだ使者の右近の丞は、これまでひそかに役目を果たしてきたが、この時はじめて「表に立つ」存在として扱われる。宰相中将の恋が公式に認められ、周囲の人々も関係を肯定的に受け入れるようになった証である。全体を通して、宰相中将はついに長年焦がれた姫君を得て、優越感と歓喜を味わう。しかしその喜びの裏には、姫君の冷ややかさや羞恥に満ちた態度が影を落とす。彼はそれを「哀れ」と感じつつもなお執拗に求める。ここに、宰相中将の恋が成就してもなお消えぬ渇望と葛藤が鮮やかに描かれているのである。宰相中将がついに雲井の雁を正妻として迎え入れ、周囲から公然と祝福されるところを描いている。しかし同時に、それまで積み重ねてきた宰相中将の執念、内大臣の敗北感、そして源氏の冷静な観察が交錯して、単なる結婚の成就を超えた人間関係の微妙さが浮かび上がっている。源氏は、前夜の内大臣邸での出来事を耳にしていた。宰相中将がいつも以上に輝く顔で現れるのを見て、彼は思わず声をかける。「手紙はもう出したのか。聡明な者でも恋のことになると平静さを欠くものだが、お前は初めの関係を大切にし、急がず時を待った。その点で凡庸な人間とは違うと認められるよ」と。源氏は祝意を示しながらも、「内大臣は頑なな性格で、自尊心が強い。今度は譲ったが、慢心して放縦に走るな。彼の気難しさを忘れてはならない」と釘を刺す。ここには、喜びを分かち合いながらもなお現実を見据える源氏らしい冷静さがある。宰相中将は晴れがましい姿で人々の中にいた。濃い直衣に香を焚き染めた小袖を重ね、父よりも華やかに見えるその姿は、源氏のしなやかな艶やかさとは異なる、力強く堂々とした美しさを放っていた。二人が並んで座していると、互いに似ていた。
2025.09.19
コメント(30)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 8〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。宰相中将は、少将が催馬楽「葦垣」を歌ったのを聞いて、自分も返しに「河口付近に土砂がたまって水が浅くなっている」と詠みたかったと思う。これは、恋の障害を越えて秘めて逢う男女の心を暗示するもので、内心では自分の恋情を露骨に重ね合わせている。対する雲井の雁は、そんなあらわな言葉を聞かされて顔を赤らめ、「軽はずみなことをしてしまった」と娘らしい恥じらいを示す。しかし男はその反応に少し笑みを見せつつ、「浅瀬にばかりとどまる存在ではない、積もった思いと酒に酔ってもう分別もつかない」と歌に託し、ついに強引に帳台の内へ踏み込んで一夜を共にする。長年の切望と今夜の酔いとが重なり、彼の恋はついに実を結ぶ。翌朝、宰相中将はすっかり気を緩めて長寝をしてしまい、女房たちが気をもむ。そこへ大臣が出てきて「得意顔の朝寝だ」と皮肉めかして笑う。伯父からもすでに半ば認められた関係として見なされていることがここで示される。中将が立ち去る姿は、寝起きであっても美しく、周囲の人々に鮮烈な印象を与えた。その後、中将はさっそく手紙を送る。以前と同じように忍んで書くが、もはや隠す必要もない状況になっているのに、雲井の雁は返事をためらい、女房たちの間でからかわれる。手紙の中には「やはり冷ややかなあなたに会うと、ますます自分が哀れに思われる。だが抑えきれない恋ゆえにまた書いてしまう」と切実な訴えが書かれ、さらに「袖にこぼれる涙を責めないでほしい」と歌が添えられていた。大臣はその手紙を見て、「字がとても上手になった」と微笑する。かつては厳しい父であったが、今や婿を認める柔らぎの姿が見える。娘が返事の歌を詠めずに逡巡していると「見苦しい」と叱るものの、父として娘の羞恥を察し、あえて立ち去ってやる。ここで大臣は、恋を咎める立場から娘を見守る立場へと変わったことが描かれている。
2025.09.18
コメント(23)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 7〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。その従順さに大臣は気を良くし、藤の葉を題材にした歌を詠む。そこから次々と和歌が交わされ、藤の花を愛でる宴が華やかに展開される。月明かりに浮かぶ藤の花は、春の他の花が散ったあとの静けさの中でひときわ映え、まさに大臣の言葉どおり「遅咲きの美の象徴」として場を彩った。音楽や歌も加わり、宰相中将が抱えていた緊張や憂いはしだいに溶けていった。しかし、宴が終盤に近づくと宰相中将は「酔いがひどくて帰れそうにない」と口実を作り、頭中将に寝所を借りたいと頼む。大臣はすでに酔い潰れたふうにして奥へ引き下がり、後のことを息子に任せてしまう。頭中将は半ば呆れつつも、妹と宰相中将を結びつけることが自らの望みでもあったため、従弟を妹のもとへ導く。宰相中将はその「妹のもとへ案内される」という事実に、自分が特別な立場を獲得したという優越感を抱く。そして、かつて「雲井の雁」と呼び慕った姫君との再会を果たす。彼女は恥じらいながらも、以前よりもさらに美しい姿を見せる。その時宰相中将は、「惨めな失恋者で終わるはずだった自分が、今こうして彼女を妻に迎えることができたのは、長年の誠実な思いのゆえだ。それなのに、彼女は冷ややかにしている」と胸の内を訴える。この一連の描写の軸には、宰相中将の「葛藤」がある。伯父の前では従順に頭を下げ、和歌や振る舞いで礼を尽くしながらも、心中では「試されている」という緊張を抱え、宴の華やかさに酔いながらも恋の行方を気にして落ち着かない。そしてついに妹のもとへ導かれた時、夢のような転機を自覚し、自らの勝利と優越を感じる。だが同時に、愛する人の冷ややかな態度がその喜びに影を落とし、歓喜と不安が同居する複雑な心境へと至るのである。
2025.09.17
コメント(25)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 6〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。宰相中将は、学問にも優れ、性格も真面目で、官吏として立派だと世間から認められているらしい、と評された。内大臣はそんな宰相中将に、礼儀正しく装いを整えて会った。最初に交わされたのはほんの少しの形式的な挨拶や真面目な会話にすぎず、やがて宴は庭の藤の花を愛でる催しへと移っていった。内大臣は藤の花について、「春の花はどれも咲き始めこそ美しいが、すぐに散ってしまうのが惜しい。その中で藤の花は夏にまでかかって咲き、色もまた人の深い愛情を象徴するようで心惹かれる」と語り、微笑んだ。その姿は気品に満ち、整った容貌がいっそう際立っていた。月明かりは藤の紫をくっきりと照らすほどではないが、それでも「藤を愛でる宴」として酒が酌み交わされ、音楽が奏でられた。やがて内大臣は酔ったふりをして、宰相中将に強く酒を勧め始める。中将は酔い潰されまいとしてこれを固辞したが、大臣は「あなたのように学問に秀でた人物が年長者を憐れんでくれないのは恨めしい。古い書物にも甥は伯父を敬い愛すべきものと書いてあるではないか。孔子の教えにも通じているはずのあなたが、私を苦しめ続けるとは情けない」と、酔いに任せたように言葉を漏らす。宰相中将はその言葉に困惑する。表向きは穏やかな宴でも、その背後には大臣が抱き続けてきた後悔と執着がにじみ出ている。酒を媒介にした感傷的な言葉の中に、大臣の「甥を近づけたい」という思いと、過去へのわだかまりが複雑に入り混じり、宰相中将はその矛先を正面から受け止めざるをえなかったのである。宰相中将は、内大臣から「甥は伯父を敬うものだ」と酔いに任せて責められ、困惑しながらも「粗略に扱ったつもりはない、祖父の代わりと思い身を尽くす覚悟だが、知らぬうちに失礼があったかもしれない」と必死に言葉を尽くす。
2025.09.16
コメント(23)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 5〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。そのことは無関心ではいられない雲井の雁に関わる家の出来事であるから、些細なことでも耳に残り、あれこれと想像を巡らせずにはいられなかった。長い年月、誠実に雲井の雁を思い続けてきた宰相中将の心が通じたのだろうか、内大臣もまた、かつてとはまるで違い、今は一人の娘の親として謙虚な気持ちを抱くようになり、宰相中将を招くにふさわしい自然な機会が訪れることを願っていた。そうした折、四月の初めに庭の藤の花が見事に咲き、紫の花房が風に揺れ合う景色を、ただ眺めるだけで終わらせてしまうのは惜しいと思った。大臣は、家で音楽の遊びを催し、夕暮れの藤の花がいっそう鮮やかに美しく見えるその折を機に、長男の頭中将を使いに出し、宰相中将を招くことにした。その時、大臣が伝えさせた言葉は、「極楽寺の法会ではゆっくりお話しする暇もなく、それが心残りでなりません。もしお時間があれば、どうぞお越しください」というものであった。そして、手紙には歌が添えられていた。「わが宿の藤の色濃き黄昏に たづねやはこぬ春の名残を」その歌の通り、美しく咲いた藤の枝に文を結びつけて送ったのである。使いを受け取った宰相中将の心は高鳴り、期待と喜びに胸を満たされた。そして恐縮の意を示しつつ返歌をした。「なかなかに折りやまどはん藤の花 たそがれ時のたどたどしくば」こうして、長く隔たりのあった両者の間に、藤の花のもとで再び近づくための契機が生まれたのである。宰相中将は、従兄の頭中将が届けた歌を見て、「気後れがして歌にならない、直してくれ」と弱音を漏らした。頭中将は「お供して行きましょう」と気軽に言ったが、中将は「窮屈な随身はいやだ」と断り、従兄を帰してしまった。そのあと、中将は父の源氏の居間へ行き、頭中将が使いに来たことを話し、内大臣からの歌を見せた。
2025.09.15
コメント(26)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 4〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。夕暮れ、花は散り乱れ、霞がたちこめて春の終わりを告げる景色を目にしたとき、中将は自然の哀愁に自らの心を重ね、いっそう深い物思いに沈んだ。人々が「雨になりそうだ」と口にしながら帰っていく声が耳に入っても、彼の視線は庭に釘付けになり、心は仏事を超えて過去の因縁に向けられていた。その時、内大臣が袖を引き寄せ、過去の恨みを解いてほしいと語りかけた。年老いてから身近な者の情けを求める心情を吐露され、祖母の法会の縁に託して赦しを乞われたのである。だが、中将にとってそれはただちに素直に受け入れられるものではなかった。自分はあの方に信頼され、庇護されるはずの存在であったのに、なぜ自分はこれほどまでに遠ざけられなければならなかったのか。なぜいまだに心を許せぬまま、外から見ると冷淡に振る舞うしかないのか。そうした疑念と屈辱が胸の奥底に根を張っており、完全に拭い去ることはできなかった。それでも中将は、祖母の遺志に思いを寄せて、つつしんで言葉を返した。「本来ならばあなたを支えに仰ぎ、守られて生きてゆくはずであった。しかし、赦しを得られぬご様子を見て遠慮してきた」と。そこには、心の奥底でまだ疼く痛みと、それを押し殺して大人の態度を保とうとする中将の苦悩がにじんでいた。この場面は、宰相中将が心の中で過去の恨みと血縁の情とのあいだで揺れ動き、表には出さない深い葛藤を抱え続けていることを際立たせている。愛する者への思慕と、父代わりである内大臣への複雑な感情とが重なり合い、彼を縛って離さない。その苦しみが、静かで落ち着いた態度の裏に潜む本当の姿として描かれているのである。天候が崩れて雨風が激しくなると、人々はそれぞれに急かされるように帰宅していった。宰相中将は、先ほどの内大臣の言葉が平生と異なって聞こえたのを思い返し、不思議に感じていた。
2025.09.14
コメント(20)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 3〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。大臣は今こそ好機と思ったのか、宰相中将の袖を引き寄せ、「なぜあなたはそんなに私を憎んでいるのか。今日の法会の仏縁に免じて、私の罪をもう許してほしい。年を取ると身近な者が恋しくてならぬのに、あまりにも厳しい仕打ちをされるのはつらいものだ」と語った。すると中将は、かしこまった様子で、「亡くなられた方のご遺志も、あなたを信頼して私を庇護してくださるようにとのことだったと承っておりました。しかし、私をお許しくださらないご様子を拝見しては、どうしても遠慮せざるを得ませんでした」と答えたのであった。宰相中将の心の内は、表面に出ることなく静かに燃え続けていた。かつての事件以来、内大臣との間には隔たりが生まれ、以前のような親しい往来はできなくなっていた。中将自身もその距離を意識しながら、あえて平静を装い、表面上は礼を欠かさず冷静に振る舞っていたが、内心では複雑な思いに絡め取られていた。どうして自分はこれほどまでにあの人に執着してしまうのか、なぜ心の安らぎを得られないのかと、絶えず自問していたのである。三月二十日の大宮の御忌日にあたり、一族が極楽寺に集まった時、中将はその場に居並ぶ高官たちに劣らぬ堂々とした姿を示し、誰の目にも立派な若者として映っていた。しかし彼の心中には、祖母の法事という厳粛さと、父のような存在である内大臣への複雑な感情が交錯していた。最も愛された祖母の供養である以上、経や供物に心を込めることは当然であったが、読経の声を響かせながらも、中将の胸には過去の屈辱と、いまだ和解できない思いが重く沈んでいた。
2025.09.13
コメント(27)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 2〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。六条院の藤のうら葉の場面では、表面上は何事もないふうに見えていても、紫の上と女三の宮をめぐる婚姻の一件以来、内大臣と宰相中将のあいだには以前のような親しみはなくなっていた。そのため、改めて話を切り出すのはためらわれ、大臣は迷っていた。新しい婿を迎えるという形をわざわざ整えるのも、人から見れば不自然に思われるだろうから、そんなやり方は避け、何かの折に直接語り合うほうが良いかもしれないと考えていた。そうして迎えた三月二十日、大宮の御忌日にあたり、一族は極楽寺へ参詣することとなった。内大臣は多くの子息を引き連れて参詣し、権勢ある家らしく多数の高官たちも参列した。そのなかにあって宰相中将は、他の高官たちにも決して見劣りせず、今を盛りとする容姿や堂々とした振る舞いによって、ひときわ気高く尊い若い朝臣に見えた。あの時以来、内大臣にとって彼と顔を合わせるのは晴れがましくも気詰まりなことであったが、今日の宰相中将は、親戚の長者への敬意を欠かさず、冷静で落ち着いた態度を保っており、その姿に大臣はとりわけ深い関心を抱いた。法会では源氏からも読経をさせた。中将にとっては最も愛された祖母である宮の法事であったため、経巻や仏像など供養の品々にも誠意をこめて仕え、丁寧に心を尽くすようすが見られた。夕方になり、参会者が次々と帰っていくころには、庭の木の花はほとんど散り尽くし、霞が漂い、春の終わりの寂しさが身にしみる景色となっていた。内大臣は母宮のかつての姿を思い出しながら、雅趣ある面持ちでその景色を眺めていた。宰相中将もまた、夕暮れの物悲しさに仏事以上に心を深く動かされ、帰りを急ぐ人々が「雨になりそうだ」などと口にする声を聞きながら、庭に心を奪われて見入っていた。
2025.09.12
コメント(22)
-

源氏物語〔33帖 藤のうら葉 1〕
源氏物語〔33帖 藤のうら葉 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔33帖 藤のうら葉〕 の研鑽」を公開してます。六条院の姫君が太子の宮へ入るための準備で、まわりは誰もが忙しく立ち働いている最中であったが、その時、姫君の兄である宰相中将は、心が物思いに囚われてぼんやりとしている自分に気づいていた。自分の心が自分で理解できないような状態で、どうしてこれほどまでに執拗にあの人を思い続けてしまうのだろうと悩んでいたのである。これほど苦しむのであれば、伯父である内大臣も、二人の恋を認めてもよいと弱気な発言をしていたことも耳にしていたのだから、もっと前から進んで昔の関係を復活させればよかったのにとも思う。だが中将は、それでもできることなら、伯父のほうから正式に「婿に迎えたい」と申し出てくる日を待ちたいと考え、過去の屈辱を雪がすような機会を求めて煩悶していた。一方、雲井の雁もまた、父である内大臣が漏らした結婚話を耳にして、深く思い悩んでいた。もしその話が進んでしまえば、自分はもう永久にあの人から顧みられることがなくなるだろうと悲しみ、接近する勇気も持てずにいたが、それでも二人の心は熱烈に互いを思い合う恋であった。内大臣はこれまで、甥である宰相中将の価値をあえて認めようとせず、結婚の件には冷淡な態度をとり続けてきた。しかし、娘の雲井の雁の心が依然として中将に傾き続けているのを知ると、父親として、甥が他の家の娘と結婚するのを黙って見過ごすことはできなくなった。けれども、すでに話が進んでしまい、中務の宮でも結婚の準備が整ったあとに今さら自分の意向を示せば、中将を苦しめることになるだけでなく、自分の家の面目を失い、世間の口にのぼりやすい不名誉となるだろう。昔の関係は、秘密にしていたつもりでも今や人々の知るところであろうし、結局は自分のほうから折れて歩み寄るしかないと内大臣はついに決心するに至ったのである。
2025.09.11
コメント(25)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 12 完〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 12 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。予期せぬ相手に惹かれたり、女性の名誉を傷つけたりしてしまうと、自分自身も人々の恨みを買い、一生心に負担を背負うことになる、という戒めの言葉が込められている。源氏が宰相中将に対して、不運な結婚や妻の欠点に苦しむことがあっても、忍耐を持ち、広く万人を愛する心を育むことが大切だと教えている。たとえ結婚相手に不満があっても、娘の親たちの好意や配偶者の価値を認めることで、不足を補い、そうした同情や理解が自分自身と妻の将来の幸福につながると諭している。この教えのもとであっても、宰相中将は初恋の人である雲井の雁を忘れて他の女性に心を向けることはできず、複雑な思いを抱えていた。一方、雲井の雁も父が憂いを見せるのを知って恥じ入る気持ちを抱きながら、表面は何事もないように振る舞い、物思いに沈んでいた。宰相中将は感情が高ぶった時だけ、情熱的な手紙を雲井の雁に送り、彼女もその真摯な手紙に心を打たれていた。純真で疑い深くない雲井の雁は、中将の言葉にしみじみと共感し、手紙を大切に読んでいた。内大臣の娘である雲井の雁と宰相中将の結婚話が内密に進んでいることが、噂として内大臣の耳に入った場面だ。内大臣はこの知らせに心を塞ぎ、複雑な感情を抱いていた。大臣は、自分が強硬に反対していたために太政大臣までもが結婚を勧めていることに戸惑いを感じつつも、その立場上、結婚を許すことは体面上とても恥ずかしいことだと思っていた。その気持ちを涙ながらに雲井の雁に伝えたとき、彼女は恥ずかしさとともに、自然と涙がこぼれてしまう自分を情けなく思い、顔を背けていた。父の苦悩を思い、どうすべきか煩悶しながらも、父が去った後も庭を眺めて物思いに沈んでいた。自分の涙を愚かだと思いつつ、父の心情を想像して心を痛めていた。そんな中、宰相中将から情のこもった手紙が届く。以前は恨めしく思っていた相手だが、手紙はすぐに開いて読み、そこには「つれなさは浮き世の常になり行くを忘れぬ人や人にことなる」という、自分の気持ちを伝える歌も書かれていた。しかし父の話については一言も触れられておらず、それを雁は恨めしく感じる。そこで返歌を書き送るのだが、その歌の意味が宰相中将にはよく理解できず、ずっと首をかしげていた、という状況が描かれている。つまり、この場面は、結婚をめぐる周囲の思惑や葛藤、そして二人の複雑な感情が絡み合う様子を繊細に表現している。(完)明日より(33帖 藤のうら葉) を公開予定。
2025.09.10
コメント(22)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 11〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。宰相中将は、内大臣が少し気落ちしていることを耳にしてはいたが、まだわだかまりが消えるまでは自分から求めるつもりはなかった。また、ほかに恋の対象を探そうという気にもならず、そうした窮屈な自分の考え方に嫌気がさすこともあった。それでも彼は、かつて六位だったことをからかった雲井の雁の乳母たちへの意地もあり、まずは納言の地位に昇進することが先決だと考えていた。源氏は、宰相中将が結婚せず中途半端な状態でいるのを見かねて、「もし雲井の雁との話を諦めたのなら、左大臣や中務の宮からも縁談が来ているのだから、誰と結婚するか早く決めたほうがいい」と促す。しかし宰相中将は何も言わず、ただ恐縮した様子を見せるだけであった。 昔の自分を振り返りながら、若い頃に受けた上の人の忠告の重要さを認め、当時は素直に聞き入れられなかったものの、今になってその教えが永遠の真理であったと深く理解している様子を描いている。長く独身でいることは、まるで実現しない幻想を追い続けているかのように見られ、そうした宿命があったとしても、結局は価値のない女と結ばれる結果になることもある。つまり、初めはよくても最後には後悔することになるのだ。若さゆえに思い上がっていても、周囲からの誘惑が多い時期には、多情な振る舞いに陥りやすい。しかし、堕落しないように常に心を引き締めていなければならない。宮中という閉ざされた環境で育ち、自由に振る舞うことができず、ほんの小さな過ちですら世間の厳しい批判を受ける中、当時の自分もまるで恋愛に狂った男のように誤解されていた。身分が低いからといって、注目されないからといって気ままに振る舞うことは許されない。驕慢な心が強い時期に、女性関係で賢い人が失敗することは歴史上でもよくあることである。
2025.09.09
コメント(29)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 10〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。宮は、自分がこれらの貴重な書物を譲る理由として、「もし自分に娘がいても、こういう物の価値がわからないような子には残したくない。それに自分には娘もいないから、あなたが持っていてくれたほうがいい」と語った。そこで源氏は礼として、立派な唐本を沈香の木の箱に入れ、高麗笛を添えて宮の侍従に贈った。近ごろの源氏は、特に仮名の書を見ることに夢中になっていて、字がうまいと評判の人物には、身分の高い低いを問わず書を頼み、集めていた。自分の書いた帳をしまう箱には、特に高貴な身分の人が書いたものだけを、帳や巻物に珍しい装丁を施して収めている。これは外国の宮廷でも見られないほど贅沢なもので、若い人たちはその墨蹟の箱を一目見たがっていた。源氏は絵も整理して娘(明石の姫君)に与えていたが、須磨で日記のように描いた絵巻だけは渡さなかった。それは、娘に見せたいと思いつつも、まだ人生の複雑な機微を理解できる年齢ではないと考えたからだった。一方、内大臣は、源氏の娘が盛大な婚礼の準備をして宮中に入るという噂を耳にする。自分の家のことではないとわかっていても、どこか物足りなく、寂しさを感じていた。内大臣の娘・雲井の雁は、美しく成長していたが、結婚もせず縁談もなく家にこもったままで、それが父の悩みの種だった。かつて彼女に熱心に想いを寄せていた宰相中将(夕霧)は、今ではすっかり落ち着き、焦った様子もない。内大臣としては、こちらから縁談を持ちかけるのは世間体が悪いと感じていた。心の中では「熱心に想ってくれていたあのときに許してやればよかった」と後悔していたが、宰相中将だけが悪いとも思えなかった。
2025.09.08
コメント(25)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 9〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。そこに漂う筆の気配は、見る者の心を震わせ、時には涙さえ誘うほどで、宮は目を離せなかった。また、日本製の鮮やかな色紙に奔放な散らし書きを施した作品にも強く惹かれ、筆の乱れの一端にまで漂う愛嬌に心を奪われ、他の作品にはほとんど注意が向かなくなった。そのまま二人は書の鑑賞を続けた。左衛門督の書は本格的な腕前ではあるものの、俗っぽさが抜けきらず、技巧を凝らしすぎている点がかえって目につく。歌の選び方もどこか作為的だった。女が書いた帳面は源氏はあまり披露せず、特に斎院の作品はまったく出さなかった。一方、若い公達が手がけた蘆手の帳面は、趣向の凝らし方がさまざまで面白い。源中将の作には、水を大きく描き、乱れた葦の茂る景色から浪速の浦を思わせる背景に、美しい歌の文字をあちこちに配して澄み渡った雰囲気を漂わせるものがあれば、まったく趣を変え、奇岩が並ぶ風景に合わせて力強い仮名を置いた作品もあり、それぞれに異なる魅力を放っていた。宮は「これは驚いた、じっくり見ないとわからない」と興味深そうに言い、もともと芸術的な趣味があるため、気に入ったものは惜しみなく褒めた。この日は終始、書の話題で盛り上がり、色紙を継ぎ合わせた巻物が次々と運ばれてきた。やがて宮は自邸に使いを出し、蔵から宝物を取り寄せる。その中には、嵯峨天皇が古万葉集から選んで書き残した四巻、さらに延喜天皇が古今集を、淡い藍色の支那製の色紙を継ぎ合わせ、同色の濃い模様入り唐紙の表紙と、同色の宝石を軸にして巻き、巻ごとに書風を変えて書いたものがあった。灯火を低くして二人で眺めながら、源氏は「よくこれほど多様な書きぶりができたものだ。今の人は、この一部分をまねするだけでも苦労するのに」と感心した。この二種類の巻物は、宮から源氏への贈り物となった。
2025.09.07
コメント(28)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 8〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。何気なく書いた一、二行の字を手に入れ、それが最上の仮名だと心から感服したことがある。それがきっかけで浮名を立てることになり、御息所は私との関係を苦い経験と思ったまま亡くなったが、必ずしも悪いことばかりではなかった。今こうしてその娘である中宮を助けているのだから、聡明だった御息所は、あの世で私の誠意をわかってくれているだろう。中宮の字は確かに美しいが、才気には少し欠ける」と、夫人にそっと語った。 源氏は、草紙(書物に仕立てるための白紙や装飾紙)を書く筆者を選び、その書風について熱心に語っていた。まず、入道の中宮は上品で格調高い字を書くが、やや力強さに欠け、華やかさも少ないと評される。院の尚侍は当代一流の書き手だが、奔放な筆運びゆえに癖が出やすい。それでも源氏は、この院の尚侍、前斎院、そして目の前にいる夫人を、この草紙の書き手として並べて高く評価した。夫人は「そんな名だたる人たちと並べられるなんて恥ずかしい」と顔を赤らめるが、源氏は「謙遜しすぎだ。あなたの字は柔らかく、調子に味がある。ただし仮名では時々、力が抜けすぎた字が混じる」と細かく評した。源氏は、無地の草紙も何冊か新たに綴じさせ、表紙や紐といった細部にも徹底してこだわった。そして「兵部卿の宮や左衛門督にも書かせよう。私も一冊書く。あの人たちも、私と一緒に書くのは晴れがましいはずだ」と自信満々に言い、墨や筆も厳選して用意した。依頼を受けた人の中には「難しい」と感じて断る者もいたが、源氏は丁寧に説得して承諾させた。さらに、薄く艶のある朝鮮紙の帳面を見て、源氏は「これは風流を好む若者に書かせよう」と思い立ち、宰相中将、式部卿の宮の兵衛督、内大臣家の頭中将などに、蘆手(絵と文字を組み合わせた書)や歌絵など自由に描くよう頼んだ。
2025.09.06
コメント(22)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 7〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。二十日過ぎに東宮の元服が行われた。東宮はすでに堂々とした成人のような風格を備えており、誰もが自分の娘を後宮に入れたいと望んだ。しかし、源氏が強い自信をもって姫君を東宮に奉ろうとしていると知ると、これほどの競争相手がいてはかえって娘を不幸にするのではないかと、左大臣や左大将らも迷い始めた。これを耳にした源氏は、「そういうことであれば天皇にも申し訳が立たない。宮仕えとは、多くの姫君の中で、わずかな愛情の差を競い合うことにこそ意味がある。高貴な家柄の立派な姫君が出仕しなければ、こちらも張り合いがない」と言い、姫君の出仕をあえて先延ばしにした。すると、出仕を遅らせようと考えていた人々の中で、まず左大臣が三女を東宮に入れ、その姫君はやがて麗景殿と呼ばれるようになった。源氏は、かつて自分の宿直所だった桐壺の室内装飾や調度を改修させていたため、姫君の東宮入りは当初の予定より遅れていた。東宮は待ちきれない様子だったが、最終的に四月に参内することが決まった。姫君の持ち物はもともと一通りそろっていたが、さらに新しく作り足し、源氏自身が意匠や図案を考え、名人たちを集めて美しく仕上げさせた。草紙を納める箱などには、後に製本して書物にできるような質の高い紙を選び、古くから書道の大家と称された人々の筆跡も多く集めた。源氏は、「世の中は昔に比べてあらゆることが衰えていく末法の時代だが、仮名の文字だけは今のほうがどこまでも面白く発展している。昔の仮名は正確ではあるが、柔らかみや変化に乏しく、単調だ。近ごろは巧みに仮名を書く人が増えた。私もかつて熱心に仮名を学んでいたころ、無難な字を手本として集めていたが、その折、中宮の母である御息所が何気なく書いた一、二行の字を手に入れ、それが最上の仮名だと心から感服したことがある。
2025.09.05
コメント(28)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 6〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。宮は「花の香をこの袖に移してしまったら、妹が浮気だと疑うだろう」と歌を詠み、源氏は「そんな言い訳を気にしているんだな」と笑った。車はすでに走り出そうとしていたが、源氏は使いを追いかけさせ、「珍しいことだと故郷の人も喜ぶでしょう、花の錦をまとって帰るあなたの姿を」と伝えさせた。宮はこれを聞き、苦笑いを浮かべた。頭中将や弁の少将たちにも、派手な冠ではなく、細長や小袿といった控えめな贈り物を源氏は渡した。その後、裳着の式を行うため西の町へ、源氏夫妻と姫君は夜の八時ごろに向かった。中宮の御殿の西の離れに式の会場が設けられ、姫君のお髪上げ役である内侍もそこへ来ていた。紫の上もこの機会に中宮と対面した。中宮に仕える女房、紫の上に仕える女房、姫君に仕える女房たちがそれぞれ盛装して座り、その数は数えきれないほど多かった。裳をつける儀式は夜の十二時に始まり、ほのかな灯りの中で中宮は姫君の姿を目にし、その美しさに見とれた。源氏は「あなたを頼りにして、礼を欠いた姿のまま御前に出てしまいました。身分の高いあなたがこうして世話をしてくれるなど、他には例のないことで、本当に感激しています」と率直に言った。中宮は「経験も浅く、何もわからないまま務めているのに、そんな挨拶をされると、かえって困ってしまいます」と謙遜して返す。その若々しく愛嬌ある姿を見て、源氏は、この美しい人々が皆自分の縁者であるという幸せを深く感じた。一方、明石の君は陰に控え、この晴れやかな裳着の式を直接見ることができず、寂しげにしていた。源氏は呼び寄せようかと思ったが、世間の目を考えて思いとどまった。このような儀式は、名文家が書いても時に煩わしく感じられるほどであり、自分の筆でだらしなく書けばかえって気品を損ねるだろうと恐れ、細かい記録は避けた。
2025.09.04
コメント(25)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 5〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。月が昇ると酒が座に運ばれ、宮と源氏は向かい合って昔話を語り合い始めた。雨上がりの夜は、濡れたように潤む月明かりが艶やかに差し込み、そよ風が花の香を運び、空気全体が甘やかな雰囲気に包まれていた。人々は心地よい酔いにひたり、侍所では翌日の合奏に備えて楽器を出し、殿上役人たちが笛を吹いたり音を試したりして賑やかな音が響いていた。そこへ内大臣の子である頭中将や弁の少将が挨拶に来るが、帰ろうとしたところを源氏が引き止め、楽器を運ばせてこの場で演奏させることにした。頭中将は和琴を担当し、華やかに爪弾き始め、宰相中将は横笛を春らしい軽やかな調子で吹き、その音は空高くまで澄んで響き渡った。弁の少将は拍子を取り、「梅が枝」を清らかな声で歌った。この少将は、幼い頃に父とともに韻塞に来て「高砂」を歌ったことのある公子でもあった。宮と源氏も時折声を合わせ、派手ではないが情趣に満ちた音楽の夜となった。酒が回ると、宮は「うぐいすの声に誘われ、花の香に心を奪われ、千年でもここに留まりたい」と歌を詠み、源氏は「色も香も移ろう春の間は、この咲き誇る花の宿を離れたくない」と返し、その杯を頭中将に渡した。頭中将は受け取ると宰相中将に回し、「うぐいすが眠る枝が靡くまで、夜半の笛を吹き続けよ」と歌う。宰相中将は「風が花の木を揺らすのに、そんなに吹いたら花が散ってしまうだろう、それは少しひどい」と冗談を言い、場は笑いに包まれた。弁の少将は「霞さえ月と花を隔てなければ、鳥もきっと心を和ませるだろう」と詠み、夜はさらに和やかに更けていった。宮が「長居したくなる場所だ」と言った通り、本当に夜明けになってからようやく帰ることになった。源氏は別れの贈り物として、自分用に仕立ててあった直衣一領と、まだ封も切っていない薫香二壺を宮の車に積ませた。
2025.09.03
コメント(24)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 4〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。源氏は、「今日のように湿り気のある空気は、香を試すのに最適だから」と言って、試香の準備をさせた。夫人たちからは、それぞれに工夫を凝らして作られた香が、美しく飾られて次々と届けられた。源氏が宮に香比べの判定を頼み、「これを見極めてくれるのはあなたしかいない」と真顔で依頼する。宮は火入れを持ってこさせ、香を焚きながら、あくまで自分は専門家ではないと控えめに言いつつも、鼻を利かせて一つ一つの香りの良し悪しを丁寧に嗅ぎ分け、少しの欠点も見逃すまいという真剣な態度で等級をつけていく。源氏が用意した香は、右近衛府の溝川近くに埋める予定を変えて、西の渡殿の下から流れ出す園の川辺に埋めておいたものを、惟光宰相の息子である兵衛尉が掘り出して持参し、それを宰相中将が座へ運び込む。宮は「こんな役は疲れるし、第一煙たい」とぼやきながらも、判定を続ける。香の原料や作り方は同じでも、作り手の趣向が反映されるため、嗅ぎ比べるとそれぞれ違った魅力があり、一番を決めるのは難しい。斎院の黒方香は落ち着いて上品、侍従香は源氏作が華やかで優美だと宮は評する。紫の上の三種の中では梅花香が明るく若々しく、清らかな気品があり、「春のそよ風に混ぜるならこれが最もふさわしい」と宮は称賛する。花散里は競争に加わるのを遠慮し、荷葉香だけを作るが、それは変わった趣と懐かしさを漂わせる香だった。明石の君は冬の趣を軽んじられないようにと、朱雀院の製法をもとに公忠朝臣が手間をかけて精製した百歩の処方を参考にし、薫衣香を作る。これは苦心の跡が感じられる、しっとりと優美な香りだった。宮はどの香にも好意的な評を与え、源氏は「まるで八方美人の審判だ」と笑っていた。
2025.09.02
コメント(18)
-

源氏物語〔32帖 梅が枝 3〕
源氏物語〔32帖 梅が枝 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔32帖 梅が枝〕(うめがえ)の研鑽」を公開してます。どちらにも美しい糸が結ばれており、細かい部分まで優美に整えられていた。それを見た宮は、「美しいですね」と言って眺めていたが、香と一緒に添えられていた短歌に目がとまり、やや芝居がかった様子で読み上げた。花の香は散ってしまった袖にはとどまらないけれども、どうして浅く香らせてしまえるだろうかというような意味の歌であった。やがて宰相の中将が贈り物を持ってきた使いを見つけ出してもてなした。紅梅色の中国製の布で作られた長い帯が、贈り物に添えられていた。返事の手紙も紅梅色の紙にしたため、庭の紅梅の枝に結びつけて届けた。それを見ていた宮は、「なんだか内容を知りたくなるようなお手紙ですね。なぜそんなに秘密にするんですか」と言って、手紙を読みたがった。それに対して源氏は、「そんなことありません。ただ、そうやって何でも深読みするのが困るんですよ」と笑って返し、先ほど詠んだ歌を改めて紙に書いて宮に見せた。花の枝に心をさらに強く惹かれる。人がとがめる香は隠しているけれどもという意味のもので、香と恋の想いを重ねたような一首だった。源氏は、自分でも少し過剰な演出だとは思っていた。「一人娘の裳着なのだから仕方がないことです。でも、この騒ぎをあまり大げさにしないようにしたいので、他の誰かではなく、ぜひ中宮に御所からおいでいただいて、腰結いをお願いしたいと思っています。あの方は家族のような存在でありながら、やはり立派なお人柄なので、普通の儀式の格ではもったいないと思って」と語った。それを聞いて、宮も「そうですね。あやかる相手というのは慎重に選ばないといけませんね。中宮以上の方はいませんよ」と賛成した。その後、前斎院からも香が届けられ、宮が来ているこの機会に、六条院にいる夫人たちが調合した香も届けさせる使いが出された。
2025.09.01
コメント(22)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 愛犬のいる生活
- 山ん歩 ラストはモミジ
- (2025-12-04 20:54:48)
-
-
-

- チワワな生活☆
- ボクわん蔵とわん丸ちゃんの令和7年1…
- (2025-11-30 23:00:05)
-
-
-

- 猫の里親を求めています。
- *みにゃさんの愛、募集ちぅ-2024年1…
- (2025-10-19 01:27:40)
-