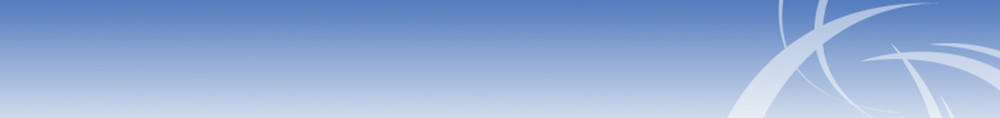2010年12月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
藁畳の防虫加工処理
藁畳には、ほとんどの場合防虫加工処理が施されています。 ・畳表 ・畳床 ・縁下紙 縁の下に使用している ・糸 逢着用の糸 ・裏シート 畳の裏面のシート畳床について、JIS(日本工業規格)では、「ダニ、その他の害虫が発生しないように、適切な防虫処理をしなければならない。但し、防虫処理には人体に悪影響を及ぼす薬剤を使用してはならない」として防虫処理が義務付けられています。その防虫処理の方法には、「防虫加工紙、誘電加熱処理、真空殺菌処理、さらに防虫加工畳糸の使用など」があり、殺虫剤にはフェンチオン、フェニトロチオン、ダイアジノンなどの有機リン系農薬が高濃度で使われています。防虫処理とは、農薬を使用することと同じであるという認識が必要です。 ■ 誘電加熱処理 畳全体にマイクロ波や高周波を当て、65~70℃程度に加熱し、殺虫する方法です。 この場合、その時点で発生しているダニを殺すことはできても、いずれ部屋に敷き詰め使用して いる間に湿気を吸い込み、ダニが再発生します。 さらに、水分の多いところでは非常に高温になり、裏に防虫紙が張ってあってビニールシートが 当たっていると蒸れたような状態になり、藁の弾力性もなくなり、畳が傷むという欠点がありま す。 ■ 真空殺菌処理 真空状態にし、酸素を奪う方法です。 ■ 熱風乾燥処理 熱風乾燥と熱とで殺虫する方法です。 ■ 防虫加工紙 畳の下部に縫いこまれており、そこに防虫用の殺虫剤を染み込ませています。 藁床の防虫処理に殺虫剤を使用した場合、農地でのそれを使用するよりはるかに高濃度に なるといわれます。 【使用される主な殺虫剤】 ・フェニトロチオン(MEP) ・フェンチオン ・ダイアジノン ■ 防虫加工不織布 防虫加工紙同様に畳床に縫いこんであり、そこに防虫用の殺虫剤を染み込ませています。 ■ 裏シート(裏打ちシート) 床面からの湿気から畳床を保護するためのシートに、防虫加工されているものです。 防虫シートとして畳に縫い込まれる場合と、防湿及び防虫シートとして畳の下に敷き込まれて いる場合があります。 使用される薬剤は、有機リン系のものやホウ素系化合物などです。 ■ 防虫加工畳糸使用 麻、ポリエチレン、ポリエステルなどの畳糸 防虫畳糸、防虫畳縁、防虫縁下紙など、いたるところで防虫加工されていますが、いずれも 防虫加工紙と同じように農薬をしみ込ませたものです。 ■ 防虫剤 畳の下に撒く。 【使用される薬剤】 ・ナフタリン ・フェニトロチオン(MEP)藁畳(建材床の一部を含む)において注意すべき点は下記のようになります。 (畳床) ・畳床の防虫処理方法及び薬剤 ・稲わら床の原料である藁の残留農薬 (畳表) ・畳表の着色料 ・畳表の原料である藺草の残留農薬 ・畳表の防カビ・防ダニ処理薬剤日本伝統の藁畳は良い面が多くあります。しかし、建物が高気密化されていき室内の密閉度を上げた結果、藁畳の特質を生かすことが困難になってきました。それは密閉された中で、室内の湿気が逃げることなく常時高湿度の状態のため、藁畳が湿気を吸い上げ、藁の中にいる微生物が活動しやすい環境をつくってきたからです。そこで従来の藁畳に固執しない建材床などの畳や防虫対策を施した畳が普及してきました。その反面、上記の問題(防虫薬剤などによる健康影響)が起きてきたのも事実です。現在では、防虫処理の問題の改善をした畳など様々な畳が生産され、流通されつつあります。このように畳原料の生産者の方、畳を製造されておられる方は日本の伝統である畳を守るためにも改善、努力をしておられます。
2010.12.28
-
畳表の原料 藺草生産時の農薬
畳表生産時に使用される農薬の目的は何でしょうか? ■ 雑草対策 雑草は、藺草の成長不足や根白に影響を及ぼします。 そこで植付け前と植付け後に雑草の発芽を止める除草剤を使用します。 ■ 病虫害対策 ・イグサ芯虫蛾 ・紋枯病このように畳表の原料である藺草の栽培には多かれ少なかれ農薬が使用されています。敏感な方は自然素材でも反応する方もいらっしゃいますが、できるだけ農薬の使用量が少なく、残留性が少ない畳表を選ばれる方が良いといえます。
2010.12.27
-
着色料
着色料は、藺草の色のばらつきを均一化し、畳表の色を鮮やかに保ち、より青く見せるため使用されます。畳表は青いほうが新しく美しいという情報によって、より青く着色された畳が多く流通し始めました。着色した場合、質の悪い藺草を使用しても最初は綺麗に見せることができるという理由もあります。このような理由で、特に中国産の畳表に多く使用されています。しかし一方で、着色料を利用することによって、そこに住まう人の健康に影響を及ぼすことになりました。さらに、着色料によって藺草自体の繊維や色素(葉緑素)を傷めることで耐久性も低下し、畳本来の良い特性が生かされなくなってきました。では、一体どのような着色方法や着色料があるのでしょうか?着色の方法には2種類あります。 ・直接畳表に噴射するタイプ 中国産の畳表によく使用される方法 ・染土に混ぜるタイプ 【主な着色料】 ・マラカイトグリーン 以前よりかなり減ってきているといわれます。 → この色素についての問題点は、「マラカイトグリーン」をご覧ください ・硫黄 硫黄を燃やしたときに出る漂白作用のある二酸化硫黄という物質で薫蒸した藺草は、 黒味が消え、すっきりした色調の藺草になり、高級な畳表として販売されています。 しかし、この二酸化硫黄で薫蒸した畳表は、畳表本来のにおいでなく、鼻を刺激する 異臭がします。 ・金属イオン このように着色加工した畳表は、その着色料のにおいがしますが、それを今まで新しい畳のにおいと勘違いされてきました。畳は横になったり、寝そべったりして身体中が接触しやすい場所です。さらに乳幼児の場合、寝そべって皮膚への接触以外に、舐めたりする場合があります。では、一体どうやって着色料を使用している畳表とそうでない畳表を見分けるのでしょうか?一般に言われるのが、畳を乾いた雑巾で拭くということです。これは畳を拭くことで雑巾に青や緑の色がつく畳表の場合、ほとんどが化学的な着色料を使用しているといえるからです。但し、染土で染められた畳表を同じように雑巾で拭いた場合も、若干の青染土の青みがつく場合がありますが、2度目に拭くとほとんどつかなくなります。 ※青染土を使用の場合、着色料を使用した畳表と区別がつきにくい
2010.12.19
-
マラカイトグリーン
【特性、特徴など】 ・塩基性有機色素 ・金属光沢のある青緑色 ・水によく溶けるので、唾液や汗で溶けて口や皮膚から人体に吸収される ・着色力が強い ・強い塩基で防カビ剤の役割も果たす ・光により分解する ・日光やアルカリに弱い ・生体内で酵素により還元され、ロイコマラカイトグリーンになる 【主な用途】 ・繊維の染色 ・紙製品の染色 ・鑑賞魚の白点病や水カビ病などの治療 【毒性・症状など】 ・発がん性が指摘される ※但し、日本においても、又、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)に おいても毒性評価がなされておらず、国際基準も設定されていない 【その他】 ・食品衛生法により食品中からマラカイトグリーン及び主な代謝物のロイコマラカイト グリーンが検出されたものは流通、販売等禁止されている ・アメリカでは1981年、EU加盟国では2002年に食品関連への使用が禁止 ・中国では、2002年に食用動物への使用が禁止 ・薬事法に基づき、2005年8月養殖水産動物への使用は禁止されている ・2008年7月、中国産ウナギ蒲焼きから検出 【関連サイト】 ・ マラカイトグリーンについて(平成22年8月17日) (内閣府食品安全委員会) ・ 中国産養殖鰻のマラカイトグリーン検出について (厚生労働省) ・ ご存知ですか?マラカイトグリーン (神奈川県衛生研究所)
2010.12.17
-
ポリスチレンフォーム
ポリスチレンを原料とするポリスチレンフォームには、製法によって、押出法とビーズ法の2つの種類があります。■ 押出法ポリスチレンフォーム 【別名】 XPS 【製造方法】 熱可塑性のポリスチレン樹脂と難燃化剤、炭化水素や代替フロンなどの発泡剤を高温・高圧 下で混合して、常温・常圧の環境に発泡剤の瞬時の気化力を利用して発泡させながら連続的 に押し出して製造します。 押し出された発泡体は裁断された後、さらに寸法を安定させるために、一定期間熟成されま す。 【特性など】 ・ビーズ法よりも断熱性、耐圧性、耐候性に優れる ・透湿抵抗が大きいものが得られる ・柔軟性に欠ける ・リサイクルができる 【主な用途】 畳床、断熱材■ ビーズ法ポリスチレンフォーム 【別名】 EPS、発泡PS、発泡スチロール、発泡スチレン樹脂、発泡ポリスチレン、 フォームスチレン、ポリスチレンフォーム 【製造方法】 ポリスチレン樹脂と炭化水素系の発泡剤からなる原料ビーズを予備発泡させた後に金型に充 填し高温蒸気を当てることによって約30倍から80倍に発泡させてつくります。金型形状をかえる ことで様々な形状の製品をつくることができます。 発泡剤は、主にカセットコンロに使われる天然ガスのブタンや原油成分であるペンタンなどの 炭化水素ガスが使われています。 【特性など】 ・不完全燃焼を起こすと、大量の煤(炭素粒子)が発生する ・リサイクルできる 【主な用途】 畳床、断熱材、梱包材、フロート材(ブイや生簀の浮き)ポリスチレンフォームの問題点 畳床や断熱材によく使用されているポリスチレンフォームにもいくつかの問題点も考えられます。 ・燃焼時に、黒い煤が大量に発生する ・スチレン(スチレンモノマー)が放散する可能性がある ※業界の自主規制により放散速度が設定され、室内の床に敷き詰めたときの室内濃度 指針値に換算し、厚生労働省の定める室内濃度指針値220μg/m3を下回るようにされて います。 但し、逆にいうと放散されないわけではなく季節や室内の環境(換気など)によって は何らかの影響を及ぼす可能性はあるといえます。
2010.12.15
-
インシュレーションファイバーボード(インシュレーションボード/軟質繊維板)
インシュレーションボードとは、 主に木材などの植物繊維を成形した繊維板(ファイバーボード)のうち、密度0.35g/cm3未満の 軟質繊維板のことです。 用途によって3つに分けられます。 タタミボード 畳床用 A級インシュレーションボード 断熱用 シージングボード 外壁下地用 【特徴】 断熱性・吸音性・耐久性にすぐれる 【製造方法】 木材を多量の水とともに解繊し、接着剤などを添加した後、繊維を水に分散させた状態で 金網上に流して、脱水しながら成形したものを乾燥して固める湿式法で製造されます。 【用途】 ・畳床 ・断熱材 ・内装下地材 ・家具などの芯材 インシュレーションボードは、合板と違い建築基準法ではホルムアルデヒド発散建築材料の告示 対象外であるため、居室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用することができ ることになっています。 但し、この製造に使われている接着剤はメーカーにより違いがあるのでホルムアルデヒドの揮発 量は一定でないので下記の点に気をつける必要があります。 ・インシュレーションボードを畳床に使用する場合は、インシュレーションボードのホルムアルデヒ ド放散量について確認する。
2010.12.14
-
不乾性油
ヨウ素価100以下で、空気中に放置しても固化しない油脂 飽和脂肪酸(パルミチン酸やステアリン酸など)、又は、二重結合の数が少ない不飽和脂肪酸 (オレイン酸など)を多く含んでいる。 【主な不乾性油】 オリーブ油、つばき油、落花生油、ひまし油、ヤシ油、豚脂、牛脂 【主な用途】 ・食用 ・化粧品 ・石けん ・潤滑油
2010.12.11
-
半乾性油
ヨウ素価100~130で、乾性油と不乾性油の中間の性質を示す。 【主な半乾性油】 綿実油、ごま油、米ぬか油、ナタネ油、コーン油 【主な用途】 ・食用 ・化粧品 ・石けん ・潤滑油
2010.12.10
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…
- (2025-11-16 06:30:06)
-
-
-

- 心の病
- 深淵なる聖堂 (Remastered)
- (2025-10-18 14:20:02)
-
-
-

- 介護・看護・喪失
- 【速報】障害者施設の入所者を殺害し…
- (2025-11-14 04:16:43)
-