2023年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

恒大集団の財務状況と傘下のEVメーカー・恒大汽車の危機
恒大集団は、1996年に許家印氏が不動産会社「恒大」として設立した。 2009年、香港証券取引所に「中国恒大」として上場。 2020年9月末、中国当局・中国人民銀行)による不動産関連企業などの負債比率の高い企業に対して金融機関の融資を制限する動きが出たことを受け、恒大集団が債務不履行に陥る可能性があると報道された。 2021年6月末時点で恒大集団の負債は1兆9700億元に対し自己資本は4110億元だった。 習金平政権の不動産価格沈静化のための関連企業への引締めによる中国の不動産不況は深刻化している。各地で大規模なゴーストタウン(鬼城)が発生。 資金難に陥った開発業者がマンションの建設工事を途中で取りやめ、購入者が住宅ローンの支払いを拒否する事態も発生している。 2022年7月23日、経営危機に陥っている恒大集団は、夏海鈞最高経営責任者(CEO)らが辞任したと発表した。グループ会社の預金流用に関与しており事実上の解任だった。 2022年8月4日、恒大集団は広州市で進めていたサッカースタジアム建設事業向けなどの土地使用権を市に返還すると発表した。これに伴い、約55億2000万元(約1090億円)が返金される。資金は巨額債務の返済に充てると報じられた。 恒大汽車は自動車製造のために3年間で450億元(約8500億円)を投じ、2025年に生産販売量100万台を実現するという目標を掲げていた。統計によると、2021年上半期の時点で恒大汽車が投入した資金はすでに500億元(約9500億円)を超えたという。 恒大集団傘下の新興EVメーカーの恒大汽車(恒大新能源汽車集団)は2023年3月23日、新たな資金調達ができなかった場合、工場の操業停止に追い込まれるリスクがあると発表した。 中国市場ではEV販売の大きな伸びが報じられていたが、恒大汽車によれば、2022年7月に予約販売を開始した初の市販モデル「恒馳(ヘンチー)5」は、これまでの納車台数が900台余りにとどまっているという。 恒大汽車は香港証券取引所に上場している。2021年の決算報告書を期限までに提出できず、2022年4月から株式の取引が停止されたままだ。2023年3月23日に公表した未監査の財務データによれば、2021年末時点の現金および現金同等物の残高は12億8700万元(約247億円)、総資産は595億2000万元(約1兆1404億円)、総負債は588億3000万元(約1兆1272億円)。 3月24日、中国恒大集団は事業再編の一環として、EV子会社の中国恒大新能源汽車集団(恒大汽車)が2事業をグループの別の部門に売却すると発表した。恒大汽車は2事業を名目上2元で売却し、約247億9000万元の売却益を計上する。 販売台数の伸びが著しい中国のEV業界は、BYDを除く全企業が2022年度赤字決算となった。恒大汽車が黒字になる見込みは、現在の中国のEV市場にはない。 恒大集団に1千億円支払い命令中国の裁判所、創業者も対象2023年5月13日 共同通信 経営再建中の中国不動産大手、中国恒大集団は13日までに、中国の裁判所から同社と創業者の許家印主席が約60億元(約1170億円)の補償金などを支払う命令を受けたと発表した。恒大に投資した会社が支払いを求めて訴えていた。恒大は債務履行を求める訴訟などが増え、資金繰り改善の足かせとなっている。 投資会社は、恒大グループの50億元の株式を引き受けていた。株式の買い戻しや関連費用の支払いを広東省広州市の裁判所が命じた。 中国メディアによると、恒大の主要事業会社の恒大地産集団に対して債務履行などを求める訴訟が2月末時点で1317件あり、請求金額などは計約3124億元。 ― 引用終り ― 巨大なベンチャーキャピタル・恒大集団の未来は不明なまま。 不動産企業、EV企業の破綻の連鎖にも、共青団(中国共産主義青年団)のエリートを締め出した習金平の中国共産党は、動じない体制となった。
2023年05月31日
コメント(1)
-

三菱重工業、決算好調、ガスタービン事業のシェア世界トップ
三菱重工は原発の輸出政策で失敗、豪華客船建造でも失敗したところへ、中型旅客機・三菱リージョナルジェッ(MRJ)ト改め三菱スーパージェット(MSJ)が米国の型式認定を得ることができず撤退のダメ押しとなった。MSJの開発担当の子会社三菱航空機のプロジェクト凍結時、2021年3月期決算の債務超過額は5,559億円。2022年3月期の債務超過額は、5,647億円に拡大。 誤った決断を続けた経営陣により「オワコン」とされた三菱重工は、地道な現場の努力が実り、2023年3月期決算は絶好調。ガスタービン事業は、新たに世界シェアトップとなった。24年3月期は過去最高益を更新する見通し。 参謀クラスの能力が低いのは日本の悪しき「伝統」なのかもしれない。 “オワコン扱い”だったのになぜ?三菱重工の決算が「絶好調」な理由2023年5月19日 ITmedia ビジネスオンライン … (略) …●ガスタービン事業が世界シェアトップに 特筆すべきは、ガスタービンの世界シェアがついにトップとなったことだろう。 近年、同社はグローバルなエネルギーシフトや脱炭素社会への舵切りに向けて、水素ガスを利用した大型のガスタービンをはじめとした、環境負荷の低い高効率なタービン事業が躍進している。高効率なガスタービンは、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行期における中間エネルギー源として注目を集めているのだ。 同社の決算内容をみても、ガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)事業が特に業績を伸ばしている。同事業の売上収益は前年同期比19%増の7368億円を達成。三菱重工の全社における売上収益は4.2兆円であったことから、全社売上のうちおよそ2割がガスタービンによるものとなっているといえるだろう。 ガスタービンの世界シェア争いは、ドイツのシーメンスやアメリカのゼネラル・エレクトリックと競争を繰り広げており、19年には3位だった世界シェアが、およそ4年で33%までシェアを伸ばしてトップとなったのである。 特に中国や米国、そして日本でも大型・高効率のガスタービン需要が拡大している。アフターコロナに伴う経済活動の再開に伴って、効率がよく、環境負荷のできるだけ小さい三菱重工のガスタービンが選ばれているようだ。 日本では緩和的な金融政策の継続によって大幅な円安が発生しているため、為替要因によって業績が押し上げられているのではないかという懸念もある。しかし、ガスタービンの世界シェアは出力ベースで調査がなされていることから為替要因以上に国内外からの受注が好調であることの表れであり、事業として健全に成長しているといって差し支えないだろう。 現に、三菱重工における同社の円安に伴う収益の増加要因は3000億円といわれているが、この影響を控除したとしても受注高は前年度比で増加している。他企業の間では賃上げや物価高に伴う原価や販管費の高騰によって為替要因で辛うじて増収増益、実質的には減益となっている者も少なくない中で、同社は着実に健全な成長を続けていることが分かる。 では、今年撤退を発表したMRJは全社業績の足を引っ張ってしまったのだろうか? 結論からいえば、そういうわけでもなさそうだ。 ●MRJが産んだ新たなビジネス 付箋に欠かせない「貼って剥がせるのり」が、強力な接着剤の製作過程における失敗作から誕生したように、単体でみれば一見失敗したようにみえるビジネスであっても、そこから収益の基盤を生み出す例は決して少なくない。 MRJの失敗も例に洩れず、三菱重工業にとって、新たな門出を告げる契機となった。その経験から学んだ教訓は、事業のリスク管理と経営戦略の再構築に大いに役立ったのである。また、MRJ開発に関わった技術者の知識や経験は、他の航空宇宙関連事業に生かされている。 ― 引用終り ― MSJの開発について国は507億5千万円の補助金=税金を出した。債務超過額と補助金を足しただけで1兆円を超える出費となっている。 記事は航空機のMRO(メンテナンス、リペア、オペレーション)事業の成長に大いに役立っているとしているが、投入した金額と得られる利益のバランスが全く取れていない。 MRO事業が含まれる「航空エンジン」事業の売上収益は前年同期の716億円から1265億円にしか増加したに過ぎない。 基盤となる既存事業を軽視し、企業の存続を危ぶまれるものとした経営の判断は、正しく批判、総括されるべきだろう。東芝やシャープのようにならなかったのは、不幸中の幸いとすべきこと。パナソニック、東芝、ソニー、日立製作所、三菱電機、三菱重工、IHIといった日本の電機、重工業業界を中心とした大企業は、「選択と集中」で象徴されるGEを手本とした。近年の業績の推移をみると、GE「お手本」としたことは到底正解とは言えない。自画自賛の方針で大博打を三つも打って外した三菱重工の経営陣は頭を切り替えることができるだろうか。ギャンブル癖は中々治らないと聞くだけに気になる。 熱効率が優れていることを誇るべきガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)事業に対して、頭脳明晰な三菱重工経営陣は、経営資源を適切に振り向けられるだろうか?
2023年05月30日
コメント(0)
-

スカイマーク黒字化、最終利益57億円
2023年5月15日、スカイマークは2023年3月期決算(単体)を発表した。東京証券取引所に再上場後初となる通期決算は、最終利益が57億円の黒字(前年同期は67億円の赤字)で、4年ぶりで黒字化となった。 スカイマーク株式会社は、日本の東京都大田区に本社を置く航空会社。1996年11月に、当時のH.I.S社長である澤田秀雄らの出資により設立された。1998年9月、東京/羽田 - 福岡線を開設した。 運賃はANA、JALに比べて低額であるが、スカイマークはLCCではない。 2020年度の国内線輸送人員は日本航空(JAL)や全日本空輸(ANA)に次いで国内第3位。主なハブ空港は神戸空港と羽田空港。 2022年現在、定時運航率5年連続1位を達成している。2019年に世界航空会社定時運航率ランキングは世界3位。 2006年10月に、「スカイマークエアラインズ株式会社」から略称として定着していた「スカイマーク」に社名を変更した。 2014年、独立性を保ってきたが、LCCの新規参入などによる経営悪化に伴いJAL、ANAに支援要請を行った。 2015年1月28日、東京地方裁判所に申民事再生法適用を申請した[。 2016年3月28日付で、東京地方裁判所からの監督命令の取り消し決定と民事再生手続きの終結が発表された。 2017年7月7日、ボーイング737-800型機を3機追加発注した。1機は2018年に、2機は2019年導入。 スカイマーク4年ぶり黒字、最終利益57億円…社長「旅行と友人や親族訪問が爆発的に伸び」2023年5月15日 読売新聞 航空会社のスカイマークは15日、2023年3月期決算(単体)を発表した。東京証券取引所に再上場後初となる通期決算は、最終利益が57億円の黒字(前年同期は67億円の赤字)となった。コロナ禍で厳しい業績が続いたが、4年ぶりに黒字化した。 売上高は前期比79.6%増の846億円だった。観光やレジャーを中心に旅客需要が戻った。下期の旅客数は、コロナ禍前となる18年度実績を上回る回復ぶりを見せた。 洞駿社長は15日の決算記者会見で、「旅行と、友人や親族訪問(での利用)が爆発的に伸びており、今年度も勢いが衰えていない」と述べた。スカイマークは15年に経営破綻後、上場廃止となり、昨年12月に東証グロース市場に再上場した。 ― 引用終り ― 運用機材はボーイング737-800型機(座席数:Y177席)29機。GECAS、ILFCなどの会社からのリース機材が大半。
2023年05月29日
コメント(0)
-

近づくと危ないクルマの特徴
長期連休中などに自動車を運転していると、近づいたら危ない、挙動不審なクルマに多数遭遇する。 そんな時は車間距離を十分とるなどして身を守るということだろうが、日ごろから後続車が激しくイライラしない程度に車間距離をとっていると、ブレーキをかけることの少ないスムーズな運転が実現できる。 近づきたくないクルマの特徴をまとめた記事が下記。 フラフラ運転や低速走行、傷だらけの車両に要注意! 近づいたら危険なクルマの特徴とは?2023年5月15日 くるまのニュース … (略) … 「近づくと危ないクルマ」にはいくつかのパターンがありそうです。 大きく3種類に分類でき、1つは運転スキルが乏しいドライバーによるもの。2つめは、あおり運転を仕掛けてくるドライバーや、一般道でスピードを出しすぎるドライバー。3つめは、単純にそばに寄らないほうが良いクルマです。 1つめの運転スキルが乏しいドライバーに起因する危ないクルマの特徴を詳しく見てみましょう。 ●フラフラ走っている、真っ直ぐ走れていない フラフラした挙動のドライバーは、道に迷っていたり、本当に運転スキルが乏しいケースがあります。普段あまり運転していないサンデードライバーや初心者に多い傾向です。 高速道路の分岐で判断が遅れて分離帯に突っ込んだり、単なる車線変更でも周囲を見渡す余裕がないので接触事故を起こすケースなどが考えられます。 ●前がガラガラなのに、法定速度よりかなり遅い これは初心者よりも最近は高齢者にも多い運転でしょう。法定速度以下ということは超安全運転をしていると勘違いしているか、単純に速度を出すのが怖くてノロノロ走っていることも考えられます。 ●ボディの至るところに傷がある ボディにいくつもの擦り傷やヘコみがあるクルマの場合、車両感覚を掴むのが上手でない人が多い傾向があり、つまり多少ぶつけても気にしないと言いますか、傷つくことに無頓着だといえます。 またそういった人に限って日頃のメンテナンスを後回しにしたり、洗車もしないなどクルマに愛情を注いでいないようです。 ●不必要な場面でブレーキを踏む 一般ドライバーの方のなかでも多いのが、不必要なブレーキです。周囲に危険があるわけでもないのに前走車のブレーキランプが何度も点灯したら、後続車はそのたびに同じようにブレーキを踏まなければいけません。 本人は速度調整のつもりなのでしょうが、後続車の迷惑になることも理解しないまま、漫然とブレーキを踏む運転も危険な行為のひとつ。そういったクルマから距離を置いたほうが良いでしょう。 ― 引用終り ― 十分な車間距離をとっていれば「不必要な場面でブレーキを踏む」クルマにつきあって頻繁にブレーキを踏むことは避けることができる。 そのほかとして、「スーパーカーや超高級車」、「馬運車や家畜の運搬車両」、「緊急車両」が記事であげられている。「馬運車や家畜の運搬車両」や砂利などをたくさん積んだダンプトラックなどに近づくのも、一般に避けられていると見受けられる。 緊急車両が近づいてきた場合は、緊急車両が通り抜けしやすい場所にクルマを停車するのがよいはず。接近する、追走するなどはもってのほかだ。 「ボディの至るところに傷がある」クルマ、「スーパーカーや超高級車」については、ショッピングセンターの駐車場で、人々が隣に駐車することを避けている様子がみてとれる。 都会ではない事例と思うが、近づかない方がよいものとして、「歩行者と同じ交通規則となる人」で、歩道があるにもかかわらず車道を走行している「原動機を用いる歩行補助車又はショッピング・カート」がある。高齢化の進展とともに歩行補助車に関する事故は増えることが考えられる。
2023年05月28日
コメント(0)
-

イギリスがウクライナに供与する劣化ウラン弾は核兵器?
劣化ウランの主成分のウラン238の放射能半減期は45億年。人間のおおよそ100年に満たない人生から見るとプルトニウムも劣化ウランも体内に取り込まれた場合の毒性の高さにかわりはない。 米国は劣化ウランを弾芯とした対戦車砲弾を使って、湾岸戦争の戦車戦を一方的に戦い、大勝利を挙げた。 湾岸戦争後、従軍した多くの兵士が放射線障害と思われる障害を訴えたが、その事実は隠ぺいされ、まとめられた資料は明らかにされていない。イラクでは、がんや先天性異常を含め、重篤な病気が増えたと報告もある。 ロシアは劣化ウラン弾のウクライナへの供与を非難しているが、彼らが劣化ウランを使用しているかしていないかは不明だ。テルミット弾などの非人道的兵器は使用している。自分の非は棚に上げ、相手の非ばかりクレイマーと同じ精神構造だ。 ウクライナに「ウラン弾」供与、英国の重大責任放射能汚染で「イラク戦争の悲劇」再現も2023年5月16日 東洋経済オンライン イギリス政府が主力戦車「チャレンジャー2」とともにウクライナに供与する軍事物資に劣化ウラン弾が含まれていることが、BBCなどの報道によって明らかになった。ロシアは反発を強めており、対抗策として核兵器の使用も辞さないとの姿勢を示している。 砲弾の原料である劣化ウランは、核兵器の製造や原子力発電で使われる濃縮ウランを作り出す過程で発生する放射性廃棄物。その劣化ウランを”有効利用”と称して兵器に使用したのが劣化ウラン弾だ。 劣化ウランの大部分を占めるウラン238は核分裂しにくいが、標的に当たると高温で燃焼して放射性微粒子となって拡散する。そのため、体内に取り込まれて内部被曝を引き起こすなど、人体や環境への悪影響が指摘されている。 5月19日から開催されるG7広島サミットで核不拡散が議題になる中、劣化ウラン弾の使用を問題視する市民グループは「ウクライナの大地を、劣化ウラン弾で汚染させるな」との署名を呼びかけている。集まった署名は岸田文雄首相やG7首脳らに届ける予定だ。 … (略) … 劣化ウラン弾自体は“通常兵器”とされ、アメリカ軍やイギリス軍はその危険性を明確に認めてこなかった。戦争で劣化ウラン弾を使ったことは認めた一方、「健康に影響を及ぼすような量ではない」などとして、健康被害との因果関係を否定し続けてきた。 湾岸戦争やイラク戦争では油田の破壊などにより、さまざまな化学物質で環境が汚染されたことや、経済制裁で医療体制に深刻な影響が出たこともあり、劣化ウランによる被害とそれ以外の被害を見分けること自体が困難だった。 … (略) … そうした中で今回、イギリスからウクライナへの供与が新たに問題になっている。 劣化ウラン弾は核兵器ではないものの、放射能汚染を引き起こす危険性を持つ。人権NGOヒューマンライツ・ナウの伊藤和子副理事長は、「『自然環境に対して広範、長期的かつ深刻な損害を与えることが予測される戦闘の方法および手段を用いることは禁止する』と定めた、ジュネーブ条約第1追加議定書」の条文にも反する」と指摘する。劣化ウラン弾が大量に使用された場合、ウクライナの復興にも重大な支障をもたらしかねない。 ― 引用終り ―
2023年05月27日
コメント(0)
-

ロシア、戦略爆撃機を北に移動…Tu-160、Tu-95
ロシアは戦略爆撃機を北に移動した。NATOの「北方拡大」への対抗措置との見方もされている。核戦争の準備ではなく、最近ロシア国内で多発している破壊行為を避けるためと考えたい。 2022年12月5日、国営ロシア通信は、モスクワの南東約200kmに位置する中部リャザニ州にあるディアギレボ空軍基地で燃料が爆発し、3人が死亡、6人が負傷した。同基地は、戦略爆撃機Tu95などの拠点。 12月5日朝、ロシアの複数の独立系メディアは、中部サラトフ州のエンゲリス空軍基地で、ドローンによる攻撃があったと通信アプリで明らかにした。Tu-95戦略爆撃機2機が損傷を受け、軍人2人が負傷したと報じた。 12月26日、ロシア南部、国境から450km離れたサラトフ州エンゲリスにある空軍基地で、2回の爆発音が聞こえたとウクライナのニュースメディア「RBCウクライナ」が報じた。同基地は戦略爆撃機Tu-95を配備するロシアの遠距離航空部隊の拠点。 2023年5月12日、ウクライナ南部クリミアで、ロシア軍のMi-28攻撃ヘリが訓練中に墜落し、乗員2人が死亡した。ロシア国防省は機体の異常が原因との見方を示した。 5月13日、ロシアの有力紙コメルサントは、ウクライナと国境を接するロシア西部ブリャンスク州で同日、ロシア軍のMi-8ヘリコプター2機とSu-34戦闘爆撃機、Su-35戦闘機各1機の計4機がほぼ同時に墜落し、ヘリ1機はミサイルで撃墜されたと報じた。 ロシア国営タス通信は当初、救急部隊の情報を基に、ロシア軍の 戦闘機1機とヘリコプター 1機の計2機が墜落したと伝えた。 この件についてロシア国防省は沈黙している。 ロシアの軍用機は、ウクライナでの戦闘で失われる一方、ロシアの領域で墜落、破壊が続いている。 北欧国境は、ロシア国内の西部、南部よりなにがしか安全なように見受けられる。 ロシア北欧国境に核爆撃機16機=NATO拡大で対抗―ウクライナ退避も狙いか2023年5月15日 時事通信 ノルウェーのメディア「バレンツ・オブザーバー」は13日、ロシア北西部ムルマンスク州のオレニヤ空軍基地に核兵器を搭載可能な戦略爆撃機16機が駐機しているのが、7日撮影の衛星写真で確認されたと伝えた。同基地は、北大西洋条約機構(NATO)加盟国のフィンランドやノルウェーまで約200キロの距離。ウクライナ侵攻を踏まえたNATOの「北方拡大」への対抗措置の可能性がある。 確認された16機の内訳は、TU160超音速戦略爆撃機2機とTU95戦略爆撃機14機。同メディアによると、ノルウェーの軍事専門家は「(ロシアによる)警告だ」と指摘した。 オレニヤ空軍基地は州都ムルマンスク南方にあり、2011年までは海軍飛行場だった。核貯蔵施設から近いとされる。ウクライナ侵攻開始前はTU22M爆撃機などが置かれていたが、昨年8月にTU160が確認され、10月までにTU95を含めて10機以上に増えたという。 戦略爆撃機は、遠方から巡航ミサイルを発射する形でウクライナ各地への空爆に使用。昨年12月には拠点であるロシア中部サラトフ州のエンゲリス空軍基地などに対し、ウクライナ軍によるとされるドローン攻撃が起きた。この際に移動させた戦略爆撃機がオレニヤ空軍基地にあるというが、同メディアは機体の増加について「短期的な退避のためだけではない」と伝えている。 ― 引用終り ― 残念ながら核弾頭を装備した大陸間弾道ミサイルのスイッチは、ロシアの誇大妄想狂、または狂人の手に握られている。
2023年05月26日
コメント(0)
-
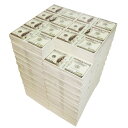
3銀行連続破綻、アメリカ発金融不安
2023年3月8日、仮想通貨(暗号資産)分野に注力し、苦境に陥ったシルバーゲート銀行の持ち株会社の「シルバーゲート・キャピタル」は、銀行業務を終了し、任意清算に踏み切ると発表した。 2023年3月10日、シリコンバレー銀行が経営破綻した。シリコンバレー銀行は、米国・カリフォルニア州に本社を置く銀行で、主にテクノロジー業界に特化した金融サービスを提供していた。 3月12日、米国・ニューヨーク州金融監督当局はシグネチャー・バンクの事業を同日付で停止したと発表した。シグネチャー・バンクは暗号資産(仮想通貨)関連企業との取引で知られていた。 5月1日、米金融当局は、経営不振に陥っていたファースト・リパブリック銀行(FRC)を公的管理下に置き、事業の大部分をJPモルガン・チェースに売却すると発表した。FRCの破綻は、アメリカの銀行破綻としては史上2番目の規模。 爆発に向けたカウントダウン──米銀行の連続破綻は必然だったInevitable Collapseニティシュ・パーワ(スレート誌ライター)2023年5月11日 Newsweek … (略) … 一連の破綻についてFRBは、大手金融機関への監視が強まる一方で、より小規模な銀行が監視を免れたことなどが原因と分析し、規制改革を求める材料にするだろう。 今回の一件で、SVBの破綻から6週間以上が過ぎても、米金融システムがその打撃から立ち直っていないことがはっきりした。相次いだ破綻は「伝染」ではない。FRCという火種の爆発に向けたカウントダウンは、はるか前から始まっていたのだ。 ― 引用終り ― 金融機関が破綻したとき、日本では、普通預金や定期預金といった預金が保険対象となり、一定限度額まで保護される(ペイオフ制度)。ペイオフ制度の限度額は、原則として「1金融機関につき元本1000万円と破綻日までの利息分」。金利のつかない当座預金などについては、全ての預金が保護される。 米国では、FDIC(連邦預金保険公社)が預金補償する。対象は、普通預金、貯蓄預金などで、補償額は25万ドル。しかし、この補償は日本では全額が保証される決済用預金などの金額も合わせた部分も含まれる。 米地銀でさらなる合併も当局は容認の公算=イエレン財務長官2023年5月15日 ロイター イエレン米財務長官は13日、銀行業界の現在の環境と一部地銀の収益への圧力から、米地銀業界ではある程度の合併・買収(M&A)が起こる可能性があり、規制当局はそうした合併を容認する公算が大きいと述べた。 主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議の合間にロイターのインタビューに答えた。 イエレン氏は、預金保険対象の預金に占める割合が高い小規模な地銀に圧力がかかっていることを示す証拠はなく、ほぼ全ての銀行は預金保険対象外の預金の予期しない流出に備えて十分な流動性を確保していると自信を示した。 しかし、地方の中規模銀行のセクターではある程度の合併が生じる可能性があると指摘。「今の環境ではさらに合併が起こるかもしれないし、そうなれば規制当局も受け入れると思う」と述べた。 また「残念なことに、いったん銀行株に圧力がかかると、その銀行が十分な自己資本と流動性を備えているにもかかわらず、預金保険を受けられない預金者の間で懸念が生じることがある」と述べ、銀行株への圧力で預金保険制度対象外の預金者に不安が生じる可能性を指摘した。 ― 引用終り ― イエレン米財務長官は、預金は補償されており不安になる必要はないが、金融機関の破綻は妨げることができないと言った。 救済合併が決まっていても、預金が補償されていても、「破綻懸念」の情報が流布されたとたん、大量の預金がネットを通じて引き出され、金融機関が破綻する構図が示された。この傾向に歯止めをかけることは、今のところほぼ不可能。 資本主義の根幹をなす金融制度は、ネット社会の進展により著しく不安定なものとなった。 この脅威は、大手の預金額が大きい金融機関であればあるほど深刻だ。
2023年05月25日
コメント(0)
-

ゼレンスキー大統領はフランス政府専用機A330-200でG7広島サミット入り
ウクライナのゼレンスキー大統領はサウジアラビアで開催されていたアラブ連盟の首脳会議の後、サウジアラビア・ジッダから19日にG7サミット出席のため日本へ向けて出発。5月20日、日本・広島空港に到着した。 2022年2月にロシアがウクライナ侵略戦争を開戦以降、ゼレンスキー大統領の海外訪問は12か国目。 ゼレンスキー大統領の乗機は、フランス空軍所属のフランス政府専用機・エアバスA330-200型機だった。機体には、フランス国旗をイメージした白地に青と赤のラインが入り、胴体前側の左右側面には「REPUBLIQUE FRANCAISE」(フランス共和国)と記されている。 当初、ゼレンスキー大統領はG7サミットにオンラインで参加する予定だったが、本人の強い希望で対面での出席に変更されたとのこと。それをマクロン大統領がサポートした。 ゼレンスキー氏、なぜフランス機で日本へ?外交筋が明かした舞台裏宋光祐2023年5月20日 朝日新聞DIGITAL … (略) …ゼレンスキー氏、なぜTシャツ姿?保安庁幹部が語った情報戦の教訓 フランス外交筋によると、今回の準備が始まったのは、ゼレンスキー氏が今月14日、G7サミットを前に、イタリアとドイツに続いてパリを訪問した時だった。ゼレンスキー氏とマクロン氏は同日夜にフランス大統領府で夕食をともにしながら会談。この際に、ゼレンスキー氏が「G7に出席したい」と述べ、マクロン氏に航空機の手配を直接依頼したという。 サミットを前にした欧州諸国歴訪では、ゼレンスキー氏が欧州に軍事支援を訴えかける場面が目立っていたが、水面下では訪日への調整が始まっていたことになる。この外交筋は、ゼレンスキー氏がフランスの政府専用機で日本に来たことについて、「両大統領の継続的な関係性による信頼の証しだ」と話す。 ― 引用終り ― ゼレンスキー大統領は21日、G7サミット出席の首脳とともに平和公園の原爆資料館を見学した後、岸田首相とともに原爆慰霊碑に花を捧げた。帰途の機内から自国民向けの動画声明を出した。「世界は私たちの立場に耳を傾けてくれた」と述べ、「世界の多数派」の理解を得たとして、訪日を含む一連の海外訪問の成果を強調した。 3月の岸田首相のウクライナ訪問は、成果ありと判断できる。ウクライナへの武器供与ができない日本の連帯の心も伝わったことだろう。 岸田首相の隠密行ウクライナは民間のビジネスジェットで果たされた。使用機材はボンバルディア・グローバル 7500。乗客定員14人でベッド、シャワーも完備されているとのこと。 岸田首相戦地 ウクライナ電撃訪問こうして実現した2023年3月22日 NHK政治マガジン … (略) … 取材によると、モディ首相との首脳会談など主な日程は20日の早いうちに終わる。 通常、現地での予定がぎっしりと組まれる総理の外国出張としては違和感がある。 政府・与党内から「23日の朝までに帰国すれば、総理は参議院の予算案審議に出席でき、国会運営への影響はない」という声も聞こえてきた。とすれば、インドに加えてウクライナを訪問する時間が確保できることになる。 政府関係者に取材を重ねると、インドから、経由地のポーランドに入る方法を検討していることがわかってきた。 極秘に準備されたチャーター機 総理の安全に関わるため、秘密保持を徹底しながら、機動的に移動する手段をどう確保するのか。 通常、総理の外国訪問には、自衛隊が運航する政府専用機を使う。実際、岸田も今回、インドに行く際は政府専用機に搭乗している。ただ、政府専用機は大型で常に2機体制で移動するため目立つ。しかも同行記者団も同乗しているため、隠密行動はできない。 そこで浮上したのが民間のビジネスジェットをチャーターすることだった。ビジネスジェットであれば少人数で機動的に移動できる。 徹底された情報管理 ただ… 一方、3月中旬になっても、多くの政府関係者はインドからの転戦を否定していた。 「今回のウクライナ訪問は絶対にない。インドからは予定通り日本に帰ってくる。22日には総理が出席する会議がたくさんある」 情報共有がされていなかったのか、知っていて言わなかったかは判断しがたいが、情報管理の徹底ぶりがかいまみえる場面だった。 ただ、ある政府関係者が私たちの問いに「行かない」とは決して言わず、こう話した。 「とにかく、5月のサミットまでに行きたい。サミットまでの日程を見てもらえればわかると思う」 また別の官邸幹部は、インドへの出発直前、「このタイミングで行くかどうか… でも、もし行く時が来たら、しっかり伝えてほしい」と話した。 これまで半年以上の取材で決して使わなかった「行く時が来たら」という言葉を使っていた。国会は続いているので、平日は、日程の確保が難しい。となると、週末や祝日を利用して、となり、21日の祝日を生かせるこのタイミングが有力かもしれないという取材実感が強まっていった。 インドで極秘の“かご脱け” 3月19日。岸田はインドへの出発直前に記者団にウクライナ訪問について問われ、次のように答えた。 「訪問の時期は、検討し続けておりますが、今まだ何も具体的に決まったものはありません」 翌20日、岸田は記者団とともに訪れているインドで極秘行動に出る。 現地時間午後7時。同行記者の1人、官邸クラブの小口は、岸田が現地日本企業との夕食会を終えて少し赤い顔で滞在先ニューデリーのホテルに戻ったのを目撃している。エスカレーターをのぼり、フロント階につくと、SPや秘書官とともに足早にエレベーターに乗り込んだ。ウクライナ訪問を警戒はしていたものの、これがインドで岸田を見る最後の瞬間になるとは、そのときは知るよしもなかった。 そのおよそ30分後、同行記者団はインド訪問に関する外務省のブリーフに参加するため、プレスルームに集められた。その裏で極秘な作戦が遂行されていたとは知らずに。 ― 引用終り ― グローバル 7500 諸元 乗客数:最大19人 乗員:4 全長×全幅×全高 33.8 m×31.7 m×8.2 m エンジン:ゼネラル・エレクトリック パスポート 20 推力:18,650 lbf / 83 kN 巡航速度 通常マッハ 0.85 高速巡航時マッハ 0.90 航続距離:14,260 km 離陸距離:1,792 m 着陸距離:768 m 最高高度:15,545 m
2023年05月24日
コメント(0)
-

少子化本格化…女子大・短大の閉校相次ぐ中続く、新設大学、学部の認可
少子化が本格化し、国内各地で大学の閉校のニュースが報じられるようになった。 少子化は本質的な閉校理由ではないとする見解もある。女子大、短期大学は、その存在理由を失ったということもあるのだろう。国立女子大学のお茶の水女子大学、奈良女子大学は大丈夫かな。 女子大と短大が消えていく少子化・定員割れで募集停止、閉校相次ぐ2023年5月6日 J-CASTトレンド 女子大や短大の募集停止、閉校が目立っている。恵泉女学園大(東京都多摩市)、神戸海星女子学院大(神戸市灘区)、上智大学短期大学部(神奈川県秦野市)、岐阜聖徳学園大短大部(岐阜市中鶉)・・・。入学者数の定員割れが続いていたため、苦渋の決断を強いられたようだ。 共学・大規模校志向も影響 恵泉女学園大学・大学院は3月22日、2024年以降の学生募集停止を公表した。18歳人口の減少、とくに近年は共学志向など社会情勢の変化の中で、入学者数の定員割れが続いたことを理由としている。「存続のためにあらゆる可能性を模索し、将来のありかたについて慎重に検討を重ねてまいりましたが、このたび閉学を前提とした募集停止という苦渋の決断に至りました」とウェブサイトに記している。 神戸海星女子学院大学も4月17日、24年度以降の学生募集を停止すると発表した。学生がすべて卒業する27年3月に閉校する予定だという。 大学側は朝日新聞の取材に、「18歳人口の減少、特に近年の女子の実学志向、共学志向、大規模校志向などで定員確保に苦慮してきた」と理由を説明。担当者は「在学生への責任を果たすため、このタイミングで苦渋の決断をした」と話している。 ― 引用終り ― 少子化は1990年代から始まっている。一方、1990年には372校だった大学は、2022年に620校と1.6倍になり増加し続けた。2000年以降で募集停止となった私立大学は16校。 閉校になる大学の特徴は3つ。 小規模校、立地に問題がある、入学定員の充足率が低い。 募集停止・廃校となる大学は何が敗因か~16校の立地・データから分析した・前編石渡嶺司大学ジャーナリスト2023/3/30 YAHOO!JAPANニュース ◆少子化だけではない募集停止※本シリーズは全4回です 募集停止・廃校となる大学は何が敗因か~16校の立地・データから分析した ・中編(2023年4月4日公開)募集停止・廃校となる大学は何が敗因か~16校の立地・データから分析した ・後編(2023年4月10日公開)募集停止・廃校となる大学は何が敗因か~16校の立地・データから分析した ・最終章(2023年4月18日公開) 恵泉女学園大学の募集停止を受けて、先日、関連記事を出しました。 女子大氷河期サバイバル~私立女子大65校の未来像をデータから検証(2023年3月25日公開) その前に、ヤフトピ入りした毎日新聞記事についても、コメントを入れたこともあり、しばらくメディア取材が続きました。 その中でよく言われるのが「少子化を理由としない専門家は石渡さんくらい」とのこと。 恵泉女学園大学はプレスリリースの中で少子化を理由にしています。 それを受けて、少子化だから募集停止となった、とするコメントが多くあります。 前記事でも出しましたが、恵泉女学園大学が募集停止となったのは少子化だけではありません。 いや、少子化が前提としてあることは私も同意します。しかし、それで終わらせるのは、募集停止の当事者はともかく、中立の視点を持つ専門家としてはちょっと情けない。そう思います。 経済評論家が企業倒産の理由を聞かれて「不況ですからね」で終わらせるでしょうか? 小・中学校教員や塾講師が児童・生徒の成績不振について「勉強しなかったからでしょう」で終わらせます?また、そういう説明で納得できますか? 不況であっても、倒産しない企業がある以上、もう少し踏み込んだ説明が経済評論家には求められるはず。 生徒・児童が勉強していなくても、そのうえでなぜ勉強に手が付かないのか分析することが小・中学校教員や塾講師の仕事であるはずです。 そもそも、少子化が理由で大学が募集停止になるなら、大学数はもっと少なくなっています。 ― 引用終り ― 募集停止、閉校の原因の深堀はよいことと思う。 多くの大学が研究機関としての機能を失い、大学教育のための教育機関としての役割を失いつつある時代に、少子化=学生数の減少が明らかなのに、学問としての専門性に欠ける大学が増え続けた理由、金の流れの方(関係者の皮算用)に興味がわく。 2012年11月、田中真紀子元文部科学大臣は2012年に大学新設を認めないと述べたことを猛烈に批判され、結果、更迭された。行政手続きとしての適不適は別として、この時点で大学が多過ぎることは明らかだった。 自民党は政権与党として、大学の独立行政法人化をすすめ国立大学への交付金を減額する一方で、文部科学省を通じて、大学の設置を認可し続けた。 2017年5月、朝日新聞が「これは総理のご意向」等と記された加計学園の獣医学部新設計画に関する文部科学省の文書の存在を報道した。安倍元首相は、森友学園問題とともに認可などのプロセスをモリカケ疑惑として追及され続けた。怪しいことこの上ない。 田中眞紀子大臣、大学新設3校認めず…審議会の抜本的な見直しへ 田中眞紀子文部科学大臣は、大学設置・学校法人審議会の抜本的な見直しを決め、審議会が答申した3校の大学新設は認可しないことを11月2日の定例記者会見で述べた。2012.11.2 リセマム 田中眞紀子文部科学大臣は、大学設置・学校法人審議会の抜本的な見直しを決め、審議会が答申した3校の大学新設は認可しないことを11月2日の定例記者会見で述べた。 主な理由として、全国約800ある大学の質の低下や、定員不足を海外からの留学生でカバーするなど大学運営に問題があることを挙げた。堀越学園では、8年間で40億円もの借金を抱え、このような事態が発生する状況では、大学設置・学校法人審議会に任せられないという。 今回の答申のうち、短大を廃止して4年制大学を新設する3校については認可しない。また、4年生大学の学部の変更16件は認可する。学部の変更については柔軟に対応していくという。 田中大臣は、「本当の学力のある自立した人物を育成することが重要で、早いうちから自分に何が向いているかを知って欲しい。」と述べた。 ― 引用終り ― 「優秀な官僚」は、悪事の証拠を残さない。このようなことが続くと三権分立の建前が崩壊し、民主主義は外形さえ保てなくなる。 森友問題、佐川氏ら不起訴共同通信, Kyodo2023年2月3日 ロイター 東京地検特捜部は27日、森友学園問題を巡り、学園側と財務省近畿財務局との交渉記録などの情報開示請求に対し「不存在」との虚偽の理由で不開示決定をしたとして、虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで告発された財務省元理財局長の佐川宣寿氏ら3人を嫌疑不十分で不起訴とした。「対象文書が残存しているとの認識を認めるに足りる証拠がなかった」としている。 決裁文書の改ざんを苦に自殺した近畿財務局の元職員の妻らが告発状を提出。「文書の保有が確認できなかった」との理由で17年3~5月の不開示に携わったとして佐川氏、当時の理財局総務課長と国有財産審理室長を告発対象としていた。 ― 引用終り ―
2023年05月23日
コメント(0)
-

ペリカン便はどこにいったか 宅配便の栄枯盛衰
クロネコヤマトの宅急便は1976年に始まった。収益性の低い運送事業の改革となった。 ヤマトの宅配事業の急成長を見て、宅配事業の将来性を確認した日通の「ペリカン便」は1977年に始まった。 「ペリカン便」は、2009年4月より、日本通運と郵便事業株式会社とで設立したJPエクスプレス株式会社で運営されたが、2010年7月1日、JPエクスプレス株式会社の宅配便事業が郵便事業株式会社のゆうパック事業に引き継がれ、消滅した。 取扱い量が成長を続けた宅配業界であるが、カンガルーの西濃、こぐまの名鉄宅配便、犬のマークのフットワークエクスプレスなど取扱事業者も増えた。全国規模での宅配事業の展開は容易なことではなく、宅配事業を止めたところも多い。飛脚の佐川急便のように、宅配事業を通じて各地方別のフランチャイズ運営から、全国企業になった物流事業者は多くはない。 2010年2月、日本郵政グループの日本郵便の2010年3月期の単独決算は、7年ぶりとなる179億円の最終赤字となった。日本通運との宅配事業統合を見直すのに伴う特別損失が主な要因だが、景気低迷などによる宅配事業の収益悪化という構造的な課題が残された。 2022年11月11日に発表した2023年3月期第2四半期決算によると、郵便・物流事業の売上高(営業収益)は9469億円(前年同期比0.7%減)、営業損失63億円(前年同期は72億円の利益)となった。取扱数量は総計で1.6%減。郵便は1.2%減、ゆうメールは2.9%減。ゆうパックは厳しい競争環境等により2.8%減(うち、ゆうパケットは2.4%減)となった。 赤字の郵便事業をカバーすべく、強化した宅配事業ゆうパックだったが、経営の強引さが目立つ郵政グループが事業をすすめたため赤字体質は是正されず、必要な投資も行われなかった。 もはや懐かしい「日通のペリカン便」どこいった!? 2010年に消滅? 意外な「統合先」とは2023/5/12 くるまのニュース宅配便として知られていた「ペリカン便」今はいずこに!? 現在では、日常生活での商品購入手段としてネット販売が広く普及しています。それを支えているのは「宅配便」の存在です。 … (略) … 小荷物を発送するのは、現在ではごく簡単なことですが、宅配便が存在するまでは、個人が行うのもひと苦労なことでした。 というのも、郵便小包(現:ゆうパック)もしくは「チッキ」と呼ばれた鉄道小荷物に頼るしかなかったのです。そのため発送したい人は、荷物を郵便局や駅まで運ぶ必要がありました。 さらにチッキの場合、自宅まで届けてもらうことはできず、荷物を受け取るには駅に行かねばなりませんでした。 1970年代に宅配便が開始されると、その便利さから80年代には急速に普及。最初に宅配便サービスを広げたのはヤマト運輸ですが、これを追うように大手輸送会社も続々とこの市場に参入し、宅配便サービスの競争が始まりました。 そのため不便だった鉄道小荷物は、1986年に姿を消しています。 このようにして開始されたペリカン便は、その後も順調にサービスを拡充。1991年には、国内航空便を用いて速達性を高めた「スーパーペリカン便」、2000年からは冷凍品の輸送も可能な「クールペリカン便」もスタート。 このほか「ゴルフペリカン便」「スキーペリカン便」なども用意され、様々な需要に応じていました。 しかし元来、日本通運は小規模な個人向け輸送よりも、鉄道や海運、大型トラックを利用した法人向け輸送を得意としています。 さらに宅配便市場ではヤマト運輸と佐川急便の2トップが圧倒的に強かったため、同市場でのシェアを伸ばせませんでした。 そして同様に、郵便による宅配便サービス「ゆうパック」(2007年から郵便小包から宅配便貨物に変更)を扱っていた「郵便事業株式会社(現:日本郵便株式会社)」もまた、収益が伸び悩みに。 そこで両者は統合による競争力強化を狙い、新たに「JPエクスプレス」を設立。ペリカン便ブランドは日本通運から離れ、JPエクスプレスが引き継ぐことになりました。 なお両社の出資比率は、郵便事業が66%、 日本通運が34%でした。 しかし事業を始動した2009年4月の段階では、システム的な問題などにより事業統合ができないままだったため、ひとまずペリカン便事業のみで営業し、同年10月にサービスの統合を目指していました。 ところが2009年10月の統合も総務省から認可が下りず再延期。JPエクスプレス自体の赤字も拡大しており、2010年3月期末の累積損失は約681億円に達しています。 そこで2010年7月、JPエクスプレスを清算、同社のペリカン便事業を郵便事業のゆうパック部門が引き受けることに。つまりペリカン便のサービスはゆうパックに引き継がれて一本化されたのでした。 そして同時に、ペリカン便のブランドはここでついに消滅することになったのです。 … (略) … ではペリカン便が消滅したあと、これらのクルマはどうなったのでしょう。 実は一部のクルマでは、ペリカン便・日本通運のロゴを消し、黄色+青帯を残したままゆうパックの集配に用いられていました。 それなりの台数が塗装変更を受けぬまま、ペリカン便カラーで残っていたのです。 2010年のペリカン便消滅から10年以上が過ぎた2023年現在でも、地域によっては時折その姿を見ることができるようです。 なお前述のスーパーペリカン便は、郵便事業にペリカン便が統一された後も残り、現在は「エクスプレスハイスピード」というサービス名で展開中です。 ― 引用終り ― 日本通運、福山通運などが表記している「通運」とは、鉄道貨物輸送の両端の貨物取扱駅において、荷主と鉄道の間に介在し、鉄道輸送を補完し、発荷主戸口から着荷主戸口までの輸送を遂行する事業をさしている。陸運の主役が鉄道輸送だった時代の言葉だ。 2001年に経営破綻し宅配事業から撤退した「フットワークエクスプレス」は、日本郵便の一員となっている。 民事再生法の適用申請を行い2003年、フットワークエクスプレス株式会社が復活。2009年、オーストラリアの物流会社「トール・ホールディングス」の子会社となり、2012年、トールエクスプレスジャパンへ社名変更。 2015年、親会社のトール・ホールディングスが日本郵便により買収された。
2023年05月22日
コメント(0)
-

NIB実用化…安価なバッテリーの実用化とEVビジネスの闇
車載電池世界最大手、中国・CATL(寧徳時代新能源科技)は2023年2月、一部のEVメーカーにバッテリーの「値下げ計画」を提示したと報じられた。その後、バッテリーの主要原料でEVの普及拡大に伴い絶対的に不足するとされ高騰を続けたリチウム(炭酸リチウム)の相場が短期間で急落した。 2023年2月、中国では炭酸リチウムの価格が1トン当たり44万元(約850万円)に高騰した相場が、4月6日、半額以下の21万6000元(約420万円)まで急落した。 リチウム価格の下落でCATLの提示した「値下げ計画」は崩壊した。値下げは、バッテリーの8割をCATLから調達しなければならないとの条件が付されていたからだ。 リチウム価格下落は、中国におけるEV需要鈍化と、市場が不安定でトレーダーが慎重になっていることが背景とされた。コバルト、ニッケルなど、バッテリーに関連する他の金属も値下がりした。 2023年4月16日、CATLはナトリウムイオン2次電池(NIB)が、中国の自動車メーカーChery Automobile(奇瑞汽車)のEVに採用されたと公表。NIBが量産車に搭載されるという発表は世界初。 今後、多数のEVや定置用蓄電池などにNIBが使われる見込みで、これまでリチウムイオン電池(LIB)が担ってきた大容量蓄電池の市場の一角をNIBが占めるとされる。 炭酸リチウムの取引価格は下落の要因が増え、一層の下落が続くとみられている。 炭酸リチウムと異なり、高仕様ハイニッケル三元系バッテリーに使用される水酸化リチウムの価格は依然として高めr。3月9日、LME(ロンドン金属取引所)で取引される水酸化リチウムの価格は、トン当たり7万2239.13ドル(約974万円)。2ヵ月前より11.67%下落だが同期間の炭酸リチウムの価格は32.7%下落だった。 ナトリウムイオン電池時代幕開け関連メーカーが50社超で価格はLIBの1/2へ野澤 哲生 日経クロステック/日経エレクトロニクス2023.05.08 日経クロステック 「我々のナトリウム(Na)イオン電池(NIB)は、中国Chery(奇瑞汽車)の電気自動車(EV)に搭載される」――。2023年4月16日の中国CATL(寧徳時代新能源科技)による発表は、電池にとっての新時代の幕開けになった。 ― 引用終り ― 今後はエネルギー密度の低いが安価なNIBと、エネルギー密度は高いが高価なLIBが、大容量蓄電池市場を分け合うことになる。ただしEVについてはNIBが次の時代の主役になるとは言えない。 素材の高騰もあり製造原価が高いため赤字ビジネスと化しているEV事業は、今後、耐久性などの品質も勘案され、黒字販売のビジネスに転換する可能性が多少高まった。 次世代技術とされるバッテリー関連、給電関連の多くの技術が量産化途上のため、現在量産・実用化されているバッテリーによるEV市場の拡大、シェアの確保は、必ずしも将来のEV市場の基盤とはならない。加えて、自動運転、安全運転補助などの運転制御技術の進歩が加わり、次世代の自動車に関する技術標準は、過渡期の表現がふさわしい状態。 米フォード、EV事業3900億円の赤字23年12月期見通し北米2023年3月24日 日本経済新聞 米自動車大手フォード・モーターは23日、電気自動車(EV)事業の調整後EBIT(利払い・税引き前利益)が2023年12月期に30億ドル(約3900億円)の赤字になるとの見通しを明らかにした。赤字幅は22年12月期の21億ドルから拡大する。販売台数の増加に伴い収益は改善し、26年12月期には事業利益率が8%に達するとの見通しも示した。 ― 引用終り ― 2023年3月23日、米国・フォード・モーターは、2023年のEV事業の損益が30億ドル(約3900億円)の赤字になる見通しを明らかにした。生産や開発への巨額投資が響き、赤字は21年の9億ドル、22年の21億ドルから拡大している。フォード社はこの赤字を既存のガソリン車の販売による利益でカバーするとしている。 フォードモーターばかりでなく、ガソリン車の販売の圧迫するほどEV販売が好調な中国のEVトップのBYD以外、中国のEV専業メーカーはすべて赤字だ。 好調ばかりが報じられる中国のEVメーカーだが、実は1社を除いて軒並み巨額の赤字を記録していた!そのうち倒産ラッシュとなる気配2022/12/07 Life in the Fast Lane中国 中国では「後先考えず」とにかく売りまくるというビジネススタイルも珍しくはない この記事のコンテンツ 1.中国では「後先考えず」とにかく売りまくるというビジネススタイルも珍しくはない 1.1商品力よりも、その経営戦略が業績を大きく左右 1.2中国のEVメーカーは「売れば売るほど赤字」? 1.3ただし唯一「儲かっている」自動車メーカーも 1.4あわせて読みたい、中国のEVメーカー関連投稿 1.5こんな記事も読まれています … (略) …ただし唯一「儲かっている」自動車メーカーも ただ、そんな「赤字まみれ」の中国EV業界にあって唯一利益を出しているのがBYD。 BYDはウォーレン・バフェットが出資していることでも知られますが、BYDは現在中国最大の電気自動車メーカーとなっており(中国2位のバッテリーメーカーとしても知られる)、今年上半期には64万1350台を販売し、その利益は206%増の36億元という、ほかのEVメーカーとは全く異なる業績をあげています。※やっぱりバフェットは先見の明があったんだな・・・ ― 引用終り ― 2022年8月31日、中国・BYDの株価が午前の香港市場で急落。投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏率いる投資・保険会社バークシャー・ハサウェイがBYD株の保有を縮小したのがきっかけとなり、トレーダーの間ではバフェット氏がさらに持ち分売却を進める可能性が警戒され、売り注文が殺到した。 2023年4月11日、バークシャー・ハザウェイは、BYDの香港上場株式248万株を5億3993万香港ドル(6878万ドル)で売却したことが、証券取引所に提出された資料で明らかになった。3月末時点のバークシャー・ハザウェイのBYD株の保有比率は11.13%から10.90%に低下した。 中国では補助金給付をあてにしたEV大量製造・赤字販売が、新車販売台数の水増し疑惑の発生を招いている。 内燃エンジンよりもEVの方がナンバーが取得しやすいため、中国ではEVの方が買ってすぐに使える。EV補助金は個人ではなく、販売会社に給付されるため、売りやすいEVの製造原価割れの販売、BYDを含め販売台数の水増しが横行している。 EV世界一のテスラの車は、電池をパナソニック製から中国・CATL、韓国・LGに変えてから、発火事故が多発している。米国・シボレーのEVもLGの発火事故で総額20億ドルのリコールを行っている。 現時点で、EVビジネスは闇だらけだ。 赤字続く中国EV「零跑汽車」新車販売台数の水増し疑惑発覚ディーラーが告発2023年4月25日 36Kr 2022年9月に香港上場を果たした中国の新興電気自動車(EV)メーカー「零跑汽車(Leap Motor)」が、新車販売台数を不正に操作した疑いが強まっている。きっかけは、あるディーラーの店長が公開した告発動画だった。 告発動画によると、零跑汽車はディーラーに対し、新エネルギー車に対する補助金政策が終了する22年12月末までに新車のナンバープレートを取得するよう圧力をかけ、国からの補助金を不正に受け取っていた疑いがあるという。告発動画を出した店長は、零跑が要求する販売目標を達成するため、親戚や友人の名義でナンバープレートを取得し、その車を中古車並みの価格で販売する必要に迫られた。この店長は、同社が報告していた22年12月の新車販売台数8493台のうち、4916台はこの不正操作で水増しされたものだと主張している。 ― 引用終り ―
2023年05月21日
コメント(0)
-

ロシア軍の補給不足と戦勝パレード……戦車T34たった1台
2023年5月9日、ロシアの第二次大戦の対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードは無事行われた。例年と比べて極めて小規模で……。 2023年3月22日、米・国防総省高官は、ウクライナに侵攻したロシア軍が前線で燃料や食料などの補給不足に悩まされ、凍傷を負った兵士も出ているとの分析を明らかにした。ロシア軍が食料や燃料などの再補給を計画するものの実施に至っていないと指摘。洋上の艦船の燃料や、精密誘導兵器などの武器や弾薬の在庫も不足し始めているとした。 4月30日、ロシア国防省は、兵站担当の国防次官について、ミハイル・ミジンツェフ上級大将に代わり、アレクセイ・クズメンコフ上級大将が国防次官に任命されたと発表した。 ロシアによるバフムト攻撃を主導しているワグネルの創設者・エフゲニー・プリゴジン氏は、弾薬が不足し「無駄で不当な」損失を被っているとして、10日にウクライナ東部ドネツク州バフムトから部隊を撤退させると5月5日に表明した。プリゴジン氏SNSで「数万人の戦闘員の死傷者」の責任はセルゲイ・ショイグ国防相らにあると非難した。 5月7日、ワグネル創設者のエフゲニー・プリゴジン氏は、ロシア政府がさらなる武器供給を約束したとして、バフムトからの撤退方針を転換し戦闘を継続する可能性を示唆した。 ロシア政府は人員・兵器の損耗、不足を隠ぺいするため、対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが中止になるとの、ロシアの兵站不足を案じる見方が報じられた。 兵站不足でも、権威付けの行事は強行されるのだが。 ロシア、軍事パレード中止で損耗隠蔽か9日に対独戦勝記念日2023年5月8日 産経ニュース ロシアは9日、第二次大戦の対ドイツ戦勝記念日を迎える。ウクライナ侵略を続ける中、首都モスクワなど各地で行われる恒例の軍事パレードは今年、少なくとも20都市以上で中止が決定されたと伝えられる。3日に起きたクレムリン(露大統領府)への無人機攻撃などを踏まえた安全対策が理由とされる一方、侵略による人員や兵器の損耗を隠すためだとの見方も出ている。 プーチン大統領は当日、モスクワで行われる式典で演説する予定。軍事パレードとともに国民の愛国心を鼓舞し、団結を内外に誇示する機会としたい思惑だ。 ショイグ国防相が3月に説明したところでは、モスクワ中心部の「赤の広場」での軍事パレードには軍人1万人超と戦車など125の地上兵器が参加する予定だ。将兵1万2千人と190の兵器が参加したウクライナ侵略前の2021年より小規模だが、昨年とはほぼ同じ規模となる。 ただ、例年は事前にパレードに加わる兵器が発表されるが、今年は7日時点でも明らかにされていない。航空部隊の参加の有無も公表されていない。 軍事パレードについてショイグ氏は3月時点で、22年と同数の「28都市」で実施すると表明していた。しかし露独立系メディア「ビョルストカ」は今月3日、4月下旬~5月上旬に少なくとも21都市でパレードの中止が決定されたと伝えた。ロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島や同国国境に近い都市だけではなく、国境から数千キロ離れた複数の都市も含まれるという。 米シンクタンク「戦争研究所」は4日、各地での軍事パレード中止について、「安全対策」を名目にウクライナ侵略による露軍戦力の損耗を覆い隠そうとしている可能性が高いと指摘。自作自演説が指摘されるクレムリンへの無人機攻撃も、パレード中止を正当化する口実と分析する。 ― 引用終り ― 5月9日は第2次世界大戦で旧ソビエトがナチス・ドイツに勝利したことを祝う「戦勝記念日」で、ロシアで最も重要な祝日の1つとし、愛国心を高揚はかるため、軍事パレードにて新兵器の披露や大統領による演説が行われてきた。 2022年のモスクワのパレードでは、前年と比べて1000人少ない兵士およそ1万1000人が参加した。 兵器については、前年より60少ない、131披露された。 2023年の軍事パレードの様子は、兵士8000人、航空機の展示飛行ナシ。戦車は第二次世界大戦時の現役T34-85が1台。S-400防空システムや核戦争用のヤルス大陸間弾道ミサイルがパレードした。T-14など戦車、装甲兵員輸送車などの装甲車両をパレードに出す余裕がないことが示された。 プーチン大統領の演説ではクレムリンへの無人機攻撃は、語られなかった。 第二次世界大戦のナチス・ドイツとの戦いは、ソビエト連邦で「大祖国戦争」と呼ばれ、苦難の末に勝利した栄光の日と位置づけられている。ソ連邦は、第二次世界大戦で世界最多の2600万人の兵士と市民が死亡したとされている。 ユーリー・オーゼロフ監督の映画『ヨーロッパの解放』は、ソビエト連邦製作の独ソ戦を描いた戦争映画シリーズ。大祖国戦争に勝利し、ヨーロッパを解放したという体で製作されている。1970年に製作を開始し完成に3年を要した国家的事業の全5部の超大作映画で、総上映時間は合計で7時間48分。第一部 「クルスク大戦車戦」、第二部 「ドニエプル渡河大作戦」、第三部 「大包囲撃滅作戦」、第四部 「ベルリンの戦い」、第五部 「最後の突撃」。 ナチズムからの解放ではあったが、東欧諸国にとっては、ソ連邦による社会主義体制の圧政の始まりだった。
2023年05月20日
コメント(0)
-

ロシアは燃えている…大火災、
2023年5月4日、ロシアは、モスクワのクレムリンへのドローン攻撃について、背後に米国の存在があると指摘し非難の矛先をウクライナから変更した。根拠のないロシアの主張に対して、米国はすかさず否定した。 プーチン大統領を狙うなら、標的の位置が不明確で、成功率の低いこんな稚拙な攻撃をするはずがない。 5月9日は第2次世界大戦で旧ソビエトがナチス・ドイツに勝利したことを祝う「戦勝記念日」で、最も重要な祝日の1つであり、攻撃の意図示す時期としては適切なタイミング。 ロシア、クレムリン無人機攻撃「背後に米国」非難の矛先変更ロイター編集2023年5月4日 ロイター ロシアは4日、プーチン大統領殺害を目的としたクレムリンへのドローン(無人機)攻撃について、背後に米国の存在があると指摘した。証拠も示さないロシアの主張に、米政府はすかさず否定した。 ロシアは前日、ウクライナが夜間にドローンを使ってプーチン大統領殺害を図ったものの未遂に終わったと表明。これに対しウクライナのゼレンスキー大統領は最大の関心はロシアの侵攻から自国を守ることだとし、関与を否定していた。 ロシア大統領府のペスコフ報道官は4日、「このような行動やテロ攻撃に関する決定は、キエフでなくワシントンで下されることを、われわれはよく知っている」と述べ、米国が攻撃の背後にいることは「間違いない」と述べた。 これに対し、米国家安全保障会議(NSC)カービー戦略広報調整官はMSNBCテレビに対し、ロシアの主張は虚偽であり、ワシントンはウクライナに対し国外への攻撃を促すことはなく、そんなことはできないと述べた。 ― 引用終り ― ロシアの自作自演も疑われているクレムリン攻撃よりも気になるのは、ロシア国内で次々と発生している燃料貯蔵施設などの爆発。 2023年3月、戦車用のディーゼルエンジンを製造するヤロスラブリ自動車工場で火災発生。 4月、サンクトペテルブルグの廃火力発電所で火災発生。モスクワ東方100kmのカザンの戦車訓練センターで大爆発発生。 4月29日、クリミア半島セヴァストポリの石油備蓄施設で火災発生。 5月3日前日、ロシア本土と占領下のクリミア半島を結ぶ橋の近くで燃料貯蔵庫で火災発生。 5月4日、ロシア南部クラスノダール地方の黒海沿岸の港ノボロシースクに近いイルスキーの製油所で石油製品備蓄施設の一部が炎上。モスクワの東1400kmのスヴェルドロフスク州64か所で山火事発生。 火災、爆発ではないが5月にブリャンスク州で2日連続で列車脱線事故が発生している。 ロシア国内の反プーチン勢力などの活動でもあるのだろう。ロシアでは昨年から毎月のように各所で、爆発、大火災が発生しており、ウクライナ軍特殊部隊の仕業だけとは思えない。 ソ連、ロシアの原子力潜水艦は火災が発生、沈没することで有名だった。 ウクライナ侵略戦争開始前のロシアの事情をよく知らないのが、もともと爆発事故、大火災が多い国なのだろうか?
2023年05月19日
コメント(0)
-

帝国ホテルの将来計画
コロナ禍も明け、日本の観光関連業界は、利用者の拡大、インバウンド客の取り込みに取り組んでいる。 帝国ホテルはさらなる高級化路線を選んだ。 2024年度から2036年度にかけて帝国ホテル東京の本館と隣接するタワー館を建て替え、本館は最低でも50~60平方メートルとし、1室の面積の拡大し、コンシェルジュの配置を厚くするなどして、海外富裕層の取り込みの強化をはかる。 2030年度竣工予定の新しいタワー館は、賃貸オフィスと現在も好評のサービスアパートメント(長期滞在サービス)をいっそう充実した設備で展開し、より安定した経営基盤、財務基盤を得る建物にする。 帝国ホテル東京の隣接地に2029年度に完成する建物の高層部で、NTT都市開発とともに100室規模のスモールラグジュアリーホテルを開業する。 注目されるのは、2026年、京都・祇園の新ホテル建設計画だ。 帝国ホテルが「悲願の京都」に開業する深い意味東京本館の建て替えや30年ぶり新館で狙う客層星出 遼平 梅咲 恵司 : 東洋経済 記者2023/05/06 東洋経済オンライン … (略) … 次の世代の舞台作り――2026年には京都の祇園に新ホテルを建設します。実に30年振りの新規開業です。 これも本館の建て替えと同様に、次の世代の舞台作り(成長戦略)の一環だ。「京都にいまさら投資するのはどうか」と社内でも異論があったが、京都は国際的にも有名な観光都市で優位性がゆるがない。結果的に、祇園といういい場所にホテルを開業することができることになった。 国の登録有形文化財である「弥栄(やさか)会館」の一部を保存活用した歴史・文化的価値のあるホテルで、難しい工事となるが、2026年春の開業に向けて着々と準備を進めている。 京都という土地柄、建物の高さ制限(計画地では12メートル)がある。本計画は地域の景観への配慮や計画の意義を評価いただき、弥栄会館と同じ高さ(31.5メートル)の特別許可をいただいたが、その規模からすると、客室は60部屋程度となる。 国内勢のホテルとして、外資系のホテルにはない雰囲気やサービスを提供したい。そういった意味で、(イベントを共同開催するなど)地元の皆様との連携も大事になってくる。 この京都の新拠点は「短い期間で稼いで終わり」ということではなく、50年、100年と続くホテルをしっかり手がけていきたいと考えている。規模を大きくせず、少ない客室で、ひとつひとつのサービスのグレードを上げていく。 ――京都開業後のグループ内連携策を教えてください。 当社にとって、京都にホテルを造る意味は大きい。例えば、海外のお客様が日本に来るときに東京から入って、西に移動して大阪から帰るケースがあるとする。この場合、ひと昔前は帝国ホテル東京に泊まって、京都駅前の他社のホテルに泊まることが多かった。 3年後に京都に拠点ができるとなると、お客さまは私どものサービスを京都でも受けられる。帝国ホテルは大阪(大阪市)にも、上高地(長野県松本市)にも拠点がある。 さらに、帝国ホテル東京の隣接地で再開発計画があり、2029年度に完成するその建物の高層部では、私どもがNTT都市開発とともに100室規模のスモールラグジュアリーホテルを開業する。 長年の経験とノウハウを結集させた、ハイエンドの富裕層のお客さまを意識したホテルになる。外資系のラグジュアリーホテルの上に位置するようなホテルにしようかと考えている。 京都にホテルができる段階でわれわれのブランドを世界にどうアピールしていくかは、いま学習しているところだ。外国のお客様も国内のお客様も、日本にある帝国ブランドのホテルを回遊してもらえるようにしていきたい。 ― 引用終り ― 国内の観光業、宿泊業が人手不足、人材不足に悩む中、従業員募集についても帝国ホテルというブランドは有効性が高いと思われる。安価な大衆的サービスがセルフ化、自動化されるにつれ、高級なサービスは、ヒトによる接客が益々重要になると推測される。
2023年05月18日
コメント(0)
-
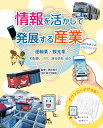
正社員不足「旅館・ホテル」の75.5%
コロナ禍で観光が厳しく制限され、旅館・ホテル、公共交通機関などの経営が大打撃を受けた。 コロナ禍が明け、観光など人々の自由な移動が可能となり事業の復活へのチャンスがきたとき、深刻な人手不足を再び思い知らされることになった。人手不足で、事業・設備をフル稼働できないとの声が、各所から聞こえてくる。 帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」によると、業種別の厳しい人手不足の状況が見て取れる。 正社員の人手不足割合では、6カ月連続で業種別トップ「旅館・ホテル」が 75.5%で、深刻な人手不足が続いている。 非正社員は「飲食店」が85.2%でトップ。飲食店は、パート・アルバイトなどを含む非正社員が全体の7割以上を占めており事業運営の主戦力だ。正社員で業種別トップの「旅館・ホテル」(78.0%)は、非正社員についても2番目の高水準。 長時間、低賃金、不安定労働を前提に売価が組立てられている日本のサービス業のビジネスモデルが、根本的な見直しを迫られている。 正社員の人手不足「旅館・ホテル」75.5%が実感「飲食店」非正規社員不足も85.2%に2023年5月5日 J-CAST会社ウォッチ 新型コロナウイルスによる経済の停滞も抑制され、徐々に経済のスピード感が戻ってきている。しかし、さまざまな業種で人材確保がひっ迫し、人手不足を叫ぶ声が漏れ聞こえる。 こうしたなか、帝国データバンクが2023年5月2日に発表した「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」によると、正社員の人手不足は全業種で51.4%にのぼった。とりわけ「旅館・ホテル」では、人手不足が8割に迫る深刻な高水準である実態も明らかになった。 また、非正規社員で業務を行っている「飲食店」においては、8割超の現場で人手不足を感じるなど、コロナ前の水準に戻ってきていることがわかった。 全業種の過半数の企業で人手不足の実態4月としては過去最高値に はじめに、2023年4月時に全業種に対して従業員の過不足状況を聞いてみると、「不足」と答えた企業は「51.4%」に上った。前年同月比では5.5ポイント上昇している。 また、非正社員では「30.7%」となっており、4月としては4年ぶりに3割超の水準に達した。 同社では 「例年4月は新卒新入社員が加わることもあり、月次では(過不足状況は)やや低下する傾向があるものの、5割を上回った。4月としては過去最高を記録した」と分析。 続いて、正社員の人手不足割合を業種別でみてみると、「旅館・ホテル」が「75.5%」で最も高くなった。毎月の統計では6カ月連続で業種トップとなり、深刻な人手不足が続いている。 次いで、IT人材不足が顕著な「情報サービス」も「74.2%」で続いた。 同社では 「実際に企業からは『案件が多いものの人手が足りない、という状況が継続している』(ソフト受託開発、神奈川県)などの声が聞かれた。」としている。 他業種を見てみると、「メンテナンス・警備・検査」は「67.6%」と、9カ月連続の高水準。「建設」も「65.3%」は12カ月連続で6割超となった。 また、「物流2024年問題」が話題に上がる「運輸・倉庫」も「63.1%」と6割超の高水準となった。 さらに、レンタカー業などを含む「リース・賃貸」は「60.7%」とコロナ禍以降で最も高くなった。 つぎに、非正社員の業種別では「飲食店」が「85.2%」で唯一の8割超に達した。 同社は飲食業の従業員の特徴について 「飲食店は、パート・アルバイトなどを含む非正社員の就業者全体の7割以上を占めている特徴があるなかで、就業者数がコロナ前まで回復していない状態が続いている」とコメント。 飲食店以下、「旅館・ホテル」(78.0%)、「飲食料品小売」(58.7%)、「娯楽サービス」(47.2%)など、個人向け業種が上位に多く並んでいるようだ。 ― 引用終り ― 円安のため、外国人労働者の大幅な増加は望めない。 日本のサービス業の多くは、一人の労働者に多くの柔軟な役割を担わせており、DXによる省人化、合理化が困難、またはそのための設備投資が巨額になる可能性が高いなど、人手不足の解消策の実行は容易ではない。 自動化、機械化をすすめた回転ずしチェーンは、生産工場、装置産業の姿に近づきつつある。即ち人件費ではなく、設備投資額が大きくなっている。 2020年 2 月 27 日に発表された日本政策金融公庫のニュースリリースですでに「ホテル・旅館業の人手不足感が調査開始以来、過去最高」と示されているので、人手不足感がコロナ禍前に戻ったとも言える。 深刻な人手不足は、低賃金により低付加価値となっている日本のサービス業の根本が見直される契機、「安いニッポン」改革の契機になるだろうか。 「ホテル・旅館業の人手不足感が調査開始以来、過去最高」雇用動向に関するアンケート調査結果(生活衛生関係営業の景気動向等調査特別調査結果2019年10~12月期)株式会社日本政策金融公庫 ■ 従業者の過不足感は、「不足」と回答した企業割合が37.2%と、前年調査を2.6ポイント下回った。業種別にみると、ホテル・旅館業が67.0%と前年調査を4.9ポイント上回り、調査開始以来、過去最高となった(3ページ)。 ■ 従業者の不足への対応は、「従業者の新規採用」と回答した企業割合が34.6%と最も高く、次いで、「営業時間の短縮」(34.4%)、「従業者の多能化・兼任化」(30.0%)となっている(5ページ)。 ■ 従業者の採用に向けた取り組みで効果的なものは、「身内や知人等への紹介依頼」と回答した企業割合が39.3%と最も高く、次いで、 「求人サイトの活用」(20.7%)、「ハローワークへの求人」 (18.7%)となっている(8ページ)。 ■ 従業者の定着化に向けた取り組みで効果的なものは、「賃金の引き上げ」と回答した企業割合が45.4%と最も高く、 次いで、「休日・休暇の増加」(37.1%)、「勤務時間の削減」(26.7%)となっている(9ページ)。 ■ 従業者の賃金水準は、1年前と比べて「上昇した」と回答した企業割合が、正社員で37.2%、非正社員で48.5%となった。賃金を引き上げた企業割合は、調査開始以来、過去最高となった(10ページ)。 ― 引用終り ―
2023年05月17日
コメント(0)
-

軽自動車はガラパゴス?
物流の基本は既存の社会・交通インフラを可能な限り有効に活用することにある。一般に「物流インフラ」とされるものは、大きさなど何らかの規格がある。 日本の道路は橋梁、トンネルなどが多いため、必ずしも世界規格のコンテナ(海洋コンテナ)はトラックに隻刺したまま通ることができない。日本の物流コストが高いことの一因であるが、世界規格に合わせることは金銭面で困難なようだ。 非関税障壁ともされる軽自動車も日本独自規格だ。安全面などから軽自動車の全長、全幅は拡大されてきたが、「軽」規格の規定はないが、軽トラックは、狭小なあぜ道、林道、海辺の住宅街を曲がることのできる実質最小回転半径は小さく保たれている。農林漁業者の高齢化、就労人口の減から農業・林業・漁業も衰退しているが、今のところ、サイズ、使い勝手の面で「軽」は、必要とされている。 下記の記事は、軽自動車を「安い車」として使っているコンサルタント氏の意見。 軽自動車ところか日本の乗用車のブランド別で販売数1位のホンダN-BOXは、コンパクトカーと同等レベルの価格帯の安くない軽。 日本独自規格「軽自動車」はガラパゴスのままで良いのか…世界で戦える"日本の超小型車"という生き残り策2023年4月30日 プレジデントオンライン 軽自動車の値上がりが続いている。小型車との比較で価格面、税制面の優位性がなくなりつつあり、このままいけば日本独自規格の「軽」は廃れゆく運命なのか。自動車業界に詳しいマーケティング/ブランディングコンサルタントの山崎明氏は「サイズや排気量で規定するのではなく、燃費で規定するように変えれば、軽をはじめとする“超小型車”にまったくちがう未来の可能性が生まれる」という──。■15年前の軽自動車を乗り換えるには何がベストか わが家には妻がメインに使っている軽自動車が1台ある。2008年式の三菱アイで、三菱がダイムラー傘下の時代に開発されたからか、リアにエンジンを搭載するというスマートと同じユニークなレイアウトを採用しており、デザインも欧州車に通じる雰囲気があって非常に気に入っている。 すでに15年が経過しており、あちこちに劣化を感じるようになってきた。私も妻もほかにデザイン的に納得できる軽自動車がなく、今まで使い続けてきたわけだが、しかし15年となるとそろそろ買い換えを検討しなければならない。そこで候補車を考えることにした。 … (略) … ■想像以上の満足感 ところが、青山一丁目のホンダ本社でN-ONEを借りて乗り出した瞬間、衝撃を受けることになる。なんとも素晴らしい乗り味なのである。 まず発進加速がスムーズでパワーも十分、音もさほどうるさくなく、軽に乗っているという感覚が希薄なのだ。この感覚は、電気自動車の日産サクラにちょっと通じるものがある。もちろんサクラのほうがさらに加速が良く(電気自動車は発進加速が得意なのである)、静かではあるのだが。 CVT特有の癖はあるものの、今まで乗った軽のCVTの中では最良に感じられ、これなら十分我慢できる仕上がりである。 N-ONEの美点はそれだけでなく、乗り心地も良いのである。RSというスポーティグレードにもかかわらず直接的な突き上げがほとんどなく、非常に快適だ。 室内も十分に広く、車高もそれほど高くないのでコーナリングも軽自動車としては安定感があり、全体的に非常に満足できる車だった。■しかし、「軽」にしては高すぎないか… ではN-ONEに買い換えるのか……というと、ちょっと躊躇(ちゅうちょ)する要素がある。それは価格だ。 N-ONEのターボ車を買おうとするとプレミアムツアラーかRSということになるが、安いほうのプレミアムツアラーでも188万9800円もするのだ。ナビやETCなどを付けると、総額で220万円ほどになる。 現在、軽自動車はどれもかなり高価になっていて、N-ONEだけが突出して高いわけではない。NAモデルでも150万円程度が当たり前になっており、ターボモデルでは170万~200万円となる。 ここで1つ疑問が生じてしまう。200万円も出すのなら、ほかにも選択肢があるのではないかと。 ■小型車のハイブリッドと重なってくる価格帯 たとえば同じホンダでも、フィットという小型車がある。フィットは159万2800円から買うことができ、e:HEV(ハイブリッド)でも199万7600円で買えるのである。 ハイブリッドなら123馬力の電動モーターを装備しているので、軽ターボの64馬力とは走りのゆとりがまったく異なる。また燃費も、N-ONEターボの21.8km/L(WLTCモード、以下同)に対し、フィットe:HEVは30.2km/Lと圧倒的に良い。 システム出力116馬力のトヨタ・ヤリス・ハイブリッドも201万3000円から購入でき、燃費はなんと36.0km/Lである。 ■維持費を考えても小型車ハイブリッドに軍配 軽自動車のベネフィットは維持費の安さである。 … (略) …■軽自動車は日本だけの独自規格 ではなぜ軽自動車はこんなに高いのか。 ハイブリッド車はより大きな車体により大きなエンジンを備え、モーター・バッテリーも備えているのに200万円程度で売ることができるのに、軽ターボ車は200万円近くしてしまう。その主たる理由は、「軽自動車」という規格そのものにあると思われる。 日本人にとって軽自動車というのは当たり前の存在であるため、海外にあまり行ったことのない人が海外に行くと、「海外では軽はあまり走ってないですね」などという感想を聞くことがある。そもそも軽自動車というのは日本独自の規格であり、海外で採用している国は1つもない。 軽自動車は終戦直後の通産省による「国民車構想」からスタートし、1949年に成立した規格で、本格的に販売が始まったのは1955年発売のスズライト(スズキ自動車)からである。 … (略) … ■インド進出時は「パワー不足」でNG 軽自動車が安くならないのは、日本独自の規格のため海外での競争力がまったくないからである。 軽自動車の規格は徐々に大きくなっていて、現在では排気量660cc、全幅1480mm以下、全長3400mm以下、全高2000mm以下となっている。多くの軽自動車が前後左右に“見えない壁”で押しつぶされたようなデザインになっているのはこの規格のせいである。 このサイズは、世界的に見るとあまりに特殊で、とくに排気量が小さすぎ、横幅も狭すぎる。 スズキが1981年にインドに進出したとき、最初に作り始めた車種はアルトだったが、エンジンは800ccに拡大していた。当時高速道路が存在しなかったインドの交通環境でも、550cc(当時の軽規格)では「パワー不足」と判断されたからである。 全幅の狭さは狭い道路では有効だが、速度が増すと視覚的にも運転感覚的にも不安定感が出てしまう。また、必然的にドアが薄くなり、側面衝突時の不安を感じさせる。インドで売られている最新のワゴンRは日本で売られているものとはまったく異なり、全幅は1620mmと軽規格より140mm幅広い。 ■「日本市場限定」が軽自動車の成長阻害要因 このようなことから、日本の軽自動車は事実上「日本市場専用車」なのである。つまり日本で売られている台数がすべて。その割には車種が多いので1車種当たりの生産台数は限られる。 ― 引用終り ― 他メーカーと比較しても価格がホンダの軽をとりあげて「軽なのに高い」と論じるのは、世間をミスリードする。 軽の一つ上、コンパクトカーにおいては、5ナンバー、3ナンバーの大きな分かれ目が全幅。日本の道は狭いところがたくさんある。山道、あぜ道を走る車のことを考えないのは、多数派、都会人の横暴。 自動車関連諸税の高い日本で、「軽」は相変わらず庶民の味方であり、独自規格を続けた方がよい。もしかしたら税収をより多く欲しい財務省の敵かもしれない。
2023年05月16日
コメント(0)
-

「小さな書店」がブーム、儲かるカラクリを追う
駅周辺や商店街にあった雑誌販売を中心とした従来型の「街の書店」が急速に姿を消している。コンビニの雑誌取扱いが増えたことや、雑誌と書籍の売上比率が逆転したことが、経営に大きな打撃を与えたという。 アマゾンが発展する前から図書館が発達している米国では、独立系と呼ばれる小規模書店の数が毎年増加してきた。それらの書店は書店員たちが独自の品ぞろえをし、カフェを備え、地域向けイベントに力を入れるなど、ネットでは味わえない人々とのつながり、体験を大切にしているとされる。 日本でも下記の記事で、このような傾向が示されている。情報の取得についての紙媒体の比率が低下する中、「紙の本」「本屋」好きの人々による様々の試みが続けられることだろう。 書店の閉店ラッシュの中で“小さな書店”がブーム棚貸しビジネスで「本屋のアンテナショップ化」「仕入れルートの多様化」で書店開業の障壁が低くなった週刊女性PRIME 2023年4月1日 日本全国で書店の閉店が止まらない。出版科学研究所によると2000年と2022年の書店の店舗数を比較すると約半分に減っている。そんな中、小さいながらも品ぞろえを充実させ、独自の魅力を放つ「小さな書店」が増え始めている。本は利益率が低い商品。どう利益を生み出しているのだろうか? 「小さな書店」の利益構造を探った。 書店閉店のニュースが絶えない。書店調査会社のアルメディアによると、2000年には2万1495店あった書店が、2020年には約半数の1万1024店まで激減している。 “小さな書店”の開業数は近年増加中 今年1月31日に『MARUZEN&ジュンク堂書店渋谷店』が12年の歴史に幕を下ろすなど、近年は都心の大型書店の閉店も目立つ。 「たしかに全体の書店数自体は減少していますが、その一方で、いわゆる独立書店と呼ばれる、小規模ながらも独自の個性を発揮して店づくりを行う“小さな書店”の開業数は近年増加しつつあります。私が知る限りの開業数だけでも、2015年には6店だったのが、2021年には79店の書店がオープン。2022年は50店と、勢いが少し落ち着いてはいますが、全国で小さな書店が相次いで生まれているという実感があります」 そう教えてくれたのは、本屋ライターの和氣正幸さん。各地の書店について取材執筆を続けながら、自身も『BOOKSHOP TRAVELLER』という書店を経営している。では、近年新しく生まれた小さな書店にはどういった特徴があるのだろうか。「新刊書店もあれば、古本を扱う書店、ジャンルやテーマを絞って取り扱う書店、イベントスペースを設けてサロン活動をする書店など、そのスタイルは実に多様。独立書店の厳密な定義づけは難しいものの、従来の枠にとらわれず、新しい発想で自由に経営している書店と考えればわかりやすいかもしれませんね。既存の大型書店やチェーン書店とは異なる魅力と個性で、厳しい環境下でも本に携わっていきたいという“意志のある書店”ともいえると思います」(和氣さん、以下同) 一般的に厳しいといわれる書店経営。理由のひとつとして、本や雑誌の利益率の低さが挙げられる。書店は取次と呼ばれる卸業者を介して出版社から商品を仕入れるのが基本的なルートだ。売り上げの約8割を出版社や取次会社に支払うため、書店の粗利益は2割から3割程度と小売業のなかでもとりわけ低い。「いわゆる薄利多売を試みようとしても、現在では本や雑誌はそう多くの数が捌けるような商品ではありません。小さな書店が少ない粗利から家賃や人件費を捻出したうえでしっかり黒字で収めるのは、実際のところ厳しいという構造的な難しさはありますね」 本をただ売るだけでは、なかなか儲けが上がらないというジレンマを抱えている書店業界。大型書店も例外ではなく、店頭での書籍雑誌の売り上げ以外のところで収益源を持っている場合がほとんどだ。 近年開業が相次いでいる“小さな書店”も同様で、本の売り上げにプラスして、例えばカフェを併設したり、本以外の雑貨を取り扱ったり、さまざまな試行錯誤によって経営を続けている。サービスの増加で書店開業の障壁は低くなっている 和氣さんの『BOOKSHOP TRAVELLER』も、「棚貸し」という珍しい形態の書店。作家やクリエイター、個人の無店舗本屋や出版社などに棚の一区画を貸し出し、店内では各出店者がセレクトした書籍を自由に手に取ることができる。いわば、棚単位で小さな本屋が集まった複合書店だ。「棚貸しというビジネスモデルは、店舗の棚を月額でレンタルすることで固定収入を得られるという仕組みで、2017年に開店した『みつばち古書部』(大阪市阿倍野区)がこのスタイルの源流になると思います。私の店ではシェアしている棚以外のスペースでは、自分でセレクトして仕入れた新刊を売っているので、小売業としての面ももちろんありますが、たくさんの方と棚を通して緩くつながっていくコミュニティー運営の側面が強い、業態でもありますね」 … 略) … 小さな書店の開業が増えた背景には、仕入れルートの多様化という変化もある。そもそも新規書店が大手取次に口座を開く場合、「信任金」という初期費用がかかる場合がほとんどで、それが個人書店の開業の足かせとなることも多かった。 しかし近年は、楽天ブックスネットワーク株式会社が提供する書籍少額取引サービス『Foyer(ホワイエ)』や、書店と出版社の現場をつなぐ取引プラットフォーム『一冊!取引所』といったサービスも誕生し、書店開業の障壁はさらに低くなっている。『一冊!取引所』を運営する、株式会社一冊の渡辺佑一さんは次のように話す。 「現在、日本には2900社ほどの出版社があるといわれていて、近年は“ひとり出版社”も生まれています。さらに数多く存在する書店と各出版社が取引を行う際の手間は双方にとって膨大なものとなっている状況があり、オンラインでさまざまなやりとりを簡単に完結できるサービスが必要だという思いから『一冊!取引所』を立ち上げました。同システムを使っていただくと、書店が仕入れたい本を、出版社によっては1冊単位で直接取引することも可能になります」 … (略) … 本の仕入れ方法や事業計画などのノウハウが世に広く開示された そもそも、本の仕入れの仕組みは、数年前までは部外者からするとブラックボックスだったと和氣さんは語る。 「新刊書店『Title』(東京都杉並区)の店主である辻山良雄さんが出版した『本屋、はじめました 新刊書店Title開業の記録』(苦楽堂、後にちくま文庫)や、ビールが飲める書店『B&B』(東京都世田谷区)のオーナー・内沼晋太郎さんの著書『これからの本屋読本』(NHK出版)が発売されたことが、新規書店の開業ラッシュに大きな影響を与えています。本の仕入れ方法や事業計画などのノウハウが世に広く開示されたことで“やってみたい”と背中を押された人も多いのではないでしょうか」 … (略) … 「書店経営といっても、もちろん金銭だけではない部分でやりがいや人とのつながりを重視して続ける方もいます。そういった情熱を持った方が出版業界や書店業界を支えているのもまた事実です。ぜひ身近にある“小さな書店”を訪れて、できれば本を一冊でも購入していただけるとうれしいですね」(和氣さん) ― 引用終り ―
2023年05月15日
コメント(0)
-

物流危機「2024年問題」…ラストワンマイルだけでなく国内の陸送全般の問題
物流業界の危機「2024年問題」が話題になっている。コロナ禍でものが作れないことが話題となってきたが、ものがあっても容易に届かない時代が目前に迫っている。 主に自動車を使用しての安価な宅配の進展、コンビニエンスストアの少量多頻度配送の確立、そして通信倍の普及拡大などで、人々は便利な生活を実現してきた。 少子化、高齢化、運転免許制度の細分化に加えて、2024年から働き改革による運転手不足が予定されている。コロナ禍で発展した通信販売などの影響で実売店でも、店舗側の配送料無料・即日配送なども重なり、定時、定点に荷物が届かない…という事態が予測されている。 誰か(消費者)の便利は、誰か(物流関係者)の努力に大きく支えられていた。 物流危機「2024年問題」の元凶は過剰サービス。送料無料・即日配送で疲弊する運転手たち=原彰宏2023年4月27日 MONEY VOICE 物流の「2024年問題」 働き方改革を目的とした改正労働基準法の施行により、2024年4月からトラック運転手の時間外労働に年960時間の上限が課され、年間拘束時間は現行の3,516時間から原則3,300時間へと厳格化されことになりました。それにより、運転手の労働環境改善が期待される一方で、1人の運転手が1日で運べる荷物量が減るため、人手不足が深刻化して物流が滞るリスクが指摘されています。 人件費増加で中小事業者の利益が圧迫される懸念もあり、輸送効率向上や運賃へのコスト転嫁などが課題となっています。 物流業界では、慢性化している運転手不足がさらに深刻となり、各地で荷物が運べなくなる事態が懸念されています。 野村総合研究所は、この問題により2030年に予想される国内の荷物量のうち35%が運べなくなる可能性があると試算しています。 ラストワンマイル……物流におけるラストワンマイルとは、最終拠点からエンドユーザーへの物流サービスのことを表現したもので、「最後の1マイル」という距離的な意味だけではありません。 お客様へ商品を届ける物流の「最後の区間」のことを「ラストワンマイル」と表現しています。 EC(ネット通販)の普及で、人々の買い物スタイルが、お店に足を運ぶのではなく、PC画面上でマウスをクリックすることで買い物を楽しむスタイルに変わってきています。 人々の買い物のあり方が大きく変わるなかで、物流市場への参入事業者が年々増加していて、他社との差別化を図るために「送料無料」「当日配送」などに取り組む事業者が多く出てきました。 それまで拠点を集約し、配送の部分を宅配業者に委託する形で物流を構築していたものを、よりエンドユーザーに近い場所に配送拠点を設けることで、ラストワンマイルを縮めてサービス強化する動きが活発化してきました。 しかもドライバーの努力によるもので、価格転嫁ができないものです。まさに「サービス合戦」ですね。 全国対応、当日配送、翌日配送サービス…。 ところが、これらのサービスが、今後は継続できないかもしれないという「物流の危機」が訪れようとしています。 「宅配業者への配送料金が見合っていない」「年々増加し続ける宅配貨物の物量」「再配達による業務効率の低迷」など、ECの拡大によって宅配サービスの取扱量が急増しているなかでの、ラストワンマイルの物流サービスのあり方が考えられる時期にきているところに、この「物流の2024年問題」がのしかかってきているのです。 過剰サービスだった? 労働人口の減少や作業内容等の物流労働環境の問題により、物流の担い手が年々減っているなかで「働き方改革」が進められているのはよくわかります。・トラック運転手の時間外労働に「年960時間の上限」設定・年間拘束時間が、現行の3516時間から原則3300時間へと厳格化 これらを守るということは、1日に運べる量は減少し、即日配達とか翌日配達などの、今までのサービス提供が困難になると指摘されています。 たしかに、健康被害や過労死、人で確保にとっても悪いイメージとなる長時間労働の実態是正は重要です。過労が事故につながることもありますからね。 翌日配達だけでなく、即日配達は顧客にとって本当に必要なのかという「過剰サービス合戦」のあり方も見直すべき時なのかもしれません。 そういった今までの“あたりまえ”となった風潮の見直しも、場合によっては必要かもしれませんね。 ドライバーの収入減も問題に この残業制限などは、ドライバー側からは“収入が減る”ことを懸念する声も出ています。 … (略) … 業務が大変な割には儲けが少ないと、ドライバーの“成り手”が減っていきます。そうなると、ものが運べなくなるのです。 企業側も対策しているが… 人手不足対策として物流網維持のためには、 ・料金割増し ・運送頻度低下 ・輸送の効率化(ダブル連結トラック活用) ・トラック輸送から船や鉄道に転換 ・複数の会社での共同輸送など、様々なことが試みられています。 また、再配達の多さや荷受け・荷降ろし時の待ち時間の長さも長時間労働を招く要因となっています。 … (略) … ローソンは、これまで1日3回コンビニエンスストアへ配送を行なっていたチルド・定温商品について、2回に削減することで、コスト抑制とCO2排出量の削減を行なうとしています。 これも2024年4月に施行される働き方改革関連法に向けての取り組みになります。 元々コンビニエンスストアへの配送業務は長時間拘束になりやすい配送体制で、新しい基準を満たすために、現状の配送スケジュールを実現するには、配送車と配送ドライバーの追加が必要となり、年間約20億円のコスト増が見込まれるそうです。 このため、配送スケジュールを見直すことで、コストを抑えようとしているのです。 ― 引用終り ― 関連法制とインフラの整備が進まなければ、自動運転トラック、ドローン、宅配ロボットの普及は進まない。 物流の2024年問題は、2024年を過ぎても課題であり続けることだろう。少子高齢化は社会のあらゆるところに見直しを迫る。 物流について、コンビニは配送スケジュールだけでなく、人口減少地帯を中心に、営業時間の見直しを迫られることだろう。
2023年05月14日
コメント(0)
-

韓国の「好感度を持っていない」国のトップは中国
韓国・聯合ニュースによると、韓国で行われた世論調査で、回答者の9割以上が中国に好感を持っていないことが分かった。 「好感を持っていない」国で中国は91%、北朝鮮88%、日本37%、米国33%。 韓国の反日勢力の懸命のアピールにもかかわらず中国、北朝鮮の好感度は著しく低下している。反中国、反北朝鮮では金にならないので、盛り上がりに欠ける。今後も韓国の反日勢力は一層激しく反日アピールを繰り返す。 「親日か反日か」揺れる韓国尹大統領の関係改善路線に野党が猛反発大統領を「日本の手下」と罵り大衆扇動に血道をあげる李在明2023.4.6 JBpress … (略) …尹錫悦氏の支持率、下げ止まったか 同31日に公表された韓国ギャラップの世論調査によれば、尹錫悦大統領の支持率は昨年11月以来の最低値である30%にまで下落した。これは尹政権による元朝鮮半島出身労働者(元徴用工)問題に対する解決策の発表と日韓首脳会談の余波が続いているためという。また、福島第一原発の処理水の放出、福島産水産物の輸入論争も影響しているようである。 他方、リアルメーターが3日に発表した世論調査によれば、尹大統領の支持率は前週から0.7ポイント上昇した36.7ポイントとなり下げ止まりの兆候を示している。これは日韓の問題の論争に関し、大統領室と与党・国民の力が積極的に対応したことが効果をもたらしたとしている。 ― 引用終り ― 日本に対する好感度は63%であり、「親日か反日か」で韓国の世論は揺れていないようだ。政局だけが大きく揺れている図がみてとれる。 強硬で執拗な反日勢力は侮れないし、政権が代わっても軍部に反日分子がいるので、日本は引き続き日韓関係について油断してはならない。北朝鮮に対して「好感を持っていない」が88%もあることから、北朝鮮の手先となった者が世論を反日に動かそうとしている可能性も十分考えられる。北朝鮮の金王朝が存続する限り、韓国の反日に終わりはない。 韓国人の9割以上が中国に好感持たず日本に対しては…―韓国メディア2023年4月24日 Record China 韓国・聯合ニュースによると、韓国で行われた世論調査で、回答者の9割以上が中国に好感を持っていないことが分かった。 市民団体「正しい言論市民行動」が23日に発表した調査結果によると、各国に対する好感度を尋ねた質問では、中国に「好感を持っている」と答えた人はわずか9%にとどまり、「好感を持っていない」は91%に上った。 北朝鮮に対しては「好感を持っている」が12%、「好感を持っていない」が88%、米国に対しては「好感を持っている」が67%、「好感を持っていない」が33%、日本に対しては「好感を持っている」が63%、「好感を持っていない」が37%だった。 また、北朝鮮が安全保障上の「脅威である」と答えた人は83%で、中国が「脅威である」と答えた人も77%に上った。一方、日本については「脅威である」との回答が53%だったが、「助けになる」も37%だった。 このほか、回答者の82%が韓国社会の対立が深刻であると考えており、特に保守派と進歩派の対立が深刻だとの回答が83%、与野党の対立が深刻だとの回答が84%に上った。また、69%が「韓国社会は公平さを欠いている」と回答した。 ― 引用終り ―
2023年05月13日
コメント(0)
-

日本郵便の下請けたたき…コンプライアンス違反
日本郵政グループのコンプライアンス感覚のなさを示す記事があった。 拡大するゆうパックの配送は、主に外部の下請け業者が支えている。下請法関連の取引関係について、過去より下請け事業者側に改善されていることに気づかないブラックな経営陣のもと、安い料金をフックにゆうパックは拡大を続ける。 郵政民営化とは、法令を遵守しない民間企業を社会に放つことではなかったはずだ。 ゆうパック「下請けたたき」値上げ拒否の代償 社内調査で判明横領・窃盗など深刻な弊害も2023年4月24日 東洋経済オンライン 郵便局と下請け業者をめぐる、極めて残念な実態が明らかになった。日本郵便は4月14日、郵便物やゆうパックの配達、集荷などを委託する下請け業者の値上げ要請に対し、不適切な対応があったと発表した。 今年2月、経済産業省・中小企業庁は中小企業に対し、発注者側の企業が価格交渉や価格転嫁について適正に対応しているかを調査し、結果を発表した。148社の状況が示されたが、日本郵便は「コスト上昇分に対して価格転嫁がなされているか」という点で「むしろ減額された」との回答が多く、最低ランクの評価だった。 これに対し、日本郵政の増田寛也社長は「ここまで低レベルの得点ということは深刻な問題が内在しているのではないか。これから突き止めていかなければならない」と語っていた。 そこで、日本郵便は全国に1001ある集配郵便局と13支社で、配達・集荷などの委託契約に関する自主調査を実施したという経緯だ。 原因は「認識不足」だが 調査の対象は2021年6月から2022年5月までの取引。下請けからのコスト上昇を理由とした委託料の引き上げ要請に対し、協議せずに据え置く、または据え置いた際に理由を文書やメールで回答しなかった例が139局、2支社でみられた。全体の約13.9%にあたる。 2022年7月に改正された下請中小企業振興法の振興基準では、価格交渉・価格転嫁について年1回以上の協議を行うことや、下請けから労務費やエネルギー価格が上昇したとの申し出があった場合に、遅滞なく協議を行うといった基準がある。 日本郵便は本社でこうした基準を認識できていなかった。「恥ずかしながら、振興基準の内容について改正があることも把握していなかった。認識が遅れてしまった」(担当者)という。そのため各郵便局や支社へ浸透させることもできなかった。 また、これまで各郵便局が下請けから要望を受けた際に、どう記録し、どのタイミングで支社に報告するか、本社と連携するかなど、手続きを明確化できていなかった。今後は書類ベースでの管理を見直し、電子化するなどで手続きの漏れを防ぐ構えだ。 現在は約5500件すべての委託契約について見直し協議を進めており、4月10日時点で2割弱が完了した。物価上昇もあるため、すべての契約の委託料を引き上げる方針だ。この原資については「会社全体の予算から生み出して実施する」など明確な説明はなかった。 日本郵便は今秋、燃料高騰や人件費上昇などを織り込み、ゆうパックの料金を値上げする予定だ。今回の全面的な契約見直しとは関係ないとしているが、一段のコスト増となれば手当ては必須。秋以降に再度の値上げに踏み切る可能性もありそうだ。 契約外の作業を押し付ける 今回公表した事例には、単に認識不足が原因とは考えられない例もあった。毎年秋ごろ、営業用のタオルを郵便局から業者に無償で配達させていたというものだ。 1つの郵便局で発覚したものだが、契約にない作業を無償で押し付ける行為は単なる下請けいじめだ。「あってはならないこと。詳細を確認し、業者にお金を支払うことを最優先で進めている」(担当者)。この件についての処分はなされていない。事実関係を確認した上で対応するという。 下請けに対して厳しい取引を持ちかけるのは、物流業界の根深い問題と言える。2022年に公正取引委員会が物流業界を対象に行った調査(3万社の荷主と4万社の物流事業者が対象)で、運送会社からもっとも多く寄せられた回答は「買いたたき」。それに「不当な利益提供の要請」が続いた。 日本郵便も荷主企業からこうした取引を持ちかけられたら苦しいはずだ。郵便物やゆうパックの配達は、下請けの協力なくして成り立たない。委託先との関係は根本から見直す必要がある。 実際、買いたたきの弊害も散見されている。近年の郵便局の不祥事では社員に加えて、下請け会社社員によるゆうパックや代金の横領・窃取の事件も多く発生している。郵便局の集配人からは「業務を放棄するなど、質の悪い業者が多い」との声もある。 一方で、下請け運送会社の幹部からは「委託料が安いのに1人当たりが運ぶ荷物量は多い。もう2度とやりたくない」という声もあった。 ― 引用終り ― 一時の利を追い求めて悪、負のサイクルを続ける日本郵政グループが、順法企業となるためには、役員とマネジメント層の頭の中と胸の内を改めないことには、変わらないと見た。 悪貨は良貨を駆逐する(トーマス・グレシャム) 郵政民営以下
2023年05月12日
コメント(0)
-

世界経済 3つの大事件 ヤバい日本経済
世界経済の3つのヤバいできごと。 その① アメリカのファースト・リパブリック・バンクが5月1日に破綻した(日時はことわりのあるものを除き現地時間)。「しかし、JPモルガン・チェースが買収した。金融システムは大丈夫だし、金融市場もこれで落ち着く」という有識者のコメント。 その② 5月3日にFED(アメリカの中央銀行)が、0.25%の利上げを発表、「今後の利上げに対しては中立的」というメッセージを出した。だが、株式市場や債券市場関係者の多くは、それでも「今後は年内に利下げに転じるはずだ」と解釈している。 その③ 日本銀行の植田新総裁という人物および、彼の初の金融政策決定会合後の記者会見を、世間が現状であまりに礼賛している。 3つの「世界同時多発『ヤバい』」が起きている 実はアメリカよりも日本のほうがもっと深刻だ2023年5月6日 東洋経済オンライン 今、世界では3つの「同時多発『ヤバい』」が起きている。 「3つの事件」の影響は深刻だ ヤバいその①:アメリカのファースト・リパブリック・バンクが5月1日に破綻した(日時はことわりのあるものを除き現地時間)。「しかし、JPモルガン・チェースが買収した。金融システムは大丈夫だし、金融市場もこれで落ち着く」という有識者のコメントが「ヤバい」。 これはまったくの間違いだ。これからアメリカ、そして世界の金融市場は静かにどんどん悪くなる。 ヤバいその②:5月3日にFED(アメリカの中央銀行)が、0.25%の利上げを発表、「今後の利上げに対しては中立的」というメッセージを出した。だが、株式市場や債券市場関係者の多くは、それでも「今後は年内に利下げに転じるはずだ」と解釈している。これもまったくの間違いだ。 つねに願望で動く株式市場が、わざと誤解して盛り上がっているのはいつもどおりだが、合理的で理論派のはずの債券市場も、理屈でなく願望で動いており、利下げ願望を織り込んでいる。債券市場の投資家まで願望で動いているのは相当ヤバい。株式・債券の暴落は今後何度でも起きる。 ヤバいその③:日本銀行の植田和男新総裁がすばらしい人物であることは私も知っている。だが、植田新総裁という人物および、彼の初の金融政策決定会合後の記者会見を、世間が現状であまりに礼賛しているのがヤバい。 彼がどんなにすばらしい人格者だとしても、どんなに優秀でも、それと無関係に、日本経済も日本金融市場も国債市場もすでに事実として追い込まれており、身動きできない。「ソフトランディング」はできない。その事実からほとんど目をそらしているに等しい日本社会、日本の論壇がヤバい。 今挙げたように、この1週間前後のうちに、ほぼ同時に起きた「3つの事件」の影響は深刻で根深い。なぜなら、こんなにも重要な3つの問題が同時に噴出したのに、投資家たちは、目をつぶるばかりか、正反対の楽観的な方向に解釈して逃げ切ろうとしているからだ。 そして実際、市場はこの楽観的な願望解釈をもとに動き始めたからだ。これらの問題はどうやっても解決することはできず、ダメージを甘受するしかないという意味で深刻である。 ― 引用終り ― 記事の筆者は「世界の金融市場がヤバい。しかし、どんな手を打っても完全に「詰んでしまった」というのに近い日本が、いちばんヤバいのだ」と記事を結んでいる。日本経済の論壇は以前から十分にヤバいが、日銀総裁の評価を誤っていることぐらいで、そんなにヤバいことになるとは思えない。世界中で巨額のつけ(負債、債権)を積み増している中国は、本当にヤバそうに見える。プーチンのロシアがばらばらに解体されても、世界経済は破滅的な打撃を受けないと思われる。 トマ・ピケティは『21世紀の資本』で資本主義が詰んでいることを世界に示した。勘違いのせいで、日本の金融市場が詰んだ後の世界、経済社会の先陣を切るということだろうか。 マネー、投資資金をワイワイ騒いで無理やり上げ下げしているバブル経済がいつまでも続くはずがないわけだが、終わりの兆しを見た、口火を切るのは日本、巨額の債務を抱える日本政府ということか。 「過去の事例とは違うから今回は問題ない、問題は大きくならない」「市場はよい方向に向かい回復する」などの一連の発言に疑問を唱えて、警鐘を鳴らす記事であることは分かる。 日本政府と日銀は、日本経済がヤバい状態を続けていることは先刻承知しており、自分たちが、延命策を続けていることも自覚している。エリート、支配層が、衆愚に知らせないだけのことだ。
2023年05月11日
コメント(0)
-

合体再編 東海キヨスクとェイアール東海パッセンジャーズが10月に合併
進化し、売上・利用者が増加している都市部のエキナカの売店だが、利用者のニーズを受けることを含め、さらなる変身が必要とされているようだ。 JR東海は、駅構内に小売店舗を運営する東海キヨスクとジェイアール東海パッセンジャーズ(JRCP)を2023年10月1日付で合併し、「株式会社JR東海リテイリング・プラス」で、駅構内における店舗の役割の見直し、統廃合・再配置などを進める。 エキナカの買物をワンストップでキヨスクとJRCPが10月合併JR東海、流通事業を再編食品新聞 / 2023年5月1日 16時24分 JR東海はグループの流通事業を再編する。駅構内を中心に小売店舗を運営する東海キヨスクとジェイアール東海パッセンジャーズ(JRCP)を今年10月1日付で合併、「株式会社JR東海リテイリング・プラス」として新体制を敷く。存続会社は東海キヨスクで、JRCPを吸収合併する。資本金7億円。売上高は単純合算で835億円(東海キヨスク532億円、JRCP303億円、ともに22年度見込み)。 JR東海リテイリング・プラスは両社の事業を継承し、①売店・コンビニ・土産店・弁当店などの「駅構内小売事業」②カフェなどへのチェーン加盟による「フランチャイズ(FC)事業」③「新幹線車内販売事業(パーサー業務含)」④「駅弁製造事業」の4事業を運営する。 これまでキヨスクは土産品を中心に、JRCPは弁当を中心に扱っていたが、合併により駅構内店舗の集約・大型化を進め、駅利用客が土産品・弁当・飲料などをワンストップで購入できる環境を整える。 ― 引用終り ― 近鉄が導入しているファミリーマートなど、コンビニエンスストアにエキナカを譲る気はない、ということのようだ。JR東海は成立ち、環境は異なりながらも東日本が辿った道を想定しているのだろう。 JR東日本は、2001年から Suica が利用可能なエキナカのコンビニエンスストアとして、JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営する「NewDays」を出店している。 2015年3月14日より、キオスクの一部店舗が順次新業態『NewDays KIOSK』に転換されている。
2023年05月10日
コメント(0)
-

就職氷河期世代は老後も氷河期?
公的年金制度の破綻、公的年金の額の低さを悲観、嘆き声をきくが、国民年金の話か、厚生年金の話か分からない。公務員に給付される共済年金の話はでてこない。老後の不安を煽るための「年金不安」「年金不満」の記事は気を付けてみる必要がある。 月収15万円・48歳の独身男性「ご馳走はチキンラーメン(具なし)」の絶望感…ロスジェネ世代「良いことなんて一度もなかったよ。」幻冬舎ゴールドオンライン 2023年4月22日 11時30分 … (略) … わずか、非正規社員平均の6割程度の給与…衝撃の年金額 厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査』によると、大卒・男性・正社員(雇用期間の定めなし、平均年齢42.1歳)の平均月収は40.1万円。賞与も含めた年収は平均661万円です。 それに対して、大卒・男性・非正規社員(雇用期間定めなし、平均年齢51.3歳)の月収は26.3万円。年収は平均372万円。正社員と非正規社員、年収で1.7倍の差が生じています。 前出の男性と同様、40代後半で比較してみると、正社員は月収50.7万円、かたや非正規社員だと24.3万円。ダブルスコア以上の給与格差が生じます。さらに前出の男性は月収15万円だといいますから、平均値の6割程度という低賃金に甘んじています。 大学卒業以来、非正規社員の6割という給与で65歳まで働き続けるとすると、生涯賃金は9,316万円と1億円に届きません。また65歳から手にする厚生年金は単純計算、月4万1,000円程度。国民年金を満額もらえるとすると、月10万5,000円。現役を引退して年金だけで暮らしていく、と宣言するには心許ない金額でしょう。 現在、厚生年金に加入できるのは70歳まで。そこまで保険料を払い年金を増やそうとしたら、厚生年金は月4万6,000円程度と、5,000円ほど増加します。焼け石に水、といったレベルでしょうか。 ただ年金支給年齢を繰り下げる「年金の繰下げ受給」で、75歳まで年金の受取りを待ったとしたら、年金は65歳での支給額よりも84%アップ。老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて増額され、その増額は生涯続きます。そうなると75歳で手にする年金額は月19.3万円。48歳時点の月収を大きく超え、やりくりの仕方によっては「年金だけ」でも暮らすことができそうです。 不遇の世代といわれ、卒業以来、「良いことなんてなかったよ……」が口癖の就職氷河期世代。非正規社員としてでも75歳まで年金を受け取らずに働いた先には、少しは報われる未来が待っている……それが幸せなことだと錯覚してしまうほど、現在の絶望感はかなりのものです。 ― 引用終り ― 上記の記事は、過去どれぐらいの期間厚生年金に加入していたか分からないフリーターの話から、厚生年金に話をつなげている。 また厚生年金は現役時代の給料の多寡が反映されるので、低賃金で長く働いた場合、年金の受給額は低い。10年間加入すると厚生年金の受給資格が発生するが、非正規で職を転々とした場合、10年加入すること自体がハードルとなる。 老後の厳しさを示すために、厚生年金と生活保護の金額より少ない国民年金だけの平均月額の比較をするなら分かる。 手に職ということで、寿司職人、和食・フレンチなどの調理人になった人々も、会社組織の従業員として厚生年金の対象とならないと、国民年金だけなら老後生活は厳しい。日本の「食」の低価格化によりプロの調理人の活躍の場は、著しく減少している。 日本の中小企業経営者の間で、経営が苦しくなったら真っ先に払わないくてよいものとして「厚生年金保険料」という情報が行き渡ってきた。厚生年金保険料が給料から天引きされていても、納付されているとは限らない。年金定期便はしっかりと点検した方がよい。 いずれにしろ就職氷河期世代で低賃金の仕事を転々とした場合、老後も氷河期が続くことは確実。そのような日本社会の仕組みだからだ。
2023年05月09日
コメント(2)
-

アベノミクスの成果 タイ、ベトナムより安い日本のリアル
労働基準法や公的社会保険が例外扱いしてきた正規外従業員は、安倍政権で例外ではなくなり、労働者の賃金水準は低くなった。眩学者竹中平蔵氏が唱えた、富が富裕層から低所得層に徐々に滴り落ちるとするトリクルダウン理論は実現せず、国内の貧富の差は拡大、貧困層が増大した。 生計の再生産費用に満たない賃金が当たり前となり、文教予算を減らしたお陰で子育て費用の負担は一段と重くなり少子化を加速した。人口減となり、安倍政権が描いた、女性、高齢者も働く「1億総活躍社会」は速やかに実現した。実現したとたんに人口減で「1億」の総人口は、崩壊することが明確に見て取れるようになった。GDPが拡大しないことがはっきりしたので、国内市場は将来性が一段と乏しくなった。 イノベーションに長けた企業は海外で稼ぎ、内部留保は増大したが、投資は稼げる海外で行われた。生計の再生産費用の安い日本では、従業員の給料も上げる必然性に乏しかった。需要の伸びない国内の賃金や物価は長く上がらず、企業はコスト削減として付加価値を削ってでも売価を低位に維持した。世界中で金利が上昇する中、金融緩和を続けたことによる円安も重なって、日本は世界の中で一層安くなった。 多くの社会主義国家のように、物価が安くて平和な日常のようであるが、その安さが資本主義・日本の重大な課題となりつつある。日本は工業社会の世界の中で、資源に乏しい加工貿易国であり、鎖国するわけにもいかないので、国内の物価安を基盤とした経済社会の組立は、不動産、株式などの資本が安い、海外から買われる国、草刈り場と化している。防衛費の比率を増やしたアベノミクス・安倍政権であるが、経済的には安い日本を実現し売国に結びついていた。 少子化で国民が減り、資本が海外に移転しつつある日本で軍備を増強し、自公連立政権は何から守ろうとしているのか不明。売り物の美しい国・日本を高い兵器類で守っているのだろうか?冊封国家として、宗主国である米国の安全保障を支援しているのだろうか? 日本の部長は「タイより年収が低い」の衝撃的事実 「安いニッポン」は現実になっている東洋経済オンライン / 2023年4月29日 19時0分 「日本企業の部長クラスの年収は、タイよりも低い」 経済産業省が2022年5月に発表した「未来人材ビジョン」という報告書が衝撃的な事実を明らかにし、各メディアを賑わせました。日本は「アメリカや中国に負けている」などというレベルではなく、これまで後ろを走る国だと思っていた「東南アジアにも負けている」――元・LinkedIn日本代表の村上 臣氏はそう言います。同氏の新刊『稼ぎ方2.0』から一部抜粋、編集してお届けします。 安いニッポン 元・LinkedIn日本代表として、キャリアに関する発信を続けている私は、「今こそ、誰もが会社の外にもキャリアを持つ必要がある」と訴えています。 なぜ今、会社の外にもキャリアを持たなければならないのか。ひとつの根本的な理由は、「1社で働いているだけでは給料が増えないから」です。 日本の平均給与(実質)の推移を見ていくと、1992年に472.5万円のピークを迎え、以降は徐々に下がっています。2009年にはリーマンショックの影響で421.1万円まで下がり、そこから少し持ち直してはいますが、2018年時点で433.3万円。ピーク時から40万円近く下がっています。 「失われた30年」という言葉があるように、日本はバブル崩壊後、現在に至るまで長期的な経済低迷を続けています。日経平均株価は1989年に3万8915円の史上最高値をつけてから、一度も高値を更新していません。 もちろん国もこの状況を黙って見過ごしているわけではなく、「生産性を向上させよう」「イノベーションが経済成長のカギ」みたいなことを主張してはいます。 けれども、実際には景気回復に向けた展望は見えていません。このまま失われた40年、50年が続く可能性も現実味を帯びています。 皆さんも薄々感じているとは思いますが、このまま給料は増えないと考えるのが現実的ではないでしょうか。 日本の平均年収は「シンガポール」「タイ」より低い? そもそも、どうして日本で働く人たちの給料がずっと上がらないのでしょうか。原因は諸説あり、簡単に説明することはできません。ただ、あえて主な原因を挙げるとすると、第一に日本の国際競争力の低下があります。 かつての日本企業はグローバルな競争で強さを発揮してきましたが、バブル崩壊以降は徐々に新興国に追いつかれる状況が目立つようになりました。GDPは2011年に中国に抜かれ、一人当たりGDPも韓国や台湾に追い抜かれようとしています。 今までは、グローバルで稼いだお金を給料として従業員に還元していたわけですが、国際競争力が低下した結果、それができなくなっているわけです。このまま国際競争力が低下すれば、給料が増えないどころか、減る危険性も考えられます。 そして、将来の日本を担う子どもたちを育成する「教育」の面でも、日本の国際競争力の低下は如実に表れています。イギリスの教育専門誌であるタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)が世界の大学の中から104の国と地域の1799校を独自の基準でランク付けした「世界大学ランキング」というものがあります。 この2023年版において、日本からランクインしたのは117校。その中で日本のトップは東京大学の39位。2021年版の36位、22年版の35位から順位を下げています。日本で2番目の京都大学は68位であり、200位以内に入っているのは、東大と京大の2校にとどまっています。 … (略) … そんな日本の国際競争力低下を反映し、今や日本人の給料よりも、タイやシンガポールといった東南アジアの国々の給料が高くなっているという話もあります。経済産業省によると、日本の大企業の部長職の平均年収は約1714万円。一見すると高そうに思えますが、アメリカ(約3399万円)、シンガポール(約3136万円)、タイ(約2053万円)と比べると、かなり低い水準です。 OECDが発表している平均賃金を見ても、日本は34カ国中24位と低迷しています。韓国(19位)には2013年に抜かれていますし、ここ数年ではスロベニア、リトアニアといった中東欧の国々にも抜かれている状況です。 ちなみに、このランキングは円安が加速する前の2021年時点の為替レートで計算されており、現在の為替水準に置き換えると、日本の低落傾向は決定的になると見られています。 実際に、日本の給料が一向に上がらないため、日本に出稼ぎに来ていた外国人が母国に戻ってしまう動きが出てきています。例えば、日本では近年ベトナム人労働者の数が急増してきましたが、もはや日本で働く金銭的なメリットは薄れつつあります。 日本とベトナムで大きな収入の差はなくなっている 経済発展が著しいホーチミンやハノイといった大都市では、日本とベトナムで大きな収入の差はなくなっています。しかも、ベトナムではこれから年10%くらい給料が上がっていくと見込まれています。あと10年もすれば両国の給料には決定的な差がつく可能性が大です。だったら、母国に帰って普通に働こうと考えるベトナム人が増えるのは当然の成り行きです。 海外からの出稼ぎが減少するのと対照的に、「安いニッポン」に見切りをつけて、海外に出稼ぎに行く人たちも出始めています。日本では低賃金で働いていた寿司職人や美容師などが、アメリカやシンガポール、オーストラリアなどに渡り、収入が数倍になったという話を頻繁に聞くようになっています。 特にワーキングホリデーの制度を利用できるオーストラリア、カナダといった国では、アルバイトをしながら旅行を楽しみ、なおかつ給料の半分くらいを貯金するような日本の若者がいます。 … (略) … これまでの日本では、手に職をつけるタイプの仕事をする人たちは、若い頃に下積みをコツコツとこなし、いずれ独立して自分の会社や店を持つというモチベーションを持っていました。 しかし、これからは専門学校で基礎的なスキルを身に付けたあと、すぐに海外を目指すという動きが加速するかもしれません。少なくとも、今、一流の寿司職人はこぞってニューヨークを目指しています。気がつけば、一線級の職人たちはみんな海外で働いているといった状況が現実のものになるかもしれないのです。 ― 引用終り ― スイスのビジネススクールIMDが発表する「世界競争力ランキング」で、日本は1989年から1992年まで4年間にわたり1位だった。その後、下落傾向が続き、2022年は3つ順位を下げ2020年と並び過去最低の34位となった。マレーシア、タイにも抜かれ、もはや日本は先進国ではない現実を見せつけた。
2023年05月08日
コメント(0)
-

英国王戴冠式費用の税金使用反対51% 英国王室財産 皇室の経済
英国王室は利益を生む莫大な資産を持っている。 日本の皇室は国の祭祀を担うが、英国王室は王室の都合、離婚問題が発端で英国教会を作った。 愛される存在であろうとする英国の王室は、英連邦の象徴として機能してきた……はずだった。 5月6日に行われる、不倫して再婚したチャールズ国王の戴冠式に税金を投入することに「反対多数」との世論調査の結果が報じられた。 国王戴冠式、税金投入に過半数が反対 英世論調査2023年4月19日 JIJI.com 英国民の51%が、来月6日に行われるチャールズ国王(King Charles III)の戴冠式に税金を投入すべきではないと考えていることが、18日公表の世論調査で分かった。 世論調査会社「ユーガブ(YouGov)」が成人4246人を対象に実施したもので、回答者の51%が、戴冠式の費用を政府が「負担すべきではない」と答えた。「負担すべきだ」との回答は32%、「分からない」が約18%だった。 年代別では、生活費高騰の影響を特に受けている若者に反対が多く、18~24歳の約62%が「負担すべきではない」と回答した。肯定派は15%にとどまった。一方、65歳以上では「負担すべきだ」が44%、「すべきではない」が43%と拮抗(きっこう)している。 政府は、戴冠式と関連イベントの経費をまだ明らかにしていない。大規模な警備費用などを含め、総額数千万ポンドに上るとみられている。 1953年のエリザベス女王(Queen Elizabeth II)の戴冠式の費用は、現在の価値で2050万ポンド(約34億円)。エリザベス女王の父、ジョージ6世(George VI)の戴冠式(1937年)には同2480万ポンド(約41億円)が費やされた。 ― 引用終り ― 英国の民主主義は根が深い。日ごろは平和主義の皇室を軽んじている右翼の諸氏なども不敬と唱え、日本ではこのようなアンケートを取ること自体が身の危険を招きそうだ。 米国育ちのメーガンは、英国王室が莫大な財産保有するのに、それらがちっとも自分の自由にならないことに不満を抱き、米国に戻ったのだろう。 英国王室は、あなたが考えているよりも多くの収入源を持っているロイヤルファミリーの生活を支えているのは王室助成金だけではないBy Amy Mackelden 2019/11/29 BAZAAR イギリスのロイヤルファミリーは、国民に多額の出費を強いていると考える人もいるかもしれないが、これは本当のところ事実ではない。 財政について論じるため、英国王室の公式ウェブサイトは「王室財政は、曖昧さと秘密主義で隠されることで、王政はときにお金のかかる制度だと述べられてきました。しかし、現実では王室は公金はできるだけ賢く、効果的に費やされるよう、そして王室財政をできる限り透明で理解されるようにすることを約束しています」と記している。 王室のメンバーたちは、様々な収入源から収入を得ている。そして毎年、その金額を公表しているのだ。そこで、エリザベス2世女王の主な収入源を分析すると同時に、キャサリン妃、ウィリアム王子、メーガン妃、ヘンリー王子が、公務のために受け取っているお金について分析してみよう。 王室助成金 英国王室最大の収入源は王室助成金だ。これは、女王の公務を支援するために政府によって支払われるもの。英国王室の公式ウェブサイトによると、助成金は実際にはクラウン・エステート(君主の公的な不動産にあたる)の収入から得られる利益の一部から来るものだそうだ。 クラウン・エステートは、イギリス国内における143億ポンド(約2兆226億円)もの大規模の不動産事業で、その収入利益は国庫へ、つまりは国民全体にもたらされる。女王は法律的にはクラウン・エステートを所有してはいるが、この機関は独立した委員会によって運営されている。政府は、クラウン・エステートの年間収益を参考にし、王室助成金としていくらを王室に与えるかを決定する。 クラウン・エステートの収益の大部分は、政府に直接流れるが、約15%が王室助成金となり、年間の支払金は、ロイヤルファミリーの公務、基本的な維持費、プレス対応、警備、そして数名の重要な王室メンバーの旅費として使用される。『The Express』紙によると、2018~2019年の支出は、およそ2千万ポンド(約27億1千万円)の増額が見込まれると報告。これは、バッキンガム宮殿の改装が延長されたためだそう。 女王の公的な住居の維持や年間を通じて訪問者を迎えるロイヤル・コレクション・トラストは、毎年多額のお金を生み出す。とはいえ、このトラストの収入の大部分は、(例えばウィンザー城や戴冠宝器などの)王権と関連する、価値の高い芸術品や不動産資産の手入れをするのに還元され、ロイヤルファミリー個人に利益をもたらすものではない。 王族公領 女王の収入のほとんどは、ランカスター公領からのもの。英国王室の公式ウェブサイトによると「13世紀に創設されたランカスター公領は、ランカスター公爵の名(訳注:現在の称号保有者はエリザベス女王)で、王室のためのトラストとして保有されている土地、不動産、資産の独特なポートフォリオ」とある。この領地の印象深い資産には「イギリスとウェールズにおける18,481ヘクタール(約185㎢)もの土地と、商業用、農業用、住居用の不動産で構成されています」とのこと。 一方で、チャールズ皇太子の収入のほとんどは、コーンウォール公領からのもの。皇太子のウェブサイトによると、ウィリアム王子とキャサリン妃、ヘンリー王子とメーガン妃は「公務活動には、コーンウォール公領からの収入を使用し、公務旅行や財産管理の補助には、女王の王室助成金の資金援助を受けます」とある。 TV番組『CNN Money』は、コーンウォール公爵夫妻(チャールズ皇太子とカミラ夫人)の収入の90%は、コーンウォール公領が生み出すと明かした。夫妻はこの公領から2,800万ドル(約30億6千万円)を得たと2018年に報じた。これには少々驚きであろう。 個人的な収入、投資、遺産 女王は、個人的な支出には、個人的な収入を使用する。それは「女王の個人的な投資ポートフォリオや私有地から派生するもの」だと公式ウェブサイトにある。女王はバルモラルやサンドリンガムを所有し、それらは、父親のジョージ6世国王から受け継いだものだ。 女王自身の投資や不動産から女王が得る収入は女王のもの、そして他のロイヤルファミリーメンバーにとってもそれは同じだ。『The Express』紙によると、女王は多くの貴重な資産を所有しているが、その詳細は公表されていない。 公的なロイヤルファミリーの住居、ロイヤル・コレクションの芸術品、そして戴冠宝器は、女王の私的財産ではない。これらは女王が君主である間、彼女の所有物となっているに過ぎない。女王はそれらを売却することはできず、それらはやがて彼女の後継者へと引き継がれる。 メーガン妃は、自身で築き上げた資産を持つことで知られている。それは、彼女がロイヤルファミリーに嫁ぐ前、女優、そしてインフルエンサーとして活躍していた時期に得たものだ。そして、ヘンリー王子とウィリアム王子ともに、亡くなった義母のダイアナ妃、そしてエリザベス王妃(クイーン・マザー)から受け継いだ資産を有する。 ― 引用終り ― 日本は、皇室に関わる莫大な国有資産があるが、皇族の自由になる財産は非常に限られており、贈与の限度額は日本国経済の拡大を反映しているとは思えない低い水準。 この水準をみて、国会で過半数の自公連立政権が贈与の限度額の改正を唱える声を聞かないし、ネトウヨの諸氏も騒いでるふしはない。 公務に割く時間は多く、金は自由にならない皇族の方々は、国と国民のためにその役割を務めているということらしい。 宮内庁公式サイト皇室の経済皇室財産・皇室の費用 すべて皇室財産は、国に帰属します。また、すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経る必要があります(憲法第88条)。予算に計上する皇室の費用には、内廷費・皇族費・宮廷費があります(皇室経済法第3条)。内廷費 天皇・上皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので、法律により定額が定められ、令和5年度は、3億2,400万円です。皇族費 皇族としての品位保持の資に充てるためのもので、各宮家の皇族に対し年額により支出されます。 皇族費の基礎となる定額は法律により定められ、令和5年度の皇族費の総額は、2億6,017万円です。 なお、皇族費には、皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります。宮廷費 儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費、皇室用財産の管理に必要な経費、皇居等の施設の整備に必要な経費などで、令和5年度は、61億2,386万円です。財産授受の制限 皇室の財産の授受については、次に掲げる金額の範囲内の場合や通常の私的経済行為等の場合を除き、国会の議決を経ることを要します(憲法第8条、皇室経済法第2条、皇室経済法施行法第2条)。 賜与の限度額(年度間) 譲受の限度額(年度間)天皇・内廷皇族 1,800万円 600万円宮家の皇族(成年) 各160万円 各160万円同(未成年) 各35万円 各35万円(参考)憲法第8条に基づき国会の議決を求めた事例皇太子明仁親王殿下のご結婚の際の議決(昭和34年3月13日議決)天皇陛下のご即位の際の議決(平成2年6月26日議決)皇太子徳仁親王殿下のご結婚の際の議決(平成5年4月28日議決)天皇陛下のご即位の際の議決(令和元年6月21日議決)天皇陛下のご即位の際の議決(令和2年3月31日議決)皇室財産の相続の特例 ― 引用終り ― 皇位継承式典関係費について、開かれた皇室とし透明性を高めたい勢力がいる一方、オリンピック開催と同様に、費用について闇から闇にとどめたい勢力もいる。DX推進を民間に訴える官庁がある一方で、許認可を含め、紙とハンコに留まろうとする官庁がある構図に似ている。理由は様々あるのだろうが、民主的な感じがしない。 皇位継承式典関係費133億円当初予算より支出27億円減18~20年度、概要など公表なく2021年7月15日 東京新聞 天皇陛下の皇位継承式典関係費として2018年度から20年度までに支出した公費は総額133億円で、当初の予算の160億円より27億円の減額となることが関係省庁への取材で分かった。内閣府の皇位継承式典事務局(今年3月廃止)は省庁別の予算概要を発表した一方、支出の公表は一部にとどまり、皇室制度に詳しい識者らは「公費の適正使用を国民が確認できるように支出の概要も政府が公表する必要があった」と指摘する。(阿部博行) 本紙の取材で分かった省庁別の支出(1000万円以上)をみると、内閣府は陛下が即位を宣言された「即位礼正殿の儀」の8億9000万円のほか「饗宴の儀」や「祝賀御列の儀」の実施経費など計24億9000万円だった。この中には「即位の礼実施本部」が皇居・宮殿に大型モニターを設置した経費など7億7000万円の運営費も含まれる。 当時の安倍晋三首相夫妻が主催し、外国元首らを都内のホテルに招いた晩さん会は2億1000万円かかり、予算を4000万円ほど超過した。招待者に古典芸能を紹介した文化事業や来場者の本人確認のため顔認証システムを導入した経費などが想定以上にかさんだ。 宮内庁は計34億2000万円を支出し、このうち皇室の最重要祭祀「大嘗祭」で使用した大嘗宮の造営関係費は12億5000万円かかった。当初は19億円と試算されたが、建設・造成工事の一般競争入札で予定価格より6億円安く落札され、総経費が抑制された。 外務省の支出は全省庁で最多の計43億円だったが、予算よりは約7億8000万円の減額となった。外国元首らのホテル代を含む滞在費が31億3000万円を超え、支出の7割を占めた。 警察庁は警備関係費として計28億5000万円を支出した。平成の式典時と違い過激派の活動が沈静化したことなどから、予算より約9億7000万円の減額。防衛省は要人輸送用ヘリコプターの整備費など計25000000円を支出した。 全体的な経費削減の要因は、業務内容の整理・簡素化と儀式装束などの再利用、各種工事・物品購入で行った一般競争入札の効果などが考えられるという。予算総額は前回の約124億円の3割増だったが、支出総額や内訳は「前回の関係資料が行政文書の保存期間(5年)を過ぎ、存在を確認できない」(各省庁の会計担当者ら)ため、前回との比較が難しい状況だ。 ― 引用終り ―
2023年05月07日
コメント(0)
-

金融危機……米国の大手銀行の破綻と資本主義の危機
ロシアに関する金融制裁、米国経済のインフレが話題になっている。経済界では大きな出来事が起こりニュースにもなっているが、大きな話題にはなっていないと感じる。 2023年3月10日、米国のシリコンバレーバンクが経営破綻した。総資産が2022年末の時点で、およそ2090億ドル、日本円でおよそ28兆円。 3月12日、米国のシグネチャーバンクが経営破綻した。総資産は2022年末の時点でおよそ1103億ドル、日本円でおよそ14兆7800億円。 米国の銀行の破綻として史上2番目と3番目の銀行破綻がわずか3日の間に起きたことなります。 3月16日 、全米14位、カリフォルニア州を地盤とする中堅銀行のファーストリパブリック銀行に米大手11行が経営支援のため計300億ドルの無保険の預金大手行が共同で資金支援。3月24日に発表した1~3月期決算で巨額の預金流出が明らかになった。3月28日、米ニューヨーク株式市場で同行の株価は一時、前日終値に比べ5割安の2ドル台に暴落、終値は同43.3%安の3.51ドルで破綻が懸念されている。 3月19日 経営危機のクレディ・スイスグループをUBSグループが30億フラン(4,260億円)買収すると発表。 4月24日、スイスの金融大手クレディ・スイスは、第1・四半期に610億スイスフラン(680億ドル)の資金が流出したと発表した。 4月1日、ファースト・リパブリック銀行が経営破綻。連邦預金保険公社(FDIC)は同行を管理下に置いた。ファースト・リパブリック銀行の全84店舗は1日午前から、JPモルガンの支店として営業する。 クレディS、第1四半期680億ドル資金流出UBS買収前に歯止め掛からず2023年4月24日 ロイター スイス金融大手クレディ・スイスは24日、UBSによる買収を控えて第1・四半期決算を発表、差し引き610億スイスフラン(680億ドル)の資産が流出したと明らかにした。 「現在は流出ペースが緩やかになっているものの、2023年4月24日時点でまだ反転していない」とした。 第1・四半期に預金は670億フラン減少した。 クレディ・スイスの旗艦ウェルスマネジメント部門が運用する資産は3月末時点で5025億フランと、前年同期の7070億フランから減少した。 UBSによる買収にあたり、スイス国立銀行(中央銀行)は、両行に2000億フランの流動性支援措置を策定した。 クレディ・スイスによると同措置を利用した純借入残高は第1・四半期末時点で1080億フラン。 またマイケル・クライン氏の投資銀行事業を1億7500万ドルで買収する契約は双方の合意に基づき解消したと明らかにした。 ― 引用終り ― 「6月金融危機」説なども流れているが、世界的な金融危機の再来は、今のところないとされている。
2023年05月06日
コメント(0)
-

子どもが足りない、人口減社会の近未来と現在
金融緩和を続けても内需が拡大しない国内向けの投資は増えない。 海外で利益を上げている企業は、収益の拡大を予想できる海外に投資する。 国内でジリ貧となっている企業に、設備や人材に投資する余力はないとなっている。 韓国も中国も、若い労働人口を構成する子どもの数が相対的に少ない。 世界の工場役が交代し、人口が多く、若年人口が多いインド、インドネシアが世界経済の伸びしろを支える日がくると思われる。 「企業の賃上げ」続いても、手放しで“好景気”と喜べない…一体なぜ?2023年4月24日 Finasee 新年度で1つの区切りを迎え、次なるスタートとしての転職を意識し始めた人も多いのではないかと思います。データを参考にして、現在の労働市場の環境は実際のところどうなっているのかを見ていきましょう。 労働市場は今どうなっている? 人材採用、人材開発、人材アウトソーシングサービスなどを展開しているツナググループ・ホールディングスに属する、多様な働き方の調査研究機関である「ツナグ働き方研究所」は、官公庁などが発表している労働市場関連のデータをまとめた「最新 労働市場データレポート」を毎月発表しています。 4月14日に、3月下旬までに公表された最新データをベースにした、2023年2月度のレポートが発表されました。この数字を見ると、今の労働市場の環境は、決して悪くないことが分かります。 ざっと、同レポ―トが取り上げている数字を列挙すると、次の通りです。 ●有効求人倍率(季節調整値)・・・1.34倍 ・正社員の有効求人倍率・・・・・1.02倍 ・パートのみ有効求人倍率・・・・1.35倍●完全失業率・・・・・・・・・・・2.6% 出所:ツナグ働き方研究所「最新 労働市場 データレポート」(2023年2月度) … (略) … <過去の有効求人倍率>1988年・・・・・・1.01倍1989年・・・・・・1.25倍1990年・・・・・・1.40倍1991年・・・・・・1.40倍出所:総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」 つまり有効求人倍率1.34倍という数字は、日本経済が世界で非常に高いプレゼンスを持っていた、80年代バブル期に匹敵する高さなのです。 ちなみにリーマンショックが起こった直後の2009年は有効求人倍率が最も落ち込んだ時で、この時の倍率は0.47倍でした。 完全失業率とは? 次に完全失業率を見てみましょう。完全失業率とは、15歳以上の働く意欲のある労働力人口に占める、無職かつ求職活動を行っている人の割合です。 この「無職かつ求職活動を行っている人」を完全失業者といい、さらに細かい定義を言うと、下記の3つの条件を満たしている人のことを指します。 … (略) … 「好景気だ」と喜べない理由 このように、有効求人倍率と完全失業率の両面から見ても、今の日本の労働市場環境は極めて堅調であることが分かります。ですが、今のマクロ経済の状況には、決してバブル期ほどの好況感があるとは思えません。 それにもかかわらず、労働市場環境の現状を示す有効求人倍率と完全失業率が、バブル期に準じる数字になっているのはなぜでしょうか。 バブル期においては、日本経済の強さから求人数が求職者数を大きく上回り、有効求人倍率を高めるのと同時に失業率を低下させました。しかし昨今の状況は、日本経済が強いからというよりも、労働者不足が原因と考えられます。 つまり、求人数が増大しているというよりも、求職者数が大幅に落ち込んでいることから有効求人倍率が上昇し、完全失業率が低下しているように見えるのです。 現実に、企業はそれほど正社員を必要とはしていないようです。これは、正社員の有効求人倍率と、パートのみ有効求人倍率の数字を比較すると一目瞭然です。後者が1.35倍という高さであるのに対し、前者は1.02倍でしかありません。 他にも、労働者不足はさまざまなところに影響を及ぼします。その最たるものが賃金です。今年の春闘賃上げ率は平均で3.69%という高さになったことが、連合の「2023春季生活闘争 第4回回答集計結果」で出ています。しかし、これも日本経済が絶好調だからというよりも、賃上げをしないと人が集まらないからという事情があります。 一般的に、経済の基本書などには「有効求人倍率が1倍を大きく上回り、完全失業率が低水準の時は好景気と判断される」、「企業が儲かるとベースアップなど賃上げに動くので好景気と判断される」などと書かれています。 ですが、少子化による労働生産人口の減少(特に若年層)によって有効求人倍率が押し上げられ、同時に完全失業率が低下しているのであれば、いわゆる好景気に該当する状況であったとしても、日本経済の強さとは別問題と言えるため、単純に喜べる話ではないということなのです。 ― 引用終り ― 人口の絶対値が足りないこと、若年層が少ないことが国内経済の根底にあるので、企業が一時的な需要の増大に対して構造的に対処することはない。 正社員を増やすことはないし、非正社員は十分な数採用できていない。 売上の低下に合わせて、企業を縮めていけば、いずれその事業からの撤退となる。 コロナ前比で「非正社員も正社員も減った」450社 飲食チェーンや旅行関連企業の減少が目立つ東洋経済オンライン 2023年4月24日 コロナ禍が上場企業の雇用に与えた影響はどの程度なのか。有価証券報告書で各社が公表している従業員数を基に、各社の非正社員と正社員の雇用に与えた影響を調査してランキングした。 コロナの影響を受けていない「コロナ前」を2017年11月期~2018年10月期、コロナ影響を最も受けた時期を2021年11月期~2022年10月期として比較している。時期で比較しているため、個別の企業によってはコロナ影響とは関係ないケースも含まれる。 順位は非正社員の減少率が高い順とした。ランキングには正社員の減少率も併載している。数カ月から1年など有期の雇用期間を過ぎたら契約満了となる、再雇用の義務のない非正社員のほうが減少率は大きかった。ランキング上位にはコロナの影響を強く受けた、飲食チェーンや旅行関連企業が目立つ結果となった。 ― 引用終り ― 街中の多くのチェーン店で売りたい商品よりも目立つ形で、アルバイト・パート募集の幟・広告が出ている。 非正規社員を基盤としたビジネスモデルで収益を組み立てているこれらのチェーン店は、事業の継続のためにビジネスモデルの修正を強いられる。 吉野家「人員不足の為休業」一部店舗貼り紙にネット驚き約12日で再開も...各店でアルバイトの絶対数足りず2023年5月1日 J-CASTニュース 大手牛丼チェーン「吉野家」の東京・新宿の店舗に、「人員不足の為休業します」と伝える貼り紙が出ていたとツイッターの投稿が相次ぎ、驚く声が上がっている。 客の多い都心の店舗だったため、飲食業の人手不足を再認識した人も多かった。アルバイトの採用難などの背景について、吉野家を取材した。 十数店舗が何らかの理由で休業 貼り紙が出ていたとされたのは、吉野家の西新宿8丁目店だ。東京メトロ丸の内線・西新宿駅前にあり、警視庁の新宿署や東京医科大学病院にも近い。 ツイッター上の写真投稿によると、この店が2023年4月19日15時から5月1日10時まで人員不足のため休業するとして、近隣の吉野家を利用するよう呼びかけていた。貼り紙の写真はいくつか投稿され、まとめサイトも取り上げるなど関心を集めている。公式サイトの店舗情報でも、この期間の「一時休業のおしらせ」が出ていた。 27日のツイッター投稿では、アルバイトを時給1200~1500円で募集している店の貼り紙も紹介された。 店は、5月1日から営業を再開している。店舗情報では、ゴールデンウィーク期間中の6日までは、短縮営業を続けて17時の閉店になっている。 吉野家の広報担当者は5月1日、J-CASTニュースの取材に対し、西新宿8丁目店がこの期間に人手不足で休業したことを認めた。新宿地区では、JR中央線・大久保駅に近い北新宿百人町店が、同じ期間に同様な理由で休業したことも明らかにした。 吉野家は、23年3月末時点で全国に1196店あり、広報担当者は、5月1日現在で十数店舗が何らかの理由で休業しているとした。 ― 引用終り ―
2023年05月05日
コメント(0)
-

米国が引き起こす対立 外交が招く分裂、内政が招く分裂
プーチン大統領の外交戦略としてのウクライナ侵略は失敗した。外交的には旧ソ連のCSTO同盟国が離反しつつある。経済制裁などにより国内経済は低迷。数々の大爆発、火災の発生が偶発的なものでなければ、国内統治にも危機を招いていている。 では、連合国(UN)側である米国が覇権国家として「わが世の春を謳歌している」かと言えば、けっしてそうではない。外交的にも国内的にも分裂している。 「第2次南北戦争」は起こるのか追い込まれたバイデン政権24年米大統領選に向け〝米国有事〟の可能性が絵空事ではない理由国際投資アナリスト・大原浩氏寄稿zakzak by夕刊フジ 2023年4月24日 6時30分 中国やロシア、中東など世界の安全保障環境が厳しさを増している。国際投資アナリストの大原浩氏は、米民主党のジョー・バイデン政権こそ、一連の混乱を招いた元凶だと指摘する。大原氏は寄稿で、24年の米大統領選に向けて「〝米国有事〟が勃発してもおかしくない」と警鐘を鳴らしている。 バイデン大統領は2021年1月の就任以来、アフガン撤退の大失敗だけではなく、米国抜きのイラン・サウジアラビア国交正常化まで許してしまった。バイデン政権が外交で無策であることは明白だ。ウクライナ戦争においても、対ロシア経済制裁やウクライナ支援の手法が稚拙で、結果として中国とロシアを接近させた。習近平国家主席はロシアを訪問してプーチン大統領と会談し、両国の協力をアピールした。 それどころか、バイデン政権の強権的な外交手法を嫌った多くの国々が米国離れを起こした。 例えば、4月13日に中国・上海訪問中のブラジルのルラ大統領が「人民元やその他の通貨が国際決済通貨になってはならないのか。なぜ、自国の通貨で決済できないのか」と発言した。 米国が、ドルが基軸通貨であることを利用して、ロシアの中央銀行の資産を凍結し、国際的な決済システム「SWIFT」から排除したことが影響しているとみられる。この制裁はロシアに大した打撃を与えなかったどころか、世界中の国々に「米ドルで資産を持っていると何をされるかわからない」という恐怖を与え、ドル離れの加速という大ブーメランとなって返ってきた。 ウクライナ戦争でも、米国はバイデン政権自らの覇権を重視しているように見える。最悪なのが天然ガスのパイプライン「ノルドストリーム爆破疑惑」である。バイデン政権は限りなく黒に近い灰色だといえよう。 疑惑をスクープしたジャーナリスト、シーモア・ハーシュ氏は新たに「ゼレンスキー大統領がロシアから安くディーゼル燃料を購入する一方、米国が燃料購入代として送った数億ドルの支援を側近とともに着服している」と報じた。ウクライナをめぐっては、2014年にバイデン大統領の息子、ハンター氏が、国営天然ガス会社ブリスマに高額報酬のコンサルタントとして就任したことも知られる。 米国の内政においても、シリコンバレー銀行などの破綻による「連鎖的金融危機」はまだ序章だといえる。イエレン財務長官は「預金を全額保護する」との発言で沈静化を図っているが、そのための資金の裏付けが必要であり、債務問題がのしかかる。 このように追い込まれたにもかかわらず、バイデン氏は延命を図り、24年大統領選挙への出馬を画策している。 ニューヨーク州の大陪審ではトランプ前大統領が起訴された。民主党支持者が多い同州だが、民主党系のメディアにも起訴は「暴挙」との見方が散見され、中間層だけではなく、党内の良識派にまで見放されつつある。 ― 引用終り ― 大原氏は第二次南北戦争を起こしたい勢力とみうけられる。 世界経済で大きな成長要素を持つ余地が減少するにつれ、膨大な投資資金、マネーが行き場を失っている。かくして火のないところに煙を立てる輩が増えるので、現代の経済社会は安定することがない。 SDGs で環境保全を中心にまとまり始めた世界を、超過利潤を得るため安定を好まない勢力が解体し、闘争的な環境を作ろうとしている。 米国の共和党は国内の貧富の差を拡大する政策を打ち、トランプ政権で国内の白人の貧富の差が問題だ大きく打ち出した。マッチポンプそのものだ。 上記の記事でも積極的に米国離れを起こした国は、独裁的運営をする国が多いこと、政権の危機が政権トップの命にかかわるような国が多いことは記さない。 「ノルドストリーム爆破疑惑」にいたっては、誰が起こしたのか全く明らかになっていない。シリコンバレー銀行などの破綻による「連鎖的金融危機」は、知る限り銀行経営の問題であり、FRBが主体となって、バイデン政権とともに解決すべき問題だ。 記事を表した大原氏は、数々の反対・疑惑があるのに大統領選に出馬すると問題視し、民主主義を軽視している。投票で必ず勝つ者だけが立候補するのは、独裁国家だ。米国の分裂を激化させたトランプ前大統領も数々の疑惑塗れのまま政権についたし、今のところ次期大統領選に立候補する可能性を否定していない。 ウクライナ戦争を引き延ばしているように見受けられるバイデン大統領より、2003年にイラクが大量破壊兵器(WMD)所有しているとして、誤った情報をもとにイラクに武力侵攻した共和党・ジョージ・W・ブッシュ元大統領の方がよほど問題だ。不確かな情報をもとに武力侵攻をするプーチンのウクライナ侵略のモデルとなったようにみえるからだ。 ブッシュ元大統領親子は、あからさまにエネルギー利権をもとに米国外交を左右した。 米国の各勢力は、国内勢だけでなく、ロシアや中国を含む様々の勢力がSNSなどを駆使して「世論」を左右していることを重視している。 国内政治勢力の分裂が生じているのは、米国だけではない。 2024年米大統領選挙、予備選挙の「異変」:アイオワ党員集会が消える? 渡辺 将人北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院准教授 2024年4月20日 笹川平和財団 民主党大改革:予備選州順位変更で52年ぶりの首位交替か 2024年米大統領選挙に向けての動きが活発化してきた。本稿では予備選挙の激変を伝え、共和党各候補の動向を補足的に解説する。 アメリカ大統領選挙は予備選挙過程の1戦目であるアイオワ州党員集会から始まり、2戦目のニューハンプシャー州予備選に続くのが慣わしだった。予備選挙過程は全米同日一斉開催ではなく州ごとに順繰りで行われる。2024年大統領選挙では、1972年から続いてきたアイオワ党員集会が、民主党側で日程と方式の両面で変更される見通しが強まっている。緒戦州の結果が選挙戦の世論調査や後続州の有権者の投票行動に影響を与えるため、緒戦州が握る過大な影響力は問題だった。アメリカの政治学者の間でもアイオワ党員集会の賛否は長年議論されてきた。 それでも全米一斉投票にしないのは小さな州を緒戦にすることで資金力や知名度のない新進候補にもチャンスを与える意義があったからだ。全米一斉投票やカリフォルニア州など巨大州が緒戦だと大物候補だけが有利になる。アイオワが人種的少数派の少ない白人州であることや農業に偏った産業構造を持つことなど「アメリカの平均ではない」問題は、主として民主党内にあった批判である。共和党にとってキリスト教右派から穏健派まで満遍なく存在する農村アイオワは共和党支持層の理想的な見本市だった。予備選は党事であり、「有権者の平均」は政党で異なる。「アメリカの平均州」の抽出論が非現実的だったのは、共和党と民主党で「平均」定義が一致しないからだ。「平均」をおさえた上で両党で開催日も州順も揃えるなら永久に調整できない。そもそもイデオロギー上は本当の「平均」かもしれない無党派はどのみち予備選に参加しない問題もある。 今回の民主党改革は民主党全国委員会(DNC)がアイオワ民主党を「先頭集団」から脱落させることが目的だった。アイオワにペナルティを与えるためだ。2020年1月の党員集会で当日中に得票集計が完了しなかった混乱への罰である。だが、政治的な思惑も交錯する。この騒動で結果不明のまま後続州ニューハンプシャー戦が始まり、アイオワでは泡沫候補で3位にも手が届かなかったバイデンを延命させたからだ。いわばバイデン政権は2020年のアイオワの混乱の産物である。 当時、サンダースとウォーレンという「左派2強」に加え、LGBT の新星ブディジェッジが追随し、古参の穏健派は勢いがなかった。現副大統領のハリスに至ってはアイオワ党員集会前に力尽きて撤退した。こうした事情から、アイオワのあの日の夜の混乱が左派候補を食い止めるためだったのかとの陰謀論まで語られる始末だった。伏線が皆無だったわけではなく、地元紙「デモイン・レジスター」の伝統行事である党員集会直前の世論調査が突然公表中止にされた事件がさらに騒めきを生んだ(表向きには電話調査で一部の質問員がブディジェッジの名前を聞き忘れたことが理由とされたが、全結果がお蔵入りにされた) ― 引用終り ― 国際政治・経済の評価は、様々な要素・事実をどのように切り取ることも可能。外部から見た一国の政治構造をどのように評価することも可能。 事実も真実も一つとは限らない。
2023年05月04日
コメント(0)
-

分裂するロシア 外交と内政
現在、プーチン大統領が行ったウクライナ侵略戦争は失敗を続けており、戦争が長期化、泥沼化するとみられている。 武力侵攻を行ったことにより経済制裁下にあるロシアと貿易を行う国は、イラン、北朝鮮、など限られている。中国とインドも貿易を継続しているようだ。 2023年4月18日 対ロシアの貿易赤字が巨額となったインドとロシアは、貿易赤字と市場アクセスの問題に取り組むことで合意したとインド外務省が発表した。 インドとロシア貿易赤字と市場アクセスの問題に取り組みへロイター 2023年4月19日 16時8分 インドとロシアは18日、貿易赤字と市場アクセスの問題に取り組むことで合意したとインド外務省が発表した。 ウクライナ戦争以降、ロシアからの輸入が4倍以上に増加したため、インド政府は貿易不均衡の縮小を目指している。 ロシアのマントゥロフ産業貿易相は17日、訪問先のニューデリーで、両国が自由貿易協定(FTA)について協議していることを明らかにした。 関係筋によると、インドは2月24日から4月5日にかけて、ロシアから石油を中心に513億ドル相当の商品を輸入した。前年同期は106億ドルだった。 ― 引用終り ― 経済発展中のインドは、戦闘機、戦車などの兵器と、産業の発展により不足するエネルギーをロシアに依存してきた。インドは待っても届かないロシア製の兵器にしびれを切らせ、韓国を含む西側の兵器の購入に転換するだろう。半導体不足のロシア製戦車は、FCS(火器管制装置)があてにならず、使い勝手の悪い兵器類をインド軍部も欲しくはないはず。 2022年のロシアGDPはマイナス2.1%。2023年以降もロシア経済は低迷を続けることだろう。 ロシアの侵略戦争で大きな利を得るのは、今のところ各国の軍需産業だけにみえる。 2022年の実質GDP成長率はマイナス2.1%(ロシア)2023年03月06日 JETRO ロシア連邦国家統計局は2月20日、2022年の実質GDP成長率をマイナス2.1%(速報値)と発表した。卸売・小売業や製造業の不振によりマイナス成長となった。他方で、農林水産業や建設業は堅調に推移したことや、政府支出の増加が経済を下支えした。 産業別でみると、マイナス成長の主な産業は卸売り・小売り・車両修理業(前年比12.7%減)、水道・廃棄物処理業(6.8%減)、保健・社会サービス(3.2%減)、製造業(2.4%減)、運輸・倉庫業(1.8%減)だった。他方で、一部の産業はプラスとなり、農林水産業(6.6%増)、建設業(5.0%増)、宿泊・飲食サービス業(4.3%増)、公務・軍事安全保障・社会保障(4.1%増)だった。 需要面では、最終消費支出は家計が1.8%減、政府が2.8%増だった。総資本形成は3.2%減となった。総固定資本形成は5.2%増だったが、在庫の減少が影響した。 ― 引用終り ― プーチン大統領の権勢は、資源輸出による経済の繁栄が支えられてきた。 長引く戦争のため、ロシアの輸出は減り、輸入は減らすことができない。 他国の領土の侵略に失敗して権威を失い、経済制裁で経済を失ったプーチンのロシアが解体・分裂するとの見方も多い。長引くアフガン紛争に関わり崩壊したソ連邦をみる思いだ。これ以上分裂したくないロシア人は、これまでプーチンを支持してきた。 侵攻失敗ならロシアが20カ国に分裂核使用辞さない「ならず者国家」へ強欲資本主義・中国が狙う「属国化」2023.2/9 zakzak … (略) … 欧米のロシア専門家の間では、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、「プーチン退場」「ロシア崩壊、もしくは弱体化」という近未来のシナリオが声高に語られるようになった。 中国の習主席は、これらをどう読んだだろうか? 米外交専門誌「フォーリン・アフェアーズ・リポート」最新号は、「3つのシナリオ」を提示した。①和解成立の可能性は低い。②苦戦を強いられたロシアは核を使用する可能性がある。③中国の『属国』として生き延びる。 暗い見通しばかりだ。もし、ウラジーミル・プーチン大統領が去り、ロシア連邦が崩壊すれば、ロシアは20の「国家」に分裂する予測も成り立つとする。 ― 引用終り ― プーチン大統領の地方版は各地にたくさんいることだろう。 最近過激で不条理な発言が目立つ、メドベージェフ氏はどうするのだろうか?
2023年05月03日
コメント(0)
-

CSTO諸国も見限るプーチンのロシア
旧ソ連の6カ国で構成され、「ロシア版NATO」とも言われる集団安全保障条約機構(CSTO)が崩壊の危機を迎えている。 ロシアがウクライナ侵略戦争に注力し、CSTO加盟諸国の要請にこたえられていないため、ロシア離れが加速しているとされる。 「ロシアは助けてくれない」 小国アルメニア、西側参加望む声も2023年4月22日 AFPBB News アルメニアの首都エレバンのオペラ座近くで、言語学者のアルトゥール・サルグシャンさん(26)は、ロシアは頼りにできないパートナーであり、アルメニアは他の「同盟国」を探すべきだと語った。 サルグシャンさんは「アルメニアが集団安全保障条約機構(CSTO)を抜け、ロシアの影響下から離れる日を夢見ている」と話した。CSTOはロシアが主導し、旧ソ連諸国で構成される。 宿敵アゼルバイジャンと衝突した時も、「窮地に陥ったアルメニアを、ロシアとCSTOは助けてくれなかった」と、サルグシャンさんは強調した。 1991年のソ連崩壊以降、人口約300万人のアルメニアはロシアの軍事的、経済的支援に依存してきた。国内にはロシア軍の基地があり、ロシア語話者も多い。 しかし今日、多くのアルメニア人が、トルコの支援を受けるアゼルバイジャンからアルメニアを軍事的に守るという責任を縮小しているロシアを、許せないと語る。 昨年12月中旬、アルメニアと係争地ナゴルノカラバフ(Nagorno-Karabakh)をつなぐ唯一の道路をアゼルバイジャンが封鎖すると、ロシアへの不満はさらに高まった。そのロシアは現在、ウクライナとの戦争で身動きが取れなくなっている。 ― 引用終り ― CSTOは、旧ソ連諸国が1992年に作った軍事同盟。加盟国は、ロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン。 CSTOの目的は、条約加盟国の国家安全保障、とその領土保全。安全保障の主役は、ロシア、ロシア軍であり、ウクライナ侵略のため、これらの諸国に駐留する軍隊を引き揚げているロシアは、頼りにならないとCSTO加盟国の多くが感じているということだ。 フィンランドは歴史上の教訓を踏まえ中立を保ってきたが、ロシアの武力侵攻をみてやむなくNATO加盟を決断した。 NATO加盟国を増加させ、CSTO加盟国の離反する動きを招いているので、ロシア・プーチン大統領のウクライナ侵略開戦は、安全保障上の観点から完全に失敗、間違いだったということになる。 経済制裁による経済の低迷、徴兵による身近な人々の死などもあり、プーチン政権の信頼性は低下し、ロシア国内では大規模な爆発・火災が続いており、反体制派が活発な動きみせているいと見受けられる。 プーチン大統領の抱いた、汎スラブ主義に基づくソ連邦の復権は、愚かな妄想とされるだろう。人類をはじめ、地球は、大きな破壊力を有する核兵器を持つ愚か者と心中したくはないはずだが、コロナ禍で妄想を大きくした核弾頭のボタンを押す権利を持つロシアのトップを止める術はない。 みんなの地球は大丈夫かな?
2023年05月02日
コメント(0)
-

SAのガソリン価格差問題と人気SAベスト10
長期連休のたびにEVの航続距離不足が話題になる一方、内燃エンジン車、HEV、PHEVは国内で使用するに十分な航続距離を備えている。 サービスエリア、パーキングエリアに併設された給油所は、市中との価格差もあり、利用者は減る一方のようだ。高速SA、一般道とのガソリン価格差は、全国的に10円以上の差があるケースは多いとのこと。 高速SAのガソリン価格“ここまで違うか…” インター周辺のスタンドとの価格差が鮮明に乗りものニュース 2023年4月22日 11時42分実際の給油すると価格差すごいですよ! SA・高速入口周辺・幹線道路沿いでガソリン価格調査 ガソリンスタンド情報サイト「gogo.gs」を運営するゴーゴーラボ(神奈川県鎌倉市)は2023年4月21日、ゴールデンウイークに向けて高速道路SA、IC周辺・幹線道路沿いのガソリン価格を比較した特集を公開しました。 今回は東名の海老名SAと、その近くのICになる厚木IC周辺のガソリンスタンドでレギュラーガソリン価格(/1L)を調査しています。 海老名SAのガソリンスタンドの価格は上下線平均で185円(4月15~21日)だったのに対し、厚木IC周辺のスタンド5店舗の平均は156.4円、同IC周辺の幹線道路沿いスタンド5店舗の平均は158.2円だったそうです。 SAのスタンドとの価格差は、それぞれ28.6円、26.8円という結果に。SAの価格とIC周辺スタンドの平均価格とで50L給油した場合、1430円もの差が生まれる計算です。 高速SA、一般道とのガソリン価格差は地域により異なるものの、全国的に10円以上の差があるケースは多いようです。ゴーゴーラボは、高速道路に入る前に給油したほうがいいとしています。 ― 引用終り ― 遠距離ドライブの中継地点だったSAは、民営化以降、レジャーの目的地と化しているところも少なくない。海老名SAのように、名物商品と駐車場の混雑で有名なところもある。海老名SAの「メロンパン」は2日で3万個近くを売り上げるほど人気で、最近では他のSAで「海老名SAのメロンパン」として販売するようになった。 刈谷ハイウェイオアシス(愛知県刈谷市・伊勢湾岸自動車道)の目印は大きな観覧車。充実した「のりもの遊園地」を併設している。刈谷市との連携(建設条件?)もあり、一般道からの利用も容易。温泉施設、地産品を取り扱うスーパーマーケットまで普段使いできる施設となっている。 目的地にしたいくらい♪日本全国おすすめの大人気サービスエリア10選 2023年4月29日 Trabel Book … (略) … 一昔前は、眠気覚ましやトイレ休憩のためだけに利用していたSA・PAも、最近ではご当地限定のお土産や名物の美味しい物、素晴らしい景色などを楽しめるところが増えていて、度々メディアでも取り上げられているほどです。旅の途中で素通りしてしまうのがもったいないほど、おもしろいサービスエリアがとても多く、旅行ではなくサービスエリアに買い物や遊びに行くというのを目的に高速道路を利用する人々もたくさんいます。 そこで今回は、日本全国にあるサービスエリアの中でも、目的地にしたいくらい魅力的なおすすめ大人気サービスエリア10選をご紹介します。 ― 引用終り ― SA・PA名のみメモ。■有珠山SA (北海道)■那須高原SA (栃木県)■諏訪湖SA (長野県)■寄居PA(上り)■幕張PA (千葉県)■海老名SA (神奈川県)■刈谷ハイウェイオアシス (愛知県)■淡路SA (兵庫県)■宮島SA (広島県)■別府湾SA (大分県)
2023年05月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1









