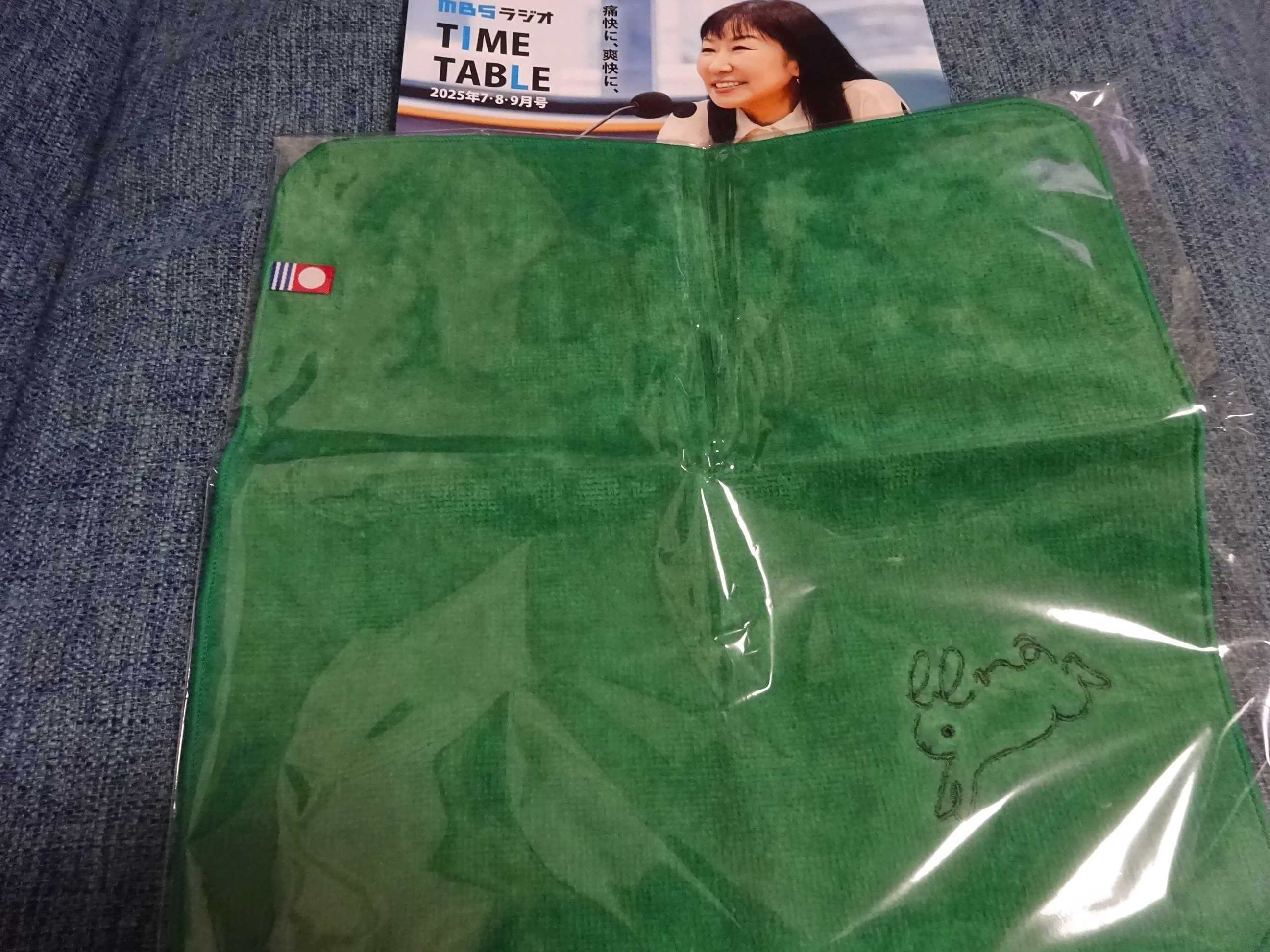全47件 (47件中 1-47件目)
1
-
じいちゃん
久しぶりの更新です。先日4月8日、祖父が他界しました。亡くなったのは父方の祖父で、大学に入ってすぐまでの約20年一緒に暮らしてきた、じいちゃんでした。一昨日、昨日とお通夜、告別式がありほぼ3日間実家に帰ってきました。いつも寝ていた部屋で、まるで寝ているかのように横になっている姿も最後にお棺に入る直前に触れたときの冷たい感触もはっきり残っているのに不思議と今でも実感がありません。自分の祖父母は皆健在だったので、今回初めて家族がいなくなるという経験をしたためなのかもしれません。今でも、うちに帰ったら今でテレビを見ながら「おう、あっちか~」って声をかけてくるんじゃないかって気がして、写真の中で元気そうに笑ってるじいちゃんがもういないなんて、信じられないです。亡くなる直前は体を壊して入退院を繰り返していて、人工呼吸器を着けたまま、おかゆ位しか食べられないでいたじいちゃんを見ていたから、式の最中は楽になれてよかったね、なんて思っていたんだけどいざ火葬されて、骨になっちゃったじいちゃんがお墓の下に納められるのを見ていると、やっぱりもうちょっと生きてて欲しかったって思わずにはいられませんでした。しょっちゅうばあちゃんと喧嘩してたじいちゃんだけど、自分や妹やいとこの子達、もちろんばあちゃんにも、すごく優しくて親戚が集まるたびに、一番年長だった自分に小遣いをくれて「お菓子でも買ってこいよ」って言っていたじいちゃん。書道がうまくて、よくお手本を書いてもらったりしたっけ。マラソンも得意で、毎年新年のニューイヤーと箱根駅伝は必ず見ていました。今でも市民マラソンでとった3位の賞状は、じいちゃんの部屋に飾ってあります。そんなじいちゃんも、パーキンソン病を患ってからは年とともに静かになっていって実家に帰っても一人テレビを見ながら、せんべいなんかを食べている姿ばかり見るようになりました。丁度孫達が大学生や社会人になった頃だったから、段々会う機会も減っていってたしもうちょっと、遊びにいっとけば良かったかなぁなんて、やっぱり思います。喪主だった父が、告別式の最後に、つたない言葉で生前のじいちゃんの事を語っていたときには、何だか言葉に出来ないものがこみ上げてきて、たまらなかった…誉められたところばかりじゃない父だけど、あの時ばかりは、泣きそうになりながら喋ってる姿を見て、頑張れって、言ってやりたくなりました。中学生の時にじいちゃんに買ってもらった自転車は、今でも乗ってるよ。28インチのでかい自転車で、47000円もする立派なやつ。こうやって書いていても、やっぱりどこかで信じられなくて、大泣きしてた従姉弟とか、冷たくなったじいちゃんの手とか、父の言葉とかが只々、頭の中でぐるぐる回っています。いつかふとした時に、それを実感して、すごく悲しくなるのかと思うとその瞬間が来るのがすごく怖いです、、来月、49日でまたお線香あげに行くから、覚悟しとかなきゃ。向こうではうまいもの食ってね、じいちゃん。悲しいけど、じいちゃんの分も頑張って生きようと思った、葬式のお話でした。
2006年04月11日
コメント(70)
-
肯定文
このところ、すごく大事な事が少しづつできるようになってきた。 それは「自分を肯定する」こと。 もっと正確に言うと「『今の自分』を肯定する」こと。 これってできている人からしたら、まだそんな事やってんの? って感じの事なのかもしれないけど、はい、今自分はそれをやっております。 前に読んだ(確か)ドラゴン桜で 「今あるものに片っ端からマルをつける」というのがあった。 これはつまり、とりあえずこれが足りない、あれが欲しい、 こうだったらいいのになぁ、っていう願望は一旦脇にのけておいて 今自分の周りやあるいは自分自身としてあるものに 文字通り片っ端からマルつけする、つまり肯定してやるというもの。 多分、言い方を変えれば、受け入れるとか認めるってことなんだと思う。 これを地道に繰り返してみた。 とりあえず過去の後悔も、未来への不安も置いといて、 「今の自分にはこれがある」とか 「とりあえず今は○○が足りない自分がいる(けどそれもマル)」 ってな具合に自分に言い聞かせてみた。 そうして繰り返しているうちに、自分にあるものとないものが 整理されてきて、特に「今あるもの」がそれなりにあるということが 大分わかってきた気がする。(それなりに、だけどさ) 世間的には、今はないけど必要なものにフォーカスして、 「もっと○○しなきゃ」とか「頑張って△△するぞ」ってな感じで 自分を鼓舞するのがは前向きな姿勢だとみなされる傾向がある ように感じるけど、自分はいくらそれをやっても前に進めなかった。 で、そんな自分をダメなんだと思い込んでた時期があったりした。 でも、最近いろんな人のアドバイスを聞いてみて 同じ事をするにも別のモチベーションの高め方があるんじゃないかと 思うようになったので、ちょっと視点を変えて間違い探しから マルつけに発想を変えてみた。 確かに一歩間違えば自己完結しちゃうから堕落の道へまっしぐら かもしれないけど、少なくとも自分には 間違い探しよりも、マルつけの方が性に合っている気がする。 他にも似たようなので「自分に○○することを許す」っていうのがあった。 本当は○○したいんだけど、…だからなぁ、、 ってな感じで理由をつけてやらなかったことはたくさんある気がするけど 「いいじゃんそれ、やってみなよ!」と 後押ししてくれる声のおかげで踏み出せる一歩から始まる 展開っていうのも面白いんじゃないだろうか。 そんな事を考えて、 最近はちょっと自分にOKサインを多めに出すようにしている。 やっぱり、その方が自分はうまくいくらしい。 ちょっと古いけど、これが「オレ流(?笑)」なのかも。 やっぱり自分はマル付け足し算式でいこう、うん。 その方が自分に自信が持てるみたい。 自信、つまりは自分の人生を信じるって意味では、 前を進んでくれているユースケに少し近づけたかな? なんて思いながら、今日は遅いので寝ます。 おやすみなさい。
2006年02月15日
コメント(1)
-
言葉
最近、mixiというコミュニティサイトで主に日記を更新しており、こっちでの更新がストップしていたため、こちらにも同じものを更新してみます。このところ車内で良く目にする朝日新聞の広告があります。 言葉は 感情的で、 残酷で、 ときに無力だ。 それでも 私たちは信じている。 言葉のチカラを。 個人的には読売をとっているし、朝日の新聞の勧誘は どこよりもしつこくて嫌いだから、朝日自体にもあまり いい印象は持っていないんだけど、 それでもやっぱりこの広告は目にとまります。 前の哲学バトンで 「言葉」 ある意味その存在に最も感謝しているもの と書きました。 そう、今でも本当に感謝しているのがこの言葉というものの 存在。 自分にとって、言葉っていうのはとても大切で、数知れない 意味を持つものであります。 上手な文章を書く事はできないし、うまく喋ることもできない それでも伝えたい事を伝えるのは、最後はやっぱり言葉です。 確かに時に無力ではあるけれど、 自分もその力をどこかで信じている。 ふと車内で見つけたその広告を見て、気がつきました。 言葉を使って何を表現するかは人それぞれ。 愛情や怒りの言葉、文学的な表現から科学の文章まで、 その言葉を持って紡ぐ事ができるものはそれこそ限りなく この世に存在しています。 しかも伝え方によって全く逆の内容が伝わることもしばしば。 うまく伝えるには、センスが大切なのかもしれません。 今度、そう思うようになったきっかけになった友達と 会う約束をしました。 伝えたいことはたくさんあったのに、 伝えるべき言葉を搾り出せないまま ただ黙ることしかできなかった。 そんな記憶を少し苦々しく思うと同時に 当時より少し、言葉を覚えた自分がどれくらい 自分の中にあるものを伝えられるのか試してみたい。 そんな事を考えています。 言葉はどれくらい人に気持ちを伝える事ができるんだろう。 言葉は 感情的で、 残酷で、 ときに無力だ。 それでも 私たちは信じている。 言葉のチカラを。
2006年02月14日
コメント(3)
-
20世紀少年
最近はまっている漫画があります。浦沢直樹の『20世紀少年』という漫画です。Monsterなどでも知られる天才浦沢直樹ですが、この漫画でもその才能をこれでもか、と言うほど発揮し、非常に複雑で、しかしあっという間に引き込まれて読み切ってしまうそんな漫画に仕上がっています。自分としては、オッチョの師匠が非常に自分を助けてくれました。前の日記でも書きましたが、かなり深いです。手塚治虫もやはり本当に天才漫画家だと思いますが、こういう漫画をかける人が同じ日本人であるというのはやはり誇らしく思えるものです。
2006年01月11日
コメント(2)
-
自分
今日はちょっと自分の事を突き詰めて考えてみました。ほとんど自己満足で書いている文章ですが、ある意味で決意文でもあります。今日はこれから自分がどう生きていくことになるのか、久しぶりに、何年ぶりに、まともに頭を働かせて考えました。その結果を載せることにします。父は公務員です。消防士として立派に勤めを果たしています。本当はやりたかったことがあったらしいのですが、消防士になったからには消防士として、任務を全うしています。その姿には小さな頃から憧れを持っていました。私生活では多少だらしなさがあるものの、それを差し引いても、やはり人のためになる仕事と言うものにはずっと関心がありました。しかし、そんな父が自分の進学するにつれて口にするようになったのが、「公務員だからお金が…」という言葉でした。小さい頃はその意味がわからなかったものの、自分が就職するような年になってくると、その言葉の意味がわかってきました。公務員は、給料が安い。いつしか、それが自分の公務員に対してのイメージになっていきました。そして、いつからか、「絶対に公務員にはならない。俺は子供には金がないから…という言い訳はしたくない」と強く思うようになったのです。それからというもの、ある意味で公務員アレルギーと言えるほどに、公務員と言う職種に対して抵抗を感じていたように思います。国連職員を目指そうかと思ったときにも、給料が安いのだけは…とどこかで感じ、いつしかそれを投げてしまったよううに思います。しかし、このところ、たくさんの助けを経て、ようやく自分の今の姿、つまり今までの失敗も成功も全て含めて形成されてきた自分自身に、ようやく向き合う勇気が持てるようになってきたのです。公務員にはなりたくないと思う一方で、やはり誰かの役に立てる人間でありたいと言う思いはずっと失われることはなく、むしろ抑えてきた時間の中でより強く思うようになっていたのです。やはり自分は人のために何かをしたい。その気持ちだけは、嘘偽りなく自分の心の中に存在していると、確信するようになったのです。受験の失敗で入った大学やその後進学した日本最高峰の大学院での日本のアカデミックの現場の現状や、保守的な周りの常識に流されそうになり、どこかで自分にも、日本にも、そして世界にも失望しながらも、それでも捨てる事ができなかったのは、やはり自分ができることが誰かの役に立つのなら、それはどんなことであっても自分にとっては真実だという想いでした。あまりにも未知すぎる世界に飛び込んで行く事への恐怖は全く隠すことができませんが、それでも自分は踏み出したいと思ったのです。それが本当に自分の中にいる自分自身と向き合うことだったのです。いつか出口氏の本で読んだあの文章が、今でも自分の中で非常に大きな割合を占めています。それは誰になんと言われても変わる事はないであろう、自分の信念だからでしょう。きっと一生涯変わる事はないんだろうと思っています。改めて、今日から自分は一歩でも前に歩き出そうと決めました。迷ったり立ち止まったり絶望するときには、20世紀少年にあった、この言葉を思い出すことにします。「絶望に打ち勝つ方法などない。…ただ…歩き出すだけだ。」と。自分はきっとまたどんどん変わっていくでしょう。しかし、今日得たこの言葉は、変わる事はない。自分がどうこの言葉を持ち続けていくのか、これからが楽しみでもある、スタートです。最後に、もう一度出口氏の言葉を残しておきます。あなたが、居間でテレビを見ていたとする。画面にはどこかの国の戦争が映し出され、両親を殺された幼い子供が、親の死体にすがって泣いている。可哀相に。誰もがそう思うだろう。だが、はたしてそれが同情であり得るのか。それが同情になるにはいったい何が必要なのか。同情とは、相手と同じ感情を自分の中に抱く好意を指すと、先に述べた。親を亡くした子供と同じ感情を持つことが、はたして私達には可能であろうか。その子供は、まだ幼いのに、これからたった独りで生きていかなければならないのである。その日の寝るところ、食べるものもないかもしれない。しかも、子供というのは独力で困難な状況を克服することができない。そのときの子供の心には、悲しみや絶望以前に、言葉にならないほどの恐怖が渦巻いているのではないだろうか。そのうえ、子供は大人以上にむき出しの繊細な神経を持っている。そうした子供の感情と、もし私たちが同じ感情を抱くことができるのなら、それは素晴らしいことではないか。そのためには、強力な想像力がいる。もちろん、まったく同じ感情を抱くことなど不可能で、要は程度の問題である。違った環境に置かれた私達が、ほんの少しでもこの子供と同じ感情を抱くのならば、居ても立っても居られなくなるはずである。それでも、私達は何もできないというジレンマに立たされるであろう。でも、こういった想像力を身につけている人間は、必ず人生のどこかで何かをするだろうし、少なくともその人の中には弱いものに対する優しさが芽生えるはずである。『きのうと違う自分になりたい』より
2006年01月11日
コメント(0)
-
☆2006年☆
いつもブログ上でお世話になっている皆様、明けましておめでとうございます☆昨年から始めたこのブログも、山のように一気に書いたり数ヶ月放置したりと自分の性格がしっかり表れた更新ぶりでしたが、コメントや掲示板への書き込みを頂いた皆様には本当に感謝しています。今年度どう変わっていくのかはわかりませんが、改めて、どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m
2006年01月03日
コメント(3)
-
いつ眠ってますか?
今日は9時過ぎに夕飯を食べてからすぐに眠ってしまって、2時過ぎに目が覚めました、なのでこんな時間に更新ですが、、夜10時から2時までに眠ると良いというのは一度は聞いた事があるんじゃないでしょうか?今まではあまり意識した事がなかったんですが、今日偶然その状況になってみたら、すごく体の調子が良い!(気がします…)これは何かある!と思って早速調べてみたらどうやらこの時間帯には、安心物質、抗アレルギー物質、成長ホルモンなど(同じものかもしれませんが…)を分泌する働きが活発になり、安眠&疲労回復が格段に良くなるらしいのです。サイトによってはこの4時間だけ寝ればいい!と断言しているものまでありました。朝うまく起きられない。これは今までずーーーーーーーっと抱えてきた自分の大難問だったのでもしかしたらこれは何か起こしてくれるかもしれません。とにかくまずはやってみます。効果があるようなら、またここで取り上げます♪他に睡眠について面白い情報があれば教えて下さい☆彡
2005年12月15日
コメント(2)
-
TBS あの時原爆投下は止められた…
今日の昼間、TBS系で再放送をしていたのを偶然目にしました。TBSテレビ50年~戦後60年特別企画”ヒロシマ”・・・・・あの時原爆投下は止められた・・・・・いま、明らかになる悲劇の真実と題した、広島の原爆が投下されるまでの経緯をその当時の戦況や諸外国の思惑、そして生々しい再現VTRを交えてまとめたドキュメントです。…と、一言で片付けてしまうにはあまりにも濃い内容だったように思います。少なくとも、小中学校で知識として習っただけの戦争、原爆とは全く別の、今この年になったからこそわかる当時の日米の人間が抱えていたそれぞれの思惑や苦しみが、痛いほど伝わってくるような、そんな番組でした。全く見る予定でなかったにも関わらず、2時間テレビの前から動けませんでした。再放送のようなので、細かい説明などは他のブログなどですでになされていると思いますから、自分の私見だけを書きます。広島と長崎で原爆が落ちた。それによりたくさんの人が被爆し、死んだ。それを機に日本が降伏し、戦争が終わった。そうした内容は、今やどこの小中学校でも習うことだし全く聞いたことがないという高校生以上の人間はほとんどいないでしょう。しかし、自分と同世代で、終戦直前に当時の昭和天皇が戦況をどう見て、そして何故、原爆投下まで至ってしまったのか、その過程や原爆が投下された広島が、その時どんな状況になっていたのかあるいは被爆した人たちが、それからこの60年の間どのような思いで生き抜いてきたのかなんて、自分自身、今日この番組を見るまで決して知ることはなかったと思います。そして、これまでに例え今日のように知る機会があったとしてもその当時の人の気持ちになってそれを想像してみる、あるいはそこから自分にできることは何かを考えてみるなんて、今日このタイミングで番組を見るまで、やっぱりなかったと思いました。印象的なのは、アメリカで原爆を開発し、投下し、その映像を撮ったという科学者が、原爆記念館を訪れ、そして被爆された方と会談するという場面。その科学者は「罪もない人などいないのです、全員が加害者なのです。」そう言ったのを覚えています。どちらも加害者であり、そして加害者です。アメリカ人としては真珠湾の奇襲で友を失い、日本人としては原爆やその他の爆撃により数多くの人間を殺されたわけですから、一方的にどちらかが相手に謝って欲しいと言っても、それは簡単なことではありません。原爆の威力の凄まじさを目の当たりにした直後は概してアメリカが全て悪かったかのように感じてしまいましたが、日本が真珠湾で奇襲をかけたことも事実。もちろんそれが原爆を擁護する理由にならないのは当然のことだとしても双方が本当の意味でお互いのしたことに対して真摯に謝罪をするのは果たして可能なのだろうか、とどこか釈然としない疑問を感じました。戦争については自分は日本に生まれ育っていますから、日本人を被害者として見るのが当たり前になっていますが、もしアメリカ人に生まれていたとしたら、それは全く逆になるわけです。一方的にアメリカ人に家族、友人を殺されたと言ってもそれはアメリカ人からも全く同じ事を言い返されることになるのかもしれません。片方から見ただけの論理は通じない、それが戦争の怖さなのかと思いました。そして、事は日米間のみならず日韓、日中、あるいは東南アジア諸国とも同じことが言えるわけです。今でも、あちこちで争いが続いていますがそのどれを取っても、一元的に誰が悪い、誰が被害者だと言い切れるものではないのかもしれないと思うと、気が遠くなるような難しい問題なんだと実感してしまいました。考えてみたら、普通の個人同士での争いでもそういうことは多かれ少なかれあるのかもしれないですね。必ずどちらかが悪い、どちらかが良い、そう言い切れないことが大多数。だからこそ、その問題がどこから、どう生じたのか、何をどこまで巻き込んだ問題なのか、そうしたあらゆる立場に立っての視点が必要なんだろうと、改めて思いました。もちろん、許し難い犯罪も数多くあるのも事実ですが。今まで歴史って、単にテストに出るところを覚えまくるだけの暗記力勝負の科目だとしか思っていませんでしたが、最近こうした背景の話がわかるようになるにつれて、興味が出てきました。多面的に見る。言葉で言うと簡単ですが、もっともっと自分の視野を広げて偏った見方にとらわれずに物事を見、判断できるようになりたいと、今日は改めて強く思いました。
2005年11月23日
コメント(1)
-
初心に戻って
今日は高校時代の友達Sに会ってきました。Sは当時から非常~に努力家で、恐れ入ってしまうほどに何でも必死に努力する人でした。(受験生時代には一日平均12時間、最長18時間勉強したとか…)そんなSは実は自分より一足早く、大学院の修士課程で留学しようとしていたことが発覚しました!結果的に第2志望は受かったものの、日本の大学に残ることを決め現在は都内の大学院で研究を続けています。高校のときまでは勉強にしても何にしても、同じような事をしているので程度の差こそあれ、自分の理解できる領域のことが多かったので相手が何をしているかつかみやすく、自分と相手との距離感も取りやすかったんですが、さすがに大学院ともなると、相手の話も専門的過ぎてほとんどわからなくなってくるので何だかすごくかっこいい事をやっているように見えました。特に、非常に努力をしてきた人なので、それが長い時間を経て着実にその人の血肉になっているのがわかり8の尊敬と、2の焦りを感じながら別れました。このところ、改めて思うのは「長い間努力してきた人は、報われているかどうかは別としてその時間の間に着実に変わっていっている(しかも恐らく良い方向に)」ということです。まあ、言ってみれば当たり前のことなんでしょうが大学くらいまでは皆が同じ事をしていたので、違いがあったとしてもそれが表面に出てきにくいし、お金のような数値的な基準が明確ではなかったこともあってかどれくらい頑張っているかというのが、表面に出てくることはまれだったように思います。それが、就職などで各分野、全く違う人生を歩みだした途端にはっきりと現れてくるのだから面白いなあ、と思いました。それと同時に、そうした努力を怠ってきた自分が、そんな彼らから取り残されたような気になり少しだけ、焦りました。でも、すぐに焦ってもどうにもならないのでもとに戻りましたけど。今自分がするべきことはなんだろう。その「するべき」の基準が少しづつ変わり始めています。以前は「ある目標達成のために」だったり「社会一般の慣習において」でした。今は…何だろう、「当たり前のこととして」かな。当たり前、という基準もかなりあやふやなものなので結局明確に定義することはできないのかもしれないですが、以前よりもずっとシンプルで、楽なものに変わってきたように思います。うまいこと力が抜けた、というのかな。結構自分の今の立場に危うさを感じながらも、多すぎる情報に惑わされないで初心に戻り淡々と飄々と生活していこうと思う今日この頃です。あ、ちなみに今日会ったSは大学では主席だったそうです。やっぱりその努力は見習わなきゃかな。そろそろ自分の事ばかり書くのは終わりにしよっと。
2005年10月17日
コメント(1)
-
想像力
先日の長ーい更新から、また少し落ち着いて考えてみました。結局、迷い迷ってもといたところ、と書きましたがその、もといたところ、にいた頃に読んでいた本を改めて読み返してみました。その本は出口先生という大学受験の現代文の予備校教師としてはおそらく日本一有名でかつ自分の知る限りでは唯一現代文を超えた、更に上位の部分まで教えてくれる先生です。(あ、スピリチュアルという意味ではないです:笑)本の名前は『きのうと違う自分になりたい』中経出版で、丁度浪人生で人生に一番迷っていた頃に読んだ本です。(いかにも、って感じのタイトルですよね)さて、この本は個人的に当時非常に衝撃を受けた箇所があったということでアマゾンで先日買いなおしましたが、改めて今読んでみると、自分が忘れてしまっていた事や当時は気がつかなかった大切な考え方がたくさん含まれていました。こんな本を当時の自分は読んでいたとは、タイトルに魅かれたとはいえ良い選択だったと思いました。もともと、当時は環境問題に興味があって農学部を志望していたんですが環境問題といっても非常に広範に渡る分野なので詳細な専攻を決めかねていたのとあまりに深刻な問題であるように見えたため、焼け石に水であるように感じられてどういう道を辿ろうか、非常に迷っていた時期でした。そんなときに、この本の中でこんなくだりを見つけました。(長いけど引用します。著作権大丈夫かな…笑)相手の立場に立ち考えるためには想像力が必要であり、同情というのは世間で言われているマイナスのイメージのものではなく、相手の気持ちを理解するために必要な感覚である。という内容の文章の続きです。あなたが、居間でテレビを見ていたとする。画面にはどこかの国の戦争が映し出され、両親を殺された幼い子供が、親の死体にすがって泣いている。可哀相に。誰もがそう思うだろう。だが、はたしてそれが同情であり得るのか。それが同情になるにはいったい何が必要なのか。同情とは、相手と同じ感情を自分の中に抱く好意を指すと、先に述べた。親を亡くした子供と同じ感情を持つことが、はたして私達には可能であろうか。その子供は、まだ幼いのに、これからたった独りで生きていかなければならないのである。その日の寝るところ、食べるものもないかもしれない。しかも、子供というのは独力で困難な状況を克服することができない。そのときの子供の心には、悲しみや絶望以前に、言葉にならないほどの恐怖が渦巻いているのではないだろうか。そのうえ、子供は大人以上にむき出しの繊細な神経を持っている。そうした子供の感情と、もし私たちが同じ感情を抱くことができるのなら、それは素晴らしいことではないか。そのためには、強力な想像力がいる。もちろん、まったく同じ感情を抱くことなど不可能で、要は程度の問題である。違った環境に置かれた私達が、ほんの少しでもこの子供と同じ感情を抱くのならば、居ても立っても居られなくなるはずである。それでも、私達は何もできないというジレンマに立たされるであろう。でも、こういった想像力を身につけている人間は、必ず人生のどこかで何かをするだろうし、少なくともその人の中には弱いものに対する優しさが芽生えるはずである。こんな文章でした。この文章を読んで、まさに強烈なジレンマに襲われたのを憶えています。もし自分がそんな状況にいたとしたら、そう考えると恐ろしいという言葉では言い表せないくらいの真っ暗闇に放り込まれたような気分になり、それと共に、今そんな状況にいる子供が数多くいるにも関わらず自分は何一つできることがないということに、壮絶なジレンマを抱えました。人生のどこかで何かをするだろう。きっと自分はそうだろう。そう直感したことを、今でもはっきりと憶えています。もっとも、それからもう何年も経っていたので、そんな気持ちはすっかり薄れていつの間にか自分の事で精一杯になりすぎて、人の気持ちを考えるとか、相手の立場に立ってみるとか、そんな余裕をすっかり無くしてしまっていました。そんな中、前の日記で書いたような大きな気づき、原点回帰をすることができました。上に出した文章は、自分の原点ってどこだろう、と考えたときに真っ先に思いついたものだったんです。理屈でも感情でもなく、何もしなくても心の底から湧きあがってくる、自分でも止めることのできない想い、それがあの文に書かれていました。そこで、自分は改めて、その想いに素直に生きてみようと思います。…とは、言えません(笑)当時は、何があっても上の文にあったような子供達のために何かをしたい、自分の人生をそれに捧げたい、それくらいの気合を入れていました。しかし、そうやって人のために、という気持ちだけでは不十分なんじゃないか、そう思えるようになったのは、最初に読んだときからの成長なんでしょうか。もし、自分が非常に辛い立場にあったとして、それを助けてくれる、救ってくれる人が現れたとしたら、どんなにか感謝することでしょう。それこそ、一生ご恩は忘れません、という位の気持ちになるでしょうね。でも、その人がもし自分を助けるために家族を捨てていたり、自分は幸せだと思えていなかったりしたら、その事をもし助けられた方が知ったら、その時にはどういう気持ちになるんでしょうか。少なくとも、手放しに喜ぶことはできないはずです。先日、AYAねえさんのブログで書かれていたのがヒントになったんですが自己犠牲、というのは一見非常に崇高なものに見えるかもしれないですが、それが本人が「自分を犠牲にしてでも」というような、ある種後ろ向きの動機でなされた事であるときには、手放しに賞賛できるものではないように思うんです。もし、自己犠牲というものが本当の意味で素晴らしいとすれば、それは本人には犠牲という感覚はなく、ただ自然にそれをすることがその人にとっての喜びであるからやっているだけ、それが周りからは「犠牲」に見える、という場合だけなのではないでしょうか。そんな風に思ったんです。そう考えたとき、確かに自分は何かをしたいし、するだろうけれどもその時に自分を犠牲にしてまで、という気持ちではいけないだろうと思ったんです。そうではなくて、自分がまず幸せだと思えること、それが最優先で、その前提があって初めて誰かに手を貸すことが本当に意味のあることになるのではないか、今はそんな風に考えるようになりました。もちろん、何かをしたいという気持ちに変わりはありません。むしろ大きくなっているくらいです。でもだからこそ、安易な手助けはしたくないとも、思ったんです。もっとも、それが正しいのかどうかは、誰にもわからないと思うんですけどね。いずれにしても、自分としてはそこまで考えが至ったということはこれまでの長い試練の時間も無駄ではなかったのかな、と思えるきっかけになりました。まだまだこれからたくさんの気づきや学びがあるとは思いますが、ひとまず自分の芯になってくれそうな感覚をつかむことはできたと思います。まあ、実際に現実的にはなかなか簡単には事は運ばないわけですが…しばらくの間スピリチュアルなものに浸っていたこともあって、ここで書いたことはかなり観念的で抽象的なことではあるんですが、これはあくまでも自分が学び、考えたことをただ文章にしただけです。それが結果としてこうしたものになるというのは、もともと自分はスピリチュアルな素質があったということなんでしょうかね?(笑)いずれにしても、今言えることは、今までで最も確かな一歩を踏み出すことができたということだけですね。それが正しいのかどうかは、今はわからないですが。ちょっと堅い話が続いてしまったので、今度はもっと柔らかい文章にしたいなぁ。では、良い週末を☆彡
2005年10月14日
コメント(2)
-
ひと区切り
この数日間の間、久しぶりに自分の世界が変わるような体験をしました。というか、まだその中に居ます。たかだか1週間程度の間に、何人もの人から様々な指摘を受けてその度にどうしようもないほどの衝撃を受けていました。あまりにもそれらが的を得ていたので、ちょっとエネルギーを使いすぎてしまいしばらく何もせずに過ごしました。そうしてしばらく時間を置いてみて、ようやく見えてきたもの。それは自分が数年間ずっとしてきた勘違い、というか思い違いです。結果としてどういうことを自分は間違ってきてしまったのか。それは大学に入った頃に考えた「目的論」と「結果論」という考え方です。一般的に「目的論」というと『哲学で、すべての事象は何らかの目的によって規定され、その目的に向かって生成変化しているとする立場。』のことを指し、「結果論」は『原因・動機などを考えずに、物事の結果だけをみて行う議論。』のことを指すそうです。(共に大辞泉より)しかし、当時自分が考えていたのは何かを頑張るときにどういう気持ちで物事を頑張ろうとするのがいいのか、ということでした。(丁度大学受験の後でしたから。)自分なりの言葉で目的論と結果論を説明すると目的論は『○○大学に入りたいから頑張る。』という考え方で結果論は『頑張った結果、○○大学に合格した』という考え方です。これだけ見ていると、ほとんど変わらないし、どちらでもいいような気がします。どちらがいいかは別として、自分がどうだったという事だけ言うと高校生くらいまでの自分は丸っきり結果論的な考え方だったので、いわゆる「人事を尽くして天命を待つ」という言葉が大好きでした。できる限りのことをきちんとやったら、後は結果に従おう。落ちても受かっても、自分にふさわしい結果が自分に来る。というようなある意味の潔さがあったように思います。それに対して、大学受験に失敗して希望の大学に入れずその結果入った大学に満足できなかった自分は、いつしか「やっぱり、ちゃんと目標を設定して、それに向かって戦略を立てなきゃダメなんだ!」という風に考えるようになっていきました。もちろん、それ自体がいけないのではなくて、「自分に合わない考え方を『無理に』しようとした」ことが問題だったのだと、今は思います。それ以来「○○のためには△と□を~までにやって、その次は…」というように頭の中でどうしたらゴールにたどり着けるのか、ひたすら最短ルートを考えてその途中にあるものは全部飛ばして、一直線にゴールに向かう、そんな生活スタイルが身についていきました。自分では意識していなかったんですが、途中の無駄と思える過程は全部飛ばして必要だと思えるところだけを取ることに一生懸命になりすぎていたので周りの人の言うことも、全然聞いていませんでした。自分の考えに合う人の言うことだけ聞いて、合わない人の言うことは全部無視。もちろんどれも話は聞いていましたけど、都合の悪いものはすぐ忘れる。そんな事をしていたように思います。というのも、今思い出せる人からのアドバイスって自分に都合のいいものしか、ないからです。でも、あるときふと思いました。「で、自分の人生のゴールは何だ?」「あれ……全然わからないぞ…」「まずい…、これじゃあゴールへの最短ルートも作れない、 というかそもそも道が全く見えない…」正直、これにはすごく焦りました。ゴールさえあればそこに向かってまっすぐに走るのはすごく慣れていたのでいつの間にか、それしかできなくなっていたんです。でも、そもそも人生のゴールなんて、すぐに見つかるものではないですよね。ちなみに「ゴール」というとちょっとわかりにくいですが、これは「人生の目標」とか「本当にやりたいこと」とか「夢」というイメージの言葉です。(以下「目標」にします)どちらにしても、そうなってしまっては自分は目標なしには走れません。すぐに目標探しに走りました。そう、「目標を見つけることが目標」になっていったんです。結局今の時点でも見つけることはできていません。というよりも、そんなものをはっきりと見つけられる人なんているんでしょうか?と思うようになりました。確かに、目標を設定してそれに向かう戦略を立てて実行する、というのは非常にシンプルで確かな考え方ですが、そもそもそれが当てはまるのって生活の中の末端の部分の話ばかりで、一番根本的な人生の目標みたいなものにはまず当てはめられないような気がします。この考え方はライブドアの堀江氏も言っていたことで、それもあって実践している時にはすごくシンプルで強力な考え方だ!これで自分は一気に成長した!と思っていました。でも、いろんな落とし穴があることには気がつきませんでした。目標が見つからないことには使えないのは言いましたが、それよりももっと重要なのが「途中で目標を変えにくい」ということなんです。つまり、目標まっしぐらになっていると「人の話を聞けなくなる」ということ。自分の目標しか見えなくなるので、それが仮におかしかったとしても気がつかないし人がせっかくアドバイスしても、それは目標に向かうための障害にしか見えず結果としてまるっきり人の話を聞かずに突っ走ってしまうことになるわけです。「自分は確実に前に進んでいると思い込んでしまう」わけです。自分は一度火がついたら一気に進んでしまう性格なので、これでうまくいくと思ったら何でもかんでも当てはめて突っ走ってしまいました。そんな落とし穴に、しっかりとはまってしまっていることに気がついたのが、つい先日の友達や家族からの助言だったんです。もちろん、「目標を設定して戦略を…」という考え方でうまくいく人もいると思います。ただ、それが自分にとってベストなのかはまた別問題。実際に、そうやってひたすら一直線に進もうとしていた自分は友達や家族からみて「らしくない」「頑張りすぎてる」「余裕がない」というように見えたそうです。ただ、自分では全く気がついていませんでした…今日ふと思ったのは、やっぱり自分には自分に合ったやりかたなり考え方があってこれまでいろいろと迷ったり悩んだりしてきたものの、結局行き着くのはもともといたところなんじゃないかな、ということです。今振り返ってみれば、そうやって自分に合わないような考え方で頑張って前に進もうとしていたときには、自分自身が意味もなくすごく焦っていて何故か怖い事ばかりで、何より「楽しい」という感覚がどこかにいってしまっていました。それはやっぱり、自分の中の何かが「今の自分はおかしいぞ」というシグナルを出していたんだろうと、今では思います。少し前の、高校生くらいの頃を振り返ってみれば自分は随分肩の力が抜けて、楽に生きていたような気がします。もちろん、まだ高校生だったから気楽だったというのも多分にあるとは思いますが多分、当時の自分が一番「らしかった」んじゃないかな、と思います。友達や家族に聞いてみたところ、やっぱりそうだったと言われました。当時考えていたのはどんなことだったのか、はっきりとは覚えていませんがすごく重要な自分のモットーとして「結果を急がない」というのがあったような気がします。あるいは「やるだけのことをきちんとやることに集中する、後はあれこれ心配しない」つまり『なるようになる!』という事でしょうか(笑)でも、そういえば、何か目標に向かって無理してでも頑張ろうとしていた大学受験時に比べて「やるだけのことをやろう」「これだけやってダメならしょうがない」と思えていた大学院受験のときのほうが、随分と気が楽だったし、たまたまかもしれないですが結果も良かったように思えます。(もちろんその一言で片付けられるものではないですが)それは多分、そういう考え方、生き方が自分に合っていてその自分に合った進み方をしているときの方が良い結果が出る、ということなんじゃないかと思います。もちろん例外はあるかもしれないにしても、自分にひたすらムチ打って「頑張ろう、頑張ろう」として生きるよりも、自分にとって自然に感じられるやり方で、やるだけやって後は流れに任せてしまうくらいの余裕を持っていたほうが、最終的に自分は幸せに生きられるんじゃないかなぁ、そんな風に思ったのが、つい数十分前の事なんです。そして、「よし、それじゃあやっぱりそうして楽にやってみよう」と思ったら、ようやくこうしていろいろな事が言葉で整理できて説明できるようになり、意味もなく焦りを感じることもなく、落ち着いて言葉を並べることができたんです。そして何より、自分にいろいろな形でアドバイスをくれた友達や家族に本当にたくさん迷惑をかけたなぁ、ととっても申し訳なく思うと同時にそれでも自分を見ていてくれて、見捨てずにアドバイスをくれたことに本当に、本当に心から感謝できたわけです。いい友達を持ったなぁ、いい家族を持ったなぁ、そう思えるのってすごく幸せなんですね。この話をまとめられるようになるまで、何年もの間T君にはとてもお世話になってきました。彼は高校からの親友で、大学受験に失敗したときや大学院に合格したときも含めて随分といろいろと語り合ってきましたが、今回の事ではかなり険悪なムードになったり、相当不愉快な言葉を言ったりしてしまいました。それでも、何だかんだで彼が一番最後に「おう、なら頑張って☆応援するんで」とサラッと言ってくれた事には、人生で一番感謝しました。本当に、嬉しかった。何だかすごく遠回りをしてきて、結局最後にはスタート地点に戻ってきたようなそんな気がする今日この頃ですが、結果としてそれで良かったのかな、とも思います。スーパーで野菜を選ぶとき、いろいろ迷ってみて、結局もともと持っていたものが一番良かったなんて良くあることですし。それくらいの、気楽なとらえかたができるようになれば自分も大分「らしさ」が戻ってきたのかな、なんて思えるようになりましたし。この文章は、決して詳細を全部書いているわけでもないし結構省略したり脚色したりしてはいるんですが、今一番重要なのはこうやって自分がずっと抱えて迷ってきた大きな石を一つ手放すことができたという事です。それだけで、これからの自分も変わっていけるんじゃないかな。それも楽な方に。そんな気がします。すぐに自分が変われるかどうかは別として、これが一つの区切りになるのは確かだと思います。もちろん、この気づき自体が間違っている可能性もあるんですが、少なくともこれまでの自分の「落とし穴スタイル」よりはもっと自分に正直な生き方ができると確信しています。本当は、それで今度は何をしようと思っているのかも書くつもりでしたがちょっと長くなりすぎたので、また次の更新で書くことにします。ひとまず、今日言いたかったのは、このことに気がつかせてくれたT君を始めとする自分の大切な友達と、普段から迷惑かけっぱなしにもかかわらずちゃんと自分のことを見ていてくれる家族に、心からありがとうと言いたい、それだけです。本当にどうもありがとう。そして、これからもよろしく!読んでいて抽象的でわかりにくい部分も多々あったかもしれないですが、最後まで読んでくれて、どうもありがとう!!良い一週間をお過ごしください(-人-)☆彡
2005年10月12日
コメント(0)
-
久しぶりに更新してみて
昨日久しぶりに日記を更新したら、早速何人かからコメントをもらいました。アクセス数もしばらく水面ギリギリだったのに、一気に増えていました。何となく書いていたつもりだったこのブログでも自分が思っていた以上にたくさんの人が見てくれているんだなぁとちょっと実感してしまって、とても嬉しくなりました(*^o^*)そういえば、ここのところあれこれ悩んでいたり、忙しかったりしたのも手伝って全然更新をしていなかったけど、それも元を正せば、いつの間にか「いいこと書こう」とか「かっこいい事言おう」と思ってネタを温め過ぎて、逆に書きづらくなっちゃった…という悪循環にハマッていたからなんじゃないかな、と思います。昨日、万物は流転するというタイトルに変えてみてもっと気楽に毎日変化していく自分の足跡を残していくくらいのつもりで、つまらない事でもマイペースで続けていく方が自分らしいじゃん☆、と思いました。ということで、これからは少し力を抜いてまさにつれづれなるままに、その日の出来事や感想なんかをつらつらと、『なるべく』毎日更新していけるようにします。やっぱり、頭が先行してしまうと手が動かなくなっちゃうんですね。そうじゃなくて、手を動かしながら、勝手に動く頭で考える。そんなイメージでこれからは書いてみようと思います。改めて、見に来てくれたり、コメントを下さる皆様どうもありがとうございます!今日は就職した先輩に「やっぱりに人の縁は大切だね」と言われました。今まで何度も聞いたし、自分も言ってきた言葉ですが改めてこのブログという場でつながることができたご縁に感謝してこれからもそれを温めていけるようにしたいな、と今日は思いました。
2005年09月29日
コメント(2)
-
panta rhei
タイトルを変えました。panta rheiは「パンタ レイ」と読みます。古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスが言った言葉ですが、雅代さんが紹介していたアインシュタインの「唯一の普遍は変化」と同じ意味です。日本では鴨長明が書いた方丈記の冒頭「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず」というくだりがありますが、やはり同じ意味です。自然界では変化こそがあるべき姿ですし、このブログも変化していかなくては。そう思ってタイトルから変えました。これから徐々に元気に更新していきます!
2005年09月28日
コメント(4)
-
雨ニモマケズ
この頃、余裕があります。ちなみに、心の余裕です。金銭的なものではありません(笑)先日、ヤンキースの松井こんな事を言っていました。好調が続いていた中、その日はノーヒットだった時(のはずです)のインタビューです。「今はそう簡単に崩れない感じがしてるんですよね。一つ一つ、段階を踏んで来てるから。同じことですよ、どんな時でも、やり続けるのは。」これが、まさに「余裕」ですよね。「そう簡単には崩れない」という「感じ」。その感覚が心にゆとりをもたらすんでしょうね。今の自分にもその感覚があるんです。木で例えるなら、風が吹くだけで吹き飛ばされてしまいそうな程細かった木の幹が、今は雨や風ではびくともしない、太い太い幹になったような気分です。そう簡単には、倒れません。写真は、旅行で行った青森県の世界遺産である白神山地にある、樹齢400年にもなる「マザーツリー」と呼ばれるブナの木です。まだまだ自分は、こんなに太い幹を持ってはいないけれど、いつかは地に深く根を張り、どっしりとした幹を持ち、静かに大地にそびえ立つこの木のようになりたい、そう思うわけです。また、何かがつかめそうな気がしています。
2005年07月28日
コメント(5)
-
久しぶりの更新です☆
随分と長い間お休みをもらっていましたが、いよいよ仮始動です☆まだ本格的に始動するわけではないので、これからちょっとづつサイトの雰囲気もいじりながら、自分のペースで更新を続けてみようと思っています。しばらくお休みしていた一番の大きな理由は、「自分が変わった」から。もっとも、いつからというのははっきりとは言えないんですが。ブログを始めてから数ヶ月の間に、自分は常に変化してきました。アインシュタインが言っていた様に「唯一の不変は変化」です。自分も日ごとに、いやむしろこの一瞬一瞬毎に変化していきます。中国の諺で「男子三日会わざれば刮目して待つべし」というものがありますが、自分も男子、数ヶ月も時間があれば驚くほどに変化していくものです。その変化に伴って、ある意味で自分の分身でもあるこの日記も変化を遂げていくべきだと思っていたんです。が、自分がどう変わったのか、またどう変わっていくのかということがわからなければ、この日記も自分の変化に連動して変えていくことができません。そのため、自分がこの数ヶ月の間にどう変化していったのかを探る必要があったのです。タイトルには(仮)とつけました。「つれづれなるままに…」というくだりで始まる徒然草。しばらくは吉田兼好のコンセプトと同じく、とくにテーマを決めず、肩の力を抜いてあれやこれやと思うことをつらつらと述べてみようと思います。そのうちに、明確なテーマが見えてくるかもしれません。今の自分には一番そんなスタンスが合っているような気がしました。ちょっと今までの日記とは雰囲気が変わるかと思いますがどうぞお時間の許す限りお付き合い下さいo(^-^)o
2005年07月19日
コメント(4)
-
脱皮中
しばらく更新を見送っています。ただいま脱皮中。脱皮をすると、時に全く違う姿になることもあります。でも、姿は変わっても、本質は変わりません。新しいステージにむけて、しばし充電中ということなんです。
2005年07月03日
コメント(5)
-
減点法と加点法
今日は張り切っていきましょう☆テーマは「減点法と加点法」です(^-^)今まで読んできた本やブログでもいろんな方が言っていましたが、世の中の物事の評価の仕方は、基本的に「減点法」と「加点法」の2つに分けることができそうです。(その他の考え方があればコメント下さい☆)それについてやっと、自分なりの解釈ができるようになったので、紹介します♪(2つの考え方の正確な定義は知らないので、自分なりの解釈で 説明をしている点はご了承下さいね。)まず減点法と加点法はどんなものかですが、100点満点のテストを例に出して簡単に説明すると、減点法は、100点満点中で間違ったところから点を引いて残ったものが自分の点数で、間違ったところを直せば100点に近づくという考え方ですね。それに対して、加点法は丸がついたところの点数を足していくことで自分の点数が決まって、丸の数を増やしていけば100点に近づくという考え方ですね。日本の学校では基本的に減点法が採用されているので、加点法の方はイメージがしにくいかもしれないですね。ちょっと一般化してみるとわかりやすいかもしれません。減点法では、足りないもの、問題のあるところにフォーカスしていってそれを改善することで物事をより良くしようとする考え方で、対して、加点法では今、手元にあるものにフォーカスして、それをどんどん伸ばしていく事で物事を良くする考え方と考えてみるとどうでしょう、少しわかりやすくなりましたか?さて、このところずっと気になっていたことが一つあるんです。それは、私の周りには減点法派(?)が多い、ということです(;^_^Aこの2つの考え方は、基本的に同じ事を別の視点から言っているだけなのでつまるところ、言っている事は同じはずなんですが、フォーカスするところが違うので、言い方も大分変わってくるみたいなんです。その違いがわからなかったので、友達や家族と同じことについて話していても何か噛み合っていない様な感じがしてずっと気になっていたんですよね。でも、この2つの見方の違いに気がついたら、すっきりしました。だって、つまりは「同じ事を言いたかっただけ」ってことですから(笑)これって、ものの見方だから絶対どちらがいいという事はないと思います。ただ、どちらの方が自分に合っているか、という意味ではそれぞれで違うんだということがポイントですね☆個人的には「今あるもの」にフォーカスする加点法の方がしっくりくるのでこれからは少し意識して加減法的に、「今あるもの」についてフォーカスしてみようと思いました(*^_^*)ということで、早速「やるべきことリスト」を「やったら10点プラスするリスト」に改名します(笑)やるべきことをいっぱい書き出すと「まだこんなにある…」と考えちゃうので一つやったら10点づつプラスすることにします。その日の終わりに、何点取れたか集計してみることにしました♪さて、明日は何点取れるかな~☆
2005年06月05日
コメント(3)
-
油絵
先日、ある方に聞いたお話が印象的だったので簡単に要約して紹介します(^-^)人生ってのは、油絵みたいなもんだ。油絵ってのは一回絵の具を乗せただけじゃ、何の深みもないものなんだ。何度も何度も上から絵の具を重ねていって始めて、深みのあるいい絵になる。人生ってのもそれと似たようなもんだよ。何度失敗したって、また上から絵の具を重ねていけばいいんだ。できる絵は、最初に描いたものとは違うものになってるかもしれないけどそっちのほうが深みのあるいい絵になっているはずだ。このところ少し守りに入っていた自分には、とても響く言葉でした。また、後世に残したい言葉が増えました(笑)
2005年06月02日
コメント(5)
-
ホープレスではなかった
今日はYahooである記事を見つけたので、簡単に更新します。Yahoo ニュース不屈の男、米で映画化 服役→子連れホームレス→証券で成功、億万長者今流行の成功法則本を開けば、この手の話は枚挙に暇がありません。それでも、彼のお母さんの言葉はきっとある種普遍的な法則なんでしょうね。そんなことを彼のお母さんのこの言葉を見て思いました。そして自分も、いつかきっと子供に同じ事を話してあげるんだろうと思いました。『あなたが望むなら、百万ドル(約一億円)だって手にすることができる』と。(決してお金の問題ではないことは、わかりますよね?(;^_^A )強く望むこと、自分を信じること。シンプルですがパワフルな法則じゃないでしょうかね(*^_^*)
2005年05月25日
コメント(4)
-
充電中…(ρ.-)
10日間、ずいぶん更新をさぼってしまいしたね(;^_^Aというか、このところ連日の畑仕事で疲れ切っていたので少しお休みをもらっていた…つもりです(笑)さて、今日のお題は…と言いたいところですが、どうやらまたサイトのリニューアルをする時期になってきたみたいです。このところ学ぶことが多すぎて、今までのスタンスの書き方では書きたいことが全部表現できなくなってきていたので、子供が成長するにつれて、好みや趣味も変わってくるように自分が変わったら、サイトも変えていくほうが良いみたいです。変化の多い時期には、ものを変える頻度も増やすほうがいいですよね。ということで、研究室の田植えが終わるまで、もう1週間くらいお休みしてサイトの雰囲気を一新しようと思います(^-^)田植えが終わったらまた更新を再開しますので今後ともあつしの銀色スプーンをどうぞよろしくお願いします(-人-)それでは、皆様良い一週間をお過ごし下さい☆
2005年05月22日
コメント(6)
-
ほめて伸ばす時代
前々回の矢野祥君の話の続きを更新したいんですが、これは何とか納得のいくものを書きたいので、今日ちょっと違うお題について書かせて頂きます(^^ゞもうちょっとそのお話の更新は待って下さい(-人-)今日は別の話ですが、これも自分としてはずっとずっと書きたかったものなのでちょっとお時間を取って頂けると嬉しいです☆さて、今日も前々回の子供はみんなスペシャル♪につながる子供のお話です☆「子供はみんなスペシャル」というのは、私の受け取り方としては子供はもともとみんなすごい才能をたくさん持って生まれてくるそれぞれがスペシャルに素晴らしい存在なんだよ!という事を一言で表した、素晴らしい表現だと思ってます(^-^)この表現は先日紹介した矢野祥君のお父さんが、本の前書きで話していたお話から取ったものです。本当に子供の事を愛しているんだなぁ…というのがとっても伝わってくる、いい文章を書かれています。さて、その祥君のお父さんやお母さん、そして先日読んだ小林正観さんが共通しておっしゃっている事があります。それが「子供をみんな肯定してあげる」 ということです。子供のうちは(個人的には大人になってからも、だと思いますが)いろんな事に興味を持ったり、何かに熱中したりするのってすごく自然な事ですよね。そのために他の事がお留守になっちゃう事もしばしば。例えば、セミの幼虫の孵化する直前の様子をご飯も食べずに何時間もじぃ~っと見ている子供だったり、絵本が好きで好きで遅くまで読みふけってしまう子供だったり。そうやって没頭しちゃっている時に、普通は親からどう言われるでしょうか?「セミばっかり見ていないで、早くご飯食べなさい!」「遅くまで本読んでないでさっさと寝なさい!」なんて怒られちゃったこと、誰でもあるんじゃないでしょうか。でも、どうやら本当に自分の才能を伸ばせる子は、こう言うときの親の対応が大分違っていたようです。子供が何かに熱中しているときには、それを気が済むまでさせてやってその後で「何見てたの?」「どんなお話だったの?」「何がわかったの?」という形で、全部一旦肯定してあげる。そしてそこで子供が得たものを子供に説明させてあげるようにするそうです。そうすると、子供はすっごく喜んでいくらでもお話してくれる。今こういう事を言っても、ある程度年をとってしまうとそれほど熱中してしまう感覚はわからなくなってしまうかもしれませんね。でも、思い出してみてください。子供のとき大好きだったウルトラマンやカブトムシ、女の子ならお人形や友達とのおままごと、○○ごっこなどなど、そのことについてだったらいくらでも親にお話しできちゃうぞ!っていうような事が、誰でも一つ二つはあったと思うんですよね。で、そういうお話を「へぇ、すごいね~☆」 「よく見つけたね~☆」「とっても面白いね☆」 「もっとそのお話聞かせて?」と言った感じで、お母さんやお父さんに聞いてもらえたらきっとものすごく嬉しかったと思うんです。話しているときも、とっても自信満々だったと思うんです。「○○ばっかりしてないで…」と言いたいところをぐっと押さえて、子供がやっていることを認めてあげる♪そうしたら絶対子供は元気になると思いませんか?(^-^)☆さて、ちょっと前置きが長くなりましたが、今日のタイトルでもある「ほめて伸ばす時代」という言葉の意味を説明します。これは今までずっと不思議で不思議でしょうがなかったことから来ています。それは、「どうして宿題をやらないと怒られるのか」ということです。大抵の場合、宿題を忘れるとドラえもんののび太君みたいに「廊下に立ってなさい!!(ちょっと古いかな)」なんて感じで怒られて罰則を科せられるのが普通ですよね。小林正観さんの本で「先生に『なぜ宿題をしてこないと生徒を立たせるんですか?』と聞くと 答えられる先生ってあんまりいないですよね。」と書かれていました。もう、ほんとその通りだと思います☆☆自分も昔「何で○○しなきゃいけないの?」「何で○○しちゃダメなの?と何でも親に聞きまくるナゼナゼ坊やでした☆(親にしてみれば厄介な子供ですよね:笑 今もそのまんまですが…)とりあえず宿題をやるのはいいとしても「どうしてやらないとダメか」というのはず~っと不思議でしょうがなかったんですよ(;^_^Aで、結局は「なんでも!」とか「やらなきゃいけないから、やるの!」というちょっと意味不明な理由で強引に納得させられていたような気がします(笑)でも、今考えてみても、やっぱり変なものは変ですよねぇ(笑)そもそも「~しなきゃダメ」「~しちゃダメ」という教育の仕方って、普通に考えておかしい部分がいっぱいあると思うんですよ。でも、そうは言っても、それじゃあどうするのさ?という事ですが正直言ってしまえば「どうして○○か」という質問って、確実な答えがない場合がたくさんあると割り切る一番だと思います。先の宿題の例なんかがいい例ですよね。そこで自分としてお勧めしたいのが、また小林正観さんの本のお話になりますが「じゃあ逆に宿題をやってきた生徒がいたらその生徒の名前を言って みんなで拍手してあげましょう☆」だと。これ、どうですか?パチパチパチパチ☆☆(大拍手:笑)今必要なのって、こういう発想じゃないでしょうか☆30人中4人だけやってこなかったら、次は拍手して欲しいと思ってその内少なくとも2人位は宿題をやってくるんじゃないでしょうか?仮にやってこなかったとしても、やらなかったことを怒られて罰を受けるよりも、遥かに気持ちが楽ですよね。つまり、今日の話全部をまとめると、タイトルの通りこれからは『ほめて伸ばす時代』になるんじゃないか?という事です。今までのようにできないこと、やらなかったことをあげつらって責めるような器の小さい教育の仕方ではなくて、できたところに注目してあげる。そんな伸ばし方が、これから求められてくる主流になるんじゃないでしょうか。ちなみに、これって前に書いたどうやったらできるか? の発想に似てませんか?「できない理由」に注目せずに「どうしたらできるか」に注目する。「何ができなかったか」に注目せず「何ができたか」に注目する。 この視点の変え方は、あらゆる部分で応用できると思います。素直に考えてみて下さい。誰だって「ほめてもらったほうが頑張れる」と思いませんか?では、最後も小林正観さんの言葉で締めくくります。「宿題をやらなければいけない」といった『ねばならない』じゃなくて 「やったら、えらいね」って言って抱きしめてあげましょう、喜んであげましょう。子供というのは、誉められるのが嬉しくて生きている存在なのですから。
2005年05月12日
コメント(9)
-
ちょっと中休み…感謝の言葉
さて、前回紹介した矢野祥君ですが本編に行く前に、ちょっと中休みを頂きます(;^_^A今日は『ありがとう』という表現についてちょっと思ったことをつらつらと書かせて頂きます☆今日お会いした方々の口から、何度も何度も「ありがとう」という言葉が出てきました。ありがとう、っていうのは感謝を示す言葉ですが同じ意味として、日本では「すいません」の方がよく使いませんか?荷物を持ってもらって「すみません」席を譲ってもらって「すみません」何か手伝ってもらっても「すみません」……あれ?何だか謝ってばっかりだぞ?(笑)以前アメリカやアフリカに言ったときの事なんですがふと思い出してみると、どこへ行っても、何をしてもThank you! とかAsante sana! (スワヒリ語のThank you)と言っていたような気がします。お店でコーヒーを受け取るときもThank you!スーパーで会計してもThank you!お店を出るときもThank you!タクシーに乗ってもThank you!露店や道端のおばちゃんからバナナを買ってもAsante sana!(アフリカではよく元気なおばちゃんがフルーツを売っていました☆)もう朝から晩まであいさつ代わりにThank you Thank youばっかり言っていた様な気がします(自分だけですかね?:笑)今、考えてみるとこれってすごく素敵じゃないですか☆特に買い物するたび「ありがとう!」って言うのって日本ではなかなかしませんしね(;^_^Aせっかくなので、これから1週間だけでいいので、ちょっと意識して「ありがとう」って、たくさん言ってみませんか?自分ひとりで始めるより、みんなでやったほうがありがとうの輪は広がりますしね♪「すいません」って言っちゃうかわりに「ありがとう☆」 こんな発想があっても面白いですよね♪
2005年05月10日
コメント(5)
-
子供はみんなスペシャル♪
さてさて、今日は子育てに関心のある方には自信を持ってお勧めしたいお話の予告編です☆このブログを始めたのが3月の終わり頃です。一番最初に、何を書いたらいいかなぁ…とあれやこれや迷っていた中まず何よりも真っ先に浮かんだのが、今回紹介する矢野祥君の事でした。昨日の日記も、2週間位温めていたものでしたが、こっちはもう1ヶ月です(笑)まさに、あつしの銀色スプーンのブログ史上、最も書きたかったテーマです。矢野祥君という少年の事をご存知の方はどれくらいいるんでしょうか?恐らくアメリカでは相当に有名な少年なんですが、日本では自分以外の人が話題にしているのをまだ聞いたことがありません。一言で彼の事を紹介するならば「史上最年少で大学生になった天才少年」です☆(日本語では相応しい表現が天才という言葉しかないのであえてこう書きます。)彼は9歳でアメリカの大学に入学し、12歳で医学部の大学院生になっています。IQは驚くなかれ、200以上のどこか、すなわち計測不能だそうです。そんな彼の事を知ったのは古本屋でたまたま見つけた「僕、9歳の大学生」という本でのこと。(本のリンクは下にあります☆)何気なく読んだこの本で、まさに体に電気が走るような衝撃を受けたんです!それは何に対してか、9歳で大学生になった天才少年に?そうじゃないんです。彼のご両親の「教育に対する姿勢」に対してです。初めにはっきりと言っておくと、彼のご両親は決して天才ではありません。いわゆる英才教育で幼い頃からビシバシ教育した訳でもありません。では、一体何がそんなに素晴らしいと思うのか。それを次回の日記で書いていこうと思います。その前に先の本「僕、9歳の大学生」はこちら↓http://books.yahoo.co.jp/bin/detail?id=30898186(楽天で取り扱ってないので、直接リンクできないんです)そして、祥君のお母さんが書いた、「私はリトル・アインシュタインをこう育てた」http://books.yahoo.co.jp/bin/detail?id=31109091という本も出版されています。この2冊は、あつしの銀色スプーンの読んだ教育関係の本の中でもまさに座右の書として何度も何度も、本当に何度も読んだ、希代の名著だと思っています。(あ、ちなみにIQを高くする方法などは書いてありませんので そういう効果を期待して読まないでくださいね。)子供を育てている方に読んでみてほしい本を2冊だけあげるとしたら、間違いなくこの2冊をあげるでしょう!確信を持ってお勧めします☆それ位確信を持って紹介しようと思う理由は、次回明らかにします。リンクしたページを読んで、しばしお待ちを☆ヒントは今日のタイトル♪これを読んでいるママさん達へできたら今すぐこの2冊買って読んで下さい!いまいちだったら返金保障します(←嘘です、さすがに無理です(;^_^A )あくまでも主観ですが、それ位の気持ちでお勧めしたい本なんです。子供として、こんな育てられ方したい!そんな思いに駆り立てられました。読んだことがある方は感想をお願いしますね☆他にもよい本が幾つもあるので、追々ご紹介します♪
2005年05月08日
コメント(5)
-
どうやったらできるか?
さてさて、先日のフォトリーディングのちょっと訂正を書いたので見ていない方は先にこちらへどうぞ☆さて、今日のお題は、実は振り返ること約3週間前…4月17日の日記で書くのを先に延ばしてから今まで温めてきた話です。自分にもよくあることなんですけど、新しく何かに挑戦しようとするときや素敵なアイデアが浮かんだときに「でも、自分にできるかな…」って尻込みしちゃって、結局何もせず仕舞いってことはありませんか?あるいは「自分には無理だぁ~(+_+)」ってちょっとビビッちゃって諦めちゃったこと、誰でも一つや二つありますよね。さて、そんな時に心に光明をもたらしてくれたのが一時期、時の人だったほりえもんが言っていた『どうしたらできるか?』を考える。という台詞なんです。これ、実は本田健さんも同じようなことを最新著書「きっとよくなる」の中の「言い訳をしないと宣言する」という見出しの文で自分ができない理由を探し出し、正当化するのが言い訳の本質ですという、先の言葉とは裏返しの表現で言い表しています。どちらの言葉も訴えていることは同じだと思います。「どうしてできないか、ばかり一生懸命探してないで どうしたらできるのか、を頭使って考えなさい」と。どうでしょう?皆さんは 「…だからできないよ」 とか 「~じゃないから自分には無理だよ」 なんて、言っちゃってませんか?ちなみに、自分はしょっちゅう言っちゃってます(;^_^Aせっかくですから、皆さんご一緒に「言い訳をしない宣言」しましょう☆弱気になっちゃったときにはこの言葉「どうしたらできるだろう?」を思い出して、心の中で唱えましょう♪そうやって自分の可能性を一つ一つ解放していけば、世の中ちょっとずつ良くなる…はず(笑)
2005年05月06日
コメント(9)
-
☆ 続・フォトリーディング ☆
昨日のフォトリーディングに思いのほか反響があったのでちょっと焦って更新してます(笑)私はホームスタディ講座でこの3日間やってきましたがブログ仲間でフォトリーディングをやっている人は3日間集中講座で習得された方が多いそうです(;^_^Aで、ちょっと気になったのは、私が本を読むのが速くなったのがフォトリーディングによるものなのか、本の読み方が変わったからなのかちゃんと見極めないと、下手にお勧めしちゃいけないかな、ということです。実は、集中講座やホームスタディ講座で学ぶ内容は実際には写真のように写し取って読むフォトリーディングだけでなく『予習をして、フォトリーディングして、復習をして 更に活性化(再復習みたいなものです)をする』という一連の読み方なんですね。もしかしたらその一連の読み方のおかげで速くなったのかも…という疑問がフツフツと沸いてきちゃいました(笑)これを確かめるためには自分も集中講座を受けてみるしかない!ということで(笑) 近いうちに集中講座も受けてみようと思います☆それで、あまり変化がないようであれば今回速くなったのはホームスタディのおかげ☆ってことになりますよね♪これを書こうと思ったのも、実はホームスタディ講座をやるのには集中講座と同じ3日分位を家などでやらなければならない上に最初のうちはフォトリーディングをするにはかなり集中できる環境でないと難しいという事情があって、もし迷っている人がホームスタディ講座を注文したはいいけど、家などがうるさくて集中できな~い(>_
2005年05月06日
コメント(0)
-
☆フォトリーディング☆
長かったGWも今日で終わりですが、皆様どんな休日を過ごされましたか?(まだ6日休んで3連休が残っている人もいるかもしれないですね☆)さて、今日はこの3日間で学んだフォトリーディングについてです。ブログ仲間の方にはこれを既にやってらっしゃる方もたくさんいますが、すごい人になると毎日1冊の本を読み、それを日記で紹介されています。(→和歌山の風達人 ヒロさんのブログへ)フォトリーディングは、簡単に言ってしまうと本を速く読むための方法です。詳しくは、歩くシンクロマスター・宝地図ナビゲーター・望月俊孝さんのHPで紹介されていますので、そちらへどうぞ☆詳しい内容は、HPや本を見てもらった方がわかりやすいと思うので、今日は自分がやってみた感想を載せることにします(^-^)ちなみに、フォトリーディングは3日間の集中講座か、家でCDを聞きながら学ぶホームスタディ講座の2種類の方法で学べます。私がやったのは、ホームスタディ講座の方なので、そちらについての感想を書きますね。3日間集中講座を受けたことがある方は、是非コメントお願いします♪さて、このホームスタディ講座ですが私自身、感想文にありがちな「正直始めたときは半信半疑でした…」という気持ちでCDを聞き始めたんですが、今ひとまず7枚のCDを終えた時点での感想としては…「もう、今までの読み方には戻れない…(笑)」 です。正直言ってしまえば、今の時点ではまだ本を写真のように写し取る、ということが実感としてはよくわかってないです。が、どうして今までの読み方に戻れないと思うのか、というと、この読み方だと・今までにない速さで、短時間で本の重要な部分を理解できるから・短時間で読んだ割に、内容を今までより格段に思い出すことができるからという2点に集約されますね。実際、今までの読み方で普通に1回読んだ本の内容って、半年後、1年後に覚えてますか?それで素直に「はい」と答えられちゃう人は、ここで読むのを止めていいです(笑)普通の人は、1度読んだだけの本の内容を、1年経っても覚えていることはなかなかできないと思うんです。しかもその1冊読むのに、大抵2,3時間はかけているはずですよね。でも、今はせいぜい30分もあれば、ずっと忘れないくらいの理解度で本を一冊読んでしまうことができる自信がついちゃいました☆今回3日間かけてこのホームスタディ講座を受けてみて、単なる一受講生として思うことは、「今までの数倍の速さで本を読んで、 かつ何年経っても忘れない(というよりは思い出せる)ような夢のような技術 を習得できちゃった。ラッキー☆」ということです。これはすごいですよ~♪近い将来、何か実績を残してこのすごさを証明したいですね☆既にフォトリーダーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします(^.^)まぁ、そうは言っても、きっとこれを読んだだけでは、すぐに申し込もうとは思わないですよね~(;^_^Aでも、それでいいんだと思います。今すぐにやらなくても、いつかまた誰かがフォトリーディングの事を話題に出したときに、あなたの耳がピン!と反応すれば、自分からその話を聞いたり調べたりしようと思うかもしれないですよね。そうしたら、今度は自発的に学ぼうとするわけですから、きっと吸収力も段違いでしょう☆この日記が、そんなきっかけの一つになれば嬉しいです♪明日から、一日一冊を目指して楽しく読書させていただきます (^^))((^^)v
2005年05月05日
コメント(6)
-
改めて『自分発』を考える
しばらく日記の更新をお休みさせてもらっていました。訪問して下さったみなさん、同じ状態のままですみませんでした(+_+)今回は少しだけ思うところを書くことにします。次回はフォトリーディングのことを書く予定ですので、すぐにそちらに飛んでもらっても結構です。お時間のある方は、しばしお付き合いくださいませ。丁度2ヶ月前の3月5,6日に八ヶ岳でソースのワークショップを受けてきました。それからというもの、ソースの勉強会を通じて知り合った方や、講演会で知り合った方々に更に別のセミナーを紹介して頂き、そこで知り合った方にまた別のイベントを…といった具合に、まさに芋ずる式に一気にご縁を頂くことができました。本当に、信じられないくらいのハイスピードで、どんどん素敵な方を紹介して頂けちゃったんです☆そんな嬉しい時間が2ヶ月も続くと、今度は自分の処理速度が追いつかなくなっていたようなんですね。皆さん本当に素晴らしい方ばかりだったので、優先順位なんてつけられず、それこそ一日何時間もメールを書きっ放しでした。そんな中で、このブログを更新するのが後回しになっていたのが事実でしょうか。更新していない間、リンクさせて頂いている方々のハイレベルなブログをたくさん読ませてもらっているうちに、「何でこのブログ書いてるんだっけ?」というところまで立ち返ってみる必要があるような気がしていたんです。そのため、ちょっとブログから離れて、初心に戻ろうと思いました。このブログをリニューアルしたときに考えていたことを振り返ってみて、いつの間にか、あれこれカッコいい文章を書こうと肩肘張っていた自分に気がつきました。「今日はどんなこと書こうかな、ルンルン♪」 と思っていたのが、いつの間にか「今日は何書いたらいいかなぁ、、う~ん((+_+))」とまぁ、ワクワクではなくなっちゃっていましたね(;^_^Aこれでは、ワクワクを発信するという一番重要なコンセプトが見えなくなっちゃいますね。ということで、あつしの銀色スプーンはまた初心に戻り、ワクワクを伝えようとして書き始めた時のことを思い出して、コメントをもらうたびに嬉しくなって書き溜めておいたネタを、また一つ一つ丁寧に書いてみようと思いました。始めたばかりの頃に、ツイてるファシリテーターさんにまずはひたすらGive&Giveするんだよ☆ということを繰り返し言って頂きました。その基本に立ち返ることにします(^-^)得た情報は発信するほどに、自分のものになるという事を丁度、ツイてるアホな学生さんも日記で書かれています。改めて、『自分発』の情報をどんどん出して行こうと思います☆読んでくれてありがとうございます(*^_^*)これからも遊びに来て下さいね♪
2005年05月05日
コメント(3)
-
ドラゴン桜
先日の講演会&パーティーから早4日…『あっ』という間に時間は過ぎてしまいますね。さて、先日の日記で紹介したドラゴン桜ですが、東大合格請負漫画の名の通り、偏差値30台の経営難の高校から東大合格者を5年後に100人出す!という形で一気に進学校に建て直してしまおうとする桜木弁護士の物語です。始めの方こそ、経営難の話ですが、勉強の仕方や指導の仕方の話に入ってくると、英語の勉強法やコーチングの考え方、メモリーツリー(マインドマップ)、疑問を持つ頭の使い方などなど実生活にも役立つような良質の情報が満載です!!特に、普段こうした漫画を敬遠されてしまうような子育てをされている主婦層の方々にも是非一読してもらいたいないようだと思います☆というのも、私が思うにこの本でテーマになっている教育の根底にあるのは「与えられた選択肢の中から人生を選べる人間にではなく、 自分の人生は自分で創れる人間になって欲しい!」というものなんだと思うからです。(自分も心からそう思っています)読むほどに、人に教える、人を育てるって奥が深いなぁ…と思う漫画です。ドラゴン桜、一度読んでみませんか?
2005年04月28日
コメント(8)
-
越山雅代さん講演会&ゲラゲラ強運感電パーティー
参加してきました!越山雅代さんの講演会にパーティー☆会場にいらっしゃった方からキラキラしたエネルギーが見えるくらい本当に活気溢れる、超元気パーティーでした(*^_^*)たくさんの素晴らしい方に知り合うことができて、また 福の神様 が周りにたくさん増えました!! わ~いヾ(@⌒▽⌒@)ノさてさて、今日は多くの方があつしの銀色スプーンを知って下さったのでちょっとお気に入りの日記をダイジェストで載せますね☆既に読んでくださっている方は、ちょっと回想してもらった後で最後にある明日の予告を見てくださいね♪ブログを始めた当時は日常の疑問からくる「なんでだろう?」をテーマに日記をつけていました。その頃のブログを幾つか紹介します(*^_^*)4月4日英語ができない? 本当に英語できないですか?と聞いてみたいんです☆続いて、今の『あつしの銀色スプーン』にニックネームを変えて、サイトをリニューアルしてからのものです(^o^)4月11日☆銀色スプーン☆ 私の銀色スプーンというニックネームの由来です♪4月14日シェアーすること シェアーすることを、自分なりに噛み砕いてみました♪4月17日詩 この素敵な詩はRINKO★さんのHPからお借りしました☆ あ、、、4つしかないや…(笑)ま、まぁそんなこんなで、これからもワクワクへの気づきや発見をどんどん更新していきますので、遊びに来てください♪次回のダイジェストに向けてネタを作っておかねば(;^_^A明日は歩くシンクロマスター・宝地図ナビゲーター・望月俊孝さんのブログでも紹介されていました、ドラゴン桜についてです☆私の大好きな教育について、実はとても深い本質を突いています(*^_^*)「東大なんてうちの子には関係ないわ~」と思っているママさん方(笑)騙されたと思って少し読んでみてください☆詳しくは明日の日記で語りますので、乞うご期待(*^o^*)今日の講演会&パーティーではどんな素晴らしい出会いがありましたか?出ていらっしゃらない方はどんな休日でしたか?良かったら足跡を残して行ってくださいね☆
2005年04月24日
コメント(9)
-
幸福は最良の薬!
先日紹介した詩があまりに素敵だったので、しばらく更新をためらってしまっていました(*^.^*)コメントを残してくださった皆様、ありがとうございます!まだ見ていない方は『詩』へどうぞ☆さてさて、実は今日も急遽入手した素敵な情報を紹介します!(書こうと思っていたネタはまた後日…(*^.^*))ついさっき、Yahooを見ていてすごく面白い記事を発見してしまいました☆「幸福は最良の薬」を裏付ける研究成果という記事です。簡単に言うと、「幸せを感じている人はそうでない人より健康だ」ということを科学的に解明しようとしたものです。記事でも書かれていますが、「どういうときに幸せを感じるか」という条件は人それぞれ違って当たり前ですよね。でも、ひとまず「幸せなほうが元気でいられる」という事が科学的に証明されたら、今以上に多くの人が『幸せ』ということについて考えるようになるんじゃないかな、と密かに期待しているんです☆普通に暮らしていたら、「自分の幸せって何だろうなぁ」って考える機会は意外とないものですよね。(こちらに来て下さる方はそうでもないかもしれないですが)そんな何気なく暮らしている人が、この記事を見て、「そっか、幸せだと元気になれるんだ」ということを一瞬でも考えたらもしかしたら自然に幸せについて考えるようになるかもしれない。無意識に幸せについて考えるようになるかもしれない。そんな人が日本の人口130,000,000人のうち0.1%でも現れてくれればなんと130,000人が幸せについて考えるようになるってことですよ!(0.01%でも13,000人ですからね。凄い威力です:笑)そんなことを考えたら、ワクワクしてきちゃいました☆皆さんはこの記事を見てどう思いましたか?コメントに思ったことを残していって下さい(*^_^*)
2005年04月21日
コメント(8)
-
詩
今日は偶然出会った素敵な詩をご紹介します☆書こうと思っていたことはありましたが、あまりに心に響いてきたので是非皆さんとシェアーしたいと思い、紹介させて頂きます(*^_^*)『招待』 ~ オライア・マウンテン・ドリーマー (ネイティブアメリカンの長老)の詩 ~あなたが生活のために何をしているかは、どうでもいいことです。私は、あなたが何に憧れ、どんな夢に挑戦するのかを知りたいと思います。あなたが何歳かということも関係のないことです。あなたが、愛や夢や冒険のためにどれだけ自分を賭けることができるのか知りたいのです。あなたがどの星座に生まれたかということもどうでもいいことです。あなたが本当に深い悲しみを知っているか、人生の裏切りにさらされたことがあるか、それによって傷つくのが怖いばかりに心を閉ざしてしまっていないかを知りたいのです。あなたが自分のものであれ、人のものであれ、痛みを無視したり、簡単に片づけたりせずに、それを自分のものとして受け止めているかどうかを知りたいのです。また、喜びの時には、それが私のものであれ、あなたのものであれ、心から夢中になって踊り、恍惚感に身をゆだねることができるかを知りたいのです。気をつけろとか、現実的になれとか、たいしたことはないさなどと言わずに。私は、あなたの話すことが本当かどうかには関心がありません。私はあなたが自分自身に正直であるためには、他人を失望させることでさえ あえてできるかどうかを知りたいのです。たとえ裏切りだと責められても、自分自身の魂を裏切るよりはその非難に耐えうる方を選ぶことができるかどうかを。たとえ不実だと言われても、そんなときにあなたがどうするかによって、あなたという人が信頼に値するかどうかを知りたいのです。私は、あなたが本当の美がわかるかを知りたいのです。それが見た目に美しく見えない時でも、毎日そこから本当に美しいものを人生に汲み上げることができるかどうかを。私は、あなたがたとえ失敗しても、それを受け止めて共に生きることができるかどうか、それでも湖の縁に立ち、銀色の輝く満月に向かってイエスと叫ぶことができるかどうかを知りたいのです。あなたがどこに住んでいるか、どれだけお金があるかはどうでもいいことです。それよりも、あなたが悲しみと絶望に打ちひしがれ、どんなに疲れ果てていても、また朝が来れば起き上がり、子どもたちを食べさせるためにしなければならないことをするかどうかを知りたいのです。あなたが誰を知っているか、あなたがどうしてここへ来たかは関係ありません。私とともに決して怯まずに 炎の只中に立つことができるかどうかが知りたいのです。あなたがどこで、何を、誰と勉強したかはどうでもいいことです。私が知りたいのは、皆が見捨ててたった一人になったとき、あなたの内側からあなたを支えるものは何かということです。私はあなたが自分自身としっかり向き合い、その何もない時間の中にいる自分を心から愛しているのかどうかを知りたいと思っているのです。いつもお世話になっている★RINKO★さんのページからお借りしました。★RINKO★さん、どうもありがとうございました(*^o^*)
2005年04月17日
コメント(8)
-
ワクワクに向かって
今日はサルサクラブに行ってまいりました☆自分は踊りはあまり経験がないので、ちょっと怖いもの見たさに近い感覚で連れて行ってもらったんですが、これが思った以上に楽しいんです!ラテンのノリノリの音楽に合わせて、踊る、踊る、踊る…いつの間にか、自分の中の悩みや迷いがどこかに吹っ飛んじゃいました(笑)スポーツと同じで「無心で体を動かす」ことのパワーを体感した一日です☆さて、今日は自分のことを書かせて頂きます。今日ふと、ワクワクしながら「ああしよう、こうしよう☆」と考えていて自分のワクワクってチョロQみたい、と思っちゃいました(^.^)一回ぜんまい巻いて走り出したら、ねじが終わるまで止まらない(笑)そこで「危ない!それ以上いったら落ちちゃうぞ!」って止めて下さる方がいらっしゃるから、まだ勢い余って崖から落ちずに済んでいます。そんなイメージがふと浮かびました。日頃お世話になっている皆さん、本当にありがとうございますm(_ _)m明日からまた普通に発信していきます☆
2005年04月16日
コメント(4)
-
シェアーすること
今日はお昼過ぎまで断水なので水が出ません(ToT)トイレの後で洗面所に行って、何気なく蛇口をひねっても、、、 「シーン。」 水が出ない…普段全く意識しない、蛇口をひねれば水が出るということも、いざなくなってみると大変なことなんですね(・_;)電気やガス、お金に食べ物などなど、身近なものであるのが当たり前になっているものがなくなったら…と考えてみるのも、何かひらめくきっかけになるかもしれませんね☆さてさて、今日は先日得たひらめきから☆私の心のメンター(まだお会いしてないので『心の』にさせて頂きます)である越山雅代さんの著書『幸運へのダイナマイト』の中で『シェアーさせて頂きます』、というくだりがでてきます。私は超幸運な事に、こんな素晴らしい本に出合わせて頂きましたので皆様とシェアーさせて頂こうと思います☆この本はまさにスルメ本!読めば読むほど、噛めば噛むほど新しい発見があってどんどん味が出てきます☆是非ご購読を!さて、今日は本の中で言われている「シェアーする」ことについて、自分なりに思ったことを書こうと思います。英語のシェアー(share)という言葉を辞書で引くと「分かち合う」という意味が載っています。確かにこのニュアンスはとっても近いんですが、『分かち合う』っていう言葉って、日常的に使いますか?分かち合うってとても素敵な言葉なんですけど、『シェアーさせて頂きます』を 『分かち合いさせて頂きます』っていうと、すごいものを頂くみたいに思えて、思わず『いえいえ、ご遠慮させていただきます』って返したくなっちゃいませんか?(自分だけ?:笑)少し話はそれますが、この分かちあいとかシェアーっていう考え方はアフリカのケニアでは『ハランベー』と言う言葉で表現されていて、彼らの生活の中ではごく当たり前のものとして日常的にあることなんですね。世界の中では、当たり前の言葉だったりする、シェアーという考え方ですが日本ではあまり使わない言葉なので、ちょっと自分なりに噛み砕いてみました。自宅や友達の家で『ホームパーティー』をしたことのある人は多いと思います。ホームパーティーと言っても、日本ではせいぜい10人くらいだけど留学生の友達なんかに呼ばれてパーティーに行くと、大体30人以上の人がそれぞれの作った料理を持ち寄って、好きなものを自由に取って食べてね☆っていう形でやるんですね。ここで思うに、シェアーすることって自分が作ったものをテーブルに並べることに似てると思うんです(^^)自分は作ったものを並べるだけ。食べるかどうかは取る人の自由です。取ってもらうことを期待しちゃうと、それはシェアーじゃなくなっちゃう。「どうぞご自由に☆」、が合言葉。そこで「おいしいよ~(^.^)」って言ってもらえると嬉しいですよね☆それが嬉しいから、次はまたおいしいものを作って来よう、って思う。そして、受け取ってくれた方が今度は自分の料理を並べてくれたら、それがシェアーってもんでしょう(*^_^*)今自分がやってるシェアーも、やっぱりそれと同じじゃないでしょうかね。情報発信という形でテーブルに並べさせて頂いて、コメントやメールで「おいしいよ~!」って言ってもらえると超嬉しい☆だからまたおいしいものを作ろう!と思って頑張って発信する。すると忘れた頃に、今度はあちらから素敵な情報をシェアーして頂けたりして(^.^)どうでしょう~自分なりにシェアーすることを噛み砕いてみたんだけどもっといい例えがあったら教えてください☆自分もどんどんここで発信していくので、情報をシェアーしましょう!こんな素敵な姿勢で、人生の素晴らしさをシェアーできるなんて越山雅代さんと、幸運へのダイナマイトに出会えたことに本当に心から感謝しています(#^.^#) あなたが今日回りの方とシェアーさせて頂いたことは何ですか? あなたがテーブルに並べたもの、受け取ったものを3つづつ考えてみてください☆
2005年04月14日
コメント(8)
-
パターン
先日、ツイてるファシリテーターさんのスリーインワンメソッドの一日ショートプログラムに参加させてもらいました。どういうものか、自分なりに噛み砕いて説明します。ソースで得たワクワクのエネルギーを車のエンジンorアクセルだとすれば自分の心の中でひっかかっていること等が無意識のうちにブレーキになってしまうこともあるんじゃないでしょうか。スリーインワンではそのブレーキをそっと外してやるのが大きな目的になります。ここで重要なのが、人の反応にはパターンがある、ということです。嫌なことがあった時に衝動買いをして気を晴らす人、やけ食いをしてストレス解消をする人などなど、いろんなパターンがありますが、これって、誰も赤ちゃんの時には絶対やってないですよね。オムツが濡れてるからって、腹いせにミルクをがぶ飲みする赤ちゃんがいたら 怖すぎます(笑)自分が何かマイナスの感情を抱くようなものに対して起こす行動というのはこれまでの時間の中で作られた自分のパターンなんだ、というのが重要なポイントです。つまり、そのパターンをきちんと理解して、自分がそれに陥ってしまっていることに気がつくことで、新しいプラスのパターンに持っていくことができるということなんですね。具体的な手法はここでは言いませんが、受けてみた感想としては「狐につままれたように、すっきりちゃった☆」です。人間って、すごいですね。きちんと手順を踏んで適切な処置をすることで、自分の中でかかっているブレーキをスッと外すことができるんです。本音を言ってしまえば、まだ「信じられな~いw(☆o◎)w」です(笑)でも、確実に自分の中の何かが解放されたのを感じます。表現力が足りなくて、これを皆さんにお伝えできないのが口惜しい…劇的な変化ではない分、余計に凄みを感じます。私がこのブログをリニューアルしたのは、一つ大きなブレーキを外すことができたからなんですよ。リニューアルOPENしました☆でも書きましたが『ワクワクに気づいている人が周りにいなくて寂しいなぁ…』 ↓『☆ワクワクに気づいた自分が中心になって発信しよう!☆』という方針の大転換です☆今までは自分と同じように考えている人が周りにいないと「あれぇ、自分がおかしいのかなぁ…」 と考えてしまっていました。でも、周りと違ったら周りに合わせないといけないというブレーキを外してしまうことで、「自分が周りと違うのは、まだみんなが気がついていないだけ。」 「よし、じゃあ最初に気がついた自分がそれをみんなに広めよう☆」 という発想の転換ができるようになりました。今日からは自分が発信源です☆みなさんも、知らないうちに踏んでしまっているブレーキをスリーインワンで外してみませんか?☆あなたが本当はやりたいと思っているのにやっていないことは何ですか?一緒に少しづつ、初めてみませんか??
2005年04月11日
コメント(10)
-
☆銀色スプーン☆
さて、質問にありました新しいニックネームの 銀色スプーンですがこの名前は私の大好きな映画 『マトリックス』(一番最初のです)に出てくる、スプーン曲げをしている少年から取りました。どんなシーンか簡単に説明します。預言者Oracle(この人には未来が見えるんです)に会いに来たネオは待たされている部屋でスプーンを曲げている少年を目にします。不思議そうに見ているネオに対して、少年は言います。「曲げようと思ったら曲がらないよ。そうじゃなくて真実を見ようとしなきゃ。」ネオ「真実?」少年は「ここにスプーンはないんだよ。(英語で"There is no spoon.")曲がるのはスプーンじゃなくて自分自身なんだ。」と返します。この後で、ネオはスプーンを曲げるわけですが、実はこの後のシーンで、ネオがエレベーターの上に乗って「心を解き放て("There is no spoon.")」とつぶやくシーンが出てきます。これがカッコいいんだなぁ~☆私のURLの最後にあるnospoonとニックネームはこのシーンから取ったものなんです☆ 『心を解き放て』 自分を縛り付けているもの例えば、思い込みや、社会の常識、遠慮、不安などから自分を解放するという言葉が、自分の心に強く、強く響きました。自分が思っている以上に、気がつかないうちにいろいろなものに制限されて生きていることに、ふと気がついたんですね。じゃあ、もし「自分を本当の意味で解放することができたら自分は一体どれくらいのことができるんだろう?」という疑問が自分の中からフツフツと湧き上がってきました。さすがにネオのようにスーパーマンになるのは無理かもしれないけど(笑)もし自分を縛り付けているものから自分を解放して自分の才能や能力を100%出し切ることができたらきっとすごいことができるんじゃないかな☆そんな思いを込めて、あつしの銀色スプーンという名前にしました。マトリックス、個人的にすごくおススメです☆見たことのない方は是非一度見てみて下さい。一緒に本当の意味で心を解放しましょう☆
2005年04月11日
コメント(3)
-
リニューアルOPENしました☆
リニューアル工事中にコメントを頂いた皆様、どうもありがとうございました!ニックネームもデザインも題名もみんな一新してしまったので「あれ?別の人?」と思われた方もいるかもしれないですね、あつしの銀色スプーンの新しい人生コンセプトができたので、それに合うようにブログのコンセプトも新しくした次第です(*^o^*)新しくした経緯を簡単にまとめますね。これまでのコンセプト「なんでだろう?」は不思議なもので疑問が沸くのは大抵ネガティブなところからなんですよね。日記の最初に「どうして…ないんだろう」という否定が入っちゃうのは良くないなぁと思っていたので、新しいコンセプトに変えようと思っていました。そこで今回打ち出した新しいコンセプトは 「『日本で始めて自由にワクワクを生きることに決めた学生』がワクワクを生きるためのエッセンスを世の中に発信する!」というものです!正直、学生でワクワクしながら生きようとしてる人ってまだまだ世の中には多くないので、自分だけ世の中の流れから取り残されちゃったような気がして、内心寂しいなぁと思ってたんです。でも、先日素晴らしいワークショップ(後の日記で紹介します☆)を受けたことで自分の中で大きなパラダイムシフトが起きたんです。それは…『ワクワクに気づいている人が周りにいなくて寂しいなぁ…』 ↓『☆ワクワクに気づいた自分が中心になって発信しよう!☆』思わず「これだ!」と叫んじゃいました(笑)自分の信じる道を、ワクワクを頼りに生きていくために必要なものは何だろう。日々学んだことからそのヒントを発信していこうと思います☆
2005年04月11日
コメント(0)
-
リニューアル!
ブログのデザイン等等を一新する事に致しました☆更新が完了するまでちょっとお休みします(_ _).。o○更新後の日記も見に来てくださいね!おやすみなさい~(笑)
2005年04月09日
コメント(5)
-
情報の扱い方
今日は天気の良い入学式になってほんと良かったです~☆(前日も書きましたが、小学校では大雪の入学式だったので…)やっぱり入学式は学生も、親の方もみんな「ウキウキ + ちょっとドキドキ」している雰囲気がしていいオーラが満ちていますね☆さて、今日のなんでだろうは「どうしたら得たものを効率よく自分のものにできるだろう?」です。この頃新学期ということもあって、環境が変わって一気にたくさんの情報が舞い込んでくるようになりました。このブログからにもたくさんの方が遊びに来てくれるし、そのリンクを伝っていくだけでも膨大な良い情報が得られます。その他にも本やテレビから得られる情報、電車の中吊り広告や隣の人のおしゃべり、友達との雑談などなど、自分に入ってくる情報は数限りなくありますね。最近、いいアンテナを張れるようになってきたので、自分の欲しい情報をキャッチしやすくなったのはいいんですが、その分キャッチしすぎちゃって、整理が追いつかない~(+_+)状態です。マインドマップや最近始めた速読なんかを利用して、なるべくたくさん吸収したいと思って頑張っています。今日は結論らしい結論はなくて、皆さんは得られた情報をどうやって自分のものにしているのかちょっと聞いてみたかったので書きました☆「天才とは素晴らしいメロディーを思いつく人間のことではなく、 思いついたメロディーを忘れずにいられる人間のことだ」というような言葉をある有名な音楽家が残していたを思い出しました。この頃、いかに得たものを自分の血肉になるまで消化するか、ということに気を使っています。皆さんのアイデアを教えてくださいね☆日頃得た情報や気づきを自分のものにするために、どんな工夫をしていますか?
2005年04月05日
コメント(2)
-
英語ができない?
明日はいよいよ入学式でございます☆昨日、喉ががらがらでまたも予定をキャンセルして寝ていただけに今日は何とか復活!明日の式には無事に出られそうです。思い出すのは小学校の入学式…何故か4月なのに『記録的な大雪』(笑)桜舞う入学式のはずが、窓の外は銀世界(笑)長靴の中までびちょびちょになりながら通った初めての小学校は忘れたくても忘れられない思い出です(T_T)さてさて、今日のなんでだろうは「英語ができる、できないのってなんでだろう」です。というか、できるできないってどういう事だろう、の方が正しいですね。日本人が英語ができないと言われて久しいですが、ほんとでしょうか?確かに、友達の留学生が英語で話しかけるとビビッて全然喋れなくっちゃう日本人の人は多いです。が、面白い話をききました。こんな例を挙げてみます。「あなたはスキーできますか?」「あなたは泳げますか?」これに対して「ボーゲン使えば滑れるよ」「23メートルくらいなら泳げるよ」っていうような答えが返ってくるのは普通ですよね。…で、何が言いたいというと。スポーツならちょっとできれば『できる』って言っちゃいますよね、ってことです。面白いですよね~_(^^;)英語だと「挨拶くらいならできます」って言っても全然『できる』って認めてもらえないのに。ここの感覚の違いは、まぁ教育システムの…とかいろいろと説明はできるんでしょうが、とりあえず「『できる』っていうのに、ネイティブ並にペラペラである必要はない」ってことは確かですよねそれだけわかれば、大分気持ちの面で楽になるんじゃないでしょうか。スポーツなどではよく言われているようですが「これは難しい!」と思って取り組むのと、「こんなのチョロイさ!」と思って取り組むのではモチベーションや効率に大きな差が生まれますしね。その意味で、これから「英語ができなかった人」は英語が少し『できる』人」に気持ちを切り替えましょう!ものの見方って重要なんだなぁ、と思う今日この頃です。明日は入学式です☆
2005年04月04日
コメント(4)
-
タイミング
今日の3回目の更新です、書くことがたくさんある日って幸せですね~今日のなんでだろうは、「どうして同じ素晴らしい機会に恵まれても、変わろうとする人とそうでない人がいるんだろう」です。先日本田健さんの講演会に行った時に気になることがありました。それは「講演を聞いて満足しちゃっている人」「講演の内容が完全にスルーしちゃっている人」が思った以上にたくさんいるということでした。たまたま知り合いと会場で会ったんですが、彼はもう講演が聞けただけで大満足!さらに健さんにサインもらえて握手までしてもらって、もう最高!と言っていました。ほとんどアイドルのサイン会状態(笑)そのこと自体は、全然問題はないんですが、どこか「あれっ?」と思ったんですよね。さらに、講演を聞いても「あ~疲れた、さっさと帰ろう~」という雰囲気の人も周りに結構いたりして、さらに「あれっ?あれれっ?」と思ったんです。私自身にはすごくためになった内容だったので良かったんですが、他の人の受け取り方があまりにいろいろだったので、どこかショックを受けてしまっていました。「こんな素晴らしい講演を聞いたのに中身が伝わってない!」という気持ちです。それがどこかでひっかかっていたんですが、うまく消化できなかったので少し表に出すのを控えていました。で、今日何気なく手に取った「ユダヤ人大富豪…」で通るべき大切な関門の一つでこんな感じのものがあったんです。「時には自分を見失ってしまうことがあるかもしれない。 人が良くなろうとしないのを見て傷ついてしまうことがあるかもしれない」まさに今のタイミングですね!周りの人が本当の意味でもっと良くなってほしいと願っている反面、それがなかなか成ってくれないのが、どこか悲しく思えていました。そのあとに、それを乗り越えるには「それぞれの人がベストな人生を送っていることを信頼してあげよう」「みんなそれぞれにベストなタイミングがあるんだよ」というような事が書いてあってまた目から鱗です(T_T)今までは自分と同じペースで周りの人が変わっていってほしいとどこかで願っていたんですよね。やっぱりせっかくならみんなで新しい気づきを得て、良く変わっていきたいですから。でも、そう考えていると、自分とペースが違う人、特に自分よりペースが遅い人を見て「この人は全然変わろうとしないなぁ」と、どこか非難めいた気持ちになっていました。でも、考えてみたら自分と同じように変わる必要なんて全くないしそれを押し付けちゃったら、それこそ傲慢ですよね。それぞれの人がみんなベストなタイミングで変わっていくんだ、ということに気がついたら、すごく楽になりました。自分は少し早くにそのベストのタイミングがきたんですね、きっと。今自分がたくさん変わっているのは、自分にとって今がベストだからだと思えるとこれから起きていく変化がすごく楽しみになりました(*^_^*)それが自分にとってベストなんだと思えると、受け取るのも楽だし受け取るときも気持ちよく受け取れますしね☆もっともっと自分の人生を信頼して楽しんでいこうと思う、いいきっかけになりました。信頼って、いい言葉ですよね~これからもっともっと素敵な変化が訪れることを期待して、今日はゆっくり休みます。おやすみなさ~い!
2005年04月02日
コメント(3)
-
ゴホン(+_+) ゴホン(+_+)
今朝は素敵な気づきがあったので上機嫌で二度寝しました(笑)旅行の疲れも少し残っていたので、軽い休みをとるつもりで軽く休んだ後で、以前から計画していた部屋の大改装(部屋に敷いているマットを取り替える作業)を親に手伝ってもらって一気に仕上げてしまいましたv(^o^)思ったより大事になってしまって部屋を全部掃除することになっちゃったんですが、やっぱり、部屋を掃除すると気分がいいですね☆で、ちょっと張り切りすぎたのか、その後少し仮眠を取ったら明らかに体がだるい…顔が赤い(元々日焼けで真っ赤ですが:笑) 体が熱い…咳がひどくて喉が痛い…これは風邪!?ですよね、明らかに。とってもショックでしたが、明らかに熱がある感じだったので泣く泣く今夜の友達の家での『男飲み』はキャンセルすることにしました。久しぶりだったので、楽しみにしてたのになぁ…まだ頭痛はしないものの、明らかに風邪の第一段階だったので、こじらせないうちに治すべく、すぐに処置をしました。で、前置きが長くなってしまいましたが、ここからが今日のメインです☆風邪を引いたら、まずは栄養を取って、薬を飲んで、暖かくして寝るのが基本ですよね。今日は、その基本に忠実に従ってご飯を軽く食べて、薬を飲んで、暖かくして布団に入りました。母に言われた「お茶でうがい」ももちろんやりました。水分も取ったほうがいいので、お茶を何回も取りました。あと、病は気からと言いますし、今日は「これだけきちんと体のことを考えて手を打ったんだから、すぐに良くなるよ」と自分に言い聞かせる、というか体に教えてあげました。で、少し仮眠を取った後で目がさえていたので、何か元気の出るものを読もうと思って本田健さんの「ユダヤ人大富豪の教え」を手に取りました。読み出してから数十分後、ちょっと体の変化に気がつきました。「あれ、何か、だるくないぞ…?」さっきまでのあの熱があるとき独特の、体が火照るような感じが嘘みたいにきれいさっぱりなくなっちゃったんですよ~ヽ(^。^)ノびっくりでした!何だか文章にしてしまうと、味気ない感じですが、久しぶりに自分の体の不思議さにびっくりさせられましたね、今日は。病は気からって、本当だったのかなぁ。でも、さっきのだるさと体の火照り方は明らかに38.5度くらいはあったぞ…ともあれ、ほんの3時間前までは「明日は絶対一日安静だな」と思うような状態だったのが、このわずかな時間の間に劇的に回復したのには「体って不思議~!」と思わずにはいられませんでしたね(゜o゜)/今日思ったのは、ちゃんと面倒見てやらないと、体調を崩すというサインを出してくれるしサインに気づいてきちんとした手当てをしてやれば、ちゃんと元気になるっていう形で体は応えてくれるんだなぁ、ということでした。今こうしてブログに載せられるのも、ちゃんと体が応えてくれたからなので今日は自分の体をたくさん誉めてやりたい気分ですね!皆さんも、健康にはくれぐれもお気をつけ下さいね。危ないなと思ったら無理をさせずに、すぐにきちんと労わってあげることで体は思った以上に応えてくれるみたいですよ☆1.栄養と水分をなるべくたくさん取る2.薬を飲む3.お茶でうがいをする(飲むだけでも効果的みたいです)4.暖かくして布団に入る以上の基本は、これからもきちんと守ろうと思いました(*^_^*)今日の何でだろうは次の投稿で出しますね。
2005年04月02日
コメント(0)
-
早起きは…
今日は早い時間に目が覚めてしまったので、ちょっとだけ投稿です。やっぱり朝の空気はいいですね☆早起きは三文の徳、今日はいいことあるかな~昨日寝る前と今朝読んだ2冊の本から素晴らしい気づきがあったのでなんでだろうはお休みして紹介します☆一冊目は後藤芳徳さんの人脈大改造ですこのところGive&Giveの大切さを耳にすることが多かったので、自分なりに実践してきたつもりだったんですが、どうしても後輩や経験の浅い人に自分が「与える」ということにフォーカスしてしまっていたので目上の方にどうやってGiveしたら良いものかと思っていました。そこで、この本の中でギブ&ギブについて「いつの時代でも言われたこと以上のことをやる人間もいて、そうした人が抜き出て行く」「ギブ&ギブで相手の期待を良い意味で裏切り続け、期待以上のことをやり続けていきましょう」という内容のことが書いてあって、まさに目から鱗でした(T_T)良い意味で期待を裏切る、このことが本質なのではないか、と気づいたら、世の中には無駄なものなど一つもないような気がしてきました☆少し停滞気味だった情熱が戻ってきたような気になって体が温かくなるのを感じられるほどでした。世界はうまくできているもんですね~もう一冊は小俣 貫太さんの斎藤一人の百戦百勝 (商売編)です↓こちらは文庫なんですが、一人さんの百回聞けCDがついていて、とってもお得です!この中で一人さんがこれからの世の中の動きを、歴史を交えつつ見事に予想していることに驚くと同時に、「カッコいい商人」の生き方を一貫して説いている姿勢に脱帽です。当たり前のことを当たり前に見聞き行う、それが徹底されているんだと思いました。どんな小さな出来事からでも、更に自分を高めるヒントが得られる今日この頃。何かと感謝しっ放しです(-人-)自分が変わると全てが変わって見える。そんな体験をこの頃何度もさせて頂いています。自分一人だけでは決して乗り越えられなかったような山を、いとも簡単に乗り越えられるようになってしまうような出会いにたくさん恵まれました。これからも感謝を忘れずに人、物に限らずささいなご縁を大切にしていこうと思う朝でした。
2005年04月02日
コメント(0)
-
本田健講演会
旅行から帰ってきて鏡を見たらびっくり!スノボの雪焼けで顔が真っ赤です、まるでお猿さん(笑)もともと日に焼けると赤くなる体質なんですが、今回は思いっきり赤くなってしまいました。「何か酔っ払いみたいだよ」、と妹(笑)しばらくちょっと恥ずかしいですね(それ自体がネタになるので問題ないですが)さて、今日のなんだろうは『どうして世の中には素晴らしい講演をされる方、素晴らし文章を書ける方 など様々な素晴らしい方がたくさんいるんだろう』です。先日、本田健さんの学生向け講演会に参加してきました。以前から敬愛していた方だったので、著書も一通り読んでいますしどんなことを話されるのか、とっても楽しみでした。そこで講演を聞いて思ったのは「思ったほど目新しいことがない」ということでした。とても新しい発見に満ちた講演を期待して行ったのである意味でどこかショックだったのは確かですが、裏を返してみると「それだけ本田健さんの考え方が自分のものになっている」とも取ることができますよね。そうやって視点を変えることができたら、すごく意味のある講演会に思えました。少し、本田健さんに近づけたような気になって何だか嬉しくなりました。この頃、素敵な方と近づく機会が増えてきてその人たちの出すオーラのようなものを受け取ることができてとても幸せに思います。やはり、その人の本を一冊読むよりもたった1分でも直接お会いして話をするほうが多くのものを得られる、というのは嘘ではないと思いました。これからも、どんどん行動していくべく、心機一転の新学期です。
2005年04月01日
コメント(2)
-
旅行後所感
旅行の話は下に書いたので、そこで感じたことなどを書いてみます。今日のなんでだろうは「人生でこんなに素晴らしいことがまだまだあるみたいなのに、どうして自分は(みんなは)気がつかなかったんだろう」ということ。思うに、フォーカスするところが、無意識にでも自分で思っているよりずっと狭い範囲に限定されちゃっていたからではないか。どんな日常であれ、楽しいこと嬉しいことを受け取ろうと思えば大抵何かしら受け取れるものですよね。逆に、マイナスの要素を見ようとすれば、やっぱりどんなことからでも見つけられるみたいです。友達で、とってもポジティブでいろんなことに挑戦するしいろんなことに興味があって、とってもエネルギーに溢れている人と逆に何を見ても聞いても達成しても、とってもネガティブに「自分は所詮…だから。○○はいいよなぁ…」と考えるタイプの人がいます。そのどちらも、確かにそれぞれのパーソナリティーは持っているんですが、やっぱり楽しそうなのは前者ですよね。ただ、だからって全部が全部いいことだらけ、とは行かないようですが。実際、後者の友達の方が一般的な見方でははるかに成功しています。どちらがいい悪いということではなくて、単純にその違いがどうして生まれるのか、それはどういう違いにつながるのかそういうものが不思議だったんですよね。ポジティブシンキングと一言に言ったって、それができない人はたくさんいるしそれができてもどこかで撃沈してしまう人もいます。それは何故だろう。どうしたら改善できるんだろう。そんなことをいつからか、考えていました。この3日間、その両方のタイプの友達と一緒にいたおかげで何となくですがその疑問を説くヒントが得られたような気がします。つまりは「バランス」なのかな。マイナスの面にフォーカスしてしまう人は、プラスの面には目がいかないしその逆の場合はマイナスの面に目を向けにくいようです。だから、常に同じパターンの考え方やものの見方で全部のことを解釈しようとしてしまう。そこから違いが生まれて、かつどちらも本当にうまくいっていると本人が思えなくなっているような気がします。例えば、今回の温泉旅行もいろんなことをしてとっても楽しかった反面たくさんお金を使ったので、今月はピンチかもしれません。温泉に行かなかったとしたらこんな楽しい時間を過ごせなかったかもしれないけど逆に自分の時間は自由に取れたという見方もできます。つまり、どんなことも見ようによってはプラスにもマイナスにも取れる部分は含んでいるし、しかもその取り方のさじ加減は個々人の価値観にほとんど完全に依存しているから、「感じ方の違い」はどうしたって生まれてきますよね。それをまずちゃんと知ることなのかな、と思いました。自分にとってどうでもいいことが相手には重要だったりその逆だったりすることはよくあります。でも、自分で思っているよりわかってなかったのかもしれないですね。取りようによっては何でもプラスマイナス両面があってそれをどう感じるかはそれぞれ違う。そんな原則を、この旅で実感しました。できるだけ、両方の見方を、かついろんな価値観の人の目線に立ってできるようにしたいと思いました。それがバランスをとる、ということの意味なんじゃないか、と。それから、帰り道に楽しい旅を急に現実に戻してしまうような出来事があって少し気分を害したんですが、そのことを経験してみて、エネルギーの流れを感じることともっと柔軟なものの見方をすることを考えられるようになりました。楽しいだけの出来事は、実際には存在しないのかもしれません。その中にはどこかしら楽しくないものも含まれているかもしれないし、あるいはその後で楽しくないものが訪れるかもしれない。でも、それは世の中がプラスだけでできているわけじゃないからマイナスの部分が現れても「当たり前なんだ」と受け入れてしまう。そうすることで必要以上にマイナスの部分にフォーカスしすぎないように自分の気持ちを落ち着かせることができた気がしました。まだまだこの考え方は実験段階ですが、そうやってプラスのところにはマイナスが流れてきて、マイナスのところにはプラスが流れてくるのが当たり前というような感じ方は、生きていくうえでとても自分を成長させてくれるような気がします。実際に、楽しいだけの旅行の後で多少それと相対するもの(嫌な出来事など)が訪れるのはある意味当たり前だから、そこで感じるマイナスの感情をうまく受け入れてそれをうまくプラスに向かわせる流れを作り出してみよう。(もちろん必ずということではないですが、こう考えると楽でした)そうすることでプラス→マイナス→プラス→マイナス→…という波のようなものを感じて受け取れるようになった気がします。明けない夜は無い、という見方に似ていますね。正直、大学時代の4年間は人生で最も静かに辛い時期でしたがその4年間があったから今の自分の感性であったり、ものの見方、考え方が磨かれたという面は少なからずあるように思います。ただ、だからといってそれだけでその4年間が今すぐ全て浄化できるわけでもない。それがどこか矛盾しているように思えてずっとすっきりできませんでした。でも、「いつかあの4年間があったから今の自分がある」と言えるようになることを信じてもいいだろうと思います。それと同時に、「でも、まだ今はそれは言えないよ」という自分の感情も全く同様に受け入れてやることが必要なんだと強く思いました。今の時点で感じる否定的な感情を否定して、一足飛びに全部プラスにとらえられるようになる程まだ自分は成長していません。やっぱり嫌なものは嫌。何でもかんでもポジティブに取れるほど自分はできてないし、時にはマイナス思考になるときもある。まずそのちょっと後ろ向きなわがままさをちゃんと受け入れよう。でも、いつかはほとんどのものを受け入れて前向きにとらえられるようになる日が来るということも、やっぱり同様に受け入れて信じよう。その両方があって、バランスというものが取れるようになるんでしょうね。100%書きたいことがかけたわけではないですが、残したかったものは残せたような気がします。この旅行が与えてくれたものは、とても大きいんです。だからこそ、それを前に生かしたいと思いました。何らかの形で先の自分に、あるいは次世代に残したいと思ったんです。なんでだろうの疑問の答えにはなってないかもしれないですが、今日はちょっと頭を使いました。
2005年03月30日
コメント(1)
-
温泉旅行!!
温泉旅行から帰ってきました!本当は3日間の睡眠時間合計が10時間未満なので今日は寝ちゃうつもりだったんですが、書きたいことがありすぎて、やっぱり書きます(笑)2泊3日で、一昨日から群馬県の草津温泉に行ってきました。高校のときの友達と、車で温泉旅行!っていうことで実は初めは内心「ちょっと枯れた卒業旅行だな…」なんて思っていたこともあったけど(笑)蓋を開けてみてビックリ!間違いなく人生の中でベスト3に入る素晴らしい旅行になりました(^-^)本当にいい旅だったぁ~3日間みんなで歌い踊って(笑)たくさん温泉に使って裸の付き合いをして夜は飲みながら語り合い、最後にはスノボーまでできて、やりたいことは全部詰め込んだ旅行になりました。こんなに充実した3日間は、人生でもそうは出会えないような気がします。食事も現地の郷土料理で美味しかったし、温泉でお肌はツルツルスノボーは1日だけど思いっきり滑れたので文句なし。でも、それ以上に何が良かったかって、やっぱり一緒に行った友達ですね!3日間一緒にいてずっと笑いっぱなしのような感じで多少のピンチもさらりとかわしてすぐ仲良くなれるそんな形の仲間が自分にいたんだなぁ、ということを改めて感じた3日間でした。本当に素敵な友達は人生の宝、と誰かが言っていたのがわかるような気がします。今回の旅を終えて、こんなに気持ちよくいられるのは間違いなく一緒に行った友達のおかげです。みんなに出会えて良かった、と心から思います。どうもありがとう。これからも、どうぞよろしく。こんな日記が書ける自分はとっても幸せ者ですね☆今日は何でだろうはお休みで、単純に楽しかったことを日記にしました。温泉は本当にいいものですね。好きな人と一緒に行くには実はとってもいいところですよ。読んでくれている皆さんも是非!!
2005年03月30日
コメント(0)
-
☆☆結婚式☆☆
今日は友達の結婚式の二次会→会場の高校の時の同級生と飲みに行ってきました。新郎は同級生なので、23歳。お相手は少し年上の姉さん女房です。二人ともすごくきれいで幸せそうでした(^-^)さてさて、今日感じた疑問は、『なんでこの年になるとみんな勝ち負けを意識し始めるんだろう』ということ。帰り道、幸せそうな二人を見た後で出てくる感想がきれいに2分してるんです。ある人は「幸せそうだったなぁ、俺もああやって幸せな結婚したいなぁ」またある人は「俺らももうそんな年かぁ、早いなぁ…早く相手見つけなきゃ。」しかも、どちらも相手は見つかってない募集中の身であるにも関わらず、こんなにきれいに感想が違っているのには、久しぶりに会った事も重なって、とても驚きました。割合的には圧倒的に後者の方が多いので、更に驚きです。その後の飲み会でもまぁ、いろいろと思ったことはあるんですが今日は時間があまりないのでまとめちゃいましょう。今日の帰り道、とても強く思ったことがあります。それはこれ。「(自分にとっての)本物の目標やワクワクをきちんと見分けられるようにしよう。」別の言い方をすると、自分が本当に望んでいる状態、目標、歩みたい道程をきちんと見分け、確認するようにしよう、と。それは必然的に、自分が取るべきものとそうでないものを見分けることにつながるからです。今日幸せな結婚を果たした二人には、心から祝福を送りました。自分はまだお相手を探している途中ですけど、ゴールインが早いかどうかで勝ち負けにしちゃうのは、どこか本質からずれちゃっているような気がします。自分は多少周りより遅くなっても、本当に結婚したいと思うまでじっくり待とうと思いました。それが今日確認できたので、これからはもっと素直に相手と付き合えるような気がします。まだ、気がする、程度ですけどね(^-^)そんな事を考えながら、ふと、ようやく自分も今までいた場所から歩き始められた様な気がしました。それはなぜかって?ほんの数日前から、目に映るものが以前とは違って見えるようになったから。多少語弊があるのは承知で大げさに言うと、映画『マトリックス』の中でネオが生き返って、カタカナで書かれたマトリックスのプログラムが見えるようになった時のような気分ですね。「おおっ!世界はこんな風にできていたのか!」という気分です。周りにいる人間の意見とか、世間の流れとか、自分の周りの環境にいつの間にか押し流されていっていたんだってことに気がついたんですよね。あと1ヶ月前に今日の出来事があったら、自分はどう思ったかな。もしかしたら、多くの人と同じように焦っちゃっていたかもしれません。流されていることに気がつくことが、流されなくなるための第一歩。表面的に見えるものの裏に流れているものが、本当に本当に何となくですが、感じられるようになった気がします。さて、これからそれをどう生かしていこうかな。明日から、卒業旅行で温泉に行ってきます。のんびりお湯につかって、英気を養ってきま~す!
2005年03月27日
コメント(2)
-
なんでだろう?
なんでだろ~ぉ なんでだろ~で始まるテツandトモの曲が一時期流行りましたよね。この曲を聞いていて、自分の子供の頃を思い出しました。ちっちゃい頃はなんでもかんでも「なんで?なんで??」を連発してました。もっとも今でも全く変わってないんですけど(笑)このブログでは、日頃から感じている「なんでだろう?」を取り上げて自分なりにその理由を探って行こうと思います。というのも、自分から「なんでだろう?」と思う好奇心を取ったら何も残らないと断言できるからです!(笑)せっかく書くなら、自分の一番ワクワクすることを書かないとね!今日は最初なので、軽く日記を載せることにします。今日は就活中の後輩を誘って高田馬場で飲んできました。彼の住んでいる寮は、なんと村上春樹の「ノルウェイの森」の主人公の住んでいた寮のモデルになったものなんだそうです!しかも、建て直したりせずに、今でもそのままの状態で学生が住んでいるそう。(つまり相当ボロいということでもありますが…)そんな彼と、今日は仕事とこれからの人生について熱く語ってきました。先日あった勉強会で、知り合った方々からたくさんの教えてもらえたのでこれをどうしても誰かに知らせたい!ということで就活で忙しい中、夕飯ご馳走するということで強引に付き合ってもらったんです。で、あれこれと話をしているうちに、実は彼も自分と同じく経営などに興味を持っていることが発覚!結局、自分が読んできた本やら会ってきた人たち、参加してきたセミナーなどなど知っていることを全部話してしまいました。話す前は、そこまで大きなインパクトは与えられないだろうから何かのきっかけに、程度の参考になればと思って話そうと思っていたのにふたを開けてみたら「人生変わりました」と大絶賛(笑)先日読んだ、「教えることの不思議」に書いてあることがそのまま実践できた体験になりました。また、先日「アウトプットするほどインプットされる」ということを教えてもらう機会があり、それを試してみる意味もあったんですが、これがまた効果絶大!自分が普段どんなことを考えているのか、自分の口から出てくる内容に自分自身びっくりしてしまいました。いつの間にか、人に語れるくらいの自分を持てるようになってたんだな、と。今日はたくさん与えることに集中して彼と話をしました。でも、気がついたら、たくさんもらっていたのは自分の方みたいですね。これからどんどん先に自分から与える、というのを実践していこうと思いました。以前自分に気持ちよくご馳走してくれた先輩に本当に感謝です。その先輩も、更に先輩の方から「後輩にはおごれ!」と言ってご馳走してもらったそうです。帰り道に先輩がそのことを話してくれたとき、自分も必ず後輩にしてあげようと思ったのをよく覚えています。今日はそれが叶って、自分もすごく気分が良くなりました。だから今度は、彼が後輩に気持ちよくご馳走してやってくれ、と言って別れました。こういうのが、いい流れになってくれたらいいなぁと思います。今日は素晴らしい日になりました。
2005年03月26日
コメント(2)
全47件 (47件中 1-47件目)
1
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 水と油の意見から学ぶのです。
- (2025-11-26 07:02:13)
-
-
-

- みんなのレビュー
- (株)みやまさん…
- (2025-11-26 17:27:25)
-