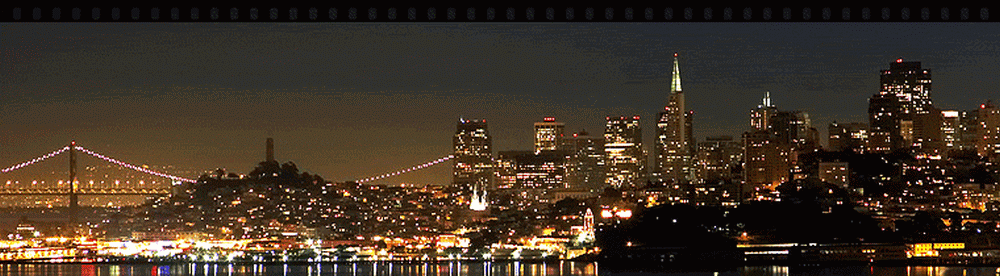2019年01月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 28日(月) 【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】 ★左京区・一乗寺の狸谷山不動院で一月二十八日、「初不動」が営まれた。「狸谷飲み放題」といわれるがん封じのご利益があるとされる笹酒が、参拝者にふるまわれる。江戸時代中期に修行をしていた僧・木食上人が境内の滝の水を竹筒にくんで病人に飲ませたところ、たちまち病気が治ったという。この故事にちなんで、護摩の火で温めた笹酒が振る舞われるようになったとされる。狸谷不動院は桓武天皇勅願の不動尊を安置したのがはじまり。毎月二十八日が本尊の「不動明王」の縁日で一月は初不動として知られ、家内安全や商売繁盛を願って全国一円から参拝者が訪れ、本堂前では山伏姿の修験者から竹筒に入った酒が竹の杯に注がれ、無病息災を祈りながら飲み干していた。又、「狸谷さん」の愛称で交通安全の神社として、一年中車の祈祷で賑わっている。本尊の不動明王の縁日が毎月二十八日で、年初めの一月は初不動として親しまれている。笹酒は、約三〇〇年前に木食(もくじき)上人が、修行する滝の水を青竹の筒に入れて病人に飲ませたところ、病がたちどころに治ったという故事にちなんでいる。この日、参拝者は白い息をはずませながら長い階段を登った後、山伏姿の修行僧から温かい酒を注いでもらった. ✸画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.29
コメント(0)
-
"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 26日(土) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事]★京都府南丹市美山町のかやぶき集落を明かりで照らす「美山かやぶきの里 雪灯廊(とうろう)」が二十六日、始まった。新雪で覆われた山里にあたたかな光がともり、観光客らが幻想的な冬の風景を楽しんだ。来月二日までの午後五~八時、里に約五〇〇基以上の灯籠をともし、かやぶき民家二十戸とともにライトアップする。開幕に合わせるように午前中に約20センチの積雪があり、日没後に点灯されると、こんもり雪をかぶったかやぶき民家が浮かび上がった。国内のほか台湾、中国などからの観光客も数多く訪れ、写真に収めたり、雪灯籠作りを楽しんだ。ぼたん鍋などの屋台が並び、花火の打ち上げもあった。★画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.27
コメント(0)
-

"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 25日(金) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事]★上京区・北野天満宮では、承和十二年(八四五)六月二十五日に生まれ、延喜三年(九〇三)二月二十五日に没した学問の神様・菅原道真を偲び、御縁日として、終日境内周辺に露店が所狭しと立ち並び、参拝者の人波が絶えない。 「天神さん」として親しまれ、二十一日の東寺・「弘法さん」と共に毎月開かれる京都の二大縁日で、境内一円に露店が多数並ぶ。その一年最初の縁日を「初天神」と呼び、「終い天神」と共に例月よりも多くの人出で賑わう。ほころび始めた梅の芳香を楽しむ人や参道に軒を連ねる露店をゆっくり見て回る人など、多くの参拝者でに今朝は冷え切ったものの穏やかな天候に恵まれ、境内は授与される梅の枝を求める人や、合格祈願をする家族連れらでにぎわった参道には古着や食品、骨とう品に混じって菜の花やツバキなどを扱う店もあり、訪れた人が寒中に彩りを添える花を買い求めていた。✸画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.26
コメント(0)
-

"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 21日(月) 【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】 ★南区・東寺は延暦十三年(七九四)の平安遷都の時に羅城門の東に開創して、西の西寺(現在は廃寺)とともに平安京の二大官寺の一つとされた。 弘仁十四年(八二三)に嵯峨天皇が弘法大師空海に下賜されて、真言密教の道場とされた。三月二十一日に没した弘法大師空海の遺徳を偲び、毎月命日の二十一日に大師堂で御影供法要が営まれる。 参拝者は金堂や大師堂にお参りし、線香の煙を体に擦りつけて無病息災を祈った後、この日、境内一円に約千数百軒の種々雑多の露店が立ち並ぶ「弘法さん」として知られる市が開かれ、東大門から九条大路に面した南大門にかけては植木市、大門を入ると古道具類、金堂や大師堂周辺では食べ物や生活用品など、ジャンル別に並んでいます。その一年最初の縁日を「初弘法」と呼び、弘法大師・空海の命日にちなむ毎月二十一日の「縁日」の中でも、年末の終(しま)い弘法と並んで多くの人でにぎわう。 金堂や大師堂では、参拝者が手を合わせて無病息災などを祈っていた。 ★京の三弘法めぐり 弘法大師ゆかりの三ヶ寺を、弘法さんの命日である二十一日に巡る習わし東寺では初弘法、神光院では、大師が厄除け修行をしたという境内で山伏による大護摩焚きと火渡りが行われ、仁和寺では三弘法めぐりの納めとして、裏山の御室八十八ヶ所霊場をめぐります。. 2019年 1月22日(火) 【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】 ★京都十六社朱印めぐり市内十六社を年頭に新しい年もいい年でありますようにと・・・そんな願いを込めて参拝することで、一年間のあらゆる御利益が得られるそうです。 二月二十五日まで。 熊野 若王子神社 学業成就・商売繁盛 熊野神社 縁結び・安産・病気平癒 新熊野神社 健康長寿・病魔退散 特にお腹守護 (能楽隆昌 発端の地) 藤森神社 勝運と馬の神様 市比賣神社 女人禁制 (京都唯一)わら天神 安産 (厄除・家内安全) 今宮神社 健康長寿・良縁開運 粟田神社 旅立ち守護・厄除 六孫王神社 出世開運・家運隆昌の守護神 上御霊神社 厄除・学業成就 (鎮霊の社) 岡崎神社 子授け・安産・厄除 西院 春日神社 病気厄除 (厄除・病気平癒・ 交通旅行安全) 御香宮 安産・厄除・病気平癒 吉祥院天満宮 受験合格・開運招福 (ちえと能力開発の神様) 豊国神社 出世開運・厄除招福・良縁成就・商売繁盛 長岡天満宮 合格祈願・厄除開運 (学問の神様)※ 期間中全ての朱印を受けると記念の干支置物がいただけます。 ✸画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.22
コメント(0)
-

"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 14日(月) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★福笹(ざさ)を手に寺院を回る新春の恒例行事「泉山七福神巡り」が十四日、東山区の泉涌寺山内の寺院であった。商売繁盛や家内安全を願う多くの参拝者でにぎわった。 泉山七福神巡りは毎年、成人の日に行われる。山内の寺院では戒光寺に弁財天、雲龍院に大黒天など七福神をそれぞれまつる。番外となる新善光寺の愛染明王と泉涌寺の楊貴妃観音堂を含めた9カ所をめぐる。 参拝者は福禄寿をまつる即成院で福笹を授かって巡回を始めた。縁起物のタイや俵、熊手などを表した「吉兆」を福笹に飾り付け、一年の幸せを願い、各寺で手を合わせて祈願していた。戒光寺では、小正月にちなんで邪気を払うとされる小豆がゆが振る舞われ、参拝者が体を温めていた。 ★平安時代からの和歌の伝統を受け継ぐ歌道宗家・冷泉家の歌会始が十四日、上京区の冷泉家住宅で開かれた。門人ら約七〇人が集い、初春のよろこびを込めた和歌を朗々と詠み上げ、新年をことほいだ。 藤原俊成、定家を遠祖とする冷泉家の恒例行事。狩衣(かりぎぬ)姿の第二十五代当主冷泉為人さんと袿袴(けいこ)をまとった女性六人が披講の儀式に臨んだ。今年の兼題は「早春野辺(そうしゅんののべ)」で、当主夫人の貴実子さんの「さゆる風去年(こぞ)となりけり春立ちてかすみたなひくみとり萌(も)ゆ野辺」など九首を独特の節回しで詠み、門人たちが唱和した。 続いて、即興で和歌を詠む当座式では「枯野(かれの)」の題が出され、門人たちが厳かな表情で筆を手に、和紙に向かっていた。 ★下帯姿の男性が体をぶつけ合うなどして無病息災を願う「裸踊り」が十四日、伏見区の法界寺であった。寒空の下、上半身裸の男性や子どもたちが仏への帰依を意味する「頂礼(ちょうらい)」の掛け声を連呼し、踊りを奉納した。 同寺では、元日から二週間にわたって五穀豊穣(ほうじょう)などを願う「修正会(しゅしょうえ)」が行われており、最終日のこの日は締めくくりの「結願(けちがん)法要」の一環として裸踊りが営まれた。下帯は安産祈願の腹帯として重宝されている。 僧侶たちが本堂の薬師堂で読経する中、隣接する国宝の阿弥陀堂の縁側では、地元の児童ら一〇人が頭上に掲げた手をたたきながら、「頂礼、頂礼」と元気よく繰り返した。参拝客からは「かわいい」と歓声が上がった。水をかぶった男性十一人も登場し、勢いよく体をぶつけ合っていた。 ★下鴨神社で「初大黒えと祭」が行われ、菊と二葉葵の飾りの付いた五合桝に大国神像が授与されます。 半桝を「繁昌」に引っ掛け、下鴨の繁昌大国とも親しまれている縁日です。大国さんは福徳円満・長寿・殖産興業にご利益のある神様とされていますが、干支も護って頂けます。 境内の各干支の神様にお参りして、お土産に干支守りを持って帰る。✸画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.20
コメント(0)
-
"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 13日(日) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★華道未生流笹岡の「初いけ式」が十三日、下京区のホテルで開かれた。今年は創流一〇〇周年の節目となり、各界の招待者と門人ら約五〇〇人を前に、笹岡隆甫家元が年始の花を生け、一層の飛躍を誓った。 笹岡家元はこけむした太い枝から真っすぐな若枝を伸ばす紅梅と赤い実をしっかりとつけた千両に、仏手柑(ぶっしゅかん)を取り合わせ、「(流派の)老若が一緒になって日本文化を押し上げていく担い手になってほしい」との願いを託した。 続いて、全国から集った流派代表一〇人が新春を飾る若松を生け、一年の精進を祈った。 ★一月十三日午後零時半、皇后杯「全国都道府県対抗女子駅伝競走大会」は西京極陸上競技場において三十七回目の号砲が鳴り、花火が上がってスタート。 今朝の京都は報道のヘリコプターが飛び交い、駅伝ムードは盛り上がり、冬の京都の素晴らしい情景です。 世界に、オリンピックに、羽ばたこうとするホープ達には、京の都大路は日本の女子マラソン界をはぐくんできた母なるロードだろう。 都大路は世界への滑走路。 「ふるさと制度」が変わったのに伴って、今年も全国から六百人を超える女性ランナーが京都にやってきた。 今大会も各年代のトップランナーが顔を揃えた。 次代を担う中高生、躍進著しい大学生、世界トップレベルの実業団のホープが続々と力走し、熱戦が期待される。「選手にとっては、育ててくれたふるさとに恩返しできる意義深い大会」である。 京都から世界に羽ばたく地元郷土のヒロイン達に大きな声援を送って上げてください。 往復四十二.一九五キロのコースで今年もどのようなドラマが展開されるのか楽しみです。★新春気分もそのままに、九区間になどらえた“数え歌”のような短章でスタート。 一区・いつも輝くランナーの顔。見るものすべてに勇気をくれる。 二区・逃げるぞ追うぞ。駅伝の魅力は抜きつ抜かれつ。 三区・寒い冬にも熱い戦い。冬枯れの都大路が華やいでくる。 四区・呼んでいる。たすきを待つチームメートが見えたら、そらラストスパート。 五区・ゴールを目指す中盤の展開。ここらが勝負の胸突き八丁。 六区・ロードを埋める大声援。ふるさと選手との一体感 (レース直前の調整練習に励む選手達)が忘れられない。 七区・涙流した厳しい練習。苦しいときに思い出せばパワー全開。 八区・ハッとする、かわいい中学生の走りに無限の可能性が見えた。 九区・苦労を忘れるゴールの一瞬。 そこには四十七チームそれぞれに、順位を超えたドラマがある。 結 果 42.195㌔のコースを愛知が優勝を成し遂げた。 第一位 愛 知 2時間15分43秒 第二位 京 都 2時間16分45秒 第三位 大 阪 2時間17分1秒 第四位 兵 庫 2時間17分13秒 第五位 千 葉 2時間17分26秒 第六位 長 野 2時間17分47秒 第七位 神奈川 2時間18分15秒 第八位 静 岡 2時間18分38秒 来年(2020年)は一月十二日に開催決定。✸画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.17
コメント(0)
-
"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 12日(土) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★茶道武者小路千家の初釜が十二日、上京区の官休庵で催された。着物姿の招待客が次々と訪れ、新春の一碗を楽しんだ。午前十時に始まった初席には、各界の二十四人が席入り。茶室環翠園には正月飾りの「綰柳」(ワンリュウ)や干支にちなんだ香台が調えられ、列席者は千宗守家元が練った濃茶を服した。宗屋家元後嗣の結婚が六月に予定されていることから、正客を務めた伊吹文明衆議院議員が祝いの言葉を述べた。床には四代一翁宗守の軸「茶道有無雪塵」が掛けられ、宗左家元と宗旦前家元がそろって「明けましておめでとうございます」とあいさつした。えとにちなんだ新調の水指や六代覚々斎作の茶杓「猪ノ子」などで、宗左家元がふくよかな濃茶を練った。炉縁や食籠(じきろう)など宗旦前家元好みの道具も多く用いられ、継承を感じさせた。正客の千宗室裏千家家元は「(宗左)家元の初のお茶をいただき、縁起良くありがたい。而妙斎(じみょうさい)宗匠(前家元)と猶有斎(ゆうゆうさい)宗匠(家元)とで、ちょっとずつお茶の味に幅があるように感じられます」と話しかけた。十四日まで続き、約一五〇〇人を迎える。十七~二十日の東京初釜には、約千人が訪れる予定。 2019年 1月 13日(日) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★煎茶道二条流の「初煎会」が十三日、中京区のホテルで開かれた。今年は二条雅荘家元の孫紀文さんも初めてお運びを担い、親子三代で各界の招待客や門人ら約二〇〇人をもてなした。二条家元が「初春をことほぎ、一煎つとめさせていただきます」と挨拶。家元雅荘嗣がまろやかな玉露を入れるかたわら、列席者は和やかに年始の言葉を交わした。家元席には、黄檗宗の近藤博道管長が記し力強い「無事」の軸が掛けられ、一年の平穏を祈った。また、香煎席なども設けられた。宗屋家元後嗣は「茶の道は清浄なまっすぐな一筋の道であり、御代の変わる今年、原点に返る意味を込めた」と語った。君が代の楽譜の蒔絵が施された棗も用い、新たな時代の到来を祝った。薄茶席には有隣斎前家元の結婚に際し表千家から贈られた花入も飾られ、一層喜ばしい雰囲気に包まれた。十一日~十四日の四日間で約八六〇人を迎える。 ★皇風煎茶禮宗家も北区の清風苑道場で初茶会を催し、門下生らが一年無病息災を祈る大福茶を味わった。 ★新成人らが弓道の上達を誓う新春恒例の「通し矢」が十三日、東山区 の三十三間堂であり、晴れやかに着飾った男女約一六〇〇人が気持ちを新たに矢を放った。慶長年間に始まったと伝えられ、「三十三間堂の通し矢」とも呼ばれています。江戸時代、武士が一二〇メートルある三十三間堂の軒下で弓の技術を競ったのが始まりとされる。弓引き初めは、かつて三十三間堂の端から端まで六十六間の距離を一昼夜で何本通せるかを競ったもの。戦後、京都府弓道連盟などが「三十三間堂大的(おおまと)全国大会」として主催し、今年で六十六回目。底冷えがする境内の射場で、あでやかな振り袖姿の女性たちが六〇メー トル先の的を狙った。静寂の中、かじかむ指先に神経を集中させながら弓を射ると、観光客たちがカメラのシャッターを切っていた。 ☆楊弓 小弓の一種で、もともと主に楊で作られていました。 室町時代には公家や武家の遊びとして、江戸時代には庶民のスポーツとしても親しまれ、祇園社や六角堂などの寺社付近に射場が設けられ、参詣者を集めたといいます。 http://www.e-kyoto.net/image/ev/ev_000069.jpg ★同じ日「柳のお加持」が行われる。 正式には「楊枝浄水供」と呼ばれ、後白河天皇の病が浄水で治癒したことに由来します。天台宗密教の修法で加持祈祷した浄水(清水に柳の枝を浸す)を当日妙法院門跡が浄水に柳の枝を浸してその水を参拝者の頭上に振りかける秘儀で功徳が分け与えられる。 特に頭痛に効くという。古くは平安時代に行われ、それによって柳にまつわる伝説が数多く生まれた。この日堂内は無料で開放されます。 ★画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.15
コメント(0)
-
"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 6日(日) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★伏見五福めぐり初詣を兼ねて、散策の「伏見ご利益巡り」。 酒蔵が並び、名水が流れ、城下町の香りが残る伏見を回る良い機会となるでしょう。 ■場 所: 長建寺・藤森神社・大黒寺・乃木神社・御香宮神社 ■期 間: 1/1~/15(※毎年同じ日程です) ■料 金: 受印料300円(一ヵ所) (色紙授与の場合 1000円)★京の底冷え三つの山に囲まれた京都盆地では、風の無い快晴の夜に地面の表面から熱が放射されるという「放射冷却」という現象が起こり、これに伴った冷気が溜まってかなり冷え込みます。 冷気湖、又は寒気湖と呼ばれる現象で、「京の底冷え」と言われる由縁です。 今では都市化が進み、もう鴨川に氷が張ることは少なくなりました. 2019年 1月 7日(月) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★茶道裏千家の初釜式が七日、上京区の今日庵で始まった。穏やかな日差しの中、招待された政財界人や文化人らが次々と訪れ、和やかに年始のあいさつを交わした。 初席は午前9時、平成茶室聴風(ちょうふう)の間に千宗左表千家家元や千宗守武者小路千家家元、西脇隆俊京都府知事、門川大作京都市長ら四十六人を迎えた。 千宗室家元が、好みの雪花三友皆具(かいぐ)や伝来の万代屋形(もずやがた)釜などの道具を調え、ゆったりと濃茶を練って列席者をもてなした。亥(い)年生まれで八回り目の年男となる玄室前家元が削った茶杓「一すじ」も用いられた。 千家元は、「『猪突(ちょとつ)猛進』の言葉のように、イノシシは突っ走るイメージがあるがその生態は地面を掘り、食物を得る。私たちも脚下照顧で歩みを進めていきたい」と語った。 十二日までに約二千人を招く。十六日からは東京で初釜式を催し、十九日までに約二三〇〇が出席する予定。 ★小川流煎茶の初煮会は三清庵小川後楽堂で開かれた。床には、山階宮晃親王の「精神茗一杯」の軸が掛けられ、鮮やかな朱色が映える彩色高小川後楽欄付炉台などの道具がめでたさを醸した。 小川後楽家元が煎茶手前で滋味あふれる一煎入れ、約一五〇人にふるまった。 ★京の花街の祇園甲部、祇園東、先斗町、宮川町で七日、年頭恒例の始業式が営まれた。芸舞妓たちは「おめでとうさんどす」と新春をことほぎ、正装の黒紋付き姿で伎芸向上を誓い合った。 祇園甲部の式典は、祇園甲部歌舞練場が耐震化に向けて休館中のため、昨年に続き、隣接のギオンコーナーで催された。芸舞妓やお茶屋関係者など約一一〇人が出席した式典後、京舞井上流家元の井上八千代さんが地唄「倭文(やまとぶみ)」を舞い、ロビーでは芸舞妓が晴れやかな表情で新酒を受けた。上七軒は九日に始業式を催す予定。 ✸画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.13
コメント(0)
-
"おいない"の京都最新情報
2019年 1月 2日(火) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★書道の上達を願い一年の目標や願いを書き初めする「天満書(てんまがき)」が二日、上京区の北野天満宮で始まった。 朝から初詣でにぎわう境内で、親子連れらが筆を振るい、奉納した。 学問や書家として知られる祭神菅原道真にちなみ、毎年開かれている。絵馬所では子どもからお年寄りまでが、引き締まった表情で「戌(いぬ)年」「元旦」など新年にちなんだ言葉や文をしたためた。「初志貫徹」や「合格」、「夢」など目標に向けた決意を表現したり「えがお」や「平和」などで明るい一年を願う子どももいた。 ★右京区・広隆寺で一月二日に「釿始め」(ちょうなはじめ)が行われる。 建築関係者の一年の無事を願う古式ゆかしい仕事始めの儀式です。 「わ、き、ず、え、よぃ~と~」。響き渡る木遣り音頭は労働の喜びと施主の誇りを託したもの。音頭の流れる中、狩衣をつけた職人さんが宮大工さながらに古式にのっとり、木材の運搬・計測・荒削りといった所作を演じていきます。 番匠が行う斧始めは、奈良時代に起源を持つもの。一般の番匠の家でも昭和初期まで行われていましたが、まもなく消滅。番匠保存会が昭和五十六年に年頭儀式として釿始めを復興しました。儀式用の宮大工の道具が興味深い。 2018年 1月 3日(水) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★東山区の八坂神社で三日、新春恒例の「かるた始め式」が行われた。 平安装束を身にまとった「かるた姫」たちが、境内の能舞台で初手合わせを奉納し、参拝者らが優雅な札さばきに見入った。 八坂神社が日本最古の和歌を詠んだと伝わる素戔嗚尊(スサノオノミコト)を祭っていることにちなんだ行事で、今年で四十八回目。近畿の各かるた会に所属する六歳から二十七歳までの男女計十四人が舞台に上がった。かるた姫たちは、緋袴(ひばかま)に袿(うちき)姿で二人一組となり、ゆっくりとした所作で札を取る古式の手合わせを披露。色とりどりの豪華な衣装と、読み手が歌う百人一首の響きに、初詣客らは迎春のおもむきを堪能した。 2019年 1月4日(金) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★新春恒例の蹴鞠初(けまりはじ)めが四日、左京区の下鴨神社で行われた。平安装束を身に着けた「鞠足(まりあし)」と呼ばれる人たちが優雅に鞠を蹴り上げ、四方を囲んだ見物客が歓声を上げた。蹴鞠は飛鳥時代に日本に伝わり、貴族の間で流行した。現在は一九〇三(三十六)年に発足した「蹴鞠(しゅうきく)保存会」が伝承。同神社の蹴鞠初めは昭和三十年代から同保存会が奉納している。 鞠をおはらいした後、境内に設けられた正方形の鞠庭で行われた。烏帽子(えぼし)に水干、はかま姿の鞠足が「アリ」「ヤア」「オウ」と掛け声を発し、鹿と馬の皮で作られた直径約二〇センチ、重さ約一五〇グラムの鞠を右足で蹴り上げた。 周囲には人垣ができ、鞠を続けて蹴り上げると歓声が湧き、落とすとため息が漏れた。 2019年 1月 5日(土) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事] ★左京区の赤山禅院で五日、天台宗総本山・延暦寺(大津市)の荒行「千日回峰行」を満行した僧侶による「八千枚大護摩供(ごまく)」があり、参拝者が新年の安寧を祈願した。 願い事が書かれた多数の護摩木をたく行事で、毎年営まれている。境内にある雲母不動堂で午前九時から始まり、叡南俊照、上原行照、叡南浩元の三人のの大阿闍梨(あじゃり)が不動明王像の前で護摩木を次々と炎にくべていった。 参拝者たちは煙の立ちこめる堂の中で不動真言を唱え、燃え上がる炎を見つめながらそれぞれの願いを祈った。 ✸画像が表示されない場合は下記のURLをUPしてください。http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html
2019.01.11
コメント(0)
-
"おいない"の京都最新情報
2018年 12月31日(月) [今日の情報・歳時記・催し・話題・出来事】 ★大晦日の除夜の鐘の音に誘われながら、元旦の朝にかけての迎春行事として全国的に知られている、祗園・八坂神社の「をけら詣り」。参拝後、境内の鉄灯籠に鑚火式で灯された「をけら火」(をけらは古く日本書紀にも記載されている薬草で、疫病を祓うとされる)から竹の繊維で編んだ「吉兆縄」に点火し、火が消えないようにくるくると回しながら家路につき、持ち帰った火で神棚の灯明を灯し、元旦の大福茶やお雑煮の種火にすると、一年の無病息災や心願成就を祈るとご利益があると言われてれている。 午後七時一〇分ごろ、境内三カ所の灯籠に火がともされ、くべられた木札が勢いよく炎を上げた。参拝者は縄に火を付け、消えないようにくるくると回した。公共交通を利用する参拝者向けに、今年から火消し用の水桶が設けられた。お寺が多い京の大晦日は、一年の締めくくり、煩悩を洗い落とす鐘の音がそこら中から響き渡る。 大晦日に除夜の鐘を撞いたり見学できる京都の寺院 ■洛 北■ ■洛 東■ 鞍 馬 寺 東 福 寺 勝 林 寺 知 恩 院 浄 蓮 華 院 方 広 寺 真 如 堂 ■洛 中■ 清 水 寺 報 恩 院 高 台 寺 本 満 寺 長 楽 寺 相 国 寺 青 蓮 院 清 浄 華 院 南 禅 寺 誓 願 寺 永 観 堂 壬 生 寺 金 戒 光 明 寺 頂 妙 寺 ■洛 西■ 百万遍知恩寺 妙 心 寺 毘 沙 門 堂 印 空 寺 大 覚 寺 ■洛 南■ 天 龍 寺 醍 醐 寺 常 寂 光 寺 二 尊 院 善 峯 寺 真宗高田派 専修寺京都別院 総 括今年一年間、京都を愛する京都人より京都の最新情報・不定期便 “おいないの京都最新情報”をご笑読頂きまして誠に有難う御座いました。 一年間の京都の歳時記を振り返るには、私のブログをご覧頂ければ、全てを収録しているつもりでおりますのでご参照ください
2019.01.06
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1