PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
遊び癖が出た
New!
あきてもさん
トヨタ カリーナ New!
moto,jcさん
New!
moto,jcさん
国民年金 6月11日 New! ララキャットさん
すっかり忘れていま… New! marnon1104さん
やっと20度超え。 New! danmama313さん
トヨタ カリーナ
 New!
moto,jcさん
New!
moto,jcさん国民年金 6月11日 New! ララキャットさん
すっかり忘れていま… New! marnon1104さん
やっと20度超え。 New! danmama313さん
Comments
テーマ: 猫のいる生活(136588)
カテゴリ: カテゴリ未分類
きょうは私のようなオジンにはもっとも似つかわしくない話題で。
「ルージュ(rouge)」は、 フランス語で「赤」と云う意味ですから、これでは「赤赤」になってしまう。
貸本屋世代で雑誌「ガロ」愛読者には懐かしい"つげ義春"と云う漫画家がいました。
私の大好きな作家のひとりなんですが、彼の作品に「紅い花」と云う短編マンガがあります。
釣り人である主人公の男性と、山中の小さな一杯飲み屋で店番しているキクチサヨコと云うノスタルジックなおかっぱ頭の少女との触れ合いを描いた作品です。
 このマンガはモノクロ作品なんですが、なぜか私にはサヨコの唇に真っ赤な口紅が塗られてるように見えるのです。
このマンガはモノクロ作品なんですが、なぜか私にはサヨコの唇に真っ赤な口紅が塗られてるように見えるのです。
ほとんど人の寄り付きそうもない山中の一杯飲み屋で働く少女が、真っ赤な口紅をしていると云うのはあるイミ不自然ですが、なぜか私のイメージとしては「真っ赤」が似つかわしい。
タイトルの「紅い花」が心理的に影響してるのかも知れませんが、ここでの赤い口紅は、現代風の自信と魅力の表現としてではなく、都会と縁のない少女だからこそ憧れとしてせめて口元くらいは飾りたいの心情が表れてるような。

それはクレオパトラにまで遡るのかも。
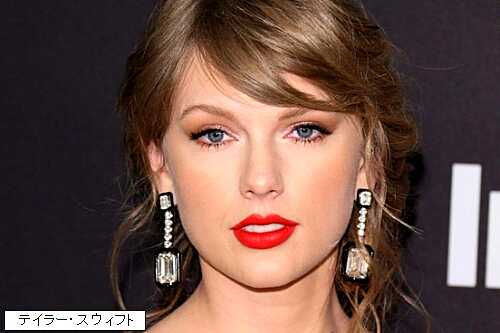
 イギリス人考古学者でメソポタミアのウルを発掘した業績で知られるレオナード・ウーリーが見つけたシュメールの「プアビ女王」の遺体は他の豪華な埋葬品とともにペンシルベニア大学博物館に展示されてます。
イギリス人考古学者でメソポタミアのウルを発掘した業績で知られるレオナード・ウーリーが見つけたシュメールの「プアビ女王」の遺体は他の豪華な埋葬品とともにペンシルベニア大学博物館に展示されてます。
今日のイラクにあたるウルは多くのシュメール王族の墓地だったのですね。
そのプアビ女王は、権力における自分の地位を象徴するために、鉛白と砕いた赤い岩を混ぜ合わせて唇を染めました。
紀元前3,500年のことです。
これが分かってる唇を赤く染めた最初でした。
 プアビ女王の影響を受けて、多くの裕福なシュメール人がザルガイの殻にリップ着色剤を入れて埋葬されていたことが発掘によって明らかになりました。
プアビ女王の影響を受けて、多くの裕福なシュメール人がザルガイの殻にリップ着色剤を入れて埋葬されていたことが発掘によって明らかになりました。
レッド・オーカーと云う天然土で、赤褐色の顔料があります。
粘土とシリカを少量含んだ酸化鉄の土です。
アメリカインディアンの赤色顔料として使われてたものですが、もっと古くは、古代エジプトの貴族が大胆な赤い唇を作るために樹脂と混ぜたレッドオーカーを使ってました。
クレオパトラは、カメムシの仲間カイガラムシ(虫)から抽出された深紅の色素であるカーミンを好みました。
 ローマ帝国でも鮮やかな赤い色合いがより高い地位を示しました。
ローマ帝国でも鮮やかな赤い色合いがより高い地位を示しました。
しかし、この時代に使われてたのは"水銀を含んだ朱色"のような赤色だったのです。
水銀ですから猛毒です。
美とひきかえに、ローマ貴族は命の危機に面してたワケです。
逆に貧しい人々は、高価な着色料が買えないので赤ワインの沈殿物を使ってましたが、それによって高貴な人より長寿だったと思います。

原因はエリザベス1世そのものにあります。
彼女はクレオパトラと同じようにカイガラムシにアラビアゴム、卵白、イチジクミルクで作った特注の深紅の口紅で唇を飾ったのがキッカケになってブームになったのですね。
 化粧品会社「エリザベス・アーデン」の創始者エリザベス・アーデンは、1920年代のアメリカ女性参政権運動の中で、女性の権利を求める闘いを象徴する色、勇気の証として「赤」を推奨して当時の活動家女性に大いに支持されたのですね。
化粧品会社「エリザベス・アーデン」の創始者エリザベス・アーデンは、1920年代のアメリカ女性参政権運動の中で、女性の権利を求める闘いを象徴する色、勇気の証として「赤」を推奨して当時の活動家女性に大いに支持されたのですね。
また彼女は第2次大戦中、兵役にとられた男性の替わりに女性が家から出て肉体労働現場へ進出するに伴い、女性海兵隊員の制服の鮮やかな深紅のトリミングに合わせた色合いと同じ色の口紅を売り出しました。

 日本に赤い口紅の原料「紅花」が、中近東、エジプトからシルクロードを経由して入ってきたのは3世紀半ば。
日本に赤い口紅の原料「紅花」が、中近東、エジプトからシルクロードを経由して入ってきたのは3世紀半ば。
奈良時代には、身分の高い男女が紅花の色素を化粧に使うようになりました。
唐の流行にならい、唇をくっきりと赤く塗っていたのですね。
平安時代になると、古代エジプトやローマと同じようにお洒落と云うより、身分や階級を表すものとして用いられました。
口紅をつけるときは唇が小さく見えるように、下唇にほんの少し紅を点すのが流行したようです。
 江戸時代後半になると、一般庶民も化粧を楽しむようになります。
江戸時代後半になると、一般庶民も化粧を楽しむようになります。
粋な江戸の女性たちの間で憧れの的になったのが「小町紅」。
紅の原料を買い取って精製し、販売する「紅屋」が続々と誕生しました。
 江戸時代に日本独特の美学が開花します。
江戸時代に日本独特の美学が開花します。
下の浮世絵画像で紅を点す女性の口元をよく見ると、下唇が緑色に見えます。
 これは「笹紅」と呼ばれるメイク法で、純度が高く精製の密度が細かい小町紅を何度も塗り重ねると、唇が玉虫色に輝くのですね。
これは「笹紅」と呼ばれるメイク法で、純度が高く精製の密度が細かい小町紅を何度も塗り重ねると、唇が玉虫色に輝くのですね。
玉虫色に光るのは品質の高い小町紅だけで、そうした小町紅は、現在の金額で1つ6~7万円もしました。
これでは一般庶民の女性たちには、とても手が届きません。
そこでこうした女性たちは、下唇を墨で塗りつぶした上から、精製の粗い安い紅を塗り流行の「笹紅」を再現したそうです。
 たかがリップスティクひとつとっても、歴史的にながめると面白いですね。
たかがリップスティクひとつとっても、歴史的にながめると面白いですね。
お化粧やファッションは時代時代を反映して、あるイミ歴史の生き証人でもあるワケです。




「ルージュ(rouge)」は、 フランス語で「赤」と云う意味ですから、これでは「赤赤」になってしまう。
貸本屋世代で雑誌「ガロ」愛読者には懐かしい"つげ義春"と云う漫画家がいました。
私の大好きな作家のひとりなんですが、彼の作品に「紅い花」と云う短編マンガがあります。
釣り人である主人公の男性と、山中の小さな一杯飲み屋で店番しているキクチサヨコと云うノスタルジックなおかっぱ頭の少女との触れ合いを描いた作品です。

ほとんど人の寄り付きそうもない山中の一杯飲み屋で働く少女が、真っ赤な口紅をしていると云うのはあるイミ不自然ですが、なぜか私のイメージとしては「真っ赤」が似つかわしい。
タイトルの「紅い花」が心理的に影響してるのかも知れませんが、ここでの赤い口紅は、現代風の自信と魅力の表現としてではなく、都会と縁のない少女だからこそ憧れとしてせめて口元くらいは飾りたいの心情が表れてるような。

それはクレオパトラにまで遡るのかも。
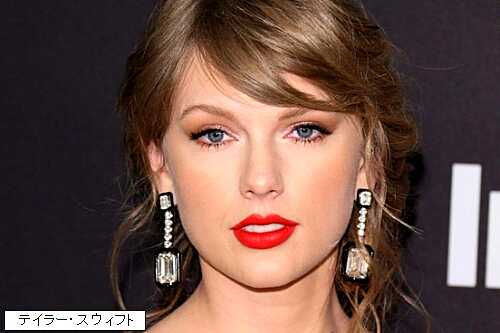

今日のイラクにあたるウルは多くのシュメール王族の墓地だったのですね。
そのプアビ女王は、権力における自分の地位を象徴するために、鉛白と砕いた赤い岩を混ぜ合わせて唇を染めました。
紀元前3,500年のことです。
これが分かってる唇を赤く染めた最初でした。

レッド・オーカーと云う天然土で、赤褐色の顔料があります。
粘土とシリカを少量含んだ酸化鉄の土です。
アメリカインディアンの赤色顔料として使われてたものですが、もっと古くは、古代エジプトの貴族が大胆な赤い唇を作るために樹脂と混ぜたレッドオーカーを使ってました。
クレオパトラは、カメムシの仲間カイガラムシ(虫)から抽出された深紅の色素であるカーミンを好みました。

しかし、この時代に使われてたのは"水銀を含んだ朱色"のような赤色だったのです。
水銀ですから猛毒です。
美とひきかえに、ローマ貴族は命の危機に面してたワケです。
逆に貧しい人々は、高価な着色料が買えないので赤ワインの沈殿物を使ってましたが、それによって高貴な人より長寿だったと思います。

原因はエリザベス1世そのものにあります。
彼女はクレオパトラと同じようにカイガラムシにアラビアゴム、卵白、イチジクミルクで作った特注の深紅の口紅で唇を飾ったのがキッカケになってブームになったのですね。

また彼女は第2次大戦中、兵役にとられた男性の替わりに女性が家から出て肉体労働現場へ進出するに伴い、女性海兵隊員の制服の鮮やかな深紅のトリミングに合わせた色合いと同じ色の口紅を売り出しました。


奈良時代には、身分の高い男女が紅花の色素を化粧に使うようになりました。
唐の流行にならい、唇をくっきりと赤く塗っていたのですね。
平安時代になると、古代エジプトやローマと同じようにお洒落と云うより、身分や階級を表すものとして用いられました。
口紅をつけるときは唇が小さく見えるように、下唇にほんの少し紅を点すのが流行したようです。

粋な江戸の女性たちの間で憧れの的になったのが「小町紅」。
紅の原料を買い取って精製し、販売する「紅屋」が続々と誕生しました。

下の浮世絵画像で紅を点す女性の口元をよく見ると、下唇が緑色に見えます。

玉虫色に光るのは品質の高い小町紅だけで、そうした小町紅は、現在の金額で1つ6~7万円もしました。
これでは一般庶民の女性たちには、とても手が届きません。
そこでこうした女性たちは、下唇を墨で塗りつぶした上から、精製の粗い安い紅を塗り流行の「笹紅」を再現したそうです。

お化粧やファッションは時代時代を反映して、あるイミ歴史の生き証人でもあるワケです。




お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.












